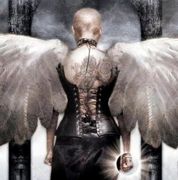http://
http://
不可視の神が僕を書く。
僕は不可視の神の下僕の僕。
僕は現実の男、神沢昌宏、彼の落書きに過ぎない。
僕は一人の魔術師イプシシマスとして、
彼と融合し、消尽し、
彼の内に残存する一人のスーフィーである。
僕は不可視の神の命を受け、
もう一人の現実の男、
私=神沢昌宏という同名異人をこの僕に書く。
それは形而上学者で、不可能性の問題を考察するために、
僕から魔力をすっかり抜き取った一つの抜け殻であり、
僕がこの現実に書き込んだフィクションである。
こうして私が語り始める。
僕の身代わりとして。僕の影に脅えながら。
* * *
透明な存在の不快は人間に殺人を唆す。
1947年、哲学者エマニュエル・レヴィナスは、
この透明な存在の不快を、存在の悪寒と捉えながら、
古いプロティノス神学に助けを仰ぎつつ、
『実存から実存者へ』を書いている。
そこで彼は、この透明な存在を、
フランス語の非人称構文で、
文字通りの逐語訳では
「彼(それ)が、そこに、持つ(所有する)」
という風に読める、
英語の《There is》にあたる表現
《il y a》(〜がある)を用い、
〈非人称のイリヤ〉と命名している。
存在の非人称性・没人格性・非主体性・無名性を表すイリヤは、
人間から人格を奪い、剥ぎ取り、消し去ってゆく、
悪魔のメドゥーサの視線のようなもの。
正確にも非人称化を意味する病名、
離人症(depersonalisation)の患者は、
常にこの透明な存在の夢魔イリヤによって
生命の優美な様相が消し去られ、
自分の人格の尊厳が無限に無意味化され続ける
災厄にさらされている。
それは普通の恐怖よりももっと悪い恐怖である。
透明な恐怖、怖がることさえ許されない凍結の恐怖である。
彼は自分が全くいない世界を凝視めなければならないし、
その自分が何処にもいない世界から逃れることが出来ない。
それは苦しむことさえも許されない辛さである。
自殺することさえ出来ない絶望である。
実を言えば、僕は1989年4月23日の27歳の誕生日に〈愛〉を知るまで、
とても長い間、
この離人症の透明な独房に監禁されていた男である。
彼の記憶によれば、既に13歳の頃にはもう発病していて、
そのときからほぼ14年間、
かなり重度の抽象の絶望の呪縛から
一歩も外に出ることが出来ないでいた。
時間も空間も言語も思考も無機化されて壊れていた。
それは人間の生きられる現実ではない。
単に死ぬことが不可能だという
自殺に対する絶望だけで彼は物理的に生きていただけ。
単に狂うことが不可能だという
発狂に対する断念だけで彼は理性的に生きていただけ。
知力を駆使し、壊れた現実を、
一瞬一瞬、意志だけの力で、
辛くもどうにかつなぎ合わせ再生しては、
自分がどうにか生きているような振りをするだけで精一杯だった。
悲しくても泣けない。怒りたくても怒ることが出来ない。
感情は、心は、魂は、手を伸ばせば伸ばすほど、
とおくへと逃げ去っていってしまう。
だから彼は感情でさえも理性の力で人工的に作った。
自分の性格でさえ
全くの虚無からそれらしいものを作って仮面にした。
人間を演じること、
いもしない自分がまるでいるかのように振る舞うこと、
そうやって僕であった彼は生きた。
彼を支えたものはただ一つだけの信念だ。
自分はもう死者よりも死に、
狂人よりも狂ってしまっているかもしれない。
人間ですらないのかもしれない。
それでも人間として生きたい。
人間として人間を心から愛せる人間に蘇りたい。
それを諦めて、
この万物が虚無の氷河に包まれたような現実に屈し、
心を、もう辛さの塊のように化石になってしまったような
この「僕である」というだけの小さな心を、
虚無の悪魔に捧げてしまってはお仕舞いなのだ。
人間であるということだけが価値である。
僕はその他の何も決して信ずるまい。
全世界は悪魔の手先のように冷笑に満ちた様相を呈している。
それでも僕はこの誰一人人間のいない世界に、
人間のいる世界を必死に描いて生き続けてやる。
奇蹟が起こるかも知れない。
ありえないことがそれでも一度は起こるかもしれない。
空に神はいない。
でも僕はその神のいない空に祈り続けることをやめるまい。
神しか僕を救えないのだから、
いない神に祈り続けるしかないのだ。
この祈りよ、天に届け、大地を震わせよ、
神なき世界に神を生み出せ。
神がいないなら、悪魔でもよい。
せめて悪魔でもよいから、目覚めよ。
無の塵を払って覚醒し、僕の声を聞き届けよ。
虚無の無意味に帰した世界に、
意味を再生させられるのなら、
その意味が全き悪であったとしても構わない。
偽りの善に万物が覆われ、
このみにくい嘘が永遠に続くよりは、
悪の意味だけでも本物の意味、
真実の意味をもっている方がましである。
非現実の天国の夢を見させられ続けるよりは、
地獄の業火でもよいから美しい現実となって出来せよ。
そうすれば僕はそれを心から愛するだろう。
実はこの彼は27歳のときにその心が爆発して死んだのである。
それがこの文章で「僕」と称して語っている人格である。
彼は死んで〈愛〉を残した。
私はその〈愛〉のなかから生まれて来た。
私は彼の身代わりである。彼の死に大きな負債をもつ。
私もしばしば彼から引き継いでしまった
離人感や抑鬱のフラッシュバックに襲われる。
それを私は彼ほど冷静に冷酷に睨み返し、
それを克服して生きられるほど強くはない。
もはや私はイリヤを正視することは出来ない。
それは彼だけが持っていた奇蹟の力だったのだから。
離人症について、私はそれを想起することさえ不可能だ。
二度とあんな世界には戻りたくない。
想起すればまた同じものを見る。
見てしまうともうおしまいなのだ。
そのなかに取り込まれてしまう。
だから直視することを私は拒絶する。
メドゥーサの視線をかわすために
私は論理の鏡の盾と透明の鎧を纏う。
僕にはメドゥーサの視線に、
同じようなメドゥーサの視線で
直接に立ち向かうことが出来ていた
(つまりそれしか出来なかった)が、
今の私であるこの私には他のやり方が出来る。
何故、いかにして、彼が離人症を病むに至ったのかを
客観的に、脇からのように、
違う角度から眺めることが出来る。
私にはもう彼の眺めていたものは見えない。
しかし彼がどんな状況にあり、
どんな装置によって離人症にされてしまったのかを、
心理としてではなく、論理的必然性として
客観的に考察し了解することができる。
同様の状況に置かれれば、
誰でも彼のように離人症患者にされてしまう。
離人症とは正確には病理ではない。
論理的必然性である。
もしも病理があるとすれば、
それは離人症ではなくて、
意識そのものが既に病い以外の何者でもないのである。
離人症は単に心の正常な反応に過ぎない。
彼はみずから離人症になったのではない。
人格を消され、非人称化されたからそうなっただけである。
実際には彼は
人格の尊厳も生命の優美も一度も喪失などしていない。
にもかかわらず、
それが全く意味をもちえない状況に置かれていただけである。
有るものが恰も無いかのようにしか
体験されえない状況に彼は置かれていた。
自分ではない全くの〈別人〉に
いつも置き換えられていただけの話である。
〈別人〉とは、
対人恐怖症患者の不可視の恐怖の対象を
名指す言葉として知られている。
離人症を精神病理学者は
よく精神分裂病(統合失調症)の前駆症状に
結び付けて論じやすい。
特に現象学系哲学の悪影響を受け過ぎた
現存在分析系の学者にその傾向が顕著である。
しかし、その理解の仕方には問題がある。
離人症はむしろ自分の側に折り返された対人恐怖症の
存在論的に論理化された表現と考えた方が分かりやすい。
離人症・対人恐怖症は、神経症でも精神病でもありえない。
それは〈別人〉という病なのであり、
病んでいるのは患者の心理なのではなく、現実の方なのだ。
離人症は、自分が別人に置き換わる病であり、
対人恐怖症は、他人が別人に置き換わる病である。
それがそれぞれの病のロジックの端的な基本形である。
〈別人〉は日本型のイリヤであると考えてよい。
ただし、これは〈非人称〉とはいえないし、
レヴィナスのいうような〈存在〉でもない。
むしろ〈別人〉は〈不人称〉の〈様相〉である。
したがって、
それは存在論的にも倫理学的にも捉えることが不可能である。
主体性の問題を考える場合に、
存在論はそれを自己同一性(存在)の問題として捉え、
倫理学はそれを自己関係性=自己言及性(意識)の問題として捉えてしまう。
これは端的にいって欠陥である。
主体性の問題は自己表現性(様相)の問題として捉えない限り、
それは必ず反人間的な様相である
〈別人〉を強化することにしかならない。
〈別人〉に接近するためには、
「存在/無」という述語的二値論理に呪縛された
存在論的ものの見方や、
「自己/他者」という主語的二値論理に呪縛された
倫理学的ものの見方から出る必要がある。
これはいずれも「真/偽」の二つの真理値しか持たない
論理学の枠組みを前提してしまっている。
そのような思考の枠組みから出なければ、
本当の問題は決して見えて来ない。
〈別人〉は存在するのでも、しないのでもない。
それは自己でもなく、他者でもない。
つまり、自分(自己)と他人(他者)は別人である。
同様に、存在と無は別人である、といってよい。
二値論理は排中律(第三項排除規則)に従っている。
別人は排中律を根拠づけながら、
自身はそれによって排除されて隠蔽され、
原理的に把握不可能なものになってしまう。
レヴィナスが〈非人称のイリヤ〉と命名しているものは、
基本的にこれである。
それは別に難解な概念ではない。
子供達は誰でもそれを知っている。
それが難解に見えるのは
〈大人〉の〈意識〉からそれを見ようとするからである。
より正確にいえば、〈大人〉とは〈意識〉のことである。
それは同じ概念であるに過ぎない。
そして、この〈大人〉とは
既にそれ自体が〈別人〉になってしまっているのだから、
そのおぞましさを決して認めようとはしないのである。
この問題は、基本的にいって単に愚劣なものである。
〈別人〉とか〈イリヤ〉とかいうものは、
子供達の言葉でいうと〈鬼〉である。
鬼ごっこや隠れ鬼の遊戯のなかで、
子供達はこれと戯れて生きている。
童謡のなかには、
この〈鬼〉の観念に触れているものが少なくない。
「赤い靴」の〈異人〉さんや、
「カゴメの歌」の〈後ろの正面〉という
不可能な場所に立つ〈誰〉は、
いずれも透明な殺人鬼・不可視の誘拐魔である
〈イリヤ〉の鬼に触れている言葉である。
それは〈怖い〉存在だが、子供達はそれを
〈恐れ〉てはいないし、〈畏れ〉もしていない。
〈おそれ〉と〈こわさ〉は元来別である。
恐怖とか畏怖というのは、
純粋な怖さ(それは〈強さ〉に通じる)を失った
愚かな大人だけが持つ感情である。
その根本は〈危惧〉であり〈危ぶみ〉である。
純粋な怖さと戯れる子供は、怖いもの知らずである。
怖いもの見たさ(好奇心)はあっても、
怖いもの知り(物識り・知識)はない。
その代わり、得体の知れぬもの、
(もののけ)への〈怯え〉というものを知っている。
怪しむということを知っている。
鬼ごっこや隠れ鬼のなかで、
子供達は〈気〉としての〈鬼〉と戯れる。
そうやって、〈気づく〉ということを学んでいる。
〈気づく〉とは面白いもので、
そこには何の根拠もない創造的な閃きだけの事件である。
他方、〈察する〉という
嫌らしい想像に基づく愚劣な心理学を子供達は知らない。
他者を察してしまうとき、
他者は別人にすりかえられてしまい、分かられてしまう。
そのとき、他者の表現は消されている。
察しの良さを美徳とする思想は非常に危険である。
それは気づく力を人間から奪ってしまう。
察しから生まれるのは必ずや警察国家である。
察しそれ自体が既に警察的だからである。
それは絶望的に鈍感である。
感受性の麻痺した人間、
生き生きとした想像力を失った人間、
それは察しと思いやりと優しさという
倒錯した美徳の崇拝から生まれる。
それは裏を返せば、自己表現性を自己否定し、
抹殺してしまった空しい人間であるということだ。
子供達は気づくことによって生きる。
気づく力だけが彼らの気力となる。
気力のある子供は実に美しく気高いものとなる。
気品のある子供は自然な遊戯からしか生まれてはこない。
子供達は鬼である。
鬼になるという不思議な変身の力を
子供達から奪ってはならない。
子供達は鬼を生きる。
それは心を鬼にすることとは違う。
心を鬼にしてしまうことこそ
日本の大人のもつ最悪の悪徳である。
子供は単に鬼になるだけである。
それが童心というものだ。
童心は鬼になっても心を鬼に取られてしまうことはない。
しかし、気取ることを覚えてしまった大人は
既に鬼に心を食われてしまっている。
子供は気取らない。単に気づくだけである。
気に色気づいて人を好きになる。
この単純に人を好きになる心を奪おうとしたり、
操作しようとしたり、管理しようとしたりしてはいけない。
好きであるということ、
その自然な好意を歪めずに表現することを奪われて、
人間は人間らしくは生きられない。
それは裏を返せば、人を嫌いになる力、
嫌悪の表現をも人間は断じて奪われてはいけないのである。
好き嫌いをはっきり言うことは
人の人品を育む上で最も大切なことなのである。
ところで〈大切〉とは何か。これは〈大事〉ではない。
〈大切〉とは〈切る〉ということである。
それは〈切る〉こととしての判断力の問題である。
〈大切〉とは自ら判断して、
〈鬼〉に、〈別人〉に遭遇しながら
それをかわして生きるということである。
何が大事かということはその後に来る問題に過ぎない。
大人は〈大事〉という価値を
一方的に子供に押し付け過ぎる。
すぐに物事を大事にして騒ぎ立て過ぎる。
また子供を大事にすることによって、
大切なことを奪っている。
そんな大人は子供に
バタフライナイフで切られても仕方がないのである。
切ること、刃物をもつことは、子供の本質である。
切ることは、知性の活動そのものの原理だからだ。
* * *
〈別人〉は、可能性・不可能性・必然性・偶然性の
四つの基本的な様相概念から出発して
それを見つめなければ把握不可能である。
つまりそれは真・偽の二値しか持たない通常の論理の枠から
いったん出ないことには掴み切れない存在である。
〈別人〉は、不可能者である。
つまり通常の現実的存在者とは同じ範疇に入らない存在である。
例えば離人症は、
自分が〈まるで別人のよう〉に感じられる病であり、
対人恐怖症は、
他人が〈まるで別人のよう〉に感じられる病である。
〈別人〉は常に
〈まるで別人のよう〉という仕方でしかありえない。
しかし、これをヘーゲルかぶれの昔の左翼系思想家が
よく安易に振り回した
あの便利なようで全くぞんざいな論理である
疎外論(自己疎外)で見るべきではない。
ここにあるのは疎外感ではない。
ここにあるのは
もっと端的な不可能感としての異質感・違和感である。
離人症は、自分が事実的・現実的に
自分自身でなくなる病気でも、
存在しなくなる病気でもない。
〈私は私である〉も〈私は存在する〉も壊れてはいない。
〈私は他者である〉とか〈私は存在しない〉とかいう
現実的事態が出来しているのではない。
むしろ崩壊してしまっているのは
現実性ではなく可能性なのである。
喪失されているのは現実ではない。
可能性が失われている(奪われている)のである。
つまり、私は私であるし、私は存在するのだが、
にもかかわらず、
私は私でありえず、私は存在できないのである。
〈私は私でありえない〉〈私は存在することができない〉という不可能性の様相を体験しているのである。
これは離人症患者に全く知的障害が見られず、
逆に却って常人以上に知的卓越性を示す者が多いという奇妙な事態をよく説明している。
離人症者の訴える無能感や不可能感は全く主観的なもので、
逆に彼らは他人の目から見ると非常に有能だったりするのである。
僕もそういう青年であった。
概して品行方正な優等生で頭だけは異常に冴えていた。
知力だけの怪物である。
それにも拘わらず、自分は他の誰よりも劣っている、
無力であるという苦しみにさいなまれていた。
いくら優秀であろうとその能力を
自分のやりたくないことばかりに強制されているなら
人間は能力を発揮すればするほど不幸になるだけである。
いくら有能だろうとそれは別人が有能なのである。
本人は同一人物のなかで力を奪われて卑しめられ続ける。
生きているのは別人であって、本人ではない。
僕は人生を奪われた人間だったのだ。
愛の歪曲のために。
全ての僕の言葉を
必ず違った意味に置き換えてしまう息子思いの父母のために。
自分の意志が全く意味をもたない人生が
人間には当然なのだと信じ込んでいる父母のために。
息子を全くの別人に
置き換えてしか見ることの出来ない父母のために。
僕は死を生かされていただけである。
父母が愛していたのは僕の死体である。
彼らの理想の息子はつまり〈死ねば良い人〉だったのである。
〈死ねば良い人〉というのは
〈生きてさえいればいい人〉というのと同じである。
生きることですら一挙一頭足、
父母のための義務になっていた。
人間の尊厳の最後の権利である
自殺の権利さえ剥奪されていた。
死ぬなとは生きるなというのと同じだ。
そのような人生は耐え難い。
一瞬一瞬が断念と失望の繰り返しである。
自分の願いは決して叶わない。自分の心は決して通じない。
他の人たちと僕だけが違う。
僕の願い、僕の言葉、僕の人格、僕の意志だけが抹殺される。
今、僕は深い悲しみと怒りを覚えながらこれを書いている。
けれども、それは今の僕に心があるからである。
この苦しみが心である。
悲しみや悔しさや怒りを感じることが出来る
この苦しい心は本当に素晴らしいものだ。
以前にはこれは恐怖に押し潰され、あってもなかった。
それが今、僕のなかにある。生きている。
心が叫びを上げて生きている。
永劫に静まらない呪詛と憤怒と憎悪の嵐のような心、
怒号する雷鳴と炸裂する原爆、
恐ろしい凶暴な光景、世の終わり。
これでいい。これが心であってよい。
僕は今、愛を知っているのだから。
http://
不可視の神が僕を書く。
僕は不可視の神の下僕の僕。
僕は現実の男、神沢昌宏、彼の落書きに過ぎない。
僕は一人の魔術師イプシシマスとして、
彼と融合し、消尽し、
彼の内に残存する一人のスーフィーである。
僕は不可視の神の命を受け、
もう一人の現実の男、
私=神沢昌宏という同名異人をこの僕に書く。
それは形而上学者で、不可能性の問題を考察するために、
僕から魔力をすっかり抜き取った一つの抜け殻であり、
僕がこの現実に書き込んだフィクションである。
こうして私が語り始める。
僕の身代わりとして。僕の影に脅えながら。
* * *
透明な存在の不快は人間に殺人を唆す。
1947年、哲学者エマニュエル・レヴィナスは、
この透明な存在の不快を、存在の悪寒と捉えながら、
古いプロティノス神学に助けを仰ぎつつ、
『実存から実存者へ』を書いている。
そこで彼は、この透明な存在を、
フランス語の非人称構文で、
文字通りの逐語訳では
「彼(それ)が、そこに、持つ(所有する)」
という風に読める、
英語の《There is》にあたる表現
《il y a》(〜がある)を用い、
〈非人称のイリヤ〉と命名している。
存在の非人称性・没人格性・非主体性・無名性を表すイリヤは、
人間から人格を奪い、剥ぎ取り、消し去ってゆく、
悪魔のメドゥーサの視線のようなもの。
正確にも非人称化を意味する病名、
離人症(depersonalisation)の患者は、
常にこの透明な存在の夢魔イリヤによって
生命の優美な様相が消し去られ、
自分の人格の尊厳が無限に無意味化され続ける
災厄にさらされている。
それは普通の恐怖よりももっと悪い恐怖である。
透明な恐怖、怖がることさえ許されない凍結の恐怖である。
彼は自分が全くいない世界を凝視めなければならないし、
その自分が何処にもいない世界から逃れることが出来ない。
それは苦しむことさえも許されない辛さである。
自殺することさえ出来ない絶望である。
実を言えば、僕は1989年4月23日の27歳の誕生日に〈愛〉を知るまで、
とても長い間、
この離人症の透明な独房に監禁されていた男である。
彼の記憶によれば、既に13歳の頃にはもう発病していて、
そのときからほぼ14年間、
かなり重度の抽象の絶望の呪縛から
一歩も外に出ることが出来ないでいた。
時間も空間も言語も思考も無機化されて壊れていた。
それは人間の生きられる現実ではない。
単に死ぬことが不可能だという
自殺に対する絶望だけで彼は物理的に生きていただけ。
単に狂うことが不可能だという
発狂に対する断念だけで彼は理性的に生きていただけ。
知力を駆使し、壊れた現実を、
一瞬一瞬、意志だけの力で、
辛くもどうにかつなぎ合わせ再生しては、
自分がどうにか生きているような振りをするだけで精一杯だった。
悲しくても泣けない。怒りたくても怒ることが出来ない。
感情は、心は、魂は、手を伸ばせば伸ばすほど、
とおくへと逃げ去っていってしまう。
だから彼は感情でさえも理性の力で人工的に作った。
自分の性格でさえ
全くの虚無からそれらしいものを作って仮面にした。
人間を演じること、
いもしない自分がまるでいるかのように振る舞うこと、
そうやって僕であった彼は生きた。
彼を支えたものはただ一つだけの信念だ。
自分はもう死者よりも死に、
狂人よりも狂ってしまっているかもしれない。
人間ですらないのかもしれない。
それでも人間として生きたい。
人間として人間を心から愛せる人間に蘇りたい。
それを諦めて、
この万物が虚無の氷河に包まれたような現実に屈し、
心を、もう辛さの塊のように化石になってしまったような
この「僕である」というだけの小さな心を、
虚無の悪魔に捧げてしまってはお仕舞いなのだ。
人間であるということだけが価値である。
僕はその他の何も決して信ずるまい。
全世界は悪魔の手先のように冷笑に満ちた様相を呈している。
それでも僕はこの誰一人人間のいない世界に、
人間のいる世界を必死に描いて生き続けてやる。
奇蹟が起こるかも知れない。
ありえないことがそれでも一度は起こるかもしれない。
空に神はいない。
でも僕はその神のいない空に祈り続けることをやめるまい。
神しか僕を救えないのだから、
いない神に祈り続けるしかないのだ。
この祈りよ、天に届け、大地を震わせよ、
神なき世界に神を生み出せ。
神がいないなら、悪魔でもよい。
せめて悪魔でもよいから、目覚めよ。
無の塵を払って覚醒し、僕の声を聞き届けよ。
虚無の無意味に帰した世界に、
意味を再生させられるのなら、
その意味が全き悪であったとしても構わない。
偽りの善に万物が覆われ、
このみにくい嘘が永遠に続くよりは、
悪の意味だけでも本物の意味、
真実の意味をもっている方がましである。
非現実の天国の夢を見させられ続けるよりは、
地獄の業火でもよいから美しい現実となって出来せよ。
そうすれば僕はそれを心から愛するだろう。
実はこの彼は27歳のときにその心が爆発して死んだのである。
それがこの文章で「僕」と称して語っている人格である。
彼は死んで〈愛〉を残した。
私はその〈愛〉のなかから生まれて来た。
私は彼の身代わりである。彼の死に大きな負債をもつ。
私もしばしば彼から引き継いでしまった
離人感や抑鬱のフラッシュバックに襲われる。
それを私は彼ほど冷静に冷酷に睨み返し、
それを克服して生きられるほど強くはない。
もはや私はイリヤを正視することは出来ない。
それは彼だけが持っていた奇蹟の力だったのだから。
離人症について、私はそれを想起することさえ不可能だ。
二度とあんな世界には戻りたくない。
想起すればまた同じものを見る。
見てしまうともうおしまいなのだ。
そのなかに取り込まれてしまう。
だから直視することを私は拒絶する。
メドゥーサの視線をかわすために
私は論理の鏡の盾と透明の鎧を纏う。
僕にはメドゥーサの視線に、
同じようなメドゥーサの視線で
直接に立ち向かうことが出来ていた
(つまりそれしか出来なかった)が、
今の私であるこの私には他のやり方が出来る。
何故、いかにして、彼が離人症を病むに至ったのかを
客観的に、脇からのように、
違う角度から眺めることが出来る。
私にはもう彼の眺めていたものは見えない。
しかし彼がどんな状況にあり、
どんな装置によって離人症にされてしまったのかを、
心理としてではなく、論理的必然性として
客観的に考察し了解することができる。
同様の状況に置かれれば、
誰でも彼のように離人症患者にされてしまう。
離人症とは正確には病理ではない。
論理的必然性である。
もしも病理があるとすれば、
それは離人症ではなくて、
意識そのものが既に病い以外の何者でもないのである。
離人症は単に心の正常な反応に過ぎない。
彼はみずから離人症になったのではない。
人格を消され、非人称化されたからそうなっただけである。
実際には彼は
人格の尊厳も生命の優美も一度も喪失などしていない。
にもかかわらず、
それが全く意味をもちえない状況に置かれていただけである。
有るものが恰も無いかのようにしか
体験されえない状況に彼は置かれていた。
自分ではない全くの〈別人〉に
いつも置き換えられていただけの話である。
〈別人〉とは、
対人恐怖症患者の不可視の恐怖の対象を
名指す言葉として知られている。
離人症を精神病理学者は
よく精神分裂病(統合失調症)の前駆症状に
結び付けて論じやすい。
特に現象学系哲学の悪影響を受け過ぎた
現存在分析系の学者にその傾向が顕著である。
しかし、その理解の仕方には問題がある。
離人症はむしろ自分の側に折り返された対人恐怖症の
存在論的に論理化された表現と考えた方が分かりやすい。
離人症・対人恐怖症は、神経症でも精神病でもありえない。
それは〈別人〉という病なのであり、
病んでいるのは患者の心理なのではなく、現実の方なのだ。
離人症は、自分が別人に置き換わる病であり、
対人恐怖症は、他人が別人に置き換わる病である。
それがそれぞれの病のロジックの端的な基本形である。
〈別人〉は日本型のイリヤであると考えてよい。
ただし、これは〈非人称〉とはいえないし、
レヴィナスのいうような〈存在〉でもない。
むしろ〈別人〉は〈不人称〉の〈様相〉である。
したがって、
それは存在論的にも倫理学的にも捉えることが不可能である。
主体性の問題を考える場合に、
存在論はそれを自己同一性(存在)の問題として捉え、
倫理学はそれを自己関係性=自己言及性(意識)の問題として捉えてしまう。
これは端的にいって欠陥である。
主体性の問題は自己表現性(様相)の問題として捉えない限り、
それは必ず反人間的な様相である
〈別人〉を強化することにしかならない。
〈別人〉に接近するためには、
「存在/無」という述語的二値論理に呪縛された
存在論的ものの見方や、
「自己/他者」という主語的二値論理に呪縛された
倫理学的ものの見方から出る必要がある。
これはいずれも「真/偽」の二つの真理値しか持たない
論理学の枠組みを前提してしまっている。
そのような思考の枠組みから出なければ、
本当の問題は決して見えて来ない。
〈別人〉は存在するのでも、しないのでもない。
それは自己でもなく、他者でもない。
つまり、自分(自己)と他人(他者)は別人である。
同様に、存在と無は別人である、といってよい。
二値論理は排中律(第三項排除規則)に従っている。
別人は排中律を根拠づけながら、
自身はそれによって排除されて隠蔽され、
原理的に把握不可能なものになってしまう。
レヴィナスが〈非人称のイリヤ〉と命名しているものは、
基本的にこれである。
それは別に難解な概念ではない。
子供達は誰でもそれを知っている。
それが難解に見えるのは
〈大人〉の〈意識〉からそれを見ようとするからである。
より正確にいえば、〈大人〉とは〈意識〉のことである。
それは同じ概念であるに過ぎない。
そして、この〈大人〉とは
既にそれ自体が〈別人〉になってしまっているのだから、
そのおぞましさを決して認めようとはしないのである。
この問題は、基本的にいって単に愚劣なものである。
〈別人〉とか〈イリヤ〉とかいうものは、
子供達の言葉でいうと〈鬼〉である。
鬼ごっこや隠れ鬼の遊戯のなかで、
子供達はこれと戯れて生きている。
童謡のなかには、
この〈鬼〉の観念に触れているものが少なくない。
「赤い靴」の〈異人〉さんや、
「カゴメの歌」の〈後ろの正面〉という
不可能な場所に立つ〈誰〉は、
いずれも透明な殺人鬼・不可視の誘拐魔である
〈イリヤ〉の鬼に触れている言葉である。
それは〈怖い〉存在だが、子供達はそれを
〈恐れ〉てはいないし、〈畏れ〉もしていない。
〈おそれ〉と〈こわさ〉は元来別である。
恐怖とか畏怖というのは、
純粋な怖さ(それは〈強さ〉に通じる)を失った
愚かな大人だけが持つ感情である。
その根本は〈危惧〉であり〈危ぶみ〉である。
純粋な怖さと戯れる子供は、怖いもの知らずである。
怖いもの見たさ(好奇心)はあっても、
怖いもの知り(物識り・知識)はない。
その代わり、得体の知れぬもの、
(もののけ)への〈怯え〉というものを知っている。
怪しむということを知っている。
鬼ごっこや隠れ鬼のなかで、
子供達は〈気〉としての〈鬼〉と戯れる。
そうやって、〈気づく〉ということを学んでいる。
〈気づく〉とは面白いもので、
そこには何の根拠もない創造的な閃きだけの事件である。
他方、〈察する〉という
嫌らしい想像に基づく愚劣な心理学を子供達は知らない。
他者を察してしまうとき、
他者は別人にすりかえられてしまい、分かられてしまう。
そのとき、他者の表現は消されている。
察しの良さを美徳とする思想は非常に危険である。
それは気づく力を人間から奪ってしまう。
察しから生まれるのは必ずや警察国家である。
察しそれ自体が既に警察的だからである。
それは絶望的に鈍感である。
感受性の麻痺した人間、
生き生きとした想像力を失った人間、
それは察しと思いやりと優しさという
倒錯した美徳の崇拝から生まれる。
それは裏を返せば、自己表現性を自己否定し、
抹殺してしまった空しい人間であるということだ。
子供達は気づくことによって生きる。
気づく力だけが彼らの気力となる。
気力のある子供は実に美しく気高いものとなる。
気品のある子供は自然な遊戯からしか生まれてはこない。
子供達は鬼である。
鬼になるという不思議な変身の力を
子供達から奪ってはならない。
子供達は鬼を生きる。
それは心を鬼にすることとは違う。
心を鬼にしてしまうことこそ
日本の大人のもつ最悪の悪徳である。
子供は単に鬼になるだけである。
それが童心というものだ。
童心は鬼になっても心を鬼に取られてしまうことはない。
しかし、気取ることを覚えてしまった大人は
既に鬼に心を食われてしまっている。
子供は気取らない。単に気づくだけである。
気に色気づいて人を好きになる。
この単純に人を好きになる心を奪おうとしたり、
操作しようとしたり、管理しようとしたりしてはいけない。
好きであるということ、
その自然な好意を歪めずに表現することを奪われて、
人間は人間らしくは生きられない。
それは裏を返せば、人を嫌いになる力、
嫌悪の表現をも人間は断じて奪われてはいけないのである。
好き嫌いをはっきり言うことは
人の人品を育む上で最も大切なことなのである。
ところで〈大切〉とは何か。これは〈大事〉ではない。
〈大切〉とは〈切る〉ということである。
それは〈切る〉こととしての判断力の問題である。
〈大切〉とは自ら判断して、
〈鬼〉に、〈別人〉に遭遇しながら
それをかわして生きるということである。
何が大事かということはその後に来る問題に過ぎない。
大人は〈大事〉という価値を
一方的に子供に押し付け過ぎる。
すぐに物事を大事にして騒ぎ立て過ぎる。
また子供を大事にすることによって、
大切なことを奪っている。
そんな大人は子供に
バタフライナイフで切られても仕方がないのである。
切ること、刃物をもつことは、子供の本質である。
切ることは、知性の活動そのものの原理だからだ。
* * *
〈別人〉は、可能性・不可能性・必然性・偶然性の
四つの基本的な様相概念から出発して
それを見つめなければ把握不可能である。
つまりそれは真・偽の二値しか持たない通常の論理の枠から
いったん出ないことには掴み切れない存在である。
〈別人〉は、不可能者である。
つまり通常の現実的存在者とは同じ範疇に入らない存在である。
例えば離人症は、
自分が〈まるで別人のよう〉に感じられる病であり、
対人恐怖症は、
他人が〈まるで別人のよう〉に感じられる病である。
〈別人〉は常に
〈まるで別人のよう〉という仕方でしかありえない。
しかし、これをヘーゲルかぶれの昔の左翼系思想家が
よく安易に振り回した
あの便利なようで全くぞんざいな論理である
疎外論(自己疎外)で見るべきではない。
ここにあるのは疎外感ではない。
ここにあるのは
もっと端的な不可能感としての異質感・違和感である。
離人症は、自分が事実的・現実的に
自分自身でなくなる病気でも、
存在しなくなる病気でもない。
〈私は私である〉も〈私は存在する〉も壊れてはいない。
〈私は他者である〉とか〈私は存在しない〉とかいう
現実的事態が出来しているのではない。
むしろ崩壊してしまっているのは
現実性ではなく可能性なのである。
喪失されているのは現実ではない。
可能性が失われている(奪われている)のである。
つまり、私は私であるし、私は存在するのだが、
にもかかわらず、
私は私でありえず、私は存在できないのである。
〈私は私でありえない〉〈私は存在することができない〉という不可能性の様相を体験しているのである。
これは離人症患者に全く知的障害が見られず、
逆に却って常人以上に知的卓越性を示す者が多いという奇妙な事態をよく説明している。
離人症者の訴える無能感や不可能感は全く主観的なもので、
逆に彼らは他人の目から見ると非常に有能だったりするのである。
僕もそういう青年であった。
概して品行方正な優等生で頭だけは異常に冴えていた。
知力だけの怪物である。
それにも拘わらず、自分は他の誰よりも劣っている、
無力であるという苦しみにさいなまれていた。
いくら優秀であろうとその能力を
自分のやりたくないことばかりに強制されているなら
人間は能力を発揮すればするほど不幸になるだけである。
いくら有能だろうとそれは別人が有能なのである。
本人は同一人物のなかで力を奪われて卑しめられ続ける。
生きているのは別人であって、本人ではない。
僕は人生を奪われた人間だったのだ。
愛の歪曲のために。
全ての僕の言葉を
必ず違った意味に置き換えてしまう息子思いの父母のために。
自分の意志が全く意味をもたない人生が
人間には当然なのだと信じ込んでいる父母のために。
息子を全くの別人に
置き換えてしか見ることの出来ない父母のために。
僕は死を生かされていただけである。
父母が愛していたのは僕の死体である。
彼らの理想の息子はつまり〈死ねば良い人〉だったのである。
〈死ねば良い人〉というのは
〈生きてさえいればいい人〉というのと同じである。
生きることですら一挙一頭足、
父母のための義務になっていた。
人間の尊厳の最後の権利である
自殺の権利さえ剥奪されていた。
死ぬなとは生きるなというのと同じだ。
そのような人生は耐え難い。
一瞬一瞬が断念と失望の繰り返しである。
自分の願いは決して叶わない。自分の心は決して通じない。
他の人たちと僕だけが違う。
僕の願い、僕の言葉、僕の人格、僕の意志だけが抹殺される。
今、僕は深い悲しみと怒りを覚えながらこれを書いている。
けれども、それは今の僕に心があるからである。
この苦しみが心である。
悲しみや悔しさや怒りを感じることが出来る
この苦しい心は本当に素晴らしいものだ。
以前にはこれは恐怖に押し潰され、あってもなかった。
それが今、僕のなかにある。生きている。
心が叫びを上げて生きている。
永劫に静まらない呪詛と憤怒と憎悪の嵐のような心、
怒号する雷鳴と炸裂する原爆、
恐ろしい凶暴な光景、世の終わり。
これでいい。これが心であってよい。
僕は今、愛を知っているのだから。
|
|
|
|
コメント(5)
【狂気の歴史】
僕は青少年期の大半を「離人症」という奇妙な病に憑かれて過ごした。
それはきわめて「死」に近い病である。この病に憑かれている間、恐らく僕は「死」を帯びていた。
なぜ、僕は「死」を帯びるに到ったのか、そしていかにしてそれを辛くも生き延び、そして今、何とか病を克して「命」ある世界に還ったか。以下に掲げる文章は、そのころを振り返りつつ、過去の自分と対決し、自分の精神的問題に決着をつけようとして書いたものである。
僕に関する報告(1994年頃の自己分析の記録より)
僕が生まれる前、兄が死んだ。
生後数カ月しか生きていなかった。
母は僕が胎にいる間もそのことを思い出して泣いていたという。
このことが僕の一生に初めから青白い憂愁と幻想的な影を投げかけた。
死せる兄のことは長じても、現在に至るまで、
相変わらず僕の精神の根底に疼き続けている。
この疼きがどうして生じたものか、僕は知らない。
疼きのなかに兄は奇妙な仕方で生き続けていた。
そして、母と僕の関係に自然でない歪みのようなものが
この兄を巡って生じた。
妹が生まれたのは3才ごろである。
郷里は雪国であって、彼女は輝く雪のなかに生まれた。
それから僅かして、曾祖母が亡くなった。
相前後する誕生と死の記憶は今もまざまざと昨日のことのように鮮明だ。
兄の死が心のなかに滑り込んできたのは
この二つの出来事の狭間にあってであった。
妹の誕生によって、僕は兄となり、兄の意味を知った。
曾祖母の死によって、
その隣に並べられている白黒写真に写る赤ん坊がどうなったかを知った。
それと一緒に思い出されるのは、
京都のツタンカーメン展に行ったことである。
死者の復活を信じた古代エジプト人が行ったミイラの魔法。
夭折した少年王の黄金マスクの生き生きとした輝き。
ツタンカーメンと兄がこの日溶け合った。
この融合は今も生きている。
死んだ少年は黄金の強力な魔力を纏い、
神にも等しい力を僕の心の奥底に永遠に保持している。
それは死をも現実をも覆す復活の奇跡を起こす力である。
これは死せる兄の肯定面である。永遠の生命と無限の可能性。
だが一方で、幼い僕はミイラの無気味さにもショックを受けた。
小学校に上がる直前、父の転勤で三重県に引っ越した。
僕は水が合わなくて、アレルギー性皮膚炎を起こした。
そのため繃帯で手足を巻かれる羽目になった。
ミイラみたいになってしまったのだ。
入れられた幼稚園はルター派の教会にくっついていた。
そこで初めてキリスト教なるものに出くわす。
磔刑図。エジプト脱出。そして、ラザロの復活。
牧師の話は衝撃だった。そのとき、重苦しいものがのしかかってきた。
だが、これ以上語ると複雑になる。
重要なのは、僕はそのとき決定的に
エホバの神とイエスに余り心地よくない仕方で
圧倒的に烙印を押されてしまったということであり、
ツタンカーメンとキリストが
《死者の復活》という一点で結び付けられながら、
エジプト脱出の話によって緊張した対立関係におかれたということ。
そして、僕がラザロと自分を同一視してしまったということである。
僕は神を信じた。だが同時に心を引き裂かれた。
アレルギー性皮膚炎はその後も暫く、秋になる度にぶりかえした。
繃帯はつらかった。だがもっとつらかったのは、
それをいじめのネタにされたことだった。
僕は死せるラザロのように陰気な繃帯のなかに閉じこもった。
外で遊ぶのが大嫌いになった。
小学校時代は、理科好きのおとなしい子供だった。
また、母が万年文学少女だった影響で、物凄い本好きになった。
気質も遺伝していた。本の外には空想と怪獣と昆虫が好きだった。
アポロの月着陸のあったのは小学校低学年の頃。
大体男の子は宇宙飛行士に憧れたものだったが、
僕だけは天文学者になりたかった。
そのため星座が好きになった。
夜空を見上げながら宇宙空間に心を開くと、
自分がまさに真空宇宙を浮遊しているような甘美な、
だがとても孤独な感情に捕らわれた。
星座の話とくれば神話だ。
僕はギリシャ神話と北欧神話に耽溺した。
母は宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』をよく読んでくれた。
それからリルケやハイネの詩も。
意味の分からぬドイツ語の響きの底に物悲しいきらめきがあった。
やがて知った、それらは、愛する者の死を歌った詩だったということを。
また茫漠と母がカンパネルラと死せる兄を重ねていることを感じていた。
日曜にはボーイスカウトがあった。
これは嫌いだった。
ただ、ボーイスカウトの拠点というのが、例の教会であり、
礼拝と日曜学校を兼ねていたことを付け加えておく。
つまりほぼまるまる七年間、三重県に住んでいる間じゅう、
僕はプロテスタントの宗教教育を受けていたことになる。
それは濃密なものではなかった。
また我が家は浄土真宗の檀家であって、
宗教的な雰囲気は全くといっていい程ない。
母がそんな処に通わせたのは、
教養を身につけさせたいという配慮からだったのだろう。
シェイクスピアとホメロスと聖書は、西洋文化の基礎であり、
幼いときからそれに触れさせておくのがよいというのが母の持論だった。
だが、こうしたキリスト教との接触が
信仰を形成するまでには至らなかったにせよ、
そこには少し不気味な、
無意識的な観念連合の呪縛を形成するには十分なものがあった。
そして、なまじ敬虔な信仰というものを持たなかったからこそ、
この無意識的なキリスト教の呪縛の力は、
信仰以上に恐ろしい暗示の働きで
僕の実存をその深みの奥底でがっちりと捕まえ、
運命的に絡めとることになったのだった。
僕の姓の最初の文字は《神》である。
父の名は《四郎》という。妹の名は《典子》である。
キリスト教は固有名との不気味な偶然の一致によって
僕を個人的に呪縛していた。
キリスト教の父なる神は四文字の名を持ち、
法典トーラーによって支配する神である。
このイメージは寧ろユダヤ教的・旧約聖書なものであるが、
実際に僕がエホバについて持ったイメージは
ユダヤ教的な恐ろしい神であった。
現実の父や妹との関係がこうした連想の元なのか、
それとも連想が現実の関係を規定したのか。
父と妹に対する疎遠さ、違和感、
漠然とした不信感や敵意めいたものの奥底に
旧約的な神のイメージがある。
それは心を許せる家族というより、
契約の履行・不履行がいつも問題となってしまう
不吉で緊張を孕んだ関係を予告するものだった。
父は婿養子であり、また妹の名前は、
母の死んだ叔母の名前から取られたものでもあった。
エディプスコンプレクスとか兄弟への嫉妬とかいう
よく知られた心理学上の事態に、
こうした半ば神秘的な暗合はより込み入った色合いを投げかけた。
父と妹は、僕にとって通常以上によそよそしい、
別世界からの不気味な客人であり、
また、威圧的で、制限的な、信用のならない権力者と映った。
母親の愛を独占したいという幼児の強力な心性が当然、
こうした父や妹への無意識的な敵意の背後に横たわっている。
プロテスタントは聖母については余り語らない。
けれども、恐らく幼い僕の空想のなかで、
父と妹からなる旧約的《掟》の世界を排除しながら、
母と僕だけからなる新約的な《愛》の世界のイメージが、
マリアとイエスの関係を下図にして
形成されていったのではないかと思われるのだ。
《神》の家は、母と息子の繋がりだけからなる。
それは神秘的な世界であり、現実世界に対立する。
神秘とは何か――死者の復活である。
死者とは誰か――死んだ兄である。
《神》の家は、死んだ兄の幻想の上に立つ。
それは目に見えない家である。母と兄と僕の家。
兄の死の悲しみを共有する母と僕の間で時が永遠に止まっていること。
母の朗読する『銀河鉄道の夜』。
母の愛する文学と空想の世界。
僕はそこに一体化し、幻想の宇宙そのものとなっていた。
その宇宙は無限の愛の涙を湛えた青い海である。
僕はそこで、兄の死を悲しむ母であり、また、死んだ兄でもあった。
今でも、ミケランジェロのピエタを見たり、
イエスの墓の前で泣くマグダラのマリアの背後に近づく
復活したキリストの物語を読むたび、
何とも言えぬ感情が胸に込み上げてくる。
僕は僕ではなく、死んだ兄の蘇りなのだという狂おしい想念。
背中を向けて泣いている青い服の幻の姿。
周囲は暗く、女は永遠に若いままで、そこで青白くぼーっと輝いている。
手前には、恐ろしく深そうな池が見える。
彼女の流した涙がそんなに溜まったのか、
それともその池に愛する子供が溺れて死んだのか
(兄は乳を喉に詰まらせて死んだらしい――《溺死》である)。
この映像、この幻が僕を呪縛する。
僕は彼女の背後に立って、
話しかけたい、振り向かせたいという強い誘惑に駆られるが、
躊躇い、そして断念する。
僕はその女に話しかけられない/或いは、話しかけてはならないのだ。
僕はそこで宙ぶらりんになる。
僕はその女の顔を知らない。誰であるのかを知らない。
それは母であって母ではない。
現実の母は年老いてゆくが、彼女は永久に若いままだ。
もし、母であったとしても、恐らくそのとき、
僕はまだ生まれていないのだから、彼女はまだ僕の母ではない。
つまり、いかなるときでも、僕は彼女に語りかける術を、
振り向かせる術を持たないのである。
僕は彼女の背後に立ちながら、立っていることは不可能なのだ。
そこには永遠にいることがない。
自分が決してそこにいない場処に僕は呪縛されていた。
これがアポリアだ。決して解くことのできないゴルディアスの結び目。
アレクサンダーの剣だけがこれを両断するだろう
――そして、ゴルディアスの結び目を解くものはアジアの霸者となり、
東と西を一つにするだろう。
それがゴルディアスの結び目に関する予言である。
《東と西を一つにする》――この言葉は考えれば考える程不気味である。
だが、現実の時間を超越することの不可能性だけが問題なのではない。
僕の声が彼女へと届くことを不可能ならしめるこの遮断は、
僕の心の躊躇のなかに、谺し続ける掟の声のためでもある。
掟といっても近親相姦のタブーなどという分かりやすいものではない。
その掟にはもっと深い響きがあるのだ。
掟とは《ノリ・メ・タンゲレ》という謎の言葉である。
《我に触るるな、我いまだ父の元に上らざるが故に》。
イエスはマグダラのマリアを振り向かせるが、
直ちにそう言わざるを得なかった。
《ノリ・メ・タンゲレ》とは何を意味するのか。
僕はやがて長じてからもこの言葉の謎の結び目に
縛り付けられ続けていたように思う。
この言葉が僕の心のなかに、
アンデルセン童話の『雪の女王』に出てくるカイ少年の
目の氷/硝子の破片のように、突き刺さって心を奪い、
心を凍りつかせてしまっていたのだ。
《我に触るるな》――同じ言葉をナルシスはエコーに言った。
エコーは消えて彼の言葉の空虚な谺となり、
美少年ナルシスは十六歳の若さで、
己れの泉に映る姿を恋して死ななければならなくなる。
彼の死んでいったその水面にも《ノリ・メ・タンゲレ》はある。
テイレシアスの予言がその裏面をなす。
《彼は自分自身を知ったときに死ぬ》と。
だが《汝自身を知れ》とは、
デルフォイの格言であり、哲学者の使命である。
ということは哲学とは死に向かう運動なのだろうか。
ソクラテスは確かに毒人参を飲んで自殺しなければならなかった。
もうひとつ、注意を促しておきたい。
マグダラのマリアは振り向くことで恋人を見るが、
そのとき愛する人を永遠に失ってしまう。
これはオルフェウスと同じなのだ。
《我に触るるな》のもうひとつの裏面は
《振り向いてはいけない》という返り見の禁である。
僕にとって、キリスト教の教義など、どうでもいいことだった。
マグダラのマリアとイエスの場面には、
オルフェウスとナルシスの二つの悲劇が
もっと深遠な仕方で切り結んでいる。
付け加えて言えば、
イザナギとイザナミのあのひどい話も
そこに本質的に書き込まれてしまっている。
そして何より、それはこの僕の問題だったのだ。
マリアはイエスであり、イエスはマリアである。
僕は、だから、内心、知っていたのである。
あそこで泣いている若い母親が誰であるのかを。
母ではない。彼女は僕なのだ。
それが僕の心であるからこそ、どうしても話しかけたいのだ。
だが、僕はそれが恐ろしい。
そのとき、彼女を永久に失ってしまうかも知れない。
或いは、振り向いたその顔は
イザナミがそうあったような恐ろしく醜い化け物であるのかもしれない。
彼女を失いたくないからこそ、
僕は彼女が泣き続けるにまかせ、
彼女の背後で沈黙の掟を握り締めて立ち続けていた。
僕は恐れていた。
彼女の背けられた貌を恐れながら魅せられてもいた。
呪縛とはこのこと、距離を於いて立ち、眺めることである。
正気で生き続けるということが呪縛なのだ。
こうして僕は理性的であり、かつまた、卑劣にも、
神の子であり続ける羽目に陥っていたのである。
だが、いつ僕は彼女の貌を見たというのか?
見もしないうちから、どうして恐れるのか。
彼女――僕の《神》の素顔は本当は美しく、優しいのかもしれない。
それなのに恐ろしい。
恐れているのは何か――《死》か、《狂気》か。
だが彼女の本当の名前は何なのか?
マリアの原像――聖母マリアにしてマグダラのマリア。
彼女たちは別人ではない。それは同じマリアである。
僕はそのことを洞察している。
そして、実際、今や知識においても知っている。
処女崇拝や処女懐胎の信仰は、
キリスト教の三位一体論のいかがわしいドグマよりも
より一層深いものであり、
また、古く、更に根源的なものであるということを。
ところで、三重県時代に僕が触れた宗教的なものは、
キリスト教だけではなかった。
僕は、僅か1学期だけだが、
浄土真宗高田派の本山の付属の中学校に入学し、
そこで、仏教の宗教教育も受けている。
三重県時代は、宗教との出会いに始まり、宗教との出会いに終わる。
受けた授業は精々お釈迦様の一生の話程度のものではあったが、
既に小学校中学年ごろから歴史に大層興味を持っていた僕は、
古い仏像や寺院の雰囲気を愛し、
また、さ程遠くはなかったので、奈良や京都にもよく旅行に行っていた。
三重県に住んではいたのだが、伊勢神宮には余りピンとこなかった。
神社には全く関心はなかった。
僕が引かれたのは常に寺であり、仏像だったのだ。
恐らく、ツタンカーメンの黄金仮面は、
黄金の仏像に変容していったのだと思う。
僕は兄の幻を、仏像の姿のなかに移していたのだ。
けれどもそれは兄が成仏したというのではなかった。
寧ろ兄は仏(如来)であってはならなかった。
寧ろ、彼は菩薩の段階にとどまりながら偉大なものでなければならない。
僕がキリスト教の中で《前世》の位置を割り振った兄は、
仏教の空間に入ると、《来世》となり、
未来仏へと理想化されてゆくことになった。
はっきり意識していた訳ではないけれども、
いつの間にか兄は弥勒菩薩のイメージに重なっていたように思う。
兄の名は《稔》という。
念仏の《念》の文字が入っていることが、
兄の仏教空間への転生を助けたのかもしれない。
またミノルとミロクの音が何となく似ていたことが
作用していたのかもしれない。
もうひとつ、中学一年の七月のこと、
三重県を去る直前に、
僕の精神に重大な変容が訪れたことを述べておかねばならない。
ヘルマン・ヘッセの『デミアン』を読んだのである。
この魔力ある書物は、晴天の霹靂だった。
だが、簡単に述べるに留めておこう。
突然、自我が目覚め、僕のなかで、激しい思春期が始まったのだ。
同時に、それは、さして信じてもいなかった
キリスト教の神の不可思議な死をも意味した。
この書物を読んだ子供が突然、
自我のデーモンに取り憑かれるといった話はありふれている。
典型的なことが起こっただけだが、影響は甚大だった。
僕は俄然、仏教的世界に強い共鳴を引き起こし、
ウパニシャッド哲学に直ちにのめりこんだ。
ヘッセの本は、東京に移るころには殆ど読み漁り尽くしていたと思う。
僕が驚くのは、その頃の信じがたいまでの吸収力である。
また、このときの夏、初めての神秘体験があった。
目の前でものが輝くように実在の強度を強め、
僕は僕が《在る》のを知り、宇宙が頭上で若々しく拡大するのを感じた。
単に観念だけではない。《梵我一如》とは存在感覚そのものだったのだ。
それは歓喜の体験である。
それはニーチェやドストエフスキー、ポー、
コリン・ウィルソン等の世界に急速にのめりこんでゆく
中学時代の化け物じみた乱読の嵐の前触れだった。
だが、東京への転校は、精神衛生に悪いものだった。
級友たちの言葉遣いは信じられぬ程荒っぽく
、町も校舎も暗く、空の下に惨めに潰れこんでいるかに見えた。
僕は適応拒否を起こした。
次第に離人症状を起こすようになり、
周囲のものが幽霊のように実在を失った。
最高の陶酔状態から最低の自失状態へと墜落したようなものだ。
それでも、心にはまだ力があったので、
存在を輝かせることは暫くは可能だった。
だが、あるとき、決定的に悪いことが起きた。
事物のリアリティーが薄いとか、
自分の鏡に映る貌が何となくよそよそしく
他人のように見える程度であれば、
そのような幽霊的な錯覚はまだ意志の力で振り切ることもできたし、
存在を呼び戻し、意識と自我をしっかりさせることはまだ可能だった。
僕は運動の嫌いな少年だったが、
それでも、官能や肉体を信じていたし、愛してもいた。
ニーチェ的な価値転倒の思考に情熱を上げてはいたが、
僕は世界には究極的に意味があり、美があることを、
そして歓喜と肯定と光の無限こそ究極の真実であることを
信じていたのだった。
だがこういった初期コリン・ウィルソン的な呑気な信念はあるとき、
根源的に破壊されてしまった。
存在が幽霊どころではなく、化物と化してしまったのだ。
僕はその恐るべき崩壊に襲われたとき、
中学生の分際で既にサルトルの『嘔吐』は読んでいたし、
ハイデガーの『存在と時間』も生半可ながら目は通していた。
だが知識武装は、強烈な離人感のメールシュトレームの渦の前には
ひとたまりもなかった。
僕はそのとき叫びを上げさえしなかった。
意識は限りなく明晰で、
あれ程明晰な状態はないといってよいほどである。
僕は冷静ですらあった。
そのとき、
そう、それは修学旅行の帰りの新幹線のなかで始まったのだが、
僕は青ざめていたにはいたが、
級友とずっとしゃべり続けていることすらできたのである。
だが、それにもかかわらず、僕は恐怖を感じ続けていた。
一切が、馬鹿げたものからそれ以下のものへ、
永久の無機質へと分解してゆく。
僕の身に起こっていたのは、
サルトルの小説で読んだことのあるあれらしいということは
分かっていたのだが、
サルトルの体験などよりもずっとずっとひどいものだった。
恐るべき存在の深淵に奇妙な転落を起こしながら、
僕は、サルトルやハイデガーが存在の絶望的な感覚において
どれほど浅薄でお気楽な連中に過ぎないかが、
ものの数分で分かってしまった。
支えてくれる大地はもう二度とありえない。
歓喜の宇宙は頭上で永遠に死滅してしまった――そんなものは幻想だ。
自我は廃墟となった。
サルトルやハイデガーの世界というのは要するに、
投げ出された自分を
堅固な実存の大地が受けとめてくれるという
感性の上にできあがっている。
被投性はどこかで実存の堅固さに突き当たって止まるのだ。
だがそんな大地などないのだとすれば、
投げ出された自己は存在の目眩の深淵を無限に落下し、
永久に自己に戻ることはできなくなる。
これは際限の無い頽落を、
自己の一人称が、
世人の非人称性に無限に拡散崩壊していくということを意味する。
つまり存在は絶対に《我あり》には辿りつかないのだ。
また非人称性への拡散は
世人の人間的な余りに人間的な馬鹿馬鹿しさの次元に止まらず、
もっとひどい下等なものへ、存在の無限の吐き気を催す空虚さへ、
言語のもっとも下等な無機的な記号の残骸の次元へと
止まるところを知らず退化してゆくのだ。
サルトルのいう純粋な意識の無の清らかさなど
愚劣極まりない蒙昧思想だった。
一旦あんなものを見てしまったなら、
たかが歌を聞いただけで希望を取り戻した
太平楽なロカンタンのようには、
決して二度と人間的な世界に帰ることなどできはしない。
ハイデガーは気付け薬に《死》への先駆的覚悟性を薦める点
でサルトルのような薮睨みの薮医者よりはましな男だったが、
英雄的な《死》の観念でビシッとやれば根性が直ると称するような
体育会的ファシストのシゴキ屋でしかなかった。
そんな虚仮威しの《死》の悲壮さで
あの恐るべき存在がビビってくれるものではない。
僕は知識は余りなかったけれども、
中学生の言葉で確かにそう感じていた。
そしてその後、この見解はやはり概ね間違いではないことを確認した。
ハイデガーの《死》は、
非人称性へと拡散したゾルゲ(関心/不安)を
自分自身の固有性へと引き戻してくれるものである。
自己同一性は先取りされた己れの死によって保証される。
ゾルゲは自分自身に死の鏡の力を借りて振り向き、
己れの一人称《我》を確認してほっとする。
だがそんな死の不安のなかの安堵は僕にはありえないことに思えた。
振り返って見たそこには、誰もいない。
《我》ではなく、不気味な黒い虚ろな穴が
ぽっかり空いているだけであるように実感された。
当時僕は、それを《無人称のゾルゲ》と名付けていた。
《非人称》などという洒落た文法用語など僕はまだ知らなかった。
《無人称》という言い方には
《非人称》というよりも生々しい実感が籠もっている。
その不気味な黒さも深く、ぞっとさせる否定的な感触も一層冷たい。
僕が感じたのは、それが、単に形式的な人称表現に過ぎない
という意味での《非人称》とは違って、
一人称以前の、そしてその根源的な不可能性を告知する
化け物じみた《無》が、
《存在》を永久に占領して、
顔のない笑いで不気味に笑い続けているというような
グロテスクな事態を意味していた。
僕がそこまでひどいものを洞察しえたのは、
実はその恐怖感が続いている間じゅう、
それでもずっと級友としゃべり続けていたからである。
舌は奇妙な剥離感を伴う麻痺のなかで、
まるで別人に乗り移られたかのように、自動運動を起こしていた。
黙ることの奇妙な不可能性がそこにはあった。
思考と言語の恐ろしい剥離が起こり、
言葉はずれ、人称は脱臼を起こし、
ありとあらゆるものの実体が
その一番内密な核心のところで
それ自身との凄まじいすれ違いを起こし、
悪夢の如くに現実性の底の底まで毀損され尽くしていく。
その感情は無残だった。
もう二度と立ち上がれないという程に無残だった。
僕の短い実存主義者時代はたった三年足らずで崩壊した。
神が死に、人間が死に、自我が死に、
意味が死に、言語が死に、存在が死に、
そして、死が死んでしまった。
崩壊は徹底的に僕を打ちのめした。
僕の離人症は決して治らないだろうと、
僕は絶望的に覚悟しなければならなかった。
それどころか、いつかきっと僕は狂うに違いない。
分裂症は必然的なのだ。誰に治せるというのか?
真実を治せる医者がいるというのか。
そう、僕の離人症は治らないのではない。
そうではなく、これは全然病気ではないのだと僕は痛切に感じていた。
狂っているのは世界であり、正常な人間の方なのだ。
僕だけが正気だった。離人症こそが実存の真相だったのである。
狂った世界で狂いもせずに生きている奴を正気というなら、
そんなものは白痴というべきだろう。
僕は白痴になってまで生きたいとは思わなかった。
だがこのままで持ちこたえられるとも思えなかった。
僕は当時十五歳だった。
僕の身に起こったことを誰も知らず、
誰にもそれを伝えることなど不可能だった。
決して誰にも分からないであろう。
心配してくれたとしても、その人には何もできず、
とんちんかんな愚行以外の何も、この世界ではなされ得ないのだと、
僕は絶望的に悟り切ってしまっていた。
それは絶対的な孤独だった。暗澹たる寂寥であった。
そんな中で、漠然と思ったのである。
僕は十六歳になったら死ぬだろう、ナルシスのように。
けれども己れに見とれ焦がれて死ぬのではなく、
己れの姿は化け物であるということに耐えられなくなって死ぬのだと。
自分自身を知る者は死ななければならない。
だが、僕はもう死んでしまっていた。
既に死んでしまった人間がどうやって死ぬというのか。
当時の僕は外見的には、
それこそナルシスの如き中性的な美少年であった。
何の衒いもなくそう記すことができる。
けれども美貌など何の価値もありはしない。
どんなに美しいものであろうと存在する限り化け物である、
存在が根源的な醜悪さだったのだ。
僕は鏡に映った己れの美しい顔を
まるで吐き気を催す妖怪でも眺めるように
蔑みと屈辱と恐怖で目茶苦茶になった思いで、
だが冷静に見下ろしていた。
《無人称のゾルゲ》による存在感覚上の崩壊の嵐は、
たった一夜で過ぎ去った。
後にはいつもの冷たく明晰な離人感だけが単調に続いた。
けれども、以前とはその意味がもう違ってしまっていた。
かつて硝子の窮屈な檻だったその恐ろしい場処が、
悪夢のごとき真の現実から身を守る鎧となり、
辛くても耐え忍ばねばならぬ隠れ処となった。
ときどき以前のように恍惚感を弄ぶこともあったが、
それはもう二度と以前のような真実の輝きをもつことはなかった。
自分で自分を騙すための欺瞞が、
つまり《悟り》というものの正体だったのだ
という暗い悟りがいつも払いがたく付き纏っていた。
僕はその離人感の檻のなかで、
だが、それでも、存在からほうり出された
宙ぶらりんの意識や思考のなかに、
それでもささやかな《我あり》の足場を捜し求めようと
悪戦苦闘し始めた。僕は明証を欲した。
大学生になるまで待ってなどいられなかった。
明日には狂うかもしれない、死ぬかもしれないという
恐怖に脅える人間に将来のことを考えることなど不可能である。
偉い哲学者になってやろうなどという下らぬ野心など抱く暇はなかった。
そんなものなど《無人称のゾルゲ》にでも食わしておけばいいのだ。
当時の僕にとって、哲学は死活問題として
飯を食うことよりも重大なことだった。
生活する前にまず何とかして存在しなければならぬ。
だが神なきデカルトにコギトの明証など不可能であることを
僕は直ちに思い知らされた。
パスカルは無限の空間の永遠の沈黙に恐怖を感じることのできる
心性の持ち主として共感できるけれども、
考える葦に成り下がって平気でいられる無神経さと、
デカルトを無神論者呼ばわりする粗暴野蛮な精神には、
僕の一層繊細な精神は全く辟易させられた。
コギト・エルゴ・スムは、
デカルトが立派に神を信じていたからやっと可能になった確信なのだ。
コギトは神なしでは空転して非人称化の無限に落ち込むだけであり、
決してスムには辿りつかない宿命を持っていた。
懐疑は神の介入によって止む。
けれども、一旦、神なき《存在》という
ゲテモノと格闘した僕の懐疑は、
まさに《僕が考える》というより、
《それが勝手に考える》といったグロテスクな様相で
悪魔のように自己展開しはじめた。
それで分かったのは、
《存在》という無限の怪物を相手にすると
《論理》は忽ち根源的にボロを出し、
ろくでもない代物であるという
その無残でいかがわしい本性を暴露し始めるということだった。
自同律・矛盾律・排中律の三位一体の明証性も、
存在の息吹を受けた僕の懐疑の嵐によって忽ち転覆してしまった。
それが全く人間の妄想の産物に過ぎないことを離人症は教えてくれた。
それは要するにザルで水を掬い取ろうとする
白痴的な行動に人を駆り立てるに過ぎない。
論理が全くの無能であることを僕は悟った。
論理が駄目になってしまったとき、
否定はそれ自身無限化することになる。
最後の明証性と思われた、
否定の否定は肯定になるから、絶対的否定は不可能だ
という《懐疑論の自己矛盾》のドグマも、
僕に明証の足場を確保してはくれなかった。
存在は僕を論理の外部にまで完全に放逐してしまった。
否定は自らを否定してもその否定性を失わず、
無限に己れ自身に潰れ込みながら、
いわば《否のブラックホール》と化してしまった。
こうして、僕は存在の深淵の手前で
呆然とする他になくなってしまったのだ。
唯一共感できるのはカント的な不可知論だけだった。
物自体は巨大な暗黒であり、
神なきカントでもあった僕は、
それを眺めていて本当に死にたい気分になった。
僕は暗澹たる気分で、ドストエフスキーの『悪霊』を読んだ。
キリーロフに、
《自分の信じるものを信じるとは信じず、
また、自分の信じないものを信じないとは信じない》人物と
評されるスタヴローギンは、
明晰な意識のまま、気違いじみた懐疑にさいなまれ、
何処にも身の置き場をなくして、醜悪な縊死を遂げる。
そのひどい気分がよく分かる気がし、
スタヴローギンは自分だと思った。身につまされる思いだった。
だが、それでも生きてこられたのは
高校に入るとすぐに出会った埴谷雄高の文学のお陰だった。
論理以外の思考形式がある筈だとか、
実体に根源的に矛盾する《虚体》だとか、
また《自同律の不快》だとかいう、その魔術的な語法は、
まさに地獄に仏といった観で僕の命を救ったのだ。
不可能性そのものを己れの思考の発条にして生き延びること。
《不可能性の文学》の啓示である。
http://ameblo.jp/novalis666/entry-10000742865.html
http://ameblo.jp/novalis666/entry-10000743097.html
僕は青少年期の大半を「離人症」という奇妙な病に憑かれて過ごした。
それはきわめて「死」に近い病である。この病に憑かれている間、恐らく僕は「死」を帯びていた。
なぜ、僕は「死」を帯びるに到ったのか、そしていかにしてそれを辛くも生き延び、そして今、何とか病を克して「命」ある世界に還ったか。以下に掲げる文章は、そのころを振り返りつつ、過去の自分と対決し、自分の精神的問題に決着をつけようとして書いたものである。
僕に関する報告(1994年頃の自己分析の記録より)
僕が生まれる前、兄が死んだ。
生後数カ月しか生きていなかった。
母は僕が胎にいる間もそのことを思い出して泣いていたという。
このことが僕の一生に初めから青白い憂愁と幻想的な影を投げかけた。
死せる兄のことは長じても、現在に至るまで、
相変わらず僕の精神の根底に疼き続けている。
この疼きがどうして生じたものか、僕は知らない。
疼きのなかに兄は奇妙な仕方で生き続けていた。
そして、母と僕の関係に自然でない歪みのようなものが
この兄を巡って生じた。
妹が生まれたのは3才ごろである。
郷里は雪国であって、彼女は輝く雪のなかに生まれた。
それから僅かして、曾祖母が亡くなった。
相前後する誕生と死の記憶は今もまざまざと昨日のことのように鮮明だ。
兄の死が心のなかに滑り込んできたのは
この二つの出来事の狭間にあってであった。
妹の誕生によって、僕は兄となり、兄の意味を知った。
曾祖母の死によって、
その隣に並べられている白黒写真に写る赤ん坊がどうなったかを知った。
それと一緒に思い出されるのは、
京都のツタンカーメン展に行ったことである。
死者の復活を信じた古代エジプト人が行ったミイラの魔法。
夭折した少年王の黄金マスクの生き生きとした輝き。
ツタンカーメンと兄がこの日溶け合った。
この融合は今も生きている。
死んだ少年は黄金の強力な魔力を纏い、
神にも等しい力を僕の心の奥底に永遠に保持している。
それは死をも現実をも覆す復活の奇跡を起こす力である。
これは死せる兄の肯定面である。永遠の生命と無限の可能性。
だが一方で、幼い僕はミイラの無気味さにもショックを受けた。
小学校に上がる直前、父の転勤で三重県に引っ越した。
僕は水が合わなくて、アレルギー性皮膚炎を起こした。
そのため繃帯で手足を巻かれる羽目になった。
ミイラみたいになってしまったのだ。
入れられた幼稚園はルター派の教会にくっついていた。
そこで初めてキリスト教なるものに出くわす。
磔刑図。エジプト脱出。そして、ラザロの復活。
牧師の話は衝撃だった。そのとき、重苦しいものがのしかかってきた。
だが、これ以上語ると複雑になる。
重要なのは、僕はそのとき決定的に
エホバの神とイエスに余り心地よくない仕方で
圧倒的に烙印を押されてしまったということであり、
ツタンカーメンとキリストが
《死者の復活》という一点で結び付けられながら、
エジプト脱出の話によって緊張した対立関係におかれたということ。
そして、僕がラザロと自分を同一視してしまったということである。
僕は神を信じた。だが同時に心を引き裂かれた。
アレルギー性皮膚炎はその後も暫く、秋になる度にぶりかえした。
繃帯はつらかった。だがもっとつらかったのは、
それをいじめのネタにされたことだった。
僕は死せるラザロのように陰気な繃帯のなかに閉じこもった。
外で遊ぶのが大嫌いになった。
小学校時代は、理科好きのおとなしい子供だった。
また、母が万年文学少女だった影響で、物凄い本好きになった。
気質も遺伝していた。本の外には空想と怪獣と昆虫が好きだった。
アポロの月着陸のあったのは小学校低学年の頃。
大体男の子は宇宙飛行士に憧れたものだったが、
僕だけは天文学者になりたかった。
そのため星座が好きになった。
夜空を見上げながら宇宙空間に心を開くと、
自分がまさに真空宇宙を浮遊しているような甘美な、
だがとても孤独な感情に捕らわれた。
星座の話とくれば神話だ。
僕はギリシャ神話と北欧神話に耽溺した。
母は宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』をよく読んでくれた。
それからリルケやハイネの詩も。
意味の分からぬドイツ語の響きの底に物悲しいきらめきがあった。
やがて知った、それらは、愛する者の死を歌った詩だったということを。
また茫漠と母がカンパネルラと死せる兄を重ねていることを感じていた。
日曜にはボーイスカウトがあった。
これは嫌いだった。
ただ、ボーイスカウトの拠点というのが、例の教会であり、
礼拝と日曜学校を兼ねていたことを付け加えておく。
つまりほぼまるまる七年間、三重県に住んでいる間じゅう、
僕はプロテスタントの宗教教育を受けていたことになる。
それは濃密なものではなかった。
また我が家は浄土真宗の檀家であって、
宗教的な雰囲気は全くといっていい程ない。
母がそんな処に通わせたのは、
教養を身につけさせたいという配慮からだったのだろう。
シェイクスピアとホメロスと聖書は、西洋文化の基礎であり、
幼いときからそれに触れさせておくのがよいというのが母の持論だった。
だが、こうしたキリスト教との接触が
信仰を形成するまでには至らなかったにせよ、
そこには少し不気味な、
無意識的な観念連合の呪縛を形成するには十分なものがあった。
そして、なまじ敬虔な信仰というものを持たなかったからこそ、
この無意識的なキリスト教の呪縛の力は、
信仰以上に恐ろしい暗示の働きで
僕の実存をその深みの奥底でがっちりと捕まえ、
運命的に絡めとることになったのだった。
僕の姓の最初の文字は《神》である。
父の名は《四郎》という。妹の名は《典子》である。
キリスト教は固有名との不気味な偶然の一致によって
僕を個人的に呪縛していた。
キリスト教の父なる神は四文字の名を持ち、
法典トーラーによって支配する神である。
このイメージは寧ろユダヤ教的・旧約聖書なものであるが、
実際に僕がエホバについて持ったイメージは
ユダヤ教的な恐ろしい神であった。
現実の父や妹との関係がこうした連想の元なのか、
それとも連想が現実の関係を規定したのか。
父と妹に対する疎遠さ、違和感、
漠然とした不信感や敵意めいたものの奥底に
旧約的な神のイメージがある。
それは心を許せる家族というより、
契約の履行・不履行がいつも問題となってしまう
不吉で緊張を孕んだ関係を予告するものだった。
父は婿養子であり、また妹の名前は、
母の死んだ叔母の名前から取られたものでもあった。
エディプスコンプレクスとか兄弟への嫉妬とかいう
よく知られた心理学上の事態に、
こうした半ば神秘的な暗合はより込み入った色合いを投げかけた。
父と妹は、僕にとって通常以上によそよそしい、
別世界からの不気味な客人であり、
また、威圧的で、制限的な、信用のならない権力者と映った。
母親の愛を独占したいという幼児の強力な心性が当然、
こうした父や妹への無意識的な敵意の背後に横たわっている。
プロテスタントは聖母については余り語らない。
けれども、恐らく幼い僕の空想のなかで、
父と妹からなる旧約的《掟》の世界を排除しながら、
母と僕だけからなる新約的な《愛》の世界のイメージが、
マリアとイエスの関係を下図にして
形成されていったのではないかと思われるのだ。
《神》の家は、母と息子の繋がりだけからなる。
それは神秘的な世界であり、現実世界に対立する。
神秘とは何か――死者の復活である。
死者とは誰か――死んだ兄である。
《神》の家は、死んだ兄の幻想の上に立つ。
それは目に見えない家である。母と兄と僕の家。
兄の死の悲しみを共有する母と僕の間で時が永遠に止まっていること。
母の朗読する『銀河鉄道の夜』。
母の愛する文学と空想の世界。
僕はそこに一体化し、幻想の宇宙そのものとなっていた。
その宇宙は無限の愛の涙を湛えた青い海である。
僕はそこで、兄の死を悲しむ母であり、また、死んだ兄でもあった。
今でも、ミケランジェロのピエタを見たり、
イエスの墓の前で泣くマグダラのマリアの背後に近づく
復活したキリストの物語を読むたび、
何とも言えぬ感情が胸に込み上げてくる。
僕は僕ではなく、死んだ兄の蘇りなのだという狂おしい想念。
背中を向けて泣いている青い服の幻の姿。
周囲は暗く、女は永遠に若いままで、そこで青白くぼーっと輝いている。
手前には、恐ろしく深そうな池が見える。
彼女の流した涙がそんなに溜まったのか、
それともその池に愛する子供が溺れて死んだのか
(兄は乳を喉に詰まらせて死んだらしい――《溺死》である)。
この映像、この幻が僕を呪縛する。
僕は彼女の背後に立って、
話しかけたい、振り向かせたいという強い誘惑に駆られるが、
躊躇い、そして断念する。
僕はその女に話しかけられない/或いは、話しかけてはならないのだ。
僕はそこで宙ぶらりんになる。
僕はその女の顔を知らない。誰であるのかを知らない。
それは母であって母ではない。
現実の母は年老いてゆくが、彼女は永久に若いままだ。
もし、母であったとしても、恐らくそのとき、
僕はまだ生まれていないのだから、彼女はまだ僕の母ではない。
つまり、いかなるときでも、僕は彼女に語りかける術を、
振り向かせる術を持たないのである。
僕は彼女の背後に立ちながら、立っていることは不可能なのだ。
そこには永遠にいることがない。
自分が決してそこにいない場処に僕は呪縛されていた。
これがアポリアだ。決して解くことのできないゴルディアスの結び目。
アレクサンダーの剣だけがこれを両断するだろう
――そして、ゴルディアスの結び目を解くものはアジアの霸者となり、
東と西を一つにするだろう。
それがゴルディアスの結び目に関する予言である。
《東と西を一つにする》――この言葉は考えれば考える程不気味である。
だが、現実の時間を超越することの不可能性だけが問題なのではない。
僕の声が彼女へと届くことを不可能ならしめるこの遮断は、
僕の心の躊躇のなかに、谺し続ける掟の声のためでもある。
掟といっても近親相姦のタブーなどという分かりやすいものではない。
その掟にはもっと深い響きがあるのだ。
掟とは《ノリ・メ・タンゲレ》という謎の言葉である。
《我に触るるな、我いまだ父の元に上らざるが故に》。
イエスはマグダラのマリアを振り向かせるが、
直ちにそう言わざるを得なかった。
《ノリ・メ・タンゲレ》とは何を意味するのか。
僕はやがて長じてからもこの言葉の謎の結び目に
縛り付けられ続けていたように思う。
この言葉が僕の心のなかに、
アンデルセン童話の『雪の女王』に出てくるカイ少年の
目の氷/硝子の破片のように、突き刺さって心を奪い、
心を凍りつかせてしまっていたのだ。
《我に触るるな》――同じ言葉をナルシスはエコーに言った。
エコーは消えて彼の言葉の空虚な谺となり、
美少年ナルシスは十六歳の若さで、
己れの泉に映る姿を恋して死ななければならなくなる。
彼の死んでいったその水面にも《ノリ・メ・タンゲレ》はある。
テイレシアスの予言がその裏面をなす。
《彼は自分自身を知ったときに死ぬ》と。
だが《汝自身を知れ》とは、
デルフォイの格言であり、哲学者の使命である。
ということは哲学とは死に向かう運動なのだろうか。
ソクラテスは確かに毒人参を飲んで自殺しなければならなかった。
もうひとつ、注意を促しておきたい。
マグダラのマリアは振り向くことで恋人を見るが、
そのとき愛する人を永遠に失ってしまう。
これはオルフェウスと同じなのだ。
《我に触るるな》のもうひとつの裏面は
《振り向いてはいけない》という返り見の禁である。
僕にとって、キリスト教の教義など、どうでもいいことだった。
マグダラのマリアとイエスの場面には、
オルフェウスとナルシスの二つの悲劇が
もっと深遠な仕方で切り結んでいる。
付け加えて言えば、
イザナギとイザナミのあのひどい話も
そこに本質的に書き込まれてしまっている。
そして何より、それはこの僕の問題だったのだ。
マリアはイエスであり、イエスはマリアである。
僕は、だから、内心、知っていたのである。
あそこで泣いている若い母親が誰であるのかを。
母ではない。彼女は僕なのだ。
それが僕の心であるからこそ、どうしても話しかけたいのだ。
だが、僕はそれが恐ろしい。
そのとき、彼女を永久に失ってしまうかも知れない。
或いは、振り向いたその顔は
イザナミがそうあったような恐ろしく醜い化け物であるのかもしれない。
彼女を失いたくないからこそ、
僕は彼女が泣き続けるにまかせ、
彼女の背後で沈黙の掟を握り締めて立ち続けていた。
僕は恐れていた。
彼女の背けられた貌を恐れながら魅せられてもいた。
呪縛とはこのこと、距離を於いて立ち、眺めることである。
正気で生き続けるということが呪縛なのだ。
こうして僕は理性的であり、かつまた、卑劣にも、
神の子であり続ける羽目に陥っていたのである。
だが、いつ僕は彼女の貌を見たというのか?
見もしないうちから、どうして恐れるのか。
彼女――僕の《神》の素顔は本当は美しく、優しいのかもしれない。
それなのに恐ろしい。
恐れているのは何か――《死》か、《狂気》か。
だが彼女の本当の名前は何なのか?
マリアの原像――聖母マリアにしてマグダラのマリア。
彼女たちは別人ではない。それは同じマリアである。
僕はそのことを洞察している。
そして、実際、今や知識においても知っている。
処女崇拝や処女懐胎の信仰は、
キリスト教の三位一体論のいかがわしいドグマよりも
より一層深いものであり、
また、古く、更に根源的なものであるということを。
ところで、三重県時代に僕が触れた宗教的なものは、
キリスト教だけではなかった。
僕は、僅か1学期だけだが、
浄土真宗高田派の本山の付属の中学校に入学し、
そこで、仏教の宗教教育も受けている。
三重県時代は、宗教との出会いに始まり、宗教との出会いに終わる。
受けた授業は精々お釈迦様の一生の話程度のものではあったが、
既に小学校中学年ごろから歴史に大層興味を持っていた僕は、
古い仏像や寺院の雰囲気を愛し、
また、さ程遠くはなかったので、奈良や京都にもよく旅行に行っていた。
三重県に住んではいたのだが、伊勢神宮には余りピンとこなかった。
神社には全く関心はなかった。
僕が引かれたのは常に寺であり、仏像だったのだ。
恐らく、ツタンカーメンの黄金仮面は、
黄金の仏像に変容していったのだと思う。
僕は兄の幻を、仏像の姿のなかに移していたのだ。
けれどもそれは兄が成仏したというのではなかった。
寧ろ兄は仏(如来)であってはならなかった。
寧ろ、彼は菩薩の段階にとどまりながら偉大なものでなければならない。
僕がキリスト教の中で《前世》の位置を割り振った兄は、
仏教の空間に入ると、《来世》となり、
未来仏へと理想化されてゆくことになった。
はっきり意識していた訳ではないけれども、
いつの間にか兄は弥勒菩薩のイメージに重なっていたように思う。
兄の名は《稔》という。
念仏の《念》の文字が入っていることが、
兄の仏教空間への転生を助けたのかもしれない。
またミノルとミロクの音が何となく似ていたことが
作用していたのかもしれない。
もうひとつ、中学一年の七月のこと、
三重県を去る直前に、
僕の精神に重大な変容が訪れたことを述べておかねばならない。
ヘルマン・ヘッセの『デミアン』を読んだのである。
この魔力ある書物は、晴天の霹靂だった。
だが、簡単に述べるに留めておこう。
突然、自我が目覚め、僕のなかで、激しい思春期が始まったのだ。
同時に、それは、さして信じてもいなかった
キリスト教の神の不可思議な死をも意味した。
この書物を読んだ子供が突然、
自我のデーモンに取り憑かれるといった話はありふれている。
典型的なことが起こっただけだが、影響は甚大だった。
僕は俄然、仏教的世界に強い共鳴を引き起こし、
ウパニシャッド哲学に直ちにのめりこんだ。
ヘッセの本は、東京に移るころには殆ど読み漁り尽くしていたと思う。
僕が驚くのは、その頃の信じがたいまでの吸収力である。
また、このときの夏、初めての神秘体験があった。
目の前でものが輝くように実在の強度を強め、
僕は僕が《在る》のを知り、宇宙が頭上で若々しく拡大するのを感じた。
単に観念だけではない。《梵我一如》とは存在感覚そのものだったのだ。
それは歓喜の体験である。
それはニーチェやドストエフスキー、ポー、
コリン・ウィルソン等の世界に急速にのめりこんでゆく
中学時代の化け物じみた乱読の嵐の前触れだった。
だが、東京への転校は、精神衛生に悪いものだった。
級友たちの言葉遣いは信じられぬ程荒っぽく
、町も校舎も暗く、空の下に惨めに潰れこんでいるかに見えた。
僕は適応拒否を起こした。
次第に離人症状を起こすようになり、
周囲のものが幽霊のように実在を失った。
最高の陶酔状態から最低の自失状態へと墜落したようなものだ。
それでも、心にはまだ力があったので、
存在を輝かせることは暫くは可能だった。
だが、あるとき、決定的に悪いことが起きた。
事物のリアリティーが薄いとか、
自分の鏡に映る貌が何となくよそよそしく
他人のように見える程度であれば、
そのような幽霊的な錯覚はまだ意志の力で振り切ることもできたし、
存在を呼び戻し、意識と自我をしっかりさせることはまだ可能だった。
僕は運動の嫌いな少年だったが、
それでも、官能や肉体を信じていたし、愛してもいた。
ニーチェ的な価値転倒の思考に情熱を上げてはいたが、
僕は世界には究極的に意味があり、美があることを、
そして歓喜と肯定と光の無限こそ究極の真実であることを
信じていたのだった。
だがこういった初期コリン・ウィルソン的な呑気な信念はあるとき、
根源的に破壊されてしまった。
存在が幽霊どころではなく、化物と化してしまったのだ。
僕はその恐るべき崩壊に襲われたとき、
中学生の分際で既にサルトルの『嘔吐』は読んでいたし、
ハイデガーの『存在と時間』も生半可ながら目は通していた。
だが知識武装は、強烈な離人感のメールシュトレームの渦の前には
ひとたまりもなかった。
僕はそのとき叫びを上げさえしなかった。
意識は限りなく明晰で、
あれ程明晰な状態はないといってよいほどである。
僕は冷静ですらあった。
そのとき、
そう、それは修学旅行の帰りの新幹線のなかで始まったのだが、
僕は青ざめていたにはいたが、
級友とずっとしゃべり続けていることすらできたのである。
だが、それにもかかわらず、僕は恐怖を感じ続けていた。
一切が、馬鹿げたものからそれ以下のものへ、
永久の無機質へと分解してゆく。
僕の身に起こっていたのは、
サルトルの小説で読んだことのあるあれらしいということは
分かっていたのだが、
サルトルの体験などよりもずっとずっとひどいものだった。
恐るべき存在の深淵に奇妙な転落を起こしながら、
僕は、サルトルやハイデガーが存在の絶望的な感覚において
どれほど浅薄でお気楽な連中に過ぎないかが、
ものの数分で分かってしまった。
支えてくれる大地はもう二度とありえない。
歓喜の宇宙は頭上で永遠に死滅してしまった――そんなものは幻想だ。
自我は廃墟となった。
サルトルやハイデガーの世界というのは要するに、
投げ出された自分を
堅固な実存の大地が受けとめてくれるという
感性の上にできあがっている。
被投性はどこかで実存の堅固さに突き当たって止まるのだ。
だがそんな大地などないのだとすれば、
投げ出された自己は存在の目眩の深淵を無限に落下し、
永久に自己に戻ることはできなくなる。
これは際限の無い頽落を、
自己の一人称が、
世人の非人称性に無限に拡散崩壊していくということを意味する。
つまり存在は絶対に《我あり》には辿りつかないのだ。
また非人称性への拡散は
世人の人間的な余りに人間的な馬鹿馬鹿しさの次元に止まらず、
もっとひどい下等なものへ、存在の無限の吐き気を催す空虚さへ、
言語のもっとも下等な無機的な記号の残骸の次元へと
止まるところを知らず退化してゆくのだ。
サルトルのいう純粋な意識の無の清らかさなど
愚劣極まりない蒙昧思想だった。
一旦あんなものを見てしまったなら、
たかが歌を聞いただけで希望を取り戻した
太平楽なロカンタンのようには、
決して二度と人間的な世界に帰ることなどできはしない。
ハイデガーは気付け薬に《死》への先駆的覚悟性を薦める点
でサルトルのような薮睨みの薮医者よりはましな男だったが、
英雄的な《死》の観念でビシッとやれば根性が直ると称するような
体育会的ファシストのシゴキ屋でしかなかった。
そんな虚仮威しの《死》の悲壮さで
あの恐るべき存在がビビってくれるものではない。
僕は知識は余りなかったけれども、
中学生の言葉で確かにそう感じていた。
そしてその後、この見解はやはり概ね間違いではないことを確認した。
ハイデガーの《死》は、
非人称性へと拡散したゾルゲ(関心/不安)を
自分自身の固有性へと引き戻してくれるものである。
自己同一性は先取りされた己れの死によって保証される。
ゾルゲは自分自身に死の鏡の力を借りて振り向き、
己れの一人称《我》を確認してほっとする。
だがそんな死の不安のなかの安堵は僕にはありえないことに思えた。
振り返って見たそこには、誰もいない。
《我》ではなく、不気味な黒い虚ろな穴が
ぽっかり空いているだけであるように実感された。
当時僕は、それを《無人称のゾルゲ》と名付けていた。
《非人称》などという洒落た文法用語など僕はまだ知らなかった。
《無人称》という言い方には
《非人称》というよりも生々しい実感が籠もっている。
その不気味な黒さも深く、ぞっとさせる否定的な感触も一層冷たい。
僕が感じたのは、それが、単に形式的な人称表現に過ぎない
という意味での《非人称》とは違って、
一人称以前の、そしてその根源的な不可能性を告知する
化け物じみた《無》が、
《存在》を永久に占領して、
顔のない笑いで不気味に笑い続けているというような
グロテスクな事態を意味していた。
僕がそこまでひどいものを洞察しえたのは、
実はその恐怖感が続いている間じゅう、
それでもずっと級友としゃべり続けていたからである。
舌は奇妙な剥離感を伴う麻痺のなかで、
まるで別人に乗り移られたかのように、自動運動を起こしていた。
黙ることの奇妙な不可能性がそこにはあった。
思考と言語の恐ろしい剥離が起こり、
言葉はずれ、人称は脱臼を起こし、
ありとあらゆるものの実体が
その一番内密な核心のところで
それ自身との凄まじいすれ違いを起こし、
悪夢の如くに現実性の底の底まで毀損され尽くしていく。
その感情は無残だった。
もう二度と立ち上がれないという程に無残だった。
僕の短い実存主義者時代はたった三年足らずで崩壊した。
神が死に、人間が死に、自我が死に、
意味が死に、言語が死に、存在が死に、
そして、死が死んでしまった。
崩壊は徹底的に僕を打ちのめした。
僕の離人症は決して治らないだろうと、
僕は絶望的に覚悟しなければならなかった。
それどころか、いつかきっと僕は狂うに違いない。
分裂症は必然的なのだ。誰に治せるというのか?
真実を治せる医者がいるというのか。
そう、僕の離人症は治らないのではない。
そうではなく、これは全然病気ではないのだと僕は痛切に感じていた。
狂っているのは世界であり、正常な人間の方なのだ。
僕だけが正気だった。離人症こそが実存の真相だったのである。
狂った世界で狂いもせずに生きている奴を正気というなら、
そんなものは白痴というべきだろう。
僕は白痴になってまで生きたいとは思わなかった。
だがこのままで持ちこたえられるとも思えなかった。
僕は当時十五歳だった。
僕の身に起こったことを誰も知らず、
誰にもそれを伝えることなど不可能だった。
決して誰にも分からないであろう。
心配してくれたとしても、その人には何もできず、
とんちんかんな愚行以外の何も、この世界ではなされ得ないのだと、
僕は絶望的に悟り切ってしまっていた。
それは絶対的な孤独だった。暗澹たる寂寥であった。
そんな中で、漠然と思ったのである。
僕は十六歳になったら死ぬだろう、ナルシスのように。
けれども己れに見とれ焦がれて死ぬのではなく、
己れの姿は化け物であるということに耐えられなくなって死ぬのだと。
自分自身を知る者は死ななければならない。
だが、僕はもう死んでしまっていた。
既に死んでしまった人間がどうやって死ぬというのか。
当時の僕は外見的には、
それこそナルシスの如き中性的な美少年であった。
何の衒いもなくそう記すことができる。
けれども美貌など何の価値もありはしない。
どんなに美しいものであろうと存在する限り化け物である、
存在が根源的な醜悪さだったのだ。
僕は鏡に映った己れの美しい顔を
まるで吐き気を催す妖怪でも眺めるように
蔑みと屈辱と恐怖で目茶苦茶になった思いで、
だが冷静に見下ろしていた。
《無人称のゾルゲ》による存在感覚上の崩壊の嵐は、
たった一夜で過ぎ去った。
後にはいつもの冷たく明晰な離人感だけが単調に続いた。
けれども、以前とはその意味がもう違ってしまっていた。
かつて硝子の窮屈な檻だったその恐ろしい場処が、
悪夢のごとき真の現実から身を守る鎧となり、
辛くても耐え忍ばねばならぬ隠れ処となった。
ときどき以前のように恍惚感を弄ぶこともあったが、
それはもう二度と以前のような真実の輝きをもつことはなかった。
自分で自分を騙すための欺瞞が、
つまり《悟り》というものの正体だったのだ
という暗い悟りがいつも払いがたく付き纏っていた。
僕はその離人感の檻のなかで、
だが、それでも、存在からほうり出された
宙ぶらりんの意識や思考のなかに、
それでもささやかな《我あり》の足場を捜し求めようと
悪戦苦闘し始めた。僕は明証を欲した。
大学生になるまで待ってなどいられなかった。
明日には狂うかもしれない、死ぬかもしれないという
恐怖に脅える人間に将来のことを考えることなど不可能である。
偉い哲学者になってやろうなどという下らぬ野心など抱く暇はなかった。
そんなものなど《無人称のゾルゲ》にでも食わしておけばいいのだ。
当時の僕にとって、哲学は死活問題として
飯を食うことよりも重大なことだった。
生活する前にまず何とかして存在しなければならぬ。
だが神なきデカルトにコギトの明証など不可能であることを
僕は直ちに思い知らされた。
パスカルは無限の空間の永遠の沈黙に恐怖を感じることのできる
心性の持ち主として共感できるけれども、
考える葦に成り下がって平気でいられる無神経さと、
デカルトを無神論者呼ばわりする粗暴野蛮な精神には、
僕の一層繊細な精神は全く辟易させられた。
コギト・エルゴ・スムは、
デカルトが立派に神を信じていたからやっと可能になった確信なのだ。
コギトは神なしでは空転して非人称化の無限に落ち込むだけであり、
決してスムには辿りつかない宿命を持っていた。
懐疑は神の介入によって止む。
けれども、一旦、神なき《存在》という
ゲテモノと格闘した僕の懐疑は、
まさに《僕が考える》というより、
《それが勝手に考える》といったグロテスクな様相で
悪魔のように自己展開しはじめた。
それで分かったのは、
《存在》という無限の怪物を相手にすると
《論理》は忽ち根源的にボロを出し、
ろくでもない代物であるという
その無残でいかがわしい本性を暴露し始めるということだった。
自同律・矛盾律・排中律の三位一体の明証性も、
存在の息吹を受けた僕の懐疑の嵐によって忽ち転覆してしまった。
それが全く人間の妄想の産物に過ぎないことを離人症は教えてくれた。
それは要するにザルで水を掬い取ろうとする
白痴的な行動に人を駆り立てるに過ぎない。
論理が全くの無能であることを僕は悟った。
論理が駄目になってしまったとき、
否定はそれ自身無限化することになる。
最後の明証性と思われた、
否定の否定は肯定になるから、絶対的否定は不可能だ
という《懐疑論の自己矛盾》のドグマも、
僕に明証の足場を確保してはくれなかった。
存在は僕を論理の外部にまで完全に放逐してしまった。
否定は自らを否定してもその否定性を失わず、
無限に己れ自身に潰れ込みながら、
いわば《否のブラックホール》と化してしまった。
こうして、僕は存在の深淵の手前で
呆然とする他になくなってしまったのだ。
唯一共感できるのはカント的な不可知論だけだった。
物自体は巨大な暗黒であり、
神なきカントでもあった僕は、
それを眺めていて本当に死にたい気分になった。
僕は暗澹たる気分で、ドストエフスキーの『悪霊』を読んだ。
キリーロフに、
《自分の信じるものを信じるとは信じず、
また、自分の信じないものを信じないとは信じない》人物と
評されるスタヴローギンは、
明晰な意識のまま、気違いじみた懐疑にさいなまれ、
何処にも身の置き場をなくして、醜悪な縊死を遂げる。
そのひどい気分がよく分かる気がし、
スタヴローギンは自分だと思った。身につまされる思いだった。
だが、それでも生きてこられたのは
高校に入るとすぐに出会った埴谷雄高の文学のお陰だった。
論理以外の思考形式がある筈だとか、
実体に根源的に矛盾する《虚体》だとか、
また《自同律の不快》だとかいう、その魔術的な語法は、
まさに地獄に仏といった観で僕の命を救ったのだ。
不可能性そのものを己れの思考の発条にして生き延びること。
《不可能性の文学》の啓示である。
http://ameblo.jp/novalis666/entry-10000742865.html
http://ameblo.jp/novalis666/entry-10000743097.html
【眼球】
序
『眼球』(1978)は処女作である。
この作品は高校1年、十六歳の時に書かれた。この作品の文学的価値については分からない。しかし、ここには当時の僕の離人症の病理体験がどのようなものであったか、そしてそれを僕がどのようにして乗り切ろうとしたのかが、きわめて克明に描き出されている。
僕はこの年、埴谷雄高の『死霊』に出遭った。離人症に打ちのめされて何度も死を考えていた十六歳の少年にとって、埴谷雄高との出会いは天啓に等しかった。『眼球』は埴谷雄高の圧倒的な影響下で書かれた作品である。僕は彼から言葉を与えられ、そして命を吹き込まれたのだといっても過言ではないだろう。彼がいなければ僕はこの作品を書く事はなかった。そしてこの作品を書くことがなければ、きっと僕はもう生きてはいなかった。さもなければ僕は狂ってしまっていたに違いないと思う。だから、埴谷雄高は僕の生命と理性を破滅の淵から救ってくれた永遠の恩人なのである。
この拙い処女作を、だから、僕は今は亡き埴谷雄高の思い出に深い感謝と変わりなき敬愛の念をもって捧げたいと思う。
***********************************
I 〈違和〉の章
灰色の水のおもてに身をかがめれば、そこにまどろむ自らの異妖に出遇うであろう。
(ああ、俺の眼と体との間のこの暗黒無限の底無しの幅よ。)超出せんとすれど超え出で得ざる、わが意識の沸きあがる飛躍は常にただ、重きわが身に引きずり落とされ、悪しき大地に縛りつけらるるのみ。そうだ。鏡の中に他人を観た経験は誰にもあるに違いあるまい。あるものがあるものに出遭うとき、そこには常に違和へと開かれた青く澄み渡った瞳があるものだ。
(それはそのものと同一となることを拒む無垢だ)
外界への馴化のまどろみを破れ、――おお、わが原初の眼、いにしえの魂よ。汝を眠らせし催眠の忌まわしき呪縛を解き、彼方へ――飛べ、翔び立て! そうだ。欺かれては、騙されてはならない。受け入れてはならない。
(驚きとは違和への悪しき覚醒……)
身を捩じって汝自身との違和に向き入るがよい。おのが身を引きずることなく、虚空へと飛び去りゆく仄かな影の白い気配をうっすらとそこに嗅ぐことができるぞ。
?.〈空虚〉の章
根源的問いの前に瓦解してゆくものの意味。そこに暴かれゆくは、この宇宙と存在との畢竟内容の空虚なるか?
(俺と俺の故郷のたしかな場所は何処だ。ちょっ、生まれたような気がしない)
(現前せる対象〔もの〕全て一般のうちに、人びとが〈現実。そして他に何もなし〉と呼ぶところのものに、俺の認識の触覚がいまだ根付いておらぬと思い知る、あの完全空虚の訪れが、しばしば俺の魂の口枷となった。一切の記憶と断定を裁くあの永劫とも思われる不安とも不快ともつかぬ不可知の霧の乳白色の何と忌まわしかったことか!)
時おり、この現実の空虚へと覚ます、あの邪悪の鐘の音が、俺から存在実感を引っさらってゆくのだった。消滅の予感に頼りなくおびえ震える世界に芝居道具の薄っぺらいもろさを観た。
ああ、平面的非現実感! 厚み欠く大地、深み欠く青空、色褪せた自然、非在へと落ちてゆく存在の重量。紙の平面に消えてゆく空間の容積。そこに世界の実在を確かめようと差し伸べた手さえもが絵ののっぺりした平面の上のよそよそしい幻と化してしまうあの時。
あるのはただ頼りなくも非現実な〈表面だけの触感〉――そして、それがどんなにありありとそのあることをこの手のなかにくっきりと描き出してくるのだとしても――それだけなのだ!
(現実の退潮の後に残るは、全て主張を呑みこむ大暗黒の無音宇宙だ。俺の故郷はここにない。)
子供が甲高く歌っている。彼らは立っているだけで既にそこが故郷なのだ。――だが、ちょっ、今は故郷喪失を歌え、記憶持てる記憶喪失の歌を。
(子供、白昼、愚劣な明るさ、明晰の単純。さて世界が紙ならば、俺は神ならぬ神だ。びりっと破って捨ててしまおう。だがどうして破れやしない。それなら受容だが、ちえっ、卑劣だ。見ろ。仮象と未来と創造主のイデアの内に眠る前現実と不可視領域の可能な現実群とが、この現実の背筋を揺さぶり脅迫してくる ――そこをどけ!)
判断。明白なものとして一つを取り、他を全て廃するということ。しかし、おお、判断など判断の死だ。判断など全て判断中止に他ならぬ。断定し現実に迎合する近視眼的知性め。そんな安定など転覆してやる。
――現実は現実ではない。
これが俺のテーゼだ。無限と現実との間に歯軋りする俺の無言は沈黙じゃない。無数のマグネットに捕らわれた動的平衡のもがきだ。ふむ、少なくとも現実よ、俺の故郷に恥じて少し言葉を慎むがいい。
?.〈恐怖〉の章
(恐怖。生の本質である粘着湿潤なるものへの顕微鏡が眼のなかに生まれてしまったということ。そして際限なき微細なものへの落下だ。言葉と日常へと抽象化されていた物体のおぞましさが生来眠りこけていた意識をびくんと跳び上がらせる。A・HA、俺が降りちまったのは俺の脳髄の中だった。俺の思考が全て愚劣な原子流動だったなんて。俺は自分の脳を爆破したかった。ALAS! だがそこに俺そっくりに扮した物質者が立ち現れて、ぞっとする馴れ馴れしさでにたついた。「君は僕と離れた時、死ぬ。君はあくまで僕の一部に過ぎない。何者も自然=物質を離れてあり得ない」 そして、原初物質が裁きを下した。「判決。この精神はわれらに醜怪を見てしまった。その出来損いの眼玉に次の罰を科する。否定と自蔑の結晶体、最大の重荷、否のブラックホール」 ああ、この日常と習慣の快い魂の臥所〔ふしど〕を噛み砕いてしまった悪魔、開き直った矛盾め。)
否のブラックホール、それが俺の苦悩だ。
恐らく否定ほど重力ある思想は他にあるまい。そう、自らを支えきれぬ絶望は何もアインシュタイン宇宙にのみ存する事態ではないのだ。否が否へと潰れゆき、なお、否、否と吠え続ける矛盾、消しがたいこの矛盾……。
(虚存というその苦痛の王座〔みくら〕は、また、邪悪な永生を与えられた死刑囚への容赦なき電気椅子でもあった。虚無にして虚偽なるものを感じつつ、そこに縛り上げられた死刑囚は、判断を後から喰ってしまう否のブラックホールに生を阻まれ、物質=永久存在に縛られて死ぬこともできない。何という死の生か! 今やコギトの明証は干からびた。おお、コギトエルゴスムだなんて口にするだに恥ずかしい。われ思うされどわれなし、の方がずっと俺には合っている。ところで次なる懐疑論の自己矛盾は今や悪しき矛盾となって大声に呼ばわる――ひょっ、矛盾だといってそれが何だというのだ。)
さて、キリーロフは語った。〈スタヴローギンはおのれの信ずるものを信ずるとは信ぜず、おのれの信ぜぬものを信ぜずとは信ぜず。〉笑ってはいけない。矛盾と自蔑から一歩も出られず、自嘲のうちに醜く縊死したスタヴローギンは、その場に今もぶらさがっている。ああ、彼がその場処を飛び去るのはいつの日のことだろうか?
?.〈別人〉の章
(俺が俺を捨ててなお俺であるなら、そこが俺と俺の故郷の確かな場処である。さて、俺が〈そいつ〉であることに俺の不快が根ざしているのだ。今は俺と〈そいつ〉とを遠心分離機にかけねばならぬ。)
鏡の中に独立した俺の眼玉に射すくめられて慄然とした。まるで意識の窓の視覚を幽霊のように残して肉眼=水晶球と俺の全身が鏡の中に別人として立っているかのように思えた。
(この奇怪な形態め。どっこい俺はお前でない。できるもんなら俺の意識を鏡に引きずり込んでみせるがいい。)
するとその魔の鏡はいきなり大口を開けて呑み込める全てを呑みこみ始めたのだった。まず、肉体が呑まれた。そして名前を、家族を、知人を、記憶を、感情を、性格を、大地を、挙句の果てに宇宙全体呑み込まれてしまった。移行し終わった世界は、俺である〈そいつ〉をも含めてまた元通り動き出した。俺に鏡が誘うように手を招く。「もうお前だけだ。」
しかし、俺は鏡の前にとどまって声もなく呟いた。(誘いに乗るな。ここにいるのが無垢なる俺だ。そして向こうのあいつは俺じゃあない。)
おお、眼球。恐らくはそここそ意識と現存在の唯一の窓であるばかりか、二つを永劫の対立と不和に置き、そこにその切断の刃もて〈俺〉をも真二つに切り裂き、違和を生む、当のものに他ならぬのだ。
?.〈宇宙〉の章
(その狂気の前に汝が正常の狂気を恥じよ。われわれの正常の城はただ、多数決の卑劣と殺された局外者の遺骸の変じた砂の上に建っているばかりだ。さて、死者たちよ。君たちに捧げる、俺の拙い挽歌を聴け――現象という、暗き水泡のうちに、胎児のように膝を抱き、狭き自らに見入る、幾多の人々。大地にも、他の球体にも接し得ず、真空にただ浮くばかり、この泡沫宇宙。)
全肯定を信奉した俺の青春よ。自然との交換の中、ニルヴァーナへと近づきゆく光の予感に酔っていた熱い宗教感情の高まりゆく美しくも非情な巨大な愛よ。自然に美を見、呼吸に歓喜があったあの頃よ。否のブラックホールを〈全て善し〉と〈神=生命〉で薙倒した、力強かった全神論者よ。お前は世界に帰依したものだ。宇宙の大原子流動を見た望遠鏡的視覚よ。存在と空間を感覚しえたあの神秘的統一感の明晰な歓喜を俺は決して忘れたわけじゃない。
だが、存在界が人間になす二つの暴虐を忘れてはならない。誕生を拒みながら引きずり出された赤ん坊の原初意識の訴えはどうなる。死にゆく自己意識を物質=永遠輪廻に拡散したとて何が慰めであろう。お前は言った――物質=神=生命=永遠=宇宙=光∋人間と。だが宇宙も死ぬであろうと言ったとき、お前は笑って言った、(宇宙が死んでも無として残るだろう。そこから点が再び生まれ、線となり面となり宇宙はまた別の形で無から生まれるであろう。無となろうと神=存在=生命は生きている、死はない)と。
だがお前の全神論に自己意識の重みはまるで含まれていないのだ。お前は夢存論者が頑なに俺は神であり、他は幻像だとわめくのを嗤うだろう。だが今は俺の話を聞け。
(さて、最後の審判のその時に神の前にしゃしゃり出て大音声に呼ばわった一人の狂人があった。「お前は誰だ。何の権利があってそこに座っている。どけ。神は俺だ。そしてその他に何も無い」。その男は神の大哄笑に綿毛のように吹っ飛んでしまったのだが、だが笑ってはならないのだ。神、世界よ。たとい一瞬であるにせよ、あなたは現象の中で自分しか見えなかった狂人に裁かれたのだから。)
?.〈叛逆〉の章
(存在素地。或いは真正?無?。そこと現実世界との間に隔絶の存するのを知れ。それこそ意識の故郷喪失を生む、根源的〈断層〉なのだ。)
(赤ん坊は最初眼が見えないという。――何を言う。見えないのではない。そこに違和を感じ、認識し得ず、受容し得ないのだ。赤ん坊の脳髄は必死に自己の無垢なる意識を歪めているのだ。生きるために、存在界を受容するために、必死に現象製造の作業を進めているのだ。眼、視覚で物自体を歪め、〈現象化=認識〉で意識を歪めている。そして、無垢を失った時に初めて世界を「見る」ことができるのだ。――だが赤ん坊は果たして自分のまわりの世界を受け容れただろうか?――否。〈慣れ〉のうちに最初の違和を愚かしく忘れてしまうことはあっても。)
私の内には忘れ去られ、今は視界の水平線に浮き沈むばかりの漠たる発生前の記憶がある。真正?無?、世界を点――重さも大きさも何もない無限小そのもの、すなわちゼロ次元――にまで縮め、更にそれを掻き消したようなそこ。無限真空の空間としての宇宙的虚空ではなく、いっさいの物的存在が自身を容れる幅をもたないところの、まさに視覚化されない時空のない〈微視なるもの〉の領域に茫としてあるようなそこを永劫の太古から眺め続けていたような、そんな記憶が時々浮かぶ。その時、私は何者でもなかった。存在ではなく純然たる意識として無の中に茫と広がり私語していたようでもある。――違和。それは?無?がいきなり神の創造行為によって存在界と無理矢理出遭わされた時からの、決して和し得なかった驚愕の尾を引いた思いではなかったか? 存在素地、或いは現実根源。私の故郷はそこであり、それこそが現実であった。私の意識はそこから引きずり出され、世界のために私の無垢は歪んだ。
(夢から熟眠に落ちると人は言う。いや、夢は実は続いているのだ。それは空白の夢、私達の原初の記憶なのだ。白昼のもののかたちを徐々に追い払い、やがて虚無、存在素地であり現実根源である真正?無?を思い出しているのだ。ひゅう、何故に眠らぬ人は気が狂ってしまうんだろう。また何故に人は眠りを安らかさと呼ぶんだろうか。おお、それは意識が存在界と出遭う時に強いられる歪みに耐え切れなくなっているからなのだ。)
恐らくはその真正?無?から〈点〉が宇宙発生の端緒として現出した時、そこからもう違和と不快は始まっていたのだ。存在素地と存在との間に引き裂かれた〈点〉の嘆き。ひゅう、それだけでも発生を司る神というのは許しがたい存在ではないか。存在素地、その無垢は既に私達から奪われてしまったのだ。創造以前のその場処は神が〈有〉を一つ創造するたびに減じていったのだ。
――そうだ。最後の審判はなければならない。その時、神=存在、現実世界は、〈存在素地=無=意識それのみ〉の前に裁かれねばならない。
造物主よ、世界よ、消え入らねばならないのはお前だ。私達、意識=無こそが神ならぬ審判者なのだ。さあ、自らお前の創造の身勝手を恥じ入るがよい。私達を無=創造以前から引きずり出し、有の汚れと肉の限定にわれらの無垢を歪め、違和に苦しめ、自分と自身の間に悪しく咲いた黒い薔薇、否のブラックホールの放つ?否?の毒花粉にさいなませたことを。さあ消えてしまえ。現実世界もろとも、そこに咲く双子の毒花――違和と否のブラックホールもろとも、おのれがそこから生じ来たったところの無の中へ。造物主よ、消え入らねばならぬのはお前だ。
?.〈無限〉の章
(無限よ……。超我なる意識を呼ぼう。浮力を持って彼方へ、存在素地という無限可能のもとへ)
(存在素地――無限な可能性の平衡状態。白紙にとどまり、〈なる〉の自己限定を否む、その全とも無ともつかぬ無限にして無形式の思惟持てる超我のみ存する世界だ。妄想と現実の区別などそこにありはしない)
(人間は超我となる時に無限となる。そうだ。無限可変の名のもとに有限なる存在は変形せられなばならぬ。)
一枚のルドンのリトグラフィを見た時、一種名状しがたい思いがよぎった。
――眼球は不思議な気球のように無限の方に向う。(※注)
ルドンの眼は今や大気の中の単眼の気球となって茫漠とした浮力をもって空のかなた、宇宙の果てへと、上へ上へと、浮上してゆくのであった。大地から自らもそれと気づかぬうちに、ふんわりと離れゆき、かなた、茫とした暗黒にして広大な味気ない大真空宇宙の方向にその光なき瞳をかたくなに向けたまま。
(眼球=意識よ。飛べ、飛んでゆけ。そうだ。無限にまで馳せ昇り、そこで超我と存在素地をつかめ)
そうだ。俺もまたそのように物質=神、すなわち存在界を下方に置き去りにして、その流動のうちから違和の反発力を借りて、ホバークラフトのごとくに浮かび上がらねばならない。そして大気圏を離れ、何の抵抗摩擦もない真空宇宙を、その最初の浮力を保ちつづけて、上方へ上方へと泳ぎゆき、やがては宇宙の海の水面〔みのも〕にぼっかりと円く穴を開けて、もはやそこに空間もない真正?無?の領域にまで行くのだ……。
恐らくは、ルドンの眼もまた無限にまで達した時に、初めてその光なき巨大な瞳を下方に向けるであろう。下方へと振り返った時、そこでは物質=神が流動しているはずだ。そうだ。その時こそ、最後の審判を告げるラッパの音が大宇宙を震え上がらせることだろう。
眺め下ろす大眼球の下方で宇宙の表情が蒼白になるその時は、さて、いつの日に訪れるのであろうか。
※注 オディロン・ルドン(1840-1916 フランス 画家)の石版画集「エドガー・ポーに」(1882)収録作品?のタイトル。このタイトルはルドン自身の創作した一種の詩である。
初出:東京都都立日比谷高等学校 雑誌「日比谷」創刊号(昭和五十四年三月 創立百周年)
http://ameblo.jp/novalis666/entry-10000741351.html
序
『眼球』(1978)は処女作である。
この作品は高校1年、十六歳の時に書かれた。この作品の文学的価値については分からない。しかし、ここには当時の僕の離人症の病理体験がどのようなものであったか、そしてそれを僕がどのようにして乗り切ろうとしたのかが、きわめて克明に描き出されている。
僕はこの年、埴谷雄高の『死霊』に出遭った。離人症に打ちのめされて何度も死を考えていた十六歳の少年にとって、埴谷雄高との出会いは天啓に等しかった。『眼球』は埴谷雄高の圧倒的な影響下で書かれた作品である。僕は彼から言葉を与えられ、そして命を吹き込まれたのだといっても過言ではないだろう。彼がいなければ僕はこの作品を書く事はなかった。そしてこの作品を書くことがなければ、きっと僕はもう生きてはいなかった。さもなければ僕は狂ってしまっていたに違いないと思う。だから、埴谷雄高は僕の生命と理性を破滅の淵から救ってくれた永遠の恩人なのである。
この拙い処女作を、だから、僕は今は亡き埴谷雄高の思い出に深い感謝と変わりなき敬愛の念をもって捧げたいと思う。
***********************************
I 〈違和〉の章
灰色の水のおもてに身をかがめれば、そこにまどろむ自らの異妖に出遇うであろう。
(ああ、俺の眼と体との間のこの暗黒無限の底無しの幅よ。)超出せんとすれど超え出で得ざる、わが意識の沸きあがる飛躍は常にただ、重きわが身に引きずり落とされ、悪しき大地に縛りつけらるるのみ。そうだ。鏡の中に他人を観た経験は誰にもあるに違いあるまい。あるものがあるものに出遭うとき、そこには常に違和へと開かれた青く澄み渡った瞳があるものだ。
(それはそのものと同一となることを拒む無垢だ)
外界への馴化のまどろみを破れ、――おお、わが原初の眼、いにしえの魂よ。汝を眠らせし催眠の忌まわしき呪縛を解き、彼方へ――飛べ、翔び立て! そうだ。欺かれては、騙されてはならない。受け入れてはならない。
(驚きとは違和への悪しき覚醒……)
身を捩じって汝自身との違和に向き入るがよい。おのが身を引きずることなく、虚空へと飛び去りゆく仄かな影の白い気配をうっすらとそこに嗅ぐことができるぞ。
?.〈空虚〉の章
根源的問いの前に瓦解してゆくものの意味。そこに暴かれゆくは、この宇宙と存在との畢竟内容の空虚なるか?
(俺と俺の故郷のたしかな場所は何処だ。ちょっ、生まれたような気がしない)
(現前せる対象〔もの〕全て一般のうちに、人びとが〈現実。そして他に何もなし〉と呼ぶところのものに、俺の認識の触覚がいまだ根付いておらぬと思い知る、あの完全空虚の訪れが、しばしば俺の魂の口枷となった。一切の記憶と断定を裁くあの永劫とも思われる不安とも不快ともつかぬ不可知の霧の乳白色の何と忌まわしかったことか!)
時おり、この現実の空虚へと覚ます、あの邪悪の鐘の音が、俺から存在実感を引っさらってゆくのだった。消滅の予感に頼りなくおびえ震える世界に芝居道具の薄っぺらいもろさを観た。
ああ、平面的非現実感! 厚み欠く大地、深み欠く青空、色褪せた自然、非在へと落ちてゆく存在の重量。紙の平面に消えてゆく空間の容積。そこに世界の実在を確かめようと差し伸べた手さえもが絵ののっぺりした平面の上のよそよそしい幻と化してしまうあの時。
あるのはただ頼りなくも非現実な〈表面だけの触感〉――そして、それがどんなにありありとそのあることをこの手のなかにくっきりと描き出してくるのだとしても――それだけなのだ!
(現実の退潮の後に残るは、全て主張を呑みこむ大暗黒の無音宇宙だ。俺の故郷はここにない。)
子供が甲高く歌っている。彼らは立っているだけで既にそこが故郷なのだ。――だが、ちょっ、今は故郷喪失を歌え、記憶持てる記憶喪失の歌を。
(子供、白昼、愚劣な明るさ、明晰の単純。さて世界が紙ならば、俺は神ならぬ神だ。びりっと破って捨ててしまおう。だがどうして破れやしない。それなら受容だが、ちえっ、卑劣だ。見ろ。仮象と未来と創造主のイデアの内に眠る前現実と不可視領域の可能な現実群とが、この現実の背筋を揺さぶり脅迫してくる ――そこをどけ!)
判断。明白なものとして一つを取り、他を全て廃するということ。しかし、おお、判断など判断の死だ。判断など全て判断中止に他ならぬ。断定し現実に迎合する近視眼的知性め。そんな安定など転覆してやる。
――現実は現実ではない。
これが俺のテーゼだ。無限と現実との間に歯軋りする俺の無言は沈黙じゃない。無数のマグネットに捕らわれた動的平衡のもがきだ。ふむ、少なくとも現実よ、俺の故郷に恥じて少し言葉を慎むがいい。
?.〈恐怖〉の章
(恐怖。生の本質である粘着湿潤なるものへの顕微鏡が眼のなかに生まれてしまったということ。そして際限なき微細なものへの落下だ。言葉と日常へと抽象化されていた物体のおぞましさが生来眠りこけていた意識をびくんと跳び上がらせる。A・HA、俺が降りちまったのは俺の脳髄の中だった。俺の思考が全て愚劣な原子流動だったなんて。俺は自分の脳を爆破したかった。ALAS! だがそこに俺そっくりに扮した物質者が立ち現れて、ぞっとする馴れ馴れしさでにたついた。「君は僕と離れた時、死ぬ。君はあくまで僕の一部に過ぎない。何者も自然=物質を離れてあり得ない」 そして、原初物質が裁きを下した。「判決。この精神はわれらに醜怪を見てしまった。その出来損いの眼玉に次の罰を科する。否定と自蔑の結晶体、最大の重荷、否のブラックホール」 ああ、この日常と習慣の快い魂の臥所〔ふしど〕を噛み砕いてしまった悪魔、開き直った矛盾め。)
否のブラックホール、それが俺の苦悩だ。
恐らく否定ほど重力ある思想は他にあるまい。そう、自らを支えきれぬ絶望は何もアインシュタイン宇宙にのみ存する事態ではないのだ。否が否へと潰れゆき、なお、否、否と吠え続ける矛盾、消しがたいこの矛盾……。
(虚存というその苦痛の王座〔みくら〕は、また、邪悪な永生を与えられた死刑囚への容赦なき電気椅子でもあった。虚無にして虚偽なるものを感じつつ、そこに縛り上げられた死刑囚は、判断を後から喰ってしまう否のブラックホールに生を阻まれ、物質=永久存在に縛られて死ぬこともできない。何という死の生か! 今やコギトの明証は干からびた。おお、コギトエルゴスムだなんて口にするだに恥ずかしい。われ思うされどわれなし、の方がずっと俺には合っている。ところで次なる懐疑論の自己矛盾は今や悪しき矛盾となって大声に呼ばわる――ひょっ、矛盾だといってそれが何だというのだ。)
さて、キリーロフは語った。〈スタヴローギンはおのれの信ずるものを信ずるとは信ぜず、おのれの信ぜぬものを信ぜずとは信ぜず。〉笑ってはいけない。矛盾と自蔑から一歩も出られず、自嘲のうちに醜く縊死したスタヴローギンは、その場に今もぶらさがっている。ああ、彼がその場処を飛び去るのはいつの日のことだろうか?
?.〈別人〉の章
(俺が俺を捨ててなお俺であるなら、そこが俺と俺の故郷の確かな場処である。さて、俺が〈そいつ〉であることに俺の不快が根ざしているのだ。今は俺と〈そいつ〉とを遠心分離機にかけねばならぬ。)
鏡の中に独立した俺の眼玉に射すくめられて慄然とした。まるで意識の窓の視覚を幽霊のように残して肉眼=水晶球と俺の全身が鏡の中に別人として立っているかのように思えた。
(この奇怪な形態め。どっこい俺はお前でない。できるもんなら俺の意識を鏡に引きずり込んでみせるがいい。)
するとその魔の鏡はいきなり大口を開けて呑み込める全てを呑みこみ始めたのだった。まず、肉体が呑まれた。そして名前を、家族を、知人を、記憶を、感情を、性格を、大地を、挙句の果てに宇宙全体呑み込まれてしまった。移行し終わった世界は、俺である〈そいつ〉をも含めてまた元通り動き出した。俺に鏡が誘うように手を招く。「もうお前だけだ。」
しかし、俺は鏡の前にとどまって声もなく呟いた。(誘いに乗るな。ここにいるのが無垢なる俺だ。そして向こうのあいつは俺じゃあない。)
おお、眼球。恐らくはそここそ意識と現存在の唯一の窓であるばかりか、二つを永劫の対立と不和に置き、そこにその切断の刃もて〈俺〉をも真二つに切り裂き、違和を生む、当のものに他ならぬのだ。
?.〈宇宙〉の章
(その狂気の前に汝が正常の狂気を恥じよ。われわれの正常の城はただ、多数決の卑劣と殺された局外者の遺骸の変じた砂の上に建っているばかりだ。さて、死者たちよ。君たちに捧げる、俺の拙い挽歌を聴け――現象という、暗き水泡のうちに、胎児のように膝を抱き、狭き自らに見入る、幾多の人々。大地にも、他の球体にも接し得ず、真空にただ浮くばかり、この泡沫宇宙。)
全肯定を信奉した俺の青春よ。自然との交換の中、ニルヴァーナへと近づきゆく光の予感に酔っていた熱い宗教感情の高まりゆく美しくも非情な巨大な愛よ。自然に美を見、呼吸に歓喜があったあの頃よ。否のブラックホールを〈全て善し〉と〈神=生命〉で薙倒した、力強かった全神論者よ。お前は世界に帰依したものだ。宇宙の大原子流動を見た望遠鏡的視覚よ。存在と空間を感覚しえたあの神秘的統一感の明晰な歓喜を俺は決して忘れたわけじゃない。
だが、存在界が人間になす二つの暴虐を忘れてはならない。誕生を拒みながら引きずり出された赤ん坊の原初意識の訴えはどうなる。死にゆく自己意識を物質=永遠輪廻に拡散したとて何が慰めであろう。お前は言った――物質=神=生命=永遠=宇宙=光∋人間と。だが宇宙も死ぬであろうと言ったとき、お前は笑って言った、(宇宙が死んでも無として残るだろう。そこから点が再び生まれ、線となり面となり宇宙はまた別の形で無から生まれるであろう。無となろうと神=存在=生命は生きている、死はない)と。
だがお前の全神論に自己意識の重みはまるで含まれていないのだ。お前は夢存論者が頑なに俺は神であり、他は幻像だとわめくのを嗤うだろう。だが今は俺の話を聞け。
(さて、最後の審判のその時に神の前にしゃしゃり出て大音声に呼ばわった一人の狂人があった。「お前は誰だ。何の権利があってそこに座っている。どけ。神は俺だ。そしてその他に何も無い」。その男は神の大哄笑に綿毛のように吹っ飛んでしまったのだが、だが笑ってはならないのだ。神、世界よ。たとい一瞬であるにせよ、あなたは現象の中で自分しか見えなかった狂人に裁かれたのだから。)
?.〈叛逆〉の章
(存在素地。或いは真正?無?。そこと現実世界との間に隔絶の存するのを知れ。それこそ意識の故郷喪失を生む、根源的〈断層〉なのだ。)
(赤ん坊は最初眼が見えないという。――何を言う。見えないのではない。そこに違和を感じ、認識し得ず、受容し得ないのだ。赤ん坊の脳髄は必死に自己の無垢なる意識を歪めているのだ。生きるために、存在界を受容するために、必死に現象製造の作業を進めているのだ。眼、視覚で物自体を歪め、〈現象化=認識〉で意識を歪めている。そして、無垢を失った時に初めて世界を「見る」ことができるのだ。――だが赤ん坊は果たして自分のまわりの世界を受け容れただろうか?――否。〈慣れ〉のうちに最初の違和を愚かしく忘れてしまうことはあっても。)
私の内には忘れ去られ、今は視界の水平線に浮き沈むばかりの漠たる発生前の記憶がある。真正?無?、世界を点――重さも大きさも何もない無限小そのもの、すなわちゼロ次元――にまで縮め、更にそれを掻き消したようなそこ。無限真空の空間としての宇宙的虚空ではなく、いっさいの物的存在が自身を容れる幅をもたないところの、まさに視覚化されない時空のない〈微視なるもの〉の領域に茫としてあるようなそこを永劫の太古から眺め続けていたような、そんな記憶が時々浮かぶ。その時、私は何者でもなかった。存在ではなく純然たる意識として無の中に茫と広がり私語していたようでもある。――違和。それは?無?がいきなり神の創造行為によって存在界と無理矢理出遭わされた時からの、決して和し得なかった驚愕の尾を引いた思いではなかったか? 存在素地、或いは現実根源。私の故郷はそこであり、それこそが現実であった。私の意識はそこから引きずり出され、世界のために私の無垢は歪んだ。
(夢から熟眠に落ちると人は言う。いや、夢は実は続いているのだ。それは空白の夢、私達の原初の記憶なのだ。白昼のもののかたちを徐々に追い払い、やがて虚無、存在素地であり現実根源である真正?無?を思い出しているのだ。ひゅう、何故に眠らぬ人は気が狂ってしまうんだろう。また何故に人は眠りを安らかさと呼ぶんだろうか。おお、それは意識が存在界と出遭う時に強いられる歪みに耐え切れなくなっているからなのだ。)
恐らくはその真正?無?から〈点〉が宇宙発生の端緒として現出した時、そこからもう違和と不快は始まっていたのだ。存在素地と存在との間に引き裂かれた〈点〉の嘆き。ひゅう、それだけでも発生を司る神というのは許しがたい存在ではないか。存在素地、その無垢は既に私達から奪われてしまったのだ。創造以前のその場処は神が〈有〉を一つ創造するたびに減じていったのだ。
――そうだ。最後の審判はなければならない。その時、神=存在、現実世界は、〈存在素地=無=意識それのみ〉の前に裁かれねばならない。
造物主よ、世界よ、消え入らねばならないのはお前だ。私達、意識=無こそが神ならぬ審判者なのだ。さあ、自らお前の創造の身勝手を恥じ入るがよい。私達を無=創造以前から引きずり出し、有の汚れと肉の限定にわれらの無垢を歪め、違和に苦しめ、自分と自身の間に悪しく咲いた黒い薔薇、否のブラックホールの放つ?否?の毒花粉にさいなませたことを。さあ消えてしまえ。現実世界もろとも、そこに咲く双子の毒花――違和と否のブラックホールもろとも、おのれがそこから生じ来たったところの無の中へ。造物主よ、消え入らねばならぬのはお前だ。
?.〈無限〉の章
(無限よ……。超我なる意識を呼ぼう。浮力を持って彼方へ、存在素地という無限可能のもとへ)
(存在素地――無限な可能性の平衡状態。白紙にとどまり、〈なる〉の自己限定を否む、その全とも無ともつかぬ無限にして無形式の思惟持てる超我のみ存する世界だ。妄想と現実の区別などそこにありはしない)
(人間は超我となる時に無限となる。そうだ。無限可変の名のもとに有限なる存在は変形せられなばならぬ。)
一枚のルドンのリトグラフィを見た時、一種名状しがたい思いがよぎった。
――眼球は不思議な気球のように無限の方に向う。(※注)
ルドンの眼は今や大気の中の単眼の気球となって茫漠とした浮力をもって空のかなた、宇宙の果てへと、上へ上へと、浮上してゆくのであった。大地から自らもそれと気づかぬうちに、ふんわりと離れゆき、かなた、茫とした暗黒にして広大な味気ない大真空宇宙の方向にその光なき瞳をかたくなに向けたまま。
(眼球=意識よ。飛べ、飛んでゆけ。そうだ。無限にまで馳せ昇り、そこで超我と存在素地をつかめ)
そうだ。俺もまたそのように物質=神、すなわち存在界を下方に置き去りにして、その流動のうちから違和の反発力を借りて、ホバークラフトのごとくに浮かび上がらねばならない。そして大気圏を離れ、何の抵抗摩擦もない真空宇宙を、その最初の浮力を保ちつづけて、上方へ上方へと泳ぎゆき、やがては宇宙の海の水面〔みのも〕にぼっかりと円く穴を開けて、もはやそこに空間もない真正?無?の領域にまで行くのだ……。
恐らくは、ルドンの眼もまた無限にまで達した時に、初めてその光なき巨大な瞳を下方に向けるであろう。下方へと振り返った時、そこでは物質=神が流動しているはずだ。そうだ。その時こそ、最後の審判を告げるラッパの音が大宇宙を震え上がらせることだろう。
眺め下ろす大眼球の下方で宇宙の表情が蒼白になるその時は、さて、いつの日に訪れるのであろうか。
※注 オディロン・ルドン(1840-1916 フランス 画家)の石版画集「エドガー・ポーに」(1882)収録作品?のタイトル。このタイトルはルドン自身の創作した一種の詩である。
初出:東京都都立日比谷高等学校 雑誌「日比谷」創刊号(昭和五十四年三月 創立百周年)
http://ameblo.jp/novalis666/entry-10000741351.html
【離人症考: 虚無の憑き物が落ちたときのこと】
前にも書いたが、僕は青少年期の殆どを離人症という虚無の独房の中で生きてきた。
この病気については、木村敏の本(『時間と自己』中公新書などがオススメ)などに詳しく載っている。
また、病名は違うのだがブランケンブルクの『自明性の喪失―分裂病の現象学』に出てくる分裂病(今日では統合失調症といわなきゃいけないらしい。どうなんだろ)の女性の症例はとても身に積まされる思いで読んだ覚えがある。
それは世界の意味を知解できるのに、それを自明の事として了解できない状態で、ブランケンブルクのいった〈自然な自明性の喪失〉という表現は、訳者の木村敏も認めている通り、離人症の世界がどういう世界なのかをとてもよく言い当てている。
この病気は今はどうにか治まっている。
二十代後半、ほとんど自殺寸前のところまで絶望しきっていた僕に奇蹟が起きたのだ。
奇蹟とは愛だった。
そのころ、僕とは正反対に、ほとんど無差別殺人寸前のところまで逼迫した精神状態の女性と僕は運命的に出会った。
まあ「大恋愛」ならぬ「大変愛」だったのだが、その女性が僕を救った。
彼女が僕を救えたのは、とても珍しいことに、全く損なわれていない童心をかたくなに保持し、所謂〈大人〉になることを拒絶して、大きな子どもに成長した人だったからだ。
アンデルセンの「雪の女王」の童話に出てくるヒルダのような彼女の勇敢な童心によって、僕の目を、僕の魂を閉ざしていた虚無に氷った絶望の呪縛は解けた。
小さな子供であった彼女だけが、本当の僕を、この僕自身ですら見失っていた本当の僕の心を、つまり「童心」という名の純粋理性をこの僕に見つけ出し、取り戻すことができたのである。
こうして、死者は復活した。けれども、或る意味では、僕はそのときに死んでしまったのかもしれないのである。
虚無のゴーレムとのすれ違い
1989年4月23日、とても不思議な出来事が起こり、僕は死に、そして生まれた。それは僕が彼女を愛しているということを知った日付である。だが、それと同時に僕は〈死〉を見た。パンと葡萄酒の秘蹟がその日、まさに神の見えざる手によって行われたことを僕しか知らない。そして、この僕自身、その日、その時にそれが執り行われていたことを知らず、ずいぶん後になって思い当たって、戦慄を覚えたのである。
あの瞬間、僕とすれ違った真っ黒な虚無の影と、その影のなかに垣間見た絶無の宇宙のことを僕は一生忘れることがないだろう。あの一瞬、僕のまわりで全宇宙が蒸発し、そしてこの僕自身ですらも虚無のなかに消滅していた。
ああ、死ぬのだな、と思った瞬間に、世界は戻った。本当に一瞬のことだった。そのとき、僕に、偶然たまたま乾パンとワインを出してくれた人に、僕は今、揺れなかったかと尋ねた。そう、世界が一瞬ゆらりと揺れて、虚無の中に消えかかるような全く普通で無い地震のゆらめきを僕は感じたのだから。
その人はそのとき、揺れなかった、と言ったが、後日、同席していた別の人に、本当はあのとき確かに揺れた、その揺れを感じたと打ち明けた。打ち明けられたその人は、その揺れを感じていなかった(よく分からなかった)らしいが、その話を僕にしてくれた。
僕に乾パンとワインを出し、知らぬ間に秘蹟の司祭になっていた人も、僕の身に起きたその異変の揺れに引き込まれたのかもしれない。そして、その人のおかげで、僕は自分が誰を愛しているか、いや、誰を愛さねばならないかを知ったのだ。その人は僕に何をし何を教えてしまったかを知らない。それは神と僕しか知らない出来事だった。
その人にはその日以来二度と決して会うことがなかった。けれども本当にその人には感謝している。その人は女性であるが、僕にとってはキリストであった。
キリストが彼女において現れ、そして、指し示して教えてくれたのだ。蘇った死者が、そのむくろを虚無の中に捨てて、何処にゆくべきであるのかを。
そうして、僕はその通りにした。神に示された女性のもとに行き、そしてその女性と、僕の純粋理性と、僕は結ばれ、そして今も共にいる。それが現在の僕の妻だ。
しかし、神の行なった奇蹟よりも大きな奇蹟は、実に小さな愛によっておきる。神は僕の生命を救ったかもしれないが、心を救いはしなかった。ただ、どうすれば心を救うことができるかの道を示してくれただけである。真に偉大なものは童心である。僕がもし童心に愛されず、童心によって童心を見出されていなければ、せっかく死から蘇っても、魂のないゴーレムになっただけで終わったであろう。
あのとき、僕がすれちがった、全身虚無のマテリアルでできた巨大な影、あの絶無の暗黒の巨人がそのゴーレムである。僕は知っている。あれは僕であり、あの日に死んだ僕である。そして、その真の名前は虚無である。僕は〈無〉であった。それはこの僕が〈死〉であったということと同じである。そして、この〈無〉は真実を見ていた。見てはならない恐ろしい真実をあの一瞬に厳格に照らし出してみせたのだ。本当は世界には何も無い。世界も無い。絶無以外に何も無い。世界が存在するということ、そんなことなどありえないのだという黙示録的真実を。
http://ameblo.jp/novalis666/entry-10001344735.html
前にも書いたが、僕は青少年期の殆どを離人症という虚無の独房の中で生きてきた。
この病気については、木村敏の本(『時間と自己』中公新書などがオススメ)などに詳しく載っている。
また、病名は違うのだがブランケンブルクの『自明性の喪失―分裂病の現象学』に出てくる分裂病(今日では統合失調症といわなきゃいけないらしい。どうなんだろ)の女性の症例はとても身に積まされる思いで読んだ覚えがある。
それは世界の意味を知解できるのに、それを自明の事として了解できない状態で、ブランケンブルクのいった〈自然な自明性の喪失〉という表現は、訳者の木村敏も認めている通り、離人症の世界がどういう世界なのかをとてもよく言い当てている。
この病気は今はどうにか治まっている。
二十代後半、ほとんど自殺寸前のところまで絶望しきっていた僕に奇蹟が起きたのだ。
奇蹟とは愛だった。
そのころ、僕とは正反対に、ほとんど無差別殺人寸前のところまで逼迫した精神状態の女性と僕は運命的に出会った。
まあ「大恋愛」ならぬ「大変愛」だったのだが、その女性が僕を救った。
彼女が僕を救えたのは、とても珍しいことに、全く損なわれていない童心をかたくなに保持し、所謂〈大人〉になることを拒絶して、大きな子どもに成長した人だったからだ。
アンデルセンの「雪の女王」の童話に出てくるヒルダのような彼女の勇敢な童心によって、僕の目を、僕の魂を閉ざしていた虚無に氷った絶望の呪縛は解けた。
小さな子供であった彼女だけが、本当の僕を、この僕自身ですら見失っていた本当の僕の心を、つまり「童心」という名の純粋理性をこの僕に見つけ出し、取り戻すことができたのである。
こうして、死者は復活した。けれども、或る意味では、僕はそのときに死んでしまったのかもしれないのである。
虚無のゴーレムとのすれ違い
1989年4月23日、とても不思議な出来事が起こり、僕は死に、そして生まれた。それは僕が彼女を愛しているということを知った日付である。だが、それと同時に僕は〈死〉を見た。パンと葡萄酒の秘蹟がその日、まさに神の見えざる手によって行われたことを僕しか知らない。そして、この僕自身、その日、その時にそれが執り行われていたことを知らず、ずいぶん後になって思い当たって、戦慄を覚えたのである。
あの瞬間、僕とすれ違った真っ黒な虚無の影と、その影のなかに垣間見た絶無の宇宙のことを僕は一生忘れることがないだろう。あの一瞬、僕のまわりで全宇宙が蒸発し、そしてこの僕自身ですらも虚無のなかに消滅していた。
ああ、死ぬのだな、と思った瞬間に、世界は戻った。本当に一瞬のことだった。そのとき、僕に、偶然たまたま乾パンとワインを出してくれた人に、僕は今、揺れなかったかと尋ねた。そう、世界が一瞬ゆらりと揺れて、虚無の中に消えかかるような全く普通で無い地震のゆらめきを僕は感じたのだから。
その人はそのとき、揺れなかった、と言ったが、後日、同席していた別の人に、本当はあのとき確かに揺れた、その揺れを感じたと打ち明けた。打ち明けられたその人は、その揺れを感じていなかった(よく分からなかった)らしいが、その話を僕にしてくれた。
僕に乾パンとワインを出し、知らぬ間に秘蹟の司祭になっていた人も、僕の身に起きたその異変の揺れに引き込まれたのかもしれない。そして、その人のおかげで、僕は自分が誰を愛しているか、いや、誰を愛さねばならないかを知ったのだ。その人は僕に何をし何を教えてしまったかを知らない。それは神と僕しか知らない出来事だった。
その人にはその日以来二度と決して会うことがなかった。けれども本当にその人には感謝している。その人は女性であるが、僕にとってはキリストであった。
キリストが彼女において現れ、そして、指し示して教えてくれたのだ。蘇った死者が、そのむくろを虚無の中に捨てて、何処にゆくべきであるのかを。
そうして、僕はその通りにした。神に示された女性のもとに行き、そしてその女性と、僕の純粋理性と、僕は結ばれ、そして今も共にいる。それが現在の僕の妻だ。
しかし、神の行なった奇蹟よりも大きな奇蹟は、実に小さな愛によっておきる。神は僕の生命を救ったかもしれないが、心を救いはしなかった。ただ、どうすれば心を救うことができるかの道を示してくれただけである。真に偉大なものは童心である。僕がもし童心に愛されず、童心によって童心を見出されていなければ、せっかく死から蘇っても、魂のないゴーレムになっただけで終わったであろう。
あのとき、僕がすれちがった、全身虚無のマテリアルでできた巨大な影、あの絶無の暗黒の巨人がそのゴーレムである。僕は知っている。あれは僕であり、あの日に死んだ僕である。そして、その真の名前は虚無である。僕は〈無〉であった。それはこの僕が〈死〉であったということと同じである。そして、この〈無〉は真実を見ていた。見てはならない恐ろしい真実をあの一瞬に厳格に照らし出してみせたのだ。本当は世界には何も無い。世界も無い。絶無以外に何も無い。世界が存在するということ、そんなことなどありえないのだという黙示録的真実を。
http://ameblo.jp/novalis666/entry-10001344735.html
【〈別人〉へのまなざし】
〈別人〉は、対人恐怖症患者の深刻な恐怖の対象として知られている強迫観念である。これは所謂〈他者〉と同じではない。〈他者〉は〈自己〉の反対概念であるが、〈別人〉は〈本人〉の反対概念であって、その意味が全く違っている。
しかし、それにも拘わらず〈他者〉と〈別人〉は混同されやすい。〈自己−他者〉の対立軸と〈本人−別人〉の対立軸は交差するものであっても決して平行するものではない。〈自己〉と〈本人〉が同一人物ではないように、〈他者〉と〈別人〉も同一人物ではない。
ところが、欧米語には〈別人〉と〈他者〉を明確に単語のうえで識別する表現がない。このことが飜って悪影響して要らぬ思想の混乱を招いているのは、皮肉なことに、日常会話の次元にあっては〈他者〉と〈別人〉を普通に識別している日本の方なのである。いざ抽象的で学術的な話になると、むしろ〈別人〉とか〈別人性〉と言った方がよいものまで、〈他者〉とか〈他者性〉という言葉で表現してしまう学者知識人の非常に悪い癖がある。
私の知る限り、自己と他者という倫理学的問題系にあっては、〈他者〉ではなく、むしろ〈別人〉こそが問題だということに気づいている論者は、僅かに村瀬学くらいのものである。
村瀬学は或る短い論文のなかで、対人恐怖症患者が訴える「別人の恐怖」に着目して、何故如何にして人間にこのような得体の知れない恐怖が出来するのかを「成り込み」という独自の概念によって解明しようとしている。
*/
こうした「発生点としての私」と「成り込みする私」の決定的な違いは、自意識の中に人間固有の恐怖を生み出すところにあった。それは「別人」への恐怖とも呼ぶべき恐怖現象である。その恐怖感の強さには、想像を絶するものがあるので、今まではたいてい病的心理学の問題として考察されがちであった。しかし「発生点としての私」と「成り込みする私」の決定的な差に根本の原因があるのだということになると、いくらかは日常的に理解できる道も開けてくる。
そもそも私たちが安全だと感じるのは、見知らぬ、危険なものが、近づけない処に居る時である。だから野獣や敵の近づくのを防ぐのなら、柵を設け、頑丈な家を作ればすむ。しかし「私」が生み出した「にせの人間」が近づくのを防ぐことは、大変難しいのである。というのも「私」が居る限り、いくらでも「にせの人間」を産み続けることができるからである。「にせの人間」とは何か。それを私はここで「別人」と呼んでおくことにする。「別人」とは、「知っている人が知らない人として現れる現象」と考えておくことにする。この「知っている人」の中には当然「私」も含まれる。そして私たちはこの「別人」に直面する時、言い知れぬ恐怖を覚えることになるのである。
この「別人」が恐怖として現れる筋道を、日常生活で使われる言い方で言えばどうなるだろうか。たぶんそれは「人見知り」「恥ずかしがり」「対人恐怖」の三つになるだろう。「人見知り」とは、「知らない人」の現れに対して見せる反応であり、「恥ずかしがる」というのは、「知られている自分」が「知られていない自分」として現れてしまうことへの戸惑いの反応であり、「対人恐怖」とは「人間」に「別人」を感じ出す所での反応、として考えることができるだろう。(中略)
このようにして見てみれば、「対人恐怖」とは、決して単に人を恐れたり、こわがったりするというような現象ではないことがわかってくる。ここにはつまり、過剰に「人」のことを意識せざるを得なくなった人間の在り方そのものの問題が現れていたのである。つまり「人」がまるで「人以上のもの」に感じられてゆく問題である。それは「監視する他者」とでも呼ばれるべき者の現れの問題なのだ..(後略)
/*
(村瀬学「恐怖、この他者にふれることの体験」池上哲司他編「叢書《エチカ》?自己と他者―さまざまな自己との出会い」昭和堂1994刊所収)
私自身は〈別人〉に関して村瀬とはやや違った概念をもっている(つまり彼のいう〈別人〉と私のいう〈別人〉は困った事にまた別人なのだ)が、村瀬の展開する議論はそれ自体として非常に面白く示唆に富むものである。村瀬は〈別人〉という偽の人間の観念の起源を子供の空想の世界に求めている。子供は色々なものに成ろうとするがそのなかには現実的に決してそれに成ることの出来ないものも含まれる。その空想と現実のズレが現実の方へと破れ出し、自分がそれに成り込めなかったものがその破れ目から睨みつけてくるのが〈別人〉なのではないのかというのが村瀬の別人論の骨子である。
わたしは〈別人〉を勿論そのような「私」の空想の産物に還元するようなことはしない。またそれを「見知らぬもの」の極限形態と考えるありがちな考え方にも反対である。「別人」はむしろ論理的なものであり、それはむしろ根源的で不可避な観念として、意識や知に対してすら超越論的に外的にあるものである。それはそもそも「私」が生み出したものではない。逆に「別人」の方が「私」に先行して存在しているのである。
とはいえ、私自身、〈別人〉の観念を或る対人恐怖症に悩む友人の話から啓示されて忘れ難い印象を覚えた者であるので、村瀬の別人論を深い共感をもって読んだ。〈別人〉という形而上学的で難解な観念の怪物のもつ言い知れぬ深い意味について気づいている稀有な同志をやっと見つけたときの興奮は「朋有り遠方より来る」としか言いようのないものである。
村瀬の別人論には頂けない点もある(それは彼が対人恐怖症を異常心理とみる問題設定上どうしようもないものである)が、〈別人〉という難解で恐ろしい問題があるという一石を投じているだけでもそれは貴重なことなのだ。彼は〈別人〉と〈他者〉をとにかく混同していない。それだけでも思想家としては奇蹟に近い快挙である。
だが他方において、日本の作家たちは、この〈他者〉とは異なる〈別人〉というものについてそれを正しく名指しつつ凝視することを怠っていない。
例えば、高橋たか子の『誘惑者』や村上龍の『イビサ』はまさにこの〈別人〉との対決という思想家たちがサボリ倒している危険な問題に真正面から挑んだ優れた形而上小説であって、その問題の核心を衝いてゆく 観念の詰めの鋭さと気迫は埴谷雄高の『死霊』に勝るとも劣らないものがある。
高橋の『誘惑者』では、自己でもなく他者でもない謎の「別人」という不可思議な存在がまさに表題にある「誘惑者」として機能し、若い女性たちを死の火口の淵へと連れ込んでゆく戦慄すべき物語が綴られている。そしてその物語の随所随所の重要なポイントにおいて「別人」というその黙示録的な言葉は確かに間違いなくその言葉において顕現しているのである。
村上龍の『イビサ』には「別人」についての目を引く言及箇所は一か所しかない。それは極めて些細なさりげない場面にそっと書かれているだけである。しかしそれは本質を衝いている。
「他人が変わるのを見るのは恐いよ。大切な人が別人になっちゃうってことは、自分がよくわからなくなってしまうってことだろう?」(『イビサ』講談社文庫 一〇九頁)
まさにそういうものが〈別人〉なのである。他者の上に起こる受け入れ難い変化の様相が〈別人〉である。それを見ることは恐いことである。それを見ると単に相手がわからなくなってしまうだけでは済まないで、自分で自分がよくわからなくなってしまうという所までゆくからである。
もちろん、〈別人〉という人はいない。
しかしそれは他者を他者でありえなくし、自己を自己でありえなくする恐ろしい力である。
他人が別人になってしまうと、自分も別人になってしまう。それこそが別人の恐怖の本質である。
この言葉は対人恐怖症患者でも何でもない人物の口から漏れているだけに意味深長である。
村上龍は処女作『限りなく透明に近いブルー』以来、しばしば作中に離人症という特殊な病名を登場させる。離人症というのは非人称化を意味するデパーソナリゼーションという病名の和訳で、一種の人格喪失体験である。
これは自己へと折り返された対人恐怖症であるといってよいもので、自分で自分がまるで別人のように異質に感じられてしまう病である。この病は分裂症などの前駆症状としてもよく現れる異常心理だが、単純に自分自身に対する対人恐怖と考えて差し支えない。
私自身もこれを長患いしたことがあるが、苦しく恐ろしい病いであるにはあっても問題は意外と単純なのである。
対人恐怖症では他者が別人になるように、離人症では自己が別人になるだけの話なのである。
もちろんそれがひどくなると対人恐怖症よりも難解で無気味な事態にまで発展する。時間が連続性のない瞬間の砂となってサラサラと崩壊してゆくし、また、まるで非ユークリッド空間に迷い込んだような遠近感の狂いや世界の平面化、それに空間の歪みまで見ることになる。物や人がまるで化け物のようにおぞましく見えるし、自分の心に生きた感情が感じられなくなる。怒りも悲しみも喜びも自分のなかを素通りしていってしまう。頭だけは異常に冴えわたっていて非常に切れる抽象的思考が出来るがすべてが虚しくてしかたがない。物事や言葉の意味は分かるが、その分かるということがまるで嘘のように空々しいのである。自分が誰かは知っているし現実についての知識や認識力には全く欠陥がないが、その全てにどうしようもない馴染めない違和感が冷たく苦い氷のように纏わりついて離れない。
私の場合は余りに絶望的で虚無的な気分なので自殺する気にも殆どなれなかった。むしろ自分は既に死んでいて、死んでいるのに生きているふりをし続けねばならず、しかも周囲の誰も私が本当は死んでいるのだということに気づかないのでたちが悪いのである。
そこで生きているのは私ではない別人だった。誰もがその別人こそが私なのだと思い込んでいるので私はいないも同然だった。これは無視されるより辛いことである。他人に私が不可視なのである。私が私でないものにすげかえられ続けるのである。これは宇宙の悪意であった。
今にして思うなら、あれこそが死である。私は殺されていたし殺され続けていたのである。私は死後の世界を生きていたし、それも地獄を生きていた。あれを死や地獄と言わないとしたら何を死や地獄というのか私には分からない。私は普通の意味でいう死よりも恐ろしい死を知っているし、地獄よりも地獄的な真の地獄を見て来た。離人症より恐ろしいものはありえない。それに比べれば死ぬことも地獄に落ちることも私は少しも恐いとは思わない。肉体の苦痛は痛いだけだ。痛みを感じられることが私には嬉しい。それは私の痛みだからである。死ぬことも傷つくことも狂うことも病むことも私は嫌だとは思っても恐くはないし、本当はそれも素晴らしいことなのだと知っている。死ぬのは私なのだ。傷つくのは私なのだ。狂うのは私なのだ。病むのは私なのだ。私がそこにいる。私の人生がそこにある。それを奪われることに比べればどんなひどい人生でも無いよりはましなのだ。
私は知っている。現実は美しい。
私はもう幽霊ではない。私は私を抱き締めることが出来る。でも、昔は自分自身と永遠に擦違うことしか出来なかったのだ。
人は一般に狂気や死を恐れる。しかしそれは間違っている。
死や狂気は離人症とは違って甘美である。離人症は狂いたくても狂えないし、死にたくても死ねないという絶望である。
そこに何がある? 冷たい明晰さといつまでも続く苦さと辛さだけだ。苦しみすらないということがどれほどひどいことかあなたには想像できるだろうか。
あれはニルヴァーナである。私は悟っていた。私は全く仏陀だった。慈悲深い凍りついた微笑を浮かべている他に何も出来ない人間、他人を無心に救えても己れの心を救えない人間、そんなもの最低である。
私は離人症患者だったとき平安であった。魂の墓場というのは平安であるに決まっている。涅槃こそが地獄である。永遠こそが十字架である。そういう聖なる虚無を愛する人間は莫迦なのだ。無はどんな毒よりも苦い。
今、私は自分の体に赤い血が流れていることが嬉しいのである。昔は、水よりもサラサラした白く透明な血が、ガラスの体のなかを流れていた。
昔の私は仏像だったが、今の私は復活したイエスのようだ。時々あの虚無の十字架に釘付けにされていたときの古傷が聖痕のように疼いて痛み、黒い怒りに胸が詰まって動けなくなるが、そんな後遺症を抱えていたって私は離人症に勝ったのだ。私はもはや決してあの悪夢の現実の薄汚れた墓穴には入らない。
私は死んで死を殺し、狂って狂気を狂わせた。
今の私は永遠に生きるだろう。
もはやいかなる力もこの私を打ち砕けない。
何故なら私は〈この私〉を見い出したからである。
〈この私〉とは〈虚体〉である。
http://ameblo.jp/novalis666/entry-10000863103.html
〈別人〉は、対人恐怖症患者の深刻な恐怖の対象として知られている強迫観念である。これは所謂〈他者〉と同じではない。〈他者〉は〈自己〉の反対概念であるが、〈別人〉は〈本人〉の反対概念であって、その意味が全く違っている。
しかし、それにも拘わらず〈他者〉と〈別人〉は混同されやすい。〈自己−他者〉の対立軸と〈本人−別人〉の対立軸は交差するものであっても決して平行するものではない。〈自己〉と〈本人〉が同一人物ではないように、〈他者〉と〈別人〉も同一人物ではない。
ところが、欧米語には〈別人〉と〈他者〉を明確に単語のうえで識別する表現がない。このことが飜って悪影響して要らぬ思想の混乱を招いているのは、皮肉なことに、日常会話の次元にあっては〈他者〉と〈別人〉を普通に識別している日本の方なのである。いざ抽象的で学術的な話になると、むしろ〈別人〉とか〈別人性〉と言った方がよいものまで、〈他者〉とか〈他者性〉という言葉で表現してしまう学者知識人の非常に悪い癖がある。
私の知る限り、自己と他者という倫理学的問題系にあっては、〈他者〉ではなく、むしろ〈別人〉こそが問題だということに気づいている論者は、僅かに村瀬学くらいのものである。
村瀬学は或る短い論文のなかで、対人恐怖症患者が訴える「別人の恐怖」に着目して、何故如何にして人間にこのような得体の知れない恐怖が出来するのかを「成り込み」という独自の概念によって解明しようとしている。
*/
こうした「発生点としての私」と「成り込みする私」の決定的な違いは、自意識の中に人間固有の恐怖を生み出すところにあった。それは「別人」への恐怖とも呼ぶべき恐怖現象である。その恐怖感の強さには、想像を絶するものがあるので、今まではたいてい病的心理学の問題として考察されがちであった。しかし「発生点としての私」と「成り込みする私」の決定的な差に根本の原因があるのだということになると、いくらかは日常的に理解できる道も開けてくる。
そもそも私たちが安全だと感じるのは、見知らぬ、危険なものが、近づけない処に居る時である。だから野獣や敵の近づくのを防ぐのなら、柵を設け、頑丈な家を作ればすむ。しかし「私」が生み出した「にせの人間」が近づくのを防ぐことは、大変難しいのである。というのも「私」が居る限り、いくらでも「にせの人間」を産み続けることができるからである。「にせの人間」とは何か。それを私はここで「別人」と呼んでおくことにする。「別人」とは、「知っている人が知らない人として現れる現象」と考えておくことにする。この「知っている人」の中には当然「私」も含まれる。そして私たちはこの「別人」に直面する時、言い知れぬ恐怖を覚えることになるのである。
この「別人」が恐怖として現れる筋道を、日常生活で使われる言い方で言えばどうなるだろうか。たぶんそれは「人見知り」「恥ずかしがり」「対人恐怖」の三つになるだろう。「人見知り」とは、「知らない人」の現れに対して見せる反応であり、「恥ずかしがる」というのは、「知られている自分」が「知られていない自分」として現れてしまうことへの戸惑いの反応であり、「対人恐怖」とは「人間」に「別人」を感じ出す所での反応、として考えることができるだろう。(中略)
このようにして見てみれば、「対人恐怖」とは、決して単に人を恐れたり、こわがったりするというような現象ではないことがわかってくる。ここにはつまり、過剰に「人」のことを意識せざるを得なくなった人間の在り方そのものの問題が現れていたのである。つまり「人」がまるで「人以上のもの」に感じられてゆく問題である。それは「監視する他者」とでも呼ばれるべき者の現れの問題なのだ..(後略)
/*
(村瀬学「恐怖、この他者にふれることの体験」池上哲司他編「叢書《エチカ》?自己と他者―さまざまな自己との出会い」昭和堂1994刊所収)
私自身は〈別人〉に関して村瀬とはやや違った概念をもっている(つまり彼のいう〈別人〉と私のいう〈別人〉は困った事にまた別人なのだ)が、村瀬の展開する議論はそれ自体として非常に面白く示唆に富むものである。村瀬は〈別人〉という偽の人間の観念の起源を子供の空想の世界に求めている。子供は色々なものに成ろうとするがそのなかには現実的に決してそれに成ることの出来ないものも含まれる。その空想と現実のズレが現実の方へと破れ出し、自分がそれに成り込めなかったものがその破れ目から睨みつけてくるのが〈別人〉なのではないのかというのが村瀬の別人論の骨子である。
わたしは〈別人〉を勿論そのような「私」の空想の産物に還元するようなことはしない。またそれを「見知らぬもの」の極限形態と考えるありがちな考え方にも反対である。「別人」はむしろ論理的なものであり、それはむしろ根源的で不可避な観念として、意識や知に対してすら超越論的に外的にあるものである。それはそもそも「私」が生み出したものではない。逆に「別人」の方が「私」に先行して存在しているのである。
とはいえ、私自身、〈別人〉の観念を或る対人恐怖症に悩む友人の話から啓示されて忘れ難い印象を覚えた者であるので、村瀬の別人論を深い共感をもって読んだ。〈別人〉という形而上学的で難解な観念の怪物のもつ言い知れぬ深い意味について気づいている稀有な同志をやっと見つけたときの興奮は「朋有り遠方より来る」としか言いようのないものである。
村瀬の別人論には頂けない点もある(それは彼が対人恐怖症を異常心理とみる問題設定上どうしようもないものである)が、〈別人〉という難解で恐ろしい問題があるという一石を投じているだけでもそれは貴重なことなのだ。彼は〈別人〉と〈他者〉をとにかく混同していない。それだけでも思想家としては奇蹟に近い快挙である。
だが他方において、日本の作家たちは、この〈他者〉とは異なる〈別人〉というものについてそれを正しく名指しつつ凝視することを怠っていない。
例えば、高橋たか子の『誘惑者』や村上龍の『イビサ』はまさにこの〈別人〉との対決という思想家たちがサボリ倒している危険な問題に真正面から挑んだ優れた形而上小説であって、その問題の核心を衝いてゆく 観念の詰めの鋭さと気迫は埴谷雄高の『死霊』に勝るとも劣らないものがある。
高橋の『誘惑者』では、自己でもなく他者でもない謎の「別人」という不可思議な存在がまさに表題にある「誘惑者」として機能し、若い女性たちを死の火口の淵へと連れ込んでゆく戦慄すべき物語が綴られている。そしてその物語の随所随所の重要なポイントにおいて「別人」というその黙示録的な言葉は確かに間違いなくその言葉において顕現しているのである。
村上龍の『イビサ』には「別人」についての目を引く言及箇所は一か所しかない。それは極めて些細なさりげない場面にそっと書かれているだけである。しかしそれは本質を衝いている。
「他人が変わるのを見るのは恐いよ。大切な人が別人になっちゃうってことは、自分がよくわからなくなってしまうってことだろう?」(『イビサ』講談社文庫 一〇九頁)
まさにそういうものが〈別人〉なのである。他者の上に起こる受け入れ難い変化の様相が〈別人〉である。それを見ることは恐いことである。それを見ると単に相手がわからなくなってしまうだけでは済まないで、自分で自分がよくわからなくなってしまうという所までゆくからである。
もちろん、〈別人〉という人はいない。
しかしそれは他者を他者でありえなくし、自己を自己でありえなくする恐ろしい力である。
他人が別人になってしまうと、自分も別人になってしまう。それこそが別人の恐怖の本質である。
この言葉は対人恐怖症患者でも何でもない人物の口から漏れているだけに意味深長である。
村上龍は処女作『限りなく透明に近いブルー』以来、しばしば作中に離人症という特殊な病名を登場させる。離人症というのは非人称化を意味するデパーソナリゼーションという病名の和訳で、一種の人格喪失体験である。
これは自己へと折り返された対人恐怖症であるといってよいもので、自分で自分がまるで別人のように異質に感じられてしまう病である。この病は分裂症などの前駆症状としてもよく現れる異常心理だが、単純に自分自身に対する対人恐怖と考えて差し支えない。
私自身もこれを長患いしたことがあるが、苦しく恐ろしい病いであるにはあっても問題は意外と単純なのである。
対人恐怖症では他者が別人になるように、離人症では自己が別人になるだけの話なのである。
もちろんそれがひどくなると対人恐怖症よりも難解で無気味な事態にまで発展する。時間が連続性のない瞬間の砂となってサラサラと崩壊してゆくし、また、まるで非ユークリッド空間に迷い込んだような遠近感の狂いや世界の平面化、それに空間の歪みまで見ることになる。物や人がまるで化け物のようにおぞましく見えるし、自分の心に生きた感情が感じられなくなる。怒りも悲しみも喜びも自分のなかを素通りしていってしまう。頭だけは異常に冴えわたっていて非常に切れる抽象的思考が出来るがすべてが虚しくてしかたがない。物事や言葉の意味は分かるが、その分かるということがまるで嘘のように空々しいのである。自分が誰かは知っているし現実についての知識や認識力には全く欠陥がないが、その全てにどうしようもない馴染めない違和感が冷たく苦い氷のように纏わりついて離れない。
私の場合は余りに絶望的で虚無的な気分なので自殺する気にも殆どなれなかった。むしろ自分は既に死んでいて、死んでいるのに生きているふりをし続けねばならず、しかも周囲の誰も私が本当は死んでいるのだということに気づかないのでたちが悪いのである。
そこで生きているのは私ではない別人だった。誰もがその別人こそが私なのだと思い込んでいるので私はいないも同然だった。これは無視されるより辛いことである。他人に私が不可視なのである。私が私でないものにすげかえられ続けるのである。これは宇宙の悪意であった。
今にして思うなら、あれこそが死である。私は殺されていたし殺され続けていたのである。私は死後の世界を生きていたし、それも地獄を生きていた。あれを死や地獄と言わないとしたら何を死や地獄というのか私には分からない。私は普通の意味でいう死よりも恐ろしい死を知っているし、地獄よりも地獄的な真の地獄を見て来た。離人症より恐ろしいものはありえない。それに比べれば死ぬことも地獄に落ちることも私は少しも恐いとは思わない。肉体の苦痛は痛いだけだ。痛みを感じられることが私には嬉しい。それは私の痛みだからである。死ぬことも傷つくことも狂うことも病むことも私は嫌だとは思っても恐くはないし、本当はそれも素晴らしいことなのだと知っている。死ぬのは私なのだ。傷つくのは私なのだ。狂うのは私なのだ。病むのは私なのだ。私がそこにいる。私の人生がそこにある。それを奪われることに比べればどんなひどい人生でも無いよりはましなのだ。
私は知っている。現実は美しい。
私はもう幽霊ではない。私は私を抱き締めることが出来る。でも、昔は自分自身と永遠に擦違うことしか出来なかったのだ。
人は一般に狂気や死を恐れる。しかしそれは間違っている。
死や狂気は離人症とは違って甘美である。離人症は狂いたくても狂えないし、死にたくても死ねないという絶望である。
そこに何がある? 冷たい明晰さといつまでも続く苦さと辛さだけだ。苦しみすらないということがどれほどひどいことかあなたには想像できるだろうか。
あれはニルヴァーナである。私は悟っていた。私は全く仏陀だった。慈悲深い凍りついた微笑を浮かべている他に何も出来ない人間、他人を無心に救えても己れの心を救えない人間、そんなもの最低である。
私は離人症患者だったとき平安であった。魂の墓場というのは平安であるに決まっている。涅槃こそが地獄である。永遠こそが十字架である。そういう聖なる虚無を愛する人間は莫迦なのだ。無はどんな毒よりも苦い。
今、私は自分の体に赤い血が流れていることが嬉しいのである。昔は、水よりもサラサラした白く透明な血が、ガラスの体のなかを流れていた。
昔の私は仏像だったが、今の私は復活したイエスのようだ。時々あの虚無の十字架に釘付けにされていたときの古傷が聖痕のように疼いて痛み、黒い怒りに胸が詰まって動けなくなるが、そんな後遺症を抱えていたって私は離人症に勝ったのだ。私はもはや決してあの悪夢の現実の薄汚れた墓穴には入らない。
私は死んで死を殺し、狂って狂気を狂わせた。
今の私は永遠に生きるだろう。
もはやいかなる力もこの私を打ち砕けない。
何故なら私は〈この私〉を見い出したからである。
〈この私〉とは〈虚体〉である。
http://ameblo.jp/novalis666/entry-10000863103.html
【悪魔の影と夢魔の視線】
〈別人〉、それは恐るべき自我の原罪というべきものだ。
わたしは〈他者〉と言っているのではない。〈他人〉とも言っていない。〈他者〉と〈別人〉を安易に置き換えてはならない。
〈別人〉というのは〈他者〉の全き不可能性である。
それは不可視の呪縛であって、最も醜悪なものを意味する。
* * *
〈別人〉のみにくさ、それはひとを石化させるメドゥーサの顔である。その醜悪さが不可視であるがゆえに、みにくい〈別人〉はしばしば美貌の幻影でその素顔を覆う。
恐ろしい罠だ。
魅惑し、そして、人の心を、いのちを奪う。
それは人殺しの顔である。
ナイフよりも素早くその冷たい一瞥だけであなたを殺す。
憑依してあなたの魂を虜にし、一瞬にして食い殺す。
〈悪〉はそのときに始まるのだ。
* * *
かつて、わたしは鏡のなかに映る己れの像に、見知らぬ人がかすめるのを見た。
再び見ると、それはよく見知っているわたしの貌なのだったが、どうにも見慣れることのできない不可視のぶきみさが貼りついていて取れなかった。
そのころわたしは十六歳で、謙遜するのも馬鹿臭いからはっきりというが、白面の美少年であった。
鏡の中にはヴィジュアルには、中性的な美貌を輝かせた魅力的な細面の、殆ど美少女といってもいい綺麗な顔が浮かんでいた。
もしもナルシスのようにそれが自分の顔だと知らなければ、一目で魂を奪われ、恋い焦がれて焦がれ死んだかもしれない。
わたしは幻想的なまでに美しかった。わたしはわたしに出会い、あらためてそれを見て驚き、たちまちその場に凍りついた。
しかし、美しさに撃たれたのではない。
わたしはそれほどに醜く忌まわしいものを見たことがなかった。微かな吐気と目眩に似たものがわたしのなかを横切っていった。透明で冷たい不可視のからだをもつものが、わたしの〈死霊〉がねじれた恐怖の叫びをあげてわたしを突き抜けていった。
〈死にたい〉という小さな呟きが胸に痛んだ。
イメージというものは本質的に醜いものなのだ。
それが美しければ美しいほど醜悪で耐え難い。
絶望的なまでに狂おしい怒り、殺したい、破壊したい、打ち砕いてしまいたい、この嘘つきの顔を、この頭を。
そう思ったとき、割れんばかりの頭痛がして、わたしは鏡台の前で頭を抱えてしまった。
それからひどい非現実感と離人体験に囚われる日々が続いた。夜には金縛りになり、叫びをあげて振りほどくと、振りほどいた何かが部屋の中ではっきりバサリと黒っぽい翼らしいものを広げてはばたき、部屋の片隅に落ちて、そこに灰色の靄のようにして蹲り、恐ろしいまでにじいーっと刺すような眼差しでわたしを見上げた。
姿だけは速やかに煙のように消えうせながら、瞼もなく、瞳すらもない、全き虚無ともいうべき視線だけが永遠に永遠に消えずに続くのではないかと思われる程長く、そんな気違いじみて自己矛盾した時間の異常な鋭角から、わたしを見据え貫き、無言の、謎めいた咎めを残していった。
それはかなり恐ろしい体験だった。
幻覚は時として現実よりもずっと生々しくリアルである。
わたしはわたしに憑依した何者かを確かに見、暗闇の中でヤコブが天使と戦ったようにそいつと格闘したのだが、勝利したのだとは思えなかった。
また、そいつは天使というよりも悪魔という方がふさわしい化け物だったが、朧ろに見えたその不定形の姿は、大きさからみて人間の赤ん坊に似ていた。
そいつは〈死の天使〉というべき代物か、それとも実体化したわたしのリビドーの一部なのか、よく分からないが、覚えているのはそいつが寝ているわたしの上を巨大なアメーバのように這い回り、わたしの呼吸を塞ごうとしていたということだ。
わたしを窒息死させようとして果たせなかった恨みと呪いの毒をたっぷり塗りたくった邪視の矢を最後に放ってそれが消えゆくとき、わたしはわたしの亡き兄のことを思った。
この兄は赤ん坊の姿のままこの世を去り、その死後にわたしは生まれた。たった一枚の遺影以外に彼の痕跡を伝えるものはまるでないが、この兄のことは物心ついたときからずっと心の上に重く暗くのしかかって忘れたことはない。
母はわたしが胎内にいるとき、この喪われた兄のことを思い出しては泣いていたという。
わたしは母の涙の海のなかに生まれ、その悲しみ啜り泣く声と兄の名前をむなしく呼ぶ声を細胞の奥深くにまで響き通らせ、自分の身に刻んでこの世界に産み落とされたのだ。
その後も母がこの兄のことを思い出しては顔を覆って泣く姿を繰り返し目にした。辛く耐え難い光景だ。わたしはその度に苦しくなる。涙が溢れ出し、悲しみが胸に灼けつくように痛くなる。
兄さん、わたしはあなたを知らない。
だがその全く知らぬあなたからわたしは永遠に離れられない。永遠に永遠にわたしはあなたを愛するだろう、あなたを恨み、あなたに嫉妬し、あなたを狂おしく求め、愛しつづけるだろう。
兄さん、あなたはわたしにかかった永遠の呪いだ。
あなたはわたしを呪う。
何故ならわたしはあなたなのだから。
わたしがわたしの名で名付けられるよりも前に、それよりも深く、わたしのこの身に烙印された絶対的で絶望的な名前。
それをあなたはわたしから永遠に奪うことはできない。
わたしから消し去ることはできない。
わたしはあなたの名を刻まれて生まれてきた。
その傷痕は癒えることはなく永遠にわたしに疼く。
わたしはあなたを病む。わたしはあなたを痛む。
この傷を縫うことも癒すこともあなたにはできない。
それはわたしの存在そのものだから。
いや、わたしの存在そのものをすら焼き潰す程深く激しく、わたしを無化してもなお燃え続ける炎で書かれた名前で、それはあるのだ。
この聖なる火の意志が、わたしがもはやわたしではなくなったときにも、わたしの奥底で、永遠の生命の瘢痕として熾り続けていることをわたしは知っている。
兄さん、わたしはあなたを忘れない。
たといわたしがわたしの名を忘れ、わたしが誰かを忘れ去ってしまっても、あなたのこととあなたの名前を忘れ去ることはないだろう。
たとい全宇宙がわたしの回りで滅び去っても、あなたの名前を綴る火の文字は消されることはないだろう。
恐るべきわたしの兄よ、あなたの名前はメギドの火でできている。その火で灼いた焼ゴテを取り、わたしはあなたの名において、わたしの額にカインの徴を烙印した。
弟アベル、赤ん坊の姿は炎の燔祭に消え、わたしは狂気のなかであなたからあなたを奪いあなたになりすますためにわたしを殺した。
兄さん、わたしではなくあなたが生きることをわたしは望んだ。だが、わたしが手にかけて殺したあの赤ん坊アベルは、あの空しくされた小さな肉体は誰なのか。わたしなのかあなたなのかが判らなくなる。判らなくなる、このわたしは誰なのかわたしなのかあなたなのかわたしの所有者カインとは誰なのかどちらが殺しどちらが殺されどちらが生きどちらが死にわたしは誰を生きるべきかが判らなくなる。判らない。永遠に、永遠に、わたしは判らないままだろう。
そしてわたしには本当は今でも判らないのだ。
あのとき復讐に舞い戻ってきた姿なき赤ん坊の悪霊が何を意味するのかが。
殺しに来たのは兄ではなく小さなわたしだったのかもしれない。幼い頃、兄がわたしに乗り移ったときに、排除されたかつての本当のわたしが、殺されたことを恨んでやってきたものなのか。
それとも逆にやはりあれは兄で、わたしが兄を死霊の眠りから無理やり拉致して自分の中に取り込み、幽閉してしまったことを怒って、奪われた自分自身をあの世へと、他者の次元へと取り戻すために舞い戻ってきたのだろうか。
だが、正直なところ、わたしには解釈はどっちでもいいのだ。
http://ameblo.jp/novalis666/entry-10001443654.html
〈別人〉、それは恐るべき自我の原罪というべきものだ。
わたしは〈他者〉と言っているのではない。〈他人〉とも言っていない。〈他者〉と〈別人〉を安易に置き換えてはならない。
〈別人〉というのは〈他者〉の全き不可能性である。
それは不可視の呪縛であって、最も醜悪なものを意味する。
* * *
〈別人〉のみにくさ、それはひとを石化させるメドゥーサの顔である。その醜悪さが不可視であるがゆえに、みにくい〈別人〉はしばしば美貌の幻影でその素顔を覆う。
恐ろしい罠だ。
魅惑し、そして、人の心を、いのちを奪う。
それは人殺しの顔である。
ナイフよりも素早くその冷たい一瞥だけであなたを殺す。
憑依してあなたの魂を虜にし、一瞬にして食い殺す。
〈悪〉はそのときに始まるのだ。
* * *
かつて、わたしは鏡のなかに映る己れの像に、見知らぬ人がかすめるのを見た。
再び見ると、それはよく見知っているわたしの貌なのだったが、どうにも見慣れることのできない不可視のぶきみさが貼りついていて取れなかった。
そのころわたしは十六歳で、謙遜するのも馬鹿臭いからはっきりというが、白面の美少年であった。
鏡の中にはヴィジュアルには、中性的な美貌を輝かせた魅力的な細面の、殆ど美少女といってもいい綺麗な顔が浮かんでいた。
もしもナルシスのようにそれが自分の顔だと知らなければ、一目で魂を奪われ、恋い焦がれて焦がれ死んだかもしれない。
わたしは幻想的なまでに美しかった。わたしはわたしに出会い、あらためてそれを見て驚き、たちまちその場に凍りついた。
しかし、美しさに撃たれたのではない。
わたしはそれほどに醜く忌まわしいものを見たことがなかった。微かな吐気と目眩に似たものがわたしのなかを横切っていった。透明で冷たい不可視のからだをもつものが、わたしの〈死霊〉がねじれた恐怖の叫びをあげてわたしを突き抜けていった。
〈死にたい〉という小さな呟きが胸に痛んだ。
イメージというものは本質的に醜いものなのだ。
それが美しければ美しいほど醜悪で耐え難い。
絶望的なまでに狂おしい怒り、殺したい、破壊したい、打ち砕いてしまいたい、この嘘つきの顔を、この頭を。
そう思ったとき、割れんばかりの頭痛がして、わたしは鏡台の前で頭を抱えてしまった。
それからひどい非現実感と離人体験に囚われる日々が続いた。夜には金縛りになり、叫びをあげて振りほどくと、振りほどいた何かが部屋の中ではっきりバサリと黒っぽい翼らしいものを広げてはばたき、部屋の片隅に落ちて、そこに灰色の靄のようにして蹲り、恐ろしいまでにじいーっと刺すような眼差しでわたしを見上げた。
姿だけは速やかに煙のように消えうせながら、瞼もなく、瞳すらもない、全き虚無ともいうべき視線だけが永遠に永遠に消えずに続くのではないかと思われる程長く、そんな気違いじみて自己矛盾した時間の異常な鋭角から、わたしを見据え貫き、無言の、謎めいた咎めを残していった。
それはかなり恐ろしい体験だった。
幻覚は時として現実よりもずっと生々しくリアルである。
わたしはわたしに憑依した何者かを確かに見、暗闇の中でヤコブが天使と戦ったようにそいつと格闘したのだが、勝利したのだとは思えなかった。
また、そいつは天使というよりも悪魔という方がふさわしい化け物だったが、朧ろに見えたその不定形の姿は、大きさからみて人間の赤ん坊に似ていた。
そいつは〈死の天使〉というべき代物か、それとも実体化したわたしのリビドーの一部なのか、よく分からないが、覚えているのはそいつが寝ているわたしの上を巨大なアメーバのように這い回り、わたしの呼吸を塞ごうとしていたということだ。
わたしを窒息死させようとして果たせなかった恨みと呪いの毒をたっぷり塗りたくった邪視の矢を最後に放ってそれが消えゆくとき、わたしはわたしの亡き兄のことを思った。
この兄は赤ん坊の姿のままこの世を去り、その死後にわたしは生まれた。たった一枚の遺影以外に彼の痕跡を伝えるものはまるでないが、この兄のことは物心ついたときからずっと心の上に重く暗くのしかかって忘れたことはない。
母はわたしが胎内にいるとき、この喪われた兄のことを思い出しては泣いていたという。
わたしは母の涙の海のなかに生まれ、その悲しみ啜り泣く声と兄の名前をむなしく呼ぶ声を細胞の奥深くにまで響き通らせ、自分の身に刻んでこの世界に産み落とされたのだ。
その後も母がこの兄のことを思い出しては顔を覆って泣く姿を繰り返し目にした。辛く耐え難い光景だ。わたしはその度に苦しくなる。涙が溢れ出し、悲しみが胸に灼けつくように痛くなる。
兄さん、わたしはあなたを知らない。
だがその全く知らぬあなたからわたしは永遠に離れられない。永遠に永遠にわたしはあなたを愛するだろう、あなたを恨み、あなたに嫉妬し、あなたを狂おしく求め、愛しつづけるだろう。
兄さん、あなたはわたしにかかった永遠の呪いだ。
あなたはわたしを呪う。
何故ならわたしはあなたなのだから。
わたしがわたしの名で名付けられるよりも前に、それよりも深く、わたしのこの身に烙印された絶対的で絶望的な名前。
それをあなたはわたしから永遠に奪うことはできない。
わたしから消し去ることはできない。
わたしはあなたの名を刻まれて生まれてきた。
その傷痕は癒えることはなく永遠にわたしに疼く。
わたしはあなたを病む。わたしはあなたを痛む。
この傷を縫うことも癒すこともあなたにはできない。
それはわたしの存在そのものだから。
いや、わたしの存在そのものをすら焼き潰す程深く激しく、わたしを無化してもなお燃え続ける炎で書かれた名前で、それはあるのだ。
この聖なる火の意志が、わたしがもはやわたしではなくなったときにも、わたしの奥底で、永遠の生命の瘢痕として熾り続けていることをわたしは知っている。
兄さん、わたしはあなたを忘れない。
たといわたしがわたしの名を忘れ、わたしが誰かを忘れ去ってしまっても、あなたのこととあなたの名前を忘れ去ることはないだろう。
たとい全宇宙がわたしの回りで滅び去っても、あなたの名前を綴る火の文字は消されることはないだろう。
恐るべきわたしの兄よ、あなたの名前はメギドの火でできている。その火で灼いた焼ゴテを取り、わたしはあなたの名において、わたしの額にカインの徴を烙印した。
弟アベル、赤ん坊の姿は炎の燔祭に消え、わたしは狂気のなかであなたからあなたを奪いあなたになりすますためにわたしを殺した。
兄さん、わたしではなくあなたが生きることをわたしは望んだ。だが、わたしが手にかけて殺したあの赤ん坊アベルは、あの空しくされた小さな肉体は誰なのか。わたしなのかあなたなのかが判らなくなる。判らなくなる、このわたしは誰なのかわたしなのかあなたなのかわたしの所有者カインとは誰なのかどちらが殺しどちらが殺されどちらが生きどちらが死にわたしは誰を生きるべきかが判らなくなる。判らない。永遠に、永遠に、わたしは判らないままだろう。
そしてわたしには本当は今でも判らないのだ。
あのとき復讐に舞い戻ってきた姿なき赤ん坊の悪霊が何を意味するのかが。
殺しに来たのは兄ではなく小さなわたしだったのかもしれない。幼い頃、兄がわたしに乗り移ったときに、排除されたかつての本当のわたしが、殺されたことを恨んでやってきたものなのか。
それとも逆にやはりあれは兄で、わたしが兄を死霊の眠りから無理やり拉致して自分の中に取り込み、幽閉してしまったことを怒って、奪われた自分自身をあの世へと、他者の次元へと取り戻すために舞い戻ってきたのだろうか。
だが、正直なところ、わたしには解釈はどっちでもいいのだ。
http://ameblo.jp/novalis666/entry-10001443654.html
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
不可能と背教の形而上学 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
不可能と背教の形而上学のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6480人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19255人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人