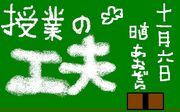|
|
|
|
コメント(75)
できるというのは「1」か「0」かですけど、
わかるというのは「1」か「0」かということではないんですよね。
例えば計算問題ができるできないは、○か×かなので、
「1」か「0」かですよ。白か黒かでも良いですが。
しかし、「わかる」という状態は、「0」もあれば、「0.1」もあるし、何となくわかるつまりわかるとわからないの中間の状態「0.5」というのもあるわけです。
あるいは「わかる」というのは定量的な問題ではなく「定性的」な問題なのかしれません。
ですから、「よくわからないけどできる状態」というのが、「わかってできる状態の準備段階」にあるとしたら、これを重視することはむしろ有効な考え方のはずです。こうした発想は欧米にはなく日本独特なのかもしれません。
わかるというのは「1」か「0」かということではないんですよね。
例えば計算問題ができるできないは、○か×かなので、
「1」か「0」かですよ。白か黒かでも良いですが。
しかし、「わかる」という状態は、「0」もあれば、「0.1」もあるし、何となくわかるつまりわかるとわからないの中間の状態「0.5」というのもあるわけです。
あるいは「わかる」というのは定量的な問題ではなく「定性的」な問題なのかしれません。
ですから、「よくわからないけどできる状態」というのが、「わかってできる状態の準備段階」にあるとしたら、これを重視することはむしろ有効な考え方のはずです。こうした発想は欧米にはなく日本独特なのかもしれません。
経験談ですが、長文です、すみません。
私の子どもは、耳から入る情報の処理に少し困難がありました。
LDのようでもあり、ディクレシアのようでもありますが、そのどれのカテゴリーにも入らない障害のような、そうでないような状態でした。
今では、それほど回りからの遅れを感じなくなっていますが、
小学校の低学年の頃は、遅れが顕著で、言葉にもかなり遅れがあったため、自分で唱えて、自分の耳で聞いて習得していくことがとても困難でした。
ですから、「しちの段」「八の段」だけではなく、「3の段」であっても「さんしちにじゅうひち」となってしまい、一なのか七なのか・・・混乱をきたすという状態で、2年生修了時にはまるっきり九九を覚えきれませんでした。
そうなることは、予想がついていたのですが・・・本人の能力の問題ですから学校の単元より先取りしたところで、習得できる状態ではなかったので本人の成長を待つことにしました。
このことを決断するのには、ものすごく勇気と決意が必要でした。
そのときの、学校の担任はどうだったかと言うと・・・
九九を習得したと判定を受けた子どもの名前を教室に順番に張り出していたわけですが、わたしの子どもは習得しきらなかったことに関しては興味がなかったらしく、がんばって覚えようね・・・というような言葉かけのひとつもなく、次の単元にはいりました。
子どもは、九九を唱えることが苦痛のなにものでもなかったので、ひとまず九九から開放されたかったようでした。
わたしは、今の時期になんとしてでも覚えさせようと、半ば虐待に近い状態で接したりすることもありましたが、なぜこれを覚えなければならないのか・・や、九九の仕組みに関しては理解できていたので本人の成長を待とうという決心しました。
そのとき、それ以上むきになっても虐待でしたから・・・。
3年生になって、割り算も意味は理解していました。
しかし、九九が怪しいためテストでは半分から三分の一くらいとれるくらいの状態でした。
でも、意味はわかっていました。
たとえば、三人兄弟なのですが
9個の飴があって、三人で仲良く分けるとしたら何個ずつになる?
というようには、わかっていました。
でも、九九が完全ではないからテストでは苦手な九九が出れば点数に繋がらないわけです。
では、地道に唱えれば覚えられるか・・・といえば、相変わらず口が回らないので字で書いてあるものを見て視覚で記憶させるわけですが、ひとたび口にだして確認をしようとすると混乱する・・ということになってしまうのでした。
わかっていても、できない・・・・ということはあるのです。
この子が、九九を完璧にマスターできたのは実に小学校4年生の夏休みでした。その年の夏休みに出された宿題は一切手をつける時間をとらず(とれず)、徹底的に九九だけをやりました。
どうやったのか・・・と言うと、やはり子どもが食いつくようなドリルに出会った・・・ということが大きかったように思います。
九九が迷路になっていたり、九九を答えていくことと暗号を解読するような文章題があったり、とにかくやっていて楽しいと思えるドリルでした。
とにかく、1か月間、あけてもくれても九九に取り組みました。
では、このドリルを2年生のときにやっていればできるようになったか?それは、無理だったと思います。
子どもには、それぞれできるようになる時期があると思います。
そしてできなくて、苦痛な子どもには、その子が自ら取り組みたくなるような教材をみつけてやればいいのです。
できない子どもにとって、100マスは、問題が100問もあって苦しいだけです。
100マスで!!できるようにする・・・というご意見に関しては、賛成しかねます。
100マスは、できる子がスピードをあげる教材です。
キシリトールさんのおっしゃるように、できない子どもの苦痛を共感したら・・・とてもじゃないけれど100マスでなんとかしよう・・・なんて発想にはならないのでは・・・と思うのです。
特殊な例をあげてしまいましたが・・・
高学年になっても九九が習得できていないお子さんが、3年生、4年生と算数の授業でずっと苦痛を味わってきていることに共感して欲しいと思い投稿しました。
わからない授業を、ずっと受けていなければならない状態を想像してあげて欲しいです。
余談ですが、九九ができなかった子どもが、今では高校一年生、数学が大好きで得意な教科になっています。
私の子どもは、耳から入る情報の処理に少し困難がありました。
LDのようでもあり、ディクレシアのようでもありますが、そのどれのカテゴリーにも入らない障害のような、そうでないような状態でした。
今では、それほど回りからの遅れを感じなくなっていますが、
小学校の低学年の頃は、遅れが顕著で、言葉にもかなり遅れがあったため、自分で唱えて、自分の耳で聞いて習得していくことがとても困難でした。
ですから、「しちの段」「八の段」だけではなく、「3の段」であっても「さんしちにじゅうひち」となってしまい、一なのか七なのか・・・混乱をきたすという状態で、2年生修了時にはまるっきり九九を覚えきれませんでした。
そうなることは、予想がついていたのですが・・・本人の能力の問題ですから学校の単元より先取りしたところで、習得できる状態ではなかったので本人の成長を待つことにしました。
このことを決断するのには、ものすごく勇気と決意が必要でした。
そのときの、学校の担任はどうだったかと言うと・・・
九九を習得したと判定を受けた子どもの名前を教室に順番に張り出していたわけですが、わたしの子どもは習得しきらなかったことに関しては興味がなかったらしく、がんばって覚えようね・・・というような言葉かけのひとつもなく、次の単元にはいりました。
子どもは、九九を唱えることが苦痛のなにものでもなかったので、ひとまず九九から開放されたかったようでした。
わたしは、今の時期になんとしてでも覚えさせようと、半ば虐待に近い状態で接したりすることもありましたが、なぜこれを覚えなければならないのか・・や、九九の仕組みに関しては理解できていたので本人の成長を待とうという決心しました。
そのとき、それ以上むきになっても虐待でしたから・・・。
3年生になって、割り算も意味は理解していました。
しかし、九九が怪しいためテストでは半分から三分の一くらいとれるくらいの状態でした。
でも、意味はわかっていました。
たとえば、三人兄弟なのですが
9個の飴があって、三人で仲良く分けるとしたら何個ずつになる?
というようには、わかっていました。
でも、九九が完全ではないからテストでは苦手な九九が出れば点数に繋がらないわけです。
では、地道に唱えれば覚えられるか・・・といえば、相変わらず口が回らないので字で書いてあるものを見て視覚で記憶させるわけですが、ひとたび口にだして確認をしようとすると混乱する・・ということになってしまうのでした。
わかっていても、できない・・・・ということはあるのです。
この子が、九九を完璧にマスターできたのは実に小学校4年生の夏休みでした。その年の夏休みに出された宿題は一切手をつける時間をとらず(とれず)、徹底的に九九だけをやりました。
どうやったのか・・・と言うと、やはり子どもが食いつくようなドリルに出会った・・・ということが大きかったように思います。
九九が迷路になっていたり、九九を答えていくことと暗号を解読するような文章題があったり、とにかくやっていて楽しいと思えるドリルでした。
とにかく、1か月間、あけてもくれても九九に取り組みました。
では、このドリルを2年生のときにやっていればできるようになったか?それは、無理だったと思います。
子どもには、それぞれできるようになる時期があると思います。
そしてできなくて、苦痛な子どもには、その子が自ら取り組みたくなるような教材をみつけてやればいいのです。
できない子どもにとって、100マスは、問題が100問もあって苦しいだけです。
100マスで!!できるようにする・・・というご意見に関しては、賛成しかねます。
100マスは、できる子がスピードをあげる教材です。
キシリトールさんのおっしゃるように、できない子どもの苦痛を共感したら・・・とてもじゃないけれど100マスでなんとかしよう・・・なんて発想にはならないのでは・・・と思うのです。
特殊な例をあげてしまいましたが・・・
高学年になっても九九が習得できていないお子さんが、3年生、4年生と算数の授業でずっと苦痛を味わってきていることに共感して欲しいと思い投稿しました。
わからない授業を、ずっと受けていなければならない状態を想像してあげて欲しいです。
余談ですが、九九ができなかった子どもが、今では高校一年生、数学が大好きで得意な教科になっています。
教師として、そして、学童期にLDを疑った子どもを持つ親として、算数の「計算」についての克服法(経験談)を少しお話したいと思います
基本的には、42の信(nobu)さんと同じ方法です。
まず「できるよう」になることが先。理屈は後です。
カンタンな例題から、ルールを見つけさせ、「このルールを使うと、もっと難しいのだって、どんどんできるよ」と、反復練習に嫌悪感を持たせず、決してたくさんやらせなくても良いから、とにかく、ルールを”使いこなせる”ようになるまで反復練習します。
次は「わかる」ですが、これは、理屈、ですよね。
これについては、私は、その単元が終わるまでに定着しなければならない・・・とは思っていません。
算数、数学って、社会や理科のように、同じことをスパイラルに、肉厚にしながら反復学習する、というのとはちょっと違いますが、でも、繰り上がりの足し算を下敷きにして、桁の多いかけざんの筆算、かけざんを下敷きにしてわりざん、引き算を下敷きにして、わりざんの筆算、わりざんを下敷きにして分数、分数と共通するものとして比、という風に、既習のものを下敷きにしながら、新しい分野を開いて学習していきますよね。
だからね、”今”は、それが「できる」ようになれば良い。なんだか、ワケわかんなかったけど、中学とか高校に行って、方程式とか習って、「あ、これって、こういうことだったんだ!!」ってわかったこと、みなさんご経験おありなのではないでしょうか?
BON☆さんの「できない子どもにとって、100マスは、問題が100問もあって苦しいだけです。100マスは、できる子がスピードをあげる教材です。」というお考えには、本当、すっごく共感!!
「高学年になっても九九が習得できていないお子さんが、3年生、4年生と算数の授業でずっと苦痛を味わってきていることに共感して欲しい」っていうお気持ちもすっごくよくわかります。(わが子に関してそれをすごく痛感してましたし、今教えている子ども達を観ていてもやはり”うちの子だけではなかった”と痛感していますから)
だけど、哀しいかな、学校での授業時間には限りがあります。
1年間で学習しなければならない内容が決まっていますから・・・
それでなくても土曜が完全になくなって、6日分のシゴトが5日に集約され、教師にも余裕がありません(私、新任の頃は土曜にお弁当持ってこさせて、子ども達と”居残り勉強”してました。のんびりした、良い時代だったんですね)
それに、放課後に子どもを残すということについても、このご時勢、安全上の観点からも、学校よりも塾やお稽古事が大事、という観点からも、不快感を示す親御さんが少なくないのも事実です。
そんなこんなで、少し理解に時間のかかる子どものフォローを学校に期待するのは期待薄だな・・と思ったので、私は家庭で上記のような”わが子の理解速度に合った分量の反復練習”をさせていました
わが子には、理解が困難であろうと思われることについては、無理に理解させようとは思いませんでした
だけどね、計算力はそれで、しっかりと身につきました
5年生の時に塾に通わせていた時には、受験は無理だろう、と思い、6年になって子どもの希望だった受験を白紙に戻し、塾を辞め、家庭学習オンリーでのんびり過ごさせました
そして、夏休みから「やっぱり私は○○中学に行きたい!」という子どもの言葉から、決して難関ではないけれど、良質な(小学校で学習する内容を超えず、基礎をきっちりと押さえた)出題をする国立中学を受験し、今はそこに通っています
本人も、算数のできない自分には無理ではないか・・・と思いながら、でも、その学校に行きたい!と目指していた学校でしたので、自信もつき、中学で「数学」の概念を学習して「お母さん、数学って面白いなぁ」と、前向きに学習に取り組んでいます
算数が苦手で「アタシはアホやから・・・・」と何事にも自信を持てなかったわが子の成長を、とても嬉しく感じています
教師って、やっぱり「すべての子どもにすべてを理解させたい」って思ってしまいがちですが、数回で理屈まで理解できる子もいれば、反復練習に時間をかけなければ定着しない子もいます。そんな中で、一人ひとりの子に劣等感を植え付けず、”そのうちわかるようになるから”と、”今”どうしても使いこなせるようになっておかなければならないルールに重点を置いての指導をしていくこと、が肝要かと・・・・
そして、親の立場としては、わが子の”現状”をきちんと、冷静に把握し、学校で足りない分を補ってあげる努力をして欲しいと思います
小学校程度の学習内容ならば、その子に寄り添える親が教えてあげるのが一番効果的だと、私は思います
焦って塾に通わせる親御さんもいらっしゃいますが、「Aちゃんが成績が上がった」塾がわが子にも向いているかどうか、結局は塾でも学校と同じ”お客さん”になっているのではないか、と塾選びを慎重になさることをオススメします♪
基本的には、42の信(nobu)さんと同じ方法です。
まず「できるよう」になることが先。理屈は後です。
カンタンな例題から、ルールを見つけさせ、「このルールを使うと、もっと難しいのだって、どんどんできるよ」と、反復練習に嫌悪感を持たせず、決してたくさんやらせなくても良いから、とにかく、ルールを”使いこなせる”ようになるまで反復練習します。
次は「わかる」ですが、これは、理屈、ですよね。
これについては、私は、その単元が終わるまでに定着しなければならない・・・とは思っていません。
算数、数学って、社会や理科のように、同じことをスパイラルに、肉厚にしながら反復学習する、というのとはちょっと違いますが、でも、繰り上がりの足し算を下敷きにして、桁の多いかけざんの筆算、かけざんを下敷きにしてわりざん、引き算を下敷きにして、わりざんの筆算、わりざんを下敷きにして分数、分数と共通するものとして比、という風に、既習のものを下敷きにしながら、新しい分野を開いて学習していきますよね。
だからね、”今”は、それが「できる」ようになれば良い。なんだか、ワケわかんなかったけど、中学とか高校に行って、方程式とか習って、「あ、これって、こういうことだったんだ!!」ってわかったこと、みなさんご経験おありなのではないでしょうか?
BON☆さんの「できない子どもにとって、100マスは、問題が100問もあって苦しいだけです。100マスは、できる子がスピードをあげる教材です。」というお考えには、本当、すっごく共感!!
「高学年になっても九九が習得できていないお子さんが、3年生、4年生と算数の授業でずっと苦痛を味わってきていることに共感して欲しい」っていうお気持ちもすっごくよくわかります。(わが子に関してそれをすごく痛感してましたし、今教えている子ども達を観ていてもやはり”うちの子だけではなかった”と痛感していますから)
だけど、哀しいかな、学校での授業時間には限りがあります。
1年間で学習しなければならない内容が決まっていますから・・・
それでなくても土曜が完全になくなって、6日分のシゴトが5日に集約され、教師にも余裕がありません(私、新任の頃は土曜にお弁当持ってこさせて、子ども達と”居残り勉強”してました。のんびりした、良い時代だったんですね)
それに、放課後に子どもを残すということについても、このご時勢、安全上の観点からも、学校よりも塾やお稽古事が大事、という観点からも、不快感を示す親御さんが少なくないのも事実です。
そんなこんなで、少し理解に時間のかかる子どものフォローを学校に期待するのは期待薄だな・・と思ったので、私は家庭で上記のような”わが子の理解速度に合った分量の反復練習”をさせていました
わが子には、理解が困難であろうと思われることについては、無理に理解させようとは思いませんでした
だけどね、計算力はそれで、しっかりと身につきました
5年生の時に塾に通わせていた時には、受験は無理だろう、と思い、6年になって子どもの希望だった受験を白紙に戻し、塾を辞め、家庭学習オンリーでのんびり過ごさせました
そして、夏休みから「やっぱり私は○○中学に行きたい!」という子どもの言葉から、決して難関ではないけれど、良質な(小学校で学習する内容を超えず、基礎をきっちりと押さえた)出題をする国立中学を受験し、今はそこに通っています
本人も、算数のできない自分には無理ではないか・・・と思いながら、でも、その学校に行きたい!と目指していた学校でしたので、自信もつき、中学で「数学」の概念を学習して「お母さん、数学って面白いなぁ」と、前向きに学習に取り組んでいます
算数が苦手で「アタシはアホやから・・・・」と何事にも自信を持てなかったわが子の成長を、とても嬉しく感じています
教師って、やっぱり「すべての子どもにすべてを理解させたい」って思ってしまいがちですが、数回で理屈まで理解できる子もいれば、反復練習に時間をかけなければ定着しない子もいます。そんな中で、一人ひとりの子に劣等感を植え付けず、”そのうちわかるようになるから”と、”今”どうしても使いこなせるようになっておかなければならないルールに重点を置いての指導をしていくこと、が肝要かと・・・・
そして、親の立場としては、わが子の”現状”をきちんと、冷静に把握し、学校で足りない分を補ってあげる努力をして欲しいと思います
小学校程度の学習内容ならば、その子に寄り添える親が教えてあげるのが一番効果的だと、私は思います
焦って塾に通わせる親御さんもいらっしゃいますが、「Aちゃんが成績が上がった」塾がわが子にも向いているかどうか、結局は塾でも学校と同じ”お客さん”になっているのではないか、と塾選びを慎重になさることをオススメします♪
5−2=3が理解できるのであれば、繰り下がりのない引き算は、出来るのですよね
たぶん、16=10+6と言うことも、理解できるのではないでしょうか?
と、したら、16を10と6に分けて図示し、6は放って置いて10から7こ消させて、残りを数えさせる
それが、他のパターンでも可能だと言うことを、同じ手順で確認させる・・・と言うのでは、どうでしょうか?
計算には「理屈」がありますが、その操作法は幾通りもあり、その子に一番理解しやすそうな操作法を”ひとつ”(最初は、ひとつ、でよいと思う)示してやるというので、いかがでしょうか?
ただし、「理解力」「定着力」には、本当に個人差があり、その個人差は大きいので、一度付きっ切りで教えて、本人が「わかった」と言っても、案外、自力ではできなかったりするものですので、”自力で”教えた操作を使いこなせるようになるまで、”確認”の作業の繰り返しが必要なのは、言うまでもありません
たぶん、16=10+6と言うことも、理解できるのではないでしょうか?
と、したら、16を10と6に分けて図示し、6は放って置いて10から7こ消させて、残りを数えさせる
それが、他のパターンでも可能だと言うことを、同じ手順で確認させる・・・と言うのでは、どうでしょうか?
計算には「理屈」がありますが、その操作法は幾通りもあり、その子に一番理解しやすそうな操作法を”ひとつ”(最初は、ひとつ、でよいと思う)示してやるというので、いかがでしょうか?
ただし、「理解力」「定着力」には、本当に個人差があり、その個人差は大きいので、一度付きっ切りで教えて、本人が「わかった」と言っても、案外、自力ではできなかったりするものですので、”自力で”教えた操作を使いこなせるようになるまで、”確認”の作業の繰り返しが必要なのは、言うまでもありません
>PutYourHands!! さん
わたしの塾にも、中学生で指をつかって足し引きしているこどもがいます。
こういう子どもは、頭の中のタイルとかおはじきなどが定着していないんだと思います。
2桁以上の引き算には2種類の仕方があります。
ひとつめは華音さんのおっしゃっているものです。
?減加法
16−7
☆16を10と6にわけて、10−7=3
☆さっきの6と3をあわせて、6+3=9
?減減法
16−7
☆7を6と1にわけて、16−6=10
☆10からさっきの残り1をひいて、10−1=9
どちらがわかりやすいかはそのこ次第です。
何度も繰り返して、頭の中におはじきや、タイルなどを10のかたまりずつにわけて操作していくことが大切なんだと思います。
わたしの塾にも、中学生で指をつかって足し引きしているこどもがいます。
こういう子どもは、頭の中のタイルとかおはじきなどが定着していないんだと思います。
2桁以上の引き算には2種類の仕方があります。
ひとつめは華音さんのおっしゃっているものです。
?減加法
16−7
☆16を10と6にわけて、10−7=3
☆さっきの6と3をあわせて、6+3=9
?減減法
16−7
☆7を6と1にわけて、16−6=10
☆10からさっきの残り1をひいて、10−1=9
どちらがわかりやすいかはそのこ次第です。
何度も繰り返して、頭の中におはじきや、タイルなどを10のかたまりずつにわけて操作していくことが大切なんだと思います。
私は小学校での知識しかないので、中学生に通じるかどうかわからないんですが。
1.九九
歌やリズムに合わせて、体を動かして、繰り返し覚える。私が勤めていた小学校(英語圏)では、九九導入の小学2年生時点では、英語の九九のリズムにしたがって、手足と手拍子をうまく組み合わせて、ずっとダンスをしながら、1の段から12の段(英語では12段まで行くようです)までずっと歌い続け、次は12の段から逆に歌っていました。
そのほかに、体を動かすのは得意なのに、算数の苦手な5年生の子の補習では、正座して、リズムに乗って、手拍子と前におじぎする動作の組み合わせの繰り返しで九九の表を一の段から12の段まで繰り返し繰り返し覚えていました。
私たちが九九の段を昔暗誦したのもそうですが、繰り返し、歌ったり、体を動かしたりすると、自然に体の中にしみこむようで、練習問題をしているときに、すぐに必要な九九がでなくて、小刻みに席に座りながら踊る動作をしている3年、4年がいて、ちょっとかわいかったんですが、その段を踊ったら自然とでてきてるみたいでした(笑)。
中学、高校の場合は、子供のように、大声で歌ったり、全身で踊ったりは無理ですが、ラップの音楽にのせたり、いすに座った上半身だけ使った手拍子系の運動だったら、家庭教師などならできるんではないでしょうか。。。
2.分数
これも、勤めていた小学校の話ですが、分数の理論を抽象的に教えるのが大変なので、実際に、丸い色紙を折ったり、きったり、ノートに貼ったりして、実際に手を使うと、結構すんなりわかるみたいです。
これも、中学・高校には幼稚かもしれませんが、このほうがわかりやすいからだまされたと思って。。。と説明したら、やってくれるかもしれません。塾のような大人数ではなく、家庭教師のように、個人をじっくり指導できる場でないと難しいと思いますが。算数の計算にしても、ルートなどにしても、抽象的にスキルで自動的にやると、わかりにくいし、うんざりする子もいますが、手を使って具体的にじっくり経験すると(ルート3とかは、折り紙を使ったりして)、案外、プラモデルを作ったり外で遊んだりするのが子供のときに好きだった中学・高校生には、わかりやすいかもしれないなと思います。
1.九九
歌やリズムに合わせて、体を動かして、繰り返し覚える。私が勤めていた小学校(英語圏)では、九九導入の小学2年生時点では、英語の九九のリズムにしたがって、手足と手拍子をうまく組み合わせて、ずっとダンスをしながら、1の段から12の段(英語では12段まで行くようです)までずっと歌い続け、次は12の段から逆に歌っていました。
そのほかに、体を動かすのは得意なのに、算数の苦手な5年生の子の補習では、正座して、リズムに乗って、手拍子と前におじぎする動作の組み合わせの繰り返しで九九の表を一の段から12の段まで繰り返し繰り返し覚えていました。
私たちが九九の段を昔暗誦したのもそうですが、繰り返し、歌ったり、体を動かしたりすると、自然に体の中にしみこむようで、練習問題をしているときに、すぐに必要な九九がでなくて、小刻みに席に座りながら踊る動作をしている3年、4年がいて、ちょっとかわいかったんですが、その段を踊ったら自然とでてきてるみたいでした(笑)。
中学、高校の場合は、子供のように、大声で歌ったり、全身で踊ったりは無理ですが、ラップの音楽にのせたり、いすに座った上半身だけ使った手拍子系の運動だったら、家庭教師などならできるんではないでしょうか。。。
2.分数
これも、勤めていた小学校の話ですが、分数の理論を抽象的に教えるのが大変なので、実際に、丸い色紙を折ったり、きったり、ノートに貼ったりして、実際に手を使うと、結構すんなりわかるみたいです。
これも、中学・高校には幼稚かもしれませんが、このほうがわかりやすいからだまされたと思って。。。と説明したら、やってくれるかもしれません。塾のような大人数ではなく、家庭教師のように、個人をじっくり指導できる場でないと難しいと思いますが。算数の計算にしても、ルートなどにしても、抽象的にスキルで自動的にやると、わかりにくいし、うんざりする子もいますが、手を使って具体的にじっくり経験すると(ルート3とかは、折り紙を使ったりして)、案外、プラモデルを作ったり外で遊んだりするのが子供のときに好きだった中学・高校生には、わかりやすいかもしれないなと思います。
> サラさん
答えから言うと、30分の18になります。
ヒントがそのまま解説に直結するんですが、
3 6 9
― = ― = ―
5 10 15
和 8 16 24
…というように、等しい分数は分子と分母に同じ数(上の例では×2、×3)をかけますよね。
そうすると、分子+分母の和も×2、×3となる。
この性質を使うと、
3 △
― = ―
5 □
和 8 48
…だと、×6することがわかります。
だから、
分子△=3×6=18
分母□=5×6=30になります。
私は自分の生徒にはこんな感じで教えています。
小6であれば比例の表を埋めたりするのは習っているので、たぶんわかるかと…。
パソコン上だと見にくい説明になってしまいましたが、参考になれば幸いです。
答えから言うと、30分の18になります。
ヒントがそのまま解説に直結するんですが、
3 6 9
― = ― = ―
5 10 15
和 8 16 24
…というように、等しい分数は分子と分母に同じ数(上の例では×2、×3)をかけますよね。
そうすると、分子+分母の和も×2、×3となる。
この性質を使うと、
3 △
― = ―
5 □
和 8 48
…だと、×6することがわかります。
だから、
分子△=3×6=18
分母□=5×6=30になります。
私は自分の生徒にはこんな感じで教えています。
小6であれば比例の表を埋めたりするのは習っているので、たぶんわかるかと…。
パソコン上だと見にくい説明になってしまいましたが、参考になれば幸いです。
そういえばここは、私がたてたトピックですね。
4年が経つんですね。
多くの方に活用していただけて幸いです。
さて、久々に書き込んでみます。
九九に関してベネッセがこんなリサーチをしていました。
http://benesse.jp/berd/center/open/report/keisanryoku/2007/hon1_2.html
苦手な子にとっては4、6、7、8が鬼門のようです。
1)前後の九九と混同しているケースが見られる。
かけられる数を前後のものとまちがえる
例)6×7で49(7×7とのまちがい)など
かける数を前後のものとまちがえる
例)6×7で48(6×8のまちがい)など
(2)似ている音の九九のまちがいが多い。
4(し)と7(しち)のまちがい
例)4×2で14(7×2とのまちがい)など
7(しち)と8(はち)のまちがい
例)8×6で42(7×6とのまちがい)など
(3)正確に九九が覚えきれていない。
± 1のまちがい
例)6×8で47、49など
誤答率が比較的高めで、誤答例多数のもの
(4)交換法則の成り立つ関係の九九をセットでまちがえる。
例)6×7、7×6をどちらも48とするなど
(5)交換法則の成り立つ関係の九九の一方をまちがえる。
例)6×8は正解だが、8×6は42など
4年が経つんですね。
多くの方に活用していただけて幸いです。
さて、久々に書き込んでみます。
九九に関してベネッセがこんなリサーチをしていました。
http://benesse.jp/berd/center/open/report/keisanryoku/2007/hon1_2.html
苦手な子にとっては4、6、7、8が鬼門のようです。
1)前後の九九と混同しているケースが見られる。
かけられる数を前後のものとまちがえる
例)6×7で49(7×7とのまちがい)など
かける数を前後のものとまちがえる
例)6×7で48(6×8のまちがい)など
(2)似ている音の九九のまちがいが多い。
4(し)と7(しち)のまちがい
例)4×2で14(7×2とのまちがい)など
7(しち)と8(はち)のまちがい
例)8×6で42(7×6とのまちがい)など
(3)正確に九九が覚えきれていない。
± 1のまちがい
例)6×8で47、49など
誤答率が比較的高めで、誤答例多数のもの
(4)交換法則の成り立つ関係の九九をセットでまちがえる。
例)6×7、7×6をどちらも48とするなど
(5)交換法則の成り立つ関係の九九の一方をまちがえる。
例)6×8は正解だが、8×6は42など
今年小学校3年になった息子を持つ父親っす。
これでも一応数学の教員免許持ってて、大学の頃にLDの疑いのある
中学3年生を塾で1年間みんなで指導して、普通高校に行かせる事に
運よく成功しました。
その子も確かに九九ダメでしたね。というか算数や数学はまったくダメ
ダメでした。ただし国語のセンスは抜群でしたが。
さて、昨年の息子を観察していると、ボクの子どもの頃とは違って
今は、2の段→5の段→3→4→6→7→8→9→1の段の順で
授業を進めているようです。そして、やっぱり、鬼門は4、6、7、8の段。
公開授業などにも顔を出しましたが、特に6〜8の段に時間をさいて
いるように見受けられました。一応、2の段と5の段で九九の意味を
説明して各段でもそれぞれ説明はしていましたが、本格的なものは、
全部の九九が覚え終わってから、「1つ6円のアメを8個買う式は?」
っていう感じでした。交換法則もあえて最後の方で、九九の表を
見ながら改めて説明といった感じでした。
息子の学校でも学習障害児の疑いのある児童がいたのですが、
教室に入る際にある九九の段を暗唱しないと入室不可だったり
廊下に出られなかったりとルールが作られていて、授業参観のときは
児童が出たり入ったりするたびに、九九を唱えだすのが、面白かったです。
授業では、九九の「6×8」などの答えが裏に書かれているカードを
使って、二人一組で九九バトル?という名前で、答えの数の多い方が
勝つとか、九九ビンゴを取り入れて、楽しく覚えさせてました。
昔はとにかく念仏のように意味不明でも唱え続けさせられたものですが
随分と変わったんですね。
これでも一応数学の教員免許持ってて、大学の頃にLDの疑いのある
中学3年生を塾で1年間みんなで指導して、普通高校に行かせる事に
運よく成功しました。
その子も確かに九九ダメでしたね。というか算数や数学はまったくダメ
ダメでした。ただし国語のセンスは抜群でしたが。
さて、昨年の息子を観察していると、ボクの子どもの頃とは違って
今は、2の段→5の段→3→4→6→7→8→9→1の段の順で
授業を進めているようです。そして、やっぱり、鬼門は4、6、7、8の段。
公開授業などにも顔を出しましたが、特に6〜8の段に時間をさいて
いるように見受けられました。一応、2の段と5の段で九九の意味を
説明して各段でもそれぞれ説明はしていましたが、本格的なものは、
全部の九九が覚え終わってから、「1つ6円のアメを8個買う式は?」
っていう感じでした。交換法則もあえて最後の方で、九九の表を
見ながら改めて説明といった感じでした。
息子の学校でも学習障害児の疑いのある児童がいたのですが、
教室に入る際にある九九の段を暗唱しないと入室不可だったり
廊下に出られなかったりとルールが作られていて、授業参観のときは
児童が出たり入ったりするたびに、九九を唱えだすのが、面白かったです。
授業では、九九の「6×8」などの答えが裏に書かれているカードを
使って、二人一組で九九バトル?という名前で、答えの数の多い方が
勝つとか、九九ビンゴを取り入れて、楽しく覚えさせてました。
昔はとにかく念仏のように意味不明でも唱え続けさせられたものですが
随分と変わったんですね。
僭越ながら小学校で算数の少人数指導を非常勤で引き受けた経験があります…
『σ( ̄▽ ̄;)記憶が正しければ』…いきなり寒かったらゴメンなさい
(>人<)
たしか教科書での導入は折り紙を"半分"に折って切り
2つに分けたウチの1つを
1/2『2ぶんの1』
板書では2分と漢字を使い
2ふんじゃないと強調
(だから"半分"のコトを別名『2ぶんの1』と呼ぶ )
)
線分=分ける
線分の下段の数字が"幾つ"に分けたのかを表し『分母』と呼ばれる部屋
線分の上段の数字は"分母(云うなればお母さん)におんぶ
 された子ども"で『分子』と呼ばれる部屋
された子ども"で『分子』と呼ばれる部屋
導入である1限目には分子が『1』である例題しか扱わず
 つに分けた1つ分DAKARA…
つに分けた1つ分DAKARA…
1/
この時点で折り紙をノートに張り
どちらニモ1/2と書き込み
2つに分けた1つ分=2ぶんの1
とも記帳
実作業も伴い鋏 で切り終えた枚数も"2つ"に『分けた』と確認しつつ…
で切り終えた枚数も"2つ"に『分けた』と確認しつつ…
では(・・?)
折り紙(新しく別の)"半分の半分"に折って切り
切り終えた枚数を4つに分けた!と確認し
4つに分けた1つ分を何と呼べる?…
とし
"半分の半分"を別名『4ぶんの1』と続けたよ〜ぉに思います…
『σ( ̄▽ ̄;)記憶が正しければ』…いきなり寒かったらゴメンなさい
(>人<)
たしか教科書での導入は折り紙を"半分"に折って切り
2つに分けたウチの1つを
1/2『2ぶんの1』
板書では2分と漢字を使い
2ふんじゃないと強調
(だから"半分"のコトを別名『2ぶんの1』と呼ぶ
線分=分ける
線分の下段の数字が"幾つ"に分けたのかを表し『分母』と呼ばれる部屋
線分の上段の数字は"分母(云うなればお母さん)におんぶ
導入である1限目には分子が『1』である例題しか扱わず
1/
この時点で折り紙をノートに張り
どちらニモ1/2と書き込み
2つに分けた1つ分=2ぶんの1
とも記帳
実作業も伴い鋏
では(・・?)
折り紙(新しく別の)"半分の半分"に折って切り
切り終えた枚数を4つに分けた!と確認し
4つに分けた1つ分を何と呼べる?…
とし
"半分の半分"を別名『4ぶんの1』と続けたよ〜ぉに思います…
もうだいぶ昔ですが、高3理系で通分ができない子を見たことはあります。
問題から答えに至るまでの係数がすべて整数の場合には、高校レベルの問題もちゃんと解けているのに、分数が入ると全ペケという、非常にわかりやすい子で。
理解力はあると踏んだので、通分について、まず理屈を教えてから演習、という流れで教えたところ、ちゃんと正解するようになりました。
同じ「できない」でも、「わからないからできない子」、「自分が納得できないものは使えない子」もいるので、「『わからなくてもできる』が先」とは必ずしも言い切れないんじゃないかなと。
理屈を教えてもできない子には「できる」を優先させてみるのも一案だけれど、「わからなくてもこのやり方をコピーすればできる」と言ってもできない子には、逆に、理屈から教えた方がいい場合もあるんじゃないかなーと思うのでした。
無闇に「できる」ことで喜びを得る子どもばかりではないよ、ということで。
問題から答えに至るまでの係数がすべて整数の場合には、高校レベルの問題もちゃんと解けているのに、分数が入ると全ペケという、非常にわかりやすい子で。
理解力はあると踏んだので、通分について、まず理屈を教えてから演習、という流れで教えたところ、ちゃんと正解するようになりました。
同じ「できない」でも、「わからないからできない子」、「自分が納得できないものは使えない子」もいるので、「『わからなくてもできる』が先」とは必ずしも言い切れないんじゃないかなと。
理屈を教えてもできない子には「できる」を優先させてみるのも一案だけれど、「わからなくてもこのやり方をコピーすればできる」と言ってもできない子には、逆に、理屈から教えた方がいい場合もあるんじゃないかなーと思うのでした。
無闇に「できる」ことで喜びを得る子どもばかりではないよ、ということで。
TT経験から...
3?←メモる
48
−19
−−−−−(線のツモリ)
29
の筆算で十の位の4は\で
消して3に訂正し
繰り下げる10と8で
縦に?と8を風船?お皿?
のような形で囲み18−9を
意識させました。
この頃の児童では計算card
の習熟で身についていて
欲しい繰り下がり計算でも
中には苦手意識のあまり
脳が拒否するかのような
態を示す児童も少なくない
のが現状です
10−9+8が得意な児童と
8−9=−1の感覚で
10−1と捉えるのを得意と
する児童では「分からん」
感覚も違いが出やすいです
学校では10−9+8を主流
指導する筈ですので...
0.3mm芯の朱書きで書き込み
指導を紹介します...
十の位の数を\で消しながら
「?のまとまりを1つ繰り
下げてあげると?」
対象児童が、1小さい数に
訂正することができたら...
(作業1)
繰り下げる10を一位数の
上に?と書きなぞらせる
(作業2)
一位数?を含めて囲む
補助線を書き足して
なぞらせながら
(作業3)
「十幾つ 引く 幾つ?」
と2つの発問で繰り返し
指導をする...
如何でしょう...
ちなみに
0.3mm芯の朱書きで書き込む
のは\も?も囲む補助線も
(児童自身に必ず鉛筆で
上からなぞらせて下さい)
書く「一連作業」を終えると
鉛筆の太さで朱が消え去り
自分で解けた達成感を残せる
と云われています
繰り返しで「できた」感を
味わって「分かった」に
是非つながって欲しいもの
です...
3?←メモる
48
−19
−−−−−(線のツモリ)
29
の筆算で十の位の4は\で
消して3に訂正し
繰り下げる10と8で
縦に?と8を風船?お皿?
のような形で囲み18−9を
意識させました。
この頃の児童では計算card
の習熟で身についていて
欲しい繰り下がり計算でも
中には苦手意識のあまり
脳が拒否するかのような
態を示す児童も少なくない
のが現状です
10−9+8が得意な児童と
8−9=−1の感覚で
10−1と捉えるのを得意と
する児童では「分からん」
感覚も違いが出やすいです
学校では10−9+8を主流
指導する筈ですので...
0.3mm芯の朱書きで書き込み
指導を紹介します...
十の位の数を\で消しながら
「?のまとまりを1つ繰り
下げてあげると?」
対象児童が、1小さい数に
訂正することができたら...
(作業1)
繰り下げる10を一位数の
上に?と書きなぞらせる
(作業2)
一位数?を含めて囲む
補助線を書き足して
なぞらせながら
(作業3)
「十幾つ 引く 幾つ?」
と2つの発問で繰り返し
指導をする...
如何でしょう...
ちなみに
0.3mm芯の朱書きで書き込む
のは\も?も囲む補助線も
(児童自身に必ず鉛筆で
上からなぞらせて下さい)
書く「一連作業」を終えると
鉛筆の太さで朱が消え去り
自分で解けた達成感を残せる
と云われています
繰り返しで「できた」感を
味わって「分かった」に
是非つながって欲しいもの
です...
>68 がんげん@えっさき さん
>どうにか分かりやすく引き算を理解させる方法はないでしょうか?
私は、教師でもなんでもなく、ただの母親ですが、自分の子に繰り下がりの引き算を教える時には、ただただ、手を使わせました。
もちろん自分の手だけじゃ足りないので、私の手も貸して、何度も何度もイメージさせましたね。
そうやって体で体感し、操作していくうちに、数の概念をしっかりわかったようで、今では(小5ですが)九九も知らないのに(わざと覚えさせませんでしたら)どんどん暗算で二桁の掛け算の計算ぐらいなら難なくやってしまっています。
実際にやって見せるほうが、言葉で教えるより、紙に書いて計算させるより、とても効果的なんだろうと私は思いますよ。
>どうにか分かりやすく引き算を理解させる方法はないでしょうか?
私は、教師でもなんでもなく、ただの母親ですが、自分の子に繰り下がりの引き算を教える時には、ただただ、手を使わせました。
もちろん自分の手だけじゃ足りないので、私の手も貸して、何度も何度もイメージさせましたね。
そうやって体で体感し、操作していくうちに、数の概念をしっかりわかったようで、今では(小5ですが)九九も知らないのに(わざと覚えさせませんでしたら)どんどん暗算で二桁の掛け算の計算ぐらいなら難なくやってしまっています。
実際にやって見せるほうが、言葉で教えるより、紙に書いて計算させるより、とても効果的なんだろうと私は思いますよ。
私の息子には、掛け算は、九九の暗証では教えませんでした。
指に3×7なら、一指一指に3を7つの指に書いて、主に足し算や引き算を使って、自分の頭の中だけで計算させていました。
そうすると、自然に10本の指だと30だから、三つの指に書いていない3本を足して9を30から引けばいいというのまで、自分で勝手に理解していましたよ。
九九で教えないと、掛け算もこのように、分配法則を使っていつも暗算で計算できるようになり、逆に計算間違いも少ないんです。
数の概念をつけるためには、九九は教えないほうがいいんじゃないかって私は思っています。
九九はどうしてもそれが出来ない子だけに教えれればいいんじゃないかって、思いますよ。
指に3×7なら、一指一指に3を7つの指に書いて、主に足し算や引き算を使って、自分の頭の中だけで計算させていました。
そうすると、自然に10本の指だと30だから、三つの指に書いていない3本を足して9を30から引けばいいというのまで、自分で勝手に理解していましたよ。
九九で教えないと、掛け算もこのように、分配法則を使っていつも暗算で計算できるようになり、逆に計算間違いも少ないんです。
数の概念をつけるためには、九九は教えないほうがいいんじゃないかって私は思っています。
九九はどうしてもそれが出来ない子だけに教えれればいいんじゃないかって、思いますよ。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
授業の工夫事典!!(塾講師・教師) 更新情報
授業の工夫事典!!(塾講師・教師)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90061人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208318人
- 3位
- 酒好き
- 170698人