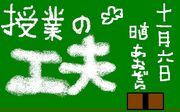みなさん。こんにちは。
私は塾の講師として中学部1〜3年生の集団授業「国語」を担当しています。
中間テストの結果がちらほら返ってくるこのごろなのですが、あまり芳しくありません。
私の塾の指導方針としては教科書の内容に沿い、定期テストの成績向上を重点としています。(採択教科書出版社はともに「光村出版」です)
なので、授業も教科書を主体に指導しています。
国語科の専任は私ひとりなので原因の追究をしてくれる人も授業の講評をしてくれる人もいません。
以下に私の指導方法を示させていただきますので、現役の教員の方々、塾講師の国語を担当されている方、あるいはその他教科問わずいろいろな方からのご意見をお待ちしております。
心からご協力をお願いいたします。
*以下の内容は主に中学国語(現代文)を想定しております。
【第一段階】
○教科書のコピーを配付し、私が音読する。
【第二段階】
○私の音読を聞き、塾生たちに読めない漢字をメモらせる。
○塾生たちが分からないであろう語句の意味を板書しメモらせる。
【第三段階】
○再度私が音読し直し、今度は内容把握のため重要事項(傍線部問題になりそうなところ)や過去の定期テスト出題事項のところにマーカーを引っ張らせ、その意味を板書する。(とりわけ「論説」の場合は意味内容を図式化し、「小説」の場合は人物相関図を図式化し板書)
【第四段階】
○再度教科書のコピーを配付し、授業でメモをしたすべてを清書させる。(これは宿題として)
○授業で取り扱った単元を三冊の参考書から抜き出したコピーを「オリジナルテキスト」として製本化し、それを宿題とする。
私は塾の講師として中学部1〜3年生の集団授業「国語」を担当しています。
中間テストの結果がちらほら返ってくるこのごろなのですが、あまり芳しくありません。
私の塾の指導方針としては教科書の内容に沿い、定期テストの成績向上を重点としています。(採択教科書出版社はともに「光村出版」です)
なので、授業も教科書を主体に指導しています。
国語科の専任は私ひとりなので原因の追究をしてくれる人も授業の講評をしてくれる人もいません。
以下に私の指導方法を示させていただきますので、現役の教員の方々、塾講師の国語を担当されている方、あるいはその他教科問わずいろいろな方からのご意見をお待ちしております。
心からご協力をお願いいたします。
*以下の内容は主に中学国語(現代文)を想定しております。
【第一段階】
○教科書のコピーを配付し、私が音読する。
【第二段階】
○私の音読を聞き、塾生たちに読めない漢字をメモらせる。
○塾生たちが分からないであろう語句の意味を板書しメモらせる。
【第三段階】
○再度私が音読し直し、今度は内容把握のため重要事項(傍線部問題になりそうなところ)や過去の定期テスト出題事項のところにマーカーを引っ張らせ、その意味を板書する。(とりわけ「論説」の場合は意味内容を図式化し、「小説」の場合は人物相関図を図式化し板書)
【第四段階】
○再度教科書のコピーを配付し、授業でメモをしたすべてを清書させる。(これは宿題として)
○授業で取り扱った単元を三冊の参考書から抜き出したコピーを「オリジナルテキスト」として製本化し、それを宿題とする。
|
|
|
|
コメント(21)
結構苦手な子ほど漢字など基本的な事項がとれていないことがあります。
また、音読を聞き、それに平行してメモをとるという作業は慣れるまできつく、中途半端になりそうな気もします。
私なら、まずはじめに今日やるべきところの漢字や語句をプリントとして作成し、やらせます(テストではなく、5分くらいで終わるように読みと書きを両方やらせます。)
その後、先生が音読せず、生徒にランダムであて音読をさせます。緊張感が出ますし、子供に声を出させたほうがいいのかなとも思います。
その後、第三段階に入ればいいのではないでしょうか?そして、次回の授業の最小に、はじめにやった語句の意味や漢字をテストし、暗記物をきちんと覚えているかをチェックします。
やはりいきなりの読解力向上は難しいので、漢字など暗記ですむものの力向上も大切でしょう。
まぁ学生講師経験者程度の意見ですので、参考になるかは自信ありませんがw
また、音読を聞き、それに平行してメモをとるという作業は慣れるまできつく、中途半端になりそうな気もします。
私なら、まずはじめに今日やるべきところの漢字や語句をプリントとして作成し、やらせます(テストではなく、5分くらいで終わるように読みと書きを両方やらせます。)
その後、先生が音読せず、生徒にランダムであて音読をさせます。緊張感が出ますし、子供に声を出させたほうがいいのかなとも思います。
その後、第三段階に入ればいいのではないでしょうか?そして、次回の授業の最小に、はじめにやった語句の意味や漢字をテストし、暗記物をきちんと覚えているかをチェックします。
やはりいきなりの読解力向上は難しいので、漢字など暗記ですむものの力向上も大切でしょう。
まぁ学生講師経験者程度の意見ですので、参考になるかは自信ありませんがw
私も学生塾講師しかやっていませんので、参考になるかわかりませんが…(>_<)
全体的に生徒主体の学習活動をする時間や内容が少ないように見受けられます。教師主導が悪いわけではありませんし、こちらから文の解釈を説明するのは大切だと思います。ただ、あまりに受け身すぎると意欲をなくしてしまうし、考える力が養われないのでは?
前の方がおっしゃっているように漢字や語句をプリントして、生徒に調べさせる・文のなかで重要な部分についてや抽象的な表現を具体的にするなど、生徒色々考えさせてから解説を加えると良いのではないでしょうか。
いかがでしょうか?
一意見として受け取ってくだされば嬉しいです。失礼致しましたm(__)m
全体的に生徒主体の学習活動をする時間や内容が少ないように見受けられます。教師主導が悪いわけではありませんし、こちらから文の解釈を説明するのは大切だと思います。ただ、あまりに受け身すぎると意欲をなくしてしまうし、考える力が養われないのでは?
前の方がおっしゃっているように漢字や語句をプリントして、生徒に調べさせる・文のなかで重要な部分についてや抽象的な表現を具体的にするなど、生徒色々考えさせてから解説を加えると良いのではないでしょうか。
いかがでしょうか?
一意見として受け取ってくだされば嬉しいです。失礼致しましたm(__)m
他人の音読を聞いて語彙力の点検をするより、自分で読んで気がつくほうがずっと効果的です。知らないことに気がつかず、できているつもりになっていることが本当にたくさんあります。
あと、塾であれば、講義だけではなく小テストなども実施したほうが緊張感が出てよいと思います。前回の復習もかねて、データー化することで、自分の足跡もたどることができます。
板書の図式化については、私も若かりしころ、好んでとった手法です。これは、高度な理解力のある人には向いていますが、理解力の乏しい子には、かえって逆効果というところもあります。
まず、ノートをあとで開いてみても、何のことかよくわからない。
箇条書き的知識のみで体系的に思考がまとまらないなど。
私は、最近は、主語・述語が明確な文で書くようにしています。
あとで、読み返しても文意がわかり、なおかつ、記述問題の練習もかねることができますので。
あと、塾であれば、講義だけではなく小テストなども実施したほうが緊張感が出てよいと思います。前回の復習もかねて、データー化することで、自分の足跡もたどることができます。
板書の図式化については、私も若かりしころ、好んでとった手法です。これは、高度な理解力のある人には向いていますが、理解力の乏しい子には、かえって逆効果というところもあります。
まず、ノートをあとで開いてみても、何のことかよくわからない。
箇条書き的知識のみで体系的に思考がまとまらないなど。
私は、最近は、主語・述語が明確な文で書くようにしています。
あとで、読み返しても文意がわかり、なおかつ、記述問題の練習もかねることができますので。
【第一段階】〜【第二段階】までに時間をかけ過ぎているように思います。音読の必要はなく、読み間違いやすい漢字、覚えにくい漢字、意味を取りにくい語句をプリントで問題にすれば10分程度で済むことではないでしょうか。
そして、静次さんのおっしゃる【第三段階】を核として授業を構成すべきだと思います。皆さんもおっしゃるように、ここでは生徒に精選された発問を与えることで、考える時間を取ることが大切でしょうね。発問は、過去問等で最も難しいレベルの問題をもとに考えるべきだと思います。良い発問は、その文章全体の理解を深めますから。
あと、【第四段階】の“清書”は知的ではなく、生徒にとって無味乾燥した時間になるかと(笑)また、個人的には、授業で扱っていないテキストを宿題として扱うことにも疑問が残ります。そのテキストをやることで成績が上がるのならば、授業で扱うべきなのではないでしょうか。
そして、静次さんのおっしゃる【第三段階】を核として授業を構成すべきだと思います。皆さんもおっしゃるように、ここでは生徒に精選された発問を与えることで、考える時間を取ることが大切でしょうね。発問は、過去問等で最も難しいレベルの問題をもとに考えるべきだと思います。良い発問は、その文章全体の理解を深めますから。
あと、【第四段階】の“清書”は知的ではなく、生徒にとって無味乾燥した時間になるかと(笑)また、個人的には、授業で扱っていないテキストを宿題として扱うことにも疑問が残ります。そのテキストをやることで成績が上がるのならば、授業で扱うべきなのではないでしょうか。
上で他の方が書かれているように、生徒が受け身過ぎ、もし教科書読むのだったら、静次さんが読まずに、ランダムに生徒に読ます方が良いと思います。
ランダムに当てられたら、生徒は次に自分が当てられるかもと思い、集中して教科書を見る可能性が高いです。
(私は英語では音読ばかりさせますが、国語は古文漢文以外は、ほとんどさせませんが)
学力が低い生徒の場合は、私は基本的にメモを取らせず、コピーを配ったりして、書かせずに、その分暗記する時間に回します。
9でtackさんが書かれているように、出題者の癖を読む、というのは重要だと思います。
定期テスト対策するなら、塾講師は学校のノートを 見ないといけないでしょう。
多少、人によって癖がありますから。
(入試などは、複数で作成や検討するから、定期試験ほど癖はないです。都道府県ごとの癖はありますが)
また私の地域では学校のワークのウエイトが高そうなので、市販のワークより、学校のワークに重点をおきます。
私の場合は、自分で出来るだけ考えず、学校で使っているノートやワーク、教科書、過去問、その他プリントなどを見て、学校の先生が何を重視しているか意図をなるべく理解し、学校の先生がして欲しいであろう事(覚えて欲しい事)を塾でするようにしています。
(国語は、ほとんど復習で進めています。)
ランダムに当てられたら、生徒は次に自分が当てられるかもと思い、集中して教科書を見る可能性が高いです。
(私は英語では音読ばかりさせますが、国語は古文漢文以外は、ほとんどさせませんが)
学力が低い生徒の場合は、私は基本的にメモを取らせず、コピーを配ったりして、書かせずに、その分暗記する時間に回します。
9でtackさんが書かれているように、出題者の癖を読む、というのは重要だと思います。
定期テスト対策するなら、塾講師は学校のノートを 見ないといけないでしょう。
多少、人によって癖がありますから。
(入試などは、複数で作成や検討するから、定期試験ほど癖はないです。都道府県ごとの癖はありますが)
また私の地域では学校のワークのウエイトが高そうなので、市販のワークより、学校のワークに重点をおきます。
私の場合は、自分で出来るだけ考えず、学校で使っているノートやワーク、教科書、過去問、その他プリントなどを見て、学校の先生が何を重視しているか意図をなるべく理解し、学校の先生がして欲しいであろう事(覚えて欲しい事)を塾でするようにしています。
(国語は、ほとんど復習で進めています。)
集団は未経験でありますが、読み方のコツ、パラフレーズリーディングだったり、感情移入をしたり云々を伝えられればと思います。その辺りは教える側が、常日頃からいかに工夫して作品なり論説を読むか次第。
そのうえで、点取り的な国語(読解力とイコールで考えるべきではない)で求められる答え方についての指導ができれば良いのでは。
国語/原文の基本は間違い探しと、出題側の一方的な子供観にあると思うので、出題作品が選ばれた意味や、著者よりも出題者が読み解いて欲しい部分を見分ける技術を伝えるべきと思います。
あとは、わからない言葉がひとつでもあれば、線を引かせて広辞苑なり国語辞典なりをひかせること(無論、教師自身も常日頃からひき続けるべき)ですかな。
そのうえで、点取り的な国語(読解力とイコールで考えるべきではない)で求められる答え方についての指導ができれば良いのでは。
国語/原文の基本は間違い探しと、出題側の一方的な子供観にあると思うので、出題作品が選ばれた意味や、著者よりも出題者が読み解いて欲しい部分を見分ける技術を伝えるべきと思います。
あとは、わからない言葉がひとつでもあれば、線を引かせて広辞苑なり国語辞典なりをひかせること(無論、教師自身も常日頃からひき続けるべき)ですかな。
塾の授業でなく学校の授業という感じがします。
目的は生徒の点数を上げることですよね?語彙力をつけたり読解解説したりに力を入れていて目的とずれた手法になっていると感じました。
生徒の学力に合わせて点数を上げることに特化することを念頭におくとよいと思います。
まず漢字と知識はテスト範囲に合わせてプリントをつくり宿題にして次回覚えたかテスト。覚えるまで再試を追いかけ。授業時間をここで使うのはもったいない。
授業では学校のノートプリントワーク過去問から出題。さらに宿題も。いまのままだと問題演習の量が少ないです。定期テストは初見の文章じゃないので問題傾向の分析後、問題と答えをセットで覚えてもらう。
根本的な読解力をつけたいなら講習時にじっくりと。情操教育をしたいなら学校に場をうつした方がよさそうです。
期末で点数を上げて生徒と保護者を是非喜ばせてください!
目的は生徒の点数を上げることですよね?語彙力をつけたり読解解説したりに力を入れていて目的とずれた手法になっていると感じました。
生徒の学力に合わせて点数を上げることに特化することを念頭におくとよいと思います。
まず漢字と知識はテスト範囲に合わせてプリントをつくり宿題にして次回覚えたかテスト。覚えるまで再試を追いかけ。授業時間をここで使うのはもったいない。
授業では学校のノートプリントワーク過去問から出題。さらに宿題も。いまのままだと問題演習の量が少ないです。定期テストは初見の文章じゃないので問題傾向の分析後、問題と答えをセットで覚えてもらう。
根本的な読解力をつけたいなら講習時にじっくりと。情操教育をしたいなら学校に場をうつした方がよさそうです。
期末で点数を上げて生徒と保護者を是非喜ばせてください!
まず教える前に生徒の基礎学力がどの程度なのでしょうか?
根本的に語彙の問題があります。
例えば、「キシャ」と聞いて
「記者」「汽車」「貴社」なのかがわかってない場合は、文章の意味が読みとれないのは当然です。また、仮に例えば「貴社」だとわかったとしても、「貴社」の意味がわからなかったら、文章全体を把握するのは難しくないrます。同様に、「用いる」を「よういる」、「行う」を「いう」などと読んでいるようなことは、根本的に読解以前の問題です。まずは漢字の読み書き、そして熟語の意味を教えることから始めないとダメでしょう。
さて、上記の問題をクリアーしていたとして、次の課題は読解力です。読解力自体が不足していると思われる場合は、一学年、あるいは二学年さかのぼっててでも、簡単な文章でなおかつ一度も読んだことがない文章(初物の文章)を読ませることが必要かと思います。今の子どもたちの読解力の低下は、初物の文章をたくさん読んで、情報を正しく読みとるというトレーニングが不足しているためです。
典型的なのが小学校の国語で、特に物語文では心情の読み取りと称して、好き勝手に児童が思いついたことを答えることを善しとする風潮があったり、あるいはもう教科書の本文を覚えるくらい読みこんでいて、それでテストをするので、事実上読解力のテストが暗記勝負になったりしまっています。これではいつまでたっても読解力が育つはずがありません。
ですから、学校で習っている単元の所を敢えてずらして(学校の授業でやる前に先取りして読ませたり、模試の過去問など学校の授業とは全然違う題材を読ませたり)、生徒にとっては初物の文章になる文章をなるべく多く読ませるようにするとよいでしょう。もちろん、定期テスト対策は別に必要になります。
結局の所、定期テスト対策と実力(読解力)アップとは分けて教えないとなんともなりません。
ちなみに、小学校高学年向けですが、
読解習熟プリント 小学校高学年(5・6年生) (3) [大型本]
渡邊 和俊 (著) 清風堂書店
という教材があります。「接続詞の使い方とか」「○○さんの考えを書き抜きなさい」のような読解に焦点を当てた問題集をやらせるのも良いかもしれません。
あと、おすすめなのは段落ごとに要点をとらえ、一言で表現するトレーニング(内容を見える化する)をすることです。マインドマップを使うとなお効果的です。マインドマップについては説明が長くなるので割愛しますが、講師が生徒と一緒に、内容を黒板にまとめていくというのがよいスタイルだと思います。
根本的に語彙の問題があります。
例えば、「キシャ」と聞いて
「記者」「汽車」「貴社」なのかがわかってない場合は、文章の意味が読みとれないのは当然です。また、仮に例えば「貴社」だとわかったとしても、「貴社」の意味がわからなかったら、文章全体を把握するのは難しくないrます。同様に、「用いる」を「よういる」、「行う」を「いう」などと読んでいるようなことは、根本的に読解以前の問題です。まずは漢字の読み書き、そして熟語の意味を教えることから始めないとダメでしょう。
さて、上記の問題をクリアーしていたとして、次の課題は読解力です。読解力自体が不足していると思われる場合は、一学年、あるいは二学年さかのぼっててでも、簡単な文章でなおかつ一度も読んだことがない文章(初物の文章)を読ませることが必要かと思います。今の子どもたちの読解力の低下は、初物の文章をたくさん読んで、情報を正しく読みとるというトレーニングが不足しているためです。
典型的なのが小学校の国語で、特に物語文では心情の読み取りと称して、好き勝手に児童が思いついたことを答えることを善しとする風潮があったり、あるいはもう教科書の本文を覚えるくらい読みこんでいて、それでテストをするので、事実上読解力のテストが暗記勝負になったりしまっています。これではいつまでたっても読解力が育つはずがありません。
ですから、学校で習っている単元の所を敢えてずらして(学校の授業でやる前に先取りして読ませたり、模試の過去問など学校の授業とは全然違う題材を読ませたり)、生徒にとっては初物の文章になる文章をなるべく多く読ませるようにするとよいでしょう。もちろん、定期テスト対策は別に必要になります。
結局の所、定期テスト対策と実力(読解力)アップとは分けて教えないとなんともなりません。
ちなみに、小学校高学年向けですが、
読解習熟プリント 小学校高学年(5・6年生) (3) [大型本]
渡邊 和俊 (著) 清風堂書店
という教材があります。「接続詞の使い方とか」「○○さんの考えを書き抜きなさい」のような読解に焦点を当てた問題集をやらせるのも良いかもしれません。
あと、おすすめなのは段落ごとに要点をとらえ、一言で表現するトレーニング(内容を見える化する)をすることです。マインドマップを使うとなお効果的です。マインドマップについては説明が長くなるので割愛しますが、講師が生徒と一緒に、内容を黒板にまとめていくというのがよいスタイルだと思います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
授業の工夫事典!!(塾講師・教師) 更新情報
授業の工夫事典!!(塾講師・教師)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37863人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90062人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人