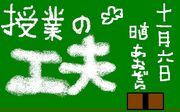既出でしたらすいません
宜しければ、教えてください
愛知県の公立中学校の理科の教科書(大日本図書)では、中1で酸・アルカリの勉強をします。今一、ピントこない点を以下にまとめます
?酸には、レモン汁、酢酸などがあり、イメージ的には「すっぱいものである」
?アルカリには、石鹸水などがイメージ的には「肌に優しい(弱アルカリ)もの」
?酸とは、BTB、リトマス紙、マグネシウムの反応が約束通りのものである
?アルカリとは、BTB、リトマス紙、フェノールフタレインの反応が約束通りのものである
?酸の力(性質)とアルカリの力(性質)が打ち消しあうことを中和という
というような感じになってますが、いざまとめようとすると
?そもそも、酸って何だ??????????????
?どう考えても、アルカリと酸は別物に見える(打ち消しあうようなイメージが湧かない)
?塩がなぜ出来るか全く説明がつかない
(さらに、塩酸と水酸化ナトリウムからは食塩ができますといわれても全然ピンとこない)
?中和して水が出てくるというのも謎
自分の中では、中和というのは化学反応式に触れてからでないと収拾がつかないような気がします。(水素イオン濃度に触れる・触れないには関らず)
自分が知りたいのは、ある程度適切な「酸・アルカリのイメージ」が湧くようなたとえ話なんですが、それ以外でも何か感想がありましたらよろしくお願いします
長文失礼いたしました
宜しければ、教えてください
愛知県の公立中学校の理科の教科書(大日本図書)では、中1で酸・アルカリの勉強をします。今一、ピントこない点を以下にまとめます
?酸には、レモン汁、酢酸などがあり、イメージ的には「すっぱいものである」
?アルカリには、石鹸水などがイメージ的には「肌に優しい(弱アルカリ)もの」
?酸とは、BTB、リトマス紙、マグネシウムの反応が約束通りのものである
?アルカリとは、BTB、リトマス紙、フェノールフタレインの反応が約束通りのものである
?酸の力(性質)とアルカリの力(性質)が打ち消しあうことを中和という
というような感じになってますが、いざまとめようとすると
?そもそも、酸って何だ??????????????
?どう考えても、アルカリと酸は別物に見える(打ち消しあうようなイメージが湧かない)
?塩がなぜ出来るか全く説明がつかない
(さらに、塩酸と水酸化ナトリウムからは食塩ができますといわれても全然ピンとこない)
?中和して水が出てくるというのも謎
自分の中では、中和というのは化学反応式に触れてからでないと収拾がつかないような気がします。(水素イオン濃度に触れる・触れないには関らず)
自分が知りたいのは、ある程度適切な「酸・アルカリのイメージ」が湧くようなたとえ話なんですが、それ以外でも何か感想がありましたらよろしくお願いします
長文失礼いたしました
|
|
|
|
コメント(41)
さっそくありがとうございます
>打ち消しあうだったかどうかは分かりませんが近いニュアンスだったように思います。明日、確認してみます
化学反応というものの存在が、中?でようやくでてきます
まぁ、初めての化学反応♪みたいな感じでも良いかもしれません(ちと難しい印象を与えそうですが)
>アルカリと肌
良く、肌は弱アルカリみたいな表現があったり生徒もそんなようなことをいうのですがなんだかなーと思います(自分から言い出しといてすいません)
ただし、そうでも言わないと「アルカリ」のイメージが全く湧かないような気がしてしまうのです
アルカリの適切なイメージなんかあるのでしょうか?
自分には、水酸化ナトリウム・アンモニア・フェノールフタレイン位しか思いつきません。これでは、ちと無味乾燥かなーと思いました
>打ち消しあうだったかどうかは分かりませんが近いニュアンスだったように思います。明日、確認してみます
化学反応というものの存在が、中?でようやくでてきます
まぁ、初めての化学反応♪みたいな感じでも良いかもしれません(ちと難しい印象を与えそうですが)
>アルカリと肌
良く、肌は弱アルカリみたいな表現があったり生徒もそんなようなことをいうのですがなんだかなーと思います(自分から言い出しといてすいません)
ただし、そうでも言わないと「アルカリ」のイメージが全く湧かないような気がしてしまうのです
アルカリの適切なイメージなんかあるのでしょうか?
自分には、水酸化ナトリウム・アンモニア・フェノールフタレイン位しか思いつきません。これでは、ちと無味乾燥かなーと思いました
アルカリってイメージ的には「ぬるぬるしたもの」
石鹸もぬるぬる、水酸化ナトリウムもぬるぬる。
酸性は逆に「さっぱりしたもの」
合わせると、ぬるぬるとさっぱりでどっちでもなくなる…みたいな
ただのイメージですが。
ちなみに梅干しって「アルカリ食品」ではあるけれど、梅干しそのものがアルカリ性ってわけじゃないですよね?
梅干し自体は酸性(青酸だっけ?)だけど、梅干しを燃やしてできる灰を水に溶かすとアルカリ性になるからアルカリ食品って呼んでたよーな。
てか、アルカリって言葉、使わないんですかね?
酸とアルカリは小学校以来ずっと身近な言葉だった気が。。
あと、うちの業界のプラントとかでアルカリと言えば苛性ソーダ(水酸化ナトリウム水溶液)を指したりします。
酸性の代表が次亜塩素酸ソーダ(通称「次亜」または「次亜塩」)、アルカリの代表が苛性ソーダ(通称「苛性」)とか。
たまに、活性炭の対象ガス性状を表現することもありますが。
石鹸もぬるぬる、水酸化ナトリウムもぬるぬる。
酸性は逆に「さっぱりしたもの」
合わせると、ぬるぬるとさっぱりでどっちでもなくなる…みたいな
ただのイメージですが。
ちなみに梅干しって「アルカリ食品」ではあるけれど、梅干しそのものがアルカリ性ってわけじゃないですよね?
梅干し自体は酸性(青酸だっけ?)だけど、梅干しを燃やしてできる灰を水に溶かすとアルカリ性になるからアルカリ食品って呼んでたよーな。
てか、アルカリって言葉、使わないんですかね?
酸とアルカリは小学校以来ずっと身近な言葉だった気が。。
あと、うちの業界のプラントとかでアルカリと言えば苛性ソーダ(水酸化ナトリウム水溶液)を指したりします。
酸性の代表が次亜塩素酸ソーダ(通称「次亜」または「次亜塩」)、アルカリの代表が苛性ソーダ(通称「苛性」)とか。
たまに、活性炭の対象ガス性状を表現することもありますが。
梅干しの酸性が青酸とは酷いことを書く人もいるもんだね・・・
(青梅に青酸配糖体が含まれてるのは事実だけど、主成分になるくらい入ってたら人間があっさり死にます。あれ、成人で致死量300mgくらいだろ)
梅干しの酸味は、ほとんどクエン酸だと思ってもらっていいです。(意外なことにピクリン酸なんかも入ってるらしいが)
ついでに、「アルカリ性食品」とか、あんなもん全く根拠ないんで。
・酸は、薄かったらすっぱい(試すなら食酢がいいでしょう)。濃かったら体に害を与える
・アルカリは、薄かったら苦い(試すなら重曹の水溶液がいいでしょう)。濃かったら体を溶かして害を与える
実験材料に使うんなら、典型的なアルカリとしては「消石灰」がいいと思う。
酸性物質と塩基性物質は相反する物質で、混ぜたら中和することを説明しといて、
BTBかアントシアニン(紫キャベツの汁とか)を混ぜた石灰水に食酢をちょっとずつ混ぜて色の変化で示せばいい。
中和で水ができることを示すんなら、無水硫酸銅か塩化コバルトを混ぜた氷酢酸に水酸化ナトリウムの粒を入れて反応させたら水の発生が簡単に可視化できると思うのでオススメ
(青梅に青酸配糖体が含まれてるのは事実だけど、主成分になるくらい入ってたら人間があっさり死にます。あれ、成人で致死量300mgくらいだろ)
梅干しの酸味は、ほとんどクエン酸だと思ってもらっていいです。(意外なことにピクリン酸なんかも入ってるらしいが)
ついでに、「アルカリ性食品」とか、あんなもん全く根拠ないんで。
・酸は、薄かったらすっぱい(試すなら食酢がいいでしょう)。濃かったら体に害を与える
・アルカリは、薄かったら苦い(試すなら重曹の水溶液がいいでしょう)。濃かったら体を溶かして害を与える
実験材料に使うんなら、典型的なアルカリとしては「消石灰」がいいと思う。
酸性物質と塩基性物質は相反する物質で、混ぜたら中和することを説明しといて、
BTBかアントシアニン(紫キャベツの汁とか)を混ぜた石灰水に食酢をちょっとずつ混ぜて色の変化で示せばいい。
中和で水ができることを示すんなら、無水硫酸銅か塩化コバルトを混ぜた氷酢酸に水酸化ナトリウムの粒を入れて反応させたら水の発生が簡単に可視化できると思うのでオススメ
塾で教えている者です。
もともと今より1つ前の学習指導要領では、中3でイオンを教え、水素イオンや水酸化物イオンを押さえてから「酸とは〜、アルカリとは〜、中和とは〜」という話をしていました。
現行の指導要領で中3の理科の授業数が減らされた時にイオンが完全に中学校からはずされ、かといって酸とアルカリをやらないわけにもいかないので中1に強引にこの単元を入れた、という経緯があったように思います。
したがってイオン抜きで酸やアルカリを教えるのが、中学校的な(単に現象だけでなく理論を教える)教え方として不自然になるのは当然なので、教科書通りに教える方が厳しいように、私は思います。
私は中1に教える時でも、酸とは水素を含むものでアルカリとは水素+酸素を含むもので、両方がくっつくと水とそれ以外のペア(塩)ができるのだ、という説明をしています(できる時には記号まで教えて反応式まで教えます)。
現象面を教えることも重要なので、そこで止めてしまって(理論的な追求をしないで)教えるという手もあるのかもしれませんが、生徒が納得しなかったりわかりにくかったりする時にどうするかを考える必要があるでしょう。
次の指導要領は多分イオンが復活するので、このあたりの教え方は大幅に変わる(元に戻る)と思います。
もともと今より1つ前の学習指導要領では、中3でイオンを教え、水素イオンや水酸化物イオンを押さえてから「酸とは〜、アルカリとは〜、中和とは〜」という話をしていました。
現行の指導要領で中3の理科の授業数が減らされた時にイオンが完全に中学校からはずされ、かといって酸とアルカリをやらないわけにもいかないので中1に強引にこの単元を入れた、という経緯があったように思います。
したがってイオン抜きで酸やアルカリを教えるのが、中学校的な(単に現象だけでなく理論を教える)教え方として不自然になるのは当然なので、教科書通りに教える方が厳しいように、私は思います。
私は中1に教える時でも、酸とは水素を含むものでアルカリとは水素+酸素を含むもので、両方がくっつくと水とそれ以外のペア(塩)ができるのだ、という説明をしています(できる時には記号まで教えて反応式まで教えます)。
現象面を教えることも重要なので、そこで止めてしまって(理論的な追求をしないで)教えるという手もあるのかもしれませんが、生徒が納得しなかったりわかりにくかったりする時にどうするかを考える必要があるでしょう。
次の指導要領は多分イオンが復活するので、このあたりの教え方は大幅に変わる(元に戻る)と思います。
>中学校的な(単に現象だけでなく理論を教える)教え方として不自然になるのは当然なので、教科書通りに教える方が厳しいように、私は思います。
確かに理論は教えにくいですが、学校では授業がやりやすいですよ。中1の生徒にとっては、酸性、アルカリ性の性質を学ぶ導入にあたる小単元で、現象に触れるだけでも十分ではないかと思いますので。また、授業できる時数としては、例えば東京書籍の指導書によると3時間程度の配当になっています。3時間では?酸性、アルカリ性の性質、?中和の実験、?中和のまとめ、くらいでどうしても時間的には一杯になってしまいますので、学習塾では“水素イオン”とか“化学反応式”まで学習しているとは、驚きました。
ここの小単元は(現行では)検証実験よりも仮説実験(授業)を行いたいところです。酸性とアルカリ性の水溶液の性質を押さえたあとで、「最強の水溶液を作ろう!」とか何とか言って混ぜる。中性になった後の水溶液を一滴取って乾かし、顕微鏡で見ると、なぜか食塩の結晶ができている…。と生徒にとって面白い授業展開ができるところなんですよね。
学校では知識にこだわるよりも、「科学する心」の育成を目的にして授業をしていることが多いようにも思いますが、その分、塾ではこれだけしか教えないの?という疑問があって当然かもしれませんね(笑)
確かに理論は教えにくいですが、学校では授業がやりやすいですよ。中1の生徒にとっては、酸性、アルカリ性の性質を学ぶ導入にあたる小単元で、現象に触れるだけでも十分ではないかと思いますので。また、授業できる時数としては、例えば東京書籍の指導書によると3時間程度の配当になっています。3時間では?酸性、アルカリ性の性質、?中和の実験、?中和のまとめ、くらいでどうしても時間的には一杯になってしまいますので、学習塾では“水素イオン”とか“化学反応式”まで学習しているとは、驚きました。
ここの小単元は(現行では)検証実験よりも仮説実験(授業)を行いたいところです。酸性とアルカリ性の水溶液の性質を押さえたあとで、「最強の水溶液を作ろう!」とか何とか言って混ぜる。中性になった後の水溶液を一滴取って乾かし、顕微鏡で見ると、なぜか食塩の結晶ができている…。と生徒にとって面白い授業展開ができるところなんですよね。
学校では知識にこだわるよりも、「科学する心」の育成を目的にして授業をしていることが多いようにも思いますが、その分、塾ではこれだけしか教えないの?という疑問があって当然かもしれませんね(笑)
>22:じゅんじゅんさん
確かに、実験後に「なぜ“塩”と“水”ができるの?」と考える生徒がいることは自然なことであると思いますし、理論的に教えたいところではあるのですよね。ただ、この段階でイオンの話をして分かる生徒は少ないでしょうし、何より短い時間で教えると指導が中途半端になってしまいます…。つまり学校における全体に対する指導としては、その答えを教えることができない現状かと思うのです。
ですから、全体に対しては「学年が上がれば分かるようになってくるよ」と言って済ませることにしています。教えすぎて、消化不良を起こす危険性に配慮しなくてはなりませんからね。もちろん、習熟度の高い子が授業後に質問をしに来た時には、化学反応式を書いて(ごく簡単に)教えるようにしています。
今の1年生にはこの単元全体を通して、原子やイオンの前に、「身の回りの物質は粒でできている」という概念を持たせることが大事かと思っています。中和の指導が難しいのは「性質が打ち消し合う→酸やアルカリの粒が消える」という誤概念を与えやすいところなんですよね。酸とアルカリの“粒”が合体して中性の水ができるという点を押さえることで精一杯の現状です。
一応3年生になって化学エネルギーについての学習において、化学反応式を学んでからもう一度中和を考えるというカリキュラムになっているんですが、リアリティがないのは確かにちょっと不満ですね。
確かに、実験後に「なぜ“塩”と“水”ができるの?」と考える生徒がいることは自然なことであると思いますし、理論的に教えたいところではあるのですよね。ただ、この段階でイオンの話をして分かる生徒は少ないでしょうし、何より短い時間で教えると指導が中途半端になってしまいます…。つまり学校における全体に対する指導としては、その答えを教えることができない現状かと思うのです。
ですから、全体に対しては「学年が上がれば分かるようになってくるよ」と言って済ませることにしています。教えすぎて、消化不良を起こす危険性に配慮しなくてはなりませんからね。もちろん、習熟度の高い子が授業後に質問をしに来た時には、化学反応式を書いて(ごく簡単に)教えるようにしています。
今の1年生にはこの単元全体を通して、原子やイオンの前に、「身の回りの物質は粒でできている」という概念を持たせることが大事かと思っています。中和の指導が難しいのは「性質が打ち消し合う→酸やアルカリの粒が消える」という誤概念を与えやすいところなんですよね。酸とアルカリの“粒”が合体して中性の水ができるという点を押さえることで精一杯の現状です。
一応3年生になって化学エネルギーについての学習において、化学反応式を学んでからもう一度中和を考えるというカリキュラムになっているんですが、リアリティがないのは確かにちょっと不満ですね。
>20 じゅんじゅんさん
全く同感です。
イオンを教えずに酸性・アルカリ性の本質を理解できるわけがありません。現象としてなんとなくわかった気になるだけでその本質が何なのかはイオンを抜きにわかるはずもないです。
丁度、高校で微分積分を教えずに落下運動を教えるのにも似て、一番の本質部分を抜きにして現象面だけでお茶お濁しているって感じを強く受けます。
でも、そこで、「それでもなんかわからないなぁ?」と言ってくる子がいれば幸いです。それこそ科学の目という科学の芽というか、本質を理解しようとする芽生えなんじゃないかと。イオンの話が理解できるかどうかは別としてイオンってものを理解すれば酸性・アルカリ性の本質が見えてくるということがわかるだけでも意味のあることだと思います。
あまりにも世の中が直感に頼りすぎて論理的にものが考えられない人が増えているのも、右脳!右脳!と直感をもてはやして左脳の機能に代表されるような論理的思考を軽視してきた現れだと思ってます。
「右脳を活性化しよう!」というのは良く聞きますけど「左脳を活性化しよう!」ってのはあまり聞きません。理屈っぽいのを嫌うからでしょうか?でも科学にとって左脳って結構大切じゃないですか?
本質が何なのかを追求する論理的な思考というのはむしろ左脳の役割であってもっと左脳を大切にしても良いんじゃないかと?
# とは言え「左脳が良くなる本」なんて書いても売れないか?(笑)
全く同感です。
イオンを教えずに酸性・アルカリ性の本質を理解できるわけがありません。現象としてなんとなくわかった気になるだけでその本質が何なのかはイオンを抜きにわかるはずもないです。
丁度、高校で微分積分を教えずに落下運動を教えるのにも似て、一番の本質部分を抜きにして現象面だけでお茶お濁しているって感じを強く受けます。
でも、そこで、「それでもなんかわからないなぁ?」と言ってくる子がいれば幸いです。それこそ科学の目という科学の芽というか、本質を理解しようとする芽生えなんじゃないかと。イオンの話が理解できるかどうかは別としてイオンってものを理解すれば酸性・アルカリ性の本質が見えてくるということがわかるだけでも意味のあることだと思います。
あまりにも世の中が直感に頼りすぎて論理的にものが考えられない人が増えているのも、右脳!右脳!と直感をもてはやして左脳の機能に代表されるような論理的思考を軽視してきた現れだと思ってます。
「右脳を活性化しよう!」というのは良く聞きますけど「左脳を活性化しよう!」ってのはあまり聞きません。理屈っぽいのを嫌うからでしょうか?でも科学にとって左脳って結構大切じゃないですか?
本質が何なのかを追求する論理的な思考というのはむしろ左脳の役割であってもっと左脳を大切にしても良いんじゃないかと?
# とは言え「左脳が良くなる本」なんて書いても売れないか?(笑)
>中学生のときに、塩酸をかなり薄めたものを舐めさせてもらったことがありますが、酸っぱかったです。
どうも有り難うございます。そうすると、水素イオン、正確にはオキソニウムイオンは、酸っぱいということになりそうですね。
これも、水素イオンそれ自体の性質というよりも、人間の味覚が「酸っぱい」と感じるようになっているということなだろうけど。
理屈をどの段階で教えるかは、難しいですね。
錘の体積=底辺×高さ÷3 てのも、小学校では水を使った実験で、そうなると教わるけど、「その方法では、ぴったり1/3かどうかは分からない」と思った。
高校で微積分をやって、三角錐、球の体積、球の面積など、公式だけ習ったけどなぜそうなるかは保留していたものが、全て解決した。
その快感は、公式だけ習って理由が分からなくてもやもやした期間があったから得られたとも言える。
中学理科の1分野、特に物理分野は、振り子の周期にしろ、弦をはじいたときの音の高低にしろ、実験結果をまとめるだけだった。電圧、電流、抵抗も何だかよく分からなかった。電圧が大きいと電流が大きい、とかそういう定性的な面しか頭に入らなかった。
これも物理をやって全てすっきりしたが、中学理科の物理分野をやらない状態で最初から理詰めでやった場合にはどうなっただろうか?
ただ物理現象の場合、定性的ではあれ、「弦が太いと、振動の速度が遅くなって低くなる」という具合に何となく理解できた。それが後の理解につながったように思える。
酸・アルカリのあたりは、どうだろうか。
生徒が理解できなくても若干説明していいようにも思う。「原子・イオンがくっついたり離れたりして、何かが起きているらしい」と分かるだけでもいいと思う。
どうも有り難うございます。そうすると、水素イオン、正確にはオキソニウムイオンは、酸っぱいということになりそうですね。
これも、水素イオンそれ自体の性質というよりも、人間の味覚が「酸っぱい」と感じるようになっているということなだろうけど。
理屈をどの段階で教えるかは、難しいですね。
錘の体積=底辺×高さ÷3 てのも、小学校では水を使った実験で、そうなると教わるけど、「その方法では、ぴったり1/3かどうかは分からない」と思った。
高校で微積分をやって、三角錐、球の体積、球の面積など、公式だけ習ったけどなぜそうなるかは保留していたものが、全て解決した。
その快感は、公式だけ習って理由が分からなくてもやもやした期間があったから得られたとも言える。
中学理科の1分野、特に物理分野は、振り子の周期にしろ、弦をはじいたときの音の高低にしろ、実験結果をまとめるだけだった。電圧、電流、抵抗も何だかよく分からなかった。電圧が大きいと電流が大きい、とかそういう定性的な面しか頭に入らなかった。
これも物理をやって全てすっきりしたが、中学理科の物理分野をやらない状態で最初から理詰めでやった場合にはどうなっただろうか?
ただ物理現象の場合、定性的ではあれ、「弦が太いと、振動の速度が遅くなって低くなる」という具合に何となく理解できた。それが後の理解につながったように思える。
酸・アルカリのあたりは、どうだろうか。
生徒が理解できなくても若干説明していいようにも思う。「原子・イオンがくっついたり離れたりして、何かが起きているらしい」と分かるだけでもいいと思う。
みなさん ありがとうございます
自分自身のいい加減さに辟易しているところですが、これも勉強と思いしっかり読ませてもらいます
と
さて、酸性→飲めるものがある アルカリ性→飲めない
というのは、中々面白いイメージですね。なるほどなーと思いました
それから、アルカリ性(もしくは酸性)がとげとげしくて、反対のものを混ぜるとまろやかになる・・というのも面白いですね
それから、うめぼしのアルカリ性食品というのは焼いた後の灰の水溶液がアルカリ性という意味なんですね
すごく、勉強になってます。おもしろいですね。
どなたかおっしゃってましたが、中1だったら事象の確認だけでよい
(酸+アルカリ→塩をしっかり徹底できれば良い)
というのも一理あるように思います
みなさん、本当にありがとうございます
あ、あと・・「さっぱり」と「ねるぬる」も結構好きですw
自分自身のいい加減さに辟易しているところですが、これも勉強と思いしっかり読ませてもらいます
と
さて、酸性→飲めるものがある アルカリ性→飲めない
というのは、中々面白いイメージですね。なるほどなーと思いました
それから、アルカリ性(もしくは酸性)がとげとげしくて、反対のものを混ぜるとまろやかになる・・というのも面白いですね
それから、うめぼしのアルカリ性食品というのは焼いた後の灰の水溶液がアルカリ性という意味なんですね
すごく、勉強になってます。おもしろいですね。
どなたかおっしゃってましたが、中1だったら事象の確認だけでよい
(酸+アルカリ→塩をしっかり徹底できれば良い)
というのも一理あるように思います
みなさん、本当にありがとうございます
あ、あと・・「さっぱり」と「ねるぬる」も結構好きですw
ちょっとひっかかるので、もう少し意見を書きます。
私は学校でも塾でも、「教科書にこう書いてあるから、指導要領ではこうなっているから、時間がこれだけしかないから、こう教えるのが正しい」という考え方には、反対です。
子どもにとって何をどうどれくらい教えるのが一番いいのか、そのために教材等をどのように配置し指導していくのか、これらについて最も考えなければならないのは、文科省の役人や教科書の執筆者ではなく、教師だと思います。
教科書や指導要領は手助けにはなるし、実際現場ではそれら通りにしなければならない面もあるでしょう。
しかしそのことと、教科書や指導要領通りに教えることが子どもにとって最も適切であるということは、一致しません。子どもの状況や教師の力量によって、何をどう教えるのが一番いいかということは異なってくるし、そもそも指導要領が最も子どもにとってわかりやすい教え方であるという論証もされているわけではありません。
私が言いたいのは、たとえ実際には教科書通り・指導要領通りに教えなければならないとしても、それが正しいのだと機械的に考えてほしくない、もっといい教え方があるのではないかと「疑心暗鬼」になっていてほしい、ということです。
本気で子どもに「科学する心」を教えたいと思うのならば、自分が教えたい科学とは何か、それは今ある教科書や指導要領や時間数などの現実の中でどのように実現し得るのか(そうでないのか)、そのことを考え続けなければならないと思います。
中学教師だって自然科学の専門家に変わりありません。子どもにとって何をどう学ぶのが一番いいのか本当にわかるのは、子どもを直接見ている教師しかいないでしょう。
そのことから逃げて、教科書通りだからそれでいいのだと考えてしまうのなら、それこそ(縛りのない)塾の講師に負けてしまうのではないかと思います。
あまり押しつける気もないのですが、トピ主さんにそんなことも考えていただけたら、うれしいです。
私は学校でも塾でも、「教科書にこう書いてあるから、指導要領ではこうなっているから、時間がこれだけしかないから、こう教えるのが正しい」という考え方には、反対です。
子どもにとって何をどうどれくらい教えるのが一番いいのか、そのために教材等をどのように配置し指導していくのか、これらについて最も考えなければならないのは、文科省の役人や教科書の執筆者ではなく、教師だと思います。
教科書や指導要領は手助けにはなるし、実際現場ではそれら通りにしなければならない面もあるでしょう。
しかしそのことと、教科書や指導要領通りに教えることが子どもにとって最も適切であるということは、一致しません。子どもの状況や教師の力量によって、何をどう教えるのが一番いいかということは異なってくるし、そもそも指導要領が最も子どもにとってわかりやすい教え方であるという論証もされているわけではありません。
私が言いたいのは、たとえ実際には教科書通り・指導要領通りに教えなければならないとしても、それが正しいのだと機械的に考えてほしくない、もっといい教え方があるのではないかと「疑心暗鬼」になっていてほしい、ということです。
本気で子どもに「科学する心」を教えたいと思うのならば、自分が教えたい科学とは何か、それは今ある教科書や指導要領や時間数などの現実の中でどのように実現し得るのか(そうでないのか)、そのことを考え続けなければならないと思います。
中学教師だって自然科学の専門家に変わりありません。子どもにとって何をどう学ぶのが一番いいのか本当にわかるのは、子どもを直接見ている教師しかいないでしょう。
そのことから逃げて、教科書通りだからそれでいいのだと考えてしまうのなら、それこそ(縛りのない)塾の講師に負けてしまうのではないかと思います。
あまり押しつける気もないのですが、トピ主さんにそんなことも考えていただけたら、うれしいです。
>32:じゅんじゅんさん
まさにおっしゃる通りだと思っています。教科書と学習指導要領に雁字搦めにされていたら、本当に大切な視点を忘れてしまいます。学習指導要領は一つの基準として考えるべきで、「水ができること」など同時に教え込んだ方が(概念形成の観点から考えたときに)効率のよいこともあります。
ですが、時間はかなり重要だと思います。塾でもきっとそうではないでしょうか。教えなければいけないことは何も「酸・アルカリ」「中和」だけではないのですから。もっと時間さえあれば、原子というものを教えて、原子の種類を覚えさせて、原子構造を教えて〜。イオンとはどんなものなのか教えて、水素イオンと水酸化物イオンを教えて〜。なんて、この“小単元”の理論だけでも書き出したら切りがないです。
もう一度言いますが、“今の中学一年生”に「酸・アルカリ」「中和」を原子やイオンの観点から約3時間配当で教えるのは物理的(化学的?)に不可能です。別に化学の単元だけを時間を使って重点的にやればよいではないか、という意見もあるでしょうが、それは現実的ではないですし、必ず他の単元の学習に皺寄せがきます。中学校では物化生地を時間的にもバランスよく学習させることが大切でしょう。
理論を教えると言うのならば、ある程度きっちり教えることが必要でしょうね。「水素イオンが関係しているんだよ」と言うだけならば容易いことでしょうし、果たして本当に“教えた”ことになるのか、と思ってしまいます(指導者側の自己満足に過ぎないのではないか)。また、結局、水素イオンって何だろうという新たな疑問も生まれます。原子も教えていない。そもそも世界は粒でできているという概念も持っているか分からない。そんな子どもたちにイオン、とは少し本質とはかけ離れていて、時期尚早であるようにも思いますけれどもね。
まさにおっしゃる通りだと思っています。教科書と学習指導要領に雁字搦めにされていたら、本当に大切な視点を忘れてしまいます。学習指導要領は一つの基準として考えるべきで、「水ができること」など同時に教え込んだ方が(概念形成の観点から考えたときに)効率のよいこともあります。
ですが、時間はかなり重要だと思います。塾でもきっとそうではないでしょうか。教えなければいけないことは何も「酸・アルカリ」「中和」だけではないのですから。もっと時間さえあれば、原子というものを教えて、原子の種類を覚えさせて、原子構造を教えて〜。イオンとはどんなものなのか教えて、水素イオンと水酸化物イオンを教えて〜。なんて、この“小単元”の理論だけでも書き出したら切りがないです。
もう一度言いますが、“今の中学一年生”に「酸・アルカリ」「中和」を原子やイオンの観点から約3時間配当で教えるのは物理的(化学的?)に不可能です。別に化学の単元だけを時間を使って重点的にやればよいではないか、という意見もあるでしょうが、それは現実的ではないですし、必ず他の単元の学習に皺寄せがきます。中学校では物化生地を時間的にもバランスよく学習させることが大切でしょう。
理論を教えると言うのならば、ある程度きっちり教えることが必要でしょうね。「水素イオンが関係しているんだよ」と言うだけならば容易いことでしょうし、果たして本当に“教えた”ことになるのか、と思ってしまいます(指導者側の自己満足に過ぎないのではないか)。また、結局、水素イオンって何だろうという新たな疑問も生まれます。原子も教えていない。そもそも世界は粒でできているという概念も持っているか分からない。そんな子どもたちにイオン、とは少し本質とはかけ離れていて、時期尚早であるようにも思いますけれどもね。
>34 あむく@さん
もし時間だけが問題ならば、私なら酸とアルカリは中1でなく中2か中3で教えます。
もともと指導要領でもそういう順序で教えていたのですから、整合性もとれるはずです。
少なくとも中2で原子や分子を教えた後で「酸性の物質とはこのような原子の組み合わせを持っている」等々教えることはできるでしょう。イオンの完全な理解に至らなくても、物質の粒子的理解と酸・アルカリとの関連を感じさせるくらいのことはできると思います。
私は私立学校で教えていたことがありますが、そこではカリキュラムをかなり組み換えてやっていて、授業時間は公立とほとんど同じでしたが能率的に深い内容まで教えることができるようになっていました。
公立学校でそれができないとしたら、指導要領の縛りが最も大きい要素ではないかと私は思います(転校生の問題などもあるでしょうが、それが最も大きい原因だとは思えません)。
私は「イオンを必ず教えるべきだ」と言っているのではありません。
子どもにとって一番いい教え方ができないとしたら、それを指導要領や時間数のせいにするのではなく、教師自身の責任としてとらえるべきではないか、と考えるのです。子どもから見ればそのようにしか見えません。
指導要領や授業時間に不満があるのなら、たとえば現場の教師がそれを変えていくような運動をするべきだと思います。何もしないで「時間がないからできない」と言っているのでは、結局子どもに対する責任を放棄しているように、私には見えます。
もし時間だけが問題ならば、私なら酸とアルカリは中1でなく中2か中3で教えます。
もともと指導要領でもそういう順序で教えていたのですから、整合性もとれるはずです。
少なくとも中2で原子や分子を教えた後で「酸性の物質とはこのような原子の組み合わせを持っている」等々教えることはできるでしょう。イオンの完全な理解に至らなくても、物質の粒子的理解と酸・アルカリとの関連を感じさせるくらいのことはできると思います。
私は私立学校で教えていたことがありますが、そこではカリキュラムをかなり組み換えてやっていて、授業時間は公立とほとんど同じでしたが能率的に深い内容まで教えることができるようになっていました。
公立学校でそれができないとしたら、指導要領の縛りが最も大きい要素ではないかと私は思います(転校生の問題などもあるでしょうが、それが最も大きい原因だとは思えません)。
私は「イオンを必ず教えるべきだ」と言っているのではありません。
子どもにとって一番いい教え方ができないとしたら、それを指導要領や時間数のせいにするのではなく、教師自身の責任としてとらえるべきではないか、と考えるのです。子どもから見ればそのようにしか見えません。
指導要領や授業時間に不満があるのなら、たとえば現場の教師がそれを変えていくような運動をするべきだと思います。何もしないで「時間がないからできない」と言っているのでは、結局子どもに対する責任を放棄しているように、私には見えます。
35:じゅんじゅんさん
理想的には、仰るように、もう少し後の段階でまとめて教えるのが(時間的にも効率が)よいのかもしれません。しかし、積分定数さんがおっしゃるように、定性的な理解の段階を踏んでおいて、後になって理解が進むという場合もあるかと思います。どちらにせよ、学校独自にカリキュラムを変えるまでに拘るところではないと私は考えています(拘るべきところは他にあります)。繰り返し考えることの利点もありますからね。
それよりも、私の県における公立校では県単位で足並みを揃えるという方向性があり、それを優先する方が生徒にとって都合がよいと思うのです。同じ教科書会社の教科書を使用することで、例えば、県で共通の試験を同じ範囲で受けることが可能になります。それが学校毎の指導の評価、如いては、指導研究の材料になり得るのですよ。私立校のようにカリキュラムの編成を工夫するのも、やはり魅力的なことではありますが、公立校ならではの工夫というものも存在する訳です。
一応確認したいのですが、学習指導要領は無視できませんよ?あと、現行のものを基準とすべきなので、過去のものは参考程度とすべきです。学習指導要領を縛りと考えるのか、その中で最大のコストパフォーマンスを発揮しようと考えるのかは、考え方の違いかもしれません。ですが、現実的、実践的なのは後者であることは公立校で働いてみて分かったことです。必ずしも学習指導要領=悪ではないですし、「自分の考えが甘かった」「カリキュラムの基準を構成することは奥が深い」と思うこともたまにあります。
理想的には、仰るように、もう少し後の段階でまとめて教えるのが(時間的にも効率が)よいのかもしれません。しかし、積分定数さんがおっしゃるように、定性的な理解の段階を踏んでおいて、後になって理解が進むという場合もあるかと思います。どちらにせよ、学校独自にカリキュラムを変えるまでに拘るところではないと私は考えています(拘るべきところは他にあります)。繰り返し考えることの利点もありますからね。
それよりも、私の県における公立校では県単位で足並みを揃えるという方向性があり、それを優先する方が生徒にとって都合がよいと思うのです。同じ教科書会社の教科書を使用することで、例えば、県で共通の試験を同じ範囲で受けることが可能になります。それが学校毎の指導の評価、如いては、指導研究の材料になり得るのですよ。私立校のようにカリキュラムの編成を工夫するのも、やはり魅力的なことではありますが、公立校ならではの工夫というものも存在する訳です。
一応確認したいのですが、学習指導要領は無視できませんよ?あと、現行のものを基準とすべきなので、過去のものは参考程度とすべきです。学習指導要領を縛りと考えるのか、その中で最大のコストパフォーマンスを発揮しようと考えるのかは、考え方の違いかもしれません。ですが、現実的、実践的なのは後者であることは公立校で働いてみて分かったことです。必ずしも学習指導要領=悪ではないですし、「自分の考えが甘かった」「カリキュラムの基準を構成することは奥が深い」と思うこともたまにあります。
>じゅんじゅんさん
最善の指導方法を模索することは確かに大切なことですね。ありがとうございます
さて、自分が教えたい科学とは?と言われるとちょっと困ってしまいます
(理科の先生としては情けないですが・・・)
ただ、思うのは
?覚えることは極力減らしたい
?一つ知識を覚えたら、せめて3つの自然現象をその知識で解明したい
?忘れてしまわないような鮮烈なイメージを持たせたい
ということです
現在の教科書は、非常に難しい・・というか書いてある説明が少なすぎる、それじゃ分からん。(と自分は思います)
それに対していかに、肉付けして、実験の仕方をひねってみたり、色々な例え話をしてみたりとその辺の工夫が必要に思います
なので、今回は「酸・アルカリのイメージというか例え話」を知りたくて投稿しました。
最善の指導方法を模索することは確かに大切なことですね。ありがとうございます
さて、自分が教えたい科学とは?と言われるとちょっと困ってしまいます
(理科の先生としては情けないですが・・・)
ただ、思うのは
?覚えることは極力減らしたい
?一つ知識を覚えたら、せめて3つの自然現象をその知識で解明したい
?忘れてしまわないような鮮烈なイメージを持たせたい
ということです
現在の教科書は、非常に難しい・・というか書いてある説明が少なすぎる、それじゃ分からん。(と自分は思います)
それに対していかに、肉付けして、実験の仕方をひねってみたり、色々な例え話をしてみたりとその辺の工夫が必要に思います
なので、今回は「酸・アルカリのイメージというか例え話」を知りたくて投稿しました。
すみません、本題の方を
酸とアルカリは塾でも実験がしやすいので、とにかく生徒の前で色々な水溶液にBTBやフェノールフタレインを入れて見せます。(牛乳とかサイダーとかは結構受けます)
BTBだとあまりわかりませんが、フェノールフタレインだとある程度は「強いアルカリ」「弱いアルカリ」が見えるので、同じアルカリ性でも強弱があるんだろう、くらいのことを言います。
普段は、リトマス紙・BTB・フェノールフタレインの色をまとめてから、イカのように説明します。
・酸は「酸っぱい」だから酸っぱいものが多い。アルカリは基本的に苦い。酸っぱい・苦い以外の味(砂糖水・食塩水)は中性が多い。
・強い酸は金属を溶かす。ただしメダル(金・銀・銅)は溶けない。(中学生には、アルカリが一部の金属を溶かすことは説明しません)
・酸性の物質は基本的に「○○酸(水)」という名前がつく。ここで二酸化炭素を水に溶かしたものが炭酸水と呼ばれることを説明する。また「硫酸銅」のように、酸の後に水以外のものがつくと酸性とは限らないことも言う。
・アルカリ性の物質は基本的に「水酸化○○」という名前がつく。ここでアンモニアが水に溶けると「水酸化アンモニウム」になること、石灰水が水酸化カルシウムの水溶液であることを言う。
・酸は酸素のことではなく「水素」のことである(昔の人がまちがえて名前をつけてしまった)こと、アルカリは「水酸化○○」だから水素+酸素が入っていることを言う。
・酸とアルカリを混ぜると、酸の「水素」とアルカリの「水素+酸素」が結びついて水ができること、それ以外の部分が固体になったものを「塩」と呼ばれることを説明する。
イオンは必要がなければ説明しませんが、子どもが突っ込んできた場合には状況(相手)に応じて説明する。時間がある時は旧カリのときにつくったプリントを使う。
こんなところでしょうか。あんまり参考になりませんが……
酸とアルカリは塾でも実験がしやすいので、とにかく生徒の前で色々な水溶液にBTBやフェノールフタレインを入れて見せます。(牛乳とかサイダーとかは結構受けます)
BTBだとあまりわかりませんが、フェノールフタレインだとある程度は「強いアルカリ」「弱いアルカリ」が見えるので、同じアルカリ性でも強弱があるんだろう、くらいのことを言います。
普段は、リトマス紙・BTB・フェノールフタレインの色をまとめてから、イカのように説明します。
・酸は「酸っぱい」だから酸っぱいものが多い。アルカリは基本的に苦い。酸っぱい・苦い以外の味(砂糖水・食塩水)は中性が多い。
・強い酸は金属を溶かす。ただしメダル(金・銀・銅)は溶けない。(中学生には、アルカリが一部の金属を溶かすことは説明しません)
・酸性の物質は基本的に「○○酸(水)」という名前がつく。ここで二酸化炭素を水に溶かしたものが炭酸水と呼ばれることを説明する。また「硫酸銅」のように、酸の後に水以外のものがつくと酸性とは限らないことも言う。
・アルカリ性の物質は基本的に「水酸化○○」という名前がつく。ここでアンモニアが水に溶けると「水酸化アンモニウム」になること、石灰水が水酸化カルシウムの水溶液であることを言う。
・酸は酸素のことではなく「水素」のことである(昔の人がまちがえて名前をつけてしまった)こと、アルカリは「水酸化○○」だから水素+酸素が入っていることを言う。
・酸とアルカリを混ぜると、酸の「水素」とアルカリの「水素+酸素」が結びついて水ができること、それ以外の部分が固体になったものを「塩」と呼ばれることを説明する。
イオンは必要がなければ説明しませんが、子どもが突っ込んできた場合には状況(相手)に応じて説明する。時間がある時は旧カリのときにつくったプリントを使う。
こんなところでしょうか。あんまり参考になりませんが……
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
授業の工夫事典!!(塾講師・教師) 更新情報
授業の工夫事典!!(塾講師・教師)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 相棒
- 59290人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209458人
- 3位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19958人