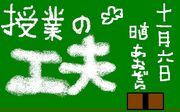ゴロ合わせ、単なる暗記以外もっと科学的な、いや革新的な社会の教授法を試行錯誤しながら考えています。ただし、一人では限界がある。一人だとそれまでのドグマから抜け出せないので、みなさんの知恵を借りたいと思います。
なんか社会だけ、気がついたら暗記とゴロしかないのは寂しいでしょ。
対象は私立中入試から高校入試までの範囲。
分野は地理、歴史、公民それぞれ。
数学、英語、技能科目などの他教科の手法もオーケー。
公式化
キーワード連想
図式化
何でもアリでいきたいと思います。
例えば、理科には「右手の法則」とかありますよね。これと同じような法則か、規則かは無理なのか。数学の定理のような発想はできないものか。
具体例では、地理の促成栽培、抑制栽培の理解のさせ方として、「色の法則」というのを私は使っています。
色の薄い野菜は抑制栽培。キャベツ、レタスは高原野菜。
色の濃い野菜は促成栽培。ピーマン、きゅうり、ナス。
次期をずらす。
大消費地へ出荷。
考えて、おぼえて、そこから整理して、文章にできるという一連の流れがわかりやすく理解できる教授法をみなさんと一緒に考えたいのですか。どうですか。
足の引っ張り合い、揚げ足取り、批判の批判なし。
こういうスタンスでいきたいと思います。
ご協力をおねがいします。
なんか社会だけ、気がついたら暗記とゴロしかないのは寂しいでしょ。
対象は私立中入試から高校入試までの範囲。
分野は地理、歴史、公民それぞれ。
数学、英語、技能科目などの他教科の手法もオーケー。
公式化
キーワード連想
図式化
何でもアリでいきたいと思います。
例えば、理科には「右手の法則」とかありますよね。これと同じような法則か、規則かは無理なのか。数学の定理のような発想はできないものか。
具体例では、地理の促成栽培、抑制栽培の理解のさせ方として、「色の法則」というのを私は使っています。
色の薄い野菜は抑制栽培。キャベツ、レタスは高原野菜。
色の濃い野菜は促成栽培。ピーマン、きゅうり、ナス。
次期をずらす。
大消費地へ出荷。
考えて、おぼえて、そこから整理して、文章にできるという一連の流れがわかりやすく理解できる教授法をみなさんと一緒に考えたいのですか。どうですか。
足の引っ張り合い、揚げ足取り、批判の批判なし。
こういうスタンスでいきたいと思います。
ご協力をおねがいします。
|
|
|
|
コメント(80)
ゆきうささんの発言を読んで、これは公立小学校の教授法にも通じるなと感じました。かつて教育技術の法則化運動というのがはやった事があります。優れた教育技術を共有化しようというコンセプトで、私の先輩なんかも熱心に参加し活動しました。けれど、これは自分なりにどうやって教えたらいいんだろうと模索していたからこそ、ああ、こんな教え方があるのか、こっちの教え方の方がいいなあという感動につながったのだと思います。
自分で教え方を考えもせず、安易にネットで検索、さらには掲示板やこうしたSNSで聞いてしまうのは、自分で教師としての伸びしろを摘んでしまっているようにしか思えません。もっともそうした努力すらしない教員が一部ではありますがいることも事実です。
教育情報の共有化は必要だとは思いますが、運用は難しいですね。
教授法ではありませんが、私はよく単元のまとめにイメージマップを書かせています。小学生でも知識のある子はどんどん言葉がつながっていきます。やる気も大事だけど知識も大事だと思います。詰め込み教育との批判で小学校ではほとんど暗記させることがなくなりましたが、知っているから面白いし、思考力も深まるように感じます。クラスを見ても御三家を受験するような子と、普通の子では知識量に明確な差があります。優秀な人材は私塾を経て私学に流出していく危機感を強く感じています。トピとははずれてしまいました。すみません。
自分で教え方を考えもせず、安易にネットで検索、さらには掲示板やこうしたSNSで聞いてしまうのは、自分で教師としての伸びしろを摘んでしまっているようにしか思えません。もっともそうした努力すらしない教員が一部ではありますがいることも事実です。
教育情報の共有化は必要だとは思いますが、運用は難しいですね。
教授法ではありませんが、私はよく単元のまとめにイメージマップを書かせています。小学生でも知識のある子はどんどん言葉がつながっていきます。やる気も大事だけど知識も大事だと思います。詰め込み教育との批判で小学校ではほとんど暗記させることがなくなりましたが、知っているから面白いし、思考力も深まるように感じます。クラスを見ても御三家を受験するような子と、普通の子では知識量に明確な差があります。優秀な人材は私塾を経て私学に流出していく危機感を強く感じています。トピとははずれてしまいました。すみません。
歴史教育について.
私は,歴史の授業に全然興味が持てませんでした.
先生は,色々な工夫をしていたのかもしれませんが,
何故,それを勉強しなければいけないのか理解出来ませんでした.
もちろん教養として大切だとは思いましたが,
それ以上の意味を高校生の頃は考えませんでした.
今,社会人となり,
さまざまな戦争がくだらない理由で戦争が展開されるのを
見てくると,歴史教育の必要性を感じます.
某国の指導者が宗教について無理解なために,
世界中を巻き込む戦争を始めたりしました.
歴史上の出来事が,
「現代にどういう意味を持つのか」
を強調して教えてもらえれば,興味も湧いたと思います.
そういう意味で,
地歴を教えるひとは,現在の政治経済に通じていて欲しいものです.
私は,歴史の授業に全然興味が持てませんでした.
先生は,色々な工夫をしていたのかもしれませんが,
何故,それを勉強しなければいけないのか理解出来ませんでした.
もちろん教養として大切だとは思いましたが,
それ以上の意味を高校生の頃は考えませんでした.
今,社会人となり,
さまざまな戦争がくだらない理由で戦争が展開されるのを
見てくると,歴史教育の必要性を感じます.
某国の指導者が宗教について無理解なために,
世界中を巻き込む戦争を始めたりしました.
歴史上の出来事が,
「現代にどういう意味を持つのか」
を強調して教えてもらえれば,興味も湧いたと思います.
そういう意味で,
地歴を教えるひとは,現在の政治経済に通じていて欲しいものです.
こんなのでよければ…
日本の気候 「雨温図を見分ける方法」
日本の気候は中学校では
1.北海道の気候
2.太平洋側の気候
3.日本海側の気候
4.瀬戸内の気候
5.中央高地の気候
6.南西諸島の気候
の6つで教えてます。
雨温図が6つあったらまず
?1番暑いところと1番寒いものを1と6とする。
?冬の降水量が多い所(つまり雪が多い)を3とする。
(降水量が谷型になってるのは3くらいなのでわかりやすい)
?2番目に寒いところを5とする
(寒いのは「北の方」とどういう所?→「高い所」と説明するとわかりやすい)
そして残った2と4はとても似ているのですが、
瀬戸内の説明によく載っている「年間降水量が比較的少ない」というのはわかりずらいので・・・
?秋に降水量が増えている(台風がよく来る)のが2とする
(瀬戸内は四国山地、中国山地と山地に挟まれているので台風の影響が比較的少ないんですね。)
これで大抵見分けることができるはず。
でもかなり適当なので、ご指摘などありましたらお願いします。
>りささん
>地歴を教えるひとは,現在の政治経済に通じていて欲しいものです.
全く同感です。
社会科はやっぱり「社会」を担っていくための勉強だと思います。
歴史をどれだけ知っていても、地理にどれだけ詳しくても、それを未来のために活かしていかなければ意味がないですからね。常に自分に関係する事として考えていくことが大切ですよね。(なかなか普段の授業では難しいことですが)
日本の気候 「雨温図を見分ける方法」
日本の気候は中学校では
1.北海道の気候
2.太平洋側の気候
3.日本海側の気候
4.瀬戸内の気候
5.中央高地の気候
6.南西諸島の気候
の6つで教えてます。
雨温図が6つあったらまず
?1番暑いところと1番寒いものを1と6とする。
?冬の降水量が多い所(つまり雪が多い)を3とする。
(降水量が谷型になってるのは3くらいなのでわかりやすい)
?2番目に寒いところを5とする
(寒いのは「北の方」とどういう所?→「高い所」と説明するとわかりやすい)
そして残った2と4はとても似ているのですが、
瀬戸内の説明によく載っている「年間降水量が比較的少ない」というのはわかりずらいので・・・
?秋に降水量が増えている(台風がよく来る)のが2とする
(瀬戸内は四国山地、中国山地と山地に挟まれているので台風の影響が比較的少ないんですね。)
これで大抵見分けることができるはず。
でもかなり適当なので、ご指摘などありましたらお願いします。
>りささん
>地歴を教えるひとは,現在の政治経済に通じていて欲しいものです.
全く同感です。
社会科はやっぱり「社会」を担っていくための勉強だと思います。
歴史をどれだけ知っていても、地理にどれだけ詳しくても、それを未来のために活かしていかなければ意味がないですからね。常に自分に関係する事として考えていくことが大切ですよね。(なかなか普段の授業では難しいことですが)
>教育情報の共有化は必要だとは思いますが、運用は難しいですね。
そうなんですよ。昔、私が飲みの席で話した教授法を、上司なんですが全然腕のなく、講師いびりが趣味みたいな人が散々っぱらめちゃくちゃに貶しておいて、後日、給与査定に関係ある研修会でその教授法を使って「私が開発しました」なんていけしゃあしゃあという言ったことがあって、ものすごく「イラッ」ときました。(無論、それをさらに書物や他の先生の授業を参考に進化させていたので。出し惜しみせずに本気でやって帳消しにしてやりましたが)なんてことも。だから「見て盗む」という昔ながらの作法はすごく理にかなっていると思うのですよね。現に私も「お、この先生すごいな」と思うと見て盗み、盗まれしながらお互いに切磋琢磨していくのが一番良い「共有化」だと思うのですよね。まぁ、でもこのトピに時間をかけて書いている時点でそんな先生はいないと思いなおした次第です。すみませんでした。
>>45
出来る限り、そうしてあげたいのですが。「効率」を考えないといけないってこともありますしね…。とにかく現代の子供たちは忙しすぎる(;^ω^)昔の社会科の授業は今で言うと「社会科見学」がメインの授業だったそうです。それを考えると書物や写真でしか見られない彼らは可哀想…。だから代理体験してきてあげるくらいしかやってあげられないふがいなさ…。
▼「まぁ、みんなやってないだろう」というネタを1つ。
国語の長文読解(ちょうど論理力についてというトピがあったので)なんですが、私は授業前に前もって問題の答えを全部教えてしまいます。そして宿題として「何故、その答えになるのか」をノートに書かせてきて、授業ではそれを発表し、みんなで精査していくという授業展開をしています。数学(算数)でも、難問は最初から解法を導こうとすると時間がかかるので予め答えを教えておいて考えて来るなんていう方法で応用が可能です。「おお、開発できた!」と思ったら某授業ライブをしている人が同じ方法を提唱しておられたので( ´・ω・) ショボーンとした記憶が。ぜひお試しあれ、ってかもっと良い方法あれば突っ込んでほしい。(他の先生からは精査されずに邪道といわれてしまうので)
そうなんですよ。昔、私が飲みの席で話した教授法を、上司なんですが全然腕のなく、講師いびりが趣味みたいな人が散々っぱらめちゃくちゃに貶しておいて、後日、給与査定に関係ある研修会でその教授法を使って「私が開発しました」なんていけしゃあしゃあという言ったことがあって、ものすごく「イラッ」ときました。(無論、それをさらに書物や他の先生の授業を参考に進化させていたので。出し惜しみせずに本気でやって帳消しにしてやりましたが)なんてことも。だから「見て盗む」という昔ながらの作法はすごく理にかなっていると思うのですよね。現に私も「お、この先生すごいな」と思うと見て盗み、盗まれしながらお互いに切磋琢磨していくのが一番良い「共有化」だと思うのですよね。まぁ、でもこのトピに時間をかけて書いている時点でそんな先生はいないと思いなおした次第です。すみませんでした。
>>45
出来る限り、そうしてあげたいのですが。「効率」を考えないといけないってこともありますしね…。とにかく現代の子供たちは忙しすぎる(;^ω^)昔の社会科の授業は今で言うと「社会科見学」がメインの授業だったそうです。それを考えると書物や写真でしか見られない彼らは可哀想…。だから代理体験してきてあげるくらいしかやってあげられないふがいなさ…。
▼「まぁ、みんなやってないだろう」というネタを1つ。
国語の長文読解(ちょうど論理力についてというトピがあったので)なんですが、私は授業前に前もって問題の答えを全部教えてしまいます。そして宿題として「何故、その答えになるのか」をノートに書かせてきて、授業ではそれを発表し、みんなで精査していくという授業展開をしています。数学(算数)でも、難問は最初から解法を導こうとすると時間がかかるので予め答えを教えておいて考えて来るなんていう方法で応用が可能です。「おお、開発できた!」と思ったら某授業ライブをしている人が同じ方法を提唱しておられたので( ´・ω・) ショボーンとした記憶が。ぜひお試しあれ、ってかもっと良い方法あれば突っ込んでほしい。(他の先生からは精査されずに邪道といわれてしまうので)
>Randa さんへ
まず、ありがとうございます。
これだけのすばらしい教案を貴重なお時間を割いて書き込んでくださったことを感謝します。
ぜひ参考にさせていただきます。
私が現在関わっている地域では、鎌倉幕府の政治史だけが出題された中学校もあります。出題範囲に対する認識は、地域性がありますねえ。毎回、全国各地を引っ越すたびにそう思います。
現在、私が鎌倉時代の授業で考えている教え方は「マインドマップ」をうまく使った構造式のものです。
Randa さんの「拠点式」と重なります。ポイントをしぼっていけばどうしても似てきますねえ。
中央に幕府の所在地と将軍
その周囲に
 執権(北条氏)
執権(北条氏) 政所から問注所・守護と地頭
政所から問注所・守護と地頭
 朝廷
朝廷 承久の乱(後鳥羽上皇)
承久の乱(後鳥羽上皇) 六波羅探題
六波羅探題
 封建制度
封建制度 御恩と奉公
御恩と奉公
 御成敗式目
御成敗式目 北条泰時
北条泰時
…等々を枝分かれさせていきます。
執権
守護と地頭
承久の乱
封建制度
御成敗式目
等々にはアンダーラインを引き、その語句の説明を生徒に記述させています。
これは全体を俯瞰してとらえるにはいいんですが、時系列が分からなくなってしまいます。
そこで、時系列にしたがった年表をとなりにまとめています。
現在の課題は、枝分かれさせた言葉同士をどうやって記憶させていくかということです。そこでダイマジンさんのベック式を一部導入させてもらっています。ベック式だと私のつくったマインドマップの枝と枝のすき間が上手い具合にうまっていくんですね。
さらに、
 六波羅探題を設置した後の影響について
六波羅探題を設置した後の影響について
 封建制度と幕府の関係について
封建制度と幕府の関係について
重要語句をそれぞれ小さな項目に枝分かれさせて分解し、そこから気がついた内容について生徒に自由に作文を書かせています。
しかし、これは完成したものではありません。
私はこの方法も単なる教え方の通過点にすぎないと考えています。毎年、毎月過去の教え方を整理整頓して、さらなる良いものを塗り上げようと日々頭を痛めているところです
地域
顧客のニーズ
理解度
その他
どんなに状況が変わっても相手が満足してくれる教え方が出来ないものかというのが一番のテーマですねえ。
まず、ありがとうございます。
これだけのすばらしい教案を貴重なお時間を割いて書き込んでくださったことを感謝します。
ぜひ参考にさせていただきます。
私が現在関わっている地域では、鎌倉幕府の政治史だけが出題された中学校もあります。出題範囲に対する認識は、地域性がありますねえ。毎回、全国各地を引っ越すたびにそう思います。
現在、私が鎌倉時代の授業で考えている教え方は「マインドマップ」をうまく使った構造式のものです。
Randa さんの「拠点式」と重なります。ポイントをしぼっていけばどうしても似てきますねえ。
中央に幕府の所在地と将軍
その周囲に
…等々を枝分かれさせていきます。
執権
守護と地頭
承久の乱
封建制度
御成敗式目
等々にはアンダーラインを引き、その語句の説明を生徒に記述させています。
これは全体を俯瞰してとらえるにはいいんですが、時系列が分からなくなってしまいます。
そこで、時系列にしたがった年表をとなりにまとめています。
現在の課題は、枝分かれさせた言葉同士をどうやって記憶させていくかということです。そこでダイマジンさんのベック式を一部導入させてもらっています。ベック式だと私のつくったマインドマップの枝と枝のすき間が上手い具合にうまっていくんですね。
さらに、
重要語句をそれぞれ小さな項目に枝分かれさせて分解し、そこから気がついた内容について生徒に自由に作文を書かせています。
しかし、これは完成したものではありません。
私はこの方法も単なる教え方の通過点にすぎないと考えています。毎年、毎月過去の教え方を整理整頓して、さらなる良いものを塗り上げようと日々頭を痛めているところです
地域
顧客のニーズ
理解度
その他
どんなに状況が変わっても相手が満足してくれる教え方が出来ないものかというのが一番のテーマですねえ。
受験生用の使用法を追加です。
受験生には、「逆歴史」と「拠点式」の併用が良いです。
(「逆歴史」も自分で命名しましたが)
大抵の人は、受験勉強を古代から始めるけど、それってかなり非効率です。
日本史でも世界史でも、近代史の方が圧倒的によく出ますから。
終わりには必ず始まりがある。
何かが起きたら、必ず何か原因がある。
1945 第二次世界大戦終戦
1941 太平洋戦争開始(第二次世界大戦の太平洋アジア方面)
1939 第二次世界大戦開始
1929 世界大恐慌
と歴史をどんどん遡っていきながら、「拠点式」をする。
そうすると出題率の高い近代史が先に出来て、たまに戻って復習すれば効率よく点が取れる。
戦後は、複雑で覚え難いから、近代史して慣れた後が良い。
(私は戦後は、普通の流れで進めていく。終戦を起点にして)
定期テストには使えませんが、受験生にはかなり有効です。
-------------------------------------------------------------------------
もう一つ、戦略的な「拠点式」の使用法追加です。
理科で使う計算は数学でも使うので、両者で必要な部分を拠点として、理科、数学の勉強を進めていく。
社会の暗記で暗記力鍛えて、それを拠点として、英語などの暗記をやる。
(意図的に拠点となるように勉強を進めます)
普通の塾では出来ないかもしれませんが。
私はこれがしたかったので、自分で塾を始めました。
(私の塾に、教科の時間割は存在しません)
受験生には、「逆歴史」と「拠点式」の併用が良いです。
(「逆歴史」も自分で命名しましたが)
大抵の人は、受験勉強を古代から始めるけど、それってかなり非効率です。
日本史でも世界史でも、近代史の方が圧倒的によく出ますから。
終わりには必ず始まりがある。
何かが起きたら、必ず何か原因がある。
1945 第二次世界大戦終戦
1941 太平洋戦争開始(第二次世界大戦の太平洋アジア方面)
1939 第二次世界大戦開始
1929 世界大恐慌
と歴史をどんどん遡っていきながら、「拠点式」をする。
そうすると出題率の高い近代史が先に出来て、たまに戻って復習すれば効率よく点が取れる。
戦後は、複雑で覚え難いから、近代史して慣れた後が良い。
(私は戦後は、普通の流れで進めていく。終戦を起点にして)
定期テストには使えませんが、受験生にはかなり有効です。
-------------------------------------------------------------------------
もう一つ、戦略的な「拠点式」の使用法追加です。
理科で使う計算は数学でも使うので、両者で必要な部分を拠点として、理科、数学の勉強を進めていく。
社会の暗記で暗記力鍛えて、それを拠点として、英語などの暗記をやる。
(意図的に拠点となるように勉強を進めます)
普通の塾では出来ないかもしれませんが。
私はこれがしたかったので、自分で塾を始めました。
(私の塾に、教科の時間割は存在しません)
>毎年、毎月過去の教え方を整理整頓して、さらなる良いものを塗り上げようと日々頭を痛めているところです。
私は結構楽しいですけどね。
テスト範囲を頭に入れて動いたり、風呂入ったり、寝ていれば、急に思い付く事がよくあります。
スポーツや科学も進化していますから、そこからヒントを貰ったり、それと同じように考えれば結構いろいろアイデアが出てきます。
あと私の「拠点式」ですが、暗記用でもありますが、小テスト用に作っています。
何回も小テストするので、なるべく子どもが書き易いように、してます。
40の暗記部分だったら、2分くらいで書かせます。
事前に覚えるように言って、ちゃんとしてくれば、すぐ書けます。
私は結構楽しいですけどね。
テスト範囲を頭に入れて動いたり、風呂入ったり、寝ていれば、急に思い付く事がよくあります。
スポーツや科学も進化していますから、そこからヒントを貰ったり、それと同じように考えれば結構いろいろアイデアが出てきます。
あと私の「拠点式」ですが、暗記用でもありますが、小テスト用に作っています。
何回も小テストするので、なるべく子どもが書き易いように、してます。
40の暗記部分だったら、2分くらいで書かせます。
事前に覚えるように言って、ちゃんとしてくれば、すぐ書けます。
>>53 >>54
まぁ、社会科を書くべきでした。すみません(;´Д`)
元井先生ですか…高校の時、習って(潜って)いました。某元暴走族講師と比肩にならないくらい良い先生でした。塾だと経営サイドがOKしないことが多く「思いつくけど、いやどうだろう…」というネタですが、幸い私は許可を頂いてやり続けています。ヴァニラ先生の論理力トピでも書かせていただきましたが、そもそも最近の生徒は、語彙力・言語背景知識が皆無なので、ある程度それがある子でないと通用しない方法ではありますが…。結構、地力のある子には有効な方法であることが確認できています。
全教科共通で教師に有効な手段は「自分だけのマスコットキャラクターや愛称をつくる」というのもありふれていますが手ですね。拠点式も全部拝読させていただきました。素晴らしい方式だと思います。
まぁ、社会科を書くべきでした。すみません(;´Д`)
元井先生ですか…高校の時、習って(潜って)いました。某元暴走族講師と比肩にならないくらい良い先生でした。塾だと経営サイドがOKしないことが多く「思いつくけど、いやどうだろう…」というネタですが、幸い私は許可を頂いてやり続けています。ヴァニラ先生の論理力トピでも書かせていただきましたが、そもそも最近の生徒は、語彙力・言語背景知識が皆無なので、ある程度それがある子でないと通用しない方法ではありますが…。結構、地力のある子には有効な方法であることが確認できています。
全教科共通で教師に有効な手段は「自分だけのマスコットキャラクターや愛称をつくる」というのもありふれていますが手ですね。拠点式も全部拝読させていただきました。素晴らしい方式だと思います。
>heavenly blueさん
>ところで、農産物の国別割合の識別なんかはどんな法則性をつかっていますか。
う〜ん、実はこれ全然きちっと分析して、法則性を持って教えたことないんです。すみません。
ということで、ちょこっと調べてみました。しかし、どれも中国、アメリカ、インドがすごいことになっていて、なんか辟易しますね。
ちなみに
米と小麦は主食の違いを考えれば概ねOKかなと。
米は
1位 中国
2位 インド
3位 インドネシア
4位 バングラディシュ
5位 ベトナム
で、アジアです。(イメージ的に米=タイが強烈ですが、2006年の生産量は6位でした。)
対して小麦は、パンを食べるヨーロッパ圏が入ってくるんですね。
1位 中国
2位 インド
3位 アメリカ
4位 ロシア
5位 フランス(ちなみに6位カナダ、7位オーストラリア、8位ドイツです)
とうもろこしとか大豆は商品として売れるから、産業として力を入れている、という南米(ブラジル、アルゼンチンなど)がポイントっぽいですね。
とうもろこし
1位 アメリカ
2位 中国
3位 EU-25
4位 ブラジル
5位 メキシコ
大豆
1位 アメリカ
2位 ブラジル
3位 アルゼンチン
4位 中国
5位 インド
ちょっと調べたら↓これが面白かったです。
http://blog.livedoor.jp/ab55693323/archives/50914453.html
茶は、セイロンティーって言葉からもスリランカがポイントかなぁ。インドのチャイ、中国のウーロン茶はもちろんですけどね。
1位 インド
2位 中国
3位 スリランカ
4位 ケニア
5位 インドネシア
綿花はインドのデカン高原ってイメージでしたけどね・・・それでは見分けがつかない・・・
パキスタンが唯一他で出てこないですが、なぜパキスタンなのか・・・う〜ん、ごめんなさい。
良いアイデアが浮かびません・・・
1位 中国
2位 インド
3位 アメリカ
4位 パキスタン
5位 ブラジル
というかんじです。
まとまりなくてごめんなさい。
>ところで、農産物の国別割合の識別なんかはどんな法則性をつかっていますか。
う〜ん、実はこれ全然きちっと分析して、法則性を持って教えたことないんです。すみません。
ということで、ちょこっと調べてみました。しかし、どれも中国、アメリカ、インドがすごいことになっていて、なんか辟易しますね。
ちなみに
米と小麦は主食の違いを考えれば概ねOKかなと。
米は
1位 中国
2位 インド
3位 インドネシア
4位 バングラディシュ
5位 ベトナム
で、アジアです。(イメージ的に米=タイが強烈ですが、2006年の生産量は6位でした。)
対して小麦は、パンを食べるヨーロッパ圏が入ってくるんですね。
1位 中国
2位 インド
3位 アメリカ
4位 ロシア
5位 フランス(ちなみに6位カナダ、7位オーストラリア、8位ドイツです)
とうもろこしとか大豆は商品として売れるから、産業として力を入れている、という南米(ブラジル、アルゼンチンなど)がポイントっぽいですね。
とうもろこし
1位 アメリカ
2位 中国
3位 EU-25
4位 ブラジル
5位 メキシコ
大豆
1位 アメリカ
2位 ブラジル
3位 アルゼンチン
4位 中国
5位 インド
ちょっと調べたら↓これが面白かったです。
http://blog.livedoor.jp/ab55693323/archives/50914453.html
茶は、セイロンティーって言葉からもスリランカがポイントかなぁ。インドのチャイ、中国のウーロン茶はもちろんですけどね。
1位 インド
2位 中国
3位 スリランカ
4位 ケニア
5位 インドネシア
綿花はインドのデカン高原ってイメージでしたけどね・・・それでは見分けがつかない・・・
パキスタンが唯一他で出てこないですが、なぜパキスタンなのか・・・う〜ん、ごめんなさい。
良いアイデアが浮かびません・・・
1位 中国
2位 インド
3位 アメリカ
4位 パキスタン
5位 ブラジル
というかんじです。
まとまりなくてごめんなさい。
>heavenly blue さんへ
ありました。
これ↓ですね、きっと。
http://www.juno.dti.ne.jp/~tkitaba/agrifood/latenamerica/news/03122001.htm
基本的に、歴史的にも経済的にもブラジルやアルゼンチンは
「農業」=「儲ける手段」
ととらえている国なんだと思います。
植民地時代からの、プランテーションによるモノカルチャー経済が染み付いてしまったためなんでしょうね。
ということで、
「ブラジルが入っていれば大豆」の理由は
”熱帯林の伐採されたところにガンガン作られているから”
となるのではないでしょうか。
いかがでしょう?
ありました。
これ↓ですね、きっと。
http://www.juno.dti.ne.jp/~tkitaba/agrifood/latenamerica/news/03122001.htm
基本的に、歴史的にも経済的にもブラジルやアルゼンチンは
「農業」=「儲ける手段」
ととらえている国なんだと思います。
植民地時代からの、プランテーションによるモノカルチャー経済が染み付いてしまったためなんでしょうね。
ということで、
「ブラジルが入っていれば大豆」の理由は
”熱帯林の伐採されたところにガンガン作られているから”
となるのではないでしょうか。
いかがでしょう?
>heavenly blueさんへ
>ところで、私の言葉足らずで誤解させてしまってごめんなさい
>アメリカ、ブラジル、アルゼンチン、中国で大豆を生産している共通点を考え>たかったんです。
なるほど、大豆を生産している国の共通点ということですね。すみません。
>しかし、おかげで古くからの生産国として中国とアメリカがふくまれ、南米の>熱帯林地域にあたる国が生産上位国として入っていれば「大豆」だとちょっと>した法則性が見つかりそうです。
まさにそうですね。
中国の急成長に伴い、穀物需要がまた爆発的に増え、その奪い合いが加熱している昨今、アメリカの穀物メジャーが進出先に選んだのがアマゾンの熱帯林なんだそうです。
小麦・とうもろこし・大豆などは全て飼料作物としての需要がものすごく高いですから、とにかく「商品」として売れるんですよね。だから
たくさんつくりたい。
↓
たくさんつくるには広大な土地が必要。
↓
面積の大きい国が上位になる
それにプラスして、気候が適していること
という感じでしょうか。
ちょっとずれますがこちら↓も興味深い記事です。
http://www.juno.dti.ne.jp/~tkitaba/agrifood/foodsecurity/news/08050201.htm
>ところで、私の言葉足らずで誤解させてしまってごめんなさい
>アメリカ、ブラジル、アルゼンチン、中国で大豆を生産している共通点を考え>たかったんです。
なるほど、大豆を生産している国の共通点ということですね。すみません。
>しかし、おかげで古くからの生産国として中国とアメリカがふくまれ、南米の>熱帯林地域にあたる国が生産上位国として入っていれば「大豆」だとちょっと>した法則性が見つかりそうです。
まさにそうですね。
中国の急成長に伴い、穀物需要がまた爆発的に増え、その奪い合いが加熱している昨今、アメリカの穀物メジャーが進出先に選んだのがアマゾンの熱帯林なんだそうです。
小麦・とうもろこし・大豆などは全て飼料作物としての需要がものすごく高いですから、とにかく「商品」として売れるんですよね。だから
たくさんつくりたい。
↓
たくさんつくるには広大な土地が必要。
↓
面積の大きい国が上位になる
それにプラスして、気候が適していること
という感じでしょうか。
ちょっとずれますがこちら↓も興味深い記事です。
http://www.juno.dti.ne.jp/~tkitaba/agrifood/foodsecurity/news/08050201.htm
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
授業の工夫事典!!(塾講師・教師) 更新情報
授業の工夫事典!!(塾講師・教師)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37860人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90056人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208307人