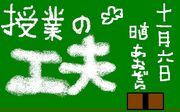ニュートン算の原典ならびに日本史上初のニュートン算を発見したので、ご報告します。
ニュートン算の問題が、ニュートンの『Arithmetica Universalis』(1707年)にあるのは知っていたが、出典を確認しようにもラテン語ということで、あきらめていた。
ところが、ニュートンのこのケンブリッジ大学での代数講義の講義録は英訳版(1728年)があるのを知った。で、グーグルのブック検索で、英訳版から、ニュートン算の箇所を見つけ、対応するラテン語原典の箇所も見つけられた。いや、グーグルってほんとすごいですね。
ラテン語原典:ページ89下のPROB ??の問題です。
http://
英訳版:ページ189のPROBLEM ??の問題です。
http://
これを見ると、今まで、ニュートン算の原典として知らされていたものとは表現がやや違っている。
さて、確かにニュートン算は、ニュートンが出題した問題であった。しかし、ニュートンの趣旨は、方程式を立てればどんな問題も解けることを主張したいために、こういう問題を出したようだ。英訳版の前半のそれらしき箇所を乏しい英語力でざっと目を通すとそんなことが書いてあるみたいだし、遠山啓氏も『数学入門・上』(岩波新書)でそう書いていた。(ただし、遠山が岩波新書の90ページに挙げている問題は、いわゆるニュートン算ではなく、英訳版178ページに挙げられている「例題」であった。)
ともあれ、ニュートンは、決して、ニュートン算などという特殊な解法の問題を考案して、極東の受験算数に資するつもりではなかった。
どうして、日本では、これが「ニュートン算」と命名され、受験算数の難問に祭りあげられたのだろうか。
今回、ニュートン原典の英訳版があることは、次の本を読んで知ったのだが、
小倉金之助『数学教育史』(1932年、『著作集6』1974年所収)
小倉は、この本で英訳版の1頁の写真を載せ(著作集では略)、こう解説しています。(96ページ)
「これは名高い『牧場の草を喰ふ牛の問題』である。実は斯様な謎のような問題は、この書の中に算術問題の所にわずか数題あるのみである。しかるにわが数学教育界にはニュートンのこの書を読みもせずに、この書の性質を誤り伝えている数学者がいるようであるから、ここに一言を加えておく。」
『牧場の草を喰ふ牛の問題』は、明治時代から受験問題集の中で「ニュートンの問題」とも呼ばれていました。
わが国の小学校算術の国定教科書の総元締めとして有名な東京帝国大学教授・貴族院議員・藤沢利喜太郎は『数学教授法講義筆記 明治32年夏期講習会』(1900年刊(明治33年))で、次の問題を紹介しています。
「牧場アリ十二頭ノ牛ハ一町歩ノ草ヲ四週間ニ食ヒ盡クシ、二十一頭ノ牛ハ三町歩ノ草ヲ九週間ニ食ヒ盡クスト云フ、三十六頭ノ牛ハ十八週間ニ幾町歩ノ草ヲ食ヒ盡クスベキカ、但草ハ一様ニ生長スルモノトス」
正に『牧場の草を喰ふ牛の問題』で、『数学三千題』という明治10年代に猖獗をきわめた問題集形式の教科書から採ってきたようです。
藤沢は、『三千題』のように、ただただ問題を数多くやりさえすればよいという勉強方法を批判します。特に、この問題を「最モタチ悪イ問題」と罵倒します。「謎ヲ解ク様」なもので、三十年も数学をやってきた自分でも解けないのだから子どもが解けないのは当然で、教育上弊害がある、と。(藤沢自身は、この問題に「種種ノ仮定ヲ加ヘテ」答を「七町二段」と出していますが。)
藤沢は、この問題の出典であるニュートンの『Universal Arithmetic』にも噛み付きます。(以下、カタカナはひらがなに、漢字も適宜直して、引用します。)
「この本は大分に古い本で、訳して『一般算術』と申しますが、ニウトンは決して教育のためにこの本を著したのではありませぬ。この時分には数学者間に問題の試合という妙なことが流行ったこと丁度封建時代に剣戟の試合が流行ったのと似ておりまして一般人民のやったことではありませぬ。唯数学者という変屈者が所々に散在して互いにやり合ったという随分面白い時代であります。」
しかし、藤沢がここで言っている「数学試合」が、有名なタルターリアとフェラーリとの三次方程式、四次方程式をめぐる1548年の試合などのことを念頭に置いていたのだとしたら、150年も時代がずれてしまい、失当である。藤沢先生、口頭の講義ということで、出典確認がおろそかなまま、口がすべってしまったか。
藤沢は、和算の遊戯的な算術(鶴亀算など)は、年数の限られた義務教育の国定教科書には載せないという見識を示した学者なのですが、この講義では、さらに次のように述べています。
「この『一般算術』という本も先ず遊戯算術と云うて善かろう。ニウトンは有名なる学者であったけれどもその時分には教育ということは余り発達しておりませんでしたから、ニウトンはこの本を教育上の助けとするために著したのではありませぬ。実にこの本は学術上より見ればとぼけた本であるにも拘わらず、これらの本より不都合なる問題を取ったというのはニウトンを崇拝するの余り、その人の寝言まで金科玉条視したからでありませう」
いやはや藤沢節の言いたい放題ですが、実証的にはやや疑問視せざるをえない与太も紛れていますなぁ。(藤沢のこの『数学教授法講義筆記』は、国会図書館の「近代デジタルライブラリー」のサイトで読めます。http://
ともあれ、ニュートン算の問題は、『数学三千題』(1880年(明治13年)刊)が初出のようです。
しかし、私が、『日本教科書大系 近代編 第11巻』(1962年、講談社)で調べたところでは、確かにニュートン算の問題は、『数学三千題』にあり、この本以前には見つけられないのですが、その問題は『牧場の草を喰ふ牛の問題』ではなく、次のような問題です。(なお、『数学三千題』も「近代デジタルライブラリー」のサイトで読むことができます。下巻の124ページ、319番です。)
「水桶あり。その溜水若干あり。また毎時若干の水流入すべし。然るに十二個の水抜を開けば七時三十分間に水尽べく、また七個の水抜を開けば十六時間にして水尽べしと云う。問幾個の水抜を開けば五十時間に尽くべきや」
この問題を本邦の嚆矢として、同類タイプの問題が受験算術界で「ニュートン算」と名づけられていくわけです。そして、藤沢利喜太郎、小倉金之助、遠山啓と明治から昭和にかけての、日本の数学算数教育界において、立場も見解も違い、特に遠山は藤沢を大批判するのですが、お歴々が、ことニュートン算を子どもに教えることに対しては、一致して反対だというのは、なるほどなぁと思います。
しかし、私自身、塾講師だったときは、ニュートン算を面積図で解説することは、年に一、二回ではあったが、なんか腕の見せ所というか、晴れ舞台という感じもあったのですが、しかし、講師がいい気になっていても、子どもにとってはどうだったのかと反省はします。
ニュートン算の問題が、ニュートンの『Arithmetica Universalis』(1707年)にあるのは知っていたが、出典を確認しようにもラテン語ということで、あきらめていた。
ところが、ニュートンのこのケンブリッジ大学での代数講義の講義録は英訳版(1728年)があるのを知った。で、グーグルのブック検索で、英訳版から、ニュートン算の箇所を見つけ、対応するラテン語原典の箇所も見つけられた。いや、グーグルってほんとすごいですね。
ラテン語原典:ページ89下のPROB ??の問題です。
http://
英訳版:ページ189のPROBLEM ??の問題です。
http://
これを見ると、今まで、ニュートン算の原典として知らされていたものとは表現がやや違っている。
さて、確かにニュートン算は、ニュートンが出題した問題であった。しかし、ニュートンの趣旨は、方程式を立てればどんな問題も解けることを主張したいために、こういう問題を出したようだ。英訳版の前半のそれらしき箇所を乏しい英語力でざっと目を通すとそんなことが書いてあるみたいだし、遠山啓氏も『数学入門・上』(岩波新書)でそう書いていた。(ただし、遠山が岩波新書の90ページに挙げている問題は、いわゆるニュートン算ではなく、英訳版178ページに挙げられている「例題」であった。)
ともあれ、ニュートンは、決して、ニュートン算などという特殊な解法の問題を考案して、極東の受験算数に資するつもりではなかった。
どうして、日本では、これが「ニュートン算」と命名され、受験算数の難問に祭りあげられたのだろうか。
今回、ニュートン原典の英訳版があることは、次の本を読んで知ったのだが、
小倉金之助『数学教育史』(1932年、『著作集6』1974年所収)
小倉は、この本で英訳版の1頁の写真を載せ(著作集では略)、こう解説しています。(96ページ)
「これは名高い『牧場の草を喰ふ牛の問題』である。実は斯様な謎のような問題は、この書の中に算術問題の所にわずか数題あるのみである。しかるにわが数学教育界にはニュートンのこの書を読みもせずに、この書の性質を誤り伝えている数学者がいるようであるから、ここに一言を加えておく。」
『牧場の草を喰ふ牛の問題』は、明治時代から受験問題集の中で「ニュートンの問題」とも呼ばれていました。
わが国の小学校算術の国定教科書の総元締めとして有名な東京帝国大学教授・貴族院議員・藤沢利喜太郎は『数学教授法講義筆記 明治32年夏期講習会』(1900年刊(明治33年))で、次の問題を紹介しています。
「牧場アリ十二頭ノ牛ハ一町歩ノ草ヲ四週間ニ食ヒ盡クシ、二十一頭ノ牛ハ三町歩ノ草ヲ九週間ニ食ヒ盡クスト云フ、三十六頭ノ牛ハ十八週間ニ幾町歩ノ草ヲ食ヒ盡クスベキカ、但草ハ一様ニ生長スルモノトス」
正に『牧場の草を喰ふ牛の問題』で、『数学三千題』という明治10年代に猖獗をきわめた問題集形式の教科書から採ってきたようです。
藤沢は、『三千題』のように、ただただ問題を数多くやりさえすればよいという勉強方法を批判します。特に、この問題を「最モタチ悪イ問題」と罵倒します。「謎ヲ解ク様」なもので、三十年も数学をやってきた自分でも解けないのだから子どもが解けないのは当然で、教育上弊害がある、と。(藤沢自身は、この問題に「種種ノ仮定ヲ加ヘテ」答を「七町二段」と出していますが。)
藤沢は、この問題の出典であるニュートンの『Universal Arithmetic』にも噛み付きます。(以下、カタカナはひらがなに、漢字も適宜直して、引用します。)
「この本は大分に古い本で、訳して『一般算術』と申しますが、ニウトンは決して教育のためにこの本を著したのではありませぬ。この時分には数学者間に問題の試合という妙なことが流行ったこと丁度封建時代に剣戟の試合が流行ったのと似ておりまして一般人民のやったことではありませぬ。唯数学者という変屈者が所々に散在して互いにやり合ったという随分面白い時代であります。」
しかし、藤沢がここで言っている「数学試合」が、有名なタルターリアとフェラーリとの三次方程式、四次方程式をめぐる1548年の試合などのことを念頭に置いていたのだとしたら、150年も時代がずれてしまい、失当である。藤沢先生、口頭の講義ということで、出典確認がおろそかなまま、口がすべってしまったか。
藤沢は、和算の遊戯的な算術(鶴亀算など)は、年数の限られた義務教育の国定教科書には載せないという見識を示した学者なのですが、この講義では、さらに次のように述べています。
「この『一般算術』という本も先ず遊戯算術と云うて善かろう。ニウトンは有名なる学者であったけれどもその時分には教育ということは余り発達しておりませんでしたから、ニウトンはこの本を教育上の助けとするために著したのではありませぬ。実にこの本は学術上より見ればとぼけた本であるにも拘わらず、これらの本より不都合なる問題を取ったというのはニウトンを崇拝するの余り、その人の寝言まで金科玉条視したからでありませう」
いやはや藤沢節の言いたい放題ですが、実証的にはやや疑問視せざるをえない与太も紛れていますなぁ。(藤沢のこの『数学教授法講義筆記』は、国会図書館の「近代デジタルライブラリー」のサイトで読めます。http://
ともあれ、ニュートン算の問題は、『数学三千題』(1880年(明治13年)刊)が初出のようです。
しかし、私が、『日本教科書大系 近代編 第11巻』(1962年、講談社)で調べたところでは、確かにニュートン算の問題は、『数学三千題』にあり、この本以前には見つけられないのですが、その問題は『牧場の草を喰ふ牛の問題』ではなく、次のような問題です。(なお、『数学三千題』も「近代デジタルライブラリー」のサイトで読むことができます。下巻の124ページ、319番です。)
「水桶あり。その溜水若干あり。また毎時若干の水流入すべし。然るに十二個の水抜を開けば七時三十分間に水尽べく、また七個の水抜を開けば十六時間にして水尽べしと云う。問幾個の水抜を開けば五十時間に尽くべきや」
この問題を本邦の嚆矢として、同類タイプの問題が受験算術界で「ニュートン算」と名づけられていくわけです。そして、藤沢利喜太郎、小倉金之助、遠山啓と明治から昭和にかけての、日本の数学算数教育界において、立場も見解も違い、特に遠山は藤沢を大批判するのですが、お歴々が、ことニュートン算を子どもに教えることに対しては、一致して反対だというのは、なるほどなぁと思います。
しかし、私自身、塾講師だったときは、ニュートン算を面積図で解説することは、年に一、二回ではあったが、なんか腕の見せ所というか、晴れ舞台という感じもあったのですが、しかし、講師がいい気になっていても、子どもにとってはどうだったのかと反省はします。
|
|
|
|
コメント(4)
>1
小倉金之助が、「しかるにわが数学教育界にはニュートンのこの書を読みもせずに、この書の性質を誤り伝えている数学者がいるようであるから、ここに一言を加えておく。」
と批判している「数学者」とは、どうも藤沢利喜太郎のことのようだな。
数学史家の小倉としては、数学史の基本的史実をおさえていない、藤沢の明治32年の講義は噴飯ものだったのだろう。私から見ても与太がひどいと思うのだから。
それに、小倉のこの本が出た昭和7年というと、藤沢が亡くなる1年前だが、藤沢主導だった第1期から第3期までの国定教科書(いわゆる「黒表紙」)を改訂する作業が始まっていて、昭和10年に第4期のいわゆる「緑表紙」がうまれるのだが、その中心だった塩野直道は小倉の影響を受けていたということだ。塩野は、藤沢が黒表紙に載せることを排した「鶴亀算」を、緑表紙には、確信犯的に載せる。
「ニュートン算」の評価をめぐる裏にこういう人間模様があったらしいということは、算数の問題とはいえ、人の世の倣いだから、納得もいく。
しかし、小倉も藤沢も、「ニュートン算」を「謎のような問題」とマイナス評価する点では一致していたのだろう。
小倉金之助が、「しかるにわが数学教育界にはニュートンのこの書を読みもせずに、この書の性質を誤り伝えている数学者がいるようであるから、ここに一言を加えておく。」
と批判している「数学者」とは、どうも藤沢利喜太郎のことのようだな。
数学史家の小倉としては、数学史の基本的史実をおさえていない、藤沢の明治32年の講義は噴飯ものだったのだろう。私から見ても与太がひどいと思うのだから。
それに、小倉のこの本が出た昭和7年というと、藤沢が亡くなる1年前だが、藤沢主導だった第1期から第3期までの国定教科書(いわゆる「黒表紙」)を改訂する作業が始まっていて、昭和10年に第4期のいわゆる「緑表紙」がうまれるのだが、その中心だった塩野直道は小倉の影響を受けていたということだ。塩野は、藤沢が黒表紙に載せることを排した「鶴亀算」を、緑表紙には、確信犯的に載せる。
「ニュートン算」の評価をめぐる裏にこういう人間模様があったらしいということは、算数の問題とはいえ、人の世の倣いだから、納得もいく。
しかし、小倉も藤沢も、「ニュートン算」を「謎のような問題」とマイナス評価する点では一致していたのだろう。
(書きたいことを書いていたら長くなってしまったので長いの嫌な方は読み飛ばしてください)
江戸時代の数量感であるとか鶴亀算の由来、植木算は近代に入ってから作られたものだとかニュートン算の由来であるとかそういった歴史的な視点から深く掘り下げた考察はさすが数学史家のメタメタさんです。
これだけネタがあるなら書籍にまとめて出版したらどうですか?
ニュートン算に対する評価は私とメタメタさんでは意見を異にしますが、それはそれでメタメタさんの見解ですからまとめて出版されても面白いと思います。
ただ、売れるかどうかという視点から言えば単なる数学史を調べて新たな史実を発見しました程度だと一般の人の食いつきは少ないでしょうね。数学史に興味のある方なら大変興味深いものだと思いますし、数学をある程度極めている人からしても教養として知っておきたいという需要はあると思います。しかし一般の人に売るとなるとやはり受験算数とリンクして中学受験生やその親御さんが買ってためになったといった満足感を与えるものでないと売れないでしょうね。
ここでのトピに対する食いつきからしてもあまりないようですから食いつきにくい題材なのかもしれません。
以前、メタメタさんがニュートン算は中学入試としては出題する意義を感じないという趣旨の発言がありましたが、そういう話材なら意見が分かれるんで受験算数を教えておられる先生の食いつきも良いかもしれません。
# 私はメタメタさんとは反対に、入試に出題されても特に問題はなく水量変化の問題などと同様標準的な問題なので、そんなに言うほど意義のないことではないという意見を言いましたし、メタメタさんがニュートン算は最近あまり出題されていないという事実誤認についても具体的に出題校も含めて指摘しました。
仮にニュートン算の問題が出題されることに意義を感じないのなら恐らくその他の特殊算にしても同様な根拠から意義のないものになってしまうはずです。結局、中学に入ってから方程式ですべて解けるんだから特殊算なんて苦労してやる必要はないと。
私も本音としてはそう思いますが、しかしそれをやめちゃったら入試で差をつけるところがなくなってしまって、しかも受験生が勉強を真剣にすることもなくなってしまうと思うんで、様々な特殊算を受験に出題したって別に構わないと思ってます。
鶴亀算に代表されるようないわゆる特殊算というのはある種日本における受験文化みたいなものだと思ってます。なくても中学に入ってから困らないけど、ないと入試で適切な選別を行えないという、単にそれだけのものじゃないでしょうか?
もちろん、昨今では特殊算そのものの基本問題だけを出題することは上位校ではなくなってますけどそれでもそれらの考え方を知らなきゃ解けない問題は多数出題されていますから、やったってしょうがないなんてことは全くないことは指摘しておきます。
江戸時代やそれ以上前にまで遡る数学史に関しては教養程度の知識があれば十分と考えているのであまり関心はありませんが、戦後の中学受験における受験算数の歴史みたいなものがあったら面白いとは思います。
私が小さいころに出題されていた算数の入試問題やそのときの流行、現在に至るまでの変遷なんかがわかると面白いですね。ある種の問題はどっかの中学校が初めに出題して、それから他校に飛び火したとかって結構あることです。この類の問題は一番初めに出題されたのはどこの中学校なのかとかそういったことを詳しく調べたものがあったら絶対買いますよ。
私は全国の中学校の入試問題集(みくに出版)は1999年からしかないんでそれより前のは学校別の過去問集にあるいくつかのものぐらいで網羅的に調べることができないんで精々10年程度の変遷しか調べられません。出来れば今ある形の問題の由来がわかる程度までの中学入試問題があれば自分でもライフワークとして調べてみようって気にはなりますけどそこまでの資料って入手できるのかなぁ・・・
江戸時代の数量感であるとか鶴亀算の由来、植木算は近代に入ってから作られたものだとかニュートン算の由来であるとかそういった歴史的な視点から深く掘り下げた考察はさすが数学史家のメタメタさんです。
これだけネタがあるなら書籍にまとめて出版したらどうですか?
ニュートン算に対する評価は私とメタメタさんでは意見を異にしますが、それはそれでメタメタさんの見解ですからまとめて出版されても面白いと思います。
ただ、売れるかどうかという視点から言えば単なる数学史を調べて新たな史実を発見しました程度だと一般の人の食いつきは少ないでしょうね。数学史に興味のある方なら大変興味深いものだと思いますし、数学をある程度極めている人からしても教養として知っておきたいという需要はあると思います。しかし一般の人に売るとなるとやはり受験算数とリンクして中学受験生やその親御さんが買ってためになったといった満足感を与えるものでないと売れないでしょうね。
ここでのトピに対する食いつきからしてもあまりないようですから食いつきにくい題材なのかもしれません。
以前、メタメタさんがニュートン算は中学入試としては出題する意義を感じないという趣旨の発言がありましたが、そういう話材なら意見が分かれるんで受験算数を教えておられる先生の食いつきも良いかもしれません。
# 私はメタメタさんとは反対に、入試に出題されても特に問題はなく水量変化の問題などと同様標準的な問題なので、そんなに言うほど意義のないことではないという意見を言いましたし、メタメタさんがニュートン算は最近あまり出題されていないという事実誤認についても具体的に出題校も含めて指摘しました。
仮にニュートン算の問題が出題されることに意義を感じないのなら恐らくその他の特殊算にしても同様な根拠から意義のないものになってしまうはずです。結局、中学に入ってから方程式ですべて解けるんだから特殊算なんて苦労してやる必要はないと。
私も本音としてはそう思いますが、しかしそれをやめちゃったら入試で差をつけるところがなくなってしまって、しかも受験生が勉強を真剣にすることもなくなってしまうと思うんで、様々な特殊算を受験に出題したって別に構わないと思ってます。
鶴亀算に代表されるようないわゆる特殊算というのはある種日本における受験文化みたいなものだと思ってます。なくても中学に入ってから困らないけど、ないと入試で適切な選別を行えないという、単にそれだけのものじゃないでしょうか?
もちろん、昨今では特殊算そのものの基本問題だけを出題することは上位校ではなくなってますけどそれでもそれらの考え方を知らなきゃ解けない問題は多数出題されていますから、やったってしょうがないなんてことは全くないことは指摘しておきます。
江戸時代やそれ以上前にまで遡る数学史に関しては教養程度の知識があれば十分と考えているのであまり関心はありませんが、戦後の中学受験における受験算数の歴史みたいなものがあったら面白いとは思います。
私が小さいころに出題されていた算数の入試問題やそのときの流行、現在に至るまでの変遷なんかがわかると面白いですね。ある種の問題はどっかの中学校が初めに出題して、それから他校に飛び火したとかって結構あることです。この類の問題は一番初めに出題されたのはどこの中学校なのかとかそういったことを詳しく調べたものがあったら絶対買いますよ。
私は全国の中学校の入試問題集(みくに出版)は1999年からしかないんでそれより前のは学校別の過去問集にあるいくつかのものぐらいで網羅的に調べることができないんで精々10年程度の変遷しか調べられません。出来れば今ある形の問題の由来がわかる程度までの中学入試問題があれば自分でもライフワークとして調べてみようって気にはなりますけどそこまでの資料って入手できるのかなぁ・・・
>3 Kabu Taro さん。
>これだけネタがあるなら書籍にまとめて出版したらどうですか?
実は、そうしたいと思っているのです。
>ただ、売れるかどうかという視点から言えば単なる数学史を調べて新たな史実を発見しました程度だと一般の人の食いつきは少ないでしょうね。
そこなんです、問題は。
>鶴亀算に代表されるようないわゆる特殊算というのはある種日本における受験文化みたいなものだと思ってます。
「受験文化」というキャッチは秀逸ですね。
私も、最近、そう思うようにもなっています。
和算がある種特殊な日本文化であったように、特殊算もある種特殊な受験文化であろうと。
>もちろん、昨今では特殊算そのものの基本問題だけを出題することは上位校ではなくなってますけど
ああ、このことを以前確認したかったのです。
>戦後の中学受験における受験算数の歴史みたいなものがあったら面白いとは思います。
>出来れば今ある形の問題の由来がわかる程度までの中学入試問題があれば自分でもライフワークとして調べてみようって気にはなりますけどそこまでの資料って入手できるのかなぁ・・・
私は、受験算数の現場からはすでに10年以上遠ざかっているので、Kabu Taro さんとは、ちょうど入れ替わりにみたいになるのでしょうか。
数年前、戦後の算数教科書を調べる機会があって、その後、初期の和算(関孝和以降の本格的なものではなく)を調べる機会があり、今回、明治から戦前の算術の教科書をあさっているのです。これで、日本での算術400年の歴史が展望できるようになりつつあります。
ただ、戦前・戦後の受験算数となると、確かに資料が入りにくい。
公的な機関では、国会図書館の「近代デジタルライブラリー」で、著作権が切れた明治時代のものからデジタル化されていて、その中にいくつか受験算術問題集がありました。
しかし、戦後の受験問題集となると、国会図書館(国際子ども図書館も含めて)、都立図書館、教育図書館(教育政策研究所)、教科書図書館、東書文庫などを実際に訪問したのですが、ほとんど無きに等しかったですね。国際子ども図書館に旺文社の過去問集とかありました。でも、力を入れて探索はしていないので、もしかすると、各出版社がちゃんと献本しているのなら、国会図書館にあるはずですが・・・
各出版社か老舗の大手塾などに戦後の受験問題集が保存されていたら、そこで、各年の「新傾向問題」を探していくと、その後流行した問題の初出が見つかるのではないでしょうか。
最近の問題で面白いなと思ったのは(といっても、たまたま知ったのですが)、時計の文字盤に数字が記入されていなくて、針の角度から(長針が数字に当たるところを指しているが、その数字はわからない)、それが何時かを答える問題です。少なくとも、10年前にはこの問題を見た記憶がありません。(しかし、私の記憶もあてにはなりませんが)
もし、この数年で創られた問題なら、創った人は著作権を主張したいところでしょうが、その事実としての創作性(初出だということ)を実証できるかどうかと、内容における創造性の主張が認められるかどうかでしょうね。でも、算数・数学数の問題は、コピーライトフリーであってほしいし、実際そういう取り扱いになっていると思いますが。
>これだけネタがあるなら書籍にまとめて出版したらどうですか?
実は、そうしたいと思っているのです。
>ただ、売れるかどうかという視点から言えば単なる数学史を調べて新たな史実を発見しました程度だと一般の人の食いつきは少ないでしょうね。
そこなんです、問題は。
>鶴亀算に代表されるようないわゆる特殊算というのはある種日本における受験文化みたいなものだと思ってます。
「受験文化」というキャッチは秀逸ですね。
私も、最近、そう思うようにもなっています。
和算がある種特殊な日本文化であったように、特殊算もある種特殊な受験文化であろうと。
>もちろん、昨今では特殊算そのものの基本問題だけを出題することは上位校ではなくなってますけど
ああ、このことを以前確認したかったのです。
>戦後の中学受験における受験算数の歴史みたいなものがあったら面白いとは思います。
>出来れば今ある形の問題の由来がわかる程度までの中学入試問題があれば自分でもライフワークとして調べてみようって気にはなりますけどそこまでの資料って入手できるのかなぁ・・・
私は、受験算数の現場からはすでに10年以上遠ざかっているので、Kabu Taro さんとは、ちょうど入れ替わりにみたいになるのでしょうか。
数年前、戦後の算数教科書を調べる機会があって、その後、初期の和算(関孝和以降の本格的なものではなく)を調べる機会があり、今回、明治から戦前の算術の教科書をあさっているのです。これで、日本での算術400年の歴史が展望できるようになりつつあります。
ただ、戦前・戦後の受験算数となると、確かに資料が入りにくい。
公的な機関では、国会図書館の「近代デジタルライブラリー」で、著作権が切れた明治時代のものからデジタル化されていて、その中にいくつか受験算術問題集がありました。
しかし、戦後の受験問題集となると、国会図書館(国際子ども図書館も含めて)、都立図書館、教育図書館(教育政策研究所)、教科書図書館、東書文庫などを実際に訪問したのですが、ほとんど無きに等しかったですね。国際子ども図書館に旺文社の過去問集とかありました。でも、力を入れて探索はしていないので、もしかすると、各出版社がちゃんと献本しているのなら、国会図書館にあるはずですが・・・
各出版社か老舗の大手塾などに戦後の受験問題集が保存されていたら、そこで、各年の「新傾向問題」を探していくと、その後流行した問題の初出が見つかるのではないでしょうか。
最近の問題で面白いなと思ったのは(といっても、たまたま知ったのですが)、時計の文字盤に数字が記入されていなくて、針の角度から(長針が数字に当たるところを指しているが、その数字はわからない)、それが何時かを答える問題です。少なくとも、10年前にはこの問題を見た記憶がありません。(しかし、私の記憶もあてにはなりませんが)
もし、この数年で創られた問題なら、創った人は著作権を主張したいところでしょうが、その事実としての創作性(初出だということ)を実証できるかどうかと、内容における創造性の主張が認められるかどうかでしょうね。でも、算数・数学数の問題は、コピーライトフリーであってほしいし、実際そういう取り扱いになっていると思いますが。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
授業の工夫事典!!(塾講師・教師) 更新情報
授業の工夫事典!!(塾講師・教師)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90011人
- 2位
- 酒好き
- 170662人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人