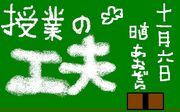はじめまして、初めてトピックを立てる、こーすけと言います。
今までずっと疑問、いや、不満に思うことを書きますので、皆さん(特に現役の公立の先生)のご意見を伺いたいです。
テスト問題を作るとき、宿題(夏休みの宿題)を出すとき、何の力を生徒に身につけさせたいのか、考えていますか?
例を挙げると、
・事前の作文の書き方指導、事後の作文の添削(評価は別)の無い、読書感想文や人権作文などの宿題。
・夏休みの復習ワークのないままに、実力テストで広い復習範囲(今まで習ったところ、など)を、中1中2に出す。
・成績の悪かった生徒を補習に呼んでおきながら、休み明けのテストで、一切補習内容を出さない。
などです。
ちなみに、理科や社会の自由研究も、教育的意義があるかは何とも言えませんが。
この問題が生徒の学習意欲の低下につながっている気がしてなりません。
「どうせやってもダメやし」この原因は、生徒の問題だけではないと感じます。
誤解の無いように、
私も以前、私立高校ですが、試験を作成した経験はあります。
その時には、「このテストの平均点が○点になるようにしよう」と決めていました。
その上で基礎問題と応用問題を配分しました。
今回だけでも勉強をした子はちゃんと取れる問題を作り、
できてない子は勉強のやり方に問題があると自覚させるようにしました。
しかし、家庭教師・塾講師をしている中で、特に勉強が苦手な生徒を指導していると、
彼の勉強不足よりも、学校の先生が出す問題(宿題)のレベルや内容が、
何を意味しているのか、何の評価をしたいのかわからない問題が増えていると感じます。
ただ難しいだけ、たださせるだけ、という悪質なテストや課題が蔓延り過ぎです。
夏休みを終えた今、皆さんはこの問題について、どう思いますか?
今までずっと疑問、いや、不満に思うことを書きますので、皆さん(特に現役の公立の先生)のご意見を伺いたいです。
テスト問題を作るとき、宿題(夏休みの宿題)を出すとき、何の力を生徒に身につけさせたいのか、考えていますか?
例を挙げると、
・事前の作文の書き方指導、事後の作文の添削(評価は別)の無い、読書感想文や人権作文などの宿題。
・夏休みの復習ワークのないままに、実力テストで広い復習範囲(今まで習ったところ、など)を、中1中2に出す。
・成績の悪かった生徒を補習に呼んでおきながら、休み明けのテストで、一切補習内容を出さない。
などです。
ちなみに、理科や社会の自由研究も、教育的意義があるかは何とも言えませんが。
この問題が生徒の学習意欲の低下につながっている気がしてなりません。
「どうせやってもダメやし」この原因は、生徒の問題だけではないと感じます。
誤解の無いように、
私も以前、私立高校ですが、試験を作成した経験はあります。
その時には、「このテストの平均点が○点になるようにしよう」と決めていました。
その上で基礎問題と応用問題を配分しました。
今回だけでも勉強をした子はちゃんと取れる問題を作り、
できてない子は勉強のやり方に問題があると自覚させるようにしました。
しかし、家庭教師・塾講師をしている中で、特に勉強が苦手な生徒を指導していると、
彼の勉強不足よりも、学校の先生が出す問題(宿題)のレベルや内容が、
何を意味しているのか、何の評価をしたいのかわからない問題が増えていると感じます。
ただ難しいだけ、たださせるだけ、という悪質なテストや課題が蔓延り過ぎです。
夏休みを終えた今、皆さんはこの問題について、どう思いますか?
|
|
|
|
コメント(106)
レスが遅くなりました。トピ主です。
>ひろくんさん
ひろくんさんも、試行錯誤されていらっしゃるんですね。
私も成績を付ける立場になって、悩み苦しみましたが、今ではいい経験させていただいたと思います。
>とみとみさん
ご意見ありがとうございます。
学校がダメになっている「おかげで」塾業界が繁盛している、というご意見ですが、
それは一面的な見方だと思います。
確かに学校より塾を信頼されている保護者・生徒は多いのは事実です。我々講師の努力もあります。
しかし、その信頼を逆手に取り(弱みに付け込み)、成績の悪い生徒を、お人よしの講師にたくさん押し付け、
保護者からは高額な授業料やら教材やら「諸経費」やらをむしり取り、
担当講師には1000円切る時給しか与えないような詐欺的な悪徳塾(特に個別指導)が蔓延っています。
また、生徒に「友達紹介キャンペーン」などで、マルチ紛いの勧誘活動をさせ、報酬を与えている、思想が偏った塾もたくさん見てきました。
仮定論は好きではないですが、
もし学校に教育力があれば(信頼があれば)、
特別な教育実践を行う私立学校を選ぶニーズに応えるような進学塾、ユニークな指導で安心感のある補習塾など、
少なくとも悪徳な詐欺まがいのニセモノ塾は駆逐されるはずかと。仮定論ですが。
それと、とみとみさんが絶賛される「福岡県の学校事情」を教えていただけますか?
もしかすると、福岡発信の教育再生が日本の教育を変えるかも知れませんから。ぜひともお願いします。
>おかじゅんさん
公立高校(進学校)は特別大変なんですね。追い詰められていますね。
自分は公立進学校出身でしたが、受験までに終わらない社会科以外の補習は無かったし、
授業内でもレベルアップできる工夫を凝らした先生方ばかりで、恵まれていたんだと思いました。
>ひろくんさん
ひろくんさんも、試行錯誤されていらっしゃるんですね。
私も成績を付ける立場になって、悩み苦しみましたが、今ではいい経験させていただいたと思います。
>とみとみさん
ご意見ありがとうございます。
学校がダメになっている「おかげで」塾業界が繁盛している、というご意見ですが、
それは一面的な見方だと思います。
確かに学校より塾を信頼されている保護者・生徒は多いのは事実です。我々講師の努力もあります。
しかし、その信頼を逆手に取り(弱みに付け込み)、成績の悪い生徒を、お人よしの講師にたくさん押し付け、
保護者からは高額な授業料やら教材やら「諸経費」やらをむしり取り、
担当講師には1000円切る時給しか与えないような詐欺的な悪徳塾(特に個別指導)が蔓延っています。
また、生徒に「友達紹介キャンペーン」などで、マルチ紛いの勧誘活動をさせ、報酬を与えている、思想が偏った塾もたくさん見てきました。
仮定論は好きではないですが、
もし学校に教育力があれば(信頼があれば)、
特別な教育実践を行う私立学校を選ぶニーズに応えるような進学塾、ユニークな指導で安心感のある補習塾など、
少なくとも悪徳な詐欺まがいのニセモノ塾は駆逐されるはずかと。仮定論ですが。
それと、とみとみさんが絶賛される「福岡県の学校事情」を教えていただけますか?
もしかすると、福岡発信の教育再生が日本の教育を変えるかも知れませんから。ぜひともお願いします。
>おかじゅんさん
公立高校(進学校)は特別大変なんですね。追い詰められていますね。
自分は公立進学校出身でしたが、受験までに終わらない社会科以外の補習は無かったし、
授業内でもレベルアップできる工夫を凝らした先生方ばかりで、恵まれていたんだと思いました。
自分も、学力・知識が仕事をしていく上で役に立つ以上、学力で順位をつけることには肯定的です。
カワイさんのおっしゃっている通り、100点の人と70点の人では採用に差がある以上、自分の実力は十分に知っておくためにも必要なことかなと思います。
中学校の定期テストで順位をつけるかどうかの結論は出ていませんが、こと受験においては定員制である以上、順位というのも気にしなくてはいけませんよね。
50人の定員で、たとえ95点取ったとしても、100点が50人いたら不合格ですよね。
いまのは極端な例ですが、そういった明確な基準があることが平等なのだと思うんです。
そういった意味で、学歴も評価の対象に入れることには賛成です。
受験勉強をしていく上で養われた忍耐力と、本番で力を発揮し結果を出せたということ。
この二つに関しては、その後どんな仕事についても必ず必要になってくることであり、いわゆる上位の高校・大学であるほど、その二つが高くなければ困難になってくるわけですから。
生徒にはいつも言ってます。
「たとえ本番で失敗したとしても、受験勉強をがんばって経験は将来確実に役に立つ」
そういった学歴を重ねていく上での背景は、ぜひ見て欲しいと思うところですね。
カワイさんのおっしゃっている通り、100点の人と70点の人では採用に差がある以上、自分の実力は十分に知っておくためにも必要なことかなと思います。
中学校の定期テストで順位をつけるかどうかの結論は出ていませんが、こと受験においては定員制である以上、順位というのも気にしなくてはいけませんよね。
50人の定員で、たとえ95点取ったとしても、100点が50人いたら不合格ですよね。
いまのは極端な例ですが、そういった明確な基準があることが平等なのだと思うんです。
そういった意味で、学歴も評価の対象に入れることには賛成です。
受験勉強をしていく上で養われた忍耐力と、本番で力を発揮し結果を出せたということ。
この二つに関しては、その後どんな仕事についても必ず必要になってくることであり、いわゆる上位の高校・大学であるほど、その二つが高くなければ困難になってくるわけですから。
生徒にはいつも言ってます。
「たとえ本番で失敗したとしても、受験勉強をがんばって経験は将来確実に役に立つ」
そういった学歴を重ねていく上での背景は、ぜひ見て欲しいと思うところですね。
ですが、そうは言っても、「どこの大学で学んできた」というのは、評価をしていく上ではたしてどれほど信頼性を持てるかは正直疑問です。
自分自身がすごく思うことは、大学4年間で学んできたことが、はたして自分の行っていた大学だからこそやれたことなのかと思います。
そして、自分の行っていた大学ならではのことを吸収しきれてもいないと思うからです。
自分が見てきたなかでも思うのですが、正直大学レベルになってくると、卒業した一人一人によって得てきたものがまるで違ってきますよね。
それなのに、「○○大卒」と一区切りにしてしまうのは、あまりにも浅はかだと思うのです。
72で述べた理由から、学歴も十分な評価の対象になると思うんですね。
ですが、それに頼り切った結果が、いまの社会の流れとなっている学歴「だけ」で判断するのはやめようという形なのだと思っています。
自分自身がすごく思うことは、大学4年間で学んできたことが、はたして自分の行っていた大学だからこそやれたことなのかと思います。
そして、自分の行っていた大学ならではのことを吸収しきれてもいないと思うからです。
自分が見てきたなかでも思うのですが、正直大学レベルになってくると、卒業した一人一人によって得てきたものがまるで違ってきますよね。
それなのに、「○○大卒」と一区切りにしてしまうのは、あまりにも浅はかだと思うのです。
72で述べた理由から、学歴も十分な評価の対象になると思うんですね。
ですが、それに頼り切った結果が、いまの社会の流れとなっている学歴「だけ」で判断するのはやめようという形なのだと思っています。
トピックの趣旨からは少しずれてきた気がしますが、そういった「知識は必ず役に立つ」という思いから、生徒には大学まで行って学んで欲しいと思っています。
うちの大学ならではのことは吸収できていなくても、大学で学んできたことはプライベートも含め、自分のなかで大きいからです。
自分は中学生を基本で教えています。
本当にやりたいことがあるならば、大学行く必要はないですが、将来の道が広がるという意味で、大学に行ける学力を付けておくことにまったく損はないと思うんですね。
大学が無関係な仕事についたとしても、身に付けた学力は必ず役に立つと思ってますし。
入る高校は正直どこであってもいいと思うんです。
ただ、行きたいと思う高校に対して努力をしていき、身についた力を本番でしっかっり発揮できるように。
そういった生徒の力を伸ばすための授業をしていけるように、生徒の力が伸びるようなテストや課題を出していきたいですね。
うちの大学ならではのことは吸収できていなくても、大学で学んできたことはプライベートも含め、自分のなかで大きいからです。
自分は中学生を基本で教えています。
本当にやりたいことがあるならば、大学行く必要はないですが、将来の道が広がるという意味で、大学に行ける学力を付けておくことにまったく損はないと思うんですね。
大学が無関係な仕事についたとしても、身に付けた学力は必ず役に立つと思ってますし。
入る高校は正直どこであってもいいと思うんです。
ただ、行きたいと思う高校に対して努力をしていき、身についた力を本番でしっかっり発揮できるように。
そういった生徒の力を伸ばすための授業をしていけるように、生徒の力が伸びるようなテストや課題を出していきたいですね。
トピ主です。皆さんの白熱した議論ありがとうございます。
で、現在トピの流れが次の二点になっています。
1.成績の付け方(評価方法・評価基準)について、意義ありというご意見。
2.「学歴」について、学歴神話は崩壊したのか、否か。
では、トピ主からの意見を。
成績の付け方は、私には何が良いのか、正直わかりません。
「相対評価」、「絶対評価」は両方あればそれはそれで良いんじゃないかな、くらいで。
そもそも、生徒たちの評価を、数値化することに無理があるのではと。
数値化という究極の抽象性を帯びた評価をしなければならないのなら、
その真逆に位置する、
究極の具体性を帯びた評価、つまり、一生徒を見守った先生達が一対一の面談形式で全員に評価とカウンセリングをする。
これくらいの覚悟が必要ではないでしょうか?
でも、こんな面談、ありえますかね?(コントですね(笑))
評価云々も大事なんですが、数値による評価が入試の合否を左右することの方が、むしろ議論されるべき点ではないでしょうか?
言い換えれば、公立高校入試における「内申書」問題です。
私見としては、第一志望は完全一発実力、当日の試験勝負でいい。第二志望以下には、内申点も考慮の一つにする。
これは、ダメですかね?化なり思いつきですが。
この方法で、
まず高校受験のチャンス(試験の実施回数)を増やすこと、
の学力試験は単なる科目毎の5科目ではなく、教科の枠を越えるような総合問題を課すこと
をやれば、第一志望は一発勝負でもいいかなと。第二志望は、少しゲタを履かせるくらいでの「内申点」を少し加える。
内申点の比重が高いことが問題なんであれば、いいかなと。
でもこれじゃダメですね。
皆さんからのご意見お待ち申し上げます。
で、現在トピの流れが次の二点になっています。
1.成績の付け方(評価方法・評価基準)について、意義ありというご意見。
2.「学歴」について、学歴神話は崩壊したのか、否か。
では、トピ主からの意見を。
成績の付け方は、私には何が良いのか、正直わかりません。
「相対評価」、「絶対評価」は両方あればそれはそれで良いんじゃないかな、くらいで。
そもそも、生徒たちの評価を、数値化することに無理があるのではと。
数値化という究極の抽象性を帯びた評価をしなければならないのなら、
その真逆に位置する、
究極の具体性を帯びた評価、つまり、一生徒を見守った先生達が一対一の面談形式で全員に評価とカウンセリングをする。
これくらいの覚悟が必要ではないでしょうか?
でも、こんな面談、ありえますかね?(コントですね(笑))
評価云々も大事なんですが、数値による評価が入試の合否を左右することの方が、むしろ議論されるべき点ではないでしょうか?
言い換えれば、公立高校入試における「内申書」問題です。
私見としては、第一志望は完全一発実力、当日の試験勝負でいい。第二志望以下には、内申点も考慮の一つにする。
これは、ダメですかね?化なり思いつきですが。
この方法で、
まず高校受験のチャンス(試験の実施回数)を増やすこと、
の学力試験は単なる科目毎の5科目ではなく、教科の枠を越えるような総合問題を課すこと
をやれば、第一志望は一発勝負でもいいかなと。第二志望は、少しゲタを履かせるくらいでの「内申点」を少し加える。
内申点の比重が高いことが問題なんであれば、いいかなと。
でもこれじゃダメですね。
皆さんからのご意見お待ち申し上げます。
続いて、学歴についてですが、
私見を書こうと思ったときに、たっつんさんのご意見を拝読し、私の意見とピッタリしているので驚きました!
本当にありがとうございます!
学歴=その人の学んで来た歩み
とするなら、たっつんさんのご意見は至極納得がいきます。
学歴=○○大卒業、△△大卒業、××大学院修士卒、☆☆高校卒業…など
とする世俗っぽい評価なら、それは偏見やバイアスに満ち満ちたものですから、彼の人物を見る物差しにはならないはず。
なのに、それが人物評価としてまかり通ってきたんですよね。
正常な社会には、そうした間違いを敏感にキャッチし、正そうとする自浄作用があるので、おそらく今は「過渡期」でしょう。
学歴とは話がズレますが、就職において、面接がやはり重視されますよね。
その面接では自分を客観的に見つめているか、自分の売りとは何かを、理論的に話す力が必要ですよね。
(もちろん、これ以外にもあるとは思っています。)
そこで必要とされる力、「自分の主張を論理的に構築し、熱意を持って話す」訓練って、学校教育の小中高校ではやはりできないですか?
出来ないなら出来ない理由が、出来るなら出来る根拠、実践しているなら実践例とその短期的な成果を教えていただきたいです。
私は新しいカリキュラムを組めば出来るのではないかと。ある意味これは、「生き抜く力」かなと。「生きる力」ではなく。
またまた皆さんからのご意見お待ちしています!
私見を書こうと思ったときに、たっつんさんのご意見を拝読し、私の意見とピッタリしているので驚きました!
本当にありがとうございます!
学歴=その人の学んで来た歩み
とするなら、たっつんさんのご意見は至極納得がいきます。
学歴=○○大卒業、△△大卒業、××大学院修士卒、☆☆高校卒業…など
とする世俗っぽい評価なら、それは偏見やバイアスに満ち満ちたものですから、彼の人物を見る物差しにはならないはず。
なのに、それが人物評価としてまかり通ってきたんですよね。
正常な社会には、そうした間違いを敏感にキャッチし、正そうとする自浄作用があるので、おそらく今は「過渡期」でしょう。
学歴とは話がズレますが、就職において、面接がやはり重視されますよね。
その面接では自分を客観的に見つめているか、自分の売りとは何かを、理論的に話す力が必要ですよね。
(もちろん、これ以外にもあるとは思っています。)
そこで必要とされる力、「自分の主張を論理的に構築し、熱意を持って話す」訓練って、学校教育の小中高校ではやはりできないですか?
出来ないなら出来ない理由が、出来るなら出来る根拠、実践しているなら実践例とその短期的な成果を教えていただきたいです。
私は新しいカリキュラムを組めば出来るのではないかと。ある意味これは、「生き抜く力」かなと。「生きる力」ではなく。
またまた皆さんからのご意見お待ちしています!
こーすけさん、
書き込みについて補足します。
進学校といってもさまざまで、中学のことがまだできていない子も、日大くらいはねらうんですね。
授業は、生徒にわからなければ意味がないので、当然生徒に合わせます。
でも、生徒の学力と進路希望にはかなりギャップがある。。。
そこで、7時間目、8時間目、進学補講、生徒面談、になるんです。
学校の先生は、当然他の校務や部活もこなしていますから、
土曜や日曜日も出勤になります。
土曜日に部活がおわったあと、進学補講、とかね。。。
公立高校では、今は こんなことは「ざら」ですよ。
夏休みも部活と補講でほとんどはつぶれます。
休暇をとっても出勤。手当てはでますが、高校生のアルバイトレベル。
それでも、みんながんばるのは、「生徒が好きだから」以外に
はありません。
度が過ぎると、ホントにたおれます。
公立高校(偏差値でいうと50以上)の学校は、みんなこんな感じですよ。
みなさん、あまりにも 公立高校をご存知ないですよね。
書き込みについて補足します。
進学校といってもさまざまで、中学のことがまだできていない子も、日大くらいはねらうんですね。
授業は、生徒にわからなければ意味がないので、当然生徒に合わせます。
でも、生徒の学力と進路希望にはかなりギャップがある。。。
そこで、7時間目、8時間目、進学補講、生徒面談、になるんです。
学校の先生は、当然他の校務や部活もこなしていますから、
土曜や日曜日も出勤になります。
土曜日に部活がおわったあと、進学補講、とかね。。。
公立高校では、今は こんなことは「ざら」ですよ。
夏休みも部活と補講でほとんどはつぶれます。
休暇をとっても出勤。手当てはでますが、高校生のアルバイトレベル。
それでも、みんながんばるのは、「生徒が好きだから」以外に
はありません。
度が過ぎると、ホントにたおれます。
公立高校(偏差値でいうと50以上)の学校は、みんなこんな感じですよ。
みなさん、あまりにも 公立高校をご存知ないですよね。
>保護者の意識を変えることは難しいと思います。塾へ行かなくても十分な学力をつけられる公教育を目指すしかありません。
その通りだと思います。
ですが、授業・勉強量の確保、内容の補習という意味では塾というのも立派な存在意義があると思うんですね。
そして、現場での対応も、学校とは違い授業が主体である分、授業に専念できる分、授業力には差が出てくると思うんですね。
また、進学塾と呼ばれているところも、進学率の確保がなければ生徒数の確保もできないため、そういった受験における情報も豊富です。
こちらも、進学に専念できるからこそだと思います。
そういった意味で、塾も学校とは違った魅力があるというのが自分なりの意見となります。
以前ニュースでこんなことをやっていました。
「東京の新設・九段中等学校にて、土曜の補習を大手進学塾に委託」と。
学校現場の先生としては、不快に思うかもしれませんが、生徒・保護者のニーズ、時代の流れから考えると非常におもしろい試みだと思います。
もちろん、新設校で資金も潤沢という特殊な状況から行えたこととも言っていました。
教育の土台が学校であるという意見に変わりはないのですが、授業に専念できない分、授業に専念できる塾・予備校と力を合わせていくことは非常に重要なことなのかなと思っています。
その通りだと思います。
ですが、授業・勉強量の確保、内容の補習という意味では塾というのも立派な存在意義があると思うんですね。
そして、現場での対応も、学校とは違い授業が主体である分、授業に専念できる分、授業力には差が出てくると思うんですね。
また、進学塾と呼ばれているところも、進学率の確保がなければ生徒数の確保もできないため、そういった受験における情報も豊富です。
こちらも、進学に専念できるからこそだと思います。
そういった意味で、塾も学校とは違った魅力があるというのが自分なりの意見となります。
以前ニュースでこんなことをやっていました。
「東京の新設・九段中等学校にて、土曜の補習を大手進学塾に委託」と。
学校現場の先生としては、不快に思うかもしれませんが、生徒・保護者のニーズ、時代の流れから考えると非常におもしろい試みだと思います。
もちろん、新設校で資金も潤沢という特殊な状況から行えたこととも言っていました。
教育の土台が学校であるという意見に変わりはないのですが、授業に専念できない分、授業に専念できる塾・予備校と力を合わせていくことは非常に重要なことなのかなと思っています。
>おかじゅんさん
いまの社会から考えると、学校の先生への重圧が強いこともうなずけます。
反論ではないのですが、現場の先生から見ての客観的な意見が聞きたいです。
現場の先生から見たとき、夏休みの位置づけってどうなんですか???
世間から見ると学校では長期休みというイメージが強いとと思うのです。
ですが、塾に対する夏休みのイメージは、「受験の天王山」として、一年で一番忙しいのは受験期と夏です。
補習を行っているのはわかりますが、学校としての取り組みとして、夏に対する活動は塾のそれと比べると目立たないと思うんですよ。
それは非常にもったいない気がするんですね。
学校であっても夏が大変というのはよくわかりますが、意識として周りの先生方の声なんかも聞かせてもらえるとうれしいです。
いまの社会から考えると、学校の先生への重圧が強いこともうなずけます。
反論ではないのですが、現場の先生から見ての客観的な意見が聞きたいです。
現場の先生から見たとき、夏休みの位置づけってどうなんですか???
世間から見ると学校では長期休みというイメージが強いとと思うのです。
ですが、塾に対する夏休みのイメージは、「受験の天王山」として、一年で一番忙しいのは受験期と夏です。
補習を行っているのはわかりますが、学校としての取り組みとして、夏に対する活動は塾のそれと比べると目立たないと思うんですよ。
それは非常にもったいない気がするんですね。
学校であっても夏が大変というのはよくわかりますが、意識として周りの先生方の声なんかも聞かせてもらえるとうれしいです。
>たっつんさん、
今は、制度がかわり、夏休み休暇以外はとれません。
何の用事もなくても、勤務時間は学校にいなければいけません。
だから、みんな補講などを積極的にやります。
普段とちがって、勤務時間内には帰れる、というのが、教員の夏休みです。(普段は、残業が当たり前。最後に帰る人は10時ごろ)。
また、公立高校の生徒は、必ずしも裕福ではない家庭も多いんですよ。
進学校においても。。。。。
ですから、塾や予備校へは行かず、「学校の補講でなんとかしてくれ」という要望はかなり強いです。
特に高3の補講の数は凄いですよ。
うちの先生たちの夏休みはこんな感じです。
■センター試験英語・March の英語、長文読解基礎・
長文読解上級・文法初級・文法上級 という種類の補講があり、
1週間から20日間まで。
■看護系数学・センター試験数学・数学初級。数学上級。
1週間から20日間まで。
■センター試験国語。 古典基礎。古典上級。現代文基礎
現代文上級。
1週間から20日間まで。
■生物、化学、物理、センター地学、
■日本史、世界史、センター地理、センター現代社会
高2だと、
■長文基礎、長文中級、文法基礎、文法中級
■国語(現代文)、古典基礎、中級、
■数学I, 理系数学、文系数学、
■化学、物理、
■日本史、世界史、
高1だと、
■長文基礎、長文中級、文法基礎、文法中級
■国語(現代文)、古典基礎、中級、
■数学I, 理系数学、文系数学、
の補習をみんなで手分けして行います。
■高1と高2には、2泊3日の勉強合宿があります。
授業時間は、基本的には2時間ずつ。
ひとりの先生に直すと、
午前か午後に部活、午前か午後に補講、という感じですかね。
もちろん、お子さんが小さい先生などは、「育児休暇」が
許可されます。1日1時間、「子育て休暇」がとることができます。
まとめると、
「勤務時間内には帰れる分だけ、普段よりはラク」
ということですね。
今は、制度がかわり、夏休み休暇以外はとれません。
何の用事もなくても、勤務時間は学校にいなければいけません。
だから、みんな補講などを積極的にやります。
普段とちがって、勤務時間内には帰れる、というのが、教員の夏休みです。(普段は、残業が当たり前。最後に帰る人は10時ごろ)。
また、公立高校の生徒は、必ずしも裕福ではない家庭も多いんですよ。
進学校においても。。。。。
ですから、塾や予備校へは行かず、「学校の補講でなんとかしてくれ」という要望はかなり強いです。
特に高3の補講の数は凄いですよ。
うちの先生たちの夏休みはこんな感じです。
■センター試験英語・March の英語、長文読解基礎・
長文読解上級・文法初級・文法上級 という種類の補講があり、
1週間から20日間まで。
■看護系数学・センター試験数学・数学初級。数学上級。
1週間から20日間まで。
■センター試験国語。 古典基礎。古典上級。現代文基礎
現代文上級。
1週間から20日間まで。
■生物、化学、物理、センター地学、
■日本史、世界史、センター地理、センター現代社会
高2だと、
■長文基礎、長文中級、文法基礎、文法中級
■国語(現代文)、古典基礎、中級、
■数学I, 理系数学、文系数学、
■化学、物理、
■日本史、世界史、
高1だと、
■長文基礎、長文中級、文法基礎、文法中級
■国語(現代文)、古典基礎、中級、
■数学I, 理系数学、文系数学、
の補習をみんなで手分けして行います。
■高1と高2には、2泊3日の勉強合宿があります。
授業時間は、基本的には2時間ずつ。
ひとりの先生に直すと、
午前か午後に部活、午前か午後に補講、という感じですかね。
もちろん、お子さんが小さい先生などは、「育児休暇」が
許可されます。1日1時間、「子育て休暇」がとることができます。
まとめると、
「勤務時間内には帰れる分だけ、普段よりはラク」
ということですね。
>カワイミミさん(69)
大学って何をするところなんでしょうね? 研究と、研究を通じた教育をするところでしょう。それが、専門科目以外の縛りが緩くなって15年ほど経ち、すっかり多様にあるいは深く考える素地が失われて久しいですし、専門科目も教育優先ゆえ専門学校みたいになってきてます。それでもおかしなことに、大卒というだけで相変わらず有難がられてますよね。
もっとも、大学が異様に増えた中で、多くの学生によって経営を成り立たせるという考え方の大学の割合が増えたのも事実でしょう。しかし既存の有名大でもそういうところは多そうですから、新設だけが悪いわけではありません。本来の役割を果たしてるところだけ大学を残すといっても実際には難しいだろうなあ、と思います。とはいえ、大学の性格を事実上変えるのではなく、学生でやってゆきたいのなら大学と別枠でやってくれ、とは思いますが。
ただ、世間が大卒を有難がるのは上記理由ではないだろう、と私には思えてなりません。であれば、専門学校卒でもバリバリ活躍できるような社会になってこそ、と私なんぞは思うんですけど。
>カワイさん
おっしゃる100点と70点のような客観的評価というものを、安易に人物評価においての客観性にすりかわる世の中というのもどうかと思います。そうすると志望書類だの面接だのは学校や大学での特定の分野の成績評価の補完でしかないということでしょうか。
そもそも大卒のほうが中高での卒業生より高く評価するのは何故でしょう?
あと、カワイミミさんのおっしゃるような現状でのやり方もあることに対してはまだお返事されてませんよね? 結局、自らの事業の継続のほうが優先じゃないんですか? (私の場合は高校受験主体しかもできない子向けの塾勤務ですんで、いくら小学校をフレネ主体にしろといっても実現可能性が今のところとてつもなく低い以上、おそらく私の現役の間は成績が低いまま放っておかれる子どもが減らないと思われ、安泰なのですが。ははは。)
大学って何をするところなんでしょうね? 研究と、研究を通じた教育をするところでしょう。それが、専門科目以外の縛りが緩くなって15年ほど経ち、すっかり多様にあるいは深く考える素地が失われて久しいですし、専門科目も教育優先ゆえ専門学校みたいになってきてます。それでもおかしなことに、大卒というだけで相変わらず有難がられてますよね。
もっとも、大学が異様に増えた中で、多くの学生によって経営を成り立たせるという考え方の大学の割合が増えたのも事実でしょう。しかし既存の有名大でもそういうところは多そうですから、新設だけが悪いわけではありません。本来の役割を果たしてるところだけ大学を残すといっても実際には難しいだろうなあ、と思います。とはいえ、大学の性格を事実上変えるのではなく、学生でやってゆきたいのなら大学と別枠でやってくれ、とは思いますが。
ただ、世間が大卒を有難がるのは上記理由ではないだろう、と私には思えてなりません。であれば、専門学校卒でもバリバリ活躍できるような社会になってこそ、と私なんぞは思うんですけど。
>カワイさん
おっしゃる100点と70点のような客観的評価というものを、安易に人物評価においての客観性にすりかわる世の中というのもどうかと思います。そうすると志望書類だの面接だのは学校や大学での特定の分野の成績評価の補完でしかないということでしょうか。
そもそも大卒のほうが中高での卒業生より高く評価するのは何故でしょう?
あと、カワイミミさんのおっしゃるような現状でのやり方もあることに対してはまだお返事されてませんよね? 結局、自らの事業の継続のほうが優先じゃないんですか? (私の場合は高校受験主体しかもできない子向けの塾勤務ですんで、いくら小学校をフレネ主体にしろといっても実現可能性が今のところとてつもなく低い以上、おそらく私の現役の間は成績が低いまま放っておかれる子どもが減らないと思われ、安泰なのですが。ははは。)
すみません、またしてもトピから外れてしまうのですが、83の内容もふまえて少し。
夏休みのもとになったのは、学校時代の記憶から、「夏が暑く集中できないので休みとした」と受け取っています。
学習指導要領の改訂のなかでの目玉は、ゆとり教育の見直しなのですが、学習の効率をふまえてのクーラーの導入というのはどうなのでしょう???
クーラーの導入が実現できれば、夏休みの短縮というのも実現できると思うのです。
週休二日制は、社会全体として取っていることなので、それを短縮するよりは夏休みの短縮のほうがいいのかなと思っています。
予算の関係なんかも絡んでくる話ですが、机上の空論としてなら意見の交換もおもしろいと思うのですが。
トピからは確実にはずれていることなので、必要そうなら別トピックとしてもいいのかなと思います。
夏休みのもとになったのは、学校時代の記憶から、「夏が暑く集中できないので休みとした」と受け取っています。
学習指導要領の改訂のなかでの目玉は、ゆとり教育の見直しなのですが、学習の効率をふまえてのクーラーの導入というのはどうなのでしょう???
クーラーの導入が実現できれば、夏休みの短縮というのも実現できると思うのです。
週休二日制は、社会全体として取っていることなので、それを短縮するよりは夏休みの短縮のほうがいいのかなと思っています。
予算の関係なんかも絡んでくる話ですが、机上の空論としてなら意見の交換もおもしろいと思うのですが。
トピからは確実にはずれていることなので、必要そうなら別トピックとしてもいいのかなと思います。
私自身はいわゆる「高学歴」ですが、就職などに関してその恩恵を受けたとは思いません。
そもそも私は就職のために大学に入ろうと思ったわけではないので。
ただ、大学をある程度ランク付けすることは少なからず意味のあることだと思います。
たとえば、カワイさんは東大なんてたいしたレベルじゃないといいます。私もそう思います。
でも、一般的に難関と呼ばれるところに挑戦するわけですから、ある程度のチャレンジ精神に恵まれなければいけません。
さらに、センター試験では満点に近い点数を取る必要がある。(今はどうか知りませんが)少しのミスも許されないのだから、自分を厳しく律し、チェックする能力が必要である。
二次試験では4教科が必須。極端な応用力は必要ないが、まんべんなくそつなくこなす必要がある。
ということで、東大生に限ってみれば、少なくとも「チャレンジ精神」、「自己反省能力」、「事務処理能力」は他大生に比べて高いレベルにあるのが普通です。
多分、他の大学も同じことだと思います。ですから、大学の序列というのは、事務仕事をミスしないで速くこなす順番じゃないでしょうか(笑)
就職の際に学歴を重視する会社というのは、そこらへんを見ている気がします。
逆に大学名を気にしない会社はそれ以外の部分を見ていると言えるかもしれません。
まとまりのない文章ですみません。
そもそも私は就職のために大学に入ろうと思ったわけではないので。
ただ、大学をある程度ランク付けすることは少なからず意味のあることだと思います。
たとえば、カワイさんは東大なんてたいしたレベルじゃないといいます。私もそう思います。
でも、一般的に難関と呼ばれるところに挑戦するわけですから、ある程度のチャレンジ精神に恵まれなければいけません。
さらに、センター試験では満点に近い点数を取る必要がある。(今はどうか知りませんが)少しのミスも許されないのだから、自分を厳しく律し、チェックする能力が必要である。
二次試験では4教科が必須。極端な応用力は必要ないが、まんべんなくそつなくこなす必要がある。
ということで、東大生に限ってみれば、少なくとも「チャレンジ精神」、「自己反省能力」、「事務処理能力」は他大生に比べて高いレベルにあるのが普通です。
多分、他の大学も同じことだと思います。ですから、大学の序列というのは、事務仕事をミスしないで速くこなす順番じゃないでしょうか(笑)
就職の際に学歴を重視する会社というのは、そこらへんを見ている気がします。
逆に大学名を気にしない会社はそれ以外の部分を見ていると言えるかもしれません。
まとまりのない文章ですみません。
>おかじゅんさん
>公立高校(偏差値でいうと50以上)の学校は、
>みんなこんな感じですよ。
私は今高校とは直接接点がないのですが、
自分自身が進学校にいた経験を考えると、
高校の先生は大変だと思います。
授業前補習で0時間目、
授業後補習で7時間目、8時間目がありましたから。
夏休みも当然補習です。
公立の高校の先生が頑張っているから、
私もお金をかけなくても
多くの子が大学へ行けると思います。
問題は、小中学校の先生で、
さぼって制度の上にあぐらをかいている先生と
頑張りすぎているけど
残念ながら空回り(制度に振り回されている)先生とで
二極化している状態があることです。
宿題の出し方一つみても、
出し方がいい加減で杜撰な先生か、
興味関心を高めようと言うあまり、
基礎基本の指導がないがしろにされている先生とがいます。
なんか、高校の先生が頑張っているのに、
それをふいにしてしまうようなことが小中学校で起きている。
ゆとり教育という制度そものがその典型で、
完全にしわ寄せが高校に行ってますよね。
まあ、それがねらいだとスポークスマンだった
寺脇研は言っているわけですから、
ねらいどおりだったわけで、
こんな下らない制度とっとと止めるべきですよね。
官僚は何やってるんだって思います。
>公立高校(偏差値でいうと50以上)の学校は、
>みんなこんな感じですよ。
私は今高校とは直接接点がないのですが、
自分自身が進学校にいた経験を考えると、
高校の先生は大変だと思います。
授業前補習で0時間目、
授業後補習で7時間目、8時間目がありましたから。
夏休みも当然補習です。
公立の高校の先生が頑張っているから、
私もお金をかけなくても
多くの子が大学へ行けると思います。
問題は、小中学校の先生で、
さぼって制度の上にあぐらをかいている先生と
頑張りすぎているけど
残念ながら空回り(制度に振り回されている)先生とで
二極化している状態があることです。
宿題の出し方一つみても、
出し方がいい加減で杜撰な先生か、
興味関心を高めようと言うあまり、
基礎基本の指導がないがしろにされている先生とがいます。
なんか、高校の先生が頑張っているのに、
それをふいにしてしまうようなことが小中学校で起きている。
ゆとり教育という制度そものがその典型で、
完全にしわ寄せが高校に行ってますよね。
まあ、それがねらいだとスポークスマンだった
寺脇研は言っているわけですから、
ねらいどおりだったわけで、
こんな下らない制度とっとと止めるべきですよね。
官僚は何やってるんだって思います。
高校もいろいろですよね。
たとえばわたしが住んでいる宮古島では、宮古高校の理数科が一番合格点が高く(県内でもトップ5位以内)、湘南高校の海洋科が高校入試の合格点が一番低いとされています。
宮古高校の普通科ですと、島の中学生の半数近くが入れるマンモス科なので300点満点で180点足らずくらいでも合格できてしまいます。
一番合格点が低いといわれる海洋科につづいて低いのが工業高校の各科、農業高校の各科です。
そういう学校では、英語や数学、国語、理科、社会の指導については、一般の公立小学校や中学校と比較して努力しているとはあまりいえないように見受けられます。
身近な例では、大学難易度ランキングで最下位に位置する大学の経済学部を出た人が、もともと数学や国語に詳しいわけでもないのに非常勤で今年は数学、去年は国語を教えていました。
うちの妹も数学に関しては、旧帝大を卒業しているだけでなく、博士課程までいったくらいの秀才なんだけど、頼まれて仕方なく国語の非常勤講師をしていました。
さらにいいますと、工業高校に入学したばかりの子が、高校の勉強を教えてほしいと個人指導を受けに来たとき、英語の教材を見せてもらうと、中学一年生レベルの問題ばかりならんでいました。
もちろん合格難易度が高い理数科の先生と比べて理解させる努力を怠っているというわけではありません。基本的なところからわからせようという努力をしているようにも思えます。
一概に、高校の教師は努力している、小中学校の教師は怠けているというのはどうかと思います。
わたしが見る限り、中学の先生たちは、受験勉強の対策にも精一杯協力しながら、カリキュラムの内容をなんとか少しでもわかってもらおうと努力をしているように思えます。
たとえばわたしが住んでいる宮古島では、宮古高校の理数科が一番合格点が高く(県内でもトップ5位以内)、湘南高校の海洋科が高校入試の合格点が一番低いとされています。
宮古高校の普通科ですと、島の中学生の半数近くが入れるマンモス科なので300点満点で180点足らずくらいでも合格できてしまいます。
一番合格点が低いといわれる海洋科につづいて低いのが工業高校の各科、農業高校の各科です。
そういう学校では、英語や数学、国語、理科、社会の指導については、一般の公立小学校や中学校と比較して努力しているとはあまりいえないように見受けられます。
身近な例では、大学難易度ランキングで最下位に位置する大学の経済学部を出た人が、もともと数学や国語に詳しいわけでもないのに非常勤で今年は数学、去年は国語を教えていました。
うちの妹も数学に関しては、旧帝大を卒業しているだけでなく、博士課程までいったくらいの秀才なんだけど、頼まれて仕方なく国語の非常勤講師をしていました。
さらにいいますと、工業高校に入学したばかりの子が、高校の勉強を教えてほしいと個人指導を受けに来たとき、英語の教材を見せてもらうと、中学一年生レベルの問題ばかりならんでいました。
もちろん合格難易度が高い理数科の先生と比べて理解させる努力を怠っているというわけではありません。基本的なところからわからせようという努力をしているようにも思えます。
一概に、高校の教師は努力している、小中学校の教師は怠けているというのはどうかと思います。
わたしが見る限り、中学の先生たちは、受験勉強の対策にも精一杯協力しながら、カリキュラムの内容をなんとか少しでもわかってもらおうと努力をしているように思えます。
OZさん
>公立小中高教師が自校もしくは自分自身について答えるのが無難
確かにそれは無難でしょう。でも、無難な議論から意味のあるものが生まれるでしょうか。
申し訳ないですが、この発言は「部外者は口を出すな」という意味に取られても仕方ないと思います。
我々塾講師も生徒と関わっています。彼らのことを考えているからこそ、公教育に対して批判的な意見も出てきます。我々も当事者です。そのことは理解して頂きたい。
公教育に携わっている方が、外部の批判を真摯に受け止め、変えるべきところは変えていかないと、何もよくならないと思います。
>会社でもそうですが、全員が同じ気持ちで仕事しているわけではありませんよね
公立学校は会社ですか?全国民が平等に教育を受けることを可能にするのが公教育の最終的使命ではないですか?
もちろん学校によって先生も違えば生徒も違う、等質な教育というのは絵に描いた餅かもしれません。でも、やはり理想は追い求めなければいけないのでは?
定期テストに関していうと、全員がOZさんのようにきちんとした考えのもとで作問してくれれば、何の文句もありません。でも、私も常々体験していることですが、平均点が30点のテストというものがなくならないのです。そして、そのテストの成績をもとに付けられる内申点が生徒の一生を左右するのです。
これを批判せずして何を批判しろというのですか。
すみません。食ってかかるような感じになってしまいました。
誤解のないように言っておくと、私は公立の先生の努力を認めない類の人間ではありません。今は塾で働いていますが、公教育が充実して、塾が不要になったとしたら、それは望ましいことだと思っています。
ただ、現状がそうでないのだから、今はいがみ合うべきでもなければ、お互いを排除しあうべきでもない、公立の先生と我々塾が協力していかなければいけないと思うのです。
>公立小中高教師が自校もしくは自分自身について答えるのが無難
確かにそれは無難でしょう。でも、無難な議論から意味のあるものが生まれるでしょうか。
申し訳ないですが、この発言は「部外者は口を出すな」という意味に取られても仕方ないと思います。
我々塾講師も生徒と関わっています。彼らのことを考えているからこそ、公教育に対して批判的な意見も出てきます。我々も当事者です。そのことは理解して頂きたい。
公教育に携わっている方が、外部の批判を真摯に受け止め、変えるべきところは変えていかないと、何もよくならないと思います。
>会社でもそうですが、全員が同じ気持ちで仕事しているわけではありませんよね
公立学校は会社ですか?全国民が平等に教育を受けることを可能にするのが公教育の最終的使命ではないですか?
もちろん学校によって先生も違えば生徒も違う、等質な教育というのは絵に描いた餅かもしれません。でも、やはり理想は追い求めなければいけないのでは?
定期テストに関していうと、全員がOZさんのようにきちんとした考えのもとで作問してくれれば、何の文句もありません。でも、私も常々体験していることですが、平均点が30点のテストというものがなくならないのです。そして、そのテストの成績をもとに付けられる内申点が生徒の一生を左右するのです。
これを批判せずして何を批判しろというのですか。
すみません。食ってかかるような感じになってしまいました。
誤解のないように言っておくと、私は公立の先生の努力を認めない類の人間ではありません。今は塾で働いていますが、公教育が充実して、塾が不要になったとしたら、それは望ましいことだと思っています。
ただ、現状がそうでないのだから、今はいがみ合うべきでもなければ、お互いを排除しあうべきでもない、公立の先生と我々塾が協力していかなければいけないと思うのです。
定期テストに関していうと、全員がOZさんのようにきちんとした考えのもとで作問してくれれば、何の文句もありません。でも、私も常々体験していることですが、平均点が30点のテストというものがなくならないのです。そして、そのテストの成績をもとに付けられる内申点が生徒の一生を左右するのです。
これを批判せずして何を批判しろというのですか。
自分も同じ気持ちです。
自分の教え子の中学で1学期の終了時点で、指導要領中1の範囲の半分を終えようとしてる先生がいます。
進行具合もさることながら、生徒の理解度も塾に行っていない生徒は5点10点がざらにいるそうです。
自分の生徒も口をそろえて「あの先生じゃまったくわからん」と言うのです。
こういった先生が実際にいる以上、学校の先生全体として批判を受けてしまいませんか???
ここに書き込みをしている方は、そういった先生ではないのですが、そんな先生がとなりに座っているときにどうするかですよね。
難しい問題だと思います。
ですが、こういった話をしているときに、
「自分はしっかりやっているのに、そんな先生と一緒にされては困る。」では、やっぱりよくならないと思うんです。
気持ちはすごくよくわかります。
ですが、そんな先生がいるという状況をなんとかできるのもまた、現場の先生でなければできないというのも事実だと思います。
そういった中で、なんとかしていくための意見交換がこのトピックの趣旨だと思うんです。
これを批判せずして何を批判しろというのですか。
自分も同じ気持ちです。
自分の教え子の中学で1学期の終了時点で、指導要領中1の範囲の半分を終えようとしてる先生がいます。
進行具合もさることながら、生徒の理解度も塾に行っていない生徒は5点10点がざらにいるそうです。
自分の生徒も口をそろえて「あの先生じゃまったくわからん」と言うのです。
こういった先生が実際にいる以上、学校の先生全体として批判を受けてしまいませんか???
ここに書き込みをしている方は、そういった先生ではないのですが、そんな先生がとなりに座っているときにどうするかですよね。
難しい問題だと思います。
ですが、こういった話をしているときに、
「自分はしっかりやっているのに、そんな先生と一緒にされては困る。」では、やっぱりよくならないと思うんです。
気持ちはすごくよくわかります。
ですが、そんな先生がいるという状況をなんとかできるのもまた、現場の先生でなければできないというのも事実だと思います。
そういった中で、なんとかしていくための意見交換がこのトピックの趣旨だと思うんです。
公立中学も小学校も夏休み制度は同じですよ。
勤務時間は、学校にいなければなりません。
たぶん、普段勤務がもっともきついのは、公立中学の先生ではないでしょうか?
予備校の生徒に、定期テストの問題を持ってこさせていますが、
出題形式が県立高校入試と同じ形式と配分でした(中3)。
英語でいえば、
中1も中2も、テストにリスニングを入れているようですし、
長文読解の配点が多くなっています。
社会は、中1、中2の内容が多いですよね。
定期テストの出題をみる限りでは、かなり県立入試を意識していると思いました。
中学の先生が大変だと思うのは、高校は、いそがしければ
部活は自分たちでやらせておいてもいいけど、
中学は部活までつきあって、しかも千差万別の生徒がいて、
その中で、授業の工夫、定期テストの工夫、進路指導、
保護者会、などなど、ストレスいっぱいだと思います。
高校は、中学側に、入試情報をいれています。
したがって、ここの学校なら、この生徒ははいれるとか、だめだとかかなり詳しいですよ。
はっきりいって、今予備校にいますが、
予備校より、中学の先生のほうが、入試情報は詳しいですよ。
勤務時間は、学校にいなければなりません。
たぶん、普段勤務がもっともきついのは、公立中学の先生ではないでしょうか?
予備校の生徒に、定期テストの問題を持ってこさせていますが、
出題形式が県立高校入試と同じ形式と配分でした(中3)。
英語でいえば、
中1も中2も、テストにリスニングを入れているようですし、
長文読解の配点が多くなっています。
社会は、中1、中2の内容が多いですよね。
定期テストの出題をみる限りでは、かなり県立入試を意識していると思いました。
中学の先生が大変だと思うのは、高校は、いそがしければ
部活は自分たちでやらせておいてもいいけど、
中学は部活までつきあって、しかも千差万別の生徒がいて、
その中で、授業の工夫、定期テストの工夫、進路指導、
保護者会、などなど、ストレスいっぱいだと思います。
高校は、中学側に、入試情報をいれています。
したがって、ここの学校なら、この生徒ははいれるとか、だめだとかかなり詳しいですよ。
はっきりいって、今予備校にいますが、
予備校より、中学の先生のほうが、入試情報は詳しいですよ。
tubolaraさんのおっしゃる
>我々塾講師も生徒と関わっています。彼らのことを考えて
>いるからこそ、公教育に対して批判的な意見も出てきます。
>我々も当事者です。そのことは理解して頂きたい。
という部分には同感ですね。
別トピで、子どもの学習意欲や、教師−子どもという垂直的関係がないと学べないのか、という問いかけをしたのも、小学校高学年でのあまりに大きい学習拒否っぷり(いずれ中学の基礎学力につながり格差を大学に向かって拡大再生産していく)があまりに酷いから、ということもあります。これがなければ、中高での勤務ももっと楽になるでしょうに。
(でも、たっつんさんいはコメント頂いてませんが)
>我々塾講師も生徒と関わっています。彼らのことを考えて
>いるからこそ、公教育に対して批判的な意見も出てきます。
>我々も当事者です。そのことは理解して頂きたい。
という部分には同感ですね。
別トピで、子どもの学習意欲や、教師−子どもという垂直的関係がないと学べないのか、という問いかけをしたのも、小学校高学年でのあまりに大きい学習拒否っぷり(いずれ中学の基礎学力につながり格差を大学に向かって拡大再生産していく)があまりに酷いから、ということもあります。これがなければ、中高での勤務ももっと楽になるでしょうに。
(でも、たっつんさんいはコメント頂いてませんが)
>おかじゅんさん
>高校は、中学側に、入試情報をいれています。
>したがって、ここの学校なら、
>この生徒ははいれるとか、だめだとかかなり詳しいですよ。
>はっきりいって、今予備校にいますが、
>予備校より、中学の先生のほうが、入試情報は詳しいですよ。
それは、例えば内申点を決めるのは中学校の教師の側ですから、
入試情報が詳しいというよりも、
入試の合否に直接影響力をもっているからだと思います。
推薦入試の場合は特にそうですよね。
逆に一般入試の場合は、当日点次第の部分があるので、
その辺は学校の先生よりも
塾の先生の方がよくわかってると思います。
実際、山梨県はどうだったわけですし、
愛知県だってオール5でも不合格になる子が続出したわけですし。
(まあ、塾側が合格実績を確保するために
無理に受けさせたというケースも多々あるでしょうけど)
>ペン太 さん
>高校の先生は中学はいったい何をしているんだと思い、
>中学の先生は小学校ではいったい何を教えているんだと嘆き、
>塾の先生は公立学校では何をやっているんだと怒る。
こういうのって信頼関係が崩れているってことだと思います。
私は学校を信用してませんが、
子どもの前ではなるべく学校をたてるようにしています。
「まず、学校の授業が大事」とか。
でも、例えば小学生に
「学校で英語やってると思うけど、何やってるの?」
「う〜ん、わかんない。っていうか授業あんまりやってない」
これだとフォローしようがないですよね。
子どもに何にも印象に残ってない。
学校で英語を習ったっていう足跡が何にもない。
「小学生のうちに、アルファベットとか
フォニックスをやっておくと、中学校でつまずかないよ」
っていうと、子どもは納得するんですよね。
中学校の先生もそう思うと思います。
小中の連携、中高の連携ができていないし、
そういうのって意識しないとできないと思うんです。
私が、小中学校の先生を良く思わないのは、
小中学校の先生の頑張っているって言うのが
往々にして精神論にすぎず、
具体的なノウハウでないからです。
小学校の間にこうするこうしておくと、
中学校の先生は助かるだろうな
というのがない。
鉛筆の持ち方から、字の書き方、ノートの書き方まで、
今の子どもたちを見て、つくづくそう思います。
今日の発表で、小学校で都道府県名を覚えさせる
ことに決まりましたが、
中学校の先生は、前からそう思っていたでしょう。
小学校の先生は、
「指導要領に書いてないから、覚えさせる必要なんて無い」
って思っている人が大半です。
でも、困るのは中学校の先生なんです。
漢字の指導も、小学校6年生で習った漢字は、
小学生の間に覚えさせなくても良い(書き指導は)。
と、指導要領でそうなっていて、
ちゃんと小学校の先生はそれを守っている(笑)。
覚えさせなくても良いだけであって、
覚えさせていけない訳じゃないです。
そうなると中学校の国語の先生が、
中学校の漢字と小学校の漢字を平行して教えなければいけない。
「小学校で教えておいてくれるとどんなに楽なことか」
って思っているでしょう。
高校は、義務教育ではないし、
入試という形で生徒を選別することができる。
でも小中学校はそういうわけにはいかない。
みんなに、
きちっと基礎基本の学力を身につけさせなければいけないのに、
それができていない。やってない。
できないことをやれと言っている訳じゃないんです。
できる(はずの)ことをやってないから怒ってるんです。
精一杯やっているという精神論じゃなくって、
具体的にどこをどう頑張っているのか?
それを示してくれないと、
だれも信用してくれないと思うんです。
逆に言えば、やることをきちんとやって、
その成果を示してくれれば、人は信用すると思うんです。
>高校は、中学側に、入試情報をいれています。
>したがって、ここの学校なら、
>この生徒ははいれるとか、だめだとかかなり詳しいですよ。
>はっきりいって、今予備校にいますが、
>予備校より、中学の先生のほうが、入試情報は詳しいですよ。
それは、例えば内申点を決めるのは中学校の教師の側ですから、
入試情報が詳しいというよりも、
入試の合否に直接影響力をもっているからだと思います。
推薦入試の場合は特にそうですよね。
逆に一般入試の場合は、当日点次第の部分があるので、
その辺は学校の先生よりも
塾の先生の方がよくわかってると思います。
実際、山梨県はどうだったわけですし、
愛知県だってオール5でも不合格になる子が続出したわけですし。
(まあ、塾側が合格実績を確保するために
無理に受けさせたというケースも多々あるでしょうけど)
>ペン太 さん
>高校の先生は中学はいったい何をしているんだと思い、
>中学の先生は小学校ではいったい何を教えているんだと嘆き、
>塾の先生は公立学校では何をやっているんだと怒る。
こういうのって信頼関係が崩れているってことだと思います。
私は学校を信用してませんが、
子どもの前ではなるべく学校をたてるようにしています。
「まず、学校の授業が大事」とか。
でも、例えば小学生に
「学校で英語やってると思うけど、何やってるの?」
「う〜ん、わかんない。っていうか授業あんまりやってない」
これだとフォローしようがないですよね。
子どもに何にも印象に残ってない。
学校で英語を習ったっていう足跡が何にもない。
「小学生のうちに、アルファベットとか
フォニックスをやっておくと、中学校でつまずかないよ」
っていうと、子どもは納得するんですよね。
中学校の先生もそう思うと思います。
小中の連携、中高の連携ができていないし、
そういうのって意識しないとできないと思うんです。
私が、小中学校の先生を良く思わないのは、
小中学校の先生の頑張っているって言うのが
往々にして精神論にすぎず、
具体的なノウハウでないからです。
小学校の間にこうするこうしておくと、
中学校の先生は助かるだろうな
というのがない。
鉛筆の持ち方から、字の書き方、ノートの書き方まで、
今の子どもたちを見て、つくづくそう思います。
今日の発表で、小学校で都道府県名を覚えさせる
ことに決まりましたが、
中学校の先生は、前からそう思っていたでしょう。
小学校の先生は、
「指導要領に書いてないから、覚えさせる必要なんて無い」
って思っている人が大半です。
でも、困るのは中学校の先生なんです。
漢字の指導も、小学校6年生で習った漢字は、
小学生の間に覚えさせなくても良い(書き指導は)。
と、指導要領でそうなっていて、
ちゃんと小学校の先生はそれを守っている(笑)。
覚えさせなくても良いだけであって、
覚えさせていけない訳じゃないです。
そうなると中学校の国語の先生が、
中学校の漢字と小学校の漢字を平行して教えなければいけない。
「小学校で教えておいてくれるとどんなに楽なことか」
って思っているでしょう。
高校は、義務教育ではないし、
入試という形で生徒を選別することができる。
でも小中学校はそういうわけにはいかない。
みんなに、
きちっと基礎基本の学力を身につけさせなければいけないのに、
それができていない。やってない。
できないことをやれと言っている訳じゃないんです。
できる(はずの)ことをやってないから怒ってるんです。
精一杯やっているという精神論じゃなくって、
具体的にどこをどう頑張っているのか?
それを示してくれないと、
だれも信用してくれないと思うんです。
逆に言えば、やることをきちんとやって、
その成果を示してくれれば、人は信用すると思うんです。
トピ主です。皆さんからのご意見が100を超え、この問題を提起した甲斐があります。
ご意見を寄せて頂いた皆様、ならびにこのトピをご覧の皆様に御礼申し上げます。ありがとうございます。
まだまだご意見は募集中ですが、そろそろ新たなトピが必要かなと思います。
現在は
「小学校での基礎的な知識・学習習慣・しつけ、と中学校での学習の連携」
の話題が出ていますが、
私もこの問題は気にかかります。
小学校と中学校の連携だけでなく、別トピでも中学・高校の連携の話題があり、皆さんも気になっていらっしゃいませんか?
そこで、私たちで「学習指導要領」や「カリキュラム・教科」などを考えるトピを提案したいのですがいかがでしょうか?
皆さんからのご意見をうかがった上でトピ立てしたいと思います。
ご意見を寄せて頂いた皆様、ならびにこのトピをご覧の皆様に御礼申し上げます。ありがとうございます。
まだまだご意見は募集中ですが、そろそろ新たなトピが必要かなと思います。
現在は
「小学校での基礎的な知識・学習習慣・しつけ、と中学校での学習の連携」
の話題が出ていますが、
私もこの問題は気にかかります。
小学校と中学校の連携だけでなく、別トピでも中学・高校の連携の話題があり、皆さんも気になっていらっしゃいませんか?
そこで、私たちで「学習指導要領」や「カリキュラム・教科」などを考えるトピを提案したいのですがいかがでしょうか?
皆さんからのご意見をうかがった上でトピ立てしたいと思います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
授業の工夫事典!!(塾講師・教師) 更新情報
授業の工夫事典!!(塾講師・教師)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90027人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6407人
- 3位
- 独り言
- 9045人