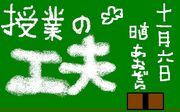|
|
|
|
コメント(16)
自分は小5・小6を10年ほど指導しています。
昨年の四谷大塚の模試でも銅の酸化・還元反応の仕組みを問う問題が出題されてましたし、ある程度原理的な部分を理解させていく必要があるとは思います。
ただ自分は元素記号を教えることにはためらいを感じます。
理由は、
1)アルファベット(大文字+小文字)で抽象化された記号が、小学生には理解・定着しづらいのではないか。
2)原子モデルや電子のやり取りを理解させずに化学反応式を扱うのであれば、結局モデル(●や△、=やーなど)を使った説明と変わらないのではないか。
結局自分はトピ主さんの挙げられた例であれば、
「酸+金属 → 水素+残り物」を覚えさせるよう指導しています。
「残り物」について出題する学校は実際少なく、出題されてもモデルを使った理解で十分対応できますので。
自分の立場(塾講師)としてはテストで点を取らせることが最優先事項であり、科学的な視点や興味を深める話はむしろ「余談」として取り込んでいます。もちろん「余談」の方が授業していて面白いし盛り上がるのですが(苦笑)。
昨年の四谷大塚の模試でも銅の酸化・還元反応の仕組みを問う問題が出題されてましたし、ある程度原理的な部分を理解させていく必要があるとは思います。
ただ自分は元素記号を教えることにはためらいを感じます。
理由は、
1)アルファベット(大文字+小文字)で抽象化された記号が、小学生には理解・定着しづらいのではないか。
2)原子モデルや電子のやり取りを理解させずに化学反応式を扱うのであれば、結局モデル(●や△、=やーなど)を使った説明と変わらないのではないか。
結局自分はトピ主さんの挙げられた例であれば、
「酸+金属 → 水素+残り物」を覚えさせるよう指導しています。
「残り物」について出題する学校は実際少なく、出題されてもモデルを使った理解で十分対応できますので。
自分の立場(塾講師)としてはテストで点を取らせることが最優先事項であり、科学的な視点や興味を深める話はむしろ「余談」として取り込んでいます。もちろん「余談」の方が授業していて面白いし盛り上がるのですが(苦笑)。
生徒の反応を見て、ですね。
生グレ姉さんさん同様なんですが、男の子には受けがいいと思います。
意味はよく分かってないけど、おれこんなん知ってるんやで。すごいやろ♪ って感じで覚えてしまう子もいてますし。
うちの塾では小2の男の子に「ブイイコール?」
って聞いたらみんな自慢げに「エフラムダ!!」って答えてます。 全く意味はわかってないんですが、響きがいいみたいで喜んでます。
元素記号や反応式も、中学生になったときに、何かようわからんけど見たことあるぐらいの記憶が片隅に残っててくれればいいなぁと思ってモデル図とか使いながら説明したりします。小さいときに軽くでも触っておくと、いざ出てきたときに拒否反応が起こりにくいと思うので。
生グレ姉さんさん同様なんですが、男の子には受けがいいと思います。
意味はよく分かってないけど、おれこんなん知ってるんやで。すごいやろ♪ って感じで覚えてしまう子もいてますし。
うちの塾では小2の男の子に「ブイイコール?」
って聞いたらみんな自慢げに「エフラムダ!!」って答えてます。 全く意味はわかってないんですが、響きがいいみたいで喜んでます。
元素記号や反応式も、中学生になったときに、何かようわからんけど見たことあるぐらいの記憶が片隅に残っててくれればいいなぁと思ってモデル図とか使いながら説明したりします。小さいときに軽くでも触っておくと、いざ出てきたときに拒否反応が起こりにくいと思うので。
小学校の時に、つぶつぶのキャラにそれぞれ決まった数の手がついていて、手をつないだり離したり、というイメージで教えてもらって分かりやすかったです。
化学反応は全部そういう絵で教えてもらいました。
その絵に化学式を重ねて、「難しくかくとこういうことだよ。中学で習うからね。」とだけ触れてくれましたが、中学で化学式を習った時もイメージがつかみやすかったし抵抗なく学べました。
子供が分かるように易しく噛み砕いて説明すれば、分かりやすくていいと思います。
ただ、確かに指導要領範囲外なので、元素記号、化学式、化学反応式は覚えたりそれを使って考えたりというのは難しいと思います。最初から元素記号で学ばせると子供の学力差で理解度に大きな差が出てきてしまうと思います。最初は和名でいいのではないでしょうか?
概念だけ掴ませて、触れるだけにとどめてみては?
化学反応は全部そういう絵で教えてもらいました。
その絵に化学式を重ねて、「難しくかくとこういうことだよ。中学で習うからね。」とだけ触れてくれましたが、中学で化学式を習った時もイメージがつかみやすかったし抵抗なく学べました。
子供が分かるように易しく噛み砕いて説明すれば、分かりやすくていいと思います。
ただ、確かに指導要領範囲外なので、元素記号、化学式、化学反応式は覚えたりそれを使って考えたりというのは難しいと思います。最初から元素記号で学ばせると子供の学力差で理解度に大きな差が出てきてしまうと思います。最初は和名でいいのではないでしょうか?
概念だけ掴ませて、触れるだけにとどめてみては?
私も記号を使ってモデル化していました。
記号がある事を知っている子がいたら、ちょっと触れる程度で。
数人は興味を持って反応式まで聞いてくる事もありました。
二酸化炭素なら炭素と酸素からなることは教える必要がありますが、
原子の比が炭素:酸素=1:2であることまでは教えなくていい
(余談として言ってましたが…)事を考えると、化学式まで
扱ってしまうと収拾がつかなくなるかな、と思います。
確かに、イオンの概念を扱わず中和を教える、など結構きついですよね。
塩酸に金属を溶かす、というあたりを学習する時に、
塩酸は水素君と塩素ちゃんのカップルです(イオンのイメージ)。
そこにアルミニウム君がくると、水素君よりカッコいいので
塩素ちゃんはアルミニウム君とカップルになってしまいます。
フラれた水素君はショックで飛び出してきてしまいます(気体発生)。
しかし、銅君はあまりカッコよくないので水素君はフラれません。
つまり、カッコいい順に並べると…
アルミニウム、水素、銅 (イオン化傾向のイメージ)ですね?
というような感じにしてました…。無理矢理ですが。
記号がある事を知っている子がいたら、ちょっと触れる程度で。
数人は興味を持って反応式まで聞いてくる事もありました。
二酸化炭素なら炭素と酸素からなることは教える必要がありますが、
原子の比が炭素:酸素=1:2であることまでは教えなくていい
(余談として言ってましたが…)事を考えると、化学式まで
扱ってしまうと収拾がつかなくなるかな、と思います。
確かに、イオンの概念を扱わず中和を教える、など結構きついですよね。
塩酸に金属を溶かす、というあたりを学習する時に、
塩酸は水素君と塩素ちゃんのカップルです(イオンのイメージ)。
そこにアルミニウム君がくると、水素君よりカッコいいので
塩素ちゃんはアルミニウム君とカップルになってしまいます。
フラれた水素君はショックで飛び出してきてしまいます(気体発生)。
しかし、銅君はあまりカッコよくないので水素君はフラれません。
つまり、カッコいい順に並べると…
アルミニウム、水素、銅 (イオン化傾向のイメージ)ですね?
というような感じにしてました…。無理矢理ですが。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
授業の工夫事典!!(塾講師・教師) 更新情報
授業の工夫事典!!(塾講師・教師)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 相棒
- 59290人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209458人
- 3位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19958人