(アロマが好きな人には耳が痛いかも)
■[BfR][CAM]エッセンシャルオイルの使用に関するQ & A(ドイツ)28.03.2008
http://
雨や風や寒さ−寒冷で湿った気候は風邪や咳や嗄れ声の典型的な季節である。
多くの消費者はユーカリやペパーミントや樟脳などのエッセンシャルオイルの去痰作用などを期待して自分で治療する。
これらの製品には吸入用や胸に塗ったりするものなどがある。しかし子どもに使うときには注意が必要である。アロマランプなどを使って室内空気に拡散させるアロマオイルについても同じである。
乳幼児は微量のエッセンシャルオイルに反応することがある。以下に「エッセンシャルオイル」についてのFAQを準備した。
Q. エッセンシャルオイル(精油)とは何か?
エッセンシャルオイルは特有の香りのある植物由来又は合成の揮発性脂溶性液状物質の異なる混合物である。油脂と違ってエッセンシャルオイルは完全に蒸発する。この混合物は多様な化学物質からなるが多くはテルペンである。
Q. どのように作用するか?
エッセンシャルオイルは吸入されれば粘膜から取り込まれ、口から入れれば胃から、皮膚に塗ると皮膚から吸収され、異なる臓器に到達する。また鼻からは嗅神経で電気化学信号を生じて脳に情報を伝える。脳は多様なホルモンを産生し免疫系に影響するのでエッセンシャルオイルが健康に影響を与える可能性がある。吸収された物質は腎臓で分離されて排泄され、一部は肺から呼気に排出される。
Q. エッセンシャルオイルはどのような目的で使用されるか?
使用方法は様々である。食べた場合は食欲増進や消化促進、入浴剤としても使われ、血液循環促進用にも使われる。香りを利用して化粧品や芳香剤としても使われる。風邪などのときは症状緩和目的で使われる。治療用や化粧品用のエッセンシャルオイルには通常希釈製品が使われるが、希釈しない精油も販売されている。
Q. 乳幼児にエッセンシャルオイルを使う場合の注意点は?
乳幼児に希釈していないエッセンシャルオイルは使ってはいけない。数滴を鼻や口に入れただけでも乳幼児に喉頭痙攣や呼吸停止などの命に関わる反応を誘発する可能性がある。さらに粘膜を刺激し嘔吐や運動障害、けいれんなどの副作用の危険性がある。
従って乳幼児には希釈した製品のみを使うべきである。疑わしい場合には医師や薬剤師に相談すること。樟脳などの強力なエッセンシャルオイルは使うべきではない。希釈は用法に従うこと。顔に使ってはいけない。子どもの皮膚に直接使用しない。エッセンシャルオイルは子どもの手の届かないところに保管すること。
Q. 特に子どもに危険なエッセンシャルオイルはあるか?
3才以下の子どもに対してはメントール、樟脳、ユーカリに注意すること。
Q. 中毒事例はよくあるか?
BfRにはエッセンシャルオイルの中毒事例がよく報告される。さらに中毒情報センターにも多くの問い合わせがある。子どもはしばしば意図せず吸入したり飲み込んだりする。エッセンシャルオイルの使用が一般に広がっているため事故の可能性も多い。
Q. 間違って与えてしまったり中毒症状が出たらどうすればよいか?
もし子どもに呼吸困難や意識レベルの変化などの急性中毒症状が出たら直ちに救急車を呼ぶこと。皮膚につけた場合は水で良く洗う、飲んでしまった場合は水やジュースなどを飲ませて希釈し、中毒情報センターに連絡すること。暴露量と物質の種類によっては家庭で様子を見るだけで良い。樟脳の場合は水やジュースを飲ませた後直ちに病院に連れて行くこと。
Q. 各種エッセンシャルオイルのリスク評価は行われているか?ティーツリーオイルについてはBfRが声明を発表している。ティーツリーオイルは医薬品ではないため有効性と健康リスクについては評価していない。
希釈されていない濃縮ティーツリーオイルが化粧品用に流通している。
ティーツリーオイルはニキビや皮膚感染症などに宣伝されているが、アレルギー誘発性があるためBfRは希釈されていない製品は販売すべきではないという意見である。
化粧品中のティーツリーオイルの最大量は1%に制限すべきである。他に各種エッセンシャルオイルの化粧品への使用量制限を設けている。皮膚に残る製品についてはユーカリ油や樟脳、メントール、サリチル酸メチルについては最大1%、洗い流す製品については樟脳5%、メントール4%、サリチル酸メチル2.5%を推奨している。有害な可能性のある成分については欧州評議会出版物を参照すること。
化粧品に使われる植物−Volume III:有害な可能性のある成分(2006)
Plants used in cosmetics - Volume III: Potentially harmful components (2006)
http://
化粧品に使われる植物−Volume III:有害な可能性のある成分(2006)
Plants used in cosmetics - Volume III: Potentially harmful components (2006)
http://
リスクのある24物質についてのデータシート
アルブチン、ベータアサロン、樟脳、カプサイシン、クメストロール、ダイゼイン及びゲニステイン、エレミシン、エモジン、エスシン、エストラゴール、ユーカリプトール、ヒペリシン、イソサフロール、メントール、サリチル酸メチル、ミリスチシン、PAH(木材タール)、ピロリジジンアルカロイド、ケルセチン、キニーネ、ルチン、ステビオシド、ツジョン、チモール
□ BfR [ Bundesinstitut fur Risikobewertung ] ドイツ連邦リスクアセスメントのこと
□ [CAM]はComplementary and Alternative Medicine(補完代替療法)のこと
EU
■ティーツリーオイル
Tea Tree Oil
http://
エッセンシャルオイルの一種
データは少ないが、市販の希釈されていないティーツリーオイルは安全ではないことを示唆する。申請者による安全性データは不十分である。
化粧用品中での安定性には疑問があり、ティーツリーオイルの特定のための標準法が必要である。
皮膚及び目の刺激性試験法は適切ではない。亜慢性毒性・経皮吸収・遺伝毒性/発がん性・生殖毒性に不備があり化粧用品中のティーツリーオイルの安全性を評価できない。
□ EU [ European Union・Food Safety : from to the Fork ] 欧州連合のこと
■[論文]嗅覚の気分や自律神経系、内分泌系及び免疫機能への影響
Olfactory influences on mood and autonomic, endocrine, and immune function
Janice K. Kiecolt-Glaser et al.
Psychoneuroendocrinology Volume 33, Issue 3, April 2008, Pages 328-339
56人の男女に寒冷昇圧ストレスを与える前後にラベンダー、レモン、水のどれかの臭いを嗅いでもらった。臭いについての情報を全く与えない場合と、先にどういう臭いを嗅いでもらうのか、その臭いに期待される効果は何かについて情報を与えた場合との比較も行った。自己申告で報告された「気分」については、レモンオイルはポジティブな気分を有意に増強した。さらにレモンは寒冷昇圧ストレスによるノルエピネフリンレベルの上昇が持続した。IL-6やIL-10、コルチゾール、心拍数、血圧、皮膚のバリア修復、痛みなどは臭いによって変化しなかった。
この論文をメディアが一斉に伝えている。
□アロマセラピーに過剰な期待は禁物
アロマセラピーでよく用いられる2つの香り、レモンとラベンダーの効能を検討したところ、片方は一時的に気分を改善したものの、どちらも創傷治癒や疼痛軽減、免疫状態の改善には有用でなく、蒸留水のほうが健康に良い効果をもたらすケースもあるとの研究結果が、医学誌「Psychoneuroendocrinology」オンライン版4月号で報告された。
花から抽出した精油が、健康で幸福な状態(well-being)を向上させるというアロマセラピーの信奉者は多く、広く使用されているが、その有効性を示す科学的データはほとんどない。今回、米オハイオ州立大学健康心理学部長のJanice Kiecolt-Glaser氏らは、蒸留水を対照として、刺激性で気分を高揚させるというレモンと、リラックス効果を持ち、睡眠を助けるとされるラベンダーの香りについて検討した。
同氏らは、十分な嗅覚を持つ56人を対象に、3回の半日セッションを行い、被験者の半数には香りの種類と期待される効果を事前に説明し、残り半数には果物や花の香りであることのみ告げた。その後、レモン油、ラベンダー油、蒸留水のいずれかを含ませた綿ボールを、被験者の鼻の下にテープで貼り、血圧と心拍数をモニターした。
また、各被験者から血液を採取し、インターロイキン‐6(IL-6)やIL-10などの生化学マーカー、ストレスホルモンのコルチゾルやノルエピネフリン(注)の変化も分析。次に、皮膚の特定部位にテープを貼って剥がすことを繰り返す標準的な検査で被験者の治癒力を、また足を冷水(摂氏0度)に浸すことで疼痛に対する反応を調べた。気分およびストレスは、3つの標準的な心理テストを用いて評価した。
その結果、レモン油では明らかな気分高揚がみられたが、ラベンダー油ではみられなかった。いずれの香りもストレスや疼痛コントロール、創傷治癒の生化学マーカーに有益な影響は認められなかった。Kiecolt-Glaser氏は「香りを楽しむならそれで良いが、心理状態の変化や本当に健康に有効であることは期待すべきでない」としている。
注: ノルエピネフリンとはノルアドレナリンのこと。
ストレス・ホルモンの1つであり、注意と衝動性(impulsivity)が制御されている人間の脳の部分に影響する。
ワシントンポスト
アロマテラピーは思ったより効かない
March 5, 2008
http://
著者はアロマテラピーに大金をはたく前に考えるよう言っている。
好きな香りで良い気分になるならそれで良し、それ以上の身体への影響は期待するな、とのこと。
|
|
|
|
|
|
|
|
科学ニュース 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
科学ニュースのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55348人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 89991人
- 3位
- 酒好き
- 170657人
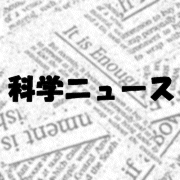


![[dir]物理学全般](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/98/58/459858_7s.jpg)




















