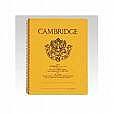日銀展望レポート(09年4月)が公表されました。
要約
http://
全文
http://
適当に解説していきたいと思います。でも僕は日銀の人でも何でもないので、どこまで本当なのかは保証できません。ま、個人的意見ということで。
要約
http://
全文
http://
適当に解説していきたいと思います。でも僕は日銀の人でも何でもないので、どこまで本当なのかは保証できません。ま、個人的意見ということで。
|
|
|
|
コメント(11)
まず、一番新聞の紙面とかで注目されるのが、「政策委員の大勢見通し」というやつです。11ページ目にあります。これを見ると、08年度、09年度、10年度のGDPやら消費者物価指数やらの見通しが載ってます。カッコの中の中央値が市場参加者の注目するところのようです。08年度はもう大体数字が固まっているので、09年度を見てみましょう。
09年度
実質GDP ▲3.1%
CPI(消費者物価)▲1.5%
大体これは政府見通しと同じです。
政府見通しはそれぞれ▲3.3%、▲1.3%です。
政府見通し
http://www5.cao.go.jp/keizai1/2009/0427zantei.pdf
の3ページ目にあります。
政府と日銀の違いははっきり言って誤差の範囲内です。日銀も、政府の経済対策がある程度景気を押し上げる効果を見ていることになります。
で、日銀のほうに戻りますが、もう少し注目してみたいのが、10年度の見通しです。GDPは+1.2%となっています。最初のページの脚注で潜在成長率を+1%前後としているので、10年度には景気は回復しているということになります。最も消費者物価は▲1%でデフレです。余談ですが、このまま行くと年金財政は徐々に痛みそうです。政策金利も上がらないでしょう。つまり預金金利は低いままです。海外金利が上昇していくようになれば、安定的な経済成長のもとでまた金利差に注目が集まって、円キャリー復活、そして円安トレンド復活というふうになるのかもしれませんね。日銀のシナリオ通りに事が運べば。
もっとも、日銀のシナリオ通りに事が運んだことは、ここ最近ありませんので注意が必要です。
09年度
実質GDP ▲3.1%
CPI(消費者物価)▲1.5%
大体これは政府見通しと同じです。
政府見通しはそれぞれ▲3.3%、▲1.3%です。
政府見通し
http://www5.cao.go.jp/keizai1/2009/0427zantei.pdf
の3ページ目にあります。
政府と日銀の違いははっきり言って誤差の範囲内です。日銀も、政府の経済対策がある程度景気を押し上げる効果を見ていることになります。
で、日銀のほうに戻りますが、もう少し注目してみたいのが、10年度の見通しです。GDPは+1.2%となっています。最初のページの脚注で潜在成長率を+1%前後としているので、10年度には景気は回復しているということになります。最も消費者物価は▲1%でデフレです。余談ですが、このまま行くと年金財政は徐々に痛みそうです。政策金利も上がらないでしょう。つまり預金金利は低いままです。海外金利が上昇していくようになれば、安定的な経済成長のもとでまた金利差に注目が集まって、円キャリー復活、そして円安トレンド復活というふうになるのかもしれませんね。日銀のシナリオ通りに事が運べば。
もっとも、日銀のシナリオ通りに事が運んだことは、ここ最近ありませんので注意が必要です。
では展望レポートの続きです。全文p3(以下、ページ番号はすべて全文です)の経済見通しが出てますが、よくエコノミストが言及するのが、日銀の景気判断です。
今回は「わが国経済は、大幅に悪化している」でした。
これは、4月8日の金融経済月報と同じ表現で、日銀は景気判断を変えていません。だからどうだ、というわけでもないんですが、かつてはここを見て、日銀の利上げが近いとか次は利下げだとかいろいろ言う人もいました。まあ今の状況じゃあまり関係ないでしょう。ちなみに、野村のレポートでは次は量的緩和だみたいなことも書いてあります。つまり金利をゼロにして当座預金の目標額を設定するというかつての政策に逆戻りするということですね。
しかし、たぶんそんなことはもうないでしょう。そうすることにどれだけの意味があるのか?時間軸効果か?時間軸効果というのは、当座預金の残高を引き上げることによってゼロ金利が長く続くことを民間主体に思い込ませ、その期待によって長期金利などを下げて金融緩和効果をもたらす、というやつです。
が、あまり目に見えて成功するものでもありません。それよりも、金利効果を減殺する、あるいは封殺する負の効果のほうが大きい、というのが日銀の白川総裁の判断でしょう。マーケットにマネーの量が供給されても必要なところに行き渡らなければマネーの意味がない。北朝鮮に食糧を援助しても貧しい庶民に行き渡らなければ意味がないのです。それを行き渡らせるのが、金利効果というわけだ。だから多分政策金利は0.1%で変わらずでしょう。
この点、野村のレポートは少し間違っているのではないかと思います。私のような若輩が経験豊かな多数のエコノミストを抱える野村を批判するのも気が引けますが。でも多くのの他社のエコノミストも量的緩和への移行を否定している感じがするので、まあいいんじゃないかと思います。
もっとも最近は日銀の金融政策で長期金利が動くことも少なそうです。
今回は「わが国経済は、大幅に悪化している」でした。
これは、4月8日の金融経済月報と同じ表現で、日銀は景気判断を変えていません。だからどうだ、というわけでもないんですが、かつてはここを見て、日銀の利上げが近いとか次は利下げだとかいろいろ言う人もいました。まあ今の状況じゃあまり関係ないでしょう。ちなみに、野村のレポートでは次は量的緩和だみたいなことも書いてあります。つまり金利をゼロにして当座預金の目標額を設定するというかつての政策に逆戻りするということですね。
しかし、たぶんそんなことはもうないでしょう。そうすることにどれだけの意味があるのか?時間軸効果か?時間軸効果というのは、当座預金の残高を引き上げることによってゼロ金利が長く続くことを民間主体に思い込ませ、その期待によって長期金利などを下げて金融緩和効果をもたらす、というやつです。
が、あまり目に見えて成功するものでもありません。それよりも、金利効果を減殺する、あるいは封殺する負の効果のほうが大きい、というのが日銀の白川総裁の判断でしょう。マーケットにマネーの量が供給されても必要なところに行き渡らなければマネーの意味がない。北朝鮮に食糧を援助しても貧しい庶民に行き渡らなければ意味がないのです。それを行き渡らせるのが、金利効果というわけだ。だから多分政策金利は0.1%で変わらずでしょう。
この点、野村のレポートは少し間違っているのではないかと思います。私のような若輩が経験豊かな多数のエコノミストを抱える野村を批判するのも気が引けますが。でも多くのの他社のエコノミストも量的緩和への移行を否定している感じがするので、まあいいんじゃないかと思います。
もっとも最近は日銀の金融政策で長期金利が動くことも少なそうです。
「国際的な金融と実体経済の負の相乗作用の帰趨」について、展望レポートではいかのように書かれています。
「昨年秋以降、金融資本市場の混乱は、米欧のみならず、新興国・資源国にも波及し、実体経済と金融の負の相乗作用は、世界的に強まっている。各種政策にもかかわらず、資産価格の下落や実体経済の悪化が続く場合には、負の相乗作用が強まり、海外経済が更に下振れたり、回復のタイミングが遅れるリスクがある。また、金融資本市場の緊張が緩和された後も、しばらくは、金融機関や投資家の慎重なリスクテイク姿勢が続き、実体経済活動を抑える要因となる可能性もある。更には、各国における景気回復が遅れた場合、保護主義的な動きが拡がり、貿易や金融取引の縮小を通じて、世界経済を更に下押しするリスクにも注意する必要がある」
いちいちごもっともだと思います。若手エコノミストにとっては日銀の展望レポートは勉強するための格好の材料にもなります。では細かく見ていきます。
資産価格の下落、実体経済の悪化ですが、個人的にはこのリスクはだいぶ少なくなってきたというのが実感です。もっとも、資産価格の下落は住宅や地価のような流動性の低いものに関してはまだ続くと思われます。しかし、株価などは底を打ったような気もします。根拠を求められると少し薄弱なのですが、米銀ストレステストの結果などは、おそらく悲観論を払しょくするのに役立つでしょう。もっとも、金融機関の痛みが続く間は株価の急騰も見込みがたいでしょうが。
そういう意味で、慎重なリスクテイクが経済活動を抑える働きは長引くと思われます。貸出が少しばかり抑制される感じがしますね。米欧では。
あと保護主義はそんなに心配しなくてもよさそうです。多少は台頭しますが、それが世界経済の足を大きく引っ張るようなことにはならないでしょう。1930年代の教訓が十分活かされていると言えるんじゃないでしょうか。多くの人は戦争よりは不景気のほうがまだマシだ、と考えてるはずですし。
「昨年秋以降、金融資本市場の混乱は、米欧のみならず、新興国・資源国にも波及し、実体経済と金融の負の相乗作用は、世界的に強まっている。各種政策にもかかわらず、資産価格の下落や実体経済の悪化が続く場合には、負の相乗作用が強まり、海外経済が更に下振れたり、回復のタイミングが遅れるリスクがある。また、金融資本市場の緊張が緩和された後も、しばらくは、金融機関や投資家の慎重なリスクテイク姿勢が続き、実体経済活動を抑える要因となる可能性もある。更には、各国における景気回復が遅れた場合、保護主義的な動きが拡がり、貿易や金融取引の縮小を通じて、世界経済を更に下押しするリスクにも注意する必要がある」
いちいちごもっともだと思います。若手エコノミストにとっては日銀の展望レポートは勉強するための格好の材料にもなります。では細かく見ていきます。
資産価格の下落、実体経済の悪化ですが、個人的にはこのリスクはだいぶ少なくなってきたというのが実感です。もっとも、資産価格の下落は住宅や地価のような流動性の低いものに関してはまだ続くと思われます。しかし、株価などは底を打ったような気もします。根拠を求められると少し薄弱なのですが、米銀ストレステストの結果などは、おそらく悲観論を払しょくするのに役立つでしょう。もっとも、金融機関の痛みが続く間は株価の急騰も見込みがたいでしょうが。
そういう意味で、慎重なリスクテイクが経済活動を抑える働きは長引くと思われます。貸出が少しばかり抑制される感じがしますね。米欧では。
あと保護主義はそんなに心配しなくてもよさそうです。多少は台頭しますが、それが世界経済の足を大きく引っ張るようなことにはならないでしょう。1930年代の教訓が十分活かされていると言えるんじゃないでしょうか。多くの人は戦争よりは不景気のほうがまだマシだ、と考えてるはずですし。
だいぶコメントが遅れてしまいました。
次の、「世界各国で取り組んでいる各種政策の影響」ですが、今の段階で結論づけるのは早すぎるのはもちろんです。しかし、大方の意見を集約して、なおかつ私見を述べるのであれば、たぶん米国の信用市場に対する政策はあらかた終わって、それでもって、ガイトナー米財務長官が言っていたような気がするのだけれど、米国の銀行システムに対する政策も、だいたい終わったのではないかと思います。つまり、金融面からはある程度落ち着いてきたかなと。景気回復の必要条件は、多少整ってきました。しかし、米国の住宅バブルが弾けたということには変わりありません。今後の米国の消費はパッとしない状況が続くでしょう。だから、景気は本格回復には至らないような気がします。
白川さんもこないだ講演で「偽りの夜明け」という言葉で表現していましたが、財政政策の影響で少し景気が回復したように見えても、政策が息切れするとすぐ景気の腰は折れてしまうと思います。市井のエコノミストも、4-6月は景気が多少いい(GDPは前期比プラス)としても7-9月にまた悪くなってしまうだろう(再びマイナスへ)、というようなイメージを持っている人が多いようです。
次の、「世界各国で取り組んでいる各種政策の影響」ですが、今の段階で結論づけるのは早すぎるのはもちろんです。しかし、大方の意見を集約して、なおかつ私見を述べるのであれば、たぶん米国の信用市場に対する政策はあらかた終わって、それでもって、ガイトナー米財務長官が言っていたような気がするのだけれど、米国の銀行システムに対する政策も、だいたい終わったのではないかと思います。つまり、金融面からはある程度落ち着いてきたかなと。景気回復の必要条件は、多少整ってきました。しかし、米国の住宅バブルが弾けたということには変わりありません。今後の米国の消費はパッとしない状況が続くでしょう。だから、景気は本格回復には至らないような気がします。
白川さんもこないだ講演で「偽りの夜明け」という言葉で表現していましたが、財政政策の影響で少し景気が回復したように見えても、政策が息切れするとすぐ景気の腰は折れてしまうと思います。市井のエコノミストも、4-6月は景気が多少いい(GDPは前期比プラス)としても7-9月にまた悪くなってしまうだろう(再びマイナスへ)、というようなイメージを持っている人が多いようです。
コメントが遅れ遅れになってもうしわけありません。
第3に、企業の中長期的な成長期待の動向、とありますが、日銀はここを結構注目しているのかもしれません。日銀というより、白川総裁ですが。白川さんは京都大学の教授時代に、なぜ日本が90年代の後半にデフレスパイラルに陥らなかったのかということに関し、中長期的な企業の期待成長率が高かったから、ということを挙げています。
内閣府に「企業行動に関するアンケート調査」というものがあり、その図1-1には、期待成長率の推移が示されているわけですが、それが近年結構下に向いている。長期的な期待成長率も90年代後半より低い。ここのところが気にかかる、と日銀は思っているのではないでしょうか。
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html
多分、日本の成長率というのはこれからますます低空飛行が続くのでしょうね。でもそれは、足元の話ではなくてもっと長期的な話です。
第3に、企業の中長期的な成長期待の動向、とありますが、日銀はここを結構注目しているのかもしれません。日銀というより、白川総裁ですが。白川さんは京都大学の教授時代に、なぜ日本が90年代の後半にデフレスパイラルに陥らなかったのかということに関し、中長期的な企業の期待成長率が高かったから、ということを挙げています。
内閣府に「企業行動に関するアンケート調査」というものがあり、その図1-1には、期待成長率の推移が示されているわけですが、それが近年結構下に向いている。長期的な期待成長率も90年代後半より低い。ここのところが気にかかる、と日銀は思っているのではないでしょうか。
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html
多分、日本の成長率というのはこれからますます低空飛行が続くのでしょうね。でもそれは、足元の話ではなくてもっと長期的な話です。
第4の、国内の金融環境の状況。企業金融が干上がってしまったため、4月時点ではなかなかタイトな金融状況でしたが、最近は多少はマシになっているのではないかなと思います。国際金融情勢の緊張は今のところは強まっていないし、日本の金融システムの安定性が崩れるようなこともありません。日本の金融システムの頑健性については、日銀は「金融システムレポート」でシミュレーション済みです。もっとも、金融と実体経済の負の相乗作用、には気をつけようか、というところだろうと思います。
またここで、日銀は「緩和的な金融環境が続く場合、金融・経済活動や物価の振幅が大きくなるリスク」について述べています。この手のリスクについては、今後常にかかれそうな感じですね。景気がよかろうが悪かろうが。
またここで、日銀は「緩和的な金融環境が続く場合、金融・経済活動や物価の振幅が大きくなるリスク」について述べています。この手のリスクについては、今後常にかかれそうな感じですね。景気がよかろうが悪かろうが。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
金融と経済に関する勉強会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
金融と経済に関する勉強会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90054人
- 2位
- 酒好き
- 170690人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208287人