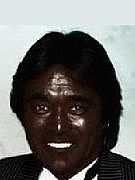シマノ事例のまとめ
・ シマノは自転車部品部門が売上68%、釣具が30%を占めている。そのほか、自動車のギア、スノーボード、ゴルフクラブなども生産している。
・ 海外への展開の流れは1960年代から米国、1970年代から欧州に進出し、現地に販売法人を設立していった。また、1973年にはシンガポールで工場生産をスタートしている。
・ 消費地の分布としては51%が欧州、26%が北米、14%が日本、残りがその他である。
・ シマノは完成品を手がけずに部品だけにこだわった一貫した経営方針をとってきた。
・ 1973年、シマノは部品をグループ化して売るデュラエース・シリーズを発売する。
相互に機能しなければならないという「システム・コンポーネントの理念」が生まれ、これにより機能、性能面を重視した開発に移っていく。
・ シマノインデックスシステム(SIS)
変速レバーをシフト分動かすと後変速機が正確に一段分ギアチェンジするシステム。これによって誰でも簡単にギアチェンジができるようになった。また、シマノはSISを導入する際に今までの顧客も考えフリクション式も使えるようにした。
それぞれが専業メーカーとして1つ1つを担当していたのでそのアイデアが出づらかった。
・ MTBニューデオーレXTシリーズ
1982年他社に先駆けて、MTB市場に乗り出し、「デオーレXT」を発売する。その後、シマノは1986年にMTB 用にSISを組み込んだ 「ニューデオーレXTシリーズ」を発売する。 またインデックスを開発できたのは、フリーハーブやUGギアなどの技術の蓄積があったためであった。
・ シマノ・トータル・インテグレーション
これによってシマノはシステム化を更に進め地位を不動のものにした。これは変速操作ブレーキを一体化したものであった。ロードレーサー用のデュアルコントロールレバー、MTB用がラピッドファイヤーと呼ばれるもので、SIS,シマノ・リニア・レスポンス、HGギア、などをあわせて、1989年から投入した。
・ システム・コンポーネント
インターフェースが標準化され、個々の部品ごとに分業されていた自転車業界の中、シマノはそれまで個別に扱われてきた変速機、シフトレバー、ブレーキなどを集合体として捉え、システムとして統合化することで新しい価値を見出した。
シマノが部品技術を効果的に改善していけたのは、部品のことだけでなく、最終顧客のニーズを把握すると同時に、そのニーズを満たす完成車の姿をきちんと描いていたからである。
・ エンドユーザー
シマノは早い段階から欧州のロードレースに入り込み完成車としての自転車全体に対する要求を直接取り入れようとした。自らが市場と接する機会を設け自転車の普遍的なニーズを汲み取る必要があった。
シマノは部品メーカーであったためどうしても最終的な商品についてのイメージを効果的なものにするために外部の企業の協力も必要となってくる。そのためSISの開発の際には完成車メーカーの方に何度も通い、組み立て方についてこと細かく注文を回った。
同時にテクニカルインフォメーションといって、新しい部品を使う上での技術的な留意点を記した資料をメーカーやディーラーに流しシステムが正常に動くように協力してもらった。
・ 生産技術と市場の創造
シマノは高品質な部品を作る際のコストを冷間鍛造技術を用いて下げている。高温での鍛造に比べ、強度、精度が高く、効率的な生産が可能になる。熱による変形もないので制度出しの工程も不要になる。
またシマノは市場を自ら作ることによってコスト増を乗り越えた。SISは割高であったため、まずハイエンドのプロ選手にその価値を認めさせ、そこからローエンドに向けて市場を拡大していった。
シマノは米国での失敗で、不良品の回収のためディーラーを直接回ることで、色々な情報を得ることができることを学んだ。シマノはその後ディーラーキャラバンと称して、現地のスタッフと日本のスタッフが組んで世界中の販売店を回るようになった。
その他にもシマノはロードレースのプロチームに技術者をメカニックとして派遣したり、様々な自転車のレースやイベントも企画している。
・ 今後の動向
現在、依然としてトップシェアを保っているシマノであるが、未だ競争の激化と成熟化という問題を抱えている。他社はシマノと互換性のある部品を発売し、MTB市場が一般大衆に普及してくるにつれて、必ずしも高度な製品を求めないユーザーに安く提供し始めたからである。また米国の独禁法などでSISなどの販売が難しくなってきている。また1993年以降MTB市場の成長も頭打ちとなり、コンフォート市場などの新たな市場の開拓、製品イノベーションが求められている。
説明用
大店法廃止により、日本が受ける海外の圧力
・大店法廃止から大店立地法へ
大店法は97年の12月に廃止され、大店立地法へと変わった。73年に施行された大店法は小売店の保護を目的とした法律であり、大型店が出店した時に中小小売業営業を保護しようとする法律であった。
その後中小小売業者から規制がまだ甘いと要請を受け、第2種大型店舗というものを制定し、500平方メートル以上というような大型点とは呼べないようなものまで規制するようになった。これらの規制はすべて中小小売業を守るためであり、小売業の活性化、あるいは商店街の活性化を期待したためであった。
しかし、実際のところ小売業はどんどん減少していき、商店街も低迷していった。またそのころ、日米貿易のバランスを見るとアメリカに対する赤字が大きく、大店法の規制を解除し、アメリカ製品を売る大型店を積極的に作るべきだという、アメリカ側の強い要請があったのも影響し、大店法は廃止された。
その後大店法に代わって、大店立地法というものが制定された。これは、今までの大店法のような大型店の出店を規制するような法律ではなく、大型店の出店による、地域環境の悪化を防止するための制度であった。
・大店法の廃止により、大型店の出店がしやすくなり、90年代になってから、欧米の企業が日本に出店してくるようになった。例としては、アメリカのウォルマートやトイザらス、フランスのカルフールなど、その他多くの大企業が日本に進出してきた。
これらの企業が日本に進出してきた理由としては、自国でのシェアがもうそれ以上アップできない状態にあったことである。株主に株を買ってもらい株価を高めるためには引き続き高成長を遂げる戦略をしていかなければならなかったことが挙げられる。
またもう一つの理由としては、日本の流通構造が遅れており、日本に進出すれば市場を席巻し、一挙に売上をつくれるとみたからである。その原因は2つあり、1つは顧客満足の問題で、消費が多様化してくると消費者は業種小売業では満足できなくなる。これにこたえるには業態小売業であるが、日本はその開発が遅れていた。2つ目は、零細店が多く、大規模な店ができると小規模で限定品ぞろえの店は対抗できない。日本はこれをサービスでカバーしようとするが売り場面積があまりに違う場合は不可能である。このような理由から多くの企業が参入して来た。
・日本進出を仕掛けてくるアメリカ企業には主に5つの特色がある。
第1にはっきりとした長期経営計画を持って日本での店舗展開を図り、短期間にチェーン展開をし、一挙に大きくすることを目的としている。一挙に大きくし株価を高め、高配当をすることが優れた経営者として評価されるからである。
第2には、日本の流通機構にかかわりなく、アメリカ式のメーカー直接取引を行うことである。これにより、流通コストをカットし、より安く消費者に商品を提供できる。日本でもトイザらスなどの参入の影響を受け、卸を必要としない取引をする大手小売企業が増え、卸売り業の売上は減っていた。
第3には日本ではそれまで考えられないような大型店を展開し高い売上を実現していくことである。アメリカは日本と違って土地も広く、地価も安いので、路面店も中小商店といえど、日本よりはるかに大きい店が多かった。こうした中で生まれた専門スーパーストアは品ぞろえの幅、奥行きと共に、従来の専門店よりはるかに大きくし、従来の専門店、大型店の専門品売り場を包み込むために2000〜3000平方メートルという大型店を展開し始めた。日本に進出してくる従来型専門店、専門店スーパーストアは大型化したまま日本に持ち込まれるので日本からみると非常識なくらい大きいがアメリカでは普通なのである。
第4には店舗を展開していないうちから、物流センターをつくり、低コスト、自家物流の体制をつくることである。これによって当初からメーカーとの取引を意識し、最初から物流センターを持っていることでぎりぎりまで価格交渉ができるのである。
第5には自社より安いところがあれば、差額を返金するといった低価格保障と、使ったもの封を切ったものも返品を受け入れる無条件返品サービスを入れることである。これらを入れるのは自社の価格と品質に自信を持っているからである。
レジュメ用
・大店法廃止から大店立地法へ
大店法は大型店から中小小売業者を保護し、小売業回の活性化を図るために施行されたものである。その後大店法は廃止され、大店立地法に代わっていった。
大店法廃止の背景
その1 大店法により小売業回の活性化を図ったが、逆に衰退していったため。
その2 アメリカからの大店法廃止の強い要望があったため。
今までの大店法のような大型店の出店を規制するような法律ではなく、大型店の出店による、地域環境の悪化を防止するための制度であった。
・海外企業の参入
大店法の廃止により、大型店の出店がしやすくなり、90年代になってから、欧米の企業が日本に出店してくるようになった。例としては、アメリカのウォルマートやとイザらス、フランスのカルフールなど、その他多くの大企業が日本に進出してきた。
参入理由
その1 自国でのシェアアップがそれ以上望めない状態であったため、更なる成長を求めるため日本に参入してきた。
その2 消費の多様化や、零細企業の多さに関係して、日本に大型店で進出すれば市場を席巻し、一挙に売上をつくれるとみたからである。
・日本進出を仕掛けるアメリカ企業の5つの特色
1 短期間にチェーン展開する。
2 メーカー直接取引を強引に進める。
3 日本では考えられない大型店を展開。
4 最初に物流センターを自前つくる。
5 低価格保証と無条件返品がサービス条件である。
日本に進出してくる欧米の流通業は世界戦略を展開している企業が多いが、一挙に日本の企業世合弁会社を作って上陸してくるものと、東南アジアに進出して、そこを足掛かりとして東南アジアの一環として進出してくるものと、カタログ販売でテストを展開の見通しがついてから進出するものの3つに分けられる。
・ シマノは自転車部品部門が売上68%、釣具が30%を占めている。そのほか、自動車のギア、スノーボード、ゴルフクラブなども生産している。
・ 海外への展開の流れは1960年代から米国、1970年代から欧州に進出し、現地に販売法人を設立していった。また、1973年にはシンガポールで工場生産をスタートしている。
・ 消費地の分布としては51%が欧州、26%が北米、14%が日本、残りがその他である。
・ シマノは完成品を手がけずに部品だけにこだわった一貫した経営方針をとってきた。
・ 1973年、シマノは部品をグループ化して売るデュラエース・シリーズを発売する。
相互に機能しなければならないという「システム・コンポーネントの理念」が生まれ、これにより機能、性能面を重視した開発に移っていく。
・ シマノインデックスシステム(SIS)
変速レバーをシフト分動かすと後変速機が正確に一段分ギアチェンジするシステム。これによって誰でも簡単にギアチェンジができるようになった。また、シマノはSISを導入する際に今までの顧客も考えフリクション式も使えるようにした。
それぞれが専業メーカーとして1つ1つを担当していたのでそのアイデアが出づらかった。
・ MTBニューデオーレXTシリーズ
1982年他社に先駆けて、MTB市場に乗り出し、「デオーレXT」を発売する。その後、シマノは1986年にMTB 用にSISを組み込んだ 「ニューデオーレXTシリーズ」を発売する。 またインデックスを開発できたのは、フリーハーブやUGギアなどの技術の蓄積があったためであった。
・ シマノ・トータル・インテグレーション
これによってシマノはシステム化を更に進め地位を不動のものにした。これは変速操作ブレーキを一体化したものであった。ロードレーサー用のデュアルコントロールレバー、MTB用がラピッドファイヤーと呼ばれるもので、SIS,シマノ・リニア・レスポンス、HGギア、などをあわせて、1989年から投入した。
・ システム・コンポーネント
インターフェースが標準化され、個々の部品ごとに分業されていた自転車業界の中、シマノはそれまで個別に扱われてきた変速機、シフトレバー、ブレーキなどを集合体として捉え、システムとして統合化することで新しい価値を見出した。
シマノが部品技術を効果的に改善していけたのは、部品のことだけでなく、最終顧客のニーズを把握すると同時に、そのニーズを満たす完成車の姿をきちんと描いていたからである。
・ エンドユーザー
シマノは早い段階から欧州のロードレースに入り込み完成車としての自転車全体に対する要求を直接取り入れようとした。自らが市場と接する機会を設け自転車の普遍的なニーズを汲み取る必要があった。
シマノは部品メーカーであったためどうしても最終的な商品についてのイメージを効果的なものにするために外部の企業の協力も必要となってくる。そのためSISの開発の際には完成車メーカーの方に何度も通い、組み立て方についてこと細かく注文を回った。
同時にテクニカルインフォメーションといって、新しい部品を使う上での技術的な留意点を記した資料をメーカーやディーラーに流しシステムが正常に動くように協力してもらった。
・ 生産技術と市場の創造
シマノは高品質な部品を作る際のコストを冷間鍛造技術を用いて下げている。高温での鍛造に比べ、強度、精度が高く、効率的な生産が可能になる。熱による変形もないので制度出しの工程も不要になる。
またシマノは市場を自ら作ることによってコスト増を乗り越えた。SISは割高であったため、まずハイエンドのプロ選手にその価値を認めさせ、そこからローエンドに向けて市場を拡大していった。
シマノは米国での失敗で、不良品の回収のためディーラーを直接回ることで、色々な情報を得ることができることを学んだ。シマノはその後ディーラーキャラバンと称して、現地のスタッフと日本のスタッフが組んで世界中の販売店を回るようになった。
その他にもシマノはロードレースのプロチームに技術者をメカニックとして派遣したり、様々な自転車のレースやイベントも企画している。
・ 今後の動向
現在、依然としてトップシェアを保っているシマノであるが、未だ競争の激化と成熟化という問題を抱えている。他社はシマノと互換性のある部品を発売し、MTB市場が一般大衆に普及してくるにつれて、必ずしも高度な製品を求めないユーザーに安く提供し始めたからである。また米国の独禁法などでSISなどの販売が難しくなってきている。また1993年以降MTB市場の成長も頭打ちとなり、コンフォート市場などの新たな市場の開拓、製品イノベーションが求められている。
説明用
大店法廃止により、日本が受ける海外の圧力
・大店法廃止から大店立地法へ
大店法は97年の12月に廃止され、大店立地法へと変わった。73年に施行された大店法は小売店の保護を目的とした法律であり、大型店が出店した時に中小小売業営業を保護しようとする法律であった。
その後中小小売業者から規制がまだ甘いと要請を受け、第2種大型店舗というものを制定し、500平方メートル以上というような大型点とは呼べないようなものまで規制するようになった。これらの規制はすべて中小小売業を守るためであり、小売業の活性化、あるいは商店街の活性化を期待したためであった。
しかし、実際のところ小売業はどんどん減少していき、商店街も低迷していった。またそのころ、日米貿易のバランスを見るとアメリカに対する赤字が大きく、大店法の規制を解除し、アメリカ製品を売る大型店を積極的に作るべきだという、アメリカ側の強い要請があったのも影響し、大店法は廃止された。
その後大店法に代わって、大店立地法というものが制定された。これは、今までの大店法のような大型店の出店を規制するような法律ではなく、大型店の出店による、地域環境の悪化を防止するための制度であった。
・大店法の廃止により、大型店の出店がしやすくなり、90年代になってから、欧米の企業が日本に出店してくるようになった。例としては、アメリカのウォルマートやトイザらス、フランスのカルフールなど、その他多くの大企業が日本に進出してきた。
これらの企業が日本に進出してきた理由としては、自国でのシェアがもうそれ以上アップできない状態にあったことである。株主に株を買ってもらい株価を高めるためには引き続き高成長を遂げる戦略をしていかなければならなかったことが挙げられる。
またもう一つの理由としては、日本の流通構造が遅れており、日本に進出すれば市場を席巻し、一挙に売上をつくれるとみたからである。その原因は2つあり、1つは顧客満足の問題で、消費が多様化してくると消費者は業種小売業では満足できなくなる。これにこたえるには業態小売業であるが、日本はその開発が遅れていた。2つ目は、零細店が多く、大規模な店ができると小規模で限定品ぞろえの店は対抗できない。日本はこれをサービスでカバーしようとするが売り場面積があまりに違う場合は不可能である。このような理由から多くの企業が参入して来た。
・日本進出を仕掛けてくるアメリカ企業には主に5つの特色がある。
第1にはっきりとした長期経営計画を持って日本での店舗展開を図り、短期間にチェーン展開をし、一挙に大きくすることを目的としている。一挙に大きくし株価を高め、高配当をすることが優れた経営者として評価されるからである。
第2には、日本の流通機構にかかわりなく、アメリカ式のメーカー直接取引を行うことである。これにより、流通コストをカットし、より安く消費者に商品を提供できる。日本でもトイザらスなどの参入の影響を受け、卸を必要としない取引をする大手小売企業が増え、卸売り業の売上は減っていた。
第3には日本ではそれまで考えられないような大型店を展開し高い売上を実現していくことである。アメリカは日本と違って土地も広く、地価も安いので、路面店も中小商店といえど、日本よりはるかに大きい店が多かった。こうした中で生まれた専門スーパーストアは品ぞろえの幅、奥行きと共に、従来の専門店よりはるかに大きくし、従来の専門店、大型店の専門品売り場を包み込むために2000〜3000平方メートルという大型店を展開し始めた。日本に進出してくる従来型専門店、専門店スーパーストアは大型化したまま日本に持ち込まれるので日本からみると非常識なくらい大きいがアメリカでは普通なのである。
第4には店舗を展開していないうちから、物流センターをつくり、低コスト、自家物流の体制をつくることである。これによって当初からメーカーとの取引を意識し、最初から物流センターを持っていることでぎりぎりまで価格交渉ができるのである。
第5には自社より安いところがあれば、差額を返金するといった低価格保障と、使ったもの封を切ったものも返品を受け入れる無条件返品サービスを入れることである。これらを入れるのは自社の価格と品質に自信を持っているからである。
レジュメ用
・大店法廃止から大店立地法へ
大店法は大型店から中小小売業者を保護し、小売業回の活性化を図るために施行されたものである。その後大店法は廃止され、大店立地法に代わっていった。
大店法廃止の背景
その1 大店法により小売業回の活性化を図ったが、逆に衰退していったため。
その2 アメリカからの大店法廃止の強い要望があったため。
今までの大店法のような大型店の出店を規制するような法律ではなく、大型店の出店による、地域環境の悪化を防止するための制度であった。
・海外企業の参入
大店法の廃止により、大型店の出店がしやすくなり、90年代になってから、欧米の企業が日本に出店してくるようになった。例としては、アメリカのウォルマートやとイザらス、フランスのカルフールなど、その他多くの大企業が日本に進出してきた。
参入理由
その1 自国でのシェアアップがそれ以上望めない状態であったため、更なる成長を求めるため日本に参入してきた。
その2 消費の多様化や、零細企業の多さに関係して、日本に大型店で進出すれば市場を席巻し、一挙に売上をつくれるとみたからである。
・日本進出を仕掛けるアメリカ企業の5つの特色
1 短期間にチェーン展開する。
2 メーカー直接取引を強引に進める。
3 日本では考えられない大型店を展開。
4 最初に物流センターを自前つくる。
5 低価格保証と無条件返品がサービス条件である。
日本に進出してくる欧米の流通業は世界戦略を展開している企業が多いが、一挙に日本の企業世合弁会社を作って上陸してくるものと、東南アジアに進出して、そこを足掛かりとして東南アジアの一環として進出してくるものと、カタログ販売でテストを展開の見通しがついてから進出するものの3つに分けられる。
|
|
|
|
|
|
|
|
高井ゼミ7期ヒロキ帰って来いよ 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
高井ゼミ7期ヒロキ帰って来いよのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90061人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208321人
- 3位
- 酒好き
- 170698人