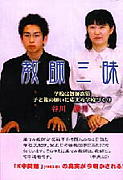氷山の一角――にもなっていないのではないか。
と思わせたのが二〇〇七年度、「指導力不足」教師が「371人」であったという文科省の調査である。(08.10.18日付新聞各紙)
二〇〇四年度の「566人」をピークに減り続けて、二〇〇七年度は「371人」だったという、その二〇〇四年にはあの「カッターナイフ殺人事件」があった。
二〇〇六年は、何度も繰り返すことになるが、北海道滝川市の「いじめ自殺・遺書隠し」発覚に端を発して「いじめ自殺」が相次ぎ、文科省への「自殺予告」の手紙が三八通を数えた。
いじめが社会問題化する中で、〇五年度までの七年間、「いじめ自殺」は「ゼロ」、いじめそのものも三万件から二万件でしかなかった、そんな文部省・文科省の調査そのものの洗い直しが求められた後の二〇〇六年度、一気にいじめは「6倍・12万件」であったと知らされて、またまた驚かされた。
そんな「時代」に、「指導力不足」の教師の数は減り続けていたというのは、何か、不思議な絵を見せられたような感じである。
「指導力減退の深刻度」
「学力低下は生徒だけの問題でない!!」
として『サンデー毎日』が教師の「不適格・指導力不足」を取り上げたのは2003年10月19日号だった。
「昔、デモシカ先生、今は理解できない・考えられない・自信がないの三無主義」というのは、八〇年代、、教師が子どもに「無気力・無関心・無感動」の「三無主義」とレッテル張りをしたことを引っかけたものである。
が「昔、デモシカ先生」として否定しているのは、事実と違う。七〇年代から八〇年代に「荒れ狂った」ともいうべき学校の秩序を回復・維持しようと孤軍奮闘したのは、いわゆる「でも・しか先生」とその後に続く世代の教師たちだった。
八〇年代に登場してくる「高学歴・高偏差値」教師と違って、高卒・詰め衿学生服のまま教壇に立つ人も多かった。着るものがなかったのである。信じてもらえないかもしれないが、ぼくが教師になったのは東京オリンピックの翌年(1965年)だったがスーツ一着そろえることが、今、車一台買うのと同じくらいの感覚であった。教師の給料では生活はできなかったのである。
当時の学校は子どもに学級費を納めさせていた。使途は学級で使う画びょうやマジック代、ぼくの場合、ここにはじめていうことだが月の後半、その学級費を「流用」してやりくりすることが何度もあった。
それよりもっと「貧しい」時代を生きた「でも・しか先生」たちは、生活感覚としての「教師力・教育術」を人の性質として持っている世代であった。
「三無主義」の時代に中高校生であった「高学歴・高偏差値」教師が、教壇に立つだけで足がふるえるというのは例外としても、「真面目」だけれど「軟弱」で小学生にさえ立ち向かって行けないというのとは全く違うのである。
教師は皆大学を卒業して免許を取得して教壇に立つわけで、ここで「高学歴」というのは奇異に思われるかもしれないが、ぼくらの時代までは、貧しい家庭のちょっとできる息子や娘が、教育大を出て教師になる、つまり教師は貧しき庶民の出身であったということだ。
しかし高度経済成長というものがあって、教師の給与も比較のしようもないくらいに良くなって、国立や有名私大出の「高偏差値」教師が教育現場に入ってくるようになった。教育大出の教師とは違うという意味で「高学歴」としたのは、詰め衿学生服で教壇に立って、お金をためてから大学に行き直したり、通信教育で教員免許を取得した教師たちとは生活体験がまるで違っていて、そのことが子どもと向き合ったときの決定的な違いとして現われる、それが「いじめ時代」の教育現場の最大の問題であるということを強調しておきたいからだ。
少し横にそれてしまったが『サンデー毎日』より半年前の二〇〇三年三月には新聞がこの「指導力不足」問題を取り上げていた。
早かったのは東京都で、不適格・指導力不足教師の再教育や、研修させても復帰させることのできない教師を一般行政職に転向させるなどの取り組みが五、六年前から始められていたというのであった。
精神的疾患で休職する教師が増えていると報じられたのもそのときがはじめてだったのではないか。
避地枝勤務なら駅やバス停まで十キロくらいの道のりを歩くしかなかった経験からすれば「ぜいたく病」といいたいが、二〇〇一年、その精神的疾患で休職する教師が「二千五百人」を超えていたという。
その二〇〇〇年代初頭の「指導力不足」教師は、全国でわずか「数十人」であった。七〇年代の末、北海道東部の町村で千六百人の中に、箸にも棒にもかからない「ダメ教師」が約二〇人、「80人に1人」の割合であったが、「事件」が起こることが当たり前になって、教師が精神を病んでいるときに、「ダメ教師」が90万人の中に「数十人」しかいない、それが「566人」になり、「371人」であったとして文科省がいう「調査」とはどんなものであるのだろうか。
指導力不足教師「371人」の八〇パーセント以上が四〇代、五〇代の教師であるという。この傾向は、調査が始まって以降ほとんど同じであったはずである。
すでに何十年も教壇に立っているわけだから「今さら」といいたくなる、いわれてしかたのないことだが、二〇〇三年、東京都の取り組みが紹介されたとき、「不適格」と認定された五〇代の女性教師は次のようにその憤懣をぶつけていた。
「揚げ足を取るような指摘ばかりだ。三〇年間、この指導で問題なかった」(2003.3.26付『読売新聞』)
と平然と語れる女性教師の意識と世間の常識のギャップの大きさに驚かされるが、「80人に1人」の「ダメ教師」の存在が道東だけのことではなかったということはできよう。
比べて精神を病んで休職する教師の「良心」をたたえなければならないとしたら、何か寂しい思いもするけれど、それでは、三〇代、二〇代の教師は大丈夫なのであろうか。
教師を目指す学生たちが、教室にいじめがあっても、止めさせる指導はしない、と明言していることについてはすでに書いたが、学生の先輩である二〇代、三〇代の教師は、今、教育現場で何をどうしているのであろうか。
と思わせたのが二〇〇七年度、「指導力不足」教師が「371人」であったという文科省の調査である。(08.10.18日付新聞各紙)
二〇〇四年度の「566人」をピークに減り続けて、二〇〇七年度は「371人」だったという、その二〇〇四年にはあの「カッターナイフ殺人事件」があった。
二〇〇六年は、何度も繰り返すことになるが、北海道滝川市の「いじめ自殺・遺書隠し」発覚に端を発して「いじめ自殺」が相次ぎ、文科省への「自殺予告」の手紙が三八通を数えた。
いじめが社会問題化する中で、〇五年度までの七年間、「いじめ自殺」は「ゼロ」、いじめそのものも三万件から二万件でしかなかった、そんな文部省・文科省の調査そのものの洗い直しが求められた後の二〇〇六年度、一気にいじめは「6倍・12万件」であったと知らされて、またまた驚かされた。
そんな「時代」に、「指導力不足」の教師の数は減り続けていたというのは、何か、不思議な絵を見せられたような感じである。
「指導力減退の深刻度」
「学力低下は生徒だけの問題でない!!」
として『サンデー毎日』が教師の「不適格・指導力不足」を取り上げたのは2003年10月19日号だった。
「昔、デモシカ先生、今は理解できない・考えられない・自信がないの三無主義」というのは、八〇年代、、教師が子どもに「無気力・無関心・無感動」の「三無主義」とレッテル張りをしたことを引っかけたものである。
が「昔、デモシカ先生」として否定しているのは、事実と違う。七〇年代から八〇年代に「荒れ狂った」ともいうべき学校の秩序を回復・維持しようと孤軍奮闘したのは、いわゆる「でも・しか先生」とその後に続く世代の教師たちだった。
八〇年代に登場してくる「高学歴・高偏差値」教師と違って、高卒・詰め衿学生服のまま教壇に立つ人も多かった。着るものがなかったのである。信じてもらえないかもしれないが、ぼくが教師になったのは東京オリンピックの翌年(1965年)だったがスーツ一着そろえることが、今、車一台買うのと同じくらいの感覚であった。教師の給料では生活はできなかったのである。
当時の学校は子どもに学級費を納めさせていた。使途は学級で使う画びょうやマジック代、ぼくの場合、ここにはじめていうことだが月の後半、その学級費を「流用」してやりくりすることが何度もあった。
それよりもっと「貧しい」時代を生きた「でも・しか先生」たちは、生活感覚としての「教師力・教育術」を人の性質として持っている世代であった。
「三無主義」の時代に中高校生であった「高学歴・高偏差値」教師が、教壇に立つだけで足がふるえるというのは例外としても、「真面目」だけれど「軟弱」で小学生にさえ立ち向かって行けないというのとは全く違うのである。
教師は皆大学を卒業して免許を取得して教壇に立つわけで、ここで「高学歴」というのは奇異に思われるかもしれないが、ぼくらの時代までは、貧しい家庭のちょっとできる息子や娘が、教育大を出て教師になる、つまり教師は貧しき庶民の出身であったということだ。
しかし高度経済成長というものがあって、教師の給与も比較のしようもないくらいに良くなって、国立や有名私大出の「高偏差値」教師が教育現場に入ってくるようになった。教育大出の教師とは違うという意味で「高学歴」としたのは、詰め衿学生服で教壇に立って、お金をためてから大学に行き直したり、通信教育で教員免許を取得した教師たちとは生活体験がまるで違っていて、そのことが子どもと向き合ったときの決定的な違いとして現われる、それが「いじめ時代」の教育現場の最大の問題であるということを強調しておきたいからだ。
少し横にそれてしまったが『サンデー毎日』より半年前の二〇〇三年三月には新聞がこの「指導力不足」問題を取り上げていた。
早かったのは東京都で、不適格・指導力不足教師の再教育や、研修させても復帰させることのできない教師を一般行政職に転向させるなどの取り組みが五、六年前から始められていたというのであった。
精神的疾患で休職する教師が増えていると報じられたのもそのときがはじめてだったのではないか。
避地枝勤務なら駅やバス停まで十キロくらいの道のりを歩くしかなかった経験からすれば「ぜいたく病」といいたいが、二〇〇一年、その精神的疾患で休職する教師が「二千五百人」を超えていたという。
その二〇〇〇年代初頭の「指導力不足」教師は、全国でわずか「数十人」であった。七〇年代の末、北海道東部の町村で千六百人の中に、箸にも棒にもかからない「ダメ教師」が約二〇人、「80人に1人」の割合であったが、「事件」が起こることが当たり前になって、教師が精神を病んでいるときに、「ダメ教師」が90万人の中に「数十人」しかいない、それが「566人」になり、「371人」であったとして文科省がいう「調査」とはどんなものであるのだろうか。
指導力不足教師「371人」の八〇パーセント以上が四〇代、五〇代の教師であるという。この傾向は、調査が始まって以降ほとんど同じであったはずである。
すでに何十年も教壇に立っているわけだから「今さら」といいたくなる、いわれてしかたのないことだが、二〇〇三年、東京都の取り組みが紹介されたとき、「不適格」と認定された五〇代の女性教師は次のようにその憤懣をぶつけていた。
「揚げ足を取るような指摘ばかりだ。三〇年間、この指導で問題なかった」(2003.3.26付『読売新聞』)
と平然と語れる女性教師の意識と世間の常識のギャップの大きさに驚かされるが、「80人に1人」の「ダメ教師」の存在が道東だけのことではなかったということはできよう。
比べて精神を病んで休職する教師の「良心」をたたえなければならないとしたら、何か寂しい思いもするけれど、それでは、三〇代、二〇代の教師は大丈夫なのであろうか。
教師を目指す学生たちが、教室にいじめがあっても、止めさせる指導はしない、と明言していることについてはすでに書いたが、学生の先輩である二〇代、三〇代の教師は、今、教育現場で何をどうしているのであろうか。
|
|
|
|
|
|
|
|
いじめの加害者たち 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
いじめの加害者たちのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- マイミク募集はここで。
- 89582人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208275人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90043人