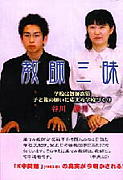日教組はすでに壊れている、と書いたのは元国交相辞任のときだった。元国交相は日本の教育のがんである「日教組をぶっ壊す」と発言して大臣辞任ばかりか、次期総選挙の立起まで取りやめということになってしまった。
そんな成り行きを見た毎日新聞が二〇〇八年十月十九日付紙面で「日本最大の教職員団体――年々低下する加入率」と日教組の現況を解説している。
かつては全国の小中高校教師の「86.3%」が日教組の組合員だった。
それが今では「28.3%」というのは47単位の平均、たとえば北教組のようにまだ「50%台」を維持している組織もあれば、最大単組であった都教組が「10%」を割り込んでいるなど、内実は一様でない。
とくに都教組は組織が大きかっただけでなく、日教組運動を牽引した大組織、その都教組の組織率が「10%」に満たないというのは、日教組の今を象徴している。
ともあれ組合員の減少傾向はこの後も続くだろうし、組織率が五分の一程度では最早、日教組が、元国交相が「ぶっ壊す」といきりたつほどの存在でなくなっているのは間違いない。そんな中での中山元国交相発言は、「選挙を視野に入れていた」としても「あまりに不用意な発言」だったと毎日新聞は締めくくっている。
問題はむしろ別なところにある。
日教組がすでに壊れてしまったとして、学校は大丈夫か、学校も壊れてしまったということになってはいないのか。
今、学校は、子どもの命を守ることもできなくなっている。
日教組が元気であった時代、学校は、子どもの命が奪われてしまうような危険なところではなかった。どこよりも完全な子どものための生活空間であり、教育の場であった。
それが今、教師が教室で子どもに殺され、カッターナイフ殺人が起こり、教室が舞台のいじめが原因で自ら命を絶つ子どもがあとを断たない。
確かに日教組は、旧文部省の政策にことごとく異をとなえ、自民党のいわゆる文教族議員の目の敵にされてきた。元国交相の発言はそんな「歴史」に「悪のり」したようなものでもあったが、学校が子どもたちにとって完全な生活空間でなくなってしまったのは、社会の変化、家族の変化、子どもの変化があるにしても、何より教師の「指導力」が減退の一途をたどっている、教室の管理さえできなくなっている、そして学校の秩序を維持することができないということに尽きるのではないか。一教師の「指導力」減退ははるかに超えて、学校全体が管理能力を失ってしまった。つまりが学校は「液状化」してしまったのではないか、ということなのである。
日教組が元気で、文部省(現文科相)の政策にことごとく反対して闘っていた頃、この大組織を引っ張っていたのは最大単組の都教組、後に続いたのが北の北教組と南の沖縄県教組だった。とくに北教組の愚直なまでの「過激」ぶりは七〇年代末のあの「主任制度化」反対闘争のときにも健在で、丁度その頃、北教組網走支部の専従として仕事をしたことがある。二年間、教育現場を離れて、労働組合の書記局にこもっていたのであるが、学校の、とくに人事の裏の事情が分かる立場であった。
網走支部傘下の組合員は千六百人、ほとんど百パーセントの組織率であったが、この千六百人の中に「指導力不足」というよりは箸にも棒にもかからない「ダメ教師」が約二〇人いた。
人事の季節、「ダメ教師」は出したいし、受け入れたくはない校長同士の駆け引きのもと「たらい回し人事」が行なわれる。いずれの学校も「戦力」になる教師を確保したいから必死で、つらい立場の校長の愚痴が組合の書記局までもれ聞こえてきて分かってしまう。
いうまでもなく「ダメ教師」がいていいわけではないが、どんな職場にもそのくらいの「ダメ人間」はいるもので、そういう人たちにも「生活」がある。つまりは「弱者」で、そういう人たちをかばって無事に乗り切って行く知恵こそが求められ、社会はそのような寛容のもとに成り立っていると受けとめるしかない。
千六百人の中の二〇人は、八〇人に一人の割合だが、それで学校が困った、何か支障をきたしかといえば、そうではなかった。なぜか?
学校の外からでは分かりづらいことであるけれど、生徒児童の非行・悪事、いじめに対処する「生活指導」というのはきわめて特殊で、ある意味で「ケイサツ的」ともいわねばならない性質の仕事である。
「ダメ教師」でなくても、生活指導を苦手とする教師のほうが多くて、体験的にいえば、同じ職員室に三、四〇人の教師がいるとして、その中に生活指導をこなせる教師が七、八人もいれば良しとしなければならない。
しかしそれで十分で、中学校なら、そのような教師を「生活指導係」として各学年に配置して、何か事あれば係を中心に学年の「教師集団」として動く。担任「任せ」にはしない。
この担任「任せ」にしないで「教師集団」として動くということを、教師の意識、使命として支えていたのが労働組合としての日教組の存在であった。日教組のメインスローガンは「教え子を再び戦場へ送らない」だが「よき組合員は、よき教師」というのもあって、「使命感」が「力」でもあるのは事実である。
日教組が壊れて、学校も壊れてしまったのではないかと危惧するのは、そういうことである。
ただでさえ「指導力」が減退の一途をたどっているときに、自分の学級さえ守ることができればいいと考えて、隣りの教室に何が起こっていようとも座視して恬淡(てんたん)としている。いられる。そして「自分の学級」さえ守ることができなくて、事件は起こってしまう。
今このときの教育現場の実態がそうであるときに、校長・教頭・いわゆる「主任」たちに教師を束ねて学校を管理できるだけの「指導力」があるかといえばそれもない。
民間からの校長登用の背景もそのゆえであるのに、かんじんの校長、教育委員会、文科省にその危機感はない。
以上に述べたことは「総論」に過ぎなくて、「各論」的に見れば学校毎に事情はあって、日教組が健在のときにも、上手くいかない、やれない学校はいくらでもあって、非行や悪事、いじめが多発すれば「教育イコール生活指導」というくらいに生活指導できる「力」が「学校」の中にあるかどうかで勝負は決まる。
教育、というより人間に関することはすべて「きれい事」では済まなくて、とくに生活指導の何たるかを直言すれば、子どもとケンカができるかということに尽きるが、大きな声が出せるか、怒鳴られるかと言い換えてもいい。
ときにチンピラみたいなワルガキと渡り合わなければならないことだってあるし、それが「いじめ」なら学級全体を敵に回すことにだってなりかねないのだから、押し負けしないで跳ね返すだけの「精神の体力」が求められる。
この「精神の体力」は作家倉橋由美子の本に出てくる。今でこそ日本の大人の「幼稚」さを指摘する言説は珍しくもないが、いちはやく六〇年代のあの政治の季節(「60年安保」
の時代)の頃から繰り返しそのことを言ってきたのは、この人を置いて外にはいない。
日本中が「一億総中流」と浮かれていた頃に、それは互いが羨望・嫉妬をおおうための隠れみのに過ぎないとする『劣情の支配する国』というのもあって、バブルがはじけて今に至っている様子を少し冷静に眺めれば、倉橋由美子の言説の多くは「予言」的であったということが分かる。
とにもかくにもこの「生活指導」というもののノウハウが、中学校には蓄積されてある。小学校には、ない。
九〇年代に小学校で「学級崩壊」や「対教師暴力」が多発して、新聞が「もがく先生」(朝日)、「嘆く先生」(読売)、「騒乱教室」(毎日)、「小学校の校内暴力最悪」(日経)と見出しをつけたのが二〇〇四年、二〇〇六年度のいじめ「6倍・12万件」の約半数は小学校で起こっている。
そんな成り行きを見た毎日新聞が二〇〇八年十月十九日付紙面で「日本最大の教職員団体――年々低下する加入率」と日教組の現況を解説している。
かつては全国の小中高校教師の「86.3%」が日教組の組合員だった。
それが今では「28.3%」というのは47単位の平均、たとえば北教組のようにまだ「50%台」を維持している組織もあれば、最大単組であった都教組が「10%」を割り込んでいるなど、内実は一様でない。
とくに都教組は組織が大きかっただけでなく、日教組運動を牽引した大組織、その都教組の組織率が「10%」に満たないというのは、日教組の今を象徴している。
ともあれ組合員の減少傾向はこの後も続くだろうし、組織率が五分の一程度では最早、日教組が、元国交相が「ぶっ壊す」といきりたつほどの存在でなくなっているのは間違いない。そんな中での中山元国交相発言は、「選挙を視野に入れていた」としても「あまりに不用意な発言」だったと毎日新聞は締めくくっている。
問題はむしろ別なところにある。
日教組がすでに壊れてしまったとして、学校は大丈夫か、学校も壊れてしまったということになってはいないのか。
今、学校は、子どもの命を守ることもできなくなっている。
日教組が元気であった時代、学校は、子どもの命が奪われてしまうような危険なところではなかった。どこよりも完全な子どものための生活空間であり、教育の場であった。
それが今、教師が教室で子どもに殺され、カッターナイフ殺人が起こり、教室が舞台のいじめが原因で自ら命を絶つ子どもがあとを断たない。
確かに日教組は、旧文部省の政策にことごとく異をとなえ、自民党のいわゆる文教族議員の目の敵にされてきた。元国交相の発言はそんな「歴史」に「悪のり」したようなものでもあったが、学校が子どもたちにとって完全な生活空間でなくなってしまったのは、社会の変化、家族の変化、子どもの変化があるにしても、何より教師の「指導力」が減退の一途をたどっている、教室の管理さえできなくなっている、そして学校の秩序を維持することができないということに尽きるのではないか。一教師の「指導力」減退ははるかに超えて、学校全体が管理能力を失ってしまった。つまりが学校は「液状化」してしまったのではないか、ということなのである。
日教組が元気で、文部省(現文科相)の政策にことごとく反対して闘っていた頃、この大組織を引っ張っていたのは最大単組の都教組、後に続いたのが北の北教組と南の沖縄県教組だった。とくに北教組の愚直なまでの「過激」ぶりは七〇年代末のあの「主任制度化」反対闘争のときにも健在で、丁度その頃、北教組網走支部の専従として仕事をしたことがある。二年間、教育現場を離れて、労働組合の書記局にこもっていたのであるが、学校の、とくに人事の裏の事情が分かる立場であった。
網走支部傘下の組合員は千六百人、ほとんど百パーセントの組織率であったが、この千六百人の中に「指導力不足」というよりは箸にも棒にもかからない「ダメ教師」が約二〇人いた。
人事の季節、「ダメ教師」は出したいし、受け入れたくはない校長同士の駆け引きのもと「たらい回し人事」が行なわれる。いずれの学校も「戦力」になる教師を確保したいから必死で、つらい立場の校長の愚痴が組合の書記局までもれ聞こえてきて分かってしまう。
いうまでもなく「ダメ教師」がいていいわけではないが、どんな職場にもそのくらいの「ダメ人間」はいるもので、そういう人たちにも「生活」がある。つまりは「弱者」で、そういう人たちをかばって無事に乗り切って行く知恵こそが求められ、社会はそのような寛容のもとに成り立っていると受けとめるしかない。
千六百人の中の二〇人は、八〇人に一人の割合だが、それで学校が困った、何か支障をきたしかといえば、そうではなかった。なぜか?
学校の外からでは分かりづらいことであるけれど、生徒児童の非行・悪事、いじめに対処する「生活指導」というのはきわめて特殊で、ある意味で「ケイサツ的」ともいわねばならない性質の仕事である。
「ダメ教師」でなくても、生活指導を苦手とする教師のほうが多くて、体験的にいえば、同じ職員室に三、四〇人の教師がいるとして、その中に生活指導をこなせる教師が七、八人もいれば良しとしなければならない。
しかしそれで十分で、中学校なら、そのような教師を「生活指導係」として各学年に配置して、何か事あれば係を中心に学年の「教師集団」として動く。担任「任せ」にはしない。
この担任「任せ」にしないで「教師集団」として動くということを、教師の意識、使命として支えていたのが労働組合としての日教組の存在であった。日教組のメインスローガンは「教え子を再び戦場へ送らない」だが「よき組合員は、よき教師」というのもあって、「使命感」が「力」でもあるのは事実である。
日教組が壊れて、学校も壊れてしまったのではないかと危惧するのは、そういうことである。
ただでさえ「指導力」が減退の一途をたどっているときに、自分の学級さえ守ることができればいいと考えて、隣りの教室に何が起こっていようとも座視して恬淡(てんたん)としている。いられる。そして「自分の学級」さえ守ることができなくて、事件は起こってしまう。
今このときの教育現場の実態がそうであるときに、校長・教頭・いわゆる「主任」たちに教師を束ねて学校を管理できるだけの「指導力」があるかといえばそれもない。
民間からの校長登用の背景もそのゆえであるのに、かんじんの校長、教育委員会、文科省にその危機感はない。
以上に述べたことは「総論」に過ぎなくて、「各論」的に見れば学校毎に事情はあって、日教組が健在のときにも、上手くいかない、やれない学校はいくらでもあって、非行や悪事、いじめが多発すれば「教育イコール生活指導」というくらいに生活指導できる「力」が「学校」の中にあるかどうかで勝負は決まる。
教育、というより人間に関することはすべて「きれい事」では済まなくて、とくに生活指導の何たるかを直言すれば、子どもとケンカができるかということに尽きるが、大きな声が出せるか、怒鳴られるかと言い換えてもいい。
ときにチンピラみたいなワルガキと渡り合わなければならないことだってあるし、それが「いじめ」なら学級全体を敵に回すことにだってなりかねないのだから、押し負けしないで跳ね返すだけの「精神の体力」が求められる。
この「精神の体力」は作家倉橋由美子の本に出てくる。今でこそ日本の大人の「幼稚」さを指摘する言説は珍しくもないが、いちはやく六〇年代のあの政治の季節(「60年安保」
の時代)の頃から繰り返しそのことを言ってきたのは、この人を置いて外にはいない。
日本中が「一億総中流」と浮かれていた頃に、それは互いが羨望・嫉妬をおおうための隠れみのに過ぎないとする『劣情の支配する国』というのもあって、バブルがはじけて今に至っている様子を少し冷静に眺めれば、倉橋由美子の言説の多くは「予言」的であったということが分かる。
とにもかくにもこの「生活指導」というもののノウハウが、中学校には蓄積されてある。小学校には、ない。
九〇年代に小学校で「学級崩壊」や「対教師暴力」が多発して、新聞が「もがく先生」(朝日)、「嘆く先生」(読売)、「騒乱教室」(毎日)、「小学校の校内暴力最悪」(日経)と見出しをつけたのが二〇〇四年、二〇〇六年度のいじめ「6倍・12万件」の約半数は小学校で起こっている。
|
|
|
|
|
|
|
|
いじめの加害者たち 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
いじめの加害者たちのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23166人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人