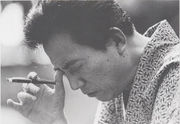大菩薩峠http://
解説
中里介山の同名の小説を「侍」の橋本忍が脚色、「血と砂」の岡本喜八が監督した剣豪もの。撮影は「大工太平記」の村井博。
あらすじ
大菩薩峠の頂上で、一人の老巡礼が何の理由もなく殺された。斬ったのは、黒の紋服に“放れ駒"の紋が印象的な深編笠の男机竜之助だ。この老人といっしょにいた孫娘お松は、折りから通りかかった盗賊、裏宿の七兵衛に救われた。竜之助は、帰宅して間もなく、宇津木文之丞の妻お浜の訪問をうけた。お浜の夫、文之丞はかつて竜之助と同門で剣を学んだ仲だが、御嶽神社の奉納試合で、竜之助と立ち合うことになっていた。竜之助の父、弾正も、残忍なまでに殺気のみなぎる竜之助の“音なしの構え"を恐れ、文之丞に勝ちをゆずるように説き、お浜もそれを懇願した。しかし虚無的な影を深くやどした竜之助は、無理矢理お浜の操をうばったうえ、文之丞を殴殺し、お浜と共に江戸へ出奔した。それから二年。吉田竜太郎と名を変えた竜之肋は芝飯倉の長屋の一隅にお浜と子供の郁太郎と共に暮していた。そうしたある日、竜之助は、直心影流、島田虎之助の道場で、見事な剣さはきでひときわ目立つ若い剣士、宇津木兵馬を知り、他流試合を申し込んだ。この兵馬は竜之助が以前殴殺した文之丞の弟であった。兵馬は、ふとしたことから江戸でお松を知り、共に竜之助を討つために腕をみがいていたのだった。一方竜之助は、金のために新徴組に加わり邪剣をふるっていたが、ある日島田虎之助に出くわし、その豪剣と、偉大な人間性にうたれた。竜之助の激しい心の動揺をよみとった虎之助は、兵馬に必殺の突きを武器に、相打ちを覚悟で竜之助に立ち向うことをすすめ、竜之助に果し状を送った。一方、いまでは夫婦とは名ばかりで、互いに憎悪し合う破綻の生活を送っていたお浜も、ついに竜之助のあまりの冷酷さにたえきれず、竜之助を刺そうとしたが、逆に竜之助の狂刃に倒れた。文久三年春--京都新選組が生まれた。島原の槌屋では、近藤、土方、斎藤などの隊士が集り、芹沢暗殺と共に、手あたり次弟に狂刃をふるう竜之助の命を奪う密謀をしていた。一方、芹沢も竜之助を誘い、兵馬の首とひきかえに近藤暗殺をそそのかした。が、ちょうど話を立聞していたお松は、芹沢につかまり、竜之助にあずけられた。そこで竜之助は、お松から大菩薩峠での悪夢のような昔話を聞かされた。竜之助は、ここで初めて、お松が自分が殺した老巡礼の娘であることを知り、煩悩になやまされ、狂ったように白刃を振りまわした。そこへ新選組が乱入した。地獄絵図の中全身に手傷をうけたまま逃げのびた竜之助は、とおりすがりの老爺に助けられ、木津街道を一人どこまでもどこまでも歩いていくのだった。
製作=宝塚映画 配給=東宝
1966.02.25
8巻 3,289m 120分 白黒 東宝スコープ
製作 ................ 藤本真澄 佐藤正之 南里金春
製作担当者 ................ 堤博康
監督 ................ 岡本喜八
監督助手 ................ 山本迪夫
脚本 ................ 橋本忍
原作 ................ 中里介山
撮影 ................ 村井博
音楽 ................ 佐藤勝
美術 ................ 松山崇
録音 ................ 渡会伸
整音 ................ 下永尚
照明 ................ 西川鶴三
編集 ................ 黒岩義民
スチール ................ 山崎淳
現像 ................ 東洋現像所
配役
机竜之助 ................ 仲代達矢
お浜 ................ 新珠三千代
お松 ................ 内藤洋子
お松の祖父 ................ 藤原釜足
宇津木兵馬 ................ 加山雄三
宇津木文之丞 ................ 中谷一郎
裏宿の七兵衛 ................ 西村晃
与八 ................ 小川安三
机弾正 ................ 香川良介
お絹 ................ 川口敦子
やくざの浅吉 ................ 田中邦衛
神尾主膳 ................ 天本英世
中村一心斉 ................ 佐々木孝丸
芹沢鴨 ................ 佐藤慶
近藤勇 ................ 中丸忠雄
土方歳三 ................ 宮部昭夫
岡田彌市 ................ 伊吹新
加藤主税 ................ 久野征四郎
沖田総司 ................ 大木正司
斥候の青山 ................ 長谷川弘
お絹の家の下働き ................ 梅香ふみ子
お梅 ................ 園千雅子
島原・不津屋の若い衆 ................ 頭師孝雄
藤堂平助 ................ 早川恭二
児島強介 ................ 滝恵一
大橋訥庵 ................ 久世竜
島田虎之助 ................ 三船敏郎
解説
中里介山の同名の小説を「侍」の橋本忍が脚色、「血と砂」の岡本喜八が監督した剣豪もの。撮影は「大工太平記」の村井博。
あらすじ
大菩薩峠の頂上で、一人の老巡礼が何の理由もなく殺された。斬ったのは、黒の紋服に“放れ駒"の紋が印象的な深編笠の男机竜之助だ。この老人といっしょにいた孫娘お松は、折りから通りかかった盗賊、裏宿の七兵衛に救われた。竜之助は、帰宅して間もなく、宇津木文之丞の妻お浜の訪問をうけた。お浜の夫、文之丞はかつて竜之助と同門で剣を学んだ仲だが、御嶽神社の奉納試合で、竜之助と立ち合うことになっていた。竜之助の父、弾正も、残忍なまでに殺気のみなぎる竜之助の“音なしの構え"を恐れ、文之丞に勝ちをゆずるように説き、お浜もそれを懇願した。しかし虚無的な影を深くやどした竜之助は、無理矢理お浜の操をうばったうえ、文之丞を殴殺し、お浜と共に江戸へ出奔した。それから二年。吉田竜太郎と名を変えた竜之肋は芝飯倉の長屋の一隅にお浜と子供の郁太郎と共に暮していた。そうしたある日、竜之助は、直心影流、島田虎之助の道場で、見事な剣さはきでひときわ目立つ若い剣士、宇津木兵馬を知り、他流試合を申し込んだ。この兵馬は竜之助が以前殴殺した文之丞の弟であった。兵馬は、ふとしたことから江戸でお松を知り、共に竜之助を討つために腕をみがいていたのだった。一方竜之助は、金のために新徴組に加わり邪剣をふるっていたが、ある日島田虎之助に出くわし、その豪剣と、偉大な人間性にうたれた。竜之助の激しい心の動揺をよみとった虎之助は、兵馬に必殺の突きを武器に、相打ちを覚悟で竜之助に立ち向うことをすすめ、竜之助に果し状を送った。一方、いまでは夫婦とは名ばかりで、互いに憎悪し合う破綻の生活を送っていたお浜も、ついに竜之助のあまりの冷酷さにたえきれず、竜之助を刺そうとしたが、逆に竜之助の狂刃に倒れた。文久三年春--京都新選組が生まれた。島原の槌屋では、近藤、土方、斎藤などの隊士が集り、芹沢暗殺と共に、手あたり次弟に狂刃をふるう竜之助の命を奪う密謀をしていた。一方、芹沢も竜之助を誘い、兵馬の首とひきかえに近藤暗殺をそそのかした。が、ちょうど話を立聞していたお松は、芹沢につかまり、竜之助にあずけられた。そこで竜之助は、お松から大菩薩峠での悪夢のような昔話を聞かされた。竜之助は、ここで初めて、お松が自分が殺した老巡礼の娘であることを知り、煩悩になやまされ、狂ったように白刃を振りまわした。そこへ新選組が乱入した。地獄絵図の中全身に手傷をうけたまま逃げのびた竜之助は、とおりすがりの老爺に助けられ、木津街道を一人どこまでもどこまでも歩いていくのだった。
製作=宝塚映画 配給=東宝
1966.02.25
8巻 3,289m 120分 白黒 東宝スコープ
製作 ................ 藤本真澄 佐藤正之 南里金春
製作担当者 ................ 堤博康
監督 ................ 岡本喜八
監督助手 ................ 山本迪夫
脚本 ................ 橋本忍
原作 ................ 中里介山
撮影 ................ 村井博
音楽 ................ 佐藤勝
美術 ................ 松山崇
録音 ................ 渡会伸
整音 ................ 下永尚
照明 ................ 西川鶴三
編集 ................ 黒岩義民
スチール ................ 山崎淳
現像 ................ 東洋現像所
配役
机竜之助 ................ 仲代達矢
お浜 ................ 新珠三千代
お松 ................ 内藤洋子
お松の祖父 ................ 藤原釜足
宇津木兵馬 ................ 加山雄三
宇津木文之丞 ................ 中谷一郎
裏宿の七兵衛 ................ 西村晃
与八 ................ 小川安三
机弾正 ................ 香川良介
お絹 ................ 川口敦子
やくざの浅吉 ................ 田中邦衛
神尾主膳 ................ 天本英世
中村一心斉 ................ 佐々木孝丸
芹沢鴨 ................ 佐藤慶
近藤勇 ................ 中丸忠雄
土方歳三 ................ 宮部昭夫
岡田彌市 ................ 伊吹新
加藤主税 ................ 久野征四郎
沖田総司 ................ 大木正司
斥候の青山 ................ 長谷川弘
お絹の家の下働き ................ 梅香ふみ子
お梅 ................ 園千雅子
島原・不津屋の若い衆 ................ 頭師孝雄
藤堂平助 ................ 早川恭二
児島強介 ................ 滝恵一
大橋訥庵 ................ 久世竜
島田虎之助 ................ 三船敏郎
|
|
|
|
コメント(6)
大菩薩峠
昔から思っていたのだが橋本忍が書いた時代劇ってなんか面白くない。それは観てるほうが時代劇に対して普遍的に求めているものが足りないからではないか?しかしこ作品は別、岡本喜八の娯楽映画魂のほうが勝ってたから。
中里介山原作。大菩薩峠で巡礼の老人・藤原釜足が通りすがりの浪人・机龍之介・仲代達矢に惨殺された。泣きじゃくる巡礼の孫娘・内藤洋子を引き取ったのは元盗賊・西村晃。龍之介は親友・中谷一郎と剣の試合をすることになっているが、その妻・新珠三千代にわざと負けてくれと体を張って懇願される。しかし、龍之介は彼の命を奪う。
「逆上」このことばが最も似合う役者、それが仲代達矢だ。
ストーリーは超有名なので割愛。
ここはどうしても市川雷蔵バージョンとの比較になる。そんなことしてもしょうがないじゃん、と言われても、やるもんね。
雷蔵と仲代では、まず体力的に差異が大きい。牛若丸と弁慶くらいか。岡本喜八監督はモノクロの画面をかなりハイキーっぽく仕上げているように見えた(ぼろっちいプリント見たのかもしれんが)のでちょっと怪奇映画の面持ち。仲代達矢の顔はかなり「濃い口」であるから、水車小屋で新珠三千代を犯すシーンなんて、ものすごくエロい。こういう生々しさは雷蔵には無理。それはどっちが良いとかではなくて、役者の個性。
内藤洋子は西村晃の手によって奉公にあがるが、女郎屋に売られてしまう。ここで仇とは知らず仲代に出会う。開かずの間で竹御簾に囲まれている。内藤はその部屋に幽霊が出るから怖いと言う。ろうそくの灯りが揺れて、内藤が身の上話しを始めるとやがて仲代は娘の「正体」を知る。御簾に人影が、、、巡礼の鐘の音がちり〜ん、と。ゾワゾワ〜っとくるなあ。竹御簾とろうそく、怪談には必須アイテムだよな。
龍之介と組む芹沢鴨が佐藤慶で、これは適役。百姓上がりの近藤勇・中丸忠雄や土方歳三・宮部昭夫を軽蔑し続けてついには女としとねの中で殺される惨めったらしいリベラリスト。顔色悪そうで、ほら、遠足行くとバスの中でゲロ吐くタイプ。パラノイア気味の仲代と病的な佐藤の取り合わせは良かった。
様式美的な美しさよりもやっぱ岡本監督だから血生臭さくて、激しくて、を期待する。それが発揮されたのは、布団に柏餅のように巻かれ、紙襖の上からメッタ突きにされた芹沢暗殺のシーンと、ラスト、龍之介が猛火の中で新選組と大立ち回りをするところ。血を吹き上げて(モノクロだから墨色だけど)ゲヘゲヘする龍之介、完璧にキレちゃう。このキレ加減が仲代龍之介の真骨頂。
内藤洋子を陰で見守る泥棒の西村晃は、女郎屋へ売り飛ばした性悪女とそのヒモ・田中邦衛をスカッとやっつける。そして内藤と宇津木・加山雄三との清らかな恋をサポートするのだ。う〜んカッコイイ。でもって島田虎之介は三船敏郎、これで画面がぐっとゴージャス、かつシマる。
総じて主役よりも脇役のほうがキラリと光ってしまうのが岡本映画の特徴なんでありますな。
昔から思っていたのだが橋本忍が書いた時代劇ってなんか面白くない。それは観てるほうが時代劇に対して普遍的に求めているものが足りないからではないか?しかしこ作品は別、岡本喜八の娯楽映画魂のほうが勝ってたから。
中里介山原作。大菩薩峠で巡礼の老人・藤原釜足が通りすがりの浪人・机龍之介・仲代達矢に惨殺された。泣きじゃくる巡礼の孫娘・内藤洋子を引き取ったのは元盗賊・西村晃。龍之介は親友・中谷一郎と剣の試合をすることになっているが、その妻・新珠三千代にわざと負けてくれと体を張って懇願される。しかし、龍之介は彼の命を奪う。
「逆上」このことばが最も似合う役者、それが仲代達矢だ。
ストーリーは超有名なので割愛。
ここはどうしても市川雷蔵バージョンとの比較になる。そんなことしてもしょうがないじゃん、と言われても、やるもんね。
雷蔵と仲代では、まず体力的に差異が大きい。牛若丸と弁慶くらいか。岡本喜八監督はモノクロの画面をかなりハイキーっぽく仕上げているように見えた(ぼろっちいプリント見たのかもしれんが)のでちょっと怪奇映画の面持ち。仲代達矢の顔はかなり「濃い口」であるから、水車小屋で新珠三千代を犯すシーンなんて、ものすごくエロい。こういう生々しさは雷蔵には無理。それはどっちが良いとかではなくて、役者の個性。
内藤洋子は西村晃の手によって奉公にあがるが、女郎屋に売られてしまう。ここで仇とは知らず仲代に出会う。開かずの間で竹御簾に囲まれている。内藤はその部屋に幽霊が出るから怖いと言う。ろうそくの灯りが揺れて、内藤が身の上話しを始めるとやがて仲代は娘の「正体」を知る。御簾に人影が、、、巡礼の鐘の音がちり〜ん、と。ゾワゾワ〜っとくるなあ。竹御簾とろうそく、怪談には必須アイテムだよな。
龍之介と組む芹沢鴨が佐藤慶で、これは適役。百姓上がりの近藤勇・中丸忠雄や土方歳三・宮部昭夫を軽蔑し続けてついには女としとねの中で殺される惨めったらしいリベラリスト。顔色悪そうで、ほら、遠足行くとバスの中でゲロ吐くタイプ。パラノイア気味の仲代と病的な佐藤の取り合わせは良かった。
様式美的な美しさよりもやっぱ岡本監督だから血生臭さくて、激しくて、を期待する。それが発揮されたのは、布団に柏餅のように巻かれ、紙襖の上からメッタ突きにされた芹沢暗殺のシーンと、ラスト、龍之介が猛火の中で新選組と大立ち回りをするところ。血を吹き上げて(モノクロだから墨色だけど)ゲヘゲヘする龍之介、完璧にキレちゃう。このキレ加減が仲代龍之介の真骨頂。
内藤洋子を陰で見守る泥棒の西村晃は、女郎屋へ売り飛ばした性悪女とそのヒモ・田中邦衛をスカッとやっつける。そして内藤と宇津木・加山雄三との清らかな恋をサポートするのだ。う〜んカッコイイ。でもって島田虎之介は三船敏郎、これで画面がぐっとゴージャス、かつシマる。
総じて主役よりも脇役のほうがキラリと光ってしまうのが岡本映画の特徴なんでありますな。
大菩薩峠
1966年2月25日封切 モノクロ シネマスコープ 120分
原作 中里介山 脚本 橋本忍
監督 岡本喜八
度々映画化されている「大菩薩峠」を岡本喜八監督の
新解釈を得て制作された意欲作。
時は、幕末。大菩薩峠で娘を連れた老巡礼が何者かに
よって殺された。その者の名は「机竜之助」
ある日、竜之助は御獄の大試合で宇津木文之丞の妻・
お浜の操をかけた甲源一刀流文之丞の必殺の突きを交わ
し、見事、撃ち殺した。文之丞の弟、兵馬は兄の敵討ち
のために、江戸の島田虎之助の道場で腕を磨いていた。
竜之助は吉田竜太郎と名を改め、未亡人となった
お浜と江戸で日陰者として暮らし始め、芹沢鴨らと
新撰組を結成し、殺戮に明け暮れていた。その冷酷
極まりない彼の態度に我慢できなくなったお浜は
竜太郎を殺そうとしたが、返り討ちに遭った。
その後、竜太郎は勤皇と佐幕がひしめく京都に出かけた。
兵馬も彼の後を追って京都を訪ねた。
岡本喜八版の「大菩薩峠」は入手が困難なため、なかなか
観ることのできない貴重な作品。冷酷な殺人鬼・机竜之助は
仲代達矢が演じ、その演技は見事の一言に尽きる。
最後で竜之助が老巡礼の娘を知り、妖鬼に取り憑かれ気の
狂ったように新撰組の隊士達を斬りまくるシーンは圧巻だが、
敵討ちに燃える兵馬との勝負がなかったのは残念。でも、作
品としての仕上がりはとてもよい。
1966年2月25日封切 モノクロ シネマスコープ 120分
原作 中里介山 脚本 橋本忍
監督 岡本喜八
度々映画化されている「大菩薩峠」を岡本喜八監督の
新解釈を得て制作された意欲作。
時は、幕末。大菩薩峠で娘を連れた老巡礼が何者かに
よって殺された。その者の名は「机竜之助」
ある日、竜之助は御獄の大試合で宇津木文之丞の妻・
お浜の操をかけた甲源一刀流文之丞の必殺の突きを交わ
し、見事、撃ち殺した。文之丞の弟、兵馬は兄の敵討ち
のために、江戸の島田虎之助の道場で腕を磨いていた。
竜之助は吉田竜太郎と名を改め、未亡人となった
お浜と江戸で日陰者として暮らし始め、芹沢鴨らと
新撰組を結成し、殺戮に明け暮れていた。その冷酷
極まりない彼の態度に我慢できなくなったお浜は
竜太郎を殺そうとしたが、返り討ちに遭った。
その後、竜太郎は勤皇と佐幕がひしめく京都に出かけた。
兵馬も彼の後を追って京都を訪ねた。
岡本喜八版の「大菩薩峠」は入手が困難なため、なかなか
観ることのできない貴重な作品。冷酷な殺人鬼・机竜之助は
仲代達矢が演じ、その演技は見事の一言に尽きる。
最後で竜之助が老巡礼の娘を知り、妖鬼に取り憑かれ気の
狂ったように新撰組の隊士達を斬りまくるシーンは圧巻だが、
敵討ちに燃える兵馬との勝負がなかったのは残念。でも、作
品としての仕上がりはとてもよい。
大菩薩峠 2005/6/16
1968年,日本,116分
巡礼の途中大菩薩峠に差し掛かった老人と孫娘、孫娘のお松が水を汲んでいる間に老人は通りかかった剣豪机竜之介に斬られ、お松は通りすがりの七兵衛に助けられる。竜之介はかつての同門の宇津木文之丞との剣術の試合を控えて、文之丞の妹だというお浜の訪問をうける…
何度も映画化されている『大菩薩峠』の岡本喜八版、冷酷な剣術家に扮した仲代達矢の目が怖い。 監督 岡本喜八
原作 中里介山
脚本 橋本忍
撮影 村井博
音楽 佐藤勝
出演 仲代達矢
佐藤慶
新珠三千代
内藤洋子
加山雄三
三船敏郎
中谷一郎
西村晃
伊吹新
久世竜
久野征四郎
宮部昭夫
中丸忠雄
川口敦子
この机竜之助という男、私にはさっぱりわけがわからない。いったい何を考えているのか。もっとも印象に残ったのはその目だが、焦点が定まっていないようなうつけた目、その奥底には狂気の根があるようで、見るものを落ち着かなくする。
彼がそのようにうつけた目をするのは、彼の父親が恐れたように彼自身が“音無しの構え”に魅入られてしまったからなのではないかと思う。音無しの構えとは、「押せば引く、引けば下がる」という受身の剣、自ら隙を作って、相手がその隙を狙ってきたところを返り討ちにするという受身の剣である。
その剣に魅入られた机竜之助は、全てに受身になる。彼は次々と人を殺すが、その発端となった宇津木文之丞との試合での面へのひと振りもあくまでもついて出てきた文之丞の剣をかわしての返り討ちであった。その後も彼はただただ受身で人を殺し続け、それで金をもらう。彼はどんどんその受身の罠に入り込んでゆき、うつけた目になり、狂って行く。その過程を描いたのがこの作品なのだ。
しかし、そのいちばん最初は竜之助が通りすがりの何の因果もない老人を後ろからばっさりと斬るエピソードである。このとき竜之助は決して受身ではない、自らその老人を殺すことを選び、迷うことなくばっさり斬った。これはもちろん彼の底なしの悪意を、彼の非常さをショッキングな形で観客に示すシーンとして機能するわけだが、同時にこれは彼の中の積極性がふと頭を出した瞬間でもあるのかもしれない。
そしてその積極性は御簾の間の亡霊によって蘇る。この亡霊の出現によって竜之助の心の何かが自分自身に向けて照らし出される。竜之助はそれを打ち払うために亡霊を切ろうとして完全に狂ってしまう。果たしてここで竜之助が知ることで狂ってしまった自分自身とはいったいどのようなものだったのだろうか。彼はいったい何を恥じていたのか。良心などとうに失ってしまっただろう彼が狂うまでに見せられたくないものとはいったい何なのか。
私が思うに、彼は大菩薩峠で老人を切り捨てた時点で狂ってしまったのではないか。音無しの構えとはそもそも相手がかかってくるまで待つ剣、裏返せば相手がかかってこない限りは相手を斬ることはない剣である。その彼が意味もなく人を斬ってしまった。この因果が彼を駆り立て、竜之助は人を斬り続けなければならない運命に落ち込んでしまった。
亡霊とはそのように彼を駆り立てるものそのものなのではないか。そしてそれは同時に彼自身である。机竜之助は自分自身を殺すために人の姿を借りて現れる亡霊を斬り続けるのだ。
もちろん、原作は世界最長といわれる長大な大河小説、こんな2時間の映画を見ただけで机竜之助という人間のことがわかるわけはない。しかし、少なくとも、岡本喜八なりの竜之助の解釈というのはこのようなものなのではないかと思う。この映画の机竜之助の目から感じられる狂気から映画全体を見てみると、そのような物語がそこにあるように思えてくるのだ。
それは岡本喜八が一貫して描く戦いの、そして殺し合いの虚しさというテーマに通じるものでもあり、人を殺すと言うことと狂気との親密さにも通じるものである。
1968年,日本,116分
巡礼の途中大菩薩峠に差し掛かった老人と孫娘、孫娘のお松が水を汲んでいる間に老人は通りかかった剣豪机竜之介に斬られ、お松は通りすがりの七兵衛に助けられる。竜之介はかつての同門の宇津木文之丞との剣術の試合を控えて、文之丞の妹だというお浜の訪問をうける…
何度も映画化されている『大菩薩峠』の岡本喜八版、冷酷な剣術家に扮した仲代達矢の目が怖い。 監督 岡本喜八
原作 中里介山
脚本 橋本忍
撮影 村井博
音楽 佐藤勝
出演 仲代達矢
佐藤慶
新珠三千代
内藤洋子
加山雄三
三船敏郎
中谷一郎
西村晃
伊吹新
久世竜
久野征四郎
宮部昭夫
中丸忠雄
川口敦子
この机竜之助という男、私にはさっぱりわけがわからない。いったい何を考えているのか。もっとも印象に残ったのはその目だが、焦点が定まっていないようなうつけた目、その奥底には狂気の根があるようで、見るものを落ち着かなくする。
彼がそのようにうつけた目をするのは、彼の父親が恐れたように彼自身が“音無しの構え”に魅入られてしまったからなのではないかと思う。音無しの構えとは、「押せば引く、引けば下がる」という受身の剣、自ら隙を作って、相手がその隙を狙ってきたところを返り討ちにするという受身の剣である。
その剣に魅入られた机竜之助は、全てに受身になる。彼は次々と人を殺すが、その発端となった宇津木文之丞との試合での面へのひと振りもあくまでもついて出てきた文之丞の剣をかわしての返り討ちであった。その後も彼はただただ受身で人を殺し続け、それで金をもらう。彼はどんどんその受身の罠に入り込んでゆき、うつけた目になり、狂って行く。その過程を描いたのがこの作品なのだ。
しかし、そのいちばん最初は竜之助が通りすがりの何の因果もない老人を後ろからばっさりと斬るエピソードである。このとき竜之助は決して受身ではない、自らその老人を殺すことを選び、迷うことなくばっさり斬った。これはもちろん彼の底なしの悪意を、彼の非常さをショッキングな形で観客に示すシーンとして機能するわけだが、同時にこれは彼の中の積極性がふと頭を出した瞬間でもあるのかもしれない。
そしてその積極性は御簾の間の亡霊によって蘇る。この亡霊の出現によって竜之助の心の何かが自分自身に向けて照らし出される。竜之助はそれを打ち払うために亡霊を切ろうとして完全に狂ってしまう。果たしてここで竜之助が知ることで狂ってしまった自分自身とはいったいどのようなものだったのだろうか。彼はいったい何を恥じていたのか。良心などとうに失ってしまっただろう彼が狂うまでに見せられたくないものとはいったい何なのか。
私が思うに、彼は大菩薩峠で老人を切り捨てた時点で狂ってしまったのではないか。音無しの構えとはそもそも相手がかかってくるまで待つ剣、裏返せば相手がかかってこない限りは相手を斬ることはない剣である。その彼が意味もなく人を斬ってしまった。この因果が彼を駆り立て、竜之助は人を斬り続けなければならない運命に落ち込んでしまった。
亡霊とはそのように彼を駆り立てるものそのものなのではないか。そしてそれは同時に彼自身である。机竜之助は自分自身を殺すために人の姿を借りて現れる亡霊を斬り続けるのだ。
もちろん、原作は世界最長といわれる長大な大河小説、こんな2時間の映画を見ただけで机竜之助という人間のことがわかるわけはない。しかし、少なくとも、岡本喜八なりの竜之助の解釈というのはこのようなものなのではないかと思う。この映画の机竜之助の目から感じられる狂気から映画全体を見てみると、そのような物語がそこにあるように思えてくるのだ。
それは岡本喜八が一貫して描く戦いの、そして殺し合いの虚しさというテーマに通じるものでもあり、人を殺すと言うことと狂気との親密さにも通じるものである。
印玄が独断と偏見とそのときの気分で選ぶオールタイム時代劇映画ベストテン。
一位 七人の侍監督黒沢明 脚本黒沢明 小国英雄 橋本忍
言わずと知れた日本映画、いや世界のベストワン、何故かキネ旬のその年のベストテンでは三位である。甘ったるい”左翼良心作”が持ち上げられる不幸な時代であった。この映画、見る度に主役が違って見える。二回目は木村功だったり、三回目はあっさりと死ぬ稲葉義男だったりと。最近はこす辛くてしぶとい農民役の藤原釜足に注目している(笑)。
この映画で始めて、殺陣に機動力、防御力といった戦略要素が取り入れられたが、これを継承する作品は少ない。相変わらず独りで大勢叩き斬るような作品ばかりである。
二位 十兵衛暗殺剣監督倉田準二 脚本高田宏治
この映画見たというひとはまったくの少数派だろう。何せビデオも出ないし、テレビ放映もない。私も一度関西方面で放映されたのを偶然見ただけであるが、この殺陣は本当に凄い。大友柳太郎が幕屋大休という実在の剣豪に扮して、近衛十四郎の柳生十兵衛と対決するのだが、まさに圧巻の名勝負である。詳しい内容はカタログハウス刊「高田宏治東映のアルチザン」でどうぞ。此の作品の殺陣の執拗さは脚本家の高田宏治の手柄であることが分かる。
しかし東映は美空ひばりの時代劇とか、どうでもいいものばかり出して、こういう傑作のビデオは出さない。
三位 徳川いれずみ師責め地獄監督石井輝男 脚本石井輝男 掛礼昌裕
石井輝男監督、今一番凄い監督かもしれない。この映画の遊戯精神には本当の知性を感じる。将軍家御上覧の入れ墨大会などという超虚構に爆笑しない人はいないだろう。吉田輝雄と小池朝雄の宿命の対決。
四位 忘八武士道監督石井輝男 脚本佐治乾
吉原伝奇もののフォーマットは小池一夫原作、石井輝男監督のこの作品ですでに出来上がっているのだった。もう少し丹波哲郎が若い頃だったらもっと良かったか。アンヌ隊員の特別サービスには特撮ファンは発狂するであろう。全裸で小笠原流の挨拶をするシーンはとくに良い(笑)。なぜビデオが出ないのか?不思議だ。
五位 上意討ち拝領妻始末 監督小林正樹 脚本橋本忍
小林正樹は「切腹」よりこっちを選びたい。三度目の対決の三船敏郎と仲代達矢だが結果はご想像通り。しかし黒づくめの衣装で今回の仲代はなかなか格好良い。原作は滝口康彦のいわゆる武士道残酷物だが、映像はかなり格調が高い。志村けん真っ青の馬鹿殿を演じる松村達夫の演技に注目。確かレーザーディスクが出ている。
六位 大殺陣監督工藤栄一 脚本池上金男
暴政への最後の手段としてのテロ行為を完全に肯定する過激作品。リーダー格の侍(大坂志郎)が家族を斬殺するシークエンスを短いショットと手が震えて草鞋が結べないシーンで表現した手腕が見事である。テロに憑かれていく若侍役の里見浩太郎も珍しく好演している。七人の侍のひとりだった稲葉義男は見事な逃げっぷりで場内を沸かす。
七位 竜馬暗殺 監督黒木和雄 脚本清水邦夫・田辺泰志
此の作品の原田芳雄ははまり役である。ちょっとこれ以上の坂本竜馬は出てこないだろう。中岡慎太郎役の石橋蓮司も好演。史実に基づいた興味深い人間ドラマ。薩摩藩首謀説に近い。難解で空虚な作品が多いATG映画の最高傑作。
八位 斬る監督三隅研次 脚本新藤兼人
大映時代劇は市川雷蔵のニヒルなキャラクター。独特の陰影ある照明と撮影で独自のムードが感じられる。他にも大映は「不知火検校」(森一生監督)「刺青」(増村保造監督)と傑作が多いのだが、ここでは代表して一本、この作品を挙げたい。弟を救うために万里昌代が全裸で斬られるシーンの残酷美はこの作品の白眉である。ほかにも、愛し合いながらも笑顔で藤村志保の介錯をする天知茂であるとか、不条理でそれゆえに美しい場面が連続する。主人公の切腹で終わるラストも何故か心地よい。日本独自の美意識、価値観を伝えるという意味ではこの作品は最高傑作である。いきなりアメリカ人などに見せてハラキリマニアにしたくなる欲求にかられる(笑)。
岡本喜八監督にも「斬る」があるが、こちらは明るく痛快な作品である。
九位 御用金監督五社英雄 脚本田坂啓 五社英雄
稀代のカツドウ屋、五社英雄に敬意を表して一票。あの冗長なラストがなければもっといいのだが。雪の中での丹波哲郎と仲代達矢の対決は見物である。余談だが、中村錦之助が演じていた役は三船敏郎が演じる予定だったらしい。
「人斬り」も面白いがやはり岡田以蔵は細身でなくては・・・文豪三島の演じる田中新兵衛は最高なのだが。
十位 風林火山監督稲垣浩 脚本橋本忍 國弘威雄
佐藤勝のテーマ曲も勇ましい戦国絵巻。三船敏郎の山本勘助、中村錦之助の武田信玄はハマリ役。最近の研究によれば武田騎馬軍団は荷駄隊が主体であり、そうなるとこの映画も「影武者」もまったく嘘になるのだが・・・
緒形拳とか田村正和とか当代の売れっ子がチョイ役で出演しているのも見物である。
その他の作品
岡本喜八監督「斬る」百姓上がりで剛力無双の高橋悦史が鼻息も荒く大活躍。女郎屋に上がり込んでのセリフ「土の匂いがする女を頼む!」にはマイった。それで出てくるのが岡田可愛なんだから通には堪えられねえでガス。まあ下品な場面は何もないのだが。
同じ岡本監督の「侍」は侍ニッポンの何回目かの映画化でストーリー自体はパッとしないが、ラストの桜田門外の変の殺陣が凄絶極まる。三船敏郎の殺陣は同じく岡本監督の「大菩薩峠」での島田虎之助vs新撰組がいちばん凄かったと思う。
げてもんでは勝プロ作品の「御用牙」「御用牙かみそり半蔵地獄責め」がおすすめ。どちらもビデオが出ている。勝新が富田勲の音楽をバックに逸物鍛え上げるオープニングには、中村玉緒ならずとも驚愕するであろう。田村高広、黒沢年男と仇役に強そうな面々を揃えているのも買いである。
石井輝男監督は他にも「御金蔵破り」(脚本野上龍雄・石井輝男)を撮っているがこれも秀作。たびたびこれを焼き直した脚本をテレビ時代劇で見かける。二枚目気取りで鼻持ち成らない大川橋蔵と朝丘雪路のやりとりが活劇をだれさせること夥しいが。橋蔵は片岡千恵蔵御大を現場に待たせるなど極悪非道を尽くしたらしい。
その報復は、加藤泰監督の「幕末残酷物語」で河原崎長一郎扮する沖田総司がきっちりつけてくれるのでアンチ橋蔵ファンは必見だ(笑)。この映画は現在のところいちばん史実に近い新撰組映画だと思って間違いない。まあ大友柳太郎の山南敬介が死ぬところなど史実と大きく違うのは確かだが、残酷なテロ集団としての新撰組を描いているのはこの作品だけなのだから。そのなかで唯一血の通った人間として描かれるのが沖田総司なのだが、平目のようなご面相という評判と肖像画をまさに彷彿とさせる河原崎長一郎の演技は最高である。
新撰組映画といえば、沢島忠監督の三船プロ作品「新選組」もなかなか面白い。三船敏郎の近藤勇はともかく三国連太郎扮する芹沢鴨の酒乱演技は真に迫っている。北大路欣也の健康過ぎる沖田総司も必見(笑)。ラストの近藤勇の断首シーンはショッキングだ。
中村錦之助はどちらかというと股旅物のいなせなやくざが良いというひとが多いが、そのなかでもお薦めが山下耕作監督の「関の弥太っぺ」。死地に赴く主人公をローアングルで捉えるラストは素晴らしい。加藤泰監督の「瞼の母」「沓掛時次郎・遊侠一匹」(これは錦之助より渥美清が絶品)も傑作。
柳生ものでは東宝、稲垣浩作品「柳生武芸帳」二作が代表作か。三船敏郎と鶴田浩二の共演が楽しい。他にも中村扇雀、先代松本幸四郎、大河内伝次郎など当時の大物がずらり出演している。一作目の「柳生武芸帳」が三船敏郎主演、二作目の「双龍秘剣」が鶴田浩二主演という構成。
東映の「柳生一族の陰謀」も面白かった。錦之介のオーバーアクトが愉しめる。
他にも忘れちゃいけない大傑作が「十三人の刺客」(監督工藤栄一 脚本池上金男)である。
あまりにも有名になってしまった作品だが、宿場町を借り切って大名行列を襲うというアイデアは凄い。剣客の西村晃を中央に配したポスターも秀逸だった。
私の母方の先祖が明石藩関係者なので思わず敵役の内田良平を応援してしまう。
こうしてみるとベストテン圏外の作品のほうが面白そうだな。この選考の順位は選外も含めてきわめていい加減であることをここに宣言いたします(笑)。
一位 七人の侍監督黒沢明 脚本黒沢明 小国英雄 橋本忍
言わずと知れた日本映画、いや世界のベストワン、何故かキネ旬のその年のベストテンでは三位である。甘ったるい”左翼良心作”が持ち上げられる不幸な時代であった。この映画、見る度に主役が違って見える。二回目は木村功だったり、三回目はあっさりと死ぬ稲葉義男だったりと。最近はこす辛くてしぶとい農民役の藤原釜足に注目している(笑)。
この映画で始めて、殺陣に機動力、防御力といった戦略要素が取り入れられたが、これを継承する作品は少ない。相変わらず独りで大勢叩き斬るような作品ばかりである。
二位 十兵衛暗殺剣監督倉田準二 脚本高田宏治
この映画見たというひとはまったくの少数派だろう。何せビデオも出ないし、テレビ放映もない。私も一度関西方面で放映されたのを偶然見ただけであるが、この殺陣は本当に凄い。大友柳太郎が幕屋大休という実在の剣豪に扮して、近衛十四郎の柳生十兵衛と対決するのだが、まさに圧巻の名勝負である。詳しい内容はカタログハウス刊「高田宏治東映のアルチザン」でどうぞ。此の作品の殺陣の執拗さは脚本家の高田宏治の手柄であることが分かる。
しかし東映は美空ひばりの時代劇とか、どうでもいいものばかり出して、こういう傑作のビデオは出さない。
三位 徳川いれずみ師責め地獄監督石井輝男 脚本石井輝男 掛礼昌裕
石井輝男監督、今一番凄い監督かもしれない。この映画の遊戯精神には本当の知性を感じる。将軍家御上覧の入れ墨大会などという超虚構に爆笑しない人はいないだろう。吉田輝雄と小池朝雄の宿命の対決。
四位 忘八武士道監督石井輝男 脚本佐治乾
吉原伝奇もののフォーマットは小池一夫原作、石井輝男監督のこの作品ですでに出来上がっているのだった。もう少し丹波哲郎が若い頃だったらもっと良かったか。アンヌ隊員の特別サービスには特撮ファンは発狂するであろう。全裸で小笠原流の挨拶をするシーンはとくに良い(笑)。なぜビデオが出ないのか?不思議だ。
五位 上意討ち拝領妻始末 監督小林正樹 脚本橋本忍
小林正樹は「切腹」よりこっちを選びたい。三度目の対決の三船敏郎と仲代達矢だが結果はご想像通り。しかし黒づくめの衣装で今回の仲代はなかなか格好良い。原作は滝口康彦のいわゆる武士道残酷物だが、映像はかなり格調が高い。志村けん真っ青の馬鹿殿を演じる松村達夫の演技に注目。確かレーザーディスクが出ている。
六位 大殺陣監督工藤栄一 脚本池上金男
暴政への最後の手段としてのテロ行為を完全に肯定する過激作品。リーダー格の侍(大坂志郎)が家族を斬殺するシークエンスを短いショットと手が震えて草鞋が結べないシーンで表現した手腕が見事である。テロに憑かれていく若侍役の里見浩太郎も珍しく好演している。七人の侍のひとりだった稲葉義男は見事な逃げっぷりで場内を沸かす。
七位 竜馬暗殺 監督黒木和雄 脚本清水邦夫・田辺泰志
此の作品の原田芳雄ははまり役である。ちょっとこれ以上の坂本竜馬は出てこないだろう。中岡慎太郎役の石橋蓮司も好演。史実に基づいた興味深い人間ドラマ。薩摩藩首謀説に近い。難解で空虚な作品が多いATG映画の最高傑作。
八位 斬る監督三隅研次 脚本新藤兼人
大映時代劇は市川雷蔵のニヒルなキャラクター。独特の陰影ある照明と撮影で独自のムードが感じられる。他にも大映は「不知火検校」(森一生監督)「刺青」(増村保造監督)と傑作が多いのだが、ここでは代表して一本、この作品を挙げたい。弟を救うために万里昌代が全裸で斬られるシーンの残酷美はこの作品の白眉である。ほかにも、愛し合いながらも笑顔で藤村志保の介錯をする天知茂であるとか、不条理でそれゆえに美しい場面が連続する。主人公の切腹で終わるラストも何故か心地よい。日本独自の美意識、価値観を伝えるという意味ではこの作品は最高傑作である。いきなりアメリカ人などに見せてハラキリマニアにしたくなる欲求にかられる(笑)。
岡本喜八監督にも「斬る」があるが、こちらは明るく痛快な作品である。
九位 御用金監督五社英雄 脚本田坂啓 五社英雄
稀代のカツドウ屋、五社英雄に敬意を表して一票。あの冗長なラストがなければもっといいのだが。雪の中での丹波哲郎と仲代達矢の対決は見物である。余談だが、中村錦之助が演じていた役は三船敏郎が演じる予定だったらしい。
「人斬り」も面白いがやはり岡田以蔵は細身でなくては・・・文豪三島の演じる田中新兵衛は最高なのだが。
十位 風林火山監督稲垣浩 脚本橋本忍 國弘威雄
佐藤勝のテーマ曲も勇ましい戦国絵巻。三船敏郎の山本勘助、中村錦之助の武田信玄はハマリ役。最近の研究によれば武田騎馬軍団は荷駄隊が主体であり、そうなるとこの映画も「影武者」もまったく嘘になるのだが・・・
緒形拳とか田村正和とか当代の売れっ子がチョイ役で出演しているのも見物である。
その他の作品
岡本喜八監督「斬る」百姓上がりで剛力無双の高橋悦史が鼻息も荒く大活躍。女郎屋に上がり込んでのセリフ「土の匂いがする女を頼む!」にはマイった。それで出てくるのが岡田可愛なんだから通には堪えられねえでガス。まあ下品な場面は何もないのだが。
同じ岡本監督の「侍」は侍ニッポンの何回目かの映画化でストーリー自体はパッとしないが、ラストの桜田門外の変の殺陣が凄絶極まる。三船敏郎の殺陣は同じく岡本監督の「大菩薩峠」での島田虎之助vs新撰組がいちばん凄かったと思う。
げてもんでは勝プロ作品の「御用牙」「御用牙かみそり半蔵地獄責め」がおすすめ。どちらもビデオが出ている。勝新が富田勲の音楽をバックに逸物鍛え上げるオープニングには、中村玉緒ならずとも驚愕するであろう。田村高広、黒沢年男と仇役に強そうな面々を揃えているのも買いである。
石井輝男監督は他にも「御金蔵破り」(脚本野上龍雄・石井輝男)を撮っているがこれも秀作。たびたびこれを焼き直した脚本をテレビ時代劇で見かける。二枚目気取りで鼻持ち成らない大川橋蔵と朝丘雪路のやりとりが活劇をだれさせること夥しいが。橋蔵は片岡千恵蔵御大を現場に待たせるなど極悪非道を尽くしたらしい。
その報復は、加藤泰監督の「幕末残酷物語」で河原崎長一郎扮する沖田総司がきっちりつけてくれるのでアンチ橋蔵ファンは必見だ(笑)。この映画は現在のところいちばん史実に近い新撰組映画だと思って間違いない。まあ大友柳太郎の山南敬介が死ぬところなど史実と大きく違うのは確かだが、残酷なテロ集団としての新撰組を描いているのはこの作品だけなのだから。そのなかで唯一血の通った人間として描かれるのが沖田総司なのだが、平目のようなご面相という評判と肖像画をまさに彷彿とさせる河原崎長一郎の演技は最高である。
新撰組映画といえば、沢島忠監督の三船プロ作品「新選組」もなかなか面白い。三船敏郎の近藤勇はともかく三国連太郎扮する芹沢鴨の酒乱演技は真に迫っている。北大路欣也の健康過ぎる沖田総司も必見(笑)。ラストの近藤勇の断首シーンはショッキングだ。
中村錦之助はどちらかというと股旅物のいなせなやくざが良いというひとが多いが、そのなかでもお薦めが山下耕作監督の「関の弥太っぺ」。死地に赴く主人公をローアングルで捉えるラストは素晴らしい。加藤泰監督の「瞼の母」「沓掛時次郎・遊侠一匹」(これは錦之助より渥美清が絶品)も傑作。
柳生ものでは東宝、稲垣浩作品「柳生武芸帳」二作が代表作か。三船敏郎と鶴田浩二の共演が楽しい。他にも中村扇雀、先代松本幸四郎、大河内伝次郎など当時の大物がずらり出演している。一作目の「柳生武芸帳」が三船敏郎主演、二作目の「双龍秘剣」が鶴田浩二主演という構成。
東映の「柳生一族の陰謀」も面白かった。錦之介のオーバーアクトが愉しめる。
他にも忘れちゃいけない大傑作が「十三人の刺客」(監督工藤栄一 脚本池上金男)である。
あまりにも有名になってしまった作品だが、宿場町を借り切って大名行列を襲うというアイデアは凄い。剣客の西村晃を中央に配したポスターも秀逸だった。
私の母方の先祖が明石藩関係者なので思わず敵役の内田良平を応援してしまう。
こうしてみるとベストテン圏外の作品のほうが面白そうだな。この選考の順位は選外も含めてきわめていい加減であることをここに宣言いたします(笑)。
大菩薩峠 (1966/日)
[Action]
製作 藤本真澄 / 佐藤正之 / 南里金春
監督 岡本喜八
脚本 橋本忍
原作 中里介山
撮影 村井博
美術 松山崇
音楽 佐藤勝
出演 仲代達矢 / 新珠三千代 / 加山雄三 / 内藤洋子 / 中丸忠雄 / 佐藤慶 / 西村晃 / 中谷一郎 / 田中邦衛 / 佐々木孝丸 / 香川良介 / 藤原釜足 / 天本英世 / 小川安三 / 川口敦子 / 大木正司 / 長谷川弘 / 木村博人 / 久野征四郎 / 滝恵一 / 三船敏郎
あらすじ 大菩薩峠の山頂で老巡礼(藤原釜足)を斬った机竜之助(仲代達矢)は帰宅して奉納試合で立ち合う予定の宇津木文之丞(中谷一郎)の妻お浜(新珠三千代)の訪問を受ける。自分の夫に勝ちを譲ってくれと言うのだ。しかし、竜之助はお浜を強姦し、試合では文之丞を撲殺したのである。2年後、お浜を連れて江戸へ出奔した竜之助は島田虎之助(三船敏郎)の道場で宇津木兵馬(加山雄三)を見掛け他流試合を申し込む。兵馬こそ文之丞の弟であった。その頃、江戸では新撰組が誕生し時代は風雲の兆しを迎えつつあった…。『大菩薩峠』4回目の映画化だが第1部だけしか作られなかった岡本喜八の監督第20作。 (けにろん) [投票]
Comments
全12 コメント>> 更新順 採点順 投票数順★5 カット割り、光と影、役者、そして殺陣。例え物語を大幅にはしょっていたとしても総てにうち震える。 [review] (ペペロンチーノ) [投票(1)]
★5 仲代の圧倒的ニヒリズム。殺陣の信じられない切れ方は現代では絶対再現不可能。中途半端で終わってしまうのが残念であるが、それを差し引いても数多ある60年代の時代劇の中で屹立したものの1本と信じて疑わない。 (けにろん) [投票(1)]
★4 仲代達矢の冷たい“眼”と三船敏郎の力強い“眼”と加山雄三の熱い“眼”。それにしてもよく斬れる刀だ。 (タモリ) [投票(1)]
★4 抜かば、斬る、斬らば、殺す、必ずに!!。あの三度笠も少し怖い。 [review] (あき♪) [投票(1)]
★4 クライマックスは壮絶の一言。これほどまでに狂気が充満した殺陣シーンを他に知らない。しかし、新珠三千代の性格描写はステレオタイプを通り越して頭弱いんじゃないかと思えてしまった。加山雄三も何しに出てきたんだか分からない。 (太陽と戦慄) [投票]
★4 物語の中の誰をとっても主人公になれるであろう密度の濃い書き込みがされている。未完の原作ならば、それを逆手にとって岡本喜八・橋本忍ならではの『続・大菩薩峠』を創って欲しかった。 (sawa38) [投票]
★4 全体よりも部分で魅せる。仲代、三船、加山、西村とはなんとスマートなキャスティング・センス。この面子で三部作付き合いたかった。 (とむとらばーつ) [投票]
★4 刀を血で洗う仲代達矢。これほどまでに理由のない悪だと見てて気持ちいい。けど、原作が未完でも映画は完結させてくれ! (リーダー) [投票]
★4 内田吐夢版の『大菩薩峠』の殺陣シーンには一寸がっかりした自分ですが(だって切れてないんだもの)これは大満足。もう斬りすぎるぐらい。 (coma) [投票]
★4 『斬る』とは打って変わって、陰気で邪悪な仲代。こういうキャラクターが主人公の時代劇もめずらしいのでは?それにしても西村晃の存在が中途半端・・・。 (リリアンヌ) [投票]
★3 人を斬れば斬るほど飢え恍惚とする仲代達矢。本物です。 [review] (たかやまひろふみ) [投票(3)]
★3 仲代達矢の演技力は、三船のそれに10倍する。が、しかし [review] (ころり) [投票]
Ratings5点 2人 **
4点 9人 *********
3点 6人 ******
2点 1人 *
1点 0人
計 18人 平均 ★3.7(* = 1)
[Action]
製作 藤本真澄 / 佐藤正之 / 南里金春
監督 岡本喜八
脚本 橋本忍
原作 中里介山
撮影 村井博
美術 松山崇
音楽 佐藤勝
出演 仲代達矢 / 新珠三千代 / 加山雄三 / 内藤洋子 / 中丸忠雄 / 佐藤慶 / 西村晃 / 中谷一郎 / 田中邦衛 / 佐々木孝丸 / 香川良介 / 藤原釜足 / 天本英世 / 小川安三 / 川口敦子 / 大木正司 / 長谷川弘 / 木村博人 / 久野征四郎 / 滝恵一 / 三船敏郎
あらすじ 大菩薩峠の山頂で老巡礼(藤原釜足)を斬った机竜之助(仲代達矢)は帰宅して奉納試合で立ち合う予定の宇津木文之丞(中谷一郎)の妻お浜(新珠三千代)の訪問を受ける。自分の夫に勝ちを譲ってくれと言うのだ。しかし、竜之助はお浜を強姦し、試合では文之丞を撲殺したのである。2年後、お浜を連れて江戸へ出奔した竜之助は島田虎之助(三船敏郎)の道場で宇津木兵馬(加山雄三)を見掛け他流試合を申し込む。兵馬こそ文之丞の弟であった。その頃、江戸では新撰組が誕生し時代は風雲の兆しを迎えつつあった…。『大菩薩峠』4回目の映画化だが第1部だけしか作られなかった岡本喜八の監督第20作。 (けにろん) [投票]
Comments
全12 コメント>> 更新順 採点順 投票数順★5 カット割り、光と影、役者、そして殺陣。例え物語を大幅にはしょっていたとしても総てにうち震える。 [review] (ペペロンチーノ) [投票(1)]
★5 仲代の圧倒的ニヒリズム。殺陣の信じられない切れ方は現代では絶対再現不可能。中途半端で終わってしまうのが残念であるが、それを差し引いても数多ある60年代の時代劇の中で屹立したものの1本と信じて疑わない。 (けにろん) [投票(1)]
★4 仲代達矢の冷たい“眼”と三船敏郎の力強い“眼”と加山雄三の熱い“眼”。それにしてもよく斬れる刀だ。 (タモリ) [投票(1)]
★4 抜かば、斬る、斬らば、殺す、必ずに!!。あの三度笠も少し怖い。 [review] (あき♪) [投票(1)]
★4 クライマックスは壮絶の一言。これほどまでに狂気が充満した殺陣シーンを他に知らない。しかし、新珠三千代の性格描写はステレオタイプを通り越して頭弱いんじゃないかと思えてしまった。加山雄三も何しに出てきたんだか分からない。 (太陽と戦慄) [投票]
★4 物語の中の誰をとっても主人公になれるであろう密度の濃い書き込みがされている。未完の原作ならば、それを逆手にとって岡本喜八・橋本忍ならではの『続・大菩薩峠』を創って欲しかった。 (sawa38) [投票]
★4 全体よりも部分で魅せる。仲代、三船、加山、西村とはなんとスマートなキャスティング・センス。この面子で三部作付き合いたかった。 (とむとらばーつ) [投票]
★4 刀を血で洗う仲代達矢。これほどまでに理由のない悪だと見てて気持ちいい。けど、原作が未完でも映画は完結させてくれ! (リーダー) [投票]
★4 内田吐夢版の『大菩薩峠』の殺陣シーンには一寸がっかりした自分ですが(だって切れてないんだもの)これは大満足。もう斬りすぎるぐらい。 (coma) [投票]
★4 『斬る』とは打って変わって、陰気で邪悪な仲代。こういうキャラクターが主人公の時代劇もめずらしいのでは?それにしても西村晃の存在が中途半端・・・。 (リリアンヌ) [投票]
★3 人を斬れば斬るほど飢え恍惚とする仲代達矢。本物です。 [review] (たかやまひろふみ) [投票(3)]
★3 仲代達矢の演技力は、三船のそれに10倍する。が、しかし [review] (ころり) [投票]
Ratings5点 2人 **
4点 9人 *********
3点 6人 ******
2点 1人 *
1点 0人
計 18人 平均 ★3.7(* = 1)
大菩薩峠
監督:岡本喜八
出演:仲代達矢、三船敏郎、加山雄三、新珠三千代、内藤洋子、西村晃
旅の巡礼をする老人を大菩薩峠で斬り殺したのは、机龍之介。彼は無音剣を操る無頼の
剣客であった。彼の元に、奉納試合で彼と対決することになっている宇津木文之丞の妻
はまが、勝負に負けてくれと懇願しに行く。が、龍之介は彼女を犯し、試合では文之丞を
殺してしまう。そして、はまを妻とする。文之丞の弟兵馬は復讐を誓い剣の腕を磨く。新撰
組に合流し京都へと行った龍之介は、その会合の宿で、彼が殺した老巡礼の孫娘お松に
出会い、錯乱する。
中里介山による有名な原作「大菩薩峠」は過去に片岡千恵蔵、市川雷蔵主演で映画化
されてきた。が、この岡本喜八監督、仲代達矢主演による作品は、とかく異彩を放ってい
る。複雑なキャラクターであり、徹底した悪人である龍之介を演じる仲代達矢は濃い。濃
すぎる。彼の目の輝きは、異常だ。そして、見所は、最初から最後まで、とにかく人を斬り
まくる龍之介。一度に数十人の敵を、表情一つ変えずに斬り、斬られた方は阿鼻叫喚と
共に、腕や手首や首を、まるでスプラッタ映画のごとく飛び散らせる。凄すぎるのは、ラス
トの京都の宿でのシーン。お松が幽霊を見た、というところから、龍之介も、彼がこれまで
に殺したおびただしい人々の霊を見るようになる。他の人々には何も見えないのに、彼は
亡霊だと思って部屋の簾を猛然と斬り始める。彼が狂乱したと思って集まってきた新撰組
の面々も、龍之介によって斬り殺される。すっかりキレてしまった彼が、足下をふらふらさ
せ、血を流しながらも殺戮マシーンと化す様子は圧倒的だ。夥しい数の人を、どれ一人同
じ方法で斬らず、いろんな角度で斬っており、場面作りは凝りに凝っている。そして迎える
唐突なエンディングには、しばし茫然。圧倒的なパワーのある作品だ。
とにかく濃くて強烈な龍之介に対して、「静」のキャラクターなのが、龍之介を仇とする兵馬
の剣の師匠島田虎之助、演じるは三船敏郎。「人を殺すための剣は、邪剣である」という
虎之助の言葉が、龍之介の心に引っかかり、最後の狂乱に結びつくのだった。
もう一つ印象的なのが、はま。夫を殺した龍之介になぜかついていき、彼の子供まで生ん
でしまう。しかし、剣の腕前は天下一品なのに、持ち前の性格ゆえ、剣の師匠であった父
からは破門され、剣客稼業という不安定な身分である龍之介に、彼女はいつも不平をこぼ
す。あなたと知り合わなかったら、文之丞と幸せな生活を続けることが出来たのに、と。こ
んな風にネガティブに描かれているヒロインというのはとても珍しい。恨み言ばかり言って
いるが、かなりしたたかな女性で、冒頭、水車小屋で龍之介に帯をほどけといわれたとき
も、自分からほどいていたくらい。水車にからまる帯がとてもエロティックだった。
岡本喜八は、インタビューで、原作もわけわからないので、脚本もわからないものになった
と答えている。ちなみに、脚本は「幻の湖」の橋本忍なのだが。話の方はどうにもならない
ため、とにかく龍之介の剣法を緻密に、凝りに凝ったものにすべく絵コンテを描きまくったそ
うだ。その成果は、十分発揮されている。ラスト15分間の、日本家屋の複雑な構造を逆手
に取った凄まじい殺戮シーンだけでも、見る価値は十分にある。
それと、お松役の内藤洋子の清楚な美しさは特筆すべきだ。娘の喜多嶋舞の数倍可憐で
美しい。西村晃、佐藤慶など脇役の存在感も光っている。
ジャズ大名
監督:岡本喜八
出演:古谷一行、財津一郎、本田博太郎
幕末、駿河の国の貧乏な藩の殿様は退屈していた。そんなところへ漂流して流れ着いたの
は、アフリカを目指していた黒人3人組。楽器を持参していた黒人三人は、ジャズの演奏を
始め、殿様もクラリネットの吹き方を教えてもらい熱中する。やがて大政奉還となり、城が江
戸と京都を結ぶ街道の通り道となるため、殿様は上の階を往来に開放し、下の階で一大ジ
ャムセッションが繰り広げられる。演奏を終えて地上に出てみると、明治の世の中になって
いた。
なんとも楽しい映画だ。アメリカ南部で食い詰めた黒人達が、アフリカを目指すためメキシコ
国境に入り、楽器を手に船に乗る。4人集まって曲が作られていく過程からして奇想天外で
面白い。インディアンの居留地では、彼らの演奏がうるさいと矢が飛んでくる。黒人達の英
語の台詞の上に、南部訛を日本語にしたらこんな感じになるのかな?という感じのなまった
日本語のボイスオーバーがかぶせてあるのがおかしい。この映画で圧倒的に面白いのは、
売り物のジャムセッションよりも、この最初の15分あまりじゃないかな。腹を抱えてしまうほ
どのおかしさだ。
長くて困難な船旅の末に日本に流れ着いた彼らを助けたのは、やはり生活に困って心中を
企てていた一家。殿様の日常生活の描写も面白い。貧乏な藩なので城はボロボロ、茶どこ
ろの静岡なのに、客人に出すお茶は出がらし。おてんばな殿様の妹は算盤をローラースケー
ト代わりに場内をすべりまわり、家来達は一度も使ったことのない大砲を一日磨いている。
殿様は不快な音を出す笛のような楽器を一日中吹いていて迷惑がられている。まったく威
厳のない殿様だ。そんなところへ、今まで見たことのないような黒人の男が3人。しかも、楽
器を持っていて、地下牢で演奏している。退屈な生活に飽き飽きしている殿様は、彼らの演
奏を聴きに行きたくて仕方ないが、家来どもが反対してなかなか行けない。彼が行きたくて
行きたくてウズウズするさまが、ほほえましい。
そして、明治維新前夜の、一大ジャムセッションは圧巻。女中達も、城の中を片づけながら、
琴や三味線、さらには鍋なども使って演奏。堅物の老中も、ついには太鼓を片手に。算盤も
パーカッションに変身。最初は上品に琴をつま弾いていた女達も、琴を立てて持って、ウッド
ベースでも弾いているのではないかというワイルドな演奏を聴かせる。往来を通りかかった
百姓一揆の面々も「ええじゃないか」と唱和しながら加わり(心中しようとしていた一家も、死
ぬことなんて忘れて踊り狂っている)、お坊さんも木魚を叩いて参加。演奏は一晩中続き、み
んな我を忘れてどんちゃん騒ぎ。気がついたら江戸時代が終わり明治になっていた!という
展開がいい。
一つの時代が終わり、新しい時代が始まり、鎖国が解け、文明開化となるという歴史の流れ
を、面白おかしく象徴させている。ジャム・セッションにはいつのまにかミッキー・カーチス、お
もちゃのピアノを弾く山下洋輔、そして屋台を引くタモリまでもが参加していて、最後はもう何
でもアリな状態。ウキウキした気分で映画館を後にすることが出来た。
監督:岡本喜八
出演:仲代達矢、三船敏郎、加山雄三、新珠三千代、内藤洋子、西村晃
旅の巡礼をする老人を大菩薩峠で斬り殺したのは、机龍之介。彼は無音剣を操る無頼の
剣客であった。彼の元に、奉納試合で彼と対決することになっている宇津木文之丞の妻
はまが、勝負に負けてくれと懇願しに行く。が、龍之介は彼女を犯し、試合では文之丞を
殺してしまう。そして、はまを妻とする。文之丞の弟兵馬は復讐を誓い剣の腕を磨く。新撰
組に合流し京都へと行った龍之介は、その会合の宿で、彼が殺した老巡礼の孫娘お松に
出会い、錯乱する。
中里介山による有名な原作「大菩薩峠」は過去に片岡千恵蔵、市川雷蔵主演で映画化
されてきた。が、この岡本喜八監督、仲代達矢主演による作品は、とかく異彩を放ってい
る。複雑なキャラクターであり、徹底した悪人である龍之介を演じる仲代達矢は濃い。濃
すぎる。彼の目の輝きは、異常だ。そして、見所は、最初から最後まで、とにかく人を斬り
まくる龍之介。一度に数十人の敵を、表情一つ変えずに斬り、斬られた方は阿鼻叫喚と
共に、腕や手首や首を、まるでスプラッタ映画のごとく飛び散らせる。凄すぎるのは、ラス
トの京都の宿でのシーン。お松が幽霊を見た、というところから、龍之介も、彼がこれまで
に殺したおびただしい人々の霊を見るようになる。他の人々には何も見えないのに、彼は
亡霊だと思って部屋の簾を猛然と斬り始める。彼が狂乱したと思って集まってきた新撰組
の面々も、龍之介によって斬り殺される。すっかりキレてしまった彼が、足下をふらふらさ
せ、血を流しながらも殺戮マシーンと化す様子は圧倒的だ。夥しい数の人を、どれ一人同
じ方法で斬らず、いろんな角度で斬っており、場面作りは凝りに凝っている。そして迎える
唐突なエンディングには、しばし茫然。圧倒的なパワーのある作品だ。
とにかく濃くて強烈な龍之介に対して、「静」のキャラクターなのが、龍之介を仇とする兵馬
の剣の師匠島田虎之助、演じるは三船敏郎。「人を殺すための剣は、邪剣である」という
虎之助の言葉が、龍之介の心に引っかかり、最後の狂乱に結びつくのだった。
もう一つ印象的なのが、はま。夫を殺した龍之介になぜかついていき、彼の子供まで生ん
でしまう。しかし、剣の腕前は天下一品なのに、持ち前の性格ゆえ、剣の師匠であった父
からは破門され、剣客稼業という不安定な身分である龍之介に、彼女はいつも不平をこぼ
す。あなたと知り合わなかったら、文之丞と幸せな生活を続けることが出来たのに、と。こ
んな風にネガティブに描かれているヒロインというのはとても珍しい。恨み言ばかり言って
いるが、かなりしたたかな女性で、冒頭、水車小屋で龍之介に帯をほどけといわれたとき
も、自分からほどいていたくらい。水車にからまる帯がとてもエロティックだった。
岡本喜八は、インタビューで、原作もわけわからないので、脚本もわからないものになった
と答えている。ちなみに、脚本は「幻の湖」の橋本忍なのだが。話の方はどうにもならない
ため、とにかく龍之介の剣法を緻密に、凝りに凝ったものにすべく絵コンテを描きまくったそ
うだ。その成果は、十分発揮されている。ラスト15分間の、日本家屋の複雑な構造を逆手
に取った凄まじい殺戮シーンだけでも、見る価値は十分にある。
それと、お松役の内藤洋子の清楚な美しさは特筆すべきだ。娘の喜多嶋舞の数倍可憐で
美しい。西村晃、佐藤慶など脇役の存在感も光っている。
ジャズ大名
監督:岡本喜八
出演:古谷一行、財津一郎、本田博太郎
幕末、駿河の国の貧乏な藩の殿様は退屈していた。そんなところへ漂流して流れ着いたの
は、アフリカを目指していた黒人3人組。楽器を持参していた黒人三人は、ジャズの演奏を
始め、殿様もクラリネットの吹き方を教えてもらい熱中する。やがて大政奉還となり、城が江
戸と京都を結ぶ街道の通り道となるため、殿様は上の階を往来に開放し、下の階で一大ジ
ャムセッションが繰り広げられる。演奏を終えて地上に出てみると、明治の世の中になって
いた。
なんとも楽しい映画だ。アメリカ南部で食い詰めた黒人達が、アフリカを目指すためメキシコ
国境に入り、楽器を手に船に乗る。4人集まって曲が作られていく過程からして奇想天外で
面白い。インディアンの居留地では、彼らの演奏がうるさいと矢が飛んでくる。黒人達の英
語の台詞の上に、南部訛を日本語にしたらこんな感じになるのかな?という感じのなまった
日本語のボイスオーバーがかぶせてあるのがおかしい。この映画で圧倒的に面白いのは、
売り物のジャムセッションよりも、この最初の15分あまりじゃないかな。腹を抱えてしまうほ
どのおかしさだ。
長くて困難な船旅の末に日本に流れ着いた彼らを助けたのは、やはり生活に困って心中を
企てていた一家。殿様の日常生活の描写も面白い。貧乏な藩なので城はボロボロ、茶どこ
ろの静岡なのに、客人に出すお茶は出がらし。おてんばな殿様の妹は算盤をローラースケー
ト代わりに場内をすべりまわり、家来達は一度も使ったことのない大砲を一日磨いている。
殿様は不快な音を出す笛のような楽器を一日中吹いていて迷惑がられている。まったく威
厳のない殿様だ。そんなところへ、今まで見たことのないような黒人の男が3人。しかも、楽
器を持っていて、地下牢で演奏している。退屈な生活に飽き飽きしている殿様は、彼らの演
奏を聴きに行きたくて仕方ないが、家来どもが反対してなかなか行けない。彼が行きたくて
行きたくてウズウズするさまが、ほほえましい。
そして、明治維新前夜の、一大ジャムセッションは圧巻。女中達も、城の中を片づけながら、
琴や三味線、さらには鍋なども使って演奏。堅物の老中も、ついには太鼓を片手に。算盤も
パーカッションに変身。最初は上品に琴をつま弾いていた女達も、琴を立てて持って、ウッド
ベースでも弾いているのではないかというワイルドな演奏を聴かせる。往来を通りかかった
百姓一揆の面々も「ええじゃないか」と唱和しながら加わり(心中しようとしていた一家も、死
ぬことなんて忘れて踊り狂っている)、お坊さんも木魚を叩いて参加。演奏は一晩中続き、み
んな我を忘れてどんちゃん騒ぎ。気がついたら江戸時代が終わり明治になっていた!という
展開がいい。
一つの時代が終わり、新しい時代が始まり、鎖国が解け、文明開化となるという歴史の流れ
を、面白おかしく象徴させている。ジャム・セッションにはいつのまにかミッキー・カーチス、お
もちゃのピアノを弾く山下洋輔、そして屋台を引くタモリまでもが参加していて、最後はもう何
でもアリな状態。ウキウキした気分で映画館を後にすることが出来た。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
橋本 忍 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
橋本 忍のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37859人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90054人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208307人