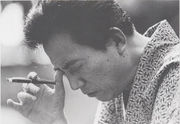http://
1967年度芸術祭文部大臣賞受賞、キネマ旬報ベストテン第3位。
スタッフ
製作:藤本真澄/田中友幸
監督:岡本喜八
原作:大宅壮一
脚本:橋本忍
音楽:佐藤勝
[編集]
配役
三船敏郎 : 阿南惟幾(陸相)
山村聡 : 米内光政(海相)
笠智衆 : 鈴木貫太郎(首相)
宮口精二 : 東郷茂徳(外相)
香川良介 : 石黒忠篤(農商相)
竜岡晋 : 石渡荘太郎(宮内相)
北沢彪 : 広瀬豊作(蔵相)
村上冬樹 : 松阪広政(司法相)
志村喬 : 下村宏(情報局総裁)
戸浦六宏 : 松本俊一(外務次官)
小瀬格 : 若松只一(陸軍次官)
中村伸郎 : 木戸幸一(内大臣)
青野平義 : 藤田尚徳(侍従長)
児玉清 : 戸田康英(侍従)
袋正 : 入江相政(侍従)
小林桂樹 : 徳川義寛(侍従)
加藤武 : 迫水久常(内閣書記官長)
北村和夫 : 佐藤総務課長(内閣官房)
玉川伊佐男 : 荒尾興攻(陸軍省軍事課長)
高橋悦史 : 井田中佐(陸軍省軍務課員)
中丸忠雄 : 椎崎中佐(陸軍省軍事課員)
井上孝雄 : 竹下中佐(陸軍省軍事課員)
黒沢年男 : 畑中少佐(陸軍省軍事課員)
吉頂寺晃 : 梅津美治郎(陸軍参謀総長)
岩谷壮 : 杉山元(陸軍元帥)
今福正雄 : 畑俊六(陸軍元帥)
山田晴生 : 豊田副武(海軍軍令部総長)
二本柳寛 : 大西瀧治郎(海軍軍令部次長)
明石潮 : 平沼騏一郎(枢密院議長)
島田正吾 : 森赳(近衛師団長)
藤田進 : 芳賀大佐(近衛師団)
佐藤允 : 古賀少佐(近衛師団)
久保明 : 石原少佐(近衛師団)
石山健二郎 : 田中静壱(東部軍司令官)
土屋嘉男 : 不破参謀(東部軍)
勝部演之 : 白石中佐(第二総軍)
加東大介 : 矢野国内局長(NHK職員)
加山雄三 : 館野守男(NHK職員)
小泉博 : 和田信賢(NHK職員)
新珠三千代 : 原百合子
川辺久造 : 木原通雄
神山繁 : 加藤総務局長(宮内省職員)
浜村純 : 筧庶務課長(宮内省職員)
天本英世 : 佐々木大尉(横浜警備隊長)
中谷一郎 : 黒田大尉(航空士官学校)
伊藤雄之助 : 野中大佐(児玉基地)
田崎潤 : 小薗大佐(厚木基地)
平田昭彦 : 菅原中佐(厚木基地)
井川比佐志 : 憲兵中尉
松本幸四郎 (8代目) : 昭和天皇
仲代達矢 : ナレーター
1967年度芸術祭文部大臣賞受賞、キネマ旬報ベストテン第3位。
スタッフ
製作:藤本真澄/田中友幸
監督:岡本喜八
原作:大宅壮一
脚本:橋本忍
音楽:佐藤勝
[編集]
配役
三船敏郎 : 阿南惟幾(陸相)
山村聡 : 米内光政(海相)
笠智衆 : 鈴木貫太郎(首相)
宮口精二 : 東郷茂徳(外相)
香川良介 : 石黒忠篤(農商相)
竜岡晋 : 石渡荘太郎(宮内相)
北沢彪 : 広瀬豊作(蔵相)
村上冬樹 : 松阪広政(司法相)
志村喬 : 下村宏(情報局総裁)
戸浦六宏 : 松本俊一(外務次官)
小瀬格 : 若松只一(陸軍次官)
中村伸郎 : 木戸幸一(内大臣)
青野平義 : 藤田尚徳(侍従長)
児玉清 : 戸田康英(侍従)
袋正 : 入江相政(侍従)
小林桂樹 : 徳川義寛(侍従)
加藤武 : 迫水久常(内閣書記官長)
北村和夫 : 佐藤総務課長(内閣官房)
玉川伊佐男 : 荒尾興攻(陸軍省軍事課長)
高橋悦史 : 井田中佐(陸軍省軍務課員)
中丸忠雄 : 椎崎中佐(陸軍省軍事課員)
井上孝雄 : 竹下中佐(陸軍省軍事課員)
黒沢年男 : 畑中少佐(陸軍省軍事課員)
吉頂寺晃 : 梅津美治郎(陸軍参謀総長)
岩谷壮 : 杉山元(陸軍元帥)
今福正雄 : 畑俊六(陸軍元帥)
山田晴生 : 豊田副武(海軍軍令部総長)
二本柳寛 : 大西瀧治郎(海軍軍令部次長)
明石潮 : 平沼騏一郎(枢密院議長)
島田正吾 : 森赳(近衛師団長)
藤田進 : 芳賀大佐(近衛師団)
佐藤允 : 古賀少佐(近衛師団)
久保明 : 石原少佐(近衛師団)
石山健二郎 : 田中静壱(東部軍司令官)
土屋嘉男 : 不破参謀(東部軍)
勝部演之 : 白石中佐(第二総軍)
加東大介 : 矢野国内局長(NHK職員)
加山雄三 : 館野守男(NHK職員)
小泉博 : 和田信賢(NHK職員)
新珠三千代 : 原百合子
川辺久造 : 木原通雄
神山繁 : 加藤総務局長(宮内省職員)
浜村純 : 筧庶務課長(宮内省職員)
天本英世 : 佐々木大尉(横浜警備隊長)
中谷一郎 : 黒田大尉(航空士官学校)
伊藤雄之助 : 野中大佐(児玉基地)
田崎潤 : 小薗大佐(厚木基地)
平田昭彦 : 菅原中佐(厚木基地)
井川比佐志 : 憲兵中尉
松本幸四郎 (8代目) : 昭和天皇
仲代達矢 : ナレーター
|
|
|
|
コメント(7)
【神宮寺表参道映画館】より
日本のいちばん長い日
1967年8月公開
監督 岡本喜八
脚本 橋本忍
セリフを暗記するほどみた映画というのが何本かある。
この「日本のいちばん長い日」がそんな映画のひとつだ。
昭和20年7月、米英中国よりポツダム宣言が通告される。
政府は閣議を何回も開くがポツダム宣言を受諾するかどうかの
結論は容易には出ない。その間に広島、長崎に原爆投下、
ソ連の参戦と事態はますます悪化する。
結局最後は天皇に直接御聖断を仰ぐことになる。
8月14日、ついに御前会議は開かれ天皇は決断した。
「戦争の継続は民族の滅亡を意味する。速やかに終結せしめたい」
こうして緊迫の24時間、「日本のいちばん長い日」は始まった。
2時間半を超える大作。
この8月14日の昼の12時の天皇の御聖断のシーンまでで20分。
ここでようやくメインタイトルがでるような長い前振り。
この映画の魅力は何といっても日本映画男優オールスターズの
演技合戦だ。
戦争遂行派による軍事クーデターを主軸として同時に壮大なディスカッション
ドラマでもある。
「日本にもう戦う力なぞは・・・」(石黒農相)
「天皇および日本国政府は連合国司令官にサブジェクト・トゥするとなっており
これは隷属であり絶対受諾など出来ません!」(畑中少佐)
「戦争が継続になったら何もかもおしまいだ。いざとなったらもうこれ(青酸カリによる自決)
しか方法がないかも知れんね」(迫水書記官長)
「もうあと二千万、日本人の男子の半分を特攻に出す覚悟で戦えば、必ず、必ず勝てます!」
(大西海軍軍令部次長)
「勝つか負けるかはもう問題ではない。日本の国民を生かすか殺すかなのです」(東郷外相)
「陸軍大臣も部内からの突き上げで苦しいのです。待てるものならもう二日
待ってあげることは出来ないでしょうか」(小林海軍軍医)
「万一終戦と決まった場合、東部軍の作戦参謀としてどのような態度をとるべきかでありますが」
(東部軍・不破参謀)
「下らん上層部の右往左往など気にするな。厚木基地は最後まで戦うぞ!」
(厚木基地・小園司令)
「建軍以来一度も敗戦を知らず、『生きて虜囚の辱めを受けず』と徹底的に教育されて
ますからね」
(蓮沼侍従武官長)
「いまさら論じてももうどうにもならん。行動あるのみだ」(椎崎中佐)
「この決定に逆らうものは反乱軍、というわけだな」(第二総軍・畑元帥)
「市谷台の将校は全員切腹するのだ」(井田中佐)
「陸相は今までの戦闘を単に補給戦に負けたに過ぎんとその責任を他の部門に
転嫁されようとるのか!」(米内海相)
「多くの兵がなぜ死んでいったのだ!みんな日本の勝利を固く信じていたからではないのか!
彼らにはなんとしても栄光ある敗北を与えねばならん」(阿南陸相)
「ついては軍の真意をお聞かせ願いたい」(第二総軍参謀・白石中佐)
「皇軍の辞書に降伏の二字なし」(横浜警備隊長・佐々木大尉)
「皇国の勝敗はかかって諸君の双肩にある」(児玉基地・野中大佐)
「天皇がやめろと言われるからやめる。聞こえはいいがこれは一種の責任逃れです」
(井田中佐)
「私はこれから明治神宮に行きその社前に額ずき、一人の赤裸々な日本人として右するか
左するか決めたいと思う」(森近衛師団長)
「私も戦争終結には反対です。いまさら無条件降伏など」(首相官邸警備の警官)
「君達だけが国を守ってるのではない。われわれ国民全員が力をあわせなくては」(徳川侍従)
「直ちに反乱軍を鎮圧する!」(田中東部軍司令官)
「現在は警戒警報発令中であり、東部軍の許可のない限り放送は出来ません」
(NHK館野アナウンサー)
「あらゆる手続きが必要だ。儀式と言ったほうがいいのかも知れない。
何しろ大日本帝国のお葬式だからね」(下村情報局総裁)
「もう年寄りの出る幕じゃないよ。これからはもっと若い人の時代でね」(鈴木首相)
「このたびの放送は天皇自らがわれわれ兵を直接叱咤激励してくれると信じている者が多数
おるようでありますが」(児玉基地・将校)
これほどのディスカッションドラマを飽きることなく見せるリズムの妙、編集の間がすばらしい。
セリフが終わるか終わらないかの内に次のカットにつないでいくその間の見事さ。
時折挿入される軍服にしみた汗、軍刀を握り締める手のアップ、音のアクセントをつける
軍靴の響き、油の切れた自転車のキーキー音。
メリハリの見事さスピード感だけでない、アクセントをつけたテンポのよさが2時間半を
あきさせない。
また玉音放送録音シーンと埼玉県児玉基地の深夜の特攻出撃シーンのモンタージュには
むなしさが漂う。
この映画に登場する男達は皆一様にストイックだ。
自己保身の欲望より日本のために何が正しいかを(たとえ後から考えると間違っていた
にしても)真剣に論じている。
その姿は美しく、下手をすれば戦争遂行論者への肯定論にもつながりかねない危うさを
秘めている。
もちろん岡本喜八の真意はそこに合ったわけではない。
児玉基地の特攻出撃シーンにおける若者の姿(おはぎにむしゃぶりつくと言ったような)や
横浜警備隊の学生(阿知波信介)が持っている岩波文庫にこそ
死んでいった者への鎮魂歌を感じることが出来る。
現在のわれわれの繁栄はこの昭和20年8月15日の決定の上に成り立っている。
その繁栄が腐敗へと転じている現在、国を立て直そうと私利私欲を捨てた行動の男達の
姿には見習うものがある。
(2002年中国・瀋陽の北朝鮮人亡命問題で有名になった阿南中国大使は
この映画に登場する阿南陸軍大臣の息子なのだ)
もちろん現実は映画と違ってあんな奇麗事ではなかったという批判もあろう。
申し訳ないが1本の映画として純粋に観賞していただきたい。
この映画に登場する男たちの真摯な姿は実に美しい。
(何しろセリフのある女優は新珠三千代だけ。しかもワンシーンのみだ)
それが僕にとってはセリフを暗記させるほど見ても飽きない魅力なのだろう。
日本人はこの映画を全員見るべきだ。
その価値はある。
日本のいちばん長い日
1967年8月公開
監督 岡本喜八
脚本 橋本忍
セリフを暗記するほどみた映画というのが何本かある。
この「日本のいちばん長い日」がそんな映画のひとつだ。
昭和20年7月、米英中国よりポツダム宣言が通告される。
政府は閣議を何回も開くがポツダム宣言を受諾するかどうかの
結論は容易には出ない。その間に広島、長崎に原爆投下、
ソ連の参戦と事態はますます悪化する。
結局最後は天皇に直接御聖断を仰ぐことになる。
8月14日、ついに御前会議は開かれ天皇は決断した。
「戦争の継続は民族の滅亡を意味する。速やかに終結せしめたい」
こうして緊迫の24時間、「日本のいちばん長い日」は始まった。
2時間半を超える大作。
この8月14日の昼の12時の天皇の御聖断のシーンまでで20分。
ここでようやくメインタイトルがでるような長い前振り。
この映画の魅力は何といっても日本映画男優オールスターズの
演技合戦だ。
戦争遂行派による軍事クーデターを主軸として同時に壮大なディスカッション
ドラマでもある。
「日本にもう戦う力なぞは・・・」(石黒農相)
「天皇および日本国政府は連合国司令官にサブジェクト・トゥするとなっており
これは隷属であり絶対受諾など出来ません!」(畑中少佐)
「戦争が継続になったら何もかもおしまいだ。いざとなったらもうこれ(青酸カリによる自決)
しか方法がないかも知れんね」(迫水書記官長)
「もうあと二千万、日本人の男子の半分を特攻に出す覚悟で戦えば、必ず、必ず勝てます!」
(大西海軍軍令部次長)
「勝つか負けるかはもう問題ではない。日本の国民を生かすか殺すかなのです」(東郷外相)
「陸軍大臣も部内からの突き上げで苦しいのです。待てるものならもう二日
待ってあげることは出来ないでしょうか」(小林海軍軍医)
「万一終戦と決まった場合、東部軍の作戦参謀としてどのような態度をとるべきかでありますが」
(東部軍・不破参謀)
「下らん上層部の右往左往など気にするな。厚木基地は最後まで戦うぞ!」
(厚木基地・小園司令)
「建軍以来一度も敗戦を知らず、『生きて虜囚の辱めを受けず』と徹底的に教育されて
ますからね」
(蓮沼侍従武官長)
「いまさら論じてももうどうにもならん。行動あるのみだ」(椎崎中佐)
「この決定に逆らうものは反乱軍、というわけだな」(第二総軍・畑元帥)
「市谷台の将校は全員切腹するのだ」(井田中佐)
「陸相は今までの戦闘を単に補給戦に負けたに過ぎんとその責任を他の部門に
転嫁されようとるのか!」(米内海相)
「多くの兵がなぜ死んでいったのだ!みんな日本の勝利を固く信じていたからではないのか!
彼らにはなんとしても栄光ある敗北を与えねばならん」(阿南陸相)
「ついては軍の真意をお聞かせ願いたい」(第二総軍参謀・白石中佐)
「皇軍の辞書に降伏の二字なし」(横浜警備隊長・佐々木大尉)
「皇国の勝敗はかかって諸君の双肩にある」(児玉基地・野中大佐)
「天皇がやめろと言われるからやめる。聞こえはいいがこれは一種の責任逃れです」
(井田中佐)
「私はこれから明治神宮に行きその社前に額ずき、一人の赤裸々な日本人として右するか
左するか決めたいと思う」(森近衛師団長)
「私も戦争終結には反対です。いまさら無条件降伏など」(首相官邸警備の警官)
「君達だけが国を守ってるのではない。われわれ国民全員が力をあわせなくては」(徳川侍従)
「直ちに反乱軍を鎮圧する!」(田中東部軍司令官)
「現在は警戒警報発令中であり、東部軍の許可のない限り放送は出来ません」
(NHK館野アナウンサー)
「あらゆる手続きが必要だ。儀式と言ったほうがいいのかも知れない。
何しろ大日本帝国のお葬式だからね」(下村情報局総裁)
「もう年寄りの出る幕じゃないよ。これからはもっと若い人の時代でね」(鈴木首相)
「このたびの放送は天皇自らがわれわれ兵を直接叱咤激励してくれると信じている者が多数
おるようでありますが」(児玉基地・将校)
これほどのディスカッションドラマを飽きることなく見せるリズムの妙、編集の間がすばらしい。
セリフが終わるか終わらないかの内に次のカットにつないでいくその間の見事さ。
時折挿入される軍服にしみた汗、軍刀を握り締める手のアップ、音のアクセントをつける
軍靴の響き、油の切れた自転車のキーキー音。
メリハリの見事さスピード感だけでない、アクセントをつけたテンポのよさが2時間半を
あきさせない。
また玉音放送録音シーンと埼玉県児玉基地の深夜の特攻出撃シーンのモンタージュには
むなしさが漂う。
この映画に登場する男達は皆一様にストイックだ。
自己保身の欲望より日本のために何が正しいかを(たとえ後から考えると間違っていた
にしても)真剣に論じている。
その姿は美しく、下手をすれば戦争遂行論者への肯定論にもつながりかねない危うさを
秘めている。
もちろん岡本喜八の真意はそこに合ったわけではない。
児玉基地の特攻出撃シーンにおける若者の姿(おはぎにむしゃぶりつくと言ったような)や
横浜警備隊の学生(阿知波信介)が持っている岩波文庫にこそ
死んでいった者への鎮魂歌を感じることが出来る。
現在のわれわれの繁栄はこの昭和20年8月15日の決定の上に成り立っている。
その繁栄が腐敗へと転じている現在、国を立て直そうと私利私欲を捨てた行動の男達の
姿には見習うものがある。
(2002年中国・瀋陽の北朝鮮人亡命問題で有名になった阿南中国大使は
この映画に登場する阿南陸軍大臣の息子なのだ)
もちろん現実は映画と違ってあんな奇麗事ではなかったという批判もあろう。
申し訳ないが1本の映画として純粋に観賞していただきたい。
この映画に登場する男たちの真摯な姿は実に美しい。
(何しろセリフのある女優は新珠三千代だけ。しかもワンシーンのみだ)
それが僕にとってはセリフを暗記させるほど見ても飽きない魅力なのだろう。
日本人はこの映画を全員見るべきだ。
その価値はある。
◎日本映画の感想文より
現代劇が主体の東宝では、頭をマルガリータにしないといけない陸軍ものは少ない。したがって、東宝の若手男優はほとんど出演しているのだが、営業活動に影響が大きいと思われるスタアは民間人役か出ていないか、どっちか
畑中少佐(黒沢年男)と椎崎中佐(中丸忠雄)が自決するシーンは皇居の中間芝でゲリラ撮影。万が一のときのことを考えて役者はともかく逃がすとして、監督自身は捕まる覚悟をしたらしい。で、ブタ箱には歯ブラシが無いと聞いて密かにポケットに持参していたそうだ。
そんなこんなであるから、いくらフィクションであると断わり書きをいれても実在の人物を実名で登場させるときには相当神経をつかったと推察されるわけだ。
戦後20年以上を経過しているとはいえ、遺族はもちろんまだ存命中の人物も多くいるこの作品には「実名」で昭和天皇が登場する。玉音放送、御前会議のシーンで姿形は遠目にぼやけているが声は明瞭に聞こえる。演技者=声の主(松本幸四郎)は言われてみればなる程とわかるが本物と区別がつかないくらい似ている絶妙のキャスティングである。
ポツダム宣言が「黙殺」から「拒絶」と解釈されて広島/長崎に原爆が投下されついに日本は終戦を迎えることになった。有史以来、敗戦の経験がない国家における不安と焦り。映画は渦中の軍部と内閣の動きを克明に取材した大宅壮一の原作を映像化している。特に戦争の責任はもとより自分達のレーゾンデートルそのものをゆるがす「敗戦」に拒絶反応を起こした軍人達のあがきが凄まじい迫力で描かれる。
近衛師団長の暗殺、ニセの命令書を作成し宮城を占拠し、玉音盤(レコード)を強奪しようとする青年将校達。対してこの敗戦処理をすみやかに行うために奔走する閣僚と官僚、終戦前夜に特別攻撃隊として出撃していくゼロ戦、日本が未曾有の事態へ向かって刻一刻と進んでいく姿。
近衛師団長・島田正吾のところへ決起を促すべく反乱将校の黒沢年男と中丸忠雄が交渉に赴く。決起の意思が無いと判断されたその時、駆けつけた中谷一郎が島田のからだに日本刀を降りおろす。「椿三十郎」レベルの血飛沫とともに床に音を立てて落下する師団長の首。あたり一面の流血。興奮しきった中谷一郎の手は硬直して握った日本刀を離せない。机に軍刀の柄をたたきつける音。これらが一気に、劇伴なしのモノクロの画面で繰り広げられるところは、一級のホラー映画の迫力だ。
反乱が失敗し玉音放送が流れ、徹底抗戦をさけぶアジビラがまかれ、青年将校達は宮城前で自決する。陸軍大臣、阿南・三船敏郎は自宅で、元近衛師団だったときのワイシャツを着て切腹する。別に軍人精神を称えるわけではないけれど、この映画で描かれたような軍人達の多くは殉死することもなく、戦争犯罪人として裁かれることもなく、その後も生き延びていく。
岡本喜八監督の戦争に対する「怒り」はこの映画のいろんなところに見受けられる。特別攻撃隊を見送る士官・伊藤雄之助の姿に、岡本監督の怒りが特に集中しているようだ。当時食料事情が悪かったから甘いものに飢えていたであろう少年のような兵隊が出撃直前にうまそうにボタモチを食べているシーン。二度と帰らない少年たちを見送る中年の伊藤のショットには、静かだが強烈なメッセージを感じた。
青年将校達の交通手段は自転車。夏の暑い盛り(8月14日)にかなりボロい自転車をキーキーいわせながら漕いで行く。軍服ったって今みたいに上等なサマーウールとかじゃないから、毛布みたいな分厚い素材なのにその上に染み出した汗。この暑さと汗が私には印象深い。単なる軍部のテロ映画ではなく、戦争に疲弊した日本と日本人全てにとっても「長い一日」だったんだなあということが、市井の人々がほとんど登場しないにもかかわらずとてもよく伝わってきた。
ナレーションの仲代達矢、新聞記者の三井弘次(「天国と地獄」のときも良かった)、NHKアナウンサーの加山雄三、近衛師団長の縁戚で反乱将校の佐藤允、シーンは少ないがいずれも重要な役で登場する、東宝のオールスター戦争映画。
現代劇が主体の東宝では、頭をマルガリータにしないといけない陸軍ものは少ない。したがって、東宝の若手男優はほとんど出演しているのだが、営業活動に影響が大きいと思われるスタアは民間人役か出ていないか、どっちか
畑中少佐(黒沢年男)と椎崎中佐(中丸忠雄)が自決するシーンは皇居の中間芝でゲリラ撮影。万が一のときのことを考えて役者はともかく逃がすとして、監督自身は捕まる覚悟をしたらしい。で、ブタ箱には歯ブラシが無いと聞いて密かにポケットに持参していたそうだ。
そんなこんなであるから、いくらフィクションであると断わり書きをいれても実在の人物を実名で登場させるときには相当神経をつかったと推察されるわけだ。
戦後20年以上を経過しているとはいえ、遺族はもちろんまだ存命中の人物も多くいるこの作品には「実名」で昭和天皇が登場する。玉音放送、御前会議のシーンで姿形は遠目にぼやけているが声は明瞭に聞こえる。演技者=声の主(松本幸四郎)は言われてみればなる程とわかるが本物と区別がつかないくらい似ている絶妙のキャスティングである。
ポツダム宣言が「黙殺」から「拒絶」と解釈されて広島/長崎に原爆が投下されついに日本は終戦を迎えることになった。有史以来、敗戦の経験がない国家における不安と焦り。映画は渦中の軍部と内閣の動きを克明に取材した大宅壮一の原作を映像化している。特に戦争の責任はもとより自分達のレーゾンデートルそのものをゆるがす「敗戦」に拒絶反応を起こした軍人達のあがきが凄まじい迫力で描かれる。
近衛師団長の暗殺、ニセの命令書を作成し宮城を占拠し、玉音盤(レコード)を強奪しようとする青年将校達。対してこの敗戦処理をすみやかに行うために奔走する閣僚と官僚、終戦前夜に特別攻撃隊として出撃していくゼロ戦、日本が未曾有の事態へ向かって刻一刻と進んでいく姿。
近衛師団長・島田正吾のところへ決起を促すべく反乱将校の黒沢年男と中丸忠雄が交渉に赴く。決起の意思が無いと判断されたその時、駆けつけた中谷一郎が島田のからだに日本刀を降りおろす。「椿三十郎」レベルの血飛沫とともに床に音を立てて落下する師団長の首。あたり一面の流血。興奮しきった中谷一郎の手は硬直して握った日本刀を離せない。机に軍刀の柄をたたきつける音。これらが一気に、劇伴なしのモノクロの画面で繰り広げられるところは、一級のホラー映画の迫力だ。
反乱が失敗し玉音放送が流れ、徹底抗戦をさけぶアジビラがまかれ、青年将校達は宮城前で自決する。陸軍大臣、阿南・三船敏郎は自宅で、元近衛師団だったときのワイシャツを着て切腹する。別に軍人精神を称えるわけではないけれど、この映画で描かれたような軍人達の多くは殉死することもなく、戦争犯罪人として裁かれることもなく、その後も生き延びていく。
岡本喜八監督の戦争に対する「怒り」はこの映画のいろんなところに見受けられる。特別攻撃隊を見送る士官・伊藤雄之助の姿に、岡本監督の怒りが特に集中しているようだ。当時食料事情が悪かったから甘いものに飢えていたであろう少年のような兵隊が出撃直前にうまそうにボタモチを食べているシーン。二度と帰らない少年たちを見送る中年の伊藤のショットには、静かだが強烈なメッセージを感じた。
青年将校達の交通手段は自転車。夏の暑い盛り(8月14日)にかなりボロい自転車をキーキーいわせながら漕いで行く。軍服ったって今みたいに上等なサマーウールとかじゃないから、毛布みたいな分厚い素材なのにその上に染み出した汗。この暑さと汗が私には印象深い。単なる軍部のテロ映画ではなく、戦争に疲弊した日本と日本人全てにとっても「長い一日」だったんだなあということが、市井の人々がほとんど登場しないにもかかわらずとてもよく伝わってきた。
ナレーションの仲代達矢、新聞記者の三井弘次(「天国と地獄」のときも良かった)、NHKアナウンサーの加山雄三、近衛師団長の縁戚で反乱将校の佐藤允、シーンは少ないがいずれも重要な役で登場する、東宝のオールスター戦争映画。
良い映画を褒める会。
『日本のいちばん長い日』(1967)ドキュメンタリー・タッチで描かれる1945年8月15日。
世に戦争映画は数多くあれど、岡本喜八監督の残した戦争映画には記憶に残る作品が多い。『独立愚連隊』、『独立愚連隊 西へ』、『肉弾』、そして『日本のいちばん長い日』などに代表される彼の作品群は他の監督の作品よりも魅力的である。
それぞれ全く違うストーリーであり、『肉弾』や『日本のいちばん長い日』などのシリアスな作品を製作する一方で、軍服を着た西部劇ともいえる独立愚連隊シリーズのような娯楽作品も手がけている。おそらく僕の観たい種類の映画のツボをどんどん押してくれているのでしょう。
鉈で割ったようなカットのリズムなのか、話の展開の豪快さか、はたまた根底にある人間味なのかははっきりとは解りません。ただ言えるのは飽きずに何度も観れる作品が多いということでしょう。どこかユーモラスな制作姿勢が窺えます。彼の撮影現場がどういう感じであったかは分かりませんが、明るい雰囲気、良い物を作ろうという雰囲気があったのでしょう。
見終わったあとに明るく楽しい思いで劇場を出られる観客が多かったのではなかろうか。もちろんこの作品や『大菩薩峠』のような楽しいでは済まされないシリアスで残酷描写の多い作品も多数あり、どれでも楽しい作品であるというわけではありません。それでも彼の作品群にはなぜかまた観たくなる大きな魅力があります。
本作品もこれまで何度も見た映画のひとつであり、実際二年に一回の頻度で見ています。骨太で、重厚で、陰鬱で、救いのないモノクロ作品ではあります。橋本忍によって構成された見事な脚本によって命を吹き込まれた日本中枢部の人物達は過去から蘇ったように活き活きとしていました。
脚本の橋本忍と撮影の村井博によってドキュメンタリー・タッチで描かれる文官と軍部のせめぎ合い、軍内部における強硬派と現実派との争いが強烈な印象を与えます。ストーリー展開が絶妙で、ともすれば一ヶ所で停滞しがちになるであろう長老達の密室劇だけではなく、血の気が多く獰猛な青年将校らの不穏で過激な動きと対比させることで立場の違いを鮮明に表すだけではなく、映画としての緩急のバランスを上手く取っている。
身体による暴力で事態を解決しようとする青年将校に対して、国権を握る政府内の文官や軍人は会議で日本の将来を決定する。若く過激な人々が決めるのではなく、思慮のある老成した人々が全てを決定するのが国の政治だというのは何たる皮肉な対比ではないでしょうか。
モノクロ画面の良さが大いに出た作品でもあります。立場上、感情を露わに出来ない長老達への光の当て方と影の作り方からはわざわざ口で多くを語らずとも、映像だけでも彼らの感情を吐露している。それが分からない青年将校たちはより具体的な行動を起こす。
会議場で円座になって囲んでいるのにもかかわらず、照明の使い方の妙とクロース・アップで三船敏郎(陸軍大臣役)を捉えるだけで陸軍相が置かれていた孤独な立場を強調する。政府内でも陸軍内部でも孤立無縁な立場になっていた陸相の当時の状況が生々しいまでに描写されていきます。
大日本帝国の法の下においては閣議決定は陸相と海相が反対すればひとつも決まらない。そのため軍部は政治に台頭し、国を誤っていきました。つまり軍部の賛成で事は一気に決するという事です。このときは海軍は敗戦やむを得ずという意見であったために、本土での徹底抗戦を叫んでいた陸軍と陸軍相にのしかかるプレッシャーは大きくなっていきます。
三船は苦悩に耐える陸相を見事に演じきりました。カメラも彼の心情や苦しみをしっかりと捉えています。彼のほかに素晴らしかったのが黒沢年男です。血気盛んな青年将校を演じた彼の目の力はとても強く覚えています。
黒沢ら青年将校が決起し、近衛兵団の指揮権を強奪し皇居を占拠するというクーデター未遂を起こす過程で陸軍の長老を暗殺するシーンがあります。このシーンでの殺人描写は血飛沫の飛び散るほどの残酷でした。リアリズム作品という性格上避けられないシーンだったのかもしれません。天本英世がテロリストとして鈴木貫太郎首相宅を襲撃するシークエンスもありましたが、全ての殺人シーンの描写はかなりどぎついものばかりでした。
8月14日零時から8月15日正午までという真夏の一日半を撮るのにモノクロを選択したため、人物を撮るときの顔や背中の汗の映し方、舞い上がる土埃などが夏の日の暑さを強調する。またヒグラシやツクツクホーシや油蝉などの夏の虫の声をふんだんに盛り込むなど音響に工夫が見られ、当時のスタッフの夏を表現することへの苦労がしのばれます。
そのかいもあり、とても密度の濃い画面を作り上げました。娯楽性は一切ない、妥協なき作品に仕上げられているため、取っつき難いと思われる方もいるかもしれません。しかし158分という上映時間は決して長くはありません。才能溢れる脚本家とカメラマン、そして監督がいれば上映時間の長さは問題ではありません。
もともと、この作品は岡本喜八監督の1967年製作作品で、東宝創立35周年記念作品の一本でした。主演は三船敏郎で阿南陸軍大将役でした。その他の俳優陣も豪華で笠智衆(首相)、山村聡(海相)、宮口精二(外務大臣)、志村喬(情報局長)、田崎潤(厚木基地司令)、島田正吾(師団長)、石山健二郎(東部軍司令) 、藤田進(連隊長)、伊藤雄之助(飛行団長)らが貫禄のある円熟した演技を見せていました。
いっぽう高橋悦史(青年将校)、黒沢年男(青年将校)、加藤武、戸浦六宏、江原達怡、土屋嘉男、加東大介、平田昭彦、藤木悠、天本英世、神山繁、佐藤允(岡本作品の顔)、久保明(青年将校) 、小林桂樹(侍従) 、中谷一郎(青年将校) 、加山雄三(NHKアナウンサー) 、井川比佐志らが新鮮な魅力を振り撒いています。紅一点ともいえる新珠三千代でしたが出番はごくわずかで、ほぼ完全に全篇通して「男祭り」の状況でした。ナレーター役の仲代達矢も淡々と大日本帝国のお葬式の司会を務めていました。
そして八代目松本幸四郎が務めた昭和天皇役が素晴らしい。クロース・アップもなく、ほとんどのシーンが身体の一部分だけが映るか声だけの登場なのですがこのことがさらに神秘的に作用し、まるで本物の天皇が出演しているような高貴な印象を与える。照明や構図もより神格を高めている。神々しく映された松本幸四郎には当時の状況を考えると多大なるプレッシャーが掛かったのではないでしょうか。
そして言えることは出演者全員が何らかの形で戦争経験を持っていた人々によって演じられていたので、現実味がありました。加東大介や三船敏郎は軍人でしたし、その他の人も何らかの形で戦争の記憶を生々しく共有していた世代です。現在の俳優で戦争物を作ってもなにか違和感があるのは戦争体験の有無と無縁ではない。
この作品が他の作品と違った魅力を湛えている理由は「玉音レコード盤奪還作戦」、「8・15クーデター未遂」、「天皇を擁する御前会議」、「文官と軍部のせめぎあい」、「軍部内での世代間の対立」というバラエティに富んだ要素が各々複雑に絡み合いながら散らかることなく、一本の大河のように繋がっているからではないか。
玉音放送というと一般国民にとっては8月15日の正午にNHKによって行われたラジオ放送を指します。しかしながら当然これを制作したのはその日の前ということになります。また天皇が人間宣言を行われたのは戦後でしたが、実際の宣言は終戦を決断された8月14日の御前会議であった。戦後マッカーサー元帥と話された折も「私のことはどうなっても良い」と述べ、元帥を感服させた陛下ですが、このときの会議でも終戦を渋る軍部に対して決意を述べられたようです。
当時の国民の感覚であれば、神である天皇にレコーディングのマイクの前に立って貰うことだけでも恐れ多いことであったと思われます。このレコーディングや玉音レコードの扱いを描いたシーンに当時の人々の心情が表れています。
真夏の暑い日に行われた御前会議で天皇がみずから現人神の地位から降りられて、国民とともに苦難の道を選ばれたことにより、ようやくこの惨たらしい戦争に幕を下ろせました。陸軍の言うように本土徹底抗戦を選択していれば、民族の誇りを保つために民族総自決に近いような惨劇があちらこちらで起こっていたかもしれません。
本土決戦を選択していれば、今のように腑抜けの政治家や国民ばかりにはならなかったという過激な意見もあるようですが、それは結果論に過ぎませんし、当時の政治家が苦渋に満ちて選択した敗戦受諾は決して間違いではなかったと断言できる。
ポツダム宣言にたいする政府の遅すぎた対応と「黙殺」を「拒絶」と誤解された外交のミスにより、広島と長崎では原爆によって人類史上最も残虐な殺戮が行われました。政府がもっと早く交渉を真剣に検討していれば避けられた悲劇は沢山ありました。軍事的にはサイパンが陥落した段階で(サイパンからならば、B-25やB-29で日本本土にたいして無給油で空爆が可能)敗戦は決定的になったにもかかわらず、なぜ続行したのか。
A級戦犯は戦争を遂行したから悪いというのではない。勝つにしろ負けるにしろ国益を最大限に引き出すことが重要である。そこを見誤る政治家や軍人こそが戦犯と呼ばれるに相応しい。戦って争うのは国益であって、軍人のプライドのためではない。誇りと国益の違いは今の政治家の発言からも明らかにはなってこない。
戦争に入った後、そして終戦間際の御前会議当時の帝国政府は無為無策であったかもしれません。しかし全ての人々は国を愛し、各々の立場から見解の相違をぶつけていく。いがみ合い、収拾がつかないことが多かった帝国政府ではありましたが、「私」ではなく「公」のために働いた結果です。これに対し良い悪いを言うつもりはありません。ただ冷静な視点は常に欠落していたように思えてならない。
御前会議後の夜、虫の声はコオロギなどの秋の虫に変わっている。それまで騒がしいほどに鳴いていた夏の虫は影を潜め、季節の移り変わりを見せつける。時代が軍国主義時代からアメリカ占領時代に変わっていくのを暗示するような音でした。
この映画は明治以来続き、日清戦争、日露戦争を勝ち抜き、アメリカと全面戦争を体験した唯一の国家であった大日本帝国のお葬式を切り取った作品です。葬式は完璧に用意され、厳粛に進められる必要があります。喪主である天皇陛下の玉音放送はまさに帝国の崩壊と日本国の再生への希望でもありました。
反乱に失敗した青年将校は全員自決し、陸相の三船も宿舎で今生の別れの後、介添えもなく割腹自殺をする。残酷な描写が多いがリアリズムに徹した作品のテーマ上、このような演出を採ったのかも知れません。
玉音放送が流れようとするなかで、三船の葬式と黒沢らの自決シーンが挿入される。死に行く者と再生に努める者という立場の違いが鮮明に表れる。クロスカッティングで編集される一連のシーンは素晴らしい。
しかしまあ、なんであんなにみんな軍服がよく似合うのだろう。小道具として使用される『出家とその弟子』、『若鷲の歌』も効果的でした。
総合評価 96点
『日本のいちばん長い日』(1967)ドキュメンタリー・タッチで描かれる1945年8月15日。
世に戦争映画は数多くあれど、岡本喜八監督の残した戦争映画には記憶に残る作品が多い。『独立愚連隊』、『独立愚連隊 西へ』、『肉弾』、そして『日本のいちばん長い日』などに代表される彼の作品群は他の監督の作品よりも魅力的である。
それぞれ全く違うストーリーであり、『肉弾』や『日本のいちばん長い日』などのシリアスな作品を製作する一方で、軍服を着た西部劇ともいえる独立愚連隊シリーズのような娯楽作品も手がけている。おそらく僕の観たい種類の映画のツボをどんどん押してくれているのでしょう。
鉈で割ったようなカットのリズムなのか、話の展開の豪快さか、はたまた根底にある人間味なのかははっきりとは解りません。ただ言えるのは飽きずに何度も観れる作品が多いということでしょう。どこかユーモラスな制作姿勢が窺えます。彼の撮影現場がどういう感じであったかは分かりませんが、明るい雰囲気、良い物を作ろうという雰囲気があったのでしょう。
見終わったあとに明るく楽しい思いで劇場を出られる観客が多かったのではなかろうか。もちろんこの作品や『大菩薩峠』のような楽しいでは済まされないシリアスで残酷描写の多い作品も多数あり、どれでも楽しい作品であるというわけではありません。それでも彼の作品群にはなぜかまた観たくなる大きな魅力があります。
本作品もこれまで何度も見た映画のひとつであり、実際二年に一回の頻度で見ています。骨太で、重厚で、陰鬱で、救いのないモノクロ作品ではあります。橋本忍によって構成された見事な脚本によって命を吹き込まれた日本中枢部の人物達は過去から蘇ったように活き活きとしていました。
脚本の橋本忍と撮影の村井博によってドキュメンタリー・タッチで描かれる文官と軍部のせめぎ合い、軍内部における強硬派と現実派との争いが強烈な印象を与えます。ストーリー展開が絶妙で、ともすれば一ヶ所で停滞しがちになるであろう長老達の密室劇だけではなく、血の気が多く獰猛な青年将校らの不穏で過激な動きと対比させることで立場の違いを鮮明に表すだけではなく、映画としての緩急のバランスを上手く取っている。
身体による暴力で事態を解決しようとする青年将校に対して、国権を握る政府内の文官や軍人は会議で日本の将来を決定する。若く過激な人々が決めるのではなく、思慮のある老成した人々が全てを決定するのが国の政治だというのは何たる皮肉な対比ではないでしょうか。
モノクロ画面の良さが大いに出た作品でもあります。立場上、感情を露わに出来ない長老達への光の当て方と影の作り方からはわざわざ口で多くを語らずとも、映像だけでも彼らの感情を吐露している。それが分からない青年将校たちはより具体的な行動を起こす。
会議場で円座になって囲んでいるのにもかかわらず、照明の使い方の妙とクロース・アップで三船敏郎(陸軍大臣役)を捉えるだけで陸軍相が置かれていた孤独な立場を強調する。政府内でも陸軍内部でも孤立無縁な立場になっていた陸相の当時の状況が生々しいまでに描写されていきます。
大日本帝国の法の下においては閣議決定は陸相と海相が反対すればひとつも決まらない。そのため軍部は政治に台頭し、国を誤っていきました。つまり軍部の賛成で事は一気に決するという事です。このときは海軍は敗戦やむを得ずという意見であったために、本土での徹底抗戦を叫んでいた陸軍と陸軍相にのしかかるプレッシャーは大きくなっていきます。
三船は苦悩に耐える陸相を見事に演じきりました。カメラも彼の心情や苦しみをしっかりと捉えています。彼のほかに素晴らしかったのが黒沢年男です。血気盛んな青年将校を演じた彼の目の力はとても強く覚えています。
黒沢ら青年将校が決起し、近衛兵団の指揮権を強奪し皇居を占拠するというクーデター未遂を起こす過程で陸軍の長老を暗殺するシーンがあります。このシーンでの殺人描写は血飛沫の飛び散るほどの残酷でした。リアリズム作品という性格上避けられないシーンだったのかもしれません。天本英世がテロリストとして鈴木貫太郎首相宅を襲撃するシークエンスもありましたが、全ての殺人シーンの描写はかなりどぎついものばかりでした。
8月14日零時から8月15日正午までという真夏の一日半を撮るのにモノクロを選択したため、人物を撮るときの顔や背中の汗の映し方、舞い上がる土埃などが夏の日の暑さを強調する。またヒグラシやツクツクホーシや油蝉などの夏の虫の声をふんだんに盛り込むなど音響に工夫が見られ、当時のスタッフの夏を表現することへの苦労がしのばれます。
そのかいもあり、とても密度の濃い画面を作り上げました。娯楽性は一切ない、妥協なき作品に仕上げられているため、取っつき難いと思われる方もいるかもしれません。しかし158分という上映時間は決して長くはありません。才能溢れる脚本家とカメラマン、そして監督がいれば上映時間の長さは問題ではありません。
もともと、この作品は岡本喜八監督の1967年製作作品で、東宝創立35周年記念作品の一本でした。主演は三船敏郎で阿南陸軍大将役でした。その他の俳優陣も豪華で笠智衆(首相)、山村聡(海相)、宮口精二(外務大臣)、志村喬(情報局長)、田崎潤(厚木基地司令)、島田正吾(師団長)、石山健二郎(東部軍司令) 、藤田進(連隊長)、伊藤雄之助(飛行団長)らが貫禄のある円熟した演技を見せていました。
いっぽう高橋悦史(青年将校)、黒沢年男(青年将校)、加藤武、戸浦六宏、江原達怡、土屋嘉男、加東大介、平田昭彦、藤木悠、天本英世、神山繁、佐藤允(岡本作品の顔)、久保明(青年将校) 、小林桂樹(侍従) 、中谷一郎(青年将校) 、加山雄三(NHKアナウンサー) 、井川比佐志らが新鮮な魅力を振り撒いています。紅一点ともいえる新珠三千代でしたが出番はごくわずかで、ほぼ完全に全篇通して「男祭り」の状況でした。ナレーター役の仲代達矢も淡々と大日本帝国のお葬式の司会を務めていました。
そして八代目松本幸四郎が務めた昭和天皇役が素晴らしい。クロース・アップもなく、ほとんどのシーンが身体の一部分だけが映るか声だけの登場なのですがこのことがさらに神秘的に作用し、まるで本物の天皇が出演しているような高貴な印象を与える。照明や構図もより神格を高めている。神々しく映された松本幸四郎には当時の状況を考えると多大なるプレッシャーが掛かったのではないでしょうか。
そして言えることは出演者全員が何らかの形で戦争経験を持っていた人々によって演じられていたので、現実味がありました。加東大介や三船敏郎は軍人でしたし、その他の人も何らかの形で戦争の記憶を生々しく共有していた世代です。現在の俳優で戦争物を作ってもなにか違和感があるのは戦争体験の有無と無縁ではない。
この作品が他の作品と違った魅力を湛えている理由は「玉音レコード盤奪還作戦」、「8・15クーデター未遂」、「天皇を擁する御前会議」、「文官と軍部のせめぎあい」、「軍部内での世代間の対立」というバラエティに富んだ要素が各々複雑に絡み合いながら散らかることなく、一本の大河のように繋がっているからではないか。
玉音放送というと一般国民にとっては8月15日の正午にNHKによって行われたラジオ放送を指します。しかしながら当然これを制作したのはその日の前ということになります。また天皇が人間宣言を行われたのは戦後でしたが、実際の宣言は終戦を決断された8月14日の御前会議であった。戦後マッカーサー元帥と話された折も「私のことはどうなっても良い」と述べ、元帥を感服させた陛下ですが、このときの会議でも終戦を渋る軍部に対して決意を述べられたようです。
当時の国民の感覚であれば、神である天皇にレコーディングのマイクの前に立って貰うことだけでも恐れ多いことであったと思われます。このレコーディングや玉音レコードの扱いを描いたシーンに当時の人々の心情が表れています。
真夏の暑い日に行われた御前会議で天皇がみずから現人神の地位から降りられて、国民とともに苦難の道を選ばれたことにより、ようやくこの惨たらしい戦争に幕を下ろせました。陸軍の言うように本土徹底抗戦を選択していれば、民族の誇りを保つために民族総自決に近いような惨劇があちらこちらで起こっていたかもしれません。
本土決戦を選択していれば、今のように腑抜けの政治家や国民ばかりにはならなかったという過激な意見もあるようですが、それは結果論に過ぎませんし、当時の政治家が苦渋に満ちて選択した敗戦受諾は決して間違いではなかったと断言できる。
ポツダム宣言にたいする政府の遅すぎた対応と「黙殺」を「拒絶」と誤解された外交のミスにより、広島と長崎では原爆によって人類史上最も残虐な殺戮が行われました。政府がもっと早く交渉を真剣に検討していれば避けられた悲劇は沢山ありました。軍事的にはサイパンが陥落した段階で(サイパンからならば、B-25やB-29で日本本土にたいして無給油で空爆が可能)敗戦は決定的になったにもかかわらず、なぜ続行したのか。
A級戦犯は戦争を遂行したから悪いというのではない。勝つにしろ負けるにしろ国益を最大限に引き出すことが重要である。そこを見誤る政治家や軍人こそが戦犯と呼ばれるに相応しい。戦って争うのは国益であって、軍人のプライドのためではない。誇りと国益の違いは今の政治家の発言からも明らかにはなってこない。
戦争に入った後、そして終戦間際の御前会議当時の帝国政府は無為無策であったかもしれません。しかし全ての人々は国を愛し、各々の立場から見解の相違をぶつけていく。いがみ合い、収拾がつかないことが多かった帝国政府ではありましたが、「私」ではなく「公」のために働いた結果です。これに対し良い悪いを言うつもりはありません。ただ冷静な視点は常に欠落していたように思えてならない。
御前会議後の夜、虫の声はコオロギなどの秋の虫に変わっている。それまで騒がしいほどに鳴いていた夏の虫は影を潜め、季節の移り変わりを見せつける。時代が軍国主義時代からアメリカ占領時代に変わっていくのを暗示するような音でした。
この映画は明治以来続き、日清戦争、日露戦争を勝ち抜き、アメリカと全面戦争を体験した唯一の国家であった大日本帝国のお葬式を切り取った作品です。葬式は完璧に用意され、厳粛に進められる必要があります。喪主である天皇陛下の玉音放送はまさに帝国の崩壊と日本国の再生への希望でもありました。
反乱に失敗した青年将校は全員自決し、陸相の三船も宿舎で今生の別れの後、介添えもなく割腹自殺をする。残酷な描写が多いがリアリズムに徹した作品のテーマ上、このような演出を採ったのかも知れません。
玉音放送が流れようとするなかで、三船の葬式と黒沢らの自決シーンが挿入される。死に行く者と再生に努める者という立場の違いが鮮明に表れる。クロスカッティングで編集される一連のシーンは素晴らしい。
しかしまあ、なんであんなにみんな軍服がよく似合うのだろう。小道具として使用される『出家とその弟子』、『若鷲の歌』も効果的でした。
総合評価 96点
10.《ネタバレ》 岡本監督自身がジレンマを語ったとおり、本作には民間人の登場がほとんどない。内地における、特に上層階級の左往右往だけが中心に描かれる。そもそも昭和20年8月15日をもって終戦とする一般的な認識自体が内地側の都合による解釈でしかなく、映画の中でも外地への終戦通達の話題は台詞として出るが、実際は外地においては8月15日に戦争は終わっていない。樺太でも、満州でも軍上層部だけが早々に逃走し、残された一般兵が8月末まで戦闘を続けている。外地一般民も同様、映画の中に登場する主要なお偉方の棄民政策の犠牲となり国家に見捨てられ抑留される事になる。映画は「敗戦」によって始まる外地のより切実で過酷な実態を一切切り捨て、8月15日をもって戦争はきっちり終結したかに描く。そういう意味では悪質な錯覚を与えかねない映画とも言うことができる。当初予定の小林正樹監督(「人間の条件」)であったなら全く別種の映画となった可能性もあったと思うが、岡本監督の本意はラストの犠牲者数のテロップにこそあった事は疑い無い。そうしたジレンマが「肉弾」(1968)のラストに強く反映されているのだと思う。 【ユーカラ】さん [DVD(邦画)] 5点(2006-07-17 11:02:15)
9.この手の映画は点数をつけにくいんですが、是非多くの人に見て欲しいという願いを込めて9点です。こんな映画、いろいろな意味で現在では作れないでしょう。娯楽性はほとんど無いですが、ある意味、現在の日本の第一歩となった1945年8月14〜15日玉音放送の録音版を巡る陸軍を中心としたさまざまな人々の動きがドキュメンタリー調に画かれているので、是非、すべての日本人が一度は見て欲しい作品です。 【はやぶさ】さん [映画館(字幕)] 9点(2005-11-27 23:01:35)
8.この映画を観て、終戦にも犠牲者がいる事を知りました。戦う事を生きがいと教えられてきた軍人たちの思いが、この長い一日を生み出したのだと思います。 【デコバン】さん [DVD(字幕)] 9点(2005-10-29 18:00:35)
7.俳優達の演技力の裏づけは、やはり彼らの戦争体験が大きいと思います。この頃の俳優達は、語るべき実体験を持っています。南方ニューギニアで飢餓地獄にあった俳優。陸軍士官学校に在籍していた俳優。この映画の阿南陸相を演じた三船は当時陸軍航空隊に属し、熊本の飛行場で25歳の終戦を迎え、毛布2枚の支給だけで娑婆に放り出される経験をしています。三船は映画中に出てきた特攻隊の飛行兵達とほぼ同年代です。くらべて最近の中堅俳優達(多感な青春期はバブルと重なっているでしょう)が物資乏しい大戦期を”また聞き”をもとに演じては土台無理ですね。私が特に印象に残っているのは、高橋悦史演じる井田中佐の近衛師団長への訴え、「中途半端に戦争止めるくらいなら、これは玉砕、殉国した前線の兵士・一般人に対し、ぬくぬくと内地にいた連中の裏切り行為ではないのか?重臣達は天皇に責任を押し付けて逃げ口上を正当化していないのか?」です。”武士に二言は無い”ということから言えば、優柔不断な上級司令官を斬り、徹底抗戦しようとした、その望みがかなわぬ時には潔く自決した畑中少佐ら青年将校達は、恥を知る真の武士です。陸相とかれら(その他にも自決者はいる)一握りの武士の存在によって大勢の”生き長らえた”皇軍将兵に”栄光ある敗北”が与えられたのだと思います。 【Waffe】さん [ビデオ(吹替)] 9点(2005-08-05 23:07:31)(良:1票)
6.日本人ならば知っておかねばならない一日であり、忘れてはならない一日、思想の左右を問わず見ておくべき作品ではないでしょうか。だから戦争反対、9条を守るべきなのか?いやいや日本は日本人が守るべきなのか?中国、韓国等に平身低頭謝り続けるべきか?日本としての自主性、独自性を貫くべきか?「東京裁判」や本作などは学校で鑑賞し議論すべき映画だと思うんだが、実際はこのあたりの歴史は端折られてしまうのが残念。 【木戸萬】さん [ビデオ(吹替)] 8点(2005-04-20 22:17:38)
5.原爆を2発も喰らい、戦力差が質量とも明白になった時点でなお、戦争続行を主張する青年将校たち。あんたらはとことん戦って切腹すればいいかも知れんが、本土決戦が始まることで犠牲になる一般国民はどうなるの?本来は守ってあげるべき存在じゃないの?と苦笑しながら観てました。しかし、大日本帝国が初めて降伏するという未曾有の事態に直面したなら、祖国の永続を確信していた人々がパニックに陥るのも無理ないかもしれないと思いました。明治維新だって遠い過去の出来事なんですから。 【次郎丸三郎】さん 6点(2004-06-11 15:32:41)
4.歴史ドキュメンタリーをドラマ化したもので、主要登場人物は実在の要人で、ストーリーもほぼ史実に準じている。こういう場合、おおまかな史実や人物像が見えているゆえに、映画として魅力あるものにするためには、高度な脚本や俳優そのものの存在感がないといくら監督ががんばっても無理がある。そういう意味で、当時の日本映画界全体の奥行きの深さを彷彿させる傑作。 【サラウンダー】さん 9点(2004-01-15 23:22:53)
3.《ネタバレ》 1945年8月15日。この日は大日本帝国の命日である。この映画はその葬式の様子を描いた作品である。まだ日本人に大和魂が残ってた頃のお話。日本は大東亜戦争に敗れた。この敗戦以来日本人はすっかりダメになってしまった。自信を失い、国家や国旗に対する誇りさえ失った。今の日本人は皆、日本の事なんかどうでもよくて、自分中心主義である。しかしこの作品に出てくる男達は皆、本気で日本の事を考えている。それぞれの行動は様々だが、僕が特に印象に残ってるのは三船敏郎演じる阿南陸軍大臣と建軍以来初めての敗戦を目前になんとしてでも戦争を続行させようとする青年将校達。阿南閣下は正に「軍人の鑑」とも言える威風堂々さがあり、敗戦と決まった時点で切腹の覚悟を決める。その一方で畑中少佐ら陸軍将校達の行動も多少無茶ではあるが日本を行く末を憂いてこその行動であり、その計画が失敗に終わった折には清く自決。彼らの志は226事件の青年将校と同様である。他にも厚木基地でのシーン(田崎潤の名セリフ「この厚木は最後まで闘う!」)や「若鷲の歌」をBGMに飛び立って行く特攻隊員達とそれを見送る指揮官役の伊藤雄之助の重い表情も印象的だった。今の気だるく平和な日本を生きる人は必見の名作!(マジで!) この「日本」は我等日本人の先祖達の多大なる犠牲の上で成り立っている事を忘れてはならない! 【和魂洋才】さん 10点(2003-11-24 18:53:30)
2.《ネタバレ》 三船敏郎の阿南陸将の割腹シーン、白黒なのに怖いくらいの迫力がありましたね。戦争終結までの日本の上層部の動きがよくわかります。笠智衆の貫太郎はとっても雰囲気が出ていました。若い黒沢年男が暴走気味な青年将校を見事に演じていて、ラストのサイドカーのシーンは印象深いです。何も、あそこまできて死ななくてもいいものをと思ってしまいますが、当時はああいう考え方の人がたくさんいたのでしょうね。時代の隔世を感じます。 【オオカミ】さん 8点(2003-11-18 19:01:40)
1.台詞が説明口調ぽいところが気になるが、効果音をほとんど用いていないため、終戦の「儀式」が進められる場の緊張感が伝わってきて良い。あと、阿南陸相(三船敏郎)と鈴木貫太郎首相(笠智衆)の名演技。 【からがも】さん 8点(2002-11-14 03:01:32)
9.この手の映画は点数をつけにくいんですが、是非多くの人に見て欲しいという願いを込めて9点です。こんな映画、いろいろな意味で現在では作れないでしょう。娯楽性はほとんど無いですが、ある意味、現在の日本の第一歩となった1945年8月14〜15日玉音放送の録音版を巡る陸軍を中心としたさまざまな人々の動きがドキュメンタリー調に画かれているので、是非、すべての日本人が一度は見て欲しい作品です。 【はやぶさ】さん [映画館(字幕)] 9点(2005-11-27 23:01:35)
8.この映画を観て、終戦にも犠牲者がいる事を知りました。戦う事を生きがいと教えられてきた軍人たちの思いが、この長い一日を生み出したのだと思います。 【デコバン】さん [DVD(字幕)] 9点(2005-10-29 18:00:35)
7.俳優達の演技力の裏づけは、やはり彼らの戦争体験が大きいと思います。この頃の俳優達は、語るべき実体験を持っています。南方ニューギニアで飢餓地獄にあった俳優。陸軍士官学校に在籍していた俳優。この映画の阿南陸相を演じた三船は当時陸軍航空隊に属し、熊本の飛行場で25歳の終戦を迎え、毛布2枚の支給だけで娑婆に放り出される経験をしています。三船は映画中に出てきた特攻隊の飛行兵達とほぼ同年代です。くらべて最近の中堅俳優達(多感な青春期はバブルと重なっているでしょう)が物資乏しい大戦期を”また聞き”をもとに演じては土台無理ですね。私が特に印象に残っているのは、高橋悦史演じる井田中佐の近衛師団長への訴え、「中途半端に戦争止めるくらいなら、これは玉砕、殉国した前線の兵士・一般人に対し、ぬくぬくと内地にいた連中の裏切り行為ではないのか?重臣達は天皇に責任を押し付けて逃げ口上を正当化していないのか?」です。”武士に二言は無い”ということから言えば、優柔不断な上級司令官を斬り、徹底抗戦しようとした、その望みがかなわぬ時には潔く自決した畑中少佐ら青年将校達は、恥を知る真の武士です。陸相とかれら(その他にも自決者はいる)一握りの武士の存在によって大勢の”生き長らえた”皇軍将兵に”栄光ある敗北”が与えられたのだと思います。 【Waffe】さん [ビデオ(吹替)] 9点(2005-08-05 23:07:31)(良:1票)
6.日本人ならば知っておかねばならない一日であり、忘れてはならない一日、思想の左右を問わず見ておくべき作品ではないでしょうか。だから戦争反対、9条を守るべきなのか?いやいや日本は日本人が守るべきなのか?中国、韓国等に平身低頭謝り続けるべきか?日本としての自主性、独自性を貫くべきか?「東京裁判」や本作などは学校で鑑賞し議論すべき映画だと思うんだが、実際はこのあたりの歴史は端折られてしまうのが残念。 【木戸萬】さん [ビデオ(吹替)] 8点(2005-04-20 22:17:38)
5.原爆を2発も喰らい、戦力差が質量とも明白になった時点でなお、戦争続行を主張する青年将校たち。あんたらはとことん戦って切腹すればいいかも知れんが、本土決戦が始まることで犠牲になる一般国民はどうなるの?本来は守ってあげるべき存在じゃないの?と苦笑しながら観てました。しかし、大日本帝国が初めて降伏するという未曾有の事態に直面したなら、祖国の永続を確信していた人々がパニックに陥るのも無理ないかもしれないと思いました。明治維新だって遠い過去の出来事なんですから。 【次郎丸三郎】さん 6点(2004-06-11 15:32:41)
4.歴史ドキュメンタリーをドラマ化したもので、主要登場人物は実在の要人で、ストーリーもほぼ史実に準じている。こういう場合、おおまかな史実や人物像が見えているゆえに、映画として魅力あるものにするためには、高度な脚本や俳優そのものの存在感がないといくら監督ががんばっても無理がある。そういう意味で、当時の日本映画界全体の奥行きの深さを彷彿させる傑作。 【サラウンダー】さん 9点(2004-01-15 23:22:53)
3.《ネタバレ》 1945年8月15日。この日は大日本帝国の命日である。この映画はその葬式の様子を描いた作品である。まだ日本人に大和魂が残ってた頃のお話。日本は大東亜戦争に敗れた。この敗戦以来日本人はすっかりダメになってしまった。自信を失い、国家や国旗に対する誇りさえ失った。今の日本人は皆、日本の事なんかどうでもよくて、自分中心主義である。しかしこの作品に出てくる男達は皆、本気で日本の事を考えている。それぞれの行動は様々だが、僕が特に印象に残ってるのは三船敏郎演じる阿南陸軍大臣と建軍以来初めての敗戦を目前になんとしてでも戦争を続行させようとする青年将校達。阿南閣下は正に「軍人の鑑」とも言える威風堂々さがあり、敗戦と決まった時点で切腹の覚悟を決める。その一方で畑中少佐ら陸軍将校達の行動も多少無茶ではあるが日本を行く末を憂いてこその行動であり、その計画が失敗に終わった折には清く自決。彼らの志は226事件の青年将校と同様である。他にも厚木基地でのシーン(田崎潤の名セリフ「この厚木は最後まで闘う!」)や「若鷲の歌」をBGMに飛び立って行く特攻隊員達とそれを見送る指揮官役の伊藤雄之助の重い表情も印象的だった。今の気だるく平和な日本を生きる人は必見の名作!(マジで!) この「日本」は我等日本人の先祖達の多大なる犠牲の上で成り立っている事を忘れてはならない! 【和魂洋才】さん 10点(2003-11-24 18:53:30)
2.《ネタバレ》 三船敏郎の阿南陸将の割腹シーン、白黒なのに怖いくらいの迫力がありましたね。戦争終結までの日本の上層部の動きがよくわかります。笠智衆の貫太郎はとっても雰囲気が出ていました。若い黒沢年男が暴走気味な青年将校を見事に演じていて、ラストのサイドカーのシーンは印象深いです。何も、あそこまできて死ななくてもいいものをと思ってしまいますが、当時はああいう考え方の人がたくさんいたのでしょうね。時代の隔世を感じます。 【オオカミ】さん 8点(2003-11-18 19:01:40)
1.台詞が説明口調ぽいところが気になるが、効果音をほとんど用いていないため、終戦の「儀式」が進められる場の緊張感が伝わってきて良い。あと、阿南陸相(三船敏郎)と鈴木貫太郎首相(笠智衆)の名演技。 【からがも】さん 8点(2002-11-14 03:01:32)
1967年東宝作品 監督 岡本 喜八 制作 藤本 真澄、田中 友幸
脚本 橋本忍 原作 大宅 壮一
出演 山村 聡、宮口 精二、笠 智衆、志村 喬、戸浦 六宏、高橋 悦史、中丸 忠雄、黒沢 年男、土屋嘉男、加東大介、神山 繁、田崎 潤、松本 幸四郎、他東宝オールスターキャスト
あらすじ
1945年、昭和20年8月14日。ポツダム宣言受諾を目の前に、日本国は揺れていた。
天皇の「聖断」に従い、和平への努力を続ける首相鈴木貫太郎をはじめとする人々と、徹底抗戦を主張して蹶起せんとした青年将校、敗戦を受け入れられぬ軍部上層──。
玉音放送を敢行せんとする政府関係者に対し、陸軍の一部軍人は近衛連隊を率いて皇居に乱入した。
8月14日正午から15日の正午のポツダム宣言迄の24時間を軸に追った凄絶なるセミドキュメントドラマ!
初めに質問です。日本映画に詳しい方教えて下さい。
日本映画で、一番長い自刃シーンが有るのは何ですか?
小林 正樹監督の「切腹」って有るじゃないですか。管理人は見ようと思いつつ未見です。あれって切腹シーンはどれくらい有るんでしょうか。ポスターが既にそう言う写真なんで、よもや無いと言う事は無いと思うのですが。何しろ内容を知らずに映画を見たい奴なんで、何も知りません。
でもって、この「日本のいちばん長い日」。
恐らくは、日本映画中五指に入る、長ぁぁい自刃シーンが有る映画ではないでしょうか。
壮大な集団劇で、2時間37分の長丁場を全くタルむ事無く魅せる手腕は見事。緊迫感を保ったままラストまで滑り込むのは、脚本と演出の勝利だと言えましょう。
尤も。
少ししか旧作映画を見ていない身で大上段に構えて申し訳ないが、日本の監督陣が得意とするのは、この手の「集団劇」だと思います。キャラクタの押し出しが苦手で、ここらがハリウッドと全く違う出来上がりになる要因です。
当時の東宝は(済みません、他の映画会社の事は一切知りません)毎年八月にはオールスターズによる戦争映画を公開しており、この作品もその中の一つです。
どうしてもお祭り騒ぎの様相が拭えないオールスターズ戦争映画の中で、この作品については余りお祭ムードを感じません。と言うより、それを多少は感じるだけに却って重い。
監督の岡本喜八は、どちらかと言うと喜劇的ムードの漂う活劇を撮る事が多い監督で、他の作品の多くは……何というかナンセンスムービーです。吹き出すと言うよりは失笑してしまうようなシーンを作るのが好きな監督だと思うのですが。が。
これには一切そう言うシーンはありません。
自身が出征し、*「肉弾」のような映画を撮っちゃう喜八っちゃんなので、軍上層部より下級兵士への思い入れは強く、一番自身が描きたかったのは、ラストに流れる戦死者の数のテロップだったと本人が零しています。
「この映画を撮っていて欲求不満になった」そうですが、そうでしょうそうでしょう。それ程に隙が無く、重厚でシリアスな作品だと思うのですよ。
でも、日本人はこう言う映画こそ見るべきだと思うんですよ。
誰だって「戦争か平和か」と聞かれたら「平和」が良いに決まっています。その質問こそが愚なのです。
戦争になる様な時は、選択肢に「平和」などない。「蹂躙」か「支配」が「搾取」か、そうした穏やかでない単語が並ぶのです。それでも悩み無く「戦争」以外の物を貴方は選べますか。
太平洋戦争が有って終戦の日が有って、近代日本が有るわけで。その最初にあった「戦争」を、日本人は恥じる必要は無いと思います。と言うか、恥じるべきではない。過去は過去。認めて前へ進むべき物です。
未だに有事法制反対だどうこう言っている現代日本人は、日本が敗戦国であり、米国に蹂躙されてきた国だと言う事を知るべきですよね。(私自身も含めてな)
自国を自国で守る事が出来ぬ「独立国」なんざおかしいんですよ。馬鹿馬鹿しいです。
さてさて。私が語るべきは三船=阿南 惟幾(あなみ これちか)陸軍大臣であります。
ん〜〜〜、いつもの調子で「格好良い!!」と萌えたい所ですが、これがなかなか。
軍人として生き、最後まで軍人の誇りを持って自刃した方なので、なかなか軽々しくそう言えません。
阿南さんが鈴木首相(笠 智衆)に洋モクを渡すシーンが有ります。
「私はたしなみませんので。」って静かに笑って手渡して去るんですが、受け取った鈴木首相は静かに
「阿南君は……いとまごいに来てくれたんだねぇ……。」
非常に静かなシーンなんですが、去る陸相の後ろ姿と共に胸に残るシーンだったのを覚えております。
その夜、阿南陸相は自宅の廊下で自刃なさいました。遺書は「一死以テ大罪ヲ謝シ奉ル」。
殆どの軍部上層部の人間が大戦後も生き延びたのに、この人は自らの命で責任をとられたんですね。
「多くの兵がなぜ死んでいったのだ!みんな日本の勝利を固く信じていたからではないのか! ……彼らにはなんとしても栄光ある敗北を与えねばならん」と敗戦に直面する兵士達の事に最後まで胸を痛めていた阿南陸相。漢らしくて素晴らしいリーダーだとは思うんですが………
貴方のような人こそ、生きるべきだったんじゃないかなあ。却ってそれは残酷なのかなあ………
でもってこの自刃シーンですが。………もー、長いです痛いです辛いです。
この映画を見始めた最初、ずっと軍服なので体型が分からず、ほっぺたが丸いので「三船ちゃん少し太った?」と思いながら見ていました。
が、自刃のシーンはズボンと白いワイシャツ。シャツの下はサラシのみで、胸はさらけ出された状態です。
………細い。多分、相当痩せている時期ではあるまいか。
自刃のシーンの多くは、後ろから見詰める義弟や部下達の目線で追われるので、細く引き締まった背中がメインになります。
まずは割腹。(ここはカメラは前から)
サラシの上から刃が入る訳ですが、白黒なので刀から滴り落ちるのはどす黒い血です。
ご存じの通り、割腹で訪れるのは緩慢な死です。腸管を切る訳で苦痛は物凄く、滅茶苦茶痛くて緩慢な死がじわじわやって来る訳です。だから苦痛を減らす為に介錯が付く訳ですが、阿南さんはそれも断ります。
「介錯をっ…!!」
「手助けは無用だッ!」
血だらけの震える指が襟元を探り、白い襟を避けて頸動脈をなぞり、腹から抜かれた刃がゆっくり持ち上がります。
思うように持ち上がらない腕を支える仕種も、それを必死に努力して行っている様も、滅茶苦茶リアル。
やっと刃が頸動脈を切り裂き、そこで阿南陸相の命は終わるのですが………
重い。(軽くてたまるかいッ) 死とは訪れるべき時に訪れる物は軽く穏やかで、訪れるべきでない時に訪れる物は重く騒がしい物です。本来そうした物です。
阿南陸相の死は、重い物であったのでしょう。
しかし。兎に角長い一連のシーン。
間に色々なシーンを挟み込む物だから更に長く、いつまで阿南さんは苦しんで居なきゃならないの、と息を詰めて見ていた私は本当に苦しかった想い出しか有りません。
三船は非常に呼吸の上手い役者で、私は勝手に三船の事を「呼吸の三船」と呼んでいますが、このシーンではそれが遺憾なく発揮されていました。
ずっとマイクは三船の呼吸を拾っているのですが、呼吸器疾患の喘息患者である私は、何が苦しかったってこの呼吸が苦しかったです。
様々な呼吸が異様に上手いのですが、殊に苦しい息は秀逸。何処で仕入れた知識なのか、その時々に実に有った呼吸を色々披露してくれます。呼吸器疾患の患者は、人の呼吸には通常の人間より遙かに敏感ですから、この点に付いては間違い有りません。
どす黒い血しぶきのこのシーンを経て、物語はそれとはほぼ無関係な顔をして終息へ向かいます。
私のような物知らずから見ると、「二・二六、太平洋戦争版?」でしたが、日本帝国はこうして藻掻きつつ、喘ぎつつ終わりを告げたのですな。
映画を見終わった感慨と共に、奇妙に虚しい気持ちになる映画でしたが……現実はこんなに綺麗な訳はないよな…とも。
上記の自刃シーンには、実は一つ零れ話が有ります。
噂なので、当人の手記から私が直接確かめた訳ではなく、私としてはすこぶる疑問な噂です。どう考えてもそれは三船のキャラとは思い難いので、恐らくは何人かの口を渡る内に、幾つかの要素が書き換えられた物だとは思うのですが………
と、思っていた矢先に情報入手。真相が分かりました。やっぱり相当話が変わってます。うん、私の想像は正しかった。
いずれこれは、「アプレ」のコーナーで取り上げたいと思っております。
ちなみに、この阿南さんの実子が、阿南惟茂(あなみ これしげ)さんで、例の在瀋陽総領事館の北朝鮮人亡命者連行事件で有名となった大使らしい。名前を聞いた時にアレ?と思ったものの、本当にそうだとは。
ううう〜〜〜〜〜〜〜〜〜む。良いのかそれで、阿南さんよ。
脚本 橋本忍 原作 大宅 壮一
出演 山村 聡、宮口 精二、笠 智衆、志村 喬、戸浦 六宏、高橋 悦史、中丸 忠雄、黒沢 年男、土屋嘉男、加東大介、神山 繁、田崎 潤、松本 幸四郎、他東宝オールスターキャスト
あらすじ
1945年、昭和20年8月14日。ポツダム宣言受諾を目の前に、日本国は揺れていた。
天皇の「聖断」に従い、和平への努力を続ける首相鈴木貫太郎をはじめとする人々と、徹底抗戦を主張して蹶起せんとした青年将校、敗戦を受け入れられぬ軍部上層──。
玉音放送を敢行せんとする政府関係者に対し、陸軍の一部軍人は近衛連隊を率いて皇居に乱入した。
8月14日正午から15日の正午のポツダム宣言迄の24時間を軸に追った凄絶なるセミドキュメントドラマ!
初めに質問です。日本映画に詳しい方教えて下さい。
日本映画で、一番長い自刃シーンが有るのは何ですか?
小林 正樹監督の「切腹」って有るじゃないですか。管理人は見ようと思いつつ未見です。あれって切腹シーンはどれくらい有るんでしょうか。ポスターが既にそう言う写真なんで、よもや無いと言う事は無いと思うのですが。何しろ内容を知らずに映画を見たい奴なんで、何も知りません。
でもって、この「日本のいちばん長い日」。
恐らくは、日本映画中五指に入る、長ぁぁい自刃シーンが有る映画ではないでしょうか。
壮大な集団劇で、2時間37分の長丁場を全くタルむ事無く魅せる手腕は見事。緊迫感を保ったままラストまで滑り込むのは、脚本と演出の勝利だと言えましょう。
尤も。
少ししか旧作映画を見ていない身で大上段に構えて申し訳ないが、日本の監督陣が得意とするのは、この手の「集団劇」だと思います。キャラクタの押し出しが苦手で、ここらがハリウッドと全く違う出来上がりになる要因です。
当時の東宝は(済みません、他の映画会社の事は一切知りません)毎年八月にはオールスターズによる戦争映画を公開しており、この作品もその中の一つです。
どうしてもお祭り騒ぎの様相が拭えないオールスターズ戦争映画の中で、この作品については余りお祭ムードを感じません。と言うより、それを多少は感じるだけに却って重い。
監督の岡本喜八は、どちらかと言うと喜劇的ムードの漂う活劇を撮る事が多い監督で、他の作品の多くは……何というかナンセンスムービーです。吹き出すと言うよりは失笑してしまうようなシーンを作るのが好きな監督だと思うのですが。が。
これには一切そう言うシーンはありません。
自身が出征し、*「肉弾」のような映画を撮っちゃう喜八っちゃんなので、軍上層部より下級兵士への思い入れは強く、一番自身が描きたかったのは、ラストに流れる戦死者の数のテロップだったと本人が零しています。
「この映画を撮っていて欲求不満になった」そうですが、そうでしょうそうでしょう。それ程に隙が無く、重厚でシリアスな作品だと思うのですよ。
でも、日本人はこう言う映画こそ見るべきだと思うんですよ。
誰だって「戦争か平和か」と聞かれたら「平和」が良いに決まっています。その質問こそが愚なのです。
戦争になる様な時は、選択肢に「平和」などない。「蹂躙」か「支配」が「搾取」か、そうした穏やかでない単語が並ぶのです。それでも悩み無く「戦争」以外の物を貴方は選べますか。
太平洋戦争が有って終戦の日が有って、近代日本が有るわけで。その最初にあった「戦争」を、日本人は恥じる必要は無いと思います。と言うか、恥じるべきではない。過去は過去。認めて前へ進むべき物です。
未だに有事法制反対だどうこう言っている現代日本人は、日本が敗戦国であり、米国に蹂躙されてきた国だと言う事を知るべきですよね。(私自身も含めてな)
自国を自国で守る事が出来ぬ「独立国」なんざおかしいんですよ。馬鹿馬鹿しいです。
さてさて。私が語るべきは三船=阿南 惟幾(あなみ これちか)陸軍大臣であります。
ん〜〜〜、いつもの調子で「格好良い!!」と萌えたい所ですが、これがなかなか。
軍人として生き、最後まで軍人の誇りを持って自刃した方なので、なかなか軽々しくそう言えません。
阿南さんが鈴木首相(笠 智衆)に洋モクを渡すシーンが有ります。
「私はたしなみませんので。」って静かに笑って手渡して去るんですが、受け取った鈴木首相は静かに
「阿南君は……いとまごいに来てくれたんだねぇ……。」
非常に静かなシーンなんですが、去る陸相の後ろ姿と共に胸に残るシーンだったのを覚えております。
その夜、阿南陸相は自宅の廊下で自刃なさいました。遺書は「一死以テ大罪ヲ謝シ奉ル」。
殆どの軍部上層部の人間が大戦後も生き延びたのに、この人は自らの命で責任をとられたんですね。
「多くの兵がなぜ死んでいったのだ!みんな日本の勝利を固く信じていたからではないのか! ……彼らにはなんとしても栄光ある敗北を与えねばならん」と敗戦に直面する兵士達の事に最後まで胸を痛めていた阿南陸相。漢らしくて素晴らしいリーダーだとは思うんですが………
貴方のような人こそ、生きるべきだったんじゃないかなあ。却ってそれは残酷なのかなあ………
でもってこの自刃シーンですが。………もー、長いです痛いです辛いです。
この映画を見始めた最初、ずっと軍服なので体型が分からず、ほっぺたが丸いので「三船ちゃん少し太った?」と思いながら見ていました。
が、自刃のシーンはズボンと白いワイシャツ。シャツの下はサラシのみで、胸はさらけ出された状態です。
………細い。多分、相当痩せている時期ではあるまいか。
自刃のシーンの多くは、後ろから見詰める義弟や部下達の目線で追われるので、細く引き締まった背中がメインになります。
まずは割腹。(ここはカメラは前から)
サラシの上から刃が入る訳ですが、白黒なので刀から滴り落ちるのはどす黒い血です。
ご存じの通り、割腹で訪れるのは緩慢な死です。腸管を切る訳で苦痛は物凄く、滅茶苦茶痛くて緩慢な死がじわじわやって来る訳です。だから苦痛を減らす為に介錯が付く訳ですが、阿南さんはそれも断ります。
「介錯をっ…!!」
「手助けは無用だッ!」
血だらけの震える指が襟元を探り、白い襟を避けて頸動脈をなぞり、腹から抜かれた刃がゆっくり持ち上がります。
思うように持ち上がらない腕を支える仕種も、それを必死に努力して行っている様も、滅茶苦茶リアル。
やっと刃が頸動脈を切り裂き、そこで阿南陸相の命は終わるのですが………
重い。(軽くてたまるかいッ) 死とは訪れるべき時に訪れる物は軽く穏やかで、訪れるべきでない時に訪れる物は重く騒がしい物です。本来そうした物です。
阿南陸相の死は、重い物であったのでしょう。
しかし。兎に角長い一連のシーン。
間に色々なシーンを挟み込む物だから更に長く、いつまで阿南さんは苦しんで居なきゃならないの、と息を詰めて見ていた私は本当に苦しかった想い出しか有りません。
三船は非常に呼吸の上手い役者で、私は勝手に三船の事を「呼吸の三船」と呼んでいますが、このシーンではそれが遺憾なく発揮されていました。
ずっとマイクは三船の呼吸を拾っているのですが、呼吸器疾患の喘息患者である私は、何が苦しかったってこの呼吸が苦しかったです。
様々な呼吸が異様に上手いのですが、殊に苦しい息は秀逸。何処で仕入れた知識なのか、その時々に実に有った呼吸を色々披露してくれます。呼吸器疾患の患者は、人の呼吸には通常の人間より遙かに敏感ですから、この点に付いては間違い有りません。
どす黒い血しぶきのこのシーンを経て、物語はそれとはほぼ無関係な顔をして終息へ向かいます。
私のような物知らずから見ると、「二・二六、太平洋戦争版?」でしたが、日本帝国はこうして藻掻きつつ、喘ぎつつ終わりを告げたのですな。
映画を見終わった感慨と共に、奇妙に虚しい気持ちになる映画でしたが……現実はこんなに綺麗な訳はないよな…とも。
上記の自刃シーンには、実は一つ零れ話が有ります。
噂なので、当人の手記から私が直接確かめた訳ではなく、私としてはすこぶる疑問な噂です。どう考えてもそれは三船のキャラとは思い難いので、恐らくは何人かの口を渡る内に、幾つかの要素が書き換えられた物だとは思うのですが………
と、思っていた矢先に情報入手。真相が分かりました。やっぱり相当話が変わってます。うん、私の想像は正しかった。
いずれこれは、「アプレ」のコーナーで取り上げたいと思っております。
ちなみに、この阿南さんの実子が、阿南惟茂(あなみ これしげ)さんで、例の在瀋陽総領事館の北朝鮮人亡命者連行事件で有名となった大使らしい。名前を聞いた時にアレ?と思ったものの、本当にそうだとは。
ううう〜〜〜〜〜〜〜〜〜む。良いのかそれで、阿南さんよ。
67年日本映画。「独立愚連隊」などの岡本喜八監督作品。
日本の終戦、8月14日正午〜玉音盤が放送される8月15日正午までの24時間を追った日本の戦争映画の総決算である。
これは古いからと言って避けるのはあまりにも愚かである。これ以上の邦画はおれは今のところ知らない。これほどの映画は今の堕落した邦画界では絶対に生まれないだろうなあ、なぜこれほどの映画が作れた国が、ここまで駄目になってしまったのか全く理解に苦しむのである。
愚痴はこのぐらいにしてそろそろ本題に入ろう。
ストーリーは7月末に連合軍側から提示されたポツダム宣言に対する日本政府がいかにして対応したのかをナレーションを含めて簡単な説明が入る。そしてもはや戦争継続は不可能である・・と天皇の御聖断が下る。しかしあくまで本土決戦を主張する陸軍は、近衛師団の参謀、古賀少佐と陸軍省の軍務課将校、畑中少佐、推崎中佐を中心にクーデター計画が水面下で進められる。その計画とは、近衛師団長、森中将を説得して近衛師団を決起させ、宮内省を占拠し玉音盤を手中にし天皇を戴き、そうすれば東部軍をはじめとした、全陸軍、国民までもが戦争継続のために決起するであろう、という計画であった。いわゆる宮城事件である。
左から推崎中佐(中村忠雄) 古賀少佐(佐藤允) 畑中少佐(黒沢年男)
玉音盤を録音している最中も、房総半島に接近中の米機動部隊の迎撃に特攻機が今日も飛び立っていく・・。全ては日本国民を護るため・・
まず近衛師団ってなに?東部軍ってなに?って話になってくるとわかりにくいので簡単に説明すると、近衛師団というのは、天皇陛下を直接御守りするために東京に司令部を置く精鋭部隊である。東部軍というのは、本土決戦に備えて温存されていた皇軍正規の精鋭部隊である。特に首都圏の防衛を任務としていた。この映画は、この東部軍と近衛師団を決起させて天皇を戴き、政府が閣議決定した終戦の企てを阻止しようと奔走する、狂信的な陸軍将校の反乱劇なのである。もちろん実話である。
この映画はストーリーも鬼気迫るものがあり、2時間半を一気にみせるテンポのよさ、過剰すぎずあっさりすぎず適切な演出、情に訴えかけるような無駄な演出もない。そして役者たちのあまりにも高すぎる演技力、そして右左などと稚拙な議論など鼻から相手にしない真摯な魂のこもった熱さを感じさせる映画である。
健軍以来敗北を知らず、巨大な軍事力で極東に君臨した巨大帝国がいかにして敗北を受け入れるにいたったか丁寧に描いている。史実に忠実に描いており、無駄なカットが全くない。完璧すぎる映画である。
負けを受け入れられない狂信的な軍人たちがたくさん登場する。軍人だけでなく、警察、民間の学生にいたるまで、戦争継続を主張していた人たちがたくさんいたのだということがよくわかる。立憲君主であった(国政に口を挟めない立場の)天皇陛下が、自ら決定しなければならなかったほどに、この時の日本は混乱していたのであった。
確かに2発の原爆を落とされ、食料もなく、最悪の状況だったに違いないが、それでもなお外地に270万の第一線部隊、本土に温存された230万の陸兵、特攻機10000、これほどの軍事力を持ちながら降伏を受け入れるのは敗北を知らず、虜囚の辱めを受けずと徹底的に教育された軍人をはじめ、末端の国民にとって大変難しいことだったのだろう。ましてやすでに戦死した300万の同朋にどう申し訳が立つと言うのか。
結局近衛師団長は決起に賛同してくれず、師団長を殺害して偽命令を出すことに。こうして宮内省を占拠したが、東部軍は結局決起せず、逆に反乱軍を取り押さえると言い出す始末。こうして彼らの反乱計画は頓挫した。頓挫した後諦めきれずビラを撒きまくって決起を国民に訴えた後、宮城横で自決する・・。
連合軍が、進駐してくれば軍はもちろん、天皇や日本国民もどういう扱いを受けるかわからない。この日本という国が地球上から消えてなくなるかもしれない。どうなるかわからない。我々は今安穏と生活しているので、この頃の日本人を愚かと笑うのは簡単である。しかし日本が消えてなくなるかもしれないという恐怖をこの頃の日本人は持っていたのである。そうなれば本土決戦してでも戦局の好転を待ったほうがよい結果になったかもしれない。誰にもそんなことはわからないのである。無論我々にも。少なくとも、彼らがここまで必死に守ろうとした日本・・今それは果たして存在しているのだろうか?彼らは今のような日本を護りたかったのだろうか?男は幼稚園児のような絵に欲情し、女は誰にでも股を開き、金が全てで人は使い捨ての超資本主義。これが当時存在していた大日本帝国と同じものだろうか?もうとっくに滅びてしまっているのではないか?ならば本土決戦したほうがよかったんじゃないか?おれは真剣にこう思うのだ。それとも日本が例え戦争に勝ったとしても、ここまで日本は腐りきったのだろうか?おれにはわからん。
それはそうと、この映画の役者たちの鬼気迫る演技、アップに耐える精悍な顔、元軍人も多く、メリハリのある美しく歯切れのよい日本語を聞かせてもらえる。
とりあえずイカれたヤケクソ精神200パーセントの軍人たちがたくさん登場するのが嬉しい。これを観てしまうとローレライだのYAMATOだので感動したなどとは簡単に言えるはずないのである!
特筆すべきは
?軍令部の大西次長。このシトが終戦が決まった時に外務省局長に
「あと、2000万!後2000万特攻に出せば必ず勝てます!あと、2000万!日本男子半分を特攻に出す覚悟で戦えば!必ず!必ず!」と嘆願する姿・・もう狂気と言う以外にない(笑)。↑で理解できるとかちょっと書いてるけど、やっぱりこれはイカレてるわ(笑)。ヤケクソという以外に言葉が浮かびましぇん。
「後2000万!後2000万!」って簡単に言うなよ(笑)。
?横浜警備隊の大隊長、佐々木大尉。このシトすごい迫力です。。
「皇軍の辞書に敗北の2字なぁぁく!最後の一兵まで戦うのみであーーーーーーる!」
「第1の攻撃目標は!終戦を画しお〜る!鈴木内閣総理大臣んん!!」
「てぇぇぇぇ!!」首相官邸を襲撃する佐々木大尉率いる国民神風隊 すごい迫力です!これぞ日本軍人!
?徹底抗戦を訴える青年将校たちに陸相、阿南大将の「この阿南の屍を越えてゆけ!」という台詞 かっこよすぎ。
三船敏郎・・!
?決起が失敗したにもかかわらず諦めきれずに決起を促すビラを撒く畑中と推崎。
「国体護持のため本8月15日早暁、決起せる我ら将兵は全軍将兵ならびに国民各位に告ぐ!(中略)・・我らただただ純忠の大義に生きんのみ!」
宮城の横で自決・・このシーンは逮捕されること覚悟で撮ったんだって この黒沢年男演じる畑中少佐はよかったね
というわけでこれは必見です・・。観るっきゃない!最期の君が代は泣けますよ。この日斃れた大日本帝国の鎮魂歌なのである。
日本の終戦、8月14日正午〜玉音盤が放送される8月15日正午までの24時間を追った日本の戦争映画の総決算である。
これは古いからと言って避けるのはあまりにも愚かである。これ以上の邦画はおれは今のところ知らない。これほどの映画は今の堕落した邦画界では絶対に生まれないだろうなあ、なぜこれほどの映画が作れた国が、ここまで駄目になってしまったのか全く理解に苦しむのである。
愚痴はこのぐらいにしてそろそろ本題に入ろう。
ストーリーは7月末に連合軍側から提示されたポツダム宣言に対する日本政府がいかにして対応したのかをナレーションを含めて簡単な説明が入る。そしてもはや戦争継続は不可能である・・と天皇の御聖断が下る。しかしあくまで本土決戦を主張する陸軍は、近衛師団の参謀、古賀少佐と陸軍省の軍務課将校、畑中少佐、推崎中佐を中心にクーデター計画が水面下で進められる。その計画とは、近衛師団長、森中将を説得して近衛師団を決起させ、宮内省を占拠し玉音盤を手中にし天皇を戴き、そうすれば東部軍をはじめとした、全陸軍、国民までもが戦争継続のために決起するであろう、という計画であった。いわゆる宮城事件である。
左から推崎中佐(中村忠雄) 古賀少佐(佐藤允) 畑中少佐(黒沢年男)
玉音盤を録音している最中も、房総半島に接近中の米機動部隊の迎撃に特攻機が今日も飛び立っていく・・。全ては日本国民を護るため・・
まず近衛師団ってなに?東部軍ってなに?って話になってくるとわかりにくいので簡単に説明すると、近衛師団というのは、天皇陛下を直接御守りするために東京に司令部を置く精鋭部隊である。東部軍というのは、本土決戦に備えて温存されていた皇軍正規の精鋭部隊である。特に首都圏の防衛を任務としていた。この映画は、この東部軍と近衛師団を決起させて天皇を戴き、政府が閣議決定した終戦の企てを阻止しようと奔走する、狂信的な陸軍将校の反乱劇なのである。もちろん実話である。
この映画はストーリーも鬼気迫るものがあり、2時間半を一気にみせるテンポのよさ、過剰すぎずあっさりすぎず適切な演出、情に訴えかけるような無駄な演出もない。そして役者たちのあまりにも高すぎる演技力、そして右左などと稚拙な議論など鼻から相手にしない真摯な魂のこもった熱さを感じさせる映画である。
健軍以来敗北を知らず、巨大な軍事力で極東に君臨した巨大帝国がいかにして敗北を受け入れるにいたったか丁寧に描いている。史実に忠実に描いており、無駄なカットが全くない。完璧すぎる映画である。
負けを受け入れられない狂信的な軍人たちがたくさん登場する。軍人だけでなく、警察、民間の学生にいたるまで、戦争継続を主張していた人たちがたくさんいたのだということがよくわかる。立憲君主であった(国政に口を挟めない立場の)天皇陛下が、自ら決定しなければならなかったほどに、この時の日本は混乱していたのであった。
確かに2発の原爆を落とされ、食料もなく、最悪の状況だったに違いないが、それでもなお外地に270万の第一線部隊、本土に温存された230万の陸兵、特攻機10000、これほどの軍事力を持ちながら降伏を受け入れるのは敗北を知らず、虜囚の辱めを受けずと徹底的に教育された軍人をはじめ、末端の国民にとって大変難しいことだったのだろう。ましてやすでに戦死した300万の同朋にどう申し訳が立つと言うのか。
結局近衛師団長は決起に賛同してくれず、師団長を殺害して偽命令を出すことに。こうして宮内省を占拠したが、東部軍は結局決起せず、逆に反乱軍を取り押さえると言い出す始末。こうして彼らの反乱計画は頓挫した。頓挫した後諦めきれずビラを撒きまくって決起を国民に訴えた後、宮城横で自決する・・。
連合軍が、進駐してくれば軍はもちろん、天皇や日本国民もどういう扱いを受けるかわからない。この日本という国が地球上から消えてなくなるかもしれない。どうなるかわからない。我々は今安穏と生活しているので、この頃の日本人を愚かと笑うのは簡単である。しかし日本が消えてなくなるかもしれないという恐怖をこの頃の日本人は持っていたのである。そうなれば本土決戦してでも戦局の好転を待ったほうがよい結果になったかもしれない。誰にもそんなことはわからないのである。無論我々にも。少なくとも、彼らがここまで必死に守ろうとした日本・・今それは果たして存在しているのだろうか?彼らは今のような日本を護りたかったのだろうか?男は幼稚園児のような絵に欲情し、女は誰にでも股を開き、金が全てで人は使い捨ての超資本主義。これが当時存在していた大日本帝国と同じものだろうか?もうとっくに滅びてしまっているのではないか?ならば本土決戦したほうがよかったんじゃないか?おれは真剣にこう思うのだ。それとも日本が例え戦争に勝ったとしても、ここまで日本は腐りきったのだろうか?おれにはわからん。
それはそうと、この映画の役者たちの鬼気迫る演技、アップに耐える精悍な顔、元軍人も多く、メリハリのある美しく歯切れのよい日本語を聞かせてもらえる。
とりあえずイカれたヤケクソ精神200パーセントの軍人たちがたくさん登場するのが嬉しい。これを観てしまうとローレライだのYAMATOだので感動したなどとは簡単に言えるはずないのである!
特筆すべきは
?軍令部の大西次長。このシトが終戦が決まった時に外務省局長に
「あと、2000万!後2000万特攻に出せば必ず勝てます!あと、2000万!日本男子半分を特攻に出す覚悟で戦えば!必ず!必ず!」と嘆願する姿・・もう狂気と言う以外にない(笑)。↑で理解できるとかちょっと書いてるけど、やっぱりこれはイカレてるわ(笑)。ヤケクソという以外に言葉が浮かびましぇん。
「後2000万!後2000万!」って簡単に言うなよ(笑)。
?横浜警備隊の大隊長、佐々木大尉。このシトすごい迫力です。。
「皇軍の辞書に敗北の2字なぁぁく!最後の一兵まで戦うのみであーーーーーーる!」
「第1の攻撃目標は!終戦を画しお〜る!鈴木内閣総理大臣んん!!」
「てぇぇぇぇ!!」首相官邸を襲撃する佐々木大尉率いる国民神風隊 すごい迫力です!これぞ日本軍人!
?徹底抗戦を訴える青年将校たちに陸相、阿南大将の「この阿南の屍を越えてゆけ!」という台詞 かっこよすぎ。
三船敏郎・・!
?決起が失敗したにもかかわらず諦めきれずに決起を促すビラを撒く畑中と推崎。
「国体護持のため本8月15日早暁、決起せる我ら将兵は全軍将兵ならびに国民各位に告ぐ!(中略)・・我らただただ純忠の大義に生きんのみ!」
宮城の横で自決・・このシーンは逮捕されること覚悟で撮ったんだって この黒沢年男演じる畑中少佐はよかったね
というわけでこれは必見です・・。観るっきゃない!最期の君が代は泣けますよ。この日斃れた大日本帝国の鎮魂歌なのである。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
橋本 忍 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
橋本 忍のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37839人
- 2位
- 酒好き
- 170669人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89536人