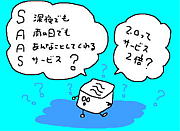SaaSは、元はちょっと内容は違いますが、ASPとして一時盛り上がっていました。
ただ、ほとんどがASPになるような状態ではありませんでした。
2000年〜2007年ごろまで、ネットワークは今現在ほど早くも安くもなかった
のは確かですし、「サービスとして使いたいものを使う」という概念も付加
されていませんでしたが、それ以外はSaaSと同じです。
そう考えると、ASPで失敗した理由は、SaaSでも失敗要因になります。
さらに、現在の方が失敗要因として高い壁になった内容もあります。
SaaSはあくまでソフトの提供形式の問題で、
・最近は特にセキュリティリスクに対して厳しくなってきていますが、
SaaSは組織の外部にデータ管理任せることになるため、
セキュリティが信用出来ないとのことでコンテンツ次第では全然
売れない可能性もある(個人情報保護法や、J-SOX等。
人事情報、ユーザー情報)
・あくまで提供方式のため、結局売れるかどうかはエンドユーザーが
利用するコンテンツ次第である。そのコンテンツはどうするのか?
・金額は?結局ASPの方が安かったら、それだけ売れていたかもしれませんが、
ここまでASPが定着していないということは、既存のソフトと比べて、
大して安くはないし、大きなメリットもなかったのではないでしょうか。
・ソフトを作る人材は集められるか?どんな人材が必要か?
少なくとも、SaaSで作るソフトに、仕様書に決められた機能しか作らない
コードを書く単なる「プログラマー」は役に立たない。
SaaSは不特定多数による利用の基本で、SaaSベンダーは売れる機能を作らない
と利用者がおらずに不良在庫が残って倒産する「製品販売者としてのリスク」
を負うため。
(仕様書通りにコード書くことを求められる個々人は、最終製品に対する
責任を負う必要がないため、理想を求めたソースを書くモチベーション自体
醸成されない。)
思いつくままに書きましたが、
これらをクリア、もしくは外さなければ、SaaSでは意味がないと思われます。
皆さんが考えるリスクと、それに対する解決案を聞いてみたいと思っていますが、いかがでしょうか。
ただ、ほとんどがASPになるような状態ではありませんでした。
2000年〜2007年ごろまで、ネットワークは今現在ほど早くも安くもなかった
のは確かですし、「サービスとして使いたいものを使う」という概念も付加
されていませんでしたが、それ以外はSaaSと同じです。
そう考えると、ASPで失敗した理由は、SaaSでも失敗要因になります。
さらに、現在の方が失敗要因として高い壁になった内容もあります。
SaaSはあくまでソフトの提供形式の問題で、
・最近は特にセキュリティリスクに対して厳しくなってきていますが、
SaaSは組織の外部にデータ管理任せることになるため、
セキュリティが信用出来ないとのことでコンテンツ次第では全然
売れない可能性もある(個人情報保護法や、J-SOX等。
人事情報、ユーザー情報)
・あくまで提供方式のため、結局売れるかどうかはエンドユーザーが
利用するコンテンツ次第である。そのコンテンツはどうするのか?
・金額は?結局ASPの方が安かったら、それだけ売れていたかもしれませんが、
ここまでASPが定着していないということは、既存のソフトと比べて、
大して安くはないし、大きなメリットもなかったのではないでしょうか。
・ソフトを作る人材は集められるか?どんな人材が必要か?
少なくとも、SaaSで作るソフトに、仕様書に決められた機能しか作らない
コードを書く単なる「プログラマー」は役に立たない。
SaaSは不特定多数による利用の基本で、SaaSベンダーは売れる機能を作らない
と利用者がおらずに不良在庫が残って倒産する「製品販売者としてのリスク」
を負うため。
(仕様書通りにコード書くことを求められる個々人は、最終製品に対する
責任を負う必要がないため、理想を求めたソースを書くモチベーション自体
醸成されない。)
思いつくままに書きましたが、
これらをクリア、もしくは外さなければ、SaaSでは意味がないと思われます。
皆さんが考えるリスクと、それに対する解決案を聞いてみたいと思っていますが、いかがでしょうか。
|
|
|
|
コメント(15)
私も同じように感じています。
特に経済産業省は中小企業約50万社(これまでITを活用していない企業)を対象に、SaaSによる
業務ツールの導入を進めています。
ここで、大企業を除き、中小企業を対象に考えると、3つの課題があると思っています。
(1)サービスの利用料がどの程度まで安価になるか?
(2)サービス提供後のサポートや保守・改修を行うための維持費は大丈夫?
(3)↑(2)に連動して、ベンダー側の組織が維持できるか?
(1)については、毎月の支払いを概算すると
回線利用料(ADSL約2,000円) + サービス利用料(一つの業務当り約2,000円)
この外に プロバイダー利用料(約2,000円) ≒ 6,000円/月
回線利用料とプロバイダー利用料はこれまで通り負担してもらえるとして、
しかし、SaaSサービス利用料は、月2,000円×12ヶ月=年24,000円 と言う金額が、
中小企業にメリットあるとは説明できません。
複数年、サービスを利用するとパッケージ購入の方が安くなるからです。
(2)サービス提供後のサポートや保守・改修を行うための維持費は大丈夫?
ベンダーが生き残るためには、ユーザー数の確保が最大の課題です。
現状、SaaSで提供されるサービス、例えば会計ソフトは、既に導入している企業があり、
利用に挫折している実態もあります。
この状況は、SaaSの普及には大きな阻害要因です。
このような背景の中、ユーザー数を確保し、サポートや保守・改修の人件費を
確保することが、ASPの歴史を
見ると、厳しい現実ばかりです。(私の理解力では)
(3)↑(2)に連動して、ベンダー側の組織が維持できるか?
ユーザーに提供するサービスの開発には、必要スキルを有する技術者の確保が必要になります。
ベンダーとしては、サポート人員、保守・改修人員を確保しつつ、新サービスの開発で他ベンダーと差別化競争を進め
ますが、経験と知識を有する技術者の数・質を維持することが、実はベンダーの課題になります。(概ねサービスのライフサイクルは3年)
3〜5年後に利益確保と技術者確保が両立できるのでしょうか
これはSaaSに限らず、パッケージソフトでも同じですが
タカシ=ウマヲさんは、解決案を求めておられるのですが、課題の整理になり申し訳ございません。
特に経済産業省は中小企業約50万社(これまでITを活用していない企業)を対象に、SaaSによる
業務ツールの導入を進めています。
ここで、大企業を除き、中小企業を対象に考えると、3つの課題があると思っています。
(1)サービスの利用料がどの程度まで安価になるか?
(2)サービス提供後のサポートや保守・改修を行うための維持費は大丈夫?
(3)↑(2)に連動して、ベンダー側の組織が維持できるか?
(1)については、毎月の支払いを概算すると
回線利用料(ADSL約2,000円) + サービス利用料(一つの業務当り約2,000円)
この外に プロバイダー利用料(約2,000円) ≒ 6,000円/月
回線利用料とプロバイダー利用料はこれまで通り負担してもらえるとして、
しかし、SaaSサービス利用料は、月2,000円×12ヶ月=年24,000円 と言う金額が、
中小企業にメリットあるとは説明できません。
複数年、サービスを利用するとパッケージ購入の方が安くなるからです。
(2)サービス提供後のサポートや保守・改修を行うための維持費は大丈夫?
ベンダーが生き残るためには、ユーザー数の確保が最大の課題です。
現状、SaaSで提供されるサービス、例えば会計ソフトは、既に導入している企業があり、
利用に挫折している実態もあります。
この状況は、SaaSの普及には大きな阻害要因です。
このような背景の中、ユーザー数を確保し、サポートや保守・改修の人件費を
確保することが、ASPの歴史を
見ると、厳しい現実ばかりです。(私の理解力では)
(3)↑(2)に連動して、ベンダー側の組織が維持できるか?
ユーザーに提供するサービスの開発には、必要スキルを有する技術者の確保が必要になります。
ベンダーとしては、サポート人員、保守・改修人員を確保しつつ、新サービスの開発で他ベンダーと差別化競争を進め
ますが、経験と知識を有する技術者の数・質を維持することが、実はベンダーの課題になります。(概ねサービスのライフサイクルは3年)
3〜5年後に利益確保と技術者確保が両立できるのでしょうか
これはSaaSに限らず、パッケージソフトでも同じですが
タカシ=ウマヲさんは、解決案を求めておられるのですが、課題の整理になり申し訳ございません。
なべさん、コメントありがとうございます。
>特に経済産業省は中小企業約50万社(これまでITを活用していない企業)を対象
>に、SaaSによる業務ツールの導入を進めています。
これ、どんなものですか?
気になります。
>しかし、SaaSサービス利用料は、月2,000円×12ヶ月=年24,000円 と言う金額が、
>中小企業にメリットあるとは説明できません。
>複数年、サービスを利用するとパッケージ購入の方が安くなるからです。
こちら、パッケージはどんなものと比較されていますか?
勘定奉行とかで、中小企業だったら機能的に十分??
SaaSはパッケージと比べて、サーバー負担は大きくなりますが、管理コストは集中するため少なくなり、同じソフトの機能だった場合、理論的にはユーザーが自前で揃えるより
安くなりそうなんですが。
また、回線の話をすると、回線利用は二つ考えがあり、
1)普通の家庭用で使うようなADSL回線を使うが、
セキュリティ確保のため、https等のセキュリティが確保できる暗号化技術が必要。そのコストをベンダーは負う必要がある。
(本日、理論的に解読が不可能、という暗号化形式の記事を@ITで見ました。
CAB方式 http://www.atmarkit.co.jp/news/200804/11/cab.html
ちなみに、それに対する反論
http://d.hatena.ne.jp/smoking186/20080412/1208008068)
2)セキュリティ確保のため、回線自体のセキュリティとしてVPNや専用回線を利用してもらう。
ただ、弊社が提携しているNTT系列の専用回線は、 ADSL形式で月2万強から3万強の種類。。 年間30万弱。。
企業向けだったら、それを負担出来るレベルの会社にまずは売り込みかけて
ソフトレベルを上げ、その後自社内で負担出来る仕組みに変更する、という
のはありだとは思いますが。一般ユーザー向けは1)でないと無理でしょうね。
> 現状、SaaSで提供されるサービス、例えば会計ソフトは、
>既に導入している企業があり、
>利用に挫折している実態もあります。
これ、会計ソフトベンダーはどこの会社ですか?(言えない場合はよいですが。)
> このような背景の中、ユーザー数を確保し、サポートや保守・改修の人件費を
>確保することが、ASPの歴史を 見ると、厳しい現実ばかりです。
こちら、私の仮説では、
ユーザーが満足できるほどのカスタマイズ(=機能)、またそれに見合う金額が提示出来ていないからではないかと。
この感覚は、実際アンケートでも裏づけがあります。
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0802/06/news008_3.html
まあ、当然自分達の業務があまりにも崩される、制度を変えないといけない、ということが多ければ、そのコストもバカにならないので、他の機能網羅して費用対効果高いソフトを選ぶでしょう。
ちょっと文字数たりないため、次のコメントにて。。
>特に経済産業省は中小企業約50万社(これまでITを活用していない企業)を対象
>に、SaaSによる業務ツールの導入を進めています。
これ、どんなものですか?
気になります。
>しかし、SaaSサービス利用料は、月2,000円×12ヶ月=年24,000円 と言う金額が、
>中小企業にメリットあるとは説明できません。
>複数年、サービスを利用するとパッケージ購入の方が安くなるからです。
こちら、パッケージはどんなものと比較されていますか?
勘定奉行とかで、中小企業だったら機能的に十分??
SaaSはパッケージと比べて、サーバー負担は大きくなりますが、管理コストは集中するため少なくなり、同じソフトの機能だった場合、理論的にはユーザーが自前で揃えるより
安くなりそうなんですが。
また、回線の話をすると、回線利用は二つ考えがあり、
1)普通の家庭用で使うようなADSL回線を使うが、
セキュリティ確保のため、https等のセキュリティが確保できる暗号化技術が必要。そのコストをベンダーは負う必要がある。
(本日、理論的に解読が不可能、という暗号化形式の記事を@ITで見ました。
CAB方式 http://www.atmarkit.co.jp/news/200804/11/cab.html
ちなみに、それに対する反論
http://d.hatena.ne.jp/smoking186/20080412/1208008068)
2)セキュリティ確保のため、回線自体のセキュリティとしてVPNや専用回線を利用してもらう。
ただ、弊社が提携しているNTT系列の専用回線は、 ADSL形式で月2万強から3万強の種類。。 年間30万弱。。
企業向けだったら、それを負担出来るレベルの会社にまずは売り込みかけて
ソフトレベルを上げ、その後自社内で負担出来る仕組みに変更する、という
のはありだとは思いますが。一般ユーザー向けは1)でないと無理でしょうね。
> 現状、SaaSで提供されるサービス、例えば会計ソフトは、
>既に導入している企業があり、
>利用に挫折している実態もあります。
これ、会計ソフトベンダーはどこの会社ですか?(言えない場合はよいですが。)
> このような背景の中、ユーザー数を確保し、サポートや保守・改修の人件費を
>確保することが、ASPの歴史を 見ると、厳しい現実ばかりです。
こちら、私の仮説では、
ユーザーが満足できるほどのカスタマイズ(=機能)、またそれに見合う金額が提示出来ていないからではないかと。
この感覚は、実際アンケートでも裏づけがあります。
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0802/06/news008_3.html
まあ、当然自分達の業務があまりにも崩される、制度を変えないといけない、ということが多ければ、そのコストもバカにならないので、他の機能網羅して費用対効果高いソフトを選ぶでしょう。
ちょっと文字数たりないため、次のコメントにて。。
続き。
>経験と知識を有する技術者の数・質を維持することが、実はベンダー
>の課題になります。(概ねサービスのライフサイクルは3年)
> 3〜5年後に利益確保と技術者確保が両立できるのでしょうか
今までの私の経験、及び最近読んだ本の知識より、日本国内だけではこの技術と質の確保は非常に大変だろうな、という印象を受けています。
「ソフトウェア企業の競争戦略」という本を今読んでいるのですが、
日本のSIerはアメリカ、ヨーロッパ、インドと比べて、1000行あたりのバグ数が
かなり少ないそうです。20倍から100倍は違うのかな。
ただ、それは日本の製造業的文化と、NASAで発展したウォーターフロー形式のプロセスを元にしたからだと思います。
根本的に上記はSaaSでキャズムを越える提供方式を確立するには、邪魔でしかないのではないかと。
まず、目的と優先度が違います。
バグの少なさ=品質の高さ、というのは、インフラとしてのソフトで絶対安定性が必要なもの(航空管制システムや、電車の運行管理、銀行のATM等決済システム、NASAのロケットを飛ばすシステム、等)で必要なだけで、皆さんはwindows使っていて、1日1回ぐらいの再起動はあんまり気になっていないと思います。
結局、一般のユーザーも、企業でも、本当に必要なのは自分がやりたいことを、確実に、スムーズに出来ること、だと思います。
amazonなら決済システム、安全なセキュリティ、間違えのない検索システム。
推薦図書が少々バグってトムピーターズのビジネス書のつもりが高杉良の小説になっても、文句言う人はほとんどいないと思います。
ただ、私の経験では、社内向け業務システム対象ですが、インフラ系(電気、ガス、銀行等)→製造業→サービス業 の順にシステムのバグに対する煩さがあります。
文化だとは思いますが、その文化こそが日本国内でASPが普及せず、
また世界に通用するソフトが日本から出てこない大きな要因ではないかと。
品質重視のシステム屋が来ても、長いことやっている人ほどソフト作成には向かないと思います。(サーバー管理にはある程度向いていそうですが。)
ちなみに、3〜5年後の利益確保に関しては、私は「キャズム」がオススメです。
マーケット範囲を狭め、そこで売って満足できるレベルのシステムを作成し、
さらに横展開出来るマーケットをせめて、ソフト自身も拡張する。
拡張できるように作っておく。
それが基本戦略ではないでしょうか。(その対象を絞り込むことこそ難しいのだとは思いますが。)
>経験と知識を有する技術者の数・質を維持することが、実はベンダー
>の課題になります。(概ねサービスのライフサイクルは3年)
> 3〜5年後に利益確保と技術者確保が両立できるのでしょうか
今までの私の経験、及び最近読んだ本の知識より、日本国内だけではこの技術と質の確保は非常に大変だろうな、という印象を受けています。
「ソフトウェア企業の競争戦略」という本を今読んでいるのですが、
日本のSIerはアメリカ、ヨーロッパ、インドと比べて、1000行あたりのバグ数が
かなり少ないそうです。20倍から100倍は違うのかな。
ただ、それは日本の製造業的文化と、NASAで発展したウォーターフロー形式のプロセスを元にしたからだと思います。
根本的に上記はSaaSでキャズムを越える提供方式を確立するには、邪魔でしかないのではないかと。
まず、目的と優先度が違います。
バグの少なさ=品質の高さ、というのは、インフラとしてのソフトで絶対安定性が必要なもの(航空管制システムや、電車の運行管理、銀行のATM等決済システム、NASAのロケットを飛ばすシステム、等)で必要なだけで、皆さんはwindows使っていて、1日1回ぐらいの再起動はあんまり気になっていないと思います。
結局、一般のユーザーも、企業でも、本当に必要なのは自分がやりたいことを、確実に、スムーズに出来ること、だと思います。
amazonなら決済システム、安全なセキュリティ、間違えのない検索システム。
推薦図書が少々バグってトムピーターズのビジネス書のつもりが高杉良の小説になっても、文句言う人はほとんどいないと思います。
ただ、私の経験では、社内向け業務システム対象ですが、インフラ系(電気、ガス、銀行等)→製造業→サービス業 の順にシステムのバグに対する煩さがあります。
文化だとは思いますが、その文化こそが日本国内でASPが普及せず、
また世界に通用するソフトが日本から出てこない大きな要因ではないかと。
品質重視のシステム屋が来ても、長いことやっている人ほどソフト作成には向かないと思います。(サーバー管理にはある程度向いていそうですが。)
ちなみに、3〜5年後の利益確保に関しては、私は「キャズム」がオススメです。
マーケット範囲を狭め、そこで売って満足できるレベルのシステムを作成し、
さらに横展開出来るマーケットをせめて、ソフト自身も拡張する。
拡張できるように作っておく。
それが基本戦略ではないでしょうか。(その対象を絞り込むことこそ難しいのだとは思いますが。)
タカシ=ウマヲさん、コメありがとうございます。
プラネットさん、経済産業省のサイト、ご紹介ありがとうございました。
タカシ=ウマヲさんが紹介してくれた、回線と提供金額のサイトは、すごく参考になりました。
また、何点かご質問があったのですが、その前に私、個人がイメージしているSaaSを利用するユーザーの
条件を明記しておきます。
※この条件をもとに、発言をしますので、このトピ立ての趣旨にそぐわない内容がありましたら、ゴメンなさい
(1)サービスの利用者は
全国の中小企業の中でも、より小規模な企業と個人事業者の50万社です。
その中でも、従業員が10名以下で、専業事務員が1名または0名(兼務)で
50万社のうち、80%以上を占めています
(2)業種は
サービス業、流通業
(この外の業種は、概ね事業規模が大きいと思われるので、対象外としています)
(3)提供するサービスは
優先順 : 会計・給与 > 販売管理・顧客管理 > その他
(その他サービスとは、最終的にはSaaS版のERPの方向で提供されるんだろうなぁ〜! 程度しか考えていません)
(4)現在IT利用している/していない
していない。または、難しくてできない。
こんな感じです。
で、ご質問にお答えします。(前置きが長くてスイマセン )
)
>これ、どんなものですか?
>気になります。
プラネットさんが紹介していただいたので、省略しますね
>こちら、パッケージはどんなものと比較されていますか?
>勘定奉行とかで、中小企業だったら機能的に十分??
価格帯は、5万円程度の会計ソフトをイメージしてます。
勘定奉行、会計王、大蔵大臣などのパッケージソフトは、分析帳票などが充実し過ぎて、上記条件で示した80%の
利用者にはオーバースペックです。
そのほとんどの企業が手書き帳簿を使用し、全てをパソコンに入力することができない企業です。(その理由は何でしょう?)
>また、回線の話をすると、回線利用は二つ考えがあり、
>1)普通の家庭用で使うようなADSL回線を使うが、...
DSL回線でYahooBB、OCNを想定しています。
2005年の古いデータで申し訳ないのですが、
インターネット利用者:8,500万人以上
契約回線種別:(DSL)1,400万、(FTTH)500万
もうしばらくは、DSL回線のままで、Web閲覧とメール中心の利用からは脱却できないと考えています。
タカシ=ウマヲさんも言っている通りです。
>これ、会計ソフトベンダーはどこの会社ですか?(言えない場合はよいですが。)
Y会計です。
利用されない理由には、薦めた会計事務所にも原因がありそうですが...
この外、品質面と採算性についてのご意見をいただきましたが、長くなるので省略させていただきます。
プラネットさん、経済産業省のサイト、ご紹介ありがとうございました。
タカシ=ウマヲさんが紹介してくれた、回線と提供金額のサイトは、すごく参考になりました。
また、何点かご質問があったのですが、その前に私、個人がイメージしているSaaSを利用するユーザーの
条件を明記しておきます。
※この条件をもとに、発言をしますので、このトピ立ての趣旨にそぐわない内容がありましたら、ゴメンなさい
(1)サービスの利用者は
全国の中小企業の中でも、より小規模な企業と個人事業者の50万社です。
その中でも、従業員が10名以下で、専業事務員が1名または0名(兼務)で
50万社のうち、80%以上を占めています
(2)業種は
サービス業、流通業
(この外の業種は、概ね事業規模が大きいと思われるので、対象外としています)
(3)提供するサービスは
優先順 : 会計・給与 > 販売管理・顧客管理 > その他
(その他サービスとは、最終的にはSaaS版のERPの方向で提供されるんだろうなぁ〜! 程度しか考えていません)
(4)現在IT利用している/していない
していない。または、難しくてできない。
こんな感じです。
で、ご質問にお答えします。(前置きが長くてスイマセン
>これ、どんなものですか?
>気になります。
プラネットさんが紹介していただいたので、省略しますね
>こちら、パッケージはどんなものと比較されていますか?
>勘定奉行とかで、中小企業だったら機能的に十分??
価格帯は、5万円程度の会計ソフトをイメージしてます。
勘定奉行、会計王、大蔵大臣などのパッケージソフトは、分析帳票などが充実し過ぎて、上記条件で示した80%の
利用者にはオーバースペックです。
そのほとんどの企業が手書き帳簿を使用し、全てをパソコンに入力することができない企業です。(その理由は何でしょう?)
>また、回線の話をすると、回線利用は二つ考えがあり、
>1)普通の家庭用で使うようなADSL回線を使うが、...
DSL回線でYahooBB、OCNを想定しています。
2005年の古いデータで申し訳ないのですが、
インターネット利用者:8,500万人以上
契約回線種別:(DSL)1,400万、(FTTH)500万
もうしばらくは、DSL回線のままで、Web閲覧とメール中心の利用からは脱却できないと考えています。
タカシ=ウマヲさんも言っている通りです。
>これ、会計ソフトベンダーはどこの会社ですか?(言えない場合はよいですが。)
Y会計です。
利用されない理由には、薦めた会計事務所にも原因がありそうですが...
この外、品質面と採算性についてのご意見をいただきましたが、長くなるので省略させていただきます。
>プラネットさん
情報ありがとうございます。
ただ、経済産業省が主導でやってますけど、これのプラットフォーム作るの、どこの会社なんでしょうか?(やはりデータ??)
また、このSaaSプラットフォームの保守はどこがやっていくのか?
セキュリティはしっかりしそうだけど、スピードや安定性、容量等のインフラ性能の向上のインセンティブを、どうやって経産省は担保するつもりなんでしょうね。
使う人が多くなるのに、売り上げが伸びないような仕組みだったらやる気なくしてしょぼいインフラしか出来なくなると思いますが。。
(たぶん本当に零細・中小企業向けの必要最低限ソフトになりそうです。。)
>なべさん
小規模な企業と個人事業者の50万社、とありますが、やっぱりそこがいいんでしょうか?なべさんが接した具体的ターゲット事例ありますか??
私は、中規模以上でもメリットあるし、さらに言えば個人向けコンテンツにもメリットあるものがあるのでは、と。(構想中)
>勘定奉行、会計王、大蔵大臣などのパッケージソフトは、分析帳票などが充実>し過ぎて、上記条件で示した80%の 利用者にはオーバースペックです。
まじですか!?
個人事業主レベルだったら、やはりそんなものなのでしょうか。
そういう意味では、1ヶ月サービス利用料1000円強、ということでしょうか。
(必要な機能分だけお金を支払う、といったイメージでしょうか。)
そういう意味では、大きな企業でのソフト値段は、やはり違いますね。。
ざっくりですが、夜時間で少々睡眠不足のため、本日はこのあたりで。。
情報ありがとうございます。
ただ、経済産業省が主導でやってますけど、これのプラットフォーム作るの、どこの会社なんでしょうか?(やはりデータ??)
また、このSaaSプラットフォームの保守はどこがやっていくのか?
セキュリティはしっかりしそうだけど、スピードや安定性、容量等のインフラ性能の向上のインセンティブを、どうやって経産省は担保するつもりなんでしょうね。
使う人が多くなるのに、売り上げが伸びないような仕組みだったらやる気なくしてしょぼいインフラしか出来なくなると思いますが。。
(たぶん本当に零細・中小企業向けの必要最低限ソフトになりそうです。。)
>なべさん
小規模な企業と個人事業者の50万社、とありますが、やっぱりそこがいいんでしょうか?なべさんが接した具体的ターゲット事例ありますか??
私は、中規模以上でもメリットあるし、さらに言えば個人向けコンテンツにもメリットあるものがあるのでは、と。(構想中)
>勘定奉行、会計王、大蔵大臣などのパッケージソフトは、分析帳票などが充実>し過ぎて、上記条件で示した80%の 利用者にはオーバースペックです。
まじですか!?
個人事業主レベルだったら、やはりそんなものなのでしょうか。
そういう意味では、1ヶ月サービス利用料1000円強、ということでしょうか。
(必要な機能分だけお金を支払う、といったイメージでしょうか。)
そういう意味では、大きな企業でのソフト値段は、やはり違いますね。。
ざっくりですが、夜時間で少々睡眠不足のため、本日はこのあたりで。。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
SaaS(Software as a Service) 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
SaaS(Software as a Service)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90024人
- 2位
- 酒好き
- 170668人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37149人