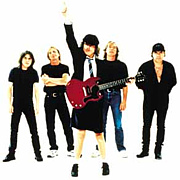はじめまして。今小学校で教育実習をしているものです。
私はピアノを習っていたというものの、音楽教育を勉強しているわけではないので音楽についての専門知識はほっとんどありません。そんな私が、このたび実習で4年生の音楽の授業を担当することになりました。ただ音楽が好きというだけで、専科志望でもなく専門知識もないため、かなり悩んでいます。。。授業の題材もいろいろ考えているのですが、限られた時数で出来ること、、、となるとなかなか良いものが浮かばず。今はパートナーミュージックというのを取り上げようかと考えています。
ところで、「パートナーミュージック」ってご存知ですか?私はこの呼び方は最近本を見て知りました。ちなみにネットでは引っかかりません;要は「違う2曲を同時に弾いても調和する」、つまりは同じコード進行の2曲の組ってことですよね。例えば「ロンドン橋落ちた」と「メリーさんの羊」などです。ピアニスターHIROSHIさんが右手で「猫踏んじゃった」左手で「犬のおまわりさん」を演奏されていますが、この2曲もそうですよね。 これ以外にもいくつかあるんですが、私の中ではネタギレな感じです。。皆さんもパートナーになる2曲ってご存じないでしょうか??もしありましたら、教えていただきたいです。
私自身、小さい頃からこんな「音楽を使った遊び」がすごく好きだったので、取り上げてみようと思い立ちました。子どもたちには、漠然としすぎているんですが「音楽ってこんなこともできるんや!おもろいやん!!」ってコトを感じ取ってもらいたいなぁ、と思っています。指導案を書くのでもっと具体的に「つけたい力」とか考えなくちゃいけないし、この授業の‘落としどころ’も考えないとだめなんですが・・・。
どんな授業になるのかまだはっきりしませんが、何かこの題材に対して、ご意見いただきたいです。やめたほうがいい、とかでも全然かまいません。音楽教育を専門とされている皆様のお考えを頂きたいと思っています。なにせ、不勉強なもので・・・。
よろしくお願いします。
私はピアノを習っていたというものの、音楽教育を勉強しているわけではないので音楽についての専門知識はほっとんどありません。そんな私が、このたび実習で4年生の音楽の授業を担当することになりました。ただ音楽が好きというだけで、専科志望でもなく専門知識もないため、かなり悩んでいます。。。授業の題材もいろいろ考えているのですが、限られた時数で出来ること、、、となるとなかなか良いものが浮かばず。今はパートナーミュージックというのを取り上げようかと考えています。
ところで、「パートナーミュージック」ってご存知ですか?私はこの呼び方は最近本を見て知りました。ちなみにネットでは引っかかりません;要は「違う2曲を同時に弾いても調和する」、つまりは同じコード進行の2曲の組ってことですよね。例えば「ロンドン橋落ちた」と「メリーさんの羊」などです。ピアニスターHIROSHIさんが右手で「猫踏んじゃった」左手で「犬のおまわりさん」を演奏されていますが、この2曲もそうですよね。 これ以外にもいくつかあるんですが、私の中ではネタギレな感じです。。皆さんもパートナーになる2曲ってご存じないでしょうか??もしありましたら、教えていただきたいです。
私自身、小さい頃からこんな「音楽を使った遊び」がすごく好きだったので、取り上げてみようと思い立ちました。子どもたちには、漠然としすぎているんですが「音楽ってこんなこともできるんや!おもろいやん!!」ってコトを感じ取ってもらいたいなぁ、と思っています。指導案を書くのでもっと具体的に「つけたい力」とか考えなくちゃいけないし、この授業の‘落としどころ’も考えないとだめなんですが・・・。
どんな授業になるのかまだはっきりしませんが、何かこの題材に対して、ご意見いただきたいです。やめたほうがいい、とかでも全然かまいません。音楽教育を専門とされている皆様のお考えを頂きたいと思っています。なにせ、不勉強なもので・・・。
よろしくお願いします。
|
|
|
|
コメント(5)
「パートナー・ミュージック」
寡聞にして私もこの概念は知りませんでした。
でも、楽しそうなのでどんどんやってみては如何ですか。
自分が楽しいと思うことを子供達に伝えて
音楽の喜びを共有できればそれが一番です。
音楽の理解、という観点で見れば
まったく別の曲が、なぜ同時に心地よく響くのか
を考えさせることになると思いますが
4年生にとっては高度すぎるかもしれませんね。
パートナー・ミュージックに限らず
音による遊び、コミュニケーションは
十分、授業で使える素材だと思います。
そうした音遊びの授業が雑音の固まりになるかならないか
そこがもっとも難しいポイントだと私には思われます。
寡聞にして私もこの概念は知りませんでした。
でも、楽しそうなのでどんどんやってみては如何ですか。
自分が楽しいと思うことを子供達に伝えて
音楽の喜びを共有できればそれが一番です。
音楽の理解、という観点で見れば
まったく別の曲が、なぜ同時に心地よく響くのか
を考えさせることになると思いますが
4年生にとっては高度すぎるかもしれませんね。
パートナー・ミュージックに限らず
音による遊び、コミュニケーションは
十分、授業で使える素材だと思います。
そうした音遊びの授業が雑音の固まりになるかならないか
そこがもっとも難しいポイントだと私には思われます。
はじめまして。
いまちょうど四年生に郷土の音楽のところで
教科書ではこきりこを取り上げていましたが、
あえて沖縄を取り上げ、
「ハイサイおじさん」と「谷茶前」を中心に
沖縄音階に触れつつ、和太鼓を叩かせたりしました。
その2曲をうまくミックスさせつつ編曲し、
合奏をこれからやっていきます。
でも、四年生じゃ大変ですねぇ〜
オレは、よく隊形移動や、笛を準備させるときに
ぱらぱらっとピアノを弾くのですが、
普通に長調で弾いて途中で短調に替えたり
おふざけしながら弾いていますが、
子どもは結構「こぇ〜」とか「くれぇ〜」とか
言って盛り上がります。
そういう楽しさって必要ですよねっ。
実習がんばってくださぃ!!ってもう終わっちゃってるかな?
いまちょうど四年生に郷土の音楽のところで
教科書ではこきりこを取り上げていましたが、
あえて沖縄を取り上げ、
「ハイサイおじさん」と「谷茶前」を中心に
沖縄音階に触れつつ、和太鼓を叩かせたりしました。
その2曲をうまくミックスさせつつ編曲し、
合奏をこれからやっていきます。
でも、四年生じゃ大変ですねぇ〜
オレは、よく隊形移動や、笛を準備させるときに
ぱらぱらっとピアノを弾くのですが、
普通に長調で弾いて途中で短調に替えたり
おふざけしながら弾いていますが、
子どもは結構「こぇ〜」とか「くれぇ〜」とか
言って盛り上がります。
そういう楽しさって必要ですよねっ。
実習がんばってくださぃ!!ってもう終わっちゃってるかな?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
音楽教育をおもしろく! 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
音楽教育をおもしろく!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- マイミク募集はここで。
- 89579人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208275人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90043人