歌舞伎座さよなら公演 六月大歌舞伎
平成21年6月3日(水)初日 27日(土)千穐楽
昼の部(午前11時開演)
一、正札附根元草摺 長唄囃子連中
曽我五郎 松緑
舞鶴 魁春
二、双蝶々曲輪日記 角力場 一幕
濡髪長五郎 幸四郎
藤屋吾妻 芝雀
山崎屋与五郎 染五郎
放駒長吉 吉右衛門
三、蝶の道行 竹本連中
助国 梅玉
小槇 福助
四、女殺油地獄 三幕
片岡仁左衛門
一世一代にて相勤め申し候
河内屋与兵衛 仁左衛門
豊嶋屋お吉 孝太郎
山本森右衛門 彌十郎
父徳兵衛 歌六
芸者小菊/母おさわ 秀太郎
豊嶋屋七左衛門 梅玉
夜の部(午後4時30分開演)
一、門出祝寿連獅子 長唄囃子連中
四代目松本金太郎 初舞台
初舞台 金太郎
染五郎
幸四郎
松緑
芝雀
友右衛門
吉右衛門
二、極付 幡随長兵衛 三幕
「公平法問諍」 大薩摩連中
幡随院長兵衛 吉右衛門
水野十郎左衛門 仁左衛門
坂田公平 歌昇
子分 極楽十三 染五郎
子分 雷重五郎 松緑
子分 出尻清兵衛 歌六
近藤登之助 東蔵
唐犬権兵衛 梅玉
女房お時 芝翫
三、梅雨小袖昔八丈 髪結新三 三幕
髪結新三 幸四郎
手代忠七 福助
下剃勝奴 染五郎
お熊 高麗蔵
家主長兵衛 彌十郎
弥太五郎源七 歌六
平成21年6月3日(水)初日 27日(土)千穐楽
昼の部(午前11時開演)
一、正札附根元草摺 長唄囃子連中
曽我五郎 松緑
舞鶴 魁春
二、双蝶々曲輪日記 角力場 一幕
濡髪長五郎 幸四郎
藤屋吾妻 芝雀
山崎屋与五郎 染五郎
放駒長吉 吉右衛門
三、蝶の道行 竹本連中
助国 梅玉
小槇 福助
四、女殺油地獄 三幕
片岡仁左衛門
一世一代にて相勤め申し候
河内屋与兵衛 仁左衛門
豊嶋屋お吉 孝太郎
山本森右衛門 彌十郎
父徳兵衛 歌六
芸者小菊/母おさわ 秀太郎
豊嶋屋七左衛門 梅玉
夜の部(午後4時30分開演)
一、門出祝寿連獅子 長唄囃子連中
四代目松本金太郎 初舞台
初舞台 金太郎
染五郎
幸四郎
松緑
芝雀
友右衛門
吉右衛門
二、極付 幡随長兵衛 三幕
「公平法問諍」 大薩摩連中
幡随院長兵衛 吉右衛門
水野十郎左衛門 仁左衛門
坂田公平 歌昇
子分 極楽十三 染五郎
子分 雷重五郎 松緑
子分 出尻清兵衛 歌六
近藤登之助 東蔵
唐犬権兵衛 梅玉
女房お時 芝翫
三、梅雨小袖昔八丈 髪結新三 三幕
髪結新三 幸四郎
手代忠七 福助
下剃勝奴 染五郎
お熊 高麗蔵
家主長兵衛 彌十郎
弥太五郎源七 歌六
|
|
|
|
コメント(8)
昼の部レポートです。
《正札附根元草摺》
『対面』で、松緑丈の曽我五郎を見たことがありますが、
『対面』が静・様式的なのに対し、
『草摺』は動・舞踊的な印象を受けました。
立役、特に荒事の力強さは、もちろんのこと、松緑丈の得意な舞踊を、
存分に見せてもらいました。
魁春丈の舞鶴は、五郎と互角の力で争う女傑です。
お姫様や傾城よりも、こうした、はつらつとした役柄や、
世話女房などの魁春丈が好きです。
《双蝶々曲輪日記 角力場》
『角力場』を見るのは4回目ですが、
過去3回は、放駒と与五郎は、1人2役でした。
さて、今回の『角力場』で感じたことは、
濡髪と放駒を、同格で、しかも同じ時代物を持ち役とする役者が
演じるのは、いかがなものか?ということです。
私の考えとしては、
濡髪がベテラン役者なら、放駒は若手役者、
同格のベテランなら、濡髪は時代物役者、放駒は和事・世話物役者、
同格でも、若手同士なら可、
と思うのです。
しかしながら、吉右衛門丈の放駒には、
いかにも、素人力士らし朴訥な雰囲気が漂い、
人気力士・濡髪を倒し、舞い上がっている様子が、伺えました。
贔屓から贈られた着物を着て、まげも大銀杏に結い直した姿は、
さすがに、カッコよく、男の色気たっぷりで、錦絵のようでした。
そんな中にも、視線だけは、茶目っけのあるところは、
吉右衛門丈のうまさだなあ、と思いました。
染五郎丈の与五郎は、つっころばしの二枚目です。
この手の役は、何度か見ていますが、その容姿とあいまって、
なかなかの大店のボンボンぶりです。
その視線のやりどころと、指先の使い方が、柔らかさを醸し出しています。
芝雀丈の吾妻は、出番は少ないのですが、
その華やかさ、可愛らしさは、ピタッとはまり、魅力満載です。
営業スマイルなんかしなくても、男がコロリとまいるような遊女で、
どこか天然系な感じがします。
存在自体が罪な女性(?)です。
平成18年6月、幸四郎丈の濡髪と、染五郎丈の放駒を見た時は、
親子競演ということもあり、何となくほのぼのしたものでした。
しかし、今回の濡髪は、始終、苦虫をかみつぶしたような表情と口跡で、
若干、違和感を感じました。
《蝶の道行》
食事の後で、しかも、場内の照明が暗かったので、少し落ちてしまいました。
梅玉丈も福助丈もキレイだった、とだけ言っておきます。
《正札附根元草摺》
『対面』で、松緑丈の曽我五郎を見たことがありますが、
『対面』が静・様式的なのに対し、
『草摺』は動・舞踊的な印象を受けました。
立役、特に荒事の力強さは、もちろんのこと、松緑丈の得意な舞踊を、
存分に見せてもらいました。
魁春丈の舞鶴は、五郎と互角の力で争う女傑です。
お姫様や傾城よりも、こうした、はつらつとした役柄や、
世話女房などの魁春丈が好きです。
《双蝶々曲輪日記 角力場》
『角力場』を見るのは4回目ですが、
過去3回は、放駒と与五郎は、1人2役でした。
さて、今回の『角力場』で感じたことは、
濡髪と放駒を、同格で、しかも同じ時代物を持ち役とする役者が
演じるのは、いかがなものか?ということです。
私の考えとしては、
濡髪がベテラン役者なら、放駒は若手役者、
同格のベテランなら、濡髪は時代物役者、放駒は和事・世話物役者、
同格でも、若手同士なら可、
と思うのです。
しかしながら、吉右衛門丈の放駒には、
いかにも、素人力士らし朴訥な雰囲気が漂い、
人気力士・濡髪を倒し、舞い上がっている様子が、伺えました。
贔屓から贈られた着物を着て、まげも大銀杏に結い直した姿は、
さすがに、カッコよく、男の色気たっぷりで、錦絵のようでした。
そんな中にも、視線だけは、茶目っけのあるところは、
吉右衛門丈のうまさだなあ、と思いました。
染五郎丈の与五郎は、つっころばしの二枚目です。
この手の役は、何度か見ていますが、その容姿とあいまって、
なかなかの大店のボンボンぶりです。
その視線のやりどころと、指先の使い方が、柔らかさを醸し出しています。
芝雀丈の吾妻は、出番は少ないのですが、
その華やかさ、可愛らしさは、ピタッとはまり、魅力満載です。
営業スマイルなんかしなくても、男がコロリとまいるような遊女で、
どこか天然系な感じがします。
存在自体が罪な女性(?)です。
平成18年6月、幸四郎丈の濡髪と、染五郎丈の放駒を見た時は、
親子競演ということもあり、何となくほのぼのしたものでした。
しかし、今回の濡髪は、始終、苦虫をかみつぶしたような表情と口跡で、
若干、違和感を感じました。
《蝶の道行》
食事の後で、しかも、場内の照明が暗かったので、少し落ちてしまいました。
梅玉丈も福助丈もキレイだった、とだけ言っておきます。
昼の部・レポートの続きです。
《女殺油地獄》
「今月、歌舞伎座で一つだけ見せてあげる」と言われたら、
迷わず、『女殺油地獄』を見ます。
私にとって、最初で最後の、仁左衛門丈の『油地獄』ですから…。
発売されたものの、あっと言う間に売り切れたポスターの
あの表情そのままの仁左衛門でした。
男の色気と、大人になり切れない子供っぽさ、複雑な心境など、
全てを出しきった舞台でした。
この与兵衛は、20歳前後なのでしょうか。
仁左衛門丈は、孝太郎丈よりも、歌六丈よりも、ずっと若く見えました。
徳庵堤茶店の場では、遊び仲間やお吉に対しては、大きな態度で、
お山の大将という感じですが、
武士という権力の前には、全くだらしないところが、笑えます。
ここからして、なりは大きくても子供だなあ、と思わせてくれました。
河内屋内の場では、お山の大将、ここに極まれり、です。
家の金を持ち出す、家族に暴力を振るう、とは、まるで現代劇です。
そして、継父・徳兵衛に対しては、憎しみの中に甘え、
母・おさわに対して、甘えの中に憎しみ、が見えてきます。
徳兵衛に対しては、
「あんたは父親なんかじゃない。俺の母親をとったヤツだ。
でも、どうして、そんな優しい目で俺を見る」。
おさわに対しては、
「俺はあんたの子だよ。でも、さびしいよ。俺より、徳兵衛が大切なのか」。
そんな叫び声が聞こえてきそうです。
おさわから勘当され、河内屋を飛びだし、花道に立った時の表情には、
怒り、寂しさ、甘え、に加え、
自分でも、どうして良いのか分からない気持ちが表れていました。
豊嶋屋油店の場で、
自分を心配して様子を見に来た両親の姿を見送り、涙ぐみますが、
両親の持参したお金が、自分の借金の返済にほど遠いことを知り、
冷やかな目つきになるところでは、ゾッとしました。
油にまみれたお吉殺しの場面は、様式美に優れた上、
「ああ、こいつは、落ちるところまで、落ちるんだな」
というやり切れない思いでいっぱいでした。
更に、「自分は、人の好意・忠告に素直になっているだろうか」と、
妙な気分で、ドキドキさせられました。
歌六丈の河内屋徳兵衛は、まさに、いぶし銀の輝きでした。
遠慮・謙虚を、絵に描いたような人物でした。
決して、気が弱く、意気地がないのではなく、
かつての主筋にあたる、おさわと与兵衛に対しては、
一歩引きつつ、大切な気持ちで接しているのだと思います。
河内屋を立派に引き継いだものの、
あの世の先代・徳兵衛に対し、「これで、いいでしょうか?」と
常に問いかけている感じです。
河内屋を飛び出した与兵衛に、先代の面影を思い出す場面は、
泣かずに見ることができませんでした。
秀太郎丈の小菊は、徳庵堤茶店の場で、少し登場するだけですが、
いかにも、営業のうまい飲み屋のおねえさんという感じでした。
「遊女に誠なし、っていう言葉知らんの?そんなに熱くならないでよ」
と、与兵衛に視線で語りかけています。
秀太郎丈のもう一役、おさわも、また絶品でした。
与兵衛の放蕩に、時に厳しく接していたと思うですが、
最後は、「不憫な子や」と、甘やかしてしまったのでしょうか。
孝太郎丈のお吉が、しっかり者の人妻を、きっちり勤めていました。
徳庵堤茶店の場では、困った人を放っておけない人のよさと、
面倒事をちゃきちゃき片づけてしまう、段取りのよさが、見て取れます。
更に、人妻としての色気が、猛烈に発散していて、
夫・七左衛門が、心配するのが、納得できます。
梅玉丈の豊嶋屋七左衛門は、いかにも実直な商人という感じで、
しかも、女房・お吉に、心底、ほれている様子が分かります。
私は、歌舞伎で、『油地獄』を見るのは、2度目ですが、
二幕目 河内屋内の場が、非常に素晴らしいと思いました。
そして、当代一流の舞台は、お金や時間を何としてもひねり出し、
見なければいけないと、改めて思いました
《女殺油地獄》
「今月、歌舞伎座で一つだけ見せてあげる」と言われたら、
迷わず、『女殺油地獄』を見ます。
私にとって、最初で最後の、仁左衛門丈の『油地獄』ですから…。
発売されたものの、あっと言う間に売り切れたポスターの
あの表情そのままの仁左衛門でした。
男の色気と、大人になり切れない子供っぽさ、複雑な心境など、
全てを出しきった舞台でした。
この与兵衛は、20歳前後なのでしょうか。
仁左衛門丈は、孝太郎丈よりも、歌六丈よりも、ずっと若く見えました。
徳庵堤茶店の場では、遊び仲間やお吉に対しては、大きな態度で、
お山の大将という感じですが、
武士という権力の前には、全くだらしないところが、笑えます。
ここからして、なりは大きくても子供だなあ、と思わせてくれました。
河内屋内の場では、お山の大将、ここに極まれり、です。
家の金を持ち出す、家族に暴力を振るう、とは、まるで現代劇です。
そして、継父・徳兵衛に対しては、憎しみの中に甘え、
母・おさわに対して、甘えの中に憎しみ、が見えてきます。
徳兵衛に対しては、
「あんたは父親なんかじゃない。俺の母親をとったヤツだ。
でも、どうして、そんな優しい目で俺を見る」。
おさわに対しては、
「俺はあんたの子だよ。でも、さびしいよ。俺より、徳兵衛が大切なのか」。
そんな叫び声が聞こえてきそうです。
おさわから勘当され、河内屋を飛びだし、花道に立った時の表情には、
怒り、寂しさ、甘え、に加え、
自分でも、どうして良いのか分からない気持ちが表れていました。
豊嶋屋油店の場で、
自分を心配して様子を見に来た両親の姿を見送り、涙ぐみますが、
両親の持参したお金が、自分の借金の返済にほど遠いことを知り、
冷やかな目つきになるところでは、ゾッとしました。
油にまみれたお吉殺しの場面は、様式美に優れた上、
「ああ、こいつは、落ちるところまで、落ちるんだな」
というやり切れない思いでいっぱいでした。
更に、「自分は、人の好意・忠告に素直になっているだろうか」と、
妙な気分で、ドキドキさせられました。
歌六丈の河内屋徳兵衛は、まさに、いぶし銀の輝きでした。
遠慮・謙虚を、絵に描いたような人物でした。
決して、気が弱く、意気地がないのではなく、
かつての主筋にあたる、おさわと与兵衛に対しては、
一歩引きつつ、大切な気持ちで接しているのだと思います。
河内屋を立派に引き継いだものの、
あの世の先代・徳兵衛に対し、「これで、いいでしょうか?」と
常に問いかけている感じです。
河内屋を飛び出した与兵衛に、先代の面影を思い出す場面は、
泣かずに見ることができませんでした。
秀太郎丈の小菊は、徳庵堤茶店の場で、少し登場するだけですが、
いかにも、営業のうまい飲み屋のおねえさんという感じでした。
「遊女に誠なし、っていう言葉知らんの?そんなに熱くならないでよ」
と、与兵衛に視線で語りかけています。
秀太郎丈のもう一役、おさわも、また絶品でした。
与兵衛の放蕩に、時に厳しく接していたと思うですが、
最後は、「不憫な子や」と、甘やかしてしまったのでしょうか。
孝太郎丈のお吉が、しっかり者の人妻を、きっちり勤めていました。
徳庵堤茶店の場では、困った人を放っておけない人のよさと、
面倒事をちゃきちゃき片づけてしまう、段取りのよさが、見て取れます。
更に、人妻としての色気が、猛烈に発散していて、
夫・七左衛門が、心配するのが、納得できます。
梅玉丈の豊嶋屋七左衛門は、いかにも実直な商人という感じで、
しかも、女房・お吉に、心底、ほれている様子が分かります。
私は、歌舞伎で、『油地獄』を見るのは、2度目ですが、
二幕目 河内屋内の場が、非常に素晴らしいと思いました。
そして、当代一流の舞台は、お金や時間を何としてもひねり出し、
見なければいけないと、改めて思いました
夜の部・レポートです。
《門出祝寿連獅子》
四代目松本金太郎丈の初舞台です。
梅玉丈の大名が名乗りを上げた後、
花道を幸四郎丈・染五郎丈らとともに、金太郎丈が入ってきました。
三階B席の下手側からは、表情は全く見えませんでしたが、
幸四郎丈も染五郎丈も、喜色満面だったことでしょう。
大名と左近一家が、天竺清涼山の獅子の話をした後、
一同が並び、お祝いの口上です。
下手側から、梅玉丈・魁春丈・福助丈・染五郎丈・金太郎丈・
幸四郎丈・芝雀丈・松緑丈・吉右衛門丈が並びました。
さすがに、茶化した口上を述べる人は誰もいなくて、
印象に残った口上は、下記の二つくらいです。
魁春丈
「金太郎さんが大きくなったら、是非、女房役を勤めたいと思います」
幸四郎丈
「まだ小そうございますが、20〜30年後には、
ひとかどの役者になっていると思いますので、
それまで、皆様、長生きをして見守ってください」
金太郎丈には、錦吾丈が後見として、ピッタリついていました。
金太郎丈が、途中、飽きてきたのか、ごそごそ動いたり、
横を向いたりして、錦吾丈も、大変だったと思います。
口上が終わると、一同がセリとともに、舞台下に去っていきました。
そして、友右衛門丈と高麗蔵丈の間狂言の後、
セリから高麗屋三代が登場し、連獅子が始まりました。
主役の金太郎丈に合わせて舞っているので、
連獅子の勇猛果敢さは、それほど、感じられなかったのですが、
客席からは、拍手の嵐でした。
《極付 幡随長兵衛》
昼の部で見た、愛嬌のある放駒も悪くないのですが、
長兵衛のような男の中の男が、吉右衛門丈には、よく似合います。
序幕 村山座舞台の場で、傍若無人の振る舞いで、
芝居の邪魔をする旗本奴に対し、身分をわきまえ、
下手下手に出ていますが、優しそうな目の奥には一つの決心を感じ、
全身には闘志がみなぎっています。
旗本奴を懲らしめ、「名は幡随院だが、仏になるには、まだ早い!」
と決めるところでは、痛快さの中に、本当の優しさが見えます。
二幕目 花川戸長兵衛内の場では、水野屋敷からの酒宴の招きに応じ、
殺されると分かっていながら、行かなければならないことを独白する
場面に、人物としての大きさを感じました。
「人は一代、名は末代」の台詞には、
まさに、名誉を守るために死ななければならない美学を感じました。
三幕目 第一場 水野邸座敷の場でも、水野らを前に、
死を覚悟した緊張感の中、やはり、下手下手に出ていますが、
風呂を勧められた時、運命を悟ったように、
ふっと、その緊張感が消えたように見えました。
三幕目 第二場 水野邸湯殿の場は、決して派手な立ち廻りでは
ないのですが、今まで押さえていたものを一気に爆発させたような
躍動感を覚えました。
芝翫丈のお時は、死ぬと分かっていながら、
夫・長兵衛の着替えの手伝いをする場面が、絶品でした。
帯を渡すところでの、ちょっとした手つきや、交わす視線が、
「ああ、この夫婦は、何も言わなくても通じ合っているのだなあ」と、
感じさせてくれます。
武家の妻とは異なる潔さが、実に、心地よく、
言葉以上に、雄弁なものを見たような気がしました。
そして、着物のしつけ糸をとる場面では、そのタイミングは絶妙で、
情感あふれ、これ以上のものはない、と思いました。
玉太郎丈の長松は、生意気で、可愛いさかりの子供を、
等身大で勤めていました。
水野屋敷へ向かう長兵衛に、「おとっちゃん、早くお帰り」
と言う場面では、お約束通り、ドッと泣けました。
仁左衛門丈の水野十郎左衛門は、大身の旗本という気品がありました。
やっていることは、卑怯極まりないのですが、
虚無感が漂い、すごい悪者には、見えませんでした。
「オレには、こういう生き方しかないのさ」と、
破滅に向かって突き進む、滅びの美学、又は悪の美学を感じました。
仁左衛門丈は、今月は二本とも悪役ですが、
子供がそのまま大人になったわがまま野郎ではなく、
どこか茶目っ気を感じます。
私が女性だったら、
「もう、与兵衛さんったら、しょうがないわねぇ」とか、
「まあ、お殿様、お戯れが過ぎますわよ」と言って、
なすがままになっているかもしれません。
《門出祝寿連獅子》
四代目松本金太郎丈の初舞台です。
梅玉丈の大名が名乗りを上げた後、
花道を幸四郎丈・染五郎丈らとともに、金太郎丈が入ってきました。
三階B席の下手側からは、表情は全く見えませんでしたが、
幸四郎丈も染五郎丈も、喜色満面だったことでしょう。
大名と左近一家が、天竺清涼山の獅子の話をした後、
一同が並び、お祝いの口上です。
下手側から、梅玉丈・魁春丈・福助丈・染五郎丈・金太郎丈・
幸四郎丈・芝雀丈・松緑丈・吉右衛門丈が並びました。
さすがに、茶化した口上を述べる人は誰もいなくて、
印象に残った口上は、下記の二つくらいです。
魁春丈
「金太郎さんが大きくなったら、是非、女房役を勤めたいと思います」
幸四郎丈
「まだ小そうございますが、20〜30年後には、
ひとかどの役者になっていると思いますので、
それまで、皆様、長生きをして見守ってください」
金太郎丈には、錦吾丈が後見として、ピッタリついていました。
金太郎丈が、途中、飽きてきたのか、ごそごそ動いたり、
横を向いたりして、錦吾丈も、大変だったと思います。
口上が終わると、一同がセリとともに、舞台下に去っていきました。
そして、友右衛門丈と高麗蔵丈の間狂言の後、
セリから高麗屋三代が登場し、連獅子が始まりました。
主役の金太郎丈に合わせて舞っているので、
連獅子の勇猛果敢さは、それほど、感じられなかったのですが、
客席からは、拍手の嵐でした。
《極付 幡随長兵衛》
昼の部で見た、愛嬌のある放駒も悪くないのですが、
長兵衛のような男の中の男が、吉右衛門丈には、よく似合います。
序幕 村山座舞台の場で、傍若無人の振る舞いで、
芝居の邪魔をする旗本奴に対し、身分をわきまえ、
下手下手に出ていますが、優しそうな目の奥には一つの決心を感じ、
全身には闘志がみなぎっています。
旗本奴を懲らしめ、「名は幡随院だが、仏になるには、まだ早い!」
と決めるところでは、痛快さの中に、本当の優しさが見えます。
二幕目 花川戸長兵衛内の場では、水野屋敷からの酒宴の招きに応じ、
殺されると分かっていながら、行かなければならないことを独白する
場面に、人物としての大きさを感じました。
「人は一代、名は末代」の台詞には、
まさに、名誉を守るために死ななければならない美学を感じました。
三幕目 第一場 水野邸座敷の場でも、水野らを前に、
死を覚悟した緊張感の中、やはり、下手下手に出ていますが、
風呂を勧められた時、運命を悟ったように、
ふっと、その緊張感が消えたように見えました。
三幕目 第二場 水野邸湯殿の場は、決して派手な立ち廻りでは
ないのですが、今まで押さえていたものを一気に爆発させたような
躍動感を覚えました。
芝翫丈のお時は、死ぬと分かっていながら、
夫・長兵衛の着替えの手伝いをする場面が、絶品でした。
帯を渡すところでの、ちょっとした手つきや、交わす視線が、
「ああ、この夫婦は、何も言わなくても通じ合っているのだなあ」と、
感じさせてくれます。
武家の妻とは異なる潔さが、実に、心地よく、
言葉以上に、雄弁なものを見たような気がしました。
そして、着物のしつけ糸をとる場面では、そのタイミングは絶妙で、
情感あふれ、これ以上のものはない、と思いました。
玉太郎丈の長松は、生意気で、可愛いさかりの子供を、
等身大で勤めていました。
水野屋敷へ向かう長兵衛に、「おとっちゃん、早くお帰り」
と言う場面では、お約束通り、ドッと泣けました。
仁左衛門丈の水野十郎左衛門は、大身の旗本という気品がありました。
やっていることは、卑怯極まりないのですが、
虚無感が漂い、すごい悪者には、見えませんでした。
「オレには、こういう生き方しかないのさ」と、
破滅に向かって突き進む、滅びの美学、又は悪の美学を感じました。
仁左衛門丈は、今月は二本とも悪役ですが、
子供がそのまま大人になったわがまま野郎ではなく、
どこか茶目っ気を感じます。
私が女性だったら、
「もう、与兵衛さんったら、しょうがないわねぇ」とか、
「まあ、お殿様、お戯れが過ぎますわよ」と言って、
なすがままになっているかもしれません。
夜の部・レポートの続きです。
《梅雨小袖昔八丈 髪結新三》
歌六丈の弥太五郎源七が、実にいい味を出していました。
忠七を助ける場面、新三の住まいに乗り込む場面では、
実に恰幅が良く、「この人に任せておけば、安心だ」と 思わせてくれます。
しかし、新三にやり込められた後、善八に、
「だから、俺は嫌だと言ったんだ」と言う場面では、
身体が一回り小さくなったように見え、 また、急に年寄り臭くも見えました。
閻魔橋の場では、すっかり落ちぶれたものの、
新三をやっつけるために、全てをかけたメラメラとした
最後の執念を感じました。
萬次郎丈の大家のおかみさんは、出番は少ないのですが、
この人ならではのうまさでした。
下から見上げるような視線には、
へりくだりながらも、何事も、瞬時に、
しっかり値踏みしているようでした。
大家が多少荒っぽいことをして稼ぐのなら、
その後をしっかりならして、ペンペン草もはえないようにするような
細やかさ(?)が、チラチラ見えるおかみさんでした。
幸四郎丈の新三には、江戸っ子の切れのよさが 感じられませんでした。
あんなに、モゴモゴしゃべる新三は、
一体、どこの出身なのか?と思いました。
《梅雨小袖昔八丈 髪結新三》
歌六丈の弥太五郎源七が、実にいい味を出していました。
忠七を助ける場面、新三の住まいに乗り込む場面では、
実に恰幅が良く、「この人に任せておけば、安心だ」と 思わせてくれます。
しかし、新三にやり込められた後、善八に、
「だから、俺は嫌だと言ったんだ」と言う場面では、
身体が一回り小さくなったように見え、 また、急に年寄り臭くも見えました。
閻魔橋の場では、すっかり落ちぶれたものの、
新三をやっつけるために、全てをかけたメラメラとした
最後の執念を感じました。
萬次郎丈の大家のおかみさんは、出番は少ないのですが、
この人ならではのうまさでした。
下から見上げるような視線には、
へりくだりながらも、何事も、瞬時に、
しっかり値踏みしているようでした。
大家が多少荒っぽいことをして稼ぐのなら、
その後をしっかりならして、ペンペン草もはえないようにするような
細やかさ(?)が、チラチラ見えるおかみさんでした。
幸四郎丈の新三には、江戸っ子の切れのよさが 感じられませんでした。
あんなに、モゴモゴしゃべる新三は、
一体、どこの出身なのか?と思いました。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
歌舞伎愛好会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
歌舞伎愛好会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37833人
- 2位
- 酒好き
- 170657人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89521人
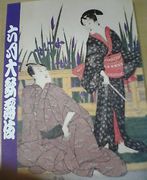





![[dir] 日本の伝統芸能](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/67/58/266758_56s.jpg)

![[dir] 邦楽](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/67/61/266761_218s.jpg)















