八月納涼大歌舞伎
平成20年8月9日(土)初日 27日(水)千穐楽
第一部(午前11時開演)
一、女暫
巴御前 福助
手塚太郎光盛 三津五郎
轟坊震斎 勘太郎
女鯰若菜 実は樋口妹若菜 七之助
蒲冠者範頼 彌十郎
舞台番 勘三郎
二、三人連獅子
親獅子 橋之助
子獅子 国生
母獅子 扇雀
三、眠駱駝物語 らくだ
紙屑買久六 勘三郎
駱駝の馬太郎 亀蔵
手斧目半次 三津五郎
第二部(午後2時45分開演)
一、つばくろは帰る
大工文五郎 三津五郎
八重菊おしの 扇雀
弟子三次郎 勘太郎
舞妓みつ 七之助
安之助 小吉
弟子鉄之助 巳之助
蒲団屋万蔵 彌十郎
祗園芸妓君香 福助
二、大江山酒呑童子
酒呑童子 勘三郎
濯ぎ女 若狭 福助
同 なでしこ 七之助
同 わらび 松也
卜部季武 巳之助
碓井貞光 新吾
坂田公時 勘太郎
渡辺綱 彌十郎
平井保昌 橋之助
源頼光 扇雀
第三部(午後6時15分開演)
一、新歌舞伎十八番の内 紅葉狩
更科姫 実は戸隠山の鬼女 勘太郎
山神 巳之助
従者右源太 高麗蔵
同 左源太 亀蔵
侍女菊野 鶴松
腰元岩橋 市蔵
局田毎 家橘
余吾将軍平維茂 橋之助
二、野田版 愛陀姫
濃姫 勘三郎
愛陀姫 七之助
木村駄目助座衛門 橋之助
鈴木主水之助 勘太郎
多々木斬蔵 亀蔵
斎藤道三 彌十郎
祈祷師 荏原 扇雀
同 細毛 福助
織田信秀 三津五郎
平成20年8月9日(土)初日 27日(水)千穐楽
第一部(午前11時開演)
一、女暫
巴御前 福助
手塚太郎光盛 三津五郎
轟坊震斎 勘太郎
女鯰若菜 実は樋口妹若菜 七之助
蒲冠者範頼 彌十郎
舞台番 勘三郎
二、三人連獅子
親獅子 橋之助
子獅子 国生
母獅子 扇雀
三、眠駱駝物語 らくだ
紙屑買久六 勘三郎
駱駝の馬太郎 亀蔵
手斧目半次 三津五郎
第二部(午後2時45分開演)
一、つばくろは帰る
大工文五郎 三津五郎
八重菊おしの 扇雀
弟子三次郎 勘太郎
舞妓みつ 七之助
安之助 小吉
弟子鉄之助 巳之助
蒲団屋万蔵 彌十郎
祗園芸妓君香 福助
二、大江山酒呑童子
酒呑童子 勘三郎
濯ぎ女 若狭 福助
同 なでしこ 七之助
同 わらび 松也
卜部季武 巳之助
碓井貞光 新吾
坂田公時 勘太郎
渡辺綱 彌十郎
平井保昌 橋之助
源頼光 扇雀
第三部(午後6時15分開演)
一、新歌舞伎十八番の内 紅葉狩
更科姫 実は戸隠山の鬼女 勘太郎
山神 巳之助
従者右源太 高麗蔵
同 左源太 亀蔵
侍女菊野 鶴松
腰元岩橋 市蔵
局田毎 家橘
余吾将軍平維茂 橋之助
二、野田版 愛陀姫
濃姫 勘三郎
愛陀姫 七之助
木村駄目助座衛門 橋之助
鈴木主水之助 勘太郎
多々木斬蔵 亀蔵
斎藤道三 彌十郎
祈祷師 荏原 扇雀
同 細毛 福助
織田信秀 三津五郎
|
|
|
|
コメント(10)
納涼歌舞伎の初日に、第一部と第二部を見ました。
《女暫》
『女暫』は、六世歌右衛門が二度、お父様の芝翫丈が三度、演っています。
私は、六世歌右衛門の舞台をナマで見たことはありませんが、
巴御前の福助丈を見ていると、化粧・動作・口跡などから、
六世歌右衛門を強く意識しているような気がしました。
福助丈の本分が特に生きているところは、震斎・若菜・舞台番などとの
コミカルなやり取りの場面でした。
最後に、花道で六法を踏むところでは、冠の紐がゆるんでしまいましたが、
アドリブをきかせ、恥ずかしそうに引っ込んでいきました。
舞台番の勘三郎丈は、演技なのか?地なのか?
という感じで、笑わせてくれました。
昨年5月の三津五郎丈の時も、そうでしたが、
この役は、最後に出てきて、オイシイところを引っさらっていきます。
うっかりすると、劇中の役者さんの記憶が、吹っ飛びそうです。
さて、範頼方で、印象に残ったのは、まず、轟坊震斎の勘太郎丈です。
悪いヤツの手下なのに、どこか三枚目の震斎を、口跡よく、
舞踊の要素を生かした動作で、演じていました。
腹出しの一人・猪俣平六の亀蔵丈は、朗々と響き渡る口跡で、
憎々しげさを、よく表していました。
親分格の成田五郎の市蔵丈よりも、強そうで、迫力がありました。
木曽方では、木曽次郎の松也丈の眉目秀麗さが、印象的でした。
納涼歌舞伎って、若手の勉強会みたいな面もありますから、
思い切って、清水冠者義高を演らせても良かったのでは?と思いました。
手塚太郎光盛の三津五郎丈は、颯爽として、しかも初々しいしく見えました。
芝のぶ丈が、後見として、花道で、福助丈に、お茶を持ってきていました。
素顔に近い芝のぶ丈の裃姿も、素敵です。
《三人連獅子》
松羽目物かと思っていたら、全然、違いました。
幕が開くと、石橋(しゃっきょう)という石舞台のようなものが、
デンと構えていました。
そこへお公家さん風の衣裳で現れた、獅子の精の親子三人の一家団欒が、
舞によって見られました。
後シテでは、獅子の姿で登場しますが、隈取はしていませんでした。
『連獅子』ですと、親が子を谷底へ落とし、試練を与える面が強いのですが、
この『三人連獅子』は、試練を受ける子を思う母親の愛情が強く感じられます。
母獅子の扇雀丈は、慈愛に満ちた雰囲気が出ていました。
ただ、親獅子の橋之助丈の、子を見守る姿勢が、やや強いように感じられ、
扇雀丈の存在の意義が薄れてしまったようです。
まあ、実の息子との共演なので、親として心配なのでしょうか。
《らくだ》
何と言っても、馬太郎の死体を演じた亀蔵丈が最高です。
見事な死体っぷり(?)です。
死体なので、セリフは一言もありませんが、
?布団の上に横たわっている、?久六の背に担がれている、
?半次に抱きかかえられ踊らされる、
の、どの場面でも、笑わせてくれます。
遊び人の半次と小心者の久六のやり取りは、
三津五郎丈と勘三郎丈のイキの合ったコンビで、ツボをはずしていません。
後半には、立場が逆転するのですが、ネタバレになるので、
あとは、舞台をご覧ください。
松也丈が、半次の妹・おやすとして登場します。
最近は二枚目役の多い松也丈も、今月は女形で三役です。
説明くさくならずに、長屋の様子や人間関係が、
松也丈のセリフから、うかがい知ることができました。
市蔵丈と彌十郎丈は、抜け目のない家主夫婦を好演でした。
彌十郎丈の女形は、『伊勢音頭恋寝刃』のお鹿くらいしか記憶にありませんが、
なかなか味のある女房でした。
《女暫》
『女暫』は、六世歌右衛門が二度、お父様の芝翫丈が三度、演っています。
私は、六世歌右衛門の舞台をナマで見たことはありませんが、
巴御前の福助丈を見ていると、化粧・動作・口跡などから、
六世歌右衛門を強く意識しているような気がしました。
福助丈の本分が特に生きているところは、震斎・若菜・舞台番などとの
コミカルなやり取りの場面でした。
最後に、花道で六法を踏むところでは、冠の紐がゆるんでしまいましたが、
アドリブをきかせ、恥ずかしそうに引っ込んでいきました。
舞台番の勘三郎丈は、演技なのか?地なのか?
という感じで、笑わせてくれました。
昨年5月の三津五郎丈の時も、そうでしたが、
この役は、最後に出てきて、オイシイところを引っさらっていきます。
うっかりすると、劇中の役者さんの記憶が、吹っ飛びそうです。
さて、範頼方で、印象に残ったのは、まず、轟坊震斎の勘太郎丈です。
悪いヤツの手下なのに、どこか三枚目の震斎を、口跡よく、
舞踊の要素を生かした動作で、演じていました。
腹出しの一人・猪俣平六の亀蔵丈は、朗々と響き渡る口跡で、
憎々しげさを、よく表していました。
親分格の成田五郎の市蔵丈よりも、強そうで、迫力がありました。
木曽方では、木曽次郎の松也丈の眉目秀麗さが、印象的でした。
納涼歌舞伎って、若手の勉強会みたいな面もありますから、
思い切って、清水冠者義高を演らせても良かったのでは?と思いました。
手塚太郎光盛の三津五郎丈は、颯爽として、しかも初々しいしく見えました。
芝のぶ丈が、後見として、花道で、福助丈に、お茶を持ってきていました。
素顔に近い芝のぶ丈の裃姿も、素敵です。
《三人連獅子》
松羽目物かと思っていたら、全然、違いました。
幕が開くと、石橋(しゃっきょう)という石舞台のようなものが、
デンと構えていました。
そこへお公家さん風の衣裳で現れた、獅子の精の親子三人の一家団欒が、
舞によって見られました。
後シテでは、獅子の姿で登場しますが、隈取はしていませんでした。
『連獅子』ですと、親が子を谷底へ落とし、試練を与える面が強いのですが、
この『三人連獅子』は、試練を受ける子を思う母親の愛情が強く感じられます。
母獅子の扇雀丈は、慈愛に満ちた雰囲気が出ていました。
ただ、親獅子の橋之助丈の、子を見守る姿勢が、やや強いように感じられ、
扇雀丈の存在の意義が薄れてしまったようです。
まあ、実の息子との共演なので、親として心配なのでしょうか。
《らくだ》
何と言っても、馬太郎の死体を演じた亀蔵丈が最高です。
見事な死体っぷり(?)です。
死体なので、セリフは一言もありませんが、
?布団の上に横たわっている、?久六の背に担がれている、
?半次に抱きかかえられ踊らされる、
の、どの場面でも、笑わせてくれます。
遊び人の半次と小心者の久六のやり取りは、
三津五郎丈と勘三郎丈のイキの合ったコンビで、ツボをはずしていません。
後半には、立場が逆転するのですが、ネタバレになるので、
あとは、舞台をご覧ください。
松也丈が、半次の妹・おやすとして登場します。
最近は二枚目役の多い松也丈も、今月は女形で三役です。
説明くさくならずに、長屋の様子や人間関係が、
松也丈のセリフから、うかがい知ることができました。
市蔵丈と彌十郎丈は、抜け目のない家主夫婦を好演でした。
彌十郎丈の女形は、『伊勢音頭恋寝刃』のお鹿くらいしか記憶にありませんが、
なかなか味のある女房でした。
第二部の感想です。
《つばくろは帰る》
文五郎の三津五郎丈は、義理人情に厚い、江戸の大工という感じが、
よく表れていました。
安之助という子供に対し、上から見下ろすのではなく、
我が子のようにいつくしむ姿に感動します。
また、弟子たちに対しては、厳しい親方であり、面倒見のよい兄貴でもあります。
今、他人のために、こうまで懸命になり、熱くなる人は、いないでしょう。
時代が違う、と言ってしまえば、それまでですが、一服の清涼剤のような、
すがすがしさを、三津五郎丈は、見せてくれました。
安之助の小吉丈は、自然体で、のびのび演っていたように見えました。
宿で、母を思いながら、子守歌を歌う場面では、こちらまで泣かされました。
まだ11歳ですが、これからが楽しみな役者さんです。
泉下の祖父・吉弥丈も、さぞ喜んでいるのではないでしょうか。
三次郎の勘太郎丈は、威勢のいい江戸の若者と、
舞妓・みつに、ほのかな想いを寄せる青年、という両面を、
よく勤めていました。
こういう職人は、将来、女房に対し、
決して、優しい言葉の一つもかけないのでしょうが、
命に代えても、守り抜くと思います。
そんなところまで、勝手に想像していました。
鉄之助の巳之助丈は、三次郎の弟分という感じが、よく出ていて、
勘太郎丈・小吉丈との掛け合いも、イキが合っているようでした。
福助丈の、花街の人々への義理と、我が子への愛情との板ばさみに苦しむ
芸妓・君香は、なかなか良かったと思います。
最初は、人生を、投げたような君香が、
安之助と文五郎の存在によって、人としての温かみが甦ってきたかのようでした。
七之助丈は、あのまま、祇園を歩いても、
舞妓で通用するような可愛らしさでした。
どこか人形を思わせるような役が似合います。
《大江山酒呑童子》
舞台装置が、斬新な感じでした。
前半の頼光・平井保昌(橋之助)・四天王の扮装は、
勧進帳の義経一行そのものでした。
そして、後半の酒呑童子と頼光らとの立ち回りは、
『土蜘』を思わせるところがありました。
演目自体は、あまり面白く感じなかったのですが、
鬼の本性を顕した酒呑童子の勘三郎丈は、見ごたえがありました。
《つばくろは帰る》
文五郎の三津五郎丈は、義理人情に厚い、江戸の大工という感じが、
よく表れていました。
安之助という子供に対し、上から見下ろすのではなく、
我が子のようにいつくしむ姿に感動します。
また、弟子たちに対しては、厳しい親方であり、面倒見のよい兄貴でもあります。
今、他人のために、こうまで懸命になり、熱くなる人は、いないでしょう。
時代が違う、と言ってしまえば、それまでですが、一服の清涼剤のような、
すがすがしさを、三津五郎丈は、見せてくれました。
安之助の小吉丈は、自然体で、のびのび演っていたように見えました。
宿で、母を思いながら、子守歌を歌う場面では、こちらまで泣かされました。
まだ11歳ですが、これからが楽しみな役者さんです。
泉下の祖父・吉弥丈も、さぞ喜んでいるのではないでしょうか。
三次郎の勘太郎丈は、威勢のいい江戸の若者と、
舞妓・みつに、ほのかな想いを寄せる青年、という両面を、
よく勤めていました。
こういう職人は、将来、女房に対し、
決して、優しい言葉の一つもかけないのでしょうが、
命に代えても、守り抜くと思います。
そんなところまで、勝手に想像していました。
鉄之助の巳之助丈は、三次郎の弟分という感じが、よく出ていて、
勘太郎丈・小吉丈との掛け合いも、イキが合っているようでした。
福助丈の、花街の人々への義理と、我が子への愛情との板ばさみに苦しむ
芸妓・君香は、なかなか良かったと思います。
最初は、人生を、投げたような君香が、
安之助と文五郎の存在によって、人としての温かみが甦ってきたかのようでした。
七之助丈は、あのまま、祇園を歩いても、
舞妓で通用するような可愛らしさでした。
どこか人形を思わせるような役が似合います。
《大江山酒呑童子》
舞台装置が、斬新な感じでした。
前半の頼光・平井保昌(橋之助)・四天王の扮装は、
勧進帳の義経一行そのものでした。
そして、後半の酒呑童子と頼光らとの立ち回りは、
『土蜘』を思わせるところがありました。
演目自体は、あまり面白く感じなかったのですが、
鬼の本性を顕した酒呑童子の勘三郎丈は、見ごたえがありました。
10日に、第三部を見てきました。
《紅葉狩》
更科姫実は戸隠山の鬼女の勘太郎丈が、立派に舞台を勤めていました。
大勢の侍女に囲まれた、身分高き姫君としての気品、
平維茂を誘惑するかのような、ちょっとした色気、
艶やかな舞いの中に見られる妖気、
など、女性としての心の移り変わりや、
魔物の片鱗をうかがわせる雰囲気が、よかったと思います。
鬼の形相となって、床を踏み鳴らし、去っていく場面では、
“鬼女”ですから、完全な立役ではなく、
女性らしい、ほのかな香りを残していました。
テーマは違うのですが、
愛する男性に対する、嫉妬・怒り・悲しみの念を持った女性を
過剰に表現すると、あんな感じなのでしょうか。
後半の鬼女としての立ち回りも、もちろん、素晴らしかったのですが、
前半が、特に印象に残りました。
更科姫に従う侍女も、なかなかよかったです。
局田毎の家橘丈が、勘太郎丈と舞う場面では、
黒と赤、影と光、平面的で地味な美しさと立体的で目を引く美しさ、
と対をなしていました。
派手さはないのですが、内面からにじみ出る、やんごとなき雰囲気に、
この人の血筋を感じました。
侍女・野菊の鶴松丈は、きりっとして、お行儀よく、
舞いでも、他の役者さんにも負けない可愛らしさ、艶やかさがありました。
中村屋さんを支える立派な役者さんになるでしょう。
山神の巳之助丈は、舞踊の家元の御曹司だなあ、という安定感がありました。
平維茂の橋之助丈は、いかにも都からやって来た武将、という男っぷりでした。
《野田版 愛陀姫》
私は、オペラを見たことがありません。
『アイーダ』は、粗筋を、サッと読んだだけです。
『愛陀姫』については、ストーリー以外に、
何をオペラから取り入れたかも、知りません。
オペラを全く見たことがない人と、少しでも知っているの人とでは、
『愛陀姫』に対する感想は、異なるのではないでしょうか?
第一に感じたことは、他の新作歌舞伎同様、非常にセリフが多いことです。
特に、心の中で思っていることや、様々な状況を、
全て、セリフで語ることに、斬新さを感じました。
独白している役者さん以外の人々の動きを全て止めたり、
あるいは、ゆっくりとした動作にすることによって、
見得と同じような効果が感じられました。
第二に、舞台装置が、前衛芸術を思わせるものが目立ちました。
背景は、かなり簡略化した中に、幾何学的な模様や、
仏教や宇宙をイメージしたのかな、と思うものがありました。
野田秀樹さん演出の舞台は、歌舞伎の『鼠小僧』『研辰の討たれ』しか、
見ていません。
もしかしたら、『愛陀姫』は、野田さんの色が、最も濃い舞台なのかな、
とも思いました。
濃姫(勘三郎丈)。
愛する者をわが手に得ようとする執念が、怖かったです。
愛陀姫(七之助丈)。
見ていて、痛々しい感じでした。
アイーダも、こんなキャラクターなのでしょうか。
木村駄目助座衛門(橋之助丈)。
忠義と愛情との板ばさみになる悲劇の武将が、ピッタリでした。
織田信秀(三津五郎丈)。
権謀術数に富んだ武将、威厳ある一国の主を好演でした。
祈祷師・細毛(福助丈)。
面白かったのですが、やや、テンションが高かったようです。
祈祷師・荏原(扇雀丈)。
インチキ臭さの中に、人を信用させてしまう厳かさが、垣間見えました。
多々木斬蔵(亀蔵丈)。
腹黒そうですが、実は単純な男。
なくてはならぬ脇役でしょうか。
『愛陀姫』を再演するのであれば、下記のような配役は、いかがでしょうか。
愛陀姫を勘太郎丈。
濃姫を七之助丈。
勘三郎丈は一歩引いて、他の役。例えば、祈祷師。
上演時間は、途中だれることなく、ちょうどいいものでした。
私は、半分も理解していませんが、画期的な作品だと思います。
《紅葉狩》
更科姫実は戸隠山の鬼女の勘太郎丈が、立派に舞台を勤めていました。
大勢の侍女に囲まれた、身分高き姫君としての気品、
平維茂を誘惑するかのような、ちょっとした色気、
艶やかな舞いの中に見られる妖気、
など、女性としての心の移り変わりや、
魔物の片鱗をうかがわせる雰囲気が、よかったと思います。
鬼の形相となって、床を踏み鳴らし、去っていく場面では、
“鬼女”ですから、完全な立役ではなく、
女性らしい、ほのかな香りを残していました。
テーマは違うのですが、
愛する男性に対する、嫉妬・怒り・悲しみの念を持った女性を
過剰に表現すると、あんな感じなのでしょうか。
後半の鬼女としての立ち回りも、もちろん、素晴らしかったのですが、
前半が、特に印象に残りました。
更科姫に従う侍女も、なかなかよかったです。
局田毎の家橘丈が、勘太郎丈と舞う場面では、
黒と赤、影と光、平面的で地味な美しさと立体的で目を引く美しさ、
と対をなしていました。
派手さはないのですが、内面からにじみ出る、やんごとなき雰囲気に、
この人の血筋を感じました。
侍女・野菊の鶴松丈は、きりっとして、お行儀よく、
舞いでも、他の役者さんにも負けない可愛らしさ、艶やかさがありました。
中村屋さんを支える立派な役者さんになるでしょう。
山神の巳之助丈は、舞踊の家元の御曹司だなあ、という安定感がありました。
平維茂の橋之助丈は、いかにも都からやって来た武将、という男っぷりでした。
《野田版 愛陀姫》
私は、オペラを見たことがありません。
『アイーダ』は、粗筋を、サッと読んだだけです。
『愛陀姫』については、ストーリー以外に、
何をオペラから取り入れたかも、知りません。
オペラを全く見たことがない人と、少しでも知っているの人とでは、
『愛陀姫』に対する感想は、異なるのではないでしょうか?
第一に感じたことは、他の新作歌舞伎同様、非常にセリフが多いことです。
特に、心の中で思っていることや、様々な状況を、
全て、セリフで語ることに、斬新さを感じました。
独白している役者さん以外の人々の動きを全て止めたり、
あるいは、ゆっくりとした動作にすることによって、
見得と同じような効果が感じられました。
第二に、舞台装置が、前衛芸術を思わせるものが目立ちました。
背景は、かなり簡略化した中に、幾何学的な模様や、
仏教や宇宙をイメージしたのかな、と思うものがありました。
野田秀樹さん演出の舞台は、歌舞伎の『鼠小僧』『研辰の討たれ』しか、
見ていません。
もしかしたら、『愛陀姫』は、野田さんの色が、最も濃い舞台なのかな、
とも思いました。
濃姫(勘三郎丈)。
愛する者をわが手に得ようとする執念が、怖かったです。
愛陀姫(七之助丈)。
見ていて、痛々しい感じでした。
アイーダも、こんなキャラクターなのでしょうか。
木村駄目助座衛門(橋之助丈)。
忠義と愛情との板ばさみになる悲劇の武将が、ピッタリでした。
織田信秀(三津五郎丈)。
権謀術数に富んだ武将、威厳ある一国の主を好演でした。
祈祷師・細毛(福助丈)。
面白かったのですが、やや、テンションが高かったようです。
祈祷師・荏原(扇雀丈)。
インチキ臭さの中に、人を信用させてしまう厳かさが、垣間見えました。
多々木斬蔵(亀蔵丈)。
腹黒そうですが、実は単純な男。
なくてはならぬ脇役でしょうか。
『愛陀姫』を再演するのであれば、下記のような配役は、いかがでしょうか。
愛陀姫を勘太郎丈。
濃姫を七之助丈。
勘三郎丈は一歩引いて、他の役。例えば、祈祷師。
上演時間は、途中だれることなく、ちょうどいいものでした。
私は、半分も理解していませんが、画期的な作品だと思います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
歌舞伎愛好会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
歌舞伎愛好会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 一行で笑わせろ!
- 82540人
- 2位
- 酒好き
- 170703人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90064人
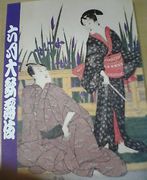





![[dir] 日本の伝統芸能](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/67/58/266758_56s.jpg)

![[dir] 邦楽](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/67/61/266761_218s.jpg)















