以下、このコミュニティ発足のきっかけとなった、ナガタさんのオタク論を転載します。
おのぞみドットコムhttp://
これから派生した論議はナガタさんの日記
http://
にあります。
「オタク論(1)
オタクなりのやりかた」
どうも皆様お久しぶり。あるいは初めまして。映画部のナガタです。ファンレターが届かないのはどうしてですか。それはさておき、今回からしばらくお題をオタク論にしてコラムを書いていきたいと思います。こないだオフィスで松村さん相手に熱く語ってたら、他のメンバーにも面白がってもらえたし、取り敢えず書き始めてしまうことにしました。
で、アニメをたくさん観ていると言うとバカにする人がいるんですが、オタクを差別してるだけなら言っておきたいことがあります。「お前らわかってねえよ!」っていう憤慨ではなく、「案外知られていないこと」をただ提示したいだけです。これから書くことを知ってなおオタクを差別するのは、僕はむしろ良いことだと思います。結論から先に言うと、そういう差別を受け入れることからオタクは始まり、だからこそオタクらしい、というかオタクならではの表現が可能になると僕は思うのです。
さて、僕の見解では、オタクが差別されるのには三通りの理由があります。
それは
★オタクがコミュニケーション能力や社会性を不足させているということ。
★オタクが公共の場で「駄目なヤツ」のレッテルを貼られているということ。
★オタクは上記二つの理由があるのにも関わらず、自尊心が強く、しかもその自尊心がまわりに理解されていないことを受け入れないので、自己満足的に見られがちであるということ。
の三つです。
ここで僕はさっそく、人によっては意外と思われるかもしれないけど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいポイントのひとつを紹介します。
それはすなわち、「オタクにコミュニケーション能力や社会性が欠落している、というのは偏見だ」ということ。「そんなわけないだろ」とか「それじゃ、今迄オタクだと思ってた彼はコミュニケーション能力や社会性が欠落しているからオタクじゃなかったのか?」とか思うのは性急です。ちょっと待ってもう少し先まで読んで下さい。
「オタクにコミュニケーション能力が欠落している、というのは偏見だ」と言うのには、「オタクにはコミュニケーション能力や社会性が欠落している人もいるし、欠落していない人もいる」という論理的な曖昧化=誤摩化しだけでなく、「オタクにはオタクなりのコミュニケーション能力や社会性がある」という積極的な意味があります。
「オタクなりのコミュニケーション能力や社会性」と言うと、オタク同志でしか通用しない閉鎖的なものに思われるかもしれませんが、例えば大工さんには大工さんの言葉や話し方、寿司屋さんには寿司屋さんの言葉や話し方があり、美術評論家や音楽愛好家(特に熱心なクラシック愛好家や、マニアックなジャズファン、熱狂的なロッカーたち)のあいだだけでしか通用しない専門用語や固有名詞があり、スポーツファンにしか理解できないそれぞれのスポーツのルールがあるように、オタクにはオタクの、それぞれのジャンルごとの、それに特別な興味を持たない人には理解できないコトバがあるわけです。オタクたちは、(特別閉鎖的な種類のオタクを除いて)互いにそういったコトバを交えつつコミュニケーションをし、彼らなりの「社会」を形成しているわけです。
とはいえ、それだけなら、お寿司屋さんはお寿司オタクで、大工さんは家作りオタクで、美術評論家は美術オタク、音楽好きは音楽オタクか、ってことになってしまう(そういう意味で「オタク」というコトバを使う人もいますけど)わけですが、僕の観察によると、どうやらそれだけでは不足です。しかしまあ「オタク」といわれる人たちがみんな引き蘢って誰とも口をきけないような人ばかりだという偏見だけはまず解消しないとこれからの話が出来ないので、地ならしの意味も込めて今回は「オタクにもオタクなりのコミュニケーション能力や社会性がある」ということを紹介させていただきました。
次回は、「★オタクが公共の場で駄目なヤツのレッテルを貼られているということ」について書こうと思います。また先取りして書いておくと、オタクは「公共の場」、たとえばテレビや学校で「駄目なヤツ」というレッテルを貼られてきたので「オタクなりのコミュニケーション能力や社会性」をオタクではない人たちへと開いていくことに困難を覚えるようになり、また逆に、自分なりのコミュニケーション能力や社会性を新しく出会う他人とのあいだに開いていくことに困難を覚えるような人たちがオタクになっていく、ということを紹介させてもらうつもりです。
少し上級のオタク論をご所望なら:
http://
2004年07月25日
17:54 ナガタ
「オタク論(2)
オタクというレッテルの背景 前編」
こんばんわ。ナガタです。
今回はまず誤らせて下さい。ファンレターをくださっていた皆様、申し訳ありませんでした。実はついさっきまでメールボックスの開け方を間違っていたことに気付かず、メールが届いているのに「だれも僕にファンレターをくれない!」と思い込んでおりました。
…ええ。もちろん僕の妄想です。いまだに1通もファンレターは届いておりません。送り先はこちらnagata@nzm.jp よろしくね☆
さて、前回は「オタクにコミュニケーション能力がないというのは偏見だ」「大工は大工の専門用語があるように、オタクにもオタクなりの専門用語がある」ということを書きました。今回は「オタクはダメなやつだ」というレッテルについてのお話です。
さて、ところで、知ってる人は既に知っているし、知らない人は知らないから面白くない、そういう話題があります。歴史の話題です。興味を持っている人か、あるいはそれを知る必然性を持っている人だけが楽しめる情報です。例えば、■1989年に宮崎勤という人が逮捕されました。■1975年にコミックマーケット(略してコミケ)が開催されるようになりました。 という二つの情報。この二つ、ちょっとだけオタクのことを知っている人たちにとっては、「オタク」というキーワードしか共通点を見い出せない情報です。
でも、ここには忘れられがち、あるいは無視されがちなふたつのキーワードがあります。そしてそれは「オタク」というキーワードに重大に関係しているのです。
そのふたつのキーワードとは何か。「コピー(もしくは複製)」そして「テレビ」です。■宮崎勤はビデオテープの蒐集家でした。正確に言えば、テレビを録画したビデオテープを集めることにたいへん執着していました。ニュースでは「暴力映像など6000本以上のコレクション」と報道されていますが、実際にはそのほとんどはテレビをただ録画したものだったと言われています。■コミケの発達にはテレビとビデオの存在が不可欠でした。テレビアニメをビデオで録画することができるようになり、アニメを題材にした同人誌(コピー機を利用して手作りする本が中心)が大量に作られ、それを売買する大勢のファンたちを新聞やニュースが取り上げたのです。「そうか、こんな楽しみ方があったのか」とニュースを観てコミケに参加するようになった人たちもたくさんいたはずです。1970年代後半以降のコピー機の廉価化と普及がこの背景にあったことはほとんど確実なことだと言えるでしょう。
僕は、「オタク」という言葉が日本語として定着するのに不可欠な要因として、「オタク」という言葉がテレビで連呼されたということがあるのではないかと考えています。折しも、「新人類」という別のカテゴリーが多用されたあとで、この「新人類」と同じくらいインパクトのある言葉がマスメディアでは待ち望まれていたのです。そこにセンセーショナルな事件として、コミケの大成長と、宮崎勤の事件がありました。(次回に続く)
ここまでの話では、どうして「オタクはダメなやつだ」というレッテルが出来上がったのかということを説明しきれませんでした。「オタク」という言葉が現在持っている意味やニュアンスというのは、簡単には説明しきれないほどに多様で深いものになってしまっているのです。次回は「オタクはダメなやつだというレッテル」編の後半ということにします。後半のメインは、なぜテレビで「オタクはダメなヤツだ」と連呼されたのか、について書こうと思います。
参考サイト:
宮崎勤事件の説明http://
コミケの歴史http://
コミケとコピー機の関係http://
2004年07月25日
17:55 ナガタ
オタク論(2)
オタクというレッテルの背景 後編
こんばんわ。ナガタです。全然ファンレターが届かないので、もうファンレターの宛先を書くのはやめました。虚しいばかりですから。もう、哀しいだけの人生なんてイヤなの。だから「ファンレターを送りたいのだが、何処に送ったら良いの?」という人はnagata@nzm.jpにお便りを下さい。ファンレターの宛先をお教えします。アドレスいま書いたじゃん、というつっこみは封殺します。どういう意味だか知らないけど、「封殺」って。
今回は、前回しりきれに終わった「オタクはダメなやつだ」というレッテルについての説明を完結させます。前回挙げたキーワードは「コピー」と「テレビ」。言い換えるならば、情報を消費する大衆と、情報を発信する企業という、マス・メディアの2つの極における人々の活動にスポットをあてていきたいということです。
前回は、コピー機が普及し始め「コミケ」が発達したこと、宮崎勤被告が一生のうちに見切れないほど大量のビデオを録り溜めていたこと、に触れました。いわば消費者側の極についての話でした。今回は「テレビ」の話をしようと思います。「テレビ」で「オタク」ということばが多用されるようになり、それまでになかったような独自の意味合いが「オタク」ということばに絡み付いていくことになったのではないかと僕は考えています。現在のような「オタク」の使われ方には、このテレビ経由で発生した意味合いだけのもの、そういったテレビ経由の意味合いに対するコミケ側の反応を含み込んだもの、こうして意味が多様化してしまった結果として「自分もまたオタクなのではないか」と思うようになった人たちが勝手に付与し出した意味などが、それぞれ勝手に発達したり、あちこちで結びついたりしているのです。
さて、前回も紹介しましたように1970年代から1980年代にかけてコミケが大きく成長しました。テレビアニメやマンガといった、中毒性の高い対象に没頭する若者が増え出したということです。「中毒性」と書いたのには、いくつかの理由があります。テレビアニメやマンガは、連続したストーリーを安く定期的に広範囲に提供するものです。学校や近所中で、あるいは地方を超えて、同年代なら誰でも話が通じ、いつでも話題が提供されていたのです。アニメを見始めたりマンガ雑誌を読み始め、そういった話題を共有する友達を見つけてしまうと、仲間全員が一斉にアニメ断ちやマンガ断ちをしない限り、あるストーリーが終わったら別のストーリー、といった流れでズルズルと消費し続けてしまうわけです。これをもって中毒性という表現を理解してくれれば取り敢えずは充分です。
で、こういった現象と宮崎勤事件とを結び付けた人たちがいたのではないかというのが僕の「オタク論」の重要な仮説の1つです。テレビで発言できる人たちというのは、1960年代にテレビが普及する過程で成人したような人たちであり、上記のような「中毒性」に対して批判的である場合が多かったのではないでしょうか。彼らにとっては、スポーツをし、勉強をして、太平洋戦争に敗れ中空状態になったアイデンティティを埋めるのが最重要項目であった、と僕は考えています(全員が全員、そうであったと乱暴なことは言えませんが)。「小説はオトナが読むもの、マンガは子供が読むもの」という認識がこの世代の特徴です。彼らの前の世代は「小説ばかり読んで勉強しないのはダメだ」と言っていたらしいのですが。
子供からオトナへと成長しなければならないのに、こともあろうにマンガやテレビマンガ(アニメは昔このように呼ばれていました。彼らは1970年代に普及し、爆発的な人気を得たテレビゲームに対しても同様の印象を持っていたのではないかと思います)に熱中して、社会貢献をしない若者が増えている。これがテレビで発言するオトナたちの感じていた危惧だったのではないでしょうか。そんなところに宮崎勤事件が起きました。それみたことか、やはり「最近の若者」はこんなになっているぞ、と報道関係者は躍り上がって喜んだのではないでしょうか。いつだってオトナは「最近の若者は・・・」と苦言を呈したいし、そういう苦言を聞きたいと思っているのでそういうオトナを歓迎するのです。
もう僕が今回言いたいことはおわかり頂けたと思います。もっとも、それだけで「オタク」ということばが成り立っているとは誰も思わないでしょう。今回(と前回)書いたことは「オタクはダメなやつである」というレッテルの「背景」です。次回以降は、「オタクの自己満足」というもっとも重大なテーマについて解説していきたいと思います。次回の話は、今まで他の人たちが語ってきた「オタク論」でも扱われてきたテーマです。それだけじゃ全然ダメだと思うのでこうやって前置きめいたことを長々書くわけですが。
2004年07月25日
17:56 ナガタ
オタク論(3)
オタクの自己満足
こんばんわ。ナガタです。とうとうファンを名乗るかたが現れました。さいきん新人として採用されたひとです。何を考えているんでしょうか。正気の沙汰とは思えません。どうしたら良いのか正直困惑しています。怖いのであまりカカワリアイになりたくないです(嘘)。でもファンレターはまだ届きません。誰でも良いからはやく送ってくれ。宛先はこちら……いや、めんどうだからもう書きません。nagata@nzm.jp
さて今回はとうとうオタク論も山場です。今回僕が書こうとしていることは、様々なひとたちの手によって既に出版されたりウェブ上にアップされたりしてきたいわゆる「オタク論」とかさなるところの大きいものになるだろうと思われます。それでもなお、今回またそれを書こうとしていることの理由は、いままで論じてきた2点と、今回扱う「自己満足」の問題とをきちんと結び付けて論じているものを僕がいまだかつて見たことがないからです。えーと、嘘です。正確に言うと、ちょっとしか見たことがなく、それもまだ不十分だと思われるからです。
このコラムでオタク論を始めたとき、「オタクには、大工には大工の専門用語があるように、オタクならではの共通語がある」というようなことを書きました。これはある意味で正しく、ある意味では正しくありません。どこがどう正しくないのかと言うと、大工さんは家を建てる、という仕事のために専門用語を発展させてきたわけですが、オタクの専門用語は、家を建てるための専門用語と比べるとだいぶ有用性の低いものなのです。その意味では、大工の専門用語とオタクの専門用語とは性格が異なっているんです。もっとも、オタクは夢や快楽の分野で非常に興味深い成果を挙げているので、夢や快楽の意義を知っている人からすればオタクの専門用語というのもけっして無駄な存在ではないのですが、もっと直接的で単純な夢や快楽で事足りるひとたち(こういったひとたちは、一般的に複雑で韜晦した夢や快楽を追い求める人達よりも相対数が常に多いわけですが)にとって、オタクというのはまったく無駄な存在、ときには有害だったり邪魔だったりする存在だと言って問題ないでしょう。家というのは、現代社会においては、大多数に必要とされるものですし、すくなくともその「意義」というのが明確なものなわけです。
ではオタクの夢や快楽というのは、どういう「意義」があるのでしょうか。これが、そのスジのひとたちにはすっかり耳タコな話なのですが、「オタクというのは、一部にしか通用しない意義を大事にし、それを発展させていこうとしている」わけです。ここで言う「一部」というのが、例えば学会や研究者仲間であったりすればオタクとは呼ばれず学者と呼ばれるだろうし、例えば展覧会や藝術家仲間であればオタクとは呼ばれずアーティストと呼ばれるだろうし、ファンや音楽仲間であればオタクとは呼ばれず音楽家と呼ばれるわけです。要するに、オタクというのは、自分や自分が愛好するものが「誰に」「どこで」評価されているのかハッキリしないひとたちを指すものだと言えるでしょう。もっとも、オタクたち自身は自分や自分が愛好するものが誰に何処で評価されているか、だいたい把握しているはずです。オタクという呼称にとって大事なのは、その「だれ」「どこ」というのが謎や無気味さを孕んでいる、ということです。「世間的に言ってどうやら怪しいらしい」というニュアンスが含まれるような「だれか」によって「どこか」で評価されることを目指す人達、それがいわばオタクなのだと言える、と僕は考えています。
ここまで書けば、過去にこのコラムに僕が書いてきたこと、すなわち、オタクは独自のコミュニケーションツールを用いることで独特の種族として自律し、マスメディアから白眼視されることで自他ともに認める「あやしい」存在となり、テクノロジーの発達によって出現した新しい市場の需要と供給を同時に満たすことで経済的にも自律してきた、ということと、今回取り上げる「自己満足」とが密接に結び付いていることが理解されるのではないかと思います。
自覚的でないオタクは、歴史的にどうしてオタクが差別されるのかを知らず、自分が使っていることばに専門用語が多く含まれていることにすら気付かず、非オタクな人とのコミュニケーションや、違う分野を専門にしている別のオタクとのコミュニケーションなどを上手に行うことができないのにも関わらず、しかし不特定多数が消費している夢や快楽を自分もまた評価することができて消費することができているということについてアイデンティティやプライドを持ったりしていると言えるでしょう。ただ、不特定多数にも色んなレベルがあって、非オタクが消費したり評価したりしてアイデンティティを獲得するような対象(スポーツや、雑誌や新聞などのマスカルチャー)が抱えている消費者の数と比べると10分の1から100分の1、下手をすると1000分の1とか10000分の1くらいの人数しか無い場合があります。オタクに限らず、「不特定多数」として認識できる人数というのは、例えば「100人以上」とかそういう認識の仕方なので、150人も不特定多数だし、100万人も不特定多数ということになるわけですね。150人と100万人とを比べたら、それはもちろん比べ物にならないと思えるわけですが、不特定多数同士だったら同じことですから。こういう「地に足の付かない勘定」というのもある種、オタクに共通する感覚だと言えないことは無いはずです。
さて、限られたスペースで、ダラダラと進めてきたこの「オタク論」ですが、今回をもちまして、一応最終回とさせて頂こうと思います。まとめながら話を進めたことで、当初考えていたよりもだいぶ絞った内容になって、書き始めたときよりも自分自身、見えるようになったものが多かったように思います。もっとも、書きこぼしたこともたくさんあって、またいつかどこかで、もっときちんと書き直したいと思っています。本論が、オタクに対する無用の誤解(そんなものがあるかどうかわからないのですが)を回避する助けになったら良いなあ。次回は、これまでの流れを踏まえて、僕が推薦するオタクカルチャーの果実を紹介したいと思います。いま考えているのは、佐藤友哉という若手小説家、フリクリというアニメ、そして『アフタヌーン』というマンガ雑誌です。←追加したり変更したりするかもしれませんけど。
『オタク論』を終えて
番外編―オタク的なものの果実たち―
前回までダラダラと「オタクとは何か」ということについて論じてきたわけなのですが、ファンレターはともかく、これといった批判の声も聞こえてこず、それはそれで不安になったので、機会をみて何人かに意見を求めたことがあります。そうしていると、特に年長のかたから「いまさらオタクを取り上げて論じることにこれといった意義を感じない」といったご指摘を賜ることがありました。10年以上前に「オタク論」というのは出尽くしてしまったのではないか、いまはもっと取り上げるに足る対象があるのではないか、ということだったと、僕はいただいた指摘をそう受け止めました。僕がいままでやろうとしてきたことは、オタク論を自分の知っている限りの狭い範囲のなかではあるけれども簡単にまとめ、いままでオタク論に興味を持っていなかった人達にも読みやすいものとして再提示しようというものでもあったので、「既に出尽くしている」という指摘は適当なものではなかったと思います。もっとも、字数は多くなってしまったし、書きクチも堅かったので、その目標は達成できたとは言いにくいのですが。また、「取り上げるに足る、もっとほかの対象があったのではないか」ということについては、それは本当に必要ならば誰かがきっと他の場所で取り上げてくれるだろうし、僕には僕なりの必然性があったわけで、これもきちんと応えるのは難しい指摘でした。逆を言えば、この指摘は、僕なりの必然性というのをきちんと記述出来なかったことを批判したものだったわけですから。既に以前までの回で書いたつもりになっていましたが、僕がこのコラムで「オタク論」を書いてきたのは、「自分はオタクかもしれない」と思っている人たちが読んで何らかの力や支えとして機能してくれたら嬉しいなと思っているからです。無用な自嘲はもったいないし、そのもったいなさに耐え切れずに、単純な自己肯定に走ってしまったらもっともったいない。それこそ「オタクであること」あるいは「オタク的な要素を持っていること」の価値や可能性を忘れてしまっていると思うんです。
で、そんなわけで、今回は僕が考えるオタク的な素敵文化の結晶をいくつかご紹介しようと思っていたのですが、字数の都合上、前回挙げた3つ(佐藤友哉、『フリクリ』、『アフタヌーン』)のうち、佐藤友哉だけを取り上げることにしました。理由というか言い訳としては、アニメやマンガはまあ手に取って再生するなりパラパラとめくるなりしてもらえればだいたいの感じはわかってもらえるし、そもそも『フリクリ』も『アフタヌーン』もしばらくは大手のアニメやマンガ取り扱い店の店先に並び続けるだろうと思われる「メジャー」の商品なので、そういうのに興味がある人はまあ、どうぞご勝手に手を差し伸べてその世界に触れてみて下さいって感じです。必要とされる勇気は、それらを手にとってレジに運ぶだけ。他方、佐藤友哉っていう若手作家の小説はどうか。これが微妙に入手困難で、しかもほとんど文字ばかりなので、いまいち手を出せない人というのが大量に存在している気がするんですね。そもそも『フリクリ』『アフタヌーン』と比べると圧倒的に知名度が低いと思われるわけで。佐藤友哉に触れたいと思ったら、書店をいくつか廻り、店員に問い合わせるくらいの興味が必要になるわけです。僕はそれを喚起したい。
さて、その佐藤友哉ですが、生まれはなんと1980年。僕よりも若い。もっとも、彼の周辺、あるいは彼の読者が読む他の作家達には、更に若い人もいるのでこれしきのことで驚いていてはいけません(例えば2002年に立命館大学在学中に佐藤友哉と同じメフィスト賞を受賞してデビューし、佐藤友哉の作品でもしばしば言及される西尾維新は1981年生まれ)。佐藤友哉がデビューするきっかけとなったメフィスト賞というのは、講談社発行のミステリ小説誌「メフィスト」の新人賞で、最初の受賞者に森博嗣、佐藤友哉が受賞する少し前にのちの三島賞作家である舞城王太郎を輩出する、イロモノ作家選出機関のようなものです。ミステリー小説という形式をとっていればあとはなにをやっても良い、面白ければなんでもアリ、という乱暴な説明でこの新人賞の解説はほとんど足りてしまう。ほとんどの作品が語り口は柔らかく、肝心の謎解きは崩壊寸前、もしくは崩壊してしまい、その崩壊の収拾の付け方でもって面白さを生み出すような、そんな、文学としては外道な作品ばかりの賞です(文学って何か、という批判的な機能も担ってると言えるわけですが)。佐藤友哉という小説家はそんな変な賞を受賞してデビューしたのです。
私見では、佐藤友哉は歴代のメフィスト賞受賞者のそうそうたる変態たちと比べても特別「変」です。他の作家が単に思考のアクロバットが鮮やかだったり、イビツ過ぎたりするのに対して、佐藤友哉の「変」さは、鮮やかでイビツな思考ゲームももちろん冴えているのだけれど、それ以上に、異常なほど「青臭さ」にこだわっているところにあります。
ただ青臭いだけの作家はそこここに溢れ返っているし、文学的なテーマとしてある程度普遍性のある「青臭さ」を選ぶ作家も多く存在しているけれど、佐藤友哉のこだわりとそれらとを混同されては困ります(誰が?)。佐藤友哉には「普遍的なテーマ」なんか存在しない。彼はごく個人的な世界観しか持とうとしません。わかったふりをしてわかってるみたいに見られるのではなくて、わかった振りをして見せることでわかっていないことを見せる、そんなノーガード戦法で挑んでくるわけです。だから彼は青臭いのですが、かといって自分のことばかり書くわけじゃない。むしろ自分のことはあまり書きたくないみたいで、多くの個性的な登場人物たちのさまざまな目線で物語を丹念に紡いでいく。にも関わらず、どこかから「物語」と「現実」との境界を突き破って作家本人が作品内に現れ出てしまう。そんなことしなければ「よくできた思考ゲーム」として小説は完結できるのに、そこに自分を登場させてしまうことで、自意識の強い、納まりのつきにくい気持ち悪い作品が出来上がってしまうのです。有名な作品を喩えに使って説明するなら、『ネバーエンディングストーリー(果てしない物語)』の主人公と作者とが同一人物であった、とか、『不思議の国のアリス』が実在の少女の妄想の克明な記録であった、とか、『ゴーマニズム宣言』や『華氏911』がまったくのフィクション(作り話)でした、とかいった場合の居心地の悪さ、ブキミさ。うまく喩えられた気がしません。わからなくてもあなたが悪いんじゃないですよ。僕が悪いんです。ごめんなさい。
もっとも、作者が作中に登場して愚痴を言ったり冒険してみたり、というのはいままでの文学やらマンガやらアニメやら、映画や音楽や絵画ですらも、使い古されてしまっていて今さら珍しい手法ではありませんね。それこそ、映画などの動画技術が発明されるまでは「すべての藝術の発端であり、完成形である」と言われていた演劇の本来の姿は、作者自身が舞台の上で虚実織りまぜて語ったことだったとも言えます。佐藤友哉はある意味で古典的な方法を現代に復活させているわけだ。だから安直なやり方であったなら、佐藤友哉以外の多くのキワモノ狙いのミステリー作家達が陥ったように、凡庸な曲芸にしかならなかった筈です。僕が佐藤友哉が凄い、と言うのは、そういった凡庸な曲芸が目新しくて喜んでいるからではありません。そもそも目新しさに喝采を送るほど、僕はたくさん本を読んでいませんしね(笑)。
佐藤友哉が面白いのは、舞城王太郎や西尾維新や清涼院流水(メフィスト賞の第2回目の受賞者)のような破天荒な物語設定や話の展開のはしばしに、執拗に、「リアル」な生きる苦しみ、締念、後悔、暗い欲動が深く刻み込まれているところです。問題はこの「リアル」っていうところ。僕にはまったく「リアル」ではないけれど、いま戦時下にある地域に暮らす人々にとってはいつ頭の上から爆弾が降ってきて、一生消えない傷を自分や家族が負うかもしれない、ということが「リアル」だろうし、僕にはまったく「リアル」ではありませんが、お父さんが一人ずつみんな違う兄弟がお母さんに捨てられて戸籍ももたずに生きたり死んだりする「リアル」もあるかも知れません。僕の「リアル」は読者であるあなたの「リアル」と色んな点で少しずつズレていて、ときにはまったく食い違っているかもしれない。文学というのはそういったズレが取りこぼしてしまうモノをなんとかして「リアル」に書き記すことが出来るものなわけなのですが、佐藤友哉は「果たして文学にそんなことができるのだろうか?」もしくは「果たして自分にそんなことをする才能はあるのだろうか?」というのをまさに紙上で実験しているかのような緊張感を持っているのです。いちファンとして僕は「文学はどうか知らないが、佐藤くん、あんたはそんなことする才能があるよ!」と言ってあげたいのですが、そういった声にはすぐ作品中から「だったらどうして僕の作品は売れないんだ!」「みんなうすら甘い優しい嘘ばかり求めていやがる」「オレもそんなうすら甘い優しい嘘をつきたいよ」「くそう!オレの嘘つき!けがらわしい!こんなオレに騙されるお前はバカだ」「こんなバカを相手にしてるオレもバカだ!」っていう叫びが聞こえてきます。ちょっと過激なんですが、ビビッドであることは悪いことではないと思うので、その点は取り敢えず突っ込まないでおきましょう。
さて、本稿はもともとは「オタク的なものの果実」として佐藤友哉を紹介しようとするものなのですが、僕にとっては、佐藤友哉のこの過激で泥沼化した自己批判がまさに「オタク的」だと思えるのです。普通の、オタク的でないような作品なら、「果たして文学には○○が可能だろうか」「果たして私には○○ができるだろうか」という問いに対して「よし、やってみよう」「はい、できました」というスタンスのものしかないと思うんです。佐藤友哉は「よし、やってみるけど、どうなっても知らないからな」「こんなの出来ちゃったけど、オレがつくりたかったのはこんなんじゃないんだ」「でも売れないと困るし、オレ、小説書くしかできないし、面白いって言ってくれる人がいるから」とか言い訳だらけ。甘えるんじゃない!と一喝できたらすっきりさわやかなのですが、そんなデリカシーのない態度では絶対に掬いきれない何かに佐藤友哉の作品は到達しえていると思うんですよ、僕は。だから、彼は面白い作品を書いている間は甘えてて良いと思う。それに彼は彼なりに甘えた振りをしながら、実は甘えることが出来ないっていうことを体現しているんだと思います。
ということで、みなさん佐藤友哉の作品を買って下さい。初心者にお薦めは『クリスマス・テロル』(表紙裏に「犯人は、読者です」っていきなりタネ明かしが。でも読者が犯人ってどういうことなんでしょうね!ちなみに僕が読んだときは本当に僕が犯人でした)が短くてコンパクトで、装釘も仰々しくて良いかと思います。もう少しレベルが高い人には『エナメルを塗った魂の比重』がお薦め。「気合いがあれば一日で読める」というくらい分厚いですが、頑張って読むに値する複雑さ&爽やかで胸に突き刺さるエンディング。なお、個人的には3号まで発行された思想誌「新現実」に連載の『世界の終わりの終わり』が好きです。まだ最終話読んでないけど。ちなみにこの「新現実」っていう雑誌も変なので、探してみて下さい。見つけたら怪しい表紙に臆することなく、どうぞ気合い入れて購入してみて下さい。すぐに読まなくても持ってればそのうち読むかも知れないし。
おのぞみドットコムhttp://
これから派生した論議はナガタさんの日記
http://
にあります。
「オタク論(1)
オタクなりのやりかた」
どうも皆様お久しぶり。あるいは初めまして。映画部のナガタです。ファンレターが届かないのはどうしてですか。それはさておき、今回からしばらくお題をオタク論にしてコラムを書いていきたいと思います。こないだオフィスで松村さん相手に熱く語ってたら、他のメンバーにも面白がってもらえたし、取り敢えず書き始めてしまうことにしました。
で、アニメをたくさん観ていると言うとバカにする人がいるんですが、オタクを差別してるだけなら言っておきたいことがあります。「お前らわかってねえよ!」っていう憤慨ではなく、「案外知られていないこと」をただ提示したいだけです。これから書くことを知ってなおオタクを差別するのは、僕はむしろ良いことだと思います。結論から先に言うと、そういう差別を受け入れることからオタクは始まり、だからこそオタクらしい、というかオタクならではの表現が可能になると僕は思うのです。
さて、僕の見解では、オタクが差別されるのには三通りの理由があります。
それは
★オタクがコミュニケーション能力や社会性を不足させているということ。
★オタクが公共の場で「駄目なヤツ」のレッテルを貼られているということ。
★オタクは上記二つの理由があるのにも関わらず、自尊心が強く、しかもその自尊心がまわりに理解されていないことを受け入れないので、自己満足的に見られがちであるということ。
の三つです。
ここで僕はさっそく、人によっては意外と思われるかもしれないけど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいポイントのひとつを紹介します。
それはすなわち、「オタクにコミュニケーション能力や社会性が欠落している、というのは偏見だ」ということ。「そんなわけないだろ」とか「それじゃ、今迄オタクだと思ってた彼はコミュニケーション能力や社会性が欠落しているからオタクじゃなかったのか?」とか思うのは性急です。ちょっと待ってもう少し先まで読んで下さい。
「オタクにコミュニケーション能力が欠落している、というのは偏見だ」と言うのには、「オタクにはコミュニケーション能力や社会性が欠落している人もいるし、欠落していない人もいる」という論理的な曖昧化=誤摩化しだけでなく、「オタクにはオタクなりのコミュニケーション能力や社会性がある」という積極的な意味があります。
「オタクなりのコミュニケーション能力や社会性」と言うと、オタク同志でしか通用しない閉鎖的なものに思われるかもしれませんが、例えば大工さんには大工さんの言葉や話し方、寿司屋さんには寿司屋さんの言葉や話し方があり、美術評論家や音楽愛好家(特に熱心なクラシック愛好家や、マニアックなジャズファン、熱狂的なロッカーたち)のあいだだけでしか通用しない専門用語や固有名詞があり、スポーツファンにしか理解できないそれぞれのスポーツのルールがあるように、オタクにはオタクの、それぞれのジャンルごとの、それに特別な興味を持たない人には理解できないコトバがあるわけです。オタクたちは、(特別閉鎖的な種類のオタクを除いて)互いにそういったコトバを交えつつコミュニケーションをし、彼らなりの「社会」を形成しているわけです。
とはいえ、それだけなら、お寿司屋さんはお寿司オタクで、大工さんは家作りオタクで、美術評論家は美術オタク、音楽好きは音楽オタクか、ってことになってしまう(そういう意味で「オタク」というコトバを使う人もいますけど)わけですが、僕の観察によると、どうやらそれだけでは不足です。しかしまあ「オタク」といわれる人たちがみんな引き蘢って誰とも口をきけないような人ばかりだという偏見だけはまず解消しないとこれからの話が出来ないので、地ならしの意味も込めて今回は「オタクにもオタクなりのコミュニケーション能力や社会性がある」ということを紹介させていただきました。
次回は、「★オタクが公共の場で駄目なヤツのレッテルを貼られているということ」について書こうと思います。また先取りして書いておくと、オタクは「公共の場」、たとえばテレビや学校で「駄目なヤツ」というレッテルを貼られてきたので「オタクなりのコミュニケーション能力や社会性」をオタクではない人たちへと開いていくことに困難を覚えるようになり、また逆に、自分なりのコミュニケーション能力や社会性を新しく出会う他人とのあいだに開いていくことに困難を覚えるような人たちがオタクになっていく、ということを紹介させてもらうつもりです。
少し上級のオタク論をご所望なら:
http://
2004年07月25日
17:54 ナガタ
「オタク論(2)
オタクというレッテルの背景 前編」
こんばんわ。ナガタです。
今回はまず誤らせて下さい。ファンレターをくださっていた皆様、申し訳ありませんでした。実はついさっきまでメールボックスの開け方を間違っていたことに気付かず、メールが届いているのに「だれも僕にファンレターをくれない!」と思い込んでおりました。
…ええ。もちろん僕の妄想です。いまだに1通もファンレターは届いておりません。送り先はこちらnagata@nzm.jp よろしくね☆
さて、前回は「オタクにコミュニケーション能力がないというのは偏見だ」「大工は大工の専門用語があるように、オタクにもオタクなりの専門用語がある」ということを書きました。今回は「オタクはダメなやつだ」というレッテルについてのお話です。
さて、ところで、知ってる人は既に知っているし、知らない人は知らないから面白くない、そういう話題があります。歴史の話題です。興味を持っている人か、あるいはそれを知る必然性を持っている人だけが楽しめる情報です。例えば、■1989年に宮崎勤という人が逮捕されました。■1975年にコミックマーケット(略してコミケ)が開催されるようになりました。 という二つの情報。この二つ、ちょっとだけオタクのことを知っている人たちにとっては、「オタク」というキーワードしか共通点を見い出せない情報です。
でも、ここには忘れられがち、あるいは無視されがちなふたつのキーワードがあります。そしてそれは「オタク」というキーワードに重大に関係しているのです。
そのふたつのキーワードとは何か。「コピー(もしくは複製)」そして「テレビ」です。■宮崎勤はビデオテープの蒐集家でした。正確に言えば、テレビを録画したビデオテープを集めることにたいへん執着していました。ニュースでは「暴力映像など6000本以上のコレクション」と報道されていますが、実際にはそのほとんどはテレビをただ録画したものだったと言われています。■コミケの発達にはテレビとビデオの存在が不可欠でした。テレビアニメをビデオで録画することができるようになり、アニメを題材にした同人誌(コピー機を利用して手作りする本が中心)が大量に作られ、それを売買する大勢のファンたちを新聞やニュースが取り上げたのです。「そうか、こんな楽しみ方があったのか」とニュースを観てコミケに参加するようになった人たちもたくさんいたはずです。1970年代後半以降のコピー機の廉価化と普及がこの背景にあったことはほとんど確実なことだと言えるでしょう。
僕は、「オタク」という言葉が日本語として定着するのに不可欠な要因として、「オタク」という言葉がテレビで連呼されたということがあるのではないかと考えています。折しも、「新人類」という別のカテゴリーが多用されたあとで、この「新人類」と同じくらいインパクトのある言葉がマスメディアでは待ち望まれていたのです。そこにセンセーショナルな事件として、コミケの大成長と、宮崎勤の事件がありました。(次回に続く)
ここまでの話では、どうして「オタクはダメなやつだ」というレッテルが出来上がったのかということを説明しきれませんでした。「オタク」という言葉が現在持っている意味やニュアンスというのは、簡単には説明しきれないほどに多様で深いものになってしまっているのです。次回は「オタクはダメなやつだというレッテル」編の後半ということにします。後半のメインは、なぜテレビで「オタクはダメなヤツだ」と連呼されたのか、について書こうと思います。
参考サイト:
宮崎勤事件の説明http://
コミケの歴史http://
コミケとコピー機の関係http://
2004年07月25日
17:55 ナガタ
オタク論(2)
オタクというレッテルの背景 後編
こんばんわ。ナガタです。全然ファンレターが届かないので、もうファンレターの宛先を書くのはやめました。虚しいばかりですから。もう、哀しいだけの人生なんてイヤなの。だから「ファンレターを送りたいのだが、何処に送ったら良いの?」という人はnagata@nzm.jpにお便りを下さい。ファンレターの宛先をお教えします。アドレスいま書いたじゃん、というつっこみは封殺します。どういう意味だか知らないけど、「封殺」って。
今回は、前回しりきれに終わった「オタクはダメなやつだ」というレッテルについての説明を完結させます。前回挙げたキーワードは「コピー」と「テレビ」。言い換えるならば、情報を消費する大衆と、情報を発信する企業という、マス・メディアの2つの極における人々の活動にスポットをあてていきたいということです。
前回は、コピー機が普及し始め「コミケ」が発達したこと、宮崎勤被告が一生のうちに見切れないほど大量のビデオを録り溜めていたこと、に触れました。いわば消費者側の極についての話でした。今回は「テレビ」の話をしようと思います。「テレビ」で「オタク」ということばが多用されるようになり、それまでになかったような独自の意味合いが「オタク」ということばに絡み付いていくことになったのではないかと僕は考えています。現在のような「オタク」の使われ方には、このテレビ経由で発生した意味合いだけのもの、そういったテレビ経由の意味合いに対するコミケ側の反応を含み込んだもの、こうして意味が多様化してしまった結果として「自分もまたオタクなのではないか」と思うようになった人たちが勝手に付与し出した意味などが、それぞれ勝手に発達したり、あちこちで結びついたりしているのです。
さて、前回も紹介しましたように1970年代から1980年代にかけてコミケが大きく成長しました。テレビアニメやマンガといった、中毒性の高い対象に没頭する若者が増え出したということです。「中毒性」と書いたのには、いくつかの理由があります。テレビアニメやマンガは、連続したストーリーを安く定期的に広範囲に提供するものです。学校や近所中で、あるいは地方を超えて、同年代なら誰でも話が通じ、いつでも話題が提供されていたのです。アニメを見始めたりマンガ雑誌を読み始め、そういった話題を共有する友達を見つけてしまうと、仲間全員が一斉にアニメ断ちやマンガ断ちをしない限り、あるストーリーが終わったら別のストーリー、といった流れでズルズルと消費し続けてしまうわけです。これをもって中毒性という表現を理解してくれれば取り敢えずは充分です。
で、こういった現象と宮崎勤事件とを結び付けた人たちがいたのではないかというのが僕の「オタク論」の重要な仮説の1つです。テレビで発言できる人たちというのは、1960年代にテレビが普及する過程で成人したような人たちであり、上記のような「中毒性」に対して批判的である場合が多かったのではないでしょうか。彼らにとっては、スポーツをし、勉強をして、太平洋戦争に敗れ中空状態になったアイデンティティを埋めるのが最重要項目であった、と僕は考えています(全員が全員、そうであったと乱暴なことは言えませんが)。「小説はオトナが読むもの、マンガは子供が読むもの」という認識がこの世代の特徴です。彼らの前の世代は「小説ばかり読んで勉強しないのはダメだ」と言っていたらしいのですが。
子供からオトナへと成長しなければならないのに、こともあろうにマンガやテレビマンガ(アニメは昔このように呼ばれていました。彼らは1970年代に普及し、爆発的な人気を得たテレビゲームに対しても同様の印象を持っていたのではないかと思います)に熱中して、社会貢献をしない若者が増えている。これがテレビで発言するオトナたちの感じていた危惧だったのではないでしょうか。そんなところに宮崎勤事件が起きました。それみたことか、やはり「最近の若者」はこんなになっているぞ、と報道関係者は躍り上がって喜んだのではないでしょうか。いつだってオトナは「最近の若者は・・・」と苦言を呈したいし、そういう苦言を聞きたいと思っているのでそういうオトナを歓迎するのです。
もう僕が今回言いたいことはおわかり頂けたと思います。もっとも、それだけで「オタク」ということばが成り立っているとは誰も思わないでしょう。今回(と前回)書いたことは「オタクはダメなやつである」というレッテルの「背景」です。次回以降は、「オタクの自己満足」というもっとも重大なテーマについて解説していきたいと思います。次回の話は、今まで他の人たちが語ってきた「オタク論」でも扱われてきたテーマです。それだけじゃ全然ダメだと思うのでこうやって前置きめいたことを長々書くわけですが。
2004年07月25日
17:56 ナガタ
オタク論(3)
オタクの自己満足
こんばんわ。ナガタです。とうとうファンを名乗るかたが現れました。さいきん新人として採用されたひとです。何を考えているんでしょうか。正気の沙汰とは思えません。どうしたら良いのか正直困惑しています。怖いのであまりカカワリアイになりたくないです(嘘)。でもファンレターはまだ届きません。誰でも良いからはやく送ってくれ。宛先はこちら……いや、めんどうだからもう書きません。nagata@nzm.jp
さて今回はとうとうオタク論も山場です。今回僕が書こうとしていることは、様々なひとたちの手によって既に出版されたりウェブ上にアップされたりしてきたいわゆる「オタク論」とかさなるところの大きいものになるだろうと思われます。それでもなお、今回またそれを書こうとしていることの理由は、いままで論じてきた2点と、今回扱う「自己満足」の問題とをきちんと結び付けて論じているものを僕がいまだかつて見たことがないからです。えーと、嘘です。正確に言うと、ちょっとしか見たことがなく、それもまだ不十分だと思われるからです。
このコラムでオタク論を始めたとき、「オタクには、大工には大工の専門用語があるように、オタクならではの共通語がある」というようなことを書きました。これはある意味で正しく、ある意味では正しくありません。どこがどう正しくないのかと言うと、大工さんは家を建てる、という仕事のために専門用語を発展させてきたわけですが、オタクの専門用語は、家を建てるための専門用語と比べるとだいぶ有用性の低いものなのです。その意味では、大工の専門用語とオタクの専門用語とは性格が異なっているんです。もっとも、オタクは夢や快楽の分野で非常に興味深い成果を挙げているので、夢や快楽の意義を知っている人からすればオタクの専門用語というのもけっして無駄な存在ではないのですが、もっと直接的で単純な夢や快楽で事足りるひとたち(こういったひとたちは、一般的に複雑で韜晦した夢や快楽を追い求める人達よりも相対数が常に多いわけですが)にとって、オタクというのはまったく無駄な存在、ときには有害だったり邪魔だったりする存在だと言って問題ないでしょう。家というのは、現代社会においては、大多数に必要とされるものですし、すくなくともその「意義」というのが明確なものなわけです。
ではオタクの夢や快楽というのは、どういう「意義」があるのでしょうか。これが、そのスジのひとたちにはすっかり耳タコな話なのですが、「オタクというのは、一部にしか通用しない意義を大事にし、それを発展させていこうとしている」わけです。ここで言う「一部」というのが、例えば学会や研究者仲間であったりすればオタクとは呼ばれず学者と呼ばれるだろうし、例えば展覧会や藝術家仲間であればオタクとは呼ばれずアーティストと呼ばれるだろうし、ファンや音楽仲間であればオタクとは呼ばれず音楽家と呼ばれるわけです。要するに、オタクというのは、自分や自分が愛好するものが「誰に」「どこで」評価されているのかハッキリしないひとたちを指すものだと言えるでしょう。もっとも、オタクたち自身は自分や自分が愛好するものが誰に何処で評価されているか、だいたい把握しているはずです。オタクという呼称にとって大事なのは、その「だれ」「どこ」というのが謎や無気味さを孕んでいる、ということです。「世間的に言ってどうやら怪しいらしい」というニュアンスが含まれるような「だれか」によって「どこか」で評価されることを目指す人達、それがいわばオタクなのだと言える、と僕は考えています。
ここまで書けば、過去にこのコラムに僕が書いてきたこと、すなわち、オタクは独自のコミュニケーションツールを用いることで独特の種族として自律し、マスメディアから白眼視されることで自他ともに認める「あやしい」存在となり、テクノロジーの発達によって出現した新しい市場の需要と供給を同時に満たすことで経済的にも自律してきた、ということと、今回取り上げる「自己満足」とが密接に結び付いていることが理解されるのではないかと思います。
自覚的でないオタクは、歴史的にどうしてオタクが差別されるのかを知らず、自分が使っていることばに専門用語が多く含まれていることにすら気付かず、非オタクな人とのコミュニケーションや、違う分野を専門にしている別のオタクとのコミュニケーションなどを上手に行うことができないのにも関わらず、しかし不特定多数が消費している夢や快楽を自分もまた評価することができて消費することができているということについてアイデンティティやプライドを持ったりしていると言えるでしょう。ただ、不特定多数にも色んなレベルがあって、非オタクが消費したり評価したりしてアイデンティティを獲得するような対象(スポーツや、雑誌や新聞などのマスカルチャー)が抱えている消費者の数と比べると10分の1から100分の1、下手をすると1000分の1とか10000分の1くらいの人数しか無い場合があります。オタクに限らず、「不特定多数」として認識できる人数というのは、例えば「100人以上」とかそういう認識の仕方なので、150人も不特定多数だし、100万人も不特定多数ということになるわけですね。150人と100万人とを比べたら、それはもちろん比べ物にならないと思えるわけですが、不特定多数同士だったら同じことですから。こういう「地に足の付かない勘定」というのもある種、オタクに共通する感覚だと言えないことは無いはずです。
さて、限られたスペースで、ダラダラと進めてきたこの「オタク論」ですが、今回をもちまして、一応最終回とさせて頂こうと思います。まとめながら話を進めたことで、当初考えていたよりもだいぶ絞った内容になって、書き始めたときよりも自分自身、見えるようになったものが多かったように思います。もっとも、書きこぼしたこともたくさんあって、またいつかどこかで、もっときちんと書き直したいと思っています。本論が、オタクに対する無用の誤解(そんなものがあるかどうかわからないのですが)を回避する助けになったら良いなあ。次回は、これまでの流れを踏まえて、僕が推薦するオタクカルチャーの果実を紹介したいと思います。いま考えているのは、佐藤友哉という若手小説家、フリクリというアニメ、そして『アフタヌーン』というマンガ雑誌です。←追加したり変更したりするかもしれませんけど。
『オタク論』を終えて
番外編―オタク的なものの果実たち―
前回までダラダラと「オタクとは何か」ということについて論じてきたわけなのですが、ファンレターはともかく、これといった批判の声も聞こえてこず、それはそれで不安になったので、機会をみて何人かに意見を求めたことがあります。そうしていると、特に年長のかたから「いまさらオタクを取り上げて論じることにこれといった意義を感じない」といったご指摘を賜ることがありました。10年以上前に「オタク論」というのは出尽くしてしまったのではないか、いまはもっと取り上げるに足る対象があるのではないか、ということだったと、僕はいただいた指摘をそう受け止めました。僕がいままでやろうとしてきたことは、オタク論を自分の知っている限りの狭い範囲のなかではあるけれども簡単にまとめ、いままでオタク論に興味を持っていなかった人達にも読みやすいものとして再提示しようというものでもあったので、「既に出尽くしている」という指摘は適当なものではなかったと思います。もっとも、字数は多くなってしまったし、書きクチも堅かったので、その目標は達成できたとは言いにくいのですが。また、「取り上げるに足る、もっとほかの対象があったのではないか」ということについては、それは本当に必要ならば誰かがきっと他の場所で取り上げてくれるだろうし、僕には僕なりの必然性があったわけで、これもきちんと応えるのは難しい指摘でした。逆を言えば、この指摘は、僕なりの必然性というのをきちんと記述出来なかったことを批判したものだったわけですから。既に以前までの回で書いたつもりになっていましたが、僕がこのコラムで「オタク論」を書いてきたのは、「自分はオタクかもしれない」と思っている人たちが読んで何らかの力や支えとして機能してくれたら嬉しいなと思っているからです。無用な自嘲はもったいないし、そのもったいなさに耐え切れずに、単純な自己肯定に走ってしまったらもっともったいない。それこそ「オタクであること」あるいは「オタク的な要素を持っていること」の価値や可能性を忘れてしまっていると思うんです。
で、そんなわけで、今回は僕が考えるオタク的な素敵文化の結晶をいくつかご紹介しようと思っていたのですが、字数の都合上、前回挙げた3つ(佐藤友哉、『フリクリ』、『アフタヌーン』)のうち、佐藤友哉だけを取り上げることにしました。理由というか言い訳としては、アニメやマンガはまあ手に取って再生するなりパラパラとめくるなりしてもらえればだいたいの感じはわかってもらえるし、そもそも『フリクリ』も『アフタヌーン』もしばらくは大手のアニメやマンガ取り扱い店の店先に並び続けるだろうと思われる「メジャー」の商品なので、そういうのに興味がある人はまあ、どうぞご勝手に手を差し伸べてその世界に触れてみて下さいって感じです。必要とされる勇気は、それらを手にとってレジに運ぶだけ。他方、佐藤友哉っていう若手作家の小説はどうか。これが微妙に入手困難で、しかもほとんど文字ばかりなので、いまいち手を出せない人というのが大量に存在している気がするんですね。そもそも『フリクリ』『アフタヌーン』と比べると圧倒的に知名度が低いと思われるわけで。佐藤友哉に触れたいと思ったら、書店をいくつか廻り、店員に問い合わせるくらいの興味が必要になるわけです。僕はそれを喚起したい。
さて、その佐藤友哉ですが、生まれはなんと1980年。僕よりも若い。もっとも、彼の周辺、あるいは彼の読者が読む他の作家達には、更に若い人もいるのでこれしきのことで驚いていてはいけません(例えば2002年に立命館大学在学中に佐藤友哉と同じメフィスト賞を受賞してデビューし、佐藤友哉の作品でもしばしば言及される西尾維新は1981年生まれ)。佐藤友哉がデビューするきっかけとなったメフィスト賞というのは、講談社発行のミステリ小説誌「メフィスト」の新人賞で、最初の受賞者に森博嗣、佐藤友哉が受賞する少し前にのちの三島賞作家である舞城王太郎を輩出する、イロモノ作家選出機関のようなものです。ミステリー小説という形式をとっていればあとはなにをやっても良い、面白ければなんでもアリ、という乱暴な説明でこの新人賞の解説はほとんど足りてしまう。ほとんどの作品が語り口は柔らかく、肝心の謎解きは崩壊寸前、もしくは崩壊してしまい、その崩壊の収拾の付け方でもって面白さを生み出すような、そんな、文学としては外道な作品ばかりの賞です(文学って何か、という批判的な機能も担ってると言えるわけですが)。佐藤友哉という小説家はそんな変な賞を受賞してデビューしたのです。
私見では、佐藤友哉は歴代のメフィスト賞受賞者のそうそうたる変態たちと比べても特別「変」です。他の作家が単に思考のアクロバットが鮮やかだったり、イビツ過ぎたりするのに対して、佐藤友哉の「変」さは、鮮やかでイビツな思考ゲームももちろん冴えているのだけれど、それ以上に、異常なほど「青臭さ」にこだわっているところにあります。
ただ青臭いだけの作家はそこここに溢れ返っているし、文学的なテーマとしてある程度普遍性のある「青臭さ」を選ぶ作家も多く存在しているけれど、佐藤友哉のこだわりとそれらとを混同されては困ります(誰が?)。佐藤友哉には「普遍的なテーマ」なんか存在しない。彼はごく個人的な世界観しか持とうとしません。わかったふりをしてわかってるみたいに見られるのではなくて、わかった振りをして見せることでわかっていないことを見せる、そんなノーガード戦法で挑んでくるわけです。だから彼は青臭いのですが、かといって自分のことばかり書くわけじゃない。むしろ自分のことはあまり書きたくないみたいで、多くの個性的な登場人物たちのさまざまな目線で物語を丹念に紡いでいく。にも関わらず、どこかから「物語」と「現実」との境界を突き破って作家本人が作品内に現れ出てしまう。そんなことしなければ「よくできた思考ゲーム」として小説は完結できるのに、そこに自分を登場させてしまうことで、自意識の強い、納まりのつきにくい気持ち悪い作品が出来上がってしまうのです。有名な作品を喩えに使って説明するなら、『ネバーエンディングストーリー(果てしない物語)』の主人公と作者とが同一人物であった、とか、『不思議の国のアリス』が実在の少女の妄想の克明な記録であった、とか、『ゴーマニズム宣言』や『華氏911』がまったくのフィクション(作り話)でした、とかいった場合の居心地の悪さ、ブキミさ。うまく喩えられた気がしません。わからなくてもあなたが悪いんじゃないですよ。僕が悪いんです。ごめんなさい。
もっとも、作者が作中に登場して愚痴を言ったり冒険してみたり、というのはいままでの文学やらマンガやらアニメやら、映画や音楽や絵画ですらも、使い古されてしまっていて今さら珍しい手法ではありませんね。それこそ、映画などの動画技術が発明されるまでは「すべての藝術の発端であり、完成形である」と言われていた演劇の本来の姿は、作者自身が舞台の上で虚実織りまぜて語ったことだったとも言えます。佐藤友哉はある意味で古典的な方法を現代に復活させているわけだ。だから安直なやり方であったなら、佐藤友哉以外の多くのキワモノ狙いのミステリー作家達が陥ったように、凡庸な曲芸にしかならなかった筈です。僕が佐藤友哉が凄い、と言うのは、そういった凡庸な曲芸が目新しくて喜んでいるからではありません。そもそも目新しさに喝采を送るほど、僕はたくさん本を読んでいませんしね(笑)。
佐藤友哉が面白いのは、舞城王太郎や西尾維新や清涼院流水(メフィスト賞の第2回目の受賞者)のような破天荒な物語設定や話の展開のはしばしに、執拗に、「リアル」な生きる苦しみ、締念、後悔、暗い欲動が深く刻み込まれているところです。問題はこの「リアル」っていうところ。僕にはまったく「リアル」ではないけれど、いま戦時下にある地域に暮らす人々にとってはいつ頭の上から爆弾が降ってきて、一生消えない傷を自分や家族が負うかもしれない、ということが「リアル」だろうし、僕にはまったく「リアル」ではありませんが、お父さんが一人ずつみんな違う兄弟がお母さんに捨てられて戸籍ももたずに生きたり死んだりする「リアル」もあるかも知れません。僕の「リアル」は読者であるあなたの「リアル」と色んな点で少しずつズレていて、ときにはまったく食い違っているかもしれない。文学というのはそういったズレが取りこぼしてしまうモノをなんとかして「リアル」に書き記すことが出来るものなわけなのですが、佐藤友哉は「果たして文学にそんなことができるのだろうか?」もしくは「果たして自分にそんなことをする才能はあるのだろうか?」というのをまさに紙上で実験しているかのような緊張感を持っているのです。いちファンとして僕は「文学はどうか知らないが、佐藤くん、あんたはそんなことする才能があるよ!」と言ってあげたいのですが、そういった声にはすぐ作品中から「だったらどうして僕の作品は売れないんだ!」「みんなうすら甘い優しい嘘ばかり求めていやがる」「オレもそんなうすら甘い優しい嘘をつきたいよ」「くそう!オレの嘘つき!けがらわしい!こんなオレに騙されるお前はバカだ」「こんなバカを相手にしてるオレもバカだ!」っていう叫びが聞こえてきます。ちょっと過激なんですが、ビビッドであることは悪いことではないと思うので、その点は取り敢えず突っ込まないでおきましょう。
さて、本稿はもともとは「オタク的なものの果実」として佐藤友哉を紹介しようとするものなのですが、僕にとっては、佐藤友哉のこの過激で泥沼化した自己批判がまさに「オタク的」だと思えるのです。普通の、オタク的でないような作品なら、「果たして文学には○○が可能だろうか」「果たして私には○○ができるだろうか」という問いに対して「よし、やってみよう」「はい、できました」というスタンスのものしかないと思うんです。佐藤友哉は「よし、やってみるけど、どうなっても知らないからな」「こんなの出来ちゃったけど、オレがつくりたかったのはこんなんじゃないんだ」「でも売れないと困るし、オレ、小説書くしかできないし、面白いって言ってくれる人がいるから」とか言い訳だらけ。甘えるんじゃない!と一喝できたらすっきりさわやかなのですが、そんなデリカシーのない態度では絶対に掬いきれない何かに佐藤友哉の作品は到達しえていると思うんですよ、僕は。だから、彼は面白い作品を書いている間は甘えてて良いと思う。それに彼は彼なりに甘えた振りをしながら、実は甘えることが出来ないっていうことを体現しているんだと思います。
ということで、みなさん佐藤友哉の作品を買って下さい。初心者にお薦めは『クリスマス・テロル』(表紙裏に「犯人は、読者です」っていきなりタネ明かしが。でも読者が犯人ってどういうことなんでしょうね!ちなみに僕が読んだときは本当に僕が犯人でした)が短くてコンパクトで、装釘も仰々しくて良いかと思います。もう少しレベルが高い人には『エナメルを塗った魂の比重』がお薦め。「気合いがあれば一日で読める」というくらい分厚いですが、頑張って読むに値する複雑さ&爽やかで胸に突き刺さるエンディング。なお、個人的には3号まで発行された思想誌「新現実」に連載の『世界の終わりの終わり』が好きです。まだ最終話読んでないけど。ちなみにこの「新現実」っていう雑誌も変なので、探してみて下さい。見つけたら怪しい表紙に臆することなく、どうぞ気合い入れて購入してみて下さい。すぐに読まなくても持ってればそのうち読むかも知れないし。
|
|
|
|
コメント(6)
以下はナガタさん私が送った感想文と、それに対するナガタさんのレスです。
読みました。
では、感想です。まず全体として
「コミュニケーション不全症候群(by中島梓)」としてのおたく(大塚英志がこだわる)いわばオタクのネガ部分を今(さら)扱っているという点で面白かったです。
最近「オタク・日本・ポップ」を中心に頭が回っていたので、このような今日メディア的に面白くない、「下からのオタク論」の重要性を改めて思い起こすきっかけとなりました。
確かに、PS2のゲームや少年ジャンプが完全にポピュラリティを持ち文化庁がアニメーション支援を打ち出し、東浩紀がギャルゲー批評しているのにもかかわらず、というよりはそれとは別にオタクは気持ち悪いものであり続けています。
それが、オタクの態度、服装、言動、趣味嗜好、もっと構造的なものの何に由来するのかはわかりません。個人的には趣味嗜好、特に性的ないし性不全的なそれと考えていますが完全に仮定段階です。
ナガタさんはオタクの評価体系の不確かさ、曖昧さをあげていますが、一理あると思います。
独自の評価体系、技術、文化を持つマイノリティ(知恵のついた弱者)は自らを権威付けしようとします。あるいはオーソリティだからこそ、独自の評価体系をもちます。それが学者、評論家、藝術家などといえます。権威付けの例としてはルネサンス期の画家があげられるでしょう。下賤な肉体労働から高い精神性を持った自由学芸へのそれです。
しかし、オタクは評価体系を作り、ネットや同人誌などで共有することだけで満足します。世間に自らの価値観を認めさせようとする努力はしません。ナガタさんが指摘なさる自己満足です。これが本来的なオタクというよりマイナーな趣味人一般のあり方なのかもしれません。オタクの場合、評価体系の共有へ向かう情熱が半端じゃないしそれがオタクがオタクたる所以の一つですが。
ただ、オタクは世間へ価値観をしらしめるのに無頓着といっても例外があります。それも重要な例外です。岡田斗司夫のように自らを日本の伝統文化の正当な継承者とする権威化です。他の趣味嗜好をともにする集団には決してみられない権威化だと私は思います。
(面白いのは岡田斗司夫がそれに加え、ナガタさんの指摘する「中毒」ではなく、批評眼という理性活動でアニメなどを見ていることを強調する点です。)
権威付けではないにせよ学者、文化人による90年代的オタク論はオタク・日本という視点を少なからず持っているように思います。
「宇宙戦艦ヤマト」「愛国戦隊大日本」などオタクは「日本」へのベクトルを多分に含んでいる。それがどんな日本なのか、それとオタク特有の気持ち悪さとどう絡んでくるのか、両者は無関係ではないとおもいます。
今回のヴェネツィアビエンナーレではある意味オタクの文化構造と呼べるものがそのまま日本代表として出品されます。「気持ち悪さ」がどの程度「世界」に伝わるのかわからないし、オタクが日本代表になってしまっていいのかとも思うし、ともすれば「気持ち悪さ」への無反省を生み出しかねない、大変に危ういものだと思うのですが、やる価値はあると思うし、見守りたいと思います。
話がそれました。
他の方のコメントでは「地方とサイレントマジョリティ」「オタクの性(不全)」の話題に興味を持ちました。
特に前者ですね。田舎でオタクは生き残れない。僕の友人は元オタクの大学中退者で、田舎に帰って家業を継いだのですが、今は立派なオヤジヤングです。やはり彼もオタクのままでは生きられず、適応したのでしょう。もっとも、3年の大学での寮生活がその素地を作ったおかげで適応できたと思われますが。
それに対するナガタさんのレス
> 感想の前に、この文章をリンクではなく、そのまま転載してコミュのトピックにしたいのですが、よろしいでしょうか?そもそもの発端だし、示唆を含んだものですので。
そうしていただけると助かります。
あれだけの量のやりとりをどれだけのひとが読むか興味深いです(笑)
オタク論については、ミクシー日記で書いたものの更に叩き台(というか、予備論というか、、、)を去年の10月にはてなダイアリーの方に書いていまして、実はそっちはミクシー日記で指摘されていたセクシャリティーの問題、それから、内容のシビアさが原因で指摘するのを避けていた教育制度と経済の問題から言及していて、自分でいうのもなんですが、ちょっと面白いと思います。
> では、感想です。まず全体として
> 「コミュニケーション不全症候群(by中島梓)」としてのおたく(大塚英志がこだわる)いわばオタクのネガ部分を今(さら)扱っているという点で面白かったです。
> 最近「オタク・日本・ポップ」を中心に頭が回っていたので、このような今日メディア的に面白くない、「下からのオタク論」の重要性を改めて思い起こすきっかけとなりました。
> 確かに、PS2のゲームや少年ジャンプが完全にポピュラリティを持ち文化庁がアニメーション支援を打ち出し、東浩紀がギャルゲー批評しているのにもかかわらず、というよりはそれとは別にオタクは気持ち悪いものであり続けています。
そうですね。「それとは別に」というのは大事なことだと思います。分裂してしまっている。語り方として、あるいはなんらかの在り方として、「オタク」的なものの状況が分裂しているわけで。画一的なものとして語ってしまっては取りこぼしてしまうものがとても多いのではないかと思います。オタクが全体的にどうであるか、ということよりも、オタクが依然担いがち(「がち」でなくても構わないのですが、つまり、オタクが依然、ときに担うような、という感じでも構わないということですけど)な気持ち悪さ、というのに取り敢えず焦点を当てたかったわけです。これはご指摘の通りメディア的に美味しくないわけです。流行としては。ただ、だからこそ、というニュアンスも含めつつ言いたいのですけども、言及し問題にする価値がある、と思うわけです。
> それが、オタクの態度、服装、言動、趣味嗜好、もっと構造的なものの何に由来するのかはわかりません。個人的には趣味嗜好、特に性的ないし性不全的なそれと考えていますが完全に仮定段階です。
これについての議論は多岐にわたって面白いものになりそうですね。是非コミュニティで他の人を交えながら議論したいところです。そうだ、このメールのやりとりも基本的にはプライベートな議論というわけではないので、田中さんさえよければ公開してくださって結構ですよ。
『評価体系」については、ニューアカの流行に象徴されるような一連の評価留保の動向が背景にあると思います。非オタクが「評価留保」という流行が過ぎ去ったあと、天然な評価が支持されるような風潮がマスメディアで復活して、それにならって天然評価をするようになる一方で、オタクたちは律儀に、80年代的な評価軸を尊重していたのではないかと思われます。ただし、ここでいう「オタク」というのは実はイメージの比較的大きな部分を占めているというだけの集団であって、比較的古い世代(岡田トシオの属するような)や、比較的新しい世代(東浩紀以降の世代)や、女性を中心とした一群はこの場合の「オタク」に含み小無事が出来ないと思います(相互に影響を与え合っているとは当然みなせるわけですが)。ここでいうような「オタク」ではないようなオタクたちはむしろ、ヒステリックなほどに評価を絶対視する傾向すらあるように思われます。また、言うなれば、80年代的な評価保留というのも、ある意味での権威付けのつもりなのかも知れないですね。
> しかし、オタクは評価体系を作り、ネットや同人誌などで共有することだけで満足します。世間に自らの価値観を認めさせようとする努力はしません。ナガタさんが指摘なさる自己満足です。これが本来的なオタクというよりマイナーな趣味人一般のあり方なのかもしれません。オタクの場合、評価体系の共有へ向かう情熱が半端じゃないしそれがオタクがオタクたる所以の一つですが。
「世間に自らの価値観を認めさせようとする努力をしない」のが自己満足なのではなく、「自分たちには自分たちの世間や歴史がある、ということに安住し、外と価値観を共有しない」という考え方が自己満足だと思うんです。言うなれば、価値観共同体みたいなもので連帯し内在し(外部を排他的に眺め)得る事を自己満足と言ってみました。メンタリティーとしては、ほかの条件(コミュニケーション能力の不足、歴史的なレッテル)が揃わなければ、非オタクも充分持ちうる性格だと思います。
> ただ、オタクは世間へ価値観をしらしめるのに無頓着といっても例外があります。それも重要な例外です。岡田斗司夫のように自らを日本の伝統文化の正当な継承者とする権威化です。他の趣味嗜好をともにする集団には決してみられない権威化だと私は思います。
> (面白いのは岡田斗司夫がそれに加え、ナガタさんの指摘する「中毒」ではなく、批評眼という理性活動でアニメなどを見ていることを強調する点です。)
> 権威付けではないにせよ学者、文化人による90年代的オタク論はオタク・日本という視点を少なからず持っているように思います。
高度経済成長の背後にナショナリズムの残滓が根強く生き続けていた事の証明のような事例だというだけで、あとはそれを継承するか否かという問題でしかないと思います。岡田トシオというひとは、僕の知る限りでは生真面目な(=タフでない)勉強家でしかなく、自説を裏付けるものであればなんでも援用しようとしてしまう。歴史的な権威の威を借りること自体は、僕の言う意味での「自己満足」とは基本的に矛盾しないと思います。
岡田トシオたちが権威を利用して獲得しようとしたのは、恐らく80年代以降の「オタク=かっこわるい」という、僕の説で言うところの「コミュニケーション能力の不足、歴史的なレッテル」の否定だと思うのですが、僕にしてみればそれは、マスメディアの力を甘く見た、ミスリーディングで愚かな考えでしかありません。もっとも僕が重視しているのは歴史的なレッテルとしての『オタク』です。岡田トシオのおかげで、「オタク」にもポジティブなイメージが附随している事は否定しませんが、しかし岡田トシオ一派のようなごく一部の親オタク勢よりもはるかに影響力の強い、無名の多数派によって、オタクのマイナスイメージは流布され流通してしまっているわけです。むしろ現実のオタクの多くは、岡田的なポジティブなオタクイメージをある種の理想として抱きながら、広く薄く流布し流通しているマイナスイメージもまたしかたないもの、受け入れざるを得ないものとして背負っていると思うんです。
悲観的な周囲の状況があって、その状況からあたかも夢を観るような気持ちで理想を抱く。というのはまったくナショナリズムの神髄のようなもので、そんな精神性とナショナリスティックな諸々の親和性はきわめて高い。というかそのまんまなんですね。そのまんまナショナリズムです。批評とナショナリズムとの関係は極めて微妙なわけで、岡田トシオ的な批評を批評と呼んでしまって良いのかは、ちょっと僕としては一概に言えないです。
だからアートとオタクとの関係は物凄く面白い。オタクと文学も極めて面白い。オタクと思想の問題も凄く面白いと思います。僕はオタクが日本代表になっても良いと思います。ただ、その際の「日本」というのは「オタク」から逆算されるような、ヒビや気持ち悪さも踏まえたデスでポップなものでなければならず、いわゆる回顧的な「日本」を温存しているものとして「オタク」がある、と考えてはならないと思います。「考えてはならない」というと高圧的ですね。、、、「そう考えたら間違っている」というか、そのような「オタク」はごく一部の異形のものだと思うんですね。限られた可能性しかないというか。
読みました。
では、感想です。まず全体として
「コミュニケーション不全症候群(by中島梓)」としてのおたく(大塚英志がこだわる)いわばオタクのネガ部分を今(さら)扱っているという点で面白かったです。
最近「オタク・日本・ポップ」を中心に頭が回っていたので、このような今日メディア的に面白くない、「下からのオタク論」の重要性を改めて思い起こすきっかけとなりました。
確かに、PS2のゲームや少年ジャンプが完全にポピュラリティを持ち文化庁がアニメーション支援を打ち出し、東浩紀がギャルゲー批評しているのにもかかわらず、というよりはそれとは別にオタクは気持ち悪いものであり続けています。
それが、オタクの態度、服装、言動、趣味嗜好、もっと構造的なものの何に由来するのかはわかりません。個人的には趣味嗜好、特に性的ないし性不全的なそれと考えていますが完全に仮定段階です。
ナガタさんはオタクの評価体系の不確かさ、曖昧さをあげていますが、一理あると思います。
独自の評価体系、技術、文化を持つマイノリティ(知恵のついた弱者)は自らを権威付けしようとします。あるいはオーソリティだからこそ、独自の評価体系をもちます。それが学者、評論家、藝術家などといえます。権威付けの例としてはルネサンス期の画家があげられるでしょう。下賤な肉体労働から高い精神性を持った自由学芸へのそれです。
しかし、オタクは評価体系を作り、ネットや同人誌などで共有することだけで満足します。世間に自らの価値観を認めさせようとする努力はしません。ナガタさんが指摘なさる自己満足です。これが本来的なオタクというよりマイナーな趣味人一般のあり方なのかもしれません。オタクの場合、評価体系の共有へ向かう情熱が半端じゃないしそれがオタクがオタクたる所以の一つですが。
ただ、オタクは世間へ価値観をしらしめるのに無頓着といっても例外があります。それも重要な例外です。岡田斗司夫のように自らを日本の伝統文化の正当な継承者とする権威化です。他の趣味嗜好をともにする集団には決してみられない権威化だと私は思います。
(面白いのは岡田斗司夫がそれに加え、ナガタさんの指摘する「中毒」ではなく、批評眼という理性活動でアニメなどを見ていることを強調する点です。)
権威付けではないにせよ学者、文化人による90年代的オタク論はオタク・日本という視点を少なからず持っているように思います。
「宇宙戦艦ヤマト」「愛国戦隊大日本」などオタクは「日本」へのベクトルを多分に含んでいる。それがどんな日本なのか、それとオタク特有の気持ち悪さとどう絡んでくるのか、両者は無関係ではないとおもいます。
今回のヴェネツィアビエンナーレではある意味オタクの文化構造と呼べるものがそのまま日本代表として出品されます。「気持ち悪さ」がどの程度「世界」に伝わるのかわからないし、オタクが日本代表になってしまっていいのかとも思うし、ともすれば「気持ち悪さ」への無反省を生み出しかねない、大変に危ういものだと思うのですが、やる価値はあると思うし、見守りたいと思います。
話がそれました。
他の方のコメントでは「地方とサイレントマジョリティ」「オタクの性(不全)」の話題に興味を持ちました。
特に前者ですね。田舎でオタクは生き残れない。僕の友人は元オタクの大学中退者で、田舎に帰って家業を継いだのですが、今は立派なオヤジヤングです。やはり彼もオタクのままでは生きられず、適応したのでしょう。もっとも、3年の大学での寮生活がその素地を作ったおかげで適応できたと思われますが。
それに対するナガタさんのレス
> 感想の前に、この文章をリンクではなく、そのまま転載してコミュのトピックにしたいのですが、よろしいでしょうか?そもそもの発端だし、示唆を含んだものですので。
そうしていただけると助かります。
あれだけの量のやりとりをどれだけのひとが読むか興味深いです(笑)
オタク論については、ミクシー日記で書いたものの更に叩き台(というか、予備論というか、、、)を去年の10月にはてなダイアリーの方に書いていまして、実はそっちはミクシー日記で指摘されていたセクシャリティーの問題、それから、内容のシビアさが原因で指摘するのを避けていた教育制度と経済の問題から言及していて、自分でいうのもなんですが、ちょっと面白いと思います。
> では、感想です。まず全体として
> 「コミュニケーション不全症候群(by中島梓)」としてのおたく(大塚英志がこだわる)いわばオタクのネガ部分を今(さら)扱っているという点で面白かったです。
> 最近「オタク・日本・ポップ」を中心に頭が回っていたので、このような今日メディア的に面白くない、「下からのオタク論」の重要性を改めて思い起こすきっかけとなりました。
> 確かに、PS2のゲームや少年ジャンプが完全にポピュラリティを持ち文化庁がアニメーション支援を打ち出し、東浩紀がギャルゲー批評しているのにもかかわらず、というよりはそれとは別にオタクは気持ち悪いものであり続けています。
そうですね。「それとは別に」というのは大事なことだと思います。分裂してしまっている。語り方として、あるいはなんらかの在り方として、「オタク」的なものの状況が分裂しているわけで。画一的なものとして語ってしまっては取りこぼしてしまうものがとても多いのではないかと思います。オタクが全体的にどうであるか、ということよりも、オタクが依然担いがち(「がち」でなくても構わないのですが、つまり、オタクが依然、ときに担うような、という感じでも構わないということですけど)な気持ち悪さ、というのに取り敢えず焦点を当てたかったわけです。これはご指摘の通りメディア的に美味しくないわけです。流行としては。ただ、だからこそ、というニュアンスも含めつつ言いたいのですけども、言及し問題にする価値がある、と思うわけです。
> それが、オタクの態度、服装、言動、趣味嗜好、もっと構造的なものの何に由来するのかはわかりません。個人的には趣味嗜好、特に性的ないし性不全的なそれと考えていますが完全に仮定段階です。
これについての議論は多岐にわたって面白いものになりそうですね。是非コミュニティで他の人を交えながら議論したいところです。そうだ、このメールのやりとりも基本的にはプライベートな議論というわけではないので、田中さんさえよければ公開してくださって結構ですよ。
『評価体系」については、ニューアカの流行に象徴されるような一連の評価留保の動向が背景にあると思います。非オタクが「評価留保」という流行が過ぎ去ったあと、天然な評価が支持されるような風潮がマスメディアで復活して、それにならって天然評価をするようになる一方で、オタクたちは律儀に、80年代的な評価軸を尊重していたのではないかと思われます。ただし、ここでいう「オタク」というのは実はイメージの比較的大きな部分を占めているというだけの集団であって、比較的古い世代(岡田トシオの属するような)や、比較的新しい世代(東浩紀以降の世代)や、女性を中心とした一群はこの場合の「オタク」に含み小無事が出来ないと思います(相互に影響を与え合っているとは当然みなせるわけですが)。ここでいうような「オタク」ではないようなオタクたちはむしろ、ヒステリックなほどに評価を絶対視する傾向すらあるように思われます。また、言うなれば、80年代的な評価保留というのも、ある意味での権威付けのつもりなのかも知れないですね。
> しかし、オタクは評価体系を作り、ネットや同人誌などで共有することだけで満足します。世間に自らの価値観を認めさせようとする努力はしません。ナガタさんが指摘なさる自己満足です。これが本来的なオタクというよりマイナーな趣味人一般のあり方なのかもしれません。オタクの場合、評価体系の共有へ向かう情熱が半端じゃないしそれがオタクがオタクたる所以の一つですが。
「世間に自らの価値観を認めさせようとする努力をしない」のが自己満足なのではなく、「自分たちには自分たちの世間や歴史がある、ということに安住し、外と価値観を共有しない」という考え方が自己満足だと思うんです。言うなれば、価値観共同体みたいなもので連帯し内在し(外部を排他的に眺め)得る事を自己満足と言ってみました。メンタリティーとしては、ほかの条件(コミュニケーション能力の不足、歴史的なレッテル)が揃わなければ、非オタクも充分持ちうる性格だと思います。
> ただ、オタクは世間へ価値観をしらしめるのに無頓着といっても例外があります。それも重要な例外です。岡田斗司夫のように自らを日本の伝統文化の正当な継承者とする権威化です。他の趣味嗜好をともにする集団には決してみられない権威化だと私は思います。
> (面白いのは岡田斗司夫がそれに加え、ナガタさんの指摘する「中毒」ではなく、批評眼という理性活動でアニメなどを見ていることを強調する点です。)
> 権威付けではないにせよ学者、文化人による90年代的オタク論はオタク・日本という視点を少なからず持っているように思います。
高度経済成長の背後にナショナリズムの残滓が根強く生き続けていた事の証明のような事例だというだけで、あとはそれを継承するか否かという問題でしかないと思います。岡田トシオというひとは、僕の知る限りでは生真面目な(=タフでない)勉強家でしかなく、自説を裏付けるものであればなんでも援用しようとしてしまう。歴史的な権威の威を借りること自体は、僕の言う意味での「自己満足」とは基本的に矛盾しないと思います。
岡田トシオたちが権威を利用して獲得しようとしたのは、恐らく80年代以降の「オタク=かっこわるい」という、僕の説で言うところの「コミュニケーション能力の不足、歴史的なレッテル」の否定だと思うのですが、僕にしてみればそれは、マスメディアの力を甘く見た、ミスリーディングで愚かな考えでしかありません。もっとも僕が重視しているのは歴史的なレッテルとしての『オタク』です。岡田トシオのおかげで、「オタク」にもポジティブなイメージが附随している事は否定しませんが、しかし岡田トシオ一派のようなごく一部の親オタク勢よりもはるかに影響力の強い、無名の多数派によって、オタクのマイナスイメージは流布され流通してしまっているわけです。むしろ現実のオタクの多くは、岡田的なポジティブなオタクイメージをある種の理想として抱きながら、広く薄く流布し流通しているマイナスイメージもまたしかたないもの、受け入れざるを得ないものとして背負っていると思うんです。
悲観的な周囲の状況があって、その状況からあたかも夢を観るような気持ちで理想を抱く。というのはまったくナショナリズムの神髄のようなもので、そんな精神性とナショナリスティックな諸々の親和性はきわめて高い。というかそのまんまなんですね。そのまんまナショナリズムです。批評とナショナリズムとの関係は極めて微妙なわけで、岡田トシオ的な批評を批評と呼んでしまって良いのかは、ちょっと僕としては一概に言えないです。
だからアートとオタクとの関係は物凄く面白い。オタクと文学も極めて面白い。オタクと思想の問題も凄く面白いと思います。僕はオタクが日本代表になっても良いと思います。ただ、その際の「日本」というのは「オタク」から逆算されるような、ヒビや気持ち悪さも踏まえたデスでポップなものでなければならず、いわゆる回顧的な「日本」を温存しているものとして「オタク」がある、と考えてはならないと思います。「考えてはならない」というと高圧的ですね。、、、「そう考えたら間違っている」というか、そのような「オタク」はごく一部の異形のものだと思うんですね。限られた可能性しかないというか。
当時、コミケ等のイベント以外ではオタクという言葉をまだ聞かなかった時期に教えて貰った意味としては。
まずは、コミケ・コミックスクエアー(これはコミケから分裂した団体で、後に消滅してしまいました)等のスタッフがアダルト同人だけを買いあさる、夏はTシャツにジーンズ、冬はトレーナーにジーンズ、必ず紙袋をさげていて、アダルト同人に並んでる彼らを差す言葉として作られたそうです。なぜオタクとなったかというと、彼ら必ず「お宅、今日何買った?」と一人称代名詞にお宅と言う言葉を頻繁に使うので「あいつらはオタクだっ!」となったとあたしは聞かされました、まーそれはともかく、当時スタッフ等からアダルト同人をオタク本と称しそれらを他の創作や通常パロ本等々とを区分けし、侮蔑する言葉として使われていたのは確かです。また、ヤオイなども当時区別語として(やっぱり侮蔑だったんだろうなぁ)使われていましたね。この当時は、高河ゆん等が参加していた「きつねぷろじぇくと」が一般創作ながらアダルト同人を抜き売り上げ1位をほこっていた頃のお話しです。ところで他になんか説がでてるのですか?^^;
まずは、コミケ・コミックスクエアー(これはコミケから分裂した団体で、後に消滅してしまいました)等のスタッフがアダルト同人だけを買いあさる、夏はTシャツにジーンズ、冬はトレーナーにジーンズ、必ず紙袋をさげていて、アダルト同人に並んでる彼らを差す言葉として作られたそうです。なぜオタクとなったかというと、彼ら必ず「お宅、今日何買った?」と一人称代名詞にお宅と言う言葉を頻繁に使うので「あいつらはオタクだっ!」となったとあたしは聞かされました、まーそれはともかく、当時スタッフ等からアダルト同人をオタク本と称しそれらを他の創作や通常パロ本等々とを区分けし、侮蔑する言葉として使われていたのは確かです。また、ヤオイなども当時区別語として(やっぱり侮蔑だったんだろうなぁ)使われていましたね。この当時は、高河ゆん等が参加していた「きつねぷろじぇくと」が一般創作ながらアダルト同人を抜き売り上げ1位をほこっていた頃のお話しです。ところで他になんか説がでてるのですか?^^;
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
オタク論、「オタク論」論 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
オタク論、「オタク論」論のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 2位
- 広島東洋カープ
- 55343人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37148人
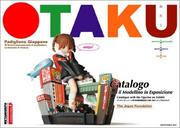


![[dir] オタク・ヲタク](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/55/59/335559_123s.jpg)




















