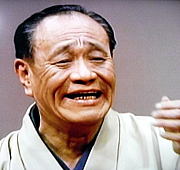六代目の持ちネタのひとつ『誉田屋』、あまり馴染みのないネタなんですが、、、ここではネタそのものの話ではなく、前から疑問に思ってたことを思いつくままに書かせていただきます。(長文御免)
===
去年大阪に帰ったときワッハ上方ライブラリで(今まで聴いたことの無かった)六代目の『誉田屋』を聴くことが出来ました。 いままで「こんだや」と読むんのだとばかり思っていたんですが、ワッハで聴くと六代目は「ほんだや」と言ってました。(今は、このネタを『紺田屋』という題で演じることも多いみたいです。)
# 噺の筋は、下記『世紀末亭』や二代目桂圓枝師匠の速記をごらんください。
さて、どっちが正しいんやろか?と前からずっと気になっていたんですが、手持ちの本やネットで調べてみました。
まず最初にチェックした(五代目・六代目の演題を集めた)「上方落語」(講談社)には『紺田屋(こんだや)』という演題で掲載されていて、ご丁寧に本文でもお店の主人は紺田屋忠兵衛と書かれています。速記もワッハで聴いた音源とは違っているところがあります。
次にネットで検索かけると、2種類の『誉田屋』の速記がみつかりました:
(a)(ワッハで聴いた音源と同じ)六代目の高座の速記:
http://
http://
(b) 二代目桂圓枝師匠の高座の速記:
http://
http://
(a)では六代目が「ほんだや」と読んでる筈なのに演題は「こんだや」となってますが、(b)では「ほんだや」となってます。
どうやら「こんだや」と読むようになったのは、米朝さんが『羽曳野にある「誉田」という地名が「こんだ」と呼ばれることから「ほんだや」ではなく「こんだや」と読むのが正しいのでは』と書かれていることからきているらしい。 更に、落語に出てくる『誉田屋(忠兵衛)』は京都・三条室町の縮緬問屋ですが、その三条室町に創業270年を数える「誉田屋(こんだや)源兵衛」という老舗の帯問屋があることも、「こんだや」と読ませる根拠を支持する材料になってるように思えます。
羽曳野にある誉田というところには「誉田(こんだ)山古墳」や「誉田(こんだ)八幡宮」があって、(私は知りませんでしたが)結構知名度が高いところだそうです。 誉田山古墳は別名「応神天皇陵」とも呼ばれていて、八幡神社の主祭神は応神天皇。 応神天皇は「誉田別尊(ほむだわけのみこと)」という別名を持つことから、その地が「誉田」と呼ばれるようになりました。 当時半島からの帰化人がその地に多く住んでいたことから、「ほむた」⇒「ほんだ」⇒「こんだ」と訛って変化し「こんだ」という地名となったという説がありますが、納得できます。 (は行とか行は、発声の仕方が非常に近いので、発音の入れ替えの例があります。)
ということは、「誉田」を「こんだ」と訛らずに「ほんだ」と読むところもあるのでは?と調べて見たところ、やはりありました。 兵庫県・たつの市と千葉県・習志野市に「誉田(ほんだ)」という地名があります。 千葉の誉田には「誉田(ほんだ)八幡神社」があります。ここは、大阪の陣のあと河内の住人が戦に負けて移住してきたところだそうで、幕末に羽曳野の誉田八幡宮から分祀して「誉田八幡神社」が出来ました。 (香川県東かがわ市にも分祀して設立された「誉田八幡神社」がありますが、こちらも「ほんだ」と呼びます。) たつの市の「誉田(ほんだ)」の由来は、不明です。
まぁ、こんなふうに「誉田」探しをしたからどうということは無いんですが、、、「ほんだ」と読むほうが普通みたいで、『縮緬問屋の「誉田屋」の命名が羽曳野の「誉田」にちなんだもの』というのは可能性のひとつにしか過ぎません。
六代目はこのネタを五代目か他の師匠から聴き覚えたんだろうと想像しますが、六代目が演じたように、二代目桂圓枝師匠の高座の速記にもあるように、もともとは「ほんだや」と言ったんだと思います。 「誉田」を「こんだ」と読むべしというのは決して自明のことでは無いですし、ましてそれを根拠に読み方のみならず漢字も「紺田屋」と変えてしまうのは、、、かなり乱暴なはなしですね。
あくまでも私の推測ですが、同じ三条室町に「誉田(こんだ)屋源兵衛」という老舗が実在するので、店が潰れてしまう「誉田屋忠兵衛」を「こんだや」とするのは差障りがあるとの配慮から「ほんだや」としたのではないかと・・・
旧い噺を一言一句変えずに演ずべし!などと云うつもりは毛頭ありませんし、時代の変化に応じて今風にアレンジするのも良いことだと思いますが、この「ほんだや」⇒「こんだや」(⇒「紺田屋」)に関してはいささか疑問に思います。
斯く云うわたしも、ワッハで六代目の「誉田屋(ほんだや)」を聴いていなかったら、「こんだや」と読むのをを信じて疑わなかったんですが。
===
去年大阪に帰ったときワッハ上方ライブラリで(今まで聴いたことの無かった)六代目の『誉田屋』を聴くことが出来ました。 いままで「こんだや」と読むんのだとばかり思っていたんですが、ワッハで聴くと六代目は「ほんだや」と言ってました。(今は、このネタを『紺田屋』という題で演じることも多いみたいです。)
# 噺の筋は、下記『世紀末亭』や二代目桂圓枝師匠の速記をごらんください。
さて、どっちが正しいんやろか?と前からずっと気になっていたんですが、手持ちの本やネットで調べてみました。
まず最初にチェックした(五代目・六代目の演題を集めた)「上方落語」(講談社)には『紺田屋(こんだや)』という演題で掲載されていて、ご丁寧に本文でもお店の主人は紺田屋忠兵衛と書かれています。速記もワッハで聴いた音源とは違っているところがあります。
次にネットで検索かけると、2種類の『誉田屋』の速記がみつかりました:
(a)(ワッハで聴いた音源と同じ)六代目の高座の速記:
http://
http://
(b) 二代目桂圓枝師匠の高座の速記:
http://
http://
(a)では六代目が「ほんだや」と読んでる筈なのに演題は「こんだや」となってますが、(b)では「ほんだや」となってます。
どうやら「こんだや」と読むようになったのは、米朝さんが『羽曳野にある「誉田」という地名が「こんだ」と呼ばれることから「ほんだや」ではなく「こんだや」と読むのが正しいのでは』と書かれていることからきているらしい。 更に、落語に出てくる『誉田屋(忠兵衛)』は京都・三条室町の縮緬問屋ですが、その三条室町に創業270年を数える「誉田屋(こんだや)源兵衛」という老舗の帯問屋があることも、「こんだや」と読ませる根拠を支持する材料になってるように思えます。
羽曳野にある誉田というところには「誉田(こんだ)山古墳」や「誉田(こんだ)八幡宮」があって、(私は知りませんでしたが)結構知名度が高いところだそうです。 誉田山古墳は別名「応神天皇陵」とも呼ばれていて、八幡神社の主祭神は応神天皇。 応神天皇は「誉田別尊(ほむだわけのみこと)」という別名を持つことから、その地が「誉田」と呼ばれるようになりました。 当時半島からの帰化人がその地に多く住んでいたことから、「ほむた」⇒「ほんだ」⇒「こんだ」と訛って変化し「こんだ」という地名となったという説がありますが、納得できます。 (は行とか行は、発声の仕方が非常に近いので、発音の入れ替えの例があります。)
ということは、「誉田」を「こんだ」と訛らずに「ほんだ」と読むところもあるのでは?と調べて見たところ、やはりありました。 兵庫県・たつの市と千葉県・習志野市に「誉田(ほんだ)」という地名があります。 千葉の誉田には「誉田(ほんだ)八幡神社」があります。ここは、大阪の陣のあと河内の住人が戦に負けて移住してきたところだそうで、幕末に羽曳野の誉田八幡宮から分祀して「誉田八幡神社」が出来ました。 (香川県東かがわ市にも分祀して設立された「誉田八幡神社」がありますが、こちらも「ほんだ」と呼びます。) たつの市の「誉田(ほんだ)」の由来は、不明です。
まぁ、こんなふうに「誉田」探しをしたからどうということは無いんですが、、、「ほんだ」と読むほうが普通みたいで、『縮緬問屋の「誉田屋」の命名が羽曳野の「誉田」にちなんだもの』というのは可能性のひとつにしか過ぎません。
六代目はこのネタを五代目か他の師匠から聴き覚えたんだろうと想像しますが、六代目が演じたように、二代目桂圓枝師匠の高座の速記にもあるように、もともとは「ほんだや」と言ったんだと思います。 「誉田」を「こんだ」と読むべしというのは決して自明のことでは無いですし、ましてそれを根拠に読み方のみならず漢字も「紺田屋」と変えてしまうのは、、、かなり乱暴なはなしですね。
あくまでも私の推測ですが、同じ三条室町に「誉田(こんだ)屋源兵衛」という老舗が実在するので、店が潰れてしまう「誉田屋忠兵衛」を「こんだや」とするのは差障りがあるとの配慮から「ほんだや」としたのではないかと・・・
旧い噺を一言一句変えずに演ずべし!などと云うつもりは毛頭ありませんし、時代の変化に応じて今風にアレンジするのも良いことだと思いますが、この「ほんだや」⇒「こんだや」(⇒「紺田屋」)に関してはいささか疑問に思います。
斯く云うわたしも、ワッハで六代目の「誉田屋(ほんだや)」を聴いていなかったら、「こんだや」と読むのをを信じて疑わなかったんですが。
|
|
|
|
コメント(5)
六代目の演じる「誉田屋」の音源を入手しました。 以前ワッハ上方のライブラリで聞いたのと同じ音源でしたが、改めて聞いてみると六代目はやはり「ほんだや」と云ってました。
私がいつも参考にする宇井無愁氏や前田勇氏の文献でも「こんだや」と書かれていますので、その影響力の大きさには感心させられます。(^^;;;
(似たような例は、「唖の魚釣り」の舞台の天王寺の池が昆陽池に変わっていたり、「蛸坊主」の舞台が茶臼山から生国魂神社に変わったり、いくつかあるようですが、、、旧い噺は聞いた人がほとんど残っていないので、仕方無いんですかね。)
実は、「芸能懇話」という雑誌に掲載された五代目松鶴口述の上方噺オチ一覧の中の「誉田屋」は「紺田屋」と書かれています。恐らく編集部が気を利かせて書き直したんでしょうが、これはご愛嬌ですかね。(笑)
私がいつも参考にする宇井無愁氏や前田勇氏の文献でも「こんだや」と書かれていますので、その影響力の大きさには感心させられます。(^^;;;
(似たような例は、「唖の魚釣り」の舞台の天王寺の池が昆陽池に変わっていたり、「蛸坊主」の舞台が茶臼山から生国魂神社に変わったり、いくつかあるようですが、、、旧い噺は聞いた人がほとんど残っていないので、仕方無いんですかね。)
実は、「芸能懇話」という雑誌に掲載された五代目松鶴口述の上方噺オチ一覧の中の「誉田屋」は「紺田屋」と書かれています。恐らく編集部が気を利かせて書き直したんでしょうが、これはご愛嬌ですかね。(笑)
>ぽこさん
>>前田勇氏の「上方落語の歴史」には誉田屋を<ほんだや>と読むのは非、と書いてありましたよ
でも、その根拠は何も書かれていないんですよね。(恐らく米朝師匠の説を採られたと思うんですが。。)
学究の徒としては、まずは疑うことから始めるのが第一歩。 権威が書いてるからといって、納得できなければ、そのまま鵜呑みにしてはいけません。 これについては、前田さんにも宇井さんにも、ちょいと不満を感じてます。
というのはさておき、、、
「誉田屋」にはいくつかの演出がありますが、「(墓を暴いて金を持ち逃げする)太い野郎が成功して善人が不幸になる非人情咄」と宇井さんはこの噺に良い印象を持っていないようですが、、、六代目の演出はその辺りをあまり感じさせないようになってますね。(^^)
>>前田勇氏の「上方落語の歴史」には誉田屋を<ほんだや>と読むのは非、と書いてありましたよ
でも、その根拠は何も書かれていないんですよね。(恐らく米朝師匠の説を採られたと思うんですが。。)
学究の徒としては、まずは疑うことから始めるのが第一歩。 権威が書いてるからといって、納得できなければ、そのまま鵜呑みにしてはいけません。 これについては、前田さんにも宇井さんにも、ちょいと不満を感じてます。
というのはさておき、、、
「誉田屋」にはいくつかの演出がありますが、「(墓を暴いて金を持ち逃げする)太い野郎が成功して善人が不幸になる非人情咄」と宇井さんはこの噺に良い印象を持っていないようですが、、、六代目の演出はその辺りをあまり感じさせないようになってますね。(^^)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
六代目 笑福亭松鶴 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
六代目 笑福亭松鶴のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37859人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90054人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208306人