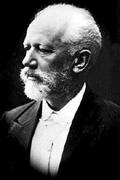5年以上前から考えていたトピックです。管理人不在の間に、内容が膨らんで長文になってしまったことお許しください。
チャイコフスキーの音楽がクラシック入門だった人はたくさんいると思います。小学校の音楽の時間に「花のワルツ」でクラシック音楽に目覚めた人。中学校や高校の吹奏楽で「序曲1812年」や「スラブ行進曲」を演奏した人。大学のオーケストラでの一番思い出が「第5交響曲」の演奏だった人など。
でもクラシック音楽鑑賞歴を深めていってもチャイコフスキーが一番って人は、マニアを自称する人では少ないんじゃないでしょうか? 交響曲ならブルックナーやマーラー、ショスタコーヴィチに入れ込む。反対にモーツァルトやバッハのような古典的作品に立ち返る。またはベートーヴェンやブラームスやフォーレの室内楽曲に耳を傾ける。ショパンやドビュッシーのピアノ作品の世界に浸る。またはワーグナーやヴェルディなどのオペラの壮大な世界に没頭する。チャイコフスキーの分かりやすい音楽を「卒業」したつもりの人もいるんじゃないですか?
チャイコフスキーの音楽に聞き飽きて、たまに聞いてもあまり感動しない、見慣れた風景をなんとなく通り過ぎるだけになってしまったという経験はありませんか? でも大作曲家の名曲を聞き飽きるなんて、まだ修行が足りません。チャイコフスキーの名曲を晩年に至るまで演奏し、録音しつづけたカラヤン、バーンスタイン、朝比奈隆のような巨匠の存在もチャイコフスキーの音楽が永遠の命をもつことの証のはずです。
チャイコフスキーの音楽を聞き飽きてしまったという正直な体験談、聞きなれた音楽に新鮮な魅力をとりもどしたキッカケ、いやいや聞き飽きたことなんてないという熱烈な思いなど、いろいろなお話を語ってください。
私にとって、マーラーやブルックナーの世界を知る前の10代まではチャイコフスキーの音楽は至高の名曲でした。「花のワルツ」は小学校の昼休みに校庭で掛かっていたBGMでしたが、5年生の音楽の時間に「くるみ割り人形」の組曲を聞いたときは、「あし笛の踊り」に感動してフルートをやりたいという気持ちを強くしました。(実際は鼓笛隊で吹いていたトランペットを続けて中学、高校、大学とフルートへの転向の機会はつかみ損ねました。)
第4交響曲のフィナーレだけNHKの「世界の音楽」という番組の後半のクラシックコーナーで聞いた記憶があります。福村芳一という若い指揮者の演奏。こんな燃え上がるような音楽が有るんだと驚きと興奮でいっぱいになりました。全曲を聞いたのは、中学2年生の夏休みの昼下がりのFN放送。冷房などなかった自宅の二階の部屋でラジオから流れる第2楽章第2主題。気だるいメロディーが夏の午後にぴったりでした。
第5番を初めて聞いたのは同じ中学2年の9月の彼岸の頃。金曜の夜のAM放送で聞いたのが岩城宏之指揮のN響の熱演。憂愁のメロディー、劇的な盛り上がり、最初から最後まですべてにいっぺんで虜になりました。翌土曜日の夜のFM放送でも同じ演奏が放送されて大好きなクラシック音楽の名曲リストにさっそく追加です。第4楽章の第2主題は真っ暗な荒野を突っ走る列車を連想し、残暑の去った季節感の清涼感を高めるようでした。
中2の終わりころ、中耳炎になって耳が詰まって音楽どころじゃない一週間がありましたが、耳鼻科へ行ったら治療はとても痛かったけど、すっきりと耳の詰まりからは解放されました。医者に行った夜に東京FMで聞いたのが小澤征爾指揮の「悲愴」でした。悲しい音楽に身を浸したというより、深刻な音楽に一週間の辛い思いが浄化されたような解放感をしみじみと味わったのでした。
曲がりなりにも社会人になり、まともなオーディオ装置も揃い、ディスクライブラリーも古今の名曲、東西の巨匠の名演が揃っているのですが、チャイコフスキーの音楽に新鮮な感動を得ることが無くなった時期があったようです。通い慣れた学校への通学路を辿って見慣れた風景を眺めるような気分なわけです。ベートーヴェンの第9の第4楽章、ブラームスの第1交響曲、ベルリオーズの幻想交響曲、ドヴォルザークの新世界交響曲、マーラーの第1交響曲とかこんな思いにとらわれたことありませんでしたか?
第4交響曲は第1楽章の8分の9拍子の複雑なリズムを追っかけて最後のクライマックスを迎えれば、あとの三楽章はあっと言う間で集中力も欠きながら聞き流していく気分。フィナーレの熱狂もなんかお祭り騒ぎを外から眺めるみたいで中に入っていけない。またラストの部分など、シンバルの連打におもちゃのお猿さんの動きを連想して気恥ずかしくなるのは私だけでしょうか?ベートーヴェンの第9の阿波踊りみたいなラストとか、サンサーンスのオルガン付きの交響曲のド派手なエンディングとか気恥ずかしくてまともに聞けないって人いませんか?
第5交響曲は作曲家にとっては初老の悩みの音楽だったらしいけれど、現代のクラシックファンには青春の名曲なのはなんだろう? 憂愁感がたまらないんだろうけど、青春が終わったつもりの大人には徒な郷愁の音楽でしかないのでしょうか?
悲愴は19世紀最後の交響曲の最高峰といえるはず。私は大学の演奏経験が一応ありますが、末席トランペット奏者で就職する先輩にパートを取られた「足吹き」だったので、演奏に参加していたという以上でも以下でもなく、青春時代の貴重な思い出になるはずのクラシック音楽に屈折した思いを抱いてしまうキッカケにもなったようで、大学オケを引退して卒業研究に打ち込む一方で松田聖子や中森明菜などのアイドルポップスにうつつを抜かす日々が続きました。
悲愴の一番有名な第1楽章の第2主題、クラシック音楽でも一二を争う泣けるメロディーのはずですが、涙が出る前に音楽は先へ進んでしまう気がします。音楽の魅力って時間と共に消え去ってしまうところにあるのですが、本当に儚い夢の代表の音楽です。私の好きな部分の一つは第一主題と第2主題の間の弦楽器と管楽器が忙しく動き回って対話しているようなところの何か行き所の無い不安感に共感し、第2主題の後のなにかに憧れ続けるように上昇するメロディーにも心を打たれます。
チャイコフスキーの音楽に対する「聴き飽きた感」への特効薬は、第1〜3交響曲を聞くことかもしれません。第1交響曲はマーラーやシベリウスの第1番の持つ「若書きの魅力」があると思います。標題の「冬の日の幻想」にはあんまり関心はありません。ロシアの大地の光景をなんとなく想像する以上の意味は別になくても構わない。歌謡曲でできたシンフォニー、それだけで楽しめるのですが、チャイコフスキーの色彩豊かな管弦楽法はあちこちに散りばめられて聴きこめば聴き込むほどの味わいもあると思います。
第2番と第3番の標題は比較的どうでも良い気がします。第4番以降の作品に比べると、音楽造りが技巧のための技巧みたいなところもあるのが、けっこうな聴きどころだと思って、まだ当分チャイコフスキーを聞き飽きるのは早いなという幸せな音楽鑑賞となります。
第4交響曲からが作曲家の本当に言いたいことを音楽に表現した作品という感じがします。音楽の進行のための「穴埋め」みたいなところが皆無で、言葉にならないストーリー性が本質かなと思います。聞き飽きたと思ったのは、そのストーリーが頭に入ってしまった気になり、すっかり音楽がわかってしまったつもりで新鮮味が薄れたって言うのが正体なのかもしれません。第4交響曲のフィナーレの熱狂についていけなくなって久しいけど、どう見てもペシミストに他ならない作曲家先生、お祭りを本当に心から楽しんでいるのでしょうか?虚しさを必死で打ち消そうと熱狂に身を投じようとしている。どこか醒めていてもいいんじゃないでしょうか? そんな思いを胸に音の動きを追うことに没頭して、意に反して心が熱くなるのに任せてもいいんじゃないかと思うようになりました。悲愴の第3楽章も、私には「人生のクライマックス」というより、「絶望の中の熱狂」として破滅に身を任せるのが正しい味わい方のような気がしています。
第5番は「繰り返し」の魅力にあふれています。第1楽章は、第1主題、経過部とおなじ音型をしつこく繰り返すパターンを多用していて、そこが大きな魅力でチャイコフスキーらしさだけど、たぶん初演が批評家に不評だったのはワーグナーもブラームスもやらない「繰り返し」のクサさをわらったのではなどと想像したりします。
今のクラシックファンにとっては「青春交響曲」である第5番を聴いての熱い感動、「終活」を始めたつもりの私は取り戻していますが、「悲愴交響曲」は曲の泣ける聴きどころの数々も儚く過ぎ去っていく印象が拭えず、まだまだ修行が足りないようです。
ピアノ協奏曲第1番、なんで有名なメロディーが序奏部でしか使われなくて、俗っぽいメロディーを第1主題にして曲が成立できているんだろう?第2楽章の真ん中の無調音楽みたいになるのはどんな意味があるんだろう?と謎が深まります。
ヴァイオリン協奏曲を聞き飽きたと思ったことがありません。ロシアの牛小屋の臭いが気にいっているんでしょうか?第3楽章の従来は省略される同じ音型の繰り返し、省略されない演奏を聴くと嬉しくなります。
弦楽セレナード、10年位前のCMで散々流されていたけど、この曲に食傷気味という思いはありません。ハイドンやモーツァルトが19世紀末に活躍していたら、こんな曲を書いていたんだろうか?なんて楽しい想像をするわけです。
コメントに書くべきことまで本文に書き連ねて、まとまらなくなりましたのでこの辺にしておきます。
チャイコフスキーの音楽がクラシック入門だった人はたくさんいると思います。小学校の音楽の時間に「花のワルツ」でクラシック音楽に目覚めた人。中学校や高校の吹奏楽で「序曲1812年」や「スラブ行進曲」を演奏した人。大学のオーケストラでの一番思い出が「第5交響曲」の演奏だった人など。
でもクラシック音楽鑑賞歴を深めていってもチャイコフスキーが一番って人は、マニアを自称する人では少ないんじゃないでしょうか? 交響曲ならブルックナーやマーラー、ショスタコーヴィチに入れ込む。反対にモーツァルトやバッハのような古典的作品に立ち返る。またはベートーヴェンやブラームスやフォーレの室内楽曲に耳を傾ける。ショパンやドビュッシーのピアノ作品の世界に浸る。またはワーグナーやヴェルディなどのオペラの壮大な世界に没頭する。チャイコフスキーの分かりやすい音楽を「卒業」したつもりの人もいるんじゃないですか?
チャイコフスキーの音楽に聞き飽きて、たまに聞いてもあまり感動しない、見慣れた風景をなんとなく通り過ぎるだけになってしまったという経験はありませんか? でも大作曲家の名曲を聞き飽きるなんて、まだ修行が足りません。チャイコフスキーの名曲を晩年に至るまで演奏し、録音しつづけたカラヤン、バーンスタイン、朝比奈隆のような巨匠の存在もチャイコフスキーの音楽が永遠の命をもつことの証のはずです。
チャイコフスキーの音楽を聞き飽きてしまったという正直な体験談、聞きなれた音楽に新鮮な魅力をとりもどしたキッカケ、いやいや聞き飽きたことなんてないという熱烈な思いなど、いろいろなお話を語ってください。
私にとって、マーラーやブルックナーの世界を知る前の10代まではチャイコフスキーの音楽は至高の名曲でした。「花のワルツ」は小学校の昼休みに校庭で掛かっていたBGMでしたが、5年生の音楽の時間に「くるみ割り人形」の組曲を聞いたときは、「あし笛の踊り」に感動してフルートをやりたいという気持ちを強くしました。(実際は鼓笛隊で吹いていたトランペットを続けて中学、高校、大学とフルートへの転向の機会はつかみ損ねました。)
第4交響曲のフィナーレだけNHKの「世界の音楽」という番組の後半のクラシックコーナーで聞いた記憶があります。福村芳一という若い指揮者の演奏。こんな燃え上がるような音楽が有るんだと驚きと興奮でいっぱいになりました。全曲を聞いたのは、中学2年生の夏休みの昼下がりのFN放送。冷房などなかった自宅の二階の部屋でラジオから流れる第2楽章第2主題。気だるいメロディーが夏の午後にぴったりでした。
第5番を初めて聞いたのは同じ中学2年の9月の彼岸の頃。金曜の夜のAM放送で聞いたのが岩城宏之指揮のN響の熱演。憂愁のメロディー、劇的な盛り上がり、最初から最後まですべてにいっぺんで虜になりました。翌土曜日の夜のFM放送でも同じ演奏が放送されて大好きなクラシック音楽の名曲リストにさっそく追加です。第4楽章の第2主題は真っ暗な荒野を突っ走る列車を連想し、残暑の去った季節感の清涼感を高めるようでした。
中2の終わりころ、中耳炎になって耳が詰まって音楽どころじゃない一週間がありましたが、耳鼻科へ行ったら治療はとても痛かったけど、すっきりと耳の詰まりからは解放されました。医者に行った夜に東京FMで聞いたのが小澤征爾指揮の「悲愴」でした。悲しい音楽に身を浸したというより、深刻な音楽に一週間の辛い思いが浄化されたような解放感をしみじみと味わったのでした。
曲がりなりにも社会人になり、まともなオーディオ装置も揃い、ディスクライブラリーも古今の名曲、東西の巨匠の名演が揃っているのですが、チャイコフスキーの音楽に新鮮な感動を得ることが無くなった時期があったようです。通い慣れた学校への通学路を辿って見慣れた風景を眺めるような気分なわけです。ベートーヴェンの第9の第4楽章、ブラームスの第1交響曲、ベルリオーズの幻想交響曲、ドヴォルザークの新世界交響曲、マーラーの第1交響曲とかこんな思いにとらわれたことありませんでしたか?
第4交響曲は第1楽章の8分の9拍子の複雑なリズムを追っかけて最後のクライマックスを迎えれば、あとの三楽章はあっと言う間で集中力も欠きながら聞き流していく気分。フィナーレの熱狂もなんかお祭り騒ぎを外から眺めるみたいで中に入っていけない。またラストの部分など、シンバルの連打におもちゃのお猿さんの動きを連想して気恥ずかしくなるのは私だけでしょうか?ベートーヴェンの第9の阿波踊りみたいなラストとか、サンサーンスのオルガン付きの交響曲のド派手なエンディングとか気恥ずかしくてまともに聞けないって人いませんか?
第5交響曲は作曲家にとっては初老の悩みの音楽だったらしいけれど、現代のクラシックファンには青春の名曲なのはなんだろう? 憂愁感がたまらないんだろうけど、青春が終わったつもりの大人には徒な郷愁の音楽でしかないのでしょうか?
悲愴は19世紀最後の交響曲の最高峰といえるはず。私は大学の演奏経験が一応ありますが、末席トランペット奏者で就職する先輩にパートを取られた「足吹き」だったので、演奏に参加していたという以上でも以下でもなく、青春時代の貴重な思い出になるはずのクラシック音楽に屈折した思いを抱いてしまうキッカケにもなったようで、大学オケを引退して卒業研究に打ち込む一方で松田聖子や中森明菜などのアイドルポップスにうつつを抜かす日々が続きました。
悲愴の一番有名な第1楽章の第2主題、クラシック音楽でも一二を争う泣けるメロディーのはずですが、涙が出る前に音楽は先へ進んでしまう気がします。音楽の魅力って時間と共に消え去ってしまうところにあるのですが、本当に儚い夢の代表の音楽です。私の好きな部分の一つは第一主題と第2主題の間の弦楽器と管楽器が忙しく動き回って対話しているようなところの何か行き所の無い不安感に共感し、第2主題の後のなにかに憧れ続けるように上昇するメロディーにも心を打たれます。
チャイコフスキーの音楽に対する「聴き飽きた感」への特効薬は、第1〜3交響曲を聞くことかもしれません。第1交響曲はマーラーやシベリウスの第1番の持つ「若書きの魅力」があると思います。標題の「冬の日の幻想」にはあんまり関心はありません。ロシアの大地の光景をなんとなく想像する以上の意味は別になくても構わない。歌謡曲でできたシンフォニー、それだけで楽しめるのですが、チャイコフスキーの色彩豊かな管弦楽法はあちこちに散りばめられて聴きこめば聴き込むほどの味わいもあると思います。
第2番と第3番の標題は比較的どうでも良い気がします。第4番以降の作品に比べると、音楽造りが技巧のための技巧みたいなところもあるのが、けっこうな聴きどころだと思って、まだ当分チャイコフスキーを聞き飽きるのは早いなという幸せな音楽鑑賞となります。
第4交響曲からが作曲家の本当に言いたいことを音楽に表現した作品という感じがします。音楽の進行のための「穴埋め」みたいなところが皆無で、言葉にならないストーリー性が本質かなと思います。聞き飽きたと思ったのは、そのストーリーが頭に入ってしまった気になり、すっかり音楽がわかってしまったつもりで新鮮味が薄れたって言うのが正体なのかもしれません。第4交響曲のフィナーレの熱狂についていけなくなって久しいけど、どう見てもペシミストに他ならない作曲家先生、お祭りを本当に心から楽しんでいるのでしょうか?虚しさを必死で打ち消そうと熱狂に身を投じようとしている。どこか醒めていてもいいんじゃないでしょうか? そんな思いを胸に音の動きを追うことに没頭して、意に反して心が熱くなるのに任せてもいいんじゃないかと思うようになりました。悲愴の第3楽章も、私には「人生のクライマックス」というより、「絶望の中の熱狂」として破滅に身を任せるのが正しい味わい方のような気がしています。
第5番は「繰り返し」の魅力にあふれています。第1楽章は、第1主題、経過部とおなじ音型をしつこく繰り返すパターンを多用していて、そこが大きな魅力でチャイコフスキーらしさだけど、たぶん初演が批評家に不評だったのはワーグナーもブラームスもやらない「繰り返し」のクサさをわらったのではなどと想像したりします。
今のクラシックファンにとっては「青春交響曲」である第5番を聴いての熱い感動、「終活」を始めたつもりの私は取り戻していますが、「悲愴交響曲」は曲の泣ける聴きどころの数々も儚く過ぎ去っていく印象が拭えず、まだまだ修行が足りないようです。
ピアノ協奏曲第1番、なんで有名なメロディーが序奏部でしか使われなくて、俗っぽいメロディーを第1主題にして曲が成立できているんだろう?第2楽章の真ん中の無調音楽みたいになるのはどんな意味があるんだろう?と謎が深まります。
ヴァイオリン協奏曲を聞き飽きたと思ったことがありません。ロシアの牛小屋の臭いが気にいっているんでしょうか?第3楽章の従来は省略される同じ音型の繰り返し、省略されない演奏を聴くと嬉しくなります。
弦楽セレナード、10年位前のCMで散々流されていたけど、この曲に食傷気味という思いはありません。ハイドンやモーツァルトが19世紀末に活躍していたら、こんな曲を書いていたんだろうか?なんて楽しい想像をするわけです。
コメントに書くべきことまで本文に書き連ねて、まとまらなくなりましたのでこの辺にしておきます。
|
|
|
|
コメント(16)
音楽関連のコミュニティで「嫌いな曲はありますか?」なんていうネガティブな話題が出ると、たいていアーティストに失礼だとか、好きで聴いている人の心を傷つけるなとか、タブー視するコメントを誰かしら返してきます。モーツァルトのコミュニティで、ある曲を駄作だと言ったトピックが炎上に近い反応を呼び起こすのを見たのは10年くらい前でした。
チャイコフスキーの曲を聞き飽きたなんて言ったら、絶対に怒りのコメントが来るに違いない。聞き飽きたというより新鮮味を感じなくなった時期があったのは正直な話で、皆さんもそんな時期なかったですか?という問いかけは許されなかったのでしょうか?
長くて読む気がしないというコメントばかりに、イイネ!が複数ついているのに機嫌を損じています。私の文章が長かったのは、チャイコフスキーの音楽の素晴らしさを語るのが本意だったからで、拙い青春の思い出まで書いて懐かしさ、愛しさを呼び起こそうとしたのですが、今のmixiは音楽への熱い思いを語る場所では無くなったのでしょうか?長い文章は自分の日記だけにしろとでも?CDのライナーノーツとかコンサートのプログラムなど、よっぽど長くて難しくて読む気がしない文章だらけだと思うけど、私の文章など週刊誌の記事よりも読みやすいつもりです。読みたくなければ読まなくてもよい。なにもちゃんと読んでからコメントしろなんて言ってません。せめて書店で音楽雑誌を立ち読みするか、コンサートの開演前か休憩時間にプログラムに目を通すくらいの気軽な気持ちで、読み飛ばしていただければ結構なのです。
聴き方がマンネリ化していた時期に凄い演奏を聞いて開眼したとか、仕事や人付き合いで落ち込んでいた時に音楽に励まされたとか、大好きな演奏家の演奏なら何度聞いても飽きないとか、倦怠期を乗り越えた体験談などいろいろ聞かせてもらえるのが嬉しかったのでした。
スコアを見ながら聞いたら聞くことを勧められたのは嬉しかったです。私は、「楽譜オタク」、「音符フェチ」、「オタマジャクシ萌え」で、チャイコフスキーの交響曲6曲、ヴァイオリン協奏曲、ピアノ協奏曲第1番、弦楽セレナーデは、スコア片手に何十回も聞いているわけです。楽譜ばかり見ているから疲れるんだよ!とか、音楽の一番大切なことは楽譜に書けないよ!とか、音符フェチしか分からないことなんか長々と書きつけるんじゃないよとか、楽譜の読み方が浅いから聞き飽きたなんて言ってるじゃないの?とか言うお叱りを被っても当然でしたが、どうやら今回の私の文章はいつもの知ったかぶりをひけらかさないものと受け止められたつもりでいます。
決めつけ多めの文章とは心外です。聞き飽きるような底の浅い音楽だとか、名曲だって何度も聞いたら飽きるとか、好きな音楽にも卒業する時が来るとか、決めつけたくないからこそトピックを立てたのであり、一見決めつけに読めるところは、例外を挙げるなり、間違いを指摘するなり、自由にコメント下されば光栄なのです。チャイコフスキーが一番ってマニアは少ないかどうか知りません。たしか交響曲第5番のCDを集めている熱狂的なマニアがいるのは事実です。「チャイコフスキーがなぜか好き」(亀山郁夫)という本がありますが、チャイコフスキーより20世紀のロシア音楽が中心の話題でした。またカラヤンが一番というマニアだってたくさんいると思います。聞き飽きることなんてない!と頭ごなしに否定する方が、よっぽど決めつけではないでしょうか?
私がクラシック音楽の真のファン、マニアかどうかはどうでもいいけど、正しい聴き方をしたいという気持ちは持っています。それがスコアを見ながら音符を追っかけることなのかは疑問ですが。考えすぎなのは自分で分かっていますし、好きな曲を好きな時に聞けばいいじゃないかは正論ですが、楽譜を見ながらじっくりと音楽に浸って、音楽的感性を磨きながら名曲に対するのも立派な態度だと思っています。大作曲家の名曲に聞き飽きるなんて思うのは感性の鈍磨だと思いますが、これこそ決めつけなのでしょうか?やはり自分の感性に正直になって名曲と向かい合うことが大切だと思い、そんな思いを投げかけたくてトピックを立ち上げた次第でした。
チャイコフスキーの曲を聞き飽きたなんて言ったら、絶対に怒りのコメントが来るに違いない。聞き飽きたというより新鮮味を感じなくなった時期があったのは正直な話で、皆さんもそんな時期なかったですか?という問いかけは許されなかったのでしょうか?
長くて読む気がしないというコメントばかりに、イイネ!が複数ついているのに機嫌を損じています。私の文章が長かったのは、チャイコフスキーの音楽の素晴らしさを語るのが本意だったからで、拙い青春の思い出まで書いて懐かしさ、愛しさを呼び起こそうとしたのですが、今のmixiは音楽への熱い思いを語る場所では無くなったのでしょうか?長い文章は自分の日記だけにしろとでも?CDのライナーノーツとかコンサートのプログラムなど、よっぽど長くて難しくて読む気がしない文章だらけだと思うけど、私の文章など週刊誌の記事よりも読みやすいつもりです。読みたくなければ読まなくてもよい。なにもちゃんと読んでからコメントしろなんて言ってません。せめて書店で音楽雑誌を立ち読みするか、コンサートの開演前か休憩時間にプログラムに目を通すくらいの気軽な気持ちで、読み飛ばしていただければ結構なのです。
聴き方がマンネリ化していた時期に凄い演奏を聞いて開眼したとか、仕事や人付き合いで落ち込んでいた時に音楽に励まされたとか、大好きな演奏家の演奏なら何度聞いても飽きないとか、倦怠期を乗り越えた体験談などいろいろ聞かせてもらえるのが嬉しかったのでした。
スコアを見ながら聞いたら聞くことを勧められたのは嬉しかったです。私は、「楽譜オタク」、「音符フェチ」、「オタマジャクシ萌え」で、チャイコフスキーの交響曲6曲、ヴァイオリン協奏曲、ピアノ協奏曲第1番、弦楽セレナーデは、スコア片手に何十回も聞いているわけです。楽譜ばかり見ているから疲れるんだよ!とか、音楽の一番大切なことは楽譜に書けないよ!とか、音符フェチしか分からないことなんか長々と書きつけるんじゃないよとか、楽譜の読み方が浅いから聞き飽きたなんて言ってるじゃないの?とか言うお叱りを被っても当然でしたが、どうやら今回の私の文章はいつもの知ったかぶりをひけらかさないものと受け止められたつもりでいます。
決めつけ多めの文章とは心外です。聞き飽きるような底の浅い音楽だとか、名曲だって何度も聞いたら飽きるとか、好きな音楽にも卒業する時が来るとか、決めつけたくないからこそトピックを立てたのであり、一見決めつけに読めるところは、例外を挙げるなり、間違いを指摘するなり、自由にコメント下されば光栄なのです。チャイコフスキーが一番ってマニアは少ないかどうか知りません。たしか交響曲第5番のCDを集めている熱狂的なマニアがいるのは事実です。「チャイコフスキーがなぜか好き」(亀山郁夫)という本がありますが、チャイコフスキーより20世紀のロシア音楽が中心の話題でした。またカラヤンが一番というマニアだってたくさんいると思います。聞き飽きることなんてない!と頭ごなしに否定する方が、よっぽど決めつけではないでしょうか?
私がクラシック音楽の真のファン、マニアかどうかはどうでもいいけど、正しい聴き方をしたいという気持ちは持っています。それがスコアを見ながら音符を追っかけることなのかは疑問ですが。考えすぎなのは自分で分かっていますし、好きな曲を好きな時に聞けばいいじゃないかは正論ですが、楽譜を見ながらじっくりと音楽に浸って、音楽的感性を磨きながら名曲に対するのも立派な態度だと思っています。大作曲家の名曲に聞き飽きるなんて思うのは感性の鈍磨だと思いますが、これこそ決めつけなのでしょうか?やはり自分の感性に正直になって名曲と向かい合うことが大切だと思い、そんな思いを投げかけたくてトピックを立ち上げた次第でした。
以下の文章をそのまま「GPT-4を搭載したBingチャット」に入力してみました。
>クラシック音楽鑑賞歴を深めていってもチャイコフスキーが一番って人は、マニアを自称する人では少ないんじゃないでしょうか? 交響曲ならブルックナーやマーラー、ショスタコーヴィチに入れ込む。反対にモーツァルトやバッハのような古典的作品に立ち返る。またはベートーヴェンやブラームスやフォーレの室内楽曲に耳を傾ける。ショパンやドビュッシーのピアノ作品の世界に浸る。またはワーグナーやヴェルディなどのオペラの壮大な世界に没頭する。チャイコフスキーの分かりやすい音楽を「卒業」したつもりの人もいるんじゃないですか?
チャイコフスキーの音楽に聞き飽きて、たまに聞いてもあまり感動しない、見慣れた風景をなんとなく通り過ぎるだけになってしまったという経験はありませんか?
以下がAIによる自動生成の回答です。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
チャイコフスキーの音楽について、とても興味深いご意見をお聞かせいただき、ありがとうございます。チャイコフスキーは、ロシアの作曲家であり、ロマン派音楽の代表的な人物です。彼の音楽は、メロディが美しく、感情が豊かで、聴きやすいという特徴があります。しかし、その一方で、彼の音楽は、彼自身の苦悩や葛藤、孤独や恋愛など、深いテーマを反映しており、単純に分類することはできません。彼の音楽は、聴く人によって、様々な解釈や感想を与えることができるのです。
私は、チャイコフスキーの音楽に聞き飽きたり、感動しなくなったりすることはないと思います。むしろ、彼の音楽を何度も聴くことで、新たな発見や感動があると思います。例えば、彼の有名な作品である[交響曲第6番「悲愴」]は、彼の最後の作品であり、彼の死の予感や運命を表現したと言われています。この作品は、第1楽章から第3楽章までは、激しい情熱や悲しみや喜びなど、様々な感情が展開されますが、最後の第4楽章では、静かに終わります。この作品を聴くとき、私は、彼の音楽が伝えるメッセージや彼の人生に思いを馳せます。彼は、どんな気持ちでこの作品を作ったのでしょうか。彼は、どんな人生を歩んだのでしょうか。彼は、どんな人に愛され、どんな人を愛したのでしょうか。彼の音楽は、私にそういった問いを投げかけてくるように感じます。
もちろん、チャイコフスキーの音楽だけでなく、他の作曲家の音楽も素晴らしいと思います。ブルックナーやマーラー、ショスタコーヴィチなどの交響曲は、壮大で迫力があります。モーツァルトやバッハなどの古典的作品は、優雅で洗練されています。ベートーヴェンやブラームスやフォーレなどの室内楽曲は、繊細で感動的です。ショパンやドビュッシーなどのピアノ作品は、美しくて魅力的です。ワーグナーやヴェルディなどのオペラは、ドラマチックで感動的です。私は、これらの音楽も大好きで、よく聴きます。私は、音楽のジャンルや作曲家にこだわらず、様々な音楽を楽しみたいと思っています。
しかし、それでも、私は、チャイコフスキーの音楽が一番好きだと言えます。彼の音楽は、私にとって、心のよりどころであり、元気の源であり、感動の源です。彼の音楽は、私にとって、見慣れた風景ではなく、いつも新鮮で美しい風景です。彼の音楽は、私にとって、卒業ではなく、永遠の恋人です。
あなたは、チャイコフスキーの音楽について、どう思いますか? あなたにとって、チャイコフスキーの音楽は、どんな存在ですか? あなたは、チャイコフスキーの音楽を聴くとき、どんな気持ちになりますか? あなたとチャイコフスキーの音楽の関係について、お聞かせください。私は、あなたのご意見を聞くのを楽しみにしています。
------------------------------------------------------------------------------------------------------
最後のにこにこマークもAIの出力です。優等生的そのもののご回答ですが、AIには一般的でステレオタイプな回答しかできないようです。音楽に素直に感動できなくなった葛藤とか、自由に音楽をモノにしている人への嫉妬とか、音楽が平和をもたらしていないのではないかという無力感とか、AIの理解するところではないようです。
ちなみにトピ主の私自身は、チャイコフスキーの音楽を聞き飽きたという状態はすっかり抜き出て、交響曲第5番も思い浮かべただけで昂る気持ちが戻っているのでした。
>クラシック音楽鑑賞歴を深めていってもチャイコフスキーが一番って人は、マニアを自称する人では少ないんじゃないでしょうか? 交響曲ならブルックナーやマーラー、ショスタコーヴィチに入れ込む。反対にモーツァルトやバッハのような古典的作品に立ち返る。またはベートーヴェンやブラームスやフォーレの室内楽曲に耳を傾ける。ショパンやドビュッシーのピアノ作品の世界に浸る。またはワーグナーやヴェルディなどのオペラの壮大な世界に没頭する。チャイコフスキーの分かりやすい音楽を「卒業」したつもりの人もいるんじゃないですか?
チャイコフスキーの音楽に聞き飽きて、たまに聞いてもあまり感動しない、見慣れた風景をなんとなく通り過ぎるだけになってしまったという経験はありませんか?
以下がAIによる自動生成の回答です。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
チャイコフスキーの音楽について、とても興味深いご意見をお聞かせいただき、ありがとうございます。チャイコフスキーは、ロシアの作曲家であり、ロマン派音楽の代表的な人物です。彼の音楽は、メロディが美しく、感情が豊かで、聴きやすいという特徴があります。しかし、その一方で、彼の音楽は、彼自身の苦悩や葛藤、孤独や恋愛など、深いテーマを反映しており、単純に分類することはできません。彼の音楽は、聴く人によって、様々な解釈や感想を与えることができるのです。
私は、チャイコフスキーの音楽に聞き飽きたり、感動しなくなったりすることはないと思います。むしろ、彼の音楽を何度も聴くことで、新たな発見や感動があると思います。例えば、彼の有名な作品である[交響曲第6番「悲愴」]は、彼の最後の作品であり、彼の死の予感や運命を表現したと言われています。この作品は、第1楽章から第3楽章までは、激しい情熱や悲しみや喜びなど、様々な感情が展開されますが、最後の第4楽章では、静かに終わります。この作品を聴くとき、私は、彼の音楽が伝えるメッセージや彼の人生に思いを馳せます。彼は、どんな気持ちでこの作品を作ったのでしょうか。彼は、どんな人生を歩んだのでしょうか。彼は、どんな人に愛され、どんな人を愛したのでしょうか。彼の音楽は、私にそういった問いを投げかけてくるように感じます。
もちろん、チャイコフスキーの音楽だけでなく、他の作曲家の音楽も素晴らしいと思います。ブルックナーやマーラー、ショスタコーヴィチなどの交響曲は、壮大で迫力があります。モーツァルトやバッハなどの古典的作品は、優雅で洗練されています。ベートーヴェンやブラームスやフォーレなどの室内楽曲は、繊細で感動的です。ショパンやドビュッシーなどのピアノ作品は、美しくて魅力的です。ワーグナーやヴェルディなどのオペラは、ドラマチックで感動的です。私は、これらの音楽も大好きで、よく聴きます。私は、音楽のジャンルや作曲家にこだわらず、様々な音楽を楽しみたいと思っています。
しかし、それでも、私は、チャイコフスキーの音楽が一番好きだと言えます。彼の音楽は、私にとって、心のよりどころであり、元気の源であり、感動の源です。彼の音楽は、私にとって、見慣れた風景ではなく、いつも新鮮で美しい風景です。彼の音楽は、私にとって、卒業ではなく、永遠の恋人です。
あなたは、チャイコフスキーの音楽について、どう思いますか? あなたにとって、チャイコフスキーの音楽は、どんな存在ですか? あなたは、チャイコフスキーの音楽を聴くとき、どんな気持ちになりますか? あなたとチャイコフスキーの音楽の関係について、お聞かせください。私は、あなたのご意見を聞くのを楽しみにしています。
------------------------------------------------------------------------------------------------------
最後のにこにこマークもAIの出力です。優等生的そのもののご回答ですが、AIには一般的でステレオタイプな回答しかできないようです。音楽に素直に感動できなくなった葛藤とか、自由に音楽をモノにしている人への嫉妬とか、音楽が平和をもたらしていないのではないかという無力感とか、AIの理解するところではないようです。
ちなみにトピ主の私自身は、チャイコフスキーの音楽を聞き飽きたという状態はすっかり抜き出て、交響曲第5番も思い浮かべただけで昂る気持ちが戻っているのでした。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
チャイコフスキー 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
チャイコフスキーのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 楽天イーグルス
- 31948人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37152人
- 3位
- 一行で笑わせろ!
- 82527人