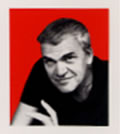信じられない報道に接して驚いています。
チェコの雑誌にて、クンデラがむかし、チェコ人学生をコミュニスト政府に「売った」という事実が指摘されました。
クンデラがコミュニストパーティーから追放されたのは1948年。
1950年に、ある大学生が西側諜報機関に通じているとクンデラが政府に密告、この若者は死刑を宣告されたが、22年の刑期と強制労働のすえ、いまはスイスに在住しているという。
これはRespektという雑誌に掲載されたばかりで、調べてみるとこの件についてはチェコ語データが大半です(Milan KunderaとRespektで検索するとわかります)。フランス語情報がいくつか。
わたしが知ったのは今日のスペインの新聞エル・パイス紙によります。
どんな事情、背景(真偽もふくめ)なのか続報をまちたいです。
http://
チェコの雑誌にて、クンデラがむかし、チェコ人学生をコミュニスト政府に「売った」という事実が指摘されました。
クンデラがコミュニストパーティーから追放されたのは1948年。
1950年に、ある大学生が西側諜報機関に通じているとクンデラが政府に密告、この若者は死刑を宣告されたが、22年の刑期と強制労働のすえ、いまはスイスに在住しているという。
これはRespektという雑誌に掲載されたばかりで、調べてみるとこの件についてはチェコ語データが大半です(Milan KunderaとRespektで検索するとわかります)。フランス語情報がいくつか。
わたしが知ったのは今日のスペインの新聞エル・パイス紙によります。
どんな事情、背景(真偽もふくめ)なのか続報をまちたいです。
http://
|
|
|
|
コメント(31)
この件、一件落着の様相ですね。
失望を味わわなくてなによりでした。
事実というのが、いかにこねまわされるか、という例でしょうか。
とにかく、そんな時代、そんなくにがあったわけですね。
これからはクンデラの作品を読むときは、綴られていないことをあれこれ思い描いてしまう習慣ができてしまいそう。
プラハの代表的な政治週刊誌だというRespektの記事の英語版はこちら。
http://english.respekt.cz/Milan-Kunderas-denunciation-2742.html
それでBBCニューズはこちらです。
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7668484.stm
もちろんニホンでも、あれこれ気に病んだひとたちはすくなくないでしょうが、マスコミでは事実上まったく触れられなかったようですね。
それだけ関心がないんでしょうか、まさか初めからガセネタだなんて睨んでいたわけではないでしょうが。
とにかく、ネットの時代、このニュースは当のチェコをはじめ世界各国で報道されたわけで、言葉さえわかれば、居ながらにして、世界のあちこちがこの問題をどう考え、どの程度の関心を払っているかが一目瞭然なのですね。
この騒動を通じて学べたこともきっとあったはずです。
失望を味わわなくてなによりでした。
事実というのが、いかにこねまわされるか、という例でしょうか。
とにかく、そんな時代、そんなくにがあったわけですね。
これからはクンデラの作品を読むときは、綴られていないことをあれこれ思い描いてしまう習慣ができてしまいそう。
プラハの代表的な政治週刊誌だというRespektの記事の英語版はこちら。
http://english.respekt.cz/Milan-Kunderas-denunciation-2742.html
それでBBCニューズはこちらです。
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7668484.stm
もちろんニホンでも、あれこれ気に病んだひとたちはすくなくないでしょうが、マスコミでは事実上まったく触れられなかったようですね。
それだけ関心がないんでしょうか、まさか初めからガセネタだなんて睨んでいたわけではないでしょうが。
とにかく、ネットの時代、このニュースは当のチェコをはじめ世界各国で報道されたわけで、言葉さえわかれば、居ながらにして、世界のあちこちがこの問題をどう考え、どの程度の関心を払っているかが一目瞭然なのですね。
この騒動を通じて学べたこともきっとあったはずです。
私は、今日の朝日新聞で、はじめてそれをしりました。
話はずれますが(ごめんなさい)、女優マレーネ・ディートリッヒはナチス・ドイツの誘いをけって、ハリウッドで活躍していたことで、戦後だいぶたってからも、ドイツ国民の間では複雑な気持ちを抱いてしまう存在だったそうです。戦争中私たちとともにいなかったじゃないか、裏切り者、みたいな(1960年位にドイツでコンサートをひらこうとしたら暴動になったそうです)。彼女はドイツに二度と帰ることなく、パリでひっそりと亡くなります。
クンデラとチェコの間にも、そうした複雑な感情、関係があったのではないかと、ふっと思いました。
「存在の耐えられない軽さ」、思い出すと、いまでもシーンごとに涙がでそうになります。
話はずれますが(ごめんなさい)、女優マレーネ・ディートリッヒはナチス・ドイツの誘いをけって、ハリウッドで活躍していたことで、戦後だいぶたってからも、ドイツ国民の間では複雑な気持ちを抱いてしまう存在だったそうです。戦争中私たちとともにいなかったじゃないか、裏切り者、みたいな(1960年位にドイツでコンサートをひらこうとしたら暴動になったそうです)。彼女はドイツに二度と帰ることなく、パリでひっそりと亡くなります。
クンデラとチェコの間にも、そうした複雑な感情、関係があったのではないかと、ふっと思いました。
「存在の耐えられない軽さ」、思い出すと、いまでもシーンごとに涙がでそうになります。
この件、事実関係が明らかになっただけでは、一件落着というふうに安易にはいかないみたいですね。
じっさい、クンデラがこうむった中傷というのは、残るものなのです。
しかも、操作された中傷によっていとも容易にひと(アーティスト)は失墜してしまうものなのです。
ヨーロッパでは、劇作家Fernando Arrabal、哲学者Bernard-Henri Lévy、作家Michel Houellebecqら知識人が連名でクンデラを守る共同宣言を発表しました。
消すことのできない中傷というのは、いつまでつづくのか。
腐肉者たちは自分たちの恥辱でもって、なぜ世捨て人を虐げるのか。
等々、権力者の恣意によって良心的な知識人が踏みにじられてしまうことにつよく憤っている内容です。
いっぽう、クンデラを訴えたとした文書に名が記載されているチェコの劇作家Yasmina Rezaは、ル・モンド紙にコラムを発表。
クンデラは抗弁、弁明するだけの客観的状況を把握できていなくて、何かいえばいうほど、敵対側を元気づけるだけだ。
かくして良心的に生きてきたひとたちの威信というものは、30秒の中傷でまるっきり失墜してしまうのだ、etc.
このコラム(フランス語)は印象的です。
http://www.lemonde.fr/archives/article/2008/10/17/milan-kundera-ou-l-offense-du-silence-par-yasmina-reza_1108120_0.html
有名な雑誌ということになっていたRespektも、その背後関係はうさんくさんものがありそうです。
CoMomotyが触れているMiroslav Dlaskを指摘しているZdenek Pesatというチェコ文学史家のたどってきた人生も苦渋にみちているようで、こころをうたれます。
繰り返しになりますが、この騒動そのものがクンデラの一冊の小説のようにも見えますが、おなじようなことがいくらでもいくらでも、当時はあったということなのでしょう。
おなじく繰り返しになじますが、ヨーロッパで共同宣言などが出されている段階で、ニホンでようやく毎日新聞のように「密告説」が流れているようでは、ニホンのジャーナリズムにいかほどのことが期待できるものだろうか、ということを考えてしまいます。
以上、ヨーロッパでのリアクションはしばらくつづくようです。
じっさい、クンデラがこうむった中傷というのは、残るものなのです。
しかも、操作された中傷によっていとも容易にひと(アーティスト)は失墜してしまうものなのです。
ヨーロッパでは、劇作家Fernando Arrabal、哲学者Bernard-Henri Lévy、作家Michel Houellebecqら知識人が連名でクンデラを守る共同宣言を発表しました。
消すことのできない中傷というのは、いつまでつづくのか。
腐肉者たちは自分たちの恥辱でもって、なぜ世捨て人を虐げるのか。
等々、権力者の恣意によって良心的な知識人が踏みにじられてしまうことにつよく憤っている内容です。
いっぽう、クンデラを訴えたとした文書に名が記載されているチェコの劇作家Yasmina Rezaは、ル・モンド紙にコラムを発表。
クンデラは抗弁、弁明するだけの客観的状況を把握できていなくて、何かいえばいうほど、敵対側を元気づけるだけだ。
かくして良心的に生きてきたひとたちの威信というものは、30秒の中傷でまるっきり失墜してしまうのだ、etc.
このコラム(フランス語)は印象的です。
http://www.lemonde.fr/archives/article/2008/10/17/milan-kundera-ou-l-offense-du-silence-par-yasmina-reza_1108120_0.html
有名な雑誌ということになっていたRespektも、その背後関係はうさんくさんものがありそうです。
CoMomotyが触れているMiroslav Dlaskを指摘しているZdenek Pesatというチェコ文学史家のたどってきた人生も苦渋にみちているようで、こころをうたれます。
繰り返しになりますが、この騒動そのものがクンデラの一冊の小説のようにも見えますが、おなじようなことがいくらでもいくらでも、当時はあったということなのでしょう。
おなじく繰り返しになじますが、ヨーロッパで共同宣言などが出されている段階で、ニホンでようやく毎日新聞のように「密告説」が流れているようでは、ニホンのジャーナリズムにいかほどのことが期待できるものだろうか、ということを考えてしまいます。
以上、ヨーロッパでのリアクションはしばらくつづくようです。
証拠文書を掴んでいるというthe Czech Institute for the Study of Totalitarian Regimesなる組織ですが、何だかいろいろあるみたいですね。
ちょっと調べてみたところ、成立そのものについてチェコ国内では反対意見もあったとか。
憲法裁判所は”統治行為論”のような論法で断定を避け、
組織は成立となったようです。
http://aktualne.centrum.cz/czechnews/clanek.phtml?id=524011
http://www.ceskenoviny.cz/news/index_view.php?id=288523
全体主義時代の糾弾に意欲を燃やしているようですが、
どうも2008年6月3日に成立した"Prague Declaration"が関係していると思われます。
チェコが主導となって、全ヨーロッパで全体主義に関する研究の取組みを進めようという宣言が出されました。
チェコのプライドにかけて共産党独裁時代の全体主義を糾弾したいのでしょうか。。。
http://www.praguedeclaration.org/
このごろグルジア問題で冷戦再発かという懸念がありますが、
ヨーロッパのほうでは日本以上にその危機意識は高いのかもしれません。
過去の歴史を悪しき時代と断じてよりよい時代へ前進しようという抒情的精神の顕れでしょうか。
クンデラが生涯かけて乗り越えようとしてきたものに、クンデラは今直面しているように思えてなりません。
「カーテン」以来著作を見ませんが、いま齢80を目前にこの事件に触れて、
またすばらしい作品を書いてくれたらうれしく思います。
長文失礼しました。
ちょっと調べてみたところ、成立そのものについてチェコ国内では反対意見もあったとか。
憲法裁判所は”統治行為論”のような論法で断定を避け、
組織は成立となったようです。
http://aktualne.centrum.cz/czechnews/clanek.phtml?id=524011
http://www.ceskenoviny.cz/news/index_view.php?id=288523
全体主義時代の糾弾に意欲を燃やしているようですが、
どうも2008年6月3日に成立した"Prague Declaration"が関係していると思われます。
チェコが主導となって、全ヨーロッパで全体主義に関する研究の取組みを進めようという宣言が出されました。
チェコのプライドにかけて共産党独裁時代の全体主義を糾弾したいのでしょうか。。。
http://www.praguedeclaration.org/
このごろグルジア問題で冷戦再発かという懸念がありますが、
ヨーロッパのほうでは日本以上にその危機意識は高いのかもしれません。
過去の歴史を悪しき時代と断じてよりよい時代へ前進しようという抒情的精神の顕れでしょうか。
クンデラが生涯かけて乗り越えようとしてきたものに、クンデラは今直面しているように思えてなりません。
「カーテン」以来著作を見ませんが、いま齢80を目前にこの事件に触れて、
またすばらしい作品を書いてくれたらうれしく思います。
長文失礼しました。
作家とはいかなるものか、ということを考えさせられるニュースだ。
作家として生きていくためには、読者の深い共感を得て、「この作家のものなら次も読んでみたい」と思われなければならない。名前は記さないが、現代の日本の売れっ子作家で、「ぼくは子供のころは優等生で何をしても親に心配をかけるようなことはまったくなかったですね」という驚くべき発言をしている人がいた。ほかの人もそうだと思うのだが、こういう人の書いたものには、私はまったく関心がない。少なくとも、お金を出して読もうとは思わない。(ホントを言えば、お金をもらっても読もうとは思わない。しかし、この人が売れっ子作家というのだから、この国の「文化状況」というのはわけがわからない)
読者の深い共感を得るためには、子供のころは「優等生」より「劣等生」、おとなになってからも紆余曲折の人生を歩いていたほうがいいだろう。いいだろうと言っても、そんなことは望んで得られるものではないし、だれも好き好んで折れ曲がった人生コースなど歩きたいと思いはしない。
しかし、そういう谷間のような人生に落ち込んでしまった人は、往々にして文学に自分の人生のはけ口を求める。深く悲哀に満ちた人生知と物悲しいユーモア。共産党政権のもとで自由と人生を求めたために曲がりくねった道を歩き続けなければならなかったミラン・クンデラは、プラハの春の挫折後、祖国チェコを追放された。
その文学は、共産党政権、非共産党政権を問わず、あらゆる体制のもとで悲哀を味わわなければならなかった人々の耳目をひきつけ、その人生にとってなくてはならないものとなった。その文章に魅惑されたものは、すでにその文学がなくてはいてもたってもいられない。(少なくとも、私はそういう人間のうちのひとりだ)
そのクンデラの前に、またひとつの悲哀、曲がりくねった谷間があらわれた。共産党政権時代の秘密警察に協力したという中傷だ。ドゥプチェクを押しつぶしたあの政権の時代には、おそらく何があっても不思議ではなかったであろう。しかし、この中傷のケースは、単なる中傷のひとつということで落着しそうだ。また、クンデラには、中傷が示すような事実はなかっただろうことは、彼の読者であればすぐにわかる。党に密告され、裏切られた『冗談』の主人公が果たす復讐の手口は、逆密告などという手口などではなく、さらに深い人間性に迫るようなものだ。しかし、それさえも復讐としてあまりにつまらなく、あまりにも浅薄なものに思え、主人公は絶望する。絶望の果てに、忘却こそ人生を癒す救いであることに気がつく。
クンデラが、憎み続けた秘密警察に一瞬でも協力したならば、クンデラは小説なるものを書いてはいないだろう。小説なるものを書くことによって一瞬たりともそのような回想をすることはがまんができないだろう。そのようなことは、あらゆる体制を憎みながら、その体制への協力を毛筋ほども拒否し続けてきた人間なら即座に理解できるはずだ。
ソ連崩壊後、私はモスクワ郊外にあるレーニン博物館を訪れたことがある。仕事柄、展示されているレーニン思い出の品などを詳しくメモしていたところ、傍らに近づいてきた老婦人に右腕をつかまれ、「この人はレーニンの秘密を探るスパイだ」となじられたことがある。
この思い出は、ソ連が崩壊した1991年の冬のこと。独裁政権が砕け散ったかけらはいたるところに落ちていた。
いまもそのかけら、残滓は旧ソ連、東欧には残っている。それどころではない。この国、日本のいたるところに、一目につかず落ちている。このかけらのために、どれだけの人が傷ついていることか。傷ついた経験のある人なら、私がここに言うこの比喩がわかるだろう。
肉体的時間が許すなら、クンデラには、このケースをもとに新しい作品を書いてほしい。クンデラ自身のためだけではなく、傷ついている人々の癒しと救いのために。
上記のものを、私の日記にも掲載させていただきました。
作家として生きていくためには、読者の深い共感を得て、「この作家のものなら次も読んでみたい」と思われなければならない。名前は記さないが、現代の日本の売れっ子作家で、「ぼくは子供のころは優等生で何をしても親に心配をかけるようなことはまったくなかったですね」という驚くべき発言をしている人がいた。ほかの人もそうだと思うのだが、こういう人の書いたものには、私はまったく関心がない。少なくとも、お金を出して読もうとは思わない。(ホントを言えば、お金をもらっても読もうとは思わない。しかし、この人が売れっ子作家というのだから、この国の「文化状況」というのはわけがわからない)
読者の深い共感を得るためには、子供のころは「優等生」より「劣等生」、おとなになってからも紆余曲折の人生を歩いていたほうがいいだろう。いいだろうと言っても、そんなことは望んで得られるものではないし、だれも好き好んで折れ曲がった人生コースなど歩きたいと思いはしない。
しかし、そういう谷間のような人生に落ち込んでしまった人は、往々にして文学に自分の人生のはけ口を求める。深く悲哀に満ちた人生知と物悲しいユーモア。共産党政権のもとで自由と人生を求めたために曲がりくねった道を歩き続けなければならなかったミラン・クンデラは、プラハの春の挫折後、祖国チェコを追放された。
その文学は、共産党政権、非共産党政権を問わず、あらゆる体制のもとで悲哀を味わわなければならなかった人々の耳目をひきつけ、その人生にとってなくてはならないものとなった。その文章に魅惑されたものは、すでにその文学がなくてはいてもたってもいられない。(少なくとも、私はそういう人間のうちのひとりだ)
そのクンデラの前に、またひとつの悲哀、曲がりくねった谷間があらわれた。共産党政権時代の秘密警察に協力したという中傷だ。ドゥプチェクを押しつぶしたあの政権の時代には、おそらく何があっても不思議ではなかったであろう。しかし、この中傷のケースは、単なる中傷のひとつということで落着しそうだ。また、クンデラには、中傷が示すような事実はなかっただろうことは、彼の読者であればすぐにわかる。党に密告され、裏切られた『冗談』の主人公が果たす復讐の手口は、逆密告などという手口などではなく、さらに深い人間性に迫るようなものだ。しかし、それさえも復讐としてあまりにつまらなく、あまりにも浅薄なものに思え、主人公は絶望する。絶望の果てに、忘却こそ人生を癒す救いであることに気がつく。
クンデラが、憎み続けた秘密警察に一瞬でも協力したならば、クンデラは小説なるものを書いてはいないだろう。小説なるものを書くことによって一瞬たりともそのような回想をすることはがまんができないだろう。そのようなことは、あらゆる体制を憎みながら、その体制への協力を毛筋ほども拒否し続けてきた人間なら即座に理解できるはずだ。
ソ連崩壊後、私はモスクワ郊外にあるレーニン博物館を訪れたことがある。仕事柄、展示されているレーニン思い出の品などを詳しくメモしていたところ、傍らに近づいてきた老婦人に右腕をつかまれ、「この人はレーニンの秘密を探るスパイだ」となじられたことがある。
この思い出は、ソ連が崩壊した1991年の冬のこと。独裁政権が砕け散ったかけらはいたるところに落ちていた。
いまもそのかけら、残滓は旧ソ連、東欧には残っている。それどころではない。この国、日本のいたるところに、一目につかず落ちている。このかけらのために、どれだけの人が傷ついていることか。傷ついた経験のある人なら、私がここに言うこの比喩がわかるだろう。
肉体的時間が許すなら、クンデラには、このケースをもとに新しい作品を書いてほしい。クンデラ自身のためだけではなく、傷ついている人々の癒しと救いのために。
上記のものを、私の日記にも掲載させていただきました。
毎日新聞につづいて読売でも19日付けで記事になったようですが、いともあっけらかんに「チェコ共産政権に抵抗→実は密告者?作家クンデラ氏に疑惑」という見出し。
これって、駐在員がすぐにニュースを送っても、本社のデスクの判断で、遅れることがあるんでしょうか。
でも、その国際感覚って。。。
亡命というのも、ニホンにのうのうとしている身には、なかなかわからないことですよね。
ただ単にどこにいるかではなくて、粛清されるかいなかも関ってきますし。
旧ロシアから西に移ったナボコフやら、スペインからラテンアメリカに生き延びたひとたち、あるいはラテンアメリカの軍事独裁政から他のくににいのちからがら、渡ったひとたち、旧ナチから西に生き延びたひとたち(トーマス・マンの場合も、戦時にドイツにとどまらずに米国から意見したということで、ドイツで反感をもっているひちたちがいるようですね)。
またはキューバから米国に逃げたひとたち。
こういうときは、えてして、何を喋ったらいいのかわからなくなるときがあります。
これって、駐在員がすぐにニュースを送っても、本社のデスクの判断で、遅れることがあるんでしょうか。
でも、その国際感覚って。。。
亡命というのも、ニホンにのうのうとしている身には、なかなかわからないことですよね。
ただ単にどこにいるかではなくて、粛清されるかいなかも関ってきますし。
旧ロシアから西に移ったナボコフやら、スペインからラテンアメリカに生き延びたひとたち、あるいはラテンアメリカの軍事独裁政から他のくににいのちからがら、渡ったひとたち、旧ナチから西に生き延びたひとたち(トーマス・マンの場合も、戦時にドイツにとどまらずに米国から意見したということで、ドイツで反感をもっているひちたちがいるようですね)。
またはキューバから米国に逃げたひとたち。
こういうときは、えてして、何を喋ったらいいのかわからなくなるときがあります。
ここでいろんな真剣な意見をうかがえて、とてもありがたいことでした。少なくともここで書かれているかたは、真剣にこの事件を考えている。それがわかり、感動とともに感慨がありました。
クンデラへの複雑な思いは、故国からすれば当然あるわけです。それはクンデラが故国に対して複雑な思いをだいているように。
けれども、クンデラの小説をよめば、中傷は中傷にすぎない、ということもいえるのではないでしょうか。少なくとも、わたしはクンデラの描く小説からは、そうした行為をする人だとは、ぜったいに思えない。
わたしも一応文筆の世界に身をおいているのですが、机にむかうとき、自分にやましいところをなくすようにしています。けっしてただしいことばかりやってきているわけではありませんし、まちがいもおかすでしょうが、省みてやましいことがあると、創作にあたり、うまくいえませんが、何か失礼な気がするのです。机のまえで、正々堂々としていたいというか。クンデラの作品からは、とにかく卑劣さがうかがえない。潔白な魂の描く真摯さであふれている。
「なぜ私は一生よそ者なのか。ここが我が家だと思えるのは、まれに自分の言葉が話せた時だけ。自分の言葉…失われた言葉を再発見し、忘れられた言葉を沈黙から取り戻す…そんなまれな時にしか自分の足音が聞こえない…」
これは、テオ・アンゲロプロス監督『永遠と一日』のなかの詩人のせりふですが、クンデラについても、「孤独な悲痛な戦い」として、いえることだと思いました。
クンデラへの複雑な思いは、故国からすれば当然あるわけです。それはクンデラが故国に対して複雑な思いをだいているように。
けれども、クンデラの小説をよめば、中傷は中傷にすぎない、ということもいえるのではないでしょうか。少なくとも、わたしはクンデラの描く小説からは、そうした行為をする人だとは、ぜったいに思えない。
わたしも一応文筆の世界に身をおいているのですが、机にむかうとき、自分にやましいところをなくすようにしています。けっしてただしいことばかりやってきているわけではありませんし、まちがいもおかすでしょうが、省みてやましいことがあると、創作にあたり、うまくいえませんが、何か失礼な気がするのです。机のまえで、正々堂々としていたいというか。クンデラの作品からは、とにかく卑劣さがうかがえない。潔白な魂の描く真摯さであふれている。
「なぜ私は一生よそ者なのか。ここが我が家だと思えるのは、まれに自分の言葉が話せた時だけ。自分の言葉…失われた言葉を再発見し、忘れられた言葉を沈黙から取り戻す…そんなまれな時にしか自分の足音が聞こえない…」
これは、テオ・アンゲロプロス監督『永遠と一日』のなかの詩人のせりふですが、クンデラについても、「孤独な悲痛な戦い」として、いえることだと思いました。
お詫び: 15番のわたしのカキコにて、「CoMomotyさんが触れている」と記すべきところを不注意にて「CoMomotyが触れている」と、失礼な言い方をしてしまいました。ふかくお詫び申し上げます。
国際的にクンデラがどのように評価されるか、それとはべつにやはり、チェコ人のあいだでの気持ちというのは二分されるようです、ちょうどAebeeさんが触れていたように。
でもただたんに一面的であるのではなく、さまざまな見方も可能であるということは、それはそれで健全だと思えるのではないでしょうか。
その点の記事は、ヘラルド・トリビューンが詳細な内容をほこっています。
http://www.iht.com/articles/2008/10/17/europe/kundera.php?page=1
国際的にクンデラがどのように評価されるか、それとはべつにやはり、チェコ人のあいだでの気持ちというのは二分されるようです、ちょうどAebeeさんが触れていたように。
でもただたんに一面的であるのではなく、さまざまな見方も可能であるということは、それはそれで健全だと思えるのではないでしょうか。
その点の記事は、ヘラルド・トリビューンが詳細な内容をほこっています。
http://www.iht.com/articles/2008/10/17/europe/kundera.php?page=1
さぼさしさんの示してくださったヘラルド・トリビューンは確かに全貌がかなり良くわかりますね。
つまるところ、全体主義の愚かさ、恐ろしさ、ということに尽きるような気がします。
私が先に引いたNY Timesでも証言をしていたプラハのJiri Hepe教授の言葉が印象に残ります(彼はハベル大統領時代の顧問だったのですね)。
"The reality is that the totalitarian regime was constructed in such a way that 99 percent of people cooperated in one way or another, and the Kundera case helps them to feel morally absolved, like they are the good guys and he was one of the baddies,"
「(粗訳)全体主義の中では99%が何らかの形でつるんでいる。今回のクンデラの事件は、あいつは悪いやつで、自分たちは正しいのだ、と思える絶好の機会を与えてくれた。」
制度の弱さとともに、人間の弱さを上手くついた発言だと思います。
今回Ripka 紙がクンデラの密告を誤報道するに至った経緯も非常に詳しく書かれています。
何よりも責めるべきはいずれにしても、22年間も強制労働につかせた、まさに、その全体主義ではありますが。
軍隊から脱走して、ドイツに逃げ、アメリカの諜報局に保護されたDvoracek氏が、高校生時代の女友達のところに、預かってもらっていたスーツケースを取りに行った時に逮捕され、22年間強制労働につくことになった。その女友達の今のご主人、当時のボーイフレンドが、「彼女が危ない目にあうと思った」から密告したのだということを、密告直後に知人(現チェコ現諜報局員)に告げています。
この女性はその後強い罪悪感にとらわれるわけですが、その女性を罪悪感から解放したかった、ということと、クンデラがDvoracekを密告したとする1950年の警察記録が発見されたことから、Ripka 紙の今回の報道に至った。報道した32歳の若い記者は「クンデラが黒だと確信していたがあまりにも激しく否定するので、あるいは間違ったかという気になった」と語っています。
この警察記録当時の1950年は、クンデラがその2年前に入党したチェコ共産党から除名された年でもあります。
クンデラの親友は、彼を見る限りそういうことができる人間ではない。50年当時は内省的な共産主義者ではあったが、熱狂的ではなかった、と発言しています。(文章を見る限り・・・といった意味では、私もうみきょんさんと同じ意見です。テキストとはしかし、欺瞞を含められる大きな危険性も帯びておりますが。)
いずれにしても99%が「こうだ」と語る喧噪の中で静かに「そうではない」と言える1%の人間になれればと思います。
それは上で21番さんが言われているような「知識人の孤独」にもつながるでしょうね。
つまるところ、全体主義の愚かさ、恐ろしさ、ということに尽きるような気がします。
私が先に引いたNY Timesでも証言をしていたプラハのJiri Hepe教授の言葉が印象に残ります(彼はハベル大統領時代の顧問だったのですね)。
"The reality is that the totalitarian regime was constructed in such a way that 99 percent of people cooperated in one way or another, and the Kundera case helps them to feel morally absolved, like they are the good guys and he was one of the baddies,"
「(粗訳)全体主義の中では99%が何らかの形でつるんでいる。今回のクンデラの事件は、あいつは悪いやつで、自分たちは正しいのだ、と思える絶好の機会を与えてくれた。」
制度の弱さとともに、人間の弱さを上手くついた発言だと思います。
今回Ripka 紙がクンデラの密告を誤報道するに至った経緯も非常に詳しく書かれています。
何よりも責めるべきはいずれにしても、22年間も強制労働につかせた、まさに、その全体主義ではありますが。
軍隊から脱走して、ドイツに逃げ、アメリカの諜報局に保護されたDvoracek氏が、高校生時代の女友達のところに、預かってもらっていたスーツケースを取りに行った時に逮捕され、22年間強制労働につくことになった。その女友達の今のご主人、当時のボーイフレンドが、「彼女が危ない目にあうと思った」から密告したのだということを、密告直後に知人(現チェコ現諜報局員)に告げています。
この女性はその後強い罪悪感にとらわれるわけですが、その女性を罪悪感から解放したかった、ということと、クンデラがDvoracekを密告したとする1950年の警察記録が発見されたことから、Ripka 紙の今回の報道に至った。報道した32歳の若い記者は「クンデラが黒だと確信していたがあまりにも激しく否定するので、あるいは間違ったかという気になった」と語っています。
この警察記録当時の1950年は、クンデラがその2年前に入党したチェコ共産党から除名された年でもあります。
クンデラの親友は、彼を見る限りそういうことができる人間ではない。50年当時は内省的な共産主義者ではあったが、熱狂的ではなかった、と発言しています。(文章を見る限り・・・といった意味では、私もうみきょんさんと同じ意見です。テキストとはしかし、欺瞞を含められる大きな危険性も帯びておりますが。)
いずれにしても99%が「こうだ」と語る喧噪の中で静かに「そうではない」と言える1%の人間になれればと思います。
それは上で21番さんが言われているような「知識人の孤独」にもつながるでしょうね。
一般的に考えて、第一報、つまりクンデラについての疑いを目にしたひとは少なからずいるだろうが、それは誤報、あるいは捏造された情報であるということに通じるひとはよりすくなくなることが考えられる。
前者のほうが後者よりニュースヴァリューが高いと考えられるからだ。
ここにきてクンデラ側も、重い腰を動かしはじめるようだ。
クンデラは、チェコでの自分の代理エージェントDiliaのボスを通じて、Respekt誌にて、先の記事について率直な否定のメッセージを同誌の巻頭に掲載することを要求している。
このメッセージの宛先であるRespekt誌のオーナーは、まだ正式なコメントを発していない。
一方、チェコの政府関係筋は、見解をあらためてはいない。
この件、さらに長引いていきそう。
わたしが参考にしたのは、メキシコのホルナダ紙であるが、関連記事は国際的にいまだ現れてはいない模様。
チェコでの事実関係の報道は、たとえばここ:
http://www.czech.cz/en/news/culture/kundera-wants-apology-on-respekt-cover/
前者のほうが後者よりニュースヴァリューが高いと考えられるからだ。
ここにきてクンデラ側も、重い腰を動かしはじめるようだ。
クンデラは、チェコでの自分の代理エージェントDiliaのボスを通じて、Respekt誌にて、先の記事について率直な否定のメッセージを同誌の巻頭に掲載することを要求している。
このメッセージの宛先であるRespekt誌のオーナーは、まだ正式なコメントを発していない。
一方、チェコの政府関係筋は、見解をあらためてはいない。
この件、さらに長引いていきそう。
わたしが参考にしたのは、メキシコのホルナダ紙であるが、関連記事は国際的にいまだ現れてはいない模様。
チェコでの事実関係の報道は、たとえばここ:
http://www.czech.cz/en/news/culture/kundera-wants-apology-on-respekt-cover/
Respekt誌のオーナーは、自身の見解をあらためる気持ちがまったくないらしい。
いっぽう、世界の著名な作家たちが一団結し、ガリマール書店をつうじてクンデラを擁護する共同宣言を発表。
署名者を列記:
Gabriel García Márquez
Nadine Gordimer
J. M. Coetzee
Orhan Pamuk
Salman Rushdie
Juan Goytisolo
Jorge Semprún
Carlos Fuentes
Jean Daniel
Pierre Mertens
Philip Roth
その内容は、クンデラへの中傷に抗議し、さらに、各国マスコミの生ぬるい報道態度をも批判した内容になっている。
(スペインのエル・パイス紙より)
いっぽう、世界の著名な作家たちが一団結し、ガリマール書店をつうじてクンデラを擁護する共同宣言を発表。
署名者を列記:
Gabriel García Márquez
Nadine Gordimer
J. M. Coetzee
Orhan Pamuk
Salman Rushdie
Juan Goytisolo
Jorge Semprún
Carlos Fuentes
Jean Daniel
Pierre Mertens
Philip Roth
その内容は、クンデラへの中傷に抗議し、さらに、各国マスコミの生ぬるい報道態度をも批判した内容になっている。
(スペインのエル・パイス紙より)
いまさら、という感もあるが。。。
この件が再燃、Dpa電によると、プラハの保守系日刊紙Lidove Novinyからのものとして、1952年に国家防衛局の副総監のJaroslav Jermanなるものが、クンデラの1950年の「諜報活動」を讃えているという文書を発表。
紙面は、これによって1950年の文書が捏造であるという疑いは消えた、と報じている。
とにかく、いまさら。。。何を言われても、こちらとしては動じることもないのだけど。
ほんとうにクンデラを嫌ってるひとたちっているんですねえ。
わたしが見たのはラ・ホルナダ紙のDPA電、いまのところ、記事はチェコ語のもの中心、イギリスのテレグラフ紙のものもあり。
http://www.telegraph.co.uk/news/6399364/Milan-Kundera-was-an-informant-to-Czech-secret-police.html#
この件が再燃、Dpa電によると、プラハの保守系日刊紙Lidove Novinyからのものとして、1952年に国家防衛局の副総監のJaroslav Jermanなるものが、クンデラの1950年の「諜報活動」を讃えているという文書を発表。
紙面は、これによって1950年の文書が捏造であるという疑いは消えた、と報じている。
とにかく、いまさら。。。何を言われても、こちらとしては動じることもないのだけど。
ほんとうにクンデラを嫌ってるひとたちっているんですねえ。
わたしが見たのはラ・ホルナダ紙のDPA電、いまのところ、記事はチェコ語のもの中心、イギリスのテレグラフ紙のものもあり。
http://www.telegraph.co.uk/news/6399364/Milan-Kundera-was-an-informant-to-Czech-secret-police.html#
ミラン・クンデラはもう九十二歳、今週はハルキももらったカフカ賞の授与式があったものの、長いことパリに住んでいるクンデラは駐フランス・チェコ大使館に出向かなかった。今ではクンデラと祖国たるチェコは和解しているとわたしたちは了解。しかしながら実際は両者の間のつながりはより複雑なものらしい。遡ること50年代、どうやらクンデラはチェコにて体制派に与していたらしいと複数の関係者の証言が伝記に綴られる模様。現在、複数の伝記が編まれているらしい。もしそれが事実とすればわたしたちのクンデラのイメージに歪みが生じかねないが、時代そのものも考慮する必要がありそう。出典はスペインの有力紙エル・パイスの今日の記事より。
https://elpais.com/cultura/2021-06-12/el-enigma-milan-kundera-el-clasico-huidizo.html?fbclid=IwAR3ZWw65nB4KyRt3b05lWVilP3CDcycjExVT7kpwm9_QMenigeXkvysn-7U
https://elpais.com/cultura/2021-06-12/el-enigma-milan-kundera-el-clasico-huidizo.html?fbclid=IwAR3ZWw65nB4KyRt3b05lWVilP3CDcycjExVT7kpwm9_QMenigeXkvysn-7U
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ミラン・クンデラ 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ミラン・クンデラのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37864人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90062人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人