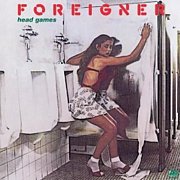「The Koln Concert」Keith Jarrett(1975年ドイツ)
「ケルン・コンサート」キース・ジャレット
1. Koln, January 24, 1975 Part 1
2. Koln, January 24, 1975 Part 2a
3. Koln, January 24, 1975 Part 2b
4. Koln, January 24, 1975 2c
現代の生きる伝説、いわゆる3大ジャズピアニストといえば、チック・コリア、ハービー・ハンコック、キース・ジャレットですね。
彼らがすごいのは、まだまだ現役感がバリバリなところですね。
もうほとんど何をしても許される状態。
しかし、3人とも異端ですね。
王道のジャズピアニストというくくりでははかりきれない。
3人ともマイルス・デイビスのもとにいた時期がありました。
マイルスのもとに集う才能と交わりながら、モダンジャズの本質と革新性をたたきこまれたんでしょうか。特にチックとキースは同じ時期にバンドにいて、ツイン・キーボードというときがありました。
キースの場合はマイルスの前にチャールス・ロイドのバンドで名声を上げましたが、さらにその前に、アート・ブレイキーのジャズ・メッセンジャーズ出身。
マイルスのもとを巣立ってからの3人が、70年代からのモダンジャズを牽引して来ました。
王道を学び、自分の個性を打ち出して、みずから新しいジャンルを形成するほどの世界を作り上げつつ、自由自在に王道との間を行き来きしながら、長年にわたって枯渇することのない才能を開拓し続ける彼ら。
なかでもキース・ジャレットの個性は際立っています。
70年代に入ってからの、「Facing you」「Solo Concert」そして75年の本作が一般的には決定打になり、70年代のソロピアノジャズの人気を確立しました。
キース・ジャレットを表現するとき、よくクラシックの素養、ということが言われます。
じゃあ彼のジャズがクラシックっぽいのかと言われると、そんなことはないでしょう。
むしろクラシックピアノの演奏家に言わせると、クラシックの演奏では作曲家の意図を再現することが最重要であって、弾き手の情感や即興は、最も抑制されるべきもの、だといいます。
それよりも事前の解釈やそれに基づく繊細なタッチ、音色、表現方法によって、いかに解釈した音楽を表現しきるか、が問われます。
昔のクラシックには、即興のパートが存在していました。
さらにジャズは、その制約を解き放ち、テーマになるフレーズのみ決めて、それ以外はジャズ的なフレーズとコード進行の即興の会話によってなりたっていきます。
チャーリー・パーカーやバド・パウエル、ビル・エヴァンスそしてマイルスらによってモダン・ジャズは進化してきました。
しかし、キースはそうした王道を踏まえながらも、弾く前に主題すら決まっていない状態で、しかもソロで演奏を開始する、という完全なる即興演奏のコンサートを行っていきます。
そこで聴かれるフレーズは、いわゆるジャズ的なものとは感触が異なります。
さらに、一つ一つの音のタッチが、非常に繊細で、緊張感をはらんでいます。
ジャズは、ともすればトリオ演奏などでも、その場のノリとグルーヴが優先され、ひとつの音の繊細さ、はクラシック音楽と比べると、あまり重視されないことが多い。
その意味では、ビル・エヴァンス的な、音のタッチに対する繊細な感覚、という点が、ジャズ界の中では最もクラシック的、な要素ともいえるでしょう。
しかし、ではキースの演奏が、繊細イコール ロマンティックなのか叙情的なのか、と言われると、まったくそんな感じではないですね。
むしろ張り詰めた空気が聞き手にも緊張感を与えるほどです。
キースのソロでは、テーマは決められていませんが、それは弾きながら探求されます。
たいてい冒頭は、探っていくところから始まります。
そしてテーマらしきものが発見されると、それがどんどん高められ、独特の熱を帯びたグルーヴを放ち、洪水のようにあふれるところまでいきます。
やがていくところまでいくと、急激にそれらはバラされます。
チャラにされてしまうのです。
そうしたすべてが、キースが何か神がかったものと対話をしているかのような、自らの中で培われたクラシックや王道の数々のジャズ音楽やそれ以外の民俗音楽などなど、すべてを放り込んだ混沌の中から、まるでガラス細工を取り出すようにつむぎだされます。
その音は、とても神秘的です。
知的で、とがって聞こえたりもします。
いわゆるロマンテックな甘い感じはありません。
都会的と表現されることもあります。
とても孤独感を感じさせることもあります。
まるで暗闇の中で、鳴り響いているように聞こえたりします。
静寂よりも静寂を感じさせたりします。
それらの対話は、本人もいっている通り、過去のジャズ的なフレーズを、避けることを旨としています。
あくまでも即興の中で、自然に降ってくる音をとらえて、鳴らしているといいます。
まるで真っ暗な中に、宇宙的な広がりを感じさせる音世界が広がる様は、いわゆる癒しの音楽とは180度違って似て非なるものです。
本作「ケルン・コンサート」は、そのような神がかった演奏の最たる作品です。
クラシック的な和声から民族的なリズムまで、感傷の手前で、クールに抑制されながら繰り出される音の洪水とすきまの静寂。
不思議なのは、だれも聞いたことのないはずのこの即興演奏に、どこかしっくりくるような、なつかしいような、親しみを覚えること。
そんなふうに、知性と情熱、神秘と懐かしさ、ジャズらしさとそうでないもの間で、ジャンルの壁を軽く越えつつ、ジャズ的なものの本質をとことん探究する冷たい情熱、それこそがキース・ジャレットの音楽がいつまでもみずみずしくて、魅力的で、色あせない理由でしょう。
本作はとっても奥が深くて神秘的でいながら、とても感性に訴える作品なので、これからジャズを聴いてみたいと思う初心者にもうってつけだと思います。
初心者向けでかつ超本格的、という意味ではビル・エヴァンスの「ワルツ・フォー・デビー」と並ぶんでしょう。
実際私も昔、いくつも名盤といわれるレコードを聴いても、なかなかジャズのよさを理解できず、入り込めなかった頃に、この「ケルン・コンサート」とビル・エヴァンスの「ワルツ・フォー・デヴィー」を聴いて、ジャズのよさを理解できるようになり、そこから色々なジャズの面白さに入ってゆくようになりました。
真っ暗にした夜の部屋で、一人でお酒でも飲みながら流してみてください。
できればカーテンを開けて星空が見えるといいですね。
まあ、ロックファンにもアピールするジャンルを越えた名盤中の名盤です。
「ケルン・コンサート」キース・ジャレット
1. Koln, January 24, 1975 Part 1
2. Koln, January 24, 1975 Part 2a
3. Koln, January 24, 1975 Part 2b
4. Koln, January 24, 1975 2c
現代の生きる伝説、いわゆる3大ジャズピアニストといえば、チック・コリア、ハービー・ハンコック、キース・ジャレットですね。
彼らがすごいのは、まだまだ現役感がバリバリなところですね。
もうほとんど何をしても許される状態。
しかし、3人とも異端ですね。
王道のジャズピアニストというくくりでははかりきれない。
3人ともマイルス・デイビスのもとにいた時期がありました。
マイルスのもとに集う才能と交わりながら、モダンジャズの本質と革新性をたたきこまれたんでしょうか。特にチックとキースは同じ時期にバンドにいて、ツイン・キーボードというときがありました。
キースの場合はマイルスの前にチャールス・ロイドのバンドで名声を上げましたが、さらにその前に、アート・ブレイキーのジャズ・メッセンジャーズ出身。
マイルスのもとを巣立ってからの3人が、70年代からのモダンジャズを牽引して来ました。
王道を学び、自分の個性を打ち出して、みずから新しいジャンルを形成するほどの世界を作り上げつつ、自由自在に王道との間を行き来きしながら、長年にわたって枯渇することのない才能を開拓し続ける彼ら。
なかでもキース・ジャレットの個性は際立っています。
70年代に入ってからの、「Facing you」「Solo Concert」そして75年の本作が一般的には決定打になり、70年代のソロピアノジャズの人気を確立しました。
キース・ジャレットを表現するとき、よくクラシックの素養、ということが言われます。
じゃあ彼のジャズがクラシックっぽいのかと言われると、そんなことはないでしょう。
むしろクラシックピアノの演奏家に言わせると、クラシックの演奏では作曲家の意図を再現することが最重要であって、弾き手の情感や即興は、最も抑制されるべきもの、だといいます。
それよりも事前の解釈やそれに基づく繊細なタッチ、音色、表現方法によって、いかに解釈した音楽を表現しきるか、が問われます。
昔のクラシックには、即興のパートが存在していました。
さらにジャズは、その制約を解き放ち、テーマになるフレーズのみ決めて、それ以外はジャズ的なフレーズとコード進行の即興の会話によってなりたっていきます。
チャーリー・パーカーやバド・パウエル、ビル・エヴァンスそしてマイルスらによってモダン・ジャズは進化してきました。
しかし、キースはそうした王道を踏まえながらも、弾く前に主題すら決まっていない状態で、しかもソロで演奏を開始する、という完全なる即興演奏のコンサートを行っていきます。
そこで聴かれるフレーズは、いわゆるジャズ的なものとは感触が異なります。
さらに、一つ一つの音のタッチが、非常に繊細で、緊張感をはらんでいます。
ジャズは、ともすればトリオ演奏などでも、その場のノリとグルーヴが優先され、ひとつの音の繊細さ、はクラシック音楽と比べると、あまり重視されないことが多い。
その意味では、ビル・エヴァンス的な、音のタッチに対する繊細な感覚、という点が、ジャズ界の中では最もクラシック的、な要素ともいえるでしょう。
しかし、ではキースの演奏が、繊細イコール ロマンティックなのか叙情的なのか、と言われると、まったくそんな感じではないですね。
むしろ張り詰めた空気が聞き手にも緊張感を与えるほどです。
キースのソロでは、テーマは決められていませんが、それは弾きながら探求されます。
たいてい冒頭は、探っていくところから始まります。
そしてテーマらしきものが発見されると、それがどんどん高められ、独特の熱を帯びたグルーヴを放ち、洪水のようにあふれるところまでいきます。
やがていくところまでいくと、急激にそれらはバラされます。
チャラにされてしまうのです。
そうしたすべてが、キースが何か神がかったものと対話をしているかのような、自らの中で培われたクラシックや王道の数々のジャズ音楽やそれ以外の民俗音楽などなど、すべてを放り込んだ混沌の中から、まるでガラス細工を取り出すようにつむぎだされます。
その音は、とても神秘的です。
知的で、とがって聞こえたりもします。
いわゆるロマンテックな甘い感じはありません。
都会的と表現されることもあります。
とても孤独感を感じさせることもあります。
まるで暗闇の中で、鳴り響いているように聞こえたりします。
静寂よりも静寂を感じさせたりします。
それらの対話は、本人もいっている通り、過去のジャズ的なフレーズを、避けることを旨としています。
あくまでも即興の中で、自然に降ってくる音をとらえて、鳴らしているといいます。
まるで真っ暗な中に、宇宙的な広がりを感じさせる音世界が広がる様は、いわゆる癒しの音楽とは180度違って似て非なるものです。
本作「ケルン・コンサート」は、そのような神がかった演奏の最たる作品です。
クラシック的な和声から民族的なリズムまで、感傷の手前で、クールに抑制されながら繰り出される音の洪水とすきまの静寂。
不思議なのは、だれも聞いたことのないはずのこの即興演奏に、どこかしっくりくるような、なつかしいような、親しみを覚えること。
そんなふうに、知性と情熱、神秘と懐かしさ、ジャズらしさとそうでないもの間で、ジャンルの壁を軽く越えつつ、ジャズ的なものの本質をとことん探究する冷たい情熱、それこそがキース・ジャレットの音楽がいつまでもみずみずしくて、魅力的で、色あせない理由でしょう。
本作はとっても奥が深くて神秘的でいながら、とても感性に訴える作品なので、これからジャズを聴いてみたいと思う初心者にもうってつけだと思います。
初心者向けでかつ超本格的、という意味ではビル・エヴァンスの「ワルツ・フォー・デビー」と並ぶんでしょう。
実際私も昔、いくつも名盤といわれるレコードを聴いても、なかなかジャズのよさを理解できず、入り込めなかった頃に、この「ケルン・コンサート」とビル・エヴァンスの「ワルツ・フォー・デヴィー」を聴いて、ジャズのよさを理解できるようになり、そこから色々なジャズの面白さに入ってゆくようになりました。
真っ暗にした夜の部屋で、一人でお酒でも飲みながら流してみてください。
できればカーテンを開けて星空が見えるといいですね。
まあ、ロックファンにもアピールするジャンルを越えた名盤中の名盤です。
|
|
|
|
|
|
|
|
洋楽名盤・新譜 レビュー 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
洋楽名盤・新譜 レビューのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6469人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19249人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208304人