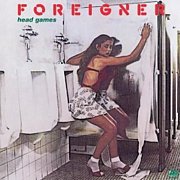The Byrds 「Mr.Tambourine Man」1965年US
1 Mr. Tambourine Man (02:29)
2 I'll Feel a Whole Lot Better (02:32)
3 Spanish Harlem Incident (01:57)
4 You Won't Have to Cry (02:08)
5 Here Without You (02:36)
6 Bells of Rhymney (03:30)
7 All I Really Want to Do (02:04)
8 I Knew I'd Want You (02:14)
9 It's No Use (02:23)
10 Don't Doubt Yourself, Babe (02:54)
11 Chimes of Freedom (03:51)
12 We'll Meet Again (02:07)
ジム(ロジャー)・マッギン(12弦ギター、ボーカル)、デヴィッド・クロスビー(ボーカル、リズムギター)、クリス・ヒルマン(ベース)、マイク・クラーク(ドラムス)、ジーン・クラーク(タンバリン、ボーカル)
バーズといえば昔、英語の教材で「Turn Turn Turn」が使われていたりして、どうも優等生的で古いポップス、というくらいの認識くらいしかなかった。結構な人がそんなイメージをもっているのではないだろうか。
しかしバーズから派生したCSN&Yをはじめとするアメリカンロックへの多大な影響、同時代のボブディランやビートルズとの絡み、80年代のREMやトム・ペティらをはじめとするアメリカンギターロックバンド、初期プライマルスクリームやザ・スミス、ストーンローゼスら英国勢、さらには最近のオルタナカントリーロックにまで及ぶその影響を考え合わせたとき、その大いなる始まりがこの1st/2ndの輝きから芽を出したことを考えたとき、この爽やかな音が全く違った新鮮さをもって聞こえてくるはずだ。全てのロックにとって最重要バンドのひとつといっても過言ではないバンド、バーズについてまずは初期の2枚のアルバムを紹介したい。
1960年代初頭のアメリカの音楽界は、公民権運動の盛り上がりに結びついた政治的なメッセージを伴うフォークの全盛期、一方ではビーチボーイズに代表されるサーフミュージックが隆盛だった。そこへ登場したのがビートルズ、作られた甘ったるいポップスに占められていた業界にR&Bの黒いフィーリングを伴ったストレートな歌詞とハードなギターやベースを持ち込みつつ親しみやすいメロディーとコーラスとシャウトを兼ね備えたビートルズの音はアメリカにも革命をもたらした。
62年に登場したボブディランは、主にニューヨークはグリニッジヴィレッジを中心に活動し、ポピュラーミュージックに恋愛の歌だけではなく社会性を持ち込み、ポップスの世界を押し広げ、時代的な背景と共に圧倒的な支持を受けていたが、そんなディランですら言葉でメッセージを伝えるフォークの限界と、ビートルズのインパクトを含めたロックという、自由で新しいスタイルの音楽に惹かれ、両者を融合させた「フォーク・ロック」という方向に大きく舵をきった、それが65年の「ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム」であり、このアルバムから漏れたお蔵入りの曲のカバーを1曲目に入れてアルバムタイトル「Mr.Tambourine Man」として同年に出されたのが、このバーズの1stアルバムである。ディランは、バーズによって蘇り全米1位にまでなったこの曲によってフォークロックへの舵取りを決意、「Like a rolling stone」の誕生に繋がるのである。
バーズの1stと2ndはこの時期のボブディランと期を同じくして、それまでのフォークとビートルズやビーチボーイズのロックを融合させた「フォークロック」の旗手としてアメリカ西海岸において登場し、先の「Mr.Tambourine Man」と2ndから「Turn Turn Turn」を全米1位に送り込み、一気にシーンの表舞台に躍り出、ビートルズに対するアメリカからの回答、とまで言われる存在となった。
ディランにさえ与えたその影響はさらにビートルズにまで逆輸入され「Nowhere man」「If I needed someone」などはバーズの影響を受けて作られたという話もある。
グループとしてだけでなくメンバー個々に、アメリカの音楽界に大きな影響を及ぼしてゆくことになるバーズの場合、個々のメンバーについて触れておくことも重要になってくるが、こと1stにおいては、当時LAの音楽界を牛耳っていた「音の壁」と呼ばれる分厚いサウンドプロダクションを得意としたフィルスペクターによって、その演奏をレオンラッセルらLAのスタジオミュージシャンのものに差し替えられ、残されたのはジム・マッギンのリードボーカル、デヴィット・クロスビーとジーン・クラークのコーラス、および「ハードデイズナイト」におけるジョージ・ハリソンの12弦ギターに影響を受けたジム・マッギンの12弦ギターだけであり、クリス・ヒルマンとマイク・クラークの音は入っていない、というのが実際であった。フォークロックのスタートは既存のLA音楽勢力の力を借りて成り立っていたというわけだ。
しかし3声コーラスにタンバリンと12弦ギターのアルペジオ的奏法という形態はバーズの個性、フォークロックの典型としてこの1stから確立され、西海岸におけるロックの大きな要素のひとつとなってゆく。
1stでは4曲がディランのカバーの他はブリティッシュビートへのコンプレックスを感じさせるような曲も多いが、逆にそれが初々しさ、フレッシュさや勢いのようなものを感じさせている気がする。2ndでもディランは2曲がカバーされているが、メンバーの個性が徐々に発揮され始めており、フォークロックの形は大幅に進化されており、全体としては1stよりもすこしゆったりと構えた印象を受ける。7曲目ではクリスヒルマンが持ち込みジーンクラークが歌うカントリーが早くも後期のカントリーロックの萌芽を感じさせる。10曲目「Wait and see」などからはREMやトムペティへの影響を感じさせるものがある。
65年の11月に「Turn Turn Turn」を1位に送り込んだ彼らだが、その10ヶ月後の66年9月にはサイケデリックロックを導入した「8 miles high」を発表し、その音楽性を大きくシフトしてゆくことになる。
聴けば聴くほど発見のある音楽史上マストなグループ、バーズの1st、2ndは朝のお出かけ前、もしくはロングドライブの一枚目にも最適、何かが始まる予感と勢いの詰まったアルバムだ。
1 Mr. Tambourine Man (02:29)
2 I'll Feel a Whole Lot Better (02:32)
3 Spanish Harlem Incident (01:57)
4 You Won't Have to Cry (02:08)
5 Here Without You (02:36)
6 Bells of Rhymney (03:30)
7 All I Really Want to Do (02:04)
8 I Knew I'd Want You (02:14)
9 It's No Use (02:23)
10 Don't Doubt Yourself, Babe (02:54)
11 Chimes of Freedom (03:51)
12 We'll Meet Again (02:07)
ジム(ロジャー)・マッギン(12弦ギター、ボーカル)、デヴィッド・クロスビー(ボーカル、リズムギター)、クリス・ヒルマン(ベース)、マイク・クラーク(ドラムス)、ジーン・クラーク(タンバリン、ボーカル)
バーズといえば昔、英語の教材で「Turn Turn Turn」が使われていたりして、どうも優等生的で古いポップス、というくらいの認識くらいしかなかった。結構な人がそんなイメージをもっているのではないだろうか。
しかしバーズから派生したCSN&Yをはじめとするアメリカンロックへの多大な影響、同時代のボブディランやビートルズとの絡み、80年代のREMやトム・ペティらをはじめとするアメリカンギターロックバンド、初期プライマルスクリームやザ・スミス、ストーンローゼスら英国勢、さらには最近のオルタナカントリーロックにまで及ぶその影響を考え合わせたとき、その大いなる始まりがこの1st/2ndの輝きから芽を出したことを考えたとき、この爽やかな音が全く違った新鮮さをもって聞こえてくるはずだ。全てのロックにとって最重要バンドのひとつといっても過言ではないバンド、バーズについてまずは初期の2枚のアルバムを紹介したい。
1960年代初頭のアメリカの音楽界は、公民権運動の盛り上がりに結びついた政治的なメッセージを伴うフォークの全盛期、一方ではビーチボーイズに代表されるサーフミュージックが隆盛だった。そこへ登場したのがビートルズ、作られた甘ったるいポップスに占められていた業界にR&Bの黒いフィーリングを伴ったストレートな歌詞とハードなギターやベースを持ち込みつつ親しみやすいメロディーとコーラスとシャウトを兼ね備えたビートルズの音はアメリカにも革命をもたらした。
62年に登場したボブディランは、主にニューヨークはグリニッジヴィレッジを中心に活動し、ポピュラーミュージックに恋愛の歌だけではなく社会性を持ち込み、ポップスの世界を押し広げ、時代的な背景と共に圧倒的な支持を受けていたが、そんなディランですら言葉でメッセージを伝えるフォークの限界と、ビートルズのインパクトを含めたロックという、自由で新しいスタイルの音楽に惹かれ、両者を融合させた「フォーク・ロック」という方向に大きく舵をきった、それが65年の「ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム」であり、このアルバムから漏れたお蔵入りの曲のカバーを1曲目に入れてアルバムタイトル「Mr.Tambourine Man」として同年に出されたのが、このバーズの1stアルバムである。ディランは、バーズによって蘇り全米1位にまでなったこの曲によってフォークロックへの舵取りを決意、「Like a rolling stone」の誕生に繋がるのである。
バーズの1stと2ndはこの時期のボブディランと期を同じくして、それまでのフォークとビートルズやビーチボーイズのロックを融合させた「フォークロック」の旗手としてアメリカ西海岸において登場し、先の「Mr.Tambourine Man」と2ndから「Turn Turn Turn」を全米1位に送り込み、一気にシーンの表舞台に躍り出、ビートルズに対するアメリカからの回答、とまで言われる存在となった。
ディランにさえ与えたその影響はさらにビートルズにまで逆輸入され「Nowhere man」「If I needed someone」などはバーズの影響を受けて作られたという話もある。
グループとしてだけでなくメンバー個々に、アメリカの音楽界に大きな影響を及ぼしてゆくことになるバーズの場合、個々のメンバーについて触れておくことも重要になってくるが、こと1stにおいては、当時LAの音楽界を牛耳っていた「音の壁」と呼ばれる分厚いサウンドプロダクションを得意としたフィルスペクターによって、その演奏をレオンラッセルらLAのスタジオミュージシャンのものに差し替えられ、残されたのはジム・マッギンのリードボーカル、デヴィット・クロスビーとジーン・クラークのコーラス、および「ハードデイズナイト」におけるジョージ・ハリソンの12弦ギターに影響を受けたジム・マッギンの12弦ギターだけであり、クリス・ヒルマンとマイク・クラークの音は入っていない、というのが実際であった。フォークロックのスタートは既存のLA音楽勢力の力を借りて成り立っていたというわけだ。
しかし3声コーラスにタンバリンと12弦ギターのアルペジオ的奏法という形態はバーズの個性、フォークロックの典型としてこの1stから確立され、西海岸におけるロックの大きな要素のひとつとなってゆく。
1stでは4曲がディランのカバーの他はブリティッシュビートへのコンプレックスを感じさせるような曲も多いが、逆にそれが初々しさ、フレッシュさや勢いのようなものを感じさせている気がする。2ndでもディランは2曲がカバーされているが、メンバーの個性が徐々に発揮され始めており、フォークロックの形は大幅に進化されており、全体としては1stよりもすこしゆったりと構えた印象を受ける。7曲目ではクリスヒルマンが持ち込みジーンクラークが歌うカントリーが早くも後期のカントリーロックの萌芽を感じさせる。10曲目「Wait and see」などからはREMやトムペティへの影響を感じさせるものがある。
65年の11月に「Turn Turn Turn」を1位に送り込んだ彼らだが、その10ヶ月後の66年9月にはサイケデリックロックを導入した「8 miles high」を発表し、その音楽性を大きくシフトしてゆくことになる。
聴けば聴くほど発見のある音楽史上マストなグループ、バーズの1st、2ndは朝のお出かけ前、もしくはロングドライブの一枚目にも最適、何かが始まる予感と勢いの詰まったアルバムだ。
|
|
|
|
|
|
|
|
洋楽名盤・新譜 レビュー 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
洋楽名盤・新譜 レビューのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 酒好き
- 170675人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37149人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90053人