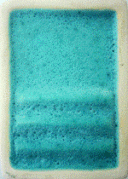|
|
|
|
コメント(44)
ちょっと付けたしです。
なおさん、てるどさんのおっしゃっていること、
ものすごく大事なことなんです。
焼き物を評価するときに日本語でよく使われる言葉で、
風格というものがありますが、
いわゆるその風格というもののある昔の釉薬というのは、
非常に微妙な焼成方法で焼かれていたんです。
電機窯を使う人間の悪い癖で、勿論僕もその一人ですが、
一口に酸化焼成と言ってしまうというのがあるんです。
確かに鉄分を黄色に発色させるには酸化雰囲気がよいのですが、
僕の経験でも、面白い黄色が出るのは弱還元焼成と、
酸化焼成の組み合わせなんです。
もっと細かく僕のやった焼き方を書いておきます。
使ったのはガス窯です。
例えば最終温度が1260℃位として、
まず1180〜1220℃付近まで酸化焼成をします。
これは鉄分が釉薬に溶け込むのが、
その釉薬ではこの温度域だからです。
この時釉薬は基本的に黄色く発色をしているのですが、
まだちょっと不安定な状態なんだと思います。
ここで、窯の中を弱還元状態にします。
要するに、釉薬に少し揺さぶりをかけているわけです。
大体20分ほどその状態を続けて、また酸化に戻して15分ほど。
温度の変化を見ながらこれを繰り返します。
還元の濃さなどによって、色々と結果が変わるので、
この辺はちょっと練習が必要になります。
で、最終的にもう一度酸化焼成をしておしまいです。
なおさんがどのような環境で焼いていらっしゃるのか、
わからないので、
この例が参考になるかは確かではないんですが、
焼き方に注意することで、色々と面白いことが起こります。
釉薬の調合も、勿論大事です。
ここに挙げた例だけではなく、本当に色々な焼き方があるので、
もし機会があるようでしたら試してみてください。
きっと面白さが広がると思います。
では。
なおさん、てるどさんのおっしゃっていること、
ものすごく大事なことなんです。
焼き物を評価するときに日本語でよく使われる言葉で、
風格というものがありますが、
いわゆるその風格というもののある昔の釉薬というのは、
非常に微妙な焼成方法で焼かれていたんです。
電機窯を使う人間の悪い癖で、勿論僕もその一人ですが、
一口に酸化焼成と言ってしまうというのがあるんです。
確かに鉄分を黄色に発色させるには酸化雰囲気がよいのですが、
僕の経験でも、面白い黄色が出るのは弱還元焼成と、
酸化焼成の組み合わせなんです。
もっと細かく僕のやった焼き方を書いておきます。
使ったのはガス窯です。
例えば最終温度が1260℃位として、
まず1180〜1220℃付近まで酸化焼成をします。
これは鉄分が釉薬に溶け込むのが、
その釉薬ではこの温度域だからです。
この時釉薬は基本的に黄色く発色をしているのですが、
まだちょっと不安定な状態なんだと思います。
ここで、窯の中を弱還元状態にします。
要するに、釉薬に少し揺さぶりをかけているわけです。
大体20分ほどその状態を続けて、また酸化に戻して15分ほど。
温度の変化を見ながらこれを繰り返します。
還元の濃さなどによって、色々と結果が変わるので、
この辺はちょっと練習が必要になります。
で、最終的にもう一度酸化焼成をしておしまいです。
なおさんがどのような環境で焼いていらっしゃるのか、
わからないので、
この例が参考になるかは確かではないんですが、
焼き方に注意することで、色々と面白いことが起こります。
釉薬の調合も、勿論大事です。
ここに挙げた例だけではなく、本当に色々な焼き方があるので、
もし機会があるようでしたら試してみてください。
きっと面白さが広がると思います。
では。
>コリッキーさん
はじめまして^^
私でお役に立てるかどうかわかりませんが。。。
私が御本を出すのに使っている長石は、釜戸長石、もしくは福島長石です。
これだと粉引きをせずとも、土によっては御本がでます。
三号釉使った事がありませんが、おそらく石灰ベースの透明釉では?
石灰透明で御本が出るのか、残念ながらわかりません。
電気窯との事ですが、還元はかけていますよね?
一番御本が出やすいのは、中性から弱還元だと思います。
それと、御本は冷める過程で出るので、ゆっくり冷ますと良いかも?
私はガス窯ですが、普通より厚壁にしてあるので、冷める時間が遅いです。
焼成条件で変わるので、一つの参考として色々御自分の窯にあった
物を見つけていくしか無いと思います^^;
粉引きをするとどうしても、口辺などの釉薬ののりは悪いですね。
私も苦労しています。
ピンホールは釉薬が落ちない程度に、全て指でキレイに馴らすか、
大きいものは筆で釉薬をぽちっと塗ります。
ピンホールの出方は土や、素焼きの加減で違ってきますね。
少しは参考になりましたでしょうか?
はじめまして^^
私でお役に立てるかどうかわかりませんが。。。
私が御本を出すのに使っている長石は、釜戸長石、もしくは福島長石です。
これだと粉引きをせずとも、土によっては御本がでます。
三号釉使った事がありませんが、おそらく石灰ベースの透明釉では?
石灰透明で御本が出るのか、残念ながらわかりません。
電気窯との事ですが、還元はかけていますよね?
一番御本が出やすいのは、中性から弱還元だと思います。
それと、御本は冷める過程で出るので、ゆっくり冷ますと良いかも?
私はガス窯ですが、普通より厚壁にしてあるので、冷める時間が遅いです。
焼成条件で変わるので、一つの参考として色々御自分の窯にあった
物を見つけていくしか無いと思います^^;
粉引きをするとどうしても、口辺などの釉薬ののりは悪いですね。
私も苦労しています。
ピンホールは釉薬が落ちない程度に、全て指でキレイに馴らすか、
大きいものは筆で釉薬をぽちっと塗ります。
ピンホールの出方は土や、素焼きの加減で違ってきますね。
少しは参考になりましたでしょうか?
>なつさん
始めまして、月子です。
粉引きに灰釉をかけていると言う事ですが、そう言う粉引きを狙っていますか?
長石釉が粉引きには一番合うと思われます。
灰釉は、上手く乗ったとしても流れやすいので、口をつける食器などには適さないような気がします。
その灰釉は粉引きしなくても、素地に吸われたようになりませんでしょうか?
濃さもあるし、土との相性で吸われたようになってしまう事もあります。
それと、ボーメの性能はわかりませんが、ボーメなどを使わず、体験的に釉薬の濃さを覚えた方が良いかと思います。
私自身も一度も使った事も、見た事すらありません。^^;
知っている作家さんも一人も使っていません。
あまりアドバイスになってないかな。^^;
始めまして、月子です。
粉引きに灰釉をかけていると言う事ですが、そう言う粉引きを狙っていますか?
長石釉が粉引きには一番合うと思われます。
灰釉は、上手く乗ったとしても流れやすいので、口をつける食器などには適さないような気がします。
その灰釉は粉引きしなくても、素地に吸われたようになりませんでしょうか?
濃さもあるし、土との相性で吸われたようになってしまう事もあります。
それと、ボーメの性能はわかりませんが、ボーメなどを使わず、体験的に釉薬の濃さを覚えた方が良いかと思います。
私自身も一度も使った事も、見た事すらありません。^^;
知っている作家さんも一人も使っていません。
あまりアドバイスになってないかな。^^;
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
釉薬コミュ 更新情報
釉薬コミュのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90068人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208325人
- 3位
- 酒好き
- 170698人