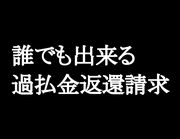訴状等の裁判文書は、A4用紙に12ポイントの文字で1行37字26行で書きます。
句読点「、」の変りに「,」を使うのが決まりです。
あまり厳密ではありませんが、こうやって書くとカッコいいです。
==========================
印紙
訴 状
平成○○年○○月15日
○○地方裁判所 民事部 御中
原 告 河 合 子 猫
【当事者】
とある県とある市かなり田舎町1−1−1
原 告 河 合 子 猫
電 話 080-0000-0001
大都会府大都会市ちょっと名の売れた町一丁目1番地
被 告 株式会社悪徳金融
上記代表者代表取締役 金 貸 太 郎
不当利得返還等請求事件
訴訟物の価額 金101万0550円
貼用印紙額 金1万2000円
==========================
【請求の趣旨】
1 被告は、原告に対し金110万0550円及びうち金100万0000円に対する平成△△年△△月11日(最終弁済日の翌日)から支払い済みまで年5分の割合による利息並びに金1万0550円に対する平成○○年○○月16日から支払い済みまで年5分の割合による利息を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決及び1に対する仮執行宣言の付与を求める。
【請求の原因】
1 当事者
被告は、貸金業登録を受けた貸金業者であり、原告は、被告の顧客であった一般市民である。
2 取引の概要
平成◆年◆月◆日上記当事者間において金銭消費貸借契約の基本契約(以下「本件基本契約」という。)が締結され、原告が、別紙引き直し計算書「借入金額」欄記載の金員を、対応する「年月日」欄記載の日に借入れ(以下「本件各借入」という。)、「弁済額」欄記載の金員を、対応する「年月日」欄記載の日に弁済(以下「本件各弁済」という。)する取引(以下「本件各取引」という。)が、平成△△年△△月10日まで反復継続して続いた。
3 過払金の発生
本件各弁済で、原告が被告に支払った金員のうち利息について、本件基本契約に基づく本件各取引に適用される約定利率(以下「本件約定利率」という。)は、年29.20%であり、利息制限法所定の制限利率を越えるため、この制限利率を越えた利息は当然に元本に充当され、元本が消滅した後の金員は過払金となる。
4 過払金に対する利息
被告は、業者登録を受けた貸金業者であり、過払金の発生について「悪意の受益者」と推定できるため、過払金には民法704条前段の利息が付加され、同利息に適用される利率は年5分の割合を下まわらない。
5 架空請求に対する慰謝料
過払金が発生した後の被告の原告に対する請求は、請求原因が存在せず、被告は最高裁判所が本件事件と同様の事案について判示した後にも同請求を継続したのであるから、不法行為が成立し、不法行為に対する損害賠償請求の対象となる。
6 過剰貸付に対する慰謝料
被告は、原告の生活が破綻することを承知で又は十分予期できたにも関わらず、原告の収入額に対し過剰といえる貸付を繰り返したのであるから、貸金業法13条に違反しており、不法行為が成立し、不法行為に対する損害賠償請求の対象となる。
7 請求額のまとめ
(1) 過払金 金100万0000円
(2) 利息未充当金 金9万0000円
(3) 架空請求慰謝料 金1万0000円
(4) 過剰貸付慰謝料 金550円
8 帰結
よって、原告は、被告に対し、過払金・利息未充当金及び慰謝料並びに過払金に対する最終弁済日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による利息及び慰謝料に対する本訴訟提起の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による利息の支払いを求める。
【証拠方法】
1 甲第1号証 基本契約書
2 甲第2号証 取引履歴
3 甲第3号証 最二判平成18年01月13日民集第60巻1号1頁
4 甲第4号証 最二判平成19年07月13日民集第61巻5号1980頁
5 甲第5号証 最二判平成16年02月20日民集第58巻2号475頁
6 甲第6号証 最一判平成17年12月15日民集第59巻10号2899頁
7 甲第7号証 最二判平成21年09月04日民集第63巻7号1445頁
8 甲第8号証 給料明細
9 甲第9号証 CIC個人情報開示記録
10 甲第10号証 JICC個人情報開示記録
【添付書面】
1 訴状副本 1通
2 甲号証写し 各1通
3 資格証明書 1通
==========================
訴状別紙 引き直し計算書
==========================
証拠説明書
==========================
そうそう、訴状と別紙の各ページ番号を下段に入れておくと、ページの継ぎ目に割り印しなくて済むので便利です。
訴状の提出をするとき、訴状正本・訴状副本・甲号証各2通・証拠説明書(正副)を準備して、法務局から相手さんの会社の代表者資格証明を取ってきて添付します。
送達などで切手も必要ですから、裁判所に確認して持って行ってください。
細かい間違いなどは受付で指摘してくれますので、その場で修正可能ですから、ご安心を。
まぁ、訴状書いて、資格証明とったら代表者が変ってたことも結構ありますが、受付で訂正できます。
こうやって訴状を出すと、数日後に第1回期日を決めてくれて、期日までに相手さんから答弁書なるものを送達されます。
過払金裁判なんて簡単なのに、業者側は結構もったいつけて、もたもたとしてますが、蛇に睨まれた蛙状態だと思って、ゆったり構えてください。
答弁書には、まともな裁判なら、原告主張に対する認否と被告の反論なんかが書かれてくるのですが、なかなか(笑)
句読点「、」の変りに「,」を使うのが決まりです。
あまり厳密ではありませんが、こうやって書くとカッコいいです。
==========================
印紙
訴 状
平成○○年○○月15日
○○地方裁判所 民事部 御中
原 告 河 合 子 猫
【当事者】
とある県とある市かなり田舎町1−1−1
原 告 河 合 子 猫
電 話 080-0000-0001
大都会府大都会市ちょっと名の売れた町一丁目1番地
被 告 株式会社悪徳金融
上記代表者代表取締役 金 貸 太 郎
不当利得返還等請求事件
訴訟物の価額 金101万0550円
貼用印紙額 金1万2000円
==========================
【請求の趣旨】
1 被告は、原告に対し金110万0550円及びうち金100万0000円に対する平成△△年△△月11日(最終弁済日の翌日)から支払い済みまで年5分の割合による利息並びに金1万0550円に対する平成○○年○○月16日から支払い済みまで年5分の割合による利息を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決及び1に対する仮執行宣言の付与を求める。
【請求の原因】
1 当事者
被告は、貸金業登録を受けた貸金業者であり、原告は、被告の顧客であった一般市民である。
2 取引の概要
平成◆年◆月◆日上記当事者間において金銭消費貸借契約の基本契約(以下「本件基本契約」という。)が締結され、原告が、別紙引き直し計算書「借入金額」欄記載の金員を、対応する「年月日」欄記載の日に借入れ(以下「本件各借入」という。)、「弁済額」欄記載の金員を、対応する「年月日」欄記載の日に弁済(以下「本件各弁済」という。)する取引(以下「本件各取引」という。)が、平成△△年△△月10日まで反復継続して続いた。
3 過払金の発生
本件各弁済で、原告が被告に支払った金員のうち利息について、本件基本契約に基づく本件各取引に適用される約定利率(以下「本件約定利率」という。)は、年29.20%であり、利息制限法所定の制限利率を越えるため、この制限利率を越えた利息は当然に元本に充当され、元本が消滅した後の金員は過払金となる。
4 過払金に対する利息
被告は、業者登録を受けた貸金業者であり、過払金の発生について「悪意の受益者」と推定できるため、過払金には民法704条前段の利息が付加され、同利息に適用される利率は年5分の割合を下まわらない。
5 架空請求に対する慰謝料
過払金が発生した後の被告の原告に対する請求は、請求原因が存在せず、被告は最高裁判所が本件事件と同様の事案について判示した後にも同請求を継続したのであるから、不法行為が成立し、不法行為に対する損害賠償請求の対象となる。
6 過剰貸付に対する慰謝料
被告は、原告の生活が破綻することを承知で又は十分予期できたにも関わらず、原告の収入額に対し過剰といえる貸付を繰り返したのであるから、貸金業法13条に違反しており、不法行為が成立し、不法行為に対する損害賠償請求の対象となる。
7 請求額のまとめ
(1) 過払金 金100万0000円
(2) 利息未充当金 金9万0000円
(3) 架空請求慰謝料 金1万0000円
(4) 過剰貸付慰謝料 金550円
8 帰結
よって、原告は、被告に対し、過払金・利息未充当金及び慰謝料並びに過払金に対する最終弁済日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による利息及び慰謝料に対する本訴訟提起の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による利息の支払いを求める。
【証拠方法】
1 甲第1号証 基本契約書
2 甲第2号証 取引履歴
3 甲第3号証 最二判平成18年01月13日民集第60巻1号1頁
4 甲第4号証 最二判平成19年07月13日民集第61巻5号1980頁
5 甲第5号証 最二判平成16年02月20日民集第58巻2号475頁
6 甲第6号証 最一判平成17年12月15日民集第59巻10号2899頁
7 甲第7号証 最二判平成21年09月04日民集第63巻7号1445頁
8 甲第8号証 給料明細
9 甲第9号証 CIC個人情報開示記録
10 甲第10号証 JICC個人情報開示記録
【添付書面】
1 訴状副本 1通
2 甲号証写し 各1通
3 資格証明書 1通
==========================
訴状別紙 引き直し計算書
==========================
証拠説明書
==========================
そうそう、訴状と別紙の各ページ番号を下段に入れておくと、ページの継ぎ目に割り印しなくて済むので便利です。
訴状の提出をするとき、訴状正本・訴状副本・甲号証各2通・証拠説明書(正副)を準備して、法務局から相手さんの会社の代表者資格証明を取ってきて添付します。
送達などで切手も必要ですから、裁判所に確認して持って行ってください。
細かい間違いなどは受付で指摘してくれますので、その場で修正可能ですから、ご安心を。
まぁ、訴状書いて、資格証明とったら代表者が変ってたことも結構ありますが、受付で訂正できます。
こうやって訴状を出すと、数日後に第1回期日を決めてくれて、期日までに相手さんから答弁書なるものを送達されます。
過払金裁判なんて簡単なのに、業者側は結構もったいつけて、もたもたとしてますが、蛇に睨まれた蛙状態だと思って、ゆったり構えてください。
答弁書には、まともな裁判なら、原告主張に対する認否と被告の反論なんかが書かれてくるのですが、なかなか(笑)
|
|
|
|
コメント(17)
平成○○年(ワ)第1192号 不当利得返還等請求事件
原 告 河 合 子 猫
被 告 株式会社悪徳金融
答 弁 書
平成○○年○○月31日
○○地方裁判所 第3民事部1係 御中
被 告 株式会社悪徳金融
大都会府大都会市大字都会字都会一番割の5
上記訴訟代理人弁護士 午志賀 磯 便
同 (担当) 下 場 鱈 樹
==========================
【請求の趣旨に対する答弁】
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
【請求の趣旨に対する答弁】
1 請求の趣旨1項及び2項は、認める。
2 同3項ないし6項は、否認又は争う。
3 同7項は、否認又は争う。
4 同8項は、争う。
【被告の主張】
1 過払金の発生について
原告は、利息制限法所定の利率に違反したことのみを理由に当然に元本に充当されるというが、そのような法律は存在しておらず、監督官庁の指導に従い、顧客重視の立場で営業してきた被告には貸金業法43条の規定が受けられると信じる特段の理由がある。
2 過払金利息について
上記1項に示したとおり、被告は健全な業務を営んでいたのであるから、仮に過払金が発生したとしても、原告が主張する「悪意の受益者」ではあり得ない。
3 架空請求に対する慰謝料について
上記1項及び2項に示したとおり、被告は貸金業法及び監督官庁の指導を重視してきたのだから、原告が主張するような架空請求では、絶対にあり得ない。
4 過剰貸付に対する慰謝料について
原告は、被告が原告に対して過剰な貸付けを行った旨、主張するが、原告は毎月かかさず弁済を続けてこれたのだから、過剰貸付とはいえない。
5 請求額について
被告は、貸金業法43条のみなし弁済の規定を遵守してきたのだから、原告の請求に理由は無い。
しかし、昨今、貸金業者は理由も無く悪者で、過払金を無条件に返さなければいけないという風潮であるので、仮に被告に過払金返還義務があるとしても、利息が付加されることはない。
6 帰結
よって、原告の請求には理由がないが、仮に被告に過払金返還義務があるとしても、その額は100万円を上回らない。
==========================
こんな感じなら良い方かな。
【請求の原因に対する答弁】以下が無く、「追って準備書面により答弁する。」みたいなのが多いです。
原 告 河 合 子 猫
被 告 株式会社悪徳金融
答 弁 書
平成○○年○○月31日
○○地方裁判所 第3民事部1係 御中
被 告 株式会社悪徳金融
大都会府大都会市大字都会字都会一番割の5
上記訴訟代理人弁護士 午志賀 磯 便
同 (担当) 下 場 鱈 樹
==========================
【請求の趣旨に対する答弁】
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
【請求の趣旨に対する答弁】
1 請求の趣旨1項及び2項は、認める。
2 同3項ないし6項は、否認又は争う。
3 同7項は、否認又は争う。
4 同8項は、争う。
【被告の主張】
1 過払金の発生について
原告は、利息制限法所定の利率に違反したことのみを理由に当然に元本に充当されるというが、そのような法律は存在しておらず、監督官庁の指導に従い、顧客重視の立場で営業してきた被告には貸金業法43条の規定が受けられると信じる特段の理由がある。
2 過払金利息について
上記1項に示したとおり、被告は健全な業務を営んでいたのであるから、仮に過払金が発生したとしても、原告が主張する「悪意の受益者」ではあり得ない。
3 架空請求に対する慰謝料について
上記1項及び2項に示したとおり、被告は貸金業法及び監督官庁の指導を重視してきたのだから、原告が主張するような架空請求では、絶対にあり得ない。
4 過剰貸付に対する慰謝料について
原告は、被告が原告に対して過剰な貸付けを行った旨、主張するが、原告は毎月かかさず弁済を続けてこれたのだから、過剰貸付とはいえない。
5 請求額について
被告は、貸金業法43条のみなし弁済の規定を遵守してきたのだから、原告の請求に理由は無い。
しかし、昨今、貸金業者は理由も無く悪者で、過払金を無条件に返さなければいけないという風潮であるので、仮に被告に過払金返還義務があるとしても、利息が付加されることはない。
6 帰結
よって、原告の請求には理由がないが、仮に被告に過払金返還義務があるとしても、その額は100万円を上回らない。
==========================
こんな感じなら良い方かな。
【請求の原因に対する答弁】以下が無く、「追って準備書面により答弁する。」みたいなのが多いです。
平成○○年(ワ)第1192号 不当利得返還等請求事件
原 告 河 合 子 猫
被 告 株式会社悪徳金融
(原告)準備書面1
平成○○年○○月○○日
○○地方裁判所 第3民事部1係 御中
原 告 河 合 子 猫
原告は、本書面により被告主張に対する反論及び求釈明を行う。
なお、略語等は、特にことわりのない限り従前の通り使用する。
==========================
第1 答弁書【被告の主張】に対する認否
1 1項について
被告が「監督官庁の指導に従い、顧客重視の立場で営業してきた。」ことについては不知。
「貸金業法43条の規定が受けられると信じる特段の理由がある。 」については否認する。
2 2項について
否認する。
3 3項及び4項について
否認又は争う。
4 5項について
否認する。
5 6項について
争う。
第2 原告の反論
1 貸金業法43条の規定が受けられると信じる特段の理由について
最高裁は、甲5等の判例により、貸金業者がみなし弁済規定の適用を受ける場合には、17条書面及び18条書面について厳格な要件事実の合致を求めており、他に最一判平成17年12月15日民集第59巻10号2899頁と照らし合わせても、被告に貸金業法43条の規定の適用を受ける特段の理由があるとはいえない。
被告が同様の主張を続けるのであれば、全ての17条書面及び18条書面の提示を求める。
2 悪意の受益者との推定について
最高裁は、甲4の判例などにより、「特段の理由がない場合には悪意の受益者と推定する。」と判示しているが、被告には最判平成21年7月14日集民第231号357頁のような特段の理由はない。
3 架空請求について
最高裁は、甲7の判例の本文の中で、「取引当時の最高裁判例の有無。」を判決理由としており、判例の事案は昭和55年から平成9年の取引であり、その行為の違法性阻却事由に該当していることを示しているが、本件事件において、被告は、甲3・甲5又は最一判平成11年01月21日民集第53巻1号98頁以後も従前と同様の取引を行っていたのであるから、違法性阻却事由は存在せず、不法行為が行われたといえる。
4 過剰貸付について
被告は、原告が返済事故も無く弁済を続けてきたことを以て、過剰貸付に該当しない旨の主張をしているが、原告が多重債務者であった事実は甲9及び甲10により明らかで、被告は当該個人情報を自由に閲覧できる立場であったのだから、また、甲1に記載されている取引開始当時の原告の収入は、甲8と比較しても十分信用できる金額であり、この収入しかない原告に対し、原告が多重債務者であると容易に知りうる被告が、原告の社会生活を脅かす金額の貸付けを行ったのであるから、過剰貸付が行われたといえる。
なお、貸金業法13条には、過剰貸付の禁止が明文化されている。
原 告 河 合 子 猫
被 告 株式会社悪徳金融
(原告)準備書面1
平成○○年○○月○○日
○○地方裁判所 第3民事部1係 御中
原 告 河 合 子 猫
原告は、本書面により被告主張に対する反論及び求釈明を行う。
なお、略語等は、特にことわりのない限り従前の通り使用する。
==========================
第1 答弁書【被告の主張】に対する認否
1 1項について
被告が「監督官庁の指導に従い、顧客重視の立場で営業してきた。」ことについては不知。
「貸金業法43条の規定が受けられると信じる特段の理由がある。 」については否認する。
2 2項について
否認する。
3 3項及び4項について
否認又は争う。
4 5項について
否認する。
5 6項について
争う。
第2 原告の反論
1 貸金業法43条の規定が受けられると信じる特段の理由について
最高裁は、甲5等の判例により、貸金業者がみなし弁済規定の適用を受ける場合には、17条書面及び18条書面について厳格な要件事実の合致を求めており、他に最一判平成17年12月15日民集第59巻10号2899頁と照らし合わせても、被告に貸金業法43条の規定の適用を受ける特段の理由があるとはいえない。
被告が同様の主張を続けるのであれば、全ての17条書面及び18条書面の提示を求める。
2 悪意の受益者との推定について
最高裁は、甲4の判例などにより、「特段の理由がない場合には悪意の受益者と推定する。」と判示しているが、被告には最判平成21年7月14日集民第231号357頁のような特段の理由はない。
3 架空請求について
最高裁は、甲7の判例の本文の中で、「取引当時の最高裁判例の有無。」を判決理由としており、判例の事案は昭和55年から平成9年の取引であり、その行為の違法性阻却事由に該当していることを示しているが、本件事件において、被告は、甲3・甲5又は最一判平成11年01月21日民集第53巻1号98頁以後も従前と同様の取引を行っていたのであるから、違法性阻却事由は存在せず、不法行為が行われたといえる。
4 過剰貸付について
被告は、原告が返済事故も無く弁済を続けてきたことを以て、過剰貸付に該当しない旨の主張をしているが、原告が多重債務者であった事実は甲9及び甲10により明らかで、被告は当該個人情報を自由に閲覧できる立場であったのだから、また、甲1に記載されている取引開始当時の原告の収入は、甲8と比較しても十分信用できる金額であり、この収入しかない原告に対し、原告が多重債務者であると容易に知りうる被告が、原告の社会生活を脅かす金額の貸付けを行ったのであるから、過剰貸付が行われたといえる。
なお、貸金業法13条には、過剰貸付の禁止が明文化されている。
ここから、本人訴訟にありがちな被告の主張を再現してみます。
はっきり言って、バカバカしい内容ですが、本当にありました。
貸金業者側も、相手が弁護士さんだとこんなバカな主張しないのでしょうが、本人訴訟で一番困るのがイレギュラーな主張や反論をされることです。
==========================
平成○○年(ワ)第1192号 不当利得返還等請求事件
原 告 河 合 子 猫
被 告 株式会社悪徳金融
(被告)準備書面1
平成○○年○○月○○日
○○地方裁判所 第3民事部1係 御中
被 告 株式会社悪徳金融
上記訴訟代理人弁護士 午志賀 磯 便
同 (担当) 下 場 鱈 樹
==========================
第1 被告の反論
1 17条書面及び18条書面の開示請求について
甲3の判例が出てしまった後の過払金返還請求事件において、17条書面及び18条書面の内容は、既に争点ではなく、開示する必要がない。
しかし、被告は、被告の主張に理由があることを立証するため17条書面のサンプルを証拠(乙1)として提示する。
乙1と甲1の内容を相互参照すると、貸金業法17条1項所定の記載事項の全てが網羅されていることがわかる。
なお、返済期間及び返済回数は基本契約に基づく契約であるため確定しておらず、各回の返済期日及び返済金額は極度額方式であるため確定していないため、合理的に判断し省略した。
2 悪意の受益者との推定について
原告は、「被告には最判平成21年7月14日集民第231号357頁のような特段の理由はない。」と断じているが、仮に過払金返還義務があるとしても、上記1項に示したとおり、被告の貸付けには合理的な理由があり、悪意の受益者と推定する余地がない。
3 架空請求について
甲7が判示しているのは、「貸金業者が借主に対し貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成するのは,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られ,この理は,当該貸金業者が過払金の受領につき民法704条所定の悪意の受益者であると推定されるときであっても異ならない。」ということであり、原告の主張は独自の解釈であり採用できない。
4 過剰貸付について
被告は、原告と基本契約を締結するに際し、金融庁の事務ガイドラインに沿った査定を行っており、手続き上なんら不備はなく、また、貸金業法13条の規定は、罰則規定の無い規範規定に過ぎず、仮に原告に対して多少の過剰貸付があったとしても、不法行為とはいえないのであるから、原告の主張には理由がない。
第2 和解申入れ
上記のとおり、被告は、被告に過払金返還義務はないと確信しておりますが、甲3の判例による「貸金業者はどんなに真面目に営業していても認めない。」という風潮を甘受するとともに、事件の早期解決のため、原告の請求のうち過払金本体の50%として、金50万円を支払い和解する用意がある。
==========================
思わず「ぷっ」と吹き出してしまいそうですが、こういう言い逃れをしてくることがあります。
ここで頭にきて短気を起こすと、裁判所の心証が悪くなりますので、冷静に対応しましょう。
はっきり言って、バカバカしい内容ですが、本当にありました。
貸金業者側も、相手が弁護士さんだとこんなバカな主張しないのでしょうが、本人訴訟で一番困るのがイレギュラーな主張や反論をされることです。
==========================
平成○○年(ワ)第1192号 不当利得返還等請求事件
原 告 河 合 子 猫
被 告 株式会社悪徳金融
(被告)準備書面1
平成○○年○○月○○日
○○地方裁判所 第3民事部1係 御中
被 告 株式会社悪徳金融
上記訴訟代理人弁護士 午志賀 磯 便
同 (担当) 下 場 鱈 樹
==========================
第1 被告の反論
1 17条書面及び18条書面の開示請求について
甲3の判例が出てしまった後の過払金返還請求事件において、17条書面及び18条書面の内容は、既に争点ではなく、開示する必要がない。
しかし、被告は、被告の主張に理由があることを立証するため17条書面のサンプルを証拠(乙1)として提示する。
乙1と甲1の内容を相互参照すると、貸金業法17条1項所定の記載事項の全てが網羅されていることがわかる。
なお、返済期間及び返済回数は基本契約に基づく契約であるため確定しておらず、各回の返済期日及び返済金額は極度額方式であるため確定していないため、合理的に判断し省略した。
2 悪意の受益者との推定について
原告は、「被告には最判平成21年7月14日集民第231号357頁のような特段の理由はない。」と断じているが、仮に過払金返還義務があるとしても、上記1項に示したとおり、被告の貸付けには合理的な理由があり、悪意の受益者と推定する余地がない。
3 架空請求について
甲7が判示しているのは、「貸金業者が借主に対し貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成するのは,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られ,この理は,当該貸金業者が過払金の受領につき民法704条所定の悪意の受益者であると推定されるときであっても異ならない。」ということであり、原告の主張は独自の解釈であり採用できない。
4 過剰貸付について
被告は、原告と基本契約を締結するに際し、金融庁の事務ガイドラインに沿った査定を行っており、手続き上なんら不備はなく、また、貸金業法13条の規定は、罰則規定の無い規範規定に過ぎず、仮に原告に対して多少の過剰貸付があったとしても、不法行為とはいえないのであるから、原告の主張には理由がない。
第2 和解申入れ
上記のとおり、被告は、被告に過払金返還義務はないと確信しておりますが、甲3の判例による「貸金業者はどんなに真面目に営業していても認めない。」という風潮を甘受するとともに、事件の早期解決のため、原告の請求のうち過払金本体の50%として、金50万円を支払い和解する用意がある。
==========================
思わず「ぷっ」と吹き出してしまいそうですが、こういう言い逃れをしてくることがあります。
ここで頭にきて短気を起こすと、裁判所の心証が悪くなりますので、冷静に対応しましょう。
平成○○年(ワ)第1192号 不当利得返還等請求事件
原 告 河 合 子 猫
被 告 株式会社悪徳金融
(原告)準備書面2
平成○○年○○月○○日
○○地方裁判所 第3民事部1係 御中
原 告 河 合 子 猫
原告は、本書面により(被告)準備書面1に対する再反論を行う。
なお、略語等は、特にことわりのない限り従前の通り使用する。
==========================
第1 再反論
1 過払金の発生についての自白
被告は、「甲3の判例が出てしまった後の過払金返還請求事件において、17条書面及び18条書面の内容は、既に争点ではなく、開示する必要がない。 」と過払金の発生を自白している。
2 悪意の受益者の推定について自白
被告は、「返済期間及び返済回数は基本契約に基づく契約であるため確定しておらず、各回の返済期日及び返済金額は極度額方式であるため確定していないため、合理的に判断し省略した。」と、甲6の基準に合致していないことを自白しているのであるから、悪意の受益者である。
3 架空請求について
被告は、自らの違法性阻却事由に言及しておらず、答弁になっていないため、自白の擬制を求める。
4 過剰貸付について
被告は、貸金業法13条の規定に罰則規定がないから不法行為とはならない旨の主張をし、法律の規定を軽視している姿勢が明確である。貸金業法1条は、「貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。」と顧客保護の姿勢を明確に規定しており、被告の答弁は、これに真っ向から対立するものであり、理由が無い。
原 告 河 合 子 猫
被 告 株式会社悪徳金融
(原告)準備書面2
平成○○年○○月○○日
○○地方裁判所 第3民事部1係 御中
原 告 河 合 子 猫
原告は、本書面により(被告)準備書面1に対する再反論を行う。
なお、略語等は、特にことわりのない限り従前の通り使用する。
==========================
第1 再反論
1 過払金の発生についての自白
被告は、「甲3の判例が出てしまった後の過払金返還請求事件において、17条書面及び18条書面の内容は、既に争点ではなく、開示する必要がない。 」と過払金の発生を自白している。
2 悪意の受益者の推定について自白
被告は、「返済期間及び返済回数は基本契約に基づく契約であるため確定しておらず、各回の返済期日及び返済金額は極度額方式であるため確定していないため、合理的に判断し省略した。」と、甲6の基準に合致していないことを自白しているのであるから、悪意の受益者である。
3 架空請求について
被告は、自らの違法性阻却事由に言及しておらず、答弁になっていないため、自白の擬制を求める。
4 過剰貸付について
被告は、貸金業法13条の規定に罰則規定がないから不法行為とはならない旨の主張をし、法律の規定を軽視している姿勢が明確である。貸金業法1条は、「貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。」と顧客保護の姿勢を明確に規定しており、被告の答弁は、これに真っ向から対立するものであり、理由が無い。
>新宿太郎さん
あけおめ^^ノ
請求物の価額のところには利息は含めないことになってます。
その分だけ貼用印紙(ちょうよういんし)代かからないということなんです。
例にしてる事案では差がありませんが、請求物の価額が110万円で、利息が10万円以上の場合、合計額の120万円以上だと印紙代が1万2000円なのですが…、(あ、0の貼用印紙代間違えてる><、)120万円未満だと1万1000円です。
実際、判決が出るまでにも毎日遅延損害金として利息は加算されて行きますよね。
未充当の利息金はこれと同様の扱いとなります。
17条書面と18条書面の部分について、履歴開示請求しても普通は17条書面及び18条書面を送付してくるわけではありませんよね。
業者が計算書みたいに加工してくるので、原告の手元に両書面がないことが多いです。
貸金業者の中には、自身が両書面を勝手に加工したものしか開示してこないのに、相手が本人訴訟だと、ナメてきて、両書面の記載内容を争ってきたりします。
原告に代理人がついてる場合、まずこんなところは争ってきませんが、本人訴訟だと大手の貸金業者でも争ってきてました。
判例も出てるし、業者の主張もめちゃくちゃなので、しっかり対応すれば確実に裁判所は被告の言い分を却下してくれます。
例でもそうですが、被告の主張そのものが自白になってるので、そこを指摘すれば十分です。
もし、被告が両書面を出さず、且つ具体的な答弁をしない場合、文書提出命令の申立てを行うという手段もありますが、そこまでやらなくても、原告が認めない限り裁判所は貸金業者の言い分を採用しません。最高裁判例出ちゃってますから(笑)
被告の代理人が生意気だったケース(遠方から呼びつけたのだが、遅刻してきて、ついでに飲み屋のねーちゃんを連れてきた馬鹿な弁護士のケース。)では、面白半分で文書提出命令の申立てをしてみましたが、数百ページありましたので、普通はそこまでしません。
文書提出命令が出たにも関わらず、被告が当該文書を提出しなかったとき、民訴224条の規定(相手方の言い分が正しいという推定。)が適用されることになります。
17条書面や18条書面を交付していたか否かってことを証拠もなく裁判所は認定できませんから、まずは提出を求めて、相手にリアクションをとらせることが大切です。
サンプルだろうが、何だろうが、提出してくれば間違いなく17条1項の規定に違反しています。
提出してこなければ、文書提出命令の申立てをするのですが、
一 文書の表示
二 文書の趣旨
三 文書の所持者
四 証明すべき事実
五 文書の提出義務の原因
以上を明らかにすればOKです。
==========================
平成○○年(ワ)第1192号 不当利得返還等請求事件
原 告 河 合 子 猫
被 告 株式会社悪徳金融
文書提出命令の申立書
平成○○年○○月○○日
○○地方裁判所 第3民事部1係 御中
原 告 河 合 子 猫
1 文書の表示及び趣旨
(1) 基本契約書及び各回の貸付確認書
(2) 各回の弁済金に対する領収証
(3) 頭書当事者間の、平成○年○月○日(基本契約締結日)から平成△年△月△日(最終取引日)までの、貸金業法17条1項及び同法18条1項所定の記載がある書面又はその写し。
2 文書の所持者
被告
3 証明すべき事実
貸金業法17条1項及び同法18条1項所定の記載内容の有無。
4 文書の提出義務の原因
頭書当事者間に締結された金銭消費貸借契約の内容並びに同取引中に原告に交付された貸付の
確認書及び同領収証であるため、民事訴訟法220条3号に該当する。
==========================
余談ですが、貸金業法を理解してない新人弁護士が被告代理人となったケースでは、その代理人に対して民訴155条2項(訴訟遂行能力の無い者に対する弁護士の付き添い命令)を上申したってのもありました。
認められませんでしたが、相手の弁護士さん笑い者になったでしょうね。
あけおめ^^ノ
請求物の価額のところには利息は含めないことになってます。
その分だけ貼用印紙(ちょうよういんし)代かからないということなんです。
例にしてる事案では差がありませんが、請求物の価額が110万円で、利息が10万円以上の場合、合計額の120万円以上だと印紙代が1万2000円なのですが…、(あ、0の貼用印紙代間違えてる><、)120万円未満だと1万1000円です。
実際、判決が出るまでにも毎日遅延損害金として利息は加算されて行きますよね。
未充当の利息金はこれと同様の扱いとなります。
17条書面と18条書面の部分について、履歴開示請求しても普通は17条書面及び18条書面を送付してくるわけではありませんよね。
業者が計算書みたいに加工してくるので、原告の手元に両書面がないことが多いです。
貸金業者の中には、自身が両書面を勝手に加工したものしか開示してこないのに、相手が本人訴訟だと、ナメてきて、両書面の記載内容を争ってきたりします。
原告に代理人がついてる場合、まずこんなところは争ってきませんが、本人訴訟だと大手の貸金業者でも争ってきてました。
判例も出てるし、業者の主張もめちゃくちゃなので、しっかり対応すれば確実に裁判所は被告の言い分を却下してくれます。
例でもそうですが、被告の主張そのものが自白になってるので、そこを指摘すれば十分です。
もし、被告が両書面を出さず、且つ具体的な答弁をしない場合、文書提出命令の申立てを行うという手段もありますが、そこまでやらなくても、原告が認めない限り裁判所は貸金業者の言い分を採用しません。最高裁判例出ちゃってますから(笑)
被告の代理人が生意気だったケース(遠方から呼びつけたのだが、遅刻してきて、ついでに飲み屋のねーちゃんを連れてきた馬鹿な弁護士のケース。)では、面白半分で文書提出命令の申立てをしてみましたが、数百ページありましたので、普通はそこまでしません。
文書提出命令が出たにも関わらず、被告が当該文書を提出しなかったとき、民訴224条の規定(相手方の言い分が正しいという推定。)が適用されることになります。
17条書面や18条書面を交付していたか否かってことを証拠もなく裁判所は認定できませんから、まずは提出を求めて、相手にリアクションをとらせることが大切です。
サンプルだろうが、何だろうが、提出してくれば間違いなく17条1項の規定に違反しています。
提出してこなければ、文書提出命令の申立てをするのですが、
一 文書の表示
二 文書の趣旨
三 文書の所持者
四 証明すべき事実
五 文書の提出義務の原因
以上を明らかにすればOKです。
==========================
平成○○年(ワ)第1192号 不当利得返還等請求事件
原 告 河 合 子 猫
被 告 株式会社悪徳金融
文書提出命令の申立書
平成○○年○○月○○日
○○地方裁判所 第3民事部1係 御中
原 告 河 合 子 猫
1 文書の表示及び趣旨
(1) 基本契約書及び各回の貸付確認書
(2) 各回の弁済金に対する領収証
(3) 頭書当事者間の、平成○年○月○日(基本契約締結日)から平成△年△月△日(最終取引日)までの、貸金業法17条1項及び同法18条1項所定の記載がある書面又はその写し。
2 文書の所持者
被告
3 証明すべき事実
貸金業法17条1項及び同法18条1項所定の記載内容の有無。
4 文書の提出義務の原因
頭書当事者間に締結された金銭消費貸借契約の内容並びに同取引中に原告に交付された貸付の
確認書及び同領収証であるため、民事訴訟法220条3号に該当する。
==========================
余談ですが、貸金業法を理解してない新人弁護士が被告代理人となったケースでは、その代理人に対して民訴155条2項(訴訟遂行能力の無い者に対する弁護士の付き添い命令)を上申したってのもありました。
認められませんでしたが、相手の弁護士さん笑い者になったでしょうね。
引き直し計算書について
ネット上に無償のものが転がってるそうですが、使った事ありません。
こんなものエクセルのワークシートに過ぎないのですから、さっさと自作しちゃいましょう。
注意点
・通常の年は1年を365日とするが、閏年は1年を366日として利息計算する。
・民法所定の充当順序は、1 費用 、2 未充当利息金 、3 元金 、の順番です。
・1円未満の端数金は、支払う側が有利なように切り捨てる。
・民法の規定に従って、初日算入しない。(借りた翌日に初めて利息が発生するという計算方法。)
自分で作ってみると、色々と面白いことがわかってきます。
そして、打ち込み作業の効率を上げることも可能です(ノートPC等ではテンキーパッドの使用推奨)。
無償配布されているものを事う場合でも、入力フォームは自作してみたらいいかも。
打ち込み作業、キーボード慣れしてる人でも、結構大変そうですが、ちょっと頭を使うと楽チンっす。
オラみたいなヘボでも、20年ぐらいの履歴の入力にかかる時間は10〜15分程度になってしまいます。
悪質な業者の場合、1顧客に6口座×約20年分ってケースもありましたので、まともに入力してたら死んでたかも…orz
スキャナー持ってないし…
ネット上に無償のものが転がってるそうですが、使った事ありません。
こんなものエクセルのワークシートに過ぎないのですから、さっさと自作しちゃいましょう。
注意点
・通常の年は1年を365日とするが、閏年は1年を366日として利息計算する。
・民法所定の充当順序は、1 費用 、2 未充当利息金 、3 元金 、の順番です。
・1円未満の端数金は、支払う側が有利なように切り捨てる。
・民法の規定に従って、初日算入しない。(借りた翌日に初めて利息が発生するという計算方法。)
自分で作ってみると、色々と面白いことがわかってきます。
そして、打ち込み作業の効率を上げることも可能です(ノートPC等ではテンキーパッドの使用推奨)。
無償配布されているものを事う場合でも、入力フォームは自作してみたらいいかも。
打ち込み作業、キーボード慣れしてる人でも、結構大変そうですが、ちょっと頭を使うと楽チンっす。
オラみたいなヘボでも、20年ぐらいの履歴の入力にかかる時間は10〜15分程度になってしまいます。
悪質な業者の場合、1顧客に6口座×約20年分ってケースもありましたので、まともに入力してたら死んでたかも…orz
スキャナー持ってないし…
あ、計算間違いなんですね。
内金請求に思えたもので。
17条18条書面については立証責任が被告にあるため、被告が立証できなきゃそれで終りですよ。つまり実物のコピー等を証拠提出できなきゃそこで終りということです。
また、文提命令というのはめったに認められないですよ。
15社くらい提訴しましたが、シティズだけは17条書面を公証役場の確定日付つきで出してきました。当然、みなし弁済は認定されてしまいました。
ここに書いた。
http://mixi.jp/view_community.pl?id=2240320
慰謝料請求を別口で請求したら最高裁までいけるのですかね?
不法行為の慰謝料については、訴えても認められないというより、立証が出来ないのですよ。
内金請求に思えたもので。
17条18条書面については立証責任が被告にあるため、被告が立証できなきゃそれで終りですよ。つまり実物のコピー等を証拠提出できなきゃそこで終りということです。
また、文提命令というのはめったに認められないですよ。
15社くらい提訴しましたが、シティズだけは17条書面を公証役場の確定日付つきで出してきました。当然、みなし弁済は認定されてしまいました。
ここに書いた。
http://mixi.jp/view_community.pl?id=2240320
慰謝料請求を別口で請求したら最高裁までいけるのですかね?
不法行為の慰謝料については、訴えても認められないというより、立証が出来ないのですよ。
>新宿太郎さん
すいません、手数料計算ミスってた><
17条18条の書面について、おっしゃるとおりです。
しかし、昨年の時点でまだ例に挙げたみたいなトンチンカンな主張をしてくる業者がいました。
ようするに、業者の思惑って、原告に「悪意の受益者ではない。」と認めさせるところにあるのでしょう。
シティーズを相手にしたのは災難でしたね><
事案の経過読ませてもらいました。
遅延損害金についての相手方主張を突き破るのに、実際の弁済に適用された利率を主張してみるって手は無かったのでしょうか?
たぶん、引き直し計算をすることになって初めて遅延損害金の適用を主張してきたと思うのですが、それまでの領収証に記載されてる利息充当金はどうなってるのでしょう?
約定に沿った弁済が行われていたときに、各回の弁済で、継続して遅延損害金を支払っていたなら手がつけられないのですが、相手方が29.2%の約定利率を適用していたのなら戦えそうですけど…。
まぁ、相手方の会社が消滅するという事情があったのだから、良い判断ではなかったでしょうか。
請求について、併せていっしょに訴訟を提起することもできれば、各請求をバラバラに行うこともできます。
ただし、一事不再理の原則がありますので、一旦請求して敗訴したものをまた請求するということは、なかなか難しく、ほとんど却下されてしまします。
高裁までで、過払金本体と利息部分で勝訴し、架空請求と過剰貸付で敗訴した事案を、上告及び上告受理申立てしましたが、両方受理されましたよ。
つまり、架空請求とか過剰貸付とかという問題には、憲法問題に絡む事情が認められるということ。
しかし、この相手方、過払金の支払いを渋っていたので、この相手方に事業資金を融資していた銀行など18社を名指しし、うち9社を相手に連帯債務履行請求事件を別に提起してたのですが、この一審判決の後、相手方と和解したので、取り下げちゃいました。
担当は第二小法廷でしたが、審議すると決めた事案を取り下げちゃってますから、審議したくてウズウズしてるかもね。
今、他の事案を、架空請求問題で上告していますので、結果が出たら書き書きします。
20年ぐらい弁済を続けてきたケースを考えてみてください。
そのうち最低10年以上は、過払い状態だったのです。
つまり、債務がないのに弁済を強要させられていたことになりますよね。
そして、支払う法的根拠のない債務のせいで多重債務に陥り家庭崩壊…。
このようなケースの救済が為されないって、どこかおかしいのではありませんか?
子供に美味しい物を食べさせたくても、新しい洋服を買ってやりたくても、借金をしている身となれば、まずは借りたお金を返すことが先決です。
しかし、この弁済が終了しており、そのことを業者側が知っていた又は当然知っているべき事情であったにも関わらず、ありもしない弁済を反復・継続させたのだから、十分不法行為となり得るし、たとえその実損を立証しきれないとしても、精神的苦痛を訴える範囲で十分です。
現実問題として、弁済金の支払いのために、ATM等のある場所までの交通費もかかりますし、機械を操作する事務手数料も請求できるはずです。
あっ、いいこと思いついた(笑)
相手方の反論に対する再反論で、「仮に不法行為と認定されなくても、ATMがある場所までの交通費及びATMを操作する事務手数料等が、実損として発生している。」と訴えてみようb
新宿太郎さん、ありがとう^^ノ
すいません、手数料計算ミスってた><
17条18条の書面について、おっしゃるとおりです。
しかし、昨年の時点でまだ例に挙げたみたいなトンチンカンな主張をしてくる業者がいました。
ようするに、業者の思惑って、原告に「悪意の受益者ではない。」と認めさせるところにあるのでしょう。
シティーズを相手にしたのは災難でしたね><
事案の経過読ませてもらいました。
遅延損害金についての相手方主張を突き破るのに、実際の弁済に適用された利率を主張してみるって手は無かったのでしょうか?
たぶん、引き直し計算をすることになって初めて遅延損害金の適用を主張してきたと思うのですが、それまでの領収証に記載されてる利息充当金はどうなってるのでしょう?
約定に沿った弁済が行われていたときに、各回の弁済で、継続して遅延損害金を支払っていたなら手がつけられないのですが、相手方が29.2%の約定利率を適用していたのなら戦えそうですけど…。
まぁ、相手方の会社が消滅するという事情があったのだから、良い判断ではなかったでしょうか。
請求について、併せていっしょに訴訟を提起することもできれば、各請求をバラバラに行うこともできます。
ただし、一事不再理の原則がありますので、一旦請求して敗訴したものをまた請求するということは、なかなか難しく、ほとんど却下されてしまします。
高裁までで、過払金本体と利息部分で勝訴し、架空請求と過剰貸付で敗訴した事案を、上告及び上告受理申立てしましたが、両方受理されましたよ。
つまり、架空請求とか過剰貸付とかという問題には、憲法問題に絡む事情が認められるということ。
しかし、この相手方、過払金の支払いを渋っていたので、この相手方に事業資金を融資していた銀行など18社を名指しし、うち9社を相手に連帯債務履行請求事件を別に提起してたのですが、この一審判決の後、相手方と和解したので、取り下げちゃいました。
担当は第二小法廷でしたが、審議すると決めた事案を取り下げちゃってますから、審議したくてウズウズしてるかもね。
今、他の事案を、架空請求問題で上告していますので、結果が出たら書き書きします。
20年ぐらい弁済を続けてきたケースを考えてみてください。
そのうち最低10年以上は、過払い状態だったのです。
つまり、債務がないのに弁済を強要させられていたことになりますよね。
そして、支払う法的根拠のない債務のせいで多重債務に陥り家庭崩壊…。
このようなケースの救済が為されないって、どこかおかしいのではありませんか?
子供に美味しい物を食べさせたくても、新しい洋服を買ってやりたくても、借金をしている身となれば、まずは借りたお金を返すことが先決です。
しかし、この弁済が終了しており、そのことを業者側が知っていた又は当然知っているべき事情であったにも関わらず、ありもしない弁済を反復・継続させたのだから、十分不法行為となり得るし、たとえその実損を立証しきれないとしても、精神的苦痛を訴える範囲で十分です。
現実問題として、弁済金の支払いのために、ATM等のある場所までの交通費もかかりますし、機械を操作する事務手数料も請求できるはずです。
あっ、いいこと思いついた(笑)
相手方の反論に対する再反論で、「仮に不法行為と認定されなくても、ATMがある場所までの交通費及びATMを操作する事務手数料等が、実損として発生している。」と訴えてみようb
新宿太郎さん、ありがとう^^ノ
シティズに関しては違うのですよ。
領収書、いわゆる17条書面は、遅れが出るまでは「利息」と書かれていて。1回遅れたあとは「遅延損害金」と書かれているんです。
つまり、期限の利益は喪失したから遅延損害金を受取ってるという仕組みができあがっていたのです。
ですので、引きなおしで初めて遅延損害金の主張ではないんです。
さらにご丁寧に、本領収書に異議等がある場合は連絡してくれとも書いてありました。
個人提訴ではありますが、その都度弁護士と相談していて、けっきょくは信義則違反で行くしかないかな?と。シティズが負けた裁判は、すべて信義則違反だったんですよ。
つまり「遅れが何回以内」だと「期限の利益の喪失」はきつい適用か?という話でした。
弁護士は「1回までだろううね」という認識でした。
控訴審では、忘れちゃったけど、高裁の判事もすぐ理解できないような主張をしてきて、けっきょく和解勧告となったのだが、和解の場でも高裁判事が説明してくれて、「下手すると一審の勝訴部分も白紙になる可能性がある」と言われて控訴を取り下げました。
架空請求については、みなし弁済適用についての当時の大蔵省通達を、業者が遵守してなかったということを崩さないと認定されないような感じを受けました。
ようは当時としては業者は大蔵省通達を守っていたことが「特段の事情」にあたると多分主張してきます。
おそらく当時の大蔵省ガイドラインに違反する取立てによる支払いを絡めないと難しいのではないでしょうか。
強いて言うならばATM返済での任意性を絡めるのかな?つまり任意に支払っていないことが詐欺、脅迫にあたるという理屈。ATMでの返済を強要されたことが立証できるならば架空請求に当たるのかもしれません。
領収書、いわゆる17条書面は、遅れが出るまでは「利息」と書かれていて。1回遅れたあとは「遅延損害金」と書かれているんです。
つまり、期限の利益は喪失したから遅延損害金を受取ってるという仕組みができあがっていたのです。
ですので、引きなおしで初めて遅延損害金の主張ではないんです。
さらにご丁寧に、本領収書に異議等がある場合は連絡してくれとも書いてありました。
個人提訴ではありますが、その都度弁護士と相談していて、けっきょくは信義則違反で行くしかないかな?と。シティズが負けた裁判は、すべて信義則違反だったんですよ。
つまり「遅れが何回以内」だと「期限の利益の喪失」はきつい適用か?という話でした。
弁護士は「1回までだろううね」という認識でした。
控訴審では、忘れちゃったけど、高裁の判事もすぐ理解できないような主張をしてきて、けっきょく和解勧告となったのだが、和解の場でも高裁判事が説明してくれて、「下手すると一審の勝訴部分も白紙になる可能性がある」と言われて控訴を取り下げました。
架空請求については、みなし弁済適用についての当時の大蔵省通達を、業者が遵守してなかったということを崩さないと認定されないような感じを受けました。
ようは当時としては業者は大蔵省通達を守っていたことが「特段の事情」にあたると多分主張してきます。
おそらく当時の大蔵省ガイドラインに違反する取立てによる支払いを絡めないと難しいのではないでしょうか。
強いて言うならばATM返済での任意性を絡めるのかな?つまり任意に支払っていないことが詐欺、脅迫にあたるという理屈。ATMでの返済を強要されたことが立証できるならば架空請求に当たるのかもしれません。
シティズに関して最高裁判断はこうです。
みなし弁済の成立しないことを前提とする利息制限法の引きなおし計算では、期限の利益喪失の主張を裁判上で行い、最高裁判所において勝訴と敗訴の両方の判決を得ている。
期限の利益の喪失の宥恕、再度期限の利益を付与したか否かの争点については、2009年4月14日には最高裁第三小法廷が原審を東京高等裁判所とする平成19(受)996号 貸金請求本訴,損害賠償等請求反訴事件において「貸金業者が,借主に対し,期限の利益の喪失を宥恕し,再度期限の利益を付与したとした原審の判断に違法がある」と判断して、勝訴した。
期限の利益の喪失の主張が信義則に反するかの争点については、2009年9月11日に最高裁判所第二小法廷が原審を高松高等裁判所とする平成19(受)1128号貸金等請求本訴,不当利得返還請求反訴事件においては「貸金業者において,特約に基づき借主が期限の利益を喪失した旨主張することが,信義則に反し許されないとした原審の判断に違法がある」と判断し、シティズは勝訴する一方、同じ2009年9月11日に同じく最高裁判所第二小法廷が原審を大阪高等裁判所とする平成21(受)138号不当利得返還請求事件においては「貸金業者において,特約に基づき借主が期限の利益を喪失した旨主張することが,信義則に反し許されないと判断し、シティズは敗訴した。この2つの異なる判決の解釈については、平成19(受)1128号判決を原則的な場合についての判断であり、平成21(受)138号は特殊な事例についての判断であるとする見解が存在する。
つまり原則はシティズ勝訴です。
みなし弁済の成立しないことを前提とする利息制限法の引きなおし計算では、期限の利益喪失の主張を裁判上で行い、最高裁判所において勝訴と敗訴の両方の判決を得ている。
期限の利益の喪失の宥恕、再度期限の利益を付与したか否かの争点については、2009年4月14日には最高裁第三小法廷が原審を東京高等裁判所とする平成19(受)996号 貸金請求本訴,損害賠償等請求反訴事件において「貸金業者が,借主に対し,期限の利益の喪失を宥恕し,再度期限の利益を付与したとした原審の判断に違法がある」と判断して、勝訴した。
期限の利益の喪失の主張が信義則に反するかの争点については、2009年9月11日に最高裁判所第二小法廷が原審を高松高等裁判所とする平成19(受)1128号貸金等請求本訴,不当利得返還請求反訴事件においては「貸金業者において,特約に基づき借主が期限の利益を喪失した旨主張することが,信義則に反し許されないとした原審の判断に違法がある」と判断し、シティズは勝訴する一方、同じ2009年9月11日に同じく最高裁判所第二小法廷が原審を大阪高等裁判所とする平成21(受)138号不当利得返還請求事件においては「貸金業者において,特約に基づき借主が期限の利益を喪失した旨主張することが,信義則に反し許されないと判断し、シティズは敗訴した。この2つの異なる判決の解釈については、平成19(受)1128号判決を原則的な場合についての判断であり、平成21(受)138号は特殊な事例についての判断であるとする見解が存在する。
つまり原則はシティズ勝訴です。
>新宿太郎さん
シティズは、真面目な貸金業者だったということじゃないでしょうか。
実際問題として、資金フローが逼迫してる企業が生き残るためには、目先の利息云々より、いかにすばやく資金需要に対応してくれるかってことの方が重要だと思います。
シティズのような貸金業者がいなければ、困るのは資金需要者の方で、本来、貸金業法43条の規定を遵守している限り、咎めるべきではなかったのではないでしょうか。
シティズは、どっちかっていうと他の貸金業者のとばっちりを受けてしまったような感じを受けています。
だから、いくらかでも過払金を取り戻せたなら大金星なのではありませんかね。
>>任意に支払っていないことが詐欺、脅迫にあたるという理屈。
これも当然指摘してます^^。
ガイドラインに関しては、「律>令」の原則を主張するつもりです。
仮に「令」に従っていたとしても、判示された「律」に違反する行為があれば不法行為となる。
被告側が「令」に従っていたことに対する非は、原告側には一切無い。
従って、被告が「令」があったことを以て対抗できる相手は原告ではなく、金融庁である。
仮に本件事件で被告が敗訴した場合、金融庁を相手に国家賠償を求めればよいだけで、原告とは全く関係が無いということ。
最高裁の好きそうな論法でしょ(笑)
そして敗訴した貸金業者が国家賠償を求めて訴訟の提起を行っても、国の訟務官に木っ端微塵に吹き飛ばされておしまいです(笑)
訟務官を相手に裁判をして勝つ方法は唯だ一つだと思う。
「国に損害がでないこと。」
うちのケースでは、国が、国家賠償を行った後に事件の原因となった公務員に対する国家賠償法1条2項の請求を行う場合、証人になるという条件を付加したから、結構甘々な答弁でした。
しかも当該公務員の陳述に明らかな虚偽を発見し指摘したから、上席訟務官さんがサジを投げた形で終結してました。
んで、なんで敗訴か、上席訟務官さんがサジを投げたことに裁判長が気づいてない(笑)
二審では、遠まわしに主張してみたんですが、これでも気づかない。
上告審では、具体的に説明しました。
シティズは、真面目な貸金業者だったということじゃないでしょうか。
実際問題として、資金フローが逼迫してる企業が生き残るためには、目先の利息云々より、いかにすばやく資金需要に対応してくれるかってことの方が重要だと思います。
シティズのような貸金業者がいなければ、困るのは資金需要者の方で、本来、貸金業法43条の規定を遵守している限り、咎めるべきではなかったのではないでしょうか。
シティズは、どっちかっていうと他の貸金業者のとばっちりを受けてしまったような感じを受けています。
だから、いくらかでも過払金を取り戻せたなら大金星なのではありませんかね。
>>任意に支払っていないことが詐欺、脅迫にあたるという理屈。
これも当然指摘してます^^。
ガイドラインに関しては、「律>令」の原則を主張するつもりです。
仮に「令」に従っていたとしても、判示された「律」に違反する行為があれば不法行為となる。
被告側が「令」に従っていたことに対する非は、原告側には一切無い。
従って、被告が「令」があったことを以て対抗できる相手は原告ではなく、金融庁である。
仮に本件事件で被告が敗訴した場合、金融庁を相手に国家賠償を求めればよいだけで、原告とは全く関係が無いということ。
最高裁の好きそうな論法でしょ(笑)
そして敗訴した貸金業者が国家賠償を求めて訴訟の提起を行っても、国の訟務官に木っ端微塵に吹き飛ばされておしまいです(笑)
訟務官を相手に裁判をして勝つ方法は唯だ一つだと思う。
「国に損害がでないこと。」
うちのケースでは、国が、国家賠償を行った後に事件の原因となった公務員に対する国家賠償法1条2項の請求を行う場合、証人になるという条件を付加したから、結構甘々な答弁でした。
しかも当該公務員の陳述に明らかな虚偽を発見し指摘したから、上席訟務官さんがサジを投げた形で終結してました。
んで、なんで敗訴か、上席訟務官さんがサジを投げたことに裁判長が気づいてない(笑)
二審では、遠まわしに主張してみたんですが、これでも気づかない。
上告審では、具体的に説明しました。
善良な営業姿勢か否かではなく、真面目に貸金業法を守っていたことを言いたかったのです。
法律が守ってくれるのは、必要最低限の権利だけじゃありませんか。
シティズの厳しい取立ても、サラリーマンを保証人としてとることも、債権を保全するという目的に適った行為に過ぎないとも言えると思います。
紹介屋の貸出元ってところは、紹介屋とのつながりを立証できれば出資法違反で摘発できるのでしょうけど、証拠は残ってないでしょうし、無関係な紹介屋が勝手に紹介して借主に手数料を請求してたって事案もあるから、立証は難しいでしょう。
こんな金融屋でも、資金需要が逼迫してる人にとっては必要だったのでしょうかね?
表の貸金業に対する風当たりが強くなって、今じゃソフト闇金なんていう無登録違法利率の業者が横行してきている。
シティズは必要悪として、存在が許されるギリギリで営業していたのではないかと、私は思います。
(他の貸金業者は全部OUTだったわけだけど…)
今後考えられる事態として、ソフト闇金との返済トラブルにおいて、ソフト闇金側が、業としていない貸付であることを主張してくるケースが増えてくると思われます。
この場合、年109.5%が出資法上限利率となり、うち利息制限法所定の利率を越える金員請求を、金銭授受にかかる手数料とかなんとかとでも言って争ってくることになるやもしれません。
もっと効率のいい方法も、実は考え付いてるのですが、実行されたらたまらないんで書きませんけどね。
これは、まだ善良なケースだと思う。
最悪のケースは、「闇から闇に葬り去る。」なんて手段がとられることも増えてくるのではないでしょうか。
不法残留している中国人やアラブ人を使って拉致し、密かに海外に送って、バラバラにして移植用のパーツとして売り飛ばすとか、監禁したまま危険な作業に従事させるとか、変態相手の性奴隷として売りさばかれるとか、若しくは、金融機関や上場企業の情報をスパイさせるとか、貸した金以上の金に替える手段なんていくらでもありそうです。
金を貸した債権者としての権利の主張は、人間をいくらでも鬼畜に変えます。
逆に、金を借りた債務者としての負い目は、人間をいくらでも卑屈に変えます。
だから、私は、法律が通用する最低限度の歯止めは必要なのではないかとも考えています。
厳しく締め付けすぎて、逆に多くの弊害が発生してくるのではないかなと危惧しています。
正直なところ、無担保・無保証で、年15%とか18%でお金を貸して安心していられる相手がどれぐらい存在すると思います?
思いつくのはせいぜいが、公務員か上場企業等優良企業の社員まででしょうし、これらに対してでも他社借入に限度額を設定し越えたら一括弁済する特約をつけるとか、退職したら一括弁済する特約は必要になるでしょう。
他は、よほど厳密に審査するか、又は保証人や担保をとらないと無理です。
金貸しだって、慈善事業でお金を貸してるわけじゃないと、ある一定の理解は必要じゃないかな。
ある一定の理解をした上で、「それでも法律に違反していたのだから、不当利得は返すべきである。」というスタンスを崩しちゃうと、悪徳業者を開き直らせ闇金がはびこることになる。今、そうなっちゃってるし。
闇金が横行しつづけると、利息制限法の改正とかいう問題も考えられますし、やりすぎ感は否めませんよね。
老子には、戦う相手のことを哀しんだものが勝つと書かれています。
貸金業者に対し、最低限度の敬意は払う必要があると、私は思います。
その上で、相手の落ち度を徹底的に叩き、墓に葬るつもりで裁判に臨んでおります。
法律が守ってくれるのは、必要最低限の権利だけじゃありませんか。
シティズの厳しい取立ても、サラリーマンを保証人としてとることも、債権を保全するという目的に適った行為に過ぎないとも言えると思います。
紹介屋の貸出元ってところは、紹介屋とのつながりを立証できれば出資法違反で摘発できるのでしょうけど、証拠は残ってないでしょうし、無関係な紹介屋が勝手に紹介して借主に手数料を請求してたって事案もあるから、立証は難しいでしょう。
こんな金融屋でも、資金需要が逼迫してる人にとっては必要だったのでしょうかね?
表の貸金業に対する風当たりが強くなって、今じゃソフト闇金なんていう無登録違法利率の業者が横行してきている。
シティズは必要悪として、存在が許されるギリギリで営業していたのではないかと、私は思います。
(他の貸金業者は全部OUTだったわけだけど…)
今後考えられる事態として、ソフト闇金との返済トラブルにおいて、ソフト闇金側が、業としていない貸付であることを主張してくるケースが増えてくると思われます。
この場合、年109.5%が出資法上限利率となり、うち利息制限法所定の利率を越える金員請求を、金銭授受にかかる手数料とかなんとかとでも言って争ってくることになるやもしれません。
もっと効率のいい方法も、実は考え付いてるのですが、実行されたらたまらないんで書きませんけどね。
これは、まだ善良なケースだと思う。
最悪のケースは、「闇から闇に葬り去る。」なんて手段がとられることも増えてくるのではないでしょうか。
不法残留している中国人やアラブ人を使って拉致し、密かに海外に送って、バラバラにして移植用のパーツとして売り飛ばすとか、監禁したまま危険な作業に従事させるとか、変態相手の性奴隷として売りさばかれるとか、若しくは、金融機関や上場企業の情報をスパイさせるとか、貸した金以上の金に替える手段なんていくらでもありそうです。
金を貸した債権者としての権利の主張は、人間をいくらでも鬼畜に変えます。
逆に、金を借りた債務者としての負い目は、人間をいくらでも卑屈に変えます。
だから、私は、法律が通用する最低限度の歯止めは必要なのではないかとも考えています。
厳しく締め付けすぎて、逆に多くの弊害が発生してくるのではないかなと危惧しています。
正直なところ、無担保・無保証で、年15%とか18%でお金を貸して安心していられる相手がどれぐらい存在すると思います?
思いつくのはせいぜいが、公務員か上場企業等優良企業の社員まででしょうし、これらに対してでも他社借入に限度額を設定し越えたら一括弁済する特約をつけるとか、退職したら一括弁済する特約は必要になるでしょう。
他は、よほど厳密に審査するか、又は保証人や担保をとらないと無理です。
金貸しだって、慈善事業でお金を貸してるわけじゃないと、ある一定の理解は必要じゃないかな。
ある一定の理解をした上で、「それでも法律に違反していたのだから、不当利得は返すべきである。」というスタンスを崩しちゃうと、悪徳業者を開き直らせ闇金がはびこることになる。今、そうなっちゃってるし。
闇金が横行しつづけると、利息制限法の改正とかいう問題も考えられますし、やりすぎ感は否めませんよね。
老子には、戦う相手のことを哀しんだものが勝つと書かれています。
貸金業者に対し、最低限度の敬意は払う必要があると、私は思います。
その上で、相手の落ち度を徹底的に叩き、墓に葬るつもりで裁判に臨んでおります。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
実況 過払い金返還請求!! 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
実況 過払い金返還請求!!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90042人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6423人
- 3位
- 独り言
- 9045人