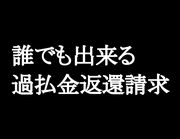過払金の返還請求を個人でする場合、さっさと訴訟を提起してしまうのが一番手っ取り早い方法です。
でも、一般の人が裁判をするとき、何を裁判所に主張すればいいかってことが一番のネックですよね。
最高裁判所以外の裁判所ってのは、基本的に『判例主義』といっても過言ではない状況ですので、逆に言えば、判例さえ主張してしまえば、あとは裁判所がきちんと判断してくれるということになります。
ぶっちゃければ、重要判例ってのを印刷して甲号証として提示すれば、必要な判断は裁判所がしてくれるってことです。
訴状の雛形は、過払金返還請求関連の書籍やネットで簡単にみつかるので、それを自分の事件に当てはめて請求金額などを書き込んで、引き直し計算書を別紙として添付し、重要判例を甲号証として提出する。
重要判例ってどんなのがあるか、ちょっと書き出してみます。
1.平成16(受)1518最二判平成18年01月13日民集第60巻1号1頁
「期限の利益特約のある契約では、貸金業法43条のみなし弁済規定の適用は受けられない。」
として、事実上、全ての貸金業者に過払金返還義務があると判示した。
2.平成17(受)1970最二判平成19年07月13日民集第61巻5号1980頁
貸金業法43条の適用が受けられないとき、原則として貸金業者は「悪意の受益者」と推定する。
最判平成21年7月14日(集民第231号357頁)によりシティーズには原則を覆す
特段の事情があると判示されたが、それ以外の貸金業者には同事情はない。
3.平成18(受)2268最二判平成20年01月18日民集第62巻1号28頁
複数の契約に対する一連計算の可否基準が示されました。
4.平成20(受)468最一判平成21年01月22日民集第63巻1号247頁
過払金の消滅時効についての判例。
5.平成21(受)1192最二判平成21年09月04日集民第231号477頁
過払金利息の発生時期についての判例
6.平成21(受)955最三判平成22年04月20日民集第64巻3号921頁
引直計算中、各回取引後の引き直し済み残高がいったん制限利息を下げた場合、
後に引き直し済み残高が基準金額を下回ったとしても、
いったん下がった制限利息はそのまま適用される。
この辺の判例を押さえておけば、未開示履歴の無い返還請求事件なら十分でしょう。
本人訴訟の場合、悪質な業者はまだ2.の「特段の理由」を争ってきますが、注釈に書いた通り主張すれば、裁判所は認めてくれます。
未開示履歴のある場合は、名古屋消費者信用問題研究会のHPに参考となる判例があります。
http://
争点:
?未開示履歴に対する文書提出命令の申立て→民訴224条1項の援用
?開示部分の冒頭残高0円計算の可否
?未開示部分に発生したと推定できる過払金の扱い
他に、
?途中で契約上の地位があった場合の判例も載ってます
ここまでを押さえておけば、裁判はほぼ勝てます。
残るケース:
?.貸金業者が会社更生法等の適用を受けた場合
?.貸金業者の経営不振で返還に応じられない場合
?.架空請求・過剰貸付など、不法行為に対する慰謝料請求
残るケースの?・?の場合には、まだ重要判例と呼べるものがありません。
たぶんもうすぐ報告できるような結果が出ると思うので、お待ちください。
?のケースは、貸金業者に事業資金を融資している銀行等を相手に訴訟を提起すれば、全額回収も可能です。判例を作りたくない銀行等が貸金業者に和解するように圧力をかけてるみたいですよ。
(続く)
でも、一般の人が裁判をするとき、何を裁判所に主張すればいいかってことが一番のネックですよね。
最高裁判所以外の裁判所ってのは、基本的に『判例主義』といっても過言ではない状況ですので、逆に言えば、判例さえ主張してしまえば、あとは裁判所がきちんと判断してくれるということになります。
ぶっちゃければ、重要判例ってのを印刷して甲号証として提示すれば、必要な判断は裁判所がしてくれるってことです。
訴状の雛形は、過払金返還請求関連の書籍やネットで簡単にみつかるので、それを自分の事件に当てはめて請求金額などを書き込んで、引き直し計算書を別紙として添付し、重要判例を甲号証として提出する。
重要判例ってどんなのがあるか、ちょっと書き出してみます。
1.平成16(受)1518最二判平成18年01月13日民集第60巻1号1頁
「期限の利益特約のある契約では、貸金業法43条のみなし弁済規定の適用は受けられない。」
として、事実上、全ての貸金業者に過払金返還義務があると判示した。
2.平成17(受)1970最二判平成19年07月13日民集第61巻5号1980頁
貸金業法43条の適用が受けられないとき、原則として貸金業者は「悪意の受益者」と推定する。
最判平成21年7月14日(集民第231号357頁)によりシティーズには原則を覆す
特段の事情があると判示されたが、それ以外の貸金業者には同事情はない。
3.平成18(受)2268最二判平成20年01月18日民集第62巻1号28頁
複数の契約に対する一連計算の可否基準が示されました。
4.平成20(受)468最一判平成21年01月22日民集第63巻1号247頁
過払金の消滅時効についての判例。
5.平成21(受)1192最二判平成21年09月04日集民第231号477頁
過払金利息の発生時期についての判例
6.平成21(受)955最三判平成22年04月20日民集第64巻3号921頁
引直計算中、各回取引後の引き直し済み残高がいったん制限利息を下げた場合、
後に引き直し済み残高が基準金額を下回ったとしても、
いったん下がった制限利息はそのまま適用される。
この辺の判例を押さえておけば、未開示履歴の無い返還請求事件なら十分でしょう。
本人訴訟の場合、悪質な業者はまだ2.の「特段の理由」を争ってきますが、注釈に書いた通り主張すれば、裁判所は認めてくれます。
未開示履歴のある場合は、名古屋消費者信用問題研究会のHPに参考となる判例があります。
http://
争点:
?未開示履歴に対する文書提出命令の申立て→民訴224条1項の援用
?開示部分の冒頭残高0円計算の可否
?未開示部分に発生したと推定できる過払金の扱い
他に、
?途中で契約上の地位があった場合の判例も載ってます
ここまでを押さえておけば、裁判はほぼ勝てます。
残るケース:
?.貸金業者が会社更生法等の適用を受けた場合
?.貸金業者の経営不振で返還に応じられない場合
?.架空請求・過剰貸付など、不法行為に対する慰謝料請求
残るケースの?・?の場合には、まだ重要判例と呼べるものがありません。
たぶんもうすぐ報告できるような結果が出ると思うので、お待ちください。
?のケースは、貸金業者に事業資金を融資している銀行等を相手に訴訟を提起すれば、全額回収も可能です。判例を作りたくない銀行等が貸金業者に和解するように圧力をかけてるみたいですよ。
(続く)
|
|
|
|
コメント(11)
そもそも過払金がどうして発生するかという根源になる判例
7.昭和35(オ)1151最大判昭和39年11月18日民集第18巻9号1868頁
債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条により、残存元本に充当されるものと解すべきである。
この判例が利息制限法1条1項及び同法4条1項の制限利息の規定は強行法規であると判断したことで、任意弁済といえども利息制限法所定の利率を超える弁済に、法的強制力がない旨を判示した。
8.昭和41(オ)1281最大判昭和43年11月13日民集第22巻12号2526頁
利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払つた債務者は、制限超過部分の充当により計算上元本が完済となつたときは、その後に債務の存在しないことを知らないで支払つた金額の返還を請求することができる。
この判例で、過払金は返還しなければいけないと最高裁が始めて認めました。
これ以降、サラ金でお金を借りて、返済に行き詰まったら裁判所に駆け込めばチャラになるという状況になりました。当時のサラ金の平均利率は年80%程度、駆け込まれたらチャラになる分を、返済できる人から取り立てようという杜撰な営業姿勢は一向に変りませんでした。
昭和57年から58年頃、裁判所に駆け込めば借金がチャラになるということがまかり通り、逆に真面目な顧客は無茶苦茶な高金利を負担するというおかしな二重構造に一定の歯止めをかけることを目的として、貸金業者らに厳格な手続きを約束させることで、将来弁済に行き詰まって裁判所に駆け込んでも借金がチャラにならない法律を作ろうと、貸金業法が制定されました。この法律が施行される条件として、これまで平均年80%だった貸出利率を、年40%まで引き下げることを決めました。
また、国会の質疑応答では、当初5年間の時限立法という位置付けで議論されておりましたが、時限立法という話はいつのまにか条文の文面から消えていました。
貸金業法43条のみなし弁済規定の誕生です。
7.昭和35(オ)1151最大判昭和39年11月18日民集第18巻9号1868頁
債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条により、残存元本に充当されるものと解すべきである。
この判例が利息制限法1条1項及び同法4条1項の制限利息の規定は強行法規であると判断したことで、任意弁済といえども利息制限法所定の利率を超える弁済に、法的強制力がない旨を判示した。
8.昭和41(オ)1281最大判昭和43年11月13日民集第22巻12号2526頁
利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払つた債務者は、制限超過部分の充当により計算上元本が完済となつたときは、その後に債務の存在しないことを知らないで支払つた金額の返還を請求することができる。
この判例で、過払金は返還しなければいけないと最高裁が始めて認めました。
これ以降、サラ金でお金を借りて、返済に行き詰まったら裁判所に駆け込めばチャラになるという状況になりました。当時のサラ金の平均利率は年80%程度、駆け込まれたらチャラになる分を、返済できる人から取り立てようという杜撰な営業姿勢は一向に変りませんでした。
昭和57年から58年頃、裁判所に駆け込めば借金がチャラになるということがまかり通り、逆に真面目な顧客は無茶苦茶な高金利を負担するというおかしな二重構造に一定の歯止めをかけることを目的として、貸金業者らに厳格な手続きを約束させることで、将来弁済に行き詰まって裁判所に駆け込んでも借金がチャラにならない法律を作ろうと、貸金業法が制定されました。この法律が施行される条件として、これまで平均年80%だった貸出利率を、年40%まで引き下げることを決めました。
また、国会の質疑応答では、当初5年間の時限立法という位置付けで議論されておりましたが、時限立法という話はいつのまにか条文の文面から消えていました。
貸金業法43条のみなし弁済規定の誕生です。
みなし弁済規定には、基本契約とか極度額方式とかに関する規定は存在しておらず、貸金業者らは、これを勝手に拡大解釈し、バンバン営業を拡大して行きました。
そして、過剰貸付に対する監督官庁の指導も形式的でしたので、ガンガン貸付け、元本を返済させず、利払いのみの自転車弁済を顧客に強いるように、業界ぐるみで突き進んで行った結果、日本中に多重債務者が溢れ反る事態となってしましました。
9.平成8(オ)250最一判平成11年01月21日民集第53巻1号98頁
口座振替による弁済でも、利息制限法所定の制限利率を超える弁済の場合には、18条書面を交付しなければ貸金業法43条の規定は適用できないと判示した。
この判例により、最高裁判所がはじめて貸金業法43条の規定の厳格適用を打ち出しました。
10.平成15(オ)386最二判平成16年02月20日民集第58巻2号475頁
17条書面(契約書。各回の借入時の通知書面。)及び18条書面(領収書)について、43条の規定を厳格運用することを求めた判例。
事実上、ほぼ全ての貸金業者に対して利息制限法所定の制限利率を上回る貸付けは不当利得になることを判示しています。残るはシティーズなど貸金業法を真面目に守っていた会社だけです。
さあ、事実上全ての貸金業者に不当利得返還義務があることになりましたが、お金を返したくない貸金業者らの抵抗は続きます。
「契約書や取引履歴を開示しなければ、返還請求されない。」という浅知恵をそのまま実行する業者が増えてきました。
11.平成16(受)965最三判平成17年07月19日民集第59巻6号1783頁
卑怯な浅知恵を使った業者に、契約書や取引履歴開示義務があると判示した。
当たり前ですよね(笑)
さらに、お金を返したくない貸金業者らの抵抗は続く。
自分達が勝手に拡大解釈して、基本契約や極度額なんてものに43条の規定を当てはめたのに、「17条書面にどうやって所定事項を書けっていうんだ!」と逆切れし、記載事項不備でも17条書面として通用すると言い張ってました。
12.平成17(受)560最一判平成17年12月15日民集第59巻10号2899頁
最高裁は、基本契約書と各回の貸出時の通知書を併せて要件を満たしている場合には17条書面として通用すると、貸金業者よりの判断をしましたが、それでも要件を満たしている業者はいませんでした。
なんのために逆切れしてたのでしょうか…、墓穴を掘りましたよね。
この後1.の判例が判示され貸金業者らにトドメが刺されました。
そして、過剰貸付に対する監督官庁の指導も形式的でしたので、ガンガン貸付け、元本を返済させず、利払いのみの自転車弁済を顧客に強いるように、業界ぐるみで突き進んで行った結果、日本中に多重債務者が溢れ反る事態となってしましました。
9.平成8(オ)250最一判平成11年01月21日民集第53巻1号98頁
口座振替による弁済でも、利息制限法所定の制限利率を超える弁済の場合には、18条書面を交付しなければ貸金業法43条の規定は適用できないと判示した。
この判例により、最高裁判所がはじめて貸金業法43条の規定の厳格適用を打ち出しました。
10.平成15(オ)386最二判平成16年02月20日民集第58巻2号475頁
17条書面(契約書。各回の借入時の通知書面。)及び18条書面(領収書)について、43条の規定を厳格運用することを求めた判例。
事実上、ほぼ全ての貸金業者に対して利息制限法所定の制限利率を上回る貸付けは不当利得になることを判示しています。残るはシティーズなど貸金業法を真面目に守っていた会社だけです。
さあ、事実上全ての貸金業者に不当利得返還義務があることになりましたが、お金を返したくない貸金業者らの抵抗は続きます。
「契約書や取引履歴を開示しなければ、返還請求されない。」という浅知恵をそのまま実行する業者が増えてきました。
11.平成16(受)965最三判平成17年07月19日民集第59巻6号1783頁
卑怯な浅知恵を使った業者に、契約書や取引履歴開示義務があると判示した。
当たり前ですよね(笑)
さらに、お金を返したくない貸金業者らの抵抗は続く。
自分達が勝手に拡大解釈して、基本契約や極度額なんてものに43条の規定を当てはめたのに、「17条書面にどうやって所定事項を書けっていうんだ!」と逆切れし、記載事項不備でも17条書面として通用すると言い張ってました。
12.平成17(受)560最一判平成17年12月15日民集第59巻10号2899頁
最高裁は、基本契約書と各回の貸出時の通知書を併せて要件を満たしている場合には17条書面として通用すると、貸金業者よりの判断をしましたが、それでも要件を満たしている業者はいませんでした。
なんのために逆切れしてたのでしょうか…、墓穴を掘りましたよね。
この後1.の判例が判示され貸金業者らにトドメが刺されました。
残るケース?について:
平成21年12月と平成22年6月に旧会社更生法241条の適用を争った裁判の最高裁判決が出て、過払金請求者側の敗訴となっています。
現状では、旧会社更生法241条(更正会社の残債務に対する免責)が適用される事案については、過払金返還請求ができません。
しかし、このような事案についても、まだ戦う余地が残っています。
よく調べてみると、更正会社の営業債権が、更正資金捻出のために、信託銀行等に債権譲渡されており、この営業債権ってのが、過払金の発生する貸付債権だったのです。
この債権譲渡は、登記所に登記されており、信託銀行等が事実上の債権者とみなせる余地がまだ残っています。
現在、最高裁判所でこのような事案を係争しております。
残るケース?について:
最近、中小の貸金業者が廃業する等が目立っています。
倒産寸前の会社から過払金を取り戻すのは、大変こんなんで、判決をもらい強制執行をかけても何も取れないことが多いですね。
しかし、この貸金業者らに事業資金を融資し、違法高利な利息の恩恵を被っていた金融機関に、全く責任がないといえるでしょうか?
上記9.以降の判決が出て、43条の規定が適用できない貸付ばかりだと判明した後の融資について、何も咎められていないのが現状です。
そこで、東京法務局中野出張所内の民事行政部債権登録課で、債権譲渡登記を調べ、債権の譲受人を見つけて『連帯債務履行請求』をしてみました。
・債権譲渡登記された譲渡債権の帰属と契約上の地位の移転があれば、連帯債務者である。
・契約上の地位の移転がない場合でも、下記13.の判例を類推援用し、金融機関等には連帯して弁済する義務がある。
・道義的責任の有無。
譲渡債権の譲受人(銀行等)をみつけて訴訟を提起し、上記事項を主張してみてください。
訴えられた銀行等から、支払いを渋っている貸金業者に圧力がかかり、全額弁済してくれます。
13.昭和45(オ)540最一判昭和49年09月26日民集第28巻6号243頁
一、甲が、乙から騙取又は横領した金銭を、自己の金銭と混同させ、両替し、銀行に預け入れ、又はその一部を他の目的のため費消したのちその費消した分を別途工面した金銭によつて補填する等してから、これをもつて自己の丙に対する債務の弁済にあてた場合でも、社会通念上乙の金銭で丙の利益をはかつたと認めるに足りる連結があるときは、乙の損失と丙の利得との間には、不当利得の成立に必要な因果関係があると解すべきである。
二、甲が乙から騙取又は横領した金銭により自己の債権者丙に対する債務を弁済した場合において、右弁済の受領につき丙に悪意又は重大な過失があるときは、丙の右金銭の取得は、乙に対する関係においては法律上の原因を欠き、不当利得となる。
上記判例は要するに、
「悪質な行為で金を騙し取った者が、共謀している第三者に金員を支払った場合、騙し取られた者は共謀した第三者に対して不当利得返還請求できる。」
ってことです。
銀行ってのは、融資を行う前に貸付先を十分に調査している(これを専門用語で、「デューディリジェンス」といいます。)ので、悪意の受益者である貸金業者が黙って不当利得を収益し、その収益した不当利得で融資金の弁済を行っていたことが明らかならば、不当利得返還請求の連帯債務者となるという論法です。
平成21年12月と平成22年6月に旧会社更生法241条の適用を争った裁判の最高裁判決が出て、過払金請求者側の敗訴となっています。
現状では、旧会社更生法241条(更正会社の残債務に対する免責)が適用される事案については、過払金返還請求ができません。
しかし、このような事案についても、まだ戦う余地が残っています。
よく調べてみると、更正会社の営業債権が、更正資金捻出のために、信託銀行等に債権譲渡されており、この営業債権ってのが、過払金の発生する貸付債権だったのです。
この債権譲渡は、登記所に登記されており、信託銀行等が事実上の債権者とみなせる余地がまだ残っています。
現在、最高裁判所でこのような事案を係争しております。
残るケース?について:
最近、中小の貸金業者が廃業する等が目立っています。
倒産寸前の会社から過払金を取り戻すのは、大変こんなんで、判決をもらい強制執行をかけても何も取れないことが多いですね。
しかし、この貸金業者らに事業資金を融資し、違法高利な利息の恩恵を被っていた金融機関に、全く責任がないといえるでしょうか?
上記9.以降の判決が出て、43条の規定が適用できない貸付ばかりだと判明した後の融資について、何も咎められていないのが現状です。
そこで、東京法務局中野出張所内の民事行政部債権登録課で、債権譲渡登記を調べ、債権の譲受人を見つけて『連帯債務履行請求』をしてみました。
・債権譲渡登記された譲渡債権の帰属と契約上の地位の移転があれば、連帯債務者である。
・契約上の地位の移転がない場合でも、下記13.の判例を類推援用し、金融機関等には連帯して弁済する義務がある。
・道義的責任の有無。
譲渡債権の譲受人(銀行等)をみつけて訴訟を提起し、上記事項を主張してみてください。
訴えられた銀行等から、支払いを渋っている貸金業者に圧力がかかり、全額弁済してくれます。
13.昭和45(オ)540最一判昭和49年09月26日民集第28巻6号243頁
一、甲が、乙から騙取又は横領した金銭を、自己の金銭と混同させ、両替し、銀行に預け入れ、又はその一部を他の目的のため費消したのちその費消した分を別途工面した金銭によつて補填する等してから、これをもつて自己の丙に対する債務の弁済にあてた場合でも、社会通念上乙の金銭で丙の利益をはかつたと認めるに足りる連結があるときは、乙の損失と丙の利得との間には、不当利得の成立に必要な因果関係があると解すべきである。
二、甲が乙から騙取又は横領した金銭により自己の債権者丙に対する債務を弁済した場合において、右弁済の受領につき丙に悪意又は重大な過失があるときは、丙の右金銭の取得は、乙に対する関係においては法律上の原因を欠き、不当利得となる。
上記判例は要するに、
「悪質な行為で金を騙し取った者が、共謀している第三者に金員を支払った場合、騙し取られた者は共謀した第三者に対して不当利得返還請求できる。」
ってことです。
銀行ってのは、融資を行う前に貸付先を十分に調査している(これを専門用語で、「デューディリジェンス」といいます。)ので、悪意の受益者である貸金業者が黙って不当利得を収益し、その収益した不当利得で融資金の弁済を行っていたことが明らかならば、不当利得返還請求の連帯債務者となるという論法です。
残るケース?について:
・平成21(受)47最二判平成21年09月04日民集第63巻7号1445頁
貸金業者が借主に対し貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成するのは,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られ,この理は,当該貸金業者が過払金の受領につき民法704条所定の悪意の受益者であると推定されるときであっても異ならない。
この判例を援用されて、架空請求に対する慰謝料請求がことごとく棄却されています。
しかし、この判例の本文をよく読むと、事案は「昭和55年11月12日から平成9年1月13日までの間」で、過払金関連の最高裁判決が全く存在していない時期のものであり、他に「その適用要件の解釈
につき下級審裁判例の見解は分かれていて,当審の判断も示されていなかったことは当裁判所に顕著であって…。」と最高裁判所の判例が無かったことが理由になっています。
これ、最高裁判所の判例があるときに、過払金が発生していることを黙ったまま請求を続けた場合にはあてはまりませんよね。
現在、この趣旨で最高裁に上告されている事案があります。
過剰貸付については、「貸金業法13条の規定は罰則のない規範に過ぎないから、不法行為にあたらない。」というのが貸金業者側の主張で、これがまかり通っています。
罰則規定がないから…って、明らかにおかしいですよね。
これも戦わなきゃいけないと思います。
・平成21(受)47最二判平成21年09月04日民集第63巻7号1445頁
貸金業者が借主に対し貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成するのは,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られ,この理は,当該貸金業者が過払金の受領につき民法704条所定の悪意の受益者であると推定されるときであっても異ならない。
この判例を援用されて、架空請求に対する慰謝料請求がことごとく棄却されています。
しかし、この判例の本文をよく読むと、事案は「昭和55年11月12日から平成9年1月13日までの間」で、過払金関連の最高裁判決が全く存在していない時期のものであり、他に「その適用要件の解釈
につき下級審裁判例の見解は分かれていて,当審の判断も示されていなかったことは当裁判所に顕著であって…。」と最高裁判所の判例が無かったことが理由になっています。
これ、最高裁判所の判例があるときに、過払金が発生していることを黙ったまま請求を続けた場合にはあてはまりませんよね。
現在、この趣旨で最高裁に上告されている事案があります。
過剰貸付については、「貸金業法13条の規定は罰則のない規範に過ぎないから、不法行為にあたらない。」というのが貸金業者側の主張で、これがまかり通っています。
罰則規定がないから…って、明らかにおかしいですよね。
これも戦わなきゃいけないと思います。
ちょっと悪質じゃないかと思う貸金業者がいます。
ジャックス
この業者は、早くから利息制限法所定の利率以内で営業していたのですが、平成9年頃以前はグレーゾーンで営業していました。
そして、この業者に取引履歴開示請求してみると、各貸付が1回払いであるかのような取引履歴が開示されます。
しかも、平成7年3月以前のものは、「社内規定に従い破棄した。」と主張し、開示しません。
開示された履歴をみてみると、平成7年から平成9年頃までは、たしかに過払金が発生しているのですが、2000円とか3000円とかという小額のものが2年分ほど見えるだけで、合算しても大した額にならず、過払金返還請求する気にならないのです。
ところが、実際に開示された履歴を引き直し計算してみると、あら不思議、ちょっと請求してみようかなと思うぐらいには過払金が発生している。
ついでに、未開示期間に取引があれば、借入れた日の翌月の指定日に元利金の全額弁済をしているわけなので、確実に過払金が発生しているのだから、推定計算で過払金返還請求する余地が残っています。
下級審では、名古屋高裁や福岡高裁で推定計算を容認している判例もあり、戦ってみるべきだと思います。
推定計算分を考慮した場合、結構まとまった金額の請求が可能になります。
(平成4年末に契約し、平成20年頃まで極度額50万円で取引継続したケースでは、推定計算無しの場合35万円程度の過払金でしたが、推定部分を含めると80万円程度の過払金となす。)
そして、この業者の平成3年末頃から平成4年末頃までの基本契約書に出資法違反の高利が明記されている場合もありました。
丁度このころに、出資法改正があり、制限利率が40.005%に引き下げられたのですが、40.55%の約定利率が記載された古い基本契約書を流用したらしく、そのまま放置されていました。
そこで、よく見直していただくとわかると思いますが、平成4年頃から平成7年3月までは、取引履歴も開示されていません。
残ってるのは、出資法違反の利率が明記された基本契約書だけ。
これまで、最高裁判所は、貸金業法43条の規定に関して、同法の厳格運用ってのを基準としています。
つまり、17条書面がきちんと記載されていなければ、みなし弁済を認めていないのです。
この事案の場合、その17条書面に出資法違反利率が明記されているのだから、民法91条を援用して、契約を無効にできる余地があるということです。
業者は、同時期の有価証券報告書を証拠として提示して、違法高利な貸付は行っていないと主張しておりますが、有価証券報告書は17条書面ではありませんから、法的にはなんの役にも立ちません。
この事案もいま上告審で争われています。
ジャックス
この業者は、早くから利息制限法所定の利率以内で営業していたのですが、平成9年頃以前はグレーゾーンで営業していました。
そして、この業者に取引履歴開示請求してみると、各貸付が1回払いであるかのような取引履歴が開示されます。
しかも、平成7年3月以前のものは、「社内規定に従い破棄した。」と主張し、開示しません。
開示された履歴をみてみると、平成7年から平成9年頃までは、たしかに過払金が発生しているのですが、2000円とか3000円とかという小額のものが2年分ほど見えるだけで、合算しても大した額にならず、過払金返還請求する気にならないのです。
ところが、実際に開示された履歴を引き直し計算してみると、あら不思議、ちょっと請求してみようかなと思うぐらいには過払金が発生している。
ついでに、未開示期間に取引があれば、借入れた日の翌月の指定日に元利金の全額弁済をしているわけなので、確実に過払金が発生しているのだから、推定計算で過払金返還請求する余地が残っています。
下級審では、名古屋高裁や福岡高裁で推定計算を容認している判例もあり、戦ってみるべきだと思います。
推定計算分を考慮した場合、結構まとまった金額の請求が可能になります。
(平成4年末に契約し、平成20年頃まで極度額50万円で取引継続したケースでは、推定計算無しの場合35万円程度の過払金でしたが、推定部分を含めると80万円程度の過払金となす。)
そして、この業者の平成3年末頃から平成4年末頃までの基本契約書に出資法違反の高利が明記されている場合もありました。
丁度このころに、出資法改正があり、制限利率が40.005%に引き下げられたのですが、40.55%の約定利率が記載された古い基本契約書を流用したらしく、そのまま放置されていました。
そこで、よく見直していただくとわかると思いますが、平成4年頃から平成7年3月までは、取引履歴も開示されていません。
残ってるのは、出資法違反の利率が明記された基本契約書だけ。
これまで、最高裁判所は、貸金業法43条の規定に関して、同法の厳格運用ってのを基準としています。
つまり、17条書面がきちんと記載されていなければ、みなし弁済を認めていないのです。
この事案の場合、その17条書面に出資法違反利率が明記されているのだから、民法91条を援用して、契約を無効にできる余地があるということです。
業者は、同時期の有価証券報告書を証拠として提示して、違法高利な貸付は行っていないと主張しておりますが、有価証券報告書は17条書面ではありませんから、法的にはなんの役にも立ちません。
この事案もいま上告審で争われています。
ちょっと一休み
私は、個人的には過払金返還請求は本人訴訟でやるべきだと思います。
残るケース?ないし?で挙げた事案やその後に書かれてる事案の場合、扱ってくれる弁護士さんって、かなり少ないと思います。
弁護士さんって、職業としてお金を稼ぐために裁判するんですよ。
すると、時間や労力ばかり掛かって、大した報酬にならない裁判より、大きな裁判とかさっさと片付けられる裁判を優先するのは、しかたないことじゃありませんかね?
貸金業者が和解すると言ってきたら、それが過払金本体の5割でも、さっさと片付けた方がたくさん仕事をこなせ、実入りが多くなるんです。
でも、過払金の請求者は、後が無いですよね。
本体の5割で和解しちゃったらそれまでです。
今直ぐ必要なお金なら、それも一つの道でしょうけど、借金の弁済が無くなり、生活はそれほど逼迫していないって人も多いですよね。
そして、値引きされ和解した場合、大抵は支払い時期はかなり遅く、裁判して判決が出るぐらいは待たされます。
中には即裁判で、バンバン回収してくれる弁護士さんもいますけど、ほんの一握りの方だけってのが実情じゃありませんか。
始めの頃は、真面目に取り組んでいた弁護士さんでも、評判を聞きつけ、お客さんが増えすぎて手が回らなくなってる方もいらっしゃいます。
そして、回収後には報酬を支払わなきゃいけない。
いい弁護士さんにも、そうじゃない弁護士さんにも…
もし、過払金返還請求の総額が300万とか500万とかまとまった金額があるようでしたら、仕事だと思って、自分で勉強してやってみるのもいいのではないでしょうか?
まぁ、忙しくてそれどころじゃないって方の場合には弁護士さんに依頼するのも一つの方法だと思いますけど、そのときは弁護士さんも収入のために取り組んでるってことは理解してあげてください。
貸金業者側についてる弁護士さん、法律知ってて強いって感じる弁護士さんいません。
過払金関連でやった中で、怖いと感じたのは、簡易裁判所の調停官らを相手に国家賠償を求めた裁判で出てきた法務省の上席訟務官さんだけです。
後は、連帯債務履行請求で引っ張り出した金融機関等の弁護士を含め雑魚弁ばかりですから、本人訴訟でも楽勝ですって。
余談ですが、明らかに国に非がある事件でも、国が裁判で勝ってしまうこと多いですよね?
あれ、なぜだかわかりましたわ。
国の訟務官さんって、はんぱなく裁判強いです。
そして、裁判所もそういう対応します。
当事者間で、「訟務官さん、負け認めちゃったじゃん。」と思っても、裁判所が認めません(笑)
上告理由として、「訟務官さんが負け認めてるのに、裁判官が気付いてない。」ってのを書いておきました。どんな判決でるんだろ?
私は、個人的には過払金返還請求は本人訴訟でやるべきだと思います。
残るケース?ないし?で挙げた事案やその後に書かれてる事案の場合、扱ってくれる弁護士さんって、かなり少ないと思います。
弁護士さんって、職業としてお金を稼ぐために裁判するんですよ。
すると、時間や労力ばかり掛かって、大した報酬にならない裁判より、大きな裁判とかさっさと片付けられる裁判を優先するのは、しかたないことじゃありませんかね?
貸金業者が和解すると言ってきたら、それが過払金本体の5割でも、さっさと片付けた方がたくさん仕事をこなせ、実入りが多くなるんです。
でも、過払金の請求者は、後が無いですよね。
本体の5割で和解しちゃったらそれまでです。
今直ぐ必要なお金なら、それも一つの道でしょうけど、借金の弁済が無くなり、生活はそれほど逼迫していないって人も多いですよね。
そして、値引きされ和解した場合、大抵は支払い時期はかなり遅く、裁判して判決が出るぐらいは待たされます。
中には即裁判で、バンバン回収してくれる弁護士さんもいますけど、ほんの一握りの方だけってのが実情じゃありませんか。
始めの頃は、真面目に取り組んでいた弁護士さんでも、評判を聞きつけ、お客さんが増えすぎて手が回らなくなってる方もいらっしゃいます。
そして、回収後には報酬を支払わなきゃいけない。
いい弁護士さんにも、そうじゃない弁護士さんにも…
もし、過払金返還請求の総額が300万とか500万とかまとまった金額があるようでしたら、仕事だと思って、自分で勉強してやってみるのもいいのではないでしょうか?
まぁ、忙しくてそれどころじゃないって方の場合には弁護士さんに依頼するのも一つの方法だと思いますけど、そのときは弁護士さんも収入のために取り組んでるってことは理解してあげてください。
貸金業者側についてる弁護士さん、法律知ってて強いって感じる弁護士さんいません。
過払金関連でやった中で、怖いと感じたのは、簡易裁判所の調停官らを相手に国家賠償を求めた裁判で出てきた法務省の上席訟務官さんだけです。
後は、連帯債務履行請求で引っ張り出した金融機関等の弁護士を含め雑魚弁ばかりですから、本人訴訟でも楽勝ですって。
余談ですが、明らかに国に非がある事件でも、国が裁判で勝ってしまうこと多いですよね?
あれ、なぜだかわかりましたわ。
国の訟務官さんって、はんぱなく裁判強いです。
そして、裁判所もそういう対応します。
当事者間で、「訟務官さん、負け認めちゃったじゃん。」と思っても、裁判所が認めません(笑)
上告理由として、「訟務官さんが負け認めてるのに、裁判官が気付いてない。」ってのを書いておきました。どんな判決でるんだろ?
余談ついでに、最高裁判所について
このトピの冒頭付近で、下級裁判所ってのは判例主義だって書きましたが、この最高裁判所ってところはちょっと違う。
判決文を読めば読むほどに、納得させられるのです。
「?」が付く判例も無いわけではありませんが、「?」が付きながらもそれなりに納得できるのです。
上記12.の判例も、法律の条文にないものの拡大解釈をある範囲で認めちゃってたりしますよね。
しかし、拡大解釈を認めてもなお適用できないって結論です。
残るケース?に出てくる判例もその一つかな。
貸金業者の過払金が発生した後の請求は架空請求であるってのは明らかな事実ですが、具体的な最高裁判所の判例が出る前には、貸金業者にも正当な請求と信じる根拠はあったわけですから、これを不法行為と一刀両断するわけにいかないってことです。
事案の取引も、最高裁判所の判例が無い時代のものですし。
ただ、この判例が一人歩きを始めてしまったって部分は、大問題ですよね。
このトピの冒頭付近で、下級裁判所ってのは判例主義だって書きましたが、この最高裁判所ってところはちょっと違う。
判決文を読めば読むほどに、納得させられるのです。
「?」が付く判例も無いわけではありませんが、「?」が付きながらもそれなりに納得できるのです。
上記12.の判例も、法律の条文にないものの拡大解釈をある範囲で認めちゃってたりしますよね。
しかし、拡大解釈を認めてもなお適用できないって結論です。
残るケース?に出てくる判例もその一つかな。
貸金業者の過払金が発生した後の請求は架空請求であるってのは明らかな事実ですが、具体的な最高裁判所の判例が出る前には、貸金業者にも正当な請求と信じる根拠はあったわけですから、これを不法行為と一刀両断するわけにいかないってことです。
事案の取引も、最高裁判所の判例が無い時代のものですし。
ただ、この判例が一人歩きを始めてしまったって部分は、大問題ですよね。
>新宿太郎さん
おお、すげ!
残高0円計算認めさせちゃってるじゃんb
しかし、さらに上手な判決があるよ(笑)
未開示の期間に既に過払金が発生していたとして、冒頭金額が過払い状態からスタートしてる。
名古屋消費者信用問題研究会さんという真面目な弁護士さんのグループが画期的判例を公開してくれてます。
http://www.kabarai.net/judgement/document.html
http://www.kabarai.net/judgement/dl/221215.pdf
新宿太郎さんの事案でも、たぶん冒頭過払い状態でいけると思う。
うちんとこ:
時効3ヶ月前滑り込みセーフで請求した事案で、引き直し後3ヶ月分の元金返ってきたら嬉しいなぁと訴訟提起した事件で、平成4年から平成9年までの履歴が開示されなかったので、適当な金額を借りていたと仮定し、それを勘に頼った利率で借りていたことにし、推定計算で冒頭過払い状態で請求しました。
元々3か月分の弁済金約6万5千円とその過払利息だけもらえれば良かったので、これで和解しましょうと言ってみたのですが、相手が拒否。
推定計算部分の元本とか利率を争ってきちゃいました。
んで、裁判所が被告の言い分を認めて、約25万円とこれの10年分の利息を認める判決が出ちゃいました。
素晴らしいですよね、被告の主張どおりの判決です(笑)
原告は、10万円ほど欲しかっただけなのに、被告に40万円近く支払えということに…
さらに原告は調子に乗って高裁に控訴しましたが、控訴審でも負けちゃいました><
お陰で、「一審で裁判所が双方の主張をすり合わせて推定計算の手直しをし、未開示期間に発生した過払金を推定したことについて、裁判所に落ち度が無い。」旨、判決されました。
まだまだこのネタに続きがあって、40万円まだ支払ってくれてないんです(ハァト)
この会社、元々大臣登録してたのですが、現在は廃業してしまってて、廃業とほぼ同時期に系列会社が県知事登録で貸金業登録し、しかも前代表者がこの系列会社の代表になり、この会社の代表は前代表の奥さんが引き継いでいます。
ちょっと暇になったら、この系列会社と前代表者を相手に連帯債務履行請求してやろうと思ってます。
ついでに、県知事登録を認めた県知事も連帯債務者としてひきづり出してやろうかと、思案中です。
おお、すげ!
残高0円計算認めさせちゃってるじゃんb
しかし、さらに上手な判決があるよ(笑)
未開示の期間に既に過払金が発生していたとして、冒頭金額が過払い状態からスタートしてる。
名古屋消費者信用問題研究会さんという真面目な弁護士さんのグループが画期的判例を公開してくれてます。
http://www.kabarai.net/judgement/document.html
http://www.kabarai.net/judgement/dl/221215.pdf
新宿太郎さんの事案でも、たぶん冒頭過払い状態でいけると思う。
うちんとこ:
時効3ヶ月前滑り込みセーフで請求した事案で、引き直し後3ヶ月分の元金返ってきたら嬉しいなぁと訴訟提起した事件で、平成4年から平成9年までの履歴が開示されなかったので、適当な金額を借りていたと仮定し、それを勘に頼った利率で借りていたことにし、推定計算で冒頭過払い状態で請求しました。
元々3か月分の弁済金約6万5千円とその過払利息だけもらえれば良かったので、これで和解しましょうと言ってみたのですが、相手が拒否。
推定計算部分の元本とか利率を争ってきちゃいました。
んで、裁判所が被告の言い分を認めて、約25万円とこれの10年分の利息を認める判決が出ちゃいました。
素晴らしいですよね、被告の主張どおりの判決です(笑)
原告は、10万円ほど欲しかっただけなのに、被告に40万円近く支払えということに…
さらに原告は調子に乗って高裁に控訴しましたが、控訴審でも負けちゃいました><
お陰で、「一審で裁判所が双方の主張をすり合わせて推定計算の手直しをし、未開示期間に発生した過払金を推定したことについて、裁判所に落ち度が無い。」旨、判決されました。
まだまだこのネタに続きがあって、40万円まだ支払ってくれてないんです(ハァト)
この会社、元々大臣登録してたのですが、現在は廃業してしまってて、廃業とほぼ同時期に系列会社が県知事登録で貸金業登録し、しかも前代表者がこの系列会社の代表になり、この会社の代表は前代表の奥さんが引き継いでいます。
ちょっと暇になったら、この系列会社と前代表者を相手に連帯債務履行請求してやろうと思ってます。
ついでに、県知事登録を認めた県知事も連帯債務者としてひきづり出してやろうかと、思案中です。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
実況 過払い金返還請求!! 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
実況 過払い金返還請求!!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37846人
- 3位
- 楽天イーグルス
- 31947人