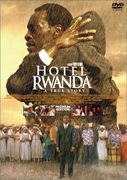大虐殺を記す : 文学とルワンダ証言
去る四月五日、東京日仏学院で行われた講演会「大虐殺を記す:文学とルワンダ証言」に行ってまいりました。だいぶ遅くなりましたが、レポートを書きました。
リポートについては、あくまでアレン教授のおっしゃったことを再現し、〔〕内に注を私が補足しています。
講師 : ピエール・アレン教授
フランス、メッツ大学文学、比較文学教授
1985年 雑誌Textyles(テクスティル)を創刊。
雑誌Etudes littéraires africaines(アフリカ文学研究誌)にも執筆。
専門: 植民地文学。フランス語圏の文学(主にベルギー、中央アフリカ、移民、アイデンティティーの問題)。
まずおさらい程度ということで、簡単にルワンダの地理と歴史の紹介があった。
ルワンダはアフリカの中央に位置する国で、隣国にはウガンダ、コンゴ、タンザニア、ブルンディがある。国土は小さく、貧しい。人口密度は高い。
歴史的に見れば、早くから同じ言語、同じ文化、同じ宗教を共有する人々が住んでいた。彼らはフツ、ツチ、トゥワという、厳密な意味での民族とも、階級ともは呼べないような、ある種のグループに分かれていた。各グループの占める割合は、85パーセントがフツ、14パーセントがツチ、そして1パーセントがトゥワだ。おもにツチ族は兵士、王族であり、国を支配していて、フツ族は農業をいとなんでいた。このグループ間の対立は古くから存在していたが、表立って大きな事件に繋がることは稀だった。少数派のツチは多数派のフツを支配し、奴隷のように扱っていた。しかしツチ族フツ族間の結婚もあり、彼らは共存し、とりあえず、バランスはとれていた。また覚えておきたいのは、ルワンダの国境がアフリカの国にあっては珍しく自然の地形による国境であることだ。ここにこの国の特異性が見られる。
ツチ・フツ間の対立の図式が顕著になったのは、ベルギーによる植民地時代だ(厳密には国連からの委任統治)。ベルギーも、それ以前の宗主国ドイツもツチ族に対し、憧れのような気持ちを抱く。そこで伝説ができた。ツチ族が遠く東のほうからやってきた民族という伝説だ。よってツチ族は民族的にフツ族とは別の民族で、その起源は遠くユーラシア大陸にまでさかのぼり、つまりよりヨーロッパ人(白人)に近い民族である、よって生まれながらにして支配層であるべき民族である、と。この説は現在ではまったく科学的根拠のないものとされている。この説を実践するためベルギーはIDカードにも民族を記すことにした。ツチ族はこの政策を歓迎し、自分たちの大儀のために利用した。
1959年 独立運動、および最初のジェノサイド(多数のツチ族が隣国ウガンダに逃亡)。
1962年 独立(グレゴワール・カイバンダ大統領)フツ族政権誕生
1973年 軍事クーデターにより政権交代(新しい大統領ジュヴェナル・ハビャリマナもフツ族だった)
その後この政権は独裁的になり、汚職もはびこるようになる。またこの時期にツチ族に対して差別的な政策が行われた。
80年代には長い間友好関係にあったベルギー国内の政権が変わったことにより、ベルギーの支持を失う。かわりにやってきたのがフランスだった。そしてその後はほとんどの西欧諸国がそっぽを向く中、フランスだけが唯一の支持国となる。
ジェノサイドが起こったのはこのような状況下でのことだった。
きっかけは1994年4月7日、ルワンダの大統領と隣国ブルンディの大統領を乗せた飛行機がミサイルによって撃ち落され、二人の大統領が死亡したことだった。誰がミサイルを発射したのかは未だにわかっていない。
すぐに復讐を呼びかけるフツ族によるツチ族の虐殺が行われた。だがこのこの虐殺は事前に長年にわたって準備されていたものであった。最初に狙われたのは、主に知識階級、弁護士、学者、医者などだった。その後残りのツチ族も狙われ、また穏健派フツ族も殺された。虐殺は3ヶ月に及んだ。
犠牲者はおよそ80万人(60万人から100万人の間で変化する)、それに加えて、その後フツ族難民が、移動中あるいは難民キャンプでのコレラの流行によって命を落とした。その数およそ25万人と言われる。人口およそ700万人の国にあって、この数字がいかに大きいかがわかる。
しかしこれほどの規模の大虐殺を事件当時、世界中はほとんど無視したような状況だった。虐殺の映像は少なく、現地にいた特派員たちも早々に引き上げ、また在留の国連軍も介入しなかった。
しかし、ひとたびことが収まり、取り返しがつかなくなってようやく、多くの「文章」が出だした。その数は「無視」したことに比較すると驚異的ですらある。それはあらゆるジャンルにわたっている。旅行記、ルポルタージュ、証言、フィクション、エッセイ、写真集、漫画(BD)さらには音楽や舞台に至るまで。中にはセラピーとしての記録もあった。
ここで大虐殺を記すという行為の意味の問題を取り上げたい。単なる素の証言という形から、美学的な色合いを強め、さらなる方向へと向かっているのではないかという問題だ。なぜなら、ひとたび文章になれば、形式をもたない内容はない。たとえそれがどんな無機質な学術論文であっても、必ずや形式にとらわれることになる。するととたんに長い間培われてきた「文学」のあらゆる拘束を受けることにより、宗教的、歴史的な含意を帯びることになる。そこに、ある種の罠がある。書かれたことにより、現実は必ずなんらかのかたちで裏切られることになる。
旅行記、ルポルタージュ、小説、写真集、エッセイ、ありとあらゆる形の芸術作品がルワンダをテーマにした。
多くの場合、これらの書物は問題を孕んでいる。なぜならほとんどが伝聞による記録だからだ。一番の当事者である犠牲者たちは死んでおり、言葉を持たない。残るは生き残った人たちである。ここにも問題がある。ひとつには、ルワンダのジェノサイドにおいて、最初に狙われたのは多くの場合、高学歴の知的階級だった。医者、教育者、法律家など。つまりきちんと文章を書けるような人々などがいなくなってしまった。もうひとつの要因として、生き残った人々は大きなトラウマを抱えていた。彼らは目の前で親、兄弟が想像を絶するような状況下で殺された。残酷な殺され方をした(マシェット、棍棒など)だけでなく、ときには父親が母親を殺し、父親が子どもを殺し、子どもが親を殺す、隣人同士で殺しあうというような惨劇を目の当たりにした。また生き残りとは言っても自分たちもまた大きな傷を負っている。そんな中で証言をするということは困難だ。
この事件を風化させないため、という意味合いで多くの記録が残されている。
まず、企画として、フランス政府はルワンダに10人ほどの作家を送り、事件について書かせた。ほとんどのひとが、それまで著述業に関わったことがなく、また作家としての野心を持っていないほうがよいとされた。中にはすでに作家として活動していたひともいたが(コート・ディヴォワール人作家ヴェロニック・タッジョはもともと児童文学の作品を出していた)稀である。こうして2000年に10冊の本が出た。4冊が大手の出版社、6冊がもっとマイナーな出版社から刊行された。
一冊挙げるとすれば
Véronique Tadjo : L’Ombre d’Imana (Actes Sud)
〔注:ヴェロニック・タッジョ 「イマナの影」(仮題)英訳あり〕
http://
http://
この問題には別の側面があった。事件をアフリカ人に語らせる場合、彼らにとっても複雑な状況に追い込まれるようになったのだ。多くの事件と違い、今回のジェノサイドについて語るとき、彼らは責任を「西欧社会」からの搾取やら、植民地主義に負わせることができなかった。明らかに事件はルワンダ独自の問題で、アフリカ人がアフリカ内部の問題に向き合うことを余儀なくさせられたのだった。
その後今度は西欧人がルワンダに出向き、ジェノサイドを語るようになる。その中でもっとも有名なのが、フィリップ・グーレヴィッチのジェノサイドの丘(原題 : Philip Gourevitch : We wish to inform you that tomorrow we will be killed with our families) だ。
http://
http://
西欧人がジェノサイドを書く場合の問題は、ジェノサイドの当事者たちにとって外側から書かれたものという面が強く出ることだ。「自分たちぬきで自分たちのことが書かれている」という心理だ。
リベラシオン紙(フランスの左翼系新聞)の記者Jean Hatzfeld(ジャン・ハッツフェルド)の著書 Dans le nu de la vie は著者ができるだけ表に出ずに当事者に言葉を託した。そして本を出版するとき、自分の名前が出ないよう出版社に頼んだが、受け入れられなかった。著者の名なしでは本が売れないからだ。後にこの本でハッツフェルドは賞を受ける。ここに、本来人道的な意図で始められたものが出版を経て、ビジネスという次元に移る。
〔注:Dans le nu de la vie では著者はジェノサイドの犠牲者の証言を集めた。10年後、 Une saison de machettesで今度は、ルワンダの刑務所に赴き、ジェノサイドを行った側の証言を集めている。ともに英訳あり〕
http://
http://
http://
http://
このように、事件の当事者が直接本を書くということは、実に稀である。当事者自身の本としてはヨランド・ムカガサナが唯一の例といえよう。しかしもともと看護士だったこの女性の本には当然編集者の手が加わっている。
Yolande Mukagasana : La Mort ne veut pas de moi〔注:ヨランド・ムカガサナ「死は私を欲しがっていない(仮題)」。この女性はまたその後ルワンダに戻り、70人あまりの加害者、被害者にインタビューして、写真とともに編集した証言集を発表している Les Blessures du silence「沈黙の傷跡(仮題)」〕
また、ジェノサイドをテーマに小説も書かれている。もっとも有名なのがカナダのケベック出身の作家 Gil Courtemanche(ジル・クルトマンシュ)のUn dimanche a la piscine a Kigali(「ある日曜日、キガリのプールで」英訳あり)だ。〔注:この小説はUn dimanche a Kigali という題で今年映画化されている〕
http://
http://
本来ジェノサイドを記すという行為にはふたつの意味合いがある。まず、記録として歴史を風化させないようにすること。そして次に哀悼の意を持ってモニュメントとすること。しかし多くの場合、もともとの人道的な意図とは裏腹に、「文章」という形をとることで、文章として存在させるために(ひとに読んでもらうために)型にはめ込んでしまい、実際にはジェノサイドを美化しないまでも、美しい本にしてしまいがちだ。
また本来、記録として遺そうと言う意思があっても、あまりの凄惨さに結局「言葉に言い尽くせない」「表現しがたい」「想像を超える」というような言葉が並ぶ。「言葉に表せない」と書いて、どれだけ読者にその凄惨さを伝えることができるのだろうか。
また、犠牲者に対する哀悼の気持ちがあり、また彼らに対してシンパシーを持ちながらも、結局「地獄のよう」「悪魔の仕業」「カオス」のような言葉が並びだすと、現実に起きた事ながら、事件は言葉の力によって宗教的、神秘的な次元に引っ張られ、同じ人間としての他者への関心や共感を持つべきところが、結果として「ひとごと」という視点でしか見られないという皮肉なことがおきる。
このように歴史的な大惨事を記録することは難しいし、危険に陥りやすい罠にさらされている。
そんな中、それでも「読み物」としての形をじゅうぶんに持ちながら、「記録」として現実を美化せずに、またセンチメンタリズムにも流されないちょうどいいバランスを保っているものとして、L’homme qui demanda du feu(Ivan Reisdorff イヴァン・レイストルフ:「火を求めた男(仮題)」)を挙げたい。この本は1978年に刊行された。つまりこのたびの大虐殺を語るものではない。50年代の事件の話だ。しかし最近の事件を受けて復刊されたものである。
http://
もうひとつの試みとしてベルギーのパフォーマンス団体Grooupovの舞台の話をしたい。Rwanda 94と題されたこの公演は5年に及ぶ試行錯誤の末、1999年に発表された。先述のヨランド・ムカガサナ本人が登場し、ジェノサイドを語ることから舞台は始まる。しかし舞台はそれだけで終わらない。テレビの映像、新聞記事、さまざまな形での音楽(コーラス、ルワンダの伝統的な歌、新しくこの舞台のために作られた歌、太鼓、オーケストラ)などで構成され、ルワンダのジェノサイドを表現していく。これは未だかつてなかった種類の表現方法だ。4時間に及ぶ公演の長さは、このジェノサイドの規模からして必要な時間だった。
結論としては、ジェノサイドという歴史的大事件について書くということはとても困難で、また本来の意図とは違ったほうに流れる危険性を孕んではいるものの、「語らなくていい」ということではけっしてなく、「そういう危険をおかしてでも語り継ぐべき」ものであり、また「語らないことは不可能」だ。
最後に質疑応答の時間が設けられました。
最初に私から質問させていただきました。
? 歌手のコルネイユについてご意見を聞かせてください。
もともとコルネイユについては語ろうと思っていた。コルネイユはジェノサイドの後、ジェノサイドの生き残りとして登場した。彼についての判断はここでは控える。後世が判断するだろう。彼には才能がある。しかし、ジェノサイドをテーマにして金儲けをしたという批判にさらされ、彼自身とても悩んだという。ここにもまたジェノサイドを語ることについての難しさがある。というのも、彼もまたジェノサイドを離れた歌を歌おうとはしているが、やはり彼の一番胸をうつ歌はジェノサイドをテーマにしたものだからだ。
ここにひとつ疑問をあげることができる。「芸術のテーマとしてジェノサイドを扱うということに道義的な問題がないだろうか?」という問いかけだ。わたしにはまだ答えが見つけ出せていない。
この質問を受けて別の質問がほかの方から出ました。
? 芸術作品になるかどうかは作品が美しいかどうかにかかっていると思うが、このことについてはどう思いますか?
ある歴史的事件を芸術作品で扱ったとき、どれだけのことが後世のひとに訴えられるかを考えなくてはならない。たとえばピカソの「ゲルニカ」を例にとってみよう。この名画を描くためにピカソが自分の魂すべてをかけてある兵器の効力を実験するためだけにひとつの村を爆撃したという事件を批判しただろうが、現在この名画を見てどれだけの人がこの事件に思いをはせるだろうか。つまりはそういうことだ。
もうひとり別の方が質問をされました
? ジェノサイドにおいて、植民地時代はまったく責任がないと言えるのだろうか?
まったくないとは言えない。特にツチ族を優遇したことは大きい。特筆すべき点は白人優位主義の人種差別的な観点によって彼らを見下したのではなく、どちらかというと、彼らを特別あがめてしまったために差別意識を植え付けたという点だ。植民地政策においてこれは珍しいことだ。
最後に質問者がいなくなったので、もういちど私から
? 現在日本で公開中の映画「ホテル・ルワンダ」についてひとことお願いします(ここで日本公開に至った経緯も説明)。
「ホテル・ルワンダ」という映画は、ハリウッドの大資本が一般大衆を対象にしてこのテーマを扱うという枠の中では、最高のものを作ったと思う。
ただしルワンダ人にとってはこの映画は複雑なものがあったようだ。たとえば、ルワンダがフランス語圏であるのに対して、映画はアングロ・サクソン系のものだった。当事者にとってはまた「自分たちのことを自分たちぬきで語っている」というふうに思われた。
しかし、最初日本で公開される予定がなかったのに公開に至ったことはとてもよいことで、そういう運動が実を結んで本当によかったと思う。
去る四月五日、東京日仏学院で行われた講演会「大虐殺を記す:文学とルワンダ証言」に行ってまいりました。だいぶ遅くなりましたが、レポートを書きました。
リポートについては、あくまでアレン教授のおっしゃったことを再現し、〔〕内に注を私が補足しています。
講師 : ピエール・アレン教授
フランス、メッツ大学文学、比較文学教授
1985年 雑誌Textyles(テクスティル)を創刊。
雑誌Etudes littéraires africaines(アフリカ文学研究誌)にも執筆。
専門: 植民地文学。フランス語圏の文学(主にベルギー、中央アフリカ、移民、アイデンティティーの問題)。
まずおさらい程度ということで、簡単にルワンダの地理と歴史の紹介があった。
ルワンダはアフリカの中央に位置する国で、隣国にはウガンダ、コンゴ、タンザニア、ブルンディがある。国土は小さく、貧しい。人口密度は高い。
歴史的に見れば、早くから同じ言語、同じ文化、同じ宗教を共有する人々が住んでいた。彼らはフツ、ツチ、トゥワという、厳密な意味での民族とも、階級ともは呼べないような、ある種のグループに分かれていた。各グループの占める割合は、85パーセントがフツ、14パーセントがツチ、そして1パーセントがトゥワだ。おもにツチ族は兵士、王族であり、国を支配していて、フツ族は農業をいとなんでいた。このグループ間の対立は古くから存在していたが、表立って大きな事件に繋がることは稀だった。少数派のツチは多数派のフツを支配し、奴隷のように扱っていた。しかしツチ族フツ族間の結婚もあり、彼らは共存し、とりあえず、バランスはとれていた。また覚えておきたいのは、ルワンダの国境がアフリカの国にあっては珍しく自然の地形による国境であることだ。ここにこの国の特異性が見られる。
ツチ・フツ間の対立の図式が顕著になったのは、ベルギーによる植民地時代だ(厳密には国連からの委任統治)。ベルギーも、それ以前の宗主国ドイツもツチ族に対し、憧れのような気持ちを抱く。そこで伝説ができた。ツチ族が遠く東のほうからやってきた民族という伝説だ。よってツチ族は民族的にフツ族とは別の民族で、その起源は遠くユーラシア大陸にまでさかのぼり、つまりよりヨーロッパ人(白人)に近い民族である、よって生まれながらにして支配層であるべき民族である、と。この説は現在ではまったく科学的根拠のないものとされている。この説を実践するためベルギーはIDカードにも民族を記すことにした。ツチ族はこの政策を歓迎し、自分たちの大儀のために利用した。
1959年 独立運動、および最初のジェノサイド(多数のツチ族が隣国ウガンダに逃亡)。
1962年 独立(グレゴワール・カイバンダ大統領)フツ族政権誕生
1973年 軍事クーデターにより政権交代(新しい大統領ジュヴェナル・ハビャリマナもフツ族だった)
その後この政権は独裁的になり、汚職もはびこるようになる。またこの時期にツチ族に対して差別的な政策が行われた。
80年代には長い間友好関係にあったベルギー国内の政権が変わったことにより、ベルギーの支持を失う。かわりにやってきたのがフランスだった。そしてその後はほとんどの西欧諸国がそっぽを向く中、フランスだけが唯一の支持国となる。
ジェノサイドが起こったのはこのような状況下でのことだった。
きっかけは1994年4月7日、ルワンダの大統領と隣国ブルンディの大統領を乗せた飛行機がミサイルによって撃ち落され、二人の大統領が死亡したことだった。誰がミサイルを発射したのかは未だにわかっていない。
すぐに復讐を呼びかけるフツ族によるツチ族の虐殺が行われた。だがこのこの虐殺は事前に長年にわたって準備されていたものであった。最初に狙われたのは、主に知識階級、弁護士、学者、医者などだった。その後残りのツチ族も狙われ、また穏健派フツ族も殺された。虐殺は3ヶ月に及んだ。
犠牲者はおよそ80万人(60万人から100万人の間で変化する)、それに加えて、その後フツ族難民が、移動中あるいは難民キャンプでのコレラの流行によって命を落とした。その数およそ25万人と言われる。人口およそ700万人の国にあって、この数字がいかに大きいかがわかる。
しかしこれほどの規模の大虐殺を事件当時、世界中はほとんど無視したような状況だった。虐殺の映像は少なく、現地にいた特派員たちも早々に引き上げ、また在留の国連軍も介入しなかった。
しかし、ひとたびことが収まり、取り返しがつかなくなってようやく、多くの「文章」が出だした。その数は「無視」したことに比較すると驚異的ですらある。それはあらゆるジャンルにわたっている。旅行記、ルポルタージュ、証言、フィクション、エッセイ、写真集、漫画(BD)さらには音楽や舞台に至るまで。中にはセラピーとしての記録もあった。
ここで大虐殺を記すという行為の意味の問題を取り上げたい。単なる素の証言という形から、美学的な色合いを強め、さらなる方向へと向かっているのではないかという問題だ。なぜなら、ひとたび文章になれば、形式をもたない内容はない。たとえそれがどんな無機質な学術論文であっても、必ずや形式にとらわれることになる。するととたんに長い間培われてきた「文学」のあらゆる拘束を受けることにより、宗教的、歴史的な含意を帯びることになる。そこに、ある種の罠がある。書かれたことにより、現実は必ずなんらかのかたちで裏切られることになる。
旅行記、ルポルタージュ、小説、写真集、エッセイ、ありとあらゆる形の芸術作品がルワンダをテーマにした。
多くの場合、これらの書物は問題を孕んでいる。なぜならほとんどが伝聞による記録だからだ。一番の当事者である犠牲者たちは死んでおり、言葉を持たない。残るは生き残った人たちである。ここにも問題がある。ひとつには、ルワンダのジェノサイドにおいて、最初に狙われたのは多くの場合、高学歴の知的階級だった。医者、教育者、法律家など。つまりきちんと文章を書けるような人々などがいなくなってしまった。もうひとつの要因として、生き残った人々は大きなトラウマを抱えていた。彼らは目の前で親、兄弟が想像を絶するような状況下で殺された。残酷な殺され方をした(マシェット、棍棒など)だけでなく、ときには父親が母親を殺し、父親が子どもを殺し、子どもが親を殺す、隣人同士で殺しあうというような惨劇を目の当たりにした。また生き残りとは言っても自分たちもまた大きな傷を負っている。そんな中で証言をするということは困難だ。
この事件を風化させないため、という意味合いで多くの記録が残されている。
まず、企画として、フランス政府はルワンダに10人ほどの作家を送り、事件について書かせた。ほとんどのひとが、それまで著述業に関わったことがなく、また作家としての野心を持っていないほうがよいとされた。中にはすでに作家として活動していたひともいたが(コート・ディヴォワール人作家ヴェロニック・タッジョはもともと児童文学の作品を出していた)稀である。こうして2000年に10冊の本が出た。4冊が大手の出版社、6冊がもっとマイナーな出版社から刊行された。
一冊挙げるとすれば
Véronique Tadjo : L’Ombre d’Imana (Actes Sud)
〔注:ヴェロニック・タッジョ 「イマナの影」(仮題)英訳あり〕
http://
http://
この問題には別の側面があった。事件をアフリカ人に語らせる場合、彼らにとっても複雑な状況に追い込まれるようになったのだ。多くの事件と違い、今回のジェノサイドについて語るとき、彼らは責任を「西欧社会」からの搾取やら、植民地主義に負わせることができなかった。明らかに事件はルワンダ独自の問題で、アフリカ人がアフリカ内部の問題に向き合うことを余儀なくさせられたのだった。
その後今度は西欧人がルワンダに出向き、ジェノサイドを語るようになる。その中でもっとも有名なのが、フィリップ・グーレヴィッチのジェノサイドの丘(原題 : Philip Gourevitch : We wish to inform you that tomorrow we will be killed with our families) だ。
http://
http://
西欧人がジェノサイドを書く場合の問題は、ジェノサイドの当事者たちにとって外側から書かれたものという面が強く出ることだ。「自分たちぬきで自分たちのことが書かれている」という心理だ。
リベラシオン紙(フランスの左翼系新聞)の記者Jean Hatzfeld(ジャン・ハッツフェルド)の著書 Dans le nu de la vie は著者ができるだけ表に出ずに当事者に言葉を託した。そして本を出版するとき、自分の名前が出ないよう出版社に頼んだが、受け入れられなかった。著者の名なしでは本が売れないからだ。後にこの本でハッツフェルドは賞を受ける。ここに、本来人道的な意図で始められたものが出版を経て、ビジネスという次元に移る。
〔注:Dans le nu de la vie では著者はジェノサイドの犠牲者の証言を集めた。10年後、 Une saison de machettesで今度は、ルワンダの刑務所に赴き、ジェノサイドを行った側の証言を集めている。ともに英訳あり〕
http://
http://
http://
http://
このように、事件の当事者が直接本を書くということは、実に稀である。当事者自身の本としてはヨランド・ムカガサナが唯一の例といえよう。しかしもともと看護士だったこの女性の本には当然編集者の手が加わっている。
Yolande Mukagasana : La Mort ne veut pas de moi〔注:ヨランド・ムカガサナ「死は私を欲しがっていない(仮題)」。この女性はまたその後ルワンダに戻り、70人あまりの加害者、被害者にインタビューして、写真とともに編集した証言集を発表している Les Blessures du silence「沈黙の傷跡(仮題)」〕
また、ジェノサイドをテーマに小説も書かれている。もっとも有名なのがカナダのケベック出身の作家 Gil Courtemanche(ジル・クルトマンシュ)のUn dimanche a la piscine a Kigali(「ある日曜日、キガリのプールで」英訳あり)だ。〔注:この小説はUn dimanche a Kigali という題で今年映画化されている〕
http://
http://
本来ジェノサイドを記すという行為にはふたつの意味合いがある。まず、記録として歴史を風化させないようにすること。そして次に哀悼の意を持ってモニュメントとすること。しかし多くの場合、もともとの人道的な意図とは裏腹に、「文章」という形をとることで、文章として存在させるために(ひとに読んでもらうために)型にはめ込んでしまい、実際にはジェノサイドを美化しないまでも、美しい本にしてしまいがちだ。
また本来、記録として遺そうと言う意思があっても、あまりの凄惨さに結局「言葉に言い尽くせない」「表現しがたい」「想像を超える」というような言葉が並ぶ。「言葉に表せない」と書いて、どれだけ読者にその凄惨さを伝えることができるのだろうか。
また、犠牲者に対する哀悼の気持ちがあり、また彼らに対してシンパシーを持ちながらも、結局「地獄のよう」「悪魔の仕業」「カオス」のような言葉が並びだすと、現実に起きた事ながら、事件は言葉の力によって宗教的、神秘的な次元に引っ張られ、同じ人間としての他者への関心や共感を持つべきところが、結果として「ひとごと」という視点でしか見られないという皮肉なことがおきる。
このように歴史的な大惨事を記録することは難しいし、危険に陥りやすい罠にさらされている。
そんな中、それでも「読み物」としての形をじゅうぶんに持ちながら、「記録」として現実を美化せずに、またセンチメンタリズムにも流されないちょうどいいバランスを保っているものとして、L’homme qui demanda du feu(Ivan Reisdorff イヴァン・レイストルフ:「火を求めた男(仮題)」)を挙げたい。この本は1978年に刊行された。つまりこのたびの大虐殺を語るものではない。50年代の事件の話だ。しかし最近の事件を受けて復刊されたものである。
http://
もうひとつの試みとしてベルギーのパフォーマンス団体Grooupovの舞台の話をしたい。Rwanda 94と題されたこの公演は5年に及ぶ試行錯誤の末、1999年に発表された。先述のヨランド・ムカガサナ本人が登場し、ジェノサイドを語ることから舞台は始まる。しかし舞台はそれだけで終わらない。テレビの映像、新聞記事、さまざまな形での音楽(コーラス、ルワンダの伝統的な歌、新しくこの舞台のために作られた歌、太鼓、オーケストラ)などで構成され、ルワンダのジェノサイドを表現していく。これは未だかつてなかった種類の表現方法だ。4時間に及ぶ公演の長さは、このジェノサイドの規模からして必要な時間だった。
結論としては、ジェノサイドという歴史的大事件について書くということはとても困難で、また本来の意図とは違ったほうに流れる危険性を孕んではいるものの、「語らなくていい」ということではけっしてなく、「そういう危険をおかしてでも語り継ぐべき」ものであり、また「語らないことは不可能」だ。
最後に質疑応答の時間が設けられました。
最初に私から質問させていただきました。
? 歌手のコルネイユについてご意見を聞かせてください。
もともとコルネイユについては語ろうと思っていた。コルネイユはジェノサイドの後、ジェノサイドの生き残りとして登場した。彼についての判断はここでは控える。後世が判断するだろう。彼には才能がある。しかし、ジェノサイドをテーマにして金儲けをしたという批判にさらされ、彼自身とても悩んだという。ここにもまたジェノサイドを語ることについての難しさがある。というのも、彼もまたジェノサイドを離れた歌を歌おうとはしているが、やはり彼の一番胸をうつ歌はジェノサイドをテーマにしたものだからだ。
ここにひとつ疑問をあげることができる。「芸術のテーマとしてジェノサイドを扱うということに道義的な問題がないだろうか?」という問いかけだ。わたしにはまだ答えが見つけ出せていない。
この質問を受けて別の質問がほかの方から出ました。
? 芸術作品になるかどうかは作品が美しいかどうかにかかっていると思うが、このことについてはどう思いますか?
ある歴史的事件を芸術作品で扱ったとき、どれだけのことが後世のひとに訴えられるかを考えなくてはならない。たとえばピカソの「ゲルニカ」を例にとってみよう。この名画を描くためにピカソが自分の魂すべてをかけてある兵器の効力を実験するためだけにひとつの村を爆撃したという事件を批判しただろうが、現在この名画を見てどれだけの人がこの事件に思いをはせるだろうか。つまりはそういうことだ。
もうひとり別の方が質問をされました
? ジェノサイドにおいて、植民地時代はまったく責任がないと言えるのだろうか?
まったくないとは言えない。特にツチ族を優遇したことは大きい。特筆すべき点は白人優位主義の人種差別的な観点によって彼らを見下したのではなく、どちらかというと、彼らを特別あがめてしまったために差別意識を植え付けたという点だ。植民地政策においてこれは珍しいことだ。
最後に質問者がいなくなったので、もういちど私から
? 現在日本で公開中の映画「ホテル・ルワンダ」についてひとことお願いします(ここで日本公開に至った経緯も説明)。
「ホテル・ルワンダ」という映画は、ハリウッドの大資本が一般大衆を対象にしてこのテーマを扱うという枠の中では、最高のものを作ったと思う。
ただしルワンダ人にとってはこの映画は複雑なものがあったようだ。たとえば、ルワンダがフランス語圏であるのに対して、映画はアングロ・サクソン系のものだった。当事者にとってはまた「自分たちのことを自分たちぬきで語っている」というふうに思われた。
しかし、最初日本で公開される予定がなかったのに公開に至ったことはとてもよいことで、そういう運動が実を結んで本当によかったと思う。
|
|
|
|
コメント(5)
Kigalisoupeさん、お久しぶりです。
真摯なレポートを本当にありがとうございました。
心して読みましたよ。
私も「伝える」ことを生業にしているハシクレ、
真実の美化というお話を
今さらながらヒシヒシと受け止めした。
「けれど、美意識をもって具現化することは止めない」
ベルギーのパフォーマンスGrooupovは気になりますね。
観たいなー。
コルネイユについては、
まだ私は1曲しか知らないのですが、
(輸入CDをどこかで入手しようと思っているのですが、なかなか)
応援したいアーティストのひとりです。
少し、彼の情報は耳に入っているのですが、
日本企業のセール方法と彼のスタイルではギャップがある様子。
Kigalisoupeさんのレポート、
mixi内にとどめておくのは もったいないので、
私のサイトの掲示板に転記させてください。
また、昨年「ホテル・ルワンダ教室」を行った経済大学の講師で、
映画評論の粉川哲夫先生のワークショップのお知らせです。
今年度のカリキュラムが決定しました。
よかったら、ぜひお出かけください。
大学生以外の、部外者の参加を歓迎します
というコメントを粉川先生より頂戴しております。
●身体表現ワークショップ
http://anarchy.translocal.jp/shintai/
『ホテル・ルワンダ』は今週、
友人と三度目の観賞をしてまいりました。
三度目にして感じることもあり、
改めて入魂の作、素晴らしい1本だと思いました。
真摯なレポートを本当にありがとうございました。
心して読みましたよ。
私も「伝える」ことを生業にしているハシクレ、
真実の美化というお話を
今さらながらヒシヒシと受け止めした。
「けれど、美意識をもって具現化することは止めない」
ベルギーのパフォーマンスGrooupovは気になりますね。
観たいなー。
コルネイユについては、
まだ私は1曲しか知らないのですが、
(輸入CDをどこかで入手しようと思っているのですが、なかなか)
応援したいアーティストのひとりです。
少し、彼の情報は耳に入っているのですが、
日本企業のセール方法と彼のスタイルではギャップがある様子。
Kigalisoupeさんのレポート、
mixi内にとどめておくのは もったいないので、
私のサイトの掲示板に転記させてください。
また、昨年「ホテル・ルワンダ教室」を行った経済大学の講師で、
映画評論の粉川哲夫先生のワークショップのお知らせです。
今年度のカリキュラムが決定しました。
よかったら、ぜひお出かけください。
大学生以外の、部外者の参加を歓迎します
というコメントを粉川先生より頂戴しております。
●身体表現ワークショップ
http://anarchy.translocal.jp/shintai/
『ホテル・ルワンダ』は今週、
友人と三度目の観賞をしてまいりました。
三度目にして感じることもあり、
改めて入魂の作、素晴らしい1本だと思いました。
5*SEASONさん、
ほんとにお久しぶりです。
私のリポート、読んでくださり、感謝です。
コルネイユのことは5*SEASONさんから教えていただいたのですものね。
mixi内にもコルネイユ・コミュがあるので、そちらにも参加しています。
コルネイユについては、わたしも応援しています。彼の歌も大好きです。でも正直言って、もともとR&Bはあまり聴かないジャンルでした。ルワンダ人のコルネイユということで関心を持ちました。だからアレン教授のコメントには考えさせられました。
粉川先生のワークショップのことも教えていただき、ありがとうございました。
またどこかでお会いできればいいですね
ほんとにお久しぶりです。
私のリポート、読んでくださり、感謝です。
コルネイユのことは5*SEASONさんから教えていただいたのですものね。
mixi内にもコルネイユ・コミュがあるので、そちらにも参加しています。
コルネイユについては、わたしも応援しています。彼の歌も大好きです。でも正直言って、もともとR&Bはあまり聴かないジャンルでした。ルワンダ人のコルネイユということで関心を持ちました。だからアレン教授のコメントには考えさせられました。
粉川先生のワークショップのことも教えていただき、ありがとうございました。
またどこかでお会いできればいいですね
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ホテル・ルワンダ 更新情報
ホテル・ルワンダのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37847人
- 3位
- 楽天イーグルス
- 31945人