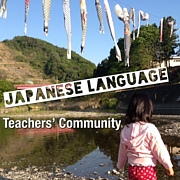トピックを検索いたしましたが、見当たらなかったので立てさせていただきます。
今教えている上級クラスで使っている「ハイスコア文法1級―日本語能力試験で差をつける出題基準外の表現 」に出てきた表現(文型)で、疑問があります。
「全然〜ない」という意味(とテキストにある)、「〜やしない」というものです。
**以下抜粋**
〜やしない(動詞ます+やしない)
意味:全然〜ない(あきらめ、怒り、軽蔑など否定的な感情をこめて用いる)
1.無理無理、うちの子は、そんないい学校に入れやしないわ。
2.客には、本当の温泉かどうかなんてわかりやしないよ。入浴剤を入れてしまおう。
**抜粋終わり**
この説明を読むと納得できるのですが、ふと「〜はしない」と置き換えられるのではないか、と思いました。
1'.そんないい学校に入れはしない。(終助詞「わ」がつくと違和感があるような)
2'.本当の温泉かどうかなんてわかりはしないよ。
また、次のような例文も考えましたが、これもどちらもいえる気がします。
3.いくら部屋を片付けろっていったって、聞きやしない。
3'.いくら部屋を片付けろっていったって、聞きはしない。
私の感覚では、3は「まったく、いい加減にしろ!」というような怒り、
3'は「だから言っても無駄だ」というような諦めがあるように思います。
皆さんは、この2つの意味の違いについてどのように思われますか。
また、何かこの2つについてご存知の方がいらっしゃったら、教えていただけませんでしょうか。
手持ちの文法書・辞書などあたってみましたが、これといった説明を見つけることができませんでした。
どうぞよろしくお願いいたします。
今教えている上級クラスで使っている「ハイスコア文法1級―日本語能力試験で差をつける出題基準外の表現 」に出てきた表現(文型)で、疑問があります。
「全然〜ない」という意味(とテキストにある)、「〜やしない」というものです。
**以下抜粋**
〜やしない(動詞ます+やしない)
意味:全然〜ない(あきらめ、怒り、軽蔑など否定的な感情をこめて用いる)
1.無理無理、うちの子は、そんないい学校に入れやしないわ。
2.客には、本当の温泉かどうかなんてわかりやしないよ。入浴剤を入れてしまおう。
**抜粋終わり**
この説明を読むと納得できるのですが、ふと「〜はしない」と置き換えられるのではないか、と思いました。
1'.そんないい学校に入れはしない。(終助詞「わ」がつくと違和感があるような)
2'.本当の温泉かどうかなんてわかりはしないよ。
また、次のような例文も考えましたが、これもどちらもいえる気がします。
3.いくら部屋を片付けろっていったって、聞きやしない。
3'.いくら部屋を片付けろっていったって、聞きはしない。
私の感覚では、3は「まったく、いい加減にしろ!」というような怒り、
3'は「だから言っても無駄だ」というような諦めがあるように思います。
皆さんは、この2つの意味の違いについてどのように思われますか。
また、何かこの2つについてご存知の方がいらっしゃったら、教えていただけませんでしょうか。
手持ちの文法書・辞書などあたってみましたが、これといった説明を見つけることができませんでした。
どうぞよろしくお願いいたします。
|
|
|
|
コメント(14)
コメントありがとうございます。
質問させていただいて以降、PCに触れられなかったもので、
お返事が遅くなって失礼いたしました。
でくさん
方言!
なるほど。驚きました。
音声的なものかな、というのは私もなんとなく思っておりましたが、
私はずっと千葉在住なもので、「共通語」と「東京方言」の差が感覚としてよくわかりません。
大阪人のでくさんからのご意見、大変参考になりました。
それにしても、「出題基準外」の問題集は一応過去問から作られているようで、ここまで出題されることに驚きました。
ありがとうございました。
Cathy of W.H.さん
Cathy of W.H.さんの「勘」と、私の感覚、だいたい同じだといえそうです。
このように自分以外の方から「勘」を教えていただけると、大変ありがたいです。
自分の感覚が自分だけじゃないようだ、とわかりますから。
でくさんのご意見にも、「は」のほうが客観的で乾いた感じ、とありますので、違いがある(または人によって違いを感じる)とするとここかな、と思いました。
それから、3'の例文、私も自分で作っておいて若干の違和感はありました。
上記のことを踏まえると、「〜っていったって」というのにやや感情がこめられているため、違和感を覚える、と言えるかもしれません。
ありがとうございました。
授業では、あえて「〜はしない」をこちらから出すことはもちろんしませんが、
もし質問が出たときには上記のように答えたいと思います。
本当にありがとうございました。
質問させていただいて以降、PCに触れられなかったもので、
お返事が遅くなって失礼いたしました。
でくさん
方言!
なるほど。驚きました。
音声的なものかな、というのは私もなんとなく思っておりましたが、
私はずっと千葉在住なもので、「共通語」と「東京方言」の差が感覚としてよくわかりません。
大阪人のでくさんからのご意見、大変参考になりました。
それにしても、「出題基準外」の問題集は一応過去問から作られているようで、ここまで出題されることに驚きました。
ありがとうございました。
Cathy of W.H.さん
Cathy of W.H.さんの「勘」と、私の感覚、だいたい同じだといえそうです。
このように自分以外の方から「勘」を教えていただけると、大変ありがたいです。
自分の感覚が自分だけじゃないようだ、とわかりますから。
でくさんのご意見にも、「は」のほうが客観的で乾いた感じ、とありますので、違いがある(または人によって違いを感じる)とするとここかな、と思いました。
それから、3'の例文、私も自分で作っておいて若干の違和感はありました。
上記のことを踏まえると、「〜っていったって」というのにやや感情がこめられているため、違和感を覚える、と言えるかもしれません。
ありがとうございました。
授業では、あえて「〜はしない」をこちらから出すことはもちろんしませんが、
もし質問が出たときには上記のように答えたいと思います。
本当にありがとうございました。
あの、私個人の感覚なので、間違っていたらすみません。
私も関東出身なので、全国的に見たら変わらないのかもしれませんが。
「〜やしない」を「〜はしない」に
言い換えることはできますが、
「〜はしない」を「〜やしない」に
全て置き換えるのは難しいような気がします。
理由は、上手く説明できないのですが、
「〜やしない」というのは、その動作主が
話し手以外のときには言えると思うのですが、
動作主=話し手のときにはあまり言わないと思うのです。
言い換えると、話し手が自分以外の人に対して
説明するときのほうによく使うと思います。
それは、「〜やしない」を使用する場面というのが
「あきらめ、怒り、軽蔑など否定的な感情をこめて用いる」
だからだと思います。
つまり、話し手が自分を軽蔑して話す場面というのが
普通の会話の中で少ないと思うのですが。
それとも、単なる方言なのですかね。
いかがでしょうか…。
私も関東出身なので、全国的に見たら変わらないのかもしれませんが。
「〜やしない」を「〜はしない」に
言い換えることはできますが、
「〜はしない」を「〜やしない」に
全て置き換えるのは難しいような気がします。
理由は、上手く説明できないのですが、
「〜やしない」というのは、その動作主が
話し手以外のときには言えると思うのですが、
動作主=話し手のときにはあまり言わないと思うのです。
言い換えると、話し手が自分以外の人に対して
説明するときのほうによく使うと思います。
それは、「〜やしない」を使用する場面というのが
「あきらめ、怒り、軽蔑など否定的な感情をこめて用いる」
だからだと思います。
つまり、話し手が自分を軽蔑して話す場面というのが
普通の会話の中で少ないと思うのですが。
それとも、単なる方言なのですかね。
いかがでしょうか…。
pptr(^Θ^)♪さん
>「〜はしない」を「〜やしない」に
>全て置き換えるのは難しいような気がします。
そうですね、私もそんな気がします。
いい例文が思いつかないのですが……。
やはり、「〜やしない」というのは特別な感情がこめられている表現なのですね。
動作主=自分、のときには使えない、というのも、おっしゃるとおりだと思います。
ありがとうございました。
G.T.O.Okuimanさん
「松島や〜〜〜」については、私もでくさん同様詠嘆だと思います。
『新明解』には、「終助詞」の項目に
「古池や 蛙飛び込む水の音」
と一緒に例として挙げられていました。
また、でくさんご指摘の「断定の助動詞」についても、『新明解』に以下のような記述がありました。
や(助動・特殊型)〔「じゃ」の変化〕(富山・岐阜以西、近畿方言)主体の断定的な判断を表す。「ほんまに、そうやおまへんか。」「あるんや」「そうや」
この「や」は「〜やしない」とは違いそうですね。
『新明解』の記述を信用するなら、「しやおへんか。」の「や」は、「そうだ」の「だ(じゃ)」ということになります。
>日本語学習の上級者向けにしても、格別に必要な日常表現で無い事は確かなので
>問題例文作成者や出題にあった事(ある事)に疑問符が生じます。
同感ですね。
まぁ、小説などで使われることはありますが、使用頻度としてはかなり低いと思います。
コメントありがとうございました。
ところで、「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で検索してみたところ、小説の会話文が多かったですが、国会答弁でも使われていて興味深いです。
例)構造改革の政策にある程度の矛盾が生じやしないかという御質問かと思います。
これは「あきらめ、怒り、軽蔑など否定的な感情」がこめられている、とは必ずしもいえない例文だと思いました。
>「〜はしない」を「〜やしない」に
>全て置き換えるのは難しいような気がします。
そうですね、私もそんな気がします。
いい例文が思いつかないのですが……。
やはり、「〜やしない」というのは特別な感情がこめられている表現なのですね。
動作主=自分、のときには使えない、というのも、おっしゃるとおりだと思います。
ありがとうございました。
G.T.O.Okuimanさん
「松島や〜〜〜」については、私もでくさん同様詠嘆だと思います。
『新明解』には、「終助詞」の項目に
「古池や 蛙飛び込む水の音」
と一緒に例として挙げられていました。
また、でくさんご指摘の「断定の助動詞」についても、『新明解』に以下のような記述がありました。
や(助動・特殊型)〔「じゃ」の変化〕(富山・岐阜以西、近畿方言)主体の断定的な判断を表す。「ほんまに、そうやおまへんか。」「あるんや」「そうや」
この「や」は「〜やしない」とは違いそうですね。
『新明解』の記述を信用するなら、「しやおへんか。」の「や」は、「そうだ」の「だ(じゃ)」ということになります。
>日本語学習の上級者向けにしても、格別に必要な日常表現で無い事は確かなので
>問題例文作成者や出題にあった事(ある事)に疑問符が生じます。
同感ですね。
まぁ、小説などで使われることはありますが、使用頻度としてはかなり低いと思います。
コメントありがとうございました。
ところで、「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で検索してみたところ、小説の会話文が多かったですが、国会答弁でも使われていて興味深いです。
例)構造改革の政策にある程度の矛盾が生じやしないかという御質問かと思います。
これは「あきらめ、怒り、軽蔑など否定的な感情」がこめられている、とは必ずしもいえない例文だと思いました。
ようすけさん
リンク先見てみました。(検索していただきありがとうございました)
ここにある「や」の説明「口頭語で,係助詞「は」がなまったもの。」は、大辞林のものですが、「なまったもの」ってなんだかいい加減な説明だなという気がしてしまいました(苦笑
「なまった」、つまりより日常語に近いということで、「はしない」より感情的、といえそうですね。
ところで「古語の影響」というのはどういうところから言えるのでしょうか。
ようすけさんの10のコメントからは、「あちこちの方言で見られるから」というように読めますが、方言に残っているから古語の影響がある、と言えるものなのでしょうか?(異議ではなく、単純な疑問です)
リンク先見てみました。(検索していただきありがとうございました)
ここにある「や」の説明「口頭語で,係助詞「は」がなまったもの。」は、大辞林のものですが、「なまったもの」ってなんだかいい加減な説明だなという気がしてしまいました(苦笑
「なまった」、つまりより日常語に近いということで、「はしない」より感情的、といえそうですね。
ところで「古語の影響」というのはどういうところから言えるのでしょうか。
ようすけさんの10のコメントからは、「あちこちの方言で見られるから」というように読めますが、方言に残っているから古語の影響がある、と言えるものなのでしょうか?(異議ではなく、単純な疑問です)
< そらさん
なまった、は確かに笑えました。なんというか、フランクな解説ですよね(笑)
古語の影響もあるかと考えたのは、理由はひとつでは無いんですが、単純に、方言が古形をよく残すという事実も念頭にありました。私は近畿の南の方に縁が深いのですが、「あかんわ。全然食べやせん(べ、にアクセント核)」みたいな使い方はなじみがあります。
また一般にも、どうも『可能+やしない』という形が多く使われるのかなとか思いまして、「こんなに食べられやしない」というと「食べられるわけがないじゃないか」といった意味に非常に近くなって、「こんなに食べられはしない」だと、みなさんの内省の通り、随分理性的な言い方に落ち着くんですよね。
係助詞というところも気になったり。
…というわけで、ややこしい問題なのかなと思っています。こうやって書いている今も、自分、幾つもの性質の違う話を変にまとめて話していたりはしやしないだろうかと少し冷や汗ものです。
ただやはり、ハとヤは用法としては明らかに別なのかな、とは思います。特に『可能+やしない』。今、学生に聞かれたら、「慣用表現です」とか答えてしまいそうです(汗)
なまった、は確かに笑えました。なんというか、フランクな解説ですよね(笑)
古語の影響もあるかと考えたのは、理由はひとつでは無いんですが、単純に、方言が古形をよく残すという事実も念頭にありました。私は近畿の南の方に縁が深いのですが、「あかんわ。全然食べやせん(べ、にアクセント核)」みたいな使い方はなじみがあります。
また一般にも、どうも『可能+やしない』という形が多く使われるのかなとか思いまして、「こんなに食べられやしない」というと「食べられるわけがないじゃないか」といった意味に非常に近くなって、「こんなに食べられはしない」だと、みなさんの内省の通り、随分理性的な言い方に落ち着くんですよね。
係助詞というところも気になったり。
…というわけで、ややこしい問題なのかなと思っています。こうやって書いている今も、自分、幾つもの性質の違う話を変にまとめて話していたりはしやしないだろうかと少し冷や汗ものです。
ただやはり、ハとヤは用法としては明らかに別なのかな、とは思います。特に『可能+やしない』。今、学生に聞かれたら、「慣用表現です」とか答えてしまいそうです(汗)
けにごしさん
コメントありがとうございます。
なるほど、こういう例もあるんですね。
これは、私も「諦め、怒り、軽蔑などの感情」は感じません。
私が9で挙げた「矛盾が生じやしないか」も同様だと思います。
(状況によっては、同じ表現で怒りがこめられることもあるかもしれませんが)
「見はしない」、というのは、私はそれほど不自然に感じませんでした。
あっても変ではないと思います。
うーん、けっこうゆれがありそうですね。
実は既に授業ではやってしまって、そのときはさらっとテキストの内容をおさえた程度にしてしまったのですが、
けにごしさんの例などを見て、「諦め、怒り、軽蔑」と言い切ってしまったのはまずかったかなと反省しています。
しかも、最近の「事故米」の偽装問題について
「どうせばれやしない、と思ったんでしょうねぇ」
なんていう例文(軽蔑の意味で)まであげてしまいました……。
「そういう感情を伴うことが多い/ある」くらいにしておいたほうがよかったのかもしれません。
ようすけさん
古語の件、お答えいただきありがとうございます。
係助詞、というのは私もなんとなく気になっています。
また、けにごしさんが挙げてくださった歌も、該当箇所以外に古語が残っていますね。
ということは、やはり……?
古語の名残、と言っても、その古い形自体がハの音便として存在するのか、まったく別の意味として存在するのか(これはなさそう?)、という問題もありますね。
単に音便の問題でしたら、感情的な区別などまったくないでしょうが、そうとも言い切れない部分もありますし。
おっしゃるとおり、かなりややこしい問題だなぁと思いました。
「慣用表現です」って便利ですよね(苦笑
いろいろとありがとうございました。
コメントありがとうございます。
なるほど、こういう例もあるんですね。
これは、私も「諦め、怒り、軽蔑などの感情」は感じません。
私が9で挙げた「矛盾が生じやしないか」も同様だと思います。
(状況によっては、同じ表現で怒りがこめられることもあるかもしれませんが)
「見はしない」、というのは、私はそれほど不自然に感じませんでした。
あっても変ではないと思います。
うーん、けっこうゆれがありそうですね。
実は既に授業ではやってしまって、そのときはさらっとテキストの内容をおさえた程度にしてしまったのですが、
けにごしさんの例などを見て、「諦め、怒り、軽蔑」と言い切ってしまったのはまずかったかなと反省しています。
しかも、最近の「事故米」の偽装問題について
「どうせばれやしない、と思ったんでしょうねぇ」
なんていう例文(軽蔑の意味で)まであげてしまいました……。
「そういう感情を伴うことが多い/ある」くらいにしておいたほうがよかったのかもしれません。
ようすけさん
古語の件、お答えいただきありがとうございます。
係助詞、というのは私もなんとなく気になっています。
また、けにごしさんが挙げてくださった歌も、該当箇所以外に古語が残っていますね。
ということは、やはり……?
古語の名残、と言っても、その古い形自体がハの音便として存在するのか、まったく別の意味として存在するのか(これはなさそう?)、という問題もありますね。
単に音便の問題でしたら、感情的な区別などまったくないでしょうが、そうとも言い切れない部分もありますし。
おっしゃるとおり、かなりややこしい問題だなぁと思いました。
「慣用表現です」って便利ですよね(苦笑
いろいろとありがとうございました。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
☆日本語教師☆ 更新情報
-
最新のアンケート
☆日本語教師☆のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6474人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19244人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208299人