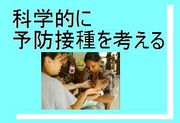「前橋レポート」とは?
前橋市医師会は1979年、インフルエンザワクチンの副作用があったことを理由に、前橋市内の小学校でのインフルエンザの集団接種を中止してしまいました。
これに伴い、予防接種の実施の有無によってインフルエンザの感染率に差が生じるかどうかを、前橋市周辺の予防接種を続けた他の市との間で比較して調査し、その結果を1987年に発表した報告書が、「前橋レポート」と呼ばれるものです。
この調査はトヨタ財団の助成金により行われたもので、医学雑誌に論文として発表されていないためか、具体的な内容はあまり知られていませんが、この全文が以下のweb siteに転載されてます。
http://
しかしながらこの前橋レポートには、調査の上でいくつか問題点が見られます。
まず、ワクチンの有効性を確かめる上でインフルエンザの感染者を数える方法として、各小学校に欠席児童数のアンケートをお願いするという極めて安直な手段に頼っており、さらにその欠席理由がインフルエンザによるものか風邪によるものか臨床的な検討を行うこと無しにごっちゃにして扱われています。
(この点に関しては調査チーム内部からも批判があったそうです)。
またインフルエンザに感染しているかどうかの判断には、調査内容によって異なる基準が採用されています。
この調査で採用した調査のデザインの検証についても、定性的な話に終始し、定量的な観点からの検証はこのレポートの中では全く行われていません。
上記のような観点から評価してみると、この前橋レポートの調査方法は極めて杜撰であり、学術論文として発表されなかった理由がこの点からうかがうことができます。
しかしその一方で、学術的な土俵に登れなかったためか専門家からの批判も少なく、調査内容が一般に知られぬまま「インフルエンザワクチンの有効性が否定された」という誤った結論だけが流布しているのが現状です。
このように「前橋レポート」には調査にあたってデザイン上の問題は多くあるものの、統計の規模を考えると単に切り捨てるのはもったいないことも確かです。
そこで、色々な条件を考慮し推計を加えながらこの「前橋レポート」から有益な情報を得られないか?、と考えるのがこのトピです。
統計上の扱いとして厳密に議論しなければならないところは多数あるのですが、元が厳密な話ではありませんので、とりあえず中学の数学程度の確率計算でわかるよう話を進めます。
(統計学上「こういうことをやるのはホントはヤバイ」という個所は、別に具体的に指摘します)
なおトピ主は、医学を専門とする者ではありませんので、ツッコミはご遠慮なくどうぞ。
ただ、都市伝説的なウソがはびこっているのはゆゆしき問題だと考えていますので、ツッコミ部分を修正した上でどっかのweb siteに加筆編集して転載するかもしれませんが、その際はご了承ください。
まぁ要するに現状では、学会発表する前の研究室内での発表、程度のクオリティです ^^
参考文献一覧
「ワクチン非接種地域におけるインフルエンザ流行状況」
前橋市インフルエンザ研究班 (1987)
(いわゆる「前橋レポート」)
http://
大月書店 科学全書42
「予防接種の考え方」
由上修三 (1992)
ISBN: 978-4272401529
感染症学雑誌 Vol.76 (2002) p.9
「インフルエンザワクチンの過去,現在,未来」
菅谷 憲夫
http://
前橋市医師会は1979年、インフルエンザワクチンの副作用があったことを理由に、前橋市内の小学校でのインフルエンザの集団接種を中止してしまいました。
これに伴い、予防接種の実施の有無によってインフルエンザの感染率に差が生じるかどうかを、前橋市周辺の予防接種を続けた他の市との間で比較して調査し、その結果を1987年に発表した報告書が、「前橋レポート」と呼ばれるものです。
この調査はトヨタ財団の助成金により行われたもので、医学雑誌に論文として発表されていないためか、具体的な内容はあまり知られていませんが、この全文が以下のweb siteに転載されてます。
http://
しかしながらこの前橋レポートには、調査の上でいくつか問題点が見られます。
まず、ワクチンの有効性を確かめる上でインフルエンザの感染者を数える方法として、各小学校に欠席児童数のアンケートをお願いするという極めて安直な手段に頼っており、さらにその欠席理由がインフルエンザによるものか風邪によるものか臨床的な検討を行うこと無しにごっちゃにして扱われています。
(この点に関しては調査チーム内部からも批判があったそうです)。
またインフルエンザに感染しているかどうかの判断には、調査内容によって異なる基準が採用されています。
この調査で採用した調査のデザインの検証についても、定性的な話に終始し、定量的な観点からの検証はこのレポートの中では全く行われていません。
上記のような観点から評価してみると、この前橋レポートの調査方法は極めて杜撰であり、学術論文として発表されなかった理由がこの点からうかがうことができます。
しかしその一方で、学術的な土俵に登れなかったためか専門家からの批判も少なく、調査内容が一般に知られぬまま「インフルエンザワクチンの有効性が否定された」という誤った結論だけが流布しているのが現状です。
このように「前橋レポート」には調査にあたってデザイン上の問題は多くあるものの、統計の規模を考えると単に切り捨てるのはもったいないことも確かです。
そこで、色々な条件を考慮し推計を加えながらこの「前橋レポート」から有益な情報を得られないか?、と考えるのがこのトピです。
統計上の扱いとして厳密に議論しなければならないところは多数あるのですが、元が厳密な話ではありませんので、とりあえず中学の数学程度の確率計算でわかるよう話を進めます。
(統計学上「こういうことをやるのはホントはヤバイ」という個所は、別に具体的に指摘します)
なおトピ主は、医学を専門とする者ではありませんので、ツッコミはご遠慮なくどうぞ。
ただ、都市伝説的なウソがはびこっているのはゆゆしき問題だと考えていますので、ツッコミ部分を修正した上でどっかのweb siteに加筆編集して転載するかもしれませんが、その際はご了承ください。
まぁ要するに現状では、学会発表する前の研究室内での発表、程度のクオリティです ^^
参考文献一覧
「ワクチン非接種地域におけるインフルエンザ流行状況」
前橋市インフルエンザ研究班 (1987)
(いわゆる「前橋レポート」)
http://
大月書店 科学全書42
「予防接種の考え方」
由上修三 (1992)
ISBN: 978-4272401529
感染症学雑誌 Vol.76 (2002) p.9
「インフルエンザワクチンの過去,現在,未来」
菅谷 憲夫
http://
|
|
|
|
コメント(36)
1)はじめに
この前橋レポートの調査の上での最大の問題点は、インフルエンザの感染者の定義が甘く、
ただの風邪のケースと十分に分離されていないこと、抗体価の調査の結果として欠席者の中でインフルエンザには感染していない割合が定量的につきとめられているにもかかわらず、その結果をふまえた上での補整あるいは考察が全くされていないことです。
急に高熱が出たなどのインフルエンザ様疾患の症状だけでは、例えばアデノウイルスによる感染などと区別するのは困難です。
言うまでもなくインフルエンザワクチンが予防に有効なのはインフルエンザウイルスによる感染のみですから、ただの風邪にかかっているのかインフルエンザにかかっているのか、注意深く分けて考えないとワクチンの有効性は正確には評価できません。
この調査が行われた20年前と異なり現代では、実際にインフルエンザのウイルスに感染しているかどうか数十分以内で検査が行える検査キットが普及していますが、実際にインフルエンザ様疾患の患者さんを診察してみると、インフルエンザウイルス以外の病原体が原因であることが相当な割合を占めることが知られています。
この具体的な数値がどこかにないかGoogle検索してみると、例えば「インフルエンザ様疾患 ウイルス分離」でGoogle検索をして最初のほうに出てくる以下の文献では、PCR反応による遺伝子分離までも行っても、インフルエンザ様疾患と判断された症状の中で、30%はインフルエンザウイルスが検出されなかった、という結果が出ています。
http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/004_chousa/04_reserch/files/35_HTML/no2/no2.htm
この調査が行われた当時はインフルエンザウイルスによる感染かどうかを迅速に診断できるキットもなく、また抗体価の検査もコスト的にHI法によるものしかできなかった、という制限を考えても、この調査内容はデザインとしては大変に歪なものです。
なのでここで、小学校の欠席者の中の実際のインフルエンザ患者の割合を調べ、この前橋レポートでは省かれている補整を試みてみます。
この時の流行の具合がわからないので、とりあえず推計の元となるデータは全てこの前橋レポートから拾うことにします。
具体的には3.D節の抗体価の調査結果を元に、3.C節での欠席児童の中で実際にインフルエンザに感染した人の割合は何%くらいなのかを推計し、ワクチンの予防接種を行った地域の中で実際のインフルエンザ患者数を補整し、ワクチンの正しい有効性を推計し、前橋市と他の市との間でどうしてこのような違いが生じたのかを考えてみます。
この前橋レポートの調査の上での最大の問題点は、インフルエンザの感染者の定義が甘く、
ただの風邪のケースと十分に分離されていないこと、抗体価の調査の結果として欠席者の中でインフルエンザには感染していない割合が定量的につきとめられているにもかかわらず、その結果をふまえた上での補整あるいは考察が全くされていないことです。
急に高熱が出たなどのインフルエンザ様疾患の症状だけでは、例えばアデノウイルスによる感染などと区別するのは困難です。
言うまでもなくインフルエンザワクチンが予防に有効なのはインフルエンザウイルスによる感染のみですから、ただの風邪にかかっているのかインフルエンザにかかっているのか、注意深く分けて考えないとワクチンの有効性は正確には評価できません。
この調査が行われた20年前と異なり現代では、実際にインフルエンザのウイルスに感染しているかどうか数十分以内で検査が行える検査キットが普及していますが、実際にインフルエンザ様疾患の患者さんを診察してみると、インフルエンザウイルス以外の病原体が原因であることが相当な割合を占めることが知られています。
この具体的な数値がどこかにないかGoogle検索してみると、例えば「インフルエンザ様疾患 ウイルス分離」でGoogle検索をして最初のほうに出てくる以下の文献では、PCR反応による遺伝子分離までも行っても、インフルエンザ様疾患と判断された症状の中で、30%はインフルエンザウイルスが検出されなかった、という結果が出ています。
http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/004_chousa/04_reserch/files/35_HTML/no2/no2.htm
この調査が行われた当時はインフルエンザウイルスによる感染かどうかを迅速に診断できるキットもなく、また抗体価の検査もコスト的にHI法によるものしかできなかった、という制限を考えても、この調査内容はデザインとしては大変に歪なものです。
なのでここで、小学校の欠席者の中の実際のインフルエンザ患者の割合を調べ、この前橋レポートでは省かれている補整を試みてみます。
この時の流行の具合がわからないので、とりあえず推計の元となるデータは全てこの前橋レポートから拾うことにします。
具体的には3.D節の抗体価の調査結果を元に、3.C節での欠席児童の中で実際にインフルエンザに感染した人の割合は何%くらいなのかを推計し、ワクチンの予防接種を行った地域の中で実際のインフルエンザ患者数を補整し、ワクチンの正しい有効性を推計し、前橋市と他の市との間でどうしてこのような違いが生じたのかを考えてみます。
2)「前橋レポート」のインフルエンザ感染者の定義と問題点
この前橋レポートの中で、ワクチンの効果の調査では、インフルエンザ感染者を次のように定義しています。
3.C節「小学校の欠席率によって見たワクチン効果」 1)「調査方法」
http://www.kangaeroo.net/D-maebashi-F-view-no-23C.html
インフルエンザ欠席者とは学校毎に決めた流行期間内の欠席者のうち,以下の条件を満たすものとした。
1. 37℃以上の発熱があって,連続2日以上欠席した者。
2. 発熱は不明であるが,連続3日以上欠席した者。
素人が考えても、これでは風邪も含まれてしまうことは明らかです。
各小学校にアンケートをおねがいし、授業を欠席した児童を集計する、という安直な方法では精度が低くなるのはしかたないにしても、これはちょっとあんまりです。
(例えば他の奈良市の調査では、欠席に加え38度以上の発熱、という条件を付けている)
次の節の抗体価の調査でのインフルエンザ感染者の定義はこの通りです。
3.D節「HI抗体価によって見た小学校のインフルエンザ流行」 2)「欠席率と感染率の関係」
http://www.kangaeroo.net/D-maebashi-F-view-no-23D.html
「流行期間内に一回でも欠席したことのある者については,インフルエンザにより欠席したものと見なして算出した。」
そう、同じ報告書の中でもインフルエンザ感染者として認定する基準が異なるのです。
ホントに読んでいて頭にくるレポートです!
しかもこの節の抗体価の調査結果では、以下のような結論になっています。
「小学校の欠席率が5%を越えるような,誰にでもかなりの流行として感じられる中規模以上の流行でも,感染者は欠席者の60%〜70%を占めるに過ぎない。小規模ないしはだらだらとした流行の場合には,その割合はさらに小さくなる。」
これをふまえ、4「総括と考按」の4節「インフルエンザ流行とHI抗体」では、次にように結論付けられています。
http://www.kangaeroo.net/D-maebashi-F-view-no-24.html
「流行時の欠席者のうち,インフルエンザ感染者は概ね60〜70%であり,逆にインフルエンザに感染していても欠席しない者すなわち「不顕性感染者」が全体の20%前後を占めることであった」
この結果は、直前の節「3) 欠席率によって見たワクチン効果」での考察が全く無意味であることを定量的に立証しています。
このレポートへの「欠席者の中にはインフルエンザ患者だけじゃなくただの風邪の人も混じっている」という批判への有効な反論は、その割合が実際にどの程度かを示すことです。
例えばこれが、別の調査では欠席者の中で80〜90%がインフルエンザ患者だった、というような具合に具体的な数値を定量的に示しているならまだ説得力がありますが、実際にはこの同じレポート内ではもっと低い結果が出ているのだから、全くお話になりません。
それがわかっているにもかかわらず、へ理屈をこねながら欠席者=インフルエンザ感染者、と固守し続けるのは、真理の追及に向けた誠実な態度とはとても思えません。
と、文句ばかり言っていても生産的ではないので、手を動かしながらもう少し深く考えてみます。
(なお、色々へ理屈をこねている部分については、最後にメッタ斬りにします)
この前橋レポートの中で、ワクチンの効果の調査では、インフルエンザ感染者を次のように定義しています。
3.C節「小学校の欠席率によって見たワクチン効果」 1)「調査方法」
http://www.kangaeroo.net/D-maebashi-F-view-no-23C.html
インフルエンザ欠席者とは学校毎に決めた流行期間内の欠席者のうち,以下の条件を満たすものとした。
1. 37℃以上の発熱があって,連続2日以上欠席した者。
2. 発熱は不明であるが,連続3日以上欠席した者。
素人が考えても、これでは風邪も含まれてしまうことは明らかです。
各小学校にアンケートをおねがいし、授業を欠席した児童を集計する、という安直な方法では精度が低くなるのはしかたないにしても、これはちょっとあんまりです。
(例えば他の奈良市の調査では、欠席に加え38度以上の発熱、という条件を付けている)
次の節の抗体価の調査でのインフルエンザ感染者の定義はこの通りです。
3.D節「HI抗体価によって見た小学校のインフルエンザ流行」 2)「欠席率と感染率の関係」
http://www.kangaeroo.net/D-maebashi-F-view-no-23D.html
「流行期間内に一回でも欠席したことのある者については,インフルエンザにより欠席したものと見なして算出した。」
そう、同じ報告書の中でもインフルエンザ感染者として認定する基準が異なるのです。
ホントに読んでいて頭にくるレポートです!
しかもこの節の抗体価の調査結果では、以下のような結論になっています。
「小学校の欠席率が5%を越えるような,誰にでもかなりの流行として感じられる中規模以上の流行でも,感染者は欠席者の60%〜70%を占めるに過ぎない。小規模ないしはだらだらとした流行の場合には,その割合はさらに小さくなる。」
これをふまえ、4「総括と考按」の4節「インフルエンザ流行とHI抗体」では、次にように結論付けられています。
http://www.kangaeroo.net/D-maebashi-F-view-no-24.html
「流行時の欠席者のうち,インフルエンザ感染者は概ね60〜70%であり,逆にインフルエンザに感染していても欠席しない者すなわち「不顕性感染者」が全体の20%前後を占めることであった」
この結果は、直前の節「3) 欠席率によって見たワクチン効果」での考察が全く無意味であることを定量的に立証しています。
このレポートへの「欠席者の中にはインフルエンザ患者だけじゃなくただの風邪の人も混じっている」という批判への有効な反論は、その割合が実際にどの程度かを示すことです。
例えばこれが、別の調査では欠席者の中で80〜90%がインフルエンザ患者だった、というような具合に具体的な数値を定量的に示しているならまだ説得力がありますが、実際にはこの同じレポート内ではもっと低い結果が出ているのだから、全くお話になりません。
それがわかっているにもかかわらず、へ理屈をこねながら欠席者=インフルエンザ感染者、と固守し続けるのは、真理の追及に向けた誠実な態度とはとても思えません。
と、文句ばかり言っていても生産的ではないので、手を動かしながらもう少し深く考えてみます。
(なお、色々へ理屈をこねている部分については、最後にメッタ斬りにします)
3)欠席者の中のインフルエンザ患者の割合の推計
さて、今までのまとめです
1) インフルエンザの中規模の流行中、一回でも欠席したことのある児童のうち、一冬明けてみてインフルエンザの抗体を確保していた者は60〜70%
2) 小規模の流行も合わせると、インフルエンザの罹患率は減る
(ただし全数がわからないので、どれだけ減るかは不明)
3) 3.C節の基準に合わせ、3.D節から1日だけ休んだ児童などを除外すると、インフルエンザの罹患率は増える
(ただしこの統計を取ってないため、どれだけ増えるかはわからない)
さてわたしはこの1)で、「前橋レポート」での表現とは異なる、慎重な表現を取りました。
インフルエンザの中規模の流行中に欠席しなかった児童の中でも、インフルエンザ不顕性感染者が全体の20%いる、という事実を思い出しましょう。
この抗体価を測定しているのは、冬が明け春になってからです。
インフルエンザの流行が終わってすぐ、ではありません。
では、インフルエンザの中規模の流行中、インフルエンザではなくただの風邪にかかって学校を休んだが、この流行期間以外にインフルエンザに感染(あるいは不顕性感染)したため冬の間で抗体を確保していた、こういった児童はどこに含まれるでしょう?
答えは、この60〜70%の中です。
よく考えれば当たり前ですが、冬が明けてから抗体価が上昇していたというだけでは、インフルエンザの流行期間中に休んだからと言ってこの時期にインフルエンザに感染したとは限らない、ということです。
インフルエンザの抗体価の測定方法としてHI法を採用した限界がここに現れています。
当時は迅速にインフルエンザの判断ができるキットがなかった、またコスト的な制限があった、ということは理解できるにしても、本当に読んでいてイライラしてくるレポートです!
では、インフルエンザの中規模の流行期間中ただの風邪で学校を休んだが他の期間にインフルエンザに感染または不顕性感染した児童(書いててホント長いな)はどのくらいの割合なのか?
インフルエンザの中規模の流行中でも他の期間でもその割合は変わらないと仮定し、この流行期間中休まなかった者の中の割合を見てみますと、その数値は、以下の表15によると20%〜40%(右から2番目の項目)と、非常にばらつきがあります。
http://www.kangaeroo.net/data/maebashi/image/1t15.gif
なお、一番右側の「感染したが欠席しなかった者の率(不顕性感染者率)」の数値ですが、これは正確には、分母は、「感染者」=「一冬の間に抗体を確保した者」、分子は、流行期間外にインフルエンザに感染して休んだ者及び一冬を通していつかはわからないけど不顕性感染した者、です。
なので、あまり意味のある数字ではないでしょう。
なお補足ですが、この抗体価の測定は、ワクチンの接種を行っていない、前橋市内の小学校5校を対象にしています。
ここで、他のワクチンの接種を行っている市の小学校も対象にしていれば。。。と考えると、大変に悔やまれます。
(もうこのデザインの失敗だけでも、本当に、トヨタ財団の金をドブに捨てたようなものです!)
さて、今までのまとめです
1) インフルエンザの中規模の流行中、一回でも欠席したことのある児童のうち、一冬明けてみてインフルエンザの抗体を確保していた者は60〜70%
2) 小規模の流行も合わせると、インフルエンザの罹患率は減る
(ただし全数がわからないので、どれだけ減るかは不明)
3) 3.C節の基準に合わせ、3.D節から1日だけ休んだ児童などを除外すると、インフルエンザの罹患率は増える
(ただしこの統計を取ってないため、どれだけ増えるかはわからない)
さてわたしはこの1)で、「前橋レポート」での表現とは異なる、慎重な表現を取りました。
インフルエンザの中規模の流行中に欠席しなかった児童の中でも、インフルエンザ不顕性感染者が全体の20%いる、という事実を思い出しましょう。
この抗体価を測定しているのは、冬が明け春になってからです。
インフルエンザの流行が終わってすぐ、ではありません。
では、インフルエンザの中規模の流行中、インフルエンザではなくただの風邪にかかって学校を休んだが、この流行期間以外にインフルエンザに感染(あるいは不顕性感染)したため冬の間で抗体を確保していた、こういった児童はどこに含まれるでしょう?
答えは、この60〜70%の中です。
よく考えれば当たり前ですが、冬が明けてから抗体価が上昇していたというだけでは、インフルエンザの流行期間中に休んだからと言ってこの時期にインフルエンザに感染したとは限らない、ということです。
インフルエンザの抗体価の測定方法としてHI法を採用した限界がここに現れています。
当時は迅速にインフルエンザの判断ができるキットがなかった、またコスト的な制限があった、ということは理解できるにしても、本当に読んでいてイライラしてくるレポートです!
では、インフルエンザの中規模の流行期間中ただの風邪で学校を休んだが他の期間にインフルエンザに感染または不顕性感染した児童(書いててホント長いな)はどのくらいの割合なのか?
インフルエンザの中規模の流行中でも他の期間でもその割合は変わらないと仮定し、この流行期間中休まなかった者の中の割合を見てみますと、その数値は、以下の表15によると20%〜40%(右から2番目の項目)と、非常にばらつきがあります。
http://www.kangaeroo.net/data/maebashi/image/1t15.gif
なお、一番右側の「感染したが欠席しなかった者の率(不顕性感染者率)」の数値ですが、これは正確には、分母は、「感染者」=「一冬の間に抗体を確保した者」、分子は、流行期間外にインフルエンザに感染して休んだ者及び一冬を通していつかはわからないけど不顕性感染した者、です。
なので、あまり意味のある数字ではないでしょう。
なお補足ですが、この抗体価の測定は、ワクチンの接種を行っていない、前橋市内の小学校5校を対象にしています。
ここで、他のワクチンの接種を行っている市の小学校も対象にしていれば。。。と考えると、大変に悔やまれます。
(もうこのデザインの失敗だけでも、本当に、トヨタ財団の金をドブに捨てたようなものです!)
4) 欠席者の中のインフルエンザ患者の割合の推計とワクチンの有効率
これまでのまとめです。
1) インフルエンザの中規模の流行中、一回でも欠席したことのある児童のうち、一冬明けてみてインフルエンザの抗体を確保していた者は60〜70%
2) 小規模の流行も合わせると、インフルエンザの罹患率は減る
(ただし全数がわからないので、どれだけ減るかは不明)
3) 3.C節の基準に合わせ、3.D節の感染者から1日だけ休んだ児童(ただの風邪と思われる)を除外すると、インフルエンザの罹患率は増える
(ただしこの統計を取ってないため、どれだけ増えるかは不明)
4) 1)の中には、この期間中にインフルエンザではなくただの風邪で欠席したが、他の期間中にインフルエンザに感染して抗体を確保した者も含まれる。
ちなみに非欠席者の中で不顕性感染した者の割合は、20%〜40%になる。
以上の3.D節の抗体価の調査の結果をふまえ、3.C節の欠席者の中のインフルエンザ患者の割合を推定しましょう。
2)と3)の効果は、この材料から言えることは定性的なものだけで定量的な評価は全くわからないので、この両方でキャンセルされる、とします。
ではトータルとして、前橋市の欠席者の中で、実際にインフルエンザに感染した人の割合はどのくらいか?
1)を高め(70%を採用)、4)を低め(20%を採用)、に取ると、55%程度
1)を低め(60%を採用)、4)を高め(40%を採用)、に取ると、35%程度
本当に幅があってさっぱりわかりません!
推計に推計を重ねているのでしかたないです ^^
とりあえず、40%とか50%とか、そんなもののようです。
また前橋市以外の市に関しても、この比率はそう大きくは変わらないと仮定します。
また、インフルエンザワクチンを接種した人もしない人も、インフルエンザウイルス以外が原因となっている、インフルエンザと似た病気の罹患率は変わらない、と仮定します。
以上の条件を以下の3.C節・表11,12で示されている各小学校のインフルエンザの罹患率に修正を加えます。
http://www.kangaeroo.net/data/maebashi/image/1t11.gif
例として、1984年の高崎市について、欠席者の中で実際にインフルエンザウイルスに感染している者の割合が40%の条件での計算方法を説明します。
非接種群の欠席率(表で言う「罹患率」)は53.9%、本当のインフルエンザの罹患率は全体の21.6%、インフルエンザによく似たその他の病気は32.3%です。
その他の病気の罹患率は、ワクチンを一回打っても二回打っても変わらない、という条件を入れていますので、一回接種群の欠席率(表で言う「罹患率」)の45.9%から、その他の病気の32.3%を引きますと、一回接種群のインフルエンザの罹患率は13.6%。
同様に、二回接種群の欠席率(表で言う「罹患率」)の38.3%から、その他の病気の37.7%を引きますと、一回接種群のインフルエンザの罹患率は6.0%。
6.0/21.6 = 27.8%、ですので、ワクチンの有効率は7割以上と言えそうです。
ただし!
統計学上、本来はこういう操作を行う際は注意が必要です。
ここで求めたインフルエンザの罹患率自体、相当な幅を持った数値です。
かなり誤差が大きい、とも表現できます。
これをお互いに足したり引いたりすると、誤差の分を考慮しないと、色々とおかしなことになります。
例えばこの計算方法で、欠席者中のインフルエンザの罹患率を30%と仮定して計算すると\
、ワクチンを接種した場合のインフルエンザの罹患率がマイナスというおかしな数値が出てしまいます。
ワクチンを接種した場合のインフルエンザの罹患率を正確に知りたい場合、その精度は、ここで行った欠席者中のインフルエンザの罹患率の見積りの精度より高い必要がある、ということです。
これまでのまとめです。
1) インフルエンザの中規模の流行中、一回でも欠席したことのある児童のうち、一冬明けてみてインフルエンザの抗体を確保していた者は60〜70%
2) 小規模の流行も合わせると、インフルエンザの罹患率は減る
(ただし全数がわからないので、どれだけ減るかは不明)
3) 3.C節の基準に合わせ、3.D節の感染者から1日だけ休んだ児童(ただの風邪と思われる)を除外すると、インフルエンザの罹患率は増える
(ただしこの統計を取ってないため、どれだけ増えるかは不明)
4) 1)の中には、この期間中にインフルエンザではなくただの風邪で欠席したが、他の期間中にインフルエンザに感染して抗体を確保した者も含まれる。
ちなみに非欠席者の中で不顕性感染した者の割合は、20%〜40%になる。
以上の3.D節の抗体価の調査の結果をふまえ、3.C節の欠席者の中のインフルエンザ患者の割合を推定しましょう。
2)と3)の効果は、この材料から言えることは定性的なものだけで定量的な評価は全くわからないので、この両方でキャンセルされる、とします。
ではトータルとして、前橋市の欠席者の中で、実際にインフルエンザに感染した人の割合はどのくらいか?
1)を高め(70%を採用)、4)を低め(20%を採用)、に取ると、55%程度
1)を低め(60%を採用)、4)を高め(40%を採用)、に取ると、35%程度
本当に幅があってさっぱりわかりません!
推計に推計を重ねているのでしかたないです ^^
とりあえず、40%とか50%とか、そんなもののようです。
また前橋市以外の市に関しても、この比率はそう大きくは変わらないと仮定します。
また、インフルエンザワクチンを接種した人もしない人も、インフルエンザウイルス以外が原因となっている、インフルエンザと似た病気の罹患率は変わらない、と仮定します。
以上の条件を以下の3.C節・表11,12で示されている各小学校のインフルエンザの罹患率に修正を加えます。
http://www.kangaeroo.net/data/maebashi/image/1t11.gif
例として、1984年の高崎市について、欠席者の中で実際にインフルエンザウイルスに感染している者の割合が40%の条件での計算方法を説明します。
非接種群の欠席率(表で言う「罹患率」)は53.9%、本当のインフルエンザの罹患率は全体の21.6%、インフルエンザによく似たその他の病気は32.3%です。
その他の病気の罹患率は、ワクチンを一回打っても二回打っても変わらない、という条件を入れていますので、一回接種群の欠席率(表で言う「罹患率」)の45.9%から、その他の病気の32.3%を引きますと、一回接種群のインフルエンザの罹患率は13.6%。
同様に、二回接種群の欠席率(表で言う「罹患率」)の38.3%から、その他の病気の37.7%を引きますと、一回接種群のインフルエンザの罹患率は6.0%。
6.0/21.6 = 27.8%、ですので、ワクチンの有効率は7割以上と言えそうです。
ただし!
統計学上、本来はこういう操作を行う際は注意が必要です。
ここで求めたインフルエンザの罹患率自体、相当な幅を持った数値です。
かなり誤差が大きい、とも表現できます。
これをお互いに足したり引いたりすると、誤差の分を考慮しないと、色々とおかしなことになります。
例えばこの計算方法で、欠席者中のインフルエンザの罹患率を30%と仮定して計算すると\
、ワクチンを接種した場合のインフルエンザの罹患率がマイナスというおかしな数値が出てしまいます。
ワクチンを接種した場合のインフルエンザの罹患率を正確に知りたい場合、その精度は、ここで行った欠席者中のインフルエンザの罹患率の見積りの精度より高い必要がある、ということです。
4a) 欠席者中のインフルエンザの罹患率を40%と仮定した修正ワクチン効果
前橋市 1984年
ワクチン接種 0回
欠席率 42.8%
その他罹患率 25.7%
インフル罹患率 17.1%
高崎市 1984年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 53.9% 45.9% 38.3%
その他罹患率 32.3% 32.3% 32.3%
インフル罹患率 21.6% 13.6% 6.0% 有効率 72.2%
桐生市 1984年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 51.8% 44.8% 39.2%
その他罹患率 31.1% 31.1% 31.1%
インフル罹患率 20.7% 13.7% 8.1% 有効率 60.9%
伊勢崎市 1984年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 58.4% 52.7% 49.1%
その他罹患率 35.0% 35.0% 35.0%
インフル罹患率 23.4% 17.7% 14.1% 有効率 39.8%
前橋市 1985年
ワクチン接種 0回
欠席率 27.7%
その他罹患率 16.6%
インフル罹患率 11.1%
高崎市 1985年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 30.9% 30.4% 18.6%
その他罹患率 18.5% 18.5% 18.5%
インフル罹患率 12.4% 11.9% 0.1% 有効率 99.2%
桐生市 1985年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 32.2% 23.5% 22.8%
その他罹患率 19.3% 19.3% 19.3%
インフル罹患率 12.9% 4.2% 3.5% 有効率 72.9%
伊勢崎市 1985年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 35.9% 34.7% 23.1%
その他罹患率 21.5% 21.5% 21.5%
インフル罹患率 14.4% 13.2% 1.6% 有効率 88.9%
前橋市 1984年
ワクチン接種 0回
欠席率 42.8%
その他罹患率 25.7%
インフル罹患率 17.1%
高崎市 1984年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 53.9% 45.9% 38.3%
その他罹患率 32.3% 32.3% 32.3%
インフル罹患率 21.6% 13.6% 6.0% 有効率 72.2%
桐生市 1984年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 51.8% 44.8% 39.2%
その他罹患率 31.1% 31.1% 31.1%
インフル罹患率 20.7% 13.7% 8.1% 有効率 60.9%
伊勢崎市 1984年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 58.4% 52.7% 49.1%
その他罹患率 35.0% 35.0% 35.0%
インフル罹患率 23.4% 17.7% 14.1% 有効率 39.8%
前橋市 1985年
ワクチン接種 0回
欠席率 27.7%
その他罹患率 16.6%
インフル罹患率 11.1%
高崎市 1985年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 30.9% 30.4% 18.6%
その他罹患率 18.5% 18.5% 18.5%
インフル罹患率 12.4% 11.9% 0.1% 有効率 99.2%
桐生市 1985年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 32.2% 23.5% 22.8%
その他罹患率 19.3% 19.3% 19.3%
インフル罹患率 12.9% 4.2% 3.5% 有効率 72.9%
伊勢崎市 1985年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 35.9% 34.7% 23.1%
その他罹患率 21.5% 21.5% 21.5%
インフル罹患率 14.4% 13.2% 1.6% 有効率 88.9%
4b) 欠席者中のインフルエンザの罹患率を50%と仮定した修正ワクチン効果
前橋市 1984年
ワクチン接種 0回
欠席率 42.8%
その他罹患率 21.4%
インフル罹患率 21.4%
高崎市 1984年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 53.9% 45.9% 38.3%
その他罹患率 27.0% 27.0% 27.0%
インフル罹患率 27.0% 18.9% 11.3% 有効率 58.2%
桐生市 1984年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 51.8% 44.8% 39.2%
その他罹患率 25.9% 25.9% 25.9%
インフル罹患率 25.9% 18.9% 13.3% 有効率 48.6%
伊勢崎市 1984年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 58.4% 52.7% 49.1%
その他罹患率 29.2% 29.2% 29.2%
インフル罹患率 29.2% 23.5% 19.9% 有効率 31.8%
前橋市 1985年
ワクチン接種 0回
欠席率 27.7%
その他罹患率 13.9%
インフル罹患率 13.9%
高崎市 1985年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 30.9% 30.4% 18.6%
その他罹患率 15.5% 15.5% 15.5%
インフル罹患率 15.5% 14.9% 3.1% 有効率 80.0%
桐生市 1985年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 32.2% 23.5% 22.8%
その他罹患率 16.1% 16.1% 16.1%
インフル罹患率 16.1% 7.4% 6.7% 有効率 58.4%
伊勢崎市 1985年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 35.9% 34.7% 23.1%
その他罹患率 18.0% 18.0% 18.0%
インフル罹患率 18.0% 16.7% 5.1% 有効率 71.7%
前橋市 1984年
ワクチン接種 0回
欠席率 42.8%
その他罹患率 21.4%
インフル罹患率 21.4%
高崎市 1984年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 53.9% 45.9% 38.3%
その他罹患率 27.0% 27.0% 27.0%
インフル罹患率 27.0% 18.9% 11.3% 有効率 58.2%
桐生市 1984年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 51.8% 44.8% 39.2%
その他罹患率 25.9% 25.9% 25.9%
インフル罹患率 25.9% 18.9% 13.3% 有効率 48.6%
伊勢崎市 1984年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 58.4% 52.7% 49.1%
その他罹患率 29.2% 29.2% 29.2%
インフル罹患率 29.2% 23.5% 19.9% 有効率 31.8%
前橋市 1985年
ワクチン接種 0回
欠席率 27.7%
その他罹患率 13.9%
インフル罹患率 13.9%
高崎市 1985年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 30.9% 30.4% 18.6%
その他罹患率 15.5% 15.5% 15.5%
インフル罹患率 15.5% 14.9% 3.1% 有効率 80.0%
桐生市 1985年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 32.2% 23.5% 22.8%
その他罹患率 16.1% 16.1% 16.1%
インフル罹患率 16.1% 7.4% 6.7% 有効率 58.4%
伊勢崎市 1985年
ワクチン接種 0回 1回 2回
欠席率 35.9% 34.7% 23.1%
その他罹患率 18.0% 18.0% 18.0%
インフル罹患率 18.0% 16.7% 5.1% 有効率 71.7%
5)結論
前橋レポートの中では、各小学校でインフルエンザにより欠席した児童数を数える際、インフルエンザだけでなくただの風邪で休んだ児童も区別せずに一緒に数え上げてしまう調査方法を取ってしまった。
このレポートの中でもその問題点については触れられてはいるが、具体的に何割程度の混入があるかの議論はなされていない。
そこで、このレポートの中で行われている抗体価の調査内容を詳しく考察し、この結果から推測してみると、欠席児童の中で実際にインフルエンザに感染している者の割合は35%〜55%程度であろうと考えられる。
この割合は前橋市以外でもそう変わらないと仮定して、ワクチン接種を行った各小学校の欠席者から実際のインフルエンザ患者の割合を修正して計算しなおしてみると、概ねワクチンの有効率は7割以上の成績であるという結果が得られた。
これは、インフルエンザワクチンの効果は7割以上という当時の厚生省の見解と矛盾しない。
よって前橋レポートの調査結果は、インフルエンザワクチンの有効性を強く示唆するものであると考えられる。
前橋レポートの中では、各小学校でインフルエンザにより欠席した児童数を数える際、インフルエンザだけでなくただの風邪で休んだ児童も区別せずに一緒に数え上げてしまう調査方法を取ってしまった。
このレポートの中でもその問題点については触れられてはいるが、具体的に何割程度の混入があるかの議論はなされていない。
そこで、このレポートの中で行われている抗体価の調査内容を詳しく考察し、この結果から推測してみると、欠席児童の中で実際にインフルエンザに感染している者の割合は35%〜55%程度であろうと考えられる。
この割合は前橋市以外でもそう変わらないと仮定して、ワクチン接種を行った各小学校の欠席者から実際のインフルエンザ患者の割合を修正して計算しなおしてみると、概ねワクチンの有効率は7割以上の成績であるという結果が得られた。
これは、インフルエンザワクチンの効果は7割以上という当時の厚生省の見解と矛盾しない。
よって前橋レポートの調査結果は、インフルエンザワクチンの有効性を強く示唆するものであると考えられる。
6) 考察
さていよいよお楽しみの時間です。
6a) なぜ前橋市の欠席率は低いのか?
もう一度、3.C節の表11, 12のデータを検討してみます。
http://www.kangaeroo.net/data/maebashi/image/1t11.gif
(ただし、ここにある罹患者数、罹患率とは、実際にはインフルエンザだけでなくただの風邪などで休んだものも相当数の割合で含まれている)
非接種群を比較してみますと、他の予防接種を続けた市と比べて、ワクチンの集団接種が行われていないのにもかかわらず前橋市の欠席率が低い、ということは確かに言えます。
これはどうしてか?
色々考えたのですが、逆説的ですが、前橋市だけが集団接種を中止してしまったため、ではないかと思いました。
なんじゃそりゃ?、因果関係としては逆効果じゃないの? と、説明が必要ですね ^^;;;
前橋市に住んでいる人の立場になってみて、去年まで行っていたインフルエンザの集団接種を今年から辞めます、と言われたらどう考えるか。
他の市では続けているのに、うちだけ辞めてしまって大丈夫なの?
副作用も恐いけど、インフルエンザにかかってしまったらどうしよう、と不安になりますね。
となると自衛策として、自分でできる予防に力を入れるのではないでしょうか。
具体的には例えば、外出から帰ってきた際には手洗いやうがいを徹底する、外を歩く時は乾燥を防ぐためマスクをする、空気の悪い場所や人ごみの中に居ることはなるべく避ける、など。
これらはインフルエンザの予防としてある程度は有効ですし、もちろん風邪の予防にもつながります。
インフルエンザの予防接種を辞めました、そうしたらインフルエンザが大流行してしまいました、これでは前橋市医師会としては全国に恥をさらすだけです。
なので、医師会あるいは学校が、手洗いやうがいの励行などの予防の指導に盛んに取り組んだ、そういう事実があったに違いないと思うのですが。
もしそういったワクチン接種以外での積極的な予防への取り組みがあったとすると、この前橋市のデータはこのままでは単純に比較できないことになってしまいます。
インフルエンザワクチンの接種をしたかしないか、のパラメーターの他に、手洗いやうがいの励行などの予防を徹底させた、という別のパラメーターも動かしてしまってるのですから、いったい何の効果を調べているのかわからなくなるためです。
このあたりが、医療と科学の違い、とも言えます。
医療として見たらどんな方法であれ病気の人が減ったのであれば結果オーライ、ですが、科学として見たら何の措置を行うとどの程度の効果が望めるのか、定量的な評価ができなくなってしまいます。
このあたり、ケチばかりつけていても建設的ではないので、もうちょっと医療寄りに歩み寄った別の角度から見てみましょう。
例えば、手洗いやうがいの励行の徹底でも、インフルエンザワクチンと同じ程度の予防効果が見られた、これを実証するのも十分な科学と言えるのです。
これを立証するためには、ワクチン接種の有無の他に、手洗いうがいの励行をしたかしないか、という独立した別のパラメーターの軸を設けて比較すればいいだけの話です。
具体的には、前橋市及び他の市の児童を、アンケート調査により以下の4つのグループに分けます。
ワクチンを打たず、手洗いうがいもしなかった群(←コントロール群)
ワクチンを打たず、手洗いうがいをした群
ワクチンを打ち、手洗いうがいをしなかった群
ワクチンを打ち、手洗いうがいをした群
このグループ同士で風邪やインフルエンザの罹患率を比較してみますと、おそらく最後の群が、最も罹患率が低くなると思われます。
また、同じ調査をインフルエンザではなく他の感染症、例えばはしかで行ってみると、手洗いやうがいでは予防できない、という結果が得られると思われます。
さていよいよお楽しみの時間です。
6a) なぜ前橋市の欠席率は低いのか?
もう一度、3.C節の表11, 12のデータを検討してみます。
http://www.kangaeroo.net/data/maebashi/image/1t11.gif
(ただし、ここにある罹患者数、罹患率とは、実際にはインフルエンザだけでなくただの風邪などで休んだものも相当数の割合で含まれている)
非接種群を比較してみますと、他の予防接種を続けた市と比べて、ワクチンの集団接種が行われていないのにもかかわらず前橋市の欠席率が低い、ということは確かに言えます。
これはどうしてか?
色々考えたのですが、逆説的ですが、前橋市だけが集団接種を中止してしまったため、ではないかと思いました。
なんじゃそりゃ?、因果関係としては逆効果じゃないの? と、説明が必要ですね ^^;;;
前橋市に住んでいる人の立場になってみて、去年まで行っていたインフルエンザの集団接種を今年から辞めます、と言われたらどう考えるか。
他の市では続けているのに、うちだけ辞めてしまって大丈夫なの?
副作用も恐いけど、インフルエンザにかかってしまったらどうしよう、と不安になりますね。
となると自衛策として、自分でできる予防に力を入れるのではないでしょうか。
具体的には例えば、外出から帰ってきた際には手洗いやうがいを徹底する、外を歩く時は乾燥を防ぐためマスクをする、空気の悪い場所や人ごみの中に居ることはなるべく避ける、など。
これらはインフルエンザの予防としてある程度は有効ですし、もちろん風邪の予防にもつながります。
インフルエンザの予防接種を辞めました、そうしたらインフルエンザが大流行してしまいました、これでは前橋市医師会としては全国に恥をさらすだけです。
なので、医師会あるいは学校が、手洗いやうがいの励行などの予防の指導に盛んに取り組んだ、そういう事実があったに違いないと思うのですが。
もしそういったワクチン接種以外での積極的な予防への取り組みがあったとすると、この前橋市のデータはこのままでは単純に比較できないことになってしまいます。
インフルエンザワクチンの接種をしたかしないか、のパラメーターの他に、手洗いやうがいの励行などの予防を徹底させた、という別のパラメーターも動かしてしまってるのですから、いったい何の効果を調べているのかわからなくなるためです。
このあたりが、医療と科学の違い、とも言えます。
医療として見たらどんな方法であれ病気の人が減ったのであれば結果オーライ、ですが、科学として見たら何の措置を行うとどの程度の効果が望めるのか、定量的な評価ができなくなってしまいます。
このあたり、ケチばかりつけていても建設的ではないので、もうちょっと医療寄りに歩み寄った別の角度から見てみましょう。
例えば、手洗いやうがいの励行の徹底でも、インフルエンザワクチンと同じ程度の予防効果が見られた、これを実証するのも十分な科学と言えるのです。
これを立証するためには、ワクチン接種の有無の他に、手洗いうがいの励行をしたかしないか、という独立した別のパラメーターの軸を設けて比較すればいいだけの話です。
具体的には、前橋市及び他の市の児童を、アンケート調査により以下の4つのグループに分けます。
ワクチンを打たず、手洗いうがいもしなかった群(←コントロール群)
ワクチンを打たず、手洗いうがいをした群
ワクチンを打ち、手洗いうがいをしなかった群
ワクチンを打ち、手洗いうがいをした群
このグループ同士で風邪やインフルエンザの罹患率を比較してみますと、おそらく最後の群が、最も罹患率が低くなると思われます。
また、同じ調査をインフルエンザではなく他の感染症、例えばはしかで行ってみると、手洗いやうがいでは予防できない、という結果が得られると思われます。
あ、どうも放置状態ですみません(実はまだ続きはあるのですが、反響が芳しくなかったので。。。)
行政の事情はわたしにはわかりませんが、とりあえず国の言い分としては以下のような感じだそうです。
ここで言われている、「必ずしも科学的評価に耐えられない多くの野外試験の成績と誤った解釈」が、具体的には前橋レポートのことを指すことは明らかでしょうね。
マスコミがワクチン反対団体のことを持ち上げて大騒ぎになってしまったため、ワクチンを受けるかどうかは個人の責任に転換させてようやく収拾させた、とぼくは解釈しています。
逆に言えば、国としては今まで通り予防接種のプログラムを用意はするけど、それを受けないで病気になった人がいたとしても、それは各国民自身の責任であって国としては責任持たないよ、ということでしょうが。
http://www.nih.go.jp/niid/topics/influenza01.html
5.インフルエンザワクチン集団接種方式に対する見直しの経緯
一方、我が国における学童生徒の集団接種方式を巡って、科学的ないし社会的な面から様々な議論がありました。社会全体のインフルエンザ流行を防ぐために学童生徒全員にワクチン接種を強制するのは人権問題であるとの批判、また学童生徒全員にワクチン接種しても社会におけるインフルエンザの流行は制圧されていないとの批判など、ワクチンの接種目的、接種対象、接種方式に対する様々な批判が起こってきました。また必ずしも科学的評価に耐えられない多くの野外試験の成績と誤った解釈によるワクチン無効論が唱えられ、まれに起こる重篤な副作用に対する行政対応が必ずしも適切ではなかったことが強調され、更にそれらに基づく様々な誤解から生じたインフルエンザワクチン全体に対する不信感がマスメディア等によって増幅されました。その結果、1980年代後半からワクチン摂取率が急激に低下していきました。
これらの批判とは別に、80年代後半には、インフルエンザなどの感染症は本人の責任で防止に努めるべきであるという個人防衛の考え方が起こってきました。1994年の予防接種法の改正に際しては基本的にこの考え方が導入され、インフルエンザワクチンは法律に基づく臨時の定期接種からはずされて任意接種になりました。この結論に至った経緯や議論に関する説明が報道等で十分なされなかったためハイリスク群に対するワクチン接種の意義などの情報も少なく、「国がインフルエンザワクチンは無効であることを認めたので、従来の強制集団接種方式を廃止した」との誤解が生じました。そのためワクチン接種を受ける人は極端に減ってきています。これは、WHOをはじめ世界各国のワクチン政策とは完全に逆行するものであり、近く出現が予想される新型インフルエンザ大流行への対策を検討する上でも大きな問題となっています。
行政の事情はわたしにはわかりませんが、とりあえず国の言い分としては以下のような感じだそうです。
ここで言われている、「必ずしも科学的評価に耐えられない多くの野外試験の成績と誤った解釈」が、具体的には前橋レポートのことを指すことは明らかでしょうね。
マスコミがワクチン反対団体のことを持ち上げて大騒ぎになってしまったため、ワクチンを受けるかどうかは個人の責任に転換させてようやく収拾させた、とぼくは解釈しています。
逆に言えば、国としては今まで通り予防接種のプログラムを用意はするけど、それを受けないで病気になった人がいたとしても、それは各国民自身の責任であって国としては責任持たないよ、ということでしょうが。
http://www.nih.go.jp/niid/topics/influenza01.html
5.インフルエンザワクチン集団接種方式に対する見直しの経緯
一方、我が国における学童生徒の集団接種方式を巡って、科学的ないし社会的な面から様々な議論がありました。社会全体のインフルエンザ流行を防ぐために学童生徒全員にワクチン接種を強制するのは人権問題であるとの批判、また学童生徒全員にワクチン接種しても社会におけるインフルエンザの流行は制圧されていないとの批判など、ワクチンの接種目的、接種対象、接種方式に対する様々な批判が起こってきました。また必ずしも科学的評価に耐えられない多くの野外試験の成績と誤った解釈によるワクチン無効論が唱えられ、まれに起こる重篤な副作用に対する行政対応が必ずしも適切ではなかったことが強調され、更にそれらに基づく様々な誤解から生じたインフルエンザワクチン全体に対する不信感がマスメディア等によって増幅されました。その結果、1980年代後半からワクチン摂取率が急激に低下していきました。
これらの批判とは別に、80年代後半には、インフルエンザなどの感染症は本人の責任で防止に努めるべきであるという個人防衛の考え方が起こってきました。1994年の予防接種法の改正に際しては基本的にこの考え方が導入され、インフルエンザワクチンは法律に基づく臨時の定期接種からはずされて任意接種になりました。この結論に至った経緯や議論に関する説明が報道等で十分なされなかったためハイリスク群に対するワクチン接種の意義などの情報も少なく、「国がインフルエンザワクチンは無効であることを認めたので、従来の強制集団接種方式を廃止した」との誤解が生じました。そのためワクチン接種を受ける人は極端に減ってきています。これは、WHOをはじめ世界各国のワクチン政策とは完全に逆行するものであり、近く出現が予想される新型インフルエンザ大流行への対策を検討する上でも大きな問題となっています。
13: サプリの口下手店長様
> 日本臨床内科医会では、「65歳以上には効き目がない」
> 日本小児科学会では、「★1歳未満については有効性が認められない、★1歳以上6歳未満児については、発熱を指標とした有効率は20-30%」
ソースを知りたいので、お持ちでしたら示していただけますか?
ワクチンそのものが個人にもたらす有効性とは少し異なりますが、最近ではこのような観点からの報告もあります。
The Japanese experience with vaccinating schoolchildren against influenza.
N Engl J Med. 2001 Mar 22;344(12):889-96
http://content.nejm.org/cgi/content/full/344/12/889
人口動態統計をもとに、学童に対して集団接種が行われていた期間、インフルエンザおよび肺炎による超過死亡が有意に少なかったことを示した報告です。
> 日本臨床内科医会では、「65歳以上には効き目がない」
> 日本小児科学会では、「★1歳未満については有効性が認められない、★1歳以上6歳未満児については、発熱を指標とした有効率は20-30%」
ソースを知りたいので、お持ちでしたら示していただけますか?
ワクチンそのものが個人にもたらす有効性とは少し異なりますが、最近ではこのような観点からの報告もあります。
The Japanese experience with vaccinating schoolchildren against influenza.
N Engl J Med. 2001 Mar 22;344(12):889-96
http://content.nejm.org/cgi/content/full/344/12/889
人口動態統計をもとに、学童に対して集団接種が行われていた期間、インフルエンザおよび肺炎による超過死亡が有意に少なかったことを示した報告です。
えー、それなりに反響があったようなので、週末に時間があれば続きを。
これから「前橋レポート」読み返して、書こうとしてた内容復習しなきゃ ^^;;;
で、実は自分の論文抱えていてあまり専門外の論文サーベイしてる時間ないのですが、前にどっかに書いた覚えがあったと思ったらここでした。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=23322214&comm_id=1898250&page=all
これの、2と15の後半のほう。再度紹介しますが、
感染症学雑誌 Vol.76 (2002) p.9
インフルエンザワクチンの過去,現在,未来
菅谷 憲夫
要旨は↓こちら
http://journal.kansensho.or.jp/Disp?style=abst&vol=76&mag=0&number=1&start=9
全文は↓こちら
http://journal.kansensho.or.jp/Disp?pdf=0760010009.pdf
「信用にたる」かどうかは主観的な観点も入るのでなんとも言えませんが、色々な疫学調査はここで紹介されてます。
てくすさんの紹介されている文献は、この著者が共著者として名を連ねているもので、4)の引用文献として載ってますね。
これから「前橋レポート」読み返して、書こうとしてた内容復習しなきゃ ^^;;;
で、実は自分の論文抱えていてあまり専門外の論文サーベイしてる時間ないのですが、前にどっかに書いた覚えがあったと思ったらここでした。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=23322214&comm_id=1898250&page=all
これの、2と15の後半のほう。再度紹介しますが、
感染症学雑誌 Vol.76 (2002) p.9
インフルエンザワクチンの過去,現在,未来
菅谷 憲夫
要旨は↓こちら
http://journal.kansensho.or.jp/Disp?style=abst&vol=76&mag=0&number=1&start=9
全文は↓こちら
http://journal.kansensho.or.jp/Disp?pdf=0760010009.pdf
「信用にたる」かどうかは主観的な観点も入るのでなんとも言えませんが、色々な疫学調査はここで紹介されてます。
てくすさんの紹介されている文献は、この著者が共著者として名を連ねているもので、4)の引用文献として載ってますね。
14>> てくすさん、張り付けずに失礼いたしました。
日本臨床内科医会HPです。
http://www.info.pmda.go.jp/iyaku_anzen/PMDSI217d.html#chapter1
6、インフルエンザの予防〈ワクチンの効果〉に、「65歳以上では、効果がみられませんでした。」はこちら
http://japha.umin.jp/influenza/index05.htm
グラフ
http://japha.umin.jp/influenza/zu0412.htm#009
乳幼児(6歳未満)に対するインフルエンザワクチン接種について(日本小児科学会)はこちらです。
http://www.jpeds.or.jp/saisin.html#75
リライトになりますが、本日のブログにインフルエンザワクチンについて、書きました。
ちなみに私は、「疑わしきは罰す(この例えはおかしいかな?)」の立場です。 ここでは、純粋に前橋レポートの統計としての正確さのみを、話題にするようにしていますが。
日本臨床内科医会HPです。
http://www.info.pmda.go.jp/iyaku_anzen/PMDSI217d.html#chapter1
6、インフルエンザの予防〈ワクチンの効果〉に、「65歳以上では、効果がみられませんでした。」はこちら
http://japha.umin.jp/influenza/index05.htm
グラフ
http://japha.umin.jp/influenza/zu0412.htm#009
乳幼児(6歳未満)に対するインフルエンザワクチン接種について(日本小児科学会)はこちらです。
http://www.jpeds.or.jp/saisin.html#75
リライトになりますが、本日のブログにインフルエンザワクチンについて、書きました。
ちなみに私は、「疑わしきは罰す(この例えはおかしいかな?)」の立場です。 ここでは、純粋に前橋レポートの統計としての正確さのみを、話題にするようにしていますが。
少し引用してみましょう。二重カッコは私が付けています。
-------------------------
さて、本会の調査によると、『ここ3年間のワクチンの効力』は徐々に下降し、昨季はワクチンを接種しない人のインフルエンザ罹患率は2.4%で、接種した人では1.7%でした(図-7)。有効率を調べてみますと、15歳以下では3年前は74.6%でしたが、昨シーズンは44.2%、16歳〜64歳では73.9%から40.3%に下降し(図-8)、65歳以上では効果は見られませんでした。つまり、現在使われているワクチンには予防効果はあるのですが、それでも罹る場合があるので、過信は禁物です。
これはウイルス流行株が『常に変異している』ためで、今シーズンはワクチンの株を流行株に合わせて組み替えられていますので、効果が上ることが期待できます。
-------------------------
一部だけ取り出して「臨床内科学会では65歳以上では効果がないと言っているので接種は無意味だ」という誤解をなさらぬよう。
-------------------------
さて、本会の調査によると、『ここ3年間のワクチンの効力』は徐々に下降し、昨季はワクチンを接種しない人のインフルエンザ罹患率は2.4%で、接種した人では1.7%でした(図-7)。有効率を調べてみますと、15歳以下では3年前は74.6%でしたが、昨シーズンは44.2%、16歳〜64歳では73.9%から40.3%に下降し(図-8)、65歳以上では効果は見られませんでした。つまり、現在使われているワクチンには予防効果はあるのですが、それでも罹る場合があるので、過信は禁物です。
これはウイルス流行株が『常に変異している』ためで、今シーズンはワクチンの株を流行株に合わせて組み替えられていますので、効果が上ることが期待できます。
-------------------------
一部だけ取り出して「臨床内科学会では65歳以上では効果がないと言っているので接種は無意味だ」という誤解をなさらぬよう。
この元の報告書は既に紹介しましたよね?
ここで言う「発熱を指標とした有効率は20-30%」とは、以下の表現が正確です。
インフルエンザワクチンを接種した子は、しなかった子に比べて、39度以上の熱を出す割合が20〜30%少ない。
ただしここで39度以上の熱というのは、インフルエンザの他に風邪なども含まれている。
おそらくこの調査では、ワクチンを打っていれば重症化が防げることを立証しようとしたんじゃないかと想像していますが、この条件だけから考えると、インフルエンザワクチンにはそれほどの効果はないが、健康なのにわざわざ子供にインフルエンザのワクチンを接種させる家庭は比較的裕福な傾向にあることがこの調査から立証されており、こういった家庭ではしつけも行き届いているため、普段からの手洗いうがいの励行も徹底されており、インフルエンザや風邪などの感染予防の効果として現れていることがこの調査結果から示唆される、という結論も成り立ってしまうんです。
これは明らかなデザイン上のミスです。
ここで言う「発熱を指標とした有効率は20-30%」とは、以下の表現が正確です。
インフルエンザワクチンを接種した子は、しなかった子に比べて、39度以上の熱を出す割合が20〜30%少ない。
ただしここで39度以上の熱というのは、インフルエンザの他に風邪なども含まれている。
おそらくこの調査では、ワクチンを打っていれば重症化が防げることを立証しようとしたんじゃないかと想像していますが、この条件だけから考えると、インフルエンザワクチンにはそれほどの効果はないが、健康なのにわざわざ子供にインフルエンザのワクチンを接種させる家庭は比較的裕福な傾向にあることがこの調査から立証されており、こういった家庭ではしつけも行き届いているため、普段からの手洗いうがいの励行も徹底されており、インフルエンザや風邪などの感染予防の効果として現れていることがこの調査結果から示唆される、という結論も成り立ってしまうんです。
これは明らかなデザイン上のミスです。
ちょっとビクビクしていたけど、これは簡単でした ^^
> 1)を高め(70%を採用)、4)を低め(20%を採用)、に取ると、55%程度
0.7 × ( 1 - 0.2) = 0.56
> 1)を低め(60%を採用)、4)を高め(40%を採用)、に取ると、35%程度
0.6 × ( 1 - 0.4) = 0.36
そんなしちめんどくさい計算しなくても、表15の「欠席した者に占める感染者率」で一発じゃん!、と思われるかもしれませんが、この3.D節での「欠席者」の定義は「流行の期間中一回でも欠席したことがある児童」、でして、3.C節の定義と異なりますので、単純に比較できないんです。
一方で、欠席しなかった、という基準は3.C節でも3.D節でも同様に扱えますので、基準として採用できるのはこちらの数字、ということです。
これをちゃんと区別して扱わないとどういうことになるか例を挙げますと、1983.12.12〜1984.2.15にAH1N1の流行があったことになっていますが、この期間での欠席した者に占めるインフルエンザの感染者率は32.4%と他の期間と比べるとかなり低い数字になっており、これはインフルエンザの流行に合わせてタダの風邪の流行も重なっていたため、と解釈できます。が、3.C節では軽い風邪で休んだケースは除外して扱っているので、そこに気付かずにこの数字をそのまま使うと色々と辻褄が合わなくなってきます。
> 1)を高め(70%を採用)、4)を低め(20%を採用)、に取ると、55%程度
0.7 × ( 1 - 0.2) = 0.56
> 1)を低め(60%を採用)、4)を高め(40%を採用)、に取ると、35%程度
0.6 × ( 1 - 0.4) = 0.36
そんなしちめんどくさい計算しなくても、表15の「欠席した者に占める感染者率」で一発じゃん!、と思われるかもしれませんが、この3.D節での「欠席者」の定義は「流行の期間中一回でも欠席したことがある児童」、でして、3.C節の定義と異なりますので、単純に比較できないんです。
一方で、欠席しなかった、という基準は3.C節でも3.D節でも同様に扱えますので、基準として採用できるのはこちらの数字、ということです。
これをちゃんと区別して扱わないとどういうことになるか例を挙げますと、1983.12.12〜1984.2.15にAH1N1の流行があったことになっていますが、この期間での欠席した者に占めるインフルエンザの感染者率は32.4%と他の期間と比べるとかなり低い数字になっており、これはインフルエンザの流行に合わせてタダの風邪の流行も重なっていたため、と解釈できます。が、3.C節では軽い風邪で休んだケースは除外して扱っているので、そこに気付かずにこの数字をそのまま使うと色々と辻褄が合わなくなってきます。
再度読み返しましたが、以下の3.C節で「公称70%以上と言われるワクチン有効率と比較して,何と低い値ではないかと言わざるを得ない」と述べていますので、ワクチンの効果についてはかなり否定的だと言えると思います。
http://www.kangaeroo.net/D-maebashi-F-view-no-23C.html
ただこれは、ただの風邪とインフルエンザを混ぜこぜにして集計しているせいであって、抗体価の検査結果から実際にインフルエンザウイルスに感染していた人の割合を推計してただの風邪で休んだ人を除いて計算しなおしてみると、確かに「公称70%以上」の通りの結果になっている、というのがわたしの推計結果です。
実はこの計算方法をわたしが思いついたのは、beach医師(仮名)が、厚生労働省が取りまとめたタミフルと異常行動との間の相関の調査結果にイチャモンを付けたのを見てです。
具体的には、異常行動が起きたあとにタミフルを服用した群を集計から除くのはおかしい、とケチを付けた件で、「そうは言っても、この集計だけからこの効果を評価するのは無理だしなぁ。。。」とぶつくさ言いながら実際に電卓を叩いてあーでもないこーでもないと数字をこねくり回していたのですが、ふと「あれ?、これって前橋レポートの解析のやりなおしに使えんじゃねえ?」と閃いたのでした。ま、当然ながらその前に前橋レポートには実際に目を通した上で「なんだーこりゃー」と呆れていたからこそ閃くことができたのですが。
おそらくbeach医師(仮名)は、厚生労働省の集計はどこかおかしいに違いないという先入観からあら探しを始めたんだろうと思いますが、同じように前橋レポートの集計のおかしい部分がわかっていればわたしと同様の方法で前橋レポートの集計がやりなおせることに気付いておかしくないはずです。なんせわたしはこのアイデアは、beach医師(仮名)から教えていただいたようなものなのですから。
つまり、beach医師(仮名)の頭脳をもってしてみれば、巷で流布している都市伝説とは全く逆の、前橋レポートは実はワクチンの有効性を証明している、という結論に到達できたはずです。
じゃぁなんでこんなことになってるの?、ということは、皆までは言いません ^^
一方forest医師(仮名)は。。。もうボケてきているに違いない、という解釈ではあまりにも失礼でしょうか ^^
http://www.kangaeroo.net/D-maebashi-F-view-no-23C.html
ただこれは、ただの風邪とインフルエンザを混ぜこぜにして集計しているせいであって、抗体価の検査結果から実際にインフルエンザウイルスに感染していた人の割合を推計してただの風邪で休んだ人を除いて計算しなおしてみると、確かに「公称70%以上」の通りの結果になっている、というのがわたしの推計結果です。
実はこの計算方法をわたしが思いついたのは、beach医師(仮名)が、厚生労働省が取りまとめたタミフルと異常行動との間の相関の調査結果にイチャモンを付けたのを見てです。
具体的には、異常行動が起きたあとにタミフルを服用した群を集計から除くのはおかしい、とケチを付けた件で、「そうは言っても、この集計だけからこの効果を評価するのは無理だしなぁ。。。」とぶつくさ言いながら実際に電卓を叩いてあーでもないこーでもないと数字をこねくり回していたのですが、ふと「あれ?、これって前橋レポートの解析のやりなおしに使えんじゃねえ?」と閃いたのでした。ま、当然ながらその前に前橋レポートには実際に目を通した上で「なんだーこりゃー」と呆れていたからこそ閃くことができたのですが。
おそらくbeach医師(仮名)は、厚生労働省の集計はどこかおかしいに違いないという先入観からあら探しを始めたんだろうと思いますが、同じように前橋レポートの集計のおかしい部分がわかっていればわたしと同様の方法で前橋レポートの集計がやりなおせることに気付いておかしくないはずです。なんせわたしはこのアイデアは、beach医師(仮名)から教えていただいたようなものなのですから。
つまり、beach医師(仮名)の頭脳をもってしてみれば、巷で流布している都市伝説とは全く逆の、前橋レポートは実はワクチンの有効性を証明している、という結論に到達できたはずです。
じゃぁなんでこんなことになってるの?、ということは、皆までは言いません ^^
一方forest医師(仮名)は。。。もうボケてきているに違いない、という解釈ではあまりにも失礼でしょうか ^^
お待たせしました、クリスマス前になんとか時間取れました。明日はまた家族サービスですが ^^
> その他の病気の37.7%は32.3の誤記でしょうか?
すみません、その通り、32.3%でして、38.3 - 32.3 = 6.0でした。
ここでは、高崎市で、インフルエンザワクチンを打たなかった人も、1回だけ打った人も、2回きちんと打った人も、インフルエンザ以外のしつこい風邪などに罹る率は変わらない、と仮定してます。
あと、インフルエンザの罹患率をだいたい35%〜55%ぐらいであろう、と推計した中で、試しに40%と50%でどのくらいの有効率になるかを試算したのが上の計算で、この範囲でも厚生省(当時 ^^)の報告によるワクチンの有効率30-80%とほぼドンピシャなので、あまり深く考えていませんでした。
実際の罹患率は、高崎市の1985年の結果を見るとわかるように、有効率99.2%なんて数字は出来すぎに決まってますので、もうちょっと多いのかな?、と思います。
あとおそらく当然のことながら、1984年と1985年のインフルエンザの罹患率はおそらく微妙に異なるだろう、と見てます。
もっときちんと計算するには、インフルエンザの抗体を確保していた人の割合と、不顕性感染した者の割合を、それぞれ適当な確率分布を仮定して重ね合わせ、積分して期待値を求めればいいんですけど、他にも評価不明な雑多なファクターがあるのはわかっているので、そこまでまともに計算しようという気力がありません ^^
また背景として、これは群馬県の地理を知っていないとピンとこないのですが、条件として前橋市と比較しやすいのは隣接している高崎市で、桐生市と伊勢崎市は両毛地区と呼ばれる少し離れている場所に立地している上に住民のカラーがかなり違います。
この住民性の差異が実はワクチンの接種率の差などにも現れているのですが、このあたり書き忘れたことなので、あともうちょっと余裕ができたら群馬県民を敵に回す覚悟で考察いたします ^^
> その他の病気の37.7%は32.3の誤記でしょうか?
すみません、その通り、32.3%でして、38.3 - 32.3 = 6.0でした。
ここでは、高崎市で、インフルエンザワクチンを打たなかった人も、1回だけ打った人も、2回きちんと打った人も、インフルエンザ以外のしつこい風邪などに罹る率は変わらない、と仮定してます。
あと、インフルエンザの罹患率をだいたい35%〜55%ぐらいであろう、と推計した中で、試しに40%と50%でどのくらいの有効率になるかを試算したのが上の計算で、この範囲でも厚生省(当時 ^^)の報告によるワクチンの有効率30-80%とほぼドンピシャなので、あまり深く考えていませんでした。
実際の罹患率は、高崎市の1985年の結果を見るとわかるように、有効率99.2%なんて数字は出来すぎに決まってますので、もうちょっと多いのかな?、と思います。
あとおそらく当然のことながら、1984年と1985年のインフルエンザの罹患率はおそらく微妙に異なるだろう、と見てます。
もっときちんと計算するには、インフルエンザの抗体を確保していた人の割合と、不顕性感染した者の割合を、それぞれ適当な確率分布を仮定して重ね合わせ、積分して期待値を求めればいいんですけど、他にも評価不明な雑多なファクターがあるのはわかっているので、そこまでまともに計算しようという気力がありません ^^
また背景として、これは群馬県の地理を知っていないとピンとこないのですが、条件として前橋市と比較しやすいのは隣接している高崎市で、桐生市と伊勢崎市は両毛地区と呼ばれる少し離れている場所に立地している上に住民のカラーがかなり違います。
この住民性の差異が実はワクチンの接種率の差などにも現れているのですが、このあたり書き忘れたことなので、あともうちょっと余裕ができたら群馬県民を敵に回す覚悟で考察いたします ^^
バイアスというか、そもそもの条件設定がもう目を覆わんばかりのダメダメさ加減なのですが、一番のバイアスは、前橋市民が予防接種を受けられなかったため自分で行える予防策を積極的に励行したのでは?、と思われるところです。
これは >>8 でも指摘しましたが、確かどっかで書いた覚えがあるのですが忘れているので再度書きますが、 前橋市で集団接種を辞めてすぐの時にインフルエンザの流行が起きたことがあり、一方でその時に隣の高崎市では流行が起きていなかったため、新聞で「インフルエンザワクチンの学童集団接種を中止した前橋市で、インフルエンザ大流行!」と煽る新聞記事が出てしまい、対応に必死になった、という記述が >>0 で挙げたこの研究班のリーダーの著書「予防接種の考え方」 の中であります。
何をどう対応したのかは、この本では具体的に書かれてませんが、予防接種を受ける機会を与えられなかった前橋市民は、おそらくは予防策に必死になったことは想像できると思います。
つまり、マスク着用、手洗い、うがい、といった日常的に行える予防策の励行の結果、このような成績になったのでは?、と思ってます。
あと、このトピのネタ、古いですが元はこちらのトピからきてまして。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=23322214&comm_id=1898250
インフルエンザワクチンの有効率のデータは色々ありますが、一番酷いのはこの2で紹介した平成12年度厚生科学研究費補助金研究報告書「乳幼児に対するインフルエンザワクチンの効果に関する研究」の、「発熱を指標とした有効率は20-30%」というものでして --;;;;
この調査に関しては、反ワクチン団体からも非難を浴びていたんですが、↑トピの >>2 でこの全文を貼りつけていたサイトの持ち主が(確かわたしの記憶によれば)お亡くなられてまして、今はlink切れです --;;;
参考までにURLはもう一度紹介しておきますが:
http://www003.upp.so-net.ne.jp/manao/2000kenkyu.html
web archiveでは読めるけど、肝心の図表のデータがないんだよなあ T_T
で、他のコミュで恐縮ですが、前にどっかで書いたはずだと探したら↓の377で指摘していたのですが、再び要点貼り付けます。実際のフィールドを対象とした調査だと思いもよらないバイアスが入ることがあり、対照実験としての条件を満たすために相当に気を使っていないと、思いもよらぬ結果になってしまうことが容易に想像できるのではないかと。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=45586302&comm_id=4271997
この調査によると、わざわざ病院に自費で予防接種を受けに来る人は、予防接種を受けていない人らに比べると、経済的に豊かであるという結果がでています(平成14年9月本報告:表6)。
また、予防接種を受けにくる人は、受けていない人らに比べると、過去半年間に風邪の症状になった割合が有為に少ない、という結果がでています(同表6)。
この要因として、予防接種を受けている経済的に豊かな人らは、受けていない人に比べてうがいや手洗いなどのしつけも行き届いているのでは?、という推測ができます。
にもかかわらず、前シーズンにインフルエンザに罹った人は、予防接種を受けている人のほうが受けていない人よりも有為に割合が多い、という逆説的な結果になっています。
これっていったいどゆこと?、と考えると例えば、朝から夕方まで保育園に預けている家庭と、専業主婦で幼稚園に通わせている家庭と、その違いが出てるんじゃ?と個人的には思います。
しかし実はアンケートの設問に、幼稚園に通っているか保育園に通っているか、ちゃんと項目分けてあるんですよね。
なのでこのクロス集計を取れば、保育園に通っている子は幼稚園に通っている子と比べると、仕事があるので少々の病気でも無理して預けて園にいる時間も長いため病気をもらってくることが多い、というお母さん方が経験として持っている感覚が実証されるはずなのですが。。。このレポートではそういう集計をやってないようで、そこらへんがわたしはとても不満です!、交絡因子の調整はとても重要です!、ぷんぷん!
これは >>8 でも指摘しましたが、確かどっかで書いた覚えがあるのですが忘れているので再度書きますが、 前橋市で集団接種を辞めてすぐの時にインフルエンザの流行が起きたことがあり、一方でその時に隣の高崎市では流行が起きていなかったため、新聞で「インフルエンザワクチンの学童集団接種を中止した前橋市で、インフルエンザ大流行!」と煽る新聞記事が出てしまい、対応に必死になった、という記述が >>0 で挙げたこの研究班のリーダーの著書「予防接種の考え方」 の中であります。
何をどう対応したのかは、この本では具体的に書かれてませんが、予防接種を受ける機会を与えられなかった前橋市民は、おそらくは予防策に必死になったことは想像できると思います。
つまり、マスク着用、手洗い、うがい、といった日常的に行える予防策の励行の結果、このような成績になったのでは?、と思ってます。
あと、このトピのネタ、古いですが元はこちらのトピからきてまして。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=23322214&comm_id=1898250
インフルエンザワクチンの有効率のデータは色々ありますが、一番酷いのはこの2で紹介した平成12年度厚生科学研究費補助金研究報告書「乳幼児に対するインフルエンザワクチンの効果に関する研究」の、「発熱を指標とした有効率は20-30%」というものでして --;;;;
この調査に関しては、反ワクチン団体からも非難を浴びていたんですが、↑トピの >>2 でこの全文を貼りつけていたサイトの持ち主が(確かわたしの記憶によれば)お亡くなられてまして、今はlink切れです --;;;
参考までにURLはもう一度紹介しておきますが:
http://www003.upp.so-net.ne.jp/manao/2000kenkyu.html
web archiveでは読めるけど、肝心の図表のデータがないんだよなあ T_T
で、他のコミュで恐縮ですが、前にどっかで書いたはずだと探したら↓の377で指摘していたのですが、再び要点貼り付けます。実際のフィールドを対象とした調査だと思いもよらないバイアスが入ることがあり、対照実験としての条件を満たすために相当に気を使っていないと、思いもよらぬ結果になってしまうことが容易に想像できるのではないかと。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=45586302&comm_id=4271997
この調査によると、わざわざ病院に自費で予防接種を受けに来る人は、予防接種を受けていない人らに比べると、経済的に豊かであるという結果がでています(平成14年9月本報告:表6)。
また、予防接種を受けにくる人は、受けていない人らに比べると、過去半年間に風邪の症状になった割合が有為に少ない、という結果がでています(同表6)。
この要因として、予防接種を受けている経済的に豊かな人らは、受けていない人に比べてうがいや手洗いなどのしつけも行き届いているのでは?、という推測ができます。
にもかかわらず、前シーズンにインフルエンザに罹った人は、予防接種を受けている人のほうが受けていない人よりも有為に割合が多い、という逆説的な結果になっています。
これっていったいどゆこと?、と考えると例えば、朝から夕方まで保育園に預けている家庭と、専業主婦で幼稚園に通わせている家庭と、その違いが出てるんじゃ?と個人的には思います。
しかし実はアンケートの設問に、幼稚園に通っているか保育園に通っているか、ちゃんと項目分けてあるんですよね。
なのでこのクロス集計を取れば、保育園に通っている子は幼稚園に通っている子と比べると、仕事があるので少々の病気でも無理して預けて園にいる時間も長いため病気をもらってくることが多い、というお母さん方が経験として持っている感覚が実証されるはずなのですが。。。このレポートではそういう集計をやってないようで、そこらへんがわたしはとても不満です!、交絡因子の調整はとても重要です!、ぷんぷん!
そうなんです、「前橋レポート」をじっくり読み込んでその問題点を把握した上で、研究リーダーの書かれた「予防接種の考え方」の記述と比較した、なんて人はわたしの他にそうめったにいないと思いますが、両方を読み比べてみると本当に「いったいなんなんだこれは」と呆然としてしまいます。
これはわたしの想像ですが、おそらく「前橋レポート」を論文としてどこかに発表しようとしたが、査読者からケチが付けられてどこの学会からも採録されず、そのケチが付けられた部分をうまくぼかして書かれたのが「予防接種の考え方」なのでは?、と勘ぐっています。
で、「前橋レポート」自体は入手が困難なので実際に読んだことがなくても、一般の書籍として出版された「予防接種の考え方」でその結果だけを読んで、元々のデザインのマズさに気付かれずに都市伝説が広まってしまった、というところじゃないかなぁ、と。
本当のところがどうなのかは、当時この研究に携わった人に聞くのが正確かと思いますが。。。
多分、forest医師ならよくご存知ではないかと ^^
「どうしてこのような優れた研究が、学術論文として発表されなかったのでしょうか?」とかしつこく聞いてみるとかして、学術論文としてまとめたことがあったかどうかの情報だけでも引き出せませんかね?
これはわたしの想像ですが、おそらく「前橋レポート」を論文としてどこかに発表しようとしたが、査読者からケチが付けられてどこの学会からも採録されず、そのケチが付けられた部分をうまくぼかして書かれたのが「予防接種の考え方」なのでは?、と勘ぐっています。
で、「前橋レポート」自体は入手が困難なので実際に読んだことがなくても、一般の書籍として出版された「予防接種の考え方」でその結果だけを読んで、元々のデザインのマズさに気付かれずに都市伝説が広まってしまった、というところじゃないかなぁ、と。
本当のところがどうなのかは、当時この研究に携わった人に聞くのが正確かと思いますが。。。
多分、forest医師ならよくご存知ではないかと ^^
「どうしてこのような優れた研究が、学術論文として発表されなかったのでしょうか?」とかしつこく聞いてみるとかして、学術論文としてまとめたことがあったかどうかの情報だけでも引き出せませんかね?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
科学的に予防接種を考える 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
科学的に予防接種を考えるのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37865人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90065人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人