みかんさんからご紹介いただいた「塵埃落定」を中国版アマゾンで試しに購入してみました。
8月29日に注文した本は9月6日に日本の自宅に到着しました。結果、8日間で到着したことになります。注文請書では到着予定は9月16日と書いていましたので、10日も早く到着したことなります。
もっとも、本代14.70元に対し、シッピングチャージは110元も使って、EMS(国際宅急便)を使って送ってきているので、早くて当たり前のような気もします。
ちょっと読み始めましたが、少数民族作家の小説を読んだことがほとんどない私にとって物凄いチャレンジです。
しょっぱなからチベット族の習慣がこれでもかこれでもかと出てきて、ギョギョギョッという感じです。日本人の考える典型的な読ませる長編小説の雰囲気があり、今から楽しみにしています。
さてどこまで中国臭さ(抹香臭さ?)から抜け切れるか。
8月29日に注文した本は9月6日に日本の自宅に到着しました。結果、8日間で到着したことになります。注文請書では到着予定は9月16日と書いていましたので、10日も早く到着したことなります。
もっとも、本代14.70元に対し、シッピングチャージは110元も使って、EMS(国際宅急便)を使って送ってきているので、早くて当たり前のような気もします。
ちょっと読み始めましたが、少数民族作家の小説を読んだことがほとんどない私にとって物凄いチャレンジです。
しょっぱなからチベット族の習慣がこれでもかこれでもかと出てきて、ギョギョギョッという感じです。日本人の考える典型的な読ませる長編小説の雰囲気があり、今から楽しみにしています。
さてどこまで中国臭さ(抹香臭さ?)から抜け切れるか。
|
|
|
|
コメント(9)
これもレポートしておきます。
最初はチベットの各種各様の風俗が紹介されて、これは凄い小説だと、ぞくぞくしながら読みました。さすがは茅盾賞を受賞した長編小説だと思いました。ところが最後から3分の1くらいになると、つまり、漢民族や中国共産党が出てくる時代になると、バタバタと話が進み、あれよあれよという間に話が終わってしまいました。
折角楽しんで読んでいたのに残念!と素直に思ってしまいました。
でも、一つの収穫は「土司」という、少数民族の管理者に与えられた職位があったことを知ったこと。世界史の教科書を見ていたら、しっかり載っていました。(^-^;)
日本語訳が出版されているのでご紹介しようと思いましたが、中古本しかなく価格は4,994円でした。個人ではちょっと手が出ない金額ですので、是非図書館で貸出してもらって下さい。
最初はチベットの各種各様の風俗が紹介されて、これは凄い小説だと、ぞくぞくしながら読みました。さすがは茅盾賞を受賞した長編小説だと思いました。ところが最後から3分の1くらいになると、つまり、漢民族や中国共産党が出てくる時代になると、バタバタと話が進み、あれよあれよという間に話が終わってしまいました。
折角楽しんで読んでいたのに残念!と素直に思ってしまいました。
でも、一つの収穫は「土司」という、少数民族の管理者に与えられた職位があったことを知ったこと。世界史の教科書を見ていたら、しっかり載っていました。(^-^;)
日本語訳が出版されているのでご紹介しようと思いましたが、中古本しかなく価格は4,994円でした。個人ではちょっと手が出ない金額ですので、是非図書館で貸出してもらって下さい。
ねずみのチュー太郎さん
『塵埃落定』読了されたのですね!
阿来が最近のブログで、『塵埃落定』について、
「これは歴史を題材としている、でも、多くの人は伝奇物語として読んでいる」というようなことを書いています。
私はまさしく後者ですね…
http://blog.sina.com.cn/s/blog_60ad606e010126qo.html
日本語版は、ちょっと見ものです。異色の訳です。
統一感に欠けるので、やはり図書館で借りて読んだ方がいいと思います。
最近彼の「空山」日本語訳が出たようですね。
こちらも、私は原文を読んだのですが、難しかったです。ぜひ、日本語版を読みたいと思っています。
『塵埃落定』読了されたのですね!
阿来が最近のブログで、『塵埃落定』について、
「これは歴史を題材としている、でも、多くの人は伝奇物語として読んでいる」というようなことを書いています。
私はまさしく後者ですね…
http://blog.sina.com.cn/s/blog_60ad606e010126qo.html
日本語版は、ちょっと見ものです。異色の訳です。
統一感に欠けるので、やはり図書館で借りて読んだ方がいいと思います。
最近彼の「空山」日本語訳が出たようですね。
こちらも、私は原文を読んだのですが、難しかったです。ぜひ、日本語版を読みたいと思っています。
みかんさん、こんにちは。
レスありがとうございました。
みかんさんに添付いただいていたURLから作者の講演会原稿を拝見しました。写真も掲載されていましたが、いたって普通のオジサンなのには笑ってしまいました。よく言って、ちょっと細めのチャン・カワイ?
私は前者です。小説であっても、まずは中国の社会を理解するために読む習慣が染みついています。チベット族は巷で言われるような神聖な民族ではなく、まったく別の面(無知蒙昧、権力に固執といった面)も持った今そこに生きている人間であると言い切るこの作家の考え方はすごいです。
一方イメージ喚起装置としてこの長編小説はうまく構成されています。その点が評価されて茅盾賞を受賞できたのだと思いますし、伝奇物として読んでも十分面白い理由はそこにあるように思います。
原稿の最後に、「しかし、たとえそうでも、私はやはり私の著作を続けるだろう。今日至る所で成功を追い求める社会において、(私が)失敗者となるのも一つの勇敢な選択なのだから。」という点に非常に興味を持ちました。気合の入った作家先生です。私は気に入りました。
みかんさんがおっしゃる日本語訳が異色の訳というのはレベルが高いということでしょうか。あるいは逆説的な意味でしょうか。最近の作品は「空山」というのですか。三部作とのことですが、ぜひ一度読んでみたいです。
レスありがとうございました。
みかんさんに添付いただいていたURLから作者の講演会原稿を拝見しました。写真も掲載されていましたが、いたって普通のオジサンなのには笑ってしまいました。よく言って、ちょっと細めのチャン・カワイ?
私は前者です。小説であっても、まずは中国の社会を理解するために読む習慣が染みついています。チベット族は巷で言われるような神聖な民族ではなく、まったく別の面(無知蒙昧、権力に固執といった面)も持った今そこに生きている人間であると言い切るこの作家の考え方はすごいです。
一方イメージ喚起装置としてこの長編小説はうまく構成されています。その点が評価されて茅盾賞を受賞できたのだと思いますし、伝奇物として読んでも十分面白い理由はそこにあるように思います。
原稿の最後に、「しかし、たとえそうでも、私はやはり私の著作を続けるだろう。今日至る所で成功を追い求める社会において、(私が)失敗者となるのも一つの勇敢な選択なのだから。」という点に非常に興味を持ちました。気合の入った作家先生です。私は気に入りました。
みかんさんがおっしゃる日本語訳が異色の訳というのはレベルが高いということでしょうか。あるいは逆説的な意味でしょうか。最近の作品は「空山」というのですか。三部作とのことですが、ぜひ一度読んでみたいです。
ねずみのチュー太郎 さま
阿来は、本当に普通のオジサンっぽいですね。性格も言いたいことははっきり言ってしまうタイプ。
以前、それでたたかれたことがあります。
(チベットは以前よりずっとよくなったなどと発言してしまった!)
彼はもともと詩人なので、言葉が美しく、時々感覚に走ってしまいがちな気がします。
それで、私はついつい伝奇的な読み方をしてしまいます。まだ読みが甘いです。
日本語版は、言葉がギャル風(今死語でしょうか)。
土司夫人を土司マダムと訳したり、〜なカンジ、とか、ゲットした、とか…
主人公の様子にあっていると言えなくもないのですが。
原作を知らずにこれを読んだら…考えたくないです。でも、面白いかなと思ったり…
翻訳って何か、と少し考えさせられました。
こう訳そうと決めたのは、阿来のユーモラスな人柄に触れたのも一つの理由だ、ということでした。
先日、復旦大学の劉志栄という先生の講座を聞いたのですが、現代の作家でぜひ読んで欲しい作品は、
劉震雲の『一句頂一万句』
余華『兄弟』
阿来『空山』
だそうです。ちょっとうれしくなりました。
(『兄弟』は好きではありませんが)
阿来は、本当に普通のオジサンっぽいですね。性格も言いたいことははっきり言ってしまうタイプ。
以前、それでたたかれたことがあります。
(チベットは以前よりずっとよくなったなどと発言してしまった!)
彼はもともと詩人なので、言葉が美しく、時々感覚に走ってしまいがちな気がします。
それで、私はついつい伝奇的な読み方をしてしまいます。まだ読みが甘いです。
日本語版は、言葉がギャル風(今死語でしょうか)。
土司夫人を土司マダムと訳したり、〜なカンジ、とか、ゲットした、とか…
主人公の様子にあっていると言えなくもないのですが。
原作を知らずにこれを読んだら…考えたくないです。でも、面白いかなと思ったり…
翻訳って何か、と少し考えさせられました。
こう訳そうと決めたのは、阿来のユーモラスな人柄に触れたのも一つの理由だ、ということでした。
先日、復旦大学の劉志栄という先生の講座を聞いたのですが、現代の作家でぜひ読んで欲しい作品は、
劉震雲の『一句頂一万句』
余華『兄弟』
阿来『空山』
だそうです。ちょっとうれしくなりました。
(『兄弟』は好きではありませんが)
みかんさん、こんにちは。
阿来は詩人さんなのですか。私は詩人とか芸術とかとは全く縁遠い生活をしています。(^-^;) もう一度文章をじっくり味わう必要がありそうです。
土司夫人を土司マダムと言ったり、〜なカンジ、〜をゲットしたという訳があると聞くと、学生に下訳させて、先生が名前だけの監修(実際には院生がチェック)するような方法を採ったのではないかと疑ってしまいます。原作のイメージはできるだけ尊重してほしいものです。
勉誠出版のツイッターを見ていると、6月17日(日)の「読売新聞」で「コレクション中国同時代小説」の第1巻『空山(くうざん)』(http://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&cPath=4_5&products_id=100082)が掲載予定とのことです。→http://www.yomiuri.co.jp/book/nextweek/ 私は読売は取っていないので、もしチャンスがあればご覧ください。
阿来は詩人さんなのですか。私は詩人とか芸術とかとは全く縁遠い生活をしています。(^-^;) もう一度文章をじっくり味わう必要がありそうです。
土司夫人を土司マダムと言ったり、〜なカンジ、〜をゲットしたという訳があると聞くと、学生に下訳させて、先生が名前だけの監修(実際には院生がチェック)するような方法を採ったのではないかと疑ってしまいます。原作のイメージはできるだけ尊重してほしいものです。
勉誠出版のツイッターを見ていると、6月17日(日)の「読売新聞」で「コレクション中国同時代小説」の第1巻『空山(くうざん)』(http://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&cPath=4_5&products_id=100082)が掲載予定とのことです。→http://www.yomiuri.co.jp/book/nextweek/ 私は読売は取っていないので、もしチャンスがあればご覧ください。
ねずみのチュー太郎 さま
ご無沙汰しています。
ちょっとお知らせしたくて久しぶりのmixiです。
大阪の十三というステキな所にあるシアターセブンという映画館で『ケサル大王』というドキュメンタリーが上映されます。
4月6日から12日まで。14:40上映開始です
http://gesar.jp/
何故これをお知らせするかというと、阿来も『ケサル王』という長編小説を書いていので、そのつながりで、私もたくさん「ケサル」とつぶやいているのです。
映画は、物語りを紹介するのと同時に、東チベットの今にいたる様々な問題を静かに描いています。チベット寺院で行われる仮面劇など、貴重な映像もたくさんあります。
もし、お時間が許せば、ぜひごらんになってください。
ご無沙汰しています。
ちょっとお知らせしたくて久しぶりのmixiです。
大阪の十三というステキな所にあるシアターセブンという映画館で『ケサル大王』というドキュメンタリーが上映されます。
4月6日から12日まで。14:40上映開始です
http://gesar.jp/
何故これをお知らせするかというと、阿来も『ケサル王』という長編小説を書いていので、そのつながりで、私もたくさん「ケサル」とつぶやいているのです。
映画は、物語りを紹介するのと同時に、東チベットの今にいたる様々な問題を静かに描いています。チベット寺院で行われる仮面劇など、貴重な映像もたくさんあります。
もし、お時間が許せば、ぜひごらんになってください。
みかんさん、こんにちは。
貴重な情報をご提供いただき、ありがとうございました。
私は仕事の関係上、現在東京に住んでいます。留守宅は大阪にあります。本日まで大阪に滞在し、これから東京に帰ろうとしていたところ、みかんさんのコメントを拝見しました。まさに入れ違いの状況です。残念!
「ケサル大王」の事は今回初めて知りました。非常に土着性の強い大王さんのようです。(^-^) これからホームページでいろいろケサル大王の情報を仕込みたいと思います。
みかんさんに以前ご紹介いただいた阿来の「空山」は、相変わらずバタバタしているため本棚の「肥やし」になっています。そろそろ手を付けないととは思っているのですが、なかなか体が動かなくて。
また何か新しい情報がありましたら、ぜひよろしくお願いします。
貴重な情報をご提供いただき、ありがとうございました。
私は仕事の関係上、現在東京に住んでいます。留守宅は大阪にあります。本日まで大阪に滞在し、これから東京に帰ろうとしていたところ、みかんさんのコメントを拝見しました。まさに入れ違いの状況です。残念!
「ケサル大王」の事は今回初めて知りました。非常に土着性の強い大王さんのようです。(^-^) これからホームページでいろいろケサル大王の情報を仕込みたいと思います。
みかんさんに以前ご紹介いただいた阿来の「空山」は、相変わらずバタバタしているため本棚の「肥やし」になっています。そろそろ手を付けないととは思っているのですが、なかなか体が動かなくて。
また何か新しい情報がありましたら、ぜひよろしくお願いします。
ねずみのチュー太郎 さま
早速お返事頂きありがとうございます。
もう少し早くお知らせしておけば…残念です。
でも、ケサルという名前を心に留めていただけただけでもうれしいです。
また、東京でも上映するのではと思いますので、その時またお知らせします。
HPを見て、ご意見をコメントしていただけたら、監督も喜ぶと思います。
大阪で見た方のいくつかの感想を載せておきます。
お暇な時に読んでください。
お忙しいと思いますが、また情報交換できたらうれしいです。
この映画のテーマ、そしてそこから受ける感動は、結局、「ケサル」の物語そのものというより
それを育んできたチベットの人たちの素朴な生き方にあるのではないかと思いました。
どこまでも広がる草原。雪をいただく山々。赤黒い頬の若い女性が、笑顔で水汲みから戻るシーン。
また同じように赤黒い頬の子どもたちが、その田舎びた風貌には似ても似つかぬ、くっきりした声で、
堂々と英雄物語の一節を朗誦する姿。どれも、いま私たちを取りまいている物質的な豊かさとは正反対の、
本質的な人間そのものの生き方を感じさせる、美しく感動的なイメージばかりでした。
それに対して、英雄ゆかりの地に続々と建てられている、常軌を逸したとしか言いようのない大きな
「ケサル像」や、牧畜の民を草原から追いたて、「近代的な」進んだ生活を強要しようとする集合アパート
の、何という無味乾燥さ。醜さ。
* * *
わたしは、特に、高僧が丘の上に旗で模様をつくっているくだりがとても感動しました。
中国が侵攻してきて、50年がすぎ、世代間、文化、地域がさまざまな形で分断されていく中で
人々のつながりを、ああいった形で構築されている方がいるというのを知ることは、
映画以外で知る以外はないかもしれません。
* * *
三宅先生もおっしゃってましたが、今回、本当に豊満な内容で圧倒されました。
タッチーな題材で精神的にも肉体的にも本当に大変な過酷な取材だったと思うのですが、
よくここまでというところまで入って感動しました。
最後の方に出てきた、経典を記した旗の仏塔?を作り、子どもたちもうれしそうな場面が、
わたしはわたしであるという強烈なメッセージと感じ、深く感動しました。
それが焼身自殺にまでつながっていくのかと思うと、居た堪れないですが、
ギリギリの美しさ、メッセージが溢れてるような気がします。
自分自身に問いかけられてるような思いです。
ケサルの話が降りてくるというはなしも映像もとても興味深く、わくわくします。
* * *
「ケサル大王伝」が幾多の困難を乗り越え、今もチベットの人々の心の中に生きていることを
嬉しく思います。通訳の青年がこの映画に参加したことをきっかけに、もっと次世代の子供たちに
伝えようと思うと語っていたのが素晴しいと思います。監督が日本人の目で埋もれた宝に光を当て
チベット人の誇りと自覚できることになって映画の意義が深くなっていると思います。
「大王伝」が中国の世界遺産として登録されてもチベットの人の心のよりどころとして生き続けて
いくことを祈ります。
早速お返事頂きありがとうございます。
もう少し早くお知らせしておけば…残念です。
でも、ケサルという名前を心に留めていただけただけでもうれしいです。
また、東京でも上映するのではと思いますので、その時またお知らせします。
HPを見て、ご意見をコメントしていただけたら、監督も喜ぶと思います。
大阪で見た方のいくつかの感想を載せておきます。
お暇な時に読んでください。
お忙しいと思いますが、また情報交換できたらうれしいです。
この映画のテーマ、そしてそこから受ける感動は、結局、「ケサル」の物語そのものというより
それを育んできたチベットの人たちの素朴な生き方にあるのではないかと思いました。
どこまでも広がる草原。雪をいただく山々。赤黒い頬の若い女性が、笑顔で水汲みから戻るシーン。
また同じように赤黒い頬の子どもたちが、その田舎びた風貌には似ても似つかぬ、くっきりした声で、
堂々と英雄物語の一節を朗誦する姿。どれも、いま私たちを取りまいている物質的な豊かさとは正反対の、
本質的な人間そのものの生き方を感じさせる、美しく感動的なイメージばかりでした。
それに対して、英雄ゆかりの地に続々と建てられている、常軌を逸したとしか言いようのない大きな
「ケサル像」や、牧畜の民を草原から追いたて、「近代的な」進んだ生活を強要しようとする集合アパート
の、何という無味乾燥さ。醜さ。
* * *
わたしは、特に、高僧が丘の上に旗で模様をつくっているくだりがとても感動しました。
中国が侵攻してきて、50年がすぎ、世代間、文化、地域がさまざまな形で分断されていく中で
人々のつながりを、ああいった形で構築されている方がいるというのを知ることは、
映画以外で知る以外はないかもしれません。
* * *
三宅先生もおっしゃってましたが、今回、本当に豊満な内容で圧倒されました。
タッチーな題材で精神的にも肉体的にも本当に大変な過酷な取材だったと思うのですが、
よくここまでというところまで入って感動しました。
最後の方に出てきた、経典を記した旗の仏塔?を作り、子どもたちもうれしそうな場面が、
わたしはわたしであるという強烈なメッセージと感じ、深く感動しました。
それが焼身自殺にまでつながっていくのかと思うと、居た堪れないですが、
ギリギリの美しさ、メッセージが溢れてるような気がします。
自分自身に問いかけられてるような思いです。
ケサルの話が降りてくるというはなしも映像もとても興味深く、わくわくします。
* * *
「ケサル大王伝」が幾多の困難を乗り越え、今もチベットの人々の心の中に生きていることを
嬉しく思います。通訳の青年がこの映画に参加したことをきっかけに、もっと次世代の子供たちに
伝えようと思うと語っていたのが素晴しいと思います。監督が日本人の目で埋もれた宝に光を当て
チベット人の誇りと自覚できることになって映画の意義が深くなっていると思います。
「大王伝」が中国の世界遺産として登録されてもチベットの人の心のよりどころとして生き続けて
いくことを祈ります。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
中国現代文学・当代文学 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
中国現代文学・当代文学のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37860人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90058人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208307人
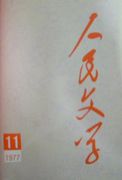



















![[dir] 台湾](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/87/71/1758771_187s.gif)



