厚生労働省がドナーの55歳定年制を導入するようですが、このことについての皆さんのお考えを聞かせてください。
ちなみに、OMPは登録人口を増やす目的での定年制の延長には疑問を持っています。確かに、登録人口はリタイヤ組が5年間残るために多くはなるだろうけれども、骨髄移植という治療法にとって、ドナーの高齢化ということは骨髄幹細胞の生着率の低下も伴うわけで、若年層の登録推進策を強化した方が移植医療にとっては好ましいはずなのだけれども。。若い人ほど拒絶反応が軽くなること、どうして財団はもっとPRしないのだろうかな。OMPはすでにドナー経験ありですが、もちろん55歳までに適合のケースがあれば、提供するつもりです。でも、提供すればいいというものでもありません。大切なのは、提供を受ける患者さんが移植医療によって助かる可能性なはず。そのためのドナー候補なんですよね。ドナー登録者数を増やす目的という定年制の延長、皆さんはどうお考えでしょうか。
ちなみに、OMPは登録人口を増やす目的での定年制の延長には疑問を持っています。確かに、登録人口はリタイヤ組が5年間残るために多くはなるだろうけれども、骨髄移植という治療法にとって、ドナーの高齢化ということは骨髄幹細胞の生着率の低下も伴うわけで、若年層の登録推進策を強化した方が移植医療にとっては好ましいはずなのだけれども。。若い人ほど拒絶反応が軽くなること、どうして財団はもっとPRしないのだろうかな。OMPはすでにドナー経験ありですが、もちろん55歳までに適合のケースがあれば、提供するつもりです。でも、提供すればいいというものでもありません。大切なのは、提供を受ける患者さんが移植医療によって助かる可能性なはず。そのためのドナー候補なんですよね。ドナー登録者数を増やす目的という定年制の延長、皆さんはどうお考えでしょうか。
|
|
|
|
コメント(21)
議論の参考のために、以下の情報源情報を掲示させていただきます。
骨髄液移植の基礎知識として
○ 造血幹細胞移植
http://www.kyoto-phu.ac.jp/labo/rinsyou/zouketukansaibouisyoku.html
ドナー年齢55歳についての審議会議事録
○ 02/05/22 第4回厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会議事録
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/05/txt/s0522-2.txt
○ 第17回 厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/03/s0314-3.html
ミニ移植についての情報源
○ 骨髄非破壊的移植の現状と展望
http://www.med.or.jp/jams/symposium/kiroku/117/pdf/117133.pdf
○ 厚生労働省班研究 原田班・高上班 合同班会議
<白血病・MDS に対するミニ移植>
http://sct.umin.jp/minute20020628.pdf
骨髄液移植の基礎知識として
○ 造血幹細胞移植
http://www.kyoto-phu.ac.jp/labo/rinsyou/zouketukansaibouisyoku.html
ドナー年齢55歳についての審議会議事録
○ 02/05/22 第4回厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会議事録
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/05/txt/s0522-2.txt
○ 第17回 厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/03/s0314-3.html
ミニ移植についての情報源
○ 骨髄非破壊的移植の現状と展望
http://www.med.or.jp/jams/symposium/kiroku/117/pdf/117133.pdf
○ 厚生労働省班研究 原田班・高上班 合同班会議
<白血病・MDS に対するミニ移植>
http://sct.umin.jp/minute20020628.pdf
omiさん、横槍なんてとんでもない。ドナー登録はあくまで個人の意志と善意で成り立っているものです。だからこそ、最終意志決定はご本人に委ねられているのですよ。しかしながら、善意とはいえ、骨髄提供には100%の安全性が保証されているわけではありません。それを承知で提供をお願いします、というのが骨髄バンクの制度です。従って、制度を運用する立場からの55歳定年制の導入と、善意をもってこの制度に協力する側からの55歳定年制、本来なら双方に同じコンセンサスがあることで望ましい制度になると思うのですよね。ドナー登録者の多くは、たぶん三次検査の案内が届いた時に、改めて骨髄移植医療というものを骨髄提供する身になって考え、その詳細を知りたくなるはずです。どなたかがおっしゃっていらっしゃいましたが、ドナー登録を軽々に知人には勧めたくない、この気持ちはOMPにはよく分かります。制度を改めれば骨髄移植医療の質が向上するのか、ドナープールを大きくすれば移植例数が増えるのか。善意をもって協力している自分たちの立場で、この問題を見つめていただきたいのです。
kotarouさん、はじめまして。
レシピエントの年齢が高齢となると、残念ながら骨髄移植後の生存率も極端に落ちてしまいます。骨髄移植という治療法も、それが100%の生存率を保証するものではありませんが、患者さんの年齢が若いほど生存率(移植成功率)は高いのが実際です。
骨髄移植財団のページに移植後日数と生存率、そして移植を受けたレシピエントの年代別の資料があります。
http://www.marrow.or.jp/DATA/hi-risk-age.gif
年齢的に移植が難しいのは、移植された骨髄が作り出す新たな免疫細胞が患者さんの細胞を攻撃する程度が重症となりやすいためで、GVHD(移植片対宿主病)という移植後の合併症の影響です。
GVHDの原因となるのは、ドナーの骨髄がつくりだすT細胞というリンパ球なんですが、この細胞は自己と非自己を見分ける仕事をし、非自己の異物(病原菌など)を認識すると同じくリンパ球の一種であるB細胞に指令を出して抗体を作らせます。T細胞は胸腺で形成され、自分の細胞に対して抗体を作らないように教育を受けます。実際には、抗原に対し過度に反応する細胞、あるいはその逆の細胞がアポトーシスという作用により細胞死することにより淘汰され、自分の細胞を見極める能力を獲得していくわけです。
骨髄移植に対する移植後リスクは、担当医の判断かと思いますが、これまでの移植実績から、やはり高齢のケースほど生存率は下がる傾向ははっきりしています。可能性がゼロではないけれど、お父様の病状や他の治療法も考え合わせて、担当医が判断されたのだと思います。
GVHD、移植にあたっては大きな問題ではありますが、さりとて免疫の役割からすると抗原に対して反応するという機能は免疫の要ともいえる働きですし・・・。シゲキさんがおっしゃるように、あとは担当医の判断なのでしょうね。
レシピエントの年齢が高齢となると、残念ながら骨髄移植後の生存率も極端に落ちてしまいます。骨髄移植という治療法も、それが100%の生存率を保証するものではありませんが、患者さんの年齢が若いほど生存率(移植成功率)は高いのが実際です。
骨髄移植財団のページに移植後日数と生存率、そして移植を受けたレシピエントの年代別の資料があります。
http://www.marrow.or.jp/DATA/hi-risk-age.gif
年齢的に移植が難しいのは、移植された骨髄が作り出す新たな免疫細胞が患者さんの細胞を攻撃する程度が重症となりやすいためで、GVHD(移植片対宿主病)という移植後の合併症の影響です。
GVHDの原因となるのは、ドナーの骨髄がつくりだすT細胞というリンパ球なんですが、この細胞は自己と非自己を見分ける仕事をし、非自己の異物(病原菌など)を認識すると同じくリンパ球の一種であるB細胞に指令を出して抗体を作らせます。T細胞は胸腺で形成され、自分の細胞に対して抗体を作らないように教育を受けます。実際には、抗原に対し過度に反応する細胞、あるいはその逆の細胞がアポトーシスという作用により細胞死することにより淘汰され、自分の細胞を見極める能力を獲得していくわけです。
骨髄移植に対する移植後リスクは、担当医の判断かと思いますが、これまでの移植実績から、やはり高齢のケースほど生存率は下がる傾向ははっきりしています。可能性がゼロではないけれど、お父様の病状や他の治療法も考え合わせて、担当医が判断されたのだと思います。
GVHD、移植にあたっては大きな問題ではありますが、さりとて免疫の役割からすると抗原に対して反応するという機能は免疫の要ともいえる働きですし・・・。シゲキさんがおっしゃるように、あとは担当医の判断なのでしょうね。
なかなかシビアなスレッドだと思います。
ドナーの55歳の基準は納得しかねます。
人は戸籍上の年齢と肉体的な年齢に大きな差があると思います。
そしてまずはその目的に疑問があります。
私は2回ほどドナーになった経験があります。
そこで感じたのは、ドクター(Dr)の目的と財団の目的に差があるのでは無いかな?という疑問です。
Drの目的は「患者さんの命を助ける・病気を治す」
財団の目的は・・・
今の形での骨髄移植以外の方法について財団は考えてないように思えるのです。
私は全ての人の目的が「正常な血液を体内で作れない病気になった人を救うこと」になったら、その方法についてもっと広く考え、実行できる思うのです。
例えば造血幹細胞は骨髄以外にも含まれます。それを培養して凍結保存しておくことも可能性はあります。
ドナーの数ではなく細胞のストックをしたら良いと思うのです。
遺伝子が個人情報であるとかの議論も生じるかもしれませんが、病気の人を救う、そのテーマでは障壁を作るべきでは無いと私は思います。
骨髄バンクに登録した人の造血幹細胞を培養して冷凍保存してそのストックが沢山あったらアンディ・フグも亡くならなかったのではないでしょうか。
自分は医療関係者でも無いし、MIXIに参加してまだ一月も経っていないのに生意気を言ってしまいました。
私は自分の造血幹細胞を冷凍保存してもらって自分でも知らないうちに誰かの役に立っても良いと思いますので、ドナーの定年に議論の前に目的が何なのかを考えたいと思いました。
ドナーの55歳の基準は納得しかねます。
人は戸籍上の年齢と肉体的な年齢に大きな差があると思います。
そしてまずはその目的に疑問があります。
私は2回ほどドナーになった経験があります。
そこで感じたのは、ドクター(Dr)の目的と財団の目的に差があるのでは無いかな?という疑問です。
Drの目的は「患者さんの命を助ける・病気を治す」
財団の目的は・・・
今の形での骨髄移植以外の方法について財団は考えてないように思えるのです。
私は全ての人の目的が「正常な血液を体内で作れない病気になった人を救うこと」になったら、その方法についてもっと広く考え、実行できる思うのです。
例えば造血幹細胞は骨髄以外にも含まれます。それを培養して凍結保存しておくことも可能性はあります。
ドナーの数ではなく細胞のストックをしたら良いと思うのです。
遺伝子が個人情報であるとかの議論も生じるかもしれませんが、病気の人を救う、そのテーマでは障壁を作るべきでは無いと私は思います。
骨髄バンクに登録した人の造血幹細胞を培養して冷凍保存してそのストックが沢山あったらアンディ・フグも亡くならなかったのではないでしょうか。
自分は医療関係者でも無いし、MIXIに参加してまだ一月も経っていないのに生意気を言ってしまいました。
私は自分の造血幹細胞を冷凍保存してもらって自分でも知らないうちに誰かの役に立っても良いと思いますので、ドナーの定年に議論の前に目的が何なのかを考えたいと思いました。
こんばんは。バンクドナーさんから移植を受けた元患者です。
ちなみに今は財団のフリーダイヤルも取っている財団のボランティアです。
年齢の引き上げは単純に可能性、チャンスが増えたという点で
良かったなぁ〜と思います。
年齢制限の条件をお話するとガッカリされる方も実際にいますし。。
現在、1年間の保留期間を終えれば2回まで提供いただくことが可能だし、
また、実際1度提供されてる方はの多くは継続登録し、2度目の提供も
希望されてる方が多いのです。
もちろん若い方のドナーリクルート活動も大切ですが
年齢引き上げに反対する理由など、何もないように思います。
>きーちさん
はじめまして。
移植医と骨髄バンクでは目的は同じでも置かれてる立場や
やるべき使命が違うだけではないでしょうか。
骨髄移植推進財団は、骨髄バンクの運営が目的であって事務局ですから。。
もしかしたらきーちさんのおっしゃる財団の役目は
造血幹細胞移植学会や、厚生労働省が取り組んでるのではないでしょうか。
造血幹細胞を凍結保存というのは、末梢血幹細胞の採取の方法のことを
おっしゃってるのでしょうか。
現在のところ骨髄バンクでは末梢血幹細胞採取は認可されてません。
血縁間で行われている末梢血幹細胞移植(PBSCT)は
ドナーの末梢血から幹細胞を多く採取するために、G-CSFという
人工的に白血球を増やすお薬を使いますが、その薬が長期的に
どんな影響があるのか確認できてないため、というのが理由の一つです。
(じゃあ、身内ならいいのか?とも思うのですが。。)
アンディ・フグさんは急性前骨髄球性白血病(AML-M3)、
予後の良いといわれているタイプの白血病でした。
移植を視野に入れていたかどうかもわかりませんし、
幹細胞の冷凍ストックがあったら助かっていたかも。。というのは
全く予測の粋を超えないひとつの可能性に過ぎないのではないでしょうか。。
ちなみに今は財団のフリーダイヤルも取っている財団のボランティアです。
年齢の引き上げは単純に可能性、チャンスが増えたという点で
良かったなぁ〜と思います。
年齢制限の条件をお話するとガッカリされる方も実際にいますし。。
現在、1年間の保留期間を終えれば2回まで提供いただくことが可能だし、
また、実際1度提供されてる方はの多くは継続登録し、2度目の提供も
希望されてる方が多いのです。
もちろん若い方のドナーリクルート活動も大切ですが
年齢引き上げに反対する理由など、何もないように思います。
>きーちさん
はじめまして。
移植医と骨髄バンクでは目的は同じでも置かれてる立場や
やるべき使命が違うだけではないでしょうか。
骨髄移植推進財団は、骨髄バンクの運営が目的であって事務局ですから。。
もしかしたらきーちさんのおっしゃる財団の役目は
造血幹細胞移植学会や、厚生労働省が取り組んでるのではないでしょうか。
造血幹細胞を凍結保存というのは、末梢血幹細胞の採取の方法のことを
おっしゃってるのでしょうか。
現在のところ骨髄バンクでは末梢血幹細胞採取は認可されてません。
血縁間で行われている末梢血幹細胞移植(PBSCT)は
ドナーの末梢血から幹細胞を多く採取するために、G-CSFという
人工的に白血球を増やすお薬を使いますが、その薬が長期的に
どんな影響があるのか確認できてないため、というのが理由の一つです。
(じゃあ、身内ならいいのか?とも思うのですが。。)
アンディ・フグさんは急性前骨髄球性白血病(AML-M3)、
予後の良いといわれているタイプの白血病でした。
移植を視野に入れていたかどうかもわかりませんし、
幹細胞の冷凍ストックがあったら助かっていたかも。。というのは
全く予測の粋を超えないひとつの可能性に過ぎないのではないでしょうか。。
kotarouさん、きーちさん、OMPです。
財団の体質については、推進協議会との間での経緯から、ドナーや患者側の願いとの乖離が存在しているのは事実だと感じています。財団はその設立経緯から、やはり「移植実績」が鍵となっているからでしょう。骨髄液移植治療は、数ある血液疾患の中で確かに重要な治療法の一つであることは間違いないと思いますけども、どの治療法にもリスクは伴います。katarouさんのおっしゃるQOLも大切な視点だと思います。
最近のティッシュエンジニアリング研究では、SE細胞からの組織再生について、さまざまな成果が報告されるようになってきました。末梢血からの造血幹細胞採取にしても、現在の方法ではドナー側の負担が大きいわけですが、SE細胞の今後の研究進展によっては新たな道が開ける可能性も十分に考えられます。ただ、ここで単眼視して欲しくないのは、骨髄移植医療も含め、これはあくまで対症療法だということです。小児白血病がなぜ増加傾向なのか、日本人になぜ成人T細胞白血病が特徴的に多いのか、予防医学の観点からもこの「なぜ」に対する研究が平行して行われるべきだと考えるわけですが、実際はどうなのでしょうかね。生活様式の変化、特に免疫系へのストレスを健康な人も考慮すべきなんでしょうね。
きーちさんご提案の造血幹細胞の冷凍保存、確かに一案かもしれませんが、臍帯血バンクをみてもわかる通り、そのネックは冷凍保存施設の維持管理コストだと思われます。毎年の患者数と維持コストを考えると、現実的にはかなり難しいかもしれません。
きーちさんの「ドナーの定年の議論の前に目的が何なのかを考えたい」というドナー側のご意見、僕もまったく同感です。この医療の目的は、「骨髄移植例数を上げること」ではないはずです。血液疾患患者の命を救うことを第一の目的にしなければ、本末転倒の制度になりかねませんし、このボランティアに参加するドナー登録者もその点を十分に理解したうえで登録して欲しいものです。救いたくても救えない命もある、そうしたリスクを伴う重みのある制度が骨髄バンクなのだと。
財団の体質については、推進協議会との間での経緯から、ドナーや患者側の願いとの乖離が存在しているのは事実だと感じています。財団はその設立経緯から、やはり「移植実績」が鍵となっているからでしょう。骨髄液移植治療は、数ある血液疾患の中で確かに重要な治療法の一つであることは間違いないと思いますけども、どの治療法にもリスクは伴います。katarouさんのおっしゃるQOLも大切な視点だと思います。
最近のティッシュエンジニアリング研究では、SE細胞からの組織再生について、さまざまな成果が報告されるようになってきました。末梢血からの造血幹細胞採取にしても、現在の方法ではドナー側の負担が大きいわけですが、SE細胞の今後の研究進展によっては新たな道が開ける可能性も十分に考えられます。ただ、ここで単眼視して欲しくないのは、骨髄移植医療も含め、これはあくまで対症療法だということです。小児白血病がなぜ増加傾向なのか、日本人になぜ成人T細胞白血病が特徴的に多いのか、予防医学の観点からもこの「なぜ」に対する研究が平行して行われるべきだと考えるわけですが、実際はどうなのでしょうかね。生活様式の変化、特に免疫系へのストレスを健康な人も考慮すべきなんでしょうね。
きーちさんご提案の造血幹細胞の冷凍保存、確かに一案かもしれませんが、臍帯血バンクをみてもわかる通り、そのネックは冷凍保存施設の維持管理コストだと思われます。毎年の患者数と維持コストを考えると、現実的にはかなり難しいかもしれません。
きーちさんの「ドナーの定年の議論の前に目的が何なのかを考えたい」というドナー側のご意見、僕もまったく同感です。この医療の目的は、「骨髄移植例数を上げること」ではないはずです。血液疾患患者の命を救うことを第一の目的にしなければ、本末転倒の制度になりかねませんし、このボランティアに参加するドナー登録者もその点を十分に理解したうえで登録して欲しいものです。救いたくても救えない命もある、そうしたリスクを伴う重みのある制度が骨髄バンクなのだと。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
骨髄バンク 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
骨髄バンクのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6475人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19252人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208306人
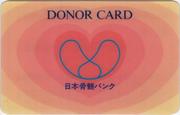



![[dir] 献血](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/19/76/3011976_247s.gif)



















