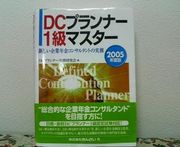自前のコミュがありますが「お客様」の来場が乏しいので、hossieさんのこの場をお借りして……。
『企業における「DC担当者」が備えるべき資格制度』 について
ご意見いただけないでしょうか?
私が知る範囲では、DC(企業年金)に関しては以下の資格があります
DCプランナー(企業年金総合プランナー):日商/きんざい
DCアドバイザー(年金・退職金総合アドバイザー):NPO・DC協会
確定拠出年金アドバイザー:銀行業務検定協会
-------------------
CFP/AFP
ファイナンシャル・プランニング技能士
-------------------
社労士
企業のDC担当者が直接「継続教育」をされる企業もあれば「運管に○投げ」の企業もあります。
『企業においてDC関連業務を推進する担当者としての資格』の要否。その理由についてのご意見を頂きたいのですが。
『企業における「DC担当者」が備えるべき資格制度』 について
ご意見いただけないでしょうか?
私が知る範囲では、DC(企業年金)に関しては以下の資格があります
DCプランナー(企業年金総合プランナー):日商/きんざい
DCアドバイザー(年金・退職金総合アドバイザー):NPO・DC協会
確定拠出年金アドバイザー:銀行業務検定協会
-------------------
CFP/AFP
ファイナンシャル・プランニング技能士
-------------------
社労士
企業のDC担当者が直接「継続教育」をされる企業もあれば「運管に○投げ」の企業もあります。
『企業においてDC関連業務を推進する担当者としての資格』の要否。その理由についてのご意見を頂きたいのですが。
|
|
|
|
コメント(13)
【思いつくところと、これまでに受けた意見】
◆資格は無用という考え◆
・資格を持っていても「勲章にしているだけ」で実務に疎い場合があります。これでは意味が無い。
・実務に長けていれば、また習熟に向けた熱意があれば、法的に「資格は要らない」から、無用だ!
・人事ローテーションで頻繁に交代する場合では「資格」を求めても形骸化するだけなのでは。
◆資格は必要という考え◆
・加入者の立場からすると「一定レベルのスキルを備えた人が担当してくれている」という安心感。
・「資格基準を達成しよう」と言う目的設定が可能。
・「資格保有者は優先して配置できる」という人事面での適材適所の判断が可能
◆現行実施資格に欠けているものは何か◆
・受取方法に関する内容が問われていない
・「売り手側の理念」に基づく科目が多く「加入者目線」での問題解決がテーマにされていない。
◆資格は無用という考え◆
・資格を持っていても「勲章にしているだけ」で実務に疎い場合があります。これでは意味が無い。
・実務に長けていれば、また習熟に向けた熱意があれば、法的に「資格は要らない」から、無用だ!
・人事ローテーションで頻繁に交代する場合では「資格」を求めても形骸化するだけなのでは。
◆資格は必要という考え◆
・加入者の立場からすると「一定レベルのスキルを備えた人が担当してくれている」という安心感。
・「資格基準を達成しよう」と言う目的設定が可能。
・「資格保有者は優先して配置できる」という人事面での適材適所の判断が可能
◆現行実施資格に欠けているものは何か◆
・受取方法に関する内容が問われていない
・「売り手側の理念」に基づく科目が多く「加入者目線」での問題解決がテーマにされていない。
ん、コメント1番乗り!
現行実施資格に欠けているもの、についてコメントを書きます。
たとえば(退職者、中途入社者ともに)ポータビリティの説明が企業側から加入者等に十分出来ていないという現状があります。
制度の仕組み、公的年金、運用の基礎、ライフプランについて知識はお持ちの方でも、実務について上手くさばけていないというか、場合によっては放置ということもあります。
私が会社でよく言われていることですが、「知らないことについて、“せめてどこに聞けばわかるか(教えてもらえるか)”を知っておけ」ということがあります。
「○○に聞いたらわかるから、自分は知らなくてもいい」では困りものですが、企業担当者には実務をこなすスキルを身につけていただきたいです。
資格=知識レベル、であれば2級より1級、DCプランナーに加え社労士も…とあればある程良い、ということになるかもしれません。
しかし企業担当者に必要なのは実務です。今の資格検定試験では大半が知識を問うものです。
そこで、「以下の事例において実施事業主の対応として適切なものはどれか」みたいな設問があっても良いと思います。
きんざいFP1級の面接試験まで行くと行きすぎかもしれませんが…
PS このコミュで、加入者、企業担当者からもっと意見をいただけると、運管側では見えない部分が見えてくるのでは、と期待しています。
現行実施資格に欠けているもの、についてコメントを書きます。
たとえば(退職者、中途入社者ともに)ポータビリティの説明が企業側から加入者等に十分出来ていないという現状があります。
制度の仕組み、公的年金、運用の基礎、ライフプランについて知識はお持ちの方でも、実務について上手くさばけていないというか、場合によっては放置ということもあります。
私が会社でよく言われていることですが、「知らないことについて、“せめてどこに聞けばわかるか(教えてもらえるか)”を知っておけ」ということがあります。
「○○に聞いたらわかるから、自分は知らなくてもいい」では困りものですが、企業担当者には実務をこなすスキルを身につけていただきたいです。
資格=知識レベル、であれば2級より1級、DCプランナーに加え社労士も…とあればある程良い、ということになるかもしれません。
しかし企業担当者に必要なのは実務です。今の資格検定試験では大半が知識を問うものです。
そこで、「以下の事例において実施事業主の対応として適切なものはどれか」みたいな設問があっても良いと思います。
きんざいFP1級の面接試験まで行くと行きすぎかもしれませんが…
PS このコミュで、加入者、企業担当者からもっと意見をいただけると、運管側では見えない部分が見えてくるのでは、と期待しています。
>>[2]
コメントありがとうございます。
>このコミュで、加入者、企業担当者からもっと意見をいただけると、運管側では見えない部分が見えてくるのでは、と期待しています。
同感です!(^^)!
私も、一企業の担当でしかなかったため、「独りよがり」なところがあるのですが、この半年フリーになって他社の教育現場に立ち会う機会に触れて、制度こそ違いあるものの、加入者の理解が不足している点や、企業担当者の悩み(努力不足※1)な点に共通点を見ております。
kounosuke1さんのご指摘も一つであり、「強制移管※2」についても十分に説明できていない担当者にも出会いました。
DCプランナー認定の目的が「(私の理解では)金融機関の導入推進担当者を対象」としている(していた※3)点で、企業担当者の「やらなくてはいけないこと」に及んでいないのではないかという思いです。「『実務』に目を向けた設問」は必要ですね。
このトピをご覧になっている方がいらっしゃれば、「疑問」「困っている事」「意見」を挙げていただきたいと思います。
「恥ずかしがらずに」この点mixiは意見が出し易いのではないかと思いますが…。
------------------
※1:担当者が「怠けている」という意味ではありません。DC専任でなければ、他の日常業務に追われるあまり、責任は感じていても「何を、どのようにすれば良いのか」ということが整理できていない方を多く見かけました。
※2:一般には「自動移換」とされているところを承知で「強制…」としています。「自動…」では加入者が「その気」にならないので。
※3:"きんざい”のテキスト編集が、少しづつ変わってきているようには思いますが。
コメントありがとうございます。
>このコミュで、加入者、企業担当者からもっと意見をいただけると、運管側では見えない部分が見えてくるのでは、と期待しています。
同感です!(^^)!
私も、一企業の担当でしかなかったため、「独りよがり」なところがあるのですが、この半年フリーになって他社の教育現場に立ち会う機会に触れて、制度こそ違いあるものの、加入者の理解が不足している点や、企業担当者の悩み(努力不足※1)な点に共通点を見ております。
kounosuke1さんのご指摘も一つであり、「強制移管※2」についても十分に説明できていない担当者にも出会いました。
DCプランナー認定の目的が「(私の理解では)金融機関の導入推進担当者を対象」としている(していた※3)点で、企業担当者の「やらなくてはいけないこと」に及んでいないのではないかという思いです。「『実務』に目を向けた設問」は必要ですね。
このトピをご覧になっている方がいらっしゃれば、「疑問」「困っている事」「意見」を挙げていただきたいと思います。
「恥ずかしがらずに」この点mixiは意見が出し易いのではないかと思いますが…。
------------------
※1:担当者が「怠けている」という意味ではありません。DC専任でなければ、他の日常業務に追われるあまり、責任は感じていても「何を、どのようにすれば良いのか」ということが整理できていない方を多く見かけました。
※2:一般には「自動移換」とされているところを承知で「強制…」としています。「自動…」では加入者が「その気」にならないので。
※3:"きんざい”のテキスト編集が、少しづつ変わってきているようには思いますが。
kounosuke1です。
試験勉強は得意で資格マニアみたいな人なのに、いろいろ話すと「伝わらない」って人いませんか?
「給付の裁定は記録関連運管に請求する」と分かっている人が、取引銀行(=運営関連運管)に相談してくる。「それは記録関連運管です。転送します」といった具合。
知識豊富なのに実務に疎いという方がいます。とすれば「DCの意義であれば加入者にそれが伝えられるか?」「制度内容であれば、加入者等からの質問に対し制度内容を理解させながら手続きの説明が理解させられるか?」が問題です。
加入者等から問い合わせが多いのは、中途退職、移受換、あたりの手続きと思います。「とりあえず電話しろと言われた」みたいな感じです。
…と、今日は思いつくまま書いてみました。「知識の実務への応用力」が求められるもの、でしょうか。
試験勉強は得意で資格マニアみたいな人なのに、いろいろ話すと「伝わらない」って人いませんか?
「給付の裁定は記録関連運管に請求する」と分かっている人が、取引銀行(=運営関連運管)に相談してくる。「それは記録関連運管です。転送します」といった具合。
知識豊富なのに実務に疎いという方がいます。とすれば「DCの意義であれば加入者にそれが伝えられるか?」「制度内容であれば、加入者等からの質問に対し制度内容を理解させながら手続きの説明が理解させられるか?」が問題です。
加入者等から問い合わせが多いのは、中途退職、移受換、あたりの手続きと思います。「とりあえず電話しろと言われた」みたいな感じです。
…と、今日は思いつくまま書いてみました。「知識の実務への応用力」が求められるもの、でしょうか。
>>[5]
ありがとうございます。
>加入者等から問い合わせが多いのは、中途退職、移受換、あたりの手続きと思います
たまたまですが、「確定拠出年金アドバイザー(銀行業務検定)」の昨年の検定試験問題を見ておりました。
-----------------------
応用問題に
「O社に勤めるEさん30歳が、勤続2年で退職した……。O社はEさんが入社して6カ月後にDCを導入している……。」
問45 EさんがO社に返還すべき金額は…
問46 退職後すぐにDB導入しているN社に入社して加入者になった時に、DCの扱いはどうなる?
------------------------
というような問があります。
この種の出題はDCPにはなかったように思います(最近あまり問題見てないけれど)。
このように『「知識の実務への応用力」が求められるもの』が重要な要素になりますね。
ありがとうございます。
>加入者等から問い合わせが多いのは、中途退職、移受換、あたりの手続きと思います
たまたまですが、「確定拠出年金アドバイザー(銀行業務検定)」の昨年の検定試験問題を見ておりました。
-----------------------
応用問題に
「O社に勤めるEさん30歳が、勤続2年で退職した……。O社はEさんが入社して6カ月後にDCを導入している……。」
問45 EさんがO社に返還すべき金額は…
問46 退職後すぐにDB導入しているN社に入社して加入者になった時に、DCの扱いはどうなる?
------------------------
というような問があります。
この種の出題はDCPにはなかったように思います(最近あまり問題見てないけれど)。
このように『「知識の実務への応用力」が求められるもの』が重要な要素になりますね。
> GORIさん
最初このトピのご趣旨がわからなかったんですが、もしかして新しい資格を練っていらっしゃるとか?
……僕の乏しい経験では企業担当者資格というのはまだちょっと早いような。
そもそも収益を確保して生き残ることが至上命題の企業が、まだニッチな業務の担当者についての資格に関心を持つ可能性は低いと思います。
結局、加入者と企業担当者の間を取り持つのが運管の役割と割り切っています。
うちは、コールセンター、ウェブは外部委託していますが、それでも僕が中にいるときは一日二桁の企業担当者からの架電を受けます。
相談の大部分は kounosuke1 さんのご指摘レベルのものですが、それってRKのWeb上で公開されている事務マニュアルや FAQ でカバーしているものです。
丁寧にそちらに担当者を誘導すると、真面目な方、余裕ある方はかなりレベルアップされます。
ただ、それって結局事務の領域です。
ここがくせ者で、僕の業界で過去3回ほどRKを跨いだ情報交換会を開いていますが、なんと40社ほと集まったメンバー、同じ運管なのにNとJで言葉の意味が通じないという事態が発生しました。
根本的に業務フローの考え方が違っていたんです。
さらにうちは、4つのうち、もう一つのRKさんにも繋いでますが、そちらについても同じことが言えます。
ついでに言えば、僕、息子、娘の三人が別々の運管でDCに加入していますが、インターフェイス、手続き、用語がすべて微妙に異なります。
魚類とほ乳類、根本的に違う生物ですが、海の中ではサメとイルカは外部からは見分けがつきにくい形態に進化(?)してます。最近、二大RKで最も使いやすいと言われる運管さん二社のウェブが似た形になってきているのを見て、おそらくこの業界のユーザー向けのインターフェイスもそのような形に収斂していくと思いますが、それが5年後なのか50年後なのか、今の僕にはわかりません。
最初このトピのご趣旨がわからなかったんですが、もしかして新しい資格を練っていらっしゃるとか?
……僕の乏しい経験では企業担当者資格というのはまだちょっと早いような。
そもそも収益を確保して生き残ることが至上命題の企業が、まだニッチな業務の担当者についての資格に関心を持つ可能性は低いと思います。
結局、加入者と企業担当者の間を取り持つのが運管の役割と割り切っています。
うちは、コールセンター、ウェブは外部委託していますが、それでも僕が中にいるときは一日二桁の企業担当者からの架電を受けます。
相談の大部分は kounosuke1 さんのご指摘レベルのものですが、それってRKのWeb上で公開されている事務マニュアルや FAQ でカバーしているものです。
丁寧にそちらに担当者を誘導すると、真面目な方、余裕ある方はかなりレベルアップされます。
ただ、それって結局事務の領域です。
ここがくせ者で、僕の業界で過去3回ほどRKを跨いだ情報交換会を開いていますが、なんと40社ほと集まったメンバー、同じ運管なのにNとJで言葉の意味が通じないという事態が発生しました。
根本的に業務フローの考え方が違っていたんです。
さらにうちは、4つのうち、もう一つのRKさんにも繋いでますが、そちらについても同じことが言えます。
ついでに言えば、僕、息子、娘の三人が別々の運管でDCに加入していますが、インターフェイス、手続き、用語がすべて微妙に異なります。
魚類とほ乳類、根本的に違う生物ですが、海の中ではサメとイルカは外部からは見分けがつきにくい形態に進化(?)してます。最近、二大RKで最も使いやすいと言われる運管さん二社のウェブが似た形になってきているのを見て、おそらくこの業界のユーザー向けのインターフェイスもそのような形に収斂していくと思いますが、それが5年後なのか50年後なのか、今の僕にはわかりません。
>>[7]
>…もしかして新しい資格を練っていらっしゃるとか?
実は、私が、ではなくて、「練っているところ」から意見を求められてまして…。
「練っているところ」には、「後発である以上、既存のDCプランナーや、DCアドバイザー、銀行業務検定などの出題には無いものを取り込まないといけない」と意見を言ったのですが、さて、具体的には何があるかというと、私が知るのは導入時に7社のプレゼンを受けたことと、導入した運管と自社の範囲しか知らないことから、情報が無くて。
>…同じ運管なのにNとJで言葉の意味が通じないという事態……。※
>…根本的に業務フローの考え方が違って…。
このことは、「運管選択時の重要要素」ですね。身をもって体験しました。
また、講師派遣を業としている会社の方が、派遣するFPの教育で頭を痛めておられました。
このようなことは「練っているところ」は全く判っていないので、判ってもらうための意見を言おうと思っています。
現在のお立場で、企業担当者が「備えておいたら良い事項」についてご教授いただけたら有り難いです。
※ J N
────────┼───────
スイッチング │ 預け替え
(掛金)割合変更 │ 配分変更 他には?
>…もしかして新しい資格を練っていらっしゃるとか?
実は、私が、ではなくて、「練っているところ」から意見を求められてまして…。
「練っているところ」には、「後発である以上、既存のDCプランナーや、DCアドバイザー、銀行業務検定などの出題には無いものを取り込まないといけない」と意見を言ったのですが、さて、具体的には何があるかというと、私が知るのは導入時に7社のプレゼンを受けたことと、導入した運管と自社の範囲しか知らないことから、情報が無くて。
>…同じ運管なのにNとJで言葉の意味が通じないという事態……。※
>…根本的に業務フローの考え方が違って…。
このことは、「運管選択時の重要要素」ですね。身をもって体験しました。
また、講師派遣を業としている会社の方が、派遣するFPの教育で頭を痛めておられました。
このようなことは「練っているところ」は全く判っていないので、判ってもらうための意見を言おうと思っています。
現在のお立場で、企業担当者が「備えておいたら良い事項」についてご教授いただけたら有り難いです。
※ J N
────────┼───────
スイッチング │ 預け替え
(掛金)割合変更 │ 配分変更 他には?
>>[8]
うーん。……そもそもこれ以上新たな資格があっても仕方がないと僕は思います。
複数の大手の運管の方と話をしても、名刺の肩書きに1級DCプランナーがあるかどうかで相手の技量を推定するのは同じでした。
これは形から入るとかいうのではなく、資格を持っていない人の場合、こちらがわかっていると思って話をしても、理解できていないということが何度もあったという共通の経験が僕らの業界の人間にはあるからです。
その意味では1級DCプランナーは、その人のスキルの裏付けとなる資格として完全に業界で認知されていますし、事業主もそういう目で見ます。
業務に携わる者として深掘りすれば、受託数を増やすには社労士、欲を言えばアクチュアリー(企業年金)、投資教育・商品選定には証券アナリストの知識が必要ですが、これらは1級DCプランナーに包摂され、かつ試験範囲にはこれらのうちDCに必要なパーツがバランス良く並んでいます。うちの息子はアクチュアリーの仕事をしており、証券アナリストのブラック・ショールズ方程式なんかを良くいじってますが、DC部分の議論では負ける気がしません。
ただDCの継続教育やってると、個別相談の要望が増えてきましたから、1級DCプランナー以外で事業主目線でもう一つ重要な資格を選べと言われれば僕は証券アナリストを推します。
で、GORIさん 、僕のRKの業務フローの書き込み、ちょっと誤解なさってますね。
ますJで「割合変更」という言葉は使っていません。スイッチング、配分変更は共通用語です。Jのマニュアルにも業務開始時からそう記載されています。SJさんも同じですし、おそらくBさんもそうでしょう。
そんな単語レベルのことを書いたのではありません。
僕が言いたかったのは、もとのシステムの理念が根本的に違うため、つなげている運管の事務フローも異なる形にならざるを得ない。このため、例えば「バック事務」があるN系の運管の場合、「給付・裁定事務」という認識なのに、J系の運管の場合「制度設計や継続教育」という認識で話が通じないといった事象がいくつかあったということです。
この件については、最近、ある大手運管のシステムの方とお話しした際、「あそこまで劇的に違うとは思わなかった」と仰ってましたので、僕だけの認識ではないです。
DCアドバイザーの出題内容が実際の事務部分をフォローするような内容を含んでいますが、この部分、Jさん、Nさん、SJさんそれぞれ事業主向けマニュアルで、自社のシステム理念に沿った形でより詳細な解説を提供してくれています。そういう意味で汎用知識を得るための資格試験にはそぐわないんじゃないかな。
この辺り、あるいはHさんがいたFさんのとこに昨年入ったS君が詳しいかも。
うーん。……そもそもこれ以上新たな資格があっても仕方がないと僕は思います。
複数の大手の運管の方と話をしても、名刺の肩書きに1級DCプランナーがあるかどうかで相手の技量を推定するのは同じでした。
これは形から入るとかいうのではなく、資格を持っていない人の場合、こちらがわかっていると思って話をしても、理解できていないということが何度もあったという共通の経験が僕らの業界の人間にはあるからです。
その意味では1級DCプランナーは、その人のスキルの裏付けとなる資格として完全に業界で認知されていますし、事業主もそういう目で見ます。
業務に携わる者として深掘りすれば、受託数を増やすには社労士、欲を言えばアクチュアリー(企業年金)、投資教育・商品選定には証券アナリストの知識が必要ですが、これらは1級DCプランナーに包摂され、かつ試験範囲にはこれらのうちDCに必要なパーツがバランス良く並んでいます。うちの息子はアクチュアリーの仕事をしており、証券アナリストのブラック・ショールズ方程式なんかを良くいじってますが、DC部分の議論では負ける気がしません。
ただDCの継続教育やってると、個別相談の要望が増えてきましたから、1級DCプランナー以外で事業主目線でもう一つ重要な資格を選べと言われれば僕は証券アナリストを推します。
で、GORIさん 、僕のRKの業務フローの書き込み、ちょっと誤解なさってますね。
ますJで「割合変更」という言葉は使っていません。スイッチング、配分変更は共通用語です。Jのマニュアルにも業務開始時からそう記載されています。SJさんも同じですし、おそらくBさんもそうでしょう。
そんな単語レベルのことを書いたのではありません。
僕が言いたかったのは、もとのシステムの理念が根本的に違うため、つなげている運管の事務フローも異なる形にならざるを得ない。このため、例えば「バック事務」があるN系の運管の場合、「給付・裁定事務」という認識なのに、J系の運管の場合「制度設計や継続教育」という認識で話が通じないといった事象がいくつかあったということです。
この件については、最近、ある大手運管のシステムの方とお話しした際、「あそこまで劇的に違うとは思わなかった」と仰ってましたので、僕だけの認識ではないです。
DCアドバイザーの出題内容が実際の事務部分をフォローするような内容を含んでいますが、この部分、Jさん、Nさん、SJさんそれぞれ事業主向けマニュアルで、自社のシステム理念に沿った形でより詳細な解説を提供してくれています。そういう意味で汎用知識を得るための資格試験にはそぐわないんじゃないかな。
この辺り、あるいはHさんがいたFさんのとこに昨年入ったS君が詳しいかも。
>>[9]
ありがとうございます。
>Jで「割合変更」という言葉は使っていません
この辺り、自分でも確信を持ってなかったのですが、J系とN系に出向いて講習を担当しているFPさんの受け売りであります。
きっちり照合していませんが、私のJ系資料と我が息子のN系資料では違っていました。もしかすると運管の違いかと。
>例えば「バック事務」があるN系の運管の場合、「給付・裁定事務」という認識なのに、J系の運管の場合「制度設計や継続教育」という認識で…
これは承知しているつもりです。
この二系列しか知らないのですが、自社に制度導入する際に7社の比較検討した際に認識しております。「一長一短」であったことは先に述べたかと…。
>そもそもこれ以上新たな資格があっても仕方がないと…
さて、資格制度ですが、このご意見には異論はありません。
ただ、「作る」と言っているところから「意見を求められている」以上、言うことだけは言っておかないと、という気持ちでおります。
おっしゃる通り、DCプランナーがあれば、一般的認知されているので間に合うとは思いますが、法的にはカバーできていても、実務面ではご指摘がある通り、カバーできていません。補うとしたらこの辺りかと思うのですが…。
なお、企業のDC担当には、アクチャリーやアナリストの資格は必要ないと考えています。DB担当なら有っても良いかとは思いますが…。
私個人としてはDCの担当に高いハードルを課すのは、あまり賛成できません。
今後の意見として、加入者に接する担当者が備えるべき、「加入者の信頼を得るための要素」を探っているところです。
少なくともコールセンターや運管に丸投げしないスキルは備えて欲しいものだと。
ご案内のSさんとは残念ながら面識記憶が無いのですが、昨年「DCマネジメント」の編集には参加していますので、代表のS女史にも、今一度確認してみることにします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
>Jで「割合変更」という言葉は使っていません
この辺り、自分でも確信を持ってなかったのですが、J系とN系に出向いて講習を担当しているFPさんの受け売りであります。
きっちり照合していませんが、私のJ系資料と我が息子のN系資料では違っていました。もしかすると運管の違いかと。
>例えば「バック事務」があるN系の運管の場合、「給付・裁定事務」という認識なのに、J系の運管の場合「制度設計や継続教育」という認識で…
これは承知しているつもりです。
この二系列しか知らないのですが、自社に制度導入する際に7社の比較検討した際に認識しております。「一長一短」であったことは先に述べたかと…。
>そもそもこれ以上新たな資格があっても仕方がないと…
さて、資格制度ですが、このご意見には異論はありません。
ただ、「作る」と言っているところから「意見を求められている」以上、言うことだけは言っておかないと、という気持ちでおります。
おっしゃる通り、DCプランナーがあれば、一般的認知されているので間に合うとは思いますが、法的にはカバーできていても、実務面ではご指摘がある通り、カバーできていません。補うとしたらこの辺りかと思うのですが…。
なお、企業のDC担当には、アクチャリーやアナリストの資格は必要ないと考えています。DB担当なら有っても良いかとは思いますが…。
私個人としてはDCの担当に高いハードルを課すのは、あまり賛成できません。
今後の意見として、加入者に接する担当者が備えるべき、「加入者の信頼を得るための要素」を探っているところです。
少なくともコールセンターや運管に丸投げしないスキルは備えて欲しいものだと。
ご案内のSさんとは残念ながら面識記憶が無いのですが、昨年「DCマネジメント」の編集には参加していますので、代表のS女史にも、今一度確認してみることにします。
ありがとうございました。
DC担当者の資格認定制度についての会議が昨日ありました。
kounosuke1さん四次元の王者さんから頂いたご意見を参考に発言して参りました。ありがとうございました。
目的は「加入者・受給者の高まる関心に的確に対応するための能力開発と資質向上」ということで、既存のDCプランナー、DCアドバイザー、確定拠出年金アドバイザーではカバーできていない「制度実施者の育成」というところに。
「2,3年で担当者が交替する例が多く、その都度レベルダウンが起こっている現状と運管指導ではカバーしきれないスキル向上」がねらいに。
対象は「企業で実務を担当している部門在籍者」に限られる見込み。
「法令・規約の読み方のコツ」を追加し、「自社の規約の重要部分を承知する」ことを提案しましたが、運管系委員からも認めていただけました。
これ以上はちょいと公開する権限もなく了解も取れていないので、「この場」ではご勘弁を。
kounosuke1さん四次元の王者さんから頂いたご意見を参考に発言して参りました。ありがとうございました。
目的は「加入者・受給者の高まる関心に的確に対応するための能力開発と資質向上」ということで、既存のDCプランナー、DCアドバイザー、確定拠出年金アドバイザーではカバーできていない「制度実施者の育成」というところに。
「2,3年で担当者が交替する例が多く、その都度レベルダウンが起こっている現状と運管指導ではカバーしきれないスキル向上」がねらいに。
対象は「企業で実務を担当している部門在籍者」に限られる見込み。
「法令・規約の読み方のコツ」を追加し、「自社の規約の重要部分を承知する」ことを提案しましたが、運管系委員からも認めていただけました。
これ以上はちょいと公開する権限もなく了解も取れていないので、「この場」ではご勘弁を。
GORIさんこんばんは。
>「2,3年で担当者が交替する例が多く、その都度レベルダウンが起こっている現状と運管指導ではカバーしきれないスキル向上」がねらいに。
現実として大半の会社で起こっていることです。「なんでこんな設計にしたんだ」と言われることもしばしばで… この部分に牽制できれば導入企業としての正しい取り組みができると期待できます。
>対象は「企業で実務を担当している部門在籍者」に限られる見込み。
ここは私のようないわゆる「DCを売る側」も対象にしてほしいです。スキル向上しなくてはならない人以外にさせる責任がある人(DCを売る側)双方が理解すればより制度発展が期待できます。
と、思うままに書いておりますが、制度発展のための取り組みは大歓迎です。
>「2,3年で担当者が交替する例が多く、その都度レベルダウンが起こっている現状と運管指導ではカバーしきれないスキル向上」がねらいに。
現実として大半の会社で起こっていることです。「なんでこんな設計にしたんだ」と言われることもしばしばで… この部分に牽制できれば導入企業としての正しい取り組みができると期待できます。
>対象は「企業で実務を担当している部門在籍者」に限られる見込み。
ここは私のようないわゆる「DCを売る側」も対象にしてほしいです。スキル向上しなくてはならない人以外にさせる責任がある人(DCを売る側)双方が理解すればより制度発展が期待できます。
と、思うままに書いておりますが、制度発展のための取り組みは大歓迎です。
>>[12]
>「DCを売る側」も対象にしてほしいです
「売り手側の担当者交代によるレベルダウン」も起きているようで、各運管を見まわしても、導入当初から関わっていらした方が、ほぼ現職についておられないのが現状とお聞きします。
9月に退職されたN社のOさん辺りが最後かということですが…。
今回「使い手側」が資格制度を考えることになった背景には、DCプランナー他が、元々「使い手側」に目が向いていなかったこともあろうかと考えています。
DCプランナーの受験者ももっと増えて良いのではないかと思いますが、「売り手」も担当者の充実には、引き続き努めて欲しいと思います。
実は、日曜日に銀行業務検定協会の「確定拠出年金アドバイザー試験」を体験してきました。出題の傾向が「導入よりは、実施、移換、給付」に寄っていましたが、今後この傾向は強くなるのでしょうね。ただ、受験者数の少なさに、ちょっとがっかり。
相互の資格制度が、刺激し合って伸びて行くことも今後の期待になろうかと思います。
>「DCを売る側」も対象にしてほしいです
「売り手側の担当者交代によるレベルダウン」も起きているようで、各運管を見まわしても、導入当初から関わっていらした方が、ほぼ現職についておられないのが現状とお聞きします。
9月に退職されたN社のOさん辺りが最後かということですが…。
今回「使い手側」が資格制度を考えることになった背景には、DCプランナー他が、元々「使い手側」に目が向いていなかったこともあろうかと考えています。
DCプランナーの受験者ももっと増えて良いのではないかと思いますが、「売り手」も担当者の充実には、引き続き努めて欲しいと思います。
実は、日曜日に銀行業務検定協会の「確定拠出年金アドバイザー試験」を体験してきました。出題の傾向が「導入よりは、実施、移換、給付」に寄っていましたが、今後この傾向は強くなるのでしょうね。ただ、受験者数の少なさに、ちょっとがっかり。
相互の資格制度が、刺激し合って伸びて行くことも今後の期待になろうかと思います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ここで学ぼう確定拠出年金(DC) 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ここで学ぼう確定拠出年金(DC)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 2位
- 広島東洋カープ
- 55343人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37148人