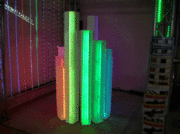と言う方向に向かってる様です。
http://
http://
(現時点で環境省なのかどこの推進なのか等は不明です)
未だ詳細不明ですが、医療・産業用途などLED等に置き換え出来ない用途以外では、一般
照明も演出照明(他業務用途)もエネルギー変換効率の悪い白熱電球から、効率の良い/
省エネであるLEDや放電管(蛍光灯他)に移行する事に成るのは、京都議定書の数値目標
を達成する上で最早必然の様です。
http://
・・・白熱電球ならではの良さ(暖かみであるとか各種特性)は、例えば色温度/演色性
などは蛍光灯やLED等で再現できたとしても、例えば調光を手軽に行える様な事や、又雰
囲気と言う様な感覚的な要素は失われる事に成ります。
(雰囲気とは、例えば商用電源は50/60Hz周期の正弦波で点灯/消灯を繰り返すのに対し、
フィラメントは直ぐにOn/Offする特性では無い為に、結果人の目には残像として殆どチラ
つかない安定した状態に見える灯りであるとか、エネルギー変換効率が悪い分熱となって
出て来る為に、見た目の色温度の暖かみだけでなく実際暖かいランプで有る事など)
時代の流れとしてこれは確かに必然的な事だと思われますが、そうなる前にLEDや放電管で、
いにしえの白熱電球と同様の手軽さで有るとか雰囲気を得られる様な、主に点灯回路の手
法が何処まで開発されるかどうかだと思います。
(例えばOn/Offの応答性に関しては、ボール型インバーター方式蛍光灯は既に白熱電球と
同じ感覚で使えますが、しかし調光機能は特殊な照明器具で無ければ得られません・・・
LEDの場合順方向電圧降下/電流が有る為に、電球の様な連続的な調光には工夫を要する等)
因みにインバーター式蛍光灯で白熱電球の様な微妙なFadeIn/Outする点灯・消灯を行
わせる回路処理はかなり面倒ですが、LEDの場合未だ簡単に可能です。
(今後多数のLEDを組み込んだ電球タイプのランプが今よりも遙かに単価下がる事に成
れば、より普及する事に成りますが、それに電球の様なFadeIn/Outする様なギミッ
クを盛り込むかどうかは、単にコストの問題です)
未だ具体的にどの様な規制(製造・販売)に成るのか解りませんし、又罰則込みと言う事
に成るのか(デッドストック的な物を所持してるだけで駄目であるとか)等も皆目分かり
ませんが、まあ既に規制される方向に進んでるのは冒頭の通りです。
照明器具などを開発する側も利用する側も、その積もりで居る他無いでしょうね・・・。
(これは照明器具などだけでなく、家電他様々な電化製品も省エネ化が義務づけられる
流れに成るのも必然だと思われます)
・・・何だか未来世紀ブラジルの世界です(苦笑)。
http://
http://
因みに照明関係だと既に各種標識や街灯などが太陽電池(及び蓄電池)と組み合わされて
ますが、太陽光/ソーラーパワーはタダであり、エネルギー消費しない等と思われてますが、
実際には太陽電池他システムを製造する為にかなりのエネルギーが使われてる事や、又
初期投資やランニングコスト(蓄電池の交換・太陽光パネルの清掃など)少なくは無いと
言う事が忘れられてます。
(住宅や施設向けの大型の太陽光発電装置は、決してペイしないと言われてますし
>導入に対しての国や自治体からの補助金が有るからこそ成立してますが)
例えばこれは都合良く見積もった内容として:
http://
・・・後放電管やLEDには環境負荷物質も含まれてると言う事を忘れては成りません。
(蛍光灯は水銀であり、LEDは砒素他>毒性低い状態でも、大量に使われる事での問題)
http://
http://
(現時点で環境省なのかどこの推進なのか等は不明です)
未だ詳細不明ですが、医療・産業用途などLED等に置き換え出来ない用途以外では、一般
照明も演出照明(他業務用途)もエネルギー変換効率の悪い白熱電球から、効率の良い/
省エネであるLEDや放電管(蛍光灯他)に移行する事に成るのは、京都議定書の数値目標
を達成する上で最早必然の様です。
http://
・・・白熱電球ならではの良さ(暖かみであるとか各種特性)は、例えば色温度/演色性
などは蛍光灯やLED等で再現できたとしても、例えば調光を手軽に行える様な事や、又雰
囲気と言う様な感覚的な要素は失われる事に成ります。
(雰囲気とは、例えば商用電源は50/60Hz周期の正弦波で点灯/消灯を繰り返すのに対し、
フィラメントは直ぐにOn/Offする特性では無い為に、結果人の目には残像として殆どチラ
つかない安定した状態に見える灯りであるとか、エネルギー変換効率が悪い分熱となって
出て来る為に、見た目の色温度の暖かみだけでなく実際暖かいランプで有る事など)
時代の流れとしてこれは確かに必然的な事だと思われますが、そうなる前にLEDや放電管で、
いにしえの白熱電球と同様の手軽さで有るとか雰囲気を得られる様な、主に点灯回路の手
法が何処まで開発されるかどうかだと思います。
(例えばOn/Offの応答性に関しては、ボール型インバーター方式蛍光灯は既に白熱電球と
同じ感覚で使えますが、しかし調光機能は特殊な照明器具で無ければ得られません・・・
LEDの場合順方向電圧降下/電流が有る為に、電球の様な連続的な調光には工夫を要する等)
因みにインバーター式蛍光灯で白熱電球の様な微妙なFadeIn/Outする点灯・消灯を行
わせる回路処理はかなり面倒ですが、LEDの場合未だ簡単に可能です。
(今後多数のLEDを組み込んだ電球タイプのランプが今よりも遙かに単価下がる事に成
れば、より普及する事に成りますが、それに電球の様なFadeIn/Outする様なギミッ
クを盛り込むかどうかは、単にコストの問題です)
未だ具体的にどの様な規制(製造・販売)に成るのか解りませんし、又罰則込みと言う事
に成るのか(デッドストック的な物を所持してるだけで駄目であるとか)等も皆目分かり
ませんが、まあ既に規制される方向に進んでるのは冒頭の通りです。
照明器具などを開発する側も利用する側も、その積もりで居る他無いでしょうね・・・。
(これは照明器具などだけでなく、家電他様々な電化製品も省エネ化が義務づけられる
流れに成るのも必然だと思われます)
・・・何だか未来世紀ブラジルの世界です(苦笑)。
http://
http://
因みに照明関係だと既に各種標識や街灯などが太陽電池(及び蓄電池)と組み合わされて
ますが、太陽光/ソーラーパワーはタダであり、エネルギー消費しない等と思われてますが、
実際には太陽電池他システムを製造する為にかなりのエネルギーが使われてる事や、又
初期投資やランニングコスト(蓄電池の交換・太陽光パネルの清掃など)少なくは無いと
言う事が忘れられてます。
(住宅や施設向けの大型の太陽光発電装置は、決してペイしないと言われてますし
>導入に対しての国や自治体からの補助金が有るからこそ成立してますが)
例えばこれは都合良く見積もった内容として:
http://
・・・後放電管やLEDには環境負荷物質も含まれてると言う事を忘れては成りません。
(蛍光灯は水銀であり、LEDは砒素他>毒性低い状態でも、大量に使われる事での問題)
|
|
|
|
コメント(19)
照明デザイナーとして、意見させていただくなら、白熱灯無しはありえません!
エネルギー問題で光をターゲットにするのは、分かりやすいのでキャンペーンとしてはいいでしょう。
何しろ、照明つけることを「電気つけて」っていうもの。
でも、一番電気つかってるのは空調でしょ?
照明で、キャンペーンやるなら、光源の使い方を提案すべきだと思う。
昼に大量に電気を使用するオフィスや工場などは、蛍光灯でいいでしょう。
点光源はLEDにしていけばいいでしょう。
演色性をそれほど求めないところだったら、放電灯でもいいでしょう。
でも、白熱灯の多くは夜つかうことが多いんじゃないかな。
東京電力の人と話をしていたときに、「誤解を恐れずに言ってしまえば、夜の電気は捨ててる状態」っていってた。
実際には捨ててはいないと思うけど、様はあまっているってことでしょう。
この夜の電力を有効活用して、昼の電力不足に当てようとするのが、エコキュートなんだから。
つまり、白熱灯はつかわれるべき夜に白熱灯やめても、あまり効果なしなんでは?
LEDや蛍光灯が嫌いなわけではないです。
全部なんでもかんでもイッショクタってのが...
LEDもけっこう良くなってきました。
下は、先日やったLEDだけの展示ブース。
演色性も随分よくなってきました。
http://www.info-station.net/blog/blog/entry/407.php#extended
エネルギー問題で光をターゲットにするのは、分かりやすいのでキャンペーンとしてはいいでしょう。
何しろ、照明つけることを「電気つけて」っていうもの。
でも、一番電気つかってるのは空調でしょ?
照明で、キャンペーンやるなら、光源の使い方を提案すべきだと思う。
昼に大量に電気を使用するオフィスや工場などは、蛍光灯でいいでしょう。
点光源はLEDにしていけばいいでしょう。
演色性をそれほど求めないところだったら、放電灯でもいいでしょう。
でも、白熱灯の多くは夜つかうことが多いんじゃないかな。
東京電力の人と話をしていたときに、「誤解を恐れずに言ってしまえば、夜の電気は捨ててる状態」っていってた。
実際には捨ててはいないと思うけど、様はあまっているってことでしょう。
この夜の電力を有効活用して、昼の電力不足に当てようとするのが、エコキュートなんだから。
つまり、白熱灯はつかわれるべき夜に白熱灯やめても、あまり効果なしなんでは?
LEDや蛍光灯が嫌いなわけではないです。
全部なんでもかんでもイッショクタってのが...
LEDもけっこう良くなってきました。
下は、先日やったLEDだけの展示ブース。
演色性も随分よくなってきました。
http://www.info-station.net/blog/blog/entry/407.php#extended
>エネルギー問題で光をターゲットにするのは、分かりやすいのでキャンペーンとしてはいいでしょう。
・・・その通りでしょうね・・・それと色んなしがらみが無い事なども。
(まあ解りやすいスケープ・ゴートですね・・・ただ解りやすいだけに、それが色んな
分野に規制を拡げる事のきっかけにも成り得ますが)
最初TVのニュースでそういう話題が出ていたのを何となく見てました。日本での言い出
しっぺが誰/何処なのか不明ですが、欧州での規制の右へ倣へ・・・だったかもです。
(Philipsのお膝元ですが)
以下にその経緯が有ると思われます(”白熱電球 欧州 規制”):
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rls=GGLG%2CGGLG%3A2007-04%2CGGLG%3Aja&q=%E7%99%BD%E7%86%B1%E9%9B%BB%E7%90%83%E3%80%80%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E3%80%80%E8%A6%8F%E5%88%B6&lr=
欧州の環境規制はどんどん厳しく成ってますが、既に実行されたRoHSに続いて、今度は
Reachと言う規制が出来た様です(RoHS程直接では無いけど、間接的には環境負荷物質
の更なる規制に繋がる内容の様です)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/RoHS
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rls=GGLG%2CGGLG%3A2007-04%2CGGLG%3Aja&q=RoHS+europa.eu&lr=
http://ja.wikipedia.org/wiki/REACH
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2007-04,GGLG:ja&q=reach+eu
白熱電球の製造・販売が規制を受けないで済む方向性は、先ずそれを絶対的に必要とす
る医療器具や産業関係は除外される事に成ると思われますが(置き換え出来る物が無い
と言う理由にて)、その必要が無い一般用途は、電球業界?の力が強くない限り、お上
の意向に抗う事は難しいでしょう。
http://www.jelma.or.jp/about/memberlist.html
(上記でお解りの通り、大量生産の大手と特殊対応の中小と言う感じですが)
店舗照明などの業務用途に関しては、対抗勢力としては先の電球業界やディスプレイ業
界等諸々が関わってくると思われますが、発言力の高い企業や政治家(所謂族議員的な
存在/スポークスマン的な存在として)が居ないと、これ又難しいと思われます。
未だ具体的な規制の枠組みなど何も出来てない様ですが(3年先より等という骨子は既
に作られつつ有る様ですが)、冒頭の通り生け贄としては余りにも解りやすいので、そ
れを阻止する働きが無ければ、どんどん規制する方向への一途に成ると思われます。
>点光源はLEDにしていけばいいでしょう。
LEDは基本的に/構造的に点光源ですが、砲弾型等のレンズ込みでは無い面実装や、基台
の上に多数のダイ(半導体/発光部)を並べたり、若しくはフロストガラス等の拡散する
素材を使う事で、かなり面光源で有るとか、又は電球の様な光り方(艶消しの電球の様
に中心にタングステンの強い発光が有り、その周りに輝度変化や淡い光り方する様な演
出など)にする事も可能なので、今後白熱電球の見た目そのもののLED電球と言うのも、
何処かが出してくると思われます。
(郷愁にせよ白熱電球の雰囲気が求められる需要が有るのなら、そういう物が開発され
るのも必然です>どこまで白熱電球に似せるのかは、技術よりもコストの問題です)
因みに舞台照明にも、既にかなりLED(砲弾型かLuxeonを多数使用したタイプ等)灯体
が使われ出してます(当然既存の照明と同等に使える面光源やスポット光源など各種)。
・・・現時点では、そういう諸々の技術的な事よりも価格の問題なので、白熱電球の規
制と言う事に成れば、必然的にLED灯体の生産量も上がり、コストも下がると思われます。
(舞台照明や店舗照明用のLED灯体等は、まだまだ非常に高価ですけど)
・・・その通りでしょうね・・・それと色んなしがらみが無い事なども。
(まあ解りやすいスケープ・ゴートですね・・・ただ解りやすいだけに、それが色んな
分野に規制を拡げる事のきっかけにも成り得ますが)
最初TVのニュースでそういう話題が出ていたのを何となく見てました。日本での言い出
しっぺが誰/何処なのか不明ですが、欧州での規制の右へ倣へ・・・だったかもです。
(Philipsのお膝元ですが)
以下にその経緯が有ると思われます(”白熱電球 欧州 規制”):
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rls=GGLG%2CGGLG%3A2007-04%2CGGLG%3Aja&q=%E7%99%BD%E7%86%B1%E9%9B%BB%E7%90%83%E3%80%80%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E3%80%80%E8%A6%8F%E5%88%B6&lr=
欧州の環境規制はどんどん厳しく成ってますが、既に実行されたRoHSに続いて、今度は
Reachと言う規制が出来た様です(RoHS程直接では無いけど、間接的には環境負荷物質
の更なる規制に繋がる内容の様です)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/RoHS
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rls=GGLG%2CGGLG%3A2007-04%2CGGLG%3Aja&q=RoHS+europa.eu&lr=
http://ja.wikipedia.org/wiki/REACH
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2007-04,GGLG:ja&q=reach+eu
白熱電球の製造・販売が規制を受けないで済む方向性は、先ずそれを絶対的に必要とす
る医療器具や産業関係は除外される事に成ると思われますが(置き換え出来る物が無い
と言う理由にて)、その必要が無い一般用途は、電球業界?の力が強くない限り、お上
の意向に抗う事は難しいでしょう。
http://www.jelma.or.jp/about/memberlist.html
(上記でお解りの通り、大量生産の大手と特殊対応の中小と言う感じですが)
店舗照明などの業務用途に関しては、対抗勢力としては先の電球業界やディスプレイ業
界等諸々が関わってくると思われますが、発言力の高い企業や政治家(所謂族議員的な
存在/スポークスマン的な存在として)が居ないと、これ又難しいと思われます。
未だ具体的な規制の枠組みなど何も出来てない様ですが(3年先より等という骨子は既
に作られつつ有る様ですが)、冒頭の通り生け贄としては余りにも解りやすいので、そ
れを阻止する働きが無ければ、どんどん規制する方向への一途に成ると思われます。
>点光源はLEDにしていけばいいでしょう。
LEDは基本的に/構造的に点光源ですが、砲弾型等のレンズ込みでは無い面実装や、基台
の上に多数のダイ(半導体/発光部)を並べたり、若しくはフロストガラス等の拡散する
素材を使う事で、かなり面光源で有るとか、又は電球の様な光り方(艶消しの電球の様
に中心にタングステンの強い発光が有り、その周りに輝度変化や淡い光り方する様な演
出など)にする事も可能なので、今後白熱電球の見た目そのもののLED電球と言うのも、
何処かが出してくると思われます。
(郷愁にせよ白熱電球の雰囲気が求められる需要が有るのなら、そういう物が開発され
るのも必然です>どこまで白熱電球に似せるのかは、技術よりもコストの問題です)
因みに舞台照明にも、既にかなりLED(砲弾型かLuxeonを多数使用したタイプ等)灯体
が使われ出してます(当然既存の照明と同等に使える面光源やスポット光源など各種)。
・・・現時点では、そういう諸々の技術的な事よりも価格の問題なので、白熱電球の規
制と言う事に成れば、必然的にLED灯体の生産量も上がり、コストも下がると思われます。
(舞台照明や店舗照明用のLED灯体等は、まだまだ非常に高価ですけど)
>落ち着かないので使い方を限定しています。
これはLEDのスペクトル成分(含まれてる色味)と点灯の仕方次第だと思います。
例えば白は純色RGB合成と、紫外線で黄色蛍光材を励起させる方式などが有りますが、
自然な色味に出来るのはコストを要するRGB合成でも、演色性等に関しての需要が増せば、
やはり量産効果でのコスト減に繋がるので。
点灯の仕方は、白熱電球はフィラメントのおかげでフリッカー出てない様に認識してますが、
実際には50/60Hzで明滅を繰り返してる状況であり、DCでLEDを点灯させる状況とはかなり異
なります。
そういう研究行われてるかどうか存じませんが、その明滅状態を認識できないけど感じてる
状況と、DCで点灯しっぱなしの状況では、無意識な部分でかなり異なる印象を抱く事にも繋
がります(掘り下げませんが、人の外部刺激に対しての感覚で有るとか認識・心理の問題と
して)。
先に電球の様なFadeIn/Outする事など記してますが、LEDも工夫すれば、電球の様な光り方/
駆動を行わせる事は可能であり、もし外観の見た目全く同じで、色温度やスペクトル成分
なども同じで、白熱電球の様な明滅するLED電球を開発したとしたら、その違いが解るかど
うか?・・・です。
(直接そういう事は行ってませんが、私は個人的にも仕事でもそういう事を色々やってるの
で、回路的にどうすればそう出来るか等も解ります)
他に別トピで高周波励起の放電管/蛍光灯に関して諸々記してますが、エネルギー変換効
率と又寿命と言う点で、こちらもどんどん置き換えられる事に成りそうです。
等という議論が今後色んな処で行われる事に成ると思います・・・。
これはLEDのスペクトル成分(含まれてる色味)と点灯の仕方次第だと思います。
例えば白は純色RGB合成と、紫外線で黄色蛍光材を励起させる方式などが有りますが、
自然な色味に出来るのはコストを要するRGB合成でも、演色性等に関しての需要が増せば、
やはり量産効果でのコスト減に繋がるので。
点灯の仕方は、白熱電球はフィラメントのおかげでフリッカー出てない様に認識してますが、
実際には50/60Hzで明滅を繰り返してる状況であり、DCでLEDを点灯させる状況とはかなり異
なります。
そういう研究行われてるかどうか存じませんが、その明滅状態を認識できないけど感じてる
状況と、DCで点灯しっぱなしの状況では、無意識な部分でかなり異なる印象を抱く事にも繋
がります(掘り下げませんが、人の外部刺激に対しての感覚で有るとか認識・心理の問題と
して)。
先に電球の様なFadeIn/Outする事など記してますが、LEDも工夫すれば、電球の様な光り方/
駆動を行わせる事は可能であり、もし外観の見た目全く同じで、色温度やスペクトル成分
なども同じで、白熱電球の様な明滅するLED電球を開発したとしたら、その違いが解るかど
うか?・・・です。
(直接そういう事は行ってませんが、私は個人的にも仕事でもそういう事を色々やってるの
で、回路的にどうすればそう出来るか等も解ります)
他に別トピで高周波励起の放電管/蛍光灯に関して諸々記してますが、エネルギー変換効
率と又寿命と言う点で、こちらもどんどん置き換えられる事に成りそうです。
等という議論が今後色んな処で行われる事に成ると思います・・・。
照明メーカーに勤務する者として一言。
世界的に見ると、電球を主照明にしているヨーロッパでは、電球の使用&生産禁止が決定しております。また、オーストラリアでも決まってます。
根本は省エネも然る事ながら、CO2削減..京都議定書によるものです。
皆さんがおっしゃる、光源的な魅力などは、もはや別世界のものです。
メーカーとしては正式に国からの指示..要請があれば真摯に対応せざる負えませんが、電球型蛍光ランプが当面の代替で、やはりLEDに力を特化する方向になります。
日本は蛍光ランプが主照明であるが故に、電球に対しての間接的な良さが魅了されてますが、世界的な観点から行動が遅い..と言って過言ではないと思われます。
世界的に見ると、電球を主照明にしているヨーロッパでは、電球の使用&生産禁止が決定しております。また、オーストラリアでも決まってます。
根本は省エネも然る事ながら、CO2削減..京都議定書によるものです。
皆さんがおっしゃる、光源的な魅力などは、もはや別世界のものです。
メーカーとしては正式に国からの指示..要請があれば真摯に対応せざる負えませんが、電球型蛍光ランプが当面の代替で、やはりLEDに力を特化する方向になります。
日本は蛍光ランプが主照明であるが故に、電球に対しての間接的な良さが魅了されてますが、世界的な観点から行動が遅い..と言って過言ではないと思われます。
>現在のLEDは低い色温度が出せないので
アンバー系(温白色:3300k)の電球色は各種LEDメーカーでも開発されつつ有る様ですが、
色温度と演色性(含まれるスペクトル成分)は別問題なので、例え電球の様な色温度のLED
が有っても、それに照らされる対象物迄電球と同じ照らされ方(元々含まれてないスペクト
ル成分/音で言うと周波数成分は対象物に照射されない訳なので、反射・吸収される波長も
全く異なる事に成りますし)に出来る物は未だ存在してないのかも知れませんね。
一例として:
http://www.stanley-nlb.com/jp/catalog/images/071101_download.pdf
http://www.stanley-nlb.com/jp/catalog/led/
現在主流であるLEDの波長は以下の様ですが:
http://www.shinkoh-elecs.com/kiso/led.html
三波長蛍光体によるRGB合成というのも有りました:
http://www.mitsubishi-cable.co.jp/jihou/pdf/99/07.pdf
多波長型も各種有る様です:
http://tech-led.com/ja2/Bicolor_Multicolor_LEDs.shtml
LEDの場合Laserの様な単一波長では無く、中心となる波長をピークとしてなだらかな山
を形成する様なスペクトル成分を含んでますが、純色RGB LEDの合成で白を発光する場合、
必然的に3つの中心となる波長と、個々のなだらかな周辺の波長しか含まれません。
(太陽光はWhiteNoiseに例えられる通り、可視領域の全ての波長を含みますが
>代表的なのは虹の七色ですが、それはほぼLEDで個々の色の中心波長を発光させる
事は可能に成ってます)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:SunLightSpectrum-280-2500nm-J.PNG
電球の場合、太陽光に近い感じの様です:
http://t.nomoto.org/spectra/Display/images/G_Lamps.gif
http://www.shokabo.co.jp/sp_opt/familiar/lamp/lamp.htm
分光分布と言う表現は馴染みが無いですが:
http://www.icoffice.co.jp/zukan/l_optical.htm
こういうのを見つけましたが、色再現性高める工夫の一つです:
http://image.itmedia.co.jp/l/im/lifestyle/articles/0509/20/l_hi_sh04.jpg
演色性と色再現性について:
http://www.ziyu1.miru285.com/2006/04/post_43.html
・・・原理的には、抜けている波長を補う発光素子が有るのなら、太陽光や白熱電球に
近づけて行く事は可能です。
(現在製品として存在しているLEDだけでは補えない部分も有るので、その部分を補完する
波長のLEDや、若しくは紫外線励起での蛍光物質が開発されるか否かです・・・現在存在
しているLEDの組み合わせで問題無ければ、多色を組み合わせる事や、個々の波長の輝度
調整を行って、白熱電球のスペクトル成分に近づけていくだけで済みます)
関係ないけどLaserでは、DPSS(ダイオード励起固体レーザー) Green/Blueの様に、
赤外線領域を非線形光学結晶(LBO/KTP等)で半分の波長にして、532nmのGreen/488nmの
Blueを得る様な事が行なわれてます(但しLBO/KTP等は非常に高価です)。
もし仮に、そうして白熱電球に近似したスペクトル成分を発光可能でも、今度は調光など
による輝度変化での、LEDの発光スペクトルのバランスの変化=色味の変化/演色性の変化
が生じる事に成ります。
(電球で有れば調光すると色温度が連続的に上下する様な変化ですが、LEDの多数スペク
トル発光素子の組み合わせでは、簡単な事では有りません)
*元々の順方向電圧降下/電流が発光方式により異なる為に、青や緑は似てますが、
赤は特性が異なる為に、独立してコントロールしなければ成りません。
コスト的に、白熱電球の演色性に近似した特性のLED灯体の場合、調光する用途では使え
ない・・・と言う事にも成ります。
(特殊な処理回路で駆動するのなら可能かも知れませんが、その分コストを要します)
アンバー系(温白色:3300k)の電球色は各種LEDメーカーでも開発されつつ有る様ですが、
色温度と演色性(含まれるスペクトル成分)は別問題なので、例え電球の様な色温度のLED
が有っても、それに照らされる対象物迄電球と同じ照らされ方(元々含まれてないスペクト
ル成分/音で言うと周波数成分は対象物に照射されない訳なので、反射・吸収される波長も
全く異なる事に成りますし)に出来る物は未だ存在してないのかも知れませんね。
一例として:
http://www.stanley-nlb.com/jp/catalog/images/071101_download.pdf
http://www.stanley-nlb.com/jp/catalog/led/
現在主流であるLEDの波長は以下の様ですが:
http://www.shinkoh-elecs.com/kiso/led.html
三波長蛍光体によるRGB合成というのも有りました:
http://www.mitsubishi-cable.co.jp/jihou/pdf/99/07.pdf
多波長型も各種有る様です:
http://tech-led.com/ja2/Bicolor_Multicolor_LEDs.shtml
LEDの場合Laserの様な単一波長では無く、中心となる波長をピークとしてなだらかな山
を形成する様なスペクトル成分を含んでますが、純色RGB LEDの合成で白を発光する場合、
必然的に3つの中心となる波長と、個々のなだらかな周辺の波長しか含まれません。
(太陽光はWhiteNoiseに例えられる通り、可視領域の全ての波長を含みますが
>代表的なのは虹の七色ですが、それはほぼLEDで個々の色の中心波長を発光させる
事は可能に成ってます)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:SunLightSpectrum-280-2500nm-J.PNG
電球の場合、太陽光に近い感じの様です:
http://t.nomoto.org/spectra/Display/images/G_Lamps.gif
http://www.shokabo.co.jp/sp_opt/familiar/lamp/lamp.htm
分光分布と言う表現は馴染みが無いですが:
http://www.icoffice.co.jp/zukan/l_optical.htm
こういうのを見つけましたが、色再現性高める工夫の一つです:
http://image.itmedia.co.jp/l/im/lifestyle/articles/0509/20/l_hi_sh04.jpg
演色性と色再現性について:
http://www.ziyu1.miru285.com/2006/04/post_43.html
・・・原理的には、抜けている波長を補う発光素子が有るのなら、太陽光や白熱電球に
近づけて行く事は可能です。
(現在製品として存在しているLEDだけでは補えない部分も有るので、その部分を補完する
波長のLEDや、若しくは紫外線励起での蛍光物質が開発されるか否かです・・・現在存在
しているLEDの組み合わせで問題無ければ、多色を組み合わせる事や、個々の波長の輝度
調整を行って、白熱電球のスペクトル成分に近づけていくだけで済みます)
関係ないけどLaserでは、DPSS(ダイオード励起固体レーザー) Green/Blueの様に、
赤外線領域を非線形光学結晶(LBO/KTP等)で半分の波長にして、532nmのGreen/488nmの
Blueを得る様な事が行なわれてます(但しLBO/KTP等は非常に高価です)。
もし仮に、そうして白熱電球に近似したスペクトル成分を発光可能でも、今度は調光など
による輝度変化での、LEDの発光スペクトルのバランスの変化=色味の変化/演色性の変化
が生じる事に成ります。
(電球で有れば調光すると色温度が連続的に上下する様な変化ですが、LEDの多数スペク
トル発光素子の組み合わせでは、簡単な事では有りません)
*元々の順方向電圧降下/電流が発光方式により異なる為に、青や緑は似てますが、
赤は特性が異なる為に、独立してコントロールしなければ成りません。
コスト的に、白熱電球の演色性に近似した特性のLED灯体の場合、調光する用途では使え
ない・・・と言う事にも成ります。
(特殊な処理回路で駆動するのなら可能かも知れませんが、その分コストを要します)
>安全な産廃処理技術は確立されてるんでしたっけ?
少し前の資料ですが:
http://www.env.go.jp/council/03haiki/y035-09/mat12_1.pdf
・・・上記の時点では、蛍光灯に関しては対象外に成ってます。
蛍光灯のリサイクル:
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8746
http://www.chemistryquestion.jp/situmon/shitumon_kurashi_kagaku104_heavymetal_recycle.html
LED(主にガリウム砒素)は:
http://www.jogmec.go.jp/mric_web/jouhou/material/2006/As.pdf
http://www.crystals.jp/MSDS%20GaAs.html
少し前の資料ですが:
http://www.env.go.jp/council/03haiki/y035-09/mat12_1.pdf
・・・上記の時点では、蛍光灯に関しては対象外に成ってます。
蛍光灯のリサイクル:
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8746
http://www.chemistryquestion.jp/situmon/shitumon_kurashi_kagaku104_heavymetal_recycle.html
LED(主にガリウム砒素)は:
http://www.jogmec.go.jp/mric_web/jouhou/material/2006/As.pdf
http://www.crystals.jp/MSDS%20GaAs.html
補足・訂正します。
>LEDの場合Laserの様な単一波長では無く、中心となる波長をピークとしてなだらかな山
>個々のなだらかな周辺の波長しか含まれません。
・・・”なだらか”と表現するのはまずいかもです。
山とは分布曲線の様な物であり、ピークが中心波長で、その前後の波長も含まれてると
言う意味合いです(スペクトル分布)。
http://www.stat.go.jp/howto/lecture4/02.htm
http://ergo1.ti.chiba-u.jp/PDF/2002/fukuda.pdf
音で言うとQ(帯域幅)と似た様な物です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%AF%E5%9F%9F%E5%B9%85
因みに
>Laserの様な単一波長
これも、He-Ne やアルゴン他のガスレーザーの場合は実際単一波長なのですが(例えば
He-Neレーザーは632.8nmの波長成分のみしか存在してません>単色性として)、半導体
Laserの場合も単一波長なのは同じでも、駆動電流/温度に応じた波長の変化を生じます
(変化しにくい波長安定化/WSTレーザーというのも有ります)。
http://www.elec.chubu.ac.jp/kuzuya-Lab/laser-j.htm
> 電球の場合、太陽光に近い感じの様です:
> http://t.nomoto.org/spectra/Display/images/G_Lamps.gif
色温度とスペクトル成分の関係性に関して解りやすい説明が有るかどうか解りませんが、
ひとまず色温度は:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%89%B2%E6%B8%A9%E5%BA%A6
それらしき資料:HTMLキャッシュしか存在してませんが:
http://209.85.175.104/search?q=cache:4dStP2rX-6UJ:cafe.mis.ous.ac.jp/sawami/%E9%BB%92%E4%BD%93%E8%BC%BB%E5%B0%84.PDF+%E8%89%B2%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E3%80%80%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB&hl=ja&ct=clnk&cd=2&gl=jp
これなどどうでしょう?
http://www.adobe.com/jp/support/techguides/color/colortheory/light.html
一般的に赤みがかった状態を色温度が低いと表現し、青みがかった状態を色温度が高い
と表現しますが、しかし赤色LEDを色温度が低いとか、青色LEDを色温度が高い・・・
とは表現しないと思います(色温度=波長と言う事でも無いので)。
(RGB発光の照明器具で、個々のバランス調整をしてRのエネルギー強い場合には色温度
が低い状態に成る事や、又はBのエネルギー強い場合には、色温度高い状態に成る事は
有っても)
一般的に照明で言われる色温度が実際どういうスペクトル分布なのかは、白熱電球や蛍
光灯他のスペクトル分布を測定する事は可能な事でも、それを個々の中心波長のLEDの
組み合わせでシミュレートする場合、どうやったら手軽に試せるだろうか?・・・とふ
と思いました(時間の有る時にでも調べて見ます)。
>LEDの場合Laserの様な単一波長では無く、中心となる波長をピークとしてなだらかな山
>個々のなだらかな周辺の波長しか含まれません。
・・・”なだらか”と表現するのはまずいかもです。
山とは分布曲線の様な物であり、ピークが中心波長で、その前後の波長も含まれてると
言う意味合いです(スペクトル分布)。
http://www.stat.go.jp/howto/lecture4/02.htm
http://ergo1.ti.chiba-u.jp/PDF/2002/fukuda.pdf
音で言うとQ(帯域幅)と似た様な物です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%AF%E5%9F%9F%E5%B9%85
因みに
>Laserの様な単一波長
これも、He-Ne やアルゴン他のガスレーザーの場合は実際単一波長なのですが(例えば
He-Neレーザーは632.8nmの波長成分のみしか存在してません>単色性として)、半導体
Laserの場合も単一波長なのは同じでも、駆動電流/温度に応じた波長の変化を生じます
(変化しにくい波長安定化/WSTレーザーというのも有ります)。
http://www.elec.chubu.ac.jp/kuzuya-Lab/laser-j.htm
> 電球の場合、太陽光に近い感じの様です:
> http://t.nomoto.org/spectra/Display/images/G_Lamps.gif
色温度とスペクトル成分の関係性に関して解りやすい説明が有るかどうか解りませんが、
ひとまず色温度は:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%89%B2%E6%B8%A9%E5%BA%A6
それらしき資料:HTMLキャッシュしか存在してませんが:
http://209.85.175.104/search?q=cache:4dStP2rX-6UJ:cafe.mis.ous.ac.jp/sawami/%E9%BB%92%E4%BD%93%E8%BC%BB%E5%B0%84.PDF+%E8%89%B2%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E3%80%80%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB&hl=ja&ct=clnk&cd=2&gl=jp
これなどどうでしょう?
http://www.adobe.com/jp/support/techguides/color/colortheory/light.html
一般的に赤みがかった状態を色温度が低いと表現し、青みがかった状態を色温度が高い
と表現しますが、しかし赤色LEDを色温度が低いとか、青色LEDを色温度が高い・・・
とは表現しないと思います(色温度=波長と言う事でも無いので)。
(RGB発光の照明器具で、個々のバランス調整をしてRのエネルギー強い場合には色温度
が低い状態に成る事や、又はBのエネルギー強い場合には、色温度高い状態に成る事は
有っても)
一般的に照明で言われる色温度が実際どういうスペクトル分布なのかは、白熱電球や蛍
光灯他のスペクトル分布を測定する事は可能な事でも、それを個々の中心波長のLEDの
組み合わせでシミュレートする場合、どうやったら手軽に試せるだろうか?・・・とふ
と思いました(時間の有る時にでも調べて見ます)。
>LEDならではの照明効果を目指して、最近、さまざまに実験を繰り返しています。
博物館他演色性が重視される需要では、メーカー関係も興味を持つのでは無いかと思い
ますが、美術館・博物館等の協議会などで(技術部会的な物が有るかどうか存じません
が)、メーカーに開発協力を仰ぐ様な事も出来るかも知れません。
(相当な需要が見込める訳なので、メーカーにも大きなメリットと成りますし)
http://event.yomiuri.co.jp/jaam/m_birenkyou.cfm
http://www.kahaku.go.jp/jcsm/
LEDの、一応の演色性を考慮した製品は未だ開発途上である為に(例えばJapanShop等で
発表されたりしますが)、開発する側としてもどういう物が求められてるのか等凄く知
りたい事だと思います。
http://www.stanley.co.jp/group/category/laboratory/01.html
http://www.nec.co.jp/contactus/business.html#device 等々
・・・他にディスプレイ/意匠関連なども、組織の力でメーカーに開発を迫る様な事を
行えば、求める物を得る事に繋がります。
(先の通り、メーカーに取っては大口需要家と成り得る訳なので、協力しないと言う事
の方が考えられません)
・・・又白熱電球を残したいと願うのなら、そういう行動を採れば良い事です。
(PSEの件では、署名や諸々よりも、著名な影響力の有る存在の鶴の一声の方が、やは
り効果的である事が立証されましたが>私はそういう影響力の有る方々を煽った一人で
すけど・笑)
>LED照明のみでの会議室をメーカーで作ったところ、10分いたら気持ち悪くなって
色味(スペクトル成分)だけでなく、先の通り感覚的な違和感と言う事だと思います。
(この場合、DC/静止状態で”点灯”している状況が、人の感覚生理/生体リズム等に取
って不快な要素に成る様な事や、そもそも人は常に何らかの刺激を受けてないと、まと
もでは居られない事など)
・・・報酬系(光刺激がどうなのかは解りませんが、外部よりの様々な刺激で脳が
活動する事は、そういう事に繋がるのでは無いかと思います)であるとか、又は洗脳
はどうやって行われるのか・・・等にヒントが有りそうです。
・・・刺激が過ぎるとこうなりますが:
http://www.amazon.co.jp/dp/4880022535
(映像や照明演出にも関わってるので出て直ぐ入手しましたが、凄く薄っぺらい、ペ
ージ単価異様に高い医学書です)
私自身は研究者でもメーカー関係でも無いので、流石に自費を投じて諸々の検証を行う
事は出来ませんが(音のFFTアナライザーは仕事で使うので持ってますが、スペクトル
分光計など必要性無いので調達出来ませんし)、私が記した様なオカルト?・・・的な
事を試されれば、私が何を記してるのかご理解戴けると思います(人の感覚生理や大脳
生理の問題として)。
因みに又新たな試みを行う事に成りました(昨日お打ち合わせしてきました)。
http://light.asablo.jp/blog/2007/12/23/2526125
現在この作品はFixした点灯状態ですが、様々な効果を持たせる事に成ります。
(表現としては、幾つかのモジュレーションを掛けて表情を造り出します
>回路などは画像の形で公開してますが、具体的な処理内容等は一切公開してません)
http://www.meta-design.jp/BodyIlluminant.html
(作家さんの求めるイメージと、それを実現する変態処理回路のコラボです・笑)
博物館他演色性が重視される需要では、メーカー関係も興味を持つのでは無いかと思い
ますが、美術館・博物館等の協議会などで(技術部会的な物が有るかどうか存じません
が)、メーカーに開発協力を仰ぐ様な事も出来るかも知れません。
(相当な需要が見込める訳なので、メーカーにも大きなメリットと成りますし)
http://event.yomiuri.co.jp/jaam/m_birenkyou.cfm
http://www.kahaku.go.jp/jcsm/
LEDの、一応の演色性を考慮した製品は未だ開発途上である為に(例えばJapanShop等で
発表されたりしますが)、開発する側としてもどういう物が求められてるのか等凄く知
りたい事だと思います。
http://www.stanley.co.jp/group/category/laboratory/01.html
http://www.nec.co.jp/contactus/business.html#device 等々
・・・他にディスプレイ/意匠関連なども、組織の力でメーカーに開発を迫る様な事を
行えば、求める物を得る事に繋がります。
(先の通り、メーカーに取っては大口需要家と成り得る訳なので、協力しないと言う事
の方が考えられません)
・・・又白熱電球を残したいと願うのなら、そういう行動を採れば良い事です。
(PSEの件では、署名や諸々よりも、著名な影響力の有る存在の鶴の一声の方が、やは
り効果的である事が立証されましたが>私はそういう影響力の有る方々を煽った一人で
すけど・笑)
>LED照明のみでの会議室をメーカーで作ったところ、10分いたら気持ち悪くなって
色味(スペクトル成分)だけでなく、先の通り感覚的な違和感と言う事だと思います。
(この場合、DC/静止状態で”点灯”している状況が、人の感覚生理/生体リズム等に取
って不快な要素に成る様な事や、そもそも人は常に何らかの刺激を受けてないと、まと
もでは居られない事など)
・・・報酬系(光刺激がどうなのかは解りませんが、外部よりの様々な刺激で脳が
活動する事は、そういう事に繋がるのでは無いかと思います)であるとか、又は洗脳
はどうやって行われるのか・・・等にヒントが有りそうです。
・・・刺激が過ぎるとこうなりますが:
http://www.amazon.co.jp/dp/4880022535
(映像や照明演出にも関わってるので出て直ぐ入手しましたが、凄く薄っぺらい、ペ
ージ単価異様に高い医学書です)
私自身は研究者でもメーカー関係でも無いので、流石に自費を投じて諸々の検証を行う
事は出来ませんが(音のFFTアナライザーは仕事で使うので持ってますが、スペクトル
分光計など必要性無いので調達出来ませんし)、私が記した様なオカルト?・・・的な
事を試されれば、私が何を記してるのかご理解戴けると思います(人の感覚生理や大脳
生理の問題として)。
因みに又新たな試みを行う事に成りました(昨日お打ち合わせしてきました)。
http://light.asablo.jp/blog/2007/12/23/2526125
現在この作品はFixした点灯状態ですが、様々な効果を持たせる事に成ります。
(表現としては、幾つかのモジュレーションを掛けて表情を造り出します
>回路などは画像の形で公開してますが、具体的な処理内容等は一切公開してません)
http://www.meta-design.jp/BodyIlluminant.html
(作家さんの求めるイメージと、それを実現する変態処理回路のコラボです・笑)
ご指摘ありがとうございます。
問題の様で有れば、トピック毎削除下さいませ。
(私が削除する事は勿論可能ですが、記されてる他の方に失礼な事なので、それは
出来かねます)
ただ、LED等の新しい灯体などに関して、関わる方々の参考に成ればと願います。
(例えばアナログレコードなども、直接関わる音楽関係者でさえ今の様な状況に成る事
は予想もしてなかった事であり、もしアナログレコード VS CDの様に、色んな面で優れ
ているのなら、過去の物は廃れ新しい物が主流に成る事は、時代の趨勢です・・・それ
で古い物の良さが失われる事に成ったとしても・・・)
*既にCDさえも売れない時代であり、Net等の”データー”の時代に移行しつつ有り
ますが(楽曲の売り上げとしては、実はそれ程変化してない等)。
問題の様で有れば、トピック毎削除下さいませ。
(私が削除する事は勿論可能ですが、記されてる他の方に失礼な事なので、それは
出来かねます)
ただ、LED等の新しい灯体などに関して、関わる方々の参考に成ればと願います。
(例えばアナログレコードなども、直接関わる音楽関係者でさえ今の様な状況に成る事
は予想もしてなかった事であり、もしアナログレコード VS CDの様に、色んな面で優れ
ているのなら、過去の物は廃れ新しい物が主流に成る事は、時代の趨勢です・・・それ
で古い物の良さが失われる事に成ったとしても・・・)
*既にCDさえも売れない時代であり、Net等の”データー”の時代に移行しつつ有り
ますが(楽曲の売り上げとしては、実はそれ程変化してない等)。
トピック名称の変更しようと思ったら、後からの編集は出来ない様です。
様々な物(物質・素材・機能他)には感応評価と言う手法で、人に取っての作用(例え
ば心地良いのかそうでは無いのか等)を主観的/他覚的(脳波他)に調査する事が行われ
ますが、当然照明にも行われてる筈と思い、簡単に調べて見ました。
官能評価:
http://blog.taste-technology.com/
http://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2005_22267/slides/03/index_1.html
直接的に白熱電球とLED/放電管系に関する官能評価の情報が存在してるかどうか迄は、
時間を掛けないとNet上に存在してるのかどうか解りませんが、ひとまずめぼしい物を
幾つか記しておきます(内容の確認は行ってません)。
*各種研究資料は、日本の場合Net上に公開されてる事は希であり、多くの場合海外
の論文などでしか情報は得られません(公開するしないは文化の違いなのか何なのか?)。
http://www.orsj.or.jp/~archive/pdf/bul/Vol.44_11_594.pdf
http://ci.nii.ac.jp/naid/110001143408/
http://www.jissen.ac.jp/kankyo/lab-maki/makiHP/thesis/Paper06.pdf
http://www.toyoda-gosei.co.jp/seihin/giho/43_no1/pdf/v43_21_26.pdf
http://www.epcc.pref.osaka.jp/press/h17/1020_1/main.html
検索キーワードとしては”官能評価+照明”や”Sensory+Evaluation+for+lighting”等。
関連学会/組織は:
http://www.jsse.net/
http://www.jspa.net/
http://www.jske.org/
http://www.gogp.co.jp/ergonomics/
http://www.ieij.or.jp/
http://www.led.or.jp/index.htm
http://www.ciejapan.or.jp/index2.html
http://www.jlassn.or.jp/
因みに主観的評価は個々の印象・感想と言う事ですが(多くは予め用意された+/−の
段階/例えば良い・普通・悪い等の選択肢から被験者に選択して貰う等)、例えばLED照明は
何だか不快・・・と言う事は解っても、心理・生理的にどうしてそうなのかは解りません。
他覚的評価は、主観/論理(言葉として表せる事)では無く無意識/生理反応を調べる事での、
生理的に/生き物としてどう感じているのか?・・・と言う事で得られます。
直接そういう研究に関わった事は無いので、どういう手法が主流なのかは存じませんが、
基本的に脈拍(plethysmograph)や脳波(EEG)により、α/β/θ/δ/γなどの脳波の状態
で生理的反応を調べる様な事が行なわれてると思われます。
(Feedback系/ポリグラフ等で使われる、GSR/Galvanic Skin Response/電気皮膚反応等を
組み合わせる事も有るのかも)
又脳の活動部位を測定する為に光トポグラフィー等も使われ出してるのかも知れません。
(上記に記した測定方法は自分でも行えますが((Pertformance用途や各種対応の為にそう
いうセンサー/簡易なセンシング機器なども作りますので))、流石に光トポグラフィーの
様な大がかりなシステムは無理です)
http://www.hitachi-medical.co.jp/product/opt/etg4000/index.html
http://www.med.shimadzu.co.jp/products/om/index.html
・・・松下辺りはそういう評価もやってそうですが(VirtualReality技術などもいち早く
自社製品の開発/評価や営業ツールとして採り入れた様な企業なので)、例えばLED照明は
何故不快なのか?等や、白熱電球とLED照明での生理的反応の違いなどは、各種手法で調
べる事が可能です。
(院生などの論文では使える手法に限界が有りますが、企業で有ればどれだけ費用を掛ける
か次第の事です)
私の場合、照明や他には映像などは演出用途と言う事でしか関わってない為に(元々は音
/音響と深く関わってますが、他に香り/Automation機器他演出用途のシステム諸々も)、
一般照明的な事(静的な照明とでも記しておきます)とは無縁です。
(演出用途では、心地よさと言う方向性も有り得ますが、基本的には如何に刺激を与えるか
と言う事が目的であり、一般照明の様な静的な状態での快適さ等と言う事とは異なるので)
例えばLED照明を普及させたい側は、マイナスに成る様な事を公開できないのは仕方無い事
としても、しかし現実的に一般照明として不快な物であるのなら、それをクリアしないと
普及はしません(必然的に不快さを軽減させる〜無くす様な方向に改善しなければ成らなく
成ります・・・なので先ずそういう研究を行うべき存在と成ります)。
別件ですが興味深いので:
http://www2a.biglobe.ne.jp/~wakaba/kougai.htm
http://www.env.go.jp/air/life/hikari_g/index.html
http://www.env.go.jp/air/report/h13-02/index.html
http://www.env.go.jp/air/life/m-syomei/index.html
http://riodb.ibase.aist.go.jp/ssrdoc/index.html
http://www.ieij.or.jp/link/ledlink.html
様々な物(物質・素材・機能他)には感応評価と言う手法で、人に取っての作用(例え
ば心地良いのかそうでは無いのか等)を主観的/他覚的(脳波他)に調査する事が行われ
ますが、当然照明にも行われてる筈と思い、簡単に調べて見ました。
官能評価:
http://blog.taste-technology.com/
http://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2005_22267/slides/03/index_1.html
直接的に白熱電球とLED/放電管系に関する官能評価の情報が存在してるかどうか迄は、
時間を掛けないとNet上に存在してるのかどうか解りませんが、ひとまずめぼしい物を
幾つか記しておきます(内容の確認は行ってません)。
*各種研究資料は、日本の場合Net上に公開されてる事は希であり、多くの場合海外
の論文などでしか情報は得られません(公開するしないは文化の違いなのか何なのか?)。
http://www.orsj.or.jp/~archive/pdf/bul/Vol.44_11_594.pdf
http://ci.nii.ac.jp/naid/110001143408/
http://www.jissen.ac.jp/kankyo/lab-maki/makiHP/thesis/Paper06.pdf
http://www.toyoda-gosei.co.jp/seihin/giho/43_no1/pdf/v43_21_26.pdf
http://www.epcc.pref.osaka.jp/press/h17/1020_1/main.html
検索キーワードとしては”官能評価+照明”や”Sensory+Evaluation+for+lighting”等。
関連学会/組織は:
http://www.jsse.net/
http://www.jspa.net/
http://www.jske.org/
http://www.gogp.co.jp/ergonomics/
http://www.ieij.or.jp/
http://www.led.or.jp/index.htm
http://www.ciejapan.or.jp/index2.html
http://www.jlassn.or.jp/
因みに主観的評価は個々の印象・感想と言う事ですが(多くは予め用意された+/−の
段階/例えば良い・普通・悪い等の選択肢から被験者に選択して貰う等)、例えばLED照明は
何だか不快・・・と言う事は解っても、心理・生理的にどうしてそうなのかは解りません。
他覚的評価は、主観/論理(言葉として表せる事)では無く無意識/生理反応を調べる事での、
生理的に/生き物としてどう感じているのか?・・・と言う事で得られます。
直接そういう研究に関わった事は無いので、どういう手法が主流なのかは存じませんが、
基本的に脈拍(plethysmograph)や脳波(EEG)により、α/β/θ/δ/γなどの脳波の状態
で生理的反応を調べる様な事が行なわれてると思われます。
(Feedback系/ポリグラフ等で使われる、GSR/Galvanic Skin Response/電気皮膚反応等を
組み合わせる事も有るのかも)
又脳の活動部位を測定する為に光トポグラフィー等も使われ出してるのかも知れません。
(上記に記した測定方法は自分でも行えますが((Pertformance用途や各種対応の為にそう
いうセンサー/簡易なセンシング機器なども作りますので))、流石に光トポグラフィーの
様な大がかりなシステムは無理です)
http://www.hitachi-medical.co.jp/product/opt/etg4000/index.html
http://www.med.shimadzu.co.jp/products/om/index.html
・・・松下辺りはそういう評価もやってそうですが(VirtualReality技術などもいち早く
自社製品の開発/評価や営業ツールとして採り入れた様な企業なので)、例えばLED照明は
何故不快なのか?等や、白熱電球とLED照明での生理的反応の違いなどは、各種手法で調
べる事が可能です。
(院生などの論文では使える手法に限界が有りますが、企業で有ればどれだけ費用を掛ける
か次第の事です)
私の場合、照明や他には映像などは演出用途と言う事でしか関わってない為に(元々は音
/音響と深く関わってますが、他に香り/Automation機器他演出用途のシステム諸々も)、
一般照明的な事(静的な照明とでも記しておきます)とは無縁です。
(演出用途では、心地よさと言う方向性も有り得ますが、基本的には如何に刺激を与えるか
と言う事が目的であり、一般照明の様な静的な状態での快適さ等と言う事とは異なるので)
例えばLED照明を普及させたい側は、マイナスに成る様な事を公開できないのは仕方無い事
としても、しかし現実的に一般照明として不快な物であるのなら、それをクリアしないと
普及はしません(必然的に不快さを軽減させる〜無くす様な方向に改善しなければ成らなく
成ります・・・なので先ずそういう研究を行うべき存在と成ります)。
別件ですが興味深いので:
http://www2a.biglobe.ne.jp/~wakaba/kougai.htm
http://www.env.go.jp/air/life/hikari_g/index.html
http://www.env.go.jp/air/report/h13-02/index.html
http://www.env.go.jp/air/life/m-syomei/index.html
http://riodb.ibase.aist.go.jp/ssrdoc/index.html
http://www.ieij.or.jp/link/ledlink.html
白熱電球製造中止に関する報道のきっかけに成ったと思われる内容を見つけました:
http://www.meti.go.jp/speeches/data_ej/ej071220j.html
(上記の通り、経済産業省筋では確実に製造中止の発言が有った様です
>巨大メディアが根拠の無い報道をする事は有り得ませんので
・・・色んな思惑で情報操作する事はさておき・苦笑)
それ以前の状況は:
http://eco.nikkei.co.jp/news/article.aspx?id=2007062007921n1
クールビズに関わる白熱電球の政府広告に関して:
http://www.env.go.jp/annai/kaiken/h19/j_0614.html
官房長官の12/19の発言(【温暖化対策】):
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071219-00000949-san-pol
トップランナー制度:
http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g70305a05j.pdf
・・・直接関係ない事ですが、例えば旧通産省の指導で家電品などの保守部品を製造終了後
メーカーが保有している事は、義務ではありませんが(業界団体のガイドラインや自主的な
事として)、お役所の指導は命令と同じ事です(その指導は経済産業省も引き継いでます)。
http://www.elepop.net/elepop274.html
トップランナー制度がどこまでの”指導力(上記の通りの意味合いを持ちます)”を持つ物な
のかは存じませんが、そう言う指導・指針はメーカーに取っては”断れない物”なのです。
等とメーカー関係者にしか理解できない事かも知れませんが・・・。
それとRoHSによる様々な変化は、それがどういう事なのかは多くのメーカーが一部部品や製品
の製造を辞めた事として(環境負荷物質の使用規制であり、それに置き換える物が無いとか、
RoHS対応で例えばIC等の設計変更や製品の製造工程の変更などのコストを掛ける程収益性無い
ので、いっその事廃止する等)如実に物語ってます。
(RoHS指令は、規制物質を使用した部品・機器類を欧州では流通させないと言う事であり、少な
くとも日本で輸出に関わる企業は否応なしに従うしか無い事なので、結果そうなりました)
白熱電球を取り巻く状況が今後どう成って行くのかは・・・。
(日本の場合米国への右へ倣へかも知れませんが・苦笑)
http://www.es-inc.jp/lib/lester/newsletter/070726_164942.html
因みにPSE問題(経済産業省が拡大解釈で中古品の規制を言い出してしまった事が発端で
あり、迷走しまくってましたが)の際ビンテージ機器類の例外措置を勝ち取ったのは署名
よりも坂本龍一氏等(JSPA)ですが(鶴の一声/社会的影響力として)、ついにご免なさい
・・・させたのは政治的な力による物だと思います(間接的に関わってたので具体的には
記せません)。
http://yoppa.blog2.fc2.com/blog-category-20.html
http://www.meti.go.jp/speeches/data_ej/ej071220j.html
(上記の通り、経済産業省筋では確実に製造中止の発言が有った様です
>巨大メディアが根拠の無い報道をする事は有り得ませんので
・・・色んな思惑で情報操作する事はさておき・苦笑)
それ以前の状況は:
http://eco.nikkei.co.jp/news/article.aspx?id=2007062007921n1
クールビズに関わる白熱電球の政府広告に関して:
http://www.env.go.jp/annai/kaiken/h19/j_0614.html
官房長官の12/19の発言(【温暖化対策】):
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071219-00000949-san-pol
トップランナー制度:
http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g70305a05j.pdf
・・・直接関係ない事ですが、例えば旧通産省の指導で家電品などの保守部品を製造終了後
メーカーが保有している事は、義務ではありませんが(業界団体のガイドラインや自主的な
事として)、お役所の指導は命令と同じ事です(その指導は経済産業省も引き継いでます)。
http://www.elepop.net/elepop274.html
トップランナー制度がどこまでの”指導力(上記の通りの意味合いを持ちます)”を持つ物な
のかは存じませんが、そう言う指導・指針はメーカーに取っては”断れない物”なのです。
等とメーカー関係者にしか理解できない事かも知れませんが・・・。
それとRoHSによる様々な変化は、それがどういう事なのかは多くのメーカーが一部部品や製品
の製造を辞めた事として(環境負荷物質の使用規制であり、それに置き換える物が無いとか、
RoHS対応で例えばIC等の設計変更や製品の製造工程の変更などのコストを掛ける程収益性無い
ので、いっその事廃止する等)如実に物語ってます。
(RoHS指令は、規制物質を使用した部品・機器類を欧州では流通させないと言う事であり、少な
くとも日本で輸出に関わる企業は否応なしに従うしか無い事なので、結果そうなりました)
白熱電球を取り巻く状況が今後どう成って行くのかは・・・。
(日本の場合米国への右へ倣へかも知れませんが・苦笑)
http://www.es-inc.jp/lib/lester/newsletter/070726_164942.html
因みにPSE問題(経済産業省が拡大解釈で中古品の規制を言い出してしまった事が発端で
あり、迷走しまくってましたが)の際ビンテージ機器類の例外措置を勝ち取ったのは署名
よりも坂本龍一氏等(JSPA)ですが(鶴の一声/社会的影響力として)、ついにご免なさい
・・・させたのは政治的な力による物だと思います(間接的に関わってたので具体的には
記せません)。
http://yoppa.blog2.fc2.com/blog-category-20.html
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
照明研究室 更新情報
-
最新のアンケート
照明研究室のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90035人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6418人
- 3位
- 独り言
- 9044人