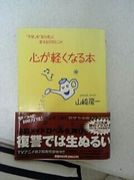(1) 「公共の」という語はそもそも「誰にでも」「開かれた」ということを示す語である。Publicの語源であるラテン語のpopulus はthe people(民衆)を、またドイツ語の「公共性」?ffentlichkeitはまさに「開かれた」?ffentlichを意味する。
(2) たとえば「ハーバーマスとデリダは、哲学への鋭く異なったアプローチにもかかわらず、アーレントモデルの跡を継いでいるように思われる。」(ジョヴァンナ・ボッラドリ「テロリズムと<啓蒙>の遺産」、13頁。ユルゲン・ハーバーマス、ジャック・デリダ、ジョヴァンナ・ボッラドリ、藤本一勇・澤里岳史訳『テロルの時代と哲学の使命』岩波書店、2004年所収。) ボッラドリはこれに続けて、ハーバーマスとデリダがアーレントの後継者であるというのは、まさにその政治に対するアプローチの仕方においてである、と指摘している。
(3)ハーバーマスのアーレント批判に関しては、拙論「歌う言葉はすでに与えられている ?ハンナ・アーレントにおける政治的なもの」、『倫理学』第22号、筑波大学倫理学研究会、2006年3月、またリオタールのアーレント批判に関しては、拙論「ポストモダンにおける公共性の問題 ?アーレントとリオタール」、『東海大学紀要文学部』第85輯、2006年9月、及び第86輯、2007年3月(分割掲載)を、それぞれ参照されたい。
(4)アーレント著、ウルズラ・ルッツ編、佐藤和夫訳『政治とは何か』岩波書店、2004年、4頁。
(5)「広場」はポリスのアゴラを範型にする。「公的領域と私的領域、ポリスの領域と家族の領域、そして共通世界に係わる活動力と生命の維持に係わる活動力??これらそれぞれ二つのものの間の決定的な区別」(アーレント、志水速雄訳『人間の条件』筑摩書房、1994年、49頁)をアーレントは確定するのである。
アーレントは言う。「<人間>は非政治的だからである。政治が生まれるのは、人間たちの間においてであり、したがって<人間>の外側になのである。」(『政治とは何か』5頁。)
(6)そもそも同じものをわれわれは区別しない。同じものはわれわれにとって「一」として存在する。例えば机の上の消しゴムの消しかす(複数)は、通常われわれにとってひとまとまりの消しかす(単数)であって、それがいくつあるか数えたりはしないのだ。
(7)「すべての人間は、お互いに絶対的に異なっているのであり、この差異は、民族、国民、人種という相対的な差異よりも大きなものである。」(『政治とは何か』6頁。)
加えてわれわれは、境界線が逆に人びとの間の差異を抹消してしまうという点に注目しなければならない。境界線を持ち込むことは、同時にその線の「内側」と「外側」を同時に持ち込むことであり、それは「内側」の中の差異も「外側」の中の差異も消去してしまうことにほかならない。つまり、境界線を持ち込むことによって実際にはわれわれは、差異を確定するのではなく、抹消してしまうのである。
(8)『政治とは何か』35頁。
(9) アーレントにおいて「家族」はむしろ政治を阻害するものである。というのも家族という在り方は、個人としての差異を伴う在り方(ひとと違う自分であるということ、あるいはひとと違う自分であるということを現すこと)を許さないし、その中で個々人の複数性が無いことにされてしまうからである。アーレントはこう言う。「ギリシア思想によれば、政治的組織を作る人間の能力は、家庭(oikia)と家族を中心とする自然的な結合と異なっているばかりか、それと正面から対立している。」(『人間の条件』45頁) また、「家族は、親しさを求めようとしても心冷たく疎遠にとどまる世界の中で、避難所、堅き砦として建てられるのである。なぜなら、それによって複数性という基本的性質が捨てられるし、それどころか、親近という概念を導入することによって、政治的なものが剥奪されてしまうからである。」(『政治とは何か』3-4頁)
(10) 例えばそれは国民、民族、家族であり、あるいはその具体的な固有名である。
(11) こうして、例えば国家は、かつて家庭が担っていた生命維持や生活保証をその主要な任務とするようになったのだが、その点においても国家は「家」である。アーレントは、現在の国家は「巨大な民族大の家政によって日々の問題を解決するある種の家族にすぎない」し、そして「家族の集団が経済的に組織されて、一つの超人間的家族の模写となっているものこそ、私たちが『社会』と呼んでいるものであり、その政治的な組織形態が『国民』と呼ばれている」ものなのだ、と指摘する。(『人間の条件』50頁。)
また、国家が成員の「生命の保証」(あるいは剥奪)をカードとして政治を進めている現在の状況に関しては、ジョルジュ・アガンベンの鋭い指摘がある。(例えば、ジョルジュ・アガンベン、高桑和巳訳『ホモ・サケル』以文社、2003年、168-169頁。)
(12)ハーバーマスによれば、重要なのは「われわれが互いにある集団のメンバーとしてだけではなく、地理的・歴史的・文化的・社会的に大きく異なる他者同士としても抱えることになる期待と要求の正当性なのである。したがってこの場合重要なのは、もはやある(固有のエートスによって特徴づけられる)集団のメンバーとしてのわれわれにとっての「善」ではなく、全員にとっての「正しさ」なのである。その場合の全員は、言語能力と行為能力を持つ主体からなる世界の全メンバーであるかもしれないし、ある(地域的あるいは全地球的な)法共同体のすべての同胞かもしれないが、とにかく全員にとっての「正しい」ものなのである。こうした正義の問いを判定する場合、われわれが求めるのは、全当事者(そして全関係者)が相互承認という対称的条件の下での非強制的な対話において十分検討した上で同意するであろう、非党派的解決である。」(ハーバーマス、高野昌行訳『他者の受容』法政大学出版局、2004年、306-307頁)。
(13)ハーバーマス、清水多吉・朝倉輝一訳『討議倫理』法政大学出版局、2005年、135頁。
(14)『討議倫理』7頁。
(15) もちろん、全くの「真空状態」で他者と出会うということが考えられるわけではない。他者と出会う「わたし」は、<われわれ>の地平の規範・言語を既に習得済みの「わたし」であり、既に常に<われわれ>の地平を背負った「わたし」である。その「わたし」が、やはり同様に何らかの地平を背負った(また、だからこそ<われわれ>の地平に対立する)「他者」と出会うのである。むしろその「ズレ」において初めてわたしは他者と出会うのだ、と言い換えても良いだろう。したがって、この場合の出会いは、それぞれの異なる言語使用や異なる世界観を引きずったままの出会い=対立である。こうして、わたしと他者は、当初はズレ=対立でしかない出会いを、相互理解の可能性へ向けて維持するということの中で、当初の言語使用の差異を少しずつ解消し、地平の差異を少しずつ融和させていくことになる。
(16) 『他者の受容』306頁。
(17) 『討議倫理』185頁。
(18) だとすれば、「広場」は在るのではない。どこかに在る「広場」にわれわれが集うのではない。他者と出会うところが「広場」になるのだ。納得していない「彼」の存在を承認するところにのみ、そして、その他者と合意を求めて出会うところにのみ、その場が「家」ではなくて「広場」になる可能性が ??と同時に「政治」の存在する可能性が ??生まれるのである。
(19) 『討議倫理』184頁。
(20) アーレントも使用していた「全員」の理念 ??彼女はこれを理性によって想定され得る普遍的なものと考えていたのだが ??に、実際のコミュニケーションによって「現実に向き合う」という限定条件を加えたのがハーバーマスであり、他者の範囲に時間軸を持ち込む(「帰り来る霊」)のがデリダであるとも言えるだろう。
(21) 『討議倫理』185頁。
(22) こうしたハーバーマスのプロジェクトを、境界を持つ共同体から境界なき共同体(「コミュニケーション共同体」)への移行のプロジェクトとして位置づけるとすれば、そこにわれわれは例えば「共通性なき共同体」、あるいは他者の歓待(デリダ)といった概念への拡がりを聴き取ることができるだろう。
(2) たとえば「ハーバーマスとデリダは、哲学への鋭く異なったアプローチにもかかわらず、アーレントモデルの跡を継いでいるように思われる。」(ジョヴァンナ・ボッラドリ「テロリズムと<啓蒙>の遺産」、13頁。ユルゲン・ハーバーマス、ジャック・デリダ、ジョヴァンナ・ボッラドリ、藤本一勇・澤里岳史訳『テロルの時代と哲学の使命』岩波書店、2004年所収。) ボッラドリはこれに続けて、ハーバーマスとデリダがアーレントの後継者であるというのは、まさにその政治に対するアプローチの仕方においてである、と指摘している。
(3)ハーバーマスのアーレント批判に関しては、拙論「歌う言葉はすでに与えられている ?ハンナ・アーレントにおける政治的なもの」、『倫理学』第22号、筑波大学倫理学研究会、2006年3月、またリオタールのアーレント批判に関しては、拙論「ポストモダンにおける公共性の問題 ?アーレントとリオタール」、『東海大学紀要文学部』第85輯、2006年9月、及び第86輯、2007年3月(分割掲載)を、それぞれ参照されたい。
(4)アーレント著、ウルズラ・ルッツ編、佐藤和夫訳『政治とは何か』岩波書店、2004年、4頁。
(5)「広場」はポリスのアゴラを範型にする。「公的領域と私的領域、ポリスの領域と家族の領域、そして共通世界に係わる活動力と生命の維持に係わる活動力??これらそれぞれ二つのものの間の決定的な区別」(アーレント、志水速雄訳『人間の条件』筑摩書房、1994年、49頁)をアーレントは確定するのである。
アーレントは言う。「<人間>は非政治的だからである。政治が生まれるのは、人間たちの間においてであり、したがって<人間>の外側になのである。」(『政治とは何か』5頁。)
(6)そもそも同じものをわれわれは区別しない。同じものはわれわれにとって「一」として存在する。例えば机の上の消しゴムの消しかす(複数)は、通常われわれにとってひとまとまりの消しかす(単数)であって、それがいくつあるか数えたりはしないのだ。
(7)「すべての人間は、お互いに絶対的に異なっているのであり、この差異は、民族、国民、人種という相対的な差異よりも大きなものである。」(『政治とは何か』6頁。)
加えてわれわれは、境界線が逆に人びとの間の差異を抹消してしまうという点に注目しなければならない。境界線を持ち込むことは、同時にその線の「内側」と「外側」を同時に持ち込むことであり、それは「内側」の中の差異も「外側」の中の差異も消去してしまうことにほかならない。つまり、境界線を持ち込むことによって実際にはわれわれは、差異を確定するのではなく、抹消してしまうのである。
(8)『政治とは何か』35頁。
(9) アーレントにおいて「家族」はむしろ政治を阻害するものである。というのも家族という在り方は、個人としての差異を伴う在り方(ひとと違う自分であるということ、あるいはひとと違う自分であるということを現すこと)を許さないし、その中で個々人の複数性が無いことにされてしまうからである。アーレントはこう言う。「ギリシア思想によれば、政治的組織を作る人間の能力は、家庭(oikia)と家族を中心とする自然的な結合と異なっているばかりか、それと正面から対立している。」(『人間の条件』45頁) また、「家族は、親しさを求めようとしても心冷たく疎遠にとどまる世界の中で、避難所、堅き砦として建てられるのである。なぜなら、それによって複数性という基本的性質が捨てられるし、それどころか、親近という概念を導入することによって、政治的なものが剥奪されてしまうからである。」(『政治とは何か』3-4頁)
(10) 例えばそれは国民、民族、家族であり、あるいはその具体的な固有名である。
(11) こうして、例えば国家は、かつて家庭が担っていた生命維持や生活保証をその主要な任務とするようになったのだが、その点においても国家は「家」である。アーレントは、現在の国家は「巨大な民族大の家政によって日々の問題を解決するある種の家族にすぎない」し、そして「家族の集団が経済的に組織されて、一つの超人間的家族の模写となっているものこそ、私たちが『社会』と呼んでいるものであり、その政治的な組織形態が『国民』と呼ばれている」ものなのだ、と指摘する。(『人間の条件』50頁。)
また、国家が成員の「生命の保証」(あるいは剥奪)をカードとして政治を進めている現在の状況に関しては、ジョルジュ・アガンベンの鋭い指摘がある。(例えば、ジョルジュ・アガンベン、高桑和巳訳『ホモ・サケル』以文社、2003年、168-169頁。)
(12)ハーバーマスによれば、重要なのは「われわれが互いにある集団のメンバーとしてだけではなく、地理的・歴史的・文化的・社会的に大きく異なる他者同士としても抱えることになる期待と要求の正当性なのである。したがってこの場合重要なのは、もはやある(固有のエートスによって特徴づけられる)集団のメンバーとしてのわれわれにとっての「善」ではなく、全員にとっての「正しさ」なのである。その場合の全員は、言語能力と行為能力を持つ主体からなる世界の全メンバーであるかもしれないし、ある(地域的あるいは全地球的な)法共同体のすべての同胞かもしれないが、とにかく全員にとっての「正しい」ものなのである。こうした正義の問いを判定する場合、われわれが求めるのは、全当事者(そして全関係者)が相互承認という対称的条件の下での非強制的な対話において十分検討した上で同意するであろう、非党派的解決である。」(ハーバーマス、高野昌行訳『他者の受容』法政大学出版局、2004年、306-307頁)。
(13)ハーバーマス、清水多吉・朝倉輝一訳『討議倫理』法政大学出版局、2005年、135頁。
(14)『討議倫理』7頁。
(15) もちろん、全くの「真空状態」で他者と出会うということが考えられるわけではない。他者と出会う「わたし」は、<われわれ>の地平の規範・言語を既に習得済みの「わたし」であり、既に常に<われわれ>の地平を背負った「わたし」である。その「わたし」が、やはり同様に何らかの地平を背負った(また、だからこそ<われわれ>の地平に対立する)「他者」と出会うのである。むしろその「ズレ」において初めてわたしは他者と出会うのだ、と言い換えても良いだろう。したがって、この場合の出会いは、それぞれの異なる言語使用や異なる世界観を引きずったままの出会い=対立である。こうして、わたしと他者は、当初はズレ=対立でしかない出会いを、相互理解の可能性へ向けて維持するということの中で、当初の言語使用の差異を少しずつ解消し、地平の差異を少しずつ融和させていくことになる。
(16) 『他者の受容』306頁。
(17) 『討議倫理』185頁。
(18) だとすれば、「広場」は在るのではない。どこかに在る「広場」にわれわれが集うのではない。他者と出会うところが「広場」になるのだ。納得していない「彼」の存在を承認するところにのみ、そして、その他者と合意を求めて出会うところにのみ、その場が「家」ではなくて「広場」になる可能性が ??と同時に「政治」の存在する可能性が ??生まれるのである。
(19) 『討議倫理』184頁。
(20) アーレントも使用していた「全員」の理念 ??彼女はこれを理性によって想定され得る普遍的なものと考えていたのだが ??に、実際のコミュニケーションによって「現実に向き合う」という限定条件を加えたのがハーバーマスであり、他者の範囲に時間軸を持ち込む(「帰り来る霊」)のがデリダであるとも言えるだろう。
(21) 『討議倫理』185頁。
(22) こうしたハーバーマスのプロジェクトを、境界を持つ共同体から境界なき共同体(「コミュニケーション共同体」)への移行のプロジェクトとして位置づけるとすれば、そこにわれわれは例えば「共通性なき共同体」、あるいは他者の歓待(デリダ)といった概念への拡がりを聴き取ることができるだろう。
|
|
|
|
|
|
|
|
思想インフラ研究会 沙千子支部 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
思想インフラ研究会 沙千子支部のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37860人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90060人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208308人