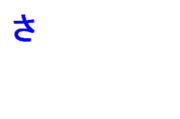はじめまして、似たようなトピックがあったのですがあえて立たせていただきました、
私が小学校5年生か、6年生のときに文章題から式をつくる問題があり、答えは 7×3 のところを 3×7 と書いて×にさせられました(実際はもっと複雑な数字だったと思いますが)
そこで先生に抗議にいったところ、「お皿の上にみかんが7個あります、お皿が3枚のときはみかんは何個?」という文章題のときには、 7×3 が正解で、 3×7は間違いだという、摩訶不思議なことを言われました。
そのときの悔しさは三十路手前の今でも忘れることはありません
これって小学校ではこのように教えるって決まっているのでしょうか?
この一件以来、小学校の先生=算数苦手のイメージがついてるのですが
私が小学校5年生か、6年生のときに文章題から式をつくる問題があり、答えは 7×3 のところを 3×7 と書いて×にさせられました(実際はもっと複雑な数字だったと思いますが)
そこで先生に抗議にいったところ、「お皿の上にみかんが7個あります、お皿が3枚のときはみかんは何個?」という文章題のときには、 7×3 が正解で、 3×7は間違いだという、摩訶不思議なことを言われました。
そのときの悔しさは三十路手前の今でも忘れることはありません
これって小学校ではこのように教えるって決まっているのでしょうか?
この一件以来、小学校の先生=算数苦手のイメージがついてるのですが
|
|
|
|
コメント(12)
レスありがとうございます、やっぱり決まっていたのですね、ググったりして、何となくそうだろうと思っていました。
私は教育学部を出たわけでもないし、偉い人がこのように教える方が良いと、経験上決めたのでしょうからなんともいえませんが、これは明らかにおかしいです。
長方形の面積は、たて×よこで、よこ×たては間違いなのでしょうか?お皿一つに、3個乗っていることが基準で、そのお皿が7個あると考えれば良いだけです。掛け算の交換法則?なんて九九を覚えるときに誰でもわかります。
算数と数学の違いといえば、それまでですが、絶対に小学生のうちから、どちらでもいいと教えるべきです。
こんな些細なことですが、個人的な苦い思いでもあり納得いきません。このトピには、教育関係者が多いと思いますが、ぜひご意見をいただきたいと思います。
私は教育学部を出たわけでもないし、偉い人がこのように教える方が良いと、経験上決めたのでしょうからなんともいえませんが、これは明らかにおかしいです。
長方形の面積は、たて×よこで、よこ×たては間違いなのでしょうか?お皿一つに、3個乗っていることが基準で、そのお皿が7個あると考えれば良いだけです。掛け算の交換法則?なんて九九を覚えるときに誰でもわかります。
算数と数学の違いといえば、それまでですが、絶対に小学生のうちから、どちらでもいいと教えるべきです。
こんな些細なことですが、個人的な苦い思いでもあり納得いきません。このトピには、教育関係者が多いと思いますが、ぜひご意見をいただきたいと思います。
みなさん ありがとうございます、やはり、順番を変えてはダメということなのですね
正直一般人の私には理解できません、500mの距離の2倍でも、2×500で、2倍だよ、500mのってことでいいと思います。
同じく、2,3×2,5で 2,3mの板で1mあたり2,5kg
という考え方でもいいと思います。というかこういう考え方を出来た方がむしろいいのではないでしょうか?
こっちを×にするという心理の方が?です。この教え方はいつ頃叩き込まれるのでしょうか?大学生の時?この順番でないとダメと聞いたら、違和感を感じる大人は結構多いと思うのですが
設問1 5両編成の電車が4台あります、全部で何両ですか?
設問2 1両につき窓が4枚ついてます 窓は全部で何枚ですか?
設問3 窓1枚につきカーテンが2枚ついてます、カーテンは?
なかなかいい例が思いつきませんが、こんなのでも、設問2は
4×20、設問3は 2×80ではないとダメってことですよね
正直一般人の私には理解できません、500mの距離の2倍でも、2×500で、2倍だよ、500mのってことでいいと思います。
同じく、2,3×2,5で 2,3mの板で1mあたり2,5kg
という考え方でもいいと思います。というかこういう考え方を出来た方がむしろいいのではないでしょうか?
こっちを×にするという心理の方が?です。この教え方はいつ頃叩き込まれるのでしょうか?大学生の時?この順番でないとダメと聞いたら、違和感を感じる大人は結構多いと思うのですが
設問1 5両編成の電車が4台あります、全部で何両ですか?
設問2 1両につき窓が4枚ついてます 窓は全部で何枚ですか?
設問3 窓1枚につきカーテンが2枚ついてます、カーテンは?
なかなかいい例が思いつきませんが、こんなのでも、設問2は
4×20、設問3は 2×80ではないとダメってことですよね
かけ算の意味は、みなさんが言われている通り、
(1あたりの数)×(いくつ分)
です。これは、小学校教師が必ず教えるべき内容です。
これを教えない、または理解していない状況だと、
文章問題で、
(文中で先に出てきた数)×(後で出てきた数)
という誤りをおかしがちです。この先入観が、他の計算にも
つながってしまい、例えば・・・
「4人で仲良く12個のあめを分けます。あめは1人
何個になりますか。」
のようなわり算の問題で、
「4÷12」
という立式をたてて、答えは3個という正解を出す
子どもも出てきます。
こういう誤った認識をしないためにも、計算における
立式の意味を理解させることが大切だと思います。
ちなみに、計算の交換法則が成り立つのは、たし算と
かけ算のみです。
(1あたりの数)×(いくつ分)
です。これは、小学校教師が必ず教えるべき内容です。
これを教えない、または理解していない状況だと、
文章問題で、
(文中で先に出てきた数)×(後で出てきた数)
という誤りをおかしがちです。この先入観が、他の計算にも
つながってしまい、例えば・・・
「4人で仲良く12個のあめを分けます。あめは1人
何個になりますか。」
のようなわり算の問題で、
「4÷12」
という立式をたてて、答えは3個という正解を出す
子どもも出てきます。
こういう誤った認識をしないためにも、計算における
立式の意味を理解させることが大切だと思います。
ちなみに、計算の交換法則が成り立つのは、たし算と
かけ算のみです。
みなさま 色々とありがとうございます、みなさんがおっしゃるとおり、小学校では、(一つあたりの数×いくつ分)と教えるのが正しい、ということが分かりました。
私もその後、調べましたが、実はこの議論は、ポツポツとでていてyahoo知恵袋でもでていました(ベストアンサーは?な感じですが)くどいようですが、あるHPで以下の文章をみつけました。新聞の投稿のようなので、引用させていただきました。私の心情とかなり似ていると思います、ご意見ありましたらよろしくお願します
「妻に叱られた算数の数え方」 (40 歳, 地方公務員)
妻が小二の娘に, 文章題の掛け算式の立て方を教えていた。 娘は, 四人に五枚ずつ色紙を配るから 「4×5」 と式を立てた。 ところが, 妻は 「5×4」 の順序でなければいけないという。
私は 「どちらも正解。 何故そうなるのか説明出来ればいいんだよ」 と口を挟んだら, 「学校ではバツになる。 混乱しちゃうじゃない。 そんなに言うなら, あなたが責任持って教えて」 と, 妻に叱られてしまった。
確かに教科書には 「一つ分の数×幾つ分 = 全部の数」 と書かれているし, 家庭学習の教材では 「4×5 としないように」 とわざわざ朱書きされている。 想像するに, 「考え方さえ合っていれば, どちらでもいい」 と教えるのは手間が掛かるし, 子供を混乱させるからかも知れない。
しかし, 答にたどり着く道が幾つもあるのが算数である。 それこそが算数の醍醐味。自分が導き出したやり方を認められてこそ, 自信と興味が深まる。 算数に限ったことではない。
娘に 「先生が駄目と言ったら, お父さんが先生に説明してあげる」 と言った曇りない口調とは裏腹に, 「学校の通りに教えるべきか」 と, 気分は晴れない。
私もその後、調べましたが、実はこの議論は、ポツポツとでていてyahoo知恵袋でもでていました(ベストアンサーは?な感じですが)くどいようですが、あるHPで以下の文章をみつけました。新聞の投稿のようなので、引用させていただきました。私の心情とかなり似ていると思います、ご意見ありましたらよろしくお願します
「妻に叱られた算数の数え方」 (40 歳, 地方公務員)
妻が小二の娘に, 文章題の掛け算式の立て方を教えていた。 娘は, 四人に五枚ずつ色紙を配るから 「4×5」 と式を立てた。 ところが, 妻は 「5×4」 の順序でなければいけないという。
私は 「どちらも正解。 何故そうなるのか説明出来ればいいんだよ」 と口を挟んだら, 「学校ではバツになる。 混乱しちゃうじゃない。 そんなに言うなら, あなたが責任持って教えて」 と, 妻に叱られてしまった。
確かに教科書には 「一つ分の数×幾つ分 = 全部の数」 と書かれているし, 家庭学習の教材では 「4×5 としないように」 とわざわざ朱書きされている。 想像するに, 「考え方さえ合っていれば, どちらでもいい」 と教えるのは手間が掛かるし, 子供を混乱させるからかも知れない。
しかし, 答にたどり着く道が幾つもあるのが算数である。 それこそが算数の醍醐味。自分が導き出したやり方を認められてこそ, 自信と興味が深まる。 算数に限ったことではない。
娘に 「先生が駄目と言ったら, お父さんが先生に説明してあげる」 と言った曇りない口調とは裏腹に, 「学校の通りに教えるべきか」 と, 気分は晴れない。
hamuyoさん、はじめまして。
私には小学生の子がいます。文章題となるとつまづき気味です。そんな時、私はその様子を頭の中で想像して式をたたせるようにしています。頭の中で考えてもらったあとに一緒に紙に整理して書くのです。
↑の文章題ではまず4人の人間を書き、そこに5枚ずつの色紙を書き込みます。
そこで、こどもはどう考えるかというと初期の段階では「5+5+5+5=20」と答えます。しかし、掛け算では?となると5が4個だから「5×4=20」と結びつくのです。
絵を描いた段階では4+4+4+4+4という発想はまず出てこないでしょう。
私が思うのにはやはり考え方が大切ということではないでしょうか? 答えがあえば式がどんなでも良いかというとそうでもないような気が私はします。本当に考えて式をたてているのか、それとも、単純に深いことは気にせずに「先に出てきた数字×後から出てきた数字」とするのか。後者は理解できていないとしか思えません。
>>答にたどり着く道が幾つもあるのが算数である
たしかにこの言葉にはとっても納得しますし、私自身それが楽しみでもあります。しかし、それは基本をおさえてこそだと思うのです。
私には小学生の子がいます。文章題となるとつまづき気味です。そんな時、私はその様子を頭の中で想像して式をたたせるようにしています。頭の中で考えてもらったあとに一緒に紙に整理して書くのです。
↑の文章題ではまず4人の人間を書き、そこに5枚ずつの色紙を書き込みます。
そこで、こどもはどう考えるかというと初期の段階では「5+5+5+5=20」と答えます。しかし、掛け算では?となると5が4個だから「5×4=20」と結びつくのです。
絵を描いた段階では4+4+4+4+4という発想はまず出てこないでしょう。
私が思うのにはやはり考え方が大切ということではないでしょうか? 答えがあえば式がどんなでも良いかというとそうでもないような気が私はします。本当に考えて式をたてているのか、それとも、単純に深いことは気にせずに「先に出てきた数字×後から出てきた数字」とするのか。後者は理解できていないとしか思えません。
>>答にたどり着く道が幾つもあるのが算数である
たしかにこの言葉にはとっても納得しますし、私自身それが楽しみでもあります。しかし、それは基本をおさえてこそだと思うのです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
算数話 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
算数話のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 一行で笑わせろ!
- 82541人
- 2位
- 酒好き
- 170695人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90065人