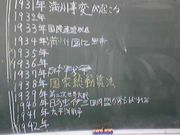「君が代」の歴史の授業。
昨年の音楽専科での実践。
当時は、子どもの活動の重要性をあまり意識しておらず、典型的なプレゼン授業になっている。
もし、再度実践する場合は、子どもの活動をいかに入れていくかを考えて行う。
●WEBサイトの操作
○模擬授業の子役、或いは授業での子どもの反応
<実践内容>
●君が代の歌詞を掲示
発問1 この曲の題名は何ですか?
○「君が代」「君が代」「国歌」
発問2 君が代のうたは、いつできたでしょうか?
(●サイトで4択を提示)
1.平安時代よりも前
2.平安時代
3.明治時代
4.昭和のはじめ(大東亜戦争中)
教師相手の授業でも分かれる。
2か3が多い。
子供だと、3か4を選択する。
説明1 正解は(●サイトで正解を告げる)1です。
○「えぇ?」とどよめきがある。
説明2 証拠があります。(●古今和歌集の写しを提示)
平安時代の始め、(●サイトをクリック)西暦905年につくられた「古今和歌集」に、
(●サイトをクリック)「よみ人知らず」、つくった人が誰だか分からないぐらい古い歌として紹介されています。平安時代で既に民謡のように誰でも知っている歌だったそうです。
だから、平安時代よりも前。
(●サイトをクリック 君が代の原典を提示)
説明3 そこには、「わが君は、千代に八千代に、細石の、巌となりて、苔のむすまで」と書かれていた。
「私の愛しいあなた様、或いは、私の大切なお父さんお母さんは、千年八千年に渡って、小さな石が大きな岩に成長し、さらに、その岩に苔が生えるまで、ずっと長生きして下さい」という長寿を祝う歌だった。
後になって、「君が代は」、つまり「天皇の治める世の中は」と変わります。
(●和歌披講譜を提示)
説明4 これは図形譜という楽譜です。
「君が代」は、和歌だったから、ちゃんと歌われていました。
当時、どんな風に歌われていたのか、聞いてみよう。
こんな風に歌われ続けてきました。
(●和歌披講の録音を聞かせる)
◎百人一首をやっていたクラスでは、子どもに暗記している一首を発表してもらい、その一首を聞いたメロディで全員で歌ってみた。
説明5 初句は、一人で歌って高さを決め、二句から全員で歌っていますね。
発問3 ところが、1853年、この人が日本に来ます。誰ですか?
(●ペリーの絵を提示)
(●ペリー来航の様子を描いた図を提示)
説明6 その時の絵です。絵の左下、実は軍楽隊と言う吹奏楽を一緒に連れてきた。それを見て、いいなと思うわけです。これ以来、日本人はヨーロッパの音楽を本格的に勉強し始めます。
(●薩摩軍楽隊の写真を提示)
説明7 このすぐ後、薩摩藩、今の鹿児島県では、自分たちで吹奏楽団も作ってしまいます。
説明8 しかし、このように、外国とお付き合いをするようになると、国歌が必要になってくる。そこで、始めは、みんなが知ってた君が代の詩に、お雇い外国人だった、フェントンというイギリス人に曲を書いてもらいます。
(フェントン作曲の「君が代」の楽譜を提示。録音も聞かせる。教師は録音と一緒に歌って聞かせる。)
説明9 これが世界で初めて認められた日本の国歌です。イギリスとの交流行事で一緒に演奏されたそうです。
でも、これ、とっても評判が悪かったのです。理由は、まず日本人らしくない。イギリス人がつくったから、当然イギリス風の音楽なんです。
それから、フェントンは日本語をよく分かっていなかったので、「イハ」とか「コケ」とかやってしまう(1つの音に2つの言葉を当てはめていること)。とっても間抜けに聞こえたようです。
それで止めます。
説明10 そこで、雅楽を演奏する人だった「林広守」が雅楽の伴奏でつくります。
(●雅楽版の「君が代」を聞かせる)
説明11 これも、問題がありました。雅楽伴奏では、海外で演奏できない。ピアノかオーケストラで伴奏できるようにしないといけない。
そこで、同じくお雇い外国人だったドイツ人のエッケルトに頼んで伴奏を書いてもらいます。
指示1 全員で歌います。
◎教師の伴奏でも良いし、CDに合わせて歌ってもよい。
説明12 この曲、不思議ではないですか?
「わざわざ最初の2小節は、ハーモニーがついていません。」
難しかったようだが、まれに気づく子がいた。
説明13 エッケルトは、日本の文化をよく勉強していました。和歌は初句を一人で歌っているのを、わざとハーモニーをつけず表現し、3小節目から一気にハーモニーをつけて、二句から全員で歌っているのを表現しています。
子どもから、「エッケルトっていい人だなぁ。」「よく考えてあるねぇ」という感想が出る。
説明14
君が代は、このように千年以上の歴史があるお祝いの歌なのです。決して戦争のためにつくられた訳ではありません。
だから、日本中の卒業式や入学式などで、歌われるのです。
<参考文献>
1.『和歌を歌う』〜歌会始と和歌披講〜
付録CD付き
日本文化財団編 協力 披講会 定価2,940円
2.披講学習会ホームページ
http://
3.CD「君が代のすべて」
http://
4.TOSS音楽セミナー 藍川由美氏の講座資料
5.『日の丸・君が代の戦後史 (新書) 』田中 伸尚 (著)
6.君が代の歴史
http://
7.国旗及び国歌に関する法律
http://
8.藍川由美HP
http://
9.CD『「日本のうた」歌唱法』カメラータ/CMCD−99029
10.藍川由美『日本の唱歌・決定版』(音楽之友社)
11.藍川由美『これでいいのか、にっぽんのうた』(文藝春秋)
12.藍川由美「演歌」のススメ(文藝春秋)
昨年の音楽専科での実践。
当時は、子どもの活動の重要性をあまり意識しておらず、典型的なプレゼン授業になっている。
もし、再度実践する場合は、子どもの活動をいかに入れていくかを考えて行う。
●WEBサイトの操作
○模擬授業の子役、或いは授業での子どもの反応
<実践内容>
●君が代の歌詞を掲示
発問1 この曲の題名は何ですか?
○「君が代」「君が代」「国歌」
発問2 君が代のうたは、いつできたでしょうか?
(●サイトで4択を提示)
1.平安時代よりも前
2.平安時代
3.明治時代
4.昭和のはじめ(大東亜戦争中)
教師相手の授業でも分かれる。
2か3が多い。
子供だと、3か4を選択する。
説明1 正解は(●サイトで正解を告げる)1です。
○「えぇ?」とどよめきがある。
説明2 証拠があります。(●古今和歌集の写しを提示)
平安時代の始め、(●サイトをクリック)西暦905年につくられた「古今和歌集」に、
(●サイトをクリック)「よみ人知らず」、つくった人が誰だか分からないぐらい古い歌として紹介されています。平安時代で既に民謡のように誰でも知っている歌だったそうです。
だから、平安時代よりも前。
(●サイトをクリック 君が代の原典を提示)
説明3 そこには、「わが君は、千代に八千代に、細石の、巌となりて、苔のむすまで」と書かれていた。
「私の愛しいあなた様、或いは、私の大切なお父さんお母さんは、千年八千年に渡って、小さな石が大きな岩に成長し、さらに、その岩に苔が生えるまで、ずっと長生きして下さい」という長寿を祝う歌だった。
後になって、「君が代は」、つまり「天皇の治める世の中は」と変わります。
(●和歌披講譜を提示)
説明4 これは図形譜という楽譜です。
「君が代」は、和歌だったから、ちゃんと歌われていました。
当時、どんな風に歌われていたのか、聞いてみよう。
こんな風に歌われ続けてきました。
(●和歌披講の録音を聞かせる)
◎百人一首をやっていたクラスでは、子どもに暗記している一首を発表してもらい、その一首を聞いたメロディで全員で歌ってみた。
説明5 初句は、一人で歌って高さを決め、二句から全員で歌っていますね。
発問3 ところが、1853年、この人が日本に来ます。誰ですか?
(●ペリーの絵を提示)
(●ペリー来航の様子を描いた図を提示)
説明6 その時の絵です。絵の左下、実は軍楽隊と言う吹奏楽を一緒に連れてきた。それを見て、いいなと思うわけです。これ以来、日本人はヨーロッパの音楽を本格的に勉強し始めます。
(●薩摩軍楽隊の写真を提示)
説明7 このすぐ後、薩摩藩、今の鹿児島県では、自分たちで吹奏楽団も作ってしまいます。
説明8 しかし、このように、外国とお付き合いをするようになると、国歌が必要になってくる。そこで、始めは、みんなが知ってた君が代の詩に、お雇い外国人だった、フェントンというイギリス人に曲を書いてもらいます。
(フェントン作曲の「君が代」の楽譜を提示。録音も聞かせる。教師は録音と一緒に歌って聞かせる。)
説明9 これが世界で初めて認められた日本の国歌です。イギリスとの交流行事で一緒に演奏されたそうです。
でも、これ、とっても評判が悪かったのです。理由は、まず日本人らしくない。イギリス人がつくったから、当然イギリス風の音楽なんです。
それから、フェントンは日本語をよく分かっていなかったので、「イハ」とか「コケ」とかやってしまう(1つの音に2つの言葉を当てはめていること)。とっても間抜けに聞こえたようです。
それで止めます。
説明10 そこで、雅楽を演奏する人だった「林広守」が雅楽の伴奏でつくります。
(●雅楽版の「君が代」を聞かせる)
説明11 これも、問題がありました。雅楽伴奏では、海外で演奏できない。ピアノかオーケストラで伴奏できるようにしないといけない。
そこで、同じくお雇い外国人だったドイツ人のエッケルトに頼んで伴奏を書いてもらいます。
指示1 全員で歌います。
◎教師の伴奏でも良いし、CDに合わせて歌ってもよい。
説明12 この曲、不思議ではないですか?
「わざわざ最初の2小節は、ハーモニーがついていません。」
難しかったようだが、まれに気づく子がいた。
説明13 エッケルトは、日本の文化をよく勉強していました。和歌は初句を一人で歌っているのを、わざとハーモニーをつけず表現し、3小節目から一気にハーモニーをつけて、二句から全員で歌っているのを表現しています。
子どもから、「エッケルトっていい人だなぁ。」「よく考えてあるねぇ」という感想が出る。
説明14
君が代は、このように千年以上の歴史があるお祝いの歌なのです。決して戦争のためにつくられた訳ではありません。
だから、日本中の卒業式や入学式などで、歌われるのです。
<参考文献>
1.『和歌を歌う』〜歌会始と和歌披講〜
付録CD付き
日本文化財団編 協力 披講会 定価2,940円
2.披講学習会ホームページ
http://
3.CD「君が代のすべて」
http://
4.TOSS音楽セミナー 藍川由美氏の講座資料
5.『日の丸・君が代の戦後史 (新書) 』田中 伸尚 (著)
6.君が代の歴史
http://
7.国旗及び国歌に関する法律
http://
8.藍川由美HP
http://
9.CD『「日本のうた」歌唱法』カメラータ/CMCD−99029
10.藍川由美『日本の唱歌・決定版』(音楽之友社)
11.藍川由美『これでいいのか、にっぽんのうた』(文藝春秋)
12.藍川由美「演歌」のススメ(文藝春秋)
|
|
|
|
コメント(1)
「海ゆかば」
詩:大伴家持
曲:信時 潔
海行かば 水漬(みづ)く屍(かばね)
山行かば 草生(くさむ)す屍
大君(おおきみ)の 辺(へ)にこそ死なめ
かへりみはせじ
(長閑(のど)には死なじ)
<原詩>
陸奥国に金を出す詔書を賀す歌一首、并せて短歌(大伴家持)
葦原の 瑞穂の国を 天下り 知らしめしける すめろきの 神の命の 御代重ね 天の日継と 知らし来る 君の御代御代 敷きませる 四方の国には 山川を 広み厚みと 奉る みつき宝は 数へえず 尽くしもかねつ しかれども 我が大君の 諸人を 誘ひたまひ よきことを 始めたまひて 金かも たしけくあらむと 思ほして 下悩ますに 鶏が鳴く 東の国の 陸奥の 小田なる山に 黄金ありと 申したまへれ 御心を 明らめたまひ 天地の 神相うづなひ すめろきの 御霊助けて 遠き代に かかりしことを 我が御代に 顕はしてあれば 食す国は 栄えむものと 神ながら 思ほしめして もののふの 八十伴の緒を まつろへの 向けのまにまに 老人も 女童も しが願ふ 心足らひに 撫でたまひ 治めたまへば ここをしも あやに貴み 嬉しけく いよよ思ひて 大伴の 遠つ神祖の その名をば 大久米主と 負ひ持ちて 仕へし官 海行かば 水漬く屍 山行かば 草生す屍 大君の 辺にこそ死なめ かへり見は せじと言立て ますらをの 清きその名を いにしへよ 今のをつづに 流さへる 祖の子どもぞ 大伴と 佐伯の氏は 人の祖の 立つる言立て 人の子は 祖の名絶たず 大君に まつろふものと 言ひ継げる 言の官ぞ 梓弓 手に取り持ちて 剣大刀 腰に取り佩き 朝守り 夕の守りに 大君の 御門の守り 我れをおきて 人はあらじと いや立て 思ひし増さる 大君の 御言のさきの[一云 を] 聞けば貴み [一云 貴くしあれば]
「海ゆかば」映像
http://www.youtube.com/watch?v=uINoxvU03Fo
「WIKIPEDIA『海ゆかば』」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E3%82%86%E3%81%8B%E3%81%B0
詩:大伴家持
曲:信時 潔
海行かば 水漬(みづ)く屍(かばね)
山行かば 草生(くさむ)す屍
大君(おおきみ)の 辺(へ)にこそ死なめ
かへりみはせじ
(長閑(のど)には死なじ)
<原詩>
陸奥国に金を出す詔書を賀す歌一首、并せて短歌(大伴家持)
葦原の 瑞穂の国を 天下り 知らしめしける すめろきの 神の命の 御代重ね 天の日継と 知らし来る 君の御代御代 敷きませる 四方の国には 山川を 広み厚みと 奉る みつき宝は 数へえず 尽くしもかねつ しかれども 我が大君の 諸人を 誘ひたまひ よきことを 始めたまひて 金かも たしけくあらむと 思ほして 下悩ますに 鶏が鳴く 東の国の 陸奥の 小田なる山に 黄金ありと 申したまへれ 御心を 明らめたまひ 天地の 神相うづなひ すめろきの 御霊助けて 遠き代に かかりしことを 我が御代に 顕はしてあれば 食す国は 栄えむものと 神ながら 思ほしめして もののふの 八十伴の緒を まつろへの 向けのまにまに 老人も 女童も しが願ふ 心足らひに 撫でたまひ 治めたまへば ここをしも あやに貴み 嬉しけく いよよ思ひて 大伴の 遠つ神祖の その名をば 大久米主と 負ひ持ちて 仕へし官 海行かば 水漬く屍 山行かば 草生す屍 大君の 辺にこそ死なめ かへり見は せじと言立て ますらをの 清きその名を いにしへよ 今のをつづに 流さへる 祖の子どもぞ 大伴と 佐伯の氏は 人の祖の 立つる言立て 人の子は 祖の名絶たず 大君に まつろふものと 言ひ継げる 言の官ぞ 梓弓 手に取り持ちて 剣大刀 腰に取り佩き 朝守り 夕の守りに 大君の 御門の守り 我れをおきて 人はあらじと いや立て 思ひし増さる 大君の 御言のさきの[一云 を] 聞けば貴み [一云 貴くしあれば]
「海ゆかば」映像
http://www.youtube.com/watch?v=uINoxvU03Fo
「WIKIPEDIA『海ゆかば』」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E3%82%86%E3%81%8B%E3%81%B0
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ディープな教材研究(Dケン) 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ディープな教材研究(Dケン)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23166人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人