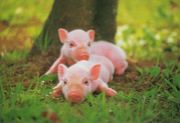自分で読んでもおかしいです・・・
まずは先にはりつけます!!
ここからはみんなで修正していこう★
(題名部分)
As Chinese girths get bigger,so does obesity issue
中国の胴回りがより大きくなるように、肥満も出ます。
(内容)
HONG KONG(Reuters)
Unhappy with her weight,Charmaine Tong desided two years ago to try a slimming tea,which supposedly contained only traditional Chinese herbs.
香港(ロイター)彼女の体重で不幸なので、Charmaine秘密結社は細くなる茶を試みるために2年前に非賛成しました。それは恐らく従来の中国の薬草だけを含んでいました。
She was overjoyed when she lost her appetite and the bathroom scales began dipping,but her happiness vanished when she began suffering a racing heart beat a month later.
食欲を失い、バスルーム規模が浸り始めた時、彼女は大いに喜びました。しかし、彼女が1か月後にレース用心臓打つことを受け始めた時、幸福は消えました。
"I chose Chinese medicine as I thought it wouldn't have chemicals and would have fewer side effects,but my heart went out of control,"said Tong,a marketing executive in Hong Kong.
私は、私としての漢方を選んだ、それは化学薬品を持たずより少数の副作用を持つだろう、と思った、しかし、私の心はコントロールできなくなりました、「秘密結社(香港において実行のマーケティング)は言いました。
She stopped drinking the tea at once,and has since regained the 3kg she lost,and more.
彼女は直ちに茶を飲むことをやめて、それ以来彼女が失った3kg以上を回復しました。
Pills and teas purporting to "melt away body fat"and help shed unwanted weight are sold widely across Hong Kong.
「身体の脂肪を次第になくす」こと、望まれない重量を流すのを支援することを意味する錠剤と茶は、香港を横切って広く売られます。
Growing affluence,a penchant for eating and a sedentary lifestyle have swollen the ranks of people who are over weight or obese in Hong Kong and China,docters say.
豊富、食べることに対する好みおよび定着しているライフスタイルを育てることは、重量以上いる人々の数を増しました、あるいは香港と中国において肥大している、と医者は言います。
Thirty percent of Hong Kong's nearly 7 million people are overweight,double the figure 10 years ago,doctors say.
香港のほぼ700万人の30パーセントは超過重量(10年前の2倍の図)である、と医者が言います。
In China,nearly one in every five Chinese is overweight and there are now at least 60 million Chinese who are obese,according to the British Medical Journal.
中国では、5人の中国人ごとのほぼ1人は英国の医学雑誌によれば、太り過ぎです。また、今肥大している少なくとも6000万人の中国人がいます。
It also found that 10 million children between the ages of 7 and 18 were overweight in 2000 in China,28 times more than in 1985.
a further 4 million were obese.
さらに、それは、7歳と18歳の間の1000万人の子供が1985年によりも28倍多くの中国で2000年において太り過ぎであることを知りました。一層の400万は肥大していました。
Obesity and overweight are major risk factors for serious chronic diseases-such as diabetes,cardiovascular disease,hypertension and stroke,and certain forms of cancer-which caused 60 percent of all deaths worldwide in 2005.
肥満、そして重量超過、主な危険要因である-糖尿病、心臓血管疾患、高血圧症およびストローク-形式慢性病のように重大、癌どれが2005年において世界的なすべての死の60パーセントを引き起こした。
"What we are seeing in our part of the world are people coming in with heart attacks at 40,strokes at 40-ish,kidney problems at 40-ish.Many of these are young mothers still looking after kids and many are breadwinners for the family,"Juliana Chan,a professor of medicine and therapeutics at the Chinse University in Hong Kong,said.
「世界の一部で私たちが見ているものは人々です、40で心臓発作とともに中へ入ること、40のishのストローク、40のishの腎臓問題。これらのうちの多数は、子供と多数が家族のための大黒柱�セった後まだ見る若い母親です、ジュリアナ・チャン、香港の中国大学の医学および治療学の教授、言いました。
※ishは40代とかかな??(坂口の意見)
”We are going to see a lot of early deaths,disabilities and there will be an enormous burden on the health care system,which can't cope.Lots of young people will come in requiring bypass operations,dialysis,rehabilitation for strokes and our productivity will reduce.”
「私たちは多くの若死を見るつもりです、不能、また、ヘルスケアシステム(それは対処することができない)上に巨大な負担があるでしょう。多くの若い人々が、バイパス手術、透析、ストロークのためのリハビリテーションおよび私たちの生産力が縮小するだろうということを要求する際に来るでしょう。」
Apart from eating too much,doing too little exercise and smoking,experts say Asia's weight problem is more pronounced than in the West because of a genetic predisposition to obesity.
あまりに食べることとは別に、運動および喫煙を行って、専門家は、肥満への遺伝素質のために西洋でよりも、アジアの体重の問題がもっと断言されるとはあまりほとんど言いません。
”For the same body weight,Asians have more body fat than Caucasians, particularly in the viscera(organs in the abdominal cavity),”said Chan.
「同じ体重のために、アジア人は特に内臓(腹腔中の器官)に、コーカサス地方の人より太ったより多くの身体を持っています」チャンは言いました。
"Because of the climate, we are not built to store so much fat ,so it spills into the liver, muscles and pancreas,which is why you hear so much about fatty liver.”
「気候のために、私たちはこれほど多くの脂肪を格納するためには構築されません。したがって、それは肝臓、筋肉および膵臓へこぼれます。そういうわけで、脂肪肝に関して非常に聞きます。」
まずは先にはりつけます!!
ここからはみんなで修正していこう★
(題名部分)
As Chinese girths get bigger,so does obesity issue
中国の胴回りがより大きくなるように、肥満も出ます。
(内容)
HONG KONG(Reuters)
Unhappy with her weight,Charmaine Tong desided two years ago to try a slimming tea,which supposedly contained only traditional Chinese herbs.
香港(ロイター)彼女の体重で不幸なので、Charmaine秘密結社は細くなる茶を試みるために2年前に非賛成しました。それは恐らく従来の中国の薬草だけを含んでいました。
She was overjoyed when she lost her appetite and the bathroom scales began dipping,but her happiness vanished when she began suffering a racing heart beat a month later.
食欲を失い、バスルーム規模が浸り始めた時、彼女は大いに喜びました。しかし、彼女が1か月後にレース用心臓打つことを受け始めた時、幸福は消えました。
"I chose Chinese medicine as I thought it wouldn't have chemicals and would have fewer side effects,but my heart went out of control,"said Tong,a marketing executive in Hong Kong.
私は、私としての漢方を選んだ、それは化学薬品を持たずより少数の副作用を持つだろう、と思った、しかし、私の心はコントロールできなくなりました、「秘密結社(香港において実行のマーケティング)は言いました。
She stopped drinking the tea at once,and has since regained the 3kg she lost,and more.
彼女は直ちに茶を飲むことをやめて、それ以来彼女が失った3kg以上を回復しました。
Pills and teas purporting to "melt away body fat"and help shed unwanted weight are sold widely across Hong Kong.
「身体の脂肪を次第になくす」こと、望まれない重量を流すのを支援することを意味する錠剤と茶は、香港を横切って広く売られます。
Growing affluence,a penchant for eating and a sedentary lifestyle have swollen the ranks of people who are over weight or obese in Hong Kong and China,docters say.
豊富、食べることに対する好みおよび定着しているライフスタイルを育てることは、重量以上いる人々の数を増しました、あるいは香港と中国において肥大している、と医者は言います。
Thirty percent of Hong Kong's nearly 7 million people are overweight,double the figure 10 years ago,doctors say.
香港のほぼ700万人の30パーセントは超過重量(10年前の2倍の図)である、と医者が言います。
In China,nearly one in every five Chinese is overweight and there are now at least 60 million Chinese who are obese,according to the British Medical Journal.
中国では、5人の中国人ごとのほぼ1人は英国の医学雑誌によれば、太り過ぎです。また、今肥大している少なくとも6000万人の中国人がいます。
It also found that 10 million children between the ages of 7 and 18 were overweight in 2000 in China,28 times more than in 1985.
a further 4 million were obese.
さらに、それは、7歳と18歳の間の1000万人の子供が1985年によりも28倍多くの中国で2000年において太り過ぎであることを知りました。一層の400万は肥大していました。
Obesity and overweight are major risk factors for serious chronic diseases-such as diabetes,cardiovascular disease,hypertension and stroke,and certain forms of cancer-which caused 60 percent of all deaths worldwide in 2005.
肥満、そして重量超過、主な危険要因である-糖尿病、心臓血管疾患、高血圧症およびストローク-形式慢性病のように重大、癌どれが2005年において世界的なすべての死の60パーセントを引き起こした。
"What we are seeing in our part of the world are people coming in with heart attacks at 40,strokes at 40-ish,kidney problems at 40-ish.Many of these are young mothers still looking after kids and many are breadwinners for the family,"Juliana Chan,a professor of medicine and therapeutics at the Chinse University in Hong Kong,said.
「世界の一部で私たちが見ているものは人々です、40で心臓発作とともに中へ入ること、40のishのストローク、40のishの腎臓問題。これらのうちの多数は、子供と多数が家族のための大黒柱�セった後まだ見る若い母親です、ジュリアナ・チャン、香港の中国大学の医学および治療学の教授、言いました。
※ishは40代とかかな??(坂口の意見)
”We are going to see a lot of early deaths,disabilities and there will be an enormous burden on the health care system,which can't cope.Lots of young people will come in requiring bypass operations,dialysis,rehabilitation for strokes and our productivity will reduce.”
「私たちは多くの若死を見るつもりです、不能、また、ヘルスケアシステム(それは対処することができない)上に巨大な負担があるでしょう。多くの若い人々が、バイパス手術、透析、ストロークのためのリハビリテーションおよび私たちの生産力が縮小するだろうということを要求する際に来るでしょう。」
Apart from eating too much,doing too little exercise and smoking,experts say Asia's weight problem is more pronounced than in the West because of a genetic predisposition to obesity.
あまりに食べることとは別に、運動および喫煙を行って、専門家は、肥満への遺伝素質のために西洋でよりも、アジアの体重の問題がもっと断言されるとはあまりほとんど言いません。
”For the same body weight,Asians have more body fat than Caucasians, particularly in the viscera(organs in the abdominal cavity),”said Chan.
「同じ体重のために、アジア人は特に内臓(腹腔中の器官)に、コーカサス地方の人より太ったより多くの身体を持っています」チャンは言いました。
"Because of the climate, we are not built to store so much fat ,so it spills into the liver, muscles and pancreas,which is why you hear so much about fatty liver.”
「気候のために、私たちはこれほど多くの脂肪を格納するためには構築されません。したがって、それは肝臓、筋肉および膵臓へこぼれます。そういうわけで、脂肪肝に関して非常に聞きます。」
|
|
|
|
コメント(14)
「貧富の格差が極めて深刻」90%が回答 2006/12/25(月) 10:08:51
中国青年報や中国大手ポータルサイトの新浪網などがこのほど1万250人を対象に行った調査によると、89.3%が「中国では現在、貧富の格差が極めて深刻だ」と答えていることが分かった。(編集担当:菅原大輔)
食生活の地域比較:南北で異なる消費パターンを追う
2006/11/24(金) 11:17:36更新
経済発展の伴う中国食生活・食料消費の現状分析(4)−張丹
従来、人々は生活する地域の気候・風土に適した農業生産を行い、そこで収穫された食料を食べ、その地域独自の食料消費パターンを形成するというような、いわば風土が与えるままの食事に慣れてきた。当然のことながら風土は農業にだけではなく、食事の好みや価値観にも反映している。
中国において、「食」にしても古くから千差万別であった。長い年月をかけて、各地域独自の食文化が形成されてきた。その中で代表的な南北の食文化の形成は中国の食生活に与える最も大きな要因である。ここには秦嶺(チンリン)と淮河(ホワイホウ)を境として、中国大陸を北と南に分け、諸側面から南北の食生活の違いを見てみる。
一般には、エンゲル係数を用いて、家計収入による生活水準が比較できる。しかし、中国において地域別の現状をみると、必ずしも所得の高い地域ほどエンゲル係数が低いといった形になっていない。経済的な要因だけでは、中国の各地域ごとの食生活の違いは説明し難いのである。
南と北(2005年都市世帯のみ)において、経済面では南の1人当たり年間可処分所得(1万789.82元)は北のそれ(9562.21元)より高い値を示しており、1人当たり年間の食料消費(南が3224.74元、北が2512.35元)も高い水準となっている。全体的にエンゲル係数は南(39.7%)が北(34.8%)より4.9ポイント高いということが分かる。
中国では、多様かつ嗜好に富んだ食料消費が発展しており、特に南ではそうした傾向が強い。南では山の幸、海の幸に恵まれた土地柄で、食料生産は特に副食の種類が北より多く、また経済的に裕福なので、より高品質の食料品が消費され、食生活面では北より豊かであると推測される。このため、南ではエンゲル係数が所得に比して高い状況がもたらされている。
消費支出の構成比(05年都市世帯のみ)から見ると、南と北において、基礎消費である食費は、上で指摘したように、南が北より4.9ポイント高くなっているが、それに対し、基礎消費としての被服・履物の占める割合は北(11.9%)が南(9.4%)より2.5ポイント高くなっている。
衣食といった基礎消費志向では、南は食費に対して、服装に対する消費が少ないが、一方、北では食費が少なく、その代わりに服装に消費されている。南では食事が大事にされ、北は服装の方を重んじる。気候の差もあるだろう。まさに南北文化においての価値観の違いが現れている。
食費構成比(05年都市世帯のみ)から見ると、穀類消費の多い北(北が11.8%、南が9.0%)に対して、肉類消費の多いのは南(北が17.6%、南が22.8%)である。鶏卵類の消費は北(北が3.0%、南が2.2%)が多く、それに対して魚介類の消費は南(北が4.1%、南が7.6%)が北を圧倒している。また寒冷の北では酒類の消費に関して、北(5.7%)が南(4.5%)より1.2ポイント高いが、外食消費については南(20.8%)と北(21.3%)がほぼ同じ比率を持っていることを示している。
以上のデータから見ると、南では伝統的な食生活を代表する植物性食品の消費が少ないのに対して、高度化・近代化を代表する動物性食品(肉類、魚介類)の消費が多い。一方、北においては植物性食料品の消費が多く、動物性食料品の消費が少ない。
経済の急速な発展に伴い、中国各地域の食生活は近代化・高度化へ進んでいると同時に、各地域の農作物の違いと長い間に形成された南北の独特的な食文化になお強く影響を受けている。現在に至っても、南北双方では独自の食に関する文化や消費のパターンを持っていることが明らかである。
経済の側面から、南は概に北より豊かであるにも関わらず、エンゲル係数も高いということが、中国における食生活の地域的な特徴として挙げられる。その原因を分析すると、経済発展に伴い、南方では食生活の近代化・高度化が北方より進み、食料消費についてより高品質の食料品や外食などとして消費され、その上、南北の食に対する価値観や独特な食文化にも影響されていると思われる。(執筆者:張丹)
中国において、都市部と農村部の格差問題が当面の最大の課題の一つである。以上見てきたように、都市部と農村部の消費パターンの相違が大きいことは、一面で格差問題の深刻性を浮き彫りにしているが、これは長期間にわたって、それぞれ別の社会的・経済的な構造の中で、消費活動が営まれた結果であると考えられる。
都市部と農村部の格差を解消するためには、農村部における所得再配分政策や社会保障制度などを早急に見直す必要がある。その成否は、地域所得格差に伴う社会問題の解決と内需拡大による持続的な経済成長の実現にも影響してくるものである。(執筆者:張丹)
食生活・食料消費の国際比較:中国独自のパターンは?
2006/12/21(木) 10:48:08更新
経済発展の伴う中国食生活・食料消費の現状分析(6)−張丹
前回までに紹介してきたように、中国の食生活は、改革開放以降の高度経済成長に伴って大きく変化してきた。主食として穀類の消費が年々大幅に減少傾向を示すと同時に、肉類、鶏卵類、砂糖、油脂類が増加、穀類中心の食生活から、畜産物中心の食生活への変化が一層進んでいる。
とは言え、独自の自然・社会風土に適した農業文化、食料・農業生産の状況や食料品の輸入状況などの食料供給体制、所得水準と栄養知識など、様々な要因が絡み合い、中国では長い年月をかけて形成された固有の食料消費の特徴をもっている。
ここでは、FAO(国連食料農業機関)の統計データを用い、世界の代表的な国々と比較しながら、中国における食生活・食料消費の国際比較を試みる。
FAOのデータによれば、2004年の1人当たり1日食料消費量は、食肉では米国(257.5グラム)、スペイン(236.7グラム)、オーストラリア(235.3グラム)が1日200グラム以上で飛び抜けて多いに比べ、中国は156.1グラムで米国の60%、欧米比較国(オーストラリア、カナダ、デンマーク、オランダ、フランス、トイヅ、イタリア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国の12カ国)の平均水準(208.3グラム)の75%となっている。
しかし、アジア諸国と比較すると、中国の肉類消費は、上位である韓国(93.1グラム)、日本(85.8グラム)を上回り、アジア第1位となっている。肉類消費の中で豚肉(98.9グラム)が多いのが特徴として挙げられる。鶏卵類の消費も多く、トップの日本(52.3グラム)に近い48.3グラムに達し、アジア比較国(中国、日本、韓国、トルコ、パキスタン、マレーシア、インドネシア、フィリピン、タイの9カ国)の中では第2位となっている。
牛乳の平均消費量について、上述の欧米諸国は1日1人当たり681.9グラムであるのに対し、アジアの国々は1日1人当たり151.8グラム。牛乳の消費量は中国ではわずか42.3グラムで、アジア諸国の中でも下位である。
穀類の1日1人当たりの消費を見ると、中国は欧米とアジアの比較国の中で、コメ(288.2グラム)と小麦(133.2グラム)の消費量が比較的多く、比較国の中で中盤ほどに位置する。また、野菜のそれ(769.8グラム)が全比較国の中でトップであり、米国(357.5グラム)の2倍であるのに対し、果物のほうは中国(154.8グラム)が米国(340.1グラム)の2分の1に過ぎず、アジア比較国の平均(175.3グラム)よりやや低い水準となっている。さらに、砂糖の消費量はわずか219.4グラムで、全比較国のなかで最下位となっている。
FAOの以上のようなデータによる比較は、従来、アジアの国々では穀類の消費量が多く、欧米諸国は動物性食品を中心とするといったような、一般的な見解との矛盾点はないが、ここで指摘したいのは、以上で見た主要食料消費の国際比較から、現段階の中国における食生活は大きく変化したといえ、国際比較を通してみると、依然として穀類への依存度が高いことが分かる。
一方、FAOによるカロリー摂取のデータによれば、04年に供給カロリーでは欧米諸国の1日1人当たり平均が約3515キロカロリーに対し、それに占める植物性の割合は約69%である。それに比べ、アジア諸国のそれは約2779キロカロリーで、その植物性比率は84%である。また、アジアの中でも、日本のカロリー摂取量は2756キロカロリーで、植物性比率は79%。これに比べ、中国はそれぞれ2935キロカロリーと78%で、カロリーは比較的高いが、植物性比率は日本とそれほど違いはない。
この国際比較の結果、現在中国の食料消費は、カロリーとしては既に飽和水準に達しており、国民の所得水準がまだ低水準にとどまっているにもかかわらず、カロリー摂取量、動物性食品から摂取するカロリー量はともに多いことがわかる。これは中国の食文化の伝統に根付いた特有の食料消費パターンに起因していると思われる。
中国では古来「民以食為天」(民は食をもって天となす)という言葉に現れているように、「食」というものを非常に重視する。多様な食品を開発し、調理に工夫を凝らし、美味・珍味を求める民族的志向は、条件さえ許せば、まず食生活を改善させたいと考える。
冒頭で指摘した様々な要因で、中国と近隣のアジア諸国の食料消費は、国際的に見て欧米の国々とは異なった、共通した特徴を持つが、それとともに、中国は独自の食料消費のパターンを持っていると結論づけることができよう。(執筆者:張丹)
中国、糖尿病と肥満
2006年12月01日(金) - トラックバック[0] - コメント[0] - 中国人の食生活
11月14日世界糖尿病日
人人享有糖尿病保険(糖尿病保険に入りましょう)
糖分や塩分、カロリーの高い食物の摂取量が急速に増えたこと、運動不足、肥満の増加、喫煙などが原因で、中国では糖尿病患者が急増しているそうです。
WHOがまとめた「世界の慢性疾患調査」によると、中国の糖尿病患者数はインドに続いて世界第2位。2025年には1億人に達すると、専門家は予測しています。
なかでも目立つのが、子どもの糖尿病患者数です。中国衛生部の調査によると、都市部の7歳から17歳の20%以上、成人の27.55%が、BMI25以上の肥満か過体重で、北京ではこの10年間に、肥満児童の割合が5−7倍も増加したとか。
たしかに深センでも、太っている子どもが多いと感じます。
子どもが幼稚園バスを降りるなり、保護者は待ち構えていて、タッパーに一口サイズに切って準備していた果物やバナナ、ヨーグルトなどを与えます。公園で遊ぶ子どもを追いかけながら、一口ずつ口に運んでいる人もいるので、家ではきっと、食べたい放題なのでしょう。マクドナルドやケンタッキーなどのファーストフード店も、親子づれであふれかえっています。
広州中一薬業の糖尿病治療薬・「消渇丸」は、国内販売シェア
78%以上。糖尿病治療薬は60億元(870億円)市場
栄養失調による疾患を予防すると同時に、慢性疾患の予防にも力を入れなければならない現実が、中国にはあります。
Q5 中国の伝統的な家庭料理にはどんなものがありますか。また伝統的な家庭料理は最近どのように変わってきていますか。
中国北部の伝統的な家庭料理は水餃子ですが、最近は餃子離れが見られるようになりました。フライドチキン、ハンバーガー、ピザなどのアメリカ風のファーストフードを好む若者が多くなったからだと思います。
中国の肥満人口6000万人 栄養不良も2400万人
約2400万人が栄養不良に陥る一方、約6000万人が肥満−。中国国家食物栄養諮問委員会の専門家がこのほど、中国のいびつな栄養事情に関する報告をまとめた。中国メディアが伝えた。
貧富の格差や、都市部と貧困農村部の地域格差が背景にある。報告は都市部での肥満対策として、行政機関などによる適切な栄養指導を実施する必要があると訴えた。「肥満」の定義は明記していない。
報告によると、全国の貧困人口は2005年末で約2365万人で、この層の栄養状態は劣悪と指摘。一方で、経済発展に伴い豊かさを享受する都市部では脂肪分を多く含む動物性食物の摂取が急増し、栄養のバランスを崩した結果、治療が必要なほどの肥満や、生活習慣病が子供にまで拡大しているという。
中国の高血圧と高脂血症の患者は計約1億6000万人、糖尿病患者は約2000万人に上る。
中国青年報や中国大手ポータルサイトの新浪網などがこのほど1万250人を対象に行った調査によると、89.3%が「中国では現在、貧富の格差が極めて深刻だ」と答えていることが分かった。(編集担当:菅原大輔)
食生活の地域比較:南北で異なる消費パターンを追う
2006/11/24(金) 11:17:36更新
経済発展の伴う中国食生活・食料消費の現状分析(4)−張丹
従来、人々は生活する地域の気候・風土に適した農業生産を行い、そこで収穫された食料を食べ、その地域独自の食料消費パターンを形成するというような、いわば風土が与えるままの食事に慣れてきた。当然のことながら風土は農業にだけではなく、食事の好みや価値観にも反映している。
中国において、「食」にしても古くから千差万別であった。長い年月をかけて、各地域独自の食文化が形成されてきた。その中で代表的な南北の食文化の形成は中国の食生活に与える最も大きな要因である。ここには秦嶺(チンリン)と淮河(ホワイホウ)を境として、中国大陸を北と南に分け、諸側面から南北の食生活の違いを見てみる。
一般には、エンゲル係数を用いて、家計収入による生活水準が比較できる。しかし、中国において地域別の現状をみると、必ずしも所得の高い地域ほどエンゲル係数が低いといった形になっていない。経済的な要因だけでは、中国の各地域ごとの食生活の違いは説明し難いのである。
南と北(2005年都市世帯のみ)において、経済面では南の1人当たり年間可処分所得(1万789.82元)は北のそれ(9562.21元)より高い値を示しており、1人当たり年間の食料消費(南が3224.74元、北が2512.35元)も高い水準となっている。全体的にエンゲル係数は南(39.7%)が北(34.8%)より4.9ポイント高いということが分かる。
中国では、多様かつ嗜好に富んだ食料消費が発展しており、特に南ではそうした傾向が強い。南では山の幸、海の幸に恵まれた土地柄で、食料生産は特に副食の種類が北より多く、また経済的に裕福なので、より高品質の食料品が消費され、食生活面では北より豊かであると推測される。このため、南ではエンゲル係数が所得に比して高い状況がもたらされている。
消費支出の構成比(05年都市世帯のみ)から見ると、南と北において、基礎消費である食費は、上で指摘したように、南が北より4.9ポイント高くなっているが、それに対し、基礎消費としての被服・履物の占める割合は北(11.9%)が南(9.4%)より2.5ポイント高くなっている。
衣食といった基礎消費志向では、南は食費に対して、服装に対する消費が少ないが、一方、北では食費が少なく、その代わりに服装に消費されている。南では食事が大事にされ、北は服装の方を重んじる。気候の差もあるだろう。まさに南北文化においての価値観の違いが現れている。
食費構成比(05年都市世帯のみ)から見ると、穀類消費の多い北(北が11.8%、南が9.0%)に対して、肉類消費の多いのは南(北が17.6%、南が22.8%)である。鶏卵類の消費は北(北が3.0%、南が2.2%)が多く、それに対して魚介類の消費は南(北が4.1%、南が7.6%)が北を圧倒している。また寒冷の北では酒類の消費に関して、北(5.7%)が南(4.5%)より1.2ポイント高いが、外食消費については南(20.8%)と北(21.3%)がほぼ同じ比率を持っていることを示している。
以上のデータから見ると、南では伝統的な食生活を代表する植物性食品の消費が少ないのに対して、高度化・近代化を代表する動物性食品(肉類、魚介類)の消費が多い。一方、北においては植物性食料品の消費が多く、動物性食料品の消費が少ない。
経済の急速な発展に伴い、中国各地域の食生活は近代化・高度化へ進んでいると同時に、各地域の農作物の違いと長い間に形成された南北の独特的な食文化になお強く影響を受けている。現在に至っても、南北双方では独自の食に関する文化や消費のパターンを持っていることが明らかである。
経済の側面から、南は概に北より豊かであるにも関わらず、エンゲル係数も高いということが、中国における食生活の地域的な特徴として挙げられる。その原因を分析すると、経済発展に伴い、南方では食生活の近代化・高度化が北方より進み、食料消費についてより高品質の食料品や外食などとして消費され、その上、南北の食に対する価値観や独特な食文化にも影響されていると思われる。(執筆者:張丹)
中国において、都市部と農村部の格差問題が当面の最大の課題の一つである。以上見てきたように、都市部と農村部の消費パターンの相違が大きいことは、一面で格差問題の深刻性を浮き彫りにしているが、これは長期間にわたって、それぞれ別の社会的・経済的な構造の中で、消費活動が営まれた結果であると考えられる。
都市部と農村部の格差を解消するためには、農村部における所得再配分政策や社会保障制度などを早急に見直す必要がある。その成否は、地域所得格差に伴う社会問題の解決と内需拡大による持続的な経済成長の実現にも影響してくるものである。(執筆者:張丹)
食生活・食料消費の国際比較:中国独自のパターンは?
2006/12/21(木) 10:48:08更新
経済発展の伴う中国食生活・食料消費の現状分析(6)−張丹
前回までに紹介してきたように、中国の食生活は、改革開放以降の高度経済成長に伴って大きく変化してきた。主食として穀類の消費が年々大幅に減少傾向を示すと同時に、肉類、鶏卵類、砂糖、油脂類が増加、穀類中心の食生活から、畜産物中心の食生活への変化が一層進んでいる。
とは言え、独自の自然・社会風土に適した農業文化、食料・農業生産の状況や食料品の輸入状況などの食料供給体制、所得水準と栄養知識など、様々な要因が絡み合い、中国では長い年月をかけて形成された固有の食料消費の特徴をもっている。
ここでは、FAO(国連食料農業機関)の統計データを用い、世界の代表的な国々と比較しながら、中国における食生活・食料消費の国際比較を試みる。
FAOのデータによれば、2004年の1人当たり1日食料消費量は、食肉では米国(257.5グラム)、スペイン(236.7グラム)、オーストラリア(235.3グラム)が1日200グラム以上で飛び抜けて多いに比べ、中国は156.1グラムで米国の60%、欧米比較国(オーストラリア、カナダ、デンマーク、オランダ、フランス、トイヅ、イタリア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国の12カ国)の平均水準(208.3グラム)の75%となっている。
しかし、アジア諸国と比較すると、中国の肉類消費は、上位である韓国(93.1グラム)、日本(85.8グラム)を上回り、アジア第1位となっている。肉類消費の中で豚肉(98.9グラム)が多いのが特徴として挙げられる。鶏卵類の消費も多く、トップの日本(52.3グラム)に近い48.3グラムに達し、アジア比較国(中国、日本、韓国、トルコ、パキスタン、マレーシア、インドネシア、フィリピン、タイの9カ国)の中では第2位となっている。
牛乳の平均消費量について、上述の欧米諸国は1日1人当たり681.9グラムであるのに対し、アジアの国々は1日1人当たり151.8グラム。牛乳の消費量は中国ではわずか42.3グラムで、アジア諸国の中でも下位である。
穀類の1日1人当たりの消費を見ると、中国は欧米とアジアの比較国の中で、コメ(288.2グラム)と小麦(133.2グラム)の消費量が比較的多く、比較国の中で中盤ほどに位置する。また、野菜のそれ(769.8グラム)が全比較国の中でトップであり、米国(357.5グラム)の2倍であるのに対し、果物のほうは中国(154.8グラム)が米国(340.1グラム)の2分の1に過ぎず、アジア比較国の平均(175.3グラム)よりやや低い水準となっている。さらに、砂糖の消費量はわずか219.4グラムで、全比較国のなかで最下位となっている。
FAOの以上のようなデータによる比較は、従来、アジアの国々では穀類の消費量が多く、欧米諸国は動物性食品を中心とするといったような、一般的な見解との矛盾点はないが、ここで指摘したいのは、以上で見た主要食料消費の国際比較から、現段階の中国における食生活は大きく変化したといえ、国際比較を通してみると、依然として穀類への依存度が高いことが分かる。
一方、FAOによるカロリー摂取のデータによれば、04年に供給カロリーでは欧米諸国の1日1人当たり平均が約3515キロカロリーに対し、それに占める植物性の割合は約69%である。それに比べ、アジア諸国のそれは約2779キロカロリーで、その植物性比率は84%である。また、アジアの中でも、日本のカロリー摂取量は2756キロカロリーで、植物性比率は79%。これに比べ、中国はそれぞれ2935キロカロリーと78%で、カロリーは比較的高いが、植物性比率は日本とそれほど違いはない。
この国際比較の結果、現在中国の食料消費は、カロリーとしては既に飽和水準に達しており、国民の所得水準がまだ低水準にとどまっているにもかかわらず、カロリー摂取量、動物性食品から摂取するカロリー量はともに多いことがわかる。これは中国の食文化の伝統に根付いた特有の食料消費パターンに起因していると思われる。
中国では古来「民以食為天」(民は食をもって天となす)という言葉に現れているように、「食」というものを非常に重視する。多様な食品を開発し、調理に工夫を凝らし、美味・珍味を求める民族的志向は、条件さえ許せば、まず食生活を改善させたいと考える。
冒頭で指摘した様々な要因で、中国と近隣のアジア諸国の食料消費は、国際的に見て欧米の国々とは異なった、共通した特徴を持つが、それとともに、中国は独自の食料消費のパターンを持っていると結論づけることができよう。(執筆者:張丹)
中国、糖尿病と肥満
2006年12月01日(金) - トラックバック[0] - コメント[0] - 中国人の食生活
11月14日世界糖尿病日
人人享有糖尿病保険(糖尿病保険に入りましょう)
糖分や塩分、カロリーの高い食物の摂取量が急速に増えたこと、運動不足、肥満の増加、喫煙などが原因で、中国では糖尿病患者が急増しているそうです。
WHOがまとめた「世界の慢性疾患調査」によると、中国の糖尿病患者数はインドに続いて世界第2位。2025年には1億人に達すると、専門家は予測しています。
なかでも目立つのが、子どもの糖尿病患者数です。中国衛生部の調査によると、都市部の7歳から17歳の20%以上、成人の27.55%が、BMI25以上の肥満か過体重で、北京ではこの10年間に、肥満児童の割合が5−7倍も増加したとか。
たしかに深センでも、太っている子どもが多いと感じます。
子どもが幼稚園バスを降りるなり、保護者は待ち構えていて、タッパーに一口サイズに切って準備していた果物やバナナ、ヨーグルトなどを与えます。公園で遊ぶ子どもを追いかけながら、一口ずつ口に運んでいる人もいるので、家ではきっと、食べたい放題なのでしょう。マクドナルドやケンタッキーなどのファーストフード店も、親子づれであふれかえっています。
広州中一薬業の糖尿病治療薬・「消渇丸」は、国内販売シェア
78%以上。糖尿病治療薬は60億元(870億円)市場
栄養失調による疾患を予防すると同時に、慢性疾患の予防にも力を入れなければならない現実が、中国にはあります。
Q5 中国の伝統的な家庭料理にはどんなものがありますか。また伝統的な家庭料理は最近どのように変わってきていますか。
中国北部の伝統的な家庭料理は水餃子ですが、最近は餃子離れが見られるようになりました。フライドチキン、ハンバーガー、ピザなどのアメリカ風のファーストフードを好む若者が多くなったからだと思います。
中国の肥満人口6000万人 栄養不良も2400万人
約2400万人が栄養不良に陥る一方、約6000万人が肥満−。中国国家食物栄養諮問委員会の専門家がこのほど、中国のいびつな栄養事情に関する報告をまとめた。中国メディアが伝えた。
貧富の格差や、都市部と貧困農村部の地域格差が背景にある。報告は都市部での肥満対策として、行政機関などによる適切な栄養指導を実施する必要があると訴えた。「肥満」の定義は明記していない。
報告によると、全国の貧困人口は2005年末で約2365万人で、この層の栄養状態は劣悪と指摘。一方で、経済発展に伴い豊かさを享受する都市部では脂肪分を多く含む動物性食物の摂取が急増し、栄養のバランスを崩した結果、治療が必要なほどの肥満や、生活習慣病が子供にまで拡大しているという。
中国の高血圧と高脂血症の患者は計約1億6000万人、糖尿病患者は約2000万人に上る。
あたしも面白いのはっけん!!
中国ニュース - 12月30日(土)12時45分 ニュース記事写真動画トピックスNewsWatch 条件検索
[PR] 24時間365日、150万曲聴き放題のナップスター。1週間無料体験実施中!
<2006チャイナパワー>超特大の4歳児ウーくん、体重は横綱級
12月30日12時45分配信 Record China
拡大写真
4歳のウーくんは、重いダンベルも軽がる持ち上げる力自慢。39.5kgの体重は標準4歳児の2倍だ。将来は横綱確実?
2006年7月9日、河南(かなん)省許昌(きょしょう)市に住むうわさの巨漢4歳児、呉培俊(ウーペイジュン)くん。4歳児の標準体重15〜20kgに対し、なんとウーくんは39.5kg(2006年現在)!生まれたときから4350gの超ビッグサイズだった彼だが、その後もぐんぐん大きくなり、今や子どもとは思えない貫禄だ。
今日は友だちと楽しくゲームをして遊んでいるウーくん。重いダンベルを軽々持ち上げ、同世代の子どもたちから羨望のまなざしを浴びていた。しかし、両親はわが子の肥満を心配し、病院で診察してもらったこともあったというが、今のところ彼の成長ぶりは健康そのもの。愛くるしい笑顔を振りまき、どこへ行っても人気者のウーくんに、将来は日本の相撲取り?と期待を膨らませているそうだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061230-0000
中国ニュース - 12月30日(土)12時45分 ニュース記事写真動画トピックスNewsWatch 条件検索
[PR] 24時間365日、150万曲聴き放題のナップスター。1週間無料体験実施中!
<2006チャイナパワー>超特大の4歳児ウーくん、体重は横綱級
12月30日12時45分配信 Record China
拡大写真
4歳のウーくんは、重いダンベルも軽がる持ち上げる力自慢。39.5kgの体重は標準4歳児の2倍だ。将来は横綱確実?
2006年7月9日、河南(かなん)省許昌(きょしょう)市に住むうわさの巨漢4歳児、呉培俊(ウーペイジュン)くん。4歳児の標準体重15〜20kgに対し、なんとウーくんは39.5kg(2006年現在)!生まれたときから4350gの超ビッグサイズだった彼だが、その後もぐんぐん大きくなり、今や子どもとは思えない貫禄だ。
今日は友だちと楽しくゲームをして遊んでいるウーくん。重いダンベルを軽々持ち上げ、同世代の子どもたちから羨望のまなざしを浴びていた。しかし、両親はわが子の肥満を心配し、病院で診察してもらったこともあったというが、今のところ彼の成長ぶりは健康そのもの。愛くるしい笑顔を振りまき、どこへ行っても人気者のウーくんに、将来は日本の相撲取り?と期待を膨らませているそうだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061230-0000
解決法ってか、予防法になる。。(T_T)
http://www10.ocn.ne.jp/~s-clinic/himan.html
http://www24.big.or.jp/~keiyousi/kenmin/himan/himan.htm
http://www.komenet.or.jp/database/health/illness01.html
・エネルギー摂取を適度にとる
・脂肪の取りすぎをおさえる
・野菜と果物を適度にとる
・大豆や豆類、ナッツ類を適度にとる
・運動量を増やす。毎日30分ぐらいの適度な運動を習慣づける
あんまいいの見つけれんでほんまごめん↓…(;_;)
http://www10.ocn.ne.jp/~s-clinic/himan.html
http://www24.big.or.jp/~keiyousi/kenmin/himan/himan.htm
http://www.komenet.or.jp/database/health/illness01.html
・エネルギー摂取を適度にとる
・脂肪の取りすぎをおさえる
・野菜と果物を適度にとる
・大豆や豆類、ナッツ類を適度にとる
・運動量を増やす。毎日30分ぐらいの適度な運動を習慣づける
あんまいいの見つけれんでほんまごめん↓…(;_;)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ザ・岩井の会 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ザ・岩井の会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23166人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人