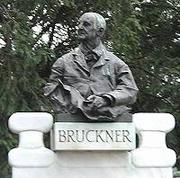ロジェストヴェンスキーのブルックナー交響曲全集を手に入れました。
今では中古でもなかなか手に入らない珍品になってしまったようです。
私はメロディアのレコードで1番のリンツと、ウィーン版、5番を持っていましたが、CDではマーラー版の4番を聴いて、これはなかなか面白いと思っていました。
まだ、全曲は聴いてませんが、どれも「ユニーク」という意味を最大に良い意味で使いたくなるビックリ箱みたいな演奏です。
ロジェストヴェンスキーという人は自分の音楽的な存在価値を極めて大事に考え抜いている人だという感じがします。
シベリウスの交響曲全集を聴いてもそう思うのですが、『いま、なぜ、自分がこの曲を振るのか』という意義が明確で、ほかの指揮者との差別化がかなり意識的になされているのです。
そして、それが、少なくとも私が聴いた範囲では、失敗していないのです。
ただし、この評価基準に『好悪』を持ち込んでしまうと、おおかた見誤ることになると思います。
だから、ブルックナーはかくあるべし、というような独善的な基準ではなく、あくまでもロジェストヴェンスキーというフィルターを通してのブルックナーという譜面をどう解釈しているのか、というのが聴きどころだと思います。
残念なのは、本当にすべての版を網羅しているわけではなく、3番の初稿もないし、5番の改訂版も欲しいところです。
今では中古でもなかなか手に入らない珍品になってしまったようです。
私はメロディアのレコードで1番のリンツと、ウィーン版、5番を持っていましたが、CDではマーラー版の4番を聴いて、これはなかなか面白いと思っていました。
まだ、全曲は聴いてませんが、どれも「ユニーク」という意味を最大に良い意味で使いたくなるビックリ箱みたいな演奏です。
ロジェストヴェンスキーという人は自分の音楽的な存在価値を極めて大事に考え抜いている人だという感じがします。
シベリウスの交響曲全集を聴いてもそう思うのですが、『いま、なぜ、自分がこの曲を振るのか』という意義が明確で、ほかの指揮者との差別化がかなり意識的になされているのです。
そして、それが、少なくとも私が聴いた範囲では、失敗していないのです。
ただし、この評価基準に『好悪』を持ち込んでしまうと、おおかた見誤ることになると思います。
だから、ブルックナーはかくあるべし、というような独善的な基準ではなく、あくまでもロジェストヴェンスキーというフィルターを通してのブルックナーという譜面をどう解釈しているのか、というのが聴きどころだと思います。
残念なのは、本当にすべての版を網羅しているわけではなく、3番の初稿もないし、5番の改訂版も欲しいところです。
|
|
|
|
コメント(13)
【5番】
ロシアのオケの金管の音色というのは目隠しをして聴かされてもわかるくらい特徴的。
その特徴が5番だと十全にユニークに生きるのだから面白い。
アダージョのリズムのギミックの面白さもさることながら、スケルツォの巨大な遅さが素晴らしい。
4番の初稿のスケルツォのことをどこかで書いたが、この4番の初稿『狩りのスケルツォ』の巨大さも類を見なかった。
ロジェストヴェンスキーはスケルツォ楽章に独特のリズム感を持っているようだ。
先入観と浅薄な知識がすぐにロジェストヴェンスキーはバレエ音楽も得意だった、などと思わせてしまう。
(白鳥の湖の全曲のレコードはCD化されてないのだろうか。あれはよかった)
フィナーレは金管が大フィーチャーされるのだが、ヤナーチェクばりにバリバリやるのが気持ちいい。
こんなのはブルックナーではない、という人は最初から聴かない方がいい。
私は断言するが、これもまたブルックナーなのだと。
ロジェストヴェンスキーの内声の引き出し方が優れているので、今まで聴いたことの無い隠れた旋律がどんどん聞こえる。
木管も金管に負けてはいない。
一番のネックは全体の録音のせいで、音色に厚みがないことだが、それさえクリアしていたら、かなりの名演だと思う。
ロシアのオケの金管の音色というのは目隠しをして聴かされてもわかるくらい特徴的。
その特徴が5番だと十全にユニークに生きるのだから面白い。
アダージョのリズムのギミックの面白さもさることながら、スケルツォの巨大な遅さが素晴らしい。
4番の初稿のスケルツォのことをどこかで書いたが、この4番の初稿『狩りのスケルツォ』の巨大さも類を見なかった。
ロジェストヴェンスキーはスケルツォ楽章に独特のリズム感を持っているようだ。
先入観と浅薄な知識がすぐにロジェストヴェンスキーはバレエ音楽も得意だった、などと思わせてしまう。
(白鳥の湖の全曲のレコードはCD化されてないのだろうか。あれはよかった)
フィナーレは金管が大フィーチャーされるのだが、ヤナーチェクばりにバリバリやるのが気持ちいい。
こんなのはブルックナーではない、という人は最初から聴かない方がいい。
私は断言するが、これもまたブルックナーなのだと。
ロジェストヴェンスキーの内声の引き出し方が優れているので、今まで聴いたことの無い隠れた旋律がどんどん聞こえる。
木管も金管に負けてはいない。
一番のネックは全体の録音のせいで、音色に厚みがないことだが、それさえクリアしていたら、かなりの名演だと思う。
【3番初稿】
なんと3番は3枚のCDに違ったバージョンが収録されていました。
まず、セカンドバージョンがCD4で、その次のCD5に初稿が収録されていたので、勘違いしましたが、無事CD5の初稿を聴いてまたまたびっくり。
まずその録音状態が、5番と全く違っていて、旧ソらしくない(?)低音と中音の充実した立派な音像です。
録音年が1988年。
5番は84年だから、この4年間に随分進歩したのかもしれない。
そしてもっと驚くのは、その演奏精度の凄さ。
ブルックナーがウィーンフィルに拒否られた、この超難しいリズムの掛け合いが頻出する譜面を何事もなくクリアしている。
相変わらずロジェストヴェンスキーのテンポ感は心地よく、この初稿には最近シモーネ・ヤングの名演がありますし、それ以前にもティントナーの当時としてはずば抜けた革新的な演奏もありますが、私としては、圧倒的にこのロジェストヴェンスキー盤をとりたい!
なんと3番は3枚のCDに違ったバージョンが収録されていました。
まず、セカンドバージョンがCD4で、その次のCD5に初稿が収録されていたので、勘違いしましたが、無事CD5の初稿を聴いてまたまたびっくり。
まずその録音状態が、5番と全く違っていて、旧ソらしくない(?)低音と中音の充実した立派な音像です。
録音年が1988年。
5番は84年だから、この4年間に随分進歩したのかもしれない。
そしてもっと驚くのは、その演奏精度の凄さ。
ブルックナーがウィーンフィルに拒否られた、この超難しいリズムの掛け合いが頻出する譜面を何事もなくクリアしている。
相変わらずロジェストヴェンスキーのテンポ感は心地よく、この初稿には最近シモーネ・ヤングの名演がありますし、それ以前にもティントナーの当時としてはずば抜けた革新的な演奏もありますが、私としては、圧倒的にこのロジェストヴェンスキー盤をとりたい!
8番の第一楽章。 85年録音。
ボックスでは第二集のCD5「ヌルテ」の後に第一楽章だけが収録されている。
どっち道いちまいには収まりきらないのだから、残りの2,3,4、楽章を一枚にまとめたのは、あのフィナーレの後に黙っていてもほかの曲がはじまらない、というので、非常に聴きやすい。良心的な見識だと思う。
これもまた素晴らしい音質だから、既に85年の時点でかなり改善されている。
演奏はトランペットがハモりパートのところが、トランペットの音質だけがほかの金管と違うのが面白い。
なんと言うか、こちらにつきぬけてくるようなソビエトのラッパが内声だけ強調しているように聞こえる。。
ウォッカを飲むとこうなるのか。
ロジェストヴェンスキーには本当にはずれがない。
返す返すも8番の初稿も入れてもらいたかったが、この85年の時点でソビエトでは譜面が無かった、ということも考えられないだろうか。
ボックスでは第二集のCD5「ヌルテ」の後に第一楽章だけが収録されている。
どっち道いちまいには収まりきらないのだから、残りの2,3,4、楽章を一枚にまとめたのは、あのフィナーレの後に黙っていてもほかの曲がはじまらない、というので、非常に聴きやすい。良心的な見識だと思う。
これもまた素晴らしい音質だから、既に85年の時点でかなり改善されている。
演奏はトランペットがハモりパートのところが、トランペットの音質だけがほかの金管と違うのが面白い。
なんと言うか、こちらにつきぬけてくるようなソビエトのラッパが内声だけ強調しているように聞こえる。。
ウォッカを飲むとこうなるのか。
ロジェストヴェンスキーには本当にはずれがない。
返す返すも8番の初稿も入れてもらいたかったが、この85年の時点でソビエトでは譜面が無かった、ということも考えられないだろうか。
モスクワ放送響との3番のCDが手に入った。
’72年の録音だという。
思いっきりソビエトとアメリカが冷戦していたころだなぁ、と思い、ちょっと1972年という年を調べてみた。
ニクソン米大統領、スペースシャトル計画開発を発令。
1月24日グアム島で元日本陸軍兵士横井庄一発見
札幌オリンピック開催。2月13日まで。
2月10日 - 横井庄一任務解除命令。(わざわざ...)
連合赤軍によるあさま山荘事件。
東武東上線成増駅前にモスバーガーの第一号実験店舗が開店。
川端康成が逗子市でガス自殺。
アメリカから日本へ沖縄返還、沖縄県発足。
大相撲名古屋場所は小結・高見山が13勝2敗で初優勝。外国人力士の幕内最高優勝は史上初。(いま、あたりまえ)
アメリカ、ベトナムからの地上勢力の撤退を終了。(アメリカが戦争に負けた)
ミュンヘンオリンピック事件。オリンピック選手村でゲリラがイスラエル人選手らを殺害。
王貞治が村山実から7試合連続本塁打を放つ。
北海道奈井江町の石狩炭鉱でガス爆発による落盤事故があり、作業員31人全員が生埋めにより死亡。(当時札幌に住んでいたことがあり、よく覚えている)
平田隆夫とセルスターズ「悪魔がにくい」「ハチのムサシは死んだのさ」
青い三角定規「太陽がくれた季節」
橋幸夫「子連れ狼」
上條恒彦「だれかが風の中で」
本田路津子「耳をすましてごらん」
ポップ・トップス「マミー・ブルー」
カーペンターズ「スーパースター」
アンディ・ウィリアムス「ゴッド・ファーザー・愛のテーマ」
↑↑↑
全部好きな曲。
ちあきなおみ「喝采」1972年度第14回日本レコード大賞大賞受賞曲
↑
年が明けてから初めてこの曲を知った。未だになぜ聴いたことが無かったのか不思議。
***********************************
と、まあ、こういう時代背景、日本が、であるが、こんな昭和のど真ん中で、モスクワではブルックナーが録音されていた。
当時の日本のオーケストラの技術では、最も厄介なのはこの3番だったろうから、おそらく初演もされていなかったのではないだろうか。
このロジェストヴェンスキーのモスクワとの3番は当トピの後年の録音と何の遜色もない。
金管はこのころの録音ではよく言われるように、ビヤーっと吠えまくる瞬間があって、その音色も実に金属的ではあるが、全くいやではない。
それだけ技術的に高いからだし、指揮者の解釈としての必然性を十分感じられるからだ。
しかも、これは『ワーグナー』だから、アダージョの後半の盛んにトランペットが襲いかかるところも不自然ではないのだ。
このころから、ロジェストヴェンスキーの譜読みは各声部に公平だったことが分かる。
いつも感心するのは、ロジェストヴェンスキーのスケルツォ、特にトリオだが、ここでも全く他で聴くことのできない悠然としたスケールのトリオを聴くことができる。
これだけでも一聴の価値ありだ。
フィナーレはここでも金管が大活躍しているし、第二主題の歌い方の微妙な【揺れ】も実に神経が細かい。
最大の難所、金管の「半拍ずれ」咆哮も難なく通り過ぎる。
後半になっても全く体力の衰えを知らない。
いわゆる《正統派》のブルックナーしか聴かない人にはもったいなくて、紹介したくもない。
’72年の録音だという。
思いっきりソビエトとアメリカが冷戦していたころだなぁ、と思い、ちょっと1972年という年を調べてみた。
ニクソン米大統領、スペースシャトル計画開発を発令。
1月24日グアム島で元日本陸軍兵士横井庄一発見
札幌オリンピック開催。2月13日まで。
2月10日 - 横井庄一任務解除命令。(わざわざ...)
連合赤軍によるあさま山荘事件。
東武東上線成増駅前にモスバーガーの第一号実験店舗が開店。
川端康成が逗子市でガス自殺。
アメリカから日本へ沖縄返還、沖縄県発足。
大相撲名古屋場所は小結・高見山が13勝2敗で初優勝。外国人力士の幕内最高優勝は史上初。(いま、あたりまえ)
アメリカ、ベトナムからの地上勢力の撤退を終了。(アメリカが戦争に負けた)
ミュンヘンオリンピック事件。オリンピック選手村でゲリラがイスラエル人選手らを殺害。
王貞治が村山実から7試合連続本塁打を放つ。
北海道奈井江町の石狩炭鉱でガス爆発による落盤事故があり、作業員31人全員が生埋めにより死亡。(当時札幌に住んでいたことがあり、よく覚えている)
平田隆夫とセルスターズ「悪魔がにくい」「ハチのムサシは死んだのさ」
青い三角定規「太陽がくれた季節」
橋幸夫「子連れ狼」
上條恒彦「だれかが風の中で」
本田路津子「耳をすましてごらん」
ポップ・トップス「マミー・ブルー」
カーペンターズ「スーパースター」
アンディ・ウィリアムス「ゴッド・ファーザー・愛のテーマ」
↑↑↑
全部好きな曲。
ちあきなおみ「喝采」1972年度第14回日本レコード大賞大賞受賞曲
↑
年が明けてから初めてこの曲を知った。未だになぜ聴いたことが無かったのか不思議。
***********************************
と、まあ、こういう時代背景、日本が、であるが、こんな昭和のど真ん中で、モスクワではブルックナーが録音されていた。
当時の日本のオーケストラの技術では、最も厄介なのはこの3番だったろうから、おそらく初演もされていなかったのではないだろうか。
このロジェストヴェンスキーのモスクワとの3番は当トピの後年の録音と何の遜色もない。
金管はこのころの録音ではよく言われるように、ビヤーっと吠えまくる瞬間があって、その音色も実に金属的ではあるが、全くいやではない。
それだけ技術的に高いからだし、指揮者の解釈としての必然性を十分感じられるからだ。
しかも、これは『ワーグナー』だから、アダージョの後半の盛んにトランペットが襲いかかるところも不自然ではないのだ。
このころから、ロジェストヴェンスキーの譜読みは各声部に公平だったことが分かる。
いつも感心するのは、ロジェストヴェンスキーのスケルツォ、特にトリオだが、ここでも全く他で聴くことのできない悠然としたスケールのトリオを聴くことができる。
これだけでも一聴の価値ありだ。
フィナーレはここでも金管が大活躍しているし、第二主題の歌い方の微妙な【揺れ】も実に神経が細かい。
最大の難所、金管の「半拍ずれ」咆哮も難なく通り過ぎる。
後半になっても全く体力の衰えを知らない。
いわゆる《正統派》のブルックナーしか聴かない人にはもったいなくて、紹介したくもない。
『6番』
文化省オケに戻って、6番。
これがまた、超名演。
ブルックナーという人はこれほど自由な解釈ができる音符を全編にちりばめていたのだ。
ロジェストヴェンスキーの好調さは、3番でもそうだったが、普通の指揮者が多少は「だれて」しまう、一つの楽章の中での音楽がちょっと停滞する個所に表れる。
そこをじっくりと面白く聴かせる才能はこれは、きっと説明は本人もできないだろう
聴いてみたところで、どこがどう、というのではなくて、とにかく飽きさせないのである。
ブルックナーは4つの典型的な楽章を生涯書き続けたといわれる。
どの曲も形式は似ているのは事実だが、実際に聴いてみると、それぞれ全く異なっている場合がほとんどだ。
唯一2番と3番のアダージョが似ている点は否定できないだろうが、これとて、ほかのだれ一人としてこういう音楽を書いていないという点を鑑みるともっと同じような曲を量産してほしかったとすら思うのである。
そんなブルックナーの様々なカラーをロジェストヴェンスキーは彼なりの色ですっかり覆ってしまっており、それでいて、まるっきりブルックナーであり続けるという離れ業をやってしまっているのだ。
ヘタにオケの音色が美しすぎるオケがブルックナー演奏を失敗しているのはロジェストヴェンスキーを聴くとなんとなく理由がわかる気がする。
文化省オケに戻って、6番。
これがまた、超名演。
ブルックナーという人はこれほど自由な解釈ができる音符を全編にちりばめていたのだ。
ロジェストヴェンスキーの好調さは、3番でもそうだったが、普通の指揮者が多少は「だれて」しまう、一つの楽章の中での音楽がちょっと停滞する個所に表れる。
そこをじっくりと面白く聴かせる才能はこれは、きっと説明は本人もできないだろう
聴いてみたところで、どこがどう、というのではなくて、とにかく飽きさせないのである。
ブルックナーは4つの典型的な楽章を生涯書き続けたといわれる。
どの曲も形式は似ているのは事実だが、実際に聴いてみると、それぞれ全く異なっている場合がほとんどだ。
唯一2番と3番のアダージョが似ている点は否定できないだろうが、これとて、ほかのだれ一人としてこういう音楽を書いていないという点を鑑みるともっと同じような曲を量産してほしかったとすら思うのである。
そんなブルックナーの様々なカラーをロジェストヴェンスキーは彼なりの色ですっかり覆ってしまっており、それでいて、まるっきりブルックナーであり続けるという離れ業をやってしまっているのだ。
ヘタにオケの音色が美しすぎるオケがブルックナー演奏を失敗しているのはロジェストヴェンスキーを聴くとなんとなく理由がわかる気がする。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ブルックナー 更新情報
-
最新のアンケート
ブルックナーのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90049人
- 2位
- 酒好き
- 170693人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208291人