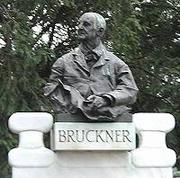アイヒホルンのブルックナー選集のボックスが出ました。
HRカッティングという音の改善がなされているらしいですが、アイヒホルンのブルックナーについては毀誉褒貶あるでしょうが、ブルックナーの音楽の価値は永遠に不滅です。
リマスターや、カッティングで変わるものでもありません。
さて私がこの世で一曲選べと言われたらブルックナーの9曲から迷いまくって9番を選ぶだろうくらい、この曲は大切です。
大切だからこそ、年に一度しか聴かない。私にとっての第九は年末に集中して聴くブル9です。
こんかいアイヒホルンのブルックナー9番を聴いて、特にアダージョのテンポがギリギリのところでブルックナーの真意と通じ合っている瞬間を感じました。
他にも素晴らしい瞬間がいっぱいありました。
前置きが長くなりましたが、、。
改めて9番の第4楽章の復元の試みを聴いて『なんと虚しい作業だろう』と思わざるを得ませんでした。
まず、ブルックナーの特徴である大胆な和音進行はいいのですが、ブルックナーの作曲の手順として、和音進行と小節数をきっちり枠付けするという習慣があったらしいので、いくら手書きのスコアが残っていたからといって、この第4楽章をブルックナーの『遺志』と受け止めるには無理な点が多すぎます。
つまりはメロディーらしきメロディーが皆無であること。
ブルックナーの書いてない部分については、どれほど凡百が集っても、捕捉できる才能があるはずもないこと。
ブルックナー自身フィナーレが間に合わないと知り、テ・デウムを!と言い残しているらしいこと。
などなど。。。、
皆様なりのご意見をお聞かせください。
他にもいろいろ復元版が出ているようですので、ご紹介もよろしかったらお願いします。
HRカッティングという音の改善がなされているらしいですが、アイヒホルンのブルックナーについては毀誉褒貶あるでしょうが、ブルックナーの音楽の価値は永遠に不滅です。
リマスターや、カッティングで変わるものでもありません。
さて私がこの世で一曲選べと言われたらブルックナーの9曲から迷いまくって9番を選ぶだろうくらい、この曲は大切です。
大切だからこそ、年に一度しか聴かない。私にとっての第九は年末に集中して聴くブル9です。
こんかいアイヒホルンのブルックナー9番を聴いて、特にアダージョのテンポがギリギリのところでブルックナーの真意と通じ合っている瞬間を感じました。
他にも素晴らしい瞬間がいっぱいありました。
前置きが長くなりましたが、、。
改めて9番の第4楽章の復元の試みを聴いて『なんと虚しい作業だろう』と思わざるを得ませんでした。
まず、ブルックナーの特徴である大胆な和音進行はいいのですが、ブルックナーの作曲の手順として、和音進行と小節数をきっちり枠付けするという習慣があったらしいので、いくら手書きのスコアが残っていたからといって、この第4楽章をブルックナーの『遺志』と受け止めるには無理な点が多すぎます。
つまりはメロディーらしきメロディーが皆無であること。
ブルックナーの書いてない部分については、どれほど凡百が集っても、捕捉できる才能があるはずもないこと。
ブルックナー自身フィナーレが間に合わないと知り、テ・デウムを!と言い残しているらしいこと。
などなど。。。、
皆様なりのご意見をお聞かせください。
他にもいろいろ復元版が出ているようですので、ご紹介もよろしかったらお願いします。
|
|
|
|
コメント(29)
そもそも未完の作品なわけですから、結局はないものねだりにすぎないのですが、復元という作業により、作曲家の本来の意図を垣間見ることができるかもしれないという幻想を捨て去ることはできません。
ただ、ブルックナーが生きた時代性を鑑みるに、作曲家が本来創出したかった音楽は、もっとアグレッシブなものだったように思います。
多分、そこには限りなく無調に近い、メロディすらないような音楽になった可能性は多分にあると思います。
もし、当時の聴衆に媚びたかもしれない、過去の改変のような音楽を9番に求めたとすれば、意外と期待外れなフィナーレになった可能性があるのではないでしょうか?
3楽章までは(少なくとも作曲家の意図により)完成していることを考えれば、コンサートにおいては、与えられたスコアの範囲内で、音楽を完結させる方向で演奏するのが、解釈論的には正しいかもしれないし、そういう演奏に我々が慣れ親しんでしまっていることも事実ですな^_^;
ただ、ブルックナーが生きた時代性を鑑みるに、作曲家が本来創出したかった音楽は、もっとアグレッシブなものだったように思います。
多分、そこには限りなく無調に近い、メロディすらないような音楽になった可能性は多分にあると思います。
もし、当時の聴衆に媚びたかもしれない、過去の改変のような音楽を9番に求めたとすれば、意外と期待外れなフィナーレになった可能性があるのではないでしょうか?
3楽章までは(少なくとも作曲家の意図により)完成していることを考えれば、コンサートにおいては、与えられたスコアの範囲内で、音楽を完結させる方向で演奏するのが、解釈論的には正しいかもしれないし、そういう演奏に我々が慣れ親しんでしまっていることも事実ですな^_^;
>ちぇるしいさん
本来創出したかった音楽は、もっとアグレッシブなものだったというのは素晴らしい言及だと思います。
確かに初稿のアグレッシブさは聴衆を意識したものとはいえず、ブルックナーの内面から噴き出る才能に従うとああいう結果になってしまうのでしょう。
そうすると、それまでの曲の作り方だけで、ブルックナーの第九のフィナーレを考えるということ自体が我々にはできなくなるのですね。
これはさらに面白い考えで
>無調に近い、メロディすら無いような音楽
というのは、アダージョの13thの咆哮を考えてもあり得るかもしれません。
ただ、それを断念した時点で、果たしてテ・デウムをつなぐ楽節を作ろうとした事実と矛盾しないか、という問題も残ります。
本来創出したかった音楽は、もっとアグレッシブなものだったというのは素晴らしい言及だと思います。
確かに初稿のアグレッシブさは聴衆を意識したものとはいえず、ブルックナーの内面から噴き出る才能に従うとああいう結果になってしまうのでしょう。
そうすると、それまでの曲の作り方だけで、ブルックナーの第九のフィナーレを考えるということ自体が我々にはできなくなるのですね。
これはさらに面白い考えで
>無調に近い、メロディすら無いような音楽
というのは、アダージョの13thの咆哮を考えてもあり得るかもしれません。
ただ、それを断念した時点で、果たしてテ・デウムをつなぐ楽節を作ろうとした事実と矛盾しないか、という問題も残ります。
補筆版のCDは入手可能なものは全て入手しています。今のところアイヒホルンによる演奏のものが一番しっくりきます。ただ、ブルックナーが書いていたらもっと充実した音楽になっていた事は間違いないな、と思います。
復元の試みは興味としてこれからも続けて欲しいと思います。散逸した楽譜が見つかる可能性もありますし、なによりもっと充実したものが出来上がることを願っていますので。今年発売されたキャラガン補筆2010年版(ゲルト・シャラー指揮、フィルハーモニー・フェスティヴァ)がアイヒホルンの演奏に次いで演奏として好きです。ただ、最後の部分がちょっと派手でブルックナーらしくないような気がしますが。アーノンクール指揮のCDは補筆されていない断片の演奏ですが、解説付きですのでなかなか良い感じです。
復元の試みは興味としてこれからも続けて欲しいと思います。散逸した楽譜が見つかる可能性もありますし、なによりもっと充実したものが出来上がることを願っていますので。今年発売されたキャラガン補筆2010年版(ゲルト・シャラー指揮、フィルハーモニー・フェスティヴァ)がアイヒホルンの演奏に次いで演奏として好きです。ただ、最後の部分がちょっと派手でブルックナーらしくないような気がしますが。アーノンクール指揮のCDは補筆されていない断片の演奏ですが、解説付きですのでなかなか良い感じです。
>HRカッティングで音が激変した〜
僕は、初期のCDを持っています。(補完版の分厚い詳しい解説書がついている)
そんなに音が変わったのですか!
音質マニアとしてはぜひ購入せねば!(笑)
***
インバルの4楽章盤は面白くなかったです。
あれがつまらなかったこともあり、アイヒホルンを聴いて驚愕しました。
8番のように4柱合体(4楽章の主題のすべての合体)があります。アイヒホルンではそこが絶妙です!(26分15秒)
この補完は公平に見てよく出来ていると思います。
3楽章の主題、ティンパニの強連打は、大勢のお坊さんによる読経のようです。
4柱合体のところは、人生の激しい煩悩が一斉に集約することによって、むしろ涅槃という境地に至ったような感じを受けます。
第3主題とテデウム主題との合体は実にスムーズで神々しい!(21分25秒)
金管の咆哮(23分43秒)にも昇天!
ここをシューリヒトが演奏したらものすごいことになっていたと夢想します。
コーダは平凡ですが、自分にとって、理想の交響曲とは何かと考えさせてくれます。平凡ではあっても、これ以外の終わり方が考えられません。
僕は、初期のCDを持っています。(補完版の分厚い詳しい解説書がついている)
そんなに音が変わったのですか!
音質マニアとしてはぜひ購入せねば!(笑)
***
インバルの4楽章盤は面白くなかったです。
あれがつまらなかったこともあり、アイヒホルンを聴いて驚愕しました。
8番のように4柱合体(4楽章の主題のすべての合体)があります。アイヒホルンではそこが絶妙です!(26分15秒)
この補完は公平に見てよく出来ていると思います。
3楽章の主題、ティンパニの強連打は、大勢のお坊さんによる読経のようです。
4柱合体のところは、人生の激しい煩悩が一斉に集約することによって、むしろ涅槃という境地に至ったような感じを受けます。
第3主題とテデウム主題との合体は実にスムーズで神々しい!(21分25秒)
金管の咆哮(23分43秒)にも昇天!
ここをシューリヒトが演奏したらものすごいことになっていたと夢想します。
コーダは平凡ですが、自分にとって、理想の交響曲とは何かと考えさせてくれます。平凡ではあっても、これ以外の終わり方が考えられません。
>YUJIさん
私なりの感想を他に書いたものを引用しますと...
?各楽器がしっかりと鳴っている。
?楽器の場所がよりはっきり分かる。
?舞台の奥行きが感じられる(ことが多い)
のですが、その反面、以前の録音になれた耳からすると、ブルックナー管の特徴だと思っていた、いい意味で曖昧な響きが、割とデッド気味に聴こえてくるきがします。
それを踏まえたうえで今回はやや復元版に疑問を呈してみようかと思ったきっかけになりました。
4つの主題が合体するところは、どうなんでしょう。。。もしかしたら、その前に各楽章の引用、過去の交響曲から、もしくは、ミサ曲からの一フレーズの引用などもあり得たかも、など、つまりブルックナーしか書き得なかった何かが、かけていたらどうしようなどという気持ちにもなります
私が一番思うのは転調の仕方です。
ブルックナーはたとえば7番の第一主題でも数回の転調をしているくらい、凡人には思いつかない転調を平気でしますし、5番のスケルツォのトリオの出だしのような、同じ音を全く役割、視点を変えたドッキリをすることがあります。
同じく5番の第二楽章の四分音符の伴奏に対する、大きな三連のノリの主題も最初にきいたときにはびっくりしました。
そういうびっくりがこの復元作業にはたしてあるだろうか、という疑問もあります。
今後の課題の一つだと思います
私なりの感想を他に書いたものを引用しますと...
?各楽器がしっかりと鳴っている。
?楽器の場所がよりはっきり分かる。
?舞台の奥行きが感じられる(ことが多い)
のですが、その反面、以前の録音になれた耳からすると、ブルックナー管の特徴だと思っていた、いい意味で曖昧な響きが、割とデッド気味に聴こえてくるきがします。
それを踏まえたうえで今回はやや復元版に疑問を呈してみようかと思ったきっかけになりました。
4つの主題が合体するところは、どうなんでしょう。。。もしかしたら、その前に各楽章の引用、過去の交響曲から、もしくは、ミサ曲からの一フレーズの引用などもあり得たかも、など、つまりブルックナーしか書き得なかった何かが、かけていたらどうしようなどという気持ちにもなります
私が一番思うのは転調の仕方です。
ブルックナーはたとえば7番の第一主題でも数回の転調をしているくらい、凡人には思いつかない転調を平気でしますし、5番のスケルツォのトリオの出だしのような、同じ音を全く役割、視点を変えたドッキリをすることがあります。
同じく5番の第二楽章の四分音符の伴奏に対する、大きな三連のノリの主題も最初にきいたときにはびっくりしました。
そういうびっくりがこの復元作業にはたしてあるだろうか、という疑問もあります。
今後の課題の一つだと思います
アイチャン君さん>
アーノンクール指揮の3番は私もいまいちと思って聞いていました。でも良く考えると冒頭のトランペットのテーマを楽譜どおりPで演奏しているのってあれくらいかもしれません。ブルックナーはもっと深いかも、、と思わされました。
ちなみにアーノンクール指揮の8番は弦楽器のボウイング(確か4楽章の冒頭)に独自色(新説?)を出していて彼らしい演奏です。なかなか悪くないですよ。まあ、好みはあるでしょうが。
ブル9ですが、確かに4つの主要主題の同時演奏はすでに8番で作曲されていたのでSMPC完成版(アイヒホルン演奏)もしくはその派生版も、もうちょっと違った補筆の仕方(?)があったかもしれませんね。個人的にはその後の割とあっさり終わる感じが物足りないです。雄大な感じはあるんですが。
アーノンクール指揮の3番は私もいまいちと思って聞いていました。でも良く考えると冒頭のトランペットのテーマを楽譜どおりPで演奏しているのってあれくらいかもしれません。ブルックナーはもっと深いかも、、と思わされました。
ちなみにアーノンクール指揮の8番は弦楽器のボウイング(確か4楽章の冒頭)に独自色(新説?)を出していて彼らしい演奏です。なかなか悪くないですよ。まあ、好みはあるでしょうが。
ブル9ですが、確かに4つの主要主題の同時演奏はすでに8番で作曲されていたのでSMPC完成版(アイヒホルン演奏)もしくはその派生版も、もうちょっと違った補筆の仕方(?)があったかもしれませんね。個人的にはその後の割とあっさり終わる感じが物足りないです。雄大な感じはあるんですが。
9番が完成していたらそれまでの音楽とは次元の違うモノになってしまったので、神がブルックナーを予定より早めに天に召してしまった。 他のシンフォニーの改訂していたので時間がなくなってしまった。十代の少女に入れ込んでいたので時間がなくなってしまった。ああ、ロリコンアントンよ 惜しいことをした。おふざけはこのくらいにして(真面目なツッコミ入れないでね)試みとしては面白いですね。ただBちゃんは4楽章完成前に寿命が尽きることが分かっていたので、3楽章の終わりをチラッと明るくして天に昇って行ったのでは?で、結論?音楽学者のみなさん補筆完成が楽しいんでしょうな。Bちゃんになったような気分で。すばらしい補筆完成版ならありかも。
惜しいことをした。おふざけはこのくらいにして(真面目なツッコミ入れないでね)試みとしては面白いですね。ただBちゃんは4楽章完成前に寿命が尽きることが分かっていたので、3楽章の終わりをチラッと明るくして天に昇って行ったのでは?で、結論?音楽学者のみなさん補筆完成が楽しいんでしょうな。Bちゃんになったような気分で。すばらしい補筆完成版ならありかも。
今何を聴いてますかトピにも書き込みましたが、
ボッシュのフィナーレの復元を聴いてぶっ飛びました。
ここには、当然みんなが期待してた、最大規模のフィナーレの復元という思想そのものがなく、第七のフィナーレのような、一見武骨で、メカニカルで、作曲法の技術が少し見えてしまうような対位法と、和音の大胆な進行が骨組みになっているのでした。
私も今まで聴いた復元版ではメロディーのないことがネックになっていたのですが、このボッシュの軽快な和音進行を聴いて、目からうろこが落ちました。
そもそもブルックナーが目指していた、第九のフィナーレは第八、第五のような巨大な、しかもフィナーレに最大の重心と意義を持たせたものではなかったのではないか、という考えが浮かんできました。
ちぇるしいさんの慧眼のとおり、メロディとは別の20世紀の先駆けとなるような大胆な和音と転調。それらを俯瞰で聴くと大きな枠で、旋律となるような今までとは違った意味での巨大さを持たせようとしていたのではないでしょうか。
すくなくとも、このボッシュの演奏を聴くと、4楽章制としての第九の骨組みがみえてきます。
ですから、わざわざ四つの主題を合体させることも必要ないかもしれないし、ブルックナー自身の結論もわからないのです。
とにかく、このボッシュのフィナーレの復元演奏は破格です。
ここでは20分で駆け抜けることで冗長さを防いでいるのではなく、和音進行そのものを聴かせようとしていることは明らかです。
そして、早いテンポをとることで、符点リズムが強調され、それがもう一つの大きな柱になって曲を形作って展開していることが分かる仕組みになっているのです。
使っている譜面はサマーレ、マツーカとかいう学者のものらしく、アイヒホルンと大差ないのかもしれませんが、解釈一つでここまで異なった演奏が生まれるというのは本当に感動します。
ただし、前半三つの楽章のテンポの速さはあくまでこのフィナーレのための布石とも言えなくもない解釈なので、ボッシュ自身がフィナーレ抜きで演奏した場合の録音も聴いてみたい気がします。
ちなみに話題になった残響の長さなど全く気になりません。それほどの残響と思えないので、ああいうことを最初に書いたのを鵜呑みにしてそれを前提に書いているレビューが多いことも、こういった、比較的若くて無名な指揮者のブルックナーの評価の邪魔になっていると思います。
ここには明らかに21世紀からのブルックナーがあります。
以上
ボッシュのフィナーレの復元を聴いてぶっ飛びました。
ここには、当然みんなが期待してた、最大規模のフィナーレの復元という思想そのものがなく、第七のフィナーレのような、一見武骨で、メカニカルで、作曲法の技術が少し見えてしまうような対位法と、和音の大胆な進行が骨組みになっているのでした。
私も今まで聴いた復元版ではメロディーのないことがネックになっていたのですが、このボッシュの軽快な和音進行を聴いて、目からうろこが落ちました。
そもそもブルックナーが目指していた、第九のフィナーレは第八、第五のような巨大な、しかもフィナーレに最大の重心と意義を持たせたものではなかったのではないか、という考えが浮かんできました。
ちぇるしいさんの慧眼のとおり、メロディとは別の20世紀の先駆けとなるような大胆な和音と転調。それらを俯瞰で聴くと大きな枠で、旋律となるような今までとは違った意味での巨大さを持たせようとしていたのではないでしょうか。
すくなくとも、このボッシュの演奏を聴くと、4楽章制としての第九の骨組みがみえてきます。
ですから、わざわざ四つの主題を合体させることも必要ないかもしれないし、ブルックナー自身の結論もわからないのです。
とにかく、このボッシュのフィナーレの復元演奏は破格です。
ここでは20分で駆け抜けることで冗長さを防いでいるのではなく、和音進行そのものを聴かせようとしていることは明らかです。
そして、早いテンポをとることで、符点リズムが強調され、それがもう一つの大きな柱になって曲を形作って展開していることが分かる仕組みになっているのです。
使っている譜面はサマーレ、マツーカとかいう学者のものらしく、アイヒホルンと大差ないのかもしれませんが、解釈一つでここまで異なった演奏が生まれるというのは本当に感動します。
ただし、前半三つの楽章のテンポの速さはあくまでこのフィナーレのための布石とも言えなくもない解釈なので、ボッシュ自身がフィナーレ抜きで演奏した場合の録音も聴いてみたい気がします。
ちなみに話題になった残響の長さなど全く気になりません。それほどの残響と思えないので、ああいうことを最初に書いたのを鵜呑みにしてそれを前提に書いているレビューが多いことも、こういった、比較的若くて無名な指揮者のブルックナーの評価の邪魔になっていると思います。
ここには明らかに21世紀からのブルックナーがあります。
以上
uberさん
ご意見ありがとうございます
シューベルトの未完成はスケルツォの書きかけが残っていてその演奏を聴いたことありますが、すぐにぶちきれて終わってしまう感じがいかにも筆を絶っている様子を想像させて、痛々しく思ったのを覚えています。
実際には単にシューベルトが作曲を忘れてだけかもしれませんが、いずれにせよ大作曲家の「未完成作品」には後世の人を放って置かない魅力があるのですね。
私はボッシュの録音を聴く前にこのトピを立てたのですが、ボッシュ体験後はやや考えが変わりました。
というのは、以前はどちらかというと、ブルックナーのような天才のみ完成は、神が渡した引導のようなものだと思っていたのですが、ボッシュの第七番風の処理を聴くと、ブルックナー自身の中には生きていれば、第10番での大フィナーレという構想すらあったのではないか、つまりベートーベンが偶数と奇数で曲の質量を変えたように、ブルックナーの中にも長大な8番のあとに、軽いフィナーレの9番を置いて、さらに、10番で総括するといった、設計があったらさぞかし面白かったろうな、と、、、まあ荒唐無稽のきわみですけど、そんな想像もできる余地のあるボッシュ盤の解釈でした。
ご意見ありがとうございます
シューベルトの未完成はスケルツォの書きかけが残っていてその演奏を聴いたことありますが、すぐにぶちきれて終わってしまう感じがいかにも筆を絶っている様子を想像させて、痛々しく思ったのを覚えています。
実際には単にシューベルトが作曲を忘れてだけかもしれませんが、いずれにせよ大作曲家の「未完成作品」には後世の人を放って置かない魅力があるのですね。
私はボッシュの録音を聴く前にこのトピを立てたのですが、ボッシュ体験後はやや考えが変わりました。
というのは、以前はどちらかというと、ブルックナーのような天才のみ完成は、神が渡した引導のようなものだと思っていたのですが、ボッシュの第七番風の処理を聴くと、ブルックナー自身の中には生きていれば、第10番での大フィナーレという構想すらあったのではないか、つまりベートーベンが偶数と奇数で曲の質量を変えたように、ブルックナーの中にも長大な8番のあとに、軽いフィナーレの9番を置いて、さらに、10番で総括するといった、設計があったらさぞかし面白かったろうな、と、、、まあ荒唐無稽のきわみですけど、そんな想像もできる余地のあるボッシュ盤の解釈でした。
シャラーという指揮者の復刻を含むブルックナーのCDがHMVにありました。
そのページの解説に版のことが書いてあり…
ボッシュの改訂版は
・「サマーレ、フィリップス、コールス、マツーカによる1992年フィナーレ復元版(サマーレ&コールスによる2005年改訂)」だそうです。
一方インバルは・「サマーレ&マツーカによる1984年フィナーレ復元版」
で
譜面が違えば当然演奏も全く違うのは当然なのでした。
いずれ金子建志氏には是非この9番フィナーレ復刻版の本を出していただきたいものです。
譜面を交えた克明な解説をCDのトラック番号がついた本が出たら、絶対買うのに。
ロジェストヴェンスキーもこの盤で録音しているようです。
ロジェストヴェンスキーはマーラー版の第四番のCDを聴いたことがありますが、全くブルックナーに聴こえないところが非常に面白かった記憶があります。
そこには4番のフィナーレの別の稿が録音されており、版自体は非常に納得のいく音楽でした。
9番の復元も是非聴いてみたい気がします。
また、アーノンクールの断片をそのまま録音したというCDが近いうちに届きます。楽しみです。
そのページの解説に版のことが書いてあり…
ボッシュの改訂版は
・「サマーレ、フィリップス、コールス、マツーカによる1992年フィナーレ復元版(サマーレ&コールスによる2005年改訂)」だそうです。
一方インバルは・「サマーレ&マツーカによる1984年フィナーレ復元版」
で
譜面が違えば当然演奏も全く違うのは当然なのでした。
いずれ金子建志氏には是非この9番フィナーレ復刻版の本を出していただきたいものです。
譜面を交えた克明な解説をCDのトラック番号がついた本が出たら、絶対買うのに。
ロジェストヴェンスキーもこの盤で録音しているようです。
ロジェストヴェンスキーはマーラー版の第四番のCDを聴いたことがありますが、全くブルックナーに聴こえないところが非常に面白かった記憶があります。
そこには4番のフィナーレの別の稿が録音されており、版自体は非常に納得のいく音楽でした。
9番の復元も是非聴いてみたい気がします。
また、アーノンクールの断片をそのまま録音したというCDが近いうちに届きます。楽しみです。
?ゲルト・シャラーの2010年版のフィナーレを聴きました。
これはテンポはボッシュに近いのですが、ボッシュが和音進行と転調の音楽だったのに対して、ゲルト・シャラーはそこからメロディーを引き出していると言っていいでしょう。
トップノートを強調することで和音進行の山脈の尾根をつたっていく感じです。
譜面もだいぶ違うようですが、実は今回はフィナーレだけをまず聴いているのですが、大変充実した演奏です。
?昨日は、内藤彰/東京ニューシティの2006年版を聴いたのですが、こちらも全体の中でのフィナーレを聴いてないのです。
ここでわかったことは、ブルックナーの音楽は各楽章だけを取り出してみても殆どの楽章が魅力満載なのに対して、この第九のフィナーレの復刻版は全体の流れの中でしか未だに価値を見いだせないということです。
考えてみれば当然のことですが、それほど、完成したブルックナーの譜面というものが代用のきかないものかが良くわかります。
それでもゲルト・シャラーの健闘ぶりはたたえられるべきで、この楽章だけ聴いてもかなりのランクだとは思いました。
?アーノンクールの断片も聴いたのですが、これはやはりアーノンクールの講演の内容の詳細が是非知りたくなります。
国内盤には翻訳が載っているそうなので、探してみようと思います。
幾多の問題を抱えつつも、それでも、ある時点までブルックナーが実際にオーケストレーションした譜面が残っているのは事実で、それを音に出してみたいというのは人情でしょう。
聴きたくない人は無理に聴く必要はありませんが、私はやはり聴いてみたいと思いました。
そして、私の最終的な妄想は、ブルックナーがこのフィナーレの譜面を全面的に改訂して、彼のフィナーレ史上最高の楽章を残した、という過去を想像することでもあります。
矛盾に満ちてはいますが、そうやっていろいろなことを想像する価値のある程度まではフィナーレの復刻作業は進んできているし、演奏そのものもかつてインバルが録音したような、無味乾燥な音の資料というレベルでなくなっているのは事実です。
ブルックナーが全く欠いていないエンディングだけは、すべての演奏が、痛々しいのですが、それは逆にブルックナー・エンディングの唯一無二さを証明しているのでしょう。
ブルックナーにはピアノ曲の小品もありますから、それらももっと広く演奏されるべきだし、交響曲の余白にそういった埋もれている作品を収録してもらいたいと思います。
別に交響曲なら交響曲しか一枚のCDに入れちゃいけないわけではないのですから。
これはテンポはボッシュに近いのですが、ボッシュが和音進行と転調の音楽だったのに対して、ゲルト・シャラーはそこからメロディーを引き出していると言っていいでしょう。
トップノートを強調することで和音進行の山脈の尾根をつたっていく感じです。
譜面もだいぶ違うようですが、実は今回はフィナーレだけをまず聴いているのですが、大変充実した演奏です。
?昨日は、内藤彰/東京ニューシティの2006年版を聴いたのですが、こちらも全体の中でのフィナーレを聴いてないのです。
ここでわかったことは、ブルックナーの音楽は各楽章だけを取り出してみても殆どの楽章が魅力満載なのに対して、この第九のフィナーレの復刻版は全体の流れの中でしか未だに価値を見いだせないということです。
考えてみれば当然のことですが、それほど、完成したブルックナーの譜面というものが代用のきかないものかが良くわかります。
それでもゲルト・シャラーの健闘ぶりはたたえられるべきで、この楽章だけ聴いてもかなりのランクだとは思いました。
?アーノンクールの断片も聴いたのですが、これはやはりアーノンクールの講演の内容の詳細が是非知りたくなります。
国内盤には翻訳が載っているそうなので、探してみようと思います。
幾多の問題を抱えつつも、それでも、ある時点までブルックナーが実際にオーケストレーションした譜面が残っているのは事実で、それを音に出してみたいというのは人情でしょう。
聴きたくない人は無理に聴く必要はありませんが、私はやはり聴いてみたいと思いました。
そして、私の最終的な妄想は、ブルックナーがこのフィナーレの譜面を全面的に改訂して、彼のフィナーレ史上最高の楽章を残した、という過去を想像することでもあります。
矛盾に満ちてはいますが、そうやっていろいろなことを想像する価値のある程度まではフィナーレの復刻作業は進んできているし、演奏そのものもかつてインバルが録音したような、無味乾燥な音の資料というレベルでなくなっているのは事実です。
ブルックナーが全く欠いていないエンディングだけは、すべての演奏が、痛々しいのですが、それは逆にブルックナー・エンディングの唯一無二さを証明しているのでしょう。
ブルックナーにはピアノ曲の小品もありますから、それらももっと広く演奏されるべきだし、交響曲の余白にそういった埋もれている作品を収録してもらいたいと思います。
別に交響曲なら交響曲しか一枚のCDに入れちゃいけないわけではないのですから。
内藤彰/東京ニューシティの2006年版 全曲
前回フィナーレのみ聴いたのだが、もちろんそんな聴き方はありえなくて、じっくりと聴ける機会を待っていた。
第一楽章。意外なほどオーソドックスな進み方。
低弦がよく転調を支えている。
ヴァイオリンの弱音での音程と表情の無さに若干の不満もあるが、破たんはしない。
第3主題のテンポが速いのはアクセントとして好ましい。しかも拙速にはなっていない。
提示部の最後に金管のトチリがあるが修正していないのがかえってライブ録音を残す姿勢がみられて良い。
ただ曲が進むとあらが目立つ。特に内声のほうが大きかったりするとハーモニーって何?となってしまう。
それに起伏が足りない。フォルテシモがうるさくないのはいいのだが、全体の迫力も犠牲にしているかのように聴こえる。
コーダのヴァイオリンがひどく下手。
ティンパニのバランスも悪い。
第二楽章=スケルツォ
スケルツォ部はリズムが全体で刻めてない。まあ、難しいのはわかるがもう少し練習してから聴かせるべきかもしれない。
問題のトリオがこれがトリオ2と呼ばれる珍しい譜面。
冗談かと思った。
まず演奏が下手過ぎて、譜面どおりなのかどうかもよくわからん。
しかし、音楽自体は非常に面白い。
ブルックナーの農民の踊り気質が出ているし、普通に演奏されるトリオの旋律も全く表情が違って出てくる。
もっとまともな演奏技術で是非聴いてみたい。
第3楽章
あっさりとしたものだ。
スケルツォに比べればずっと、こなれている。
しかし、ここでもホルンがヘロっている。
実演でも我が国のオケの一番の弱点はホルンだ。
それにしても淡々と進む。やっていることはブルックナーなのだが、鳴っている音楽がちっともブルックナーに聴こえない。
クライマックスになっても悲鳴も聞こえない。
【第4楽章】
さて、いよいよフィナーレの復元。
ここまでの『冷静』ブルックナーが功を奏している。
姿勢としてはボッシュの演奏に近い。
つまり私が提唱している第九のフィナーレは第7のフィナーレの敷衍型であるというもの。
メロディーや対位法ではなく、大きな和音の流れそのものが全体のメロディを形作っている。
未完成だから、結論が見いだせないのはもう今となっては致し方ない。
しかし、ブルックナーがどうして死に臨む2年間もかかって書き上げられなかったのか、という問題の一つの可能性はあるのではないか。
つまりいままでのブルックナー自身の方法論を乗り越えようとしていた。
それが実は上手くいってなかった。
多分の曲の冒頭から全部書き直さないと本当はダメだと気づいていたのではないか。
でも自分にはもう時間がない。そのことを十分わかっていたブルックナーはテ・デウムを持ってこようとしたりもしたが、何しろ時間がなかったのだ。
もともとそれほど筆が遅いわけではないのだが、健康がすぐれなかったことが大きな原因だろう。
返す返すも第1番のウィーン版に使った時間さえなかったら、、、と思ってしまう。
詮無いことだが。
この内藤のフィナーレだけは22分強という高速テンポが成功している。
この速いテンポでようやくブルックナーの意図が伝わるのだ。
それはそれとして、楽想の貧弱さは否めない。
これが9番の第3楽章まで書いてきた天才ブルックナーの音楽とはとても思えない。
最初から最後までモチーフが一つしかないのは、やはり未完成なのだ。
本当はここからさらなる第二第3のテーマ、副主題、対位法、フーガなどが書かれるはずだったのに違いない。
なんといってもこのキャラガン版そのものがかなり単調なのかもしれない。
いくら熱狂的なブルックナーファンの私にもこの22分はアイヒホルンの30分よりもずっと長く感じられる。
コーダも無理やり8番っぽくしているし、ワーグナーの引用っぽくしている。ああ、もう早く終わってほしいな。
前回フィナーレのみ聴いたのだが、もちろんそんな聴き方はありえなくて、じっくりと聴ける機会を待っていた。
第一楽章。意外なほどオーソドックスな進み方。
低弦がよく転調を支えている。
ヴァイオリンの弱音での音程と表情の無さに若干の不満もあるが、破たんはしない。
第3主題のテンポが速いのはアクセントとして好ましい。しかも拙速にはなっていない。
提示部の最後に金管のトチリがあるが修正していないのがかえってライブ録音を残す姿勢がみられて良い。
ただ曲が進むとあらが目立つ。特に内声のほうが大きかったりするとハーモニーって何?となってしまう。
それに起伏が足りない。フォルテシモがうるさくないのはいいのだが、全体の迫力も犠牲にしているかのように聴こえる。
コーダのヴァイオリンがひどく下手。
ティンパニのバランスも悪い。
第二楽章=スケルツォ
スケルツォ部はリズムが全体で刻めてない。まあ、難しいのはわかるがもう少し練習してから聴かせるべきかもしれない。
問題のトリオがこれがトリオ2と呼ばれる珍しい譜面。
冗談かと思った。
まず演奏が下手過ぎて、譜面どおりなのかどうかもよくわからん。
しかし、音楽自体は非常に面白い。
ブルックナーの農民の踊り気質が出ているし、普通に演奏されるトリオの旋律も全く表情が違って出てくる。
もっとまともな演奏技術で是非聴いてみたい。
第3楽章
あっさりとしたものだ。
スケルツォに比べればずっと、こなれている。
しかし、ここでもホルンがヘロっている。
実演でも我が国のオケの一番の弱点はホルンだ。
それにしても淡々と進む。やっていることはブルックナーなのだが、鳴っている音楽がちっともブルックナーに聴こえない。
クライマックスになっても悲鳴も聞こえない。
【第4楽章】
さて、いよいよフィナーレの復元。
ここまでの『冷静』ブルックナーが功を奏している。
姿勢としてはボッシュの演奏に近い。
つまり私が提唱している第九のフィナーレは第7のフィナーレの敷衍型であるというもの。
メロディーや対位法ではなく、大きな和音の流れそのものが全体のメロディを形作っている。
未完成だから、結論が見いだせないのはもう今となっては致し方ない。
しかし、ブルックナーがどうして死に臨む2年間もかかって書き上げられなかったのか、という問題の一つの可能性はあるのではないか。
つまりいままでのブルックナー自身の方法論を乗り越えようとしていた。
それが実は上手くいってなかった。
多分の曲の冒頭から全部書き直さないと本当はダメだと気づいていたのではないか。
でも自分にはもう時間がない。そのことを十分わかっていたブルックナーはテ・デウムを持ってこようとしたりもしたが、何しろ時間がなかったのだ。
もともとそれほど筆が遅いわけではないのだが、健康がすぐれなかったことが大きな原因だろう。
返す返すも第1番のウィーン版に使った時間さえなかったら、、、と思ってしまう。
詮無いことだが。
この内藤のフィナーレだけは22分強という高速テンポが成功している。
この速いテンポでようやくブルックナーの意図が伝わるのだ。
それはそれとして、楽想の貧弱さは否めない。
これが9番の第3楽章まで書いてきた天才ブルックナーの音楽とはとても思えない。
最初から最後までモチーフが一つしかないのは、やはり未完成なのだ。
本当はここからさらなる第二第3のテーマ、副主題、対位法、フーガなどが書かれるはずだったのに違いない。
なんといってもこのキャラガン版そのものがかなり単調なのかもしれない。
いくら熱狂的なブルックナーファンの私にもこの22分はアイヒホルンの30分よりもずっと長く感じられる。
コーダも無理やり8番っぽくしているし、ワーグナーの引用っぽくしている。ああ、もう早く終わってほしいな。
ゲルト・シャラーの終楽章つきの9番。
終楽章に向けて、まずは完成された三つの楽章の演奏について。
第一楽章
冒頭のトレモロが極めて弱音で演奏される。多くの演奏の中でもかなり小さいほうで、最初のクライマックスに向かって徐々にクレッシェンドするために布石として弱くしている。
その最初のクライマックスは巨大だ。
第二主題も極めて雄大に広々と歌われる。オケも優秀。
フィルハーモニー・フェスティバというミュンヘン・フィル、バイエルン放送響、バイエルン州立歌劇場管のメンバーと首席奏者たちで構成されるオーケストラだそうで、道理でうまいわけ。
寄せ集めなだけに固有の響きを持つことはないだろう。
また寄せ集めオケの特徴としてリズムが重たく引きずるような傾向があるような気がする。リハ不足のせいかもしれない。
主題提示部の最後のピチカートでの不協和音の後の展開部のティンパニーが良い。
極めて音程的な奏法で下から和音を支えているのだ。
弦が透明で金管も破たんなくオーソドックスなブルックナーが進んでいく。
【スケルツォ】は変わったリズム感だ。
一音一音踏みしめるような感覚。
それでいて決して重たく鳴っていないので、これはこれで面白いと思う。
トリオは妙に明るい。
第一楽章もそうだったが、この第九のデモーニッシュな空気感を敢えてけしているように聞こえる。
これは、ひょっとしたら、終楽章への布石かもしれない。
【アダージョ】
やはり巨大な解釈で、これはこれでフィナーレとして成り立つような重心を持つ。
この楽章はやはりそのオーケストラ特有のサウンドが欲しい。
スルスルと上手く演奏されるだけだとせっかくの天才の最後の閃きがもったいない。
【終楽章】
ウィリアム・キャラガンによる2010年に行われた最新改訂版。
なにが最終なのかよくわからないが、新しい資料が発見される可能性はないのだろうか。
アダージョが終わるとほぼアタッカともいえるほどすぐに始まる。
緊張感に満ちた響きは今までの復元版の演奏とは一線を画する。
旋律の跳躍と和音の転調がこの楽章の基軸となっているのだが、今までの復元版のノッペリとした単調なイメージがないのは、伴奏に起伏があるからだ。
おそらく譜面よりも強弱をつけていると思われる低音部の弦が有効だ。
このブルックナーの楽章の作り方は《しりとり》のように一つのフレーズが受け継がれていくものだが、試みとしては挑戦的だがいかんせん未完という事実をこれほど痛感する音楽もないと言っていいだろう。
そんななか、このシャラー盤は相当健闘している。
特に後半の復刻者のアイデアが枯渇しかけるところを演奏のエネルギーで今までにない充実した内容を聴かせるのだ。
譜面の違いはわからないが、おそらくこの2010年盤は相当改訂されているのだろう。
15分過ぎからが特に新鮮だ。
1〜3楽章までをこれほどたっぷりと振ってしかも終楽章を聴かせたシャラー盤は今のところボッシュ盤と対照的な演奏でありながら、好結果を残せたといえる。
終楽章に向けて、まずは完成された三つの楽章の演奏について。
第一楽章
冒頭のトレモロが極めて弱音で演奏される。多くの演奏の中でもかなり小さいほうで、最初のクライマックスに向かって徐々にクレッシェンドするために布石として弱くしている。
その最初のクライマックスは巨大だ。
第二主題も極めて雄大に広々と歌われる。オケも優秀。
フィルハーモニー・フェスティバというミュンヘン・フィル、バイエルン放送響、バイエルン州立歌劇場管のメンバーと首席奏者たちで構成されるオーケストラだそうで、道理でうまいわけ。
寄せ集めなだけに固有の響きを持つことはないだろう。
また寄せ集めオケの特徴としてリズムが重たく引きずるような傾向があるような気がする。リハ不足のせいかもしれない。
主題提示部の最後のピチカートでの不協和音の後の展開部のティンパニーが良い。
極めて音程的な奏法で下から和音を支えているのだ。
弦が透明で金管も破たんなくオーソドックスなブルックナーが進んでいく。
【スケルツォ】は変わったリズム感だ。
一音一音踏みしめるような感覚。
それでいて決して重たく鳴っていないので、これはこれで面白いと思う。
トリオは妙に明るい。
第一楽章もそうだったが、この第九のデモーニッシュな空気感を敢えてけしているように聞こえる。
これは、ひょっとしたら、終楽章への布石かもしれない。
【アダージョ】
やはり巨大な解釈で、これはこれでフィナーレとして成り立つような重心を持つ。
この楽章はやはりそのオーケストラ特有のサウンドが欲しい。
スルスルと上手く演奏されるだけだとせっかくの天才の最後の閃きがもったいない。
【終楽章】
ウィリアム・キャラガンによる2010年に行われた最新改訂版。
なにが最終なのかよくわからないが、新しい資料が発見される可能性はないのだろうか。
アダージョが終わるとほぼアタッカともいえるほどすぐに始まる。
緊張感に満ちた響きは今までの復元版の演奏とは一線を画する。
旋律の跳躍と和音の転調がこの楽章の基軸となっているのだが、今までの復元版のノッペリとした単調なイメージがないのは、伴奏に起伏があるからだ。
おそらく譜面よりも強弱をつけていると思われる低音部の弦が有効だ。
このブルックナーの楽章の作り方は《しりとり》のように一つのフレーズが受け継がれていくものだが、試みとしては挑戦的だがいかんせん未完という事実をこれほど痛感する音楽もないと言っていいだろう。
そんななか、このシャラー盤は相当健闘している。
特に後半の復刻者のアイデアが枯渇しかけるところを演奏のエネルギーで今までにない充実した内容を聴かせるのだ。
譜面の違いはわからないが、おそらくこの2010年盤は相当改訂されているのだろう。
15分過ぎからが特に新鮮だ。
1〜3楽章までをこれほどたっぷりと振ってしかも終楽章を聴かせたシャラー盤は今のところボッシュ盤と対照的な演奏でありながら、好結果を残せたといえる。
話題のラトル盤。
話題というよりはマスコミが無理やり【大事件】として取り沙汰したいるだけかもしれないが、聴かないわけにはいかない。
当初は、輸入盤でいいと思ったのだが、SACDが国内盤限定ということと、何よりも今回のフィナーレに関する原文解説の訳がライナーノーツに載っていることが分かり、一冊雑誌を買い足すつもりで国内盤を買った。
http://www.hmv.co.jp/product/detail/4994391
話題はフィナーレに集中するだろうが、「形式区分」と「小節数」に「演奏時間の表示」を加えた解説が素晴らしい。
これによって、どの程度完成された部分だったかが良くわかる。
今までいろいろな復元の試みを聴いてきたが、てっきりあとから想像で創作したと思っていた意外な部分がブルックナーが元々完成させていたりするのだ。
最後のほうはまるっきり想像の産物でそのことが分かるといかにもあざとい感じはあるし、物足りないなんてものじゃないが、ほかの復元の譜面よりはずっと唐突な感じがなくなっているのが今回のラトル盤の特徴だろう。
それでもこのまったくブルックナーが書いていないコーダを聴いてしまうと、あらためてこの第三楽章までのブルックナーの超ド級の天才性を再確認するし、この未完成のフィナーレに関しては、既にブルックナーの体力も枯渇していたと思わざるを得ない。
通常のブルックナーの楽章だったら、「骨格」にすぎないくらいの出来の譜面を果たして本当にブルックナーが決定稿としていたのだろうか。
何しろテンポ感がずっと一定で変化がない。リズムの権化のようなブルックナーのフィナーレの特徴がまるでない。
そもそもこの第九が未完成に終わったのも、ブルックナーの改訂癖のせいだから、この不完全で魅力の無いフィナーレをブルックナーが良しとするはずもないのだ。
死期を悟り、最初からの書きなおしをする健康状態でも精神状態でもなかったのだろう。
それにしてもこの復元のフィナーレも指揮者によってこれほど違って聞こえるものか、というくらい録音によって異なる印象を与えられる。
正直、今回のラトル盤の第一楽章には見るべきものは無いが、アダージョだけが格段に優れている。
第一楽章は見るべきものがないと書いたが、スケルツォは実はそれ以下だ。ここまでの30分はいかにも長く感じた。
典型的なブルックナーに不向きの指揮者かと思わせる演奏だ。
アダージョに関しては、フィナーレの存在、これから演奏するということを見据えたうえでの解釈だと解説には書いてあるが、そうも聴こえなかった。
充分この第三楽章が最後に鳴り終わる形でも成立する演奏である。
ただ、録音がなんともいえない『抜けの悪さ』で、むしろ通常CDの輸入盤を聴いてみたくなる感じだった。
フィナーレ復元の試みはこれからも続けられてしかるべきだが、第三楽章までの演奏と続けて演奏するのはいたずらにそれまでの3つの楽章の完成度を邪魔するだけではないか。
様々聴いた中で唯一ボッシュ盤だけが、4楽章構成としての全体を上手くまとめていたし、フィナーレの音楽の性格も第7番のフィナーレのような和音の転調そのものが曲の主眼であり、それこそがメロディとなっているという大きな枠組みをしっかりととらえていた。
今回のラトル盤はかなり残念な結果となった。
話題というよりはマスコミが無理やり【大事件】として取り沙汰したいるだけかもしれないが、聴かないわけにはいかない。
当初は、輸入盤でいいと思ったのだが、SACDが国内盤限定ということと、何よりも今回のフィナーレに関する原文解説の訳がライナーノーツに載っていることが分かり、一冊雑誌を買い足すつもりで国内盤を買った。
http://www.hmv.co.jp/product/detail/4994391
話題はフィナーレに集中するだろうが、「形式区分」と「小節数」に「演奏時間の表示」を加えた解説が素晴らしい。
これによって、どの程度完成された部分だったかが良くわかる。
今までいろいろな復元の試みを聴いてきたが、てっきりあとから想像で創作したと思っていた意外な部分がブルックナーが元々完成させていたりするのだ。
最後のほうはまるっきり想像の産物でそのことが分かるといかにもあざとい感じはあるし、物足りないなんてものじゃないが、ほかの復元の譜面よりはずっと唐突な感じがなくなっているのが今回のラトル盤の特徴だろう。
それでもこのまったくブルックナーが書いていないコーダを聴いてしまうと、あらためてこの第三楽章までのブルックナーの超ド級の天才性を再確認するし、この未完成のフィナーレに関しては、既にブルックナーの体力も枯渇していたと思わざるを得ない。
通常のブルックナーの楽章だったら、「骨格」にすぎないくらいの出来の譜面を果たして本当にブルックナーが決定稿としていたのだろうか。
何しろテンポ感がずっと一定で変化がない。リズムの権化のようなブルックナーのフィナーレの特徴がまるでない。
そもそもこの第九が未完成に終わったのも、ブルックナーの改訂癖のせいだから、この不完全で魅力の無いフィナーレをブルックナーが良しとするはずもないのだ。
死期を悟り、最初からの書きなおしをする健康状態でも精神状態でもなかったのだろう。
それにしてもこの復元のフィナーレも指揮者によってこれほど違って聞こえるものか、というくらい録音によって異なる印象を与えられる。
正直、今回のラトル盤の第一楽章には見るべきものは無いが、アダージョだけが格段に優れている。
第一楽章は見るべきものがないと書いたが、スケルツォは実はそれ以下だ。ここまでの30分はいかにも長く感じた。
典型的なブルックナーに不向きの指揮者かと思わせる演奏だ。
アダージョに関しては、フィナーレの存在、これから演奏するということを見据えたうえでの解釈だと解説には書いてあるが、そうも聴こえなかった。
充分この第三楽章が最後に鳴り終わる形でも成立する演奏である。
ただ、録音がなんともいえない『抜けの悪さ』で、むしろ通常CDの輸入盤を聴いてみたくなる感じだった。
フィナーレ復元の試みはこれからも続けられてしかるべきだが、第三楽章までの演奏と続けて演奏するのはいたずらにそれまでの3つの楽章の完成度を邪魔するだけではないか。
様々聴いた中で唯一ボッシュ盤だけが、4楽章構成としての全体を上手くまとめていたし、フィナーレの音楽の性格も第7番のフィナーレのような和音の転調そのものが曲の主眼であり、それこそがメロディとなっているという大きな枠組みをしっかりととらえていた。
今回のラトル盤はかなり残念な結果となった。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ブルックナー 更新情報
-
最新のアンケート
ブルックナーのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 酒好き
- 170675人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37149人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90052人