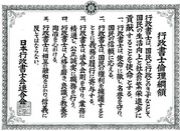示談代行と
弁護士法72条
そして司法書士法
覚書と確認書↑
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
覚 書
社団法人日本損害保険協会(以下甲という。)と日本弁護士連合会の要請を受けた財団法人日弁連交通事故相談センター(以下乙という。)とは、甲の社員である各損害保険会社(以下各社員会社という。)が家庭用自動車保険(以下新保険という。)を新たに発売するに際して、今後の任意自動車対人賠償責任保険の運用について、交通事故損害賠償をめぐる紛争当事者の正当な権利を擁護し、社会正義を実現する目的で、下記条項を相互に確認する。
第一 甲は下記1ないし4の甲または各社員会社の行なう諸施策について提案し、乙はこれに同意した。
(1)裁判所の認定基準に準ずる任意自動車対人賠償責任保険支払い基準を作成し、もって対人事故に係る保倹金または損害賠償額の支払いの適正化を期する。
(2)損害賠償額の査定、被害者との折衝等の業務を担当する職員に対しては、被害者の権利を侵すことのないように十分な指導、監督を行ない、職員の資質、能力の向上に万全を期する。
(3)交通事故損害賠償をめぐる紛争について、和解のあつ旋を目的とする中立の機関を設置する。設置の場所その他の細目について甲は乙と協議する。
(4)新保険について、対人事故に係る被保険者の負担すべき法律上の損害賠償責任の総額が確定していない場合でも、被保険者または被害者の申し出があったときは、被保険者が法律上の損害賠償貴任を負担することが明らかである金額について、保険金または損害賠償額の内払いを行ない、被保険者および被害者の交通事故による経済的負担を軽減する。
第二 乙は下記1ないし6を提案し、甲および各社員会社はこれに同意した。
(1)被害者の保険会社に対する直接請求権を新保険の約款上明記する。
(2)各社員会社は、新保険について「保険会社による示談代行」など弁護士法違反の疑いがある宣伝、広告活動を行なわない。
(3)各社員会社は、新保険の約款賠償責任条項第五条による被害者との折衝等の業務については、弁護士との緊密な連携のもとに、公正かつ.妥当な処理を行なう。
(4)各社員会社は、新保険の約款賠償責任条項第五条の業務については、必ず、会社の常 勤の職員に担当させるものとし、代理店その他部外者に委嘱しない。また、担当職員の給与は、歩合制その他取扱件数に応した報酬制度によっては支給しない。
(5)各社員会社は、保険士その他非弁護士の交通事故への介入を防止するため、次の措置をとる。
(1) 被害者の親族以外の者が被害者の代理人として反復して損害賠償の請求を行なった場合には、甲は各地域ごとに各社員全社の資料を整理して乙または乙の支部に通知する。
(2) 各社員会社は、上記の請求には原則として応じない。
(6)各社員会社は、交通事故損害賠償をめぐる紛争当事者が事件について弁護士に相談し、または委任する機会を増大させるように配慮する。その方法および内容については、甲と乙が協議のうえ決定する。
第三 本覚書に記載された事項に関連する事項、その他任意自動車対人賠償責任保険に関する一切の問題を対象として、甲と乙とは、今後、定期および随時に協議を行なうものとする。
上記のとおり確認の証として、本覚書正本二通を作成し、甲・乙双方記名調印のうえ、各々その一通を保有し、各社員会社はそれぞれ副本一通を保有する。
昭和四八年九月一日
甲 社団法人 日本損害保険協会
乙 財団法人 日弁連交通事故相談センター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
確 認 書
社団法人日本損害保険協会(以下「甲」という。)と日本弁護士運合会の要請を受けた財団法人日弁連交通事故相談センター(以下「乙」という。)とは、甲・乙間の昭和四八年九月一日付覚書(以下「覚書」という。)に関し、下記のとおり確認する。
記
第一 甲は、甲の社員である各損害保険会社(以下「各社員会社」という。)が、今後、共同して統}の任意自動車対人賠償責任保険(以下「任意保険」という。)の支払基準を作成・維持していくことが困難な状況にある事情を説明し、乙は了解した。
第二 甲と乙は、覚書および本確認書の趣旨にのっとり任意保険に関する一切の問題を対象として、今後も定期および随時に協議を行うものとする。
上記のとおり確認の証として、本確認書二通を作成し、甲・乙双方記名調印のうえ、各々その一通を保有し、各社員会社はそれぞれ副本一通を保有する。
平成九年三月二五日
甲 社団法人 日本損害保険協会
乙 財団法人 日弁連交通事故相談センター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<照会書様式>
法令解釈事前確認制度照会書
平成16年3月11日
法務大臣 野沢 太三 殿
宇治市長 久保田 勇
住所 京都府宇治市宇治琵琶33
下記について、照会します。
なお、照会者名並びに照会内容及び回答内容が公開されることに同意します。
記
1.法令名及び条項
弁護士法第72条
2.具体的な照会事項
弁護士法第72条では、弁護士でない者が報酬を得る目的で、業として他人の法律事務を取り扱ういわゆる非弁活動を禁止していますが、自動車保険に係る示談代行に関しては、日本弁護士連合会と損害保険業界との間で、一定の条件の下で合法性が確認されています。
その他の損害賠償保険(例 道路の管理瑕疵等)に係る示談代行についても、自動車保険と同様に合法と考えてよいでしょうか。
なお、自動車保険の取り扱いと異なる場合は、その理由をご教示ください。
3.公開の遅延の希望 無し
(1) 遅延希望の理由
(2) 公開可能時期
4.連絡先
?郵便番号 611−8501
?住所 京都府宇治市宇治琵琶33
?所属部署 企画管理部企画課
?担当者名 澤田尚志
?電話番号 (0774)22-3141 内線2082
?FAX番号 (0774)20-8778
?E-mail アドレス kikakuka@city.uji.kyoto.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
法令解釈事前確認制度回答書
平成16年4月15日
宇治市長殿
法務大臣 野沢 太三
本年3月11日付けで照会のあった件について,下記のとおり回答します。
記
弁護士法第72条は,罰則の構成要件の規定であり,その解釈・適用は刑罰権行使にかかわるところ,刑罰権の行使は,第一次的には捜査機関,最終的には裁判所が行うものであり,同規定の解釈・適用を行政機関が責任を持って示すことができないことから,本件お尋ねについては,回答できません。
なお,照会事項中に,自動車保険に係る示談代行に関し,日本弁護士連合会と損害保険業界との間で,一定の条件の下で合法性が確認されているとありますが,それは弁護士法第72条に違反するかどうかについての裁判所の判断を法的に拘束するものではありません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以下は筆者がインターネットから検索した論点整理
○ 司法書士による示談代行可能説
【司法書士法参照条文】
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 〜 五 (略) 六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。
ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
2 前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
一 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
三 司法書士会の会員であること。
【裁判所法参照条文】第333条 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これにより
司法書士は交通事故の示談代理・保険金請求できる。
なお行政書士はいずれも出来ない・・・・と解説している
○行政書士も出来るというある行政書士の説明
弁護士法72条と行政書士業務について
(引用はじめ)
弁護士法72条と行政書士業務の業際問題
慰謝料請求手続きの代行と弁護士法72条について
弁護士法第72条というものがあります。
そのため、行政書士が紛争に介入し、交渉を代理して行なうということは出来ません。
ただし、行政書士は書類作成に関する代理権を有しているため、貸金や慰謝料の請求書を作成し、内容証明郵便で発送することが出来ます。
また、相手方が示談に応じる場合には、示談書作成のための協議と示談書の作成を業務としておこなうことも出来ます。
●弁護士法第72条
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。
簡単にいうと、
弁護士でない者は、報酬を得る目的で「法律事件に関する事務」を行ってはいけません。
ということです。
ただ、よく読んでいただくと分かりますが、「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。」と書かれています。
つまり、行政書士は、行政書士法という「別の法律」により、一定の書類作成に関する法律事務を取り扱うことが可能、ということです。
●行政書士法第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同
じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を
作成することを業とする。
2行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
ちなみに、弁護士法72条規定の法律業務に関する例外とされるものには、以下のようなものがあります。
?債権回収についての債権回収会社(サービサー)制度
?簡易裁判所代理権認定司法書士の制度
?弁理士に対する特定侵害訴訟事件訴訟代理権の付与
?行政書士に対する各種書類作成代理権の付与
?特定社会保険労務士への紛争解決手続代理権の付与
つまり、
示談交渉は、「争訟性の有る法律事務」であり、弁護士の独占業務のため、報酬を得る目的で行う事は「非弁活動」となる。
しかし、単に意思表示を伝えるのみである内容証明通知書の作成、および紛争の終結である示談書の作成は、正当な行政書士業務である。
ということです。
ちなみに、権利義務に関する書類の作成を業として行うことが出来るのは、弁護士と行政書士のみです。
・・・・・・・・・引用おわり
弁護士法72条
そして司法書士法
覚書と確認書↑
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
覚 書
社団法人日本損害保険協会(以下甲という。)と日本弁護士連合会の要請を受けた財団法人日弁連交通事故相談センター(以下乙という。)とは、甲の社員である各損害保険会社(以下各社員会社という。)が家庭用自動車保険(以下新保険という。)を新たに発売するに際して、今後の任意自動車対人賠償責任保険の運用について、交通事故損害賠償をめぐる紛争当事者の正当な権利を擁護し、社会正義を実現する目的で、下記条項を相互に確認する。
第一 甲は下記1ないし4の甲または各社員会社の行なう諸施策について提案し、乙はこれに同意した。
(1)裁判所の認定基準に準ずる任意自動車対人賠償責任保険支払い基準を作成し、もって対人事故に係る保倹金または損害賠償額の支払いの適正化を期する。
(2)損害賠償額の査定、被害者との折衝等の業務を担当する職員に対しては、被害者の権利を侵すことのないように十分な指導、監督を行ない、職員の資質、能力の向上に万全を期する。
(3)交通事故損害賠償をめぐる紛争について、和解のあつ旋を目的とする中立の機関を設置する。設置の場所その他の細目について甲は乙と協議する。
(4)新保険について、対人事故に係る被保険者の負担すべき法律上の損害賠償責任の総額が確定していない場合でも、被保険者または被害者の申し出があったときは、被保険者が法律上の損害賠償貴任を負担することが明らかである金額について、保険金または損害賠償額の内払いを行ない、被保険者および被害者の交通事故による経済的負担を軽減する。
第二 乙は下記1ないし6を提案し、甲および各社員会社はこれに同意した。
(1)被害者の保険会社に対する直接請求権を新保険の約款上明記する。
(2)各社員会社は、新保険について「保険会社による示談代行」など弁護士法違反の疑いがある宣伝、広告活動を行なわない。
(3)各社員会社は、新保険の約款賠償責任条項第五条による被害者との折衝等の業務については、弁護士との緊密な連携のもとに、公正かつ.妥当な処理を行なう。
(4)各社員会社は、新保険の約款賠償責任条項第五条の業務については、必ず、会社の常 勤の職員に担当させるものとし、代理店その他部外者に委嘱しない。また、担当職員の給与は、歩合制その他取扱件数に応した報酬制度によっては支給しない。
(5)各社員会社は、保険士その他非弁護士の交通事故への介入を防止するため、次の措置をとる。
(1) 被害者の親族以外の者が被害者の代理人として反復して損害賠償の請求を行なった場合には、甲は各地域ごとに各社員全社の資料を整理して乙または乙の支部に通知する。
(2) 各社員会社は、上記の請求には原則として応じない。
(6)各社員会社は、交通事故損害賠償をめぐる紛争当事者が事件について弁護士に相談し、または委任する機会を増大させるように配慮する。その方法および内容については、甲と乙が協議のうえ決定する。
第三 本覚書に記載された事項に関連する事項、その他任意自動車対人賠償責任保険に関する一切の問題を対象として、甲と乙とは、今後、定期および随時に協議を行なうものとする。
上記のとおり確認の証として、本覚書正本二通を作成し、甲・乙双方記名調印のうえ、各々その一通を保有し、各社員会社はそれぞれ副本一通を保有する。
昭和四八年九月一日
甲 社団法人 日本損害保険協会
乙 財団法人 日弁連交通事故相談センター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
確 認 書
社団法人日本損害保険協会(以下「甲」という。)と日本弁護士運合会の要請を受けた財団法人日弁連交通事故相談センター(以下「乙」という。)とは、甲・乙間の昭和四八年九月一日付覚書(以下「覚書」という。)に関し、下記のとおり確認する。
記
第一 甲は、甲の社員である各損害保険会社(以下「各社員会社」という。)が、今後、共同して統}の任意自動車対人賠償責任保険(以下「任意保険」という。)の支払基準を作成・維持していくことが困難な状況にある事情を説明し、乙は了解した。
第二 甲と乙は、覚書および本確認書の趣旨にのっとり任意保険に関する一切の問題を対象として、今後も定期および随時に協議を行うものとする。
上記のとおり確認の証として、本確認書二通を作成し、甲・乙双方記名調印のうえ、各々その一通を保有し、各社員会社はそれぞれ副本一通を保有する。
平成九年三月二五日
甲 社団法人 日本損害保険協会
乙 財団法人 日弁連交通事故相談センター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<照会書様式>
法令解釈事前確認制度照会書
平成16年3月11日
法務大臣 野沢 太三 殿
宇治市長 久保田 勇
住所 京都府宇治市宇治琵琶33
下記について、照会します。
なお、照会者名並びに照会内容及び回答内容が公開されることに同意します。
記
1.法令名及び条項
弁護士法第72条
2.具体的な照会事項
弁護士法第72条では、弁護士でない者が報酬を得る目的で、業として他人の法律事務を取り扱ういわゆる非弁活動を禁止していますが、自動車保険に係る示談代行に関しては、日本弁護士連合会と損害保険業界との間で、一定の条件の下で合法性が確認されています。
その他の損害賠償保険(例 道路の管理瑕疵等)に係る示談代行についても、自動車保険と同様に合法と考えてよいでしょうか。
なお、自動車保険の取り扱いと異なる場合は、その理由をご教示ください。
3.公開の遅延の希望 無し
(1) 遅延希望の理由
(2) 公開可能時期
4.連絡先
?郵便番号 611−8501
?住所 京都府宇治市宇治琵琶33
?所属部署 企画管理部企画課
?担当者名 澤田尚志
?電話番号 (0774)22-3141 内線2082
?FAX番号 (0774)20-8778
?E-mail アドレス kikakuka@city.uji.kyoto.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
法令解釈事前確認制度回答書
平成16年4月15日
宇治市長殿
法務大臣 野沢 太三
本年3月11日付けで照会のあった件について,下記のとおり回答します。
記
弁護士法第72条は,罰則の構成要件の規定であり,その解釈・適用は刑罰権行使にかかわるところ,刑罰権の行使は,第一次的には捜査機関,最終的には裁判所が行うものであり,同規定の解釈・適用を行政機関が責任を持って示すことができないことから,本件お尋ねについては,回答できません。
なお,照会事項中に,自動車保険に係る示談代行に関し,日本弁護士連合会と損害保険業界との間で,一定の条件の下で合法性が確認されているとありますが,それは弁護士法第72条に違反するかどうかについての裁判所の判断を法的に拘束するものではありません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以下は筆者がインターネットから検索した論点整理
○ 司法書士による示談代行可能説
【司法書士法参照条文】
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 〜 五 (略) 六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。
ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
2 前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
一 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
三 司法書士会の会員であること。
【裁判所法参照条文】第333条 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これにより
司法書士は交通事故の示談代理・保険金請求できる。
なお行政書士はいずれも出来ない・・・・と解説している
○行政書士も出来るというある行政書士の説明
弁護士法72条と行政書士業務について
(引用はじめ)
弁護士法72条と行政書士業務の業際問題
慰謝料請求手続きの代行と弁護士法72条について
弁護士法第72条というものがあります。
そのため、行政書士が紛争に介入し、交渉を代理して行なうということは出来ません。
ただし、行政書士は書類作成に関する代理権を有しているため、貸金や慰謝料の請求書を作成し、内容証明郵便で発送することが出来ます。
また、相手方が示談に応じる場合には、示談書作成のための協議と示談書の作成を業務としておこなうことも出来ます。
●弁護士法第72条
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。
簡単にいうと、
弁護士でない者は、報酬を得る目的で「法律事件に関する事務」を行ってはいけません。
ということです。
ただ、よく読んでいただくと分かりますが、「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。」と書かれています。
つまり、行政書士は、行政書士法という「別の法律」により、一定の書類作成に関する法律事務を取り扱うことが可能、ということです。
●行政書士法第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同
じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を
作成することを業とする。
2行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
ちなみに、弁護士法72条規定の法律業務に関する例外とされるものには、以下のようなものがあります。
?債権回収についての債権回収会社(サービサー)制度
?簡易裁判所代理権認定司法書士の制度
?弁理士に対する特定侵害訴訟事件訴訟代理権の付与
?行政書士に対する各種書類作成代理権の付与
?特定社会保険労務士への紛争解決手続代理権の付与
つまり、
示談交渉は、「争訟性の有る法律事務」であり、弁護士の独占業務のため、報酬を得る目的で行う事は「非弁活動」となる。
しかし、単に意思表示を伝えるのみである内容証明通知書の作成、および紛争の終結である示談書の作成は、正当な行政書士業務である。
ということです。
ちなみに、権利義務に関する書類の作成を業として行うことが出来るのは、弁護士と行政書士のみです。
・・・・・・・・・引用おわり
|
|
|
|
コメント(14)
<↑最後の3行。 「事実証明」が抜けているのは・・・。 何故か?
権利義務関係書類の大部分は法律事務に含まれ、その範疇に無い事実証明書類の作成は、行政書士の専管ですから・・・
<弁護士さんが弁護士資格を以てあえて行政書士登録しているのは何故か?
弁護士が、法律事務の範疇外の事実証明書類の作成をも業としようと思えば、行政書士会へ入会する必要がある・・・
<「行政書士もできる」という説明ではないですね。 「示談」=「示談書の作成」or「内容証明通知書の作成」ですか? 論旨のすり替えは大概にしていただきたい。
筆者は論旨のすり替えではなく、ヒントを提起したのではないか・・・
単純代書である「書類の作成」と代理人として「書類を作成」することの意味の違いを考えろ・・・と・・・
権利義務関係書類の大部分は法律事務に含まれ、その範疇に無い事実証明書類の作成は、行政書士の専管ですから・・・
<弁護士さんが弁護士資格を以てあえて行政書士登録しているのは何故か?
弁護士が、法律事務の範疇外の事実証明書類の作成をも業としようと思えば、行政書士会へ入会する必要がある・・・
<「行政書士もできる」という説明ではないですね。 「示談」=「示談書の作成」or「内容証明通知書の作成」ですか? 論旨のすり替えは大概にしていただきたい。
筆者は論旨のすり替えではなく、ヒントを提起したのではないか・・・
単純代書である「書類の作成」と代理人として「書類を作成」することの意味の違いを考えろ・・・と・・・
おやぶん さま
<「代理人として作成」=「交渉」ではないですよね。
全くその通りです。
<それでは、メールのやり取りは「代理人として作成」の繰り返しでしょうか?それとも「交渉」でしょうか?
メールのやり取りは交渉です。
<「口頭で意思を伝達する」ことだけが「交渉」なのでしょうか?
Aの代理人としてA’の行政書士が、Bと何らかのやり取りを行えば、その形態を問わず相対交渉であり、弁護士法72条違反の問題が生じます。
弁護士、認定司法書士はAの代理人としてしか存在出来ません。
行政書士は、Aの代理人とはなれません。
しかし、行政書士は代理人として書類の作成が出来ます。
ここからは私見ですが・・・
この代理人として作成すること=行政書士は、双方代理の立場に立つことができる。・・・というのが私の見解です。
行政書士が、代理人として契約書を作成する場合には、A、B、C・・等、必ず複数の当事者の存在が予定されています。つまり、片面代理ではなく双方代理の立場に立つことができるとも言えます。
これを言い換えれば、意見・主張の対立はあるが、その紛争性が訴訟の提起に至るまでは顕在化していない状態とも言い換えることができ、この状態の範囲内ならば、行政書士はA、B双方の代理人として示談書の作成をすることができます。
この示談交渉・示談書作成の場合、Aの代理人としてなら行政書士はタッチできません。・・・が、AとBが帯同して相談に訪れた、又は、行政書士が間に入ることをBが了承したような場合には、可能とするのが私の見解です。但し、その場で示談が成立(示談書の作成)した場合、報酬は双方から50%ずつ収受しなければなりません。
もちろん、従来から双方代理を許容される程度の書類作成業務として、登記申請や自動車登録業務がありますが、私の私見は、こうした単純代書時代の双方代理ではなく、民法108条の但し書きの改正(追認条項の追加)及び行政書士が契約書等を代理人として作成することができるとした行政書士法改正の結果を受けて、そこから導き出した私見です。
<「代理人として作成」=「交渉」ではないですよね。
全くその通りです。
<それでは、メールのやり取りは「代理人として作成」の繰り返しでしょうか?それとも「交渉」でしょうか?
メールのやり取りは交渉です。
<「口頭で意思を伝達する」ことだけが「交渉」なのでしょうか?
Aの代理人としてA’の行政書士が、Bと何らかのやり取りを行えば、その形態を問わず相対交渉であり、弁護士法72条違反の問題が生じます。
弁護士、認定司法書士はAの代理人としてしか存在出来ません。
行政書士は、Aの代理人とはなれません。
しかし、行政書士は代理人として書類の作成が出来ます。
ここからは私見ですが・・・
この代理人として作成すること=行政書士は、双方代理の立場に立つことができる。・・・というのが私の見解です。
行政書士が、代理人として契約書を作成する場合には、A、B、C・・等、必ず複数の当事者の存在が予定されています。つまり、片面代理ではなく双方代理の立場に立つことができるとも言えます。
これを言い換えれば、意見・主張の対立はあるが、その紛争性が訴訟の提起に至るまでは顕在化していない状態とも言い換えることができ、この状態の範囲内ならば、行政書士はA、B双方の代理人として示談書の作成をすることができます。
この示談交渉・示談書作成の場合、Aの代理人としてなら行政書士はタッチできません。・・・が、AとBが帯同して相談に訪れた、又は、行政書士が間に入ることをBが了承したような場合には、可能とするのが私の見解です。但し、その場で示談が成立(示談書の作成)した場合、報酬は双方から50%ずつ収受しなければなりません。
もちろん、従来から双方代理を許容される程度の書類作成業務として、登記申請や自動車登録業務がありますが、私の私見は、こうした単純代書時代の双方代理ではなく、民法108条の但し書きの改正(追認条項の追加)及び行政書士が契約書等を代理人として作成することができるとした行政書士法改正の結果を受けて、そこから導き出した私見です。
> 6
行政書士をする前から、「行政書士は交通事故の示談書が作れる」と聞いていました。
なるほど。
示談で解決するという選択は、甲と乙の双方が訴訟などの争いをせずに話し合いでまとめるということですから、行政書士はその示談をまとめて書類にすればいいもので、それは業務の範囲であり弁護士法に違反しないでしょう。
その中で、「今までの事例ではこういうケースではみなさんはこのように解決されましたが、今回もこの線で整理してよろしいですか」という程度の「確認」は書類をまとめて書く仕事としてお金をもらう側からしたら当然の仕事でしょう。
それが、話し合いに応じない相手を捕まえて、片方の代理をするのは良くないというなら、それはその考えに従うべきでしょう。
では、家賃滞納で行政書士が家主から頼まれて賃借人のところに行くのはいけないのでしょうか。これも、私が思うに、一般的な和解などの書面の雛形を準備して、「家主さんはこの条件を提示されましたが受けられますか。」というのは問題ないと思います。そのときに、無知な相手に対して、「これで、Okなら解決しますが、でなければ裁判になります。裁判になったら、こうこうこういうことになりますがいいですか。」という一般論としての説明と、「説得」は、専門知識を有するお遣いとして、相手に対する親切のレベルだと思います。
交渉をしてはいけないといいますが、「ここで話し合ってまとめますか。争いのある事件として処理しますか。」との意思を確認して、話し合いに立ち会って、意見をまとめられない人の助け舟を出すのは、「代書屋」の典型的な仕事でしょう。「出るとこに出る」という相手にはかかわらないほうが賢明です。
『特上カバチ!』では行政書士と弁護士が仲が悪かったのかもしれませんが、『カバチたれ』の原作のマンガでは、行政書士の手に負えない仕事は弁護士に回していました。行政書士が法律問題のポータルサイトとか、大学病院で患者の行くべき診療科を決める予診をする若いの医者のような役割をすることは、国民にとって、法律が身近になるとともに、弁護士や税理士の仕事を探してくる効果もあるわけですから、うらまれる筋合いはないと思います。
私の場合、日本の相続で当事者の一人以上が韓国に住む本物の韓国人という事件の現地の下請けをすることがあります。もとの依頼を引き受けた先生から、日本語の遺産分割協議書をもらい、それを翻訳して相手に提示します。「ここではんこをいただけますか、それとも本気で争いますか。」の交渉を取り合えずは通訳として出向いてお話しています。幸か不幸か、もめた事件がありません。本国の親戚にしたら、期待もしていなかった遺産が、戸籍の調査で自分にも回ってきたわけだからかな。
相手が弁護士をつけた時点で、行政書士の立場で弁護士と話し合おうとすれば、当然に叩かれるでしょうね。
行政書士をする前から、「行政書士は交通事故の示談書が作れる」と聞いていました。
なるほど。
示談で解決するという選択は、甲と乙の双方が訴訟などの争いをせずに話し合いでまとめるということですから、行政書士はその示談をまとめて書類にすればいいもので、それは業務の範囲であり弁護士法に違反しないでしょう。
その中で、「今までの事例ではこういうケースではみなさんはこのように解決されましたが、今回もこの線で整理してよろしいですか」という程度の「確認」は書類をまとめて書く仕事としてお金をもらう側からしたら当然の仕事でしょう。
それが、話し合いに応じない相手を捕まえて、片方の代理をするのは良くないというなら、それはその考えに従うべきでしょう。
では、家賃滞納で行政書士が家主から頼まれて賃借人のところに行くのはいけないのでしょうか。これも、私が思うに、一般的な和解などの書面の雛形を準備して、「家主さんはこの条件を提示されましたが受けられますか。」というのは問題ないと思います。そのときに、無知な相手に対して、「これで、Okなら解決しますが、でなければ裁判になります。裁判になったら、こうこうこういうことになりますがいいですか。」という一般論としての説明と、「説得」は、専門知識を有するお遣いとして、相手に対する親切のレベルだと思います。
交渉をしてはいけないといいますが、「ここで話し合ってまとめますか。争いのある事件として処理しますか。」との意思を確認して、話し合いに立ち会って、意見をまとめられない人の助け舟を出すのは、「代書屋」の典型的な仕事でしょう。「出るとこに出る」という相手にはかかわらないほうが賢明です。
『特上カバチ!』では行政書士と弁護士が仲が悪かったのかもしれませんが、『カバチたれ』の原作のマンガでは、行政書士の手に負えない仕事は弁護士に回していました。行政書士が法律問題のポータルサイトとか、大学病院で患者の行くべき診療科を決める予診をする若いの医者のような役割をすることは、国民にとって、法律が身近になるとともに、弁護士や税理士の仕事を探してくる効果もあるわけですから、うらまれる筋合いはないと思います。
私の場合、日本の相続で当事者の一人以上が韓国に住む本物の韓国人という事件の現地の下請けをすることがあります。もとの依頼を引き受けた先生から、日本語の遺産分割協議書をもらい、それを翻訳して相手に提示します。「ここではんこをいただけますか、それとも本気で争いますか。」の交渉を取り合えずは通訳として出向いてお話しています。幸か不幸か、もめた事件がありません。本国の親戚にしたら、期待もしていなかった遺産が、戸籍の調査で自分にも回ってきたわけだからかな。
相手が弁護士をつけた時点で、行政書士の立場で弁護士と話し合おうとすれば、当然に叩かれるでしょうね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
MIXI 行政書士連合会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-