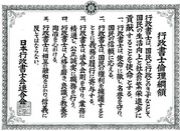http://
上のトピックのコメント34で
風のごとしサンが喝破されているごとく
行政書士制度は
国策上の必要性を持ち得ていなかったことに
歴史的悲劇がある。
ここからはワタシの日行連会長体験に基づく一考察です。
結論を先に書くと
国策的必要資格制度とすること。である。
資格制度の創世記に
当時の省庁が持つ許認可権のうち
一省一許認可的事務が一資格の萌芽を促したともいえる。
自省でシェアー出来ることは省益であった。
その中で
行政書士は文字の書けない
申請書が作れないヒトタチにとっては
もっとも身近な存在の代書人として
地域住民に密着していた。
歴史を紐解き検証しなければならないが
だからこそ知事試験として
歴史を積み重ねてきた。
要するに
その地域の行政が必要とする
代書人であれば良く
それは国家経済でもなく地域経済でもなく
地域行政に貢献できれば良し・・とするものであったと考える。
そして
幾度かの戦争と不況を経て
復員軍人の受け入れ先としての
三公社五現業が強化され
地域行政退職者の受け入れ先として
行政書士制度はその社会的価値をもたらされたのではないか。
さらに強制入会制度へ移行する直前は
資格登録のみでよかった行政書士は30万人の
我が国最大の資格者集団と書いていた。
(強制入会の廃止)という規制緩和が求められたとき
強制登録を残して100万人の集団とすれば
大きな政治的集団となることも対応策として考えていた。
また法人・個人、入会・非入会で登録料に格差を設ければ
そうとうの財源が確保でき、かなりの活動が出来るかも知れないとも。
というのも
登録事務が日行連に移管されたとき
名寄せしたところ
全国に事務所を持つ者が多く発見された。
それらは都道府県知事ごとに行政書士資格を取得して
全国ネットの展開をしていたのである。
国家資格に移行したとき
当然にこれらは一事務所という制限規定で排除されたが
現在は行政書士法人として息を吹き返した。
そして
ここにも書いたが
行政書士試験は知事試験であるが故に
地方自治法に知事への委任事務として
書かれていた。
これを自治省は気づかないまま
(改正しないまま・・・試験事務は面倒だから)
試験は知事試験のまま
行政書士法で国家資格と位置づけしていた。
地方分権一括推進法で
委任事務が自治事務=知事の事務として整理されたとき
当然に知事試験は知事資格となり
国家資格から知事資格という地方資格となった。
(現在でも地方資格の一面を残している)
わたしは真っ正面から自治省に反対した。
このときの自治大臣は我が古里の同年生
上杉自治大臣 議連会長が村上正邦であった。
国会開催中に鈴木宗男氏の予算委員長室に
上杉大臣を呼び込んで 村上 鈴木 ワタシで取り囲み
地方分権一括推進法から外すよう迫った。
当時の事務次官は
地方分権を推進する担当役所として
自ら骨抜き案をやることは出来ない。
それをやれば全省庁の地方分権が
骨抜きになるとして拒んだ。
いろいろあって
消防士試験を参考にして
自治事務としながら
試験事務を都道府県知事から試験センターに
集約化するという方法を考え出した。
しかし地方分権一括推進法の可決が迫っている中で
役所による財団設立は手続き上間に合わないため
窮余の一策として日行連が設立することになったのである。
そしてワタシは当時の副会長達とともに
新潟の銀行から一億円を借り受けて設立したのである。
三億円が必要とされていた財団が設立できたのは
当時の国対委員長だった虎サンのおかげであった。
設立の過程で当然に日行連のためのセンターであり
その目的には日行連の支援策を盛り込んでいたのだが
わたしが規制緩和に対応している間に
理事長を日行連会長でなく
余所から連れてくる工作が内外で進んでいたのである。
爾来
センター理事長は
消防試験センター関連者の天下り先となって居る。
自治省と話が付いていた
日行連からの理事長就任は妨害工作で頓挫した。
今
公益法人認定委員になって
あらためて試験センターの剰余金を診ると
13億円ある。
これを法律では公益目的に使用しなければならない。
まさに行政書士制度発展のための軍資金が眠っているのである。
この視点からセンター運営の見直し=日行連による理事長を唱えたが
副理事長の椅子をあてがわれて
満足してしまっているのではないだろうか。
ところでワタシは
経団連およびその構成員である自工会・自販連等
自動車団体と20年近く30数回に及ぶ交渉を担当した。
車庫証明と自動車登録を巡る交渉であったが
その実態は自動車という国家の基幹産業を中心とした
経済的闘いであったということができる。
行政書士制度に注目が注がれたピークの時代である。
なぜか
当時自治省は経済的行為に対する許認可権は少なく
それらは多くが他省庁にあった。
だから行政書士制度が経済界を支配するツールとなることに
気が付かなかったし、
官僚の多くは天下り先として地方行政機関を
持っていたからである。
ところが日米構造協議やグローバルスタンダード化は
経済戦争すなわち経済的行為の許認可権をクローズアップするとともに
そこには行政書士制度という予想もしなかった資格制度が
立ちはだかっていることに気づいたのである。
これにいち早く気づいたのが経産省であった。
種苗法や著作権登録、電磁的記録を独占業務とする行政書士
これはビジネスモデル・特許で世界経済戦争を戦う経産省にとって
取り込むべき重要なな資格だったが、彼らには弁理士制度があった。
そこに行政書士業務を取り込もうとしたのである。
(既にネット上ではアドミニストレーター資格(訳すれば行政書士)
を作り上げていた。)
自動車会議所という自動車団体を傘下に持つ団体がある。
自動車関係業界の「経団連」である。
ワタシが自動車業界と交渉した相手とは
この自動車会議所であった。
ここに今もあると思うが
「日行連問題対策特別委員会」がある。
日行連が国会議員を議員連盟に取り込むと
かならず彼らもその議員を取り込んでいった。
しかも自治省出身の議員が取り込まれていった。
あるとき行政書士制度推進議員連盟の事務局長を務めた
小山参議院議員が耳打ちしてくれた。
議員連盟で行政書士法改正を持ち出したら
「火傷するから手を付けるな」と自治省OBの議員に言われたと。
議員連盟では力にならない・・・そう考えて
自民党内に「行政書士検討小委員会」を作った。
委員会の決定は自民党の決定というバイパスが出来たのである。
これにより行政書士法改正は大きく進むことが出来た。
このように自治省という行政書士制度の所管省が
議員立法という生い立ちと
役人にとってメリットのない資格という
無意識状態にあることにつけ込んで
他資格を創り出した他省庁はその資格の強化と
業務範囲の拡大、そして新しい資格制度の創出と蠢いてきたのである。
表現を変えて
「経済行為を左右する許認可を業務範囲とする行政書士制度」
として考えるとき
商業登記とか他資格への参入とかは必要かも知れないが
不可欠のものではない。
行政書士制度が許認可事務を完全に掌握しておれば
我々の法改正の交渉相手は経済産業省であり経団連であり
利権官庁なのである。
他資格制度ではないのだ。
だからこそ規制緩和の矛先は
行政書士制度に向いたままであり
行政書士に業務範囲を広げる規制緩和は進まず
行政書士の独占業務に対する規制緩和は進むのである。
他資格者は経済界の要求に自らも含まれていることを見逃し
規制緩和という自らに襲いかかる嵐を忘れて
行政書士制度への彼らの要求に悪のりしているのである。悲劇である。
いまあらためて
行政書士制度を考えるとき
私たちは行政書士制度の生い立ちと
歩んできた歴史に学び
我が国経済界が最大の難敵とする
行政書士制度を国家経済の視点から「活用する」ことを
考えるべきではないだろうか。
わたしが自動車会議所に対抗するために日行連・日政連に設けた
「道路運送車両法反対特別委員会」
なんども運輸省が
それだけは旗を降ろしてくれと
懇願された委員会であったが
いつのまにか旗はおろされてしまった。
さらに監察部も消滅してしまった。
いま日行連で
行政書士制度の将来が議論されている。
私たちは目先の利益に惑わされたり
モノ欲しがりになってはいけない。
わたしは思う。
「行政書士自身が制度の価値と活用策を完全にモノにしていないこと」
から
いかに脱却して
「我が国の経済界・行政に存在価値を見せつけるか」という
優位性確立のための政策集団になることを切望している。
行政書士組織の知的資産はどこにあるのだろうか。
内閣府の「対日直接投資推進室」はそのことを良く理解している。
上のトピックのコメント34で
風のごとしサンが喝破されているごとく
行政書士制度は
国策上の必要性を持ち得ていなかったことに
歴史的悲劇がある。
ここからはワタシの日行連会長体験に基づく一考察です。
結論を先に書くと
国策的必要資格制度とすること。である。
資格制度の創世記に
当時の省庁が持つ許認可権のうち
一省一許認可的事務が一資格の萌芽を促したともいえる。
自省でシェアー出来ることは省益であった。
その中で
行政書士は文字の書けない
申請書が作れないヒトタチにとっては
もっとも身近な存在の代書人として
地域住民に密着していた。
歴史を紐解き検証しなければならないが
だからこそ知事試験として
歴史を積み重ねてきた。
要するに
その地域の行政が必要とする
代書人であれば良く
それは国家経済でもなく地域経済でもなく
地域行政に貢献できれば良し・・とするものであったと考える。
そして
幾度かの戦争と不況を経て
復員軍人の受け入れ先としての
三公社五現業が強化され
地域行政退職者の受け入れ先として
行政書士制度はその社会的価値をもたらされたのではないか。
さらに強制入会制度へ移行する直前は
資格登録のみでよかった行政書士は30万人の
我が国最大の資格者集団と書いていた。
(強制入会の廃止)という規制緩和が求められたとき
強制登録を残して100万人の集団とすれば
大きな政治的集団となることも対応策として考えていた。
また法人・個人、入会・非入会で登録料に格差を設ければ
そうとうの財源が確保でき、かなりの活動が出来るかも知れないとも。
というのも
登録事務が日行連に移管されたとき
名寄せしたところ
全国に事務所を持つ者が多く発見された。
それらは都道府県知事ごとに行政書士資格を取得して
全国ネットの展開をしていたのである。
国家資格に移行したとき
当然にこれらは一事務所という制限規定で排除されたが
現在は行政書士法人として息を吹き返した。
そして
ここにも書いたが
行政書士試験は知事試験であるが故に
地方自治法に知事への委任事務として
書かれていた。
これを自治省は気づかないまま
(改正しないまま・・・試験事務は面倒だから)
試験は知事試験のまま
行政書士法で国家資格と位置づけしていた。
地方分権一括推進法で
委任事務が自治事務=知事の事務として整理されたとき
当然に知事試験は知事資格となり
国家資格から知事資格という地方資格となった。
(現在でも地方資格の一面を残している)
わたしは真っ正面から自治省に反対した。
このときの自治大臣は我が古里の同年生
上杉自治大臣 議連会長が村上正邦であった。
国会開催中に鈴木宗男氏の予算委員長室に
上杉大臣を呼び込んで 村上 鈴木 ワタシで取り囲み
地方分権一括推進法から外すよう迫った。
当時の事務次官は
地方分権を推進する担当役所として
自ら骨抜き案をやることは出来ない。
それをやれば全省庁の地方分権が
骨抜きになるとして拒んだ。
いろいろあって
消防士試験を参考にして
自治事務としながら
試験事務を都道府県知事から試験センターに
集約化するという方法を考え出した。
しかし地方分権一括推進法の可決が迫っている中で
役所による財団設立は手続き上間に合わないため
窮余の一策として日行連が設立することになったのである。
そしてワタシは当時の副会長達とともに
新潟の銀行から一億円を借り受けて設立したのである。
三億円が必要とされていた財団が設立できたのは
当時の国対委員長だった虎サンのおかげであった。
設立の過程で当然に日行連のためのセンターであり
その目的には日行連の支援策を盛り込んでいたのだが
わたしが規制緩和に対応している間に
理事長を日行連会長でなく
余所から連れてくる工作が内外で進んでいたのである。
爾来
センター理事長は
消防試験センター関連者の天下り先となって居る。
自治省と話が付いていた
日行連からの理事長就任は妨害工作で頓挫した。
今
公益法人認定委員になって
あらためて試験センターの剰余金を診ると
13億円ある。
これを法律では公益目的に使用しなければならない。
まさに行政書士制度発展のための軍資金が眠っているのである。
この視点からセンター運営の見直し=日行連による理事長を唱えたが
副理事長の椅子をあてがわれて
満足してしまっているのではないだろうか。
ところでワタシは
経団連およびその構成員である自工会・自販連等
自動車団体と20年近く30数回に及ぶ交渉を担当した。
車庫証明と自動車登録を巡る交渉であったが
その実態は自動車という国家の基幹産業を中心とした
経済的闘いであったということができる。
行政書士制度に注目が注がれたピークの時代である。
なぜか
当時自治省は経済的行為に対する許認可権は少なく
それらは多くが他省庁にあった。
だから行政書士制度が経済界を支配するツールとなることに
気が付かなかったし、
官僚の多くは天下り先として地方行政機関を
持っていたからである。
ところが日米構造協議やグローバルスタンダード化は
経済戦争すなわち経済的行為の許認可権をクローズアップするとともに
そこには行政書士制度という予想もしなかった資格制度が
立ちはだかっていることに気づいたのである。
これにいち早く気づいたのが経産省であった。
種苗法や著作権登録、電磁的記録を独占業務とする行政書士
これはビジネスモデル・特許で世界経済戦争を戦う経産省にとって
取り込むべき重要なな資格だったが、彼らには弁理士制度があった。
そこに行政書士業務を取り込もうとしたのである。
(既にネット上ではアドミニストレーター資格(訳すれば行政書士)
を作り上げていた。)
自動車会議所という自動車団体を傘下に持つ団体がある。
自動車関係業界の「経団連」である。
ワタシが自動車業界と交渉した相手とは
この自動車会議所であった。
ここに今もあると思うが
「日行連問題対策特別委員会」がある。
日行連が国会議員を議員連盟に取り込むと
かならず彼らもその議員を取り込んでいった。
しかも自治省出身の議員が取り込まれていった。
あるとき行政書士制度推進議員連盟の事務局長を務めた
小山参議院議員が耳打ちしてくれた。
議員連盟で行政書士法改正を持ち出したら
「火傷するから手を付けるな」と自治省OBの議員に言われたと。
議員連盟では力にならない・・・そう考えて
自民党内に「行政書士検討小委員会」を作った。
委員会の決定は自民党の決定というバイパスが出来たのである。
これにより行政書士法改正は大きく進むことが出来た。
このように自治省という行政書士制度の所管省が
議員立法という生い立ちと
役人にとってメリットのない資格という
無意識状態にあることにつけ込んで
他資格を創り出した他省庁はその資格の強化と
業務範囲の拡大、そして新しい資格制度の創出と蠢いてきたのである。
表現を変えて
「経済行為を左右する許認可を業務範囲とする行政書士制度」
として考えるとき
商業登記とか他資格への参入とかは必要かも知れないが
不可欠のものではない。
行政書士制度が許認可事務を完全に掌握しておれば
我々の法改正の交渉相手は経済産業省であり経団連であり
利権官庁なのである。
他資格制度ではないのだ。
だからこそ規制緩和の矛先は
行政書士制度に向いたままであり
行政書士に業務範囲を広げる規制緩和は進まず
行政書士の独占業務に対する規制緩和は進むのである。
他資格者は経済界の要求に自らも含まれていることを見逃し
規制緩和という自らに襲いかかる嵐を忘れて
行政書士制度への彼らの要求に悪のりしているのである。悲劇である。
いまあらためて
行政書士制度を考えるとき
私たちは行政書士制度の生い立ちと
歩んできた歴史に学び
我が国経済界が最大の難敵とする
行政書士制度を国家経済の視点から「活用する」ことを
考えるべきではないだろうか。
わたしが自動車会議所に対抗するために日行連・日政連に設けた
「道路運送車両法反対特別委員会」
なんども運輸省が
それだけは旗を降ろしてくれと
懇願された委員会であったが
いつのまにか旗はおろされてしまった。
さらに監察部も消滅してしまった。
いま日行連で
行政書士制度の将来が議論されている。
私たちは目先の利益に惑わされたり
モノ欲しがりになってはいけない。
わたしは思う。
「行政書士自身が制度の価値と活用策を完全にモノにしていないこと」
から
いかに脱却して
「我が国の経済界・行政に存在価値を見せつけるか」という
優位性確立のための政策集団になることを切望している。
行政書士組織の知的資産はどこにあるのだろうか。
内閣府の「対日直接投資推進室」はそのことを良く理解している。
|
|
|
|
コメント(85)
欲しがるよりも優位性の確立を考える際に以下のことを考えてみたい。
先日の日行連総会で本年度事業計画案が承認されたが、その事業計画案の事業計画基本方針の1として行政不服申立の代理の実現に向けてを掲げ、2として長期会費未納会員に対する登録抹消の実現に向けてを掲げ最重点項目としている。
他の士業(司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、税理士)にあっっては各業法のその業務の中に審査請求及び異議の申し立てが出来ると明確に記載されており、行政書士法にはその記載が無い。
行政書士法改正では行政書士法1条の2に行政書士が作成し、官公署へ提出したものに関して改正行政不服審査法に基づく行政不服審査の申し立てを行政書士が代理人として出来ると明確に記載することが必要となる。
次に2の長期会費未納会員に対する登録抹消の実現についてだが、司法書士法及び土地家屋調査士法においては単位会の会員となるには連合会の名簿に記載されることと同時に各単位会に入会の申請を行う必要性が明記されているが、行政書士法、社会保険労務士法、税理士法では連合会の名簿に記載されることで当然に単位会の会員となり、新たに単位会に入会する申請の必要が省略されていることの違いがあり、このことが会費未納によるみなし退会が認められない理由となっている。
今年度の重点目標に掲げた1の項目は日行連及び日政連の連携した運動が必要であるが、2の項目は税理士会、社労士会との連携も可能ではないかと思われる。
行政書士の優位性を確立するためにも微力であるが尽くしてみたいと思う。
先日の日行連総会で本年度事業計画案が承認されたが、その事業計画案の事業計画基本方針の1として行政不服申立の代理の実現に向けてを掲げ、2として長期会費未納会員に対する登録抹消の実現に向けてを掲げ最重点項目としている。
他の士業(司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、税理士)にあっっては各業法のその業務の中に審査請求及び異議の申し立てが出来ると明確に記載されており、行政書士法にはその記載が無い。
行政書士法改正では行政書士法1条の2に行政書士が作成し、官公署へ提出したものに関して改正行政不服審査法に基づく行政不服審査の申し立てを行政書士が代理人として出来ると明確に記載することが必要となる。
次に2の長期会費未納会員に対する登録抹消の実現についてだが、司法書士法及び土地家屋調査士法においては単位会の会員となるには連合会の名簿に記載されることと同時に各単位会に入会の申請を行う必要性が明記されているが、行政書士法、社会保険労務士法、税理士法では連合会の名簿に記載されることで当然に単位会の会員となり、新たに単位会に入会する申請の必要が省略されていることの違いがあり、このことが会費未納によるみなし退会が認められない理由となっている。
今年度の重点目標に掲げた1の項目は日行連及び日政連の連携した運動が必要であるが、2の項目は税理士会、社労士会との連携も可能ではないかと思われる。
行政書士の優位性を確立するためにも微力であるが尽くしてみたいと思う。
調査士って、いまだにこんなことをやっているのだなぁ。(笑)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090725-OYT1T00066.htm
調査士から接待や付け届け、登記官4人処分
登記申請を代行する土地家屋調査士から接待を受けたり、付け届けを受け取ったりしていたとして、名古屋法務局は24日、同局管内の統括登記官を減給3か月(10分の1)、総務登記官や登記官など3人を戒告の懲戒処分にしたと発表した。
-----------------------------------------------
ほんの少し前までは、やれ引っ越しだ、異動だ、で手弁当でお手伝いに駆り出されて時代が
あったようで・・・・・。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090725-OYT1T00066.htm
調査士から接待や付け届け、登記官4人処分
登記申請を代行する土地家屋調査士から接待を受けたり、付け届けを受け取ったりしていたとして、名古屋法務局は24日、同局管内の統括登記官を減給3か月(10分の1)、総務登記官や登記官など3人を戒告の懲戒処分にしたと発表した。
-----------------------------------------------
ほんの少し前までは、やれ引っ越しだ、異動だ、で手弁当でお手伝いに駆り出されて時代が
あったようで・・・・・。
http://www.gyosei.or.jp/member/report/reportitem_106.html
申請取次関係研修の受講申込について申請取次行政書士管理委員会/中央研修所
この文書お読みになりましたか?
行間を読むに、従来は申し込みせずに受講するものを一部認めていたのではないか。管理委員会の判断で、一部会員の受講を認めていた。
が、新委員会としては、毅然としてこうした取り扱いを否定するとの姿勢なのではないか。
そうではければ、この時期にこんな文書を会員向けに示す必要もない。申し込みなしでの当日受講できるなど、一般会員など知る由も無い。
推測だが、一部会員とは単位会の「役員」などを示すのではないか?
申請取次関係研修の受講申込について申請取次行政書士管理委員会/中央研修所
この文書お読みになりましたか?
行間を読むに、従来は申し込みせずに受講するものを一部認めていたのではないか。管理委員会の判断で、一部会員の受講を認めていた。
が、新委員会としては、毅然としてこうした取り扱いを否定するとの姿勢なのではないか。
そうではければ、この時期にこんな文書を会員向けに示す必要もない。申し込みなしでの当日受講できるなど、一般会員など知る由も無い。
推測だが、一部会員とは単位会の「役員」などを示すのではないか?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
MIXI 行政書士連合会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-