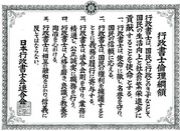行政書士法の一部改正について
一 はじめに
行政書士法の一部を改正する法律(平成一三年法律第七七号。以下「改正法」という。)が本年六月二二日に成立し、同年六月二七日に公布された。本法は、平成一四年七月一日から施行されることとなっている。
行政書士法は、その制定および数次にわたる改正の多くは議員立法により行われてきた経緯があり、今回の改正につい
ても、議員立法により行われたものである。
すなわち、本年四月一○日、自由民主党政務調査会の総務部会において改正法案が了承された後、各党間の調整を経て、六月五日に衆議院総務委員会委員長提案として国会に提出され、六月七日に衆議院本会議で賛成多数により可決、六月二一日に参議院総務委員会で可決、翌六月二二日に参議院本会議で賛成多数により可決・成立した。
今回の改正は、行政に関する手続の円滑な実施および国民の利便向上の要請への的確な対応を図るため、目的規定を整備し、行政書士が作成することができる書類に係る官公署への提出手続を代理することおよび行政書士が作成することができる契約その他の書類を代理人として作成すること等の業務を行政書士の業務として明確化するとともに、日本行政書士会連合会が行政書士の登録をしたときに行政書士証票を交付するものとすることを内容とするものである。
以下、本改正の主要な内容について説明することにする。
なお、本文中意見にわたる部分は、筆者の私見であることを予めお断りしておく。
二 主な改正内容
(1)目的規定の整備
改正の第一点は、行政書士法の目的規定を整備したことである。すなわち、行政書士法は「行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的と
する」こととされたものである(改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第一条)。
行政書士は、官公署に提山する書類の作成等のみならず、私人間の権利義務や事実証明に関する書類の作成についても、その業務範囲とするところである。
しかし、改正前の行政書士法(以下「旧法」という。)第一条では「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを目的とする」とされており、この規定のままでは「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し」の部分のみに着目して解釈した場合、行政書士法第一条の二との関係で、ともすれば本条が「官公署に提出する書類」に過度に重点が置かれており、したがって、行政書士の業務のうち「権利義務または事実証明に関する書類」を作成することは行政書士法の目的を逸脱しているのではないか、との誤解を招く可能性があった。
このため、新法第一条においては、「あわせて」と記載することにより、行政書士法は「行政に関する手続の円滑な実
施に寄与」することとあわせて、「国民の利便に資すること」を目的としていることをあらためて明確化したものである。つまりこの規定の整備は、私人間の権利義務や事実証明に関する書類の作成についても、行政書士が大きな役割を担っていることをあらためて明示したものといえる。
(2)業務の明確化
改正の第二点は、行政書士が作成することができる書類の官公署への提出手続について代理すること、および行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成することが、新たに行政書士の業務として位置づけ
られたことである (新法第一条の三)。
旧法では、行政書士は、第一条の二において、官公署に提出する書類その他の権利義務又は事実証明に関する書類を作成することができると規定されるとともに、第一条の三において、官公署に提出する書類の提出手続の代行及び当該書類の作成に関する相談に応ずることができることとされていた。
今回の改正では、第一条の二に規定する業務については変更はなく、第一条の三において、他人の依頼を受け報酬を得て、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項を除き、次の各号に掲げる事務を業とすることができる
こととされたところである。以下、新法第一条の三の各号の内容について説明する。
?行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する
手続について代理すること(新法第一条の三第一号)
旧法第一条の三においては、官公署に提出する書類の提出手続の代行及び当該書類の作成に関する相談について規定されていたが、このうち書類の提出手続の代行に関しては、許認可申請や届出の書類を依頼人に代わって官公署に提出する際に、窓口において書類の不備等があった場合、あくまで提出手続を代って行う「使者」としての行政書士は、依頼人の意思を確認しなければ訂正をすることができないものとされてきた。しかし、依頼人にとっても、このような手順を踏むことは非常に煩雑であり、円滑な手続に支障があることから、従来より許認可申請や届出等の手続業務について、代理権を付与することが求められてきたものである。
そこで、今回の改正において、行政書士が作成することができる書類の官公署への提出手続について代理することがで
きることとされたものである。
この規定により、行政書士は許認可申請、届出等の手続について代理する場合には、自ら代理人として提出書類の訂正等を行うことができることとなるものであり、行政に関する手続きの円滑な実施が促進されることが期待されるところである。
?行政書士が作成することができる契約その他の書類を代理人として作成すること(新法第一条の三第二号)
本号の業務については、今回の改正において新たに規定されたもので、行政書士が代理人として契約その他の書類を作成することができることとしたものである。
ここでいう「代理人として」とは、契約等についての代理人としての意であり、直接契約代理を行政書士の業務として位置づけるものではないが、行政書士が業務として契約代理を行い得るとの意味を含むものであると解される。またこの規定により、行政書士は契約書に代理人として署名し、契約文言の修正等を行うことができることとなる。
なお、本号に規定する業務は、行政書士でない者でも行うことができる非独占業務として新たに位置づけられたが、今回の改正では、第一条の二および第一九条の規定については何ら改正されていないところであり、第一条の二に規定する業務については、従来どおり行政書士の独占業務として位置づけられている。したがって、これまでの独占業務が非独占業務となることはないものと解される。
?行政書士が作成することができる書類の作成について相談 に応ずること(新法第一条の三第三号)
この業務については、旧法第一条の三においても行政書士の業務として規定されていたものであり、従来どおり、第一条の二の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について、相談に応ずることができることとしたものである。
(3)行政書士証票の導入について
改正の第三点は、行政書士証票の導入に関することである。
従来の規定では、日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を行ったとき、申請者に対し書面による通知を行うとともに、日本行政書士会連合会会則で規定する行政書士登録証を本人に交付することとされていた。
しかし、この行政書士登録証は行政書士名簿に登録されたことを証明するものにすぎず、行政書士の資格証明をするものではないため、例えば行政書士が官公署に書類の提出手続を行う際、行政書士であることの身分証明書の提示を求められたときに、提示できないという不都合が生じていた。
そこでこのような問題を解消するために、日本行政書士会連合会は行政書士の登録をしたときには、行政書士証票の交付をしなければならないこととしたものである(新法第六条の二第四号)。
一方、行政書士の登録が抹消されたとき、又は行政書士が第一四条第一項の規定により業務の停止処分を受けた場合には、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならないこととされた(新法第七条の二第一項)。
さらに、第一四条第一項の規定により行政書士の業務の停止処分を受け、行政書士証票を返還した行政書士が、行政書士の業務を行うことができることとなったときは、その申請があれば、日本行政書士会連合会は、行政書士証票をその者に再交付しなければならないこととされた(新法第七条の二第二項)。
なお、行政書士証票に関し必要な事項については、日本行政書士会連合会の会則で定めることとされている(新法第七条の三)。
(4)その他
前述のとおり、改正法はすでに平成一三年六月二七日に公布されているが、施行日は平成一四年七月一日とされている。
これは、改正に伴って必要な所定の準備、特に、行政書士証票の導入にあたっては、日本行政書士会連合会の会則等について規定の整備等を行う必要があることから、所要の準備期間を設けたものである。
なお、附則の第二条において、改正法の施行について必要な経過措置が規定されている。すなわち、行政書士証票の交付にあたり、改正法の施行の際、現に行政書士法第一四条第一項の規定により業務の停止処分を受けている行政書士に対しては、当該行政書士が行政書士の業務を行うことができることとなる前に行政書士証票を交付してはならないとされている。
三 おわりに
以上が改正法の内容であるが、行政書士、行政書士会および日本行政書士会連合会の関係者のみならず、行政書士制度の運用に携わる多くの関係者が、今回の改正の趣旨を十分に理解され、御協力いただくことにより、改正法の円滑な運用が図られることを強く期待するところである。
以上 月刊 「地方自治」 総務省行政課 仁瓶氏による行政書士法解説記事より引用
一 はじめに
行政書士法の一部を改正する法律(平成一三年法律第七七号。以下「改正法」という。)が本年六月二二日に成立し、同年六月二七日に公布された。本法は、平成一四年七月一日から施行されることとなっている。
行政書士法は、その制定および数次にわたる改正の多くは議員立法により行われてきた経緯があり、今回の改正につい
ても、議員立法により行われたものである。
すなわち、本年四月一○日、自由民主党政務調査会の総務部会において改正法案が了承された後、各党間の調整を経て、六月五日に衆議院総務委員会委員長提案として国会に提出され、六月七日に衆議院本会議で賛成多数により可決、六月二一日に参議院総務委員会で可決、翌六月二二日に参議院本会議で賛成多数により可決・成立した。
今回の改正は、行政に関する手続の円滑な実施および国民の利便向上の要請への的確な対応を図るため、目的規定を整備し、行政書士が作成することができる書類に係る官公署への提出手続を代理することおよび行政書士が作成することができる契約その他の書類を代理人として作成すること等の業務を行政書士の業務として明確化するとともに、日本行政書士会連合会が行政書士の登録をしたときに行政書士証票を交付するものとすることを内容とするものである。
以下、本改正の主要な内容について説明することにする。
なお、本文中意見にわたる部分は、筆者の私見であることを予めお断りしておく。
二 主な改正内容
(1)目的規定の整備
改正の第一点は、行政書士法の目的規定を整備したことである。すなわち、行政書士法は「行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的と
する」こととされたものである(改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第一条)。
行政書士は、官公署に提山する書類の作成等のみならず、私人間の権利義務や事実証明に関する書類の作成についても、その業務範囲とするところである。
しかし、改正前の行政書士法(以下「旧法」という。)第一条では「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを目的とする」とされており、この規定のままでは「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し」の部分のみに着目して解釈した場合、行政書士法第一条の二との関係で、ともすれば本条が「官公署に提出する書類」に過度に重点が置かれており、したがって、行政書士の業務のうち「権利義務または事実証明に関する書類」を作成することは行政書士法の目的を逸脱しているのではないか、との誤解を招く可能性があった。
このため、新法第一条においては、「あわせて」と記載することにより、行政書士法は「行政に関する手続の円滑な実
施に寄与」することとあわせて、「国民の利便に資すること」を目的としていることをあらためて明確化したものである。つまりこの規定の整備は、私人間の権利義務や事実証明に関する書類の作成についても、行政書士が大きな役割を担っていることをあらためて明示したものといえる。
(2)業務の明確化
改正の第二点は、行政書士が作成することができる書類の官公署への提出手続について代理すること、および行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成することが、新たに行政書士の業務として位置づけ
られたことである (新法第一条の三)。
旧法では、行政書士は、第一条の二において、官公署に提出する書類その他の権利義務又は事実証明に関する書類を作成することができると規定されるとともに、第一条の三において、官公署に提出する書類の提出手続の代行及び当該書類の作成に関する相談に応ずることができることとされていた。
今回の改正では、第一条の二に規定する業務については変更はなく、第一条の三において、他人の依頼を受け報酬を得て、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項を除き、次の各号に掲げる事務を業とすることができる
こととされたところである。以下、新法第一条の三の各号の内容について説明する。
?行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する
手続について代理すること(新法第一条の三第一号)
旧法第一条の三においては、官公署に提出する書類の提出手続の代行及び当該書類の作成に関する相談について規定されていたが、このうち書類の提出手続の代行に関しては、許認可申請や届出の書類を依頼人に代わって官公署に提出する際に、窓口において書類の不備等があった場合、あくまで提出手続を代って行う「使者」としての行政書士は、依頼人の意思を確認しなければ訂正をすることができないものとされてきた。しかし、依頼人にとっても、このような手順を踏むことは非常に煩雑であり、円滑な手続に支障があることから、従来より許認可申請や届出等の手続業務について、代理権を付与することが求められてきたものである。
そこで、今回の改正において、行政書士が作成することができる書類の官公署への提出手続について代理することがで
きることとされたものである。
この規定により、行政書士は許認可申請、届出等の手続について代理する場合には、自ら代理人として提出書類の訂正等を行うことができることとなるものであり、行政に関する手続きの円滑な実施が促進されることが期待されるところである。
?行政書士が作成することができる契約その他の書類を代理人として作成すること(新法第一条の三第二号)
本号の業務については、今回の改正において新たに規定されたもので、行政書士が代理人として契約その他の書類を作成することができることとしたものである。
ここでいう「代理人として」とは、契約等についての代理人としての意であり、直接契約代理を行政書士の業務として位置づけるものではないが、行政書士が業務として契約代理を行い得るとの意味を含むものであると解される。またこの規定により、行政書士は契約書に代理人として署名し、契約文言の修正等を行うことができることとなる。
なお、本号に規定する業務は、行政書士でない者でも行うことができる非独占業務として新たに位置づけられたが、今回の改正では、第一条の二および第一九条の規定については何ら改正されていないところであり、第一条の二に規定する業務については、従来どおり行政書士の独占業務として位置づけられている。したがって、これまでの独占業務が非独占業務となることはないものと解される。
?行政書士が作成することができる書類の作成について相談 に応ずること(新法第一条の三第三号)
この業務については、旧法第一条の三においても行政書士の業務として規定されていたものであり、従来どおり、第一条の二の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について、相談に応ずることができることとしたものである。
(3)行政書士証票の導入について
改正の第三点は、行政書士証票の導入に関することである。
従来の規定では、日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を行ったとき、申請者に対し書面による通知を行うとともに、日本行政書士会連合会会則で規定する行政書士登録証を本人に交付することとされていた。
しかし、この行政書士登録証は行政書士名簿に登録されたことを証明するものにすぎず、行政書士の資格証明をするものではないため、例えば行政書士が官公署に書類の提出手続を行う際、行政書士であることの身分証明書の提示を求められたときに、提示できないという不都合が生じていた。
そこでこのような問題を解消するために、日本行政書士会連合会は行政書士の登録をしたときには、行政書士証票の交付をしなければならないこととしたものである(新法第六条の二第四号)。
一方、行政書士の登録が抹消されたとき、又は行政書士が第一四条第一項の規定により業務の停止処分を受けた場合には、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならないこととされた(新法第七条の二第一項)。
さらに、第一四条第一項の規定により行政書士の業務の停止処分を受け、行政書士証票を返還した行政書士が、行政書士の業務を行うことができることとなったときは、その申請があれば、日本行政書士会連合会は、行政書士証票をその者に再交付しなければならないこととされた(新法第七条の二第二項)。
なお、行政書士証票に関し必要な事項については、日本行政書士会連合会の会則で定めることとされている(新法第七条の三)。
(4)その他
前述のとおり、改正法はすでに平成一三年六月二七日に公布されているが、施行日は平成一四年七月一日とされている。
これは、改正に伴って必要な所定の準備、特に、行政書士証票の導入にあたっては、日本行政書士会連合会の会則等について規定の整備等を行う必要があることから、所要の準備期間を設けたものである。
なお、附則の第二条において、改正法の施行について必要な経過措置が規定されている。すなわち、行政書士証票の交付にあたり、改正法の施行の際、現に行政書士法第一四条第一項の規定により業務の停止処分を受けている行政書士に対しては、当該行政書士が行政書士の業務を行うことができることとなる前に行政書士証票を交付してはならないとされている。
三 おわりに
以上が改正法の内容であるが、行政書士、行政書士会および日本行政書士会連合会の関係者のみならず、行政書士制度の運用に携わる多くの関係者が、今回の改正の趣旨を十分に理解され、御協力いただくことにより、改正法の円滑な運用が図られることを強く期待するところである。
以上 月刊 「地方自治」 総務省行政課 仁瓶氏による行政書士法解説記事より引用
|
|
|
|
|
|
|
|
MIXI 行政書士連合会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-