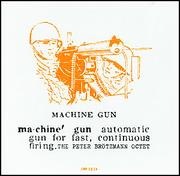Tomoko Mukaiyama at BIMHUIS
Woensdag 6 september, 22.30 uur
Bimhuis
Tomoko Mukaiyama - piano, video
Tomoko Mukaiyama , haar / haar (60’)
waarin opgenomen: Michiel Mensingh (nl, 1975), A Glitch in the Matrix (concept Tomoko Mukaiyama) (2005, 4’) (JS)
夏休みも終わり、通い慣れたアムステルダム中央駅裏側から700mほど歩いたBIMHuisに向かうのはほぼ二ヵ月半ぶりだ。
普通のジャズ・コンサートであれば9時を廻って始まり、45分ほどの2セットを挟んで20分ほどの休憩があり11時半ごろにはアンコールも済んでいる、という按配なのだが、この日は通常のジャズのコンサートでも一晩のフル・コンサートでもない。
この日のコンサートは現代音楽、インプロヴィゼーション・ミュージックのコンクールと今までのシリーズに関係した演奏者、作曲家をも招待して幾つかの会場で一週間ほど様々なコンサートが催されるフェスティバルの一環である。 下の450人収容の大ホールでは他のコンサートが9時前ごろから開かれており、それに合わせて10時半から300人程度収容のジャズ・ハウスでこのワンステージ・コンサートとなった次第である。
演者はピアノ演奏、作曲のTomoko Mukaiyama女史、1991年にこのコンクールで優勝後オランダ、日本を中心に活動しているのだそうだ。 もう3年ほど前に北の街、グローニンゲンのフリー、インプロヴィゼーションジャズ祭のオープニングコンサートで日本から招かれたグループのピアノを担当していたときに初めて耳にして作曲、時にはピアニカを演奏する日本人指揮者の下、ピアノパートのインプロヴィゼーション部分では印象的なピアノを聞いたのを記憶していたのでこの夜のコンサートに期待して夕食後、ゆっくり支度をして夜汽車に乗ったというわけだ。
この人のこの夜のプログラムは 「Haar/Haar(60’)」と題されていて、Haarはオランダ語で三人称女性所有格(彼女の)と、それにたまたま綴り、発音が同じ名詞(毛)を組み合わせた題となっていた。 60は多分60分だろうと想像した。 それにヴィデオとコンピューターでミヒル・メンシングにより作曲、操作された音響とのコラボレーションとプログラムにはある。
このような試みはジャズのコンサートではないことはないがあまり通常には行われないから、コラボレーション、コンテンポラリー・ミュージックの範疇に入るのだろう。 音楽を聴くものには勿論、その意匠、構造、音がもたらす空間、それにそれぞれの音楽体験とのすり合わせ、を通じて印象を形作りその音楽体験の意味を判断するのだろうが、わたしのこの日の眼目はピアノの両側に斜めに置かれた壁の半分のようなスクリーンに示される映像と音が交じり合うその効果のなかからどれだけ音自身が視覚効果に拮抗して自立を主張できるか、という点にあった。
それはこの20年ほど顕著になってきた視聴覚時代の「視」が音楽の世界で「聴」を浸蝕しつつある事を認識していることからくる。 音を音として捉えたいというものには眼は音に集中することを妨げるものとして機能する場合がある。 視覚の意味としての信号は音の信号より意味の種類が複雑に構成されており、もしかすると視覚の信号の方が音の信号より脳に対するインパクトが強いのではないか。 勿論、爆発音や通常レベルから突然の強弱が起こればそれでの注意が音に向かう事はあるがとりわけ動いて刺激する視覚は現代社会を睥睨するといっても過言でない感覚でもあるからだ。
現代音楽の試みの中ではこういうことは昔から行われている。 日頃、現代音楽を聴く機会の少ないものにとっては現代音楽と、ジャズの一領域であるフリー、インプロヴィゼーション・ジャズとの領域のすり合わせとしてのこのような試みは興味深いものだ。
暗いステージの中心、スタンウエー・ピアノが置かれたその両側に斜めに立てかけられたスクリーンにモノクローム・トーンで風に揺らぐ黒髪の大写しが続く。 演者が登場し、ピアノ前に位置し、暫く無音のなかに髪がゆらめく。
バッハの中庸速度の聞きなれたものが演奏されほどなくそれが変奏され、それが徐々に音の幅を持った単調な繰り返し音となりその繰り返しが少しずつずれていく。 フィリップ・グラスであれば機械的な繰り返しに響きがちだがここでは湿り気とでも言うべき響きが混じるようだ。
その音、響きもリズム、トレモロ、アルペジオと変奏していき、時には日本的旋律の部分を思わせる繰り返しともなる。
もうすでに髪の毛のそよぎはとっくに消えており音のセグメント、意識の流れの節目に挿入される映像はそれから音の意味を導くために機能すると想像する。 演者は60分のステージの中で周到に五線譜に書かれたものをその場面に応じて右に左にページを捲りながらもインプロヴィゼーションの空間は確保してあるようだ。 途中にはモーツアルト、ベートーベン、ショパン、ドビュッシーが挟まれ、時にはたゆたい、また激しく打ちつけ音の現在と過去を提示、つまり演者、作曲者の音の略歴、自我の旅路の提示という風に受け取られる構成である。 事実、節々では女性の恥毛が浅い水の中でうごめき、女性性の提示だと見受けられるし、上腕部を上げ腋の毛髪を筋肉と一緒にする映像は音をささえる肉体の提示なのだろうと単純ながらも解釈できるようだ。
音と、生身の人間の過去、現在を示す中で、ショパンのゆったりとしたポロネーズ風の気分よさに身を任せていると突然、ハイドンの驚愕の例に倣ったかと言うべき耳を圧するスピーカーからの機械的連続混濁音が数分続き、以後、鋸をヴァイオリンの弓で擦るかのような音との混ざり合い、やがて力技の繰り返し音のパターンには腋毛とそれを取り囲む上腕、肩、胸の一部が大写しにスクリーン上で微かに動いている。
それも収まりやがて個人的にもここ何年も聞いてきたモーリス・ラヴェルのピアノ協奏曲ト長調アダージョが流れてきたときには息を呑む思いだった。 そのピアノから楽譜に忠実であればフルートが加わる前あたりから徐々に変奏させて水のせせらぎを思わせる響きに変化させていく。暫く続くとこの段階では先ほどのラベルもすでに一時の夢かとおもわせるほど19世紀は彼方に消えて、 ジャズプロパーからするとフレーズの呪縛に絡まれたこのような70年代のダラー・ブランド、キース・ジャレット的なトーンが示される。 それが昂じてそこにコンピューターで合成された音が加わり、催眠効果を醸し出しピアノはここぞとばかりフォルテッシモで微かに繰り返し響きの移動を試みるとピアノフォルテからオーケストラの響きが立ち上がりクライマックスに至るようだ。
漸次トーンが強から中庸。弱に至ると最初に聞いたバッハが現れそれも消えると画面は灰色の画面に放送終了後のごま塩画面とノイズが流れそのうち徐々に強くなりそれは髪を打つシャワーの水音であることが分かる。 その音のに耳を傾けているとそこには演者はすでにステージから消えている。
Woensdag 6 september, 22.30 uur
Bimhuis
Tomoko Mukaiyama - piano, video
Tomoko Mukaiyama , haar / haar (60’)
waarin opgenomen: Michiel Mensingh (nl, 1975), A Glitch in the Matrix (concept Tomoko Mukaiyama) (2005, 4’) (JS)
夏休みも終わり、通い慣れたアムステルダム中央駅裏側から700mほど歩いたBIMHuisに向かうのはほぼ二ヵ月半ぶりだ。
普通のジャズ・コンサートであれば9時を廻って始まり、45分ほどの2セットを挟んで20分ほどの休憩があり11時半ごろにはアンコールも済んでいる、という按配なのだが、この日は通常のジャズのコンサートでも一晩のフル・コンサートでもない。
この日のコンサートは現代音楽、インプロヴィゼーション・ミュージックのコンクールと今までのシリーズに関係した演奏者、作曲家をも招待して幾つかの会場で一週間ほど様々なコンサートが催されるフェスティバルの一環である。 下の450人収容の大ホールでは他のコンサートが9時前ごろから開かれており、それに合わせて10時半から300人程度収容のジャズ・ハウスでこのワンステージ・コンサートとなった次第である。
演者はピアノ演奏、作曲のTomoko Mukaiyama女史、1991年にこのコンクールで優勝後オランダ、日本を中心に活動しているのだそうだ。 もう3年ほど前に北の街、グローニンゲンのフリー、インプロヴィゼーションジャズ祭のオープニングコンサートで日本から招かれたグループのピアノを担当していたときに初めて耳にして作曲、時にはピアニカを演奏する日本人指揮者の下、ピアノパートのインプロヴィゼーション部分では印象的なピアノを聞いたのを記憶していたのでこの夜のコンサートに期待して夕食後、ゆっくり支度をして夜汽車に乗ったというわけだ。
この人のこの夜のプログラムは 「Haar/Haar(60’)」と題されていて、Haarはオランダ語で三人称女性所有格(彼女の)と、それにたまたま綴り、発音が同じ名詞(毛)を組み合わせた題となっていた。 60は多分60分だろうと想像した。 それにヴィデオとコンピューターでミヒル・メンシングにより作曲、操作された音響とのコラボレーションとプログラムにはある。
このような試みはジャズのコンサートではないことはないがあまり通常には行われないから、コラボレーション、コンテンポラリー・ミュージックの範疇に入るのだろう。 音楽を聴くものには勿論、その意匠、構造、音がもたらす空間、それにそれぞれの音楽体験とのすり合わせ、を通じて印象を形作りその音楽体験の意味を判断するのだろうが、わたしのこの日の眼目はピアノの両側に斜めに置かれた壁の半分のようなスクリーンに示される映像と音が交じり合うその効果のなかからどれだけ音自身が視覚効果に拮抗して自立を主張できるか、という点にあった。
それはこの20年ほど顕著になってきた視聴覚時代の「視」が音楽の世界で「聴」を浸蝕しつつある事を認識していることからくる。 音を音として捉えたいというものには眼は音に集中することを妨げるものとして機能する場合がある。 視覚の意味としての信号は音の信号より意味の種類が複雑に構成されており、もしかすると視覚の信号の方が音の信号より脳に対するインパクトが強いのではないか。 勿論、爆発音や通常レベルから突然の強弱が起こればそれでの注意が音に向かう事はあるがとりわけ動いて刺激する視覚は現代社会を睥睨するといっても過言でない感覚でもあるからだ。
現代音楽の試みの中ではこういうことは昔から行われている。 日頃、現代音楽を聴く機会の少ないものにとっては現代音楽と、ジャズの一領域であるフリー、インプロヴィゼーション・ジャズとの領域のすり合わせとしてのこのような試みは興味深いものだ。
暗いステージの中心、スタンウエー・ピアノが置かれたその両側に斜めに立てかけられたスクリーンにモノクローム・トーンで風に揺らぐ黒髪の大写しが続く。 演者が登場し、ピアノ前に位置し、暫く無音のなかに髪がゆらめく。
バッハの中庸速度の聞きなれたものが演奏されほどなくそれが変奏され、それが徐々に音の幅を持った単調な繰り返し音となりその繰り返しが少しずつずれていく。 フィリップ・グラスであれば機械的な繰り返しに響きがちだがここでは湿り気とでも言うべき響きが混じるようだ。
その音、響きもリズム、トレモロ、アルペジオと変奏していき、時には日本的旋律の部分を思わせる繰り返しともなる。
もうすでに髪の毛のそよぎはとっくに消えており音のセグメント、意識の流れの節目に挿入される映像はそれから音の意味を導くために機能すると想像する。 演者は60分のステージの中で周到に五線譜に書かれたものをその場面に応じて右に左にページを捲りながらもインプロヴィゼーションの空間は確保してあるようだ。 途中にはモーツアルト、ベートーベン、ショパン、ドビュッシーが挟まれ、時にはたゆたい、また激しく打ちつけ音の現在と過去を提示、つまり演者、作曲者の音の略歴、自我の旅路の提示という風に受け取られる構成である。 事実、節々では女性の恥毛が浅い水の中でうごめき、女性性の提示だと見受けられるし、上腕部を上げ腋の毛髪を筋肉と一緒にする映像は音をささえる肉体の提示なのだろうと単純ながらも解釈できるようだ。
音と、生身の人間の過去、現在を示す中で、ショパンのゆったりとしたポロネーズ風の気分よさに身を任せていると突然、ハイドンの驚愕の例に倣ったかと言うべき耳を圧するスピーカーからの機械的連続混濁音が数分続き、以後、鋸をヴァイオリンの弓で擦るかのような音との混ざり合い、やがて力技の繰り返し音のパターンには腋毛とそれを取り囲む上腕、肩、胸の一部が大写しにスクリーン上で微かに動いている。
それも収まりやがて個人的にもここ何年も聞いてきたモーリス・ラヴェルのピアノ協奏曲ト長調アダージョが流れてきたときには息を呑む思いだった。 そのピアノから楽譜に忠実であればフルートが加わる前あたりから徐々に変奏させて水のせせらぎを思わせる響きに変化させていく。暫く続くとこの段階では先ほどのラベルもすでに一時の夢かとおもわせるほど19世紀は彼方に消えて、 ジャズプロパーからするとフレーズの呪縛に絡まれたこのような70年代のダラー・ブランド、キース・ジャレット的なトーンが示される。 それが昂じてそこにコンピューターで合成された音が加わり、催眠効果を醸し出しピアノはここぞとばかりフォルテッシモで微かに繰り返し響きの移動を試みるとピアノフォルテからオーケストラの響きが立ち上がりクライマックスに至るようだ。
漸次トーンが強から中庸。弱に至ると最初に聞いたバッハが現れそれも消えると画面は灰色の画面に放送終了後のごま塩画面とノイズが流れそのうち徐々に強くなりそれは髪を打つシャワーの水音であることが分かる。 その音のに耳を傾けているとそこには演者はすでにステージから消えている。
|
|
|
|
コメント(5)
ミュージック・トリエナーレ ケルン2007 インプロヴィゼーション
2007年 5月6日 於 ケルンシンフォニーホール
Fay Claasen, Paquito D"Rivera with WDR Big Band and WDR Rundfunkorchester
編曲・指揮 Michael Abene
火曜の夜には不定期ながらドイツ、ケルンに本拠を置くテレビ局WDRのジャズ番組がもう何十年も続いており、ドイツ文化の中心の一つであるケルンのWDRビッグバンドはヨーロッパのビッグバンドの中でも歴史があり達者なジャズメンをそろえていることで定評があるのだがそのベース奏者であり編曲も担当する Ali Haurand がホストを務めるJazzLineという番組がそのメインである。 この日はミュージック・トリエナーレ ケルン2007 インプロヴィゼーションと題してビッグバンドにシンフォニーオーケストラを加えた大編成をバックに2人のソリストが加わってインプロヴィゼーションをやろうという試みの70分の番組構成である。
2000字を越したようです。 残りは私の同日の日記をご参照ください。
ICP Orchestra
Thu. 8 May 2008 at BIMHUIS in Amsterdam
Thomas Hebert (tp)
Wolter Wierbos (tb)
Michael Moore (as,cl)
Ab Baas (cl, ts)
Tobias Delius (ts, cl)
Mischa Mengelberg (p)
Mary Oliver (alt violin)
Tristan Honsinger (cello)
Ernst Glerum (b)
Han Bennink (ds)
このグループでピアノとドラムスが40年前に活動し始めてさまざまな人が集まり今のフォーメーションとなっている。 フリー・インプロヴィゼーションジャズが好きでいろいろな機会にでかけるとこのメンバー達が個別に、また何人か他のジャズメンたちとこことは違う趣向で演じるのに出会うことが多い。 けれどこのオーケストラのメンバーは互いに気心が分っていて定期的にこのオーケストラとして集まり活動する。 それぞれの個性を示しつつ調性も組み込みながら曲を構成するのはピアノの仕事であることが多く、実際に曲の流れの各局面ではドラムスが引き締めるというのがこのグループのおおまかな仕組みだろうか。
開演30分ほど前にホールに入り最前列正面に席をとったら既にピアノはそこに座って何か弾いていたのだが先ほど入り口のところで同年輩の女性となにかごそごそスーパーのビニール袋のなかを掻き探していてその横を通って来たのにと思ったのだが私が会場の中にあるCDコーナーのオバサンと話しているうちにそのままピアノのところにいったのかそのビニール袋を無造作にピアノの上に置きポツポツとモンク風のことをやっていた。 何年か前にロッテルダムのジャズフェスティバルで同じようなところに席を取っていたのだが贔屓のイギリス人アルト奏者と控え室で一時間以上話していてこの人の演奏に遅れ最後の曲が始まる前に席に戻ったらひょこひょこと椅子からこちらの目の前まで来て睨まれたこともありこの人は油断がならない。 オランダの人間国宝なのである。 パンダといってもいいかもしれない。 演奏中は皆この人を眺め指の動きに聴き入り感心し時々の仕草に微笑む。
もう一人のパンダが居るのだがこの人はなんとも精力的なことか。 ジャズの歴史ではマックス・ローチに中学生の頃出会って以来何人も太鼓を聴いているが正に全身太鼓叩きであるこのドラマーは動き回り転げ周り寝転んでもリズムを刻んでいる。 コミックや演芸でこういうのを時々見かけ笑いと感心を得るのがあるがここではその笑いの裏には演じられる音楽のためにはそれが必要なのだという必然がありそれが演芸と彼の芸術の違いを示している。
コンサートは若いトランペットが登場し歩きながら無造作に音を出し始めるとノソノソ登場したピアノがそのビニール袋を鍵盤に下ろし音を探るように遊んでいる。 少々の悪意もあるのか機嫌が悪いのかとも思うのだがあながちそうでもないようで二人で遊んでいるうちに全員登場し少々のハードバップを崩してノスタルジーをまぶしたアンサンブルを行った後アルトヴァイオリンがアイルランド風の旋律を奏でるとそれを盛り上げるクラリネット3本がサポートしチェロとバスが弦楽パートで補強して締めはヴァイオリン一本だ。
それぞれの曲には各自充分なソロをもちアンサンブルもソロの集合が調性となるというような高度なものでありフリーがどのようなオーケストレーションを形作るかという一つの例を聴かせるのだが一方、こういう音楽が辿ってきた歴史をしめすデモンストレーションでもある。 突然ミンガスの重厚で綻びのあるアンサンブルが現れるかと思えばオーネット・コールマン調も別の曲では現れる、といった風だ。 カリプソをベースにしたものの中にアルバート・アイラーが現れメキシコ、ティファナのブラスに取って代わられるということもある。 ジャズのオーケストラならブラスが席巻することが多く弦が表に出るためには吹くのを辞めるのが一番なのだがそうなると景色が一挙に変わり異次元の世界に導かれることにもなる。 そこでは彼らの創りだす音が現代音楽とジャズの境を消しているようでもある。 クラリネットが3本あればそこで鳥の歌声を奏でるのは自然で暫し3羽が喧しくお喋りしたり飛び回ったりするのだがエリック・ドルフィーのフルートが加わるとそれをモンク風のピアノが受ける場面もある。 モンクのピアノにやおらニューオーリンズ風のトランペットが寄り添いそのうちハービー・ニコルスの3/4拍子に変わり、ブラスのバックでヴァイオリンがイルカに乗った少年のメロディーを弾くという景色が現れた。
10曲目のアンコールでは軽快なハードバップを元にしたものでこのコンサートを締めて会場の8割がたオランダに住む者を含め世界のあちこちから来た、あまり多くない100人ぐらいの聴衆に感心と満足感を与えて自由の音楽家たちは次の機会まで皆それぞれあちこちに散らばっていく。
写真はBIMHUISのプログラムから
Thu. 8 May 2008 at BIMHUIS in Amsterdam
Thomas Hebert (tp)
Wolter Wierbos (tb)
Michael Moore (as,cl)
Ab Baas (cl, ts)
Tobias Delius (ts, cl)
Mischa Mengelberg (p)
Mary Oliver (alt violin)
Tristan Honsinger (cello)
Ernst Glerum (b)
Han Bennink (ds)
このグループでピアノとドラムスが40年前に活動し始めてさまざまな人が集まり今のフォーメーションとなっている。 フリー・インプロヴィゼーションジャズが好きでいろいろな機会にでかけるとこのメンバー達が個別に、また何人か他のジャズメンたちとこことは違う趣向で演じるのに出会うことが多い。 けれどこのオーケストラのメンバーは互いに気心が分っていて定期的にこのオーケストラとして集まり活動する。 それぞれの個性を示しつつ調性も組み込みながら曲を構成するのはピアノの仕事であることが多く、実際に曲の流れの各局面ではドラムスが引き締めるというのがこのグループのおおまかな仕組みだろうか。
開演30分ほど前にホールに入り最前列正面に席をとったら既にピアノはそこに座って何か弾いていたのだが先ほど入り口のところで同年輩の女性となにかごそごそスーパーのビニール袋のなかを掻き探していてその横を通って来たのにと思ったのだが私が会場の中にあるCDコーナーのオバサンと話しているうちにそのままピアノのところにいったのかそのビニール袋を無造作にピアノの上に置きポツポツとモンク風のことをやっていた。 何年か前にロッテルダムのジャズフェスティバルで同じようなところに席を取っていたのだが贔屓のイギリス人アルト奏者と控え室で一時間以上話していてこの人の演奏に遅れ最後の曲が始まる前に席に戻ったらひょこひょこと椅子からこちらの目の前まで来て睨まれたこともありこの人は油断がならない。 オランダの人間国宝なのである。 パンダといってもいいかもしれない。 演奏中は皆この人を眺め指の動きに聴き入り感心し時々の仕草に微笑む。
もう一人のパンダが居るのだがこの人はなんとも精力的なことか。 ジャズの歴史ではマックス・ローチに中学生の頃出会って以来何人も太鼓を聴いているが正に全身太鼓叩きであるこのドラマーは動き回り転げ周り寝転んでもリズムを刻んでいる。 コミックや演芸でこういうのを時々見かけ笑いと感心を得るのがあるがここではその笑いの裏には演じられる音楽のためにはそれが必要なのだという必然がありそれが演芸と彼の芸術の違いを示している。
コンサートは若いトランペットが登場し歩きながら無造作に音を出し始めるとノソノソ登場したピアノがそのビニール袋を鍵盤に下ろし音を探るように遊んでいる。 少々の悪意もあるのか機嫌が悪いのかとも思うのだがあながちそうでもないようで二人で遊んでいるうちに全員登場し少々のハードバップを崩してノスタルジーをまぶしたアンサンブルを行った後アルトヴァイオリンがアイルランド風の旋律を奏でるとそれを盛り上げるクラリネット3本がサポートしチェロとバスが弦楽パートで補強して締めはヴァイオリン一本だ。
それぞれの曲には各自充分なソロをもちアンサンブルもソロの集合が調性となるというような高度なものでありフリーがどのようなオーケストレーションを形作るかという一つの例を聴かせるのだが一方、こういう音楽が辿ってきた歴史をしめすデモンストレーションでもある。 突然ミンガスの重厚で綻びのあるアンサンブルが現れるかと思えばオーネット・コールマン調も別の曲では現れる、といった風だ。 カリプソをベースにしたものの中にアルバート・アイラーが現れメキシコ、ティファナのブラスに取って代わられるということもある。 ジャズのオーケストラならブラスが席巻することが多く弦が表に出るためには吹くのを辞めるのが一番なのだがそうなると景色が一挙に変わり異次元の世界に導かれることにもなる。 そこでは彼らの創りだす音が現代音楽とジャズの境を消しているようでもある。 クラリネットが3本あればそこで鳥の歌声を奏でるのは自然で暫し3羽が喧しくお喋りしたり飛び回ったりするのだがエリック・ドルフィーのフルートが加わるとそれをモンク風のピアノが受ける場面もある。 モンクのピアノにやおらニューオーリンズ風のトランペットが寄り添いそのうちハービー・ニコルスの3/4拍子に変わり、ブラスのバックでヴァイオリンがイルカに乗った少年のメロディーを弾くという景色が現れた。
10曲目のアンコールでは軽快なハードバップを元にしたものでこのコンサートを締めて会場の8割がたオランダに住む者を含め世界のあちこちから来た、あまり多くない100人ぐらいの聴衆に感心と満足感を与えて自由の音楽家たちは次の機会まで皆それぞれあちこちに散らばっていく。
写真はBIMHUISのプログラムから
Tineke Postema / Ernst Glerum / Han Benink
Wed. 19 Nov. 2008 at BIMHUIS in Amsterdam
Tineke Postma (as, ss)
Ernst Glerum (b)
Han Benink (ds)
1st Set
1) Chippy (O. Coleman)
2) Eyes of the Mind (T.P)
3) Adajio No.13 (Hidro Viravodos)
4) A Flower is A Lovesome Thing (Billy Strayhorn)
5)
2nd Set
6) Mind ..... (O. Coleman)
7) Fleurette Africain (D. Elington)
8) Hot House (T. Dameron)
9) On Green Dolphin Street (Bronislau Kaper)
10) A Journey that matters (T.P)
Encore
Intermezzo
前回彼女のコンサートを聴いてもう一年半にもなるのだが、その時このように書いた。
http://blogs.yahoo.co.jp/vogelpoepjp/46485120.html
そしてその後リリースされたCD, A Journey That Matters (FNCJ-5521)では彼女の繊細かつ力強い女性性が表面に沁み出すようで、サックス奏者としての才能が際立ったものとしてアメリカやヨーロッパのジャズ界で深く彼女の存在が認識されているとこの日のプログラムにはそれぞれそれらのジャズ雑誌や高級日刊紙の名前が挙げられていた。
先週、このドラムスとベースのバックでピアノの Michiel Borstlap のピアノ・トリオをここで聴いて深い感興を得て帰宅した。 この二人はオランダの誇るフリー・インプロヴィゼーションジャズグループ、 ICPのマルチ打楽器巧者のベニンクとチェロよりも少し大きく普通のコントラバスよりも小さい楽器を弓と指で奏でるグレルムである。 私のこの日の興味はフリージャズの中に曝されたサックスがどのような演奏をするかというところにあった。
演目は自作が二つ、オーネット・コールマンのものが二つ、エリントンとストレーホーンのもの、バップ発祥期の8)、クラシックのアダージョに手を入れた3)、前述のアルバムからは三曲、4)7)10)を演奏し、マイルスからドルフィーまで、またヴォーカルでも広く歌われている9)をとりあげたが、これはオランダでドルフィーの「ラスト・デート」が録音された時ドラムを担当したベニンクに関連して、そのアルバムでは演奏されてはいないもののその独特な曲想をドルフィー調を微かに含めたものとしてこの日舞台に乗せたと思われる。
フリージャズではその言葉のように、ジャズのほかのジャンルに比べて何でもありなのだが、それでもむやみやたらと何をやってもいい、ということでもない。 むやみやたらと何でもやるというのには予め誰がどこで何をどのよのようにやるかある程度の約束事が存在するだろう。 だからまるで好きなことをやる、いうことにはたとえ約束事はしない、といってもそれを保証する取り決めが必要なのだしソロでない場合は他のメンバーとの社会性が大きな要素となる。 個と集団のあいだで緊張と緩和、同意と離反、自由と拘束などの要素が絡み合って一定時間の中で音として創造される。
百戦練磨でいつも新たな戦場を駆け巡ってきて今もエネルギーの枯渇することのない魁偉なベニンクなのだが会場に入ってフルのドラムセットが据えられているのに驚いた。 サックスの立ち位地とは1mも離れてはおらず間には腰ぐらいまでの緩衝板が置かれているだけで、ボルストラップとのピアノトリオではスネアドラム一つだけだったのとは対照的だ。 老獪で驚きが一杯のドラムスを見目麗しいポストバップの暖かく繊細な女性サックスがどのように矯めるのかというのが私の興味の一つだった。 それとも美女は野獣に喰われてしまうのだろうか。 この洗練された野獣は美女を喰うにしてもその音の美しさを充分認識しているゆえに、愛らしい幼さを曲紹介のオランダ語に響かせるサックス奏者の一方ならぬ力を秘めたアルトとソプラノの音に絡まれないように注意深くうかがっている節はある。
結論から言えば、この日のプログラムはポスマが構成して彼女がフリージャズのテリトリーにも足を踏み入れしっかりとリズムマシンを自分の統御下に置いたということなのだが、そこでの彼女の資質が大きくここに関わっている。 絶えず変化する奏法、リズムを繰り出し世界を自分にひきつけ、一瞬でも介入できる隙があれば表に飛び出してくるベニンクのドラムスは知る者にはそれが快感なのだがその強烈な個性には驚きから呆れ、さらには辟易、というプロセスを辿るものもいる。 打楽器の巨人なのだ。 それに年輪が途方もなく太い幹だ。 それがオーケストラ、カルテット、クインテット構成であればその磁場に絡めとられるリスクは低くなるのだがここでは各自丸裸状態なのだ。
スペースが足りないようです。 残りは下記のサイトをご参照ください
http://blogs.yahoo.co.jp/vogelpoepjp/56772362.html
Wed. 19 Nov. 2008 at BIMHUIS in Amsterdam
Tineke Postma (as, ss)
Ernst Glerum (b)
Han Benink (ds)
1st Set
1) Chippy (O. Coleman)
2) Eyes of the Mind (T.P)
3) Adajio No.13 (Hidro Viravodos)
4) A Flower is A Lovesome Thing (Billy Strayhorn)
5)
2nd Set
6) Mind ..... (O. Coleman)
7) Fleurette Africain (D. Elington)
8) Hot House (T. Dameron)
9) On Green Dolphin Street (Bronislau Kaper)
10) A Journey that matters (T.P)
Encore
Intermezzo
前回彼女のコンサートを聴いてもう一年半にもなるのだが、その時このように書いた。
http://blogs.yahoo.co.jp/vogelpoepjp/46485120.html
そしてその後リリースされたCD, A Journey That Matters (FNCJ-5521)では彼女の繊細かつ力強い女性性が表面に沁み出すようで、サックス奏者としての才能が際立ったものとしてアメリカやヨーロッパのジャズ界で深く彼女の存在が認識されているとこの日のプログラムにはそれぞれそれらのジャズ雑誌や高級日刊紙の名前が挙げられていた。
先週、このドラムスとベースのバックでピアノの Michiel Borstlap のピアノ・トリオをここで聴いて深い感興を得て帰宅した。 この二人はオランダの誇るフリー・インプロヴィゼーションジャズグループ、 ICPのマルチ打楽器巧者のベニンクとチェロよりも少し大きく普通のコントラバスよりも小さい楽器を弓と指で奏でるグレルムである。 私のこの日の興味はフリージャズの中に曝されたサックスがどのような演奏をするかというところにあった。
演目は自作が二つ、オーネット・コールマンのものが二つ、エリントンとストレーホーンのもの、バップ発祥期の8)、クラシックのアダージョに手を入れた3)、前述のアルバムからは三曲、4)7)10)を演奏し、マイルスからドルフィーまで、またヴォーカルでも広く歌われている9)をとりあげたが、これはオランダでドルフィーの「ラスト・デート」が録音された時ドラムを担当したベニンクに関連して、そのアルバムでは演奏されてはいないもののその独特な曲想をドルフィー調を微かに含めたものとしてこの日舞台に乗せたと思われる。
フリージャズではその言葉のように、ジャズのほかのジャンルに比べて何でもありなのだが、それでもむやみやたらと何をやってもいい、ということでもない。 むやみやたらと何でもやるというのには予め誰がどこで何をどのよのようにやるかある程度の約束事が存在するだろう。 だからまるで好きなことをやる、いうことにはたとえ約束事はしない、といってもそれを保証する取り決めが必要なのだしソロでない場合は他のメンバーとの社会性が大きな要素となる。 個と集団のあいだで緊張と緩和、同意と離反、自由と拘束などの要素が絡み合って一定時間の中で音として創造される。
百戦練磨でいつも新たな戦場を駆け巡ってきて今もエネルギーの枯渇することのない魁偉なベニンクなのだが会場に入ってフルのドラムセットが据えられているのに驚いた。 サックスの立ち位地とは1mも離れてはおらず間には腰ぐらいまでの緩衝板が置かれているだけで、ボルストラップとのピアノトリオではスネアドラム一つだけだったのとは対照的だ。 老獪で驚きが一杯のドラムスを見目麗しいポストバップの暖かく繊細な女性サックスがどのように矯めるのかというのが私の興味の一つだった。 それとも美女は野獣に喰われてしまうのだろうか。 この洗練された野獣は美女を喰うにしてもその音の美しさを充分認識しているゆえに、愛らしい幼さを曲紹介のオランダ語に響かせるサックス奏者の一方ならぬ力を秘めたアルトとソプラノの音に絡まれないように注意深くうかがっている節はある。
結論から言えば、この日のプログラムはポスマが構成して彼女がフリージャズのテリトリーにも足を踏み入れしっかりとリズムマシンを自分の統御下に置いたということなのだが、そこでの彼女の資質が大きくここに関わっている。 絶えず変化する奏法、リズムを繰り出し世界を自分にひきつけ、一瞬でも介入できる隙があれば表に飛び出してくるベニンクのドラムスは知る者にはそれが快感なのだがその強烈な個性には驚きから呆れ、さらには辟易、というプロセスを辿るものもいる。 打楽器の巨人なのだ。 それに年輪が途方もなく太い幹だ。 それがオーケストラ、カルテット、クインテット構成であればその磁場に絡めとられるリスクは低くなるのだがここでは各自丸裸状態なのだ。
スペースが足りないようです。 残りは下記のサイトをご参照ください
http://blogs.yahoo.co.jp/vogelpoepjp/56772362.html
Michael Moore Quintet
Sun. 20 Dec. 2008 at De Burcht in Leiden, The Netherlands
Michael Moore (as, cl, bas cl)
Eric Vloeimans (tp)
Harman Fraanje (p)
Clemens van der Veen (b)
Owen Hart jr. (ds)
Michae Moore は1954年カリフォルニア生まれ、幼少の頃からクラリネットを学びボストンのコンセルバトワールでジャッキー・バイヤード、ギュンター・シュラー、ジョージ・ラッセル等に師事し、1977年に卒業後1982年以来アムステルダムに拠を置いて活動しているアルトサックス、クラリネット、バスクラリネットを概ね得意とする演奏家であり ICP(Instant Composers Pool) のメンバーとしてだけではなく様々なジャンルの音楽家たちと多種のプロジェクトを進めているマルチリード奏者である。
86年以来彼はオランダ内外で様々なジャズの賞を受け、中でもダウンビート誌批評家の投票ではクラリネット部門で2000年から連続して何回か第一位として認められている。
私はこの日、風邪のため頭が重く会場では咳込み迷惑を掛けない様にとのど飴を用意して自転車を走らせた。 フリー・インプロヴィゼーション系のジャズコンサートには町のジャズ同好会主催の演奏会ではせいぜい50人ぐらいかと高をくくって入ってみれば中ぐらいの会議室然としたスペースに軽く100人は入っていてびっくりしたし、開演時間を間違えて遅れてドアを開けて入ったときには2曲目が始まったところだと言われ暗い会場の端にあった椅子をよせて舞台の横に落ち着いた。
先週家に届いたオランダジャズ専門誌では恒例の年末に、オランダ音楽関係者、批評家、コラムニスト20人ほどにアンケートで幾つか質問をした中で、今年の収穫としてその一人が今年一番のアルバムにこの人のレーベル、ramboy から25番目発売の Fragile を挙げておりそれには私も異存なくそのアルバムをこのコンサートの前にまた聴いておこうと捜したのだがなぜか見つからない。 このアルバムのピアノはこの日の Fraanje で、この人はこの何年か折に触れ他のだれかのセッションでも弾いいるのに接することがありその抒情性の高さにいつも感心するのだが、ドッビュシー、ラベルあたりのトーンを思わせ自分のピアノに配分する具合がなんともいえないくらい心地よいのだ。
この日のトランペット、 Eric Vloeimans、 ヨーロピアンピアノトリオのMarc van Roon が加わったアルバム ramboy nr. 22、 06年発売のアルバム、 Osiris も私の好きなアルバムなのだがこの日はその中からMooreの筆になる佳曲、Ishi も演奏された。 それを弾く Fraanje のピアノの解釈にはより一層の親和感を持つ。
演目には自作の Whistle Blower, Brazilian Tune, Ishi, Fiets in Orstrijk, What is to do, Meager Harvest, などに加えて Jacki Byard の Blues、 O. Coleman のものが載せられ、それぞれアルトサックス、クラリネット、バスクラリネットで演奏された。
私はオランダの各地の ICP をはじめフリー、インプロヴィゼーション系のコンサートで多くのミューシシャンたちが様々な組み合わせでセッションをするのに立ち会って、自分が好きな楽器のアルトサックスがあると聴いているうちに Michael Moore がそこにいて耳が自然とひきつけられ、その豊かな音楽性に惹かれるようになり、Michael Moore の名前がそれらのグループのメンバーの中にあると出かけるようにしている。 彼の地味な人格は音楽では深みとなって現れるようでどのコンサートに出かけても彼のソロには感心してしまう。
この夜は風邪のため重い頭でアルコールも入れずに音楽を追っているとそれでも軽い酩酊状態となりアルコールも要らないほどの彼らの音楽は私の気分を広範な音の地平で俯瞰から下降とさまざまな速度で飛翔させてくれ、夜中過ぎの演奏後、クリスマスの飾りの明かりが灯った運河沿いにに送り出されたときには滑らかで暖かいトランペットとサックスの絡み合いの音が一瞬か二瞬間、今の時期にちなんでそうしたのかクリスマスキャロルのように響いたことを思い出した。
Sun. 20 Dec. 2008 at De Burcht in Leiden, The Netherlands
Michael Moore (as, cl, bas cl)
Eric Vloeimans (tp)
Harman Fraanje (p)
Clemens van der Veen (b)
Owen Hart jr. (ds)
Michae Moore は1954年カリフォルニア生まれ、幼少の頃からクラリネットを学びボストンのコンセルバトワールでジャッキー・バイヤード、ギュンター・シュラー、ジョージ・ラッセル等に師事し、1977年に卒業後1982年以来アムステルダムに拠を置いて活動しているアルトサックス、クラリネット、バスクラリネットを概ね得意とする演奏家であり ICP(Instant Composers Pool) のメンバーとしてだけではなく様々なジャンルの音楽家たちと多種のプロジェクトを進めているマルチリード奏者である。
86年以来彼はオランダ内外で様々なジャズの賞を受け、中でもダウンビート誌批評家の投票ではクラリネット部門で2000年から連続して何回か第一位として認められている。
私はこの日、風邪のため頭が重く会場では咳込み迷惑を掛けない様にとのど飴を用意して自転車を走らせた。 フリー・インプロヴィゼーション系のジャズコンサートには町のジャズ同好会主催の演奏会ではせいぜい50人ぐらいかと高をくくって入ってみれば中ぐらいの会議室然としたスペースに軽く100人は入っていてびっくりしたし、開演時間を間違えて遅れてドアを開けて入ったときには2曲目が始まったところだと言われ暗い会場の端にあった椅子をよせて舞台の横に落ち着いた。
先週家に届いたオランダジャズ専門誌では恒例の年末に、オランダ音楽関係者、批評家、コラムニスト20人ほどにアンケートで幾つか質問をした中で、今年の収穫としてその一人が今年一番のアルバムにこの人のレーベル、ramboy から25番目発売の Fragile を挙げておりそれには私も異存なくそのアルバムをこのコンサートの前にまた聴いておこうと捜したのだがなぜか見つからない。 このアルバムのピアノはこの日の Fraanje で、この人はこの何年か折に触れ他のだれかのセッションでも弾いいるのに接することがありその抒情性の高さにいつも感心するのだが、ドッビュシー、ラベルあたりのトーンを思わせ自分のピアノに配分する具合がなんともいえないくらい心地よいのだ。
この日のトランペット、 Eric Vloeimans、 ヨーロピアンピアノトリオのMarc van Roon が加わったアルバム ramboy nr. 22、 06年発売のアルバム、 Osiris も私の好きなアルバムなのだがこの日はその中からMooreの筆になる佳曲、Ishi も演奏された。 それを弾く Fraanje のピアノの解釈にはより一層の親和感を持つ。
演目には自作の Whistle Blower, Brazilian Tune, Ishi, Fiets in Orstrijk, What is to do, Meager Harvest, などに加えて Jacki Byard の Blues、 O. Coleman のものが載せられ、それぞれアルトサックス、クラリネット、バスクラリネットで演奏された。
私はオランダの各地の ICP をはじめフリー、インプロヴィゼーション系のコンサートで多くのミューシシャンたちが様々な組み合わせでセッションをするのに立ち会って、自分が好きな楽器のアルトサックスがあると聴いているうちに Michael Moore がそこにいて耳が自然とひきつけられ、その豊かな音楽性に惹かれるようになり、Michael Moore の名前がそれらのグループのメンバーの中にあると出かけるようにしている。 彼の地味な人格は音楽では深みとなって現れるようでどのコンサートに出かけても彼のソロには感心してしまう。
この夜は風邪のため重い頭でアルコールも入れずに音楽を追っているとそれでも軽い酩酊状態となりアルコールも要らないほどの彼らの音楽は私の気分を広範な音の地平で俯瞰から下降とさまざまな速度で飛翔させてくれ、夜中過ぎの演奏後、クリスマスの飾りの明かりが灯った運河沿いにに送り出されたときには滑らかで暖かいトランペットとサックスの絡み合いの音が一瞬か二瞬間、今の時期にちなんでそうしたのかクリスマスキャロルのように響いたことを思い出した。
Paul van Kemenade at BIMHUIS
Paul van Kemenade with Eric Vloeimans, Wiro Mahieu, Harman Fraanje, Michiel Braam, Pieter Bast, Louk Boudestijn, Rein Godefroy
Sat. 27 Dec. 2008 at BIMHUIS in Amsterdam
Paul van Kemenade (as)
Eric Vloeimans (tp)
Wiro Mahie (b, el. b)
Harman Fraanje (p 1)
Michiel Braam (p 2)
Pieter Bast (ds)
Louk Boudestijn (tb)
Rein Godfroy (Fender Rhodes 3)
1st Set
1) Nyumbani Kwetu (H Fraanje)
2) Goodby Welcome (P v K)
3) Two Horns and a bass (P v K)
4) Same to earth, same place (P v K)
5) What are you sinking about (P v K)
6) In a continental mood (P v K)
2nd Set
7) Straight and stride, A Tune for N (P v K)
8) Coolmen komen (P v K)
9) Onmensheid ? (P v K)
10) Altijd herfst (always autumn) (P v K)
11) Dat is nog steeds (It still is) (P v K)
Paul vanKemenade の事は3年前のコンサートから始めて下のように記している。
http://blogs.yahoo.co.jp/vogelpoepjp/17863675.html
http://blogs.yahoo.co.jp/vogelpoepjp/50948378.html
この宵のプログラムはDVDとCDを二枚収めた新アルバムのお披露目コンサートだ。
Paul van Kemenade / Two Horns And A Bass, Duos-Trios-Quintets / Buma/Stemra en STEMRA KEMO 08
また自分が主になってこの何年も主催する自分の町 Tilburg での、ジャーミッシュの映画「Stranger Than Paradice]をもじったのか「分裂症より奇妙な」という名のジャズフェスティバルを今年も開幕してCD/DVDのお披露目をしてからの今宵の舞台だったのだ。
この日も一番前の座席に荷物を置いて場内のCDコーナーのおばさんが店を開いているときに話をしているところへ25枚づつ入った箱を2つ抱えてきたこの日の主役が値段をどうするかな、と言いながらもおばさんのとり分もあるからなあ、まあ16ユーロだなと言い、その箱をバリバリと開け湯気が立つようなのを先ず私も一つ買ったのだった。 オランダ語ではこういうのをパン屋で焼けたものが熱いまま売れていく、というような表現をするのだが実際そんな売れ行きだった。 そうしてバーで口に針金細工で開閉自由の栓が出来るようになっているビン入りのビールを待っている間、知人達と立ち話をしているうちにホールも立ち見がでるほどの盛況になっていた。
ここのスペースが小さすぎるようです。 続きは下記のサイトをご参照ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/vogelpoepjp/57232748.html
Paul van Kemenade with Eric Vloeimans, Wiro Mahieu, Harman Fraanje, Michiel Braam, Pieter Bast, Louk Boudestijn, Rein Godefroy
Sat. 27 Dec. 2008 at BIMHUIS in Amsterdam
Paul van Kemenade (as)
Eric Vloeimans (tp)
Wiro Mahie (b, el. b)
Harman Fraanje (p 1)
Michiel Braam (p 2)
Pieter Bast (ds)
Louk Boudestijn (tb)
Rein Godfroy (Fender Rhodes 3)
1st Set
1) Nyumbani Kwetu (H Fraanje)
2) Goodby Welcome (P v K)
3) Two Horns and a bass (P v K)
4) Same to earth, same place (P v K)
5) What are you sinking about (P v K)
6) In a continental mood (P v K)
2nd Set
7) Straight and stride, A Tune for N (P v K)
8) Coolmen komen (P v K)
9) Onmensheid ? (P v K)
10) Altijd herfst (always autumn) (P v K)
11) Dat is nog steeds (It still is) (P v K)
Paul vanKemenade の事は3年前のコンサートから始めて下のように記している。
http://blogs.yahoo.co.jp/vogelpoepjp/17863675.html
http://blogs.yahoo.co.jp/vogelpoepjp/50948378.html
この宵のプログラムはDVDとCDを二枚収めた新アルバムのお披露目コンサートだ。
Paul van Kemenade / Two Horns And A Bass, Duos-Trios-Quintets / Buma/Stemra en STEMRA KEMO 08
また自分が主になってこの何年も主催する自分の町 Tilburg での、ジャーミッシュの映画「Stranger Than Paradice]をもじったのか「分裂症より奇妙な」という名のジャズフェスティバルを今年も開幕してCD/DVDのお披露目をしてからの今宵の舞台だったのだ。
この日も一番前の座席に荷物を置いて場内のCDコーナーのおばさんが店を開いているときに話をしているところへ25枚づつ入った箱を2つ抱えてきたこの日の主役が値段をどうするかな、と言いながらもおばさんのとり分もあるからなあ、まあ16ユーロだなと言い、その箱をバリバリと開け湯気が立つようなのを先ず私も一つ買ったのだった。 オランダ語ではこういうのをパン屋で焼けたものが熱いまま売れていく、というような表現をするのだが実際そんな売れ行きだった。 そうしてバーで口に針金細工で開閉自由の栓が出来るようになっているビン入りのビールを待っている間、知人達と立ち話をしているうちにホールも立ち見がでるほどの盛況になっていた。
ここのスペースが小さすぎるようです。 続きは下記のサイトをご参照ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/vogelpoepjp/57232748.html
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
Europe Free Jazz 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
Europe Free Jazzのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37865人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90064人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人