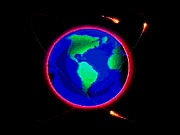お正月の読書です。つらつらと・・・・冷酒を飲みながら。
ノーベル賞は2001年が100年目だったんですね。
この本は個別の理論はほとんど語らず、受賞者の創造的エネルギーはどこからくるのか?というテーマでかかれています。
前書きから
前書きから「ノーベル(博物館)は「二つの文化」つまり自然科学と人文科学の間で永年求められてきた架け橋をなろう。」
http://
目 次
-------------------------------------------------------------------------
Part I
まえがき
序 言
アルフレッド・ノーベルとその時代
ノーベル賞の選考と授賞の制度
個人の創造性
マリー・キュリー
サミュエル・ベケット
ダライ・ラマ
アマルティア・セン
ボリス・パステルナーク
ライナス・ポーリング
アハメド・ズヴェイル
ヴェルナー・フォルスマン
バーバラ・マクリントック
ネリー・ザックス
アウン・サン・スー・チー
川端康成
ダーグ・ハマーショルド
湯川秀樹
アーネスト・ヘミングウェイ
アイザック・バシェヴィス・
シンガー
ネルソン・マンデラ
金 大中
マックス・ペルーツ
ロジャー・スペリー
フリチョフ・ナンセン
アウグスト・クローグ
リチャード・ファインマン
ラビンドラナート・タゴール
セルマ・ラーゲレーヴ
チャールズ・タウンズ
ライナス・ポーリング
エルヴィン・シュレーディンガー
アンリ・デュナン
アレクサンダー・フレミング
ヴィルヘルム・レントゲン
ペイトン・ラウス
イレーヌ・ジョリオ・キュリーと
フレデリック-ジョリ
ヨシフ・ブロツキー
ジェーン・アダムズ
C. T. R. ウィルソン
アーネ・ティセーリウス
マーティン・ルーサー・
キング・ジュニア
サンティアゴ・ラモン・
イ・カハール
ウォーレ・ショインカ
ウィリアム・バトラー・イェイツ
ジョージ・ド・へヴェシー
ピョートル・カピッツァ
フランシス・クリックと
ジェームズ・D. ワトソン
創造性を生む環境
シャンティニケタン
ブダペスト
コペンハーゲン
コールド・スプリング・ハーバー
バーゼル免疫学研究所
パスツール研究所
CERN(欧州共同素粒子原子核研究機構)
シカゴ経済学派
バークリー
ケンブリッジ
パ リ
東 京
ウィーン
ソルヴェイ会議
ICBL(地雷禁止国際キャンペーン)
Part II
コラム:2001年授賞式の印象
日本展によせて
湯川秀樹
朝永振一郎
川端康成
佐藤栄作
江崎玲於奈
福井謙一
利根川進
大江健三郎
白川英樹
野依良治
湯川秀樹と朝永振一郎の足跡
日本のノーベル賞候補
長岡半太郎の推薦状
ノーベル賞受賞者リスト
参考文献
出 典
人名索引
増補版付録
小柴昌俊
田中耕一
ノーベル賞は2001年が100年目だったんですね。
この本は個別の理論はほとんど語らず、受賞者の創造的エネルギーはどこからくるのか?というテーマでかかれています。
前書きから
前書きから「ノーベル(博物館)は「二つの文化」つまり自然科学と人文科学の間で永年求められてきた架け橋をなろう。」
http://
目 次
-------------------------------------------------------------------------
Part I
まえがき
序 言
アルフレッド・ノーベルとその時代
ノーベル賞の選考と授賞の制度
個人の創造性
マリー・キュリー
サミュエル・ベケット
ダライ・ラマ
アマルティア・セン
ボリス・パステルナーク
ライナス・ポーリング
アハメド・ズヴェイル
ヴェルナー・フォルスマン
バーバラ・マクリントック
ネリー・ザックス
アウン・サン・スー・チー
川端康成
ダーグ・ハマーショルド
湯川秀樹
アーネスト・ヘミングウェイ
アイザック・バシェヴィス・
シンガー
ネルソン・マンデラ
金 大中
マックス・ペルーツ
ロジャー・スペリー
フリチョフ・ナンセン
アウグスト・クローグ
リチャード・ファインマン
ラビンドラナート・タゴール
セルマ・ラーゲレーヴ
チャールズ・タウンズ
ライナス・ポーリング
エルヴィン・シュレーディンガー
アンリ・デュナン
アレクサンダー・フレミング
ヴィルヘルム・レントゲン
ペイトン・ラウス
イレーヌ・ジョリオ・キュリーと
フレデリック-ジョリ
ヨシフ・ブロツキー
ジェーン・アダムズ
C. T. R. ウィルソン
アーネ・ティセーリウス
マーティン・ルーサー・
キング・ジュニア
サンティアゴ・ラモン・
イ・カハール
ウォーレ・ショインカ
ウィリアム・バトラー・イェイツ
ジョージ・ド・へヴェシー
ピョートル・カピッツァ
フランシス・クリックと
ジェームズ・D. ワトソン
創造性を生む環境
シャンティニケタン
ブダペスト
コペンハーゲン
コールド・スプリング・ハーバー
バーゼル免疫学研究所
パスツール研究所
CERN(欧州共同素粒子原子核研究機構)
シカゴ経済学派
バークリー
ケンブリッジ
パ リ
東 京
ウィーン
ソルヴェイ会議
ICBL(地雷禁止国際キャンペーン)
Part II
コラム:2001年授賞式の印象
日本展によせて
湯川秀樹
朝永振一郎
川端康成
佐藤栄作
江崎玲於奈
福井謙一
利根川進
大江健三郎
白川英樹
野依良治
湯川秀樹と朝永振一郎の足跡
日本のノーベル賞候補
長岡半太郎の推薦状
ノーベル賞受賞者リスト
参考文献
出 典
人名索引
増補版付録
小柴昌俊
田中耕一
|
|
|
|
コメント(26)
『流れに抗して』
マリー・キュリー
わが道を行くというのは、ひとつの才能といえよう。創造的な人間の特徴である。
従来研究室の壁の中に閉じこもり、世界の出来事には、関心を示さなかったをいう通説があるが、彼女は、研究成果が実用に供され、医療や産業において利用されるような配慮を怠らなかった。
科学研究は社会に貢献するという理想主義的な信念に基いてのことであった。
-------------------------------------------------------------------
受賞年: 1903年(夫ピエールと)
受賞部門: ノーベル物理学賞
受賞理由: 放射能の研究
受賞年: 1911年
受賞部門: ノーベル化学賞
受賞理由: ラジウムおよびポロニウムの発見とラジウムの性質およびその化合物の研究
マリー・キュリー
わが道を行くというのは、ひとつの才能といえよう。創造的な人間の特徴である。
従来研究室の壁の中に閉じこもり、世界の出来事には、関心を示さなかったをいう通説があるが、彼女は、研究成果が実用に供され、医療や産業において利用されるような配慮を怠らなかった。
科学研究は社会に貢献するという理想主義的な信念に基いてのことであった。
-------------------------------------------------------------------
受賞年: 1903年(夫ピエールと)
受賞部門: ノーベル物理学賞
受賞理由: 放射能の研究
受賞年: 1911年
受賞部門: ノーベル化学賞
受賞理由: ラジウムおよびポロニウムの発見とラジウムの性質およびその化合物の研究
『さまざまな視線』
アマルティア・セン
センの人生を貧者の生活を改善したいという強い意志が黄金の糸のように貫いている。
彼は子どもの頃に住んでいたベンガル地方の数百万の餓死を目撃したが、中産階級の彼の家は、食料不足になったことがなかった。飢饉は貧しい階層のみ直撃したのである。実際には食料があるのに何故、飢饉が発生したのか?これが彼を貧困とはなにか?社会資源の分配はどうなっているのか?という問題の研究に向かわせた。
彼の処方箋は、「貧困であるかどうかは、一人一人の人間が、自分の生きる状況を改善する機会をもっているかどうかによる。そこで重要に成ってくるのは、経済だけではなく、健康と教育である。」とした。
それまでの経済学の枠を彼は超えた。
経済学=倫理学なのである。
-----------------------------------------------------------------------
受賞年: 1998年
受賞部門: ノーベル経済学賞
受賞理由: 厚生経済学への貢献を称えて
アマルティア・セン
センの人生を貧者の生活を改善したいという強い意志が黄金の糸のように貫いている。
彼は子どもの頃に住んでいたベンガル地方の数百万の餓死を目撃したが、中産階級の彼の家は、食料不足になったことがなかった。飢饉は貧しい階層のみ直撃したのである。実際には食料があるのに何故、飢饉が発生したのか?これが彼を貧困とはなにか?社会資源の分配はどうなっているのか?という問題の研究に向かわせた。
彼の処方箋は、「貧困であるかどうかは、一人一人の人間が、自分の生きる状況を改善する機会をもっているかどうかによる。そこで重要に成ってくるのは、経済だけではなく、健康と教育である。」とした。
それまでの経済学の枠を彼は超えた。
経済学=倫理学なのである。
-----------------------------------------------------------------------
受賞年: 1998年
受賞部門: ノーベル経済学賞
受賞理由: 厚生経済学への貢献を称えて
『怒りと反乱』
ライナス・ポーリング
広島に原爆が落ちたときに彼の活動は始まった。
核開発反対の署名運動をしたり、デモをしたり。
彼の創造は、怒りが原点にあり、反乱にむかったのだ。
注目したいのは、彼がノーベル化学賞をとっている科学者だということだ。
そして、8年後平和賞も受賞する。
2つの文化を成し遂げた人。
トレードマークのベレー帽に生き方のスタイルがあわられているようだ。
-----------------------------------------------------------------------
受賞年: 1954年
受賞部門: ノーベル化学賞
受賞理由: 化学結合の本性、ならびに複雑な分子の構造研究
受賞年: 1962年
受賞部門: ノーベル平和賞
受賞理由: 核兵器に対する反対運動
ライナス・ポーリング
広島に原爆が落ちたときに彼の活動は始まった。
核開発反対の署名運動をしたり、デモをしたり。
彼の創造は、怒りが原点にあり、反乱にむかったのだ。
注目したいのは、彼がノーベル化学賞をとっている科学者だということだ。
そして、8年後平和賞も受賞する。
2つの文化を成し遂げた人。
トレードマークのベレー帽に生き方のスタイルがあわられているようだ。
-----------------------------------------------------------------------
受賞年: 1954年
受賞部門: ノーベル化学賞
受賞理由: 化学結合の本性、ならびに複雑な分子の構造研究
受賞年: 1962年
受賞部門: ノーベル平和賞
受賞理由: 核兵器に対する反対運動
『発見への情熱』
アハメド・ズヴェイル
情熱は創造への基本的な種の1つだ。
こうした情熱はどこから来るのだろう?
彼は、レーザーを用いて、極端に短いシャッター時間で全ての物質を撮影しようとした。
彼は、宇宙の全ての現象について、美しく簡潔な解説を加えることができるという思いを持ち続けていた。
。ノーベル賞受賞記念講演では「科学の家族」に言及sじた。こうして知識が地球上に広がっていくことが、進歩・統合・楽観主義へのカギであると語った。
ひとつは美への感性、それから、善への意志があるから、それ故に真のツールとしての科学に情熱を注げるようだ。
------------------------------------------------------------------------
受賞年: 1999年
受賞部門: ノーベル化学賞
アハメド・ズヴェイル
情熱は創造への基本的な種の1つだ。
こうした情熱はどこから来るのだろう?
彼は、レーザーを用いて、極端に短いシャッター時間で全ての物質を撮影しようとした。
彼は、宇宙の全ての現象について、美しく簡潔な解説を加えることができるという思いを持ち続けていた。
。ノーベル賞受賞記念講演では「科学の家族」に言及sじた。こうして知識が地球上に広がっていくことが、進歩・統合・楽観主義へのカギであると語った。
ひとつは美への感性、それから、善への意志があるから、それ故に真のツールとしての科学に情熱を注げるようだ。
------------------------------------------------------------------------
受賞年: 1999年
受賞部門: ノーベル化学賞
『危険な好奇心』
ヴェルナー・フォルスマン
子供のような好奇心も創造の種になることがある。しかし・・・・
心臓にカテーテルを通そうと勤務していた病院の上司に相談したが、患者をッ実験にできないといわれ、自分を実験することを進言したが、これも禁止された。
しかし、1929年、彼は腕を切開し、自身の心臓の右心房に尿カテーテルを通した。その、自ら放射線医学の部署まで階段を降りて行き、レントゲン写真を撮って心臓にカテーテルが入っていることを確認し、写真を発表した。
医学会の大御所もこの実験が科学的に意義のあることを認めたが、「ここはサーカスではない」という声明とともに彼を解雇した。
信用できないばかりか、命を軽んじる危険な人間というレッテルを貼られたのだ。
単なる好奇心でここまでは出来ないだろう。
彼は、この実験が医学にどれだけ貢献するか、高次元の意志に支えられ、緻密な分析と判断をしていたのだ。
-----------------------------------------------------------------------
受賞年: 1956年
受賞部門: ノーベル生理学・医学賞
受賞理由: 心臓カテーテル法に関する発見、および血液循環系に生ずる病理学上の変化関する発見
ヴェルナー・フォルスマン
子供のような好奇心も創造の種になることがある。しかし・・・・
心臓にカテーテルを通そうと勤務していた病院の上司に相談したが、患者をッ実験にできないといわれ、自分を実験することを進言したが、これも禁止された。
しかし、1929年、彼は腕を切開し、自身の心臓の右心房に尿カテーテルを通した。その、自ら放射線医学の部署まで階段を降りて行き、レントゲン写真を撮って心臓にカテーテルが入っていることを確認し、写真を発表した。
医学会の大御所もこの実験が科学的に意義のあることを認めたが、「ここはサーカスではない」という声明とともに彼を解雇した。
信用できないばかりか、命を軽んじる危険な人間というレッテルを貼られたのだ。
単なる好奇心でここまでは出来ないだろう。
彼は、この実験が医学にどれだけ貢献するか、高次元の意志に支えられ、緻密な分析と判断をしていたのだ。
-----------------------------------------------------------------------
受賞年: 1956年
受賞部門: ノーベル生理学・医学賞
受賞理由: 心臓カテーテル法に関する発見、および血液循環系に生ずる病理学上の変化関する発見
『洞察力とひたむきさ』
バーバラ・マクリントック
彼女はインスピレーションを得たのは、トウモロコシ畑の中だった。自分が染色体の間を歩き回りながらあたりを眺めているのだと感じた。
遺伝の実験をするのには、分裂が早い微生物でおこなうのが常識だ。しかし彼女は年2回の収穫しかできない、トウモロコシでのを選んだのだ。しかしバーバラにとってはこれは利点だった、じっくり観測し、深い理解を得るための時間をえることができたからである。
彼女の才能は心からのひたむきさと洞察力にあった。
やがて、1940年トランスポゾンを発見。しかし、時代が早すぎた。受賞は、1983年。
81才と高齢でのノーベル賞受賞となったが、その一報を聞いたマクリントックは「まあ!」と一言つぶやいていつもの様にトウモロコシ畑に帰って行ったという。
彼女がそこまで先を読むことができたのは何故だろう?
曰く「研究材料が何を語ろうとしているのかを聞く」忍耐力と時間を持ち、目の前にあるものに対して開かれた態度と獲らなければないと語っている。
もっとも大切なのは、生命に対しての畏敬の念を持つことであるとこを忘れてはならないのである。
------------------------------------------------------------------------
受賞年: 1983年
受賞部門: ノーベル生理学・医学賞
受賞理由: 可動遺伝因子の発見
バーバラ・マクリントック
彼女はインスピレーションを得たのは、トウモロコシ畑の中だった。自分が染色体の間を歩き回りながらあたりを眺めているのだと感じた。
遺伝の実験をするのには、分裂が早い微生物でおこなうのが常識だ。しかし彼女は年2回の収穫しかできない、トウモロコシでのを選んだのだ。しかしバーバラにとってはこれは利点だった、じっくり観測し、深い理解を得るための時間をえることができたからである。
彼女の才能は心からのひたむきさと洞察力にあった。
やがて、1940年トランスポゾンを発見。しかし、時代が早すぎた。受賞は、1983年。
81才と高齢でのノーベル賞受賞となったが、その一報を聞いたマクリントックは「まあ!」と一言つぶやいていつもの様にトウモロコシ畑に帰って行ったという。
彼女がそこまで先を読むことができたのは何故だろう?
曰く「研究材料が何を語ろうとしているのかを聞く」忍耐力と時間を持ち、目の前にあるものに対して開かれた態度と獲らなければないと語っている。
もっとも大切なのは、生命に対しての畏敬の念を持つことであるとこを忘れてはならないのである。
------------------------------------------------------------------------
受賞年: 1983年
受賞部門: ノーベル生理学・医学賞
受賞理由: 可動遺伝因子の発見
『安心と痛み』
ネリー・ザックス
ナチス・ドイツによる迫害経験からユダヤ人の悲嘆の代弁者となった。
あの悲惨な状況の下、どうして創造力を維持できたのだろう?
単なる告発ではない。彼女が愛した人々とユダヤ人の運命が彼女の源泉。
空間的な調べにおいて、ときに具体的な物へのまなざしがあり、日常の小さな物事から着想を得ていたことをうかがわせる。
スピノザ研究家(H.H)
おまえは読み、片手に貝殻を持っていた。
夕ぐれがやさしい別れのばらいろとともにきた。
おまえの部屋は永遠と知己となり、
音楽は古びたオルゴールの箱に鳴りそめた。
燭台は夕のひかりに燃えていた。
おまえははるかなる祝福を受けて燃えた。
かしわの木が祖先の社からといきを送り
過ぎ去った存在が邂逅を祝っていた。
(生野幸吉訳)
---------------------------------------------------------------------
受賞年: 1966年
受賞部門: ノーベル文学賞
ネリー・ザックス
ナチス・ドイツによる迫害経験からユダヤ人の悲嘆の代弁者となった。
あの悲惨な状況の下、どうして創造力を維持できたのだろう?
単なる告発ではない。彼女が愛した人々とユダヤ人の運命が彼女の源泉。
空間的な調べにおいて、ときに具体的な物へのまなざしがあり、日常の小さな物事から着想を得ていたことをうかがわせる。
スピノザ研究家(H.H)
おまえは読み、片手に貝殻を持っていた。
夕ぐれがやさしい別れのばらいろとともにきた。
おまえの部屋は永遠と知己となり、
音楽は古びたオルゴールの箱に鳴りそめた。
燭台は夕のひかりに燃えていた。
おまえははるかなる祝福を受けて燃えた。
かしわの木が祖先の社からといきを送り
過ぎ去った存在が邂逅を祝っていた。
(生野幸吉訳)
---------------------------------------------------------------------
受賞年: 1966年
受賞部門: ノーベル文学賞
『献身と自己犠牲』
アウン・サン・スー・チー
ビルマの民主主義政治家(ミャンマーは軍事政権下の国名なので、あえてビルマと言わせてもらおう)
偉大な成果を達成するためには、目的に向けた大きな献身を必要とすることがある。
1990年総選挙で民主が勝利したにもかかわらず、軍事政権は譲らなかった。
それに抗い、今は、軟禁状態にあるが、家族の死に目にもあえずに、民主のために自己犠牲を献身している。
目的のために死すことも、また創造的喜びなのだ。
-------------------------------------------------------------------------
受賞: ノーベル平和賞(1991年)
アウン・サン・スー・チー
ビルマの民主主義政治家(ミャンマーは軍事政権下の国名なので、あえてビルマと言わせてもらおう)
偉大な成果を達成するためには、目的に向けた大きな献身を必要とすることがある。
1990年総選挙で民主が勝利したにもかかわらず、軍事政権は譲らなかった。
それに抗い、今は、軟禁状態にあるが、家族の死に目にもあえずに、民主のために自己犠牲を献身している。
目的のために死すことも、また創造的喜びなのだ。
-------------------------------------------------------------------------
受賞: ノーベル平和賞(1991年)
『言葉の中の空虚』
川端康成
川端は、別段政治運動をするでもなく、そうした主張を作品に織り込んだこともほぼない。西洋と日本の文学を融合させたことが評価されたのでもない。
川端の審美眼は、純粋で簡素な美にある。
「墨絵の真髄は、空間、省略、描かれていないものにある」と評し、
自身の作品も真髄は行間。おのずと短編中心となる。
生き方とその作品は、見事にシンクロし高い質が生まれる。
それは、あたかも一枚の絵なのだ。
------------------------------------------------------------------------
受賞年: 1968年
受賞部門: ノーベル文学賞
川端康成
川端は、別段政治運動をするでもなく、そうした主張を作品に織り込んだこともほぼない。西洋と日本の文学を融合させたことが評価されたのでもない。
川端の審美眼は、純粋で簡素な美にある。
「墨絵の真髄は、空間、省略、描かれていないものにある」と評し、
自身の作品も真髄は行間。おのずと短編中心となる。
生き方とその作品は、見事にシンクロし高い質が生まれる。
それは、あたかも一枚の絵なのだ。
------------------------------------------------------------------------
受賞年: 1968年
受賞部門: ノーベル文学賞
『孤独と影響』
湯川秀樹
「わたしの小さな世界の窓は、科学の園にだけ向かって開かれていたが、その窓からは、充分な光が差し込んでいた」
湯川の創造性の特徴は、孤独と外界からの影響の相互作用によってかたち作られたものである。
彼の孤独性は、自伝の中でも描いているが、父親との確執があるらしい。
それと京都独特のうなぎの寝床(町屋)は独特。その最深層部にいると、世間と完全に隔絶した時間が経過する。こうした環境が彼の孤独性を形成したようだ。
唯一開かれていた窓は、ヨーロッパで新しい物理学を学んでいた日本人。
彼は、これをおそらく町屋の最深層部にこもるくらいに、考えぬいたのだろう。
-----------------------------------------------------------------------
受賞年: 1949年
受賞部門: ノーベル物理学賞
受賞理由: 陽子と中性子との間に作用する核力を媒介するものとして中間子の存在を予想
*写真は湯川が論文をいれていた封筒。
湯川秀樹
「わたしの小さな世界の窓は、科学の園にだけ向かって開かれていたが、その窓からは、充分な光が差し込んでいた」
湯川の創造性の特徴は、孤独と外界からの影響の相互作用によってかたち作られたものである。
彼の孤独性は、自伝の中でも描いているが、父親との確執があるらしい。
それと京都独特のうなぎの寝床(町屋)は独特。その最深層部にいると、世間と完全に隔絶した時間が経過する。こうした環境が彼の孤独性を形成したようだ。
唯一開かれていた窓は、ヨーロッパで新しい物理学を学んでいた日本人。
彼は、これをおそらく町屋の最深層部にこもるくらいに、考えぬいたのだろう。
-----------------------------------------------------------------------
受賞年: 1949年
受賞部門: ノーベル物理学賞
受賞理由: 陽子と中性子との間に作用する核力を媒介するものとして中間子の存在を予想
*写真は湯川が論文をいれていた封筒。
『日課をこなす』
アーネスト・ヘミングウェイ
「ものを書くことは、最善の場合でも孤独な営みだ。文筆家の団体に入っても、書いている物の質がよくなるかは疑問だ。大衆の前にでると有名にはなるが作品の出来は悪くなる。作家の仕事は一人でするもので、もし優れた作家であれば、毎日、永遠かその欠如かに向かい合わなければならないのだ。
本当の作家ならば毎日の一つ一つの仕事が手の届いていないものに到達するために新たな出発でなければならない。」
かつて軍人でその経験を生かした行動的な作品、闘牛や、陽気な仲間とレストランやバーで過ごすことも多い彼のイメージと言葉のギャップを感じる人もいるだろう。
ヘミングウェイは精力的な読書家でもあった。一日に三冊を読むことができ、およそ6種の新聞と20冊の雑誌を読んでいた。
そして書くという仕事を辛抱強くこなす人間で、序章だけで40回も50回も書き直したことがあった。
彼は作品にかかるとき、まず鉛筆で書き始める。タイプライターは、会話文のうなところにしかつかわない。そして一日の終わりに修正をいれた。
そして一日の仕事の単語数を表に書き込み壁に貼った。
釣りに行った時など、その前の単語数がおおくなるっていた。
仕事が創造的にできるのは、6時間以内と決めそれそれ以上はやらなかった。
筆がうまく進んでいるうちにやめると、書けなくなるという危険を避けることができた。次の日まで潜在意識のうちにほおりこんでいたのである。
日課の積み重ねが偉大な創造に達したのだ。
-------------------------------------------------------------------------
受賞年: 1954年
受賞部門: ノーベル文学賞
アーネスト・ヘミングウェイ
「ものを書くことは、最善の場合でも孤独な営みだ。文筆家の団体に入っても、書いている物の質がよくなるかは疑問だ。大衆の前にでると有名にはなるが作品の出来は悪くなる。作家の仕事は一人でするもので、もし優れた作家であれば、毎日、永遠かその欠如かに向かい合わなければならないのだ。
本当の作家ならば毎日の一つ一つの仕事が手の届いていないものに到達するために新たな出発でなければならない。」
かつて軍人でその経験を生かした行動的な作品、闘牛や、陽気な仲間とレストランやバーで過ごすことも多い彼のイメージと言葉のギャップを感じる人もいるだろう。
ヘミングウェイは精力的な読書家でもあった。一日に三冊を読むことができ、およそ6種の新聞と20冊の雑誌を読んでいた。
そして書くという仕事を辛抱強くこなす人間で、序章だけで40回も50回も書き直したことがあった。
彼は作品にかかるとき、まず鉛筆で書き始める。タイプライターは、会話文のうなところにしかつかわない。そして一日の終わりに修正をいれた。
そして一日の仕事の単語数を表に書き込み壁に貼った。
釣りに行った時など、その前の単語数がおおくなるっていた。
仕事が創造的にできるのは、6時間以内と決めそれそれ以上はやらなかった。
筆がうまく進んでいるうちにやめると、書けなくなるという危険を避けることができた。次の日まで潜在意識のうちにほおりこんでいたのである。
日課の積み重ねが偉大な創造に達したのだ。
-------------------------------------------------------------------------
受賞年: 1954年
受賞部門: ノーベル文学賞
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
量子論と複雑系のパラダイム 更新情報
-
最新のアンケート
量子論と複雑系のパラダイムのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90036人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6416人
- 3位
- 独り言
- 9044人