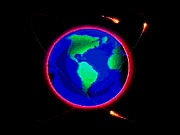光の正体にせまろうとするとき、いろいろな解釈があることに気が付く。
例えば、アインシュタインは光は粒子とし、(1905光量子説)
シュレディンガーは波だといい、(波動方程式)
ボーアは光は粒子と波動の二重性をもつとした。(相補性原理)
エヴェレット解釈では、多世界の粒子の干渉により波の様に見えるとされる(多世界解釈)
ソフィー>こんなプロの物理学者が考えても答えのでないものを私たちに考えられるの?でも基礎だけは知ってみたわ。
プラトテレス>加速運動する荷電粒子は光を放出する。これは物理の重要なpointだ。では、加速運動と同じ速度で検出器を加速させたら光は放出されないのか?
ソフィー>それは問題外だわ相対速度が重要なんでしょ?光は放出しないわ。
プラトテレス>では、静止した電子の横を検出器が通過すると光を放出する?
ソフィー>……………
プラトテレス>光を放射すると答えたいのだろう?
ソフィー>YES!
プラトテレス>でもその答えはおかしい。光を放射するかしないかの設問自体もおかしい。
ソフィー>そらきた、引っかけ問題。
プラトテレス>相対速度は実は、放射したように見えたすぎない。本当の問題は光が存在するかどうかだ。
ソフィー>そう言われると、電子は静止したままなのだから、放射しない気にもなってきたわ。
ソフィー>つまり、見えるけど、存在しない?そんなことありえるの?
プラトテレス>そう光の正体はそういうものだよ。
ソフィー>存在の有無をかけた矛盾なんて許されないわ!
プラトテレス>いや、いいんだよ、もともと力学は運動を扱う物で、存在の有無には関与しないんものなんだ。そこに有無の問題を投げかけちゃいけないんだ。
宇宙創世時のパラメータ問題に関しても同じことさ。
例えば、アインシュタインは光は粒子とし、(1905光量子説)
シュレディンガーは波だといい、(波動方程式)
ボーアは光は粒子と波動の二重性をもつとした。(相補性原理)
エヴェレット解釈では、多世界の粒子の干渉により波の様に見えるとされる(多世界解釈)
ソフィー>こんなプロの物理学者が考えても答えのでないものを私たちに考えられるの?でも基礎だけは知ってみたわ。
プラトテレス>加速運動する荷電粒子は光を放出する。これは物理の重要なpointだ。では、加速運動と同じ速度で検出器を加速させたら光は放出されないのか?
ソフィー>それは問題外だわ相対速度が重要なんでしょ?光は放出しないわ。
プラトテレス>では、静止した電子の横を検出器が通過すると光を放出する?
ソフィー>……………
プラトテレス>光を放射すると答えたいのだろう?
ソフィー>YES!
プラトテレス>でもその答えはおかしい。光を放射するかしないかの設問自体もおかしい。
ソフィー>そらきた、引っかけ問題。
プラトテレス>相対速度は実は、放射したように見えたすぎない。本当の問題は光が存在するかどうかだ。
ソフィー>そう言われると、電子は静止したままなのだから、放射しない気にもなってきたわ。
ソフィー>つまり、見えるけど、存在しない?そんなことありえるの?
プラトテレス>そう光の正体はそういうものだよ。
ソフィー>存在の有無をかけた矛盾なんて許されないわ!
プラトテレス>いや、いいんだよ、もともと力学は運動を扱う物で、存在の有無には関与しないんものなんだ。そこに有無の問題を投げかけちゃいけないんだ。
宇宙創世時のパラメータ問題に関しても同じことさ。
|
|
|
|
コメント(72)
最近「量子コンピュータ」なるものに興味を持ち、量子(光も量子と考えられています)についていろいろ調べています。
光は電磁波の一種です。
波長が長いやつほどエネルギーが低くて
電波
赤外線
光(赤に橙、黄に緑、青、藍、紫 いわゆる七色、概念的な区分けです)
紫外線
X線
の順に波長が短くてエネルギーが高いです。(かなり端折って並べました、あしからず)
この電磁波ってやつをミクロで見るとある最小単位っていうやつが見えてきます。この最小単位を量子と定義しましょう。
ここが理解しづらいところですが。
電磁波は電場と磁場のゆらぎ(乱暴ですが)です。このゆらぎを波と考えてください。波長は電場とか磁場のゆらぎの山から次の山までに走る距離と考えてください。
電場と磁場は相互に強めあっているぐらいに考えてください。
だから波といっても海の波のように連続して伝播しているというより、電場と磁場のゆらぎが光速(ゆらぎは真空中では一定の速度、光速で移動します)
それで光なのですが、レーザ装置はこの光の強さを調節できまして、光を量子として秒間千個ぐらいにしぼって送出することができます。
秒間千個ってどのくらいってことですが、光は月まで届くのに1.5秒かかります。
ということは月までの間にゆらぎが千個程度しか存在しないと想像できます。
ゆらぎを局所的に月までの間に千個程度しか存在しないような間隔で送出できるということです。
時間がないので続きは後で書きます。
光は電磁波の一種です。
波長が長いやつほどエネルギーが低くて
電波
赤外線
光(赤に橙、黄に緑、青、藍、紫 いわゆる七色、概念的な区分けです)
紫外線
X線
の順に波長が短くてエネルギーが高いです。(かなり端折って並べました、あしからず)
この電磁波ってやつをミクロで見るとある最小単位っていうやつが見えてきます。この最小単位を量子と定義しましょう。
ここが理解しづらいところですが。
電磁波は電場と磁場のゆらぎ(乱暴ですが)です。このゆらぎを波と考えてください。波長は電場とか磁場のゆらぎの山から次の山までに走る距離と考えてください。
電場と磁場は相互に強めあっているぐらいに考えてください。
だから波といっても海の波のように連続して伝播しているというより、電場と磁場のゆらぎが光速(ゆらぎは真空中では一定の速度、光速で移動します)
それで光なのですが、レーザ装置はこの光の強さを調節できまして、光を量子として秒間千個ぐらいにしぼって送出することができます。
秒間千個ってどのくらいってことですが、光は月まで届くのに1.5秒かかります。
ということは月までの間にゆらぎが千個程度しか存在しないと想像できます。
ゆらぎを局所的に月までの間に千個程度しか存在しないような間隔で送出できるということです。
時間がないので続きは後で書きます。
光の話の続きです。
光の波長ってやつは10の-7乗メートルぐらいになります。
光量子ってやつがどのぐらいの大きさかはわかりませんが、有名な2重スリットの実験について説明します。
スリットが一つだとスリットの後ろにある壁に
[ ]
こんな感じに光の帯([]で囲まれたところ)ができます。
ところが2重スリットを通すと
[||||||||]
こんな感じに干渉縞ができるという実験です。
スリットの大きさはそれぞれ10の-6乗メートルぐらい
スリットの間隔は10の-5乗メートルぐらい
にします。(波長の10倍程度)
スリットの間隔が大きすぎると干渉縞はできません。上記程度がよろしいようです。
通常の光源は波長間隔程度に連続的に光子を出します。従って連続した波のように光子がスリットに向かいます。
レーザーで秒間千個程度に調整した光子をあてたらどうなるでしょう。干渉を観測するためにレーザからみてスリットの後ろに測定器を置きます。(スリットと測定器の間には光子は1個以上存在しない状況と考えてください。なんといっても地球と月までの間に光子は千個程度の間隔で送出されるのですから)
それでも干渉縞はできるようです。
測定器には点(点っていってもどのくらいの大きさでしょう?)が点在するように測定されていきます。
測定時間が短いと(秒間千程度の光しか届かないのですから)干渉縞を認識できませんが、十分長時間測定すれば干渉縞として測定できます。
2重スリットだと光が届きにくい場所があるのです。
別々の光が波として干渉しているのではないようです。
(光のエネルギーは間違いなくマクロな視点では局所的にかたまっているといえます:光電効果から)
ではなぜ干渉縞ができるのでしょう。
ややこしくなってきました。
でももっとややこしい話があります。
光の波長ってやつは10の-7乗メートルぐらいになります。
光量子ってやつがどのぐらいの大きさかはわかりませんが、有名な2重スリットの実験について説明します。
スリットが一つだとスリットの後ろにある壁に
[ ]
こんな感じに光の帯([]で囲まれたところ)ができます。
ところが2重スリットを通すと
[||||||||]
こんな感じに干渉縞ができるという実験です。
スリットの大きさはそれぞれ10の-6乗メートルぐらい
スリットの間隔は10の-5乗メートルぐらい
にします。(波長の10倍程度)
スリットの間隔が大きすぎると干渉縞はできません。上記程度がよろしいようです。
通常の光源は波長間隔程度に連続的に光子を出します。従って連続した波のように光子がスリットに向かいます。
レーザーで秒間千個程度に調整した光子をあてたらどうなるでしょう。干渉を観測するためにレーザからみてスリットの後ろに測定器を置きます。(スリットと測定器の間には光子は1個以上存在しない状況と考えてください。なんといっても地球と月までの間に光子は千個程度の間隔で送出されるのですから)
それでも干渉縞はできるようです。
測定器には点(点っていってもどのくらいの大きさでしょう?)が点在するように測定されていきます。
測定時間が短いと(秒間千程度の光しか届かないのですから)干渉縞を認識できませんが、十分長時間測定すれば干渉縞として測定できます。
2重スリットだと光が届きにくい場所があるのです。
別々の光が波として干渉しているのではないようです。
(光のエネルギーは間違いなくマクロな視点では局所的にかたまっているといえます:光電効果から)
ではなぜ干渉縞ができるのでしょう。
ややこしくなってきました。
でももっとややこしい話があります。
>おとーたん さん
そうですエヴェレットの多世界解釈ってやつですね。
確か「タイムライン」って小説でそのような話がでてきます。
ただ量子の世界、話はややこしくて
不確定性原理ってやつがからんできます。
光子が局所的位置を持つならどちらかのスリットを通るんだろう。と思うわけです。
で、どちらのスリットを通ったか知ろうとするわけです。
どうすればいいか
偏光を使います。
光の偏光には垂直、水平、右回り、左回りってのがありまして、偏光装置には
(1)水平偏光を右回り、垂直偏光を左回りに偏光するやつと
(2)水平偏光を左回り、垂直偏光を右回りに偏光するやつ
があります。
それでスリットを通る光子の偏光を垂直か水平にしてやるんです。
例えば片方のスリットの前に(1)を
別のスリットの前に(2)を置いてやるわけです。
そうして測定器に届いた光子の偏光が右回りか左回りかわかるようにしてやります。
垂直偏光が左回りになっていれば(1)
右回りになっていれば(2)を通ったことがわかります。
水平偏光の場合その逆です。
しかし、そうして実験すると干渉縞が観測できないのです。
[||||||||||]こうならず
[__________]こうなります。
だから多世界解釈によるパラレルワールドの光子と干渉した
という考えも、どうも違うような気がします。
最も量子コンピュータってやつはこの多世界解釈を前提にしているのかなという気もしますが。
そうして、もう一つ、量子コンピュータに必要なエンタングルメントっていうやっかいな性質が確認されており、
2重スリットの実験をややこしくしてくれます。
そうですエヴェレットの多世界解釈ってやつですね。
確か「タイムライン」って小説でそのような話がでてきます。
ただ量子の世界、話はややこしくて
不確定性原理ってやつがからんできます。
光子が局所的位置を持つならどちらかのスリットを通るんだろう。と思うわけです。
で、どちらのスリットを通ったか知ろうとするわけです。
どうすればいいか
偏光を使います。
光の偏光には垂直、水平、右回り、左回りってのがありまして、偏光装置には
(1)水平偏光を右回り、垂直偏光を左回りに偏光するやつと
(2)水平偏光を左回り、垂直偏光を右回りに偏光するやつ
があります。
それでスリットを通る光子の偏光を垂直か水平にしてやるんです。
例えば片方のスリットの前に(1)を
別のスリットの前に(2)を置いてやるわけです。
そうして測定器に届いた光子の偏光が右回りか左回りかわかるようにしてやります。
垂直偏光が左回りになっていれば(1)
右回りになっていれば(2)を通ったことがわかります。
水平偏光の場合その逆です。
しかし、そうして実験すると干渉縞が観測できないのです。
[||||||||||]こうならず
[__________]こうなります。
だから多世界解釈によるパラレルワールドの光子と干渉した
という考えも、どうも違うような気がします。
最も量子コンピュータってやつはこの多世界解釈を前提にしているのかなという気もしますが。
そうして、もう一つ、量子コンピュータに必要なエンタングルメントっていうやっかいな性質が確認されており、
2重スリットの実験をややこしくしてくれます。
エンタングルメント(量子のもつれ?)
切っても切れない縁みたいなものと考えてください。
例えば、光子の場合ですが、ペアなる光子に対して片方を垂直変更にしたらもう片方が水平偏光になるという状態を作ることができます。こうして生まれた光子はエンタングルメントな状態にあります。双子の光子とでも思ってください。
この光子たちにとってのエンタングルメントとは片方の偏光を垂直にすると、もう片方が水平偏光に変わるというものです。
エンタングルメントが崩れていなければ必ずそうなります。
従って片方が垂直偏光であることがわかればもう片方は水平偏光だと考えて間違いありません。
ただし、どちらが垂直でどちらが水平かは測定しないとわかりません。
そんな光子を作る際にそれぞれの進行方向を別方向に分けます。
片方を2重スリットに、もう片方を偏光測定器に向かわせます。
2重スリットの前に例の偏光装置を置かなければ干渉縞を観測できます。
例の偏光装置を置けば干渉縞は観測できません。別の測定器に向かった光子の偏光が垂直か水平かがわかるのでスリットを通る際に光子の偏光が垂直か水平かがわかるからです。
とはいっても神がわかるだけで、われわれ観測者がひとつひとつの光子の偏光を判っているわけではないのですから不思議です。
さらに偏光測定器に向かった光子の偏光を乱す装置を偏光測定器の前に置きます。(偏光測定器を外してもいいのですが、それではあたりまえすぎるので)
すると再び干渉縞が観測されます。
スリットへ向かった光子の測定器までの距離より別の光子の偏光測定器までの距離のほうを遠くにしてやっても干渉縞が観測できるできないの結果に影響はでません。
スリットへ向かった光子の偏光がわかるようになっていて、どちらのスリットを通ったかわかる場合は干渉縞ができなくて、どちらのスリットを通ったかわからない場合は干渉縞ができる。というわけです。
スリットに向かった光子が干渉縞をつくるかつくらないかを決めているかのような動きです。
切っても切れない縁みたいなものと考えてください。
例えば、光子の場合ですが、ペアなる光子に対して片方を垂直変更にしたらもう片方が水平偏光になるという状態を作ることができます。こうして生まれた光子はエンタングルメントな状態にあります。双子の光子とでも思ってください。
この光子たちにとってのエンタングルメントとは片方の偏光を垂直にすると、もう片方が水平偏光に変わるというものです。
エンタングルメントが崩れていなければ必ずそうなります。
従って片方が垂直偏光であることがわかればもう片方は水平偏光だと考えて間違いありません。
ただし、どちらが垂直でどちらが水平かは測定しないとわかりません。
そんな光子を作る際にそれぞれの進行方向を別方向に分けます。
片方を2重スリットに、もう片方を偏光測定器に向かわせます。
2重スリットの前に例の偏光装置を置かなければ干渉縞を観測できます。
例の偏光装置を置けば干渉縞は観測できません。別の測定器に向かった光子の偏光が垂直か水平かがわかるのでスリットを通る際に光子の偏光が垂直か水平かがわかるからです。
とはいっても神がわかるだけで、われわれ観測者がひとつひとつの光子の偏光を判っているわけではないのですから不思議です。
さらに偏光測定器に向かった光子の偏光を乱す装置を偏光測定器の前に置きます。(偏光測定器を外してもいいのですが、それではあたりまえすぎるので)
すると再び干渉縞が観測されます。
スリットへ向かった光子の測定器までの距離より別の光子の偏光測定器までの距離のほうを遠くにしてやっても干渉縞が観測できるできないの結果に影響はでません。
スリットへ向かった光子の偏光がわかるようになっていて、どちらのスリットを通ったかわかる場合は干渉縞ができなくて、どちらのスリットを通ったかわからない場合は干渉縞ができる。というわけです。
スリットに向かった光子が干渉縞をつくるかつくらないかを決めているかのような動きです。
>43: 全充 さん
はじめまして。
>42 の書き込みと、この書き込みの中盤までは分かるのですが、
>さらに偏光測定器に向かった光子の偏光を乱す装置を偏光測定器の前に置きます。
<
以降の部分が、よく分かりません。
出典となった、本か、あるいは、ネット上の論文などあれば、ご紹介いただけないでしょうか。
光子は光速で動くことしか出来ないので、光子にとっては、内部での時間経過が存在せず、そのために、全く同時に、宇宙の全ての場所に存在する(もちろん、確率的に)ことになると思うので、観測者である人間には、時間的前後関係があるように見えても、光子にとっては、全ての現象は、同時に起きている。従って、距離は関係ない、ということだと思うのですが、
この解釈であっているのかどうか、今ひとつ自信が持てません。
はじめまして。
>42 の書き込みと、この書き込みの中盤までは分かるのですが、
>さらに偏光測定器に向かった光子の偏光を乱す装置を偏光測定器の前に置きます。
<
以降の部分が、よく分かりません。
出典となった、本か、あるいは、ネット上の論文などあれば、ご紹介いただけないでしょうか。
光子は光速で動くことしか出来ないので、光子にとっては、内部での時間経過が存在せず、そのために、全く同時に、宇宙の全ての場所に存在する(もちろん、確率的に)ことになると思うので、観測者である人間には、時間的前後関係があるように見えても、光子にとっては、全ての現象は、同時に起きている。従って、距離は関係ない、ということだと思うのですが、
この解釈であっているのかどうか、今ひとつ自信が持てません。
>UFO教授様
論文は、
S. P. Walborn, M. O. Terra Cunha, S. Padua, and C. H. Monken at the Universidade Federal de Minas Gerais in
Brazil. Physical Review A, (65, 033818, 2002).
http://grad.physics.sunysb.edu/~amarch/Walborn.pdf
解説もあります。 http://grad.physics.sunysb.edu/~amarch/
2002年ブラジルのミナス・ジェライス大学で行われた実験です。
私も最初「ハイゼンベルグの顕微鏡(日経BP)」を読んで、うそだろうそんな実験が成功したなんて、もっと世間が騒ぐだろうと思い、とある物理フォーラムで質問したら、上記論文がインターネットに上がっているよと教えてもらいました。
今確かめたらまだ存在していました。
どうも物理学会では「ほらね実験でも確かめられたでしょ」みたいに不思議でもなんでもないように扱われているようです。
UFO教授のおっしゃるとおり、光にとっての時間は我々の感じている時間とは別なんだなと思います。
論文は、
S. P. Walborn, M. O. Terra Cunha, S. Padua, and C. H. Monken at the Universidade Federal de Minas Gerais in
Brazil. Physical Review A, (65, 033818, 2002).
http://grad.physics.sunysb.edu/~amarch/Walborn.pdf
解説もあります。 http://grad.physics.sunysb.edu/~amarch/
2002年ブラジルのミナス・ジェライス大学で行われた実験です。
私も最初「ハイゼンベルグの顕微鏡(日経BP)」を読んで、うそだろうそんな実験が成功したなんて、もっと世間が騒ぐだろうと思い、とある物理フォーラムで質問したら、上記論文がインターネットに上がっているよと教えてもらいました。
今確かめたらまだ存在していました。
どうも物理学会では「ほらね実験でも確かめられたでしょ」みたいに不思議でもなんでもないように扱われているようです。
UFO教授のおっしゃるとおり、光にとっての時間は我々の感じている時間とは別なんだなと思います。
ちょっと横槍ですが
光子を考える上で重要なことは
光子は粒と決め付けてイメージしてはならないということです.
観測機で測定すると光子の存在確立は空間的にも時間的にも狭い範囲に限定できるので粒のように考えることができますが.
複スリット問題で扱われている光子は最初粒ではありません.
光子は空間上に広がっているとイメージしてください.
広がった光子は二つのスリットを通ることができます,そしてスクリーン上に干渉縞を作ることができるのです.
この広がりは量子力学の確立の概念から来ています.
こう言った例えは適当ではないかもしれませんが,
一m^3の立方体の形の広がりを持つ光子があったとしましょう.(本当にそんなのがあるかは知りません)
その立方体の中に光子は100%存在します.
しかし立方体を半分に切った空間の中には50%で存在します.ただ,もう片方の空間にも50%存在します.
ということができます.
また光子は時間的にも広がりを持ちます.
理想的な単色平面波は無限の空間的時間的広がりを持ちます.
このイメージは大学の物理の先生直伝ですので間違いない!
多少私の誤解が入っているかもしれませんが.
光子を考える上で重要なことは
光子は粒と決め付けてイメージしてはならないということです.
観測機で測定すると光子の存在確立は空間的にも時間的にも狭い範囲に限定できるので粒のように考えることができますが.
複スリット問題で扱われている光子は最初粒ではありません.
光子は空間上に広がっているとイメージしてください.
広がった光子は二つのスリットを通ることができます,そしてスクリーン上に干渉縞を作ることができるのです.
この広がりは量子力学の確立の概念から来ています.
こう言った例えは適当ではないかもしれませんが,
一m^3の立方体の形の広がりを持つ光子があったとしましょう.(本当にそんなのがあるかは知りません)
その立方体の中に光子は100%存在します.
しかし立方体を半分に切った空間の中には50%で存在します.ただ,もう片方の空間にも50%存在します.
ということができます.
また光子は時間的にも広がりを持ちます.
理想的な単色平面波は無限の空間的時間的広がりを持ちます.
このイメージは大学の物理の先生直伝ですので間違いない!
多少私の誤解が入っているかもしれませんが.
ブラジル、ウォルボーン博士の実験では
2重スリットの前に偏光板を置いてもスリットのある壁を通過する前の光子の偏光状態がわかっていない場合は干渉縞ができて
判っている場合は干渉縞が出来る。
という結果を示しています。
しかし確かにスリットのある壁を通り抜けた光子は
どちらのスリットをも抜けた状態と
右回りと左回りの偏光どりらの可能性も持った状態で
先の壁に到着することになりますね。
この重ね合わせの状態が生ずる干渉が壁への到着位置に対する干渉を引き起こすのですが
偏光状態関数は位置の状態関数とは変数分離できるので
偏光状態は位置の干渉に影響しないのかなと思います。
ただし非専門家の想像です。
2重スリットの前に偏光板を置いてもスリットのある壁を通過する前の光子の偏光状態がわかっていない場合は干渉縞ができて
判っている場合は干渉縞が出来る。
という結果を示しています。
しかし確かにスリットのある壁を通り抜けた光子は
どちらのスリットをも抜けた状態と
右回りと左回りの偏光どりらの可能性も持った状態で
先の壁に到着することになりますね。
この重ね合わせの状態が生ずる干渉が壁への到着位置に対する干渉を引き起こすのですが
偏光状態関数は位置の状態関数とは変数分離できるので
偏光状態は位置の干渉に影響しないのかなと思います。
ただし非専門家の想像です。
ウェバさん、をはじめとすう知的なこのコミュに集まる方に知ってほしいのです。
水は、化学的には化学式 H2O で表される水素と酸素の化合物ですけど水素2つに酸素一つの純粋な水など自然界に存在しないことは懸命な人ならおわかりでしょう。
このように自然界に存在しない「水」を作るためにわざわざ蒸留という方法を使ってまで混ざり気のない水を作らなければいけなかったのです。
水だけではなく物質はそんなに純粋ではないと僕は思うのです。
相対性理論は光と時間と重力の相対関係に注目した画期的な理論なのにどうしてその三つにもう一つ加えて人が入らないのかが僕には不思議です。
光は個人の網膜にある視細胞の桿体,錐体の働きによって暗明順応にも個体差が見られるのに必ず同じ基準で見えているのではないと思うのです。
これは光の問題ではなく光なしには人はものを視覚で認識することができないという問題がありますし、色弱、色盲、目の見えない人でも光は感じられるのことであり無理やり認識できない「素粒子」を当てはめることはないと思います。
時間の認識についても嫌な事をしていると時間は長く感じられ逆もまた然りで時間は主観の認識が決めることではなく「時計が決める」のです。
9時から5時までの勤務時間制度が出来てからどれだけの人間が早く終わらせても帰れない、遅く終わらせても帰ることが出来るという不平等を生み出したのかはこのコミュニティに集まる人ならお分かりでしょう。
最後に重力ですけど僕は重力に鍵があると思っています。
万有引力とも違う心の感じる引力を「吸引力」と呼んだりしますね。
人の心と重力の相対関係は数式では表せないと僕は考えています。
神と重力の因果関係について書くのはこのトピックスに相応しくないのでこれ以上は書きません。
素粒子を構成するさらに細かい物質を発見した学者がいたら発表するのはやめて欲しいと僕は願います。
水は、化学的には化学式 H2O で表される水素と酸素の化合物ですけど水素2つに酸素一つの純粋な水など自然界に存在しないことは懸命な人ならおわかりでしょう。
このように自然界に存在しない「水」を作るためにわざわざ蒸留という方法を使ってまで混ざり気のない水を作らなければいけなかったのです。
水だけではなく物質はそんなに純粋ではないと僕は思うのです。
相対性理論は光と時間と重力の相対関係に注目した画期的な理論なのにどうしてその三つにもう一つ加えて人が入らないのかが僕には不思議です。
光は個人の網膜にある視細胞の桿体,錐体の働きによって暗明順応にも個体差が見られるのに必ず同じ基準で見えているのではないと思うのです。
これは光の問題ではなく光なしには人はものを視覚で認識することができないという問題がありますし、色弱、色盲、目の見えない人でも光は感じられるのことであり無理やり認識できない「素粒子」を当てはめることはないと思います。
時間の認識についても嫌な事をしていると時間は長く感じられ逆もまた然りで時間は主観の認識が決めることではなく「時計が決める」のです。
9時から5時までの勤務時間制度が出来てからどれだけの人間が早く終わらせても帰れない、遅く終わらせても帰ることが出来るという不平等を生み出したのかはこのコミュニティに集まる人ならお分かりでしょう。
最後に重力ですけど僕は重力に鍵があると思っています。
万有引力とも違う心の感じる引力を「吸引力」と呼んだりしますね。
人の心と重力の相対関係は数式では表せないと僕は考えています。
神と重力の因果関係について書くのはこのトピックスに相応しくないのでこれ以上は書きません。
素粒子を構成するさらに細かい物質を発見した学者がいたら発表するのはやめて欲しいと僕は願います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
量子論と複雑系のパラダイム 更新情報
-
最新のアンケート
量子論と複雑系のパラダイムのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90024人
- 2位
- 酒好き
- 170668人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37149人