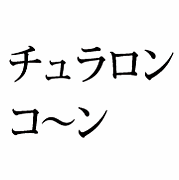|
|
|
|
コメント(49)
線引きが難しいですよね。
原語読みにしたら、中国史や韓国史を白紙に戻さなきゃいけません。。
たくさんの方が書いてらっしゃいますが、
そもそも日本語の音韻体系でしか書き表せないのですし
日本人にとってはありえない発音や、なじみのない発音もありますしね…
あんまり細かくしちゃうと、ソクラテスは正しくはソークラテースだし(苦笑)
ただ個人的には、ラテン語由来のものはぜひラテン語に則して書いてほしい!
ラテン語の音は日本語と非常に近いというのもありますが、
なにも英語にならわなくてもいいじゃないかと思うのです。
ブルータスよりはブルートゥス!
また、ヨーロッパの人名などは原語表記でこそわかる、という利点があります。
カエサルって言われたらユリウスさんしか出てこないけど、
ツァーリって言われたら「あ、雷帝ね」みたいな。
日本人にしたらジョージとゲオルクは別人だし、チャールズとカールとも別人だし、
カタカナを見ればどこの国の人かわかる。便利です。
>みきてぃさん
ニーチェの著作にもありますよね。どちらが先か知らないのですが(汗)
あれは「ツァラトゥストゥラはかく語りき」でしたか。教えられるまでわかりませんでした(笑)
原語読みにしたら、中国史や韓国史を白紙に戻さなきゃいけません。。
たくさんの方が書いてらっしゃいますが、
そもそも日本語の音韻体系でしか書き表せないのですし
日本人にとってはありえない発音や、なじみのない発音もありますしね…
あんまり細かくしちゃうと、ソクラテスは正しくはソークラテースだし(苦笑)
ただ個人的には、ラテン語由来のものはぜひラテン語に則して書いてほしい!
ラテン語の音は日本語と非常に近いというのもありますが、
なにも英語にならわなくてもいいじゃないかと思うのです。
ブルータスよりはブルートゥス!
また、ヨーロッパの人名などは原語表記でこそわかる、という利点があります。
カエサルって言われたらユリウスさんしか出てこないけど、
ツァーリって言われたら「あ、雷帝ね」みたいな。
日本人にしたらジョージとゲオルクは別人だし、チャールズとカールとも別人だし、
カタカナを見ればどこの国の人かわかる。便利です。
>みきてぃさん
ニーチェの著作にもありますよね。どちらが先か知らないのですが(汗)
あれは「ツァラトゥストゥラはかく語りき」でしたか。教えられるまでわかりませんでした(笑)
台湾のように狭いところでも、駅名の仮名書はローマ字表記で国語(マンダリン)表記に福老語表記、客家語表記などがあったりする。しかも国語表記にもピンインローマ字表記を採用してたりして(ピンイン表記はHを捲舌の記しだったりしてラテン語式の音と大きく異なる)多くの現地人は読めません。
無双さんが仰るとおり中国大陸では大きく7,8区の方言区に分けられてますが
感じの読みそのものまで違うから地名全てを普通語(マンダリンチャイニーズ)で読むのは言語破壊に等しい。しかし最近政府は北京などをBEIJINGと言う風に修正するよう世界に向かって要求し始めてますね。ホンコンがシャンガンになる日は近いのかも。
無双さんが仰るとおり中国大陸では大きく7,8区の方言区に分けられてますが
感じの読みそのものまで違うから地名全てを普通語(マンダリンチャイニーズ)で読むのは言語破壊に等しい。しかし最近政府は北京などをBEIJINGと言う風に修正するよう世界に向かって要求し始めてますね。ホンコンがシャンガンになる日は近いのかも。
こういう話には2つの点を共通の認識としておさえておく必要があると思います。
表音表記は仮名でもローマ字でもハングルでもあくまで言葉の表記であり、
発音記号表記ではないということ。あくまで言葉を表記するシステム。
したがってかな書きは日本語の、ハングルは朝鮮語の、ラマカムヘン文字は
タイ語を表記するときの方式であるという当たり前の認識。
もう一つは政治的側面があるということです。
引用の記事は削除しましたが、言語をどう表記するかという問題には
これは母語であっても母国語であっても極めてその国がどうありたいかを
為政者は考えて決めるものだから、ロシアがロシア語を旧ソビエト連邦に
強制使用させたのも、中国共産党が満州族が整理した言語を共通語にした
のも、世界に向かってペキンをベイジンと表記するように逼ってるのも、
毛沢東ですらちゃんと喋れない人工言語を全国民に広めようとしてるのも
国内の地名の発音までマンチューリアン制作ピジン漢語で統一してるのも
すべて何らかの理由があるのでしょう。
アメリカでも人名は多民族移民の国だからローマ字綴りであったとしても
人のより読み方が違うために本人にどう発音するのか確認するそうです。
新聞なんかで珍しい名前だと発音について注釈が入る。
北欧3国のデンマーク語とノルウェイ語スウェイデン語の発音と表記など
の関係を見ても面白いよ。これは政治的というよりトライブが持つ根源的
要素により例え不便であっても伝統と信じてる発音表記のシステムを変え
ることが難しいという実例だと思う。
表音表記は仮名でもローマ字でもハングルでもあくまで言葉の表記であり、
発音記号表記ではないということ。あくまで言葉を表記するシステム。
したがってかな書きは日本語の、ハングルは朝鮮語の、ラマカムヘン文字は
タイ語を表記するときの方式であるという当たり前の認識。
もう一つは政治的側面があるということです。
引用の記事は削除しましたが、言語をどう表記するかという問題には
これは母語であっても母国語であっても極めてその国がどうありたいかを
為政者は考えて決めるものだから、ロシアがロシア語を旧ソビエト連邦に
強制使用させたのも、中国共産党が満州族が整理した言語を共通語にした
のも、世界に向かってペキンをベイジンと表記するように逼ってるのも、
毛沢東ですらちゃんと喋れない人工言語を全国民に広めようとしてるのも
国内の地名の発音までマンチューリアン制作ピジン漢語で統一してるのも
すべて何らかの理由があるのでしょう。
アメリカでも人名は多民族移民の国だからローマ字綴りであったとしても
人のより読み方が違うために本人にどう発音するのか確認するそうです。
新聞なんかで珍しい名前だと発音について注釈が入る。
北欧3国のデンマーク語とノルウェイ語スウェイデン語の発音と表記など
の関係を見ても面白いよ。これは政治的というよりトライブが持つ根源的
要素により例え不便であっても伝統と信じてる発音表記のシステムを変え
ることが難しいという実例だと思う。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
私たちの愛する世界史単語 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
私たちの愛する世界史単語のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37860人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90060人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208307人