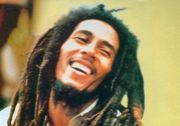ラスタ
母なる大地アフリカから強制連行され植民地支配によって政治的、経済的、文化的な自立の道を奪われた黒人奴隷たちは、自らを肯定的に捉えるために、新しいアイデンティティとそれを支える世界観を編み出した。こうして生み出されたのが数々のヨルバ系宗教である。しかしアフリカの宗教に根拠を求めない新たな信仰も生み出された。それがジャマイカで生まれたラスタファリアニズムやマルコムXやモハメッド・アリが信仰したブラック・ムスリムである。ここではラスタファリアニズム(以下ラスタ)の話をしよう。
ラスタの教えを要約するこんな具合だ。
1930年、ラス・タファリ(Ras Tafari)という人物がエチオピア帝国で皇帝の座についた。彼は即位に際してハイレ・セラシエ(Haile Selassie)を名乗った。皇帝ハイレ・セラシエは生き神「ジャー(Jah)」であり、黒人の救世主である。黒人は古代イスラエル人の末裔なのだが、黒人より劣った存在である白人の邪悪な陰謀により、ジャマイカで幽囚の生活を送っている。ジャマイカの状況は光りなき地獄・バビロンだが、エチオピアは天国だ。しかし、無敵の皇帝ハイレ・セラシエは、世界各地に誘拐されたアフリカ起源の民を故郷に戻す準備をしている。ラス・タファリの旗の下、近い将来に、黒人が世界を統治する。
荒唐無稽な教えである。しかしこれはジャマイカの下層階級の人が生きるに足る世界と歴史を構築しようとした結果うまれたものなのである。だから、ここでいわれる「ジャー」は、セラシエ帝の実像とは何の関わりもない。その証拠に、1970年代のエチオピア革命と皇帝の死は、ラスタ運動に本質的な打撃を与えなかった。
よく唱えられる「ジャー・ラスタファーライ」という言葉は「神であるセラシエ皇帝」という意味だ。ジャーの語源はキリスト教の絶対神エホバ(Jehovah)である。英語圏の賛美歌でよく使われる"God"、"Lord"、"Jesus"と同じように"Jah"はレゲエの歌詞に頻繁に登場する。
ヴードゥー教の天国は「ギニア」だがラスタたちは「天国はエチオピアにある」と考えているところがおもしろい。しかし「ギニア」にせよ「エチオピア」にせよ実在の国とは無関係の、抽象的な存在にすぎない。
ラスタの思想的ルーツとしてエチオピアニズム(旧約聖書に登場し、近代になっても植民地化されなかった黒人のキリスト教王国エチオピアをアフリカ起源の人たちの魂の故郷とみる考え方)があげられる。意外なことだがエチオピアは大航海時代のずっと前からキリスト教国家なのである。
もう一つのルーツがマーカス・ガーヴィーの「アフリカ帰還運動」である。マーカス・ガーヴィーの思想はブラック・ムスリムにも大きな影響を与えた。カーヴィーはジャマイカで生まれ、1910年代にアメリカに渡ってアフリカ帰還運動を組織し、一時は黒人大衆から絶大な支持を受けた人物である。
ラスタは旧約聖書を聖典とし、多くの者が Ethiopian Orthodox Church の信徒でもある。セラシエにせよガーヴェイにせよ、彼らは宗教的にはいずれもキリスト教徒であった。この点はヴードゥーと相通じるものがありそうだ。
黒人社会がキリスト教と対峙した時、その全面受容は白人社会への編入を意味し、完全拒否は社会的孤立を招く。宗教が黒人の団結を促し、社会改編の大きな力となるのは「キリスト教の影響を受けながら、独自の宗教観を形成した場合」である。
ラスタは「奴隷の宗教」だという従来のキリスト教を批判し、来世志向から世直しへと救済のイメージの転換。自然食や菜食主義を戒律にした。では厳しい宗教かというと全く逆である。
聖なる草「ガンジャ(ganja=マリファナ)」をガンガン吸ってハイになったり、強いカリスマ的リーダーを立ててきちんとした組織を作りたがらない傾向がある。
カリフォルニア(!)からやってきた白人の(!)人気レゲエ・バンド「ビッグ・マウンテン」は、ステージから観客にこう呼び掛けた。「私たちはラスタだ。ここにいる者はみなラスタだ。どんな肌の色でも、どんなことばをしゃべっても、ジャーの教えを理解する者はみなラスタだ。だからあなたたちは、日本中にラスタの教えを広める義務がある」 この大らかさは どうだろう。
**もっと詳しくラスタについて知りたい方は"THE DREAD LIBRARY"の中の"
FUNDAMENTALS: THE RASTAFARIANLIFESTYLE" by Michael Katz をお読みになるか、イーサクリエーションズ・オンラインショップ をお訪ねください。
ラスタ=レゲエではない
さて、「ラスタ=レゲエ」ではない、ということだが、ルーツ・レゲエ=ラスタの音楽、というふうに思われがちだ。しかし実はラスタには独自の音楽がある。それが「ナイアビンギ(nyabinghi)」だ(単にビンギ(binghi)とも呼ばれる)。もしあなたがコアなレゲエ好きなら、きっと聞き覚えがあると思う。
ナイアビンギというのは、もともとラスタの集会を指すことばだった。ラスタマンが輪になって集まり、ガンジャを吸い、一晩中ドラム叩きながら歌い(chant チャント)踊るという、宗教儀式である。
ドラムといってももちろんドラム・セットがあるのではなく、ベース、フンデ(funde)、リピーター(akete)と呼ばれる大中小の太鼓のことを指す。これをブル・ドラム(burru drum)という。このブル・ドラムのビートがナイアビンギである。
ベースは、4ビートの頭を叩き、3拍めで音を消す。フンデは、屋台骨となるビートを刻み、リピーター(アケテ)は即興でプレイする。
カウント・オシー & ザ・ミスティック・レヴェレーション・オブ・ラスタファリ(Count Ossie & The Mystic Revelation of Rastafari)やラス・マイケル & ザ・サンズ・オブ・ニガス(Ras Michael & The Sons of Negus)といった面子が、ナイアビンギ界の大物ミュージシャンだ。ラス・マイケルは、レゲエ・ミュージシャン達とコラボレイトしたことで有名になった。
ラスタの思想が多くのレゲエ・ミュージシャンに支持されたこと。そしてナイアビンギとレゲエの音楽的相性が良かったこと。この2つの理由によりレゲエとビンギはクロスオーバーしていったのである。
70年代、ナイアビンギはレゲエのアレンジに積極的に取り入れられた(90年代にもリヴァイヴァル)。ボブ・マーリーの"TIME WILL TELL"などは、典型的なナイアビンギ・スタイルである。
ナイアビンギの存在があきらかになったのは1958年のことである。それまでの数百年間、ブル(後述)のリズムは門外不出の伝統であった。ナイアビンギの太鼓の起源は、ブル、クミナ、西キングストンでのドラミングのリヴァイヴァル・スタイルの複雑な相互浸透である。
クミナの儀式とナイアビンギ
ナイアビンギの太鼓は、もともとブルとアフリカ系宗教・クミナで使われていた。
クミナの儀式には、太鼓の演奏とダンスが欠かせない。アフリカでは、太鼓はコミュニケーションの道具だ。通過儀礼や特別な行事、さらに病気のときも、クミナと太鼓が必要とされる。生贄が捧げられ、憑依現象がおこるまでダンスは続く。儀式で先祖の霊がよびだされると神聖なお告げがもたらされる。
クミナ特有のドラミングは、1930年代にキングストンに移動して、ナイアビンギのルーツとなった。
ブル・ドラミング(burru drumming)も、ナイアビンギのルーツだ。それは、まず1903年にClarendonの教区ではじめて演奏され、のちに西キングストンでも演奏された。小尖塔の破壊が多くのラスタたちをキングストンへ追いやったときに、ラスタたちはブル・ドラミングを学んだ。ブルはガーナからダンスを借用したと考えられている。
「ブル」(burru)は奴隷時代から伝わるアフリカの太鼓、ブル・ドラム(burru drum)を打つ者をさす言葉である。その多くは犯罪者だといわれ、どんどん数が減っている。ラスタは、西洋の影響をうけていない純粋なアフリカの音楽をブルから学んだのだといわれている。
ラスタとナイアビンギのなれそめ
ラスタマンにとって、そしてジャマイカの庶民音楽や伝統音楽にとって太鼓は重要な役割を果たしている。
太鼓は、アフリカ人の心臓の鼓動だ。白人はアフリカの声、心臓の鼓動を止めることができなかった。
すくなからぬ数の奴隷が脱走し、ジャマイカの奥地へ逃げこんだ。「マルーン」と呼ばれる逃亡奴隷たちである。よく知られたグループとして、Saramaka、Boni、the Maroons of the Guianasの名が挙げられる。マルーンたちは密生したジャングルと武器で自衛した。
マルーンたちの世界はアフリカン・ミュージックの宝庫であった。アフリカの習慣、そして音楽はじょうずに保存された。
太鼓は、神の声でもある。単なるポリリズム(polyridim:ジャマイカでは、"ridim"が太鼓、太鼓の演奏スタイル、そしてリズムを意味する)の道具ではない。太鼓はアフリカで決定的な役割を果たしてきた。太鼓がどれほどたくさんのリズムや、隠された意味を持っていようとおどろくには当たらない。
「カウント・オシー(Count Ossie)」として知られているオズワルド・ウィリアムスはレゲエ以前の大衆音楽家である。黎明期のラスタファリアン・ドラマーで、最初にナイアビンギをレコーディングした人物のひとりでもある。彼はアフリカやラスタの文化の確立にもつくした。
ラスタの中でも ボブ・マーリーも所属したTwelve Tribes of Israel(TTI)という分派が最も先鋭的であった。TTIは、信者であるミュージシャンのレコードにふきこんだ信仰告白を伝道の手段として利用、一般 大衆へ教義の浸透を図ったのである。カウント・オシーはアメリカ風にいえば singing preacher であった。若い歌手達はカウント・オシーら先達から音楽のみならずラスタの思想についても指導を受けることになった。こうして若い世代のラスタ化は速やかに進行したのである。
「ラスタの宗教音楽はいまでもナイアビンギだ。カウント・オシーが若いころ学んだやつさ。」とあるラスタマンはいう。
1950年代後半、バック・オー・ウォール(Back O' Wall)と西キングストンは、クミナ、ブル、myal、新興復興運動、ポコマニアおよび他のキリスト教の宗派、といったアフリカやアフロ・ヨーロピアン・ミュージックのるつぼだった。当時、カウント・オシーは他のラスタ同胞とともに、マーカス・ガ−ヴェイの思想、ラスタファリアニズム、黒人文化、および黒人身請け運動といった目的のため、定期的に旅行をしていた。
カウント・オシーがブル・ドラムの演奏を学んだのは、そのころであった。オシーは、まずフンデの演奏を学び、つづけてアケテをマスターしたという。オシーの師は、"Brother Job"と呼ばれるブル・マンだった。
西キングストンでのラスタの集会では1953年までルンバ・ボックスだけが使われ、太鼓は使われていなかった。オシーは、ブルのリズムをもとにした新しいドラミング・スタイルを編み出そうと考え、アケテを特注した。オシーはラスタに音楽を与えるため全力投球した。
搾取する白人と搾取される黒人という独立してもまったく改善されない 社会構造への批判を、正面きって行った宗教がラスタファリアニズムである。ラスタの音楽は、信者の社会認識を反映する。ダウンビートは重苦しい世の中の死を象徴するが、アケテ・ドラマーが軽快なアップビートで、ラスタの力を通 して社会が復興するぞ、と答えるしくみになっているのだ。
ナイアビンギの語源
KATE LOWE女史の"NYABINGHI"が底本です
もともとナイアビンギは「手当たり次第に取り憑く女」という意味で、ウガンダの伝説的なアマゾン・クイーンの名が由来らしい。しかしジャマイカでは「圧制者に対する死」を意味する言葉となった。
19世紀半ばから20世紀半ばにかけて、東アフリカのウガンダでは白人帝国主義国家に対する軍事行動がつづけられた。指導者はカリスマ性のある女たちである。そのひとり、ムフムサ(Muhumusa)は伝説的なアマゾンの女王「ナイアビンギ」の霊に憑かれてレジスタンスを組織し、ドイツ軍と勇敢に戦った。しかし1913年、英国軍に監禁されてしまったという。ナイアビンギの霊は女性に憑依することが多かったらしいが、後年憑依された男性が英国軍にいどんでいる。
英国は1912年に魔術条例を定めてナイアビンギ・ムーブメントを殲滅しようと企てた。キリスト教の教会や地元のアンチ・ナイアビンギ宗派が呼応した。1500から1600人もの「魔女」が火あぶりにされたという。
ナイアビンギを踊ることは圧制者を滅ぼしてほしいという祈りをジャーへ届ける確かな方法だと、ラスタたちは信じていた。ドレッド・ロック時代、ラスタたちは圧制者に死をもたらすために踊ったが、今日では「ビンギ(binghi)」とよばれラスタの特別 な儀式のときに踊られている。
● ナイアビンギを踊る日 ●
1月6日 ハイレ・セラシエ皇帝誕生式典日
1月23日 皇帝誕生日(1892)
4月25日 皇帝ジャマイカ訪問(1966年)
8月1日 奴隷解放日
8月17日 マーカス・ガーベイ誕生日
11月2日 皇帝戴冠式
"Grounation" とよばれるナイアビンギの儀式もジャマイカでは有名である。 "Grounation" は「地上での人生の肯定」といった意味合いで毎年4月21日頃行われる。これがラスタの礼拝の唯一のきまった機会である。最初の "Grounation"は1958年の3月、キングストンのバック・オー・ウォールにある Coptic Theocratic Temple で行われた。
ラスタたちは田舎に集まって料理をしたり、ガンジャを吸ったり、ジャーに祈ったり、キャンプファイヤーをしたりして仲間たちと楽しむ。いうなればラスタ流バカンスだ。ラスタは自然のままの食べ物( "ital"という)や塩を使わない料理をたべ、肉は食べない。ラスタの一家の中にはそのまま田舎に残るものもいるという。
こうしてナイアビンギはラスタ流に消化され、ビンギという身内の平和なイベントになっていったのである。
ナイアビンギ・ディスクガイド
JACKさんのラスタなサイト"VOHIVOHI" のディスクガイドをご覧ください。
母なる大地アフリカから強制連行され植民地支配によって政治的、経済的、文化的な自立の道を奪われた黒人奴隷たちは、自らを肯定的に捉えるために、新しいアイデンティティとそれを支える世界観を編み出した。こうして生み出されたのが数々のヨルバ系宗教である。しかしアフリカの宗教に根拠を求めない新たな信仰も生み出された。それがジャマイカで生まれたラスタファリアニズムやマルコムXやモハメッド・アリが信仰したブラック・ムスリムである。ここではラスタファリアニズム(以下ラスタ)の話をしよう。
ラスタの教えを要約するこんな具合だ。
1930年、ラス・タファリ(Ras Tafari)という人物がエチオピア帝国で皇帝の座についた。彼は即位に際してハイレ・セラシエ(Haile Selassie)を名乗った。皇帝ハイレ・セラシエは生き神「ジャー(Jah)」であり、黒人の救世主である。黒人は古代イスラエル人の末裔なのだが、黒人より劣った存在である白人の邪悪な陰謀により、ジャマイカで幽囚の生活を送っている。ジャマイカの状況は光りなき地獄・バビロンだが、エチオピアは天国だ。しかし、無敵の皇帝ハイレ・セラシエは、世界各地に誘拐されたアフリカ起源の民を故郷に戻す準備をしている。ラス・タファリの旗の下、近い将来に、黒人が世界を統治する。
荒唐無稽な教えである。しかしこれはジャマイカの下層階級の人が生きるに足る世界と歴史を構築しようとした結果うまれたものなのである。だから、ここでいわれる「ジャー」は、セラシエ帝の実像とは何の関わりもない。その証拠に、1970年代のエチオピア革命と皇帝の死は、ラスタ運動に本質的な打撃を与えなかった。
よく唱えられる「ジャー・ラスタファーライ」という言葉は「神であるセラシエ皇帝」という意味だ。ジャーの語源はキリスト教の絶対神エホバ(Jehovah)である。英語圏の賛美歌でよく使われる"God"、"Lord"、"Jesus"と同じように"Jah"はレゲエの歌詞に頻繁に登場する。
ヴードゥー教の天国は「ギニア」だがラスタたちは「天国はエチオピアにある」と考えているところがおもしろい。しかし「ギニア」にせよ「エチオピア」にせよ実在の国とは無関係の、抽象的な存在にすぎない。
ラスタの思想的ルーツとしてエチオピアニズム(旧約聖書に登場し、近代になっても植民地化されなかった黒人のキリスト教王国エチオピアをアフリカ起源の人たちの魂の故郷とみる考え方)があげられる。意外なことだがエチオピアは大航海時代のずっと前からキリスト教国家なのである。
もう一つのルーツがマーカス・ガーヴィーの「アフリカ帰還運動」である。マーカス・ガーヴィーの思想はブラック・ムスリムにも大きな影響を与えた。カーヴィーはジャマイカで生まれ、1910年代にアメリカに渡ってアフリカ帰還運動を組織し、一時は黒人大衆から絶大な支持を受けた人物である。
ラスタは旧約聖書を聖典とし、多くの者が Ethiopian Orthodox Church の信徒でもある。セラシエにせよガーヴェイにせよ、彼らは宗教的にはいずれもキリスト教徒であった。この点はヴードゥーと相通じるものがありそうだ。
黒人社会がキリスト教と対峙した時、その全面受容は白人社会への編入を意味し、完全拒否は社会的孤立を招く。宗教が黒人の団結を促し、社会改編の大きな力となるのは「キリスト教の影響を受けながら、独自の宗教観を形成した場合」である。
ラスタは「奴隷の宗教」だという従来のキリスト教を批判し、来世志向から世直しへと救済のイメージの転換。自然食や菜食主義を戒律にした。では厳しい宗教かというと全く逆である。
聖なる草「ガンジャ(ganja=マリファナ)」をガンガン吸ってハイになったり、強いカリスマ的リーダーを立ててきちんとした組織を作りたがらない傾向がある。
カリフォルニア(!)からやってきた白人の(!)人気レゲエ・バンド「ビッグ・マウンテン」は、ステージから観客にこう呼び掛けた。「私たちはラスタだ。ここにいる者はみなラスタだ。どんな肌の色でも、どんなことばをしゃべっても、ジャーの教えを理解する者はみなラスタだ。だからあなたたちは、日本中にラスタの教えを広める義務がある」 この大らかさは どうだろう。
**もっと詳しくラスタについて知りたい方は"THE DREAD LIBRARY"の中の"
FUNDAMENTALS: THE RASTAFARIANLIFESTYLE" by Michael Katz をお読みになるか、イーサクリエーションズ・オンラインショップ をお訪ねください。
ラスタ=レゲエではない
さて、「ラスタ=レゲエ」ではない、ということだが、ルーツ・レゲエ=ラスタの音楽、というふうに思われがちだ。しかし実はラスタには独自の音楽がある。それが「ナイアビンギ(nyabinghi)」だ(単にビンギ(binghi)とも呼ばれる)。もしあなたがコアなレゲエ好きなら、きっと聞き覚えがあると思う。
ナイアビンギというのは、もともとラスタの集会を指すことばだった。ラスタマンが輪になって集まり、ガンジャを吸い、一晩中ドラム叩きながら歌い(chant チャント)踊るという、宗教儀式である。
ドラムといってももちろんドラム・セットがあるのではなく、ベース、フンデ(funde)、リピーター(akete)と呼ばれる大中小の太鼓のことを指す。これをブル・ドラム(burru drum)という。このブル・ドラムのビートがナイアビンギである。
ベースは、4ビートの頭を叩き、3拍めで音を消す。フンデは、屋台骨となるビートを刻み、リピーター(アケテ)は即興でプレイする。
カウント・オシー & ザ・ミスティック・レヴェレーション・オブ・ラスタファリ(Count Ossie & The Mystic Revelation of Rastafari)やラス・マイケル & ザ・サンズ・オブ・ニガス(Ras Michael & The Sons of Negus)といった面子が、ナイアビンギ界の大物ミュージシャンだ。ラス・マイケルは、レゲエ・ミュージシャン達とコラボレイトしたことで有名になった。
ラスタの思想が多くのレゲエ・ミュージシャンに支持されたこと。そしてナイアビンギとレゲエの音楽的相性が良かったこと。この2つの理由によりレゲエとビンギはクロスオーバーしていったのである。
70年代、ナイアビンギはレゲエのアレンジに積極的に取り入れられた(90年代にもリヴァイヴァル)。ボブ・マーリーの"TIME WILL TELL"などは、典型的なナイアビンギ・スタイルである。
ナイアビンギの存在があきらかになったのは1958年のことである。それまでの数百年間、ブル(後述)のリズムは門外不出の伝統であった。ナイアビンギの太鼓の起源は、ブル、クミナ、西キングストンでのドラミングのリヴァイヴァル・スタイルの複雑な相互浸透である。
クミナの儀式とナイアビンギ
ナイアビンギの太鼓は、もともとブルとアフリカ系宗教・クミナで使われていた。
クミナの儀式には、太鼓の演奏とダンスが欠かせない。アフリカでは、太鼓はコミュニケーションの道具だ。通過儀礼や特別な行事、さらに病気のときも、クミナと太鼓が必要とされる。生贄が捧げられ、憑依現象がおこるまでダンスは続く。儀式で先祖の霊がよびだされると神聖なお告げがもたらされる。
クミナ特有のドラミングは、1930年代にキングストンに移動して、ナイアビンギのルーツとなった。
ブル・ドラミング(burru drumming)も、ナイアビンギのルーツだ。それは、まず1903年にClarendonの教区ではじめて演奏され、のちに西キングストンでも演奏された。小尖塔の破壊が多くのラスタたちをキングストンへ追いやったときに、ラスタたちはブル・ドラミングを学んだ。ブルはガーナからダンスを借用したと考えられている。
「ブル」(burru)は奴隷時代から伝わるアフリカの太鼓、ブル・ドラム(burru drum)を打つ者をさす言葉である。その多くは犯罪者だといわれ、どんどん数が減っている。ラスタは、西洋の影響をうけていない純粋なアフリカの音楽をブルから学んだのだといわれている。
ラスタとナイアビンギのなれそめ
ラスタマンにとって、そしてジャマイカの庶民音楽や伝統音楽にとって太鼓は重要な役割を果たしている。
太鼓は、アフリカ人の心臓の鼓動だ。白人はアフリカの声、心臓の鼓動を止めることができなかった。
すくなからぬ数の奴隷が脱走し、ジャマイカの奥地へ逃げこんだ。「マルーン」と呼ばれる逃亡奴隷たちである。よく知られたグループとして、Saramaka、Boni、the Maroons of the Guianasの名が挙げられる。マルーンたちは密生したジャングルと武器で自衛した。
マルーンたちの世界はアフリカン・ミュージックの宝庫であった。アフリカの習慣、そして音楽はじょうずに保存された。
太鼓は、神の声でもある。単なるポリリズム(polyridim:ジャマイカでは、"ridim"が太鼓、太鼓の演奏スタイル、そしてリズムを意味する)の道具ではない。太鼓はアフリカで決定的な役割を果たしてきた。太鼓がどれほどたくさんのリズムや、隠された意味を持っていようとおどろくには当たらない。
「カウント・オシー(Count Ossie)」として知られているオズワルド・ウィリアムスはレゲエ以前の大衆音楽家である。黎明期のラスタファリアン・ドラマーで、最初にナイアビンギをレコーディングした人物のひとりでもある。彼はアフリカやラスタの文化の確立にもつくした。
ラスタの中でも ボブ・マーリーも所属したTwelve Tribes of Israel(TTI)という分派が最も先鋭的であった。TTIは、信者であるミュージシャンのレコードにふきこんだ信仰告白を伝道の手段として利用、一般 大衆へ教義の浸透を図ったのである。カウント・オシーはアメリカ風にいえば singing preacher であった。若い歌手達はカウント・オシーら先達から音楽のみならずラスタの思想についても指導を受けることになった。こうして若い世代のラスタ化は速やかに進行したのである。
「ラスタの宗教音楽はいまでもナイアビンギだ。カウント・オシーが若いころ学んだやつさ。」とあるラスタマンはいう。
1950年代後半、バック・オー・ウォール(Back O' Wall)と西キングストンは、クミナ、ブル、myal、新興復興運動、ポコマニアおよび他のキリスト教の宗派、といったアフリカやアフロ・ヨーロピアン・ミュージックのるつぼだった。当時、カウント・オシーは他のラスタ同胞とともに、マーカス・ガ−ヴェイの思想、ラスタファリアニズム、黒人文化、および黒人身請け運動といった目的のため、定期的に旅行をしていた。
カウント・オシーがブル・ドラムの演奏を学んだのは、そのころであった。オシーは、まずフンデの演奏を学び、つづけてアケテをマスターしたという。オシーの師は、"Brother Job"と呼ばれるブル・マンだった。
西キングストンでのラスタの集会では1953年までルンバ・ボックスだけが使われ、太鼓は使われていなかった。オシーは、ブルのリズムをもとにした新しいドラミング・スタイルを編み出そうと考え、アケテを特注した。オシーはラスタに音楽を与えるため全力投球した。
搾取する白人と搾取される黒人という独立してもまったく改善されない 社会構造への批判を、正面きって行った宗教がラスタファリアニズムである。ラスタの音楽は、信者の社会認識を反映する。ダウンビートは重苦しい世の中の死を象徴するが、アケテ・ドラマーが軽快なアップビートで、ラスタの力を通 して社会が復興するぞ、と答えるしくみになっているのだ。
ナイアビンギの語源
KATE LOWE女史の"NYABINGHI"が底本です
もともとナイアビンギは「手当たり次第に取り憑く女」という意味で、ウガンダの伝説的なアマゾン・クイーンの名が由来らしい。しかしジャマイカでは「圧制者に対する死」を意味する言葉となった。
19世紀半ばから20世紀半ばにかけて、東アフリカのウガンダでは白人帝国主義国家に対する軍事行動がつづけられた。指導者はカリスマ性のある女たちである。そのひとり、ムフムサ(Muhumusa)は伝説的なアマゾンの女王「ナイアビンギ」の霊に憑かれてレジスタンスを組織し、ドイツ軍と勇敢に戦った。しかし1913年、英国軍に監禁されてしまったという。ナイアビンギの霊は女性に憑依することが多かったらしいが、後年憑依された男性が英国軍にいどんでいる。
英国は1912年に魔術条例を定めてナイアビンギ・ムーブメントを殲滅しようと企てた。キリスト教の教会や地元のアンチ・ナイアビンギ宗派が呼応した。1500から1600人もの「魔女」が火あぶりにされたという。
ナイアビンギを踊ることは圧制者を滅ぼしてほしいという祈りをジャーへ届ける確かな方法だと、ラスタたちは信じていた。ドレッド・ロック時代、ラスタたちは圧制者に死をもたらすために踊ったが、今日では「ビンギ(binghi)」とよばれラスタの特別 な儀式のときに踊られている。
● ナイアビンギを踊る日 ●
1月6日 ハイレ・セラシエ皇帝誕生式典日
1月23日 皇帝誕生日(1892)
4月25日 皇帝ジャマイカ訪問(1966年)
8月1日 奴隷解放日
8月17日 マーカス・ガーベイ誕生日
11月2日 皇帝戴冠式
"Grounation" とよばれるナイアビンギの儀式もジャマイカでは有名である。 "Grounation" は「地上での人生の肯定」といった意味合いで毎年4月21日頃行われる。これがラスタの礼拝の唯一のきまった機会である。最初の "Grounation"は1958年の3月、キングストンのバック・オー・ウォールにある Coptic Theocratic Temple で行われた。
ラスタたちは田舎に集まって料理をしたり、ガンジャを吸ったり、ジャーに祈ったり、キャンプファイヤーをしたりして仲間たちと楽しむ。いうなればラスタ流バカンスだ。ラスタは自然のままの食べ物( "ital"という)や塩を使わない料理をたべ、肉は食べない。ラスタの一家の中にはそのまま田舎に残るものもいるという。
こうしてナイアビンギはラスタ流に消化され、ビンギという身内の平和なイベントになっていったのである。
ナイアビンギ・ディスクガイド
JACKさんのラスタなサイト"VOHIVOHI" のディスクガイドをご覧ください。
|
|
|
|
|
|
|
|
JAH RASTAFARI 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
JAH RASTAFARIのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37834人
- 2位
- 酒好き
- 170665人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89528人