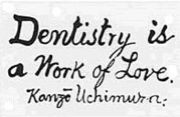以下,産業歯科保健研究会で小清水 美千子先生(元日立製作所勤務:薬剤師)が講演された内容を抜粋します.なお薬剤は,製品名で記載しています.
薬剤が口腔に及ぼす影響として,以下のものが挙げられる.
◆味覚異常
◆歯の形成不全と着色
口腔内,歯肉,歯牙,唾液,痰,舌,口唇など
◆歯肉肥大症
◆口腔乾燥症
◆唾液分泌過剰
◆口唇炎(口唇異常感)
◆口内炎
◆その他
「味覚異常とは?」
一種の神経症状で,味覚の減退,消失,苦味感,味覚倒錯など,症状は多彩である.
一次性として,遺伝,中枢・末梢神経伝達路障害,老人性,突発性などがある.
二次性として,薬物性,口腔内病変(口腔内・唾液性疾患),全身疾患(貧血,糖尿病,肝・腎不全,胃切除後など),亜鉛欠乏,頭部外傷,放射線,感冒後,心因性,食事性などがある.
味覚異常を起こす薬剤として,
●抗悪性腫瘍剤,抗生物質を中心に多種多様である
●医療用医薬品の添付文書の副作用の項に記載がある薬剤は日本医薬品集(20002/7)で検索すると191件に上る
薬剤性味覚異常の発現機序
◇金属キレート能に起因する
薬剤の持つキレート能により,生体内の亜鉛が過剰に排泄されることに起因するとする報告がある.つまりこれらの薬剤を用いると亜鉛の尿中排泄を増加する.
◇抗コリン作用に起因する
ブスコパンなどの薬品が口渇,尿閉塞を起こす
◇原薬の苦味に起因する
向精神薬(10%)に発現し,注意が必要である
◇原因不明の作用に起因する
薬剤性味覚障害の報告がある主な薬剤として,
利尿剤,Ca拮抗剤,血管収縮剤,鎮吐剤,消化性潰瘍剤,高尿酸血症治療薬,糖尿病治療薬,骨・Ca代謝薬,免疫抑制剤,解熱鎮痛剤,抗ヒスタミン剤,抗てんかん剤,抗パーキンソン薬,向精神薬,肝臓疾患用剤,自律神経用剤,抗生物質,抗菌剤,サルファ剤,抗拮抗剤,抗真菌剤,AIDS治療剤,抗がん剤,その他(具体的な薬品名は省きました.知りたい方は一報ください)
薬剤性味覚障害の治療として,
◆第一に原因となる薬剤の減量,中止であるが,原疾患の治療上,投薬の継続が必要な場合,亜鉛製剤の内服が試みられる
◆特に食事制限がされていない患者では,*亜鉛含有量の多い食品の摂取が予防的に働く可能性が考えられる
*亜鉛含有量の多い食品(含有量:?)
牡蠣:40.0,小麦胚芽:15.0,スモークレバー:9.0,パルメザンチーズ:7.3,煮干:7.2,胡麻:7.1,豚肝臓:6.9,たたみ鰯:6.6,凍り豆腐5.5,するめ:5.4などがある.
「歯の形成不全と着色」
●口腔内を青,青黒色に着色させる薬剤に,次硝酸ビスマス末という下痢止めがあるが,現在はあまり使用されていない
●歯肉を青,青黒色に着色させる薬剤に,上記の次硝酸ビスマス末の他にデルマトール末がある
●歯肉を着色,変色させる薬剤に,抗生物質(テトラサイクリン系,マクロライド系,オキサゾリジノン系など)やアクロマイシントローチ(テトラサイクリン含有の歯科用材),鉄欠乏貧血治療薬がある.MRI造影剤は黒色に変化させる.
●唾液においては,結核治療薬が橙赤色にさせ,パーキンソン病治療薬が黒色にさせる
●痰においては,ハンセン病治療薬による着色,結核治療薬が同じく橙赤色にさせる
●舌を黒色にさせる薬剤に,口内炎治療薬,抗生物質(テトラサイクリン系),高血圧治療薬,MRI造影剤などがあり,抗生物質(マクロライド系),ヘリコバクターピロリ除菌剤なども舌を変色させる
●口唇の変色においては,副腎皮質刺激ホルモンが黒褐色,紫色に変色させる
以上.
続きは,歯科衛生士として,如何に患者さんの薬剤の影響に言及するかと,
ジェネリック医薬品のことにも少し言及いたします.
薬剤が口腔に及ぼす影響として,以下のものが挙げられる.
◆味覚異常
◆歯の形成不全と着色
口腔内,歯肉,歯牙,唾液,痰,舌,口唇など
◆歯肉肥大症
◆口腔乾燥症
◆唾液分泌過剰
◆口唇炎(口唇異常感)
◆口内炎
◆その他
「味覚異常とは?」
一種の神経症状で,味覚の減退,消失,苦味感,味覚倒錯など,症状は多彩である.
一次性として,遺伝,中枢・末梢神経伝達路障害,老人性,突発性などがある.
二次性として,薬物性,口腔内病変(口腔内・唾液性疾患),全身疾患(貧血,糖尿病,肝・腎不全,胃切除後など),亜鉛欠乏,頭部外傷,放射線,感冒後,心因性,食事性などがある.
味覚異常を起こす薬剤として,
●抗悪性腫瘍剤,抗生物質を中心に多種多様である
●医療用医薬品の添付文書の副作用の項に記載がある薬剤は日本医薬品集(20002/7)で検索すると191件に上る
薬剤性味覚異常の発現機序
◇金属キレート能に起因する
薬剤の持つキレート能により,生体内の亜鉛が過剰に排泄されることに起因するとする報告がある.つまりこれらの薬剤を用いると亜鉛の尿中排泄を増加する.
◇抗コリン作用に起因する
ブスコパンなどの薬品が口渇,尿閉塞を起こす
◇原薬の苦味に起因する
向精神薬(10%)に発現し,注意が必要である
◇原因不明の作用に起因する
薬剤性味覚障害の報告がある主な薬剤として,
利尿剤,Ca拮抗剤,血管収縮剤,鎮吐剤,消化性潰瘍剤,高尿酸血症治療薬,糖尿病治療薬,骨・Ca代謝薬,免疫抑制剤,解熱鎮痛剤,抗ヒスタミン剤,抗てんかん剤,抗パーキンソン薬,向精神薬,肝臓疾患用剤,自律神経用剤,抗生物質,抗菌剤,サルファ剤,抗拮抗剤,抗真菌剤,AIDS治療剤,抗がん剤,その他(具体的な薬品名は省きました.知りたい方は一報ください)
薬剤性味覚障害の治療として,
◆第一に原因となる薬剤の減量,中止であるが,原疾患の治療上,投薬の継続が必要な場合,亜鉛製剤の内服が試みられる
◆特に食事制限がされていない患者では,*亜鉛含有量の多い食品の摂取が予防的に働く可能性が考えられる
*亜鉛含有量の多い食品(含有量:?)
牡蠣:40.0,小麦胚芽:15.0,スモークレバー:9.0,パルメザンチーズ:7.3,煮干:7.2,胡麻:7.1,豚肝臓:6.9,たたみ鰯:6.6,凍り豆腐5.5,するめ:5.4などがある.
「歯の形成不全と着色」
●口腔内を青,青黒色に着色させる薬剤に,次硝酸ビスマス末という下痢止めがあるが,現在はあまり使用されていない
●歯肉を青,青黒色に着色させる薬剤に,上記の次硝酸ビスマス末の他にデルマトール末がある
●歯肉を着色,変色させる薬剤に,抗生物質(テトラサイクリン系,マクロライド系,オキサゾリジノン系など)やアクロマイシントローチ(テトラサイクリン含有の歯科用材),鉄欠乏貧血治療薬がある.MRI造影剤は黒色に変化させる.
●唾液においては,結核治療薬が橙赤色にさせ,パーキンソン病治療薬が黒色にさせる
●痰においては,ハンセン病治療薬による着色,結核治療薬が同じく橙赤色にさせる
●舌を黒色にさせる薬剤に,口内炎治療薬,抗生物質(テトラサイクリン系),高血圧治療薬,MRI造影剤などがあり,抗生物質(マクロライド系),ヘリコバクターピロリ除菌剤なども舌を変色させる
●口唇の変色においては,副腎皮質刺激ホルモンが黒褐色,紫色に変色させる
以上.
続きは,歯科衛生士として,如何に患者さんの薬剤の影響に言及するかと,
ジェネリック医薬品のことにも少し言及いたします.
|
|
|
|
コメント(20)
続きです.
「歯肉肥大症」
薬物性の歯肉肥大症として,
★フェニトイン性歯肉増殖症で,これは抗けいれん薬のアレルビチン,ビタントールによるもの
★カルシウム拮抗薬によるもの歯肉増殖症で,これは高血圧や狭心症治療薬のアダラート,バイロテンシン,ワソラン,ヘベッサーなどによるもの
上記,2疾患の薬剤は,いずれも長期服用をするものです.
★シクロスポリンAによる歯肉増殖症で,これは免疫抑制剤のサンディミュンによるもので,高確率で発症します
「口腔乾燥症」
唾液腺の何らかの障害によって,唾液腺の機能低下や消失による口腔の異常な乾燥状態を示す.
口腔乾燥により,口腔の違和感,強い口臭,舌痛症や口腔粘膜の疼痛,口内炎や口腔カンジタ症,粘膜潰瘍や義歯性潰瘍の頻発,咀嚼,嚥下,味覚,構音などの障害を示すようになる.また,時として口渇と伴う.
口腔乾燥の原因として,
◆腺因性:シェーグレン症候群をはじめとする慢性萎縮性唾液腺炎,放射性治療による唾液腺萎縮,加齢による唾液腺変性など
◆薬剤性:
◆全身性代謝疾患:甲状腺機能亢進症,脱水症,下痢,糖尿病など
◆生活習慣:口呼吸,ストレス,咀嚼回数の減少,喫煙など
◆ビタミン欠乏:VB1,VB2,VB6,葉酸など
口腔乾燥症の原因となる主な薬剤として,
●抗精神病薬:ウィスタミン,フルメジン
●抗躁薬:リーマス
●抗パーキンソン病薬:アーテン
●鎮痙薬:ブスコパン
●眼科用薬:硫酸アトロピン
●抗悪性腫瘍:ブリプラチン
●抗ヒスタミン薬:ピレチア
●Ca拮抗薬:アダラート,ペルジピン,ヘルベッサー,ワラソン
●X線造影剤:イソビスト
口腔乾燥症の治療として,
◇原因療法:原因の除去,改善
◇唾液腺機能が残っている場合:機能賦活療法(耳下腺洗浄手技),唾液分泌量を促進する薬剤の使用
◇唾液腺機能が消失している場合:含嗽剤,人工唾液などの投与
*口腔乾燥症改善の適応をもつ主な医療用医薬品
外用薬:サリベート(噴霧式エアゾール剤)
内用薬:エボザックカプセル,サリグレンカプセル,サラジェン錠,フェルビテン錠,白虎加人参湯エキス顆粒・錠
「唾液分泌過剰」
唾液分泌過剰を起こす主な薬剤として,
☆抗精神薬:セレネース,ドグマチール
☆抗不安薬:ベンザリン
☆抗てんかん薬:テグレトール
☆自律神経作用薬:ベサコリン
☆抗原虫薬:クロロキン
「口唇炎」
口唇炎を起こす主な薬剤として,
★催眠薬:フェノバール
★抗精神薬:ノバミン
★副腎皮質ホルモン薬:リンデロン
★含嗽薬:アズノール
「口内炎」
口内炎を起こす主な薬剤として,
●抗躁薬:リーマス
●抗てんかん薬:テグレトール,デパケン
●関節リウマチ治療薬:シオゾール
●ビタミンA剤:チョコラA
●抗悪性腫瘍剤:メトレキセート,アドリシアシン,ブレオ,ノバントロン,インターフェロン製剤
「歯科治療に関係のある薬剤」:抗凝固剤
抗凝固剤を服用する代表的疾患に,脳卒中,脳梗塞(脳血栓,脳塞栓),心房細動,大動脈瘤,虚血性心疾患,狭心症,心筋梗塞,各種心臓弁膜症,肺梗塞,下肢静脈瘤,慢性動脈閉塞症,様々な血管の閉塞状態,何らかの血管の手術を受けたことのある人.
抗凝固剤の代表的な薬剤名として,
バファリン81,バイアスピン,ミニマックス顆粒,アスピリン末,EAC錠,パナルジン,塩酸チクロピジン,エパデール,ソルミラン,イコサペント酸エチル(EPA),ワーファリン,プレタール,アンプラーグ,オパルモン,ドルナー,プロサイリン
これらの薬剤は,歯科の外科的処置を行う前に7日間,2日間の服用中断をしなければならない.しかし,病状によっては,中断ができない場合があるので,必ず主治医の確認を取る.
*抜歯時のワルファリンカリウム療法:抜歯は抗血栓薬(ワルファリン,抗血小板薬)の内服継続下で行うのが望ましいとの専門化の見解がある(20004 日本循環器学会のガイドランより)
今回,ざっと通読して分かるように,同一の薬剤が口腔に複数の影響を及ぼしていることが分かります.
しかし,往々にして患者さんは内服している薬剤に関して,公にしたくないようです.特に歯科においてはです.
「一元管理」にあるように,医科,歯科において,その患者さんに関する「薬歴」は共有するべきであり,この考えの下に作成された「薬歴手帳:お薬手帳」を持参している方も多いことでしょう.
そこで,歯科医療従事者は,初診時に薬暦手帳持参の有無を確認することが重要です.
仮に持参されていても,歯科で処方された薬剤に関して記載していないことも多いようです.今後は,チーム医療としての「一元管理」に留意しましょう!
最後にジェネリック医薬品に関して少し述べます.
大方の薬剤師は,後発医薬品に関して否定的・懐疑的であるようです.
それは,成分が同じでも,全くの同一の効果が得られる訳ではなく,副作用に関しての研究もないとのこと.
安易に安いから・・・と勧められたり,自ら求めることを,推奨していませんでした.
「歯肉肥大症」
薬物性の歯肉肥大症として,
★フェニトイン性歯肉増殖症で,これは抗けいれん薬のアレルビチン,ビタントールによるもの
★カルシウム拮抗薬によるもの歯肉増殖症で,これは高血圧や狭心症治療薬のアダラート,バイロテンシン,ワソラン,ヘベッサーなどによるもの
上記,2疾患の薬剤は,いずれも長期服用をするものです.
★シクロスポリンAによる歯肉増殖症で,これは免疫抑制剤のサンディミュンによるもので,高確率で発症します
「口腔乾燥症」
唾液腺の何らかの障害によって,唾液腺の機能低下や消失による口腔の異常な乾燥状態を示す.
口腔乾燥により,口腔の違和感,強い口臭,舌痛症や口腔粘膜の疼痛,口内炎や口腔カンジタ症,粘膜潰瘍や義歯性潰瘍の頻発,咀嚼,嚥下,味覚,構音などの障害を示すようになる.また,時として口渇と伴う.
口腔乾燥の原因として,
◆腺因性:シェーグレン症候群をはじめとする慢性萎縮性唾液腺炎,放射性治療による唾液腺萎縮,加齢による唾液腺変性など
◆薬剤性:
◆全身性代謝疾患:甲状腺機能亢進症,脱水症,下痢,糖尿病など
◆生活習慣:口呼吸,ストレス,咀嚼回数の減少,喫煙など
◆ビタミン欠乏:VB1,VB2,VB6,葉酸など
口腔乾燥症の原因となる主な薬剤として,
●抗精神病薬:ウィスタミン,フルメジン
●抗躁薬:リーマス
●抗パーキンソン病薬:アーテン
●鎮痙薬:ブスコパン
●眼科用薬:硫酸アトロピン
●抗悪性腫瘍:ブリプラチン
●抗ヒスタミン薬:ピレチア
●Ca拮抗薬:アダラート,ペルジピン,ヘルベッサー,ワラソン
●X線造影剤:イソビスト
口腔乾燥症の治療として,
◇原因療法:原因の除去,改善
◇唾液腺機能が残っている場合:機能賦活療法(耳下腺洗浄手技),唾液分泌量を促進する薬剤の使用
◇唾液腺機能が消失している場合:含嗽剤,人工唾液などの投与
*口腔乾燥症改善の適応をもつ主な医療用医薬品
外用薬:サリベート(噴霧式エアゾール剤)
内用薬:エボザックカプセル,サリグレンカプセル,サラジェン錠,フェルビテン錠,白虎加人参湯エキス顆粒・錠
「唾液分泌過剰」
唾液分泌過剰を起こす主な薬剤として,
☆抗精神薬:セレネース,ドグマチール
☆抗不安薬:ベンザリン
☆抗てんかん薬:テグレトール
☆自律神経作用薬:ベサコリン
☆抗原虫薬:クロロキン
「口唇炎」
口唇炎を起こす主な薬剤として,
★催眠薬:フェノバール
★抗精神薬:ノバミン
★副腎皮質ホルモン薬:リンデロン
★含嗽薬:アズノール
「口内炎」
口内炎を起こす主な薬剤として,
●抗躁薬:リーマス
●抗てんかん薬:テグレトール,デパケン
●関節リウマチ治療薬:シオゾール
●ビタミンA剤:チョコラA
●抗悪性腫瘍剤:メトレキセート,アドリシアシン,ブレオ,ノバントロン,インターフェロン製剤
「歯科治療に関係のある薬剤」:抗凝固剤
抗凝固剤を服用する代表的疾患に,脳卒中,脳梗塞(脳血栓,脳塞栓),心房細動,大動脈瘤,虚血性心疾患,狭心症,心筋梗塞,各種心臓弁膜症,肺梗塞,下肢静脈瘤,慢性動脈閉塞症,様々な血管の閉塞状態,何らかの血管の手術を受けたことのある人.
抗凝固剤の代表的な薬剤名として,
バファリン81,バイアスピン,ミニマックス顆粒,アスピリン末,EAC錠,パナルジン,塩酸チクロピジン,エパデール,ソルミラン,イコサペント酸エチル(EPA),ワーファリン,プレタール,アンプラーグ,オパルモン,ドルナー,プロサイリン
これらの薬剤は,歯科の外科的処置を行う前に7日間,2日間の服用中断をしなければならない.しかし,病状によっては,中断ができない場合があるので,必ず主治医の確認を取る.
*抜歯時のワルファリンカリウム療法:抜歯は抗血栓薬(ワルファリン,抗血小板薬)の内服継続下で行うのが望ましいとの専門化の見解がある(20004 日本循環器学会のガイドランより)
今回,ざっと通読して分かるように,同一の薬剤が口腔に複数の影響を及ぼしていることが分かります.
しかし,往々にして患者さんは内服している薬剤に関して,公にしたくないようです.特に歯科においてはです.
「一元管理」にあるように,医科,歯科において,その患者さんに関する「薬歴」は共有するべきであり,この考えの下に作成された「薬歴手帳:お薬手帳」を持参している方も多いことでしょう.
そこで,歯科医療従事者は,初診時に薬暦手帳持参の有無を確認することが重要です.
仮に持参されていても,歯科で処方された薬剤に関して記載していないことも多いようです.今後は,チーム医療としての「一元管理」に留意しましょう!
最後にジェネリック医薬品に関して少し述べます.
大方の薬剤師は,後発医薬品に関して否定的・懐疑的であるようです.
それは,成分が同じでも,全くの同一の効果が得られる訳ではなく,副作用に関しての研究もないとのこと.
安易に安いから・・・と勧められたり,自ら求めることを,推奨していませんでした.
「降圧剤が歯肉に及ぼす影響」について
コミュのメンバーから個人的に質問を受けましたが,
この場を借りて皆様にも情報を提供します.
高血圧治療薬には,以下のものがあります(処方される頻度の高い順)
◆カルシウム拮抗剤:ノルバスク,アムロジン,アダラート,ニコールなど
◆アンテギオシン?受容体拮抗剤(ARB):ブロプレス,ディオパン,ミカルディス,ニューロタンなど
◆ACE阻害剤:タナトリル,レニベース/エナラートなど
◆β遮断剤:テノーミン,インデラル,メインテートなど
◆利尿剤:フルイトラン,オイテンシン/ラシックスなど
◆α遮断薬:カルデナリン,ミニプレス,デタントールなど
これらの中で,Ca拮抗剤が副作用として歯肉増殖を起こします.
頻度的にはわずかだそうですが,そのような患者さんに遭遇した場合の対処を記載します
(当社の薬剤師,歯科医師などに確認しました).
●担当の医師に相談して降圧剤の種類を変更してもらう
●歯肉増殖は口腔内が不潔であり,乱暴なブラッシングで憎悪するので,
適切なプラークコントロールを身につけてもらう
●降圧剤による歯肉増殖は,仮性ポケットが多いようだが,
上記の事柄をもってしても改善しないようであれば,外科的に切除する
アメリカ政府の調査では,利尿薬が一番効果あるとの見解が示されました.
利尿薬は古くからある薬剤で,日本では“古臭い”と敬遠されていますが,
心疾患のある人に多く処方されており,また腎疾患既往者には禁忌です.
ARBなどは,苦味を感じるようになり,他のどの薬剤も口腔乾燥は,逸がれないようです.
歯科衛生士,歯科医師の単独判断で勝手な見解は出せませんが,
薬剤師によれば「歯肉増殖は副作用なので,薬を変更してもらうべき」と申しています.
患者さんの担当医師と十分な連携を取り,一元管理を目指してください.
お勧めの「全身疾患治療薬と歯科」関連の書籍ですが,
デンタルハイジーンの編集長に確認してみました.
◇歯界展望別冊「Q&A歯科のくすりが分かる本2008」
◇歯科医院必携くすりの完全ガイド(2005)
ここだけの話,近々に最新版が発刊されるとか・・・
コミュのメンバーから個人的に質問を受けましたが,
この場を借りて皆様にも情報を提供します.
高血圧治療薬には,以下のものがあります(処方される頻度の高い順)
◆カルシウム拮抗剤:ノルバスク,アムロジン,アダラート,ニコールなど
◆アンテギオシン?受容体拮抗剤(ARB):ブロプレス,ディオパン,ミカルディス,ニューロタンなど
◆ACE阻害剤:タナトリル,レニベース/エナラートなど
◆β遮断剤:テノーミン,インデラル,メインテートなど
◆利尿剤:フルイトラン,オイテンシン/ラシックスなど
◆α遮断薬:カルデナリン,ミニプレス,デタントールなど
これらの中で,Ca拮抗剤が副作用として歯肉増殖を起こします.
頻度的にはわずかだそうですが,そのような患者さんに遭遇した場合の対処を記載します
(当社の薬剤師,歯科医師などに確認しました).
●担当の医師に相談して降圧剤の種類を変更してもらう
●歯肉増殖は口腔内が不潔であり,乱暴なブラッシングで憎悪するので,
適切なプラークコントロールを身につけてもらう
●降圧剤による歯肉増殖は,仮性ポケットが多いようだが,
上記の事柄をもってしても改善しないようであれば,外科的に切除する
アメリカ政府の調査では,利尿薬が一番効果あるとの見解が示されました.
利尿薬は古くからある薬剤で,日本では“古臭い”と敬遠されていますが,
心疾患のある人に多く処方されており,また腎疾患既往者には禁忌です.
ARBなどは,苦味を感じるようになり,他のどの薬剤も口腔乾燥は,逸がれないようです.
歯科衛生士,歯科医師の単独判断で勝手な見解は出せませんが,
薬剤師によれば「歯肉増殖は副作用なので,薬を変更してもらうべき」と申しています.
患者さんの担当医師と十分な連携を取り,一元管理を目指してください.
お勧めの「全身疾患治療薬と歯科」関連の書籍ですが,
デンタルハイジーンの編集長に確認してみました.
◇歯界展望別冊「Q&A歯科のくすりが分かる本2008」
◇歯科医院必携くすりの完全ガイド(2005)
ここだけの話,近々に最新版が発刊されるとか・・・
先日、当院のHPにこんな問い合わせがありました。
「子供(5歳)が内科にかかり、テトラサイクリン系の薬を処方された。後で調べたら永久歯の変色の可能性があるとのこと。今できる対処はありますか?」
当院の歯科医師が
「教科書には1週間ほどの服用なら問題ないとされているが、それでも永久歯に横縞の変色が出現するかどうかは、生えてみないとわからない。
お子様の永久歯に変色が現れないことを私も願っている。
薬剤が、どれだけ口の中に影響するのか、医師、保護者に伝わっておらず、情報提供が足りないことを歯科医師として申し訳なく思っている。」
と、返信しました。
また、カリエスリスクが高いのに、喘息のドライシロップ服用を止めるわけにいかず、カリエス予防にほとほと困っている保護者も多いです。
>医師の大半は,歯科の知識も無く,関心もないとおっしゃっていました.
>歯科の分野に関しては,もっと積極的に歯科医が関わるべきですね.
本当に。大きくうなずいてしまいました。
「子供(5歳)が内科にかかり、テトラサイクリン系の薬を処方された。後で調べたら永久歯の変色の可能性があるとのこと。今できる対処はありますか?」
当院の歯科医師が
「教科書には1週間ほどの服用なら問題ないとされているが、それでも永久歯に横縞の変色が出現するかどうかは、生えてみないとわからない。
お子様の永久歯に変色が現れないことを私も願っている。
薬剤が、どれだけ口の中に影響するのか、医師、保護者に伝わっておらず、情報提供が足りないことを歯科医師として申し訳なく思っている。」
と、返信しました。
また、カリエスリスクが高いのに、喘息のドライシロップ服用を止めるわけにいかず、カリエス予防にほとほと困っている保護者も多いです。
>医師の大半は,歯科の知識も無く,関心もないとおっしゃっていました.
>歯科の分野に関しては,もっと積極的に歯科医が関わるべきですね.
本当に。大きくうなずいてしまいました。
>ルルさん
コメントありがとうございました!
喘息用のドライシロップの甘味に関して,薬剤師に質問してみますね.
暫くお待ちくださいませ.
テトラサイクリン(TC)服用による変色歯に関して,以下,日本審美学会のテキストによれば,
TCによる変色は,薬剤の服用の時期,期間,量と歯冠形成時期よの関係により様々ですが,
2歳くらいまでにTCを大量に服用すると,上顎前歯,第一大臼歯に変色を起こします.
その発現率は80%以上となります.
TC投与量26〜29mg/kg/day,投与期間4〜6日間,総投与量270〜500mgで,
変色を引き起こすといわれています.
なお,歯冠萌出後の17〜19歳までの間,ミノサイクリンを長期服用すると,
すべての歯の歯質内部に灰色の着色が認められ,
特に歯頚部3分の1が濃く着色したという報告もあります.
「変色歯の分類(福島)」
?型:TC服用時期 出生〜3歳,前歯の切縁から歯冠中央部まで変色,
第一大臼歯歯冠が変色,小臼歯,第二大臼歯は変色していない.
?型:TC服用時期 出生〜6歳,前歯〜第二大臼歯の歯冠および中切歯,
側切歯,第一大臼歯の歯根上部まで変色する.
?型:TC服用時期 3歳〜6歳,前歯と第一大臼歯の歯頚部から歯根,
小臼歯と第二大臼歯の歯根が変色,前歯の切縁から歯冠中央部には変色は認められない.
可能であれば,TC系薬剤は他のものに変更して頂きたいですね.
変色歯は,患者さんにとって審美的にも辛いものであると思われるからです.
コメントありがとうございました!
喘息用のドライシロップの甘味に関して,薬剤師に質問してみますね.
暫くお待ちくださいませ.
テトラサイクリン(TC)服用による変色歯に関して,以下,日本審美学会のテキストによれば,
TCによる変色は,薬剤の服用の時期,期間,量と歯冠形成時期よの関係により様々ですが,
2歳くらいまでにTCを大量に服用すると,上顎前歯,第一大臼歯に変色を起こします.
その発現率は80%以上となります.
TC投与量26〜29mg/kg/day,投与期間4〜6日間,総投与量270〜500mgで,
変色を引き起こすといわれています.
なお,歯冠萌出後の17〜19歳までの間,ミノサイクリンを長期服用すると,
すべての歯の歯質内部に灰色の着色が認められ,
特に歯頚部3分の1が濃く着色したという報告もあります.
「変色歯の分類(福島)」
?型:TC服用時期 出生〜3歳,前歯の切縁から歯冠中央部まで変色,
第一大臼歯歯冠が変色,小臼歯,第二大臼歯は変色していない.
?型:TC服用時期 出生〜6歳,前歯〜第二大臼歯の歯冠および中切歯,
側切歯,第一大臼歯の歯根上部まで変色する.
?型:TC服用時期 3歳〜6歳,前歯と第一大臼歯の歯頚部から歯根,
小臼歯と第二大臼歯の歯根が変色,前歯の切縁から歯冠中央部には変色は認められない.
可能であれば,TC系薬剤は他のものに変更して頂きたいですね.
変色歯は,患者さんにとって審美的にも辛いものであると思われるからです.
当医院の患者さんの約7割は高齢者なので、服用している薬のチエックはとても慎重にしています。
>医師の大半は,歯科の知識も無く,関心もないとおっしゃっていました
唯一、医師が歯科治療に配慮してくれている事といえば、
ワーファリンやバイアスピリンなど、血液抗硬化剤を処方している場合です。
この時は必ず「歯科にかかる時は服用している薬を歯科医師に提示してください」と医師から患者さんに説明があり、患者さんも気をつけて下さいます。
当医院では初診時にはもちろん薬の問診をするのですが、いつも来ている患者さんでも、観血処置をする際や口腔内に変化がみられた際は再度問診します。
私達の知らないところで、新たに病気をしてしまったり、薬の種類が変わっている可能性があるからです。
薬の事を先生任せにするのではなく、衛生士もキチンと知識を持って患者さんの口腔管理が出来るようにすることはとても重要ですよね
このトピでまた勉強しなおします
>医師の大半は,歯科の知識も無く,関心もないとおっしゃっていました
唯一、医師が歯科治療に配慮してくれている事といえば、
ワーファリンやバイアスピリンなど、血液抗硬化剤を処方している場合です。
この時は必ず「歯科にかかる時は服用している薬を歯科医師に提示してください」と医師から患者さんに説明があり、患者さんも気をつけて下さいます。
当医院では初診時にはもちろん薬の問診をするのですが、いつも来ている患者さんでも、観血処置をする際や口腔内に変化がみられた際は再度問診します。
私達の知らないところで、新たに病気をしてしまったり、薬の種類が変わっている可能性があるからです。
薬の事を先生任せにするのではなく、衛生士もキチンと知識を持って患者さんの口腔管理が出来るようにすることはとても重要ですよね
このトピでまた勉強しなおします
>おっさん
コメントありがとうございます!
高齢者の服用に関しては,頻回なインタビューが必要ですね.
いつ何時処方が変更されるか分かりませんから.
健康のために飲んでいる薬剤が歯科治療において害となってはなりませんね.
>ルルさん
「小児用喘息薬シロップ剤の甘味料」に関して,当社の薬剤師に質問しました.
以下に医療用の主な製品と使用甘味料を記載します.
●イノリンシロップ⇒D-ソルビトール,白糖
●ベネトリンシロップ⇒サッカリンナトリウム
●ブリカニールシロップ⇒D-ソルビトール
●ホクナリンドライシロップ⇒精製白糖
●メプチンシロップ⇒精製白糖
サッカリンについて.
過去に発がん性を疑われ使用禁止になった経緯があります.
しかし,その後,様々な調査により発がん性は見られなかったため,
リストから外されたそうですが,安全性維持のため,食品衛生法により,
各食品においては使用量が制限されています.外装にその旨と使用量の記載があります.
コメントありがとうございます!
高齢者の服用に関しては,頻回なインタビューが必要ですね.
いつ何時処方が変更されるか分かりませんから.
健康のために飲んでいる薬剤が歯科治療において害となってはなりませんね.
>ルルさん
「小児用喘息薬シロップ剤の甘味料」に関して,当社の薬剤師に質問しました.
以下に医療用の主な製品と使用甘味料を記載します.
●イノリンシロップ⇒D-ソルビトール,白糖
●ベネトリンシロップ⇒サッカリンナトリウム
●ブリカニールシロップ⇒D-ソルビトール
●ホクナリンドライシロップ⇒精製白糖
●メプチンシロップ⇒精製白糖
サッカリンについて.
過去に発がん性を疑われ使用禁止になった経緯があります.
しかし,その後,様々な調査により発がん性は見られなかったため,
リストから外されたそうですが,安全性維持のため,食品衛生法により,
各食品においては使用量が制限されています.外装にその旨と使用量の記載があります.
ママ佐竹様
nene様
貴重なコメントをいただきありがとうございました。
ドライシロップは常々気になっておりましたので、いい機会に勉強させていただきました。
砂糖使用ではないのですね。
これまではドライシロップ服用患児の保護者には「虫歯の原因は砂糖のみにあらず!」ということで、歯質強化やプラークコントロール、他のシュガーコントロールなどで対応しておりましたが、保護者には少し安心してもらえそうです。
患者の服薬に関しては、日々重要なチェック項目のひとつですね。
当院の医局のパソコンの中には、薬剤検索のサイトが「お気に入り」に入っており、すぐにその場で調べられるようになっています。
調べたところでそのままにしては何の意味もないので、唾液減少などの副作用は口腔内に起こりうる変化を患者さんによく説明し、適切な口腔ケアを心がけたいと思っています。
nene様
貴重なコメントをいただきありがとうございました。
ドライシロップは常々気になっておりましたので、いい機会に勉強させていただきました。
砂糖使用ではないのですね。
これまではドライシロップ服用患児の保護者には「虫歯の原因は砂糖のみにあらず!」ということで、歯質強化やプラークコントロール、他のシュガーコントロールなどで対応しておりましたが、保護者には少し安心してもらえそうです。
患者の服薬に関しては、日々重要なチェック項目のひとつですね。
当院の医局のパソコンの中には、薬剤検索のサイトが「お気に入り」に入っており、すぐにその場で調べられるようになっています。
調べたところでそのままにしては何の意味もないので、唾液減少などの副作用は口腔内に起こりうる変化を患者さんによく説明し、適切な口腔ケアを心がけたいと思っています。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ベテラン歯科衛生士への道 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ベテラン歯科衛生士への道のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90050人
- 2位
- 酒好き
- 170693人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208292人